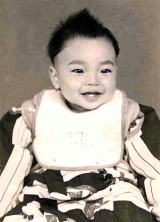|
所得税の配偶者控除と扶養控除廃止はより生活苦を招きます
マニフェスト比較検討 その④
●民主党は、マニフェストの中で「子ども手当」(中学生まで1人月2万6,000円の支給)を掲げています。しかしその財源として所得税の「扶養控除」「配偶者控除」をも廃止するとしています。当初、住民税については言及されていませんでしたが、今では、所得税だけの控除廃止とされています。そこで、民主党の所得税の控除廃止と「子ども手当」との関係で、その軽減される金額の試算を行ってみました。なお、小泉改革にで増税とされる以前の旧税額とも比較しておきました。
●細かい試算の内容は、このホームページに掲載していますで、ご覧ください。
|
試算① 児童手当が所得制限されていた
800万円以上の世帯も 増税で大きな軽減とはならない
世帯年収950万円
夫 950万円 妻 主婦 子ども 長男7歳 長女2歳
社会保険 33万 生命保険10万
|
●共同通信の報道(8月15日付)では、いままで児童手当が所得制限で該当されていなかった高所得世帯も恩恵があるとしています。「現在は児童手当を受けていない年収800万円を超えた世帯を境に、子ども手当の効果がより大きく現れる」「年収800万円超で効果大」としています。そこで950万円の世帯で試算をしてみました。
|
|
増税額
・新税制による増税額= 228.000円(A)
・旧税制からの増税額 = 420.000円(B)
|
|
|
増税と子ども手当(C)の相殺額
現在より軽減額 (A)―(C)=396.000円軽減
平成17年度よりの軽減額(B)―(C)=204.000円軽減
|
|
|
|
●結果は、効果はあるものの、増税額も大きく共同通信のいうほどの『効果大』とはなっていませんでした。
|
試算② 子どもが中学生までは軽減されるが、すぐ増税になる
世帯年収735万円
夫 600万円 妻135万円(パート)
子ども 長男19歳(学生) 長女14歳
社会保険30万円 生命保険5万円
|
●子どもが2人で児童手当が該当しない中学生以上の家庭で試算してみました。
増税額
・これからの所得税の控除による増税額=44.000円(A)
・平成16年度所得税・住民税からの増税額=119.600円(B)
|
増税と実質の子ども手当(C)の相殺額
現在より軽減額 (A)−(C)= 266.000円軽減
平成16年度よりの軽減額(B)―(C)= 192.400円軽減
|
●結果は、中学生以上の家庭では子ども手当で家庭負担が軽減されます。しかしまもなく年齢で軽減から負担増に転換してしまいます。
|
試算③ 子ども手当で児童手当も廃止で、思ったほど軽減されない
世帯収入400万円
夫 400万円 妻 主婦 子ども長男2歳
社会保険20万円 生命保険5万
|
●現に児童手当(3歳未満児)を受けている若い家庭での子ども手当の効果を試算しました。
増税額
所得税の控除廃止によるこれからの増税額=42.000円増税(A)
平成17年度と比較して =79.000円増税(B)
|
増税額と実質の子ども手当(C)の相殺額は
現在からの軽減額 (A)−(C)=150.000円軽減
平成16年度からの軽減額 (B)―(C)=113.000円軽減
|
●結果は、家計は助かるものの思ったほどではありません。やはり増税による相殺もあります.。
|
試算④ 家計は助かるが2人の子ども手当は、ほぼ1人分の手当となる
世帯収入(500万 母の年金も入る)
夫 330万 妻100万(パート) 母75歳(年金70万)
子ども 長女2歳 長男1歳
社会保険25万 生命保険5万円
|
●小さい子どもが二人いる家庭では、児童手当てとの関係でどのように家計が助かるか試算してみました。
増税額
所得税控除廃止によるこれからの増税額 =43.500円増税(A)
平成17年度と比較しての増税額 =44.100円増税(B)
|
増税額と実質の子ども手当(C)を相殺すると
現在と比べると (A)−(C)= 340.500円軽減
平成17年と比べると(B)―(C)=339.900円軽減
|
●結果は、子ども手当で家庭は助かるものの実質的には1人分ほどの軽減でした。
|
試算⑤ 母子家庭の子が実家に戻ってきた場合、年金生活者は厳しい
世帯収入(480 年金生活+パート)
夫 400万(66歳年金) 妻(主婦58歳)
子(22歳パート80万) 孫 長男1歳児
社会保険25万 生命保険5万
|
●母子家庭の親子が、年金生活者の実家に戻ってきた場合を試算してみました。
|
増税額
新税制による増税額 ③−②=38.000 円増税(A)
旧税制と比較して税額の増 ③−①=137.450 円増税(B)
|
実質の子ども手当額 (C)
|
増税額と実質の子ども手当を相殺して
現在と比べると(A)−(C)= 154.000円軽減
平成17年度と比べると (B)―(C)=54.500円軽減
|
●ここでも増税額が大きく、子ども手当がかなり機能していません。特に年金生活者の場合は、前回の年金控除額の改定(増税)がかなり影響しています。
|
試算⑥ 子どもが義務教育を越えれば、とにかく増税だけです
世帯収入 503万円
夫 400万円 妻103万円 (臨時)
子ども長男21歳(学生) 次男19歳(学生)
社会保険30万 生命保険5万
|
●中学校を卒業した家庭ではどうなるのか試算してみました
|
増税額
現在からの増税額 =19.000 円増税
平成17年度と比較して=31.400 円増税
|
●結果は、当然増税だけとなります。このような家庭に対しての対応が強く求まれています。
|
試算⑦ 就職できない子を扶養する年金生活の家庭は特に苦しい
世帯収入(300万円 年金生活)
夫 300万(66歳) 妻(主婦59歳)
子 (23歳 無職・就職活動中)
社会保険20万 生命保険5万
|
●退職したが子どもが大きくなり大学を卒業しても就職できていない家庭の状態を試算してみました。
|
増税額
現在からの増税額 ③−②=38.000 円増税
平成17年度と比較して③−①=108.500 円増税
|
●子どもが大きくなっても就職できない家庭、リストラされて親のうちにいる家庭はこの不況下でかなり多くなっています。また年金生活者への配慮は特に重要です。
|
試算⑧ 配偶者特別控除は旧税制に戻すべきである
世帯収入 450万円
夫 400万円 妻50万円 (臨時)
子ども長男21歳(学生) 次男19歳(学生)
社会保険30万 生命保険5万
|
●ここでは配偶者特別控除が有利だった旧税制を振り返るために試算しました。
|
増税額
現在からの増税額 =19.000 円増税
平成16年度と比較して= 68.600円増税
|
●配偶者特別控除の合算がなくなり定率減税を配した小泉改革以降の税制が増税を招いていることは明らかです。その上にさらに所得控除の廃止ではたまりません。
|
試算⑨ 障害者などの控除加算の廃止は絶対にストップを
世帯収入 503万円
夫 400万円 妻103万円 (臨時)
子ども長男19歳(学生) 次男12歳(障害1級)
社会保険30万 生命保険5万
|
●現行税制には障害者控除および同居特別障害控除が加算がありますが、扶養控除、配偶者控除でこれらの加算も通常では廃止されてしまいます。これが廃止された場合を試算しました。
増税額
現在からの増税額 ③−②=65.000円増税(A)
平成17年度と比較して③−①= 67.000円増税(B)
|
増税と実質の子ども手当(C)の相殺額
現在より軽減額 (A)−(C)=187.000円軽減
平成16年度よりの軽減額(B)―(C)=185.000円軽減
|
●結果は、子ども手当で家庭負担が軽減されますが、障害児者の扶養控除加算は今後とも続くものであり、この廃止は絶対にやめるべきです。また特定扶養親族、老人扶養親族における控除額加算も廃止してはいけません。
配偶者控除廃止と子ども手当支給における 結論
・所得税の扶養控除・配偶者控除は、子ども手当が支給される家庭をのぞけば、著しい増税となります。
・子ども手当も児童手当と増税で相殺される場合は、予想される金額は思ったよりもより少ないものとなります。
・ここでの試算は民主党のマニフェストで計算していますが、所得税にとどまらず住民税の「控除」廃止にまでいくと庶民への大増税になります。
・また「同居特別障害者」「特定扶養親族」「老人扶養親族」などの控除額の加算を廃止すべきではありません。このまま手をこまねいていると控除廃止に伴って加算も廃止されかねません。これは特に特にストップすべきです。
・子ども手当の財源は、扶養控除、配偶者控除の廃止から財源確保すべきではありません。社民党のマニフェストにあるように自公政権、特に小泉改革で甘やかされてきた富裕層、大企業などから応分の負担=ここでの増税からもとめるべきです。
・また現行の児童手当は企業負担もあります。子ども手当では企業負担も継続すべきです。
・小泉改革で増税となった税制度改悪をいったん元に戻してから新制度を構築すべきです。
・子育て援助対策としては、子ども手当だけで全てOKとはなりません。小泉改革で切り捨てられた義務教育の国庫支出金を就学援助や公立保育所への国庫支出金の復活も忘れてはなりません。問題とされている学校給食の未納問題などの解決は、「義務教育は無償」の原則からも学校給食費の無料化なども検討すべきです。現に無料化している自治体もあります。
特に、今の社会情勢においては控除廃止の政策は生活をさらに圧迫
●特に、今の大不況の社会状況では、家族の就職難、リストラなどで家族内に失業者を抱えている世帯が多くなっています。100万円以下の激しい低賃金化や、離婚によって母子家庭の子どもが実家にもどるなどによって扶養家族が増える世帯もさらに多くなっています。大不況の今だからこそ扶養者がいる世帯への扶養控除の廃止は避けるべきです。
●また配偶者控除の廃止も富裕層の専業主婦の問題ではなく、今の社会状況では、夫がリストラされ妻の配偶者控除の対象になっている家庭も少なくありません。現に世帯主の離職はいままでになく増大しています。
これらの厳しい世帯での控除廃止は、必ず生活破壊となって行きます。
●さらに心配すべきは大企業の「家族手当」「扶養手当」「住宅手当」廃止の傾向です。大企業では小泉改革当時から成果主事給与として「扶養手当」「家族手当」は属人的な弊害としてこの間、削減と廃止化をすすめてきました。国の所得税制度で、扶養控除・配偶者控除は廃止されるとなると―必ず大企業から給与の「扶養手当」「家族手当」を廃止する傾向がかなり強まると思われます。
また、民間の手当廃止の傾向が強まるのなら、これもまた公務員給与にも「扶養手当」「住宅手当」を廃止するという影響が強まるとみるべきです。すでに人事院勧告では「住宅手当」を問題にしています。
国の控除廃止の政策は、様々に連動して官民の労働者の実質賃金の引き下げにもつながりかねません。
●私は、これらの理由から「生活第一」を守るためにも、子ども手当の財源を所得税の廃止に求めてはならないと主張します。
(つづく)
|

 市の選挙の最中に、県外の選挙の応援には行かないでしょう・・・。しかも、「山梨に講演にいきたいから、いい?」と、この
市の選挙の最中に、県外の選挙の応援には行かないでしょう・・・。しかも、「山梨に講演にいきたいから、いい?」と、この