~愛こそ全て~
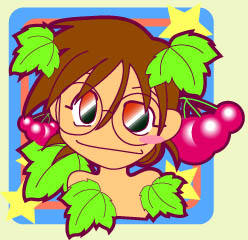
島尾 朱音の場合
いい天気だなぁ。
窓の外の見事な庭を眺めながら、朱音はぼんやりとそんなことを考えていた。
秋の陽射しは、池の水面に反射して眩しいほどだった。紅や黄色に染められた木の葉や、枝振りのいい松の木。玉砂利の小径は、池にかかるアーチ型の橋へと続いている。
あそこ、並んで歩いちゃったりするんだろうか。
朱音は自分の想像にぞっとする。柄じゃないと解っているだけに、恥ずかしさを通り越して悪寒すら感じてしまうのだ。
ゆったりとしたクラシックのメロディ。サーモンピンクのカーペットに、白いグランドピアノ。テーブルの上には、品のいい小さな花かごが飾られている。その向こうには、仕立てのいいスーツを着た男性が、緊張した面持ちで座っていた。
誰がどう見ても、お見合いとしか呼べないシチュエイションだった。ただし、朱音の頭の中をのぞいては。
既に目の前にいる男性が、佐々木だったか笹川だったか、定かではない。どんな会社に勤め、どんな仕事をしているのか。住んでいる所や家族構成、その他諸々、叔母に聞いていたはずだが、全部頭から抜け落ちてしまっていた。さっきだって、向こうから声をかけてくれなければ、朱音はひたすらぼんやりとホテルのロビーのソファーに座り続けていたに違いなかった。最初は嫌々、一昨日からは必死で写真と向かい合っていたが、脳細胞が拒否したのか、とうとうその顔を記憶することはできなかった。
大体、朱音には結婚する気などないのだ。今まで男性と付き合ったことがないわけではない。でもいつも思ってしまうのだ。
なんか、違う。
それがなんなのか。朱音自身にも解らない。けれど、一度違うと思ってしまうと、それはずっとついて回るのだ。“好き”とか“嫌い”とか以前の問題になってしまう。まぁ、美汐にならないだけマシかとは思うのだが。
理想が高い訳じゃないんだけどね。
朱音は目の前の男性に乾いた笑顔を返しながら、ふとそんなことを考えていた。
「なによぉっ、そんなに笑うコトないでしょっ」
台所から顔を出した朱音は、子供のように頬を膨らます。千紗も美汐も、コタツをばんばん叩きながら、声を出して笑っているので、朱音がそんな顔をしているなどということに気づきもしない。水が出しっぱなしなのを思い出して、朱音は仕方なしに流しの前へと戻った。
食事会の調理担当は言うまでもなく美汐だが、後片づけについては特に決まっていない。朱音が場所を提供しているせいか、千紗が自ら洗い物をかってでることがほとんどだ。しかし今日の千紗は、村瀬さんの一件で荒れているし、既に缶ビールが三本空いている。本人は“やる”と言い張ったが、部屋はもちろん食器の提供者でもある朱音としては、どうしても頷けずにいた。その程度で千紗が酔うなどとは思わなかったが、いらついている彼女が感情のまま壊れ物を扱えばどうなるか、短い付き合いではないだけに容易に想像がついた。
そう、元はといえばその千紗の気を紛らわせようと、話題を変えようとした、それだけだった。
「そういや、あたし、この間お見合いしたのよね」
失言だった。千紗と美汐がそれを聞いて、黙っているわけがなかった。美汐は相変わらず、鋭いというか陰険というか、そういう突っ込みをしてくるし、千紗に至っては断った修羅場の一件を持ち出して、自分には聞く権利があると主張する始末だ。確かに、入稿前に手伝うことができなかったのは、朱音自身引け目に感じる部分があり、ついついべらべらと喋ってしまった結果が、これだった。
「で、どうしたの、その相手」
美汐が涙を拭いながら、そう尋ねる。とりあえず朱音は無視を決め込んで、洗い物を続けていた。自分でも柄ではないとは思ったけれど、なにもそんなに笑わなくてもいいではないか。
「朱音ちゃぁん、拗ねないでよぉ。朱音ちゃんに結婚されちゃうと、美汐、寂しいわっ」
美汐が妙に甘ったれた声で訴えてくる。
「はいはい」
投げやりに相槌を打ちながら、朱音は食器をすすぎ、重ねていく。マトモに相手をしていたら疲れるだけなのだ、この連中は。
「朱音ちゃんってばっ」
「美汐、朝御飯は。本気で千紗に作らせる気なの」
あえて突き放すように、話題を変える。美汐に対して話を逸らすには、食事に関することが一番だった。
「あ、うん。パンにしよ、パン。千紗、このペースで、朝飯、食べられるとは思えないし」
「みそ汁どうすんの」
コンロに載せられたままの鍋を覗きながら、朱音は尋ねる。中には豆腐とワカメのみそ汁が、ちょうど椀に二杯分程度残っていた。
「千紗の飯にする。あたしとあんたは、サンドイッチでいいでしょ。ポテトサラダも残ってるし」
「はぁーい」
朱音は傍らの水切りカゴに重なった食器にふきんをのせると、手を拭き、台所の明かりを消した。
よし。これで完全に話は逸れた。すっかり安心しきって、定位置である千紗と美汐の間に腰を下ろすと、
「で、その野郎とは、その後どうなったの」
美汐はにっこりと微笑んだ。朱音が甘かったのか、美汐がねちっこいのか。彼女はため息を一つつくと、気付いたように千紗へと視線を向けた。千紗は、テーブルに突っ伏したまま肩を震わせている。いつの間にか、ビールが日本酒に変わっていた。静か静かだと思っていたら、ずっとこうして笑っていたという訳か。それにしても。
「笑いすぎじゃない」
朱音はそんな千紗の髪を、軽く引っ張った。顔を上げた彼女の瞳には、うっすらと涙が浮かんでいた。
「お腹、いたい」
息も絶え絶えな千紗の頭の軽く小突いて、
「どういう訳か、気に入られて会ったわよ。この間の日曜も」
「気に入られてって、あんた、言ったの。その、盆と、年末は、家にいないって。その、一ヶ月くらい、前も、使い物にならないよ、って」
苦しそうに千紗は、そう訊いた。朱音は眉間にしわを寄せながら、
「言えない、言えない」
「言わなきゃダメじゃない、結婚の第一条件なんだから」
美汐はそうしてタバコに火をつける。完全に楽しまれている。朱音は、軽い頭痛を感じた。
「どんなヤツなの。いい男」
「フツーの人。フツーのサラリーマン、らしい」
朱音の返答は、あまりにも頼りない。なにしろ二回会った今でも、相手の名前も顔も完全に覚えていないのだから仕方がなかった。
「じゃダメだ」
美汐があっさりと言い放つ。続けて、
「朱音は、犯罪者か、甲斐性なしが好きなんだもんねぇ」
「なんじゃそりゃ」
千紗が不得要領な顔をする。
「ギャンブラーとか、女で身を滅ぼしかねないヤツとか。でなけりゃ、完全な犯罪者とかが好きなんだもん、この人」
「美汐っ、誤解を招くようなこと言うのやめてよっ」
「ほぉ。んじゃ、否定できるの」
朱音が絶句すると、美汐は勝ち誇ったように煙を吐いた。千紗は冷ややかな視線を美汐に向けると、
「あんたね、自分のことタナに上げてよく言うわ」
「言ったもん勝ち」
にっと笑った彼女を見て諦めたのか、朱音と千紗は話題を元に戻す。朱音にとっては、どちらも歓迎すべきことではなかったが、これ以上美汐と不毛な会話を続けるよりはマシだった。
「次いつなの、その人と会うの」
笑うだけ笑って、すっきりとしたらしい。千紗は頬杖をついて、日本酒のグラスを揺らしていた。すっかりいつもの、千紗に戻っている。その表情にも、からかったり茶化したりする様子は欠片もなかった。
「さぁ」
「さぁって、朱音」
千紗が不満そうに彼女の名前を呼ぶ。朱音は、まだどこか面白がっている美汐と、本気で心配しているらしい千紗を見比べながら、
「この間会ったときにね、電話番号を聞かれたのよ」
淡々と、まるで人事のように朱音は言葉を続ける。
「で、一応教えたんだけど、あたし、電話嫌いでしょ。だから、そう言ったの。電話が嫌いだから、かかってきても出ませんよって」
「へ」
千紗が間の抜けた声を出す。どうも、朱音の言葉をよく理解できなかったようだ。美汐はというと、髪の毛をかき混ぜながら、
「フツーの野郎なら、暗に断られたって思うぞ、それ」
「じゃない。それきり音沙汰ないから。はい、この話、終わり」
そんな彼女の言葉を聞いて、千紗と美汐は、どちらからともなくため息をついた。
もしかして、お見合いというものを一番面白がって、それでいて茶化していたのは朱音自身ではないのだろうか。
二人の頭に、なんとはなくだが、そんなことがふっと浮かんだのだった。