

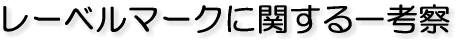
ソニークラシカルの新しいマーク
(92・3・3掲載)
アメリカのレコード会社CBSレコーズを買収したソニーが、ドイツ・グラモフォンでカラヤンやアバド付きのプロデューサーをしていたギュンター・ブレーストを社長に迎えて「ソニー・クラシカル」というレーベルを発足させたのは1989年のことでした。
そこで、それまで使われていたCBSの目玉マークや“MASTERWORKS”といったロゴ(図1)に代わって使われるようになったのが、図2のようなマークです。ホログラフィをバックに赤字で描かれた訳の分からない図形が、十六分音符の白抜きだと気がついた時は、デザイナーのユーモラスなセンスに感心したものでした。
ところが、最近このマークにはもっと深い意味が込められているのではないかと思うようになったのです。 図3を見て下さい。日本コロムビアのマークですね。この十六分音符の形はソニー・クラシカルのマークそのものです。もともと日本コロムビアという会社は米コロムビア(ちょっと前までのCBSレコーズ、現SME)の子会社として設立されたもので、米コロムビアとその兄弟会社であった英コロムビアのレコードを販売するために、十六分音符マークと、“Columbia”という商標の使用権を与えられていたのです。
| 図3 |
 |
ところが、後に英コロムビア(英グラモフォンと合併してEMIとなっていました)は東芝と、米コロムビアはソニーとそれぞれ合弁会社を設立して日コロからは離れてゆき、マークと商標だけが残ってしまいました。
その後本家の方ではどうなったかというとアメリカではCBSの傘下に入ったのちも、“Columbia”はレーベル名として使用していましたし(ポップスでは依然使っています)、イギリスでもEMIの統一マーク(図4・昨年からは図5)が制定されるまでは、最近まで使われていたみたいです。(図6)
いずれにしても、現在では米、欧、日本の全く資本関係のないレコード会社がそれぞれのテリトリー内でのみ、このマークの使用権を有しているということになります。従って輸入盤などで使用権のない地域に販売する時には、図7のようなシールを貼るなどして、その旨のお断りをする必要が出て来るわけです。
| 図7 |
 |
|
図8 |
 |
同じように、特定の地域でしか使用が認められないケースでは“DECCA”(日本とアメリカでは、この商標はMCAに使用権があるので“LONDON”になってしまいます。※)とか犬のマークとかも有りますね。His Master's Voiceというキャプションがついた英グラモフォンの犬のマーク(図8)などは、平板レコードが発明されて以来の由緒あるマークなのですが、イギリスではもはやレーベル名ではなくレコードショップの名前になってしまいました。
そこでソニー・クラシカルです。
新しいレーベルの発足にあたっては、国によって使用権が認められない黴の生えたマークよりは、全世界共通に使えるマークの方が良いに決まっています。そして、ここが重要なのですが、このマークを決定した人の「おらっちはいまでこそおちぶれて東洋の成金野郎にのっとられてしまったけど、もとをたどれば由緒正しい家柄の出なんだぜ」という、ルーツとかアイデンティティとか、なんかそういったものをはっきりさせておきたいある種の怨念のようなものが、十六分音符への先祖がえりという形をとってあらわれてきたのです。
と、いかにも本当らしく書いてきましたが、実は私は、このマークの制定意図については、全く知識が有りません。あるいはどこかで公になったものがあったのかもしれませんが、あいにく眼に触れる機会を持たないまま、今に到っています。したがって私の考えはとんでもなく見当外れなのかもしれません。それはそれでいいんじゃないと笑って済ませるところから、人間の堕落がはじまるのです。
(※)現在では、MCAもDECCAも同じ"UNIVERSAL"グループに入っているため、日本でも"DECCA"が使われるようになりました。(02/1/26追記)










