![]()
(02/12/17作成)
(03/1/16掲載)
モーツァルトの「魔笛」は、私が最も好きなオペラです。「途中で話がおかしくなってしまって、プロットが破綻している」という指摘はありますが、そんなものは、次から次へと現れる美しく魅力的な音楽の前には、ほんの些細な疵に過ぎません。「オペラ」とは言っても、これは例の稀代の興行師、エマニュエル・シカネーダーの台本によって作られたドイツ語の「ジンクシュピール」、つまり「歌芝居」ですから、モーツァルトもかたくるしいイタリア・オペラを作る時よりは、もっと自然な、霊感に満ちた音楽を書くことが出来たのではないでしょうか。中でも、そのシカネーダー自身が扮するキャラクター「パパゲーノ」のために作られた2曲のアリア、幕が開いてしばらくしてパパゲーノが登場する時の自己紹介の歌「おいらは鳥刺し」と、終幕のフィナーレの前に歌われる「恋人か女房があれば」は、シンプルな有節歌曲の形をとった、とってもキャッチーなナンバー、1度聴いたら、すっかり虜になってしまうことでしょう。ステージで見ると、「鳥刺し」ではパンフルートで「ソラシドレ」という合いの手を入れたり、「恋人か〜」では鈴を叩きながら歌ったりと、歌手にも歌うだけではなく別の才能が必要になってきますから、大変でしょうが。
もっとも、「恋人か〜」では、実際に歌手が鈴を叩いているのではなく、オーケストラの団員がチェレスタできちんと伴奏してくれていますから、歌手は叩く真似をしていればいいのですけれどね。中には、ザルツブルク音楽祭のように、指揮者が自らチェレスタを弾いて、パパゲーノはピットまで降りてきてそれを眺めてる、なんて演出もありましたよね。レヴァインとか、ショルティとか(レヴァインの場合、台詞までしゃべっていました)。・・・えっ、チェレスタ?ちょっと待ってください。チェレスタという楽器は、確かモーツァルトの時代にはなかったはず、そう、これは1886年にパリのオーギュスト・ミュステルという人が初めて作った楽器です。1892年に初演されたチャイコフスキーの「くるみ割り人形」の中の「金平糖の踊り」で初めて公衆の前でその音が披露されたというこの楽器が、その100年前、1791年に作られた「魔笛」の中で使われるはずなんか、ありませんよね。だったら、一体モーツァルトはどんな楽器で演奏するために、この曲を作ったのでしょう。
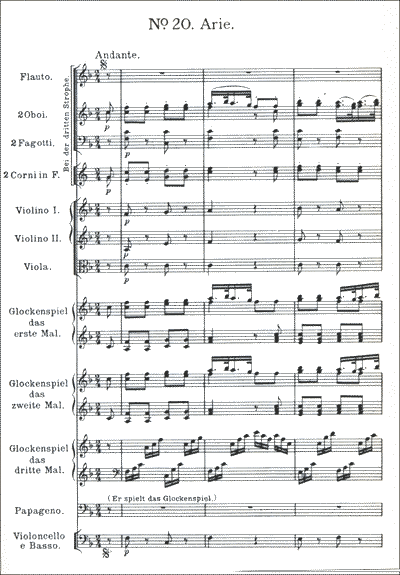 |
これが、その「恋人か〜」のスコアの最初のページです(この画像はペータース版ですが、「新モーツァルト全集」のベーレンライター版も内容は同じです)。その「鈴の音」を出す楽器は、「Glockenspiel」とありますね。グロッケンシュピールといえば、「グロッケン」ともいいますが、あの「鉄琴」ですよね。スタンドも何もついていないかわいい楽器、オーケストラでも良く使われますね。
うん、これだったら、いかにも鈴のような音が出せるでしょう。しかし、この譜面を見てください。2段になっています。上がメロディー、下が和音を押さえて伴奏みたいに、どう見てもピアノみたいな鍵盤楽器の譜面です。確かグロッケンは2本のバチを使いますよね。でも、これが2本のバチだけで演奏できますか?とりあえず、2回目のイントロをチェレスタで演奏したものをお聴き下さい。
ちなみに、この楽器がオペラの中で最初に出てくるところ(第1幕のフィナーレ)では、スコアの指示は「Glockenspiel(Stromento d'acciajo)」となっています。カッコ内はイタリア語で「鉄の楽器」つまり「鉄琴」ということです。しかし、やはり譜面は2段、左手では和音を弾くように書かれています。
ここで、面白いものをごらんいただきましょう。その「魔笛」をモーツァルトが見に行った時のことを、奥さんのコンスタンツェに書いて送った手紙の一部です。
・・・それからパパゲノがグロッケンシュピールでアリアを歌う時、舞台へいった。今日は自分であれを鳴らしたくてたまらなくなったものだから。それで、シカネーダーが一度休む所で、いたずらしてアルペジオを鳴らした。奴さん驚いて、舞台裏をみて、ぼくをみつけた。二度目の時はやらなかった。すると今度はだまってしまって、ちっとも先へすすまない。奴さんの考えがわかったので、ぼくがまた和音をならしてやったら、やっと奴さんもグロッケンシュピールを叩いて「黙れ、大口野郎」といったものだから、みんな大笑いさ。このいたずらで、はじめて彼が自分で楽器をならすのでないことがわかった人も、大勢いるだろうと思う。・・・
1791年10月8日のコンスタンツェあての手紙
訳:吉田秀和 講談社刊「モーツァルトの手紙」(1991年:講談社学術文庫)
モーツァルトが「グロッケンシュピール」を鳴らして、シカネーダーをからかった様子が活き活きと綴られていますね。しかし、これを読んで、もしかしたら別の情景を思い浮かべた方もいるのではありませんか?それは、あの、1984年に公開された映画「アマデウス」の中の1場面です。「魔笛」を上演しているオケピットの中で、アマデウス役のトム・ハルスがそれこそチェレスタみたいな楽器を演奏しています。歌の途中でモーツァルトが倒れてしまうので、シカネーダー役のサイモン・キャロウ(吹き替えはブライアン・ケイ・・・そんなことまではいい・・・ごもっとも)は「先へすすまない」ことになってしまいます。このシーンは、脚本のピーター・シェーファーが明らかにこの手紙をヒントに作り出したものだと、私は思っているのですが。それはそれとして、その「チェレスタみたい」な楽器から出てきた音が、まさに「鉄琴」の音だったのです。外観はチェレスタ、演奏もチェレスタのように両手、10本の指で弾けるもの、しかし、音はチェレスタのような洗練されたそれこそ「天上の」音ではなく、鉄琴を金属のバチで叩いた時の荒々しい音、そう、この楽器こそが、モーツァルトが「魔笛」で指定した楽器だったのですね。
 |
実は、「グロッケンシュピール」という言葉については、以前から疑問に感じていたことがありました。これはドイツ語ですが、Glocken=鐘、spiel=演奏ですから、「鐘を演奏すること」というのが本来の意味のはずです。しかし、いまの「鉄琴」には、「鐘」などどこにもありません。そこで、この件について調べてみたところ、こんなことがわかりました。そもそも「Glockenspiel」という言葉は、教会などに設置された、多くの鐘を鳴らして音楽を奏でる装置、いわゆる「カリヨン」を指し示すものでした。16世紀ごろには、それぞれの鐘を手元で演奏できるように、ワイヤーでつなげられた鍵盤がつけられるようになります。それで、専門の演奏家がこの鍵盤(かなり大きな物ですが)を操作して、オルガンのように演奏できるようになりました(下図)。
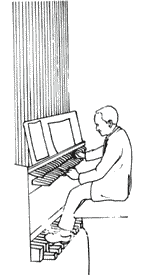 |
| 大図説 世界の楽器(小学館 1981年刊)より |
さらに18世紀になると、大きな鐘ではなく、金属の棒を叩く、家庭用(?)のコンパクトな楽器が作られます。それが19世紀になると、そこから鍵盤がなくなって、中にあった金属を直接バチで叩く楽器となります。これが、現在のグロッケンシュピールになるわけです。
つまり、モーツァルトの時代では、「グロッケンシュピール」といえば、鍵盤つきの楽器「キーボード(キード)・グロッケンシュピール」のことだったのです。もちろん、そのころは今の「グロッケンシュピール」はまだありませんでした。後に作られる「チェレスタ」は、いわば先祖がえりというわけです。そして、この楽器は、硬いバチではなくフェルトで覆われたハンマーで金属片が叩かれますから、「キーボード(キード)・グロッケンシュピール」が持っていた粗野な音は、見事に一掃されています。
この「キーボード(キード)・グロッケンシュピール」を実際に見たことがある人など、ほとんどいないでしょうね。いわば1度は失われてしまった楽器、それが、最近では「オリジナル楽器」の波に乗って、再評価されているのでしょう。後述のクリスティとガーディナーの録音では、博物館にあったものを参考に、ロビン・ジェニングスという楽器製作者が復元したものが使われています。実際、このパパゲーノの曲には、どう考えても洗練されたチェレスタではなく、荒削りなキーボード・グロッケンシュピールの音のほうが似合っているように、私には思われるのですが。
 |
| ロビン・ジェニングスによる復元モデル (ガーディナー盤のライナーノーツより) カラー写真 |
このような厳格なコピーではなくても、チェレスタのメーカーとして知られるシードマイヤー社で通常の商品として製造されているものもあります。こちらのサイトに写真がありますので、ご覧になってみてください(「Models」から行けます)。
最近のオペラハウスやCDでは、そのあたりの事情はどうなっているのでしょう。まず、私が持っているオペラの映像です。(06/4/27追記)
|
そして、主にスタジオで録音されたCDです。網かけはオリジナル楽器による演奏。(06/11/6追記)
|
オリジナル楽器の隆盛とともに、グロッケンシュピール(もちろん、キーボード・グロッケンシュピール)が使われるようになったことが、良くわかりますね。
カラヤンが面白いことをやっています。楽譜の指定に正直に、いわゆる「グロッケンシュピール」つまり鉄琴を使って演奏しているのです。もちろん、どんな名手でも左手の和音はひけませんから、その部分はチェレスタで、つまり、あのパートを2人で演奏することになります。「帝王」カラヤンはキーボード・グロッケンシュピールという楽器を知らなかったということですね。そういう時代だったのです。しかし、「アマデウス」のサウンドトラックを担当したはずのマリナーが敢えてチェレスタを使っているのは、なにか特別の思い入れをこの楽器に感じているせいなのでしょうか。
(06/10/31追記)
必要があってもう一度全てのCDを聴き返してみたところ、ベーム盤でもグロッケンとチェレスタを併用していることが確認できました。
(06/11/6追記)
まだ入手していなかったモダン楽器による演奏のCDを取り寄せて聴いてみたところ、1972年のサヴァリッシュ盤でもグロッケンとチェレスタを併用していることが分かりました。1981年のハイティンク盤も、再度聴き直してみるとやはり併用であることが確認できました。従って、モダン楽器で最初にキーボード・グロッケンシュピールを使用したのは、1987年のアーノンクールということになります。ちなみに、第1幕フィナーレでグロッケンシュピールが使われる部分では、サヴァリッシュ盤でだけ、右手の部分をチェレスタで演奏しています。
(16/7/23追記)
こちらのブログでは、20世紀にミュステルによって作られたキーボード・グロッケンシュピールである「ジュ・ドゥ・タンブル」について述べられています。さらに、こちらのサイトでは、実際に「チェレスタ」、「ジュ・ドゥ・タンブル」、そして、「ヒストリカル・キーボード・グロンケンシュピール(パパゲーノ・ベルズ)」の写真を見ることが出来ます。