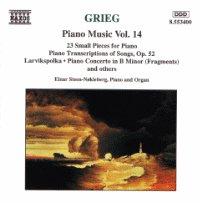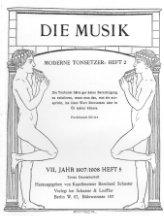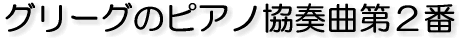
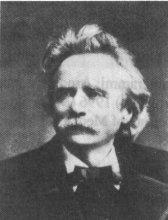
1868年に作曲されたグリーグのピアノ協奏曲作品16は、古今のピアノ協奏曲の中でも特に人気のある曲で、コンサートやレコーディングではもはや定番となっています。私たちにとっても、今回は2度目の機会です。
ところで、グリーグのピアノ協奏曲と言えば、もちろん完成した形ではこの1曲しか存在していないわけですが、実は彼は1883年に出版社(C・F・ペータース)からの要請でもう1曲ピアノ協奏曲を作曲しようと試みているのです。結局「ミューズの神がちっとも動こうとしない」ために、この構想は立ち消えになってしまい、残念ながら「ピアノ協奏曲第2番ロ短調」が世に出ることはありませんでした。
この曲の草稿は現在はベルゲン公立図書館に所蔵されており、未出版の曲に対する作品番号であるEG番号で〔EG 120〕が与えられています。もちろん断片的なスケッチしか残ってはいませんが、一部のものは印刷譜として実際に見ることが可能です。また、後述のように録音もありますので、未完に終わったこの曲の片鱗をうかがい知ることはできるでしょう。
スケッチを調べてみると、少なくとも次の4つの楽章について作曲の筆を取った形跡が認められます。
 第1楽章
第1楽章
ゆっくりとしたオーケストラの序奏に続いて〔譜例1〕のような物悲しいテーマがカデンツ風に登場し、Allegro へと続きます。譜例の上の「SOUND」アイコンをクリックすると、音が聞こえます。
この後、スケッチは突然中断されています。
 Andante の楽章
Andante の楽章
協奏曲との関連には疑問ももたれている楽章です。印刷譜や録音されたものはありません。
 Caprice Andante espressivo - Allegroの楽章
Caprice Andante espressivo - Allegroの楽章
2通りのスケッチが残されています。やはり印刷譜、録音はありません。
 Finale
Finale
2通りのスケッチが残っています。
- Variant 1 /有名な「トロルハウゲンの婚礼の日」を思わせる、明るく軽やかなテーマです〔譜例2〕。
- Variant 2 /Andante 楽章から借用されたテーマで、スケルツォ的なキャラクターを持っています。もとの文献でも縮小印刷されているので、見ずらい点はご勘弁下さい。最初の小節の4つ目の音はEisです。このD-Eisという増音程が、北欧的というよりはオリエンタルな雰囲気を醸しだしています〔譜例3〕。
資料・文献
Grieg Piano Music Vol.14 (NAXOS
8.553400)
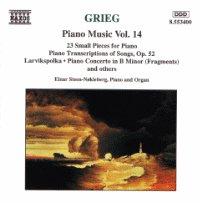
そもそもこんな企画を思い立つ発端となったCDです。Einar
Steen-Nøklebergのピアノで、掲載した譜例を全て実際に音で聴くことができます。また、ライナーノーツを書いたØyvind
Nordheimと、その日本語訳のコピーを送ってくださった(㈱)アイヴィーの野田晃子さんのおかげで、次の文献を知ることができました。
Edvard Grieg/Gesamtausgabe Band20 von R. Andersen, F. Benestad, K. Oelmann
(Peters)

ピアノ協奏曲の成り立ちについての記述と、スケッチから復元された〔譜例3〕が掲載されています。ちなみに、オスロ・エドヴァルド・グリーグ委員会とオスロ大学音楽学研究所との共同作業によるグリーグ全集の刊行は、1995年にこの第20巻が出版されて、すべて完了しました。
Edvard Griegs musikalischer Nachlaß von J. Röntgen
(Die Musik 1907/8)
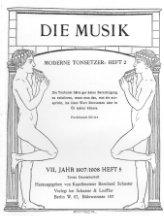
グリーグの友人、ユリウス・レントヘンが、グリーグの死後に書いた彼の遺稿に関する論文です。ここにはピアノ協奏曲(〔譜例1〕、〔譜例2〕)の他に、弦楽四重奏曲やピアノ五重奏曲のスケッチも掲載されています。90年も昔のこんな古い文献を即座に入手することが出来たのは、豊富な蔵書と機敏なサービスを誇る、国立音楽大学附属図書館さんのおかげです。






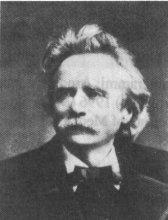
![]() 第1楽章
第1楽章![]() Andante の楽章
Andante の楽章![]() Caprice Andante espressivo - Allegroの楽章
Caprice Andante espressivo - Allegroの楽章![]() Finale
Finale