











◆最近の紀行
坂本行3 天橋立行2 石垣島行13 関西JR大回り行
札幌・層雲峡・登別ハブ&スポーク行
黒島行2 石垣島行12 石垣行ならず2 石垣行ならず はわい行 鹿児島行7 函館行5 函館行4
◆北海道
利尻行 札幌行9 増毛行 稚内から札幌行 稚内行6(追憶編2) 稚内行5(追憶編) 雪まつり行
層雲峡行3 定山渓行 札幌行8
函館行3 札幌行7 札幌行6 洞爺湖行 札幌行5 層雲峡行2 層雲峡行1
函館行2 札幌行4 旭山動物園行 支笏湖行3 支笏湖行2 支笏湖行1
札幌行3 襟裳行2 襟裳行1 釧路行4 網走行2 釧路行3 釧路行2
積丹行2 積丹行1 札幌行2 札幌行1
稚内行(旅愁編) 稚内行(徘徊編) 稚内行(望郷編) 函館行 旭川行 網走行 根室行 稚内行
帯広行2 釧路行1 帯広行1
◆東北
弘前行3 八戸行2 田野畑行 山寺行2 米沢行2 青森行3
東北新幹線「はやて」の車内から 仙台行5 盛岡行4
田沢湖行 花巻行 三陸縦貫行4(前谷地-石巻-仙台) 三陸縦貫行3(釜石-盛-気仙沼-前谷地)
三陸縦貫行2(久慈-宮古-釜石) 三陸縦貫行1(八戸-久慈)
八戸行 角館・横堀行 鶴岡行 会津若松行2
山形行3(芋煮会編) 弘前行2 秋田行2 弘前行1 塩釜・松島行 仙台行2006 平泉行
仙台行3(ダイバート編)
「陸羽西線」の車窓から 山形行2 羽黒山行 山形行1
東北新幹線「こまち」の車窓から 盛岡行(ソウルフル編)
郡山行 裏磐梯行
東北新幹線「はやて」の車窓から 青森行(望郷編) 青森行2(食いしん坊バンザイ編) 盛岡行
盛岡行(激闘わんこそば編) 米沢行 山形新幹線「つばさ」の車窓から 山寺行 喜多方行 仙台行
仙台行(食いしん坊バンザイ編) 会津若松行 秋田行 宮古行 ローカル線考
◆関東甲信越
松代行2 松代行1 あずさの車窓から 新潟行2 新潟行1 村上行 諏訪行2 諏訪行1
常陸大宮行
北鎌倉行 水戸行 「スーパーひたち」の車窓から 「小田急線」の車窓から
長野行 東京地震行 「妙高」の車窓から 「あさま」の車窓から 横浜行
箱根湯本行 長岡行 東京行 野辺山行2 野辺山行1 宇都宮行 飯田線行1 飯田線行2 横須賀行
伊豆熱川行 小田原行
◆北陸
白川郷行 「サンダーバード」の車窓から2 五箇山行 金沢行17 金沢行16 金沢行15 高岡行2
金沢行14 兼六園行 那谷寺行 東尋坊行 金沢周遊行 「はくたか」の車窓から
福井行2 福井行1 金沢寿司行2 金沢寿司行1 金沢行12 金沢行11 小浜行 雨晴行 金沢行10
「サンダーバード」の車窓から 富山行 のと鉄道の車窓から 金沢行9(昇天編) 金沢行奇譚
金沢行7(食い編4/4) 金沢行6(食い編3/4) 高岡行 金沢行5(食い編2/4) 金沢行4(食い編1/4)
金沢行3 金沢行2 金沢行1 金沢行(序章) 輪島行 北陸大返し 敦賀行
◆東海
伊勢志摩行 飛騨高山行 岐阜行 松阪行 犬山行 名古屋行 新幹線行3 新幹線行2 新幹線行1
馬籠・妻籠行
◆近畿
醍醐寺行 吉野行 近江八幡行2 竹生島行 天王山行 談山神社行 金剛山行 明石行2
宝塚2大聖地巡行 西明寺行
長谷寺行 高雄行 生駒山行 坂本行2 洲本行
伏見稲荷行 伏見城行 神戸行2 加太行
篠山行2 黒滝行 布引の滝行 小谷城行 鞍馬行 丹波観音寺行
観音寺城行 太秦行 天橋立行 高取城行
沼島行3 六甲行 室生寺行 今井町行 岳山行2 岳山行1
天安門行 赤目四十八滝行 斑鳩行 坂本行 堺行 彦根行2 篠山行 那智行 岩屋行
叡山行 高野行 熊野行 十津川行2
十津川行1 天理行2 天理行1 舞鶴行2 舞鶴行1 近江八幡行 舞子行 沼島行2 沼島行1
安土行2 安土行1 明石行 伏見行 伊賀上野行 福知山行 和歌山行
神戸行 長浜行2
紀伊半島行 大津行 京都行 姫路行2 姫路行 長浜行 奈良行 彦根行1 大阪行
◆中国
広島行3 児島行 姫路行3 境港行 安来行 三木城行 竹田行 餘部行 米子行2(乗馬編)
米子行1(大山編)
津山行 宮島行 しまなみ行 萩行4 萩行3 萩行2 呉行 龍野行 福山行
山口行 松江行2 備中高梁行 岩国行 播州赤穂行
長府行 倉敷行 山陽新幹線「レールスターひかり」の車窓から 「スーパーやくも」の車窓から
広島行2 広島行1 岡山行 尾道行 「スーパーはくと」の車窓から 松江行
鳥取行2(砂丘地獄編) 鳥取行1 下関行 萩行 出雲行 山陰行(出雲3号編)
◆四国
松山行3 祖谷行 道後温泉行 高松行4 宇和島行2 讃岐行4(阿波・淡路編)
讃岐行3(高所編) 讃岐行2(うどん編)
讃岐行1(発動編) 宇多津行 丸亀行 高松行3 「マリンライナー」の車窓から
「琴電」の車窓から 松山行2 高松行2 琴平行 徳島・鳥取行 徳島行2(寄り道編)
徳島行3(風雲帰阪編) 宇和島行 徳島行 松山行 高知行 高松行
◆九州
呼子行2 鹿児島行6 芥屋行 能古島行 湯布院行2 「ゆふいんの森」の車窓から
中津行 柳川行 鹿児島行5 志賀島行 知覧行 鹿児島行4
大宰府行 呼子行 名護屋行 杵築行 島原行 宮崎行2 壱岐行2 壱岐行1 飫肥行2 飫肥行1
つばめの車窓から 湯布院行 長崎行2 博多行5
「甘木鉄道」の車窓から
博多行4 秋月行 海ノ中道行 佐世保行2 佐世保行1 博多行3
「みどり」の車窓から 唐津行 博多行2(中洲礼賛)
九州行(終焉編) 九州行(風雲編) 九州行(郷愁編) 九州行(疾走編) 九州行(立志編)
鹿児島行(疾風怒濤編) 門司港行 小倉行 宮崎行 九州縦断行 鹿児島行2 熊本行
阿蘇行 長崎行1 鹿児島行 盛岡→鹿児島行 博多行
◆沖縄
那覇行4 石垣島行11 辺戸岬行 石垣島行11 石垣島行10 西表島行2
石垣島9 那覇行3 那覇行2 石垣島8 伊江島行2 伊江島行1
石垣島行7 新城島行 石垣島行6 名護行 慶良間行 宮古島行3 鳩間島行
久高島行 黒島行 那覇行 西表島行 石垣島行5 石垣島行4
嘉手納行 勝連城行 沖縄行15 沖縄行14(チービシ編) 伊良部島行
宮古島行2 宮古島行1 沖縄行13(アッテンド編) 沖縄行12(着陸復航編) 波照間行 沖縄行11
沖縄行10 小浜島行 沖縄食行 竹富島行 石垣島行3 沖縄行8 沖縄行7 沖縄行6
石垣島行2 石垣島行1 沖縄行5
沖縄行2006(その3) 沖縄行2006(その2) 沖縄行2006(その1) 沖縄行1996
◆その他
鉄道マニア 駅弁考1
コラム
| 世間は皇位継承、改元がらみのの10連休。 1日ぐらいはまったく仕事をしない日を作ってもよかろうと、前日から『明日は休むもんね』モードを全開にした。夜のアルコールも少し控え目。エライ。 城山に登ったり、チャリを転がしたりしていたのは、遥か昔のことのような気がするほど、このところ生活習慣が激変している。 3年前の東京大転倒がきっかけだが、去年の突発事案も大きく関与しているのは間違いない。 とにかく心が病んでいるゾ。 これではイカン。精神的な疲弊は、肉体的な消耗によって解決するのだ。 FBの過去の同日記録掲出サービスで、5年前の新緑詣での記事が現れた。 そーだ、そーだ、自分は新緑を愉しみに生きていたのだ、と我が事ながら思い出した。 近江坂本に行こう。 『碧空に翠蓋をかざす』季節ではないか。 ただ新緑にまみれるだけではなく、からだも痛めつけよう。 近江坂本の日吉大社を目的地に定めた。 日吉大社にはこの季節、何度も行っている。ただ過去の訪問は、画竜点睛を欠いていた。 日吉大社の広大な境内には標高381メートルの八王子山が聳えている。聳えていると言って過言でないほど、山がそそり立っている。 その山頂近くに日吉大社の起源とされている「金大巌(こがねのおおいわ)」があり、その岩を守護するように三宮、奥総社、牛尾宮などの社殿が建てられている。その社殿群は大社の外郭からも八王子山山頂にその姿を認めることができる。 前々から一度は登っておきたいと思っていたのだが、機会を逸し続けて今に至っている。 今日、その負債を清算するのだ。 JR「比叡山坂本駅」から日吉大社へ向かう参道ぞいは、比叡山の僧侶の隠居所である里房が連なっている。信長が各戦場に連れまわした石積み集団穴太衆による穴太積みの石垣が里房を囲っている。沿道の楓の輝きが忘れかけていた安寧と充足の記憶を呼び覚ます。 2020年のNHK大河ドラマの主人公は明智光秀のようだ。坂本は光秀ゆかりの地として旗ざし物が並んでいる。ドラマタイトルは「麒麟がくる」らしい。 イマイチだと思った。 鳥居をくぐり境内に入る。 大社の神獣は猿である。 神猿と書いて「まさる」と読む。 神猿舎には実際に猿がいる。 (マサル君) たぶん、誰もが心中、そう呼びかけているはず。 西本宮から宇佐宮、白山宮を巡る勝手知ったるルートの先に三宮遥拝所、牛尾宮遥拝所を左右に配した登山道の入口がある。 ここからが未踏の山登りである。 |
登山道入口は石段。 段差がある。かなり高い。 最近、気がついたことだが、筆者は右足の股関節におそらく疾患がある。右足で踏み上がると微妙な違和感があるのだ。疲労が重なるとそれが明らかになる。日常生活では露わになることはないが、運動時にそれと気がつくと少し心に翳りがさす。誰もが若者のままではいられないのだ。 石段はすぐに尽き、それなりに幅員のある坂道が始まる。 幅員はあるが、坂の傾斜はかなりキツい。 つづら折れの坂道をハヒハヒ言いながら登る。 後ろから女子が二人ついてくる。 女子に負けるわけにはいかない。 ここで張らなくてもいい見得を張ってしまった。 登山道に入る前に500ミリリットルのミネラルウォーターを買ってバッグに放り込んであるが、当初、口もつけずにひたすら登った。しかし、なかなか山頂にたどりつかない。距離も斜度も想定外だった。 へばった。 やうやう、奥の院エリアにたどり着いた。 ミネラルウォーターは三分の一になっている。もう1本買っておけばよかった。 ジャケットは裏地を通して浸透してきた汗で斑模様になっている。 心臓はバクバクしているし、何よりも立っていられない。岩に腰掛けたが、それでも足りない。全身の力が抜け落ちてゆく感覚に襲われた。 (まずい、肛門が弛んでしまいそうだ) 脱糞だけは避けねばならない。 人は死ぬと、筋肉が弛緩して膀胱や直腸から漏れ出るものだが、死んでもないのに漏れ出るのは嫌だ。あるいは、今、実は、死にかけているのだろうか。(臨死体験中?) 真剣にヤバイと思った。 ジャケットを脱ごうとしたが汗のせいで袖口がひっかかりうまく脱げない。かなりもどかしい状態を何とかクリアして半袖シャツ姿で社殿の石段に横たわった。 麓から吹き上がってくる風が涼しい。日陰になっていた石の冷たさが心地よい。何度も大きく深呼吸をして気息を整えた。 たぶん熱中症になりかけていたのだろう。 冷たい石に横になったのが良かったのかもしれない。 いやあ、無理しちゃいけんね、ホンマ。 琵琶湖を見下ろす景観を堪能して下山。 大社を出るとすぐ脇に「芙蓉園」という茶店がある。 以前もここで庭を見ながら湯豆腐を食べた。 今回も同じ活動。湯豆腐に生ビールを一杯。生き返りました。 気がつけば心の風通しが良くなっている。なんか清清しい気分。今日は正解だったな、脱糞しかけたけど。 |


| 老母のための、恒例「年またぎ温泉ツアー」で久しぶりに天橋立を訪れた。 天橋立は、今、世界遺産登録に意欲的らしい。 域内のあちこちに世界遺産登録を目指すポスターが貼ってあった。 筆者は(世界遺産への道、未だし)との印象を持ったが・・・ 足がやや不自由な老母を連れ歩くと(稼動範囲は極めて狭いが)バリアフリーに敏感になる。 世界遺産は、景観として電線やら看板やらにいろいろ制約があるらしいが、バリアフリーにもうるさいはずなのだ。階段に過敏な拒否反応を示す老母を見ていると、古くからの観光地であるがゆえにエレベーターやエスカレーター、スロープの設置があまり進んでいないことがよく分かる。しかも、その手の世界遺産対策を十分に整えたとしても、それは世界遺産登録申請ができるようになったにすぎず、認定されるかどうかは、また、別の話なのである。 頑張れ!天橋立。 特急「はしだて1号」から天橋立駅に降り立った筆者達を迎えたのは寒波と寒風。 駅からほど近い(と筆者は思っている)飲食店で昼飯を、との筆者の目論見は、寒気で肢の動きが著しく衰えてしまった老母ににべもなく拒否されて頓挫。老母の必殺技『何でこんな仕打ちを受けなきゃいけないの!?』攻撃に、目的のエリアに行かず、絵に書いたような観光地のスタンドで蕎麦を食べた。筆者も「にしん蕎麦」を食べてしまった。蕎麦を食べるなんて何年ぶりのことだろう。もちろんどこに持ってゆきようもないままならぬ感情に流されてのことである。 駅そばの天橋立ビューランドのケーブルカー乗り場にはとても歩きつけないようだったので、投 |
宿前に『もう一歩も歩きたくない』状態の老母をタクシーに押し込み、阿蘇海を回りこんだ対岸にある笠松公園のケーブルカー乗り場前まで乗り付け、とりあえず荒天ではあったが、天橋立のパノラマは経験させ得た。タクシーに乗れば、車内は暖かいし、笠松公園ならばケーブルカー乗り場の前まで乗り付けられる。 阿蘇海はほぼ諏訪湖なみの全周らしい。諏訪湖と言えば、亡父の位牌を守る老母を連れて行った記憶が蘇る。亡父存命中に家族で行った箱根湯元を皮切りに、父没後、諏訪湖、金沢、沖縄、湯布院、道後温泉、鹿児島、神戸、祖谷渓、倉吉、と随分連れ歩いたもんだ。もちろん地元の京都、大阪、奈良、明石は日帰りで幾度も出かけている。 年末年始の旅行は今年で4回目だが、あきらかに老母の体力は落ちている。齢90で自分のことはすべて自分でこなしているのだから立派なものだがもはや距離のある旅行は無理だと判断した。今年が最後になるだろう。 明けて元旦。 昨日の天気が嘘のような青空が広がった。 老母は足の調子が戻らないので宿で温泉三昧。 筆者は久しぶりに天橋立を散策した。 まずは、ビューランドのリフトへ。ビューランドは進化しているような気がする。 晴天下の絶景を堪能し、天橋立全長3.6キロを歩く。途中、冠島と沓島が海面上に浮いて見える蜃気楼に出くわした。冬の寒い日などにみられる景色らしい。 昨日タクシーで訪れた笠松公園に到着。帰路は観光船。元旦の初詣客が列を成す智恩寺を眺めて初詣とする。宿では、蟹三昧の一夜とノドグロ、鮑、ブリしゃぶなど充実の海鮮三昧と丹波牛の一夜を満喫した2泊3日の旅だった。 |

石垣島行13 →back (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
| 沖縄の年、ということにするか 2018年は、老母のツアコンとして年末年始を『わいはー』で過ごして以降、めっきり漂泊と縁遠くなっていた。 何ゆえ?と記憶をまさぐった結果(仕事のせいだ)と気がついた。 前年の11月から新部門の事業を立ち上げていたのだ。 忙しかったから、というキレもなければヒネリもないオチ。 とは言え、その新事業のために4月中に2回も那覇に出張している。 以降、ひと段落つき始めた6月まで『半年も』漂泊できなかった。 6月末には毎年、ダイビング(と言っても体験ね)のために沖縄に行っている。今年も石垣島でもろもろ予約を入れていたのだが、既述のとおり、機材故障で那覇にUターンしてしまった。 その後、七夕にもう一度石垣島に行った。それもまたこの紀行に既述である。 しかし、まだダイビングをしていない。 体験ダイバーの望みは、年に1回、海中浮遊をする。これのみである。 ちゅうことで、9月のアタマに三度、石垣島行を敢行。 ショップのオーナーからも「6月の仇を9月にとりますか」と歓迎をうけ、ダイビング初体験のSを同行し、南ぬ島石垣空港に降り立った。 2泊3日なので弾丸ツアーだが、いいのである。リフレッシュとは、ほんのひと時でいいから日常を忘れることだと思っている。だから時間の長さは関係ない。海の中で浮遊していると本当に頭 |
の中から日常が消え去っている。正確に言うと消え去っていることにすら気がつかない。 今日は、大崎でベタ凪に遭遇。 これほどのベタは過去に記憶ないぐらいのベタ。海面が平面と化していた。 初体験のSが一緒だから、今回は3ダイブなしで、シュノーケリングをいつもよりパチャパチャした。 七夕のときは、宿泊したホテルで、眼前の海を見ながらのモーニングと海岸沿いの散歩で、ちょっとびっくりするくらいの開放感が筆者を包みこんだ。 7年ぶりの黒島をチャリで周回したら何か忘れ物があったことを忘れていた忘れ物が見つかったような(変すか?レトリック)安心感に包まれた。 初訪沖の1996年以外にはプライベートでしか訪れていなかった沖縄に22年ぶりのビジネスフライトが生まれたのも何かの巡りあわせかもしれない。 ちゅうことで沖縄県には、この年5回訪れたことになる。 沖縄の年、ということで、ひとつ。 石垣島では「担たん亭」には2回行けた。「しゃぶしゃぶ太陽」も2回行った。 那覇では「ha-na」に3回、「シェフズテーブルサクモト」に2回、初見の店で「まつもと」と「糸満屋」も得た。充分だ。 後日譚となるが、この後、神ならぬ身ゆえ、想像もつかなかった多忙な日々が筆者を待ち受けていたのであった。 合掌。 |

| JRには「大回り乗車」という日帰りアトラクションが用意されている。 筆者は「鉄」ではないので細かいことはよくわからないが、要するに、決められた区間内で、経路が交錯することなく(同じ駅を2度通過しない)、その日のうちに、途中下車することなく(改札から外に出てしまわずに)乗車した駅の隣駅で降りると、運賃は1駅区間の料金で賄えるという制度らしい。 決められた区間というのが肝で、筆者はそれを知らずに、一筆書き乗車の制度と混交し、大阪駅を出て、福知山に向かい、京都から新大阪で改札を出ようとしたら、区間外ということで莫大な運賃を支払った経験がある。何事も確かな裏付け知識がないといけないということだ。そのときの失敗では、まず、ICカードで入場しないほうが面倒が無くて便利だと知った。新大阪駅で改札を出ようとしたら、『有効時間がなんたら』との表示(たぶん、そんな感じの)が出て、通過阻止をされた。駅員に事情を話し、通過した駅を明示したら、記述のごとく大回り乗車が認められなかった。切符だったら時間管理なんかなかったかもしれない。(無論、悪事を働くことはしません) さて、この決められた区間というのは、仙台、新潟、関東、関西、福岡など全国に幾つかあるので興味のある人はネットで調べてください。 関西では西は「播州赤穂」「相生」「姫路」「加古川」の山陽道ライン、丹波路は「谷川」「篠山口」「新三田」「尼崎」のライン、大阪環状線のライン、「天王寺」から「和歌山」までの紀州路ライン、「和歌山」から「五條」「高田」「桜井」か「王寺」いずれかを経て「奈良」への大和路ライン、「奈良」から「京都」へのラインか、「加茂」「柘植」を経て「草津」に至るライン、「草津」から琵琶湖を一周するラインが区間内となる。 同じ駅を2度通れない以上、盲腸線となる部分 |
は攻められない。(盲腸線とは終点で他の路線に接続しない路線のこと。「鉄」ではないので、そんなもんで、ひとつ。) まず、大阪発、和歌山経由を試みたところ、和歌山での乗り継ぎが3分で、何番線の電車に乗り換えればいいのか、迷ってしまい、乗り継ぎに失敗し、さっそく撤退した。 乗り継ぎ列車の発車番線はしっかりと掌握しなければならないことを知ったのである。 此度の出陣、2度はあらじ!と信長の美濃攻めのような気迫で臨んだ第3次攻撃。 時間的に紀州路を組み込むと1時間の待機が生まれるため紀州路は放棄。 10時24分に「大阪」を出発した。 10時45分に「天王寺」 「王寺」「奈良」(奈良っていつの間に高架になっていたの?)「木津」を経て 11時34分に「加茂」。11時42分発の「柘植」行きに乗り換えた。 途中、「平城山」駅で新発見。「平城山」と書いて「ならやま」と読む。無理だ。 12時38分に「柘植」。13時1分発の「草津」行きに乗り換えた。 電車は忍者の意匠が施されている。 甲賀の里なのだ。 ちなみに「甲賀」と書いて「こうか」と読む。濁らないのね。 13時47分に「草津」。13時51分発の新快速に乗り換えた。 14時35分に「長浜」。15時11分発の「近江塩津」行きに乗り換えた。 15時34分に「近江塩津」。15時40分発の湖西線経由新快速「姫路」行きで 16時57分に「京都」通過。 17時22分に「新大阪」着。 運賃は160円。 読書三昧の1日を終えた。 |
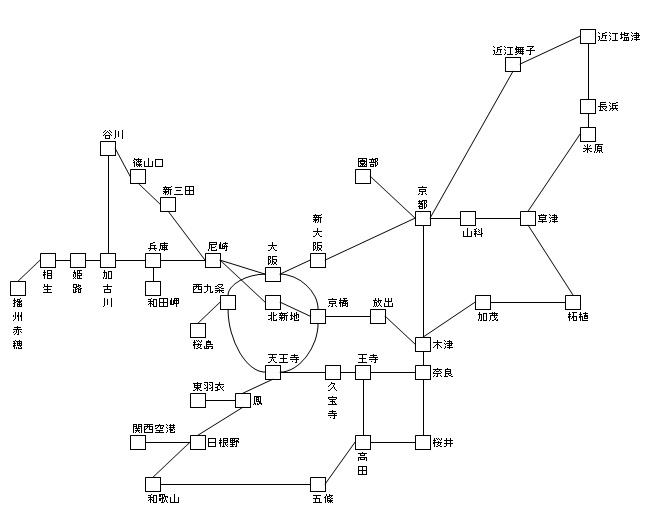



| 漂泊不足で息が詰まりかけていた。 このままでは窒息死するかもしれないから救急救命のために札幌へ飛ぶことにした。 札幌を起点にしたハブ&スポーク戦術を実施するのだ。 ハブは札幌、新千歳、スポークは大雪山系層雲峡と登別。 まずはハブとなる札幌に夜、到着。 「たる善」「だるま本店」「バーVespa」で酒食を愉しむ。 翌日は、大雪山系層雲峡温泉に向かう。 大浴場が気にいっているホテルがそこにある。 「野口観光グループ」所有のリーズナブルな「朝陽亭」というホテルだ。 チャイニーズの団体さんが多い大バコで食事もバイキングなんだが、大浴場が3種類あってこれが気にいっている。風呂に浸かることが主目的なので酒食への拘りはない。それにバイキングは糖質制限修行僧にとっては危険物件を自主的に避けることができるのでむしろありがたい。 「野口観光」は札幌を起点にして自社所有の各温泉地へバスで送迎してくれる。まさに今回のハブ&スポーク戦術のためにあるようなリゾート会社だ。保有している施設は函館、層雲峡、洞爺湖、北湯沢、登別、札幌定山渓、函館湯の川などにリーズナブルタイプからハイグレードタイプまでいろいろなホテルが揃っている。 札幌から大雪山系に向かうには、車を転がせない筆者の場合、札幌から旭川に出て、さらに上川町に向かわなければならず、交通費だけでも往復で1万円近くにはなる(JRの特急などを使っての話だが)送迎経費は、宿代に含まれてはいるのだろうが、札幌、層雲峡間、車で4時間を往復で送迎してくれるのはオトク感がある。 「朝陽亭」は3回目の投宿なので、過ごし方も心得ている。 到着時すぐと、深夜、早朝と、湯船が空いている時間帯を見計らって温泉で四肢を伸ばし、3種の浴場を満喫した。 札幌への帰路の出発前に眼前に聳える黒岳(標高1984m)のロープウェイに乗って5合目へ。ロープウェイの始発は6時だったが、すでにそこそこのトレッカーが並んでいた。5合目からはリフトで7合目まで登れる。ロープウェイは7分、リフトは15分、ロープウェイ駅からリフト駅までは少し歩くのでざっくり30分程度、往復では1時間を見なければならないのでちと慌しく動いた。 早朝の大雪山、気温は20度には届いていないだろう。この日の最高気温は25度だった。大雪山系の山襞には残雪が輝いている。8月になると |
消えると言うが7月末の今まで残っているのもすごい。 ロープウエイからリフトに乗り継ぎ、ひとり、清涼な山の空気を吸い込んでいると、植生が高山のそれとなり、野鳥の囀りが抜けるような青空に響き渡っていた。 7合目ではリスがうろちょろしていた。 山を降りたら、バスが待っている。再び札幌に戻る。 今宵は、フレンチの「TATEOKA TAKESHI」「バー・プルーフ」「バー・Vespa」で酒食を楽しむ。 翌日、再び「野口観光」のバスに揺られて登別へ行く。 出発が昼過ぎだったので、すすきのの「カレーショップ・エス」でスープカレー(もちろんライスはヌキ)、バス待ち合わせの札駅で「タルタルハンバーグ牛忠」で軽く酒食。 一昨日と同じバス利用者の待ち合わせ場所には筆者ひとりきり。 「今日は貸し切りですね」 黄色のスタッフジャンパーを着た受付係りの女性にバスまで案内されながら言われた。 「洞爺湖の方は、インバウンドも含めてパンパンだよぉ」 ドライバー氏と受付係りの車外での話しが聞こえる。 洞爺湖あたりがインバウンドには一番人気なのか。 トマムはどーなんだろう? 登別「石水亭」は、これまた「野口観光グループ」のリーズナブル温泉宿である。 資本が同じ、宿のグレードも同じとなれば、浴場の造りも似たようなもので、逆に初めての投宿だが、勝手知ったる感があって気楽に過ごせる。 夜はお約束のバイキングで、これまた微妙な違いはあるが層雲峡のそれとほぼ同じである。 到着時、深夜、早朝と、湯船が空いている時間帯を見計らって温泉で四肢を伸ばす。 翌朝、登別の温泉街を散策する。 熊牧場も早朝のこととてまだ開いていない。一昨日の層雲峡とは真逆の天候。道南は霧が多い。霧雨が山と温泉街を包んでいる。 帰阪の日なので、札幌駅へのバスで、途中、新千歳空港に立ち寄ってもらう。札幌駅へは無料なのだが、新千歳で降りる場合は500円が必要となる。空港利用料でも請求されるのだろうか。 それでも、札幌から新千歳までのエアポート快速でUシートを利用するよりも安い。 新千歳空港で、「円山公園竈」「バー・ジアス」で酒食を取り、今回の漂白を終える。 |

| 石垣島の周辺に浮かぶ離島は、竹富島、小浜島、黒島、西表島、波照間島、由布島、鳩間島、新城島、嘉弥真島、与那国島と、かなりある。 未踏の島は、由布島、嘉弥真島、与那国島だが、今回はそれらに向かうことなく7年ぶりに黒島に渡った。 ハートアイランドとも言う。 ハートの形をしているから。 人口よりも牛口が多い。 石垣牛の肥育の多くはここが担っている。 石垣島の離島ターミナルから高速船で30分。 離島ターミナルをハブとして各離島に足を伸ばす船会社は安栄、八重山、平田、ドリカンの4社が主だったところ。感覚的には路線バスのようなものだ。ただし、バスは沈まない。 実は、久しぶりという点ではまったく同じ波照間島に向かおうかと思ったのだが、石垣島にはまだ2日ほどの距離にある台風8号が急速に勢力を増していると聞き、さらに、黒島に向かうカップルが乗船券売り場で「今日はたぶん遊泳禁止ですよ」と言われていたので即座に断念した。 かつて波照間島に渡ったとき、外洋に出たとたん、高速艇がガブルガブル。「転覆」とか「沈没」とかの単語が脳裏に浮かぶ浮かぶ。ちゅう経験をしていたので、波照間に行くときは絶対に海がおとなしい時と決めているのだ。 黒島行きのチケットを買った。 黒島は、石垣島から見ると、眼前に浮かぶ竹富島の裏側にある。 石垣島、竹富島の間の海は環礁に囲まれた比較的穏やかな海原が広がっているが、その裏側に出ると、さすがに海がうねりだす。しかも今日はうねりが大きい。高速艇が途中、何度もエンジンカットをしたり出力を落としたりして、大きな波をやりすごしている。 (波照間行きにしなくて正解) なにしろ、石垣、波照間航路は欠航率も高い。 無事にたどり着いても、帰ってこれなくなる可能性がある。 黒島に到着。 |
ここではレンタサイクルで島をのんびり周遊するしかやることがない。 前回もそうだった。 しかも同じ船で渡って来た僅かな人々と島のあちこちで何度も出くわすのである。なにがなし連帯感まで生まれるのである。 今回、前回と違ったのはレンタサイクルに電動アシストが備わっていたこと。 小浜島でもサイクリングをしたことがあるが、あの島は高低がそこそこあり、かなり消耗した。 それに比べると黒島はフラットであまり疲れなかったような記憶があったのだが、楽をするために電チャリを借りた。 漕ぎはじめて気がついた。 なだらかではあるが、緩~い坂道がけっこうある。それに島を周回するため、方向によっては向かい風となる。その風がかなり強いのだ。上り坂と向かい風のWパンチに出会い、電チャリを借りた幸運を神に謝した。 島は7年前と変わらない佇まい。 プズマリ、西の浜、仲本海岸、黒島灯台、幾つかの御獄(ウタキ)、伊古旧桟橋、島の周囲は出し惜しみのないコバルトグリーンの海。牛口が多いから『ここは北海道か?』と見まがうばかりのフラットな牧草地が広がるのどかな景色。3時間、チャリを漕ぎ、気がついたらかなり汗みずくになっていた。同時に久しぶりに爽快な気分も得られた。島がちょうどいい大きさなのだ。3時間で島を1周半した。無論、日焼け止めは最強のSPF50+を何度も塗っている。 電動アシスト自転車がレンタサイクルに常備されているんだったら、小浜島にも今度、行ってみるか。 南の島でアクティブに過ごすときには汗だくになるので、1日のうちに着替えが上も下も一度は必要になるから、そのつもりでいなけれいけなかったのだとホテルに戻って気がついた。シャツは汗みずくになったし、濃いブルーのズボンは腰まわりが白く塩を吹いている。汗がね。そこまで出ます。 |

石垣島行12 →back (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
| 2週間前、謎のUターンで潰えた石垣島行だったが、実は筆者には今年、隠しダマがあった。 11年前、初めて石垣島に上陸した2007年。 ちょうどその日は七夕。 夏の大三角形を眺めながら、ホテルのテラス席でオリオンを呑んだ。海風がオリオンビールの旗をたなびかせ、ホテルマンがテラス席の客ひとりひとりにことわりを入れた後、照明が落とされた。市街地から離れた海辺のホテルは天の川と煌く星座たちの天蓋に覆われた。 胸ときめいたそのときの体験は、今も筆者の脳裏に住み着いている。 再訪の想いは強いが、ウイークデーの真ん中の漂泊はなかなか難しい。泊は、金夜と土夜を狙うしかない。かつ、7月第1週の日曜日は、仕事の都合で地元を離れるわけにはいかない。つまり、七夕の夜7月7日に石垣に滞在できるのは7月1日か2日が日曜日のときだけなのだ。 2日が日曜日だと、金曜の夜が七夕になるので、実に慌しいことになる。 今年は1日が日曜日。7年に一度の千載一遇のチャンスだった。だから、かなり前から石垣行の予定をたてていた。 ホテルもあのテラス席のあるリゾートホテル。 2泊しかできないが、ひさしぶりに離島でバカンスを。 金曜日の夜、石垣に到着する那覇乗り継ぎの便は2週間前のあの忌まわしいソラシドエアだった。那覇空港混雑とのことで伊丹発那覇行きの便も1時間延着。石垣行きの乗り継ぎ便も30分の遅延とのアナウンスがあった。 嫌な予感がする。 搭乗口にはいっかな機材が現れない。 すると搭乗口の変更サインが出た。 ボーディングブリッジではなく、バス移動となった。あの黄緑色のソラシドエアの機体は別の駐機場にいたのだ。アナウンスのとおり、30分遅れで那覇をテイクオフした機は、途中、Uターンすることなく石垣島にランディングした。 |
空港から市街地に向かう途中にヤラブの並木道がある。硬くて渋い実は何の役にもたたないが、この並木道をくぐりぬけると石垣にやって来たとの思いが強くなる。 知己の弁護士から石垣島のしゃぶしゃぶ屋の情報を得、予約していた時間にちょうど間に合うタイミングだった。 「しゃぶしゃぶ太陽」という店で寛ぐ。大将との話しも愉しく満喫できた。 初日のホテルは、繁華街のホテルだったが、明日は11年前のリゾートに泊まる。 朝、チェックアウトしたら離島ターミナルのコインロッカーに荷物を放り込み、とりあえず離島へ渡海。 昼すぎ遅くに離島ターミナルに戻り、ホテルにチェックイン。 2週間前、キャンセルした「坦たん亭」で石垣牛を堪能する。 部屋のテラスから星空を見上げ、願いをかなえた翌朝は、ホテル前のビーチを散策。 眼前に浮かぶ竹富島、その後方に西表島の島影。エメラルドグリーンに輝く海原と幾隻ものボートや離島と石垣を結ぶ高速船の姿。輝きを増しつつある朝日を浴び、薄いピンクに染まる水平線の向こうの白い雲。 まさに、これこそが石垣島の魅力という瞬間。 今年は仕事がたてこみ、いつになく漂泊の機会がなかった。満を持した2週間前はトラブル続きで、顔に瘡蓋の烙印までおされる始末。そのノリベンジは、僅かな滞在ではあったが、心の底から満喫して、空港に向かった。 ヤラブの並木道を抜ける。 空港の搭乗待合室の売店では宮古島のダグズバーガーのダグズシーフードツナサラダが売られている。『世界で一番高価なツナ』と自ら謳いあげる瓶入りのツナを購入。 帰路は関空への直行便だった。 さらば「南(ぱい)ぬ島」 |

| 那覇で過ごすことになった。 計画なら、ない。なにせ石垣島でダイビングをするつもりだったのだ。 その計画がパーになった今、何をする? 最近、古琉球の戦国時代に興味を持ち、訪沖のたびに時間を見繕っては、関連の場所を訪れていた。 不測の事態ではあるが、奇禍を奇貨居くべしとして、何箇所か回ってみることにしよう。 百貨店リウボーの中に沖縄歴史博物館があるので、まずそこから。 おもろまちに沖縄県立博物館があるので、次はそこに。 沖縄県立博物館の愛称は「OKIMU(おきみゅー)」 そう言えば、大宰府にあった九州国立博物館は「きゅーはく」だったな。南の国の博物館の愛称はどことなく可愛い。 「おきみゅー」の外観はグスクの石垣を模しているようだ。 かなりの収穫を得た。 久米三十六姓発祥の久米村の碑を訪れ、波上宮を海側の波之上臨港道路から眺める。参宮もした。 古琉球は、グスク時代と呼ばれる各地の有力者(「按司(あじ)と沖縄では呼ぶ)の興亡の歴史を紡いでいる。三山と呼ばれる三つの王国が覇を競い、最終的には、尚巴志が琉球を統一する。尚巴志は小国の按司から中山の国王となり、北山、南山ふたつの王国を滅ぼす。彼が中山の主邑としたのが首里であった。首里城を中心に栄えた街並とは別に、当時、明、朝鮮、日本、南蛮との間で繰り広げられた交易の基地として那覇が栄えることになる。 当時、那覇は島だった。 ステーキ街で有名な辻や、既述の久米がその島内にあり、集落を形成した。 サンゴの環礁に囲まれた琉球は、座礁の危険があり、大型船舶の停泊適地が少なかった。那覇(島)の南東方向の島影に停泊地を作り那覇港とした。今の奥武山の手前あたりである。 その頃、明から渡ってきた渡来人は主に福建 |
省出身で、彼らは島に村を作った。その仕事は琉球と明の間の交易事務と船舶の運用だった。集落名を久米村(くにんだ)と言う。ギルド的なその集団を久米三十六姓と呼んだ。 琉球を統一した尚巴志の懐刀となる懐機(かいき)も、久米村出身の明人だった。 懐機は、尚巴志に命じられ、那覇(島)と首里を結ぶ道路を建設する。那覇から安里までの浮道を長虹堤(ちょうこうてい)と呼ぶ。 歴史探訪を済ませ、瀬長島に渡る。 日本最南端の駅ゆいレール赤嶺駅前から瀬長島ホテル行きの無料送迎バスが出ている。 2015年に開業した「ウミカジテラス」のある島だ。島と言っても海中道路で繋がっているので陸路で渡れる。 「ウミカジテラス」は、島の北面にあたる傾斜地に造成された商業施設で、全体を白で統一したなんというか、いかにもエーゲ海っぽい雰囲気を狙ったちゅう感じの、オジサンはたぶん消費のコアターゲット層でないことだけは確実な所だ。 ただし、那覇空港の滑走路の南端にあり、離着陸する民間のシップや空自のファイターを間近に見ることができるので、そこは買いである(筆者的に)。また、ウミカジテラスの裏側にある斜面の公園は実に広闊で、南国の空と海の青、雲の白、草木の緑のコントラストをのんびりと眺め、時の移ろいをしばし忘れることができる憩いの場である。 陽が沈み始めたら、ゆきつけのビストロのシェフと地場の居酒屋に向かう。 首里城の建つ丘陵の川を挟んだ反対側、南西面の斜面にある店。周囲は住宅地だし、観光客が無目的にここに足を踏み入れることは絶対にないエリアだった。 シェフの親族が作る、シェフの苗字と同じ名の泡盛をショットで飲み続け、定休のビストロに戻って、ワインを浴びていたら、しこたま酔った。帰路、前のめりに倒れて地面とキスする羽目になったのは、いかにも今回の不運の総決算のようで、これはこれでアリか。いや、ないな、断じて。 |

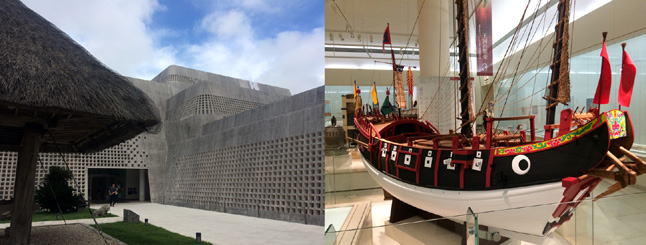

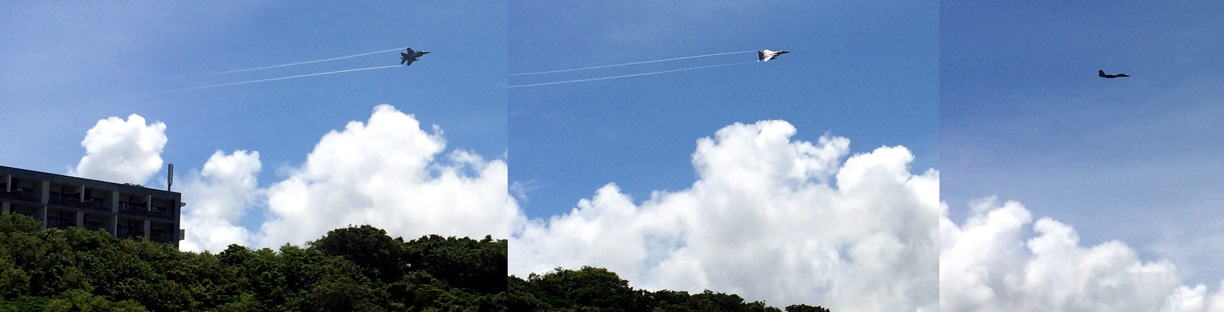

| 久しぶりにエアでトラブル遭遇。 これで遭遇回数は5回となった。 最初のトラブルでは、ガスによる視程不良で伊丹発仙台行きが、仙台上空を2、3回旋回した後、着陸を断念し、羽田にダイバートした。 2回目は、東北大震災のとき。 羽田発福岡便が欠航となった。 3回目は冬の札幌。新千歳発伊丹行きが、欠航となった。 その日、記録的な降雪が新千歳を襲い、多くの便が欠航となった。 自分の予約機は、まだ2時間遅れとの表示が出る中、それよりも前の便が次々に欠航表示となるのを見て、速攻で翌日の便を予約し(購入はせずに)札幌駅前のホテルの予約もとった。 もし、飛べば、エアの予約はキャンセルすれば済むし、ホテルもキャンセルの電話を入れれば、この状況下でキャンセル料は取らないだろうと判断した。 結局、予約機は欠航となり、迅速な機動が我が身を救った。 4回目は伊丹へのランディングが天候不良で関空になったことだが、これは些事と言える。 そして今回、那覇空港乗り継ぎで石垣島に行く予定だった。機材遅れですでに出発は1時間の遅延。それでも1時間後にはANAと共同運航のソラシドエア737-800のF席に身を沈めた。 夕刻、那覇から石垣に向かう機のF席は真横から西日を受ける。 その西日が動き始めた。 インディージョーンズ最後の聖戦でハリソンフフォードとショーンコネリーが飛び乗ったヒンデンブルグ号でのシーンのようだ。 筆者の右頬にあたっていた南国の強烈な日差しが、機内の壁をゆっくりと斜めに刷き始め、やがて反対側のA席に差し込むようになった。そしてその位置で太陽は固定した。 つまり、180度旋回をしてそのまま飛んで |
るということだよなとブツブツ言っていたら、機長からのアナウンスがあった。 「当機は那覇コントロールからの指示により、部品に点検が必要になったため、那覇空港に引き返します」 やっぱ、Uターンしてたんだ。 当たったところでちっとも嬉しくない。 那覇空港に戻った。 部品を点検してもう一度飛び立つ一縷の期待もあえなく、機長からのアナウンスに一蹴された。 「皆様を、地上係員が誘導し、払い戻しの手続きなどを3階の3番カウンターで承ります」 仙台のときと同じだな。 石垣島の滞在は2泊しか予定していなかったから、明日、代替便が飛んでも、朝イチから予約していたダイビングは無理。あきらめるしかないか。あるいは、夜、代替便が飛んでくれるのか?いろいろ思い悩んでも時間の無駄。こういうときは迅速な機動である。 3階3番カウンターに一番乗りし、係員からの説明を聞く。 今日中の代替便は無し。今日のこれ以降の便も満席、明日も夕方の便までは満席とのこと。払い戻しをしてもらう。何かの不具合があったのか、払い戻し手続きに手間取っている。筆者の後ろにはすでに長蛇の列。ダイビングのキャンセル、石垣島のホテルのキャンセル、石垣島での夕食予約のキャンセルを済ませていたら、やっと手続きが終了した。今回は宿泊料と称して20000円の現金を渡された。 カウンターを離れ、2連泊できる那覇のホテルの予約を完了し、ホテルに向かったのは21時。ホテルのそばに行きつけのビストロがあるので、そこに電話。 「ヴォンソワール、サカノさーん今どこ~?」 シェフは筆者の名前を間違えて覚えている。 「すぐそばです。これからひとり入れますか?」 |
| 年末年始はやっぱ、ワイハーだよね。 ちゅうことで大晦日の昼、大阪を発った。 現地の気温は8.9度。 比較的温かい。 最低気温は1.6度だから、朝、夕はちょっと冷えるようだ。 予報では、降雪というサインも出ていたが、さすがに雪は降らなかった。 初めてのワイハーまで新大阪から「スーパーはくと」で3時間強。 終点「倉吉」から車で10分程度で「はわい温泉」に到着。 目的地「はわい温泉」の出島にある「千年亭」に旅装を解いた。 「はわい」の地名は「羽合」に由来する。鎌倉時代まで遡る由緒ある(?)地名らしい。 パスポートを持っていない筆者がハワイなどに行くはずもないのである。 鳥取は何度か訪れていたが、倉吉は初めてだ。 2016年に震度6弱の「鳥取地震」で白壁土蔵群などが被害をうけた倉吉。 断層型地震で、ズレた断層を境に被害の明暗がくっきりと分かれたと乗車したタクシーのドライバーが言っていた。 「まだブルーシートのところもありますよ」 1年2ヶ月たっても復興は道半ばのようだ。 せめて温泉消費で復興の後押しをしよう。 年の瀬の帰省ラッシュのせいか「スーパーはくと」はかなり混んでいた。 指定席が3号車だったので、2号車の後ろの車輌に乗り込んで座席に座った。 後から来た家族連れがもじもじしている。 |
座席の位置がわからないのか、チケットを見てあげたら、驚天動地の事実が発覚。 3号車だと思って乗車したこの車輌は「増2号車(まし2号車)」なんですって!人の座席に居座っていたわけだ。謝罪して撤収。もう1つ後ろの車輌に移動した。 編成が、1号車、2号車、増2号車、3号車、4号車・・・となっていた。 なんなんだ?増2号って? 1、2、3、4、5、6と順番に号車を振るわけにはいかないのか?「鉄」ではない筆者には了解できない出来事だった。 はわい温泉は、日本海から2キロほど内陸にある、海と川で繋がっている汽水湖の東郷湖のほとりにある。 絶景というほどではないが、湖畔の眺めはそれなりに広寛で、海鳥が飛び交い、都会の雑踏を離れた解放感が我が身を包む。 温泉がよかった、露天と内湯の大浴場と浴場が男女日替わりの入れ替えとなり都合6種の風呂に浸かりまくった。日帰り入浴もあるので、日中は混雑するが、早朝と夜は、ほぼ独り占め状態のときもあり、満喫度は高い。 部屋の内湯の半露天風呂は老母がいたく気にいり、メイクルームの時以外は一歩も部屋を出ず、日がな一日まさに文字通り、入り浸っていた。 鳥取の宿だから、夜はズワイガニ。 境港であがったズワイをひとり1パイずつかぶりつき、それ以外にも刺し身、天麩羅、茶碗蒸し、雑炊とカニまみれの一夜を過ごす。 |
鹿児島行7 →→→back 鹿児島行1 2 3(疾風怒涛編) 4 5 6 7
| 師走の第二日曜日、博多から乗車した「さくら543号」は空いていた。 前日、社用で入福したが、事前予約での宿がぜんぜん空いていなかった。海外の宿泊検索サイトはあまり使いたくなかったがやむを得ず使用し、博多駅前に何とか予算内のホテルを抑えることができた。 (なんでか?)と思っていたが、中部国際空港セントレアから福岡空港に降り立ってみれば、土産物店に「嵐ファンの皆様、博多へようこそ」のPOPが。8日の金曜日から3日連続でコンサートがあったのね。それで納得。 なかなかにバタバタした毎日が続いていたので、ちょっと漂泊することにした。 この「さくら」は東に向かっていない。 まっすぐ南下している。 35分ほどで熊本。 博多、熊本間は、京都、名古屋間並に近い。 熊本に停車。 降客のほうが乗客よりも多い。 新幹線は、博多、熊本間のシャトル便のようなものかもしれない。 さらに1時間弱で鹿児島中央に到着。 博多、鹿児島間は1時間26分。 久しぶりの鹿児島。 今回の目的は、ただ1点。温泉に浸かること。これのみ。 筆者の偏見と独断に満ちたランキングでは、『景色のいい露天風呂』部門、暫定日本一が城山観光ホテルなのだ。 だから城山観光ホテルに泊まる。 ただ、難儀なことにホテルが城山の頂上にあり、一旦投宿すると下界に下りるのが億劫になる。 |
夜はホテル内の施設を使うことにする。 目的専一主義を掲げて夜の愉しみはある程度我慢しよう。鹿児島ではトップランクのホテルだから施設もそれなりの水準ではあるのだ。 ここは、朝のバイキングの評判もいい。しかし、筆者は朝を食べないから、この点はあまり関係ない。 チェックインが14時にはできるので、早めに宿に入り、速攻で露天風呂に浸かる。優れた作戦は常にシンプルなのである。 とは言え、昼前に入鹿したのでホテル入り前の昼食で食べる愉しみの保険をかけておくことにしよう。夜がものすごくハズレとは思っていないが・・・ 「あぢもり」の「黒しゃぶ」を食べに行くことにした。 飛び込みではたぶん入れないと思ったので予約を入れた。開店早々の11時半に入りたかったが、案の定、その枠は埋まっていて12時半からの食事となった。 糖質制限修行の身というのに、食い意地が勝って、ヒレカツとコロッケのつくコースを頼んでしまった。 (どーしたー?) 一口、二口だけにするかと悩んでいたが、思いのほかミニサイズだったので残さずに食べてしまう。しかし、健常人だったら、このサイズは少しもの足らんだろう。 まあいい。「黒しゃぶ」と称するこの店の黒豚しゃぶしゃぶはデェ好きだ。食レポは前回のこの記事で。 2時にホテルにチェックインし、1時間おきに露天風呂に浸かりにゆく。 早朝も含めて4回入浴し、カタルシスを得た。 |

| 市電は「十字街」電停から分岐して「函館どつく前」行きと「谷地頭」行きに別れる。 「谷地頭」まで行って駅から歩いて15分程度で立待岬だ。 岬への坂道は、冬期路面凍結のため車はすでに進入できない。 坂道を登ると、石川啄木一家の墓碑が海を眺める墓地の一画にポツンと佇んでいる。文筆の才を生涯の借金形成に浪費し、知人、縁者から今なら1500万相当の借財を築いた啄木は、けっして模範的社会人ではなかった。だが、その才を惜しみ早世を弔ってくれる友人達に恵まれたのは、その人柄に幾ばくかの愛すべき徳性があったのだろう。 啄木の墓の先、坂道がその先に浮かぶ空から身を離すように下り始めると、眼前に立待岬が現れる。 多くの北海道の岬がそうであるように、風浪は身を切るように鋭く、強い。眼下に岩を噛む波頭は白く猛々しい。見渡す限り周囲に人の姿はない。岬を周遊して市内に戻る。 昼、函館山へ。 函館山の標高は334メートル。山頂展望台までのロープウェイは昼は空いている。夜景の時間になると混むらしい。筆者は夜景の時間は酒食を楽しんでいるから、夜景にはとんと縁が無い。 十字街に戻り、市内に17店舗を展開するご当地バーガー「ラッキーピエロ」ですり替えバーガーを食す。バンズを持参の低糖質のパンに目にも留まらぬ速さですりかえるのだ。在函中、この十字街銀座店と函館駅前店を利用した。やはり、夜の酒食を楽しむなら昼はこの程度に抑えるべきだ。 |
神戸北野のフレンチ「ル・パッサージュ」のシェフと知己であったことから、過去2回ほど訪店していた「ル・プティ・コション」が1ヶ月前に店をたたんでしまったことを、予約時の電話でシェフ本人から聞かされた。喪失感を埋めるべく新しいフレンチを求めた筆者は「ロワゾー・パー・マツナガ」を訪れた。五稜郭公園前電停よりさらに「湯の川」方面に2つ「柏木町」電停から5分ほどの住宅街の一角に店はあった。 冬の北海道の日没は早い。 すでにあたりは闇に包まれている。住宅街を貫く街路は街灯も少なく人影もない。11月にしてはいつもより早い降雪が北の国特有の寂寥感をいや増してくれる。背後から、メインストリートを通る市電の鉄路を穿つ音が遠く響いてくる。なぜか「千と千尋の神隠し」を思い出した。 ワインをペアリングでオーダーし、好みを聞かれても、おまかせで通す。しかし、思わずサンテミリオンが好きなことを漏らしてしまったのはソムリエの話術の巧みさか。「それではサンテミリオンをお持ちしましょうか」との申し出を丁重に辞し「薦めてもらうもので知見を広めたい」と応える。最後にソムリエが持って来た2本のうち1本を選んだら、サンテミリオンに似ていた。似たものを持ってきたわけか、とすればもう1本を選んでも、きっとサンテミリオンっぽいものだったに違いない。こういうサービスは心に残る。楽しく時を過ごして店を出る。ソムリエやフロア担当と一緒に見送りに出てきたシャフは「千鳥」の大悟に似ていた。 |

| 弘前から奥羽本線特急「つがる」に乗って新青森まで30分。 新青森から新函館北斗までは北海道新幹線「はやぶさ」で1時間。 新幹線効果か、この日、筆者にとって青森と函館が観光圏としてひとつになった。 地元ではもともと相互に親近感はあったかもしれないが、かつて筆者は東北旅行と北海道旅行をカップリングしたことはなかった。青函連絡船の時代は海を越えるだけで4時間半はかかったし、青函トンネル貫通後も青森、函館間は特急で2時間だった。新幹線駅が本土も北海道も新駅で、在来の基幹駅までの乗り換えがあるため実質的にはそれほど短縮されていないのだろうが、感覚的には障壁が取り払われたように感じるのである。 青函トンネルに入る前、津軽海峡の沿岸をはやぶさは疾駆する。 新幹線のことゆえ眺望はそれほど楽しめない。 はるかに、降雪に霞む海岸線が見えるのみ。 青函トンネル内の速度は在来線のそれとなる。海峡を抜けるのに30分程度。瀬戸大橋と比べれば青函トンネルに見所はない(あたりまえか)。景色を楽しむならトンネルより橋の方がいい。 新函館北斗、函館間は「はこだてライナー」で15分。新函館北斗までの運賃で函館まで区間内だと勘違いしていたため、一旦、改札を出て切符を買わねばならない羽目にあいつつも、昼、函館に到着。 空港からバスで市内に入るよりも、鉄路で函館駅に降り立つほうが気持ちが高揚する。 最近、五稜郭そばに宿をとることが多かったが、久しぶりに駅前のホテルに投宿した。 |
飲食店は、五稜郭公園前周辺に多いので、夜はやや不便だが13階に大浴場があるこのホテルで湯につかることにした。13階建てはこの地では高層の部類だ。眺めも楽しめる。「旅人の湯」と銘打たれたちょっと黄色く濁った湯は、筆者が利用するときはいつもガラガラだった。四肢を伸ばして湯を独り占めした。 日常の昼食が非常に軽くなったため、旅先で、往時のように欲望のままに食いまくることができなくなってしまった。夜の愉しみが何割ほどか落ちてしまうのだ。中途半端な午後ならば、そのまま何も食べずにすごすのだが、この日は正午近くに到着したために、欲が湧いた。 「函館ビール」に行って「社長のよく飲むビール」を飲もう。 函館駅前から電停で二つ目の界隈にある。歩いてゆける。朝市の通りをまっすぐ進めばいい。ただし、この日降雪が著しく、視界を遮るほどの風と雪が筆者の顔を撃つ。機能的にはまさにこのためにある冬靴を正しい使途で今季、初の使用ができた。いつもはレインシューズがわりに使われているので靴も本望だろう。 アルコール度数10%、モルトが通常の2倍の「社長のよく飲むビール」と「地ビール4種の飲み比べセット」で3皿ほどのつまみを頼む。店を出る頃には雪が止んでいた。 夜、五稜郭公園前電停のそばの「開陽亭本店」へ。時化のためイカが入らず、活イカは食べられなかったが、カニ味噌豆腐、牡蠣フライ、毛蟹を楽しむ。甲羅酒も作ってくれて満喫度アップ。 翌朝、立待岬へ行く。 |
| 「到着地の天候は雪。気温は零度です」 20人にも満たない乗客を乗せてボンバルディアQ400はタキシングを開始した。 プロペラがすぐ横で回っている。 あまり気持ちがいいものではない。 歯医者で、施術中にドリルがはずれたら・・・?などという恐ろしい妄想にかられることがあるが、こいつだったらそれ以上のスケールの惨事に見舞われるな、などと、とにかく高速で回っているものが外れるシーンを恐怖する性格は変えられない。 ANA保有の一番小さい機材だ。当然のことながら地面は近い。 離陸を開始すると、ジェットの時よりも速度感がある。 レシプロ機の滑走距離は短い。 V1・・・VR・・V2。 V1はもう離陸をやめられないスピード、VRで機首上げ、V2がテイクオフ。 機長と筆者はこのとき一心同体である。 軽い。 機は、ふわりと地上を離れた。 半分は、筆者のおかげである。 巡航高度に達するまでかなりゆれた。大陸からの寒気団が北日本を覆っている。その前衛が関西にもかかり始めていた。 クリティカル11を乗り越え、ボンバルディアは巡航高度に達した。クリティカル11とは離陸時の3分、着陸時の8分、航空機事故の発生確率が高い時間帯のことだ。事故の8割がこの時間帯に集中すると言う。 眼下は一面の雲海。雪雲が広がっている。典型的な西高東低の気圧配置で青森空港にランディングしたときには気温が氷点下1度になっていた。空港からバスで弘前まで1時間弱。途中の道路標識では氷点下2度となっていた。 9年ぶりの弘前である。 9年前に訪れた割烹と言うか、居酒屋と言うか |
「津軽路弥三郎」の暖簾を潜る。 カウンターに座る。前回もカウンターだった。 カウンターは5席程度しかないが奥の座敷は広いのだろう。その日はどこぞの先生たちの宴会で50人の酔漢の嬌声がカウンター席にも届いていた。 「どちらからですか?」 女将さんに聞かれた。 「大阪です」 「寒いでしょう?こっちは」 実は真冬の北海道にちょこちょこ出かけているうちに北国の寒気に強くなっていた。 しかし、ここは期待に応えなければならない。 「寒いですね~」 これが正しい「忖度」の使い方である。 この日は50人の団体さんのために、料理もあらかじめコースで、ということだったので、前回味わった皿を頼むことはできなかった。 隣に座った常連さんとの話しが弾み、店を出るときには女将さんから切ったりんごをサランラップに包んで数切れ渡された。東北ってのはこういうところがある。それが筆者は好きだ。 朝、弘前城を散策。 雪灯篭祭りのときに転倒した場所を数箇所、思い出しながら場内を歩く。祭りのときとは逆に追手門から東門へのルートをとった。 本丸前の「杉の大橋」の欄干の赤が雪の白と対蹠的で美しい。 朝の弘前城は人影もほとんどない、深閑とした佇まいの中に昨夜来の降雪で薄く雪化粧をした城内は美しい。空気が澄んでいる。東北でのみ感じる城下町の凛とした気色が、忘れていた東北への憧憬を思い出させてくれた。 やっぱ東北の城下町はいいな。 雪雲の裏から、どんよりと濁った黄色い目玉のような太陽がこちらを盗み見している。これもまた雪国らしくていい。 |

| 46年ぶりだ60年ぶりだとの東京での寒気を伝えるニュースを大阪で見せられ続けた10月の中旬。 避寒という訳ではないが沖縄に向かった。 最近少し慌しくなった日常から距離を置いて気分転換を図るのだ。慣れているつもりではいても沖縄行ということで気分は高揚している。 11度だ13度だと言っている関東圏よりは4、5度は気温が高い関西だが、日中20度を越えない日が多くなり、季節の移ろいは実感していた。 でも、那覇は31度。 どーゆー恰好で行くか? 那覇行きの787は、かなり空いていた。3列シートにひとりだけという席が多い。 わけならば、たぶん、ある。 台風のせいだ。 台風21号。 超大型。 もし本土に上陸ということになれば2000年以降では初の超大型台風の上陸になるらしい。 ちなみに強風域の半径が500キロだと大型。超大型だと半径600キロになるから、北海道の一部から九州の一部まで、ほぼ本土の全域を覆う大きさになる。 そんな奴が沖縄に近づいている。 行かないわな、普通。 でも行っちゃう。 今まで沖縄で台風による欠航や遅延のトラブルに見舞われたことがないのだ。何度か台風に遭遇したり、接近されたりしたことがあるが、ダイビングが中止になったり、飲食店が臨時休業になったりはしてもエアに影響を受けたことはない。関空で南海もJRも強風のため橋を閉鎖され慌てたときもエアはちゃんと飛んでくれた。 今回は那覇で2泊のショートステイ。台風が来なければ、南部あたりへ路線バスの旅でもしようかと考えていたのだが、台風接近では、そのプランは捨てる。何をするでもなくぼ~んやりしながら、夜の喰い物屋のことだけを考えよう。 那覇での服装は半袖。袖まくりのできるジャケットを羽織ってはいたが、これは寒暑のためではなく、ポケットが欲しかったから。 訪沖初日の夜は、県庁裏のイタリアン「ピキタン」へ。事前に連絡して糖質制限のディナーを用意してもらっている。電話をかけたとき、いつも大量に「お持ち帰り」をするせいか、この日は、事前にお持ち帰りの品をある程度オーダーしておくことになった。リストランテやトラットリアといったコジャレタ店ではない。日常使いの気のおけない食堂風だが、営まれているご夫婦との交感も楽しみでここを訪れている。初日の訪店で糖質制限のデザートや食材を買い込み、滞在中の間食や昼食に利用する準備が整った。 古島にあった同じく糖質制限の店、中華の「グ |
ルメエッセンス」が店をたたんでしまった今、「ピキタン」は筆者の心強い味方である。 店を出て、国際通りの「波照間」で豆腐よう(ここの豆腐ようはかなり好きなのだ)と島らっきょの天ぷらで泡盛を少し。 最近、マイブームのファミリーマートの沖縄限定泡盛コーヒーも買い込み、ホテルでピキタンのデザートを早くもひとつ開封。泡盛コーヒーは、泡盛をコーヒーで割ったカクテルで300CCの容量でブラック、アルコール度数は13度。 翌昼。 おもろまちのシネマQで「アトミックブロンド」を見る。シャーリーズセロンの姉御が蹴るは殴るは飛ぶは撃ちまくるは。 台風は沖縄の東方の大東島にそれつつあった。 いかにも台風らしい方向の定まらぬ、傘を巻き上げるような強風がたまに吹くが、雨はそれほどではなく、交通機関にも影響はなかった。那覇では、バスが止まると、皆、休みになってしまう。 2泊しかないのであと1食の夜が悩みどころだったが「シェフズテーブルサクモト」に予約を入れた。 松山のそばにシェフひとりで切り盛りする店がある。開業して21年になる。カウンターで8名ほどの小さな店だが、筆者とは生年が1年しか違わないシェフとの相性はよく、大阪のゆきつけの店に雰囲気が似ていることもあって、ちょこちょこと通うようになった。尻の座りの良さは抜群。 基本的には3皿のおまかせだがポーションがあるので女子はそれで満腹になる。それでもなんだかんだと幾つかの品をさらに食べることになるのだが。 店を出ればかつての「バー・ステア」が近い。マスターが亡くなり、店は「バー高梨」が引き継いでいる。少し飲みすぎていたので今宵の訪店はあきらめた。ホテルに帰り、泡盛コーヒーでピキタンのドルチェ。 あっという間にもう帰阪の日である。 夜遅く帰るのが好きではないので、それがどこであれ、帰阪の途には昼過ぎにつく。普段はほとんど昼食に時間も量も割かないが、沖縄にあればルーティンがある。「ジャッキーステーキハウス」へ。すいていた。やっぱ台風さまさまか。 普段はステーキを2枚食べるのだが今日は1枚だけ。タコスは2P、ノースープ、ノーライス、ノーブレッド。 エアは定刻に飛んだ。 台風は沖縄には上陸しなかったが、本土へは向かっている。その後を追うように飛んだ乗機は、伊丹行きだったが、空港周辺の気象が悪く、紀淡海峡上空で何度も旋回した。結局、天候回復はならず関空にダイバードとなった。交通費として1500円が支給された。 |
広島行(その3) →→→back 広島行1 広島行2 広島行3
| 47都道府県すべてに足跡を残してはいるが、泊まったことのない県が五つあった。それは佐賀、広島、奈良、滋賀、富山の5県だった。 広島以外はいずれもまあ、納得はいくでしょー(ごめんなさい4県の皆さん)。しかしなぜか中国地方の殷賑広島をスルーしていた。もちろん市内や宮島や呉などを訪れてはいたのだが・・・ 折良く週末にかけて広島に所用があったので、この際泊まることにした。 健康上の理由で糖質制限を始める前は、広島に行けばお好み焼きかつけ麺を食べていた。それもかなり好きだったのだが。 お好み焼きは、広島駅ビルASSEの2階にある「麗ちゃん」が定番だったが、もはやあれだけの糖質を一食で摂取する勇気はない。名物の牡蠣は宮島で食べているから、初見の食べ物に注目して広島のソウルフードをあたっていたら「ウニホーレン」と「ホルモン天ぷら」が視界に入ってきた。と、言うかなぜ今まで目にとまっていなかったのかが不思議だ。 瀬戸内の魚も食べたかったので歓楽街流川にある「おゝ井すし」をチョイス。 胡町(えびすまち)電停から平和大通りに向かって南下すると流川町のエリアに入る。筆者は初めての訪問。初見のせいかもしれんが、猥雑さに関してはかなりハイレベル。ここまでの猥雑感は筆者の行きつけエリアにはないかもしれん。難波や天王寺の方はいかんので比較でけん。 酒販店の軽トラがビュンビュンといきかっている。ぼーっとしていると跳ね飛ばされかねない。 市電の通りに近い流川のメイン街路の角地に店はあった。老舗らしいが、肩ひじはった感じのない町場っぽさがあって初見でも気軽に楽しめる。アテだらけで頼んでも文句を言われなさそうなの |
もいい。ひいてもらった中では「かわはぎ生ちり」が絶品だった。肝が甘い。お目当ての「ウニホーレン」は、ほうれん草のバター炒めのウニ載せだ。ウニを使っているからワンコインというわけにもいくまいが糖質制限OKフードなのは間違いない。心強いソールフードだ。土地の名物は糖質過剰でNG物件が多いのだ。 カープがリーグ優勝を決めた週だったので、大将から升酒をふるまわれた。気さくないい大将だった。「サザエの壺焼き」もよかった。握りは6カン。最後に芽ネギで締めるのが店の流儀か。 「おゝ井すし」の裏手に最近店を拡張した(以前は2階でバーのみだったようだが、1階の中華料理店が店をたたんだのを機に焼き肉系居酒屋を設けたらしい)「サコイ食堂」があった。 「ホルモン天ぷら」をオーダー。天麩羅だから糖質制限的にはNGだが、お好みやそばよりは良かろうもん。いかにも広島風にタレには一味をたっぷり。「タン塩」がまた旨かった。 翌朝、広島駅の駅ビル「ASSE」の2階に上がる。既述のとおり以前なら「麗ちゃん」だが、今回は鉄板焼きの「さち」に向かう。「麗ちゃん」はあいかわらず大行列だ。「さち」は穴場的、とは言え昼すぎには満席になっていた。カウンター形式だが目の前に鉄板があるわけではない。ここでも「ウニホーレン」をオーダー。バケットがついてきた。残そうと思ったが1枚にウニホーレンを乗っけてみた。(!)旨いがな。生ビールを飲んでいたが白ワインをグラスで頼む。店の女将さん(かな?)からは「グッチョイ!」と言われた。きさくな気のおけない女将さんだった。また来ることは確実。 広島で遊ぶ足がかりを得た一夜だった。 |



| 短い夏が終わろうとしていた。 漁業も観光業も島を支える基幹産業の活動期間は僅か5ヶ月。5月に始まり9月にはシーズンが終わる。その9月の一旬、筆者は利尻島に降り立った。いつも稚内から利尻水道越しに眺めていた利尻富士の麓にやって来たのだ。 ウニ漁の盛期はとうに過ぎ去り、気温は20度と、半袖のインナーに長袖の薄いジャケットがちょうど良い気候だったが、島にはすでに長い冬を迎える前の寂寥感が漂い始めていた。 ニシン漁で賑わった往時から昭和初期には2万を越えた島の人口はもうすぐ2千を切る。 離島、と言えば沖縄の諸島を思い浮かべるが、観光地化が進んだあのエリアは離島感が希薄になった。訪問者の若者比率が高いのだ。エアや船の客の中で筆者が最年長なんてことはよくあることだ。一方、同じ離島でもここ利尻では下手すると筆者が最年少なんてことになりかねない。利尻登山や礼文トレッキングが目的であろう高齢者が多いせいだ。高齢=過疎のイメージが直結し利尻には極めつけの離島感が生まれる。なればこそ漂泊の行き着く先にはぴったりということになる。 利尻に渡るには、稚内からのフェリーばかりが頭に浮かんでいたのだが、札幌からエアーという手段があることにふと気がついた。思い立ったら即実行。丘珠からか?と思いきや、なんと新千歳から利尻空港への便がある。コミューター機か?と思いきや、なんと機材はボンバルディアですらなく、ジェットの737-500だった。 利尻島は周囲60キロ程度の円形の島で、中央部に1721mの利尻山が聳えている。小さな島に1700m超の突起があるのだから、とにかく島のどこにいても山が目につく。と、言うか何かにつけ山に目がいってしまうのである。なぜか「ダンテズピーク」という火山映画が脳裏に浮かんだ。利尻山の最後の噴火は8千年前。火山評価は近時、1万年はたたないと死火山とは呼ばせないそうで利尻山は、活火山C級になっている。標高が高いためか植生が豊かで、ために水蒸気が発生しやすく山頂を雲が隠すことが多い。 |
島の中心は沓形(くつがた)という町だが、筆者の宿泊先はその反対側にある周囲に何もない海に向かって建つ3階建てのホテルだった。ウニ漁をする漁師が経営するホテルで、リゾートアルバイトの女子がふたり、気仙沼からやはりリゾートアルバイトに来ているOさんが送迎の車を運転している。Oさんの話を聞いた。東北大震災の津波で当時経営していた8軒の飲食店が全滅してしまったのだと。でも家族や従業員は無事だったのが幸いだった。あれから8年たつが今でも夏は北海道で出稼ぎをしている。同じ漁師出身で料理屋もやっていたからだろうか、ホテルの大将とは喧嘩しながら楽しくやっているそうな。 島を一周する定期観光バスがあったので利用した。レンタサイクルで島一周というのも面白そうだ。いつかやってみよう。 バスは鴛泊(おしどまり)フェリーターミナルを起点に、時計まわりに観光スポットを廻ってゆく。「姫沼」「野塚展望台」「利尻島郷土資料館」「オトタマリ沼」「仙法志御崎公園」「利尻町立博物館」「人面岩・寝熊の岩」を経てフェリーターミナルに戻る3時間半ほどのツアーだが港の手前で空港で降ろしてもくれる。 「姫沼」はその名の由来に浪漫を感じたいところだが、昔、ヒメマスの養殖用に作った沼だからその名になったそうな。しかも、周囲が海で海産物の豊富な島にヒメマスは不要ということですぐに廃れてしまったというトホホな話。水面が静かな状態ならば逆さ利尻富士が見える。木道が周囲を巡っていて一周15分程度で消費できる。 「オトタマリ沼」は「姫沼」よりも一回り大きく周囲約1キロ、20分程度で回れる。ここから見える利尻富士が「白い恋人」のパッケージデザインになっている。 「仙法志御崎公園」は利尻山の斜面がゆるやかに海に向かっている姿を捉えられる唯一のポイントかもしれない。なかなかの景勝である。オットセイにも会える。 空港でバスを降りて、札幌に戻った。思いのほか心に染みる島だった。また来よう。 |




| 「世界遺産」認定というのは、観光地として究極の太鼓判とかお墨付きを得たということか。かなり潰しが効きそうである。 「国宝」の上に金箔の額をつけて「世界遺産」って上書きしているようなダメ押し感がある。 世界遺産の合掌造り集落と言えば、白川郷と五箇山が頭に浮かぶ。 あれ?2か所だっけ?という初歩的な疑問もそこに生まれる。 白川郷と五箇山は何が違うんだ?と、実はよくわかっていなかったことに気づかされる。 とりあえず、五箇山は消費した。 白川郷はどうだ? 日本三大秘境のひとつが白川郷だということは、年初に三大秘境のひとつ祖谷渓を訪れたときに認識した。秘境の秘境たるゆえんは、人里からあまりに遠く、道なき道を分け入らねばたどり着けないところにある。しかし、今や、日本国内あまねく自動車道や鉄道が整備され、いまどきの秘境は、秘境足りえない。それでも祖谷渓は秘境っぽかったが。 金沢駅から白川郷行きのハイウェイバスに乗ったが途中「五箇山」で降りてしまった。次の停留所は終着「白川郷」だったから五箇山、白川郷は隣接地帯という解答を得たわけだ。しかし、ハイウェイバスは五箇山からは拾ってくれない。五箇山から白川郷までは世界遺産シャトルバスを使わねばならない。五箇山の二つの合掌造り集落「相倉」と「菅沼」間をつなぎ、さらに白川郷まで足を伸ばす路線バスだ。菅沼から白川郷まで40分弱。国道156号をバスは走る。ハイウェイバスは五箇山インターから白川インターまで東海北陸自動車道を走るので25分ほどでついてしまう。ちなみにこの世界遺産シャトルバスも白川郷、高岡間を結んでいる。相倉から先でハイウェイに乗るらしい。 日本3大秘境のひとつ白川郷は賑わっていた。祖谷渓に比べれば秘境感は希薄。秘境のもつ秘め |
やかさは皆無。すがすがしいほどに観光地。まあ、観光地なわけだが。 中華もアングロサクソンもゲルマンもラテンもスラブもヒスパニックも、もちろんドメスティックもわちゃわちゃいる。 金沢、名古屋、高山などから来る高速バスは、白川郷バスターミナルに集まってくる。世界遺産バスもここが終着(あるいは始発)である。ターミナルから少し離れたところに展望台行きのシャトルバス乗り場があった。10分程度で白川郷を見下ろす天守閣とよばれるレストハウスまで200円で連れて行ってくれる。レストハウス前に展望台があった。 見下ろしたとたん(ああ、これがアレね)と誰もが思う白川郷の展望。 人並みを掻き分け、最前列からとりあえず1枚、パシャ。 シャトルバスで集落に戻り、そぞろ歩きを始める。 茅葺屋根の家だろうと何だろうとここにあるのは皆、ヒトんちである。観光客は、要するにヒトんちを見て回ってヒトんちの写真を撮りまくっているわけだ。住宅展示場で新居のモデルハウスを巡るのとそんなにかわりはないかもしれない。 白川郷は、五箇山よりも広い。茅葺屋根の数が違う。次々と視界に現れる民家を辿ってゆくとテーマパークにいるような感覚にとらわれる。足も疲れてきたし、そろそろ引き返すかと思うと視線の先に新たな茅葺屋根が現れ、先へ先へと人の足を誘うのである。アリ地獄みたいだ。 高台にある家の裏で、白人が彼女と一緒にニッコリ微笑んで墓石をバックに自撮りしていた。墓だぞ、それ。セメタリーだって。オリエンタルな時代もののモニュメント程度の認識なんだろう。ある意味、あたってはいるが。 さて、ヒトんち巡りも満喫した。当分茅葺屋根はいらないな。 |


「サンダーバード」の車窓から2 →back 「サンダーバード」の車窓から 「サンダーバード」の車窓から2
| 湖北に広がる青田の海を列車は渡ってゆく。 稲の育ち具合の差か、濃淡の異なる幾重ものグラデーションが美しい。 「京都」を越え「山科」を過ぎ「大津」から湖西線に乗り入れ、しばし広大な琵琶湖の湖面を眺めたあとの景色である。湖西線は踏み切りの無い高速走行路線として設計されたため、全線が高架である。ために眺めがいい。 湖西線と北陸本線が交わる「近江塩津」を過ぎればすぐに嶺南の中心地「敦賀」だ。駅前には大きなカニツメのオブジェがある。筆者が来阪した15年前は、まだ「敦賀」は交流電化区間で、直流車両の新快速はここまで走ってこなかった。これを直流化し、新快速が来るようになり、西に向かって「姫路」までを結ぶようになったのは、筆者来阪の4年半後だ。所用時間は、およそ3時間30分。営業キロ数225キロは、東京、掛川間に相当する。 「敦賀」の先で、北陸トンネルが口を開けて待っている。新幹線以外の狭軌では日本最長の陸上トンネルである。トンネルを抜けると「今庄」。冬ならば車窓がいきなり白銀の世界に変わる降雪地帯だ。 峰続きではあるが頭ひとつ抜けた日野山が目にとまる頃には、それを境に湖北の山岳地帯が遠ざかり、再び田園が車窓に広がり「武生」に至る。行司岳を見やりつつ「鯖江」を通過する。メガネフレームの生産日本一の街だ。橋立山の中腹にSABAEと書かれた文字の横、まんまるメガネが右下に流し目をくれている看板が目立つこと、目立つこと。 |
足羽川を渡ると嶺北の都邑「福井」。かつては北国の王、柴田勝家の北ノ庄城が7層の天守閣を聳えさせたこともある北の都である。 九頭竜川を越える。 青田の広がるどこにでもある日本の車窓が続くが、はるか遠くに小さく丸岡城のシルエットが見える。別名、霞ケ城。北陸では唯一の現存12天守のひとつだが、それと気づく人は少なかろう。 「丸岡」を通過。 列車は「芦原温泉」に到着。田園風景が終わり、小さな丘の連なりに両脇を挟まれつつ進むと、進行方向左手に小丘が見える。大聖寺城跡を公園とした錦城山公園である。最寄り駅の「大聖寺」を過ぎれば観音山に聳える加賀寺の金色の観音が目を引く「加賀温泉」に到着する。 「加賀温泉」の先、「粟津」は那谷寺の玄関口だ。その隣は「小松」。左後方の海岸寄りに空港がある。自衛隊と国内線旅客機の共同運用の空港だ。管理の主体は空自が行っている。駅前にコマツの巨大なダンプが鎮座している。 鉄路はグイグイと日本海に近づき、海に流れ込む直前の手取川を渡る。北陸新幹線の延伸高架がいくつかまばらに立っている。そして、広大な北陸新幹線白山車両基地(白山総合車両所)が現れる。小松空港にランディング中のエアの窓からもそれとわかる巨大な施設だ。 「松任」「野々市」「西金沢」と金沢辺縁の住宅地を過ぎ、高架に視界を遮られ、それとわかりづらいが犀川を越え、やがて特急サンダーバードは「金沢駅」に到着する。約2時間半の旅の終わりである。 |
| 盛夏の一日、世界遺産「五箇山」へ向かった。 五箇山は南砺市の南西にある。 (南砺市?なんて読む?どこだ?!) 惜しい!なんてじゃなくて南砺(なんと)市。 富山県民でなければ、それが日本地図のどこに位置するかは誰にもわからないはず。 位置はわからずとも、北鉄のハイウェイバスが連れてってくれるから悩む必要はない。 金沢駅東口のバスターミナル2番から五箇山までは1時間弱。日帰りハイキング感覚で行ける。料金も1540円とリーズナブル。 ハイウェイバス予約システムを使ってコンビニで料金を支払うと正規のチケットが手に入る。この発券システムでは、座席位置の指定まではできないが受け取ったチケットには座席位置が印字される。予約時に席指定ができないから、てっきり好きなところに座ればいいと早合点していた筆者は、後から乗車してきた客から追い立てられることになった。 金沢市街を後に、北陸自動車道を北上すると進行方向左側に一際目をひく高い塔が見えてくる。クロスランドおやべのクロスランドタワーというものらしい。寡聞にして知らなんだ。金沢の先は津幡、そこから分岐して能登方面が七尾、富山方面が高岡、というのが筆者のだいたいの土地勘なのだが、高岡の手前に小矢部市というのがあるなどとは盲点である。富山の闇は深い。 小矢部と砺波の境で東海北陸自動車道に乗り換え、南下を開始する。 それまで遠くにあった山の稜線がだんだん近づいてきた。やがてバスは山峡に分け入る。車窓に占める空の割合がどんどん小さく、遠くなってゆく。ここまで来れば立派に人跡未踏(来てるけど)の雛の風格だ。少なくとも近辺に人家は見当たらない。 長いトンネルに入った。トンネルを抜けると、すぐにまた長いトンネル。そのトンネルを抜ける |
と、不意に眼下に渓谷が現れた。ハイウェイは渓谷沿いに続いているが、バスはここで下道の国道156号線に降り「五箇山の里」停留所に停車した。バスを降りる。 国道沿いに歩くと駐車場があり、そこに展望台が設けられていた。見下ろすと、渓谷の下、庄川の流れを北に押しやるように丸いこぶのような土地が突き出している。そのこぶの上に茅葺屋根の小民家がひっそりと、まるで箱庭のように佇んでいた。 (おおお!) 神の雫ばりの感嘆符が思わず口をつく。 こぶの周りを取り巻くように流れているはずの川の水面は見えない。見下ろす集落は、緑の山に囲まれた、日当たりのいい谷あいの村のように見える。 国道を下り、集落に出る。 周囲の山々の緑が濃い。 山の端の上、空が高く、青い。 夏雲は陽光を浴びてどこまでも白い。 つまり「THE 夏!」である。 (これこれ!) 最近、沖縄以外で出会うことのなくなった夏に久しぶりに再会した気分だ。 五箇山と言うがそれは地区名で、この合掌造りの集落名ではない。五箇山にはふたつの集落があり、互いに距離を置いている。車で15分くらい離れているだろうか。筆者が降り立ったのは菅沼(すがぬま)集落である。もうひとつは相倉(あいのくら)集落という。 観光客の姿は少ない。インバウンドもここまでは足を運ばないのだろう。ただし、ドイツ人の夫婦と世界遺産バスの停留所で一緒になった。 時の流れが実にたおやかだ。静寂の中に村がある。箱庭のような小さな村。頭に浮かんだのは「ムーミン谷」。 「日本昔話」でもいい。 |




石垣島行11 →back (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
| 6月21日、北陸が入梅した。 去年は、6月13日だから1週間以上遅い。 九州に続いて6月7日に四国から関東甲信越にかけて入梅宣言を出したが雨が降らず『早まったか~』と唇を噛んだ気象庁、北陸に関しては慎重になったのか。 その翌22日、沖縄が梅雨明けした。 昨年よりも6日遅い梅雨明けだった。 さっそく石垣島へ飛んだ。6月下旬から7月七夕にかけてがお勧めのシーズンだ。台風リスクは極小だし、観光客も少ない。 実際のところ、沖縄本島から石垣島は500キロ程離れているし、緯度にして2度、経度にして3度ほども南東にずれた海に浮かんでいるから、那覇が梅雨明けしていなくても、石垣が梅雨明けしているケースは十分にあるのだが。本土の天気予報は、先島諸島も沖縄本島もひっくるめて沖縄とするくらいに精度には気を使っていない。 那覇乗り継ぎだったが、関空からの便は満席。最近この季節でも空いてない。 国際通りに繰り出すほど時間にゆとりがなかったから、空港内の「A&W」で「メルティダブルバーガー」を購入して、大阪から持参した「ダイズインターナショナル」の「丸ダイズパン(ゴマ)」糖質量1個1.2グラムという安心のバンズですり替えバーガーを作って昼食とした。 夕方、石垣空港着。この便も満席。 空港から市街地へのバスは2社が走らせている。東運輸とカーリー観光だ。東運輸は本数が多いが、途中、幾つもの停留所に停まるので感覚的には骨折した亀のようにトロい。しかも2系統のルートがあって判断に悩んだりする(4系統と10 |
系統で、4系統の方が早い)。カーリー観光は、離島ターミナルまでノンストップだが1時間に1本だ。折りよくカーリー観光のバスが停まっていたので乗車。 これまたいつものように「体験ダイビングでゴメンネゴメンネ~」と言いつつ、いつものダイビングショップの船に乗る。 同行は他に6名。皆ファンダイビングだ。体験は筆者だけ。ゴメンネゴメンネ~。 名蔵湾とマンタシティ、御神崎でのダイビングは昨年と同じ。 3.5メートルほどのマンタを間近で見る。去年も遭遇した。最近、マンタの引きが強い、と言うかここでしかマンタを見ることがないので、どれほどついているのかが分からない。 石垣港の沖合にクルーザーが停泊していた。去年はゴールデンプリンセスだった。同じだろうと思っていたら、サファイヤプリンセスだった。姉妹船なのだろう。 ダイビングから戻って、島最古参のステーキハウス「担たん亭」へ。 翌日、那覇に移動して、やはりゆきつけの「ピキタン」と「琉球珈琲館」夜はイタリアンの「ha-na」へ。翌朝「ジャッキーステーキハウス」もはや金沢同様、書くことがなくなっている。 来沖すれば「かりゆしウェア」を買い付けている。もう10年以上になる。気に入ったデザインがなければ買わないことも多いが、今年、心覚えの何軒かの店を回ったが、一時、隆盛を極めていた頃に比べると、店もなくっていたり、品揃えも単調になっているように思える。下火になったのか?・・・ちょっと寂しい。 |

| 都市部の朝のラッシュ風景はどこも同じだ。 博多も例外ではない。 ただ、混雑はあまり長続きしないようだ。9時を回れば地下鉄空港線はある程度落ち着きを取り戻している。 初来福のKは一仕事終えた翌日、新幹線の予約を遅めにとって自由時間を設けていた。3年前は金沢を案内したが、今回は博多の案内役を買ってでた。しかし、何度も書いているが博多は観光資源に乏しい。福岡タワーに登るのも、大宰府に行ってからキューハク(九州博物館)を見るのも、あまり心浮き立つプランとは思えない。どうしようか。ガイドとしては手持ちのカードが心もとないワンペア程度しかないことに嵩じはてるのであった。 よし、西に向かうことにしよう。地下鉄空港線は姪浜から西唐津までJR筑肥線に乗り入れている。途中、筑前前原で降りて糸島半島を北上すれば、芥屋大門(けやのおおと)に行ける。料理旅館が数軒あるだけの雛だが、玄海の魚をそこでつまんで昼酒、というのも乙じゃないか。あるいは終点西唐津まで行って、東松浦半島を遡上し、呼子か、名護屋城跡を訪れるのもいいかもしれないとそこまで考えて、はた、と膝を叩いた。呼子では七ツ釜、名護屋城跡にも行ったことがあるが、イカシューマイ発祥の店「萬坊」の海中レストランを消費したことがなかった。そーだ!呼子でイカを食べるバイ!にわか博多弁の違和感を無視して今日の方針が固まった。ひとつの旅にはひとつのイベントがあれば十分タイ!しかも、この路線は、海岸線を存外長く走る。オーシャンビューを眺めることができる地下鉄なんて、言葉自体に矛盾が満ち満ちていてイイじゃないか。 地下鉄空港線、快速西唐津行きは姪浜を過ぎたあたりで車内の乗客がほとんどいなくなってしまった。金曜の昼前、実にのどかな車内から眼前に広がるのどかな玄界灘の広闊な美景を眺める。梅 |
雨の中休みの蒼天の下、新緑と海の青が開放感をいや増してくれる。 筑前前原を過ぎるとドアが開閉ボタンによる操作に切り替わった。気分はいやが上でもローカルである。終点の一駅前、唐津にむかって鉄路は大きく回りこんだ。唐津城が近づいてくる。 降りて駅前のタクシー乗り場から呼子の萬坊海中レストランへ向かう。 呼子大橋の手前に萬坊はあった。 当日予約は受けつけないそうだがウィークデーの金曜日だし11時の開店前に店にゆけば席はあるだろうと、たかをくくっていた。ヨミにはずれなし。(ただし正午にはほぼ満席になっていた) 海中レストランだから店内を海面下に降りてゆく。(海上にも席あり) 店のレイアウトは内に生簀を囲み、外が海となっている。生簀は、底部で海と繋がっているそうな。生簀際の席と海に面した外周の席がある。生簀の中には巨大な鯛が泳いでいるが、海際は小魚がたまに窓をつつくばかり。しかし、目を離していると不意に大きな影がサッと窓を横切る。ジョーズか何かの海洋ミステリー映画のようだ。 イカセットを頼む。 魚豆腐(ぎょどうふ)、イカシューマイ、メカブ、イカの姿造り、ご飯は1杯だけおかわり自由、お吸い物とオレンジ、葛餅がついて2980円(税込み)。これに鯛の刺身を別注。 やがて2ハイのイカがうらめしそうな目をして現れた。イカ刺しが甘い。刺身以外の部位は、途中でいったん厨房へ持ち帰り天麩羅か、塩焼きにしてくれる。さすがにイカ刺しに飽きてきた頃に実にいいタイミングで天麩羅が現れる。計算されつくしているのだろう。 それなりに満ち足りた気分で、来た道を戻り、博多駅へ。デイトスの「まるとく食堂」で手羽明太、明太ダシまき、魚ロッケなどをついばみつつハイボールと焼酎を空けて今日はオシマイ。 |

| 新緑の季節を迎えた。 去年は東福寺の翠蓋ならぬ翠海のような新緑を満喫した。 比叡山の東山麓にある近江坂本の日吉神社でもこの季節は、新緑が美しい。 紅葉の名所は新緑の名所でもあるから、京都界隈ならどこでもアタリだろう。 醍醐寺に向かった。 醍醐寺は、京都の東南方、東山の裏側にある山科から伏見に向かって南下する途上にある。JRで京都を過ぎ山科まで行き、京都市営地下鉄東西線に乗り換える。 ちなみに、エスカレータの立ち位置は、東京は左、大阪は右と、なんとなく認識されていると思うが、関西は皆、右だと思ってはいけない。確かに、神戸は大阪と同じ右立ちだが、京都は微妙である。と、言うか京都は左立ち派だ。JRや阪急、京阪で京都にやって来た大阪人が混ざると有無を言わさず右立ち先行になり、後に続く京都っ子もしゃーないと右に倣うのだが、山科みたいに大阪人なんか来やしないところに行けば気づかされる。あ、左か、と。山科の地下鉄に乗ろうとうかうかとエスカレーターに右立ちしていたら、皆が左なのに気がつき、すぐさま左寄せした。 閑話休題(あだしごとはさておき) 秀吉の醍醐の花見で高名な醍醐寺には上醍醐と下醍醐がある。修験道のメッカとして知られる上醍醐の方が縁起的には古い。 筆者が初めて醍醐寺を訪れたのは2月の初旬だった。 夕刻、陽の落ちるまでの短い時間で醍醐寺を消費しなければならなかったため、下醍醐はコマ落としのフィルムのように高速で、上醍醐はハヒハヒ言いながら登った。 今日は国宝、重文の宝庫、下醍醐に専念する。 |
醍醐駅から醍醐寺までは歩いて10分程度。住宅街を遊歩道が貫いている。緑道というらしい。道標も道なりに丁寧に並んでいる。あれ?こんなに整備されてたっけ?以前に来たのは2008年だったから9年の歳月が流れている。インバウンドの急増で観光立地に目覚めたのかもしれない。 周囲に堀を巡らし、白壁の塀と松に囲まれた様は戦時の兵力駐屯地を思わせる。総門の向こうに仁王門が見える。この遠近感がなかなかのものだ。総門と仁王門の間に三宝院があり、その手前で拝観料を支払う。 拝観料1500円。 高っ~ こんなに高かったっけ? まずは三宝院を拝観する。普段非公開区域となっている「本堂(弥勒堂)・奥宸殿」を拝観できた。庭園がまたいい。写真撮影禁止の表示がそこここにあるので、皆、美しい庭園を前に(撮っていいのかよ?駄目なのかよ?)と悩んでいる。係りの女性に問えば庭はOKとのこと。家族や、夫婦でいいのか?悪いのか?とひそひそ話しをしている人たちに「庭はいいそうですよ」と伝えて感謝の嵐をうける。実際、この庭はイイネ。廊下の床板がキュッキュと鳴る。ここも鴬張りなのか? 仁王門のむこうに翠蓋がある。そのトンネルを抜けると、国宝の五重の塔だ。金堂やら不動堂やら旧伝法学院などの堂右の先、池のむこうに、翠に包まれた赤い弁天堂が水面に逆さ絵を浮かべながら現れる。これこれ、これが今年のお目当てだったのよ。 霊宝館で仏像や襖絵も見た。この拝観料こみでの1500円だったのね。丸山応挙の師、石田幽汀(いしだゆうてい)の蘇鉄に孔雀図が気に入っちゃった。 |

| 4月も2旬を過ぎた23日、桜の名所「吉野」へ向かった。 今年の関西は花冷えが長かった。開花が遅れ、京阪では4月10日頃が満開だった。 さすがに23日ともなれば散っているだろうが、吉野は下千本、中千本、上千本、奥千本と標高差によって開花時期がずれる。もしかしたらとの期待は少しだけ抱いていた。 近鉄阿部野橋駅から吉野まで特急で1時間16分。車内は空いてる。10日に近鉄の特急指定席をチェックしたときはすべて満席だったから、明らかに時期ハズレなのだろう。 久しぶりの行き当たりばったり行だったが、案の定、想定外に見舞われた。 そもそも吉野は初めてだし、現地情報を何一つ仕入れていなかった。吉野駅からロープウェイが出ていることは知っていたが、その先は皆目わからん。たぶんバスが出ているだろうからそれに乗って奥千本まで行けばいいとたかをくくっていた。閑散期ならそれでいいのだろうが、甘かった。桜の盛時は過ぎているのだろうが、筆者みたいなトンチキが意外と多かったのだ。 列車は13時過ぎに吉野に到着した。 ロープウェイ乗り場に向かう。 係員が「あと6名!」と叫んでいた。4人目でロープウェイに乗車したが、あと2名、まだ押し込むつもりか?というほどに詰め込まれた。東急東横線か? しかたあるまい。年間の稼ぎ時は僅かな間でしかないのだろうから、と自らをなだめる。 しかし、このロープウェイは古い。恐いほどに古い。浅草花やしきのローラーコースターのように恐い。花やしきのローラーコースターは昭和28年生まれだが、このロープウェイの支柱に表示されていたのは昭和3年5月の日付。脳裏を駆け巡るのは「落下」の2文字。支柱を越えるたびにブラブラと揺れる。ちょっとしたアトラクション |
だ。幸い、ゴンドラは落ちることもなく吉野山駅(山上駅)についた。 ロープウェイの係員が大声で案内している。 「バスは竹林院前からになります!竹林院前までは1時間ぐらいです!バス待ちは2時間です!」 (やっちまったか~!) 行き当たりばったりでむかえるお約束の「想定外」。なし崩し的に山登りがスタートした。まったくその気はなかったのに。当然、準備はなし。ポーチには特急内で飲み残したミネラルウォーターが少し。低糖質のチョコバーが1本。足回りはウォーキングシューズだったので助かった。 これが人影も見当たらない雛の城山なら少しは危機感を持つところだが、世界遺産吉野山、桜の名所吉野山だ。観光客だらけだから道も整備されているし、案内表示も間然するところなし、と判断。高取城に登るよりも気軽に歩き始めた。 下千本から金峯山寺蔵王堂へ。仁王門が大きい。世界遺産だ。勝手が分からぬので寄り道をして体力を失いたくないからパス。吉水神社、東南院にもわき目もふらずとりあえず竹林院へ。バス亭には長蛇の列ができていた。後で知ったのだが、バスと言ってもコミュニティバスのようなもので、ワゴン車サイズなのだ。乗車人員は30名にも満たないだろう。何回転もピストン輸送しなければあの行列は解消できない。そのまま登山を継続。上千本に上がり、吉野水分神社から上が奥千本となる。高城山展望台(登って損した)を過ぎ、金峯(きんぷ)神社まで1時間半の有酸素運動となった。奥千本では、なんとか桜を愛でることができた。 吉野山駅の標高は300m程度で、金峯神社は765m。比高は465m。ちょっとした城山征服事業だな。帰路、往路で気になっていた、豆腐豚まん、桜ソフトクリームを見やりつつも、手を出さずに撤収。翌日、もちろん筋肉痛でC3POみたいに歩くことになった。 |
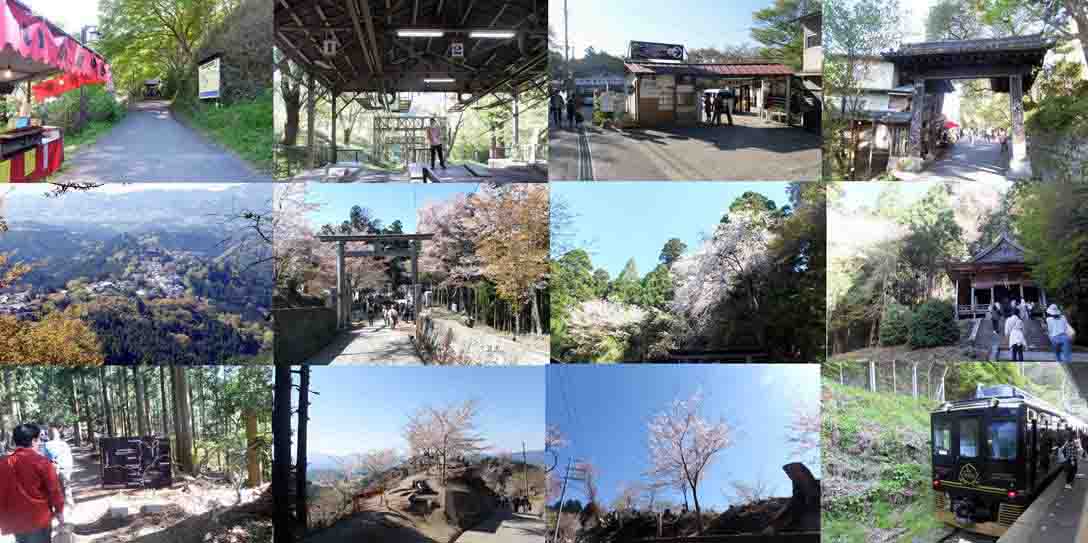
| JR琵琶湖線(と言っても米原から京都までの東海道本線の区間愛称なのだが)の近江八幡は、大阪から新快速で1時間強の位置にある。大阪をテコの支点とすれば、ちょうど姫路の反対側である。 琵琶湖の東岸に広がる近江の野は今も古の時を刻んでいるかのように長閑だ。京阪の雑踏に気忙しさを感じたらここに逃れてくればいい。「開発」という名の商業主義の尖兵も、ここまでは侵食できずにいる。 とは言え、昭和の一時期、琵琶湖の内湖を次々と干拓してしまったことがあったらしい。 「やられた、とおもった」と『街道をゆく』で司馬遼太郎をして嘆息せしめたのは、安土山の麓まで打ち寄せていた湖面が埋め立てられてしまい、湖の畔に浮かんでいたはずの安土城址が平山城になってしまっていたことであった。 近江八幡の始まりは、本能寺の変後である。焼失した安土城の変わりに八幡山城が築かれ、安土城下の町をその麓に移したところから町の歴史が始まる。 第2次大戦後、昭和の干拓前の地勢では「大中の湖」と「小中之湖」「西の湖」などの内湖が安土城跡の前面に広がっていた。八幡山城はその「西の湖」の西岸の山上に建てられた。 安土山は標高199mのなだらかな小丘だが、八幡山は標高283mで急峻な山容である。 近江の野を走る新幹線から山腹にロープウェイをかけたその姿は遠望できる。 城はあるが、城下は城下町特有の防衛的町割を成していない。八幡山駅から城まで1本の主道が近江の野を貫いており、八幡山の手前で東に折れ |
たあたりが町の中心となる。町は碁盤目状に形成され「武」よりも「商」のイメージが強い。メンソレータムの近江兄弟社はこの地の出身だ。 琵琶湖から水を引き、八幡堀と称し、防衛と水運に利用したが、現在、観光の要となっている堀めぐりの船の基点もこの界隈にある。船着場の近くに日牟禮(ひむれ)八幡宮があり、楼門、拝殿、本殿が並ぶ荘厳な佇まいを見せている。 八幡宮のそばにはバームクーヘンで有名となったクラブハリエのヴィレッジもある。クラブハリエの母体たねやは近江八幡が出自の和菓子屋だ。八幡山ロープウェイ乗り場は、そのヴィレッジの先にある。ロープウェイは、かつての二の丸跡まで登りそこから30分程度で城跡を周回できる。 西の丸跡からは琵琶湖を見下ろすことができるが、既述のとおり、眼下の多くの農耕地はかつては水を湛えた湖岸だった。湖の対岸にある比良山系の頂の僅かな残雪が白く輝いている。頭上には琵琶湖を越えて西進する旅客機の飛行機雲がたなびいていた。琵琶湖上空には、多くの航空路が集約している。 北の丸跡からは「西の湖」が見えるが、これは干拓前の内湖の12%ほどの広さでしかない。そしてその先にこんもりとした小山然の安土城跡と峰続きになっている、これは高さのある観音寺城跡が見渡せる。近江の軍事拠点の変遷が伺えて面白い。 本丸跡には秀次菩提寺の村雲御所瑞龍寺があった。京都から移設したものらしい。 山を降りて、近江八幡駅に向かう。駅前にある近江牛の老舗「カネ吉山本」の直営レストラン『ティファニー』で近江牛でも食べてゆくか。 |


札幌行9 →→→back 札幌行1 2 3 4 5 6 7 8 9
| 今さらではあるが、羽田も大きくなった。筆者の記憶では往時、滑走路は2本だけだった。それが今では4本になっている。利発着の便がひっきりなしに往還している。成田は本当に必要だったのか? テイクオフで速度を上げる乗機の777-300とランディングしてきたJAL機がターミナルを挟んで瞬時、並走した。 東方の雲海の上に富士が浮かんでいる。思いのほか雲の少ない関東平野を見下ろしながら、機首が北に向けられる。猪苗代湖を湛える磐梯山を臨んだところで雲に視界を阻まれた。 「目的地の天候は曇り、気温はマイナス1度」機長からのアナウンスがあった。 今日は少し暖かいようだ。 鳥目になるかと思われるほどの雲海が切れた。山塊がなければ、雲は湧かない。陸地が切れたのだ。恐山を跨ぎ、そして、海峡を越えた。 高度を下げ、近づいてきた雲の上にブロッケン現象の輪と機の影が浮かぶ。新千歳にむかって苫小牧上空を通過する。 羽田のテイクオフとは真逆に、ランディング中にテイクオフのタイエアと並走した。 札幌行も回を重ねた。新千歳空港には行きつけの店が幾つかあるのだが、帰路の伊丹便13時出立前にすべてを消化することができず、哀しい思いをしていた。今回は、入札と同時にスープカレーの「lavi」と円山公園「竈」の十勝牛100%ビーフを消費することにした。昼はほとんど食べない習慣があり、夜に皺寄せがあるが「さっぽろジンギスカン本店」で帳尻を合わせることにした。2店とも時間を気にせずゆったりと過ごせるのがいい。ホテルにチェックイン後、横になって酔いを醒ませる利点もある。 |
夜、久しぶりのジンギスカンの後バーに寄る。「ドゥエルミターヂュ」と「Vespa」。 2日目、夜は寿司の「たる善」を予約しているので昼は控える。定山渓温泉の日帰りパック1800円という手頃なアトラクションは昨夏に手に入れた。車で1時間強の位置にある定山渓温泉は札幌っ子の日帰り温泉の好適地だ。幾つかの温泉宿のひとつで浸かり放題の時間を過ごせる。前回も利用した定山渓ビューホテルの湯を利用した。広いのが気に入っている。昼過ぎまで浸かって帰路のバスを待つ頃には日帰り湯治客の車が次々とホテルに入ってゆく。 宿で昼寝をして「たる善」へ。締めはバー「プルーフ」と「ボウバー」。 翌日は小樽へ散歩。札幌からは30分強だから気軽に行ける。とは言え、夜はビストロの「クネル」に予約を入れているので昼はやっぱり軽く。途中、陽光降り注ぐ好天だったが運河につく頃には俄かに天候が変わり、吹雪に見舞われた。フード付のキルトコートを着てこなかったのはうかつだった。北の大地では、強風で寒気が増す。風に向かうと呼吸困難にすらなる。駅中の「なると屋」のざんぎを2個だけ食べて札幌に戻り、またまた昼寝。夜は南2西8のビストロ「クネル」へ。 帰阪の日、新千歳。「Lavie」と「竈」は消費しているので、ゆとりをもって「ジアス」で時を過ごす。厚岸産の牡蠣のフライとワイン蒸し、前菜盛り合わせ、山わさびの粕漬けで、サッポロクラシック樽生、ワインの白、赤、流氷ハイボールと北海道ハイボールを嗜み、エアに乗る。 今回の漂泊は、SNSを封印することにした。TVのニュース以外、身近な情報には一切触れずにいた。昔は、こうだったのだと思い、なにがなし満喫しながら漂泊の旅を終える。 |


| 松山への入城ルートは空路、陸路、海路、いろいろと試している。初訪は海路で広島から高速船で上陸した。陸路も楽しい。岡山から瀬戸大橋を渡って来るからだ。瀬戸内海の景色を堪能できる。ただし、所要時間は長い。大阪から4時間強はかかる。大阪からの最短ルートは空路だ。自宅のドアを出て松山市街地まで2時間強もあれば到達する。あとは未体験のチャリルートが残された課題だ。いつかはしまなみ街道を尾道からチャリで渡って今治経由でやって来たいものだ。 最初の訪問時、道後温泉のホテルに泊まった。 ホテルの大浴場で満喫したが、道後温泉本館(坊ちゃん湯)に浸かったことはない。しかし、今回は浸かることにした。 そもそも、道後温泉という単語、道後温泉本館を指すのか、道後温泉エリアを指すのか実に不分明である。 「道後温泉に行ってきた」と言うと、坊ちゃん湯に浸かってきたと思われたりする。その際、「いや、そうじゃなくて・・・」という言い訳の手間を省くためにも入っておくべしということに。 伊予鉄のチンチン電車がJR松山駅前から道後温泉まで通じている。 道後温泉駅前の駅舎はレトロな意匠だ。 駅前にはカラクリ時計があり、毎正時に「坊ちゃん」の登場人物が時計盤の裏から、格子戸からグルリと現れる。せりあがり式の時計台の下部では湯客が手ぬぐいで顔を拭っている。もう、坊ちゃん湯に行くしかないでしょという感じ。 たいして長くもないアーケード商店街は以前、訪れたとき市松タルトを購入しようとして店番の老婆に何度となくたしなめられた懐かしい場所である。あれは1996年のことだった。 宿願(というほどでもない。なんとなく宿年の借金の返済のような感じ)の坊ちゃん湯に浸かり、宿に戻る。坊ちゃん湯は宿泊施設ではない。 宿で食事を終えて、夜の松山をちょいと探訪。 バーに行きたいが、かつてこの地でバーに入ったことがない。そーゆーときは、行きつけのバーに店を紹介してもらうのが手っ取り早い。仙台、鹿児島、横浜、過去何度も助けられている京都のバーのⅰ店長に電話。 「それだったらYさんが一番じゃないですか?」 |
ⅰ店長は、松山をこよなく愛する共通の知人Y氏の名前をすかさずあげた。 (そりゃ、もっともだ) Y氏にTELし、お勧めの店を得た。 「ル・クラブ」はオーセンティックな尻の座りのいいバーだった。(もう一軒の候補は「関口」) 中世の甲冑などが並ぶ、ゴシックな店内。広島からやってきたオーナーはすでにこの地で20年とのこと。さっき電話した京都のバーの創始者Kマスターの大ファンなのだということがわかってちょっと話が弾んだ。 翌日、未訪問の物件を消費すべく市街地に向かう。城下町の常でお城まわりに官公庁が集まるのは松山も同様。繁華街、大街道のそばにある松山地裁、簡裁の隣に「坂の上の雲ミュージアム」がある。三角形の地上4階建ての造形で、地上から4階に至るまでスロープ構成になっており、回遊式に展示品を眺めることができる。とは言え、それほど興味をそそる物件もなく、壁面いっぱいのガラス越しに映し出されるレトロな洋館のほうが目を引いた。 松山地裁の裏山に建つ、この洋館は「萬翠荘」という。 重文に指定されており、なかなかに美しい。周囲あまねく翠なす樹木に覆われている様から萬翠荘と名づけられたそーな。旧松山藩主久松家の15代当主(伯爵位)の別邸である。陸軍駐在武官としてフランス生活の長かった伯爵の欧風趣味が反映している。昭和天皇の皇太子時代、松山訪問時にこの洋館に宿泊した。皇太子裕仁親王の絵も飾られているが、筆者はステンドグラスに魅了された。 松山は魚が旨いのだが、今回は郷土の名物料理を網羅して引き上げることに。 ふくめん(彩り豊かなこんにゃく麺料理)、今治ぜんざんき(鶏から)、宇和島鯛飯(鯛刺しの甘ダレぶっかけ飯)、鯛のなめろう、みかん稲荷(みかん風味の稲荷)、五色そうめん、じゃこカツ(じゃこ天のカツ版)、宇和島鯛飯は好物だったんだが、もはや健康的に危険物件となってしまった。ま、松山にお寄りの際の備忘としてお使いください。 |
| 日本三大秘境って知ってました? いや、日本三大××なら幾つも思い浮かぶんだけど、××の中に「秘境」って言葉をあてはめる了見がなかったもので、ちょっと取り乱してしまいました。 年末年始を温泉に浸かりまくるため、徳島の祖谷渓へ行った。この祖谷渓が日本三大秘境のひとつらしい。他の二つは、岐阜の白川郷、宮崎の椎葉村。白川郷って秘境なの?あと椎葉村って何?どこにあるの?人生にはまだまだ驚く余地はたくさんあるってことっすか。 祖谷渓へは、JR土讃線の大歩危から車で向かう。大歩危、小歩危は、高知に行く途中の明媚な車窓として何度か消費しているが、駅に降りたことはなかった。 大阪から岡山、そして大歩危から祖谷渓へ。都会から田舎へ向かう景色の変化の流れるような映像をよく見かけるが、今回「これがそれだわ!」と膝をたたいて得心した。深いV字谷を刻んだ祖谷渓の雛なこと! 陽を遮る対面の山が遠い南斜面に集落は集まり、そこだけは陽だまりの時間が長い。集落から離れた高地にある家はまさに斜面にしがみつくように建てられている。そして、うるさいぐらいの静寂。とにかく静かである。音がしない。ホテル最上階のベランダから見下ろすと、沈みゆく夕日が切り出す影が谷底に、実際以上に深く遠く落ちていくような錯覚を与える。「秘境」という言葉をかみ締め続けた2泊3日間だった。 せっかく祖谷渓に来たのだからせめて象徴的な物件は消費しておいた方がいいかな、と思っていたら、ホテルからベッドメイクの間「かずら橋」まで車を差し向けてくれるというありがたい提案があった。好意に甘えて地元出身のホテルの若者に案内してもらった。 「昔、自分の家より高所にある同級生の家に遊びに行 |
くと、気温がまったく違っていて寒さに震えあがりました」と九十九折れの道を慎重に運転しながら彼は言う。「秘境の湯」という投宿しているホテルから10分ほどのところに「かずら橋」があった。 橋は3年ごとに架け替える。だんだん緩んでくるらしい。今ではシラクチカズラの中にワイヤーを入れて強度を上げている。架け替えの直後が一番絞まっているとのこと。吊り橋体験は十津川の谷瀬の吊り橋以来だ。あの橋は日本最長(297m)にして高さが54m、人数制限があって一度に渡れるのは20名までだった。とにかくよく揺れて怖かった記憶がある。「祖谷のかずら橋」は長さ45m、高さ14mで谷瀬よりも小ぶりなので気楽に渡ろうとしたが、やはり橋は橋ごとに個性がある。かずら橋の両サイドにある持ち手のかずらが、持つと外側にけっこう広がるのである。(あ、なるほど、架け替えの直後が一番絞まっているってのはこういうことね)と心につぶやく。谷瀬は床面が板敷きで、隙間のない造りだった。こちらは丸太や荒削りの木をかけているが、隙間だらけで足元がすーかすーかしている。ふんふんと鼻唄まじりでスタスタ渡ってやろうという筆者の目論見は潰えた。三点確保をしながらの渡橋ははたから見ていたらかなりのへっぴり腰だったろう。橋のそばにある琵琶の滝も鑑賞した。 夜、温泉棟の灯りが消えると、満天の星が浮かびあがった。天の川も頭上を渡っている。石垣島以来の星空鑑賞。 最終日、大歩危駅に向かう送迎の車から見える祖谷渓は、山塊の間をたなびく霧か雲が雲上の絶景を描き出していた。 大歩危駅で列車を待つ間、これから街に帰るのだとの復帰感がひしひしと沸いてきた。北海道の層雲峡においてさえそんなことはついぞ思ったことがなかったから、これが秘境の秘境たる所以なのだろう。次は椎葉村か?どーやって行くんだ? |


| 沖縄岬めぐりの旅。 今回の目的地は、本島最北端の地、辺戸岬(へどみさき)。 最北端と言ってもそこは沖縄南の島。宗谷岬のような最果て感はない。海の向こうは鹿児島県だし。11月末とは言え、最高気温は28度だし。 以前、弥次喜太道中のレンタカーで1回だけ訪れたことのある辺戸岬だが、単独行となるとレンタカーは使えない。足となるのはバスしかない。 那覇から辺戸岬まで、高速、路線、村営、3種のバス乗り継ぎで4時間5分を要する。 しかも、日帰りをしなければならない。 那覇で19時に予約をいれちゃったから。 那覇空港国内線ターミナル1階出口前2番バス乗り場発となる名護BT(バスターミナル)行きの高速バス111系統に乗車。 その先は、名護BTから辺戸名(へんとな)へ向かう路線バス67系統と辺戸名から辺戸岬に向かう国頭村(くにがみそん)営バスへ乗り継ぐ。 11月下旬の那覇の朝は遅い。国際通り午前6時。夜はまだ明けていない。路面が濡れている。昨夜、雨が降ったか。天気予報では今日は晴れのはず。県庁前6時15分発のゆいレールで空港に向かう。8時発のバスでよかったのに勘違いして早起きしたため7時発のバスに乗ることになった。名護バスターミナルには定刻8時45分の到着。辺戸名行きの路線バスも、予定より1時間早い9時発の便になった。 本島北部はやんばると呼ばれるヤンバルクイナのいるエリア。行政的には国頭村(くにがみそん)になる。その中心が辺戸名。 沖縄南部から北部を結ぶ幹線道は58号線(正確には、鹿児島市から種子島、奄美大島を貫いて沖縄北部に上陸している)だが、辺戸名に向かう路線バスはバスセンターから名護十字路を左折し、市街をつきぬけ県道71号線に乗って北上した。途中、名護の黒豚ホルモンならここ!ちゅう「満味」の前を通過する。 国頭村の中心地辺戸名には9時54分到着。 辺戸名バスターミナルから大通りを100メー |
トルほど逆行したところに村営バス待合所があった。ログハウス風の外見に畳敷きの腰掛がある居心地のいい作りだ。 村営コミュニティバス、辺戸岬方面「奥」行きは始発が11時30分。次発は15時だから、始発狙いしかありえない。勘違いの早起きのおかげでここで1時間半強、足止めを食うことになる。 辺戸名大通りとは言っても時間潰しができるような店が軒を連ねているわけではない。西部劇に出てくる駅馬車が停車する一本道しかない町のようなものだ。待合所の中で畳に寝転がりながらバスを待つ。 ワゴン車サイズの村営バスのドライバー氏は郷土歴史家だった。沖縄の歴史に通じていた。運転席そばの席に座った筆者は、尚巴志による三山統一から第2尚氏となる金丸、そして阿麻和利の乱などの話で盛り上がり、意気投合した。ドライバー氏は、沖縄本島創世神のアマミキヨが最初に降り立った地、安須杜(あすむい)を愛し、琉球開闢七御嶽の中でも沖縄最高の聖地である「安須森御嶽(あすむいうたき)」のある国頭こそが久高島よりも神聖な土地なのだと力説していた。金丸も西方沖に浮かぶに伊是名島の出身だしね(故郷を追われたらしいが)と国頭からも追われた金丸への郷土歴史家としての関心の深さがひしひしと伝わってきた。 12時4分、バスは辺戸岬の停留所に到着。 辺戸岬は、隆起したサンゴ礁が台地状になった断崖絶壁の地。眼下には岩を噛む波濤の群れ。沖合い遥かには鹿児島県領与論島を望むことができた。安須杜(あすむい)の山々は、大石林山と呼ばれ、トレッキングコースが整備されている。辺戸岬の展望台から大石林山のある対岸を眺めれば、かつてNが頭頂部から顔を出した巨大なヤンバルクイナの展望台が見える。 13時44分に帰路のバスに乗る。14時18分辺戸名BT着。14時40分発15時30分名護BT着。渋滞で遅れたら際どい時間差の15時45分発那覇空港行きに首尾よく乗車し、17時17分旭橋BTで降りて、日帰り岬めぐりの旅を終えた。 |



画像右から2枚目・・・沖合にうっすら浮かぶのは与論島
| 12月に廃線となる留萌本線、留萌、増毛間の乗車を企図した筆者の計画は、夏の終わりの集中豪雨に流されてしまった。(コチラ) 稚内から宗谷本線で南下し、深川から留萌本線で終着「増毛」に向かうつもりだったが、遥か北の名寄で特急「スーパー宗谷2号」は運行停止となり、代行バスと高速バスを乗り継いですごすごと札幌に逃げこまざるをえなかった。 夏が終わり季節はうつろう。 廃線の日12月4日が近づいていた。 このまま座して廃線を待つわけにはいかない。 第二次攻撃をかけることにした。 南下作戦の失敗をうけ、再度の侵攻作戦は北上案を採用した。札幌から函館本線で深川まで上り留萌本線で増毛に行く。しかし、札幌、増毛間の往路を鉄道にすると増毛到着後、10分後に引き返す便に乗らないと3時間近く増毛にとどまらざるをえず、札幌帰着が18時25分となってしまい19時の別の予定に間に合わない。しかもこのスケジュールは往きも還りも大混雑の可能性がある。乗ってきた列車でそのまま帰るのも嫌だし。 ちゅうことで、往路はバスにした。 札幌、留萌間の高速バス「るもい号」は7時20分に札幌を出、留萌着は10時10分。路線バスの「沿岸バス」留萌発10時45分で増毛駅着11時19分。1時間半ほど増毛に滞在し、12時57分発の深川行きに乗れば「スーパーカムイ26号」に乗り継ぎ、15時55分には帰札できる。しかも往路は2790円とオトク(復路は指定席券で5470円)。 札幌駅バスターミナルから乗車し、留萌で降りたらさっそく強風のお出迎え。時あたかも大陸から雪を降らせる低気圧が押し寄せていた。こうなると北海道の沿岸部は、どこもかしこも強風の地となる。 留萌駅は絵に描いたような雛の駅だが、それでも他の留萌本線の駅よりはよほどにデカイ。 路線バスの停留所前には待合室が設けられてい |
る。風よけ、雪よけだろう。旅人は筆者のみ、あとは地元のオバチャンが3人。バスも空いていた。国道231号線を増毛に向かう。この国道は「日本海オロロンライン」の一部となっている。オロロンラインは小樽から稚内までを結ぶ国道、道道の愛称である。 バスは、海岸線をひた走る。 空も海も憂鬱な鉛色に沈み、海岸線に噛み付く波濤が幾重にも沖から連なってくる。 道が高台から海に向かうと、そのまま海中にダイビングしてしまいそうな錯覚を覚える。 やがて、バスは増毛駅停留所についた。終点はまだ先なので筆者が降りると先を急ぐかのように走り去る。 停留所は増毛駅の前にあった。 稚内と同じ終着駅の車止めが見える。 無人駅だった。ただし、売店はある。タコザンギとアマエビ汁を購入。 駅のすぐそばも海岸だ。バスから見えた寒々しい光景がここにも広がっている。 列車の到着時間が近づくとハンディマイクを携えたJR職員が現れ、12時47分着の列車が隣駅を定通したことをアナウンスした。 駅前の駐車スペースに続々と車が入ってくる。車から降りる人々は皆、大きなカメラをぶら下げていた。 (なるほど) 「鉄」は僻地へ車で来るのだ。「鉄」と言っても「撮り鉄」かもしれない。「乗り鉄」はきっと列車に乗っているのだろう。筆者は「鉄」ではなく「旅人」である。その証拠に列車よりも群がる「鉄」ちゃんを撮るほうが楽しい。 そして列車が現れた。2両編成だ。廃線を惜しみ乗りに来た「鉄」の皆さんのために増量しているのかもしれない。それでも座れずに立っている人も多い。ホームに吐き出される人数は思っていたよりも多かった。そのまま折り返しで帰る客は1組だけ。12時57分発の列車は思いのほか空き席を残して増毛を発った。 |


| 新大阪で地下鉄を捨てJRのホームに下りた。 入ってきた新快速に飛び乗る。 混んではいないが座ることはできない。東行きの新快速に新大阪から乗ればいつものことではある。どこに行くか、目的地を決めていなかったが車内アナウンスでこの電車が「近江今津」行きだということを知った。近江八幡や彦根、米原、長浜方面には行かず、京都を過ぎたら山科から湖西線に入ることになる。 (いっそ、乗り継いで敦賀まで行くか?) 敦賀をぶらぶらしてもいいし、小浜線に乗り換えて、小浜に行くのもいいかもしれない。 京都で乗客が降りて座席に座ることができた。 湖西線に入るなら進行方向右側がいい。琵琶湖を臨むことができる。晴天の秋の一日、湖の湖面が陽光をはじいてキラキラと輝いている。 琵琶湖は広い。そして古い。 面積は、東京23区や淡路島と同じ。そして数千年から数万年と言われる一般的な湖の寿命をはるかに越える400万歳という古代湖でもある。この年齢は世界で3番目。古代湖とは10万年以上存続している湖のことらしい。 1時間16分で終着駅「近江今津」についた。 敦賀まで乗り継ごうとしたら、新快速敦賀行きは40分以上待たないとやってこない。湖西線もここまで北上すると時刻表には1時間に2本しか表示されなくなる。 湖を眺めようかと改札を出た。 観光船の案内があった。駅を出て湖にむかって2ブロックほど行くと今津港観光船乗り場があるらしい。 「竹生島」行きの船がここから出ている。 琵琶湖にある3つの島のひとつ、竹生島は全島が寺社領になっている神聖な島だ。724年に行基が開いた宝巌寺とそれとは別に都久夫須麻(つくぶすま)神社がある。筆者は、対岸の長浜からしか島に渡れないと思っていたのだが、間違っていたようだ。 (と、すると竹生島に渡って対岸の長浜にも行けるのではないか) |
果たして「びわ湖横断航路」として今津港から竹生島経由で長浜港に行く乗船料が掲示してあった。これはいいイベントになるとさっそくチケットを購入。2830円を支払う。 今津港から竹生島までは25分。竹生島、長浜間は30分。今津港から見える竹生島は、長浜から見えるそれよりも間近に見える。 船は、琵琶湖八景にも数えられている湖に浮かぶ緑色のドームのような島に向かう。途中、矢印型に並べられた棒のようなものが見える。障害物にあたると障害物沿いに移動する魚の習性を利用して、沖合いの矢印部で捕獲する?(えり)漁の竿だ。 船が島に接岸した。降船したら寺社域に入るため300円の拝観料を支払う。 急勾配の石段が続く先に宝巌寺があり、途中右折すると都久夫須麻神社の鳥居を潜る。寺と神社は1本の道で円環のように繋がっていて、どちらを先に選んでも両方訪れることができる。伏見城の遺構と伝えられる神社本殿や、日本三弁才天のひとつと千手観音を本尊とする寺、そしてその三重塔、国宝の唐門は秀吉造営の大阪城の唯一の現存遺構とされている。重文の船廊下は秀吉の御座船「日本丸」の船櫓を利用して立てられた。片桐且元が植えたもちの木などコンパクトにまとまっているが、なかなか消費物件が多い。 島の滞在は50分。長浜港行きの船に乗る。 琵琶湖には460本の河川が流れ込んでいるが琵琶湖から注ぎ出ているのは瀬田川のみ。瀬田川は宇治川となり、木津川、桂川と合して淀川になる。滋賀県民が自分たちを見下す京都、大阪府民へ「水、流さへんで」とよく言うのはこの地勢あってのことだ。 長浜には何度も来ているが鉄道スクエアが未訪だった。現存最古の駅舎とD51、ED70交流機関車を見る。もちろん筆者は「鉄」ではない。スクエア内も黒壁スクエアの界隈もヒラヒラと振袖姿の女子が大量にいる。どうやら長浜着物大友宴会の当日だったようだ。 新快速に乗って帰阪。 |

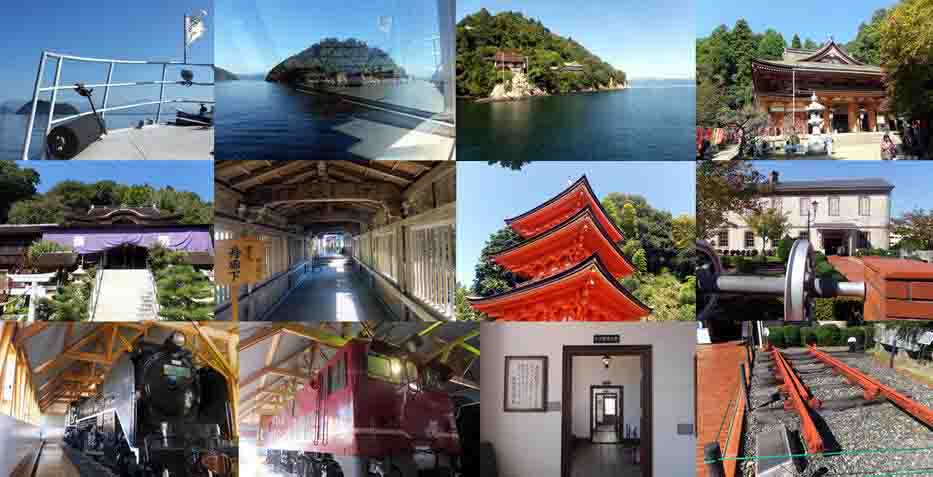


石垣島行10 →back (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
| 腰の不安を抱えていたため、夏の始めにシュノーケリングツアーで今年のサマーヴァケーションを誤魔化そうとしたが無理だった。海中という非日常への想いもだしがたく、夏の終わりにやっぱり潜ることにした。 1等星をすべて見ることができ、88ある正座のうち84を見ることができる島、石垣島へ。 ダメージを受けた腰が完全復調したわけではないが、初夏のツアーでなんとかなりそうな感触はつかんでいた。 途中、那覇に立ち寄り、「ピキタン」と「グルメエッセンス」で糖質制限な夜と昼を過ごす。 「グルメエッセンス」はゆいレール古島駅前にある。首里に近づく途中の駅だからそれなりの高台にある。海も近いから海風が爽やかだ。 石垣へは夕刻の到着。なんと夜をドライ(酒を飲まず)に過ごした。「磯」で郷土料理のミニセットを。 尖閣諸島での中国との悶着のせいだろう。海保の船が今まで見たことないほど停泊している。 もちろん、中国側も海警や偽装(?)漁船の数をそれ以上に増やしていることだろう。 今まで石垣で軍を見たことがなかったが、海自のP3Cやハーキュリー、陸自のチヌーク、UH60も哨戒している。緊迫の度合いは本土にいてはわかりづらい。現場でなければわからないのはいつの世も同じだ。しかし、政治上の諍いはどこ吹く風とばかりに石垣港の沖にはゴールデンプリンセス号が停泊している。10万トン強。石垣港は7万トンまでしか接岸できないから(ちなみに那覇港は14万トンまでOK)乗客は、ドリカン(ドリーム観光)のテンダーボートで島に上陸している。客船の客は宿泊施設は使わない。おまけに1泊もせずに沖縄本島にむかってしまう。 石垣島には今年、台風が来なかった。 海がかき回されず、海水温が高いままなので、サンゴの白化が進んでいる。いつも以上にエメラルドグリーンが美しいのは海底のサンゴが白くなってしまっているせいだ。 馴染みのショップのお迎えの車に乗る。 「今回も体験でごめんなさい」いつものお詫び。 |
指折り数えてみたら、26回目の体験ダイビングだ。年に1、2回、それぞれ1日だけ潜れればそれで満足なのでライセンスへの希求心が薄いのがいけない。シュノーケリングの後、名蔵湾と御神崎、川平石崎でダイビング。 川平石崎のマンタシティは停泊できるボートが5隻までなので順番待ちになる。待った甲斐はあった。今まで見たマンタの中でたぶん一番大きな固体を、一番近くで眺めることができた。海亀も見た。気が晴れた。 宿に戻り、土曜日6時から放映のQTV「ひーぷーホップ」の緩~い笑いに和む。どこか北海道の「水曜どうでしょう」の緩さと似ている。北と南の果ては、どこかしら共通したものがあるのだろうか。 夜、「担たん亭」でステーキ。ホテルの前に屋台のバーが出ていたので冷やかしに1杯。 空港に向かう道すがら、沿道に常緑樹のヤラブ(てりはぼく)が隙間なく植えられていた。台風の風対策なのか、少し伸びすぎのきらいがある。 帰路も那覇に立ち寄り、夜を過ごす。イタリアンの「ha-na」。路地裏にある尻の座りのいい店で、いつもの定位置に案内される。1年半ぶりだがかわいいネエネエはにこやかに迎えてくれた。 「おひさしぶりですね、痩せられました?」 健康診断にあわせて4キロ半ほど痩せたのだ。 満喫して、バーをあたったが、去年、マスターの逝去を伝えられた「バーステア」は開いていないようだ。やはり後を継ぐのは無理だったかな。 帰阪の昼は「ジャッキーステーキハウス」へ。 そう言えば「れ」ナンバーの車が多い。レンタカーは「わ」ナンバーだと思っていたが、「れ」ナンバーもそうなのか。 老母に頼まれたかりゆしウェアを求めて国際通りのショップを何軒も覗く。要望が細かいのだ。何軒目かの「マンゴーハウス」という店で「ありがとうございます」と言われた。(まだ買ってないんですけど)着ているかりゆしが去年、マンゴーハウスで買ったものだった。しかも、「そのデザインは僕が描いたんです」と言われ、あらそーなん?てな感じ。 |


金沢行17 →→→back 金沢行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
| サンダーバードから降りて、見慣れた街を歩きながら(俺は金沢に観光で来ているのだろうか)と考えていた。チケット購入時のアンケートにあった旅の目的で『ビジネスか、観光か』の選択を迫られたからだ。 (本当は、帰省といってもいいんだがな) 我ながらうまい言い回しだと思った。 心の故郷ではあるが、戸籍上の故地ではない。 何度かの訪問で、もはや観光資源にあたる気持ちもない。市内散策の後の「食事を楽しみにしている」というのが最も実相に近い。無論、食事のために来ているわけではない。しかし、食事以外に何をしているわけでもないのだ。 予約が取れれば金沢へ行こうと決めて「乙女寿司」に電話をしたが案の定飛び込みは無理であった。「千鳥寿司本店」なら大丈夫かもしれない。金沢を代表する寿司屋のひとつだし、最近は訪店回数が増えている。「小松弥助」は店をたたんで久しい。京都で店を出すという話を漏れ聞くのだが、いずれに根があってのことか葉があってのことか、確度は不明である。「小松弥助」出身の「志の助」は行ったことがないので選択肢にあがらない。 (そうだ『太平寿司』はどうだ?) 思い立って電話をいれたら席がとれた。ならばとサンダーバードに飛び乗った。久しぶりとの認識があったが記録を見返すと、なんと前回の訪店は2006年だった。 (10年ぶりですか?!)一昔も前だったのか。 店は野町にある。金沢市街地からはタクシーで2300円程度の距離だ。つまり、やや遠い。 大将は今や金沢を代表する名士のひとりである。地元の話になれば必ず誰かしら知り合いの名前 |
が出てくる。 基本、おまかせの店だが、珍しいのは料理(アテ)の合間に時折、握りを挟んでくること。アテを食べ過ぎて握りが食べられなくなるのがもったいないからだそうな。 大将の横に立つのは「タカドン」。これは10年前に当方が勝手にネーミングした握り方。 「以前、馬替から歩いてきたら、店にたどり着くかどうか不安になった」などと談笑しながら、酒がすすんでゆく。10年前にはすでに店に3年目だったというタカドンは13年選手だ。 気持ちよく店を出て、11月には30周年を迎えるバー「スプーン」でいつものひと時。 翌昼は小辰野通りにある洋食「New狸」へ。ファミリービジネスで、先代と当代の親子夫婦で営まれている。若女将の愛想の善さで、常連となる客も何割かはいるのではないか。かく言う筆者も何度目かの訪店で「お帰りなさい」と言われて訪店の頻度が上った。 この日はその若女将がいない。よく出前に行くのだ。若大将の前に座る。今まで笑顔を見た記憶がないぐらいにブッチョな大将が、笑みを浮かべてオーダーを確認した。ちょっとビックリ。ほどなく若女将も戻ってきていつもの笑顔を向けてくれた。一安心である。 離沢のサンダーバードに乗る前に金沢駅構内アントの一角にあるおでんの「黒百合」に寄る。昼時だったが折りよく座れた。昨日からの抑制された酒食で安定した精神状態を保てたのだろうか、せっかく来たのだからと欲にかられることなく軽く2、3品とビールで仕上げることができた。 帰路のサンダーバードでも呑み過ぎることなく過ごした。珍しいことである。 |
| 天下分け目の・・・と言えば、天王山。 織田信長を本能寺に討った明智光秀と、毛利との対陣を解いて中国大返しを敢行した羽柴秀吉が戦った山崎の合戦を見下ろす山である。 京都乙訓郡(おとくにぐん)大山崎町にある。 ここを西進すれば、大阪平野に入り、東進すれば京都盆地に入る。言わば、京阪間の大動脈路を扼す重要拠点となっている。 京都から大阪に向かって流れる桂川、宇治川、木津川がこの地で合流し、淀川となるが地勢は、これらの川を挟みこむように、天王山と岩清水八幡宮を山頂に頂く男山が寄り添い、地峡を成している。この隘地に、天王山の麓を西国街道(現171号線)が、男山の麓を京街道(現国1)が走っているため、古来、京阪間の戦はこの地において干戈を交えることが多い。 JR在来線、新幹線、阪急、京阪の各線もこの地に集線する。 JR京都線(東海道本線)山崎駅のそばにサントリーの蒸留所があり、そのあたりのカーブを「山崎の大カーブ」と呼び、撮り鉄には広く知れ渡っている。もちろん筆者は関係ない。 さて、天王山。 標高は270m。 京都の地下に広がる巨大な水脈(というか自然の地下ダム)の地上への唯一の漏出ポイントで、サントリーが蒸留所をこの地に定めた一因も良質な水の確保にあった。水を多く含む土壌のせいか山の地盤が弱く、名神高速の天王山トンネルは難工事となった。 以上が天王山、ワンオーワン講座である。 筆者は、3月末以来4ヶ月近くも続いているぎ |
っくり腰の後遺症による運動不足を解消するためにやってきたのだ。サントリーの蒸留所で酒を飲むために来たのでも、山崎の大カーブを走る列車を撮るために来たのでもない。 JR山崎駅前は競馬場へ行くバスの発着場となっている。しかし、駅前にはコンビニが1軒あるだけの雛である。 駅から京都方面に少し歩けば5線を跨ぐ大きな踏切がある。その踏み切りを越えれば、すぐに天王山登山道口だ。 270mの山に登るのに覚悟はいらない。とは言え、炎天下の備えにペットボトル飲料は2本用意した。 「アサヒビール大山崎山荘美術館」の脇をすぎ、すぐに「青木葉谷展望広場」の横に出る。この広場からは、樟葉方面の大阪平野を望むことができる。 「旗立松展望台」は七合目あたりか。 山崎の合戦場はここから望める。羽柴、明智両軍の配置図などもある。ここで千成瓢箪の旗印を掲げ、士気を鼓舞したらしい。桂、宇治、木津の三川が合流し淀川となるあたりだ。 「十七烈士の墓」は明治維新、禁門の変での長州軍敗戦により、久留米藩の真木和泉らが自刃した地に建てられている。 自玉手祭来酒解神社(たまてよりまつりきたるさかとけじんじゃ・・・読めん!)祭神は牛頭天皇で天王山の名の由来となったそうな。本殿横の神輿庫は板倉形式では日本最古、鎌倉時代前期の建築で重文指定だ。この神社を折れれば、山頂までは一気呵成である。 下山時、道を間違えたら傾斜がきつかった。 |


| 稚内駅前に札幌行き高速バスが停車していた。 (鉄道よりこっちの方が安いし、確実性が高いんだよな)と思いながらバスを横目に通り過ぎた。 昨日の「寿司竜」での大将との話を思い出す。 「雪が降ったら車の方が確実だ」 「鉄道の方が雪には強いんじゃないですか」 「最近は駄目だね。すぐに止まる」 JR北海道は、民心を掴み損ねる不祥事が多かった。 北海道内の鉄道は、釧網本線の釧路、網走間、根室本線の滝川、富良野間、富良野線の富良野、旭川間、日高本線の苫小牧、様似間、道南は海峡線から函館、長万部、苫小牧、札幌、余市を結ぶラインしか乗車経験がない。過去の道内移動は車がメインだった。スーパーペーパードライバーだから、ナビゲーターになるか、バスかタクシーに乗るかだが。拠点都市間(函館-札幌(丘珠ですが)や、網走-札幌)はボンバルディアでの移動だ。アメリカか?ちゅうのんが北海道。 そんなこんなで、赤字路線の多いJR北海道は、留萌本線の留萌、増毛(ましけ)間を年末には廃線とすることを発表した。 「鉄」ではないが、乗っておくことにした。 稚内から滝川で下車、滝川から増毛までを往復し、再び滝川から札幌へ向かう計画だった。 稚内駅でスマホをいじっていたら、運行情報に留萌本線の全面運休情報が出ていた。 窓口で確認したら事実だった。 久しぶりの「乗り鉄」計画はスタートから頓挫した。通過した台風8号の影響か、道内は活発な雨雲に覆われていたのである。 やむをえない。乗車券は札幌まで買ってあるので特急券を滝川停まりから札幌までの通しに買い換えた。 それでも、稚内、旭川間の未乗車区間を走破できるから良しとしよう。 特急スーパー宗谷2号は、定刻の朝7時に稚内駅を発車した。 陰鬱な鉛色の雲が空を覆い、車窓には雨だれが伝っている。 音威子府を過ぎ、名寄に近づいた頃、車内のあちこちでスマホが鳴り出した。なにごとならんと思っていたら、市町村の出す避難指示の受信音だった。名寄のナントカ川の一部が氾濫危険水位を越えたらしい。 車内アナウンスが流れた。 「この列車は名寄までとなります。名寄からはバスによる代行輸送の予定です。現在、代行のバスを調達中です」 名寄駅には定刻の10分遅れで着。。 改札に一番近いと目星をつけたドアに立ち、真っ先に飛び出す。非常時の筆者は、先行逃げ切り型だ。後手にまわるのは好きじゃない。それが奏功することもあれば、裏目に出ることもある。それでも自分で納得の行く運命を迎えたい 駅員が特急からの乗客を誘導する。 駅前には3台の大型バスが停まっていた。 先頭を切る筆者は1号車に乗り込んだが、すでに先客がいた。他の列車からの乗客か。運転席そば(つまり出入り口そば)の空き席に座る。 バスは旭川まで行くという。 旭川札幌間のスーパーカムイは運行していた。 途中トイレ休憩のために士別駅に寄ると言う。 代行バスはコンボイを組むようだ。満席になったからと言って1台が先行することはない。乗車客数のチェックも念入りに行われた。 士別に向かう途中でもバスの中でスマホの着信音が鳴り響く。今度は士別町からの避難指示だ。 行く先々に災いが待ちうけているような錯覚を覚える。 |
実際は、各市町村の警報、指示を拾えるエリアに順次入っているのだろう。 途中、そこここの脇道が冠水し、警告灯を回転させた警察車輌と道路整備車輌があちこちに停まっている。幸いバスが走る幹線道は遮断されることはなかった。 士別駅のトイレを使ったトイレ休憩タイムは少し長くかかった。大きくもない駅の男女トイレを3台の大型バスに分乗した人々が利用するのだ。特にこういう時は女性が大変だ。 到着した旭川は土砂降り。バス前に立っていたJR職員に念のため聞いてみた。 「このバスで札幌へ行くことは?」 「申し訳ありません」 先頭バスに乗車していた筆者は、みどりの窓口に一番で飛び込んだ。 「札幌まで行けますか?」 「すべての列車が運行停止しています」 「バスは?」 「中央バスセンターに行ってください」 「どこですか?それは」 旭川中央バスセンターは、駅から2ブロックほど離れた場所にあるそうな。 「ツルハを左に曲がってください」 「わかりました。ですが、ツルハって何です?」 「ドラッグストアです」 土砂降りの雨の中に飛び出した。排水口から腰の高さにまで水が逆流して噴き出している。 旭川には僅かながらも土地勘があったことも積極的な活動を促進させているかもしれない。 中央バスセンターへは後続を断然引き離して到着した。そもそも後続があるのかどうかも定かではない。 札幌までの高速バスのチケットを買い、30分に1本程度のバスの停留所に並ぶ。これならばやってくる次のバスに乗れるという位置だ。 バスに乗車して外を見ると、バス待ちの行列が伸びていた。最後尾は3本待たねば載れないと整理係りがアナウンスしている。 大雪山系層雲峡に向かうときに札幌から、この道央自動車道のラインを使用するので、途中の道路もそこそこ見覚えがある。 高速に上って、ホッと一息いれたが、しばらくして運転手がアナウンスを流した。 「道央自動車道は土砂崩れのため深川で一旦降ります」 トラブルは、固まってやってくる。 下道は当然のように混んでいた。 札幌に着くのはいつになることやら。 19時にすすきのの「たる善」を予約している。それまでには着くだろう。 砂川で再び高速に乗る。土砂崩れ区間を迂回するだけだったようだ。 旭川の土砂降りは何だったのだろうというほど落ち着いた天気の札幌へ到着。時計の針は16時を指していた。朝7時に稚内を出て、9時間、かつての九州一周計画のときのトラブルを思い出した。今回はあれほどではなかった。 駅前バスターミナルまで乗車し、特急券と乗車券の払い戻しをうける。払い戻しは緑の窓口ではなく、改札の精算窓口で行われる。旭川で精算なんぞしていたら、この時間には着いていなかっただろう。駅構内のアナウンスが「スーパーカムイの運転が再開されました」と言っている。旭川、札幌間は1時間半だ。あのまま旭川で待っていても、なんとか「たる善」には間にあったかな、などと思いながらも、先行逃げ切り成功事例として記録。それにしても、早朝の稚内であのバスに乗っていれば・・・とも思うのであった。 |
稚内行6(追憶編2) →back 1稚内行 2望郷編 3徘徊編 4旅愁編 5追憶編 6追憶編2
| 筆者の気配に驚いて飛び出してきたエゾ鹿は、すぐに警戒心を解いて草を食みだした。時折首を上げるが、こちらのことは無害だと慢心しきっている。ろくに見ようともしない。やがて鹿の子供たちも集まってきた。 (いいか、おまえたちは、害獣なんだぞ。もっと悪びれたらどうだ) 筆者の悪口は無論、通じない。膝を降り、草地にペタンと座りこんだり、足でからだを掻いたりしている。 (尻をむけるな!尻を掻くな!) 鹿に悪態をついてもヤクタイもない。 とぼとぼと駅まで戻ってきた頃には歩き疲れていた。 ノシャップ岬へはバスで行くことにする。 宗谷岬行きのバスは便数があまりないが、ノシャップ岬行きは、距離も近いし本数も多い。 終点「ノシャップ」で降りる。稚内公園から見えた自衛隊の分屯基地のレーダーサイトが間近に見える。 海に向かって少し歩く。バイカー御用達のウニ丼で有名な「樺太」は閉まっていた。売り切れと同時に閉店なのだ。 ノシャップ岬に陽が沈もうとしていた。 この地では海から日が昇り、海に落ちてゆくのである。 岬に立つわずかな人影と、岬の象徴のイルカのモニュメントがシルエットになっていた。 夏を終えようとしている岬に商店から流れるラテン音楽がこだまして寂寥感がいや増す。 柵の上に水鳥がとまっていた。 近づいても逃げようとしない。 |
いい画(え)が撮れた。 海の向こうに浮かんでいる利尻富士は、開基百年塔のときと同じく、ここでもシルエットでしか伺えない。 町に戻る。 「次はもうやってないよ」と12年前に大将から言われた「寿司竜」はまだ営業していた。初めて訪店した17年前の、「タコシャブなんてやめときな」との男前な発言を懐かしみ、大将や女将さんとの時を過ごす。72歳になったという大将は本気で引退を考えているようだ。まだ、続けて欲しいと思うのは旅人の我侭ではある。 翌朝、駅にむかう。 留萌本線の留萌、増毛(ましけ)間の廃線が年内の12月4日と決まっている。 筆者は「鉄」ではないが記念に行ってみようと思った。 朝7時の特急スーパー宗谷2号に乗れば、途中駅深川に11時に着く。留萌本線増毛行きは11時8分の接続。終着増毛には12時47分。57分には増毛を出て14時28分に深川に帰ってこられる。特急スーパーカムイ26号で14時49分発、札幌着15時55分という計画をたてていた。 稚内駅前のバスターミナルに停まっていた札幌行きの高速バスの横を通り過ぎる。 この日、この1日を象徴するシーンとして、映像的にはスローモーションのカットにしてとっておきたいくらいだ。しかし、神ならぬ身の悲しさ。まだ筆者はこの日、わが身を待ち受けている運命を知るよしもない。 |

稚内公園の風雪の門、自衛隊分屯基地

上、下ともにノシャップ岬

稚内行5(追憶編) →back 1稚内行 2望郷編 3徘徊編 4旅愁編 5追憶編 6追憶編2
| 初めて訪れたのは1999年。 夏の終わりだった。 2回目はその5年後、2004年の夏が始まる前だった。 それから12年の歳月が流れた。 2016年、三度訪れた北辺の町では、短い夏が終わろうとしていた。 すでに周囲に蝉の声はない。そもそも、この町で蝉の声を聞いた記憶もないが。 稚内空港から市街地にむかうバスが交差点でもないのに停車した。前を見ると、エゾ鹿の親子が悠々と道路を横切っている。鹿が日常に溶け込んでいる。そんな土地は北海道以外では奈良と広島(宮島)しかない。 駅前バスターミナルで降りる。 北防波堤ドームは、ローマ様式の豪奢な姿のまま、今もそこにあった。波浪から町を守るための設備にもかかわらず、まるで波浪が襲いかかってくるようなデザインだ。 ドームの内側にはバイカーやサイクリストのテントが並んでいた。以前に見たときよりも数が増えている。町は明らかに緩やかな衰退の中にあるが、北の大地に憧れるツーリストは増えているのかもしれない。 駅舎が新調されていた。映画館も入っている。小ぶりではあるが、綺麗な商業モールとなっていた。ホームも1面2線から1面1線に変わり、昭和の香り漂う以前のそれとは様変わりしている。北端のレールはかわらずにあったが、新駅舎の中をレールが貫き、出入り口から外に抜け、以前のままの屈曲した列車止めが駅舎の外にレイアウトしてあった。この列車止めの位置が以前の位置ら |
しい。12年前の画像と見比べて感慨に耽った。 12年前は老朽化した非常にスリリングなロープウェイがあった丘に今はゴンドラの姿はない。かわりに遊歩道が整備されていた。徒歩で稚内公園を登る。風雪の門まで350m、開基百年記念塔までは1650mある。途中の道は、12年前のままである。風力発電の風切り音が低い唸りをあげている。回転する羽の真横を通ったとき瞬間的に音が消えた。 開基百年記念塔は、海抜170mの丘の上に80mの高さで据え付けられている。台風8号が通過したばかりの北海道は天候が不順だった。展望室から見える利尻富士はシルエットでしか伺えない。 相対する峰にある空自、海自、陸自分屯基地のレーダーサイトが、アーミーな雰囲気を漂わせている。 来た路を戻る。 馬の背のような峰の稜線に道路が勢いよく一筆書きされたように伸びている。つづら折れと言ってもこの地では内地のようにせせこましく右に左に屈曲はしない。緩やかな曲線で海に向かっている。海に飛び込むようなというのは誇大な表現だが、他に遮るもののない地形がそう思わせる。12年前は晴天の下、眼下の海の蒼さに心を奪われたが、今日の海は鉛色の憂色を浮かべていた。 入港するフェリーの汽笛が小さな町の後背にあるこの丘にこだまして、防波堤のうちに溶けてゆく。 道を下っていると、不意に草むらからエゾ鹿が驚いたように跳ね上がった。 (びっくりさせるな!こっちも驚くわ!) |

北防波堤ドーム

撮影:2016年

撮影:2004年

撮影:2016年

撮影:2004年
| 石垣島の数ある離島の中で、西表島だけは観光ツアーを利用した方がいい。他の島はぶらりと気ままに立ち寄って、無計画であっても行き当たりばったりで島内を巡ってなんとか帰ってくることができる(スーパーペパードライバーの筆者基準では機動力は最低限、徒歩、あるいはチャリ)。西表島はその点、島が広いわりに島内の移動がちょっと不便なのだ。筆者はかつて「一般客」として不安な道行を経験している。だから、今回は観光ツアーに便乗することにした。 「しげた丸で巡る奥西表ツアー」である。 朝、ホテルに迎えの車が来た。離島ターミナルへ向かう。八重山観光のツアーデスクで料金を支払い、往き帰りの船便の説明をうける。 西表島の上原港へ定期高速船で渡った。この港は既述のとおり、無計画の極みの果てに浦内川ボート遊覧とカンピレーの滝までのトレッキングをした際に降りた港である。その時に得た教訓が「西表に行くなら周到に計画をたてるか、ツアーを利用しろ」であった。今回、その教訓を生かすことができた。 港で待っていたツアーガイドが車で祖納港へ案内してくれる。途中、浦内川の河口を通過する。 (そうそう、ここ、ここ) 景色に見覚えがあった。バス停の位置すらほぼ記憶の通り。 祖納港からは「しげた丸」に乗船。同行のツアー客は12人くらい。皆カップルかグループである。孤高の旅人は筆者のみ。クルーザは、クイラ川を遡上する。周囲はマングローブの林。さらに水道の奥に入り水落の滝を遠望する。 とって返して船浮集落に接岸し、上陸。 急峻な山岳に囲まれ、陸の孤島と化している人 |
口50人にも満たない集落である。「東郷平八郎上陸の地」と書かれた看板があった。日露開戦前に立ち寄ったらしい。さらに「イリオモテヤマネコ発見捕獲の地」碑がある。地元ではその昔、貴重な動物性タンパク源として食べちゃったいたそうな。天然記念物指定以前の話だろうが。 船浮集落を後にして、サバ崎とイダの浜で2回のシュノーケリング。サバ岬には、ゴリラ岩がある。(壱岐みたい。あ、あれは猿岩か) ライフジャケットを着てのシュノーケリングは気楽でいい。疲れたら体育座りのようにあおむけになってプカプカ浮いていられる。シュノーケルクリアなどをしなければいけないときもこれならばパニックにならずにすむ。初めてシュノーケリングをした時、基本的に背中を太陽にさらしていることに気づかず、体の裏側が日焼けでひどい目にあったことがあるので、日焼け止め対策もしっかりした。 海に浸かり、サンゴと魚を見て日常から解放され、星砂の浜でコーヒーブレイクをして主島に戻った。 夜、「担たん亭」で石垣牛のフィレステーキはルーティンワークだ。 そう言えば、今年は、まだ台風がひとつも発生していない。 「台風ができませんね~」とタクシードライバーに水を向けると「フィリピンの方でタマゴはできているんだけどね~」3台のタクシーで皆、タマゴって言っていた。熱帯低気圧のことだろう。それから去年の台風21号の話もテッパンだ。与那国島の被害が凄かった。風速81メートルは観測史上4番目の強風だが、思い出した。筆者は奴のおかげで去年、本島でのダイビングを諦めたんだ。 |
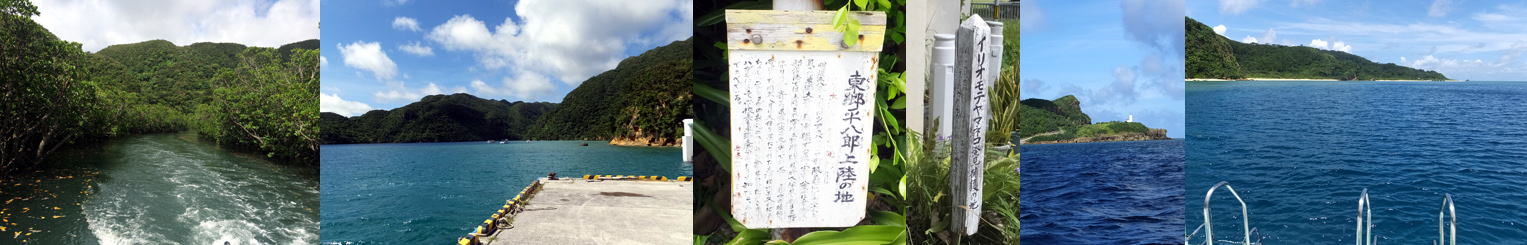
画像左から クイラ川のマングローブ 船浮港 右端から イダの浜 ゴリラ岩とサバ岬
石垣島行9 →back (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
| 今年、沖縄地方の梅雨入りは遅かった。 5月16日に入梅。 しかし、梅雨明けは異例の早さで訪れた。 6月16日に梅雨明け宣言。よし!降り続く雨でびしょびしょの内地から夏空広がる沖縄へ。毎年恒例のエクソダスだ。 伊丹空港で待っていたのはトリプル7(777)-300(ダッシュ300)。747の退役に伴い、ANAが保有する一番大きな機材となったが掲示板には満席の表示。 石垣に向かう途中、那覇で乗り継ぎ。 空港からゆいレールに乗り県庁裏にある糖質制限イタリアンの「ピキタン」に寄る。頼んでおいた糖質制限ランチを取り、テイクアウトの糖質制限ドルチェを入手。夜、ドルチェをつまむのだ。 石垣行きの便は737-500。ANAでは一番小さいボーイング。そのせいかこれまたほぼ満席に近かった。 例年なら体験ダイビングに興じるが3月下旬に患ったギックリ腰が完治していない。ウエイトとボンベを背負うことに不安を覚え、いつものショップでのダイビングを控えて八重山観光の「カヤマ島無人島シュノーケリング」を予約した。浮かんでいるだけなら腰の負担は軽かろうとの判断だが、南ぬ島(ぱいぬしま)石垣島空港に降り立つと観光会社から連絡が入った。 「最少催行人数(4名)に届かず、ツアーは中止になります」 (がひーん) 「実施が決まっている別のツアーに振り替えられますか」 「しげた丸で巡る奥西表ツアーなら」 「それでお願いします」 |
しげた丸に乗りこむことになった。 今回の宿は市街地から離れたリゾートホテル。とれなかったのだ、市街地のホテルが。以前にも宿泊したことがあるので土地勘はある。そばに「舟蔵の里」という郷土料理屋があり、そこで夜を楽しむことにした。 ホテルから歩いて5分もかからない。海岸沿いを走る道からは、さとうきび畑のむこうに天文台を頂いた前勢岳が見える。傾きつつある陽の光をうけて緑が濃い。藍が混じり始めたバックの蒼穹とのコントラストがくっきりと美しい。 店の敷地は広かった。 沖縄の郷土料理は畢竟、家庭料理の範疇だ。ご馳走というほどではない。旨い不味いと目くじらをたてる必要はないから気軽に楽しむ。 ゴーヤチャンプルー、カツオのネギまみれ、スーチキーの炙り、牛スジ煮込み、豆腐ようなどでオリオン生ビール、泡盛を2合。 古酒(玉の露7年)の香りがいいのに驚いた。牛スジ煮込みの脂がうまかったのもめっけもの。 ホテルに帰る道すがら、空を見上げると夜空には満天の星。 幹線道ではないので信号がない。街灯もない。車もない。周囲はさとうきび畑。反対側は海。明かりがないから星空が美しい。眼窩に飛び込んでくるような北斗七星を見たのは久しぶりだ。 ホテルのパブリックバスで露天風呂に浸かり、屋上のスターダストテラスでデッキチェアに寝そべり、天の川を指でなぞる。 日常生活からの逸脱度マックス。 部屋に戻り、那覇から持ってきた「ピキタン」のドルチェをつまむ。 |

| 世界で唯一の木造十三重塔は奈良県桜井市多武峰(とうのみね)の談山神社(たんざんじんじゃ)にある。 近鉄、あるいはJR「桜井駅」からコミュニティバスで終点「談山神社」まで25分、料金は490円(2016年05月現在)だがバスが着いた先は深い、実に山深い。市街地からわずか25分でこれだけ山中に分け入ることができるとはさすが奈良である。 そもそも桜井駅前(南口)に店は少ない。コミュニティバスの発車時間までの1時間弱を潰す喫茶店があったのは奇跡である。もちろんナショナルチェーンではない。地元密着系だ。朝9時、店内には先客が4名ほどカウンターに座っている。筆者は通路をはさんだテーブル席に座った。カウンター席の座の中心はおばちゃんだ。昨日の相撲の話をしている。聞き耳をたてる必要はない。開け放たれた店の扉のむこう、歩道の先10メートルまでは響き渡る大声である。横綱の品行についての意見を述べていた。大阪出身の力士(今場所十両入りした)のピンクの締め込みについては褒めていた。 話題はめまぐるしく変わる。 「そー言えばどこそこのうどん食べた?」 「いや」 「食べたほうがええよ。できたときはえらいまずかったんで1年ほど行かんかったけど、この間行ったら味が良ーなってる」 なるほど。 時間が来たので店を出る。バス停にむかう筆者の背中をおばちゃんの豪快な世間話がいつまでも追いかけてくる。 歳をとり、地域コミュニティに参加するにはか |
なりハードルが高いことが判明した。 談山神社の祭神は藤原鎌足である。 藤原鎌足が中臣鎌子であった頃、中大兄皇子(後の天智天皇)と蘇我入鹿忙殺の談合をしたのがこの地であったらしい。これにより多武峰は「談峯」「談い山」「談所が森」などと呼ばれるようになり、鎌足死後、長男の定慧が建立したというのが「談山神社」の縁起である。 拝殿に向かう石段は140段。石段の麓の受付が閉まっていたので石段途中から迂回路をとり、西の入口で拝観料を支払う。本殿、拝殿の先に神廟拝所と権殿、十三重塔が翠したたる新緑の森に浮かんでいる。かなりいい絵である。 十三重塔は高さ17メートル。入口から見ると存在感があるが、近づくにつれ何やら縮んでしまうような印象だ。 拝殿内の勾欄付廻縁に吊るされた灯篭の列が神妙な雰囲気を醸し出す。 神社の周囲の軽食屋、土産物屋には、玉や串のこんにゃくがあった。やっぱ寺社仏閣の山には(力)こんにゃくが良く似合う。奈良漬、三輪そうめんのふし(裁断時の余りもの。掛けた時の曲がり目)、しいたけなども並んでいる。 桜井駅北口からは大神神社へ、南口からは飛鳥方面石舞台行きのバスが出ている。また、山辺の道と呼ばれる日本最古の道の一部、16キロのトレッキングコースが天理駅まで続いている。筆者は、かつて天理駅から数キロを歩いたことがある。道はさらに天理から奈良へと至る。王朝の歴史の中でも創建の時代を刻んだいにしえのエリアがここだ。それは京都(平安の都)よりも草深く、闇が深いように感じられる。 |

| 八戸が城下町だったという認識が実は薄い。東北諸藩の中でも北辺にある窪田(秋田)藩、弘前藩、南部(盛岡)藩については、藩祖あるいは家名がそれぞれに高名なため、認知しているが、八戸藩にはちと疎い筆者。しかし、根城、三戸、八戸など諸氏あるが、南北朝から続く名族南部氏の支配地の一部ではある。 東北新幹線の八戸駅は、お城下からは離れている。近代的な駅の周囲に町はない。八戸の中心は八戸線で2駅先の本八戸(昔はここが八戸駅だった)にある。八戸駅は、新横浜や新大阪のような新幹線用の新設乗り継ぎ駅のような位置づけだ。 しかし、八戸駅前には「ほむら」という実に居心地のいい小さな和食屋がある。気取らない人柄の大将と、ひとつひとつ手抜かりのない料理に7年前、舌鼓を打った。記録を見返すと、枝豆と里芋のチップの突き出し、香りが匂い立つようなカモの薫製・しめ鯖・サルナシ(小さなキウイみたいな緑の実)、えぞばふんとむらさき2種のうに・マグロとひらめ、いかそうめん・いかの肝醤油。いかそうめんには追加で頼んだうにを載せている。サワラの南蛮・なすの炙りにみょうがと味噌を挟んだ一品・あまだいの焼き、さんまのつみれ汁、毛ガニのほぐし身とカニミソみそあえ、アナゴごはんを少し・山芋の醤油漬け・山菜のみずの身、と手をかけ、品を揃えた料理の数々。都市圏でもなかなかに出会えない店だった。帰り際に「さっきのマグロは?」と聞くと「津軽です」照れながらの答えが人柄をあらわしている。「三厩?」「いえ」「大間?」「ええ。先入観なく食べてもらいたいもんで」どこまでも謙虚な大将だった。今回、再訪の思いが強かったが、本八戸を中心とする八戸の繁華街に行かずしては画竜点睛を欠くと、未練を断ち切り本八戸に向かった。 繁華街は六日町にある。ふと、山形は七日町だったなと思い出した。 六日町の交差点の北東角に「ばんや」があった。外観はただもう、ひたすらに渋い。三船敏郎が懐手で入ってきそうな宿場町の居酒屋の佇まいだ。18時開店の店は、予約を取らない。開店5分前で店頭には6名ほどの人垣があった。縄のれん |
がかけられると客が順次招じ入れられる。一人二人客はカウンターへ、それ以外はテーブル席へ。店内は広いわけではない。どちらかと言えば狭い。そして外観同様に渋い。昭和生まれのオヤジが等しく脳裏に浮かべるであろう「居酒屋」の店内。演歌が似合うだろう。振り子時計でないのが不思議なくらいの、しかし国鉄の待合室にかかっていたような正調派の壁掛け時計の長針はきっちりと10分進めてある。絵に描いたような佇まいに笑みが浮かぶ。 飛び込みの一見さんは、こういうときは流れに完全に身をまかせるものだ。店の作法がわからないときは守りに入る。席割を終えた順に飲み物の注文を取り始めた。ルーティンなのだろう。こういうとき性急に料理のオーダーをしてはいけない。まず、たしなめられる。事実、何組かの客がたしなめられていた。飲み物を受注しながら、別働隊の年配のおばちゃんが突き出しを順次出し始める。開店直後のちょっとした慌しさが落ち着くまではこの突き出しでゆっくり飲るのだ。突き出しはイカのワタ和えのようなもの。タイミングを見計らいながら、焼きウニ、刺身はまつかわ(鰈)、馬刺しをオーダー。隣あわせになった地元水産加工業者のお兄さんと言葉を交わす。お勧めのタコの白子と漬物を半分(量が多いからと言っていた)で、地元の酒を。田酒や豊盃があるが、これは津軽の酒だ。八戸にあれば南部の酒にせねば、と八仙と作田を1杯ずつ。あとは芋焼酎水割りを2杯。心地よく酔った。 「おすすめの立ち飲みバーがあるんだけど」と隣のお兄さんから誘われたが、体調不良でつきあえない。至極残念。 翌朝、八戸駅に向かうタクシーのフロントグラス越しに雪を頂く山容が見えた。あれは?と問えば八甲田山とのこと。北海道、大雪山と同様、幾つかの山の連なりを八甲田山と言う。 八戸駅から青森へ。新幹線ではもったいない。新幹線の新青森開通によって東北本線の目時、青森間が第3セクターとなった青い森鉄道に揺られていこうではないか。 |
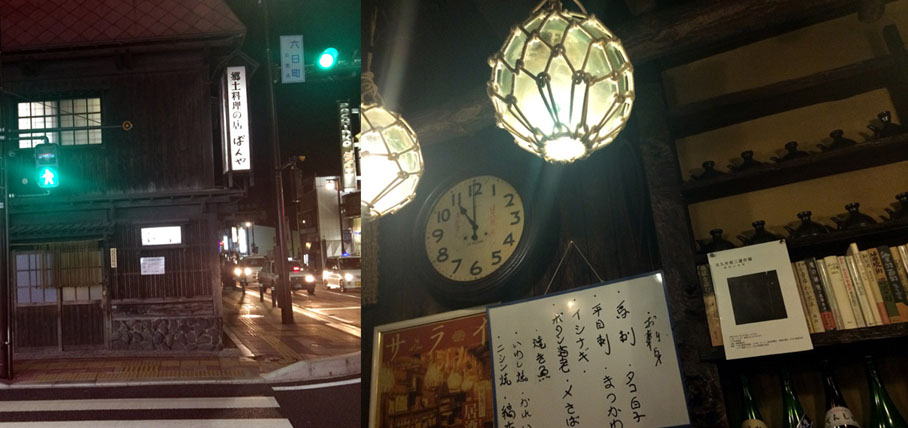


| 東京駅6時32分発の「はやぶさ1号」は東北新幹線の一番列車だ。その行き先表示は、明日から新函館北斗駅となる。今日はまだ新青森まで。しかも筆者は途中駅八戸で降りる。八戸着は9時21分。 40分弱の接続で、八戸10時7分発久慈行きの久慈線に乗り換える。久慈着11時50分。 JRの次に三鉄(三陸鉄道)北リアス線に接続する。久慈発12時13分宮古行きで、途中駅田野畑で降車。13時4分。東京を出てから6時間32分。三陸はやっぱり遠い。 田野畑駅は、NHKの朝ドラ「あまちゃん」で畑野駅として登場している。公共放送のNHKは民間の実在名称を使えない(広告にならないようにとの配慮から)からいろいろと面倒くさい。三鉄は、駅によってはドラマの時の駅標まで立てている。 盛岡から山田線で宮古まで出て、三鉄北リアス線で北上するルートが見た目では最短なのだが、2015年12月の土砂流入の影響で、山田線は、現在でも上米内~川内駅間の運転を見合わせバス振替輸送となっている。 もともと不採算路線だった三陸の鉄路を震災をきっかけにBRT化(バス・ラピッド・トランジット=バス高速輸送システム)しようとしたJR東日本の提案を、暫定的に受け入れた気仙沼線と大船渡線に対し、鉄道復興に固執したのが山田線だった。願いかなって盛岡-宮古間が復旧したのもつかのま、上述のとおり一部区間が再び不通となり、復旧の目処はついていない。悲運である。 余談だが、BRTになれば、鉄道に比べて運行本数を増やし運行間隔を短くすることができる。鉄道敷地をBRT専用道とすることで安全性、定期運行性も確保できる。ただし、専用道は一部区間に限られ、それ以外では一般道となるし、大量 |
輸送はできない。駅という地域の象徴的施設を失い、単なるバス亭が現れるということもある。長所もあれば短所もあるわけだ。 山田線は全通時でも1日4往復程度しかなく、1時間おきに運行している106急行バス(山田線に平行する国道106号を使用)は2時間15分程度で盛岡-宮古間を結んでいる(鉄道は快速で2時間、ローカルで2時間半程度)。これを使って盛岡から北上した場合、乗り継ぎの悪さで、田野畑着は14時1分になる。と、いうことで八戸経由になったわけだ。 八戸を起点として、三陸海岸をローカル線でつないで仙台まで南下したのは7年前だった。 その2年後に震災があった。 大阪在住15年、それ以前は関東に40年。漂泊の地は東北が多かった。東北は筆者の思い入れで染め上げられている。その脳裏に浮かぶ景色の多くが濁流に呑みこまれ、流された。青森、仙台には2014年に訪れ、消費活動で復興支援をした。しかし、三陸沿岸には足を伸ばせなかった。三陸の景色を見ると涙が滂沱として零れ落ち感情を抑えきれなくなってしまうのだ。いい歳をして恥ずかしいことだ。だが、やっと訪れた。 それでも、かつて訪れたことのない土地を選び、感情をできるだけ平穏に保つことにした。 久慈線も、三鉄も海岸の眺望は素晴らしい。しかし、この美しい海の彼方から津波が来たのだ。何度も引用しているが「自然は人間を愛してなんかいない」のである。 嵩上げ工事と堤防工事のクレーンや工事車両が車窓の中、延々と現れる。田野畑駅は高台にあったが、駅前には「津波到達点」の標柱があった。駅の標高は18mだった。宿泊した第3セクター経営のホテルも10階建ての3階までが津波で浸水した。 |


「堀内」が駅の正規名称「袖が浜」が朝ドラでの名称 「田野畑駅」
| 鷲羽山(わしゅうやま)という大相撲力士がいたが、この四股名は、出身地に聳える鷲羽山(わしゅうざん)という山名に由来する。聳えると言っても標高は133mだ。 鷲羽山は岡山県倉敷市にある。 美観地区で有名な倉敷エリアではない。瀬戸大橋のかかる児島エリアにその山はある。 児島と言えば、ジーンズである。 JR児島駅は、エレベーターから自動販売機から階段からありとあらゆるものがジーンズで染められている。町にはジーンズストリートまであるらしい。しかし、ジーンズに興味がないのでそれ以上は食いつかずに、目的地の鷲羽山下電ホテルに向かうことにする。 駅前から送迎バスをお願いする。 駅中のベンチで待っていてくれと言われたが、駅前には何もないから、それ以外に時間潰しの方法はない。最近、駅前に何もないところで降りることが多いような気がする。 ホテルは鷲羽山の麓にある。 鷲羽山は、児島半島の先端部にあり瀬戸内海に面している。ホテルは全室オーシャンビューである。プライベートビーチもある。昭和天皇が臨幸した由緒あるホテルらしい。だから設備は古い。内装を改装はしているがいかにも昭和な作りの中に微妙な平成薫が漂っている。下電は、鉄道会社の名前だろうと予測できるが、フルネームが浮かばない。筆者はマニアではないのである。調べたら「下津井電鉄」の略称だった。すでに鉄道事業からは撤退しているが名称は残っているらしい。ホテルの資本もすでに鉄道会社のものではない。 眼前の瀬戸内海を、思っている以上の近さで多 |
くの船舶が往来する。船足の速さには少し驚かされる。 温泉大浴場の広さに満喫し、部屋にある露天のジャグジー風呂にも満足した。バイキングの夕食に期待はなかったが、逆の意味で裏切られた。 (あら、けっこういけるじゃない) 層雲峡のバイキングとは出来が違っていたのはめっけものだ。ワインは岡山県産のマスカットベーリーAを使ったサッポロポレール。北海道新千歳空港の「竈」では余市のぶどうを使ったグランポレールだったが、岡山にもサッポロのワイナリーがあるらしい。 早朝の大浴場を独り占めしたあと、鷲羽山山頂まで登ることにした。遊歩道が整備されているので決死の覚悟はいらない。 展望台はふたつあり、レストハウスとビジターセンターがそれぞれに設置されている。 徐々に高度を上げてゆくと、眼下に瀬戸内海とそこに浮かぶ島々、四国に向かう瀬戸大橋が見渡せる。秀麗な景色だ。山頂に近づくと、山の陰となって見えなかった下津井の町並みも現れる。 海辺のホテルに戻り、帰路につく。瀬戸大橋線の「快速マリンライナー」に乗って、橋を渡らなかったのは初めてだ。車中を見回すとスマホを覘いている人が少ない。なにがなし嬉しくなる。 岡山に戻ったら、足を伸ばして倉敷へ。 美観地区のそばにあるビストロ「みやけ亭」に寄って、タンシチューを食べるのが岡山に行ったときの楽しみのひとつだ。えびす通商店街の中にある名代トンカツ「かっぱ」の前には10名ほどの待ち行列ができていた。土曜日の倉敷は観光客が多いのだろう。昼を食べて帰阪の途につく。 |


| 冬祭りのド定番と言えば、札幌「雪まつり」。 皆と同じことをするのが好きじゃない天の邪鬼の性格からか、祭りのさなかに飛び込むことが少ない筆者。とは言え、ちょっと外した感じには抵抗感がないので、弘前の「雪灯篭祭り」や支笏湖の「氷濤まつり」、層雲峡の「氷瀑まつり」には行っている(外した感じなんて、弘前、支笏湖、層雲峡の皆さん、御免なさい)。 一人っ子だからか団体行動が苦手なんである。集団生活の中に放り込まれたら、初日で窒息死する。漂泊好きだが、ツアー旅行が選択肢にあがることは一度もなかった。思いつきさえしない。反社会的生命体だ。社会不適合者だ。でもサイコパスじゃないのでそこのところは、ひとつ。 しかし、よくできたもんで、齢を重ねるにつれ圭角が多少なりともとれたのだろう。若い頃ほどには斜めに構えなくなった。それでも15度くらいは斜めだと思うが。 ちゅうことで、前置きが長くなったが札幌の「雪まつり」に初参加。 「プロジェクションマッピングがとにかくいいから」と勧めるタクシードライバー氏の後押しと、昨年すすきのに開店した馴染みのバーに顔出しをしたら楽しいだろうという思いもあって、ちょっと覘いてみることになった。 さすがにすすきの界隈のホテルはとれなかったが、地下鉄南北線で一駅南の中島公園駅そばにあるエクセルホテルが確保できた。すすきのまでは徒歩圏内だ。 雪祭りは3箇所で実施されているらしい(後知恵だが)。それと知らずにすすきの会場の氷彫刻を見に行ったのは既述のバーの知己が出展してい |
ると知ったからである。 プロジェクションマッピングは、18時開始というので、これはハナから諦める。17時開店の「さっぽろジンギスカン本店」を優先する。筆者はなにごとにつけ酒食優先である。 メイン会場の大通公園へ向かう。すすきの交差点を越えたら、なんと市電が駅前通りを北上してくるではないか。すすきの駅を始点とした盲腸線だった市電が環状線化したらしい。ループ化は2015年12月だから、つい1ヶ月前のことだ。狸小路に駅ができていた。 大通公園に出た。テレビ塔方面にジャンプ台があった。スノーボードの競技会をやっていた。落ちかける陽光の中、空中に浮かぶスノーボダー。いいアングルである。 テレビ塔から西に向かって何ブロックか歩く。巨大な雪像を見て、堪能したので引き返し、西6丁目あたりから南下する。その先にお目当ての店がある。 「さっぽろジンギスカン本店」はラム肉使用の店だ(ちなみに「だるま」はマトン)。釣具屋の2階にカウンターのみ15席で営業している。開店は17時。17時10分に備え付けのゴム動力の半自動ドア(開けるのは手動、閉まるのはゴム動)を開けたら、さすがは雪祭り開催中である。すでに満席。カウンターの後ろにある待ち席にもすでに8名の客が店内を覆う煙にいぶされている。待ちましょう、今日は。ジンギスカンの後は、バーの止まり木に羽を休める計画だから心理的にゆとりがある。近場から寄ってゆけば「ドゥ・エルミターヂュ」「プルーフ」「ヴェスパ」という順番になる。計画を達成。満喫。 |





| 立春は過ぎたが、北海道はまだ冬のど真ん中。札幌で雪祭りが始まったその日、筆者は大雪山へ向かった。 北海道の屋根、大雪山で真冬を体感しなければ春を迎えることができない。 4年前、ロープウェイで5合目まで登った黒岳で体感した深い雪の中での孤独感、孤立感が忘れられない。人間なんてちっぽけなものだと素直に思った。厳冬期の北海道を体感するために大雪山に行くのだ。 宿からの送迎バスは札幌駅まで来てくれる。札幌旭川間のJRは特急スーパーカムイで片道4300円弱。時間は1時間半程度。ただし、層雲峡へは旭川からさらに網走方面に移動してバスでむかうしかないから、往復で1万円以上はかかるだろう。ホテル代1万5千円にはオトク感がある。 (ありり?) 4年前とルートが違うようだ。高速道央自動車道を比布で降りて、その後も整備された道を走っている。旭川・紋別自動車道らしい。上川層雲峡ICを降りたら、層雲峡温泉までは25キロ程度。以前はもっと下道の走行時間が長かったような気がした。3時間半程度でホテル着。前回よりも30分は早い。ドライバー氏に聞いたら、以前は旭川駅にも寄って宿泊客をピックアップしていたが、今では札幌と旭川へは別々の送迎バスを出しているからとのこと。そー言えばそうだったか。繁盛しているのかな。 4年ぶりに帰ってきた層雲峡温泉は、石狩川沿いに聳える断崖絶壁の谷あいの町。 前回も投宿した朝陽亭へ向かう。 インバウンドの中華系観光客が収益の柱だろう。 |
陽が沈みかけた頃にはバスが次々とやってきた。バイキングの2食に期待はしていない。風呂が気にいって今回も来たのだ。 大浴場2種のひとつには露天風呂が併設され、他のひとつの浴槽はかなり広い。ホテルが高所にあり、浴場も7階なので眼前に地獄谷と呼ばれる巨大な断崖を見渡せる。2階にある瞑想の湯と称する広いが閉鎖された空間の湯も筆者のお気に入りだ。これら三つの浴場を時間交代で男湯、女湯としている。もちろん全部に浸かる。 層雲峡温泉の石狩川沿いで「氷瀑まつり」が開催されていた。客が増える5時前にひと風呂あびてから「氷瀑まつり」会場に向かった。 高台にあるホテルから川底にある会場までは凍りついた坂道を下らなければならない。宿からシャトルバスも出ているのだが、歩いてゆくのが大切なのだ。ときおり強風がパウダースノーを巻きあげる。厳寒仕様のコートのフードを喉元まできつく締める。手袋はしているが指先の感覚がなくなり始めた。冬靴と言えどもところどころアイスバーン化した坂道の歩行はなかなかに難儀である。体重移動は垂直に、ペンギン歩きが雪道の基本。僅かな距離だが、心理的にも体力的にもかなり消耗する。(そう、そう、これこれ)喜ぶ筆者。 早暁、露天風呂に浸かり、2階に降りて瞑想の湯でも温まる。 帰路のバスは途中、砂川のサービスエリアで1時間弱の昼食休憩タイムをとる。なにがしのバックがあるのかもしれない。沖縄でも那覇から美ら海水族館にむかう観光バスは名護パイナップルパークに必ず立ち寄るもんね。 |

氷点下は12度!

祭りの〆は花火
| 2013年には伊勢神宮で20年に一度の式年遷宮があった。2016年05月には、伊勢志摩サミットが開催される。 なんだかんだと注目されているのか伊勢志摩。 20年前にJRで紀伊半島を一周したことがある。 大阪を基点に和歌山から特急「黒潮」に乗り換え、新宮で一泊。翌朝、特急「南紀」に乗りついだ。阪和線、紀勢本線の旅だ。このラインだとちょうど伊勢志摩や鳥羽のあたりで鉄路が内陸に寄ってエリアからはずれてしまう。 14年前、大阪在住となってからは、近鉄で松阪まで行ったことはあるが伊勢志摩に行ったことはまだない。行ってみようか、という気になった。 前泊となった名古屋の宿は某Cホテル。 35年前、初めてのひとり旅で泊まった宿だ。円筒形の構造で、部屋がぐるりと扇型に(それもかなり狭い。なぜなら安いから)配置され、まるで監獄のようなイメージだった。その記憶を懐かしみ、投宿したのだが記憶のままの監獄ぶりに100パー後悔した。 それもあって、見晴らしのいい、ゆったりとした温泉のある宿で、四肢を伸ばしたくなった。 ちょうどいいホテルが検索サイトにあがっていた。ラグジュアリーなツインルームで眺めがいい。露天岩風呂と大浴場もHPの画像を見る限り外れはなさそうだ。送迎バスが出ているのは志摩礒部駅。土地感がないからそこに街があるのか、何があるのか一切わからない。伊勢志摩は筆者にとってはブラックボックスなのであった。 名古屋から特急でおおよそ2時間。志摩礒部駅には、何もなかった。志摩スペイン村がそばにあるからか、駅舎はスペイン風の立派な造りだが、 |
駅前には静かなロータリーがあるだけ。バスが来るまで1時間あるので周辺を散策した。軽食喫茶があった。入り口には「名古屋から来ました」という貼紙がある。何を意図しての開示だかよくわからん。コーヒーを頼んで三々五々と店に入ってくる地元民の世間話を盗み聞きして時間を潰す。 送迎バスは、伊雑ノ浦と呼ばれる内湾ぞいに高度を上げてゆく。鴨の群れが浮かんでいるが、暖冬のせいで今年は渡りの数が少ないらしい。道路ぞいには舗装工事車両がいたるところに停まっており、ガードレールの設置工事もあちこちで進められている。サミットの準備のようだ。伊勢志摩の再舗装は何十年ぶりかもしれない。5月までには警備の警官2万人の簡易宿泊所も作らねばならないそうな。 ホテルは丘の上にあった。周囲には何もない。足(車)がなければ何もできない。部屋は的矢湾側の高層階で眺望はなかなかにいい。カラフルな的矢大橋のむこうには志摩スペイン村が見える。 さて、風呂だ。 1日4便ある送迎バスの第1便に乗ったのは、風呂を独り占めするためだ。時が夕刻に近づけば団体さんのバスが列をなして押し寄せてくるに違いない。風呂も施設も人だらけになる可能性がある。正しい思惑は正しい結果を生んだ。浴場をほぼ独り占め状態。 早めに湯に浸かれば夜の酒食も早い。すると、団体さんの食事が始まる7時頃には、もうひとっぷろガラガラの風呂にザブンと浸かれる。 朝イチでも湯につかり、満喫して帰阪の途についた。近鉄大阪難波まで特急で2時間半。ちょうどいい感じかな。 |

画像左から、1枚目:的矢大橋と的矢湾 2枚目:的矢大橋の先にある志摩スペイン村 3枚目 的矢牡蠣のいかだ 4枚目 鴨の群れ
| 姫路の街を歩いていると、どこかしら金沢に似ているような気がする。 ただし、姫路城界隈限定ということでひとつ。 城の東面にあたる姫路公園から姫路市立美術館裏、清水門跡のあたりのお堀端が、金沢城の白鳥路を思い起こさせるからかもしれない。静謐な落ち着きがあるエリアなのだ。 姫路へは在来線のJR新快速で大阪から1時間で行ける。 1時間という時間が、日常圏からの軽い逸脱にちょうどいい。文庫本を携え、音楽を聴きながら、軽くウトウトしているといつの間にやらついている。 時間的には、倉敷に行くのと30分くらいしか変わらない。ただし、倉敷には新幹線の岡山経由で行くことになるので交通費が大きく違う。 距離的に遠くだからか、倉敷には何度か泊まりがけで遊びに行っているが、姫路で泊まったことはない。いや、正確には一度ある。ただし、それは東京出張からの帰り路で新幹線姫路行き最終20時50分発に乗車した際、不覚にも寝過ごしてしまったからだ。23時55分に姫路で車掌からゆり起こされたが、都心ならいざ知らず播州の夜は早いのである。大阪方面への終電などとうになくなっている。だからあの一泊はノーカウント。 藩政時代、山陽道の要衝に外様を置くはずもなく、姫路藩は徳川の譜代大名が治めている。譜代や親藩の石高は低いから(姫路藩の石高は15万石)加賀百万石と比較するのは可哀想ではある。経済力が違えば、街の規模や、文化の華やぎにも差がつくのはいたしかたない。ましてや徳川恩顧の譜代連中は質素倹約が骨の髄まで染み付いている |
から、織田家中できらびやかな文化に触れた前田利家のような藩祖を持つ加賀藩とは生い立ちからして違うだろう。 それでも、なんとなくもったいないなあと思うのである。 世界遺産姫路城以外にもなにかしら売り出しがあっていいんじゃないか。 書写山円教寺なんて古刹もあるし、授産施設の太陽公園もある。家島諸島も瀬戸内の島々の中では活気のある漁師町らしい。 うまくパックできないものかね。 駅前はかなり改修されて綺麗になっているが、観光客の消費の中心にはならないだろう。むしろアーケードのみゆき通りに個性的な店を増やしてもうちょっと派手にしたり、みゆき通りの東端にある飲み屋街を広げてくれれば泊まりたいと思うようになるんじゃないかな(個人的な感想として)。食文化では、気軽に食べられるものとして姫路おでんがある。ひねぽんなんてのもあったな。周辺地域から仕入れれば、明石のたこ焼きもいいんじゃないか。龍野のそうめんや醤油、加古川の穴子、赤穂の塩や瀬戸内の魚で名物料理や料亭、寿司屋を盛り立ててくれれば、ますます泊まりたくなると思う(あくまでも、個人的な感想として)。もちろん生活者の立場からすれば、いい店もたくさんあるんだろうけど、いかんせん人口に膾炙していない。部外者が町おこしみたいなことをけしかけるのも失礼とは思うが、けっこう好きな街なのでお許しを。 あ、津山のホルモンうどんもいけるんじゃないか?いや、津山は岡山か。 |

金沢行16 →→→back 金沢行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
| 見慣れた車窓を置き去りにして、列車が、生活圏を離れてゆく。新しい景色が次々と現れる心ときめくひととき。それが旅の始まりだった。18歳のあの頃の新鮮な喜びは、今も心の片隅にすみついている。 しかし、今やあのときめきは、なかなか得られない。当たり前のことだが、経験とは慣れの言い換えでもある。山陽や東海道の新幹線が、通勤電車のようになってしまったら終わりである。挙句の果てにエアを使い始めたら情緒的には死んだも同然だ。それでも、車窓を眺めながら聞く音楽によって、失われていたちょっと湿っぽい感傷が蘇ることもある。iPodを持ち歩くゆえんである。とりあえず小柳ゆきの「be alive」とサザンの「あなただけを」で気持ちを入れて8時10分大阪始発のサンダーバード5号に乗りこむ。 乗ったはいいが、このサンダーバード、そんなに停まらんでもええ!ちゅうくらいにあちこちで停まる。車内アナウンスが停車駅を告げている。 新大阪、京都、堅田、近江今津、敦賀、武生、鯖江、福井、芦原温泉、加賀温泉、小松、松任、終点金沢。一度聞いただけで諳んじているわけだから、筆者の金沢行も年季が入っている。しかし堅田に停まるサンダーバードがあるとはシラナンダ~。 JR西日本の特急には最近、車内販売がない。UCCブラック無糖のホットを傾けながら車窓に目をやる。陽光が眩しい。琵琶湖の湖面が輝いている。小春日和の好天は、しかし敦賀の海側に壁のように聳える鉛色の雲が現れるまでのことだった。列車はすぐに長い北陸トンネルに入る。トンネルを抜けると空は一面、鈍い暗灰色となり、今庄を越える頃には山襞は雨煙につつまれていた。あと暫くの季節の移ろいで雨は雪に変わるのだろう。この鉛色の世界が北陸の冬である。 |
芦原温泉と加賀温泉の間、大聖寺の前あたりで雪がうっすらと積もっていた。今シーズン初の雪見である。大聖寺を過ぎたら雪はすぐに消えた。 小松でまた積雪。金沢市内にもあられのような粒粒の残雪があった。 北陸新幹線の影響だろう。「乙女寿司」「つる幸(和食)」「利休(和食)」「高砂(おでん)」の予約がとれなかった。金沢駅構内のおでん「黒百合」は予約なし。朝から店を守る「のん兵衛オヤジ」のあしらい役Mちゃんの姿がなかった。(あれれ?)と思ったが帰阪の朝に寄ったらちゃんといた。何がなしホッとする。 百万石通りは金沢城を中心とした周回道路で、武蔵が辻で左右に分かれ、東に主計町茶屋街、東茶屋街を擁し、金沢城と兼六園の石垣下を縫って広坂下から繁華街の香林坊に至り、左折すれば犀川を越え、西茶屋街、右折すれば武蔵が辻に至る。観光客はこの周回線の周辺に集中するから、このラインを外れればいい。広坂の上から伸びる小立野通り沿いの「千取寿司本店」、おでんの「若葉」、洋食の「New狸」はまだ観光客には浸食されていないようだ。和食は寺町通りをかなり奥に入った「しげ乃木」がある。バーはスプーン。 久しぶりにゆっったりとした時間を過ごした。 ブリおこしの雷鳴こそないが、雨脚しげし。兼六園も濡れている。それが艶めいていてむしろ風趣に富んでいる。昨夜は紅葉のライトアップで無料開放されていたが、これは少し見慣れてしまったせいか、初めて見たときほどの喜びはなかった。雨中の散歩に飽いて喫茶店に入る。必ず寄る店があるのは、ここ金沢と那覇ぐらいのものだ。「漆の実」という漆器屋の4階に喫茶室がある。ここで漆塗りのコーヒー茶碗に入ったコーヒーを飲むのが楽しみのひとつである。 |

| 夜、国際通りの「波照間」に向かう。昼に食べすぎたのであまり入らない。2階の島唄ライブ席に上がることもなく、1階のカウンター席で軽く地元料理をつまむ。「豆腐4種珍味盛り」が「食べるラー油、スクガラス、牛肉味噌、焦がしにんにくしょうゆ」になっていた。以前は5種で、イカスミが載っていたし、島ラッキョものっていたはずだ。せちがらい世になってきた。久しぶりなので糖質危険物件の「ゴーヤーカリカリリング揚げ」もオーダー。「アグー塩焼き」「もずく酢の物」「海老の豆腐ようソース焼き」でオリオン生ビール、菊の露水割り1杯と北谷長老古酒43度をカラカラの一合で水割り。 そこそこに切り上げて久しぶりに松山の先にあるバーに向かった。5年ぶりくらいの訪店だ。ハードシェイクが身上の渋いマスターがいる。しかし、バー「ステア」のマスターは先月、亡くなっていた。店を継いだお弟子さんに聞いた。わざわざカウンターに出してくれたありし日のマスターの写真に献杯を捧げる。 翌日、初日と同じ糖質制限のイタリアン「ピキタン」でアルコール抜きの昼食。 何かしようという意気込みもないのでおもろまちのシネマQで「進撃の巨人パート2」を見る。そう言えば、北の「札幌」、南の「那覇」。南北の街どちらにも東宝シネマズがない。 映画館を出て「琉球珈琲館」にてぶくぶくアイスコーヒーを一杯ひっかけていたら、ちょうど時分時。 心覚えにしていたゆきつけのイタリアン「hana」の予約が取れなかったので松山の「やきにく華」に行く。ここはけっこうヴォリュームがあるから気をつけながらオーダー。石垣牛とアグーを出 |
すかなり値段の張る焼き肉店だが、筆者もいろいろと経験を積んだ。石垣牛なら石垣島の「担たん亭」があるし、アグーなら名護の「満味」を知ってしまった。高額品を避けつつタン塩、上カルビ、シマチョウ、ユッケジャンスープ(小)アグー豚盛り合わせ(バラ、ロース、肩ロース)でオリオン生ビール、菊の露VIPゴールド一合、瑞泉古酒一合。そろそろ「やきにく華」は卒業かもしれないな。 今回、国際通りの微妙な変容に気がついた。 ドラッグストアが増えていた。 中華系観光客の爆買い目当てだろう。街は時代に応じて姿を変えてゆく。三越は閉店したし、OPAはドンキホーテになっている。 離沖の恒例行事は「ジャッキーステーキハウス」でのステーキ食い。 旭橋に行く。11時開店の店に11時5分に入店したが、なんとギリギリでの着席になった。 「タコスを2P」。メニューには「タコス5P」と書いてあるが、ひとつからでも好かな数を選べるのである。「テンダーロインL(250g)」と「ニューヨークステーキS」を頼む。もちろん「ノーバケット、ノーライス、ノースープ」である。「サラダ」は1皿だけで。ミディアムレアが店の推奨だがレアを頼む。ここのレアは表面がかなり赤く生々しいが、やってきたら、すぐに裏返す。皿となっている鉄板が熱いんでこれでちょうどいい焼け具合になる。オリオン生1杯、赤ワインはクォーター瓶だが理性を保つために2本で抑える。いつものように、このオーダーと食べ方は、周囲の客や店のにいにい、ねえねえの注目を浴びる。その視線が快感。 |
| フィリピン東海上にいきなり発生した台風21号は、明確な進路を定めぬまま勢力を拡大させていた。筆者は沖縄本島でこの夏最後のダイビングを企画していたのだが、21号の奴「どーこに行こうかなー」という煮え切らない態度で愚図愚図していやがる。 何となく沖縄方面に向かい始めたが「行くなら行くでテキパキしろよ」という筆者のいらだちを無視するかのように右に左に前に後ろに蛇行を繰り返す21号。 台風直撃ならばあきらめもつく。航空券も手数料なしでキャンセルできるのだが、微妙に先島方面に向かいつつあるように見える予想進路にANAは欠航予報を出さずにいた。運行状況で欠航の可能性が発表されないとキャンセル料金をとられてしまう。運行デスクに電話をいれても明確な回答は返ってこない。出立ギリギリまでチェックを続けたが、払い戻しの画面表示は出ず、台風の進路は先島!と腹をくくってチェックインした。 ラウンジに入った直後に那覇空港を含む沖縄方面の航空券の変更、解約受け入れ情報が出た。 遅せえよ! もう行くしかない。 台風が先島に向かったとしても、海は大荒れだろうからダイビングは諦める。 那覇でのんびり何もしない週末を過ごそう。 ただし、台風次第では速攻で帰阪もありえる。那覇空港のカウンターでさっそく確認した。 「石垣に台風があるとき那覇空港の本土への離発着便って欠航しますか?」 「しないと思いますよ」 「ですよね~400キロ強は離れてるんだから~」 「台風情報なら米軍のも見たらどうですか」 |
さすが沖縄である。気象庁の台風情報よりも米軍の台風情報の方が信頼されているのだろうか。JTWC(アメリカ海軍Joint Typhoon Warning
Center)なんて名称は、聞いたこともなかった。 日差しは強烈だが、心なしか風が強い。晴れてはいるが時折、急に雲が空を覆い雨が降り出す。しかし、長続きはしない。雨脚もか細い。 新作のかりゆしウェアを仕入れに国際通りに出る。去年は気に入った柄がなく購入を諦めたが今年は首尾よく2着購入した。袖を通すのは来夏になるだろう。 酒食の口あけは通常、国際通りの「波照間」なのだが、「ピキタン」というご夫婦で営まれている糖質制限イタリアンの店に向かった。県庁裏にひっそりと佇む民家のような簡素な作りだが、もう何度か訪れているので尻の座りのいいゆきつけの店化している。かなり厳格な糖質制限食を提供してくれるので常のように食べまくるわけにはいかないが、持ち帰り用にタルトなどのドルチェを幾つか買い込み、滞在中のデザートとして宿の冷蔵庫に保存するという新戦法を編み出した。 翌昼は、ゆいレールの古島駅のそばにある、これまた糖質制限の中華料理「グルメエッセンス」へ。島豆腐を使った豆腐麺で豚焼肉天津麺と豆腐皮の餃子をオーダーした。 出てきた麺を見て思い出した。 (しまった~ここは量が多いんだった) 盛りの多い麺のほかにもサラダや茹で玉子が別皿に盛られている。天津麺だから玉子焼きが浮いている。ゆでタマゴがタマゴかぶりになるからなのか別皿に置いてある。何とか餃子も消費してもはや何をする気力もないぐらいの満腹感を得た。 宿で午睡。 |
| 何もすることがないのでとりあえず温泉にでもつかるか。 10年前の筆者ならばありえない選択肢である。 だが、今ならありえる。 老いたわ。 その一言につきる。うやむやのうちに温泉好きになっちゃった。 市内から札幌の奥座敷、定山渓温泉へ向かう。 札駅のバスターミナルで温泉日帰りパックを購入。販売元は「じょうてつ」である。正式名称は不明。でもきっと定山渓鉄道あたりだろう。会社ロゴが東急っぽいと思っていたら東急グループだった。料金は、1800円。これで往復のバス運賃と温泉施設の利用料がパックされている。 チケットを使える温泉施設(主に観光ホテル)は定山渓温泉で11箇所、豊平郷温泉で1箇所、小金湯温泉で2箇所ある。 バス代は片道770円、往復で1540円。260円で既述の温泉に浸かりまくれるなんてなんとオトクなパックだ!と感嘆した。ちなみに豊平郷は「ほうへいきょう」と読む。市内にある豊平は「とよひら」。宮古島の平良が「ひらら」と「たいら」だったのを思い出した。どうでもいいことか。 路線バス(快速もあり)はだいたい1時間に2、3本運行している。ただしお盆期間ということもあってか片道1時間程度の道行きに2時間ほどもかかってしまった。しかし、何もしないつもりの1日だったから目を吊り上げることもなく「なんもなんも」とのんびりムード。何もかも許せる珍しい筆者。 定山渓温泉東2の停留所で下車し、最初に入った定山渓ビューホテルの受付でチケットをもぎられた。かわりにホテル内の施設パスを渡される。 |
(あれ?他の施設ではどーやって権利行使するの?)と思ったら、温泉施設は掲載された協賛施設の中からひとつだけを選択するシステムだった。そらそーだよな。入浴料が260円で幾つものホテルを巡れるわけがないわな。 それでも定山渓ビューホテル内にある数種類の温泉を行ったり来たりして湯船に浸り、元はとった気になる。筆者は元をとることに執拗に拘るのである。 定山渓と言うくらいだから渓谷である。底部を流れる川は豊平川。JRで札幌駅に到着する前に車窓に現れる川である。河川敷は、冬季には排雪場になる。 街はこの渓谷の両岸を囲むように走る周回道路沿いに形成されている。国道230号線沿いのバス停で路線バスを乗り逃しても心配はない。バスは、この周回道路を一周し、各宿の客を拾ってもう一度同じバス停に戻ってくるからだ。 長閑な定山渓大橋から渓谷を眺め、周囲の山々の緑とその頭上に輝く白い夏雲に心癒される。渓谷の東側が朝日岳、西側が夕日岳。実に分かりやすい。国道沿いの定山渓神社の奥には夕日岳登山口があるが、今日は、夜の酒食がメインイベントなので、控えることにする。 温泉街のマスコットキャラクターは河童らしい。札幌の奥座敷だけあって家族連れがスパリゾート感覚で次々とやって来る。札幌からは一本道なのだ。定山渓の先には中山峠があり、さらにその先には洞爺湖がある。以前、洞爺湖に向かう途中、ここを通り過ぎたことがあったから今日、定山渓行を思いついたのだ。洞爺湖まではここからさらに1時間半程度はある。 |

札幌行8 →→→back 札幌行1 2 3 4 5 6 7 8 9
| 車窓から見える路面が濡れている。日照雨(そばえ)でも降ったか。 空は青い。 指折り数えれば2008年以来7年ぶりの夏の北海道。8月11日。大阪では11日連続の猛暑日、東京でも4日前まで8日連続の猛暑日を記録している。しかし札幌は午後4時で23度。ちなみに襟裳では最高気温が17度。 エアポート快速は緑したたる北の台地を疾駆している。最近、雪原ばかりの景色に馴染んでいたが、昔は北海道には夏から秋に来ていたのだ。ひどく懐かしい気分に浸った。恵庭を過ぎた。次は北広島だ。新札幌、札幌と続く。 車内アナウンスは落ち着いた男性の声で、自動音声アナウンスの多くが女性になっている昨今、なかなかにユニークである。これを聞くたびに「北海道にやって来た」気分に浸れる。 札幌は、数多ある日本の都市中、観光資源の豊富さにおいては帝王だと思っている。磐石すぎて何一つ消費しなくても「札幌に行った」というだけでお腹いっぱいという感じ。 T38、大通り公園、テレビ塔、時計台、旧北海道庁本庁舎、すすきの、狸小路、藻岩山、大倉山ジャンプ台、サッポロビール園、北大キャンパス、羊が丘展望台、札幌ドーム、モエレ沼公園。ね、お腹いっぱいでしょ。食事だってラーメン、ジンギスカン、カニや海鮮、スープカレー、チーズやソフトクリームの酪農製品、道産の食材を活かした和食屋、洋食屋は幾つもある。もー何だってアリでしょう。これで小一時間、車や電車に揺られれば、小樽、余市、積丹、定山渓、洞爺湖、支笏湖なんてのが控えている。あ~お腹いっぱい。堪能した。もう帰るか。 |
今回は何もしないつもりでやって来た。しかし、リゾートホテルのような大自然の真っ只中で何もしないというよりは何もできないというのとは違い、大都市のホテルの一室で何もしないでいるのは極めてストレスが溜まることに気がついた。やっぱ何かしよ! とは言っても行き当たりばったりの無計画な旅なので(いつものことか)大きなイベントを思い浮かべることもできず、とりあえずホテルを出て札駅に向かうことにする。 (そうだ、サッポロビール園に行ったことなかったな) ド定番の観光資源である。時間も有り余っていたので札駅から歩いて行った。無料のビール博物館で時を過ごしているうちにジンギスカンホール開店の11時半になった。園内にアナウンスが流れ、いそいそと向かう。総合案内所で入店のためのチケットをもらわなければならないようだ。予約あり、なしで振り分けられる。今日はすんなり入れた。ついていたのか? 園内には3区画ほどの飲食エリアがあるが、やはり来園客のお目当てはジンギスカンだろう。次々とジンギスカンホールに吸い込まれてゆく。 館内は広く、天井は高い。昔使われていたビールの仕込み釜が、ビールサーバーの上に聳えたっている。ここでしか飲めないとプレミアム感を出すファイブスターというジョッキをうぐうぐしながら生ラムジンギスカンやぐるぐる巻きラムソーセージを消費。その他2種類のビールでジョッキ3杯と赤ワインハーフで席を立つ頃には館内は満席。高い天井が煙でうっすらとかすんでいる。 そーだ。夜は「さっぽろジンギスカン本店」に行こ。 |

石垣島行8 →back (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
| 梅雨の中休みが終わり、大阪も朝から雨に煙っている。車窓をつたう幾筋もの雨滴が物憂げな街並みを斜めに割いていた。 出勤時間帯にストローハットを頭に載せ、かりゆしを着て乗車したら、まるで山下清が現れたみたいな視線を注がれた。早々に御堂筋線を降りて新大阪から特急「はるか」に乗り換える。 例年6月下旬に梅雨明けとなる沖縄の今年の梅雨明けは異様に早かった。6月11日には明けている。一方、東北地方は今日の段階でまだ梅雨入りもしていない。九州は記録的大雨で、鹿児島では24日には6月の降雨量が観測史上最大となっていたがその翌日にも50年に一度の大雨が降っている。 737は巡航高度40000フィート(12192メートル)時速515マイル(829キロ)で沖縄本島の東方沖を通過し、久米島や宮古島をも左に見下ろしながら石垣島に向かう。 雨の関空から夏空の石垣へ。2013年3月7日に開港したおーりとーり「南(ぱい)ぬ島石垣空港」。 旧空港は航空母艦並の滑走路だった。かつて、石垣便のパイロットは各キャリア皆、歴戦の猛者ばかりだった(に違いない)。あまりに短い滑走路は中型機を受け入れず、小型機ですら、安心はできなかった。車輪が接地した瞬間、それと知っている乗客は皆、心をひとつにして祈ったもんだ。(逆噴射!!) 腹に食いこむ安全ベルトが逆に安心の証。離陸時はゼロヨンのようなスタートダッシュだった。 それが、なんと、ま~ったくスムーズなソフトランディングである。安全な新空港。 しかし、その代償は、市街地からの距離。以前 |
の3倍にはなったろう。旧空港は市街地に近かった。離陸の30分前に市街地を出てもチェックインして搭乗できるぐらいの近さだった(空港施設もちっさかったからね。玄関開けたら2分で搭乗口)。それが、空港から市街地へは、タクシーで3000円弱、30分はかかるようになってしまった。旧空港は1000円程度で行けたから、皆、タクシーを利用していた。最近はレンタカーだそうな。島には今や3000台のレンタカーがあるとのこと。タクシードライバーが皆「前の(空港)方が良かった」と嘆いている。 石垣に来たら郷土料理「磯」と石垣牛の「担たん亭」はルーティンワーク。今回は「ゆらていく」という初見の店も訪なった。「磯」の刺身。載っているのは大葉ではなく、長命草。ツマは大根ではなくパパイヤである。島に来たねえ。んでもってホテルの大浴場の湯には先ほど食べた長命草が浮かんでいた。 南風が強い。 梅雨が明けて夏が始まるこの時期の南風を「夏至南風(カーチバイ)」と呼ぶ。そして風は翌日も収まらなかった。海が風のせいでがぶり、ダイビングボートは皆、西表島か、竹富島の島陰で風を避けて停泊することになった。 日常生活でたまった心の澱を水中で落として今回もさっぱりした。来て、潜って、帰る、慌ただしい旅程の帰路は那覇乗り継ぎだ。県庁裏の糖質制限のイタリアン「ピキタン」に向かう。事前に予約をしていたが、11:30開店の店に飛び込み、ワインを4杯飲みながら、ランチを食べて12:10には店を出る。大量のパンとドルチェとグリッシーニを買いこんだ。食事に来たというよりも仕入れに来たみたいだ。 |

金沢行15 →→→back 金沢行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
| 金沢のツアーガイドはこれで何度目だろう。今回はKを案内することになった。 金沢市内の観光資源は意外と狭い範囲に点在している。ゆるゆると歩いて3時間で消費可能だ。 北陸新幹線開業後、初の金沢行である。 どーなんでしょう? 街は変容を遂げているのでしょうか。 大阪からサンダーバードで2時間35分。北陸新幹線の東京、金沢間とほぼ同じ時間だが、こちらは時速130キロ走行。旅はスピードではなく時間である。2時間半という経過時間が日常からの離脱感を醸成するのだ。 なにはともあれ、金沢着が12時17分というのはちと具合が悪い。 サンダーバードは人気列車で休前日、休日の午前の便は、ほぼ満席で運行している。20分前にも大阪発のサンダーバードが到着しているのでその列車から吐き出された関西人が飲食店を先取りしている可能性がある。しかも、北陸新幹線が開通した今、関東人もやってくる。東京駅を9時32分に発車した「かがやき507号」の金沢着は、12時6分。まずい。なんとしてもまずい。 しかし、駅構内のおでん屋「黒百合」は2組待ちで、あまり長く待つこともなかったが、ここは帰りに寄ってもいいので「寺起屋」に向かう。 犀川大橋端の背の高い木造建築の店だ。居酒屋と言うか、定食屋と言うか、なんとなく時間調整の間繋ぎに便利使いさせてもらっている。しかし、店が閉まっていた。はて?今日は金曜日だし、休みのはずはないが・・・臨時休業かな?と後で調べてみたら、なんとなく店をたたんだっぽい。近江町市場にあった「さわいのパン」以来、金沢 |
で2軒目の喪失物件となった。しからば、と宇宙軒へ向かう。さすがにここはスルスルと入れた。地元民しかいないしね。店の看板メニュー「豚バラ(とんばら)」を目当ての観光客はまずいないでしょう。「豚バラW(ダブル)」と生ビールを消費。 腹ごなしに金沢散歩。 3時間ツアーのうち、金沢城や、兼六園を明日のために省いた2時間コースにする。ほぼこちらをご覧ください。 東茶屋街の銭湯がなくなっていた。金箔の店「箔一」に変わっていた。街は変容している。 天神橋を渡ったら、既述コースを逸脱し緑に包まれた白鳥路を渡り、金沢城石川門下に出る。この静かな小路を筆者はこよなく愛している。 香林坊に戻り夜を待つ。 それにしても、駅構内、街中、いずれも思ったより落ち着いていた。GWや11月2週目以降(ズワイ蟹の解禁と寒ブリシーズン)は知らず、シーズンオフのこの季節は落ちついたもんだ。これはよかった。 「乙女寿司」で寛ぎのひとときを過ごし「バースプーン」へ。金沢の夜が更けてゆく。 翌昼「ニュー狸」へ。 「お帰りなさい」嬉しいお出迎えの挨拶に、日頃、ひとりだけの身で食べられずにいたメニューを爆注。可哀想にKは腹がパンパンになってしまった。まだ後があるので、生ビールとワインを一人1杯と1本ずつでおさえておく。 天徳院、成巽閣(せいそんかく)…前田家の奥方の御殿。群青の間が有名。フランスから輸入したウルトラマリンブルーだそうな。兼六園を廻って腹ごなしをしてから乗車時間まで「黒百合」。 完璧だ。 |

| 今年の桜は早かった。 桜の季節到来をまったく実感できなかった。 仕事に追われていたせいもあるし、関西では開花以降、天候不順が続いたせいもある。 しかし、まだ最後の切り札がとってある。 GW明けの函館である。 函館の桜はGW明けに満開を迎える。4年前も寒気に震えながら五稜郭で満開の桜を愛でた。今年もここで挽回するのだ。 前回から、函館での活動拠点を五稜郭前に据えるようになったが、函館空港から五稜郭公園前に停まる定期巡回バスがなくてやや不便だった。しかし、いつの間にか「とびっこ」という巡回バスが運行を開始していた。ラッキーである。 いそいそと五稜郭公園に向かった。 桜は・・・見事に散っていた。 五稜郭一面、真緑。 遅咲きの八重桜だけが濃いピンクの団子となって筆者を迎えてくれたが、あまり嬉しくない。 今年の桜は北海道でも早かったのだ。 釧路の桜が満開というニュースが流れていた。釧路の桜は北海道の桜の幕引きみたいなもんだ。 しょうがない。桜は諦めた。 函館は、前回の訪問であるていどまっとうな消費をすませていたので、あくせくする必要のない土地になっている。前回訪れて尻の座りのよかった店で酒席を楽しめればそれで十分だが、それでも何かひとつ話を盛っておくか、と函館港内のクルーザーに乗船した。 昔日、青函連絡船で青森から函館に渡ったことがあったが、なぜか函館入港の記憶はほとんど残っていない。函館山を海から眺めるのだ。 |
観光遊覧船「ブルームーン」は、桟橋を離れて真っ直ぐ航走し、20分程度でUターンして真っ直ぐ帰港する。ときめきにかける40分の航海。途中、ドックに護衛艦の姿を見たことがせめてもの想い出となった。たぶん、本領はナイトクルーズで発揮されるのだろう。筆者は夜は飲むのが優先だから叶わぬ話である。 ベイエリアの赤レンガ倉庫街のはずれにある「函館ビール」は、アルコール度数10度、モルトモルトした味わいの通称「社長ビール」が筆者のお気に入りだったので今回も消費。 (あれ?) 前回ほど強いモルト感が得られなかった。記憶が味の底上げをしてしまっていたか?聞いてみたが店の娘も「製造法も、ビリュワリーも替えていませんし・・・」と言っていた。 居酒屋「昌栄丸」、フレンチの「ルプティコション」も再訪。 それだけでもかなりの寛ぎを得られたが、宿の前のバーでラクレットを出していたので迷わず扉を開けた。北海道と言えば、チーズ。筆者は、プロボローネチーズのステーキを札幌で、ラクレットをかけまわしたポテトを帯広で、それぞれ始めて経験して以来、北海道のチーズは無抵抗に受け入れる傾向がある。 店内は若者むけのダーツバーだった。 電子式のダーツがゲームセンターのような音響を奏でる本来ならありえない環境だが、なぜか居心地が良かった。 ベーコンやソーセージのラクレットがけというメニューがあるのに、ポテトもバケットも含まれるセットを頼んでしまったのは失敗だった。 |

| 「稲田屋」は日本酒蔵の経営する居酒屋で、作りは古民家風。店内は畳敷きで全席掘りごたつ形式。尻に敷くクッションが分厚い。店内外、あますところなく昭和である。 落ち着くねえ。 東京在住時、たまに寄っていた神田須田町の黒板塀に囲われた鰻屋「神田川本店」みたいに落ちつく。 6年ぶりの米子の、6年ぶりの店でしみじみとした時を過ごした。 前回は、医学会が催されていて、店内は学会参加の医療従事者で満ち溢れていたように記憶している。今宵は落ちついたものだ。それでも時がたてば満席だ。人気店なのだ。 来る途中、タクシーの窓からはメインストリート沿いにもそそられる店構えが幾つか見えた。あたりもつけずにそぞろ歩いてのれんを潜っても面白いかもしれない。 米子を始発駅とする盲腸線がある。 終点、境港駅へ向かう境線だ。 境港には漫画家水木しげるの記念館がある。駅から記念館までの商店街を水木しげるロードと称し、沿道には、漫画に出てくる妖怪の像が並んでいる。土産物屋も飲食店も、鬼太郎一色と言って過言ではない。ひとつの漫画(あるいはその作者)に街ひとつがこれだけもたれかかっているのも珍しいんじゃないか。 家族連れが多い。子供たちは、ビデオでも見ているのだろうか、居並ぶ妖怪達の名を連呼しながら像に向かって突進してゆく。子供の記憶力はものすごい。もちろん好きなものに限っての話だが。筆者は幼少時、怪獣の名前と身長、体重、特徴などを諳んじていた。もっと成績に繋がるものを諳んじておけよ、と今は思 |
う。 境線には鬼太郎電車が4編成ある。先頭車両に書かれた妖怪の違いで4種。4匹(?)は、目玉親爺と鬼太郎、ネコ娘、ねずみ男となっている。車内も妖怪のイラストが天上、額面に描かれ、モケットにも妖怪がプリントされている。 米子、境港駅間には16の駅があるが、それらはすべて妖怪名の愛称がある。境港駅は鬼太郎駅、米子駅はネズミ男駅だ。始発から終点まで45分。平日は時間帯(通勤通学時)によって本数が増えるから行き違いが多くなり、10分程度余分にかかるときもある。境線はもちろん単線だ。 大阪への帰路は、特急「やくも」。伯備線は、倉敷から山陽本線に乗り入れ、岡山を目指す。東よりの鳥取からだと特急「スーパーはくと」が智頭急行線を走り、姫路で山陽本線に乗り入れることになる。 米子を出てしばらく、車窓に大山が現れた。 (あのてっぺんまで登ったんだ)と思うと感慨もひとしおである。標高1700m超の山に登ったらしっぺ返しもでかい。1週間は腿から足裏まで筋断裂で階段すらよう使えんよーになった。 鉄路は高梁(旧備中松山)あたりまでは単線だ。日野川沿いに遡上する。川は列車の進行方向とは逆に日本海に注ぎ込むが、いつのまにか分水嶺を越えたらしい。川の流れが列車の進行方向と同じになっている。名前もきっと高梁川に変わっているだろう。 関西、関東ではすでに葉桜の時期だが、山峡の桜は今が盛りだ。群生はしていない。今年は桜の開花から雨が多く、かつ筆者も仕事に追われてゆとりがなかった。桜の季節をパスしたような気分になっていたが山中の一本桜の趣がなぜか心に沁みた。 |

| 「足立美術館」 足立区にある、もんじゃ焼きと文化フライ、荒川河川敷の花火大会を紹介する区立美術館。 では、もちろんない。 アメリカに日本庭園専門誌があるらしい。 その名も「Sukiya Living(数奇屋リビング)」。その誌上で外国人ジャーナリストが選出する日本庭園の中で毎年日本一に選ばれるのが、この足立美術館だそうな。2015年現在「12年連続日本一」と美術館では謳い上げている。 いつ頃からか、その存在を知った筆者だが初めてその名を聞いたときはもちろん足立区の美術館だと思った。 足立美術館は、島根県安来市にある。安来は「やすぎ」と読む。「やすき」ではない。安来節の安来である。マスコットキャラクターは「あらエッサ君」だ。どじょうすくいの格好をした愛らしいキャラである。 JR山陰線の「安来駅」は鳥取県の「米子駅」の隣にある。安来は県境の街である。駅前から足立美術館の無料シャトルバスが出ている。駅から美術館までは20分。米子駅発のバスも本数は少ないながらもあることはある。 美術館につくと、駐車場が異様に広い。 その日、どこかの女子大が観光バスを連ねて訪れていた。「××大学様」と書かれたプレートを掲げた大型のバスが4台。ついたばかりらしく、女子の団体さんが列を成している。この流れの中に入るのは躊躇われるから、間つなぎに売店でコーヒーを飲み、集団とタイムラグを作る。 「Sukiya Living」で日本一に選出された日本庭園は池泉回遊式ではないので庭園内に人影はない。美術館の内、外から鑑庭できるが、庭内に立ち入ることができ |
ない。しかし、背後の山を借景としてかなり奥行きのある構図になっている。一方向からしか見れないという点では絵画的である。館内からの眺めでは天上、床が額縁のようにも感じられる作りだ。陽光を弾くように輝く白砂が美しい。 庭以外に美術品の収蔵も豊かだ。 横山大観、北大路魯山人らの展示コーナーが常設されており、その日は、特別展として、竹内栖鳳と橋本関雪の日本画展も催されていた。 館名の足立は設立者である素封家、足立全康の苗字に由来する。大阪にて実業家として功なり名遂げた足立は、出身地の島根に美術館を設立した。昭和45年のことである。その後、昭和53年に横山大観の「紅葉」に出会う。その絵に大きな肝銘を覚え、意欲的な収集により日本一の大観コレクションを揃えるに至る。 日本人よりも海外での知名度が高い「足立美術館」。 池泉回遊式の兼六園、後楽園、偕楽園、六義園、栗林公園などとどこでどう点差がつくのか、ちと分からないところではある。投票した外国人ジャーナリストには「来てんのか?ホントに、ここへ?」という疑問もむけられないではない。だって、観光の幹線ルートからは程遠い雛にあるんだもの。それが、逆にいいとも言えるが、鳥取と島根の県境ですからね。 しかし、高いディレッタンティズムを感じる豪奢な美術館だ。建築も絵画的な日本庭園も、大観の絵も、魯山人の器もそれぞれなかなかにいい。 米子に宿を取れば、日本海の海産物、加工品、鳥取の大山地鶏、県産牛や豚、名物の白ネギやアゴ(トビウオ)のチクワやら辛味薩摩揚げなどを肴に地酒を干す楽しみもあるので、ご一考を。 |

| ま~ったくその気がなかったのに路線バスの旅になってしまった那覇空港、名護BT(バスターミナル)間。高速バスがのる沖縄自動車道は本島東海岸沿いに北上するが、筆者の路線バスは西海岸をべた~っと走り続ける。琉球村を過ぎ、真栄田岬への道を左に見つつ、東海岸のリゾートホテル群や各ビーチ、恩納村あたりに並ぶ高級リゾートホテル前をひとつひとつ拾ってゆく。蛭子能収のようにぶつぶつ悪態をつく筆者。 3時間10分もバスに乗り続けた。新幹線なら東京、岡山間を走破している。 滅入った気持ちは、やんばる島豚の焼肉屋「満味」で晴れた。豚肉とホルモン各種を堪能。 帰路のタクシーで、名護にキャンプをはる日ハムの選手をよく乗せていると言うドライバー氏の話を聞く。大沢親分の頃、20数年前からのことだそうだ。大谷が助手席に座っていたとか、中田はやっぱヤンチャだとか、ピッチングコーチだった江夏はかたぎには見えなかったなんて話。 翌朝。路線バスの旅は続く。名護BTから本部港へ。バス亭の目の前が港だ。接舷していたフェリーに乗船。 左手に瀬底島を見つつ、半島と島をつなぐ瀬底大橋をくぐり抜ける。瀬底島の先に三日月型の形状からクロワッサンアイランドと呼ばれる水納島が現れた。もちろん海上からでは島の形はわからない。右手後方に、沖縄海洋博公園のエメラルドビーチの人工の砂浜が白く輝いている。 Tシャツと背抜きのジャケットでは海風が少し涼しすぎる。それでも気温は24度。昨日は夕陽がきれいだった。今日は雲量やや多し。 30分程で伊江島についた。 港から城山(ぐすくやま)までは徒歩で30分。の |
どかな島ののどかな昼下がり。しかし、伊江島は沖縄戦の激戦地だった。道端に戦争の爪痕を残す公益質屋跡の遺跡がある。その廃墟を前には粛然たるを得ず。 地元民は城山と言うが、訪れる人はなぜか「タッチュー」と呼ぶその山は「未知との遭遇」に出てくるデヴィルズ・タワーのようだ。 南登山口から中腹の展望台までの階段で5分。さらにその先の岩山の階段で5分、段差がでかく、はひはひ言いながらも10分で山上だ。 山上には遮るもののない360度のパノラマが広がる。滑走路が見える。島には3本の滑走路が並んでいる。2本は米軍のものだ。米軍使用地は島の4割程度を占める。 その昔、カタンナーパという大男がタッチューから巨岩を投げつけて外敵を撃退したという話が島に残っている。山上には彼が投石の際、踏ん張ったために残されたという足跡がある。 タッチューを降り、港のそばのレストラン「いーじまとぅんが(いえじま家族の台所)」でゴーヤチャンプルーと伊江島牛ステーキなどを店のネーネーになぜか笑われながらオーダー。オリオンの生は、山登りの発汗で1杯目は瞬時に蒸発。2杯目を頼むと再びネーネーの笑い。箸が転がってもおかしい年頃なのだろう。 みやげ物屋で「イエラム(伊江島のラム)」を見つけた。ゴールドとクリスタルの2種。ゴールドはなかなか。次回、来島したとき、もうちょっと熟成が進んだ頃に買ってこ。 ひとつの旅にはひとつのイベントがあればいい。タッチューと路線バスの旅でやんばる攻略の事前調査を終わらせることにする。那覇に戻って飲もう。 |


| 沖縄本部半島、美ら海水族館のある海洋博公園から海を隔てた正面にどろろん閻魔君に出てくるシャポじい(これは知らん人の方が多いな)のような島が望見される。つば広のトンガリ帽のような地形で、つまり中央のトンガリ部分以外のつば広部はすべて平坦地である。島の名は伊江島。中央の突起部は城山(ぐすくやま)。通称「タッチュー」。海抜は172m。さほど高くないが周囲がほとんどフラットなため屹立感は実勢値を上回っている。 伊江島へはフェリーで渡るしかない。本島本部港と伊江港間約30分。 本部港へは名護から陸路だが、スーパーペーパードライバーの筆者にレンタカーという選択肢はない。名護BT(バスターミナル)から路線バスで約40分の行程だ。 その前に名護BTへは那覇空港から高速バスで1時間40分だ。 以上の攻略路を踏まえて事前調査は入念に成された。侵攻は深く静かに一歩ずつ着実に進めるのだ。 本部半島へは過去4回訪れているが、うち2回はやじきたメンバーとの道中でレンタカー使用だったからあまり土地勘は涵養されていない。1回は那覇から美ら海水族館への日帰り観光バスツアーで、これまた土地勘は養われない。 那覇から名護を経て伊江島に渡り、タッチューを攻略してその日のうちに那覇に戻るのは時間的には無理がある。本部発のフェリーはシーズンによって違うが1日3往復便しかない。 なので名護に一泊する必要がある。 これあるを想定して前回、すでに名護までの攻 |
略の事前調査を終了させていた。今回は名護を橋頭堡にさらに一歩踏み込むのだ。 那覇空港に降り立って那覇市街をスルーするのは始めてだ。那覇空港から名護BT行きの高速バスは夕刻発だったが、企図していた発車時刻の45分前に計画になかった「名護」行きのバスが目前に現れた。 (はて、ダイヤが乱れているのかしらん?もしかして那覇着の10分前に出発していたはずのバスが遅れて来た?) 「名護BT行きですか」 「そうです」 乗り込んだ。 このときはまだ気づかなかったが、走り始めて気がついた。走路が高速バスと違う。 (やっちまった!) 那覇空港から名護BTまで、高速に乗らない路線バスがあることなど想像の埒外。スマホで確認したら確かに16時発(そのとおりだった)18時53分名護BT着の路線バスがあった。なんと嘉手納経由ですぜ。本来、予定していた高速バスは16時45分発18時30分着なので到着は23分遅く、出発は45分のアドバンテージ。つまり1時間10分弱も余分な時間を過ごすことになってしまった。 それでもホテルのチェックインは19時、そのあとに訪れる店には19時半で予約している。 (ま、いいか)とバックシートに背を預けた。 ふと気がつくと渋滞。 那覇市街、金曜日の夕刻。そりゃあ混むわな。結局名護BTに着いたのは19時10分。3時間10分もバスに乗っていたことになる。 |
| 仙台と山形を結ぶ仙山線のダイヤは、ざっくり1時間に1本。山形、仙台間の移動をYahooの路線情報で検索すると、高速バスが選択肢の上位に挙がるくらいにローカルな線だ。しかし、山形から15分から20分で「山寺」駅に行ける。 眼前に聳える岩山にせり出す御堂が懐かしい。指折り数えて34年ぶりの山寺だった。 「閑さや岩にしみ入る蝉の声」 元禄2年の夏、筆者が100円で松尾芭蕉に譲った句で有名だ。後年、そのときの短冊を埋めて塚を成した。それが「せみ塚」と呼ばれる句碑で、山寺の登山道の途中に立っている。 根本中堂から登山道が始まる。石段は奥の院まで1000余段。石段が雪に埋もれている。除雪は、完璧とは言いがたい。冬靴だからいいがスニーカーや革靴では滑りまくることになるだろう。 岩から垂れ下がる氷柱は、それがペコちゃんの千歳飴だとしたら一生舐め続けなければならないほどに長くて太い。知ってます?ペコちゃんの千歳飴? 「せみ塚」も半ば雪に埋もれていた。 雪は音を包み込み、まさに真の閑さの中に塚がある。それはそれで諧謔的な風趣を感じさせる。 奥の院の先にある開山堂の石段は雪段と化している。目の端に映る断崖は足を滑らせたときの滑落の恐怖を与えてくれる。若いカップルが恐る恐るバランスを取りながら雪段を降りてくる。 開山堂の上の五大堂に登る。 ここからの眺めが山寺からの眺望の白眉だ。遠く蔵王の白銀の頂も見える。眼下に広がる雪景色は、久しぶりの好天下、陽光をはじいてほがらかに輝いている。 満喫して下山の途につく。 |
しかし、行きはヨイヨイ、帰りは怖い。 石段には片側に手すりが設置されている。除雪はその手すりのない側のごく一部しかなされていない。そして、登山者がそのルートを使っているため、下山者は、手すりはあるが除雪がされていないルートを降りるしかないのである。さすがの冬靴でもズルズルと滑る。石段は下向きの傾斜になっているから、踏み固められた雪のせいもあり、とにかく滑りやすい。筆者の前をスニーカーのメタボなお兄ちゃんが恐る恐る降りている。 (あ、これは危ないな) 思った瞬間に足をとられて尻もちをつき、数段滑り落ちる。ぶつぶつ言いながら起き上るが、その後も何度か転倒する。彼より先に行って、滑り落ちてくる彼の巻き添えを食うのは嫌だからゆっくりと後からついてゆく。 筆者は、登山時にすれ違った若者たちの範に習うことにした。手すりを脇にかかえこみ重心を落として滑り降りるのだ。 これは楽だ。 しかし、スピードがつきすぎると重心を失い、上半身が後ろに残り、結局転倒に近い状態になってしまう。スピード調整のため手すりをかかえこむ腕にはかなり力が入る。前を行くお兄ちゃんも筆者の真似をしようとしたが、膂力が足りないのかバランス感覚に問題があるのか尻モチをついた状態での滑落になってしまう。後ろ向きにズリズリと下ってゆく姿勢をとることになった。 駅前に戻り、古民家風の作りの蕎麦屋「焔蔵ENZOU」で玉こんひゃく、げそ天で瓶ビールを飲る。万金を積んで食べる豪華料理よりも今、このときだけは、これが一番旨い! |

| 宇都宮を過ぎたあたりから、北向きの日陰の残雪が目立ち始めた。 列車は関東平野を抜けつつある。 那須塩原まで来れば輪郭のない霧のような雲に包まれた山々が車窓に近づいてくる。 新白河を過ぎ、トンネルをひとつ潜り抜けるごとに雪面が増えてゆく。遠ざかる関東。 冬のど真ん中東北へ。 福島で東北新幹線と切り離された山形新幹線は在来線区へ入る。高架からの車窓は、民家が間近に迫り、踏み切りを通過する日常的な車窓にとって変わられる。 まだ所々で地面が顔を出しているが、雪面の方が遥かに広い。少し前までは残雪というイメージだった雪面はいまや積雪という言葉を使わねばならぬほどに威勢を増している。 盆地である米沢には峠を越えねば入れない。列車が巻き上げる飛雪のむこう、黒々とした紡錘型の針葉樹の上に斜面にまばらな樹林を載せた白い峰々の影が聳え立つ。無音のその世界に色彩はない。灰白色に包まれたまさに水墨画の世界だ。 そして列車は米沢駅に到着した。 前週末、1日で80cmの降雪があった市内の道路脇には除雪された雪の壁がそそり立っている。幹線道の除雪は最優先事項だが、排雪はそのスピードに追いついかないのだろう。すでに12月から1月で米沢市の除雪関連予算の4億5千万を使い切ってしまったと言う。 宿に荷を降ろし、精肉店が経営する米沢牛の店に向かう。12年前、隣り合った地元の建築会社社長からタンステーキを1枚ご馳走になり、この店は11月末にチャンピオン牛を競り落とすから |
訪店するならそれ以降に、と教わった店だ。店にシェフはいない。調理免許を取得した女性陣が調理する。品数は少ないがどーして供される料理は旨い。気取りのない店内には演歌が流れ、座敷がメインのその店のカウンターに腰かけ、12年前と変わらない佇まいに安堵の笑みを漏らす。宴席があるらしい。予約の名が聞こえた。12年前の社長と同じ名だ。会長と言っていた。筆者は12年前に隣り合わせた人だと勝手に確信した。無論、宴会場に顔を出しはしない。 タンステーキのほかに思い出の一皿、「肉納豆」を。納豆ユッケのようなものだ。チャンピオン牛のフィレステーキにも舌鼓をうって店を出た。 朝、奥羽山脈にかかる雲の上端が輝き始めた。眼下の街灯の光の輪が薄くなり、暗白色に翳る家々の屋根の雪がわずかに白みを帯びる。対面の朝陽連峰、飯豊連峰の雪が白く輝き始めた。誘われるように外に出る。顔を出したばかりの朝陽が筆者の影を雪面に長く刷く。城下町の人々は礼儀正しい。「おはようございます」見ず知らずの筆者にも声をかけてくれる。上杉謙信、上杉鷹山、上杉景勝、直江兼継らの像や碑が並ぶ上杉神社は、上杉謙信という神韻性を帯びた武将を始祖とする上杉家の凛とした家風を偲ばせる。 列島が高気圧に覆われたその日、「暖かいね」との会話が地元の人々の間で交わされていた。県内の気象予報の地域区分は、庄内、最上、村山、置賜(おきたま)すべてで晴れ。最低気温0度、最高気温10度。 米沢を後にして山形にむかう。この間山形新幹線で40分、在来線各駅停車で50分。その差10分、ちっとも新幹線ではないのである。 |

| 大寒から立春までの、1年で一番冷え込む時期。大阪は久しぶりに厳しい寒波に襲われていた。 市内で雪が降ることはまずないが、実は大阪にも積雪地帯がある。しかも、そこには樹氷の森が広がっていると言う。蔵王のアイスモンスターとは少し違うが、その日筆者はその樹氷を見るために大阪府内を南進していた。 大阪南東部、奈良との県境にある標高1125m、大阪府で一番高い山、それが金剛山である。 日本有数の登山者数を誇る山でもある。富士山に次いで日本第2位という記述もあちこち見かける。樹氷は、この山にできる。 地下鉄御堂筋線「なんば」駅経由、南海高野線「なんば」~「河内長野」間を急行で30分弱、「河内長野」から南海バスで「金剛登山口」あるいは「金剛山ロープウェイ前」まで35~45分程度、大阪の市街地から1時間強で金剛山の山懐深くにわけいることができる。 日曜日の朝、電車は空いていた。しかし、河内長野駅前のバス亭には行列ができていた。停車しているバスに乗り切れず次のバスを待つ人々の行列だ。皆、一様に登山姿だ。筆者は、北国装備ではあるが登山靴ではなく冬靴を履いている。今日は登山の意志はない。大阪で雪景色に浸かるという得難い体験をしたいだけなのだ。 次のバスにギリギリで乗車。もちろん座ることはできない。標高700mあたりまで登る道はかなり蛇行している。不自然な体勢で吊り革や手すりを掴んでいると姿勢を保つのに苦労するほどバスは揺れる。終点の少し前にある「金剛登山口」で停車ボタンが押され、かなりの乗客が降りてしまった。皆、冬山登山をするつもりなのだ。バス |
から降りた人々はアイゼンを装着している。 登山口からさらに高度を上げて終点「金剛山ロープウェイ前」のバスロータリーに到着した。バスから降りた人々はここでもアイゼンを装着している。総じてリピーターが多いのだろう。先ほどの登山口と違い、ロープウェイ前で降りるのは小さな子供を連れた家族が多い。皆、一様にソリを持参している。ここは大阪府民が子供に雪遊びを体験させる定番スポットなのかもしれない。 バス亭からロープウェイ駅までは坂道をしばらく登らなければならない。路上には雪。幸いアイスバーンではなかった。滑り止め機能付の北海道産冬靴だが、慎重にすり足気味に歩を進める。 ロープウェイは標高700mの千早駅から970mの金剛山駅まで約6分で一気に登ってしまう。大阪湾を遠くに見下ろす眺望は素晴らしい。山に目を転ずれば、山頂部の木々は一面、白銀の化粧を施されている。 駅から山頂まで40分の遊歩道があるが、無論、雪に覆われている。筆者は冬登山が目的ではないので、そのコースはとらず、そばにある「府民の森ちはや園地」に向かった。 頭上や周囲の木々の梢は着氷により白くコーティングされている。それが目の届く限りの森すべてに広がり、時折雲間から除く陽光に輝く様は、筆者にここが大阪府内であることを瞬時忘れさせるほど美しい。来阪13年目であるが、いままで放置していたのは迂闊であった。 山頂なので流れ去る雲が近く、早い。 白蓋を雪雲に翳すひと時。 筆者はこの日、大阪で冬の一日を愉しんだ。 |

札幌行7 →→→back 札幌行1 2 3 4 5 6 7 8 9
| 2年前すすきのの「ラフィラ」で買った冬靴。 冬靴とは読んで字の如し、冬季用の靴のことである。ソールが滅茶苦茶柔らかく、物によってはピンやスパイクがついていたり、クルミの殻とか貝とかの破砕物がソールに混ざっていたりする。雪上あるいは氷上でのグリップ力に優れている。その昔、北国の雪道をなめていた筆者は革靴で七転八倒の辛酸を舐めた。歩き方が悪いのだと自らを苛んでいた。しかし先代の冬靴(現在は2代目)を購入して雪道歩行が可能となり、靴の性能が重要だったことに気付かされた。 爾来、雪国に行くときは冬靴を履いている。しかし、北国行の機会乏しく、筆者の冬靴は、大阪で雨靴として稼動するという本来の機能を発揮する機会のない不遇の日々をかこっていた。内側にボアついてるから蒸れるし。 冬靴に冬靴らしい活躍の場を与えるため、筆者は、札幌に向かった。寒冷地装備は、ファー付フードキルトコート、手袋、厚手の靴下、そして冬靴。いずれも日常では使用していない。 夕刻、入札。 (道路に雪がない) 除雪された雪が道端に僅かに積み上げられてはいるが、歩道はカラカラ。車道にも雪がない。完全な肩透かし状態。 夜、ゆきつけの寿司屋「たる善」へ行き「道に雪が少ないですね」「昨日、排雪したんです。それに今年は暖かいし」などと話をした翌日。 朝から嵐。 (よしよし) 札幌市内でも暴風雪。背後からの突風にからだが持っていかれそうになる。横殴りの雪と地面に |
積もった雪が吹き上げられて、瞬間、ホワイトアウト。フード付コートのフードはこういう時のためにある。 遠出を諦め昼は、近所の「カレーショップ・エス」でスープカレーのライス抜きを。夜は「さっぽろジンギスカン本店」「バー・プルーフ」「バー・ドゥ・エルミタージュ」とはしご。 帰阪の日。 雪は小降りになっていたが、早めに札駅(さつえき=札幌駅の略称)に向かう。在来線は今だに大混乱。快速エアポートだけが定時運行。 空港で筆者の便は2時間遅れとの発表。昨夜のうちに空港の積雪が24時間でこの日の道内最大の27センチとなり、2本ある滑走路が使用不能になってしまった。結局223便が欠航することになった。筆者の便もその後欠航が決定。 欠航確定以前に明日の便と今夜のホテルを予約しておいた。早めに欠航が決まった連中から順次先約されてしまうからだ。なに、欠航でなければそのまま帰ればいいのだ。エアは予約だけして決済しなければ自動的にキャンセルになるし、ホテルだってこういう状況下ではキャンセルの連絡を入れてもキャンセル料は取るまい。なにしろ次々に予約が入るはずなのだから。 予定外の夜は札駅西口の居酒屋「北○(きたまる)」ホテルもJRタワー接続。高層階からの眺めが帰りそびれて思いのほかささくれだっていた気分を癒してくれた。ラッキーである。 空港では、2日にわたって昼食を摂った。「竈(かまど)」で北海道短角牛のつなぎなしハンバーグ。新千歳改装前からある「キタカレー」でスープカレーと何とも旨いカキフライ。 |

ついたときにはカラッカラ~ 一晩で北の国らしくなったすすきの
| 「高岡は何県にあるでしょう?」と問われて「え?え?なに?何?たかおか?たかおかって・・」なんて時間稼ぎをしても決して正解できない。 それが高岡。 答えはもちろん「富山県」。 もちろんって言葉、いいのか?使って。ちょっと嫌われそうな感じがする。 それはともかく、恐らくは、あなたの頭に浮かんだ県名ではなかったでしょ? 実は、この紀行にも何度か登場しているが、富山県下では富山に次ぐ2番目の都市である。 2015年開通の北陸新幹線「新高岡駅」は「高岡駅」から一駅隣、城端線の駅になる。最速の「かがやき」は停まらない。各駅の「はくたか」と富山金沢間のシャトルとなる「つるぎ」は停まる。ライバルの富山駅は北陸本線富山駅に新幹線駅も併設され「かがやき」も停まる。これはちょっと悔しいだろうな。 もっとも高岡富山間は在来線で15分。高岡金沢間でも40分、特急なら20分だ。筆者は金沢から高岡に足を伸ばすことが多い。各駅とは言えかつての特急名を引き継いだ「はくたか」や「つるぎ」が走るようになれば15分となる。 高岡はこれまで観光資源をあまり宣伝してこなかった。宣伝下手というよりは、宣伝してもアクセスに難があるから人が来ないだろうと諦観の念に囚われていたのかもしれない。 氷見線「雨晴海岸」からの海越しの立山連峰の景色や、氷見のブリ、白川郷、万葉集の歌人大伴家持が国守として政務をとった国庁跡近くの万葉歴史館などを並べたてるまでもなく、市内には「日本三大仏」のひとつ「高岡大仏」があり、国宝 |
「高岡山瑞龍寺」がある。高岡古城公園の水郷も落ち着いた佇まいを見せる。新幹線が開通すれば金沢を消費した観光客の一足伸ばした観光地になるかもしれない。 ブリ起こしが鳴り響き、あられが地を叩く一日、筆者は何度目かの高岡入りを果たした。大仏と古城公園は以前、消費していたので、今回は瑞龍寺が目的である。町を開いた前田家2代目当主利長の菩提寺である。 駅を出て、駅前大通りを南下すると「八丁道」という参道が大通りと交差する。 利長の菩提寺である瑞龍寺とその墓所を東西に結ぶ参道だ。その長さはその名の通り八丁(870m)、石畳の道の両側に松並木が続くかなり奥行き感のある参道だ。その日、冬支度のため樹木の上に雪囲いを組み上げていた。 参道西端にある瑞龍寺に向かう。 総門、山門、仏殿、法堂が一直線に並び、中央の仏殿を取り囲むように回廊が繋がっている。総門をくぐり、山門から一歩その中に足を踏み入れると、芝の中庭(と言っていいのかどうか)が広い。その広さが山門から見える仏殿、その背後の法堂までの奥行きを深くしている。 総欅(けやき)造りの仏殿の造作が中に入れば素人眼にもかなり凝ったものであることが分かる。納められた須弥壇がライトアップを受けて神々しい。 かなり意表をつかれたいい物件だった。 八丁道に戻り、東端にある利長の墓に向かう。近世大名の墓石としては日本最大とのことだが、瑞龍寺でうけたほどのインパクトはあまり感じられない。寺とセットでひとつ、ということで。 |

| 室内に篭り続けるのが何やらもったいないような好天の秋の一日。 遠出をしたいわけではないが、生活圏からは離れたい。 汗をかくほどアクティブに身体を動かしたいわけではないが、ぶらぶらと気の向くままに歩き回りたい。 人が多すぎるからアスファルトと高層ビルに囲まれた大都市は不適。海と山、広い空とのどかな公園、歩き疲れたら身体を休め小腹を満たせる店がある。そんなところがいい。 そんなときは、そうだ、明石へ行こう。 大阪梅田からJR神戸線(山陽本線)新快速で40分、新大阪から新幹線こだま(たまにひかりでも停まる便がある)なら西明石まで20分、JRで一駅折り返せば、明石だ。 駅を境に、北に城跡と公園、南に港と商店街が並んでいる。城跡には重文の2層の櫓がふたつ、天守閣はない。城域は広く、市民公園となっている。芝生のむこうの天守台を守る櫓と白壁が芝の緑と天空の青に、なんとも調和していて美しい。家族連れやカップル、子供たちが思い思いの娯楽に興じている。 何度目かの明石である。 明石城公園をぶらぶらしながら、櫓から市域を見下ろすと瀬戸内の海が顔を覗かせている。その東方に目をやれば、明石海峡大橋の巨大な橋脚が2本、空を劃している。 実にのどかで心が休まる。梅田と明石では秒針の進むスピードが違っているに違いない。 駅を越えて、南側に出る。駅前には雑然と並ぶ店舗群があったのだが、その一画は再開発中で万 |
能鋼板の仮囲いで囲われていた。 昼網が並ぶ魚の棚(うおんたな)商店街では、タコが逃げ出し、鯛が弾け、揚げ物や、干物、焼き物が所狭しと並べられ、それを目当ての近隣の住民や観光客がそぞろ歩いている。 商店街内に何軒も名物の明石焼きの店が並んでいる。 鶏卵をベースに沈粉(じんこ)と小麦粉を混ぜ、明石のタコを入れたタコヤキ風のぽっちゃりした丸い焼き物を明石焼きと言う。タマゴヤキとも呼ばれる。タマゴの分量が多いのか、タコヤキよりよほどに柔らかい。そのほか、タコヤキとの違いは中にタコしか入れないことや、ソースを塗りたくらずダシにつけて食べることなどが挙げられる。とは言え、粉モノの範疇には入ろうから糖質制限的には危険物件だ。だが、今日はちょいとこれを胃袋に納めてやろうなんて了見でやってきている。 商店街を外れて、港にむかって南下する。 交差点の角に行列が出来ていた。 明石焼きの老舗「きむらや」に群がる行列だ。最後尾に並んだ。40分程度は待ったろうか。普段、行列には並ばない主義だが今日はのんびりしたもんだ。携行してきた文庫本を広げてゆったりとかまえる。 やがて順番が来た。明石焼きができるまでの間繋ぎに関東炊きを頼む。タコと牛スジ。タコがデカい。しかし柔らかい。ダシは大阪・神戸風でちょっと甘目。筆者は京風の甘くないダシが好きなんだが今日はOK牧場。散策と行列待ちの間に照りつけられた陽光で渇ききった喉にビールを流し込む。この瞬間がたまらない。 |

金沢行14 →→→back 金沢行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
| 高校生の頃、部活でやってきて・・・から、何やかやと、すでにこの「紀行」では筆者の思い入れをたっぷりと謳い上げてきた愛惜の地、金沢。 11月第2週のズワイガニの解禁日前にもかかわらず今年2回目の訪沢を果たした。 とりあえずゆきつけの寿司屋の当日飛び込み予約が通ったのが理由だが、それ以外にも金沢への思い入れゆえの動機もある。 来年3月の北陸新幹線開業が問題だ。別に問題ではないか。新幹線が開通すれば関東軍が大挙流入し、街が変容するに違いないと筆者は不安がっているのである。 東京で一人暮らしをしている孫娘を心配して「歌舞伎町なんてところに行っちゃあ駄目だよ」と言っている田舎のお婆ちゃんの脳裏に浮かぶ「歌舞伎町」がそのまま電車に乗ってやってきて田舎の静かな町並みをいいように弄ぶんじゃないかというような被害妄想ではある。 だから、金沢駅から武蔵が辻に向かって歩いている最中にも、昔日の思い出が蘇り、思わず視界が涙で滲んでしまうのだ。嗚呼、街が犯される。だから、そんなことないって。 暗がり坂を降り、主計町を流し、東茶屋街から浅野川端を歩き、白鳥路を抜け、広坂からしいのき迎賓館に出た。 なんかイベントをやっているわけだ。 「サケマルシェ」ですって。 酒蔵のブースがいっぱい。有名料理店も出店している。後で聞いたが、これ以前にもワインやビールやパンやスイーツや小物なんかのイベントもやっていたそうな。新幹線開業の日までお祭りは続きそうな勢いだ。 こっちは、しみじみと街を歩いていても、街は |
まったくそんなつもりではないのがわかった。ウエルカム新幹線なのである。街をあげての歓迎ムード。いいのかここまで盛り上がって。いいのか。ここいらへんが筋金入りのイケズ気質の京都人との県民性の違いかもしれない。有頂天に近いはしゃぎっぷりだ。 石川県は、アンテナショップを銀座に移したそうな。家賃の高さに愕然としたと言う。 当人がその気なんだから、他人があれこれ心配しても仕方がない。とりあえず寿司を食おう、と夜、片町に繰り出したら豚カツの「ぶんぷく」が店をたたんでいた。夫婦で営む片町を代表する豚カツ屋さんだったが奥さんの具合が悪くなったらしい。家族経営の店に多い幕引きだ。近江町市場の「さわいのパン」の閉店を思い出した。 ちょっとした変化が街に訪れている。昼の散策時に気づいたが、ガイジンが多いのだ。 常宿のホテルのエレベーターに乗り込んだら、なんと皆ガイジン。それも白人。アジア系でないのである。箱がいっぱいになる11人ほどの中で日本人は筆者ひとりだけ。ホンマかいな。海外からの観光客、急増ですか。 お目当ての寿司屋に入っても(そのうち、この店にもガイジンが入ってくるようになるんだろうな)と思っていたら、本当に2人入ってきた。ニューヨカーだった。ハネムーンでやってきたそうな。すげえな。「オイシイ」を連発していた。箸使いも堂に入ったもんだ。かなりの日本通ってことですか。 大将が「イエローテール」なんつってブリを出していた。やるなあ。 でも「バイ貝」で窮してた。窮した挙句「エスカルゴ」って、それは違うでしょ。 |

鹿児島行6 →→→back 鹿児島行1 2 3(疾風怒涛編) 4 5 6 7
| 温泉宿の鉄則は「チェックインはお早めに」である。その効能は「一、宿泊客の入れ替えの間隙を縫って投宿することになるから、ガラガラの浴場を独占できる」「二、外が明るいから眺望自慢の湯なら風呂につかりながら景色を愉しめる」 海辺の温泉宿の大浴場から、オーシャンビューを満喫できるのは、日が沈む前か朝しかない。夜なんか、ガラスの向こうは真っ暗闇だ。朝は朝で宿泊客が大挙して入浴するから浴場は混雑する。だから、チェックインはお早めになのである。日没前のかなり早い時間にチェックインする客は少ない。たいてい、ご当地の観光資源を見回ってから宿に来るからだ。広々とした大浴場や露天風呂を独占する気持ちよさは自己満足度のかなり上位にランキングされる。 あれほど「温泉は好きじゃない、興味がない」と言っていたのに、この変節ぶり。ま、人は変わるということで、ひとつ。子供のとき蕗の薹は、食べられなかったでしょ。食べ物だけでなく、本だって、芸術だって、土地だって、住まいだってその人にとっての適齢期がきっとあるのだ。何かのきっかけでそれまで歯牙にもかけていなかった事物が、身近なものになる。適齢期と言ってしまうと、早すぎるの、遅すぎるのと賞味期限があっての話に聞こえてしまうが、そういうことではない。その人にとって必然の出会いは、若いときでも老いてからでもあるのである。 と、言うわけで、大型の秋台風18号がゆっくりと南大東島に近づいていた秋の一日。鹿児島市内にのりこんだ筆者。 まずは昼食。黒豚しゃぶしゃぶを食べる。 「華蓮」「いちにいさん」「黒福多」は関西、関東に |
支店があるので今日はパス。当地にしかない「吾愛人(わかな)」「寿庵」「あぢもり」のラインナップから今日は、黒豚しゃぶしゃぶ発祥の店「あぢもり」を選択。ここは、ポン酢やゴマダレを使わず、バラ肉はダシだけで、ロース肉はダシにタマゴを溶くだけで食べる。このタマゴの味が濃いんだ。食べ終わるまで味が薄まってへたることがないほどの濃さ。満喫した。 食後、城山観光ホテルに投宿。 鹿児島市内を見下ろす標高108mの城山山上に建てられたホテルを筆者はいつも見上げてばかりだったが、とうとう宿泊することになった。 ホテルの海側の客室と、露天風呂からの錦江湾と桜島の眺望が素晴らしい。今まで、城山展望台からか、鹿児島港ドルフィンポートからの眺めでこの景色は、消費しつくしたと思っていたが上には上があるもんだ。あ、考えてみたら「仙巌園」からも見たことなかった。 朝5時半(夏場は5時)から深夜24時まで宿泊客はこの露天風呂にいつでも入れる。地下1000mから湧き出るちょっとヌルッとした湯に浸かりながら日がな一日、桜島を眺めていた。 ホテルのもうひとつのウリは、「朝食のおいしいホテルランキング」2011年、全国第3位にランキングされた80種の和洋バイキング料理。いかんせん、朝は食べない主義なので、このウリは筆者のツボには効かず。 台風18号は、未明には北東方向に去った。雲が切れ、陽光を背に虹がかかった。昨日、城山で鳴いていた蝉たちは吹き払われちまったかな。噴煙を上げる桜島を眺めながら最後の露天風呂を楽しんだ。ホンマ、どっこも行かなかったな。 |

温泉の画像は、ホテルHPから拝借
石垣島行7 →back (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
| 夏が夏らしくなかった8月も終わり、いよいよ秋の気配が漂い始める9月の一日、不完全燃焼気味の夏の気分を取り戻すべく、去り行く夏の女神の後ろ髪を鷲掴みにして引き摺り倒すために関空から沖縄にむかった。 那覇経由、石垣行きの今回の旅の目的は同行のⅰ氏と体験ダイビングを愉しむにある。過去、訪沖は果たしていたが仕事がらみで沖縄を消費しそびれた氏のリベンジマッチも兼ねている。 乗り継ぎの那覇で街に出た。4時間しかないので那覇市内の代表銘柄を磨り潰す。つまり、首里城。首里駅のそばに「首里そば」があるから沖縄すばも同時に消費できるという計画はいきなり頓挫。日曜日で「首里そば」が定休。次善の策で宜保の「御殿山」へ。非常に分かりにくい立地で、何度か道を見失いながらやうやうたどり着いた。14時半頃だったが、駐車場には「わ」ナンバーの車列。3組くらいの待ちで古民家然とした畳敷きの店内に上がれたのは僥倖だった。 店探しに時間を浪費したので首里城へはタクシーで向かう。めでたく首里城も消費。以前より広くなってね?まるで訪れるたびにどんどん城の体をなしてゆく金沢城みたいだ。 石垣行きの便の出発時間を10分勘違いしていたため、やや慌しく空港に向かう。首尾よくナローボディの737に乗機し、石垣へ。 郷土料理「磯」に行くのは定番活動。ダイビングの前日、アルコールを抑制するぐらいの自制心は持っているのだ。翌朝、ホテルから港へ。 「お久しぶりです?」 ダイビングショップのオーナーやインストラクターには6月にも世話になっているから、あまり |
お久しぶり感はないが「どーもどーも」的に船に乗りこむ。 シュノーケルの後、名蔵湾で1ダイブ、次いで川平石崎に向かう。マンタの遭遇率の高いマンタスクランブルというポイントの隣、マンタシティで待機。このポイントは停泊できるのが5隻までという制限がある。やがて入れ替えとなり海に潜った。マンタはかつてシュノーケル中に海上から見たことはあったが、海中では遭遇したことがなかった。今回はいかに? いた! 優雅に翼のようなヒレをゆらめかせて悠々と泳ぐマンタ。呼吸を抑えながら、サンゴの根でマンタの遊泳を観賞する。ダイビング後も、シュノーケルでもう一度マンタに遭遇。 港に戻り、石垣島のヒーロー具志堅用高のロッキー風立像で記念写真を撮り、夜を迎えた。 これまた日曜、月曜定休だった「坦たん亭」には行くことが出来ず、筆者イチオシの石垣牛のフィレステーキはおあずけ。ただし、肥育一筋120年、金嶺家三代目当主の店「金牛」で石垣牛を消費。カルビ、ロースはもとより、数が少なく幻と言われたハラミも食べられたのはラッキーか。 島唄酒場「島結」で、豆腐ようを舐めなめ、泡盛かたむけ、カチャーシーを踊りまくる頃には、メートルはリミッターを越えていた。 ふと目覚めた深夜3時。窓の外が異様に明るい。誘われるようにバルコニーに出ると、世界が白銀色に濡れている。目前の石垣港に月の通い道が揺れていた。今日は中秋の名月だったのだ。 帰路、那覇で「ジャッキーステーキハウス」を消費して今回の弾丸ツアーを締めくくった。 |

青森行3 →back 青森行(望郷編) 青森行2(食いしん坊バンザイ編) 青森行3
| 大寒は極寒だったが、それから3日。初春の暖気が列島を包んだらしい。青森駅前の道端に除雪で積み上げられた雪が溶け始めていた。 10年ぶりの青森行は1月下旬の一日だった。 新幹線の開通で、青森は身近な土地になり、最果て感は払拭された。 それでも、さすがに青森駅構内のNHK大河「軍師菅兵衛」のポスターにはリアリティが感じられない。 (どこの話じゃ?) ちゅうぐらいには、陸奥(みちのく)と関西は離れている。 気合の入った酒食を一度でも体験した土地はそこを足がかりにして徐々に浸透してゆくことができるのだが、何度か訪れている青森には、まだ定点を確保できずにいた。たまにそういう真空状態の地がある。宮崎なんかもそうだ。 今夜で、その負の連鎖を断ち切る。 10年前は、駅広市場の寿司屋で食べた三色丼の竜飛の雲丹が感動的だった。 今でも行きたいと思っている。 しかし、記憶も記録も遠い日の花火のように美しいが儚い。 残っている記録は、その前夜に入った郷土料理で「ほや」「じゃっぱ汁」「いちご煮」「帆立飯」などを「田酒」でやったこと、帆立のバター焼き定食と貝焼みそ定食を食べたことなど。ま、ワンオーワン(入門編)は卒業しているということで、ひとつ。 今宵は、シニア世代に足をつっこみつつある我が尻のより良い座り心地を求めて「しんまち通り」の奥にある居酒屋「はた善」へ。駅前からは、ちょいと離れている。 |
案内されたカウンターの端に座る。 奥には小上がりがあるが、カウンター席と、その前面の厨房の距離感が近い。 接客の女の子の感じが良かったので、おじさんは、すぐにこの店が気にいってしまった。 目の前で大将が包丁を引いている。 突き出しは、「イカヌタ、ナメコおろし、モズク」だったが、このモズクがパキパキ!かつて新潟で食べたオスモズクとどっちがパキパキ?というくらいパキパキ。パキパキモズクの好きな筆者はこれでもうこの店の虜。 刺身の盛り合わせは、「ニシン!、ホッキ、ブリ、ヒガレイ、大トロ、ヤリイカ」ヒガレイはミズカレイ、ミズクサカレイのことだと大将。 日本酒純米3杯盛りは「豊盃(弘前)、田酒、亀吉(黒石)」で地の酒を。 さらに「豊盃」の大吟醸を竹筒で。 塩ウニ、帆立味噌貝焼き、八甲田牛のステーキをつまんでいたら、隣に座っていた地元の独り客と言葉を交わすようになった。 そのうち、その人が筆者の大学の10年先輩のOBであることが発覚。1学年の人数が少ない学校なので、あまりOBとは出会わない。ましてや青森の居酒屋で隣同士になるなどという設定はSF作家だってはばかるだろう。 あまり同窓会指向のない性格だから、OB会などには一回も出たことがないのだが、このときばかりは話しが弾んだ。大将からもつっこみを入れられながら、楽しく時を過ごす。 先輩の誘いを受け、行きつけの店にはしご酒。 漂泊の旅人生でも稀有なひととき。 |

| 北緯24度14分、東経123度56分の蒼海に島がふたつ浮かんでいる。 石垣島から南西方向に、竹富島、黒島を結んだ延長線上24キロ、西表島の大原港からは南東方向に高速船で15分程度の位置だ。 島の名は新城島(あらぐすくじま)。通称「ぱなり」。島がふたつに離れ(ぱなり)ていることからそう呼ばれている。 ふたつの島の間は、干潮時にはサンゴ礁が浮かび上がり、歩いて渡ることもできる。 石垣島離島ターミナルからパナリへの定期航路はない。観光ツアーで行くしかないのである。 ツアー客が少ないと不実施になると離島ターミナル内の平田観光ツアーデスクで言われた。 シュノーケリングと島散策の1日コースは料金1万500円。シュノーケルセットのレンタル料が別途1千円必要になる。 幸い、人数が集まり翌日の観光ツアーは実施の運びとなった。その日のツアー客は10名。 ツアーデスクに9時15分集合。 専用クルーザーが来るのかと思いきや、西表島大原港行きの定期高速船に乗りこむことになった。一般客は皆、西表島で降り、ツアー客だけが西表島から15分程度のパナリに向かう。 パナリのひとつ上地島は人口10名程度。もうひとつの下地島は牛の放牧地で管理者が3名ほど常駐している。牧場のサイロが妙に目立つ。 開発の手が伸びていないパナリの海は、エメラルドグリーンに輝いていた。石垣の諸島中、その美しさはトップクラスだろう。 島には4か所の御嶽(うたき)があり、立ち入り禁止、撮影禁止である。年に一度の豊年祭は、部外者は立ち入り禁止と言う。秘祭の部類だろうか。沖縄の神 |
事は男子禁制も多い。島人が皆西表や石垣に移り住んでしまったこと、開発の手が入らぬこと、定期船が運航していないこと、パナリは禁忌の島なのかもしれない。 ツアーのレストハウスを基点として午前と午後にシュノーケリングを楽しむ。昼食後の島散策は自由行動というわけではない。ガイドに案内してもらうのだ。そこはかとなく「監視の目」を感じるのも禁忌の島ならではのことか。 上地島は1.76平方キロの米粒型の島で縦方向2キロ、横方向1キロ。集落はひとつしかないし、島を周回するような道路もない。散策に時間はかからない。琉球時代、海上の不審船監視や通報の烽火をあげた「タカニク(火番盛)」という台場は、島で一番見晴らしがいいようだ。島の周囲360度が見渡せる。もうひとつの見晴らし台「クイヌパナ」からの眺めも美しい。 白い砂浜が続くビーチに降りる。目前を泳ぐ魚の群れに手が届きそうなほど海の透明度が高い。 ライフジャケットを着込み、たまに体育会座りのように背面浮きになりながら、エメラルドグリーンの海にたゆたっていると、時の経つのを忘れてしまいそうだ。 17時に石垣島に戻った。 SPF50の日焼け止めはきちんと塗っていたはずである。かつてチービシで、シュノーケリングは背中を陽にさらすという基礎知識を持たず、前面にばかり日焼け止めを塗り、背中やふくらはぎ、耳の後ろなどを真っ赤にした経験はここで活きる。・・・はずであったが、左右の肩甲骨のあたりが漏れていた。赤い腫れに、間髪をいれず炎症止めローションスプレーをかけまくった。 |

石垣島行6 →back (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
| 梅雨前線の北上が遅く、北方の寒気の張り出しが強い。本土上空は真っ白な雲の絨毯に覆われていた。羽田を発って足摺岬をかすめ大隅半島沖を通過しても雲海は途切れることなく続いている。B737-800は絶え間なく震えている。 輝く雲海を見つめていたら鳥目になってしまった。目を閉じてしばし機窓に頭をあずけて眠りに落ちた。 気がつけば、機体の揺れが途切れ、雲海がなくなっていた。青く輝く海の上に綿飴のような千切れ雲が浮かんでいる。 梅雨前線を通過したのだろう。 眼下にエメラルドグリーンの海岸線に囲まれた島がゆっくりと現れた。 宮古諸島だ。 池間島と池間大橋が機窓の端から顔を出し、やがて本島が雲間に登場。建設中の伊良部大橋のループがくっきりと浮かんでいる。完成すれば無料の橋としては国内最長となる。橋に繋がれる伊良部島とその先の下地島は上空からはひとつ島のように見える。民間パイロットの練習空港、下地島空港とその前に広がる碧の海が今日ははっきりと見える。空港は、現在、利用会社が次々と使用を中止し、あとはRACと海保の訓練程度にしか利用されていない。 日が傾き、海面の色が銀だみに変わる。水面に映ずる雲の陰は灰色に沈み、見つめ続けていると雲の影だか島影だかが判然としなくなってくる。 そして石垣島が、島の北端、平久保崎からしずしずと現れてきた。船越(ふなくやー)や玉取崎が見え、ナローボディーの機はランディングアプローチに入り、新空港に翼を休めた。 年間100万人近くの観光客を迎えるようになった石垣島。新空港開設前は80万を目標に、しかもなかなか達成できずにいたのだが、空港完成 |
後3年もたたずにあっというまに目標を達成してしまいそうだ。 週2回、台湾からのクルーズ船もやってくる。 接岸すれば1500名の台湾人が市内に繰り出し、薬局に殺到する。人気銘柄は正露丸なのだと言う。台湾では頭痛にも正露丸を飲むらしいと空港で掴まえたタクシードライバー氏は言う。彼等の中には、スーパーに入れば、梨を手に取り、トイレで食べてしまう不心得者もいるらしい。逞しい話である。 旧空港は、市街地に近かったが新空港は3倍ほどは遠くなった。そのかわり、海岸線を見渡せる空港からの眺めは素晴らしい。国内屈指の景観を誇る空港だろう。 もともと30年以上も前からの建設計画で予定地もここだったそうだ。ただし、海を埋め立てる予定だったが、環境保護団体の猛反発により、計画は一時頓挫。海岸沿いの内陸に建設するということで、島唯一のロングコースのゴルフ場をつぶして空港建設はなった。皮肉な話だが、ゴルフ好きのオヤジ観光客むけの施設は新空港建設と引き換えになってしまった(小浜島にはあるけど)。 空港から市街地に向かう周回道路は途中に点在するリゾートホテルを結んでいるが、片側1車線(石垣に片側2車線道路はない)で、追い越し禁止ゾーンが多く、信号も多い。空港道路建設計画が進んでいるらしい。島内初の片側2車線道路が出来上がることになる。 前日に梅雨明けした沖縄。島人は口を揃えて、今年の梅雨は長くてジメジメしていたと言う。「昨日から急にカラッとしたねぇ」とのこと。 市街地の730交差点が工事中だがどういう工事なのだろう。どういう風にしたいのだろう。よくわからない。 朝、蝉の合唱で目が覚めた。 |


新石垣空港 と 2007年、新空港建設前の空港予定地の見学台と周囲の景色
| 最近、からだを動かしていないので、軽くトレッキング(ハイキングって言うよりかっこいいから)でもするかと思いたった月曜日。 どこにするか? 鞍馬貴船か春日山周遊か。京都と奈良だ。 土、日、祝なら京都は13時からバーが開いているが、今日は月曜日だから駄目。でも貴船の川床で涼を得るのも捨てがたい。奈良は、実のところゆきつけの店がない。「からだを動かしたらあとでいいことあるぞ」っていうアメとムチのアメが弱い。今日は奈良はパス。神戸はどうだ。 神戸と言えば、けっこう有名らしいが筆者は中山寺を知らなかった。ま、在阪12年、無事に過ごしてこれたので、知らなくても大過はなかったということだが。 先般、阪急今津線で寺の広告を見た。それが深層意識の底部に沈潜していたのかもしれない。寺巡りというだけなら食指は動かないのだが、中山山頂の標高478mの途中に奥の院があり、そこまでは、麓の寺から3キロ程度。そこから、かまどの神様を祀る清荒神(きよしこうじん)までさらに3キロ程度、ちょうど鞍馬寺、貴船間山岳トレイルみたいなことができそうだ。運動量が最適(筆者基準)。さらに阪急清荒神駅の隣が終点宝塚。そこで今津線に乗って西宮北口に行けば阪急西宮ガーデンに行ける。そこには鹿児島に本店のある黒豚しゃぶしゃぶの店「いちにいさん」があるのだ。休みの日なんぞ行列ができてとても入れないと聞いていたが月曜の昼過ぎならば大丈夫じゃね?(発音は平板に)と思い立った。アメとムチの絶妙なバランスが成り立ち、筆者は、阪急宝塚線中山観音駅 |
へ向かった。 中山寺は駅から徒歩5分。 近い。 安産祈願の寺らしいが、交通安全、厄除け、商売繁盛と、御利益の百貨店みたいな感じだ。 五重塔の再建工事をやっている。全体的にピカピカな感じ。なぜか「やり手」という言葉が頭に浮かぶ。聖徳太子の建立という話もあるから古刹ではあるのだが枯淡な印象は受けない。。 境内の奥に奥の院に向かう山道がある。 「奥の院を経て中山山頂へ約3.1Km」と書かれた標識の脇に「弐丁」と書かれた丁石が立っている。すぐに「三丁」の石が現れた。根拠なく山の何合目と同じように「丁」も「十丁」で山頂になるのだと思い、(ちょろいぜ)と山道を登っていった。 (ん?) 気がつけば、目の前に「十三丁」の石。 自分勝手な思い込みが崩れた瞬間。疲労感が心なし増した。あとで調べたが中山寺から奥の院までは十八丁あるらしい。 鞍馬寺の魔王院のようなものだろうが、奥の院もピカピカで、「やり手」という言葉が頭に浮かぶ。 清荒神に向かう道は往路とは別だ。 開かれた尾根伝いの道から、やや足場の悪い坂道を下り、清荒神に舞い降りる。狛犬のかわりに布袋さんが両側に立つ階段を登り、境内を散策。参道ぞいに並ぶ商店街を抜けて阪急「清荒神駅」へ。当初の予定通り、西宮で黒豚しゃぶしゃぶを堪能。 |

| 那覇での滞在が、あまりに日常的になってしまったので、変化を求めて名護へ行った。 那覇空港駅発の高速バスに乗る。 ダイヤは1時間に2本。 乗客はまばら。 レンタカーを借りるのがまっとうなものの考え方だが、筆者はスーパーペーパードライバーで、かつタクシー代をけちろうとしているからバス。 首里城方面に向かって82号線を北上。与那原、南風原(はえばる)などの地名表示に、(そー言えば原の字、多いよな)と思った。首里城周辺の平地を原と称したのか。城を中心に据えて南側にあるから南風原。でも北側にあるのは、西原(にしはら)なんだよな~。本当は北原(にしはら)だった。ウチナー口では北のことを「ニシ」と言う。明治維新後の土地調査で本土から来た官吏が聞き取りの際「ニシハラ」と聞いて、本土感覚で「西原」と記載してしまったのだと、昔、誰かから聞いた。 那覇インターから沖縄自動車道に入る。 時あたかも本土では藤の季節。 しかし、高速道の周囲を彩っているのは朝顔。紫っぽい青だから、色味は藤と同じ。ツル科の植物だから、他の樹木に寄生するように巻きつき、咲き誇っているのも同じだ。本土は藤で沖縄は朝顔か? 西原・浦添、北中城・宜野湾、沖縄南・嘉手納、沖縄北・うるまなどを通り、名護にむかう。所要時間は1時間50分程度だが、許田の出口前で渋滞につかまった。やがて終点の名護BT(バスターミナル)へ到着。 名護市役所あたりで降りればよかったのだろうが、バスターミナルの場所と雰囲気を知っておきたかった |
のでやむを得ない。 名護十字路と呼ばれる交差点が街の中心だが、そこからはちょっと離れてしまった。ざっくり2キロ強はある。 とぼとぼと心覚えのある中心地へ向かって歩き始めたが、かなり心もとない。ここに中心地があるのかとすら不安を覚える平たい街並み。 北海道と沖縄。 日本の南北両極の共通点は一極集中だ。札幌と那覇に社会資本や人口が集中し、他のエリアはどんどん寂れてゆく。(本土も同じか) 名護にはまさにそんな寂寥感が漂っている。 しかし、名護と言えば、アグー。名護はアグー豚の里なのである。 名護十字路の先、大中(南)の交差点を折れて3ブロック目に「エルフランセ」というステーキハウスがあった。店内にはファイターズ選手の色紙が壁面を埋め尽くしている。キャンプ地だったのね。黒琉豚あぐーの肩ロースステーキがオススメとのことで消費。オリオンビールの名護工場がつい目と鼻の先にあるから、できたての生ビールが飲めるのが名護のいいところだ。 名護には4回ほど来ているが、宿泊したのは1回だけ。しかも野次北メンバーでのレンタカー旅だったので、街のイメージが明確でなかった。那覇から高速バス、路線バスの乗り継ぎで島に渡ろうという計画の予備調査はほぼ果たした。 名護の手前、宜野座あたりのリゾートホテル群は、名護バスターミナルへのアクセスが面倒くさくなるから駄目だな。あ、それから名護市役所。この建物はかなりキテル。 |

右端の写真が名護市役所
| 湖東三山のひとつ龍應山西明寺(さいみょうじ)に行った。 湖東とは琵琶湖の東のこと。三山の山は寺を表す。禅宗に多い山号という奴である。 西明寺のほかに、松峯山金剛輪寺、釈迦山百済寺がある。 西明寺は、JR彦根駅の一駅西にあるJR河瀬駅が最寄になる。 寺のホームページに時刻表が載っていた。「甲良線時刻表 毎日運行(12/29~1/3は運休)」とあり、河瀬駅東口(発)で7時から毎時51分発で夕方まで便があった。それを目安に米原で「こだま」を降り、河瀬駅東口に向かう。 駅前は、商店「街」はおろか、商「店」1軒とてないシンプルさ。タクシー乗り場はあるが、客待ちのタクシーは1台もない。バス亭の時刻表を見る。 (????) ホームページに書かれていた1時間に1本のダイヤなど影も形もない。10時と13時と16時には1本もないし、その他の時間帯も1時間に1本だが、毎時51分などではない。何よりも路線図に西明寺は存在しない。 (まーた、やっちまったか)高をくくって、仔細に記事をチェックしなかったのが敗因だ。ホームページに記載されていたのは予約型乗合タクシーの運行時間だったのだ。毎時51分発は固定されていて、利用者はその1時間前にタクシー会社に電話をしなければいけなかったのだ。今から電話をしても1時間は待たねばならないので、乗合タクシーではなく、迎車を依頼した。 駅前から15分、迎車タクシーは2850円で筆者を西明寺まで運んでくれた。 |
「帰りは乗合を呼ばれた方がいいですよ」 女性ドライバーの細やかな心遣いに(もとよりそのつもりでい!ちくしょーめ)と思いはしたがそのまま口には出さなかった。悪いのは自分だからである。ちなみに復路で予約した乗合タクシーは、マイクロバスではなく、普通車だった。カウンターもタクシーのように走行距離と時間でカチャンカチャン上がってゆく。河瀬駅についたときには往路と同じくらいのメーターになっていたが請求金額は900円だった。どうやら固定料金らしい。あまり精神衛生によくないシステムだ。 西明寺は、古刹である。平安時代初期の創建で境内には国宝の三重塔と本堂(いずれも鎌倉時代)、重文の二天門(室町時代)が配されている。 惣門をくぐると「天然記念物 不断桜」という案内板があった。時あたかも桜の季節。興味を覚えて足をむけたが・・・(咲いてないじゃん!) 「天然記念物 不断桜 樹齢250年11月満開」との表示板があった。 本堂入口に向かう石段の周囲の杉並木は趣がある。石垣や庭に生している苔も見事だ。 二天門の左右に、増長天と持国天の木像が屹立しており、その迫力と姿はなかなかにいい。本堂には残りの二天、広目天と多聞天も立っている。 三重塔と本堂は飛弾の匠の手になる建築で釘が使われていない。 戦国期、織田信長の叡山焼き討ちに際し、西明寺も戦禍に巻き込まれたが、機転をきかせた僧侶が参道の中段で火を燃やし、織田軍の目を欺き、二天門、本堂、三重塔を焼失から守ったとの伝があるそうだが、実際は、軍司令官の寛恕に救われたのではなかろうか、と筆者は思っている。そこのところが今回、来訪の動機になったのだ。 |

| 港の音。 それは船の機関音であったり、波の音であったり、海鳥の鳴き声や汽笛の音であったりする。 沖縄にいる実感はこの港の音に包まれたときに生まれる。特に那覇にいるとそうだ。那覇は大都市だし国際通りは海に面していない。 那覇の泊港から高速船で50分。 そこに大小20余の島々からなる慶良間諸島が浮かんでいる。 慶良間ブルーと呼ばれる海の青さは世界屈指と言われている。(行ったことないけど世界) ボートダイビングで行ったことはあったが、上陸はしていなかった。泊港のチケット売り場で往復便の予約番号を告げて乗船券を手に入れた。 慶良間は、渡嘉敷村と座間味村の2村からなっている。それぞれの村の主島は渡嘉敷島と座間味島だ。筆者は座間味島行きの高速船に乗船した。観光リーフレットには「ようこそ座間味村」とあって、座間味村の管轄する座間味島、阿嘉島(あかじま)、慶留間島(げるまじま)、外地島(ふかじじま)などが 載っている。しかし、すぐ目の前に浮かぶ渡嘉敷島はまるでそこにないかのように省かれていた。仲、悪いのか?座間味と渡嘉敷。慶良間諸島と那覇の中間にある3つの無人島はチービシと呼ばれており、筆者はフリーツアーで上陸したことがあったが、ここが、渡嘉敷村の管轄だとは今回初めて知った。 やがて船は2日前に海開きしたばかりの座間味島に接岸した。海開きと言ってもウチナーは海に入りはしない。ビーチパーリーをやるだけだ。 東京の最高気温は14度程度という涼しすぎる気候だったが、ここは最高気温27度。すでに初 |
夏である。ただし、吹き渡る風は、そこはかとなくまだ優しい。 目前の慶良間ブルーが美しい。石垣や宮古、八重山の海も負けず劣らず美しいが、慶良間はブルーの海もさることながら、海上に浮かぶ大小の島々や岩礁が視界におさまっての美しさだと気がついた。島人にとってはまさに「故郷の山河」というイメージだろう。(海と島だけど) 離島のこととて、大規模商業施設があるはずもなく、初夏の日差しの下、島は静寂に包まれている。もちろん、スタバやマックがあるなどとは思っていない。普段、合理主義の権化のように無駄な時間を削ること、刀削麺のコックのように熱心な筆者だが、ここではあちこち無駄足を運んで散歩を楽しむ。なんとも言えない島時間感覚に染まる自分が愛おしいアイラブミーな筆者。 港から20分程度の距離に標高137mの高月山展望台がある。そこからの眺めを堪能し、眼前に浮かぶ阿嘉島にも渡ることにした。村内航路(みつしま)で座間味港から阿嘉港まで15分。料金は300円だ。帰路の高速船は、座間味発のチケットなのだが、船は阿嘉島始発ゆえ、座間味に帰ってこずに阿嘉島から乗ってかまわないと言われた。実のところ観光客の大半は座間味島から乗船するため、席とりが大変なのだ。ラッキー。 阿嘉島は阿嘉大橋で隣の慶留間島と結ばれている。さらにその先の外地島とも繋がっている。 天城展望台と、中岳展望台からの眺めも良かったがニシハマビーチに向かう頃には日が翳ってしまい、慶良間ブルーが色あせてしまったのはちょっと残念。ただ、この日15キロくらいは歩いたから運動不足の身にはよかったかな。 |

| 「長谷寺」に行った。 近鉄大阪線「長谷寺」駅へは地下鉄御堂筋線「梅田」駅から1時間強。「難波」で近鉄に乗り換え、「鶴橋」で特急に乗り継ぎ「大和八木」で特急を降り、各駅停車か準急で5駅。駅から15分程度歩くと「花の寺」の別称を持つ「長谷寺」に辿りつく。 季節に応じて、桜、牡丹、紫陽花、紅葉を楽しめるらしい。 長谷寺の参道の幅員は狭い。 狭いが交通量はそこそこにある。譲り合わねばすれ違えないボトルネックポイントが幾つかあり、車列が生じる。参拝客の多いシーズンの土日など、どうなっているのだろう、と心配になる程度には平日の昼でもクラクションが鳴りまくっている。 参道が終わり、長谷寺仁王門に至る石段の前に枝垂れ桜が咲き誇っていた。 山中にある本堂とその後背の山上まで、この枝垂れ桜を起点として山の斜面が一望に収まる奥行きのあるいい構図になっている。 (いい画じゃないか) 誰もがそう思うのだろう。桜の前で皆が時間をかけて執拗に写真を撮りまくっている。観光地では、何かにとりつかれたように撮りまくるのが日本人の証。筆者ももちろん撮りまくる。桜の前から人がいなくなるまで10分近く待機してまずは1枚。 仁王門の先には登廊がある。 山の斜面を登る屋根付階段回廊だ。 この登廊も奥行きがある。(つまり長い) 奥行きもあるが、屈曲もある。斜面を直登せず |
に右折し、左折している。 本堂には本尊の十一面観世音菩薩があり、普段は本堂内礼堂(らいどう)から菩薩像のバストアップショットしか見られないのだが、今日はその菩薩像の足元から全身を見上げられ、おまけに直に像に触れることができる太っ腹な特別拝観日であった。 撫でまわすのは足である。 (ビリケン?) ちょっと不埒な連想が浮かぶのを止めることはできない。 見上げる菩薩像はかなりデカイ。礼堂の欄間から覗くバストアップショットではこのスケールを測りそびれるだろう。光背まで入れると12メートル超の立像なのだ。重文の木造観音としては最大らしい。 本堂南面は清水寺と同じような舞台造りで、舞台がせせり出ている。そこから見下ろす伽藍の広がり、そこここに咲き誇る桜、やはりいい画である。目を水平に転ずれば、桜の海の向こうに赤い五重塔が浮かび上がる。この伽藍は、なかなかに計算されつくした造りらしい。高度なディレッタンティズムを感じる。 五重塔は近くに寄ると最初の印象ほど高くはない。遠目に大きく見える工夫でも為されているのか。聞けば、戦後、日本で初めて建てられた五重塔とのこと(明治期に三重塔が焼失したらしい) 奥の院など境内を歩き回ると高低差があるので足にくる。 寺のアトラクション度はかなり高い。 筆者は、この物件にかなり満足。 |

| 播州三木城。 関東圏では馴染みの薄い名前である。 そもそも「播州(播磨)」がイマイチのはず。 (あくまでも関東圏の人対象に) 山陽道を西から東に、赤穂、相生、たつの、姫路、加古川、明石あたりまで、北は作用から但馬の手前(だから但馬ってどこよ!)の宍粟、神河くらいまでのエリアが播州です。って言われても日本地図のどこいらへんか、わからんのが播州。関西圏の人間に「下野の国」ちゅうてもちんぷんかんぷんなのと同じだろう。 しかもこれだけ紙幅を割いて「三木」がまだ現れてないし。 「三木」は播磨の東端、「明石郡」の北部に位置する「美嚢郡」の中心。 大きく国名で捉えれば、播磨の西は備前、備中、備後、安芸と連なっている。備前、備中が岡山県、備後、安芸が広島県、播州は兵庫県(北の但馬を合わせて)ぐらいの見当でいいと思う。 戦国時代、毛利家はその版図最大の時期で、備中まで領有していた。しかも日本海側は、出雲、伯耆、因幡(島根県、鳥取県)までの大勢力だ。 備前は中国筋では希代の謀略家とされている宇喜田直家が陰謀の限りを尽くし、一国を治めていたが、播磨は、中小豪族の群生地のようで、有力大名がいなかった。 その中にあって三木城主の別所氏が播磨での最大勢力と言われ、彼が織田と毛利のどちらにつくかで播磨の中小豪族の帰趨は決まることになる。 織田方についた黒田官兵衛の姫路城は、けっこー危なっかしい位置にある。別所が毛利につけば、姫路と京都の連携を断ち切ることのできる実に |
いい位置に三木城はある。 播州の諸豪族を説きに説いて、織田方へ帰属させようとしていた官兵衛の諜略は、毛利方の外交僧、安国寺恵瓊にひっくりかえされ、別所氏が毛利方への帰属を鮮明にしたとたん、他の豪族も一気に反織田となった。 播州の東にある摂津を治める荒木村重もこの時期、造反し、官兵衛は、主家の小寺に荒木へ売られて伊丹城に軟禁されてしまう。中国戦線司令官の秀吉は、一戦場だけにかかわっておられず、三木城攻めをまったく新しい方法で攻略することになる。 爾後の秀吉の攻城の基本となる、大土木工事による攻略法だ。 三木城は足かけ3年にわたる攻城戦の後、落ちる。攻城戦、と言っていいかどうか。 老境に入った関白時代と違い、この時期の秀吉はあまり人を殺さない。三木城の周囲に城を包囲するかのような戦塞を築き、城そのものをからめとるようにして干上げてしまった。 守将の別所長治と、その家族、重臣の命と引き換えに無血開城した三木城には、秀吉軍の包囲網の配置図があるが、実相は、上記のとおりで、爾後、彼はこの中国戦線で、鳥取城、備中高松城と、巨大な土木工事による攻城戦を続けてゆく。 華々しい決戦場ではなかったが、この三木城跡には、神戸電鉄粟生線(あおせん)で行ける。 阪急神戸線で新開地まで。神電に乗り換えて三木上の丸駅下車。神電は途中、湊川や鵯越(ひよどりごえ)などちょっとそそられる駅を通る。 新開地を始発駅として有馬線もある。こちらは有馬温泉に向かう。けっこー、イイでしょ。 |

辞世の句「今はただ うらみもあらじ 諸人の いのちにかはる 我身とおもへば」
東北新幹線「はやて」の車内から →back 東北新幹線「はやて」の車窓から
| 新青森行き東北新幹線「はやて」は秋田新幹線「こまち」と連結されていた。緑のE5系と赤のE6系はJR東日本の新幹線代表銘柄だ。 「はやて」「こまち」ともに全席指定で自由席はない。「はやて」には、普通、グリーン、グランクラスの3段階の指定席がある。 終着新青森まで行くことにした。途中駅は、上野、大宮、仙台、盛岡、八戸だ。新青森まで初乗車なので、初めてついでにグランクラスに乗ってみた。普通車指定席15770円、グリーン車指定席20460円のところ、グランクラスは25460円!(えきねっと割引価格で)高っ! グリーン車と同じ2×1のシートが6列、先頭車両(10号車)に18席の仕様だった。 シートは、コクーン状の外装に収まっている。リクライニングは電動式。背もたれ、座面、フットレストの3箇所で位置調整ができる。さすがに180度フルリクライニングとはいかぬが135度くらいまでは倒れる。 シート肘掛部の先頭にコンセントがあるのは、グリーン車と同じだ。 アテンダントコールボタンもある。 30センチ程度の可変の柄の先についた百合の蕾のような形の読書灯は先端部をひねって点灯、消灯させる。 正直、車窓に目をやるにはちょっと邪魔。 車窓は思いのほか小さい。ワイドビューという感じではない。おまけにシートが車窓から離れていて、車窓に顔をびたっとくっつけて流れ行く景色を愉しむことができない。 持ち帰り可能なスリッパがひも付き巾着袋の中に入っていた。 |
列車が動き始めると、アテンダントがおしぼり(ちゃんと布タオル)を配り、サービスの軽食(和、洋選択可能)とドリンク、つまみ、菓子などの注文を受けに客席を回る。 アルコールは、ビール、ワイン(白か赤)、日本酒、シードルから選べる。ソフトドリンクも数種ある。ドリンクは何杯でも頼める。 つまみと茶菓子はひとりひとつずつ。とりあえず一揃え全部頼んだ。すべては読者の皆様へのサービス精神のなせる業である。 軽食は、和軽食を選んだ。もちろん写真をとるためだけの取材精神の発露である。洋軽食はどうせサンドイッチにきまってるしね。菓子とフルーツ付だろう。和軽食は、ちゃんとしたランチボックスだった。ただし目的地での酒食を考えると、移動時間内で腹を満たしてしまうのはもったいない。どうせ飲みまくるなら帰路の方がいいかも。 隣のグリーン車との間に車掌室前を通るエントランスを設け、グランクラスの客車まで2枚のドアで仕切っている。エントランスには、各種新聞が「グランクラス専用」とスタンプされて並んでいる。 男女共用の洋式トイレは、ウォシュレット付であった。 東京、大阪行きのチケットには都区内とか大阪市内とか特定都区市内が記載されているが、今回は、着駅の「新青森」としか記載されていない。新青森から青森までの乗車券180円が必要なのか不明だったが、駅員はそのまま改札を通してくれた。ただし、復路は180円の乗車券を買わされた。これは駅員の間違いなのか? 今回は画像大きめでサービスします。 |


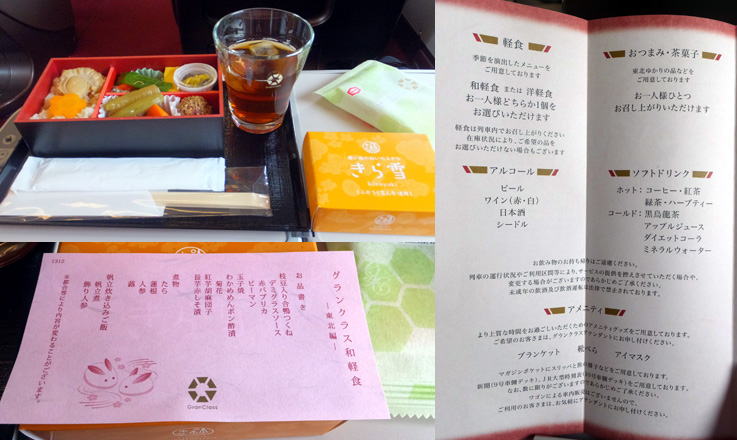

| 「木曽路はすべて山の中である」 昭和4年に筆者が島崎藤村に100円で売った書き出しである。 中仙道69次の中の木曽路11宿。その南端に馬籠宿はある。「馬籠」は「まごめ」と読む。 名古屋から中央本線、特急「しなの」で中津川まで50分弱、中津川からバスで30分弱。そこに「馬籠宿」がある。 馬籠宿は坂道に形成された宿場町だ。宿場口を曲がるといきなり大きな水車が旅人を出迎えてくれる。道は左に右に屈曲したあと、緩やかな曲線を描いて坂上に向かう。その両脇に蕎麦屋や茶屋や雑貨屋、資料館などが並んでいる。 宿場の中ほどの観光案内所で馬籠宿の隣の妻籠宿までの道のりを聞いてみた。距離的には7.8キロ程度だ。中山道を歩いてみたい。 「ちょっと、靴の底を見せてください」 (え?) 「今年は雪が少ないのでここまでは大丈夫なんですが、ここ・・・」と地元のおじさんが指差したのは「とうげ」と書かれたポイント。 「ここから先は、雪道になっていると思います。お客さんの靴では無理ですよ。周囲に民家もありませんし」 馬籠宿には積雪はおろか、残雪のひとかけらだにない。事前に雪がないとの情報は得ていたので筆者の靴は起毛のワークシューズだ。雪が積もっているとしたら、たとえそれが2ミリほどでも滑って転倒することは、たび重なる雪道転倒経験で熟知している。 「もし、行かれるのなら」 とおじさんは地図をなぞり、「ここから県道を歩け |
ばなんとかなるでしょう」と請合った。 中山道に足を踏み入れる前、宿場口の展望台から見えるはずの標高2190m、東海随一の高嶺、恵那山は山頂が雲に覆われ全容がとらえられなかった。先ほどまで快晴だった空に鉛色の雲が垂れ込め、前途の多難さを予感させた。 宿場のある標高600mから801mの馬籠峠までの登り坂の道端には白いものがちらほらと見られたが、なんとか街道は歩き得た。峠の頂上の手前に県境がある。馬籠は岐阜県、妻籠は長野県なのだ。ちなみに「妻籠」は「つまご」と読む。 頂上から先の中山道は、雪に覆われていた。 (こりゃ無理だ)峠のバス停のダイヤを見る。 11時から歩き始めて、今は12時。バスは13時36分。周囲に何もない峠での1時間半は絶望的に長い。県道7号を歩くことにした。下り道をあと5.5キロ。問題は県道もコーナーは除雪しきれていないことだ。カーブには雪が積もっている。行き交う車がほとんどなかったからよかったが、車の往来が激しければ、けっこう怖いことになっていた。 (オイラは山の神だよ~)などと呟きながら、トボトボと県道を下る。 妻籠宿の手前の大妻籠に到着。ここまで来れば雪もない。妻籠まであと2キロ。再び、旧中山道に足を踏み入れる。 妻籠宿の看板を見つけ、宿場に入ったのは13時。ここは町の美観保持運動を全国に先駆けてはじめたところ。先ほどの馬籠には観光地臭があったが、妻籠の町並みは、生活に密着した質朴な空気に満ちていた。やっぱ、ここまで歩いてきてよかったわ。 |

札幌行6 →→→back 札幌行1 2 3 4 5 6 7 8 9
| 去年、一昨年と連年、新年の1月に北海道に行っているが今年は行けないな~ 昨年は、ビジネストリップなので、翌日には東京に向かわねばならないから時間はない。しかもフリーになるのが午後9時なので、慌ただしい。 それでも、札幌の夜を楽しむのだ。 同行のNは2009年10月以来3年3ヶ月ぶりの札幌の夜である。 あのとき、今は無き「ビストロ・ポアーヴル」でチーズ攻めで陥落させてしまったお詫びの意味もかねて、今回は楽しんでいただく。 とは言え、あの時もチーズばかりを食べたわけじゃない。「スモークした鮭の白子」「釧路産さんまのエスカベッシュかぼちゃのコンフィ添え」「登別酪農館のホエー豚のソーセージ」「ラクレットをポテトとパンに」「登別酪農館のプロヴローネチーズのステーキ仕立て」「チーズ3種盛り(牧家のみそウオッシュ、ダレッジォ、ブリアサバラン)」というメニューだったのだ。 あ、やっぱチーズ多いっす。 今回は、まず寿司屋。 「たる善本店」がちょうどいい。アテが豊富なのである。 店に入ると、第36代庄之助の揮毫とともに、大鵬、北の湖、千代の富士の手形が押された掛け軸がある。3人の名横綱は皆、北海道の出身なのだ。 「今日は、レコーダーは?」 備忘のICレコーダーは、初見の店では「ん?」と構えられることが多い。 「いや、飲んべでね、何食べたか忘れちゃうと辛いでしょ」ちゅうのがいつもの言い訳。これが意外と店の記憶に残るらしい。 突き出しの「ブリ大根」で掴みはOK。おあとは「カニ身とカニ味噌あえ」「タチ」「松前漬け」「牡蠣のオイル漬け」。 「タチ」はタラ白子の地場呼称。こいつを昆布の上に乗っけて炙ったもんが旨いのだ。 「タイの昆布締め、エビ、中トロ、玉子焼き、タチカマ」を引いてもらう。 「タチカマ」は、タチをあたり鉢で擂って塩と片栗粉を入れて蒸したもの。タンパク質が塩で化学変化し、カマボコのようにプルプルの塊になるのだ。これを山葵と醤油で食べる。旨い!筆者は、さらに椀物に入れてもらうこともある。岩海苔とタチカマのすまし汁なんてなんともいえない。 |
取れたてのカズノコを塩水につけて柔らかいカズノコを締め、薄皮をはがし、もう一度さっきより少し薄い塩水につけてそこから出して洗ったばかりの出来立てのカズノコは、色が綺麗だ。バナナのようにクリームがかった黄色。味はエグミも臭みもまったくない。ポリポリ。旨いなあ。 北海道なのにすでに「若竹煮」があった。「行者ニンニクの3年漬物」には佐賀の日本酒「東一」があう。米や麦の焼酎水割りをクイクイ飲んだが、日本酒もちょいとひっかける。北限の日本酒「国稀」と根室の「北の勝」を。 締めの握りは6カン。「ヒラメのえんがわ、オオトロ(カマの部分)、オオスケ、ホッキ、軍艦はウニ(浜中町)とイクラ」 「たちと海苔の味噌汁」を腹に納めて店を出る。 「バー・プルーフ」のオーナーバーテンダーN河氏は現役最高齢バーテンダーY崎氏のお弟子さん。Y崎氏の優しいお人柄をそのまま受け継いだような接客姿勢だ。「バンブー」と「マティーニ」「ボウモア12年」をショットで。ボトルに入ったボウモアは氏が、「バー・ヤマザキ」でチーフバテンダー」をしていた頃、70年代入手の樽買いボウモアが各バーに配られていた時代のものらしい。溜めていたが、これが最後の1瓶だと言う。 「バーヤマザキの系譜」という本が札幌の出版社から上梓されたと言う。 見せてもらえば、金沢のH田氏も載っている。これはこれはと店でこの本を購入。 「バー・ドゥ・エルミタージュ」へ。こちらもY崎氏のお弟子さん。オーナーバーテンダーのN田氏は、女性らしいホスピタリティあふれるお人柄。和歌山の「蛇腹(じゃばら)」という柑橘を使った何種類ものカクテルが印象深い。味もさることながらネーミングがいい。基本、ダジャレ系。ジャバッジハンマー、ジャバレントサイド、ジャバラカー、ジャバラリータ・・・ただし、蛇腹はラムにはあわないらしい。今シーズンの「蛇腹」は終わってしまい、飲めなかった。「クォーターデッキ」と「マダムリター」をいただく。 ふと時計を見れば1時だ。Nは明日も朝から講演がある。万全の体調で臨んでもらいたい。 お開きにした。このあとは独りで「だるま」へ行ってジンギスカン3皿と生ビールを飲んだ。まったく成長しとらんな、我ながら。 |
| もう年の瀬になって、いまさらではあるが、今年は珍しいことに紅葉に彩られた秋を過ごした。 紅葉好きではないのに、意図せざる偶然が重なってそうなった。そういうこともあるか。 寒気の到来が例年より早く、西日本では記録的に早い降雪があったせいか、「今年は秋がなかった」なんて言う人も多かったが、筆者に秋はあったのである。 京都での用向きが終わり、時間が空いて、「そうだ高雄行こう」と思ったのが紅葉始め。 これが11月11日、ゾロ目の日。 市中ではまだ色づきはじめたばかりの頃。名所の色づきを待たずに、京都で一番早い紅葉ポイントに行ったのが良かった。まだ、寒気も厳しくない秋の一日だった。 さらにその週末、北陸の紅葉名所「那谷寺(なたでら)」に立ち寄った。やはり、まだそれほど寒くない。 そして、筆者の心の保養地、金沢。 普段なら飲んでくれ、食ってくれ、酔ってくれのへべれけ滞在で時を無駄遣いするのだが、なぜかパチン!と呑んだくれスイッチが切れてしまった。そんなこともあるのか。 灯ともし頃に兼六園へ向かう。 昼の間にどこかでポスターを見たのだ。 兼六園の紅葉ライトアップ。秋の段とあった。 無料公開である。 太っ腹!石川県。 広坂のそばにある真弓坂口から入園する。 「瓢池(ひさごいけ)」ごしに「夕顔亭」の灯りが遠望され、色づいた梢が照明をうけ夜陰に浮かび上がる。筆者にとっては、見慣れたと言っていい園内の景 |
色が、まったく別の絵になっていた。 水辺の周囲に設置されたライトに工夫があるのだろう。水面に映る逆さ紅葉が美しい。 けっこう幻想的だ。 街灯がついているわけではないので、園内は好ましい程度にほの暗い。人出はあるが、行き交う人の表情が見て取れるほどには明るくない。何がなし祭りの浄闇、という風情だ。なぜか、角館の枝垂桜の夜を思い出した。 そして、兼六園と言えば、「ことじ灯篭」。 考えることは誰しも同じらしい。 「ことじ灯篭」前の通り道にできた行列はかなり長い。 「ケッ!」と毒づいてきびすを返すのが常なのだが、この日はなぜか、心にゆとりがある。「いいじゃないか」と行列の最後尾に並んだ。 おそらくは後背の水景と対岸までの奥行きがあっての「ことじ灯篭」は夜は、ちょっと難しいかも。ただし、ベタな物件だから、皆、この灯篭の前に立ち、ポーズを決めて写真に収まってゆく。 築山にあたる「栄螺山(さざえやま)」に登り(高さは9メートルほど)、「霞ヶ池」越しに、金沢の冬仕度の代名詞「雪吊り」がほどこされた「唐崎松」を眺める。これは美しいじゃないか。 園内のどこかからフルートの音が響きわたってきた。ソフトバンクのCM曲「くるみ割り人形」のあし笛の踊りだ。 見上げれば、満月にわずかに欠けた月がライトアップの届かない木々のシルエットに煌煌と白い光を滴らせている。 いい夜だった。 |

| 高雄は、京都の北西部にある。高尾(東京)じゃないよ高雄だよ。 ここは、京都紅葉前線のスタート地点だ。 京都の紅葉はこの地から始まる。 11月の旬日が過ぎた一日、京都での用向きが終わり、時間を持て余した筆者は高雄へ向かった。 京都駅前バスロータリーのJRバスコーナーから高雄方面行きのバスが出ている。所用時間は45分程度だが、京都市街地を抜け、立命館大学のある衣笠を越え(つまりかなり遠くまで来て)石庭で名高い竜安寺を越え、仁和寺を通り過ぎ、ただひたすら北進するうちに道は一本道となり、いつのまにかバスは深山渓谷に分け入っている。 山城高雄停留所から槇ノ尾(とちのお)停留所を経て終点、栂ノ尾(とがのお)停留所までの3停留所間の谷川沿いに3つの寺が並んでいる。谷川の名は清滝川、3つの寺は、神護寺、西明寺、高山寺と言う。上流(終点栂ノ尾)から下り来たってもいいが、バスで座って帰りたければ山城高雄で降りて上流に向かうほうがいい。 神護寺は、紅葉で知られている。 古刹である。山号は高雄山。和気清麻呂の建立で空海上人が唐から帰朝して14年間住持した。この時期に真言密教立教の基盤を築いたと言われている。 清滝川にかかる高雄橋を渡り、石段を登り詰めると楼門が現れる。 京都市中の紅葉は色づき始めたばかりだが、神護寺ではすでに見頃をむかえていた。楼門前は、格好の写真スポットだ。カメラの砲列が並んでいる。 でかいカメラを抱えた親爺が、被写体にかかる他人を手でふり払っている。ここまで自己中心的になれれば人生はきっとストレスフリーだ。紅葉の京都で、他人を写さずに紅葉だけを写すなんてことは魔 |
法使いにだってできやしない。JRの駅貼りポスターと同じものは絶対に撮れない。あれは間違いなく立ち入り規制をして人を排除して撮っている。 境内の最奥部にある金堂に向かう石段の周囲も美しい。石段の途中から振り返って撮るショットがこの寺の白眉だろう。さらに寺域にはかわらけ投げ場まである。バルのように皿を投げよう。 神護寺の次は西明寺だ。山号は槇尾山(とちのおさん)。高雄の3つの寺の山号はそのまま停留所名に直結している。神護寺前が「山城高雄」、西明寺前は「槇ノ尾」。 清滝川の清涼な流れを覗きこみつつ、指月橋を渡る。石段の先には小ぶりな表門。表門をくぐると、本堂、客殿が手ごろな広さの境内に連なっている。 先ほどまでは晴れていた空が一転、黒雲を呼び、雨が降り出した。山の天気はままならぬ。はかったように寺前で傘を売り出した。500円ですと。拝観料は、神護寺500円、西明寺500円、この後の高山寺で500円。さらにその境内の石水院で600円だった。遊園地のように金が飛んでゆく。石水院の時はさすがに600円が惜しくなってきた。 そして高山寺。山号は栂尾山(とがのをさん)。したがって、寺前の停留所は「栂ノ尾」だ。 文化財の宝庫と言われ、鳥獣人物戯画が有名。 金堂にむかう石段は静寂に包まれ、雨に濡れた参道は、なにがなし、山形の月山山中にある五重塔に向かう杉並木を思い出させる。 そして、600円をけちらずに入ってよかった、石水院。手漉きガラスかもしれない。ガラス越しの景色が微妙に屈曲して映る。 縁台に座って眺める向山の景色も美しい。 半日イベントとしては十分なひとときだった。 |

| 石川県と岐阜県との県境に聳える白山は、霊峰として古来より白山信仰の中心的存在だ。 白山信仰の寺のひとつに那谷寺がある。 「なたでら」と読む。 十一面千手観音を本尊とし、巨岩がそそり立つ奇岩遊仙境の周囲に色づく紅葉で有名らしい。 時あたかも紅葉の季節。 那谷寺に行くことにした。 最寄駅は、北陸本線「小松駅」から西に一駅、「粟津駅」となっている。 在来線特急がひっきりなしに発着しているイメージから、金沢なら北陸本線各駅停車の数もそこそこあるだろうと思い11時過ぎに米原、大阪方面のホームに上がった。11時5分の福井行きが発車したばかりだった。次のローカルは11時30分発小松行きになっている。小松終点では粟津には届かない。その次の電車は、12時3分発の福井行きだ。なんと1時間に1本のダイヤ。 11時台の列車は、上記2本のほかに、特急しらさぎが2本、サンダーバードが2本。6本中4本が特急だ。次のサンダーバードは、隣駅、小松に停車する。のんびりローカル列車での旅は入線してきたサンダーバードに変更された。 小松駅はホームが3つの省エネ設計。上下線いずれであろうと特急通過待ちで退避する電車は臨機応変に真ん中のホームに停車する。ここでさきほど乗り逃した各駅停車福井行きが特急通過待ちで筆者を待っていた。 電車の扉がすべて閉まっている。乗客自ら車内外の開閉ボタンでドアを開け締めするタイプの電車である。地方には多い。 11時50分、粟津駅で降りた乗客は6名。駅前ロータリーにはタクシーが1台停まっていた。寺まではバスとのことだったが、バス停の時刻表を見ると那谷寺行きのバスは10時25分の次は12時35分、その次はなんと15時40分である。ためらいなくタク |
シーに切り替える。今日は初期の計画がことごとく修正されるな。 車で15分程度の距離らしいが、寺に近づくとドライバー氏がうめき声をあげた。 「ああ、駐車場待ちの大渋滞だわ」 目の前に車列が出来ていた。すかさず、自家用車の車列から離れ、迂回路を選び寺の門前にタクシーを停め得たのは地元の強みだ。迂回しながら「いつもはこんなもんだから」と1970円でメーターを止めてしまう易しいドライバー氏。なんだかんだ言って今日はついてるんじゃないか? 寺の拝観料を払いながら「粟津駅行きのバス亭はどこですか?」とおばちゃんに確認する。 「あら、バスで駅まで?ほとんどないわよ・・・ええっと、ああ12時58分があるわ。すぐにお寺を見て。そのあとこの道をまっすぐ行ったら信号のところにバス亭があるから」 「その次のバスは?」 「16時5分だから12時58分に乗るのよ!」 「はい!」 押し付けがましい親身のアドバイス。 境内に入る。入り口脇の金堂には、意外と大きな十一面千手観音が立っていた。参道を進むと、池の向こうに階段と小路を穿たれた巨岩がそそり立っている。奇岩遊仙境である。黄色や赤の紅葉が巨岩に照り映えてなかなかにいい絵である。巨岩やその奥にある本殿も、基本的に胎内めぐりの趣向をこらしているようだ。 三重の塔を眺め、楓月橋を渡ると、奇岩遊仙境を見下ろす眺望が美しい。 芭蕉は元禄2年にこの寺を訪れて、奥の細道に「石山の 石より白し 秋の風」と謳った。実は筆者が100円で売った歌だ。 バス停にむかう1本道には、寺の駐車場待ちの車列がまだ延々と続いている。その脇を歩きながらつぶやく。(やっぱ、けっこーついてたな) |

| 亡父が公務員だったので遺族である老母は公務員共済経営のKKRホテルを割安で利用できる。 年に何回か届くKKRホテルのカタログを抱えながら老母が「広島はどう?」とか「下呂もいいわね」と話しかけてくる。つまり「どっか連れてけー!」と言っているのだ。 昨年、骨頭壊死症による右大腿骨置換手術をした老母は、それはそれは熱心にリハビリを続け、杖を使いながら散歩に行けるまでに回復した。旅は、老母のフィジカルの現在(いま)の格好の観察機会である。 「松山がよさそうだな」「松山?どこ?」 「愛媛。松山の道後温泉」「道後温泉?」 「道後温泉本館から徒歩10分くらいのところにあるホテルだよ」 「夢のよーだわー。生きているうちに道後温泉に行けるなんて。一生の夢だったのよ」 そんな話は今まで一度も聞いたことないから聞き流す。ホテルの大浴場が広くて、良さそうだったので予約を入れた。 松山へは伊丹からエアで行く。 チェックイン前に観光客むけの郷土料理店に入る。様々な料理を少量づつ盛り合わせたベタなコースをオーダー。筆者はかつて畏友ⅰに学んだ。「観光地の話をするのに、誰も知らない穴場ばかりでは会話が成り立たない」というのである。ベタな観光スポットに行くことを恥ずかしがる筆者だが、ⅰに言わせるとまさにそのベタな所に行ったということで話が盛り上がるのだ、と。 お友達との旅話のために基本(ベタ)を押さえるのが親孝行というものだろう。 ホテルに荷を下ろし、一休みすると老母が「道後温泉本館(以後、道後温泉と表記)に入りたい」と言いだした。 エッチラ、オッチラ、道後温泉に向かった。 「俺はいつも上等だ」と坊ちゃんと同じことを言って3階席に入ろうとしたが、そのときになって気がついた。明治27年築の道後温泉にエスカレーターやエレベーターなどあろうはずもない。 |
「階段だぜ」「平気。登れるわ」 3階に向かった。 2階までは尻を押しながら登りきったが、3階への階段を見た瞬間、気が遠くなった。彦根城の天守閣かと思うような急峻な段幅の狭い階段が頭上に伸びている。階段と言うよりは梯子である。 それでも老母は3階を目指す。見上げた根性である。尻を押し、足を取り上げ、なんとか最上階の3階に登りきったが係りの言葉に耳を疑った。この部屋は風呂上りに涼むための部屋で湯船は2階と1階なのだと言う。風呂に入りにまた階段を下り、涼みに再び登ってこなければならない。それは無理だ。係りの言葉に甘えて、3階のチケットを2階の大部屋チケットに切り替えてもらう。 急峻な階段は登りよりも下りが怖い。現存天守閣では足がすくんで降りれなくなる子供や老人が多い。老母も「無理だわー」とおののいている。 後ろ向きに這い蹲りながら下山させる。筆者は下から後ろ向きに差し出す老母の足を掴んで階段に載せる。牛歩のように階段を下ろした。すでに3階にむかう通路は渋滞と化し、なんだなんだ何が起こっているんだ?と人垣の向こうから顔を覗かせる奴までいる。筆者の額を流れる汗は、疲労からだけのものではない。 なんとか降りきって、2階席の座布団と椅子を貰い、涼み場所を確保した後、老母は親切な係りに手を惹かれながら、浴室へ向かった。 浴室でも赤の他人に背中を流してもらい、同じ手術を受けて車椅子生活の親のよりも手術跡が大きいと驚かれ、85歳だと年齢を言っては元気だともてはやされ、先ほどの難行もなんのその、ご満悦で帰ってきた。おそらくこの後、係りや湯客同士の噂話にあがったには違いない存在感を道後温泉に残して宿に帰ったのであった。 夜半、起こされた。足が攣ったらしい。しかもこむら返りではなく脛の方だ。珍しい。後ろ向きに階段を下りたのが原因かもしれん。しばらくの間、マッサージをさせられた。 |
| 年々暑くなる日本の夏は今年も予想に違わず猛暑記録を残したが、彼岸も過ぎた9月末、すでに北海道では、記録的な速さで氷点下の朝を迎えていた。東京もすでに1週間前から真夏日が姿を消し、対抗するかのように真夏日を繰り返していた大阪の最高気温もついに30度を切った。急速に遠ざかってゆく夏の後姿。 夏好きの筆者にとって寂しい季節が訪れつつあった。去り行く夏への愛惜をこめて筆者は、宮古島へ向かった。 2度目の宮古島のその日の最高気温は31度。天気予報は雨を告げていたが真夏のようにピーカン!こーでなくっちゃ!ただし、吹き渡る風はそこはかとなく涼しく優しい。 4年前の初訪問時、観光タクシーで要所は回っているから、今回はあくせくする必要はない。 のんびりとリフレッシュ週末を愉しむのだ。 2009年の訪問時、2012年には完成予定だった伊良部島大橋はまだ建設中だった。予算やら台風やらで工期がずれこんでいるらしい。完成予定は2015年にまで伸びていた。テーゲーな感じがいかにも沖縄っぽい。 現在、無料で渡れる橋で最長を誇るのが沖縄本島の古宇利大橋(だと思って念のためチェックしたら新北九州空港連絡橋だった)だが、伊良部大橋が完成すれば、トップの座を奪うことになる。 八重山の主島石垣は、橋をかけられるほど周囲の離島と近くはない。宮古は、周囲に池間島、来間島、伊良部島(下地島と繋がっている)の3つの島がすぐ近くに浮かんでおり、架橋しやすい環境にある。すでに池間、来間にはそれぞれの島名を冠した大橋がエメラルドグリーンの海に美しい |
ループを描いて浮かんでいる。伊良部島にも橋がかかれば、ある意味、周囲の4つの島と主島を含めて宮古島ということになる。 平良港脇に建つホテルの正面には伊良部島が浮かんでいる。そして建設途中の伊良部大橋のシルエット。太陽はちょうどこの伊良部大橋の方角に沈む。美しいサンセットは眺める価値あり。 小さな島の繁華街は西里にある。ホテルから10分程度なので散歩感覚で向かう。 「でいりぐち」という居酒屋は人気店のようだ。初訪店。ママの元気がいい。予約を入れていたが接客のたびに筆者の名前を読んでくれる。それがなんとも心地よい。翌日、訪れることにしている「M」とは対極の接客である。ただし、筆者はこの「M」もけっこー気にいっている。今回も再訪の予定なのでそこのところは、ひとつ。 ついた翌日は、ダイビング。前回は八重干瀬 (やびじ)という巨大環礁帯での体験ダイビングだったが、今回は伊良部島の裏にある下地島の沿岸で潜った。体験ダイブは筆者ひとりだけ。同行のファンダイブ組は4名。ショップの常連さんのようだ。ダイビングショプの常連度って歯医者や床屋並なんじゃなかろうか。 下地島には民間パイロットの訓練専用空港となっている下地島空港があり、滑走路の進入灯が伸びるコバルトブルーの海の美しさは一見に値する。ただし、JALがその使用を中止し、ANAも一社での運用は負担が大きすぎるようで、近々その使用が中止されるかもしれないとのこと。 ボート上で何度も何度も旋回をしてタッチ&ゴーを繰り返す777とボンバルディアを見ながら今年最後の夏の1日を満喫した。 |

| 八重山の離島で上陸済みなのは、竹富島、小浜島、黒島、西表島、波照間島。 未訪の島は、由布島、鳩間島、新城島、嘉弥真島、与那国島だ。 まだまだけっこーあるもんだ。 ただし、定期航路があるのは与那国島と鳩間島だけ。他の3島は周囲の島からの日帰りツアーでないと上陸できない。 与那国島は船で4時間~4時間半もかかる。飛行機で約30分。思いつきで出かけるには若干ハードルが高い。 石垣島から高速船で40分~50分、西表島の沖合いに浮かぶ周囲3.9キロメートルの島、鳩間島に向った。 石垣港から鳩間島までは40キロ弱。 安栄観光、八重山観光フェリー、石垣島ドリーム観光の3社が船を出しているが、安栄と八重山観光フェリーは共同運航のようだ。石垣島ドリーム観光の略称はIDT。イメージキャラクターはドリカン君。離島ターミナルで観光客の輪の中にもまれるドリカン君を見た。 いつものように目が覚めるようなエメラルドグリーンの海を渡り、接岸した鳩間港ターミナルには、待合室以外には何もない。 何もないが目前に浮かぶ西表島に向って広がる瑠璃色の海の美しさは圧巻である。 集落は、港近辺に集中しており、島全体が自然のままの姿を保っている。 周囲3.9キロのほぼ楕円形の島は大きな高低差はなく、島外周を周回する道があり、徒歩で1時間程度で回れる。とりあえず周回を始める。 車の轍が残された道を歩き始めたが、周囲はもちろん、道も轍以外のすべてに草が生えており、獣道のような風情。これが島を代表する周回道だとしたら相当に雛だと覚悟を決めた。 行き交う人もなく、人の気配を察しても鳴り止むつもりのないクマゼミの合唱に包まれながら緑の道をぽ |
つねんと歩いていると、生い茂る樹木が陽光を遮る薄暗い道の先に黒い物体がわだかまっている。 (なんだ?!)ちょっとした緊張が走る。 牛だ! 牛がうずくまって道を塞いでいる! (すげえとこだな)と思いながら、鼻先をすり抜ける。 しばらく進むと今までの道よりははるかに道らしい道に遭遇した。いつものように主経路をとらずに脇道を進んでいたらしい。(それでもその主道も、舗装はされておらず、道路と呼ぶ気にはならない) それ以後は、折に触れ、海岸線に向う脇道があらわれその都度、瑠璃色の海を眺めることになった。海岸線の反対側、島の中央部は緑なす樹海である。 たまに小高い石積みの見晴台があらわれ、その上から周囲を見回すと、空の青、島の緑、海の瑠璃色、世界はその3色によって染めあげられている。 降り注ぐ強烈な日差しにとめどもなく噴き出す汗。もう若くはない筆者は、日焼け止めはたっぷり塗っている。さすがに慣れているので盲点はない。耳の先とか裏とか、サンダルを履く足の甲など隅々まで塗りたくっている。汗をかいても拭かないのである。 ちなみにSPF50の日焼け止め効果最強と思われる物件を選んでいるのだが、同じSPF50にも価格差があった。塗布後の持続力が違うそうな。世の中にはいろいろ学ぶべきことが多い。 不意に集落が現れ、知らないうちに島を一周していた。 集落を見下ろす、海抜25メートル程度の高台に灯台と物見台がある。 巨大な蜘蛛の巨大な蜘蛛の巣にびびりながら、物見台に上る。360度を見渡せるが、美しい瑠璃色の海はそれほど眺望に収まらない。 かなりのんびり過ごしたつもりだが、所要時間は1時間半程度か、都合よく入港してきた予定よりも1時間ほど早い船便に乗って、主島石垣に戻った。 |

| 大阪府北部の千里丘陵から見下ろす大阪市街のむこうに生駒山はある。 冬季の早暁、淀川端から東を見れば、太陽はこの山の背後から顔を出す。各種電波塔が山頂部にあり、特徴的なシルエットだ。 大阪と奈良の県境にあるこの生駒山の標高は642m。運動不足で鈍った身体に喝を入れるにはちょうどいい高さだ。 ちゅうことで、生駒山に向かった。 「なんば」から近鉄急行で20分。「生駒駅」に到着。小さなロータリー、ぱっとしない商業モール、駅前の幹線道路沿いに短い商店街。ありふれた都市近郊の駅前の風景がそこにあった。 生駒山周辺には幾つかのハイキングコースがあり、「生駒駅」を起点とする「生駒山上コース」もそのひとつなのだが、駅前にその類のガイドやサインは見当たらない。 一応、手元に簡便な地図を携えてはいたので、たぶん、こっちだろうとあたりをつけつつ歩き始めた。地図が簡便すぎて、やや難儀だったが何とか正道を選べたようだ。最初から登り道で、途中から石段となり、これが延々と山上まで続く。 道の周囲は民家が立ち並んでいる。住人は皆、健脚の持ち主に違いない。 やがて、山の中腹なのに商店街が現れ、料理旅館の看板が多くなった。この先に商売繁盛の願掛け寺があることは、このあとに知ることになるが、その法事客がこれらの旅館で食事をするのだろう。 やがて商売繁盛の寺、宝山寺に到着。 山襞に張り付くように堂を立て、仏を配している寺域は思いのほか広い。山岳密教系か?と錯覚した。帰路に立ち寄ってゆっくり参拝しようと心 |
覚えをし、再び登山道に戻る。 「生駒駅」のそばに起点を置く生駒山ケーブルの二つ目の駅「梅屋敷」で登山道がケーブルと接線を持つ。地図によるとちょうど全行程の三分の二程度まで来たようだが、このあとの登りがかなりハードだった。たまに城山登りをするので、この生駒山、嘗めてかかったせいだろうか、けっこうキッツイ。いつにもましてハヒハヒになった。 ヘタリこみそうになりながらも、山頂からの眺望を唯一のよすがに歩を進める。 やがて、山頂に出た。 出たがそこは、生駒山上遊園地「スカイランドいこま」の真っただ中。GWのこととて周囲は子供連れのファミリーの大群。あちこちでアトラクションの乗り物がぐるぐる回っている。 これは・・・カタルシス、ゼロだもんね。 山頂からの眺めが山登りの最大のご褒美だとしたら、それを召し上げられてしまったような肩すかし感。どこかに、見晴らし台がないかと、プレイランド内をさまよったが大阪市街地方面のビューポイントにはレストランが置かれ、飲食をしないと景観を愉しめないように設計されている。なんというセコさ。タワー系のアトラクションに乗るのはレストランに入るよりも嫌である。意地になって山頂からの眺望を求め歩いていると、一段低いところに寺の屋根が見えた。 龍光寺の境内に足を踏み入れた。 寺裏にベンチが置かれ、そこから大阪平野を見下ろすことができる。黄砂のせいかかPM2.5のせいか、はたまた春の霞か。大阪市街はもやもやしていた。まあ、それでも何とか山登りを完遂した達成感は得られたから良しとしよう。 |

| 5月6日の月曜日はハッピーマンデーだった。 新緑がひときわ眩しいこの季節だが、筆者は今年はまだ新緑にまみれていない。かくはならじ、と坂本に向かった。 JR湖西線の「比叡山坂本」駅で降り、駅前から山へ向かう坂を上る。 里坊と穴太積の町、坂本がそこにある。 比叡山の僧侶の隠居所を里坊と呼ぶ。坂本はその里坊の集落である。隠居所の集落だから、本山に近い処を選んだのだろう。町は、叡山の麓にある。 琵琶湖岸を走る西近江路(国道161号線)から分岐した県道316号線が町を貫き山に向かう一本道になっている。その両側に穴太積の石垣に囲まれた里坊の閑静な佇まいが連なる。 織田信長の軍団が引き連れた工兵部隊(石垣部門)が「穴太衆」。彼らが積み上げた石垣が穴太積と呼ばれている 県道と里坊の間の緩衝帯に今を盛りと陽光を照り返し茂っているのが楓の木々である。頭上を覆う楓の梢の隙間から木漏れ日が地面に光の雫を斑に落とし、それが風に揺れて踊っている。 「翠蓋(すいがい)を碧空に翳(かざ)すあり」 その昔、筆者が徳冨蘆花に100円で売った歌である。 滋賀県大津市に属する坂本の町は、時間の流れが至極たおやかだ。 県道は、山の麓にある日吉大社への参道の一部ともなっている。大社の入り口には、旅館風の佇まいの料理屋があるが、店前ののぼりに「ゆどうふ」などと染め抜きがあり、意外と気易くのれんをくぐれそうだ。なにせ坂本の広くも、長くもない商店街(と、言うよ |
りは商店街はない)は県道に面した「日吉蕎麦」とその奥にある「本家鶴喜そば」ぐらいしか料理店がないのだ。ちなみに「鶴喜そば」の広告コピーは、「蕎麦は一番、電話は2番、店は角から3軒目」である。電話は2番と言う番号は「0775780002」 どーでもいいことか。 土産物屋の甘味を腹に収めるわけにもいかないので、この「ゆどうふ」という選択はかなり気にいった。 「芙蓉園本館」というこの料亭は、国指定の名勝庭園などもあるのだそうだが、テーブル席と広めの小上がりがあり、観光地の田舎蕎麦屋のような雰囲気で肩ひじ張らずにいられるのがいい。 「豆腐は煮えばなが一番。決して煮詰めちゃ駄目、駄目」なんて独り言をつぶやきつつ、生ビールで喉を潤し、湯豆腐を口にする。なんかかなりいいんじゃないか? 帰路は、JRよりも山の手にある、京阪石山坂本線を使う。「坂本」駅はこの路線の終着駅である。穴太衆の発祥地なのか「穴太」という駅も途中にある。浜大津で京津線に乗り換えれば、山科から国道1号線と並走しながら京都市内に入れる。「東山」で降りて、東大路をちょいと下れば祇園である。夜は祇園で酒食をとれば、完璧なハッピーマンデー。 と、ここまで書き進めて、2008年にUPした「坂本行」を見てひったまげた。記事のほとんどがかぶってる。筆者が成長せんのか、坂本がそーゆーところなのか。ま、いいっか。けっこー気に行ってるのよここ。 |

| 桜も終わった4月の一日、博多から「芥屋」にむかった。 博多は、市内に観光資源の乏しい街だが、市営地下鉄空港線に乗れば風光明媚な海岸風景を愉しむことができるのである。そこが今回の目的地「芥屋」である。 地下鉄としての営業区間は福岡空港、姪浜間の13キロ強だが、この地下鉄、終点「姪浜」で地上に出、そのあと筑肥線内を走ることになる。この段階で車窓が観光モードに切り替わる。眼前に広がる海原は博多湾である。しかも安売り感すら漂うほど出し惜しみのないワイドビュー。ロングシートで走っているのがもったいない。ボックスシートにしてくれないかな。 「筑前前原」で下車。博多湾と玄界灘を東西に分断する糸島半島の付け根にある。 駅前から昭和バスに乗り終点「芥屋」まで。今日の目的地「芥屋の大門」に向かうつもりだったが、バスの時刻表を見て諦めた。10時台には1本もない。11時12分が次の便で1時間以上待たねばならない。「芥屋の大門」までは、車で約20分ということだったので、タクシーをつかまえる。駅前にタクシー乗り場があるから雑作もない。 「芥屋」には「芥屋ゴルフ倶楽部」という名門GCがあり、ここの名物料理「鯛茶漬け」に使用する「芥屋のタレ」を筆者はコヨナク愛している。 そろそろ読者の皆さまには、さっきから「芥屋」「芥屋」と書いているけど、まさか、このままルビもふらずに終わらせるつもりじゃねーだろーな、と、お思いになられているのではないかとお察しします。 「芥屋」と書いて「けや」と読みます。 「芥屋の大門」は「けやのおおと」です。 さて、芥屋の大門へは遊覧船が出ている。 その発着場そばまでタクシーで乗りつけたが、周囲 |
には料理旅館しかない。雛である。帰りの足が非常に心配になるほどの雛。下りるときに営業所の名刺をもらった。 女の子が店番をしている乗船券売り場でチケットを購入。 「おひとりの場合は1000円になりますけど・・」乗客が2人以上だったら700円になるらしい。「次の11時発の便は、まだお客さんひとりだけなもんですから・・・」 快く1000円を渡し、まだ20分程度はある時間を利用して芥屋の大門を海岸伝いに眺めに行った。時間までに戻れば、なんだかんだと10人ほどの客があって、筆者の財布にめでたく300円が返還された。 出港。突堤を抜ければさすがは玄界灘。4月~11月は海が穏やかだと言うが、なかなかに揺れる。チケットを買うときに女の子が「かなり揺れますが船はお強いですか?」と聞いてきたことを思い出した。 10分もすれば日本三大玄武洞のひとつ「芥屋の大門」にたどり着く。海の青さがあざやかだ。 海蝕によってできた洞窟の高さは64m、幅は10m、奥行き90m。打ち寄せる波が激しく岩肌を噛んでいる。 潮目を見ていた船が俄然、洞窟に向かう。かなり勇気のある船長だ。右に左に揺れる船を巧みに操船し、洞窟内に入ってしまった。 見上げれば、玄武岩の柱状摂理が六角形や八角形の断片を見せている。かなり迫力がある。船着き場に戻ったのは離岸して25分後。 帰路は往路で見捨てた11時12分発の芥屋行きバスが11時45分頃到着。12時すぎの発車に間に合った。船着き場からバス亭までは5分ほど歩かねばならないが、遊覧船乗り場で渡されたチラシに、バス亭までの地図があったので助かった。 |


| 観光地を「正統派」と「成り上がり」に分けると「飛騨高山」は明らかに「正統派」だ。 「正統派」の象徴はコンボイのような観光バスの大群とそれに運ばれてきた1個師団の爺婆の大群である。この爺婆は、NHKの報道を微塵の疑いもなく世論として受けとめる年齢層の集団でもある。「鶴瓶の家族に乾杯」のファンでもある。筆者のような漂泊の旅人にとっては鬼門筋と言える存在だ。思わず「天橋立」を思い出した。 じゃあ、成り上がりの観光地はどこか?って言われても、これがなかなか思いつかない。 書き出しの掴みにいいフレーズだと思って筆をすべらせたが、まずいな、何か書きたい方向からどんどん離れていきそうな気配が濃厚だ。 思いつきで文章を書き進めるのはやめよう。 「ディスニーランド」や「ユニバーサルスタジオ」を観光地と言ってよければ、これは明らかに成り上がりだろう。「ラスベガス」なんかも。と、とりあえずまとめたところで「飛騨高山」。 どこにあるんだ? いや、だいたいの位置は分かるが、ここが「飛騨高山」だ、というピンポイントの場所が分からない。調べてみてもJRに「高山」駅はあるが「飛騨高山」駅はない。 いい歳をして「飛騨高山」を知らない自分に気づかされた。どうやら「高山」の別称が「飛騨高山」らしい。「高山」=「飛騨高山」。う~ん、最初から一本とられている。 足繁く通うファンも多いと思う高山だが、お近づきになる機会がないままに半世紀も過ぎてしまうとこんな死角が生まれるという事例として。 「古い町並み」という漠然とした認識以外には「飛騨牛」というキーワードだけが頼り。 JR高山駅を降り「飛騨国分寺」に立ち寄り、三重塔と大イチョウを観賞してランチ開始までの時間調整を図った。あくまでも主目的は飛騨牛である。「ワンポンド」というステーキハウスに1 |
1時半の開店と同時に入店。躊躇うことなくA5ランクの飛騨牛フィレ200gをオーダー。 時は今、東京の桜が観測史上タイ記録の最速スピードで満開を迎えている。「こっち(高山)の桜はどうです?」「まだまだですね。4月中頃じゃないですか」 そりゃそーだ。日陰には残雪が残っている。 主目的を果たし、副次的目的である街歩きを開始。店のほど近く、市内を貫く川の対岸に大きな鳥居が見えた。とりあえずそこに向かう。 参道の先に「桜山八幡宮」があった。しかもその脇に「高山祭屋台会館」。陳列された4台の屋台でシーズンオフでもお祭りを消費した気に。出口には「桜山日光館」もある。 (日光館?) 照明を落とした館内に、金色の輝きを放つ日光東照宮全域の模型があった。 (なぜ?高山で日光東照宮?) 左甚五郎つながりで設営されたらしい。甚五郎は飛騨の人という説があるのだ。 周辺の町並みを眺めるが、写真に収めて見栄えのする角度はそう多くない。こんなもんかな、と思っていたらこれが大間違い。高山を代表する町並みは「上三之町(かみさんのまち)」で、そこに至って筆者は、どこからこれだけの人が?と思うほどの観光客に揉まれることになる。 飛騨高山名物の地酒、みたらし団子、きな粉菓子、蕎麦、高山ラーメン、せんべい、朴葉味噌料理などを消費する人々。飲兵衛は顔を赤くしながら徘徊している。 高山陣屋は、旧高山城主金森氏の屋敷を藩政時代に代官所、郡代所としたその遺構である。これが思いのほか広い。位置の見当識を失うほどに広い。と、ここいらで撤収したが、飛騨高山はエリアを網羅して楽しむ所だろう。五箇山、白川郷、温泉郷、郡上八幡、乗鞍、新穂高ロープウェイ、周囲にはかなりの観光資源が点在している。 |

| 那覇空港から首里城までを結ぶ「ゆいレール」 以外に沖縄には鉄道はない。 公共交通機関はバスである。 沖縄のバスには、市内線と市外線がある。 市内線は言うまでもなく那覇市内の循環バスだ(循環してるかどうかは詳しく調べていないが) 那覇市から離脱するには市外線を使わねばならない。 行き先別に系統化された市外線は、かなりの数になるがそれらはすべて那覇バスセンターに集線している。那覇バスセンターはゆいレールの旭橋駅にある。 知念方面38番「志喜屋」行のバスを待った。 東海岸にむけて沖縄本島南部の東西を横断する路線だ。「知念」方面へのバスである。 バスに揺られること50分。筆者が降車したのは「安座真(あざま)サンサンビーチ入口」。ここからフェリーと高速船が1日に6便程、沖合5 キロに浮かぶ島に向かっている。 島の名は「久高島(くだかじま)」。 知念半島の斎場御嶽(せーふぁうたき)と並び沖縄では最も神聖な領域とされている。創世神話の地である。ニライカナイから流れ着いた沖縄の祖神アマミキヨが降臨した島だ。 12年に一度、午年(ウマトシ)に開かれる秘祭「イザイホー」の島であることは星野宣之氏の伝奇漫画「ヤマタイカ」に詳しい。イザイホーは1978年以降は霊力をうける祝女(ノロ)がおらず、祭りは中断されている。 高速船で島まで15分。 島の住民は200名程度。集落は、港と漁港のある島西部に集中し、島の東に人の手は及ばず自 |
然のままの姿が残されている。 鳥の鳴き声がのどかに響く。 平坦な島なのでレンタサイクルにギヤはない。 細長い島の中央を1本の道がまっすぐ島東端のカベール岬にむかっている。カベール岬は、アマミキヨが上陸したとされている霊地である。 道を取り囲む亜熱帯の樹木は岬に近づくにつれて徐々に背が低くなる。 岬にむかう一本道は、まさに沖縄の原風景のようである。 岬に立ち海を眺める。 時の流れがたおやかになってゆく。本島上空にかかる雲量は多かったが、この離島の空に雲は少ない。思いのほか早く雲を流し去る風は二月風廻り(ニンガチカジマーイ)の名残りか。 流れる雲の合間から太陽が顔を出し、3月初旬にしては力強い陽光を降り注ぐ。その陽を背に海を眺めるとみるみるうちに海面の色が変わってゆく。これ、これ、このコバルトブルーの海を見な ければ沖縄に来た甲斐がない。 島北岸にも美しい浜が連なり、ロマンスロードなどという気恥ずかしい名称も、その光景を見れば許容してしまうほどには心が洗われる。遠くに本島東海岸が見える。 「男子禁制」の沖縄七獄中最高位の霊地である「クボウウタキ」には「立ち入り禁止」の結界がはられている。この島の秘祭、一度でいいから立ち会ってみたいものだ。とぼんやり思った。 2時間ほど島をまわり、那覇に戻る。翌日、鏡を見て気がついた。 (日焼けしてる!3月初旬なのに!) 沖縄の紫外線、侮るべからず。 |

| 札幌から道南西部の洞爺湖に向かった。道内有数の観光地であり、温泉街でもある。 宿の送迎バスは札幌駅南口のバスターミナルから出る。指定された待合室では、黄色いスタッフジャンパーのおばちゃんたちがごったがえす観光客をさばいている。 「××号の人はこちらに並んでください!」 バスの行き先はそれぞれに異なるようだ。 はて、待ち合わせの場所こそ駅の反対側で違えど、去年、層雲峡に行ったときも似たような黄色いジャンパーを見たような・・・思い出した!野口観光である。道内温泉観光業者の大手なのかもしれない。きっと道内の温泉に行こうとすれば野口観光は避けては通れない存在なのだ。知らないけど。 今年も年明け1月に北海道にやってきた筆者。 降りしきる雪。一面の雪景色。そして静寂。 圧倒的な自然の前に人為などなすすべもない絶望的な心もとなさ。そんなこんなを年に一度は体感したくて冬の北海道に足を運んでしまうのだ。そして幾ばくかの時を過ごし、雪を知らない街に帰る。嗚呼、なんかいいなあ。それは、エメラルドグリーンの海と強烈な日差し、どこまでも青い空とそこに浮かぶ高く白い雲、それらに染まるために沖縄に行くのとはちょっと違う心理作用なのである。 洞爺湖へは2時間半の行程だ。国道230号線の最高地点は中山峠。吹雪に視界を阻まれ、峠の駅からは何も見えなかったがここに至るまでの中央分離帯の雪はまるで障壁のようである。 やがて、バスは洞爺湖畔に到着。 宿に荷を下し、温泉街を散策する。街は層雲峡 |
よりは広い。遠くの山上に輝く灯りはウィンザーホテルだろうか。 日没間近い氷点下の温泉街を歩き回る酔狂な奴はいない。人影はなかった。これだけは間断なく通り過ぎる車のヘッドライトを逃れて裏通りに入る。カルデラ湖の周囲は当然、山並みに囲まれている。湖畔に至る道はすべて斜面であり、スリップ事故対策か、坂道の途中にある交差点では、坂上側の道路はきれいに除雪されている。 湖畔の道を歩き、身も心も冷えきったあとに温泉に浸かり、四肢を伸ばす。これがたまらない愉悦である。もう、こうとなっては温泉嫌いとは言えまいな。確かに温泉宿は苦手である。主に食事が原因なんだが、それを「主義」と言うには頑なさを欠き、「嗜好」と言うには筋を通しすぎてきた。そろそろ温泉嫌いの看板を下ろしてもいい頃合だろう。眺望の良い大浴場や露天風呂に惹かれる我が身はもはや留めようもない。 露天風呂が良かった。夕も夜も深夜も早暁も浸かったが、きわめつけは日が昇ってからだ。 雲か霧か、はたまた雪か、湖の対岸までがわずかに見渡せる程度だった視程が、急に開けはじめた。すると目前に全山雪に覆われた真っ白な羊蹄山が浮かび上がってきたのである。 それまでの光景がこの宿のベストビューだと思っていた筆者は、この変化を喜び満喫した。 爾後、帰路の道中、羊蹄山は終始車窓の友となった。往路ではまったく気がつかなかったのは天候のせいだろう。嵐の止んだ中山峠でこの美しい山に最後の一瞥を投げ、今回の漂泊は終焉を迎えた。 |

| 伝播者(スポークスマン)が後世に書を残すことによって人は歴史に名を刻み、多くの人に存在を知られることになる。 土地も似たようなもので、雛と思えるような小ぶりな町であっても、名産品や景観などユニークなものがあれば、地名は人口に膾炙する。 網走だって富良野だって町は小さい。湯布院は人口1万程度だ。それでもこれらの地は高名だ。 一方、ローカルではそれなりに知られていても全国区になれない町もある。 「洲本」なんか、典型例じゃないかと思う。 関東圏ではおそらく聞き慣れない名のはずだ。 秋も深まりゆく好天の一日、筆者は洲本にむかった。洲本は、淡路島最大の温泉地だ。 神戸三宮発洲本行き(あるいは方面行き)の高速バスは最低でも1時間に1便は出ている。所要時間は1時間半程度。舞子から明石海峡大橋を渡り、淡路島の半分強を縦断する。 洲本高速バスセンターで下車。 目前は波止場。のどかな漁師町の風情が漂っている。夏には海水浴場として人が溢れかえるであろう大浜公園も、その喧騒は今はない。うららかな秋の日差しをあびて黒松が照り輝いている。 浜の背後に、小高い一峰があり、頂上に白い天守閣が浮かんでいる。 洲本城である。 標高133mの三熊山(高熊山、乙熊山、虎熊山の総称)山頂に築かれた城は、豊臣政権下、すでに天下統一の趨勢も見極められた頃、賤ヶ岳の七本槍の1人、貂の皮の槍鞘で知られる脇坂安治により本格的な天守、石垣が造営された。 |
瀬戸内を扼す、西日本最大級の海軍基地にしようとの構想だったらしい。 天守閣は、いかにも昭和なコンクリートの再建品で展望台仕様。時代考証に意を払う設計ではないようだ。眺めはなかなかにいい。 意外に急峻な坂を登り詰めると、天守閣前に茶屋があった。老婆がひとり、茶屋の前に出て客引きをしている。多くもない観光客が散発的に通り過ぎるが、引き止める老婆に応じる者はいない。 (茶ぐらい飲んでいってやればいいじゃないか) 歳の頃、我が老母ほどの老婆に感情移入して、優しい気分になった筆者はすれなく通り過ぎる観光客に厳しい視線を向ける。肉親でなければ、筆者も優しい男になれるのである。 「コーヒーあります?」 「はい、はい」嬉しそうに応じる笑顔は、もしかしたらこの日最初の客かもしれないことを伺わせた。屋内の簡易テーブルに腰かけ、老婆の昔話に耳をかたむける。肉親でなければ、筆者もいい聞き手になれるのである。 城を後に、城下町を散策する。思いのほか長い閑寂なアーケード商店街を抜けると町の防衛ラインであろう川に出た。川端には寺町もある。ちゃんと城下町の造りなのだ。 神社にコミカルな狸の石像があった。芝居好きの「柴右衛門狸」とある。なんとも長閑な淡路の港町に似つかわしい風情で、日常の喧騒をしばし忘れさせてくれた。 海を眺めつつ大浴場に浸かり、淡路の魚をつつき、淡路牛とタマネギなど淡路の野菜を焼き、淡路ビールを飲む。至福の一時とはこのことだな。 |

| 家族揃って初詣に行く人って、何かこう、揺ぎ無い人生観、確立された生活習慣なんてものを持っていそうな感じがする。 筆者にそういうものはない。 それでも、年が明ければ寺社仏閣に立ち寄ることもある。初詣というよりは、アトラクションに近い。そこに宗教的な匂いはない。 去年は元旦からチャリを転がし、人っ子一人いない茨木の神社を訪れたりしたが、今年は、何か活動的になれないままに三が日も過ぎ、4日の仕事始めを終えたところで、なんとすぐに土曜日を迎えた。 三が日のどんちゃん騒ぎの後片付けがたいした手間もかからずに終わり、昼前にはかなり落ち着いた気持ちを得たので、思い立って京都へ向かった。地元、大阪で初詣をしてもよかったが、そこはそれ、揺ぎ無い人生観、確立された生活習慣がないので、アトラクション的に愉しい方向に気持ちが寄った。だったら、京都でしょう。(初詣のあとでバーで一杯なんて乙じゃないか) 新大阪25番線に入線した岡山始発の「ひかり」自由席の3人掛けの真ん中に座り、京都に向かう。車内に立ちんぼの姿はない。 京都の初詣4大スポットは、「伏見稲荷大社」が第一位で、次いで「八坂神社」「下鴨神社」「北野天満宮」と続く。今日は伏見稲荷を選択。 伏見稲荷大社には、参道すぐの楼門、外拝殿、本堂、の奥に千本鳥居がならぶ稲荷山が控えている。山頂は233m、3つの峰を擁し、それらを赤い願掛けの鳥居がぐるりと囲んでいる。 かつて、この千本鳥居の一周を試みたが、日没サスペンデッドで断念した過去がある。今日はリベンジを果たす。 大晦日、元旦は知らず、5日の午後イチともなれば、人混も少しは解消されていると思う。本堂の鐘の前は順番待ちの行列が出来ているが、筆者は賽銭もおみくじもしないので関係ない。ただただ、千本鳥居一周のみが望みである。 |
赤い鳥居が立ち並ぶ回廊の景色は幽玄である。しかし鳥居奉納とは願掛けであり、赤い鳥居は言ってしまえば人々の欲望の象徴である。1本1本にそれぞれ人の欲望が宿っていると思えば、裏寒い光景でもあり、あるいはそのことへ愛おしさを感じる人もいるかもしれない。鳥居の表は赤く塗られているだけだが、裏面に奉納日と奉納者の氏名などが書かれている。 四つ辻と呼ばれる鳥居の周回の基点までは、多少の渋滞があるも、それでもストレスを感じるほどのノロノロ行進にはならない。四つ辻から、いよいよ峰を巡り、鳥居の周回が始まるのだが、多くの参拝客はここで帰ってしまう。眺めはいい。 伏見区の市街地を見下ろしていると、偶然、飛行船が樹木の隙間から現れた。 「御膳谷奉拝所」あたりが半周の位置付けだろうか。鳥居の数もまばらになる。鳥居の奉納はまだまだ余地があるということだが、奉納すれば、やはり自分の鳥居を見に行きたくなるだろう。このあたりに鳥居を立てられると、かなりの運動量になるな。 やがて山頂に行き着いた。山頂にも社があり、参拝のための小さな行列ができていた。おそらくこの時期だけの行列だろう。 下山すれば、足が笑っている。 往路はJR奈良線の「稲荷」駅から来たが、復路は京阪電車の「伏見稲荷」駅を使う。 「祇園四条」で降りてバーに寄るのだ。バー・ベスパは土日祝日は、午後1時から開店している。3時過ぎに入店し新年の挨拶を交わす。カクテルを数杯空けているうちに小腹がすいてきた。駄目もとで近くにある「祇園おかだ」に電話を入れると、幸いなことに今日から営業とのこと。これ幸いと正月5日から和食を愉しむ。食後、バー・インディゴの扉をあける。カクテルのあとグレンリベットのボトラーもので30年の「ARTIST」をショットで。 近来、稀に見るいい正月の一日となった。 |

| 「彦右衛門」 「は」 「儂は会津へ行く」 「殿、この彦右衛門も是非、御供を」 「・・・・儂が会津に行けば三成が旗を上げるであろう。三成は大阪で西国大名をかき集め、この伏見の城を攻めてくるであろう。・・・その数・・・十万、いやもっと多いかもしれん」 「・・・」 「すまん・・・兵は何人いる?そちが所望するだけ置いていこう」 「兵はこれから殿が天下を取る戦の時にいくらでもいりましょう。ここはどうせ落ちる城、捨て駒は少ないに越したことはございません」 「捨て駒などと思うておるか」 「水くさい『彦、死ね』これですむことでござる 。殿、この鳥居彦右衛門には遠慮のう言うてくだされ。捨て駒と言うてもこの捨て駒、彦右衛門でのうては務まりませぬ。三河武士がいかに奮戦玉砕するかを天下に示すのが役目でござりましょうが。言うてくだされ、死ねと、さ、彦、死ねとおっしゃりませ」 家康、彦右衛門の視線から眼をそらす。 「彦ぉ・・・酒を飲もう」 家康に注ごうとする彦右衛門を制し、「いや、わしが注ぐ」 鳥居彦右衛門、歳は家康より3つ上、今川の人質時代から片時も家康のそばから離れたことはなかった 「おまえには本当に世話になった・・・おまえのからだで儂の足を温めてもろうたこともある」 「殿は長い苦労をなされました」 「最後まで世話になる」 |
「なんの、もうお役にはたてまえと思っておったのに死に花を咲かせて、いや、武士としてもう一度夢を見ることができます。殿、彦右衛門、嬉しゅうございます」彦右衛門、干した杯を刀のこじりに打ち付けて割る。 「明朝はお早いお立ち、これにて」 足を引きずり立ち上がり、退出しようとする彦右衛門の足をさする家康。 「彦ぉ、足は痛まぬか、足は・・・」 「なんの・・・なんの」 (あの足は三方ケ原の戦の時だった)家康の回想 退出した彦右衛門の背中にむかい、「すまん・・・」嗚咽を漏らす家康。顔を手で覆い、泣く。 「彦ぉ・・・すまん」 昭和60年TBSの6時間ドラマ「関ヶ原」のワンシーンである。徳川家康は、森重久弥。鳥居彦右衛門元忠は、芦田伸介。両名とも故人。筆者にとっては名にし負う名シーンのひとつである。 舞台は伏見城。 新幹線A席から東山の峰を眺めて、はるか東の峰に城郭のシルエットを認めた方もいらっしゃるのではあるまいか。あれが伏見城である。 ただし、近鉄「丹波橋」駅から徒歩15分程度のところにあるこの伏見桃山城は、キャッスルランドというテーマパークの客寄せパンダとして造営されたコンクリートの城である。そもそも、伏見城の縄張りも、どのような城郭だったのかも正規の資料は残っていない。つまり、想像の産物なのである。キャッスルランドが経営難で閉園し、城は京都市の管理のもと残され、今でも無料で外観を見られはするが、耐震構造上の問題から城内に入ることはできない。それでも、やはり見に行 かずにはおられぬのである。 |

| 故あって大阪に10年住み暮らしている。 関西では「神戸に住んで、大阪で働いて、京都で遊ぶ」のが一番だと言うが(誰が言ったのかわからんけど)筆者は「大阪に住んで、働いて、神戸と京都で遊ぶ」のが一番だと思っている。大阪は東は京都、西は神戸の真ん中にある。どちらに行っても20分~30分なのだから。 今日は、神戸に向かうことにした。 「新大阪」まで最寄駅から3駅。言わずと知れた新幹線のために出来た駅だ。新幹線は結局、大阪駅まで行かなかった。淀川を越えるための橋の建設費が足りなかったのかもしれない。「惜しいなあ、もうちょとなのに。でも予算が・・」って感じ?橋代がね、足りなかったんじゃないかなあ。 お盆のこととて、新幹線は、西行きが指定もグリーンも満席状態。在来線乗り場に向かう。「三ノ宮」までは20分程度。ちなみに、一般に神戸と称されるエリアの中心は「三ノ宮」である。「神戸」駅もあるが繁華街からは外れている。さらに余談を進めると、「三ノ宮」はJRの駅名で、阪急、阪神、市営地下鉄などは「三宮」駅となっており、「ノ」の字がないのである。どーです、関東の皆さん、面倒くさいでしょう?JRは国鉄時代から地場勢力と戦っているのかもしれない。 「大阪」駅はJRのみ。私鉄、地下鉄は皆「梅田」駅なのだ。 「三ノ宮」で降り、各駅停車で「元町」へ。 駅を出て、港まで徒歩で南下する。 港町神戸は横浜といろいろ対比できるところが面白い。メリケンパークには山下公園。その横ポートタワーにはマリンタワー。その先、中突堤には山下埠頭。なんとシンメトリーな。 |
商業モールモザイク1階に「明治屋神戸中央亭」があり、ここのタンシチューが好きなのだが、今日は、来る途中「六段」という炭火焼の店でヘレステーキを食べた。この店のステーキは旨い。 中突堤には3~4隻の神戸港クルーズ船が入れ換わり立ち替わり入港してくる。その1隻に乗ることにした。今夏(ちゅうか今年)筆者はどっこにも行っていないのである。夏の想ひ出に、せめて海に出ようとの涙ぐましい思いつきであった。 1200円を支払い、クルーズ船「ファンタジー」に乗船。 夏の日差しを嫌ってか、乗客は皆客室に入ってしまう。露天のデッキには筆者ひとりきり。 汽笛を鳴らして出港した船は、ハーバーランドを横目に沖合に向かう。神戸港の水は綺麗じゃない。沖縄の海とは違う。でも、いいのである。この夏唯一の海の想ひ出を自ら貶める必要はない。 防波堤の手前にはドックが並ぶ。そのひとつ、三菱重工神戸造船所に海自の潜水艦が2隻横付けされていた。1隻は艦番号が確認できた。505だ。SS505は「ずいりゅう」。2900トン「そうりゅう」型潜水艦の5番艦として2013年3月に就役の予定ということをチェック。 あ~もー満ち足りてしまった。OK牧場。今日1日は満点。軍艦を見れば男の子は満足なのだ。 その後、神戸空港の脇を通り、空港へ渡る連絡橋をくぐる。空港への離着陸便を間近に眺め、やがて船はUターンして再び連絡橋をくぐり抜け、ポートアイランドに沿いながら、出港した桟橋に到着。45分間のクルーズ終了。 帰路、大丸前の森谷商店でミンチカツを購入。 |


| 大阪湾は、神戸から和歌山にかけての本土湾岸と淡路島東岸、双方の湾曲部に囲まれ、大きなタマゴ型の内海を形成している。 タマゴの南端部を、本州を南北に分断する中央構造線が走り、紀伊半島から淡路島の南端部に渡り、鳴門海峡から徳島方面に抜ける。和歌山市よりやや北西方向の構造線上に「加太」はある。 「かだ」と読む。普通は読めん。筆者は「かぶと」と言って失笑を買った。 難波から南海特急「サザン」で50分強。終点「和歌山市駅」から盲腸線の「加太線」で30分弱で「加太」に到着。 駅前には何もない。 駅から海までは徒歩20分程度。その加太湾正面に、4つの島が浮かんでいる。 沖ノ島、地の島、虎島、神島の4島は、これらを総称して「友ヶ島」と呼ぶ。明治の世から太平洋戦争の終焉まで、大阪湾を扼する軍事要塞だった。軍艦の主砲がよく戦の雌雄を決する時代にあってこその要塞だったが、時代は変遷する。航空機が地上、あるいは海上作戦の強力な支援機動力として存在感を発揮するようになってからは、近接戦闘を想定した要塞の存在価値は失われてしまった。友ヶ島は、一度も戦闘に加わることなく終戦をむかえ、武装解除されたあと、要塞跡地として残された。 今日は、要塞跡地ハイキングである。 加太湾から友ヶ島加太航路で渡船が出ている。所用時間は20分。 島北側の野奈浦桟橋に接舷すると、目前には友ヶ島案内センターがある。桟橋から海岸沿いに南下すれば、第2砲台跡が現れる。この島には全部 |
で6箇所の砲台跡があり、天蓋の中に設置された要塞砲が島の四周を死角なく睨んでいたことを伺わせる。砲台そばの弾薬庫は薄暗い。 第2砲台の先に日本標準時135度(東経)の、子午線が通る日本最南端の地であることを記す「子午線広場」がある。その広場の上に友ヶ島灯台が白く輝き、今でも稼動している。 灯台のそばには第1砲台跡。って、灯台を目標にされたらそれだけで弾着が集中しそうだが。 湾内への潜水艦の進入を探知するための旧海軍聴音所跡まで来たら、島の峠を越えて尾根づたいにトレッキングする。島の最高地点標高119mの三角点にタカノス山展望台があり、ここからの眺めが美しい。紀淡海峡を見晴るかし、西に四国、東に和歌山の連峰、北には神戸の六甲山系が遠望できる。昨夜の雨と強風で空気中のチリが吹き払われたか、視界は良好、すばらしい空と海の青さ、山々の緑だ。北西方向には明石海峡大橋の2本の巨大な橋梁が浮かんでいる。 島南端には探照灯跡がある。探照灯も攻撃目標としてはあからさまなところだから、さすがに周囲に砲台跡はなかった。 島、北端の虎島までは4キロ。虎島と沖ノ島を結ぶ細い地峡は、潮が引いているときにしか渡れない。島南部を歩き回っただけで4キロを消費している。北端までの往復8キロで1日12キロのトレッキングはなかなかハードだった。 ・・・と、島に渡っていれば書いていたんだろーなー、とエア紀行をここで締めくくる。 すいません、朝からの強風で、船が出なかったんです。すべてがパンフレットなどからの空想の産物なんで、そこのところは、ひとつ。 |

| 3月もあと1週間で終わってしまう最後の日曜日、Fと一緒に丹波篠山に向かった。 JR「丹波路快速」は大阪と丹波篠山を1時間ちょっとで結んでいる。もっともJRに「丹波篠山」駅は存在しない。「篠山口」駅が篠山城のある小さな市街地に向かう最寄駅となる。 明治以降、鉄道が日本各地に伸びたが、お城下に乗り入れることはまずなかった。城下町の多くは駅から離れている。 「電化されていれば別ですけど、蒸気機関車なんかが街中を走ったら迷惑だったでしょうからね」 Fがもっともなことを言う。 筆者は漠然と、近代文明を嫌悪する近世の保守性が原因かと思っていたが、煙害回避というのは一理ある。 宝塚を過ぎ、渓谷を走る列車から見える遠くの山並みが霞み始めた。霧とも霞みともつかぬその白いベールが急速に近づき列車を包みこんだ、その瞬間、窓外を雪が舞った。もうすぐ4月だと言うのに、雪かい。 やがて列車は「篠山口」駅に到着。1時間では旅情が湧く暇はない。 駅は東西に駅前口を持ち、それなりに大きい。 タクシー乗り場に客待ちのタクシーが数台、待機している。タクシーに乗車して行き先を告げる。 「いわやへ」 丹波篠山名物「ぼたん鍋」の店「いわや」が今日の短い旅の目的地だ。 猪肉の鍋を「ぼたん鍋」と呼ぶ。 周囲を白い脂肪に囲まれた切り身が、まさにぼたんの花のように見えるのでそう呼ばれている。 「いわや」までは20分程度。店は篠山城のある |
市街地からも離れている。野中の1本道を進む車中から茅葺屋根の農家が見えると家相鑑定士のFが歓声をあげる。 「いわや専用コシヒカリ栽培地」と書かれた田んぼの先、ちょっと小高い土地に大きな屋根と茅葺の屋根の「いわや」が現れた。 店の前には猪の剥製。引き戸をあけて店内に入れば、広々とした板敷きの間のそこ、ここに細長く囲炉裏が切られている。 予約名を告げ、囲炉裏端に腰を下ろす。毎回かどうかは知らぬが、当日の追加ができないこともあるらしい。今日は2人で肉6人前を予約しておいた。時期的に生肉でなく冷凍モノになるかもしれなかったが、今日はラッキーにも生肉だった。 鍋は味噌仕立て。 くつくつと味噌が煮立ち、いい香りがあたりを漂う。火の通った猪肉を口に運ぶ。 脂が旨い!肉をネギと一緒に口に入れるとさらに旨い。6人前の肉は多かったかなと思っていたが、途中で、これなら楽に食いきれると踏んだ。 「あまごを2本お願いします」 川魚の串うちを注文した。 囲炉裏の中で赤々とおこる炭火の周囲に串を刺す。まだ、生きているあまごはピクピクしながら焼かれてゆく。 これまた、旨い。なにより風情がある。 猪肉を使ったサブメニューが幾つかあるが、鍋とあまごと酒だけ。これがいいのである。 家族連れの小さな子供が、じっとしていられなくなったのだろう。広い店内を走りまわる。古民家然とした店内では、田舎に帰省した気分が横溢し、むしろほほえましくさえあった。 |

札幌行5 →→→back 札幌行1 2 3 4 5 6 7 8 9
| 夜景にはとんと縁のない人生を送っている。 嫌いなわけではない。 ただ、もっと好きなものが夜景の邪魔をしているのだ。神戸の夜景なんてその気になれば、いつでもいけるような近場にあるのに行ってない。函館だって、札幌だって、長崎だって、何度か訪れているにもかかわらず夜景は見たことがない。 「夜」の「景色」と書いて夜景。 この「夜」というのがどうもいけない。 筆者は「夜」になると、飲み食いを始める習性がある。夜景を愛でるよりも酒食に溺れる方が好きなのだ。夜景を見ながら、旨い酒食がとれればいいのだが、なかなかそう都合よくはいかない。 そういう意味では、東京は強い。高層ビルに入っている料理店から見る東京の夜景は、やはり素直に綺麗なもんだ。大阪もいいかもしれないが、行きつけの店が皆、地下にあるか地上1階にあるので望むべくもない。 札幌、すすきので常宿にしているホテルの窓から藻岩山が見えた。 斜面に設置されたロープウェイの架線を黒い物体が移動しているのが望見される。 (しめた!ロープウェイが動いている!) 札幌市民ご自慢の藻岩山からの夜景は、ロープウェイに乗らなければ得られない。過去2回、市電のロープウェイ駅で降り、ロープウェイの山麓駅まで歩こうとするとなぜか、毎回、運休の憂き目にあっていた。今回は三度目の正直だ。 冬のいいところは、陽が沈むのが早いことだ。 料理屋が店を開ける前に夜景を拝める絶好のチャンスがやってきた。 ホテルの前でつかまえたタクシードライバー氏に行き先を告げると |
「やっと改修が終わったんですよー」「はい?」 「いや、老朽化したロープウェイを2年ぐらいかけて新しくしたんです」 2010年の4月から2011年の12月まで改修工事で運休していたのだ。さらにそれ以前から老朽化のため運休していたらしい。 これで過去の空振りのわけがわかった。 時計は16時に近い。 「メーターを止めて待ってますよ」 ドライバー氏の申し出を受け、「てっぺんまでどんぐらいかかるんですか?」と問えば、「そーですねー17時頃にここで待ち合わせってことでどーでしょー」 1時間あれば大丈夫だろう。 ロープウェイは15分おきに発車する。00、15、30、45分発だ。5分程度の乗車だが、ありゃ、山頂まではロープウェイとケーブルカーの2段階になっているではないか。 「もーりすカー」と呼ばれるミニケーブルカーも00、15、30、45の発車だ。乗り継ぎが悪い。中間点で時間待ちが発生する。 展望台に上がった。 陽は遥か支笏湖の方向に沈み、山々の隙間から茜色の光条が遠くの町並みをピンスポットで照らした後、やがて静かに淡く消えていった。 樽前山、風不死岳、恵庭岳も拝める。 夕闇が忍び寄り、テレビ塔やT38(JRタワー)、すすきのの観覧車などの周辺でポツリ、ポツリと灯がともりはじめた。 (こりゃあ、綺麗なもんだ) 初めて見た札幌の夜景はたしかに美しかった。 堪能し、すすきのに戻った。「たる善」で魚と寿司を、「バー・プルーフ」で酒を堪能。 |

| 二泊三日でおさえたプリンスホテル系列の宿は温泉観光地によくある「ツアー客誘致の大箱」タイプで料金はリーズナブル。しかも筆者のような漂泊のひとり者も歓迎とのこと。一泊二食が1万円で札幌駅までの送迎バス付(片道4時間)を考えるとかなりお得な感じ。 もちろん、部屋食にはならないし、朝も夜もバイキング型式だが、糖質制限修行の筆者にとっては、好きなもの(低糖質物件)を選べるバイキングはありがたい。大雪山のど真ん中で料理専門店の味を期待するのは野暮だ。大浴場の雰囲気だけで選んだと言っても過言ではなかったが、この選択は正解。真昼間、深夜、早朝と、大浴場(3種)と露天風呂に浸かり続けた3日間だった。 風呂掃除で温泉が閉鎖となる10時から13時の間に黒岳に登ることにした。 黒岳は標高1984m、ロープウェイは5合目1300mまで運転している。5合目からはリフトで1520mまで上がり、その先は登山道となっている。 ロッジ風の意匠のロープウェイ駅には「標高670m」の表示があった。 駅構内には上川中学校の高梨沙羅選手(15歳)の応援ポスターが。ちょうどユースオリンピックに優勝した直後のことでもあり、2014年のソチオリンピックから正式種目になる女子ジャンプ期待の星ということなのだな。頑張れ!沙羅チャン! ロープウェイの乗客は筆者ひとりのみ。しかもリフトは運休中だった。5合目がゴールだ。 昨日とはうってかわって天も地も灰白色に包まれた荒天。麓駅を出ると、ゴンドラはみるみる高度を上げてゆく。かなりの迫力だ。 (あ、こりゃあFは駄目かもしんないな) |
高所恐怖症のFの雲辺寺ロープウェイでの姿を思い出し、ひとり微笑する。 眼下の砂防堰堤の底部を流れる水が氷瀑と化して、すさまじい画になっている。 ゴンドラはあっと言う間に、900m地点にある2号鉄塔を越えて、5合目駅終点についた。 展望台を兼ねている屋上に出たとたん、突風によろめいた。かなりの強風だ。飛雪か降雪かもわからぬ雪が顔面を叩く。 黒岳山頂は、雪雲に覆われ山容を見極めるのは難しい。時折、雲が動き、僅かながらに山頂のシルエットが浮かび上がる。 まさに「カムイミンタラ」の名に相応しい光景だ。アイヌ語で「神々の遊ぶ庭」という意味だ。 駅を出て、運休中のリフト乗り場に向かって歩く。強風にあおられ、木々の梢に積もった雪がドサドサと落ちてくる。からだを屈めながら前進する。氷点下も10度を切ると思考能力は低下する。 「前へ進む」「振り返り帰路を確認する」そんなシンプルなことしか頭は働かない。自分の呼吸音と風が巻き起こす空気の擦過音、それだけが周囲のすべてである。大自然を前に、己がいかに無力な存在であるかを認識するひととき。もしかしたら、この孤独感、孤立感を求めて冬季の雪国に来る癖がついてしまったのかもしれない。 運休中のリフトは当然、雪に埋もれている。 キンキンに冷えて、ホテルに戻る。露天風呂に行くと5合目の吹雪と同じような風雪が露天のフロアに吹き荒れている。すぐさま湯に浸かる。湯から上の顔は極低温。からだはホカホカ。これが露天風呂の醍醐味か~ |

ホテルHPの画像を拝拝借 天空露天風呂「朝陽山」、大浴場(雲海の湯「黒岳」)、(癒しの湯「桂月」の瞑想の湯と雪見の湯-閉鎖空間をうまく演出していて確かに瞑想を催される。露天は飛雪舞い強風がそのまま湯面を吹き渡る最高の状態。露天はこうでなくちゃという感じ。

| 北海道の中央、旭川から石狩川沿いに上川町を抜け、北見を通り網走にむかって東進する国道39号線。その中間点に大雪山がある。 大雪山と呼ばれてはいるが、そういう名の孤峰があるわけではない。 旭岳を筆頭に、北鎮岳、白雲岳、愛別岳などの2000m超級の山々が連なる連峰の総称である。だから大雪山系と呼ぶこともある。面積は神奈川県に等しい。まさしく北海道の屋根である。 秋の紅葉はこの大雪山から始まり、紅葉前線はこの地より南下を開始する。 国道39号線は、この山系の底部を貫いている。上川町を過ぎてしばらくゆくと山系のひとつ「黒岳」のふもとに温泉郷が現れる。古くから大雪山の観光拠点として栄えた「層雲峡」である。 札幌から温泉旅館(ホテル)の送迎バスに揺られて4時間、いよいよ大寒を迎えたその日、筆者は層雲峡に旅装を解いた。 弘前の「雪灯篭祭り」で転倒三昧したあの日から、積丹でも転倒を繰り返し、支笏湖「氷とう祭り」で冬靴(北海道用語)を履き、チェスターフィールドからキルトコートに切り替え、手袋を嵌め、厚手の靴下、ヒートテックの装着など厳冬期の装備を徐々にアップグレードしてきた筆者は、ついに真冬の大雪山にも適応できる実用本位(格好つけるのやめた)のいでたちを獲得したのであった。最後のハードルはフードつきコートだった(頭、覆わないと厳寒期の寒風に対応できないことは支笏湖で知った)。 ホテル着は午後4時。すでに山の稜線に隠れた落日のあとを追って夜の帳が迫っている。 この日、層雲峡では「第37回氷瀑まつり」が開 |
催されていた。 部屋からは石狩川沿いに設営された「氷瀑まつり」会場が見下ろせる。青白くライティングされた会場に人の姿がパラパラと見受けられる。支笏湖の「氷とう祭り」よりも寂しそうだ。頭上には「地獄谷」と呼ばれる岩塊が聳えている。 そそくさと部屋を出て、ホテルの玄関前に出ると、目の前にエジシカが現れた。 こっちをじっと見つめている。北海道だなあ。 温泉郷の宿の中でも高台に位置するホテルだったので、積雪を踏みしめ踏みしめ、下り坂を降りてゆく。途中、黒岳ロープウェイの駅があった。 「標高670m」の表示がある。すでに今日の運行は終えている。明日、乗ることにしよう。 ヨーロッパ風のロッジを意匠したロープウェイ駅の先に「層雲峡」唯一の短いメインストリート(商店街)がある。道の両側に並ぶホテルやペンションの食堂やレストランが宿泊客以外にも提供されている。飲食専門のラーメン屋もあるが、すでに火を落としているようだ。 200円を支払い、「氷瀑まつり」会場に入る。 支笏湖の「氷とう祭り」同様、氷のオブジェ、氷のトンネル、氷の塔が、赤、青、緑、黄、各色のライトを受け、闇の中、鮮やかに浮かび上がっている。氷点下は10度以下だと思うが、天気がよく、風が弱かったので体感温度はそれほどでもない。 それよりもなによりも、ホテルやまつりの会場を席捲する中国語の群れに驚かされた。まさにイヤー・オブ・ザ・ドラゴンだ。チャイナパワー、恐るべし。 |

| 東京にいた頃は滝なんぞ、見に行こうなどとはこれっぽっちも思わなかったが、関西に来てからは、実に気軽に滝見物にいそしんでいる。 「箕面大滝」へはチャリで、「赤目四十八滝」と「布引の滝」は電車に乗って、「那智の滝」はドライブ旅行で行った。 今回、ぶらり途中下車の滝にフューチャーされたのは「黒滝」。 電車で向かう。降車駅は「三田」の先の「新三田」。関東圏の人は「みた」と読んだでしょ。残念でした「さんだ」が正解です。 新大阪から大阪で乗り換え、JR宝塚線、快速宝塚行きに。川西池田で福知山線に乗り換え、新三田に到着。乗車時間は約1時間。 宝塚線(福知山線の一部区間呼称)は宝塚を過ぎると、車窓が急速にローカル線化する。武庫川上流の渓谷に沿って山峡に分け入るその変化は、中央線で八王子を過ぎ、大月界隈を走っている感覚に似ている。 「武田尾」駅などホームがトンネルの中だ。トンネルからはみ出した部分は武庫川橋梁にかかっている。完全に山峡の駅。 とにもかくにも新三田到着。 駅前は、それなりに開発されているかと思いきや、バスロータリーしかなかった。三田牛の飲食店でもあるかとの淡い期待は儚く潰えた。 新三田からバスに乗る。このバスの本数がまた少ない。1日6本。10時39分のバスに乗ることになったが、その1本前は8時54分、1本後は13時30分。 目指す「黒滝」は「二瀬川」停留所を降りて徒歩すぐということだが、いつものように準備不足のおっとり刀での道行きゆえ、胸中には若干の不 |
安がたゆたっている。 「渡瀬」行きのバスがやってきた。これに乗って「二瀬川」で降りる。揺られること30分弱、田には酒米「山田錦」がたわわに実っている。 「二瀬川」停留所に到着。 県道17号線沿いの停留所前には「ドライブイン黒滝」があった。営業しているとは思えない。 (滝はどこにあるの?) 抱いていた不安が現実化した。滝のありそうな地形や気配が微塵も感じられない。雛にあってはいつものように看板や標識などの誘導物件の姿は当然のようにない。 県道沿いの農産物直売所で滝の所在を聞く。 そぼ降る雨の中、田んぼの中を歩くうち、急に水音が聞こえてきた。 何かの管理事務所のような建物を回り込んだ瞬間、眼下に滝が現れた。 落差のある高い滝ではない。横幅が広い滝だ。 落差は、4メートル、幅30メートル。 階段を下りて滝のそばに行く。落差が少ないから眼前に見てもあまり迫力はない。むしろ上方から見下ろした方が美しい。過大な期待を胸に行かなければ十分に満足できる物件だ。晴れていたらピクニック気分でランチボックスを開けるのもありかもしれない。 停留所で帰りの時間はおさえてある。ただし、時間になってもバスが現れない。地方の路線バスって本当に来るのかどうか実に不安になる時がある。もしかしたら早めに通過してしまったのではないか?とか様々なネガティブイメージが脳裏に浮かぶ。 バスの姿が見えたとき、心の底から安堵した。 |

| 山陽新幹線「新神戸」駅の裏に滝がある。 「新幹線の駅そばに滝?さぞかしちょぼい滝だろう」と思っていた。 山陽新幹線は、新大阪を出ると、すぐに六甲山系を貫く長いトンネルに入る。トンネルを抜けたところが新神戸だ。 つまり、山岳地帯に駅がある。しかも名水で知られた神戸だから、滝のひとつやふたつ、あっても当然のことなのだが、文明の利器の代表銘柄のような新幹線と自然はなかなかに結びつかない。 週末の一日、新大阪から新神戸へ「こだま」で移動。N700系や、九州新幹線「さくら」や「みずほ」の登場で山陽新幹線の車両運用も大きく変わった。ミサイルのような500系はずいぶん前から「こだま」に格落ちしていたが、ひかりレールスターも「こだま」になっていた。東海道新幹線と違って山陽新幹線は「こだま」になると、すべての車両が左右2席ずつに換装される。グリーン車のようになるのだ。これはなかなかにいい。ケチなJR東海は決してそんなことはしない。 新神戸駅の地上階で外に出る。 薄暗い高架下を公道が山側に抜けているが、ちょっと見、その先に道が続いているとも思われんような寂しい雰囲気。場末な感じなのだ。 壁に「布引の滝0.4Km」と赤い矢印付の表示がなければ、なかなかあっちには行かないだろう。 高架を抜けると、住宅が現れ、視界を遮る左まわりのゆるい坂道を進むと、いかにもハイキングコース然とした渓流沿いの探勝路が現れた。 (0.4Kmは400m、ちょろいぜ) と思った途端、すぐにしっぺ返しがきた。 階段がきっつい!そして長い!途中休憩をいれ |
たくなるが、意地で歩き続けた。 下方に渓流を覗き込みつつ、もはや渓谷と言っても過言ではない地形と化したハイキングコースには、途中、小さな滝が現れ、歩き始めてから15分後、豊かな水量を思わせる轟きが耳を打ち、布引の滝「雄滝(おんたき)」が現れた。 落差43m、岩頭から5段にひねりながら落下する様はなかなかのものだ。 「いいのか、こんなに安直に来れて」と少し申し訳なくなるほど、しっかりした滝だ。 日本三大神滝のひとつに数えられる名瀑。(なに?なに?神滝って?)とにかく、華厳の滝、那智の滝に肩を並べる滝なのだ。 ハイキングコースはさらに続く。 途中、展望台があり、さらにその先には渓流にかかる「猿のかずら橋」が現れる。 道はここで分岐する。 橋を渡ると、かなり急峻な坂道の先に「滝山城」跡がある。 この坂道もかなりキッツイが、下山時、時間を節約しようとショートカットしたら、落ち葉ザクザクの滑落しそうな不整備路に出てしまい、目をむきながら北野の一角に舞い降りた。 後日、再訪したときは橋を渡らずに直進した。 やはり坂道と階段が続き、やがて布引貯水池に出た。目の前にダム湖が広がり、この眺めはなかなかにいい。ダム湖をキャットウォークで渡った先、祠の脇に急勾配の階段が伸びている。階段を登り、公道に出てしばらく。「布引ハーブ園」が現れた。山頂まで登り、さすがに体力を使い果たし、ロープウェイを使って新神戸駅そばまで降りてしまったのであった。 |

| 志賀島を先端に頂く海ノ中道が東から包み込むように腕を伸ばし、西は糸島半島にガシッとガードされた博多湾。 その中央に、ひとつの島が浮かんでいる。 それが「能古島」。 能古島と書いて「のこのしま」と読むけん。 今日はおいが島のこつ教えちゃるけんねぇ~ 島へはフェリーで渡る。 地下鉄「姪浜」駅からバスで10分、徒歩30分程度のところに「能古渡船場」がある。 姪浜は天神から7駅目。途中駅には、「大濠公園」や、ヤフードームの「唐人町」がある。 渡船場の対岸にはマリーナを挟んで「マリノアシティ福岡」というアウトレット兼飲食店街の複合商業施設がある。マリナ大橋で結ばれているが両者独立した施設で、連携の利便性はない。 マリノアシティで昼飯を食べ、炎天下、歩くにはちょっと長すぎるマリナ大橋を「はひはひ」と渡り、渡船場を目指す。 古びた待合所のような渡船場には、お盆休みのこととて、すでに中高生や大学生が列をなしていた。そーなのだ。能古島は博多っ子が幼少時から慣れ親しんでいるプレイランドなのだ。 船は朝夕を除けば1時間に1便。ただし、乗船時間は10分程度。あっと言う間に島につく。 島の渡船場のそばに「のこの市」という観光案内所がある。建屋内のショップで売られている「のこバーガー」が名物のようだ。レンタサイクルもそのショップで扱っており、バーガーを求める客の合間をぬってチャリを借りた。電動アシスト車もあったが、マウンテンバイクにする。 島は基本的には山。最高点の海抜は195m。 |
集落は渡船場のある島南端部に密集し、平地はほぼその部分に限られる。地図を見ると島北端に近く「アイランドパーク」という公園(有料)があった。そこにむかって「桜道」と書かれたコースをこぎ始める。 平地は瞬間的に尽き、すぐに坂道となる。勾配はかなりきつい。21段変速のマウンテンバイクでも汗みずくであがきながらの登坂となった。 眺望はいい。途中、チャリを停めて何度も対岸の博多湾の景色を堪能した。 右下方から波音に雑じって嬌声が聞こえる。 海岸沿いに海水浴場があり、キャンプ村も兼ねているらしい。バンガローで宿泊もできるし、手ぶらでやってきてバーベキューも楽しめるとは後刻知った。 30分程度、かなりへばりながらも、ほぼ島頂上と思われる「アイランドパーク」の入り口に辿り着いた。(もしかたら島中央の展望台の方が高いかもしれないが、そこのところは、ひとつ) 外から覗くとのどかな市民公園程度の施設だったので、入場料を払ってまでも、との強い欲求は芽生えず、渡船場のある島南端部に戻ることにした。往路の「桜道」は東岸を走るが、「自然探勝路」が西岸にある。探勝路とあるのでチャリで行けるか不安になり「桜道」を戻ってしまったが(マウンテンバイクなのに!)たぶんいけるのではないか。島一周12キロの推奨路と思われる。 火宅の作家「壇一雄」は晩年、この島に住んでいたらしい。旧宅が残っている。 九州出身芸能人の重鎮、井上陽水にも「能古島の片想い」ちゅう名曲(?)があるらしい。申し訳ないっす。筆者は知りません。 |

| 浅井氏の居城、小谷城は、湖北の要衝だった。 読みに濁りを入れるのがこの地の特徴なのか、 「浅井」は「あざい」だし「小谷」は「おだに」だ。微妙にはずされるのである。 それはともかく「小谷城」は日本五大山城に数えられているらしい。Wikiによれば、春日山城、月山富田城、観音寺城、小谷城、七尾城が挙げられている。 (ん?ちょっと待て!) 日本三大山城の岩村城、高取城、高梁城はどーなってんの? 織田信長の小谷攻めにより、浅井氏は滅び、羽柴秀吉が湖北の要を長浜に据えてから、小谷は歴史の一頁に書き込まれるだけの存在になってしまった。敗亡した浅井氏への思い入れはあまりないが、小谷城を訪れることにした。 米原経由で北陸本線に乗り入れ北上。長浜を越え、2駅「河毛(かわけ)」駅で降りる。 前駅の「虎姫」駅でも見かけたがNHK大河ドラマ「江」にあやかって浅井三姉妹のパブリシティが氾濫している。 (しまった!) 天の邪鬼の気味ある筆者は、集団行動が苦手。ブームに乗るなんてまっぴら御免なのだが、今日はノーマークで来てしまった。「龍馬伝」では高知、「天地人」では新潟・山形方面、「篤姫」では鹿児島、一過性のブームに踊るオバチャンたちがガヤガヤと集まる地を歩くのはとめどもなく恥ずかしいことのひとつである。 河毛駅前には、ほぼ何もなかった。 三姉妹もののイベント会場が、小谷城の麓にあるらしい。ワゴン車で小谷城まで連れて行ってくれた。料金は200円。同乗者は6名。 「ブームが終わればすみやかに撤収!」そういう |
計画のもとに設置されたのであろう各会場はすべからくプレハブ様の簡易設計。すぐれて正しい見識である。 麓からバスで城山の途中、番所跡まで連れて行ってくれるらしいが、筆者は乗らずに徒歩で攻めることにする。 天守閣が残っているわけでも再建されているわけでもないが、城域は広い。 入山して最初に現れるのが出丸跡。城防衛の最前線の砦跡で、上方から眺めれば、土塁のあとがはっきりとわかる。 中腹の望笙峠からの見晴らしも気持ちがいい。 途中、高札に筆書きされた城跡の説明がそこここにあり、訪問者へのホスピタリティはかなり高い。高札以外にも「熊出没注意!」や「スズメバチ注意!」の標識があり、嫌が上にも緊張感を高めてくれる。 番所跡を通過する際、低周波の羽音が周囲を何度も行き交い、威嚇的に頭上でホバリングを始めた。背をかがめながらそそくさと通り過ぎる。 本丸まで汗みずくになりながら登ると、小谷城跡で一番の眺望が待っている。 眼下に城の支城となった丁野山城、中山城を擁した丁野山が、山本山城のあった山本山が、城内の曲輪、山崎丸のあった支峰が、近江の野に、あるいは伸び、あるいは浮かんでいる。 琵琶湖を背景に信長が城攻めの拠点とした虎御前山も指呼の間に見える。 落城の悲哀を想起させる光景だ。 本丸の後背の中丸、京極丸、小丸、山王丸まで登り、降りることにした。 番所跡を通るとき、再び、威嚇するかのような羽音に追われ、これからは白い帽子も用意しようと心に誓ったのであった。 |

| 新幹線で「米原」へ。在来線に乗りついで特急「しらさぎ3号」の自由席に腰を下ろした。北陸方面へは湖西線を利用することが多いが今日はダイヤの都合で湖東から北上する。 米原と長浜は思いのほか近い。 長浜を過ぎ、列車は浅井氏旧領をひた走る。近江の象徴伊吹山が車窓の友になる。 近江塩津から湖西線と合流し、敦賀に停車。「しらさぎ」はその後、武生(たけふ)、鯖江(さばえ)と細かい停車を繰り返し、福井に着いた。 近年改装されたJR福井駅の隣にえちぜん鉄道福井駅がある。えちぜん鉄道勝山永平寺線の始発駅だ。 映画館のように、入線してきた電車の乗客が改札を出終わるまでホームには入れない。 ホームには2両編成のロングシート車輌が止まっていた。2ドアなのでドア間のロングシートがすばらしくロングだ。 ホームのベンチに人影があった。目をやると、人ではなく恐竜が座っていた。福井は恐竜王国。 「恐竜博士」が観光客を迎えているらしい。 福井駅から2駅目、福井口駅で勝山永平寺線と分岐する三国芦原線の終着駅は三国港。 数十年前、筆者はこの路線に確かに乗っている。当時の鉄道会社は京福電鉄だったはずだ。 車窓は北陸ののどかな穀倉地帯を映し出している。遠くまで広がる稲穂の海が風にそよいで、緑のウェーブを四周に送っている。 1時間に2本のダイヤ。 単線だから行き違いの待ち合わせもある。 ゆったりとした時が流れている。大きな綿雲が思いの外低空をのんびりと流れて行く。 三国港駅についた。 歩き始める。 県道の緩い坂を登りきったところで「荒磯遊歩 |
道」入り口が現れる。 数十年前の記憶が淡くはじけた。 あのときはここでアシナガ蜂にしつこくつきまとわれたのだった。 海岸線の崖上を遊歩道は右に左に上に下に、うねりながら続いている。左手は海、右手は緑の樹林。緑のトンネルが続く。 三国港駅を出て40分くらいだろうか。眼前の視界が開け、断崖と岩を噛む荒波の光景が現れた。 「東尋坊」である。 (あれ?) 数十年前に見たときより全体がスモール? どうやら、勝手に記憶を膨らませてしまったらしい。よくあることではある。まあ、いい。 今日は東尋坊を越えて「雄島」まで行くのだ。 島にかかる赤い欄干の橋と鳥居は、東尋坊からも遠望できる。しばらく歩くと立ち入り禁止のロープと看板が現れた。 「荒磯遊歩道はこの先、老朽化が進み、危険なので迂回路を使ってください」とある。 (迂回路って?) 県道のことであった。再び、時折歩道部分のない危なっかしい県道を歩く。(趣に欠けるなあ) 遊歩道を修復する予算もないのかな。 何はともあれ、雄島に到着。赤い橋は改修工事中で通行止めだった。島の別名は「鯨島」というらしい。確かに鯨のように見える。 「島の裏側にまわると、これがエイみたいに見えるんですよ」とは売店のオバチャン。 東尋坊に戻る。参道のまわりに土産物屋が立ち並ぶ門前町のような東尋坊タワー周辺の駐車場のタクシー乗り場でタクシーをつかまえた。 帰路のえちぜん鉄道は1両編成のボックスシート車輌。福井からはサンダーバードで一気に京都まで。京都で一服。これが目的でもあった。 |


| 避暑地を求めて京都へ行った。 京都盆地の内側は名だたる暑寒の地だから避暑にはならない。被暑になってしまう。 山だ。山に逃れるのだ。 叡山鉄道、通称「EIDEN」は出町柳を起点に叡山に向かう叡山本線と鞍馬へ向かう鞍馬線の2系統で運行している。今日は、鞍馬へ行こう。 出町柳から鞍馬までは30分。2両編成の観光車両「きらら」はのどかな京の北東角をゆるゆると登坂してゆく。 途中、宮本武蔵VS吉岡一門の決闘で知られる一乗寺下り松の「一乗寺」駅、幕末、朝廷から失脚した岩倉具視が逼塞していた岩倉村の「岩倉」駅、川床で有名な「貴船口」駅などがある。 終点「鞍馬」で降りる。 「仁王門」が聳えている。その背後には木々の緑を深々と湛えた鞍馬の山。 「九十九折参道」の階段を登ってゆく。 「由枝神社(ゆきじんじゃ)」の鳥居と神殿のむこうに聳える大きな杉は樹齢800年。太陽の照り返しが神殿の天井を輝かせる。 ただ、ひたすらに階段を登る。 汗みずくになり、本殿金堂のある山上に至る。鞍馬山の山頂はまだ上だがお山(寺)のてっぺんはここだ。標高は410m。(仁王門が210m)仁王門からは約1キロの行程だ。本堂の狛犬は虎だから、狛寅とでもいうのだろうか。 見晴らし台のむこうには、比叡山が見える。 本殿金堂からさらに800m先に「奥の院魔王殿」がある。峰づたいに歩くコースだ。 途中、道を外れて杉の木を祀る庵の前へ。周囲に人影もなく、静寂に包まれていた。ちょっとゾ |
クッときたのでそそくさと撤退した。 地質が硬いため、樹木の根が地下へ伸びず、地表に露出している「木の根道」を越え、奥の院に出た。このまま下り階段をさらに進むと貴船に出られる。約600mの急坂だ。 急ピッチで下る。 ふと、気配を感じた。 明らかに背後から気配が近づいてくる。 九十九折れの方向転換で後背に横目をむけた。遠くのカーブで極彩色のカラフルなひらひらしたものが瞬間、目に映ったがすぐに木々の梢に隠れた。(男ではないぞ)ピッチをあげる。 ダンダンダン。かなり早く階段を下る。 気配は消えない。 むしろ距離が詰まっている。 足音が耳に届くまで詰められていた。 いつの間にか追われる立場になっていた。 さらにスピードを上げる。 足音はすでに僅か数mの距離に近づいている。 前に人影が現れ、つかえた。歩を緩める。 足音は背後についた。 振り返った。 女だ。しかもヒラヒラのフリフリ衣装の。足回りはさすがにシューズだった。 (・・・・・) 西門に至り、貴船川に出る。川床を覗きながら、貴船神社の奥院まで散策。 それにしても涼しい。 百貨店などの入り口でエアカーテンが外気の進入を防ぐために強めの冷気を吹き出しているが、まさにそのような冷気が川から伝わってくる。 でも、さっきの坂道の方がヒヤッとしてたな。 |

| 人口よりも牛口が多い「黒島」。 石垣島主島の離島ターミナルから高速船で25分ほどの距離に浮かんでいる。ハートアイランドと呼ばれているのは、島が微妙なハート型だから。 黒島に向かう竹富島、小浜島の裏側の水道は、すさまじいエメラルドグリーンだ。 島と環礁に守られた水域を少し外れるのだろうか、大きくうねりながらも40ノットの船速に翳りは見られない。水しぶきが後甲板のシートにはねあげり続け、気がつけば、下半身がズブ濡れだ。 やがて黒島に接舷。 埠頭には小さな待合所があるだけ。レンタサイクルの出張受付に女の子がひとり。店は歩いて1分のところにある。 変速機のないママチャリにまたがる。ベルが壊れているが、こののどかな島でチャリのベルを鳴らすケースが想定できない。 黒島は、全島ほぼ平坦。人よりも牛が多いということは、島内がほぼ牧草地ということで、あたり一面の緑が大草原のようだ。ぽん、と放り出されたら沖縄にいるのか北海道にいるのかわからないかもしれない。 琉球王朝時代、沖をゆく船を監視する遠見台として築かれたプズマリの左にゆけば、島で一番メジャーなビーチ、仲本海岸に出る。しかし、「黒島研究所」とのぼり旗のある反対方向の未舗装の道へチャリを乗り入れる。途中、海岸と小道を遮る亜熱帯の植物群の切れ目を見つけ、チャリを捨て、分け入った。ちょっとだけハブが怖い。 薄暗い木々のトンネルを抜けると、絵に描いたように、陽光あふれる沖縄のビーチが現れた。 筆者ひとりのためだけのように。 |
干潮時なのだろう。干潟が薄く広がり、波打ち際は50mほど先にある。ズボンをめくり、ビーサンでじゃぶじゃぶと干潟に足を踏み入れる。ところどころの潮溜まりでは取り残された小魚が泳いでいる。岩陰からするりと長い影が躍り出たのはうつぼだ。このひと時だけでもかなり満喫。 チャリを主街道に戻し、何人かの観光客とすれ違うも、終始、島は自分ひとりのモノという独占感があった。 小さな、小さな、白い灯台もいい。 あちこちに「御獄」があり、祭祀の神聖な場を前にストローハットをとり、柄にもなく居住まいをただしたりする。ビーチの「御獄」のそばで数羽の孔雀が、筆者を警戒し、こそこそと茂みの中に身を隠していった。孔雀もいるのか。 まっつぐ続く道路の周囲には沖縄特有のさんごの石垣が続き、牧場との境を成している。そこをゆるゆると走る開放感はどうであろう、無論、車の姿などほとんどない。広大な草原、青い空、白い雲、まだらに雲の影が草原を、思いのほか早くすべり抜ける。太陽を遮る雲は時に島よりも大きい。あちこちで牛が耳をパタパタパタパタ。 道路のそこここに乾いた牛糞が落ちている。 柵を越えて、牛が道端の草をモシャモシャ食べている。そのむこうから小さなショベルカーが道路を掻き、路上の牛糞をさらっている。 東筋(アガリスジ)は竹富島のようないかにもな沖縄の集落。 2時間半でほぼ全島を巡った。最初に2時間400円で予約したが、追加料金はいらないと言う。善良だ。ますます好きになった黒島。 ここ、けっこーお薦めです。 |

| 旅慣れているつもりでも不覚をとることは、ままある。今回もやらかしてしまった。 梅雨空の下、紫陽花(あじさい)を見に行こうと思い立ち、関西の紫陽花スポットをチェックすると丹波の観音寺、宇治の三室戸寺が選択肢の上位1位、2位にあがった。 丹波路は昨年11月以来、消費していない。 観音寺に狙いを定めた。 関西花の寺1番札所、関西最古のあじさい寺、創建1200年弱の古刹、と聞けば行かない訳にはゆくまい。最寄り駅は「石原」とあった。駅から徒歩15分のところにあるらしい。 調べたら「福知山」の隣駅だった。 「福知山」は訪れたことがある。山陰本線、福知山線、北近畿タンゴ鉄道の分岐点、丹波の要衝だ。地域の基幹都市としての規模と機能を備えている。そこから一駅であれば、雛ではあるまい。 地図さえろくに見ずに、家を出た。 特急「こうのとり」は大阪、福知山を1時間半で結ぶ。福知山から山陰本線に乗り換える。 2両編成のワンマンカーだった。 車内放送で初めて「石原」が「いしはら」ではなく「いさ」であることを知る。 さらに、石原(いさ)駅では降車ドアは先頭車両の一番前だけだとアナウンスがあり、慌てて車両を移動する。運転手が切符を回収している。 石原は、無人駅であった。 (福知山の隣だよな?) 駅の観光案内所か駅員に寺への道筋を聞けばいいとたかをくくっていた筆者の目論見は根底から覆された。 (タクシーは?) |
あるわけもない。駅前にあるのは、車停めスペースと、1階がレストラン、2階がカラオケ屋という今どき得難いコラボの一棟のみ。 駅前に周辺地図はない。観音寺への道標などどこにもない。 (しくじったな。久しぶりに・・・) レストランに入り、ウェイトレスに観音寺までの道順を聞いた。 徒歩15分とあったが20分程度はあるんじゃないか。それでも山門前にたわわに咲き誇る色鮮やかな紫陽花を思い描きながら、えっちらおっちらと歩を進める。 寺の前まで来ると、駐車場がいっぱいだった。 (電車で来る奴はいないのね) いつものことだ。 紫陽花が目にとまった。 紫陽花ってあたりはずれの年があるよね、きっと。色鮮やかに満々と咲き乱れる年もあれば、ぼけぼけの眠たい年もある。 あれ、去年はあんなに艶やかだったのに、どーしちゃったんですか?ちゅう感じ。 桜には、そーゆー思春期の子供のような情緒不安定はない。咲くのが早いか遅いかだけで、あたりはずれはない。期待通りの結果を出す4番バッターという認識は正しいのでしょうか?どなたか園芸に造詣の深い方の意見をお聞かせください。 3月、4月は桜、4月、5月は新緑の楓、そして5月、6月は紫陽花。そーゆー認識ではるばる丹波まで来たのだが・・・う~ん、赤玉が少ないな。密度にムラがあるな。今年ははずれかな?本当は、もっとすごいのかな~ |

| 温泉好きではけっしてなかった筆者。 正確には温泉宿が好きではない。 ベッド(B)とディナー(D)は別々がいいのだ。餅は餅屋の道理で、飲食は飲食のプロの店で楽しみたい。 都市部ではそれも可能だが、温泉の湧き出る雛ではそれはかなわぬ夢。 だから、温泉そのものにNGサインは出していないが温泉宿を使ったことがあまりないのだ。 それでも、歳のせいか、広々とした湯船に四肢を伸ばして浸かり、唸り声のひとつもあげるのが好きになってきた。 そして湯布院を再攻する日がきた。 前回、来て、見て、消費できずになすことなく撤退した日から5年の歳月が流れている。いよいよ本格的な侵攻を開始するのだ。 泊まらねば湯布院は消費しきれない。 これが前回の教訓。 泊まる以上はケチらぬこと。 これはいつもの信条。 大型施設は避けるべし。 これは和倉温泉以来の訓戒。 今回は老母を連れての家族旅行。自侭にならないのは覚悟の前。老母の専属ツアーコンダクターをしっかりと勤めねばならない。 温泉に行くのは、箱根の「玉庭」以来だ。ん?諏訪湖にも行ったか。 湯布院には「亀の井別荘」、「玉の湯」、「無量塔」などの超有名どころが軒を連ねている。宿決めなど、普段のひとり旅なら悩みもしないがツアコンとなると大変だ。悩み抜いて「一壺天」という宿を選んだ。ビッグ3とは自衛隊駐屯地をは |
さんだ反対側にポツリとある宿。ヨーロピアンテイストな商店街の先に由布岳が聳え立つ湯布院駅からタクシーで10分程度。 駅前商店街の一角にある焼き肉「さめじま」でちょっと意表をつかれた旨い肉を食べたあと宿へむかった。 離れの部屋に旅装を解くと、さっそく貸し切り露天風呂に浸かる。老母は内湯にどっぽーん。内湯も露天風呂で、眼前に由布岳、右手に湯布院の街が見下ろせる。 この内湯、造りが面白い。逆L字型に部屋からテラスのように外に湯船が張り出している。L字の縦棒部が室内にある。Lの折れるところに大きな扉が開放されているが、これを閉じれば内側は完全な個室になる造りだ。冬の外気を遮断したければ扉を閉じろということなのだろう。 老人と中年オヤジの二人には部屋数が多すぎるが、まーのんびりできていいじゃないかと寛ぐことにする。どーせ、外に遊びにはいけないのだ。 老母はよほどに内湯の露天風呂が気に行ったらしく、何度も湯に浸かっている。 筆者も内湯を試したら、かなりはまった。 眼前の由布岳の上には月がかかり、山頂を覆っていた雲もいつのまにか風に吹き払われ、山の全容が青空をバックに美しく浮かび上がる。 早朝、街のある盆地の底にたゆたう朝霧を眺める。街から由布岳にむかって霧がゆるやかに流れてゆくさまは実に妖しくも幻想的だ。 「気にいったわー」 無邪気に喜ぶ老母。 年1回の外泊旅行を今年も無事に終わることができた。 |
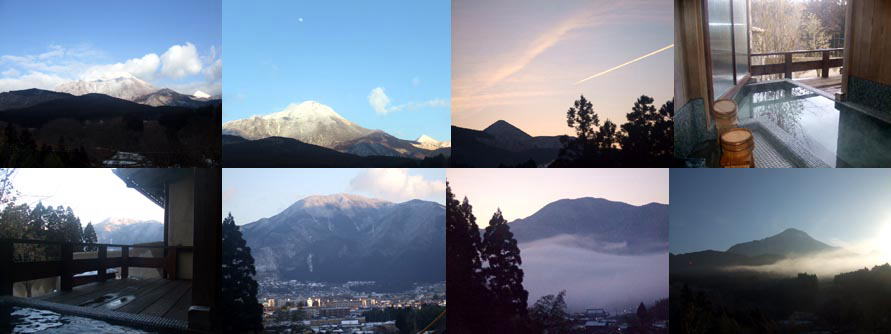
| 2009年の無謀とも言える伯耆大山(1709m)アタック時、革靴にジャケットというフザケた格好だった筆者も、2010年、わずか565mの岳山でルートを失い目をむきながら下山したことで心を入れ替えた。 ちゃんと軽登山仕様のトレッキングシューズを購入し、リュックを持ち歩くにようなった、中にはグラブとポンチョも入る。入山前にはミネラルウォーターをリュックのサイドに納める。 今日は、近江の安土、観音寺城跡を攻略だ。 標高433m、繖(きぬがさ)山の山上に築かれた観音寺城は、中世の名門六角氏の主城。繖山は、JR東海道本線の線路をまたいで、安土山に連なっている。標高108mの安土山は、繖山の支峰だ。 JR安土駅前でレンタサイクル屋の親爺が手書きの詳細な地図をくれた。 「こんなに細かい地図はここじゃなきゃもらえないよ。わしは六角氏の一族だからね」 ホントか?でも、まあ地図は嘘ではあるまい。 親爺は地図を広げながら、「この「日吉神社」の脇から「観音正寺」の参道を通ってゆくのが王道だ」と薦めてくれる。でも、どー見ても遠回りかつ、ハイキングコース1時間なんて道程が組み込まれていて時間がかかりそう。 (時間貸しのレンタサイクル料を稼ぐつもり?) 近江商人の末裔への疑惑が拭いきれず、あきらかに最短と思われる桑實寺(くわのみでら)からの入山ルートを選択した。10分程度で桑實寺(くわのみでら)の石段下に行ける。 坂下の町内会所のような建屋前の庭にチャリを停めて、山寺への階段を登る。途中、こぶりな山門の前に掲示板があった。 |
「これより桑實寺境内で有料です。本堂前の受付で「入山料」を納入して下さい」 (…京都の寺でも参拝料は徴収するしな…) 山門をくぐる瞬間「ピンポーン!」チャイムが鳴った。おそらく本堂にも通じているのだろう。なにがなし、せちがらい気持ちになる。 本堂前までの石段がすでにきつく、ちと長い。 本堂で入山料を支払う。 入山料を徴収しているわりに道を整備する気はないらしく、城跡に至る山道は、ガレ場なんかもあり、汗みずくで重力に逆らい続けることに。 足まわりってホント大事だったんだな。石段にせよ、山道にせよ、接地面は平坦ではない。微妙にランダムな傾斜がついている。だから態勢を崩しやすいし、落ち葉や折れ枝なんぞをうかつな角度で踏むとしっかりと足を滑らす。足首まで固定されているからなんとか転倒を免れること多し。 六丁、七丁、と石を刻んだ道標のあたりが一番しんどかったが、思いのほか、短時間で山頂の本丸跡に出た。 城跡までのほとんどが桑實寺の私有地だった。帰路は折り返しとしたが、チャリがなければ反対側の日吉神社へ行ったかもしれない。 本丸跡には何もない。周囲に石垣があるのみ。 巨大な遺構というイメージは少なくとも、桑實寺ルートからでは実感できない。 ガクガク膝を笑わせながら下山。チャリをまたいで、ついでだからと、安土城考古博物館と信長の館を覗いてみた。 信長の館は安土城の天守部分を屋内に再現した物件。う~ん、どーなんでしょー。これ。ちょっとしょっぱいかもしんない。 |

| よく知っているつもりで、実はあまりそーでもなかったということが9年ぶり3回目の来函でわかってしまった。 1987年の1回目は、何しに来たのか、何をしたのか、まったく覚えてない。青函連絡船の廃止が88年で、その前年に青森から乗船したという淡い記憶が浮かぶのみ。 2002年の第2回訪問は、大阪在住となったその年、大阪駅始発の寝台特急「日本海」でやってきた。たぶん移動手段が主目的。夕方5時に大阪を発ち、翌昼に函館で降り、一晩すごして、エアで帰阪するという「何やってんのおまえ」な旅。 スナッフルズのチーズオムレットはそのとき食べた。朝市で塩ラーメンも消費した。土方歳三、最期の地「一本木関門跡」に行き、市電にも乗ったがどうもそれだけでは足りない気がしていた。今回はきちんと函館を消費するぞ。 投宿先は電停「五稜郭公園前」界隈にした。考えてみれば、五稜郭にも行ってなかったのだ。 5月6日、冷涼さが勝る函館の春だが、五稜郭の桜は満開の時をむかえていた。 2006年に立て替えられた高さ107mの五稜郭タワーに登る。足元まで見下ろせる逆傾斜の強化ガラス越しに、五稜星の内を埋めるように咲き誇る淡いピンクの桜が美しい。中央には2010年に往時の姿そのままに再建された函館奉行所が見える。 タワーを降り、満開の桜を愛でつつ散策していると、この地で終焉を迎えた戊辰戦役の立役者たちの姿が浮かんでは消えてゆく。多くの人々が死んだ。140数年後の今、その地に花見客が溢れている。戦場の画像と今、目の前の平和な日常風景が重なり、妙なデジャヴに包まれた。所詮、人は死 |
ぬのだ。五十路をむかえ「それなりに楽しく生きたな」と何やら人生の終止符を待ちかねているかのような気分になることがある近時の筆者にとって、妙に懐かしい故郷のような場所に思えてならなかった。 夜、気分を変えて浮世を愉しむ。 地元客で賑わう居酒屋「昌栄丸」で道産の魚を堪能。ホッキ、ソイ、カジカ、マダラ昆布締め、カンパチ、マグロ、アブラコの骨煎餅、鮭のハラス。クラシックと焼酎で堪能。沖縄ならオリオン、北海道ならクラシックっしょ。 未消化のひとつ、函館山にも登った。「十字街」電停で降りロープウェイにて山頂へ。でも、始発はなんと10時! 函館の夜景を見なきゃいけないなあ~、などと思いつつも、なに、地元の隣町神戸の夜景だって見たことないのだ。「夜は酒!」である。 ロープウェイ駅の周辺は函館を象徴するもうひとつの顔、坂道がいっぱい。教会や寺が密集し、ある意味、城下町の寺町のようなエリアだが、武断的な顔はない。「元町教会」は、長崎の大浦天主堂とタメを張る荘厳かつ神聖な場だった。礼拝堂の椅子に腰かけ、しばし静謐な時を過ごす。 ベイエリアで赤レンガ倉庫群を抜け、「函館ビール」で社長ビール(正式名称は「社長がよく飲むビル」)を堪能。スコッチを飲んでいるようなモルトモルトしたビールが思いのほか気に入った。昼酒は旨いのだ。 2夜目は「ル・プティ・コション」。地場のフレンチ。シェフが筆者がたまに通う神戸の店のシェフと知己であるとの意外な世間の狭さに驚き、イチオシのグリーンアスパラを堪能。 |

| 特急「ゆふいんの森」は博多から久留米経由で大分に向かうレジャー特急だ。 久留米、大分間を結ぶ久大本線が電化されていないのでディーゼル仕様。大分が終点ではあるが、乗客の目的地はほぼ「湯布院」で間違いない。 全席指定でグリーンはない 概観はレトロなヨーロピアン調でデビューした89年からすでに22年以上たっているから、設計思想にかかわりなく実際にレトロだ。(車両は初代以外に2編成ある。2世、3世として建造され、3世は99年製だそうな)外装、内装(カ-テンもモックも)が由布グリーンと命名された深い緑色で統一されている。 ウッディな造りで床は懐かしくも板だ。天上と壁面の照明は丸い。連結部のデッキにあるゴミ箱も竹網のカゴという懲り方。 ハイデッカーなので車窓が通常の車両の屋根近くにあり、大きく切り取られた窓からの眺めがいい。乗客はドアのあるデッキから客席まで階段で上がる必要がある。だから、ワゴンを使った車内販売はない。車両連結部が橋のように繋がり、客室床面がフラットに隣車両と結ばれている構造も面白い。 4両編成の2両目にビュッフェがあり、3両目にサロン、車窓を愉しみながらビュッフェで買った飲食物を口にできる。 その日、かなり空き席が目立つ列車は、博多を出発したあと二日市、鳥栖、久留米で次々と客を拾ってゆく。気づけば、ほぼ満席だ。 皆、湯布院に向かっていることは間違いない。 乗客の地場率が高い。そこかしこで「けん、けん、ばい、ばい」言っている。 |
若い女性の3人組がシートを向かい合わせにしていた。久留米からスーツ姿のおじさんが乗車。 (あららら) 空いていた1シートはそのおじさんの席だ。 カールだのポッキーだのを食べながら箸が転がってもおかしいお年頃の3人組が突然押し黙る。おじさんだって居づらかろう。こういう組み合わせは悲劇だ。幸いホスピタリティあふれる車掌のはからいにより、空いていた2人席に移動できたおじさん。皆がホッとする。 久大本線は筑後川沿いに東進する。 耳納連山(みのうれんざん)が川の流れとともに車窓の友になる。斜面には雪が残っている。 筑後川は右に左に処を変える。 トンネルを潜り、やがてそのトンネルが連続し高原を走る列車の風情がいや増す。 一山越えたようだ。平地に出た。停車駅は「日田(ひた)」天領日田、九州一の繁栄を極めたと言われる街。心なしか民家の屋根瓦が立派に見える。雛祭りが有名なそうな。 湯布院までは、あと1時間弱 再び、トンネルが途切れることなく続くようになる。豊後3大温泉のひとつ「天ケ瀬」を過ぎてしばらく、名瀑「慈恩の滝(じおんのたき)」が車窓進行方向右側(C席D席側)に現れる。列車は心得たものでスピードを落とす。 「豊後森」駅では手前に山頂が平らなことから名づけられた伐株山(きりかぶさん)がある。 次の停車駅は目的地「湯布院」。 駅前に由布岳が聳え、欧風の景色を彷彿とさせるホームに2時間9分の旅を終え、列車は静かに停車した。 |


| 福岡県と大分県の県境にあって周防灘を臨む「中津」は、小倉から特急ソニックで2駅、30分ほどの距離にある。 竹中半兵衛と並び、秀吉の参謀役として活躍した黒田官兵衛(如水)が、秀吉から与えられた封地16万石の首府である。 官兵衛はここに新たな城を構えた。 中津川河口に据えられたこの城は水門から海水を引き込み、干満により堀の水位が変化する。 高松城、今治城と並ぶ日本3大水城のひとつ、中津城である。(出た!3大×城!) 官兵衛は、如水と号して後、関が原戦役に主力軍が出役し手薄となった北九州の大名領をさらさらと奪い取ってしまう。智謀の人、人生最後の大博打だったと言う説もある。歴史の神は、しかし如水に微笑まず、日本を東西に分けた大戦は1日で終結。領土をすべて家康に差し出し、彼の生涯はほどなく終わる。 黒田家の後、細川家、小笠原家が領主となり、その後、明治を迎えるまでの155年間、奥平家が中津城の最後の城主として藩政時代を司った。 つまり、中津は城下町なのである。 城の南面、中津川の反対側には寺町があり、戦時の城砦、あるいは駐屯地として機能するように街割りされている。叛乱した旧国人層を謀殺した際の血痕が消えないため、壁を赤く塗ったとの伝承が残る赤壁の「合元寺」や、河童の墓がある「円応寺」など古格な佇まいが今に残る。 譜代大名である中津藩、奥平家の下士の子として生まれたのが福沢諭吉。中津を代表する名士と言えば、この人が筆頭だろう。JR中津駅前にはちゃんと福沢諭吉の像がある。 |
駅前から城方向に伸びるアーケードの商店街にはあきらかに寂寥感が漂っている。九州のJRや私鉄の特急停車クラスの駅にしてナショナルブランドのハンバーガショップがないのはどーゆーことでしょー。(なぜかドーナツ屋はある) 中津駅前から日田行きのバスに乗る。 国道212号線を下ること30分。 「耶馬溪」の入り口「本耶馬渓」の「青の洞門」に到着。 耶馬渓は山国川とその支流に広く分布する渓谷で、本耶馬渓、深耶馬渓、 裏耶馬渓、奥耶馬渓・・・など複数のエリアに分かれている。 「青の洞門」は僧、禅海がノミで岩盤を削った隧道で、現在ではオリジナルは一部に残るのみ。国道が通るトンネルは後世の施設だ。そのトンネルを抜けると急峻な岩塊が頭上に覆いかぶさるように聳えたっている。 「競秀峰」と呼ばれる連峰だ。山国川沿いにそそり立つ岩盤はなかなかに見ごたえがある。 麓の駐車場脇に「妙見窟←約350m」と書かれた看板があった。競秀峰の一峰「妙見岩」の頂に岩窟があるらしい。いつものように衝動的に登ったら、いつものように後悔した。ハード&デンジャラス。そそり立つ岩塊の頂までほぼ直登のかなり急峻な坂を汗みずくになりながら登りきった。地上から見上げた頂が目の前にあった。競秀峰を縦走する道もあるらしいが、かなり怖そう。撤退した。(鎖場なんてのもあるそうな) 今回の耶馬溪行は、廃線となった鉄路をサイクリングコースに改修した「メイプル耶馬サイクリングロード」の下見のためだったのだが、何か疲労してしまい、目的を果たせずに撤退。無念。 |

札幌行4 →→→back 札幌行1 2 3 4 5 6 7 8 9
| 札幌は近時、金沢なみに「せっかく来たのだから」とあくせくしないですむ街と化した。 今日は、クリスマスの喧騒から逃れて来た。 イブの夜。行動計画は出来上がっている。 念のためグランメゾンのフレンチに電話をいれてみた。案の定というか、まさかというか「クリスマスメニュー」営業だと言う。札幌で1、2を争う有名店にしてこれだ。常なら一人で座るフレンチのテーブルも今日は好奇と猜疑の視線の集中砲火を浴びること必定。 当初の計画通り「さっぽろジンギスカン本店」に入る。 あたり!ガラガラだ。いつもと客の入りが全然違う。ほぼ独占状態でジンギスカンを消費。 食後はバーだ。今回は「バー・山崎」のお弟子さんシリーズ。「ドゥ・エルミタージュ」へ。 愉しく過ごして宿で熟睡。イブの夜はクリア。 札幌は周囲に低層の山が多いトレッカー垂涎の街だ。そうした山のひとつに藻岩山がある。札幌市民がこよなく愛する夜景のビューポイントでもある。以前、その眺望を愉しもうと市電で「ロープウェイ入口」駅まで行った。しかし、ロープウェイ改修工事中で営業停止状態だった。 その雪辱を晴らすことにしよう。 今回も「ロープウェイ入口」駅で下車。ちょいと歩くと目に付いたのはお馴染みの「ロープウェイ休止中」のサイン。 藻岩山と筆者の相性は限りなく悪い。 すすきのに戻り、交差点そばの「カレーショップ・エス」でスープカレーを食べる。 「北の味覚スペシャルカレー」は帆立、エビ、アスパラをはじめ北海道の味覚満載。 |
「ご飯はいらないから」と言って店員の不信を買うも、赤ワインのデキャンタ(500ml)を頼むことにより(食事じゃないんだ)ムードを偽装。 最近、昼酒に罪悪感がなくなってきた。困ったもんだ。辛さは、辛口と大辛の中間の「38口径」を指定した。 この店、辛さのランクを飛び道具で表現している。甘口から並べると「銀球鉄砲→BB弾→22口径→25口径→32口径(辛口)→38口径→357マグナム(大辛)→44マグナム→パトリオット→トマホーク→ICBM→アポロ11号」となっている。 和風だしのきいたスープカレーでイケル。 札幌駅前のシネコンで映画を見てからJRタワー展望室、T38に昇ってみる。 T38は「タワー・スリーエイト」と呼んでください。 AKB48以来、名称が判じ物化している。 AKBは秋葉原で、NBAが難波?SKEは名古屋の栄ですって?SDNはサタデーナイトでOJSがおじさんだぁ?さすがはヤリ手業界人の秋本康、あざとくたたみかけてくる。 T38の展望室はテレビ塔よりも高い。なかなかの眺望。たぶん藻岩山の代わりになる。 夕刻前。空はまだ明るい。展望室のカフェでコーヒーを飲んで時を過ごす。気がつけば、陽が沈み、眼下の市街にネオンが瞬き始めた。 美しい。 三度すすきの界隈に戻る。 「すし善本店」の孫弟子にあたるのだろうか、「棗(なつめ)」という寿司屋で夜を過ごし、今宵は「バー・プルーフ」へ。これまた山崎さんのお弟子さんの店。ここでも満喫。 |

| 水面は船端に近い。 手を伸ばせば掌に水を遊ばせることもできる。 船の推進は一本の竿によるのみ。 推進機のない船は静かだ。 川下りの船上からは見上げるような高さの川端を歩く人の姿もなく、年末までまだ若干猶予を残す町は初冬の、ややけだるい弛緩の中にある。 静かだ。 水郷、柳川は福岡天神から西鉄特急で46分の位置にある。 博多は市中に観光資源の少ない街だが、周辺には意外に多くの見所がある。 片道1時間圏内には、壱岐、志賀の島(含む海の中道)、唐津、門司、太宰府、秋月、糸島等々がある。 2度目の柳川。 1度目は名物の「鰻せいろ」を老舗で食べた。 店に入るまで行列に並び、入ってからもずいぶん待たされた記憶しかない。 生来、天の邪鬼の気味ある性格が災いして乗り合いになる川船は敬遠した。しかし、柳川と言えば川下りだろう。 余命の目盛りを省みれば、狷介な戯言に時を費やすよりは、名物を経験するほうが賢明との道理に気がついた。 水郷、柳川は柳川城を護る堀割りが市内を取り巻いている。その堀が古くは生活用水を提供し、運輸の要にもなり、今は観光の柱になっている。 川下りはその堀割4キロほどを行くのだが竿で推進する船だから70分ほどの所要時間を要する。 コースは片道コースだ。川を下ったら、終点の北原白州記念館そばから駅まで業者の無料送迎バスで帰ってくるか、有料のバスかタクシーを利用 |
する。無論、徒歩で帰ってくるという手もある。
往路を徒歩で水郷散策とし、復路を川上りで柳川駅に戻るという旅なれた選択肢もある。 西鉄柳川駅からほど近いところに、おそらくは川下り観光でも最大手の業者の船付場があった。 それをパスして中小の業者に乗ろうとしたが、人生はままならない。中小では、乗客が運行の採算点に達するまで船が出ない。定刻運航をしているのは大手なのだ。業者に促され、道を戻って大手の船に乗る。船底に尻をつけ、炬燵のような掛け布団をかぶった台に足をつっこむ。無論、船のこととて火力があるわけではない。(12~2月は火鉢を置くそうな、後で知った) ゆるゆると水郷を進む船は、途中12の橋をくぐり抜ける。長い竿を巧みにくりこみ、低い橋桁をくぐる船頭の竿さばきが楽しい。 堀の対岸に自家の庭を作り、川越しの景色を楽しむ風流な家もある。船着き場のある日吉神社では婚礼の際、新婦が白い船に乗って、披露宴会場「勝島」へ向かうそうな。「勝島」も式当日は川に面した入場口を緋毛氈で飾りたてると言う。 途中、1時間強の船旅に飽いた客を目当てに茶屋が待ちかまえている。甘酒やビールなどを物販している。茶屋には船が接舷できる仕掛けだ。店主の飼い犬だろうか、愛らしい奴が一匹、船端に顔を近づけてきた。 終点には水天宮や「御花(おはな)」と呼ばれる藩主の遊息地もある。ここの別邸はなかなかに豪奢だ。堀の周囲を柳が囲むこの界隈が、水郷柳川の写真によく使われている。 徒歩で駅に戻った。船より脚の方が早い。1時間もかからずに柳川駅についた。 |

| コスプレって楽しいっ!めっちゃ楽しいねっ!コミケの皆さんの気持ち、わかりました。 いきなりすいません。人生初コスプレのドーパミンがまだ乾ききっていないもんで・・・ 無茶振り企画の大家Fの呼集に応じて京都四条大宮に集合したメンバーは4名。 目的地は「東映太秦映画村」。太秦は、洛中から見れば北西方向にある。嵐電に乗って12分。 事前に予約した時間に指定の場所に赴く。 「すいません、時代劇スターになりに来ました」 扮装はその場でチョイスできる。 お殿様から遠山の金さん、水戸黄門の御一行、武蔵、義経、股旅姿、銭型平次、丹下作膳、旗本退屈男、暴れん坊将軍、柳生十兵衛、坂本竜馬、新選組などなど。 皆で語らい、新選組に扮することになった。 他の3名が隊士の装束を選んだので、筆者は土方歳三にした。変身扮装料が微妙に違う。 メイク、結髪、着付けまですべて「東映のベテラン専門家」が引き受けてくれる。 浴衣に着替えて、メイク室へ。 ドーラン塗りまくり、アイシャドーかけまくり。テープでグイグイとひっつめまくり。 目が釣りあがってゆく。 「目をあけていいですよ」との声に鏡を見る。 (しぃえぇぇぇぇぇぇ!) 己が顔ながら、怖いほどベタな時代劇顔。 田村正和でゆくか?大河内伝次郎でゆくか、今後のキャラ設定に迷う。(迷わんでええ) 「どれ、まいてゆこぉか」 衣装室で羽織袴に剣道の胴を装着。刀(ノサダ)を腰間にたばさめば、気分はもう新選組! |
4人全員の準備が整う。 映画村の時代劇セット内を1時間ほど自由行動ができるとのこと。 最初のうちは観光客気分でヘラヘラ歩いていたが、「すいません、一緒に写ってもらっていいですか?」同じ観光客から声をかけられ、「お安い御用です」と一緒に並んでパチリ。 言葉を交わしたところ、当方も観光客だとは思ってもいなかったことが判明した。説明してもなかなか信じない。 (なるほど・・・) その後も次々と声をかけられ、一緒に記念写真に納まっているうちに完全に映画村の人になりきってしまった。表情はキリキリと引き締まり、動作は鷹揚、口数少なく、どんどん反り返ってゆく。 4人皆、新選組の装束だったのがよかったのか。 ダンダラ羽織は時代劇ではテッパンの衣装だ。記号化していると言ってもいい。それが集団で歩いているから、みんなの記念写真欲求モードがハイになるとゆー図式だ。4人バラバラだとこうはゆくまい。殿様と金さんと鞍馬天狗と花魁が歩いていてもニーズは生まれない。 49年の生涯のたった1時間。人生で写した集合写真の数倍の写真に納まった。これだけ多くの記念写真に参加したのは初めてだ。(無論、赤の他人のアルバムに収められるのだ) 滅茶苦茶に面白い。 自分であって自分でないのだ。日常、過剰にすぎる自意識から開放され、他人を演じることによって誰かを演じてる誰かになってしまった。 ××と役者は一度やったらやめられないって、こーゆーことなのね。 |

| 今さらながらだが天橋立へ行った。 絵に描いたような観光地だった。 バス駐車場に次々と入ってくる大型観光バス。 そこから吐き出される無数のオジチャン、オバチャン。その大群に取り囲まれる気恥ずかしさはどう表現すればいいのだろう。まさに翻弄状態。 考えてみれば、筆者の漂泊先にベタな観光地は多くない。観光地に行ったと言っても雛が基本。 さらに言うと、実は都市部で旨いもの食って呑んだくれてることが多い。 「観光地へ」というのは漂泊ではなくスタンプラリーだ。一部のラーメンマニアみたいなもんだ。 そーゆー観光地はアダルト指数が高い。 オジチャン、オバチャンばっかり。しかもツアー主体。間違ってもAKB48はいない。あ、そんなこともないか。この間、薬師寺でAKB48のコンサートの設営を目にしたもんな。 アダルト観光に対峙するは、昔から「るるぶ」観光と決まっている。これまたうるさいことに違いはないが、最近の若い連中はすぐ海外に行っちまうからな。国内旅行なんてどーなんでしょ? やっぱ国内はオジチャン、オバチャンが主流。 綾小路公麻呂のステージを見にバスツアーでやってくる中高年の皆さんのよーな集団。 はあああ・・・・書いていて気が滅入ってきたなあ。今夜はオマールエビとワインにしよう。 閑話休題。 日本三景は「宮島」「松島」「天橋立」。 皆、テイストは同じだが、このみっつの中では天橋立が一番稼働に自由度がありそー。 第3セクターの北近畿タンゴ鉄道の天橋立駅の後背に「天橋立ビューランド」があり、モノレー |
ルかリフトで山の頂上に登れる。 そこから見下ろす天橋立は「飛龍観」と呼ばれ、股のぞきで見ると確かに龍が飛び立とうとしているように見える。写真にとったが、人間の錯覚を利用した光景だから、カメラに収まった画は普通に眺める画と同じ。そりゃそーだ。 ビューランドを降り、徒歩で天橋立を渡る。 観光船もあるが、これは渡り終わった対岸「一の宮」からの帰路に使えばいい。 天橋立は、内海の阿蘇海と外海の宮津湾の間に形成された周囲を松に囲まれた全長3.6キロの砂洲だ。この砂洲により両海は隔てられている。南側の砂洲を切り、2本の航路が確保されているが阿蘇海から外海の宮津湾に船が出るとき、回転式の橋で船の通行を可能ならしめている。その「廻旋橋」の袂に文殊菩薩を本尊とする「智恩寺」はある。 天橋立を渡る人は徒歩でもレンタサイクルでもOK。 歩けば小一時間で対岸の「一の宮」につく。 「元伊勢 籠神社」があり、その境内を抜けると対岸同様ケーブルカーとリフトが待っている。これで「傘松公園」へ上がる。 ここでもまた天橋立の景色を堪能できる。 もちろん股覗きもあり。 観光船で天橋立に戻り、特急「文殊」に乗れば、新大阪まで直通で2時間20分強。お手軽、お手軽。きっと関西圏の小中学校の社会見学か修学旅行先なんだと思う。 帰ってから知ったのだが、天橋立のオイルサーディンは土産物として珍重されているそうな。しくじった。 |

仙台行5 →→→back 仙台行 1 2 3 4(2006) 5
| 「エライ近いんですね仙台って」 東京から東北新幹線で仙台まで初めてやってきた関西出身のFが言う。 車両は「はやて」に連結された「こまち」だから東北新幹線の中でも最速。仙台までは上野と大宮にしか停まらない。所要時間は1時間40分で東京、名古屋間の「のぞみ」と大差ない。 「エライ単調な車窓ですねぇ」 Fは外を眺めるたびにため息をつく。 その単調な景色が距離感を奪うのだろう。東北新幹線は仙台までの移動の大半を関東平野の突破に費やしている。平野なんだから車窓は常にフラットなのはやむをえざるところだ。 相模平野を越え、丹沢山塊を抜け、伊豆のトンネル群と熱海でのオーシャンビュー、富士山の裾野を迂回し霊峰を望み、富士川、大井川、天竜川を跨ぎ、浜名湖を眺めながら名古屋に行く東海道新幹線の車窓の多彩さとは確かにエライ違いだ。 Fに限らず、関西人は東北地方については観念的な位置感覚しか持っていない。時間的把握ができていないから実にアバウトだ。 東京を出たら、仙台があって、その上が盛岡。青森がその上にのっかっている、程度の認識だ。 たぶん、宇都宮、郡山、福島は忘れ去られている。小山や新白川、那須塩原は認識すらない。 なに、関東人だって似たようなものだ。 神戸から先は岡山があって、広島があって、終点博多に到着、ぐらいの認識でしかない。 姫路や福山、新山口などは忘れ去られている。 厚狭(あさ)や三原、徳山は認識すらない。 関東人にとって関西のむこうは九州であるのと同様、関西人にとって関東のむこうは北海道だ。 |
「仙台で牛タンを食おう」という今回の目的は、西で言えば、「高松でうどんを食おう」とテイストは似ている。うどんの方が安いが。 とは言え、夕方に入仙して翌昼には帰らねばならない。夜と昼しか食べられないから、いきおいスタンプラリー的な酒食にならざるをえない。(筆者は朝は食べない。そこのところは、ひとつ) 口開けは、牛タンではなく牡蠣。 国分町の「かき徳」に行く。 ここは古い。筆者が初めて仙台を訪れた頃からある。あれは1981年だったから、少なくとも29年は営業していることになる。調べたら創業75年だそうな。ここの牡蠣豆腐が好きなのだ。牡蠣料理のオンパレードを堪能。 その後、2軒の牛タン屋をはしごした。 「味太助」と「利久」。 老舗中の老舗と成長著しい新興店。 81年に筆者が来たときは「太助」という名前だったように記憶している。創業者が亡くなって、息子と婿が店を分かったようだ。息子が継いだ「味太助」が昔ながらの店舗を使っている。 バーに行こうと、京都の「Bar Vespa」へ電話を入れ、I店長に教えを乞う。「The Bar an」を推薦された。オーセンティックな背筋が伸びるような佇まいのバーだった。 そこで寿司屋を紹介してもらった。 「龍匠」。朝4時まで営業している。 糖質制限の神様、お許しください。寿司を7カン食べてしまいました。 気がつけば3時。 翌昼、「The Bar an」のマスターから教えてもらった牛タン屋「司」で締めた。 |
金沢周遊行 →→→back 金沢行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
| 東南から北西にむかって、つまり内陸から日本海側に向かって左肩上がりに、3つの台地が伸びている。北からそれぞれ、卯辰山(うだつやま)丘陵、小立野(こだつの)台地、寺町台地と呼ばれている。 3つの台地間の谷は河岸段丘を形成し、その底部を浅野川と犀川が流れている。 高低差のあるこれらの土地を結ぶのは無論、坂道。まさに金沢は坂の街である。 老舗の薬問屋、醤油屋などが立ち並ぶ尾張町・博労町の先に神社がある。その後背に聳えるご神木の大ケヤキの脇から「くらがり坂」というあまり日当たりのよくない物寂しい坂がある。狭くて暗い、しかしどこか懐かしいその坂を下りると浅野川ぞいの主計町茶屋街に出る。尾張町の旦那衆が花街の主計町へ通う裏道であったことが分かるしかけだ。浅野川ぞいを「中の橋」まで風情ある家並みが続く。 中の橋を渡り、対岸で浅野川をわずかに遡上する。少しだけ川から離れ、しかしすぐに右折すると、道は東茶屋街に通じている。 背後に背伸びしているのが卯辰山丘陵。山麓には寺院群があり、城下北面の守りを担う。 茶屋街中に銭湯と「自由軒」がある。ファミリービジネスの洋食屋だ。筆者が最後まで飽きずに食べられたハヤシライスはここしか知らぬ。 茶屋街を抜け細い路地をいくつか曲がると再び浅野川に出る。風情のある「梅の橋」がかかっているはずだ。お彼岸の一日の深夜、梅の橋、中の橋など浅野川にかかる7本の橋を無言で渡る神事がある。「七つ橋渡り」と言う。9月の金沢を彩る行事だ。 梅の橋の上流「天神橋」の右手を行けば大きな通りにぶつかる。百万石通りである。金沢城の周囲を一周する周回道路だ。 百万石通り沿いに時計回りに歩けば、周囲は法曹関連の事務所、裁判所エリアになる。つまりお城下ということだ。城下町の法曹関係施設は全国ほぼ一律、大概このエリアにある。 百万石通りはやがて兼六園入り口、金沢城石川 門下に出る。 3つの台地のうち、中央にある小立野台地の先端部に金沢城と兼六園はある。兼六園は戦時には兵員駐屯地の役割を担う。兼六園と石川門の間、堀下を潜るように百万石通りは繁華街香林坊にむかっている。途中、兼六園坂下の脇に小辰野台地に上がる広坂がある。 広坂を上り、道なりに歩を進めれば、小辰野通りだ。直進すれば金沢大学付属病院があり、その正面には五木寛之が通ったというおでんの「若葉」がある。さらにその先に天徳院があり、徳川家から迎えた姫君珠姫を奉っている。グリル「ニュー狸」や「千取寿司本店」、蔵元「福光屋」はい |
ずれもこの通りの界隈にある。 広坂に上らず、香林坊にむかう右手のレトロな赤レンガは旧制四校の建物で、現在石川近代文学館として開放されている。金沢が生んだ文学者、徳田秋声、泉鏡花、室生犀星、五木寛之らの資料が展示されている。伝統の旧制三校(京大)との南下戦資料もある。 左手は、輪島塗や九谷焼の取り扱い商がいくつか並び、その中の1軒「漆の木」の4階で「抹茶かき氷(白玉ミックス)」を愉しむのが、訪沢時の筆者の習慣だった。 東急の109、百貨店ダイワの前が香林坊だ。 金沢最大の繁華街。 片町と呼ばれる飲食店街が左手に広がる。 「乙女寿司」「宇宙軒」「バースプーン」「小松弥助」「おでん高砂」「おでん三幸」「グリル大塚」などがある。 香林坊を左折すれば犀川に出る。 昭和3年施工の犀川大橋のレトロな姿と、対岸の橋詰にある3階建の木造建築、定食の「寺起屋」を眺めてその先は寺町台地に上がる坂となる。右手に西茶屋街と左手に寺町が広がる。寺町には忍者寺の名で親しまれる「妙立寺」がある。戦時には城下の前線防御陣となる砦群の役回りを担う寺社の中でも、最も戦時想定の意匠をこらした寺だ。さまざまな工夫が忍者寺と呼ばれるゆえんだが、忍者がいたわけではない。 香林坊に戻ろう。百万石通りを離れて、ゆるい坂下に向かう。鞍月用水のせせらぎに耳をかたむけ、さらに進むと大野庄用水がある。金沢は用水の町でもある。大野庄用水よりも百万石通り側の区画が長町。武家屋敷街だ。冬になると壁のまわりに「こも掛け」をして雪よけとする。 長町を流し、百万石通りに戻る。 北国新聞の社屋は、金沢のランドマークのひとつかもしれない。すぐそばに「おでんよしぼう」がある。 北国新聞の先、金沢ニューグランドホテルの前にあるギアマンのステンドグラスが美しいハイカラな神社は尾山神社。加賀百万石の始祖、前田利家・松夫妻を祭神とする神社だ。 百万石通りをさらに進むと香林坊と並ぶ金沢の繁華街「武蔵が辻」界隈に出る。 名鉄エムザがある。武蔵が辻スカイビルもかつての金沢のランドマークだった。その足元に広がるのが昨年改装なった近江町市場。 武蔵が辻を左に下れば、金沢駅。 駅構内の商業モール百万石の中に「おでん黒百合」がある。「ぶどうの木」のレーズンサンドを購入するなら、黒百合そばの販売所で。レストラン部門はあまりすすめられぬ。 兼六園や金沢城に入らなければ、2時間程度で周遊可能な速攻観光コース案内でした。 |
| 夏が終わる前に今年最後のダイビングを。 うきうきと週末ダイビングを計画して那覇に降り立った筆者を待ちうけていたのは1本の留守番電話だった。 「ダイビングショップ××です。台風9号が発生して沖縄に向かっています。明日のボートダイビングは申し訳ありませんが中止になります」 終わった。 筆者の夏が終わってしまった。 沖縄に向けて飛び立つまでは熱帯低気圧だった雲の渦がちょっと目を放している間に立派な台風に成長してしまったとゆーこJo※▲ちょだ。 (すいません。あまりのショックに打鍵が乱れてしまいますた・・・あ、また乱れた) ここ3年、台風なんぞかすりもしなかった沖縄本島に、なぜ今年は続々と台風がくる? 本島西方40キロに浮かぶ慶良間諸島の端、本島との中間点にある無人の環礁群、チービシ。そのひとつクエフ島周辺での体験ダイビングは、パーになった。パーである、パー! 失望はでかかったが、翌夜には最接近するという台風情報にちょっとワクワクする。(不謹慎) 来阪9年、それ以前の東京生活も含めて台風の直撃というのは遠い過去の記憶でしかない。子供の頃の話だ。沖縄で台風直撃はデッケー自慢話のネタになるぞ。ワクワク。(不謹慎) 夜、国際通りの「波照間」で地場の肴(ラフテー、珍味五豆腐(アーサー、島らっきょ、肉味噌、イカスミ、スクガラスを乗せた一口大の島豆腐)、ゴーヤーカリカリリング揚げ、ゴーヤーチャンプルー、アグーのスペアリブピバーツ塩焼き、豆腐よう、モズク酢の物、ナーベラーンプシー)でオリオンと泡盛を飲む。翌朝のダイビングがないのだから全開だ。 都合3回の三線ライブも消費。 もし直撃ということになれば、交通機関もストップするだろうから遠出はできない。 店だって開けるかどーかわからないが、ダイビングから酒食に訪沖のメインテーマに置き換えることにしたのでガッツを入れて予約を入れる。 初見の店を増やすことにした。 「波照間」「りゅうび」「あだん」「てだこ亭」「カフェ・マファリ」「ジャッキーステーキハウス」「バー・ステア」「バー・グラス」「アメリカン食堂」「焼肉華」「首里そば」これら那覇でのルーティンワークははずす。 「呉屋てんぷら店」の魚てんぷらと「松原屋製菓」のバタークリームショートは残す。 翌昼、時折、叩きつけるような風雨に見舞われながら、それでも、台風の接近はどこか遠い話ぐらいの天候の中、とことこと辻のステーキ街に向かう。 午前11時の開店を狙って「ステーキハウス88本店」か「ジュージレストラン」を目指す。 開店時間を勘違いていたのか88は開店していたが、ジョージは閉まっていた。選択の余地なく88に入店。国際通りの支店で不満足な経験をしたことがあるが本店は未訪だった。特上サーロインS(250g)にタコスも2個食べちゃった。スーチカー、オリオンと赤ワイン(ハーフ)。 店を出ると、ジョージが開店していた。 入店。 フィレミニョン200g、タコス2ピース、赤ワインをグラスで2杯。 ここは、ステーキハウスの定番、プレートのじゅわじゅわがない。かねてより、あれは火が通り過ぎるんじゃないかと思っていたのだが、火が通り過ぎないようにとの気遣いからなのだろうか。ガーリックはちょっと強すぎた。タコスはさっきの88と同様少しシナっとしている。肉肉しさはこっちが上、サルサソースもこっちが筆者好み。88は少し甘くてケチャップテイストが強い。 国際通りに戻り、「ぶくぶく茶屋・琉球珈琲館」でぶくぶく珈琲を1杯。 ここに来なければ那覇に来た気がしない。 夜、もしかしたら店を開けないかも、そのときは携帯に連絡しますと言われていた「ラ・コール」を訪店。 雲の流れはさすがにすさまじく速い。嵐、接近の気配が濃厚。 店は、ちゃんとしたフレンチだった。 |
ワインセラーにはワインがすらり。サーブもしっかりしている。ガツン系の皿はないが、また来ようと思った。ビルを見たらサービス料がかかっていないのも好感度を上げた。いいね。 翌昼、やちむんを散策。途中、すさまじい風雨に見舞われ、ショップに雨宿り。 壺焼きを眺めて時を過ごす。人間国宝となった金城次郎氏を頂点に一族の作品を見比べるのも面白い。息子の金城敏男氏の図柄は父の作風をしっかり受け継いでいる感じ。ただし、その息子(つまり次郎氏の孫)の金城吉彦氏の図柄の方が筆者好みの柔らかさがある。 カラカラを買う気になった。泡盛を入れるとくりのようなものだ。ついでに陶器のような風合いの琉球グラスも。家で泡盛を楽しもう。 猛烈な風雨は通過したはずの台風の巻き返しだろうか。弱まった一瞬を逃さず、アーケード街に退避。その直後、ふたたび雨勢が増し、アーケードの天井をものすごい音をたてて雨がたたいている。排水の樋から吐き出されるジェット水流のような雨水は、ところによって樋をあふれ滝のように店頭に注いでいる。 三越前の「碧」でコース料理を。 肉の種類で値段が異なる。青パパイヤの突き出しとサラダ、エビ2尾、南城産黒毛和牛特上サーロイン、野菜スープのコースを頼む。 鉄板焼きの店だが、店員は全員女性。 本店は久茂地にあったが、9月中旬、銀座三越出店にスタッフ総出のため、店をたたんでしまった。那覇にはあと3店舗ある。 エビの焼き具合がいい。甘い。殻と頭をぐいぐい鉄板に押し付けてエビせんべいを作る。 ステーキは半身を焼いた後、脂身のそぼろを刻み始める。ゴーヤチャンプルーに入れると香ばしくなるとのこと。新宿「善庵」風にさらに細かく刻んでもらいパンに挟んで食べてしまった。 島豆腐、紅芋、たまねぎ、ピーマン、ゴーヤチャンプルーなども焼き、ポン酢で。 パン4個を消費し、さらに「特上サーロイン(石垣産)」を追加。沖縄ぜんざい、コーヒー、オリオン瓶1本、コートデュローヌ赤1本。 それにしても、どこまで食う? 夜は「hana」へ。 地場密着系のイタリアンだ。ポーションがでかい。島豆腐とトマトのカプレーゼ、県産豚中味(ナカミー)のトマト煮込み、真サバのフリットプッタネスカソース、エビとマッシュルームのガーリックオイル煮、生ビール、カヴァ1本。 小上がりのようなテーブル席が3つ、フロアーのテーブル席が3つ。こじんまりしている。 テーブルウォッチはない。 フロア担当の女の子は厨房とテーブルの間をもっぱら配膳のためだけに行き来する。その瞬間をとらえて、まとめてオーダー。 シェフはひとりだろうから、逐次オーダーよりも一括発注の方がサーブはいいだろう。無論、全品が一気に並んでしまう信じがたい店もあるがここはなぜかそんな感じがしなかったし、そのとおりでもあった。ここもまた来ようと思った。 帰阪の昼、やっぱり「ジャッキーステーキハウス」に寄る。アメリカ占領時代の1953年から開業、米人に飲食を提供するための認可「Aサイン」を得た店。 テンダーロインSサイズ、ニュヨークステーキSサイズ、タコス2ピース。 3軒のステーキハウスで、タコスが一番パリパリしていたのはジャッキーだった。 サルサも筆者はジャッキーが一番好きだな。 ジャッキーのタコスはチーズの細切りがたくさん乗っている。 これがまた旨い。 「あ、ハムエグもください」 この店、メニューは英字標記に日本語標記がルビされているのだが「ham egg」は「ハムエグ」となっている。「ッ」は省略。 当然、ベーコンエッグは「ベーコンエグ」 なんかいい。 オーダーを聞きにきたネエネエには「ライスもパンもスープもいらないからねと毎度おなじみの決め打ちを。 あ~食った、食った。 |
盛岡行4 →→→back 盛岡行 激闘わんこそば編 ソウルフル編 盛岡行4
| 梅雨明け以降の連日の猛暑には辟易していた。 涼を求めてエアで東北へ逃亡。 着陸地点の秋田は豪雨に見舞われていた。上空から覗く雄物川の水位はまさに喉元一杯。実際、ところによって泥色の濁流が堤防を越えてしまったらしい。秋田新幹線は冠水により運休。空路を選んでラッキーだったのだ。 夜は「和食すがわら」で過ごした。 きっぷのいい大将と、グラスが空くのを瞬時も見逃さないおかわり上手な女将さんの店。2回目の訪店で、前回、次に来たら教えてくれると大将が約束してくれた白いコーヒーゼリーのレシピを開陳してもらい後顧の憂いなく秋田を後にする。 今回の逃亡の主目的地は秋田ではない。 魔に魅入られたように田沢湖にふらりと立ち寄り、古傷を全開させてしまう過ちを犯しつつも筆者は着実に盛岡に近づいていった。 秋田新幹線と言うが、新幹線らしいスピードで走行するのは盛岡、東京間のみ。秋田、盛岡間は田沢湖線在来特急のスピードでしか走れない。 車窓から臨む周囲の山襞にからまるのは水煙か霞か。時折、雲が薄くなり陽光が勢いを取り戻しかける。しかし、すぐに幾重にも重なる雲のヴェールに隙間を埋められ日中とは言え薄暗い。 翠の山々を潤す雨と上空にたちこめる鉛色の雲 になぜか心が安らぐ。 昼前に盛岡着。 6年ぶりだ。前回も6年ぶりの訪問だった。彗星のように6年ごとの周回軌道を描く筆者の人生。 「パイオニア牧場」で岩手短角牛を食べる。 脂身の少ない、赤身主体のステーキが筆者好みだが、聴けば、経営が変わってしまったそうな。 |
かつては、牧場とレストランを兄弟で経営していたはずなのだが… 月日と共に人生も変転する。その流れは押しとどめようもない。いつのまにか盛岡駅に「ビアードパパ」が出店していた。 過去を懐旧するために探した、ほぼ100%のフルーツゼリー「北の旬絞り」を見つけたときの安堵感は何なのだろう。 仙台同様、盛岡もまた杜の都だ。 ミニ東京然とした仙台よりも適度に雛な盛岡には旅人の孤独な心を慰める優しさがある。いつものように開運橋で北上川を越える。川上の岩手山が迎えてくれる。城下町の通例通り、繁華街は盛岡駅のそばにはない。盛岡城跡を含む街の中心部は駅から徒歩15分程度の距離にある。 盛岡城跡には天守閣もないし郭すらほとんどない。何もないことのあらまほしさよ。 南部鉄の風鈴の涼やかな音が街中に響き渡る。 今日は「さんさ踊り」の初日だ。 徳島阿波踊りの連のように、チーム編成で独特のかけ声と太鼓を音頭に優雅な舞いを繰り返し目抜き通りをパレードする「さんさ踊り」。踊り手個々が太鼓を胸の前に抱えるように背負い込み、たおやかな所作の踊りと相まって勇壮にして艶なり。 「南部どぶろく屋」でどぶろくを傾けながら、雲丹やほや、陸奥の味覚を楽しんで宿に帰る。 テレビからは盛岡「さんさ踊り」のニュースが流れている。それを見ている間にも窓の外から「さんさ踊り」の鐘と太鼓のライブ音響が聞こえてくる。 渦中にある実感が旅先での漂泊感を癒す一瞬。 |

| 財団法人日本城郭協会というのがあるらしい。 そこが日本三大山城サミットを開催しているらしい。 そのサミットには日本三大山城を擁する市町が参加しているらしい。 「らしい」の3連発で、どーにも歯切れが悪くてすいません。いつの間に日本三大山城なんてものが世間での合意形成を得ていたのかがちょっとふに落ちなくて。筆者は何も聞いてなかったし。 皆さん、日本3大山城をご存知でしょうか。 (え~と、備中高梁城は間違いなく入るな…) 鉄道マニアではないがお城好きな筆者は、脳裏に幾つかの城を思い浮かべた。 (う~んと…岩国城も高いとこにあったよな。それからやっぱ稲葉山城(岐阜城)も山城だ…あ、播但竹田城も典型的な山城だし…嗚呼壮烈岩屋城もあったな) なかなか、みっつに絞り込めない。そもそも3大山城の定義がつかめん。標高順なのか?規模順なのか?建造年順なのか? 正解は、美濃岩村城、大和高取城、備中松山城だそうです。(備中松山城は高梁城のことね) 1個当たり。あとははずれ。なんだか悔しい。 何で?という疑問には、各城がそれぞれ日本一の特徴を持っているからだそうな。 岩村城はまさに日本一高い城らしい。(標高721m)。高取城は、城下町から城までの標高差が日本一らしい。(446m)高梁城は天守閣が現存する城としては日本一高いところにあるかららしい(標高430m)。 なーんか我田引水っぽい話だ。でも、ま、いいか。世間は広く、山城は高いちゅうことだ。 |
とにもかくにも三大山城のうち高梁城しか攻略していないことが発覚した。こりゃあいかん。さっそく攻略計画を立てた。この時点で、すでに三大山城を認めてしまっている筆者。実に素直な好青年ではないか。 攻撃目標は、大和高取城に定めた。 岩村城は思いつきで行くには遠すぎる。名古屋へ出て、中央本線乗って恵那から明智鉄道に乗らなきゃあならん。 高取城は奈良にある。 奈良にはあるが、かなり下(南)の方だ。 地下鉄御堂筋線で天王寺へ。近鉄阿倍野橋駅から吉野行き特急2両編成に乗車して「壺阪山」駅で降りる。そんな駅、もちろん知らなかった。 11:30には侵攻開始。 石畳の細い道が続く。道の周囲は城下町を思わせる佇まい。山辺の城下町、と言うと九州の秋月を思い出した。どことなくテイストが似ている。 途中、すれ違ったお婆さんに会釈。 「お城に登られますの?」 「はい」 「たいへんやねえ。頑張ってください」 ほんわかした気分で城下町を離れ、斜度のきつくなった道をひた進む。 重力に逆らう辛さはいつもと同じ。着衣は完全に吸水力を失っている。繊維の先まで汗みずく。 標高584mの高取城、征服。13:10。 城域は広い。石垣しか残されていないが、その石垣も立派だ。よーこんなとこまで巨石を運んだもんだ。 明治24年まで城が残されていたらしい。写真が現存している。かなり立派な建造物だぞ。 |

| 石垣島の離島ターミナルから安栄観光と八重山観光、ふたつの船会社が周囲の島々へひっきりなしに高速船を送っている。 活発なその光景は、スターウォーズに出てくるモス・アイズレー宇宙港のようだ。 エメラルドグリーンの海の上、ジェット水流を猛烈な高さにまで噴出させ高速船が往来する。(プロペラ推進の船でも40ノットで航走する) 西表島に向かった。いつものように完全に思いつきの行動で計画性は皆無。下調べゼロ。 40分程度で上原港に接岸した。 西表島には上原と大原の2つの港がある。 あてにしていた観光案内所やそれに類する施設は何もない。タクシーが1台だけ停まっていた。 観光はやっておらず賃走だけとのこと。 無計画のつけは何度も払っている。いつかこれで命を落とすかもしれないと思うときがある。 船に乗っていたのは、島人以外は船会社がセットした西表観光パックのツアー客ばかり。 「Bコースの人・・・Wコースの人・・・」ガイドが船から降りてくる客を各観光ポイントへ移動する送迎バスに振り分けている。「一般のお客さん」と呼ばれた筆者は、自力で何とかするしかない。タクシードライバー氏のお勧めに従って滝見物のできる浦内川まで行くことにした。 先発したパックツアーのバスとほぼ同着。タクシー営業所の名刺と路線バスの時刻表を貰って降りる。 浦内川を遡上する観光船に「一般客」として乗船。乗船者は39人。38人はパックツアー。 30分ほどマングローブの群生する川を遡上し、上流の船着場についた。周囲には何もない。ここから片道45分のトレッキングで滝を見に行く。 |
お迎えの船は12時30分にやってくるとのこと。 密林の山登りがなしくずし的に始まった。 覚悟も予想もしていなかった展開だ。 シダに覆われた渓谷沿いの道幅は時に狭く、地面は泥に覆われている。樹木に視界を遮られているが足を踏み外せば、樹木のトンネルを潜り抜け川床へ滑落しそうなポイントもある。 怖くね?これ。 目指すカンピレーの滝の前にあるマリュドゥの滝は滑落事故が発生して閉鎖されたとのこと。 怖くね?それ。 パックツアーの人達をぐんぐん引き離して、ひとりジャングルのような道を登り続けると、不意に視界が開け滝のある河岸に出た。 幾重にも重なる棚状の岩場を滑り落ちる水流が陽光をはじいて輝いている。 帰路、ツアーご一行様とすれ違う。「あと少しですよ」先着の優位さをにおわせながら励ましの声をかける。 高齢者が多かったせいか、時間設定が過酷だったせいか、迎えの船が出発する刻限を過ぎても乗船してきた39名が揃わない。 「待ってもいいですか?」とのスキッパーの言葉に頷かなければ器量を問われる。「一般客」の筆者は待ってくれるツアーバスがあるわけじゃない。路線バスが待機してくれるとは思えない。 予定より10分遅れでメンバーを収容した船は川を下った。船着場のそばに路線バスの停留所があり、接続もよく10分待ちでバスが来た。山原港に戻ると高速船の接続もドンピシャ。 思いのほか泥だらけになった靴とズボンをぱたぱたとしながら主島石垣に戻った。 |

| むき出しの想い出というのは体によくない。 せめて毛布でぐるぐる巻きにして向かいあった方がよい。 18の歳から漂泊を続けてきた筆者は日本各地にからだによくない生(なま)の想い出が埋葬されている。歳ふり、その地を再訪する際、都市部であれば消費行動を過去と変えることで目をそらすことができる。もともと二十歳そこそこの若造の活動範囲などたかがしれている。行く店だって、移動手段だって今とは全然違う。つまり埋葬した過去の遺跡に触れずに今を生きてゆける。 でも、雛はいけない。 目をそらす物が何もない。昔日と同じ行動をするしかない。すると、癒えたと思っていた傷口が開いて大量出血で気を失うのである。 な~んで降りちゃったのかしら、田沢湖線「田沢湖駅」。駅舎は新しくなっていた。あたりまえか。指折り数えて28年ぶりだ。 湖は田沢湖駅から車で20分程の距離にある。昔は周辺住民の生活必需品を一手に担う「スーパーTakayanagi」なんかなかったように思う。途中にある「山のはちみつ屋」も同様だ。韓国ドラマ「IRIS」でカーチェイスシーンを撮影した交差点を過ぎる。ローソンがあった。田沢湖を擁する秋田県にはセブンイレブンは今のところない。 幹線道わきのアイスの辻売りは「ババヘラ」と呼ばれる。会社の車におばちゃんを何人も乗せて拠点ごとに降ろし、アイス販売をさせ、夕方、また全員を回収して戻ってくる。おばちゃんがヘラでアイスをすくうからババヘラ。 田沢湖には白浜と潟尻という2箇所の観光拠点がある。湖はほぼ円形のカルデラ湖で周囲は約20 |
キロ。白浜・潟尻間はちょうど真反対の位置にありその間約10キロで右回りをしても左回りをしても所用時間は変わらない。観光船は白浜を拠点としている。何便かに1便は潟尻にも接舷するが、乗り場はコンクリートの突堤にすぎない。 28年前は白浜に泊まったが今回は潟尻の「田沢湖ホテルエルミラドール」に旅装を解いた。 雨が断続的に降っている。 湖の主「たつこ姫」の黄金像が水位の上がった湖面に浮かんでいる。 白浜への遊覧船に乗ってしまった。28年前に埋めた触れてはいけないタイムカプセルを掘り起こしに行くようなものだ。危険な話だ。 白浜について湖畔の遊歩道を歩く。 かつて投宿した「湖心亭」は変わらずにそこにあった。ボート乗り場もある。昔もあった。こういうボートはカップルのためにしか存在しない。 田沢湖は独特の瑠璃色をしている。水深423.4mは日本一の深度を誇り透明度も高い。28年前、ボートから湖面に投じた10円玉がいつまでも消えずにゆらめきながら沈んでゆくのを見続けた記憶が蘇る。 断続して降り続く雨脚が強くなった。 いつのまにか小椋佳の「さらば青春」を口ずさんでいた。 甘いと言うよりはほろ苦い懐旧の念に包まれてしまった。 (ここに来ることはもうないだろうな) きっかけもなく不意にそう思った。 すでに雨がやんでいることにも気づかずに傘を差したままぼんやりと歩き続けていた。 やっぱ雛は危険だ。体に悪い。 |
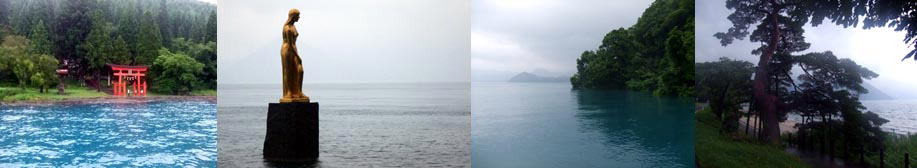
| 盛岡から東北新幹線の各駅停車「やまびこ」に乗って東京方面に一駅「新花巻」で降りた筆者。 「・・・」 何もない。 「岐阜羽島」より何もない。 下りエスカレータもない。 エレベーターは、『改札の外に出てしまうためドアを開けるのに周囲の駅員に声をかけてください』と貼り紙がある。ホームに駅員の姿はない。下に降りて、もし駅員が外にいなければ閉じ込められるのか?実に怖い。かなり長い階段をキャリーバッグを抱えてえっちらおっちらと降りた。 駅には送迎バスがやってくる。20分で今回の目的地「花巻温泉」だ。湯煙とともに深山渓谷の気を吸うのだ。温泉旅館が苦手と何度も書いているが、最近、嗜好が変化した。たま~に大浴場や露天風呂で四肢を伸ばしたくなるときがある。 「花巻温泉」のゲートを潜ると、ホテルが立ち並んでいた。バスはゲートに近いホテルから順に停まってゆく。ほぼ満席だった客席が幾つかのホテルを過ぎてだんだん空いてゆく。最後は筆者ともうひとりのみが残された。 温泉郷の最奥にある「佳松園」というホテルが今日の宿だ。 広い敷地に平屋建てのような造りだが実は4階建てとわかったのはチェックイン後のこと。フロント階は最上階の4階にあたり、3階以下は渓谷の底部にむかう地下階のような造りだった。無論渓谷面にむかって開放されている。 せっかちな筆者にしては珍しく、ゆったりした造りの客室に入り、何もしないことにした。無論テレビなんかつけない。 |
宿のそばに滝に面した遊歩道がある。ぶらりと向かう。遊歩道の入り口に貼り紙があった。 「本日、「釜淵の滝」付近にて体長1mサイズの熊が目撃されました・・・単独での散策等をお控え頂くようにお願い申し上げます」 熊さんに出会った歌を歌いながら宿に帰った。 夕刻前に大浴場に向かう。 広いガラス壁のむこうに景観を望めるホテルで最大の過ちは夜、風呂に浸かりに行くことだ。日が沈んだら、何も見えなくなる。 夕食。 前沢牛と白金豚のしゃぶしゃぶがあった。白金豚は花巻が主産地だそうな。岩手だとは思っていたが、花巻とまでは知らなかった。牛も豚も県産品だ。殻付きウニも甘くて旨い。さすがは三陸。 宿泊客は皆、上品だ。夕食と言えども、長居はせずにきれいに席を立ってゆく。 ビールを呑んで、スパークリングを1本空け、焼酎を呑んで、いつまでもだらだらと居続けるのは筆者のみ。最後まで接客してくれたのは女将さんだろうか。翌朝、実に何ともにこやかな挨拶をうけ、おもてなしされた感に包まれた。接客業の見本のような挨拶だった。これだけでまた来たくなるから人の世は面白い。 深夜の大浴場には誰もいなかった。完全に独り占め。早朝にも湯に浸かり、唸り声をあげる。湯につかって唸るようでは筆者の余命も長くはあるまい。 帰りは仙台まで。各駅停車の「やまびこ」で1時間弱。それにしても、東北新幹線、駅の数が多いな。そして駅間が短い。しかもどの駅も田んぼの真ん中にあるんですけど・・・ |

石垣島行(5) →back (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
| ホテルの前から市街地への向かう道路は、その昔、波打ち際だったそうな。埋め立てによって出来たらしい。埋め立てしなければならないほど市街地が膨張したとも思えない。何故?と問えば、港の水路建設の掘削土の捨て先だった由。 石垣港は遠浅のためその昔、船は沖合いに停泊していた。はしけを利用して港と船の間を結んでいた不便を解消するために水路建設をしたのだとか。乗車したタクシーで聞いた話だ。 「今年は、台風もまだ来ないねえ」 タクシードライバー氏はのんびりと謡うように話す。 「去年も台風はふたつしか来なかったし、温暖化の影響か、島を直撃する台風が減ったね~。今年もひとつ発生したけど、それちゃった。それ以降の台風は、最初のコースと同じようなコースをとることが多いから今年も少ないかもよ~」 助手席に三線を置いて、赤信号になると島唄を聞かせてくれるドライバー氏の話が弾む。 試してみてと渡された三線をつまびいているとなぜか心が安らぐ。西洋音楽の8音階の慌しさに比べ、3音階の三線の緩さが都市生活で荒んだ心に潤いを与えてくれる。メロディにならずともその音だけで癒される。 「夜、眠れないと三線をつまびくの。そーするとコロッと眠れるよ」 このタクシーには島滞在中、もう一度乗車することになる。離島ターミナルで乗車した瞬間、「お客さん覚えているね~」と言われて「三線の人じゃあないですか」 やっぱ、島は狭い。 朝、向かえの車に揺られ、マリーナへ。 |
22人乗りのクルーザーは、ショップの2人とダイバー3人、体験ダイビングの3人を乗せて川平石崎(かびらいしざき)を目指す。 マンタスクランブルと呼ばれるほどマンタとの遭遇率が非常に高いポイントだ。 体験ダイビングでは、流石にそこで潜らせてはもらえなかった。シュノーケリング。素もぐり禁止、マンタに触れちゃいけない。マンタにすっごい気を遣っている。もちろんルールは遵守。 水深は8~15mほど。 ライセンス保持者が海中で待ち構える円陣の内環に浮かんでマンタを待つ。 ちゃぽちゃぽしているうちに来たね、マンタ、それも次から次へと何匹も現れ、回遊している。 堪能させてもらった。 潜りは御神崎の周辺で2回。 初めて石垣島に来たとき、この岬の灯台の下からエメラルドグリーンの海を眺めていた。白い航跡をひきながら岬に近づいてくるクルーザーの群れを非日常として堪能した記憶が鮮やかに蘇る。 あの頃はダイビングなんぞやることになるとは微塵も思わなんだ。岬から海を眺めた2ヵ月後、冒険野郎のFの引き込みで体験ダイビングを経験した。そして3年後の今、眺めていた船に乗り込んでいる自分がいる。 先のことは誰にもわからない。 夜、「竹茂(ちくも)」に行く。 京都祇園の店からのれん分けされたという、串焼きの店。可愛い奥さんときりっとした若い大将が営んでいる。 「本店に行っても何も出ないと思いますよ」 気さくな大将がからりと笑いながら言った。 |

石垣島行(4) →back (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
| 梅雨の中休みといった好天の東京を巨人機(ボーイング747)は飛び立った。 大きく右バンクしながら上昇を続ける機から思いのほか大きな富士山の特徴的なシルエットが捕らえられた。6月もあと数日で終わるというのに山頂にはまだ雪が残っている。よく見ようと目をこらした瞬間、雲の幕が割り込んで瞬く間に白い混沌の中。 梅雨前線を越えるとき、気流が乱れ、機体が上下左右に大きく揺さぶられた。慣れてはいるが気持ちのいいものではない。 やがて機は高度を下げ、雲中を抜けた。 海が見えた。まだ中空に高い太陽の、雲間から零れ落ちる陽光が海面に銀色の斑を作る。期待をしていたエメラルドグリーンの輝きはなかった。 那覇で一泊。 夜は「居酒屋りゅうび」へ。 ゆいレール沿い久茂地川の端に店はある。県庁前と見栄橋の間だ。突き出しに「うずらとミニトマトのベーコン巻き串」が出てきた。これ、筆者好物。突き出しだけで幸せな気分になる。 「りゅうび元祖ソーキ網焼き」は、商標登録番号5080135号で時価とある。甘めの味付けはやや苦手な部類だった。なーべーら味噌煮(ヘチマと豆腐の味噌煮)とスクガラス豆腐、もずくでオリオンの生と泡盛「咲元」を消費。沖縄にいるのだ感に包まれた。幸せなひととき。 翌昼、旭橋の「ジャッキーステーキハウス」でパンもライスもスープもサラダもいらんからと、テンダーロインステーキS150g、ニューヨークステーキS200g、ハンバーグステーキS200gを食べ、オリオンの生を飲み、店のネエネエの失笑を背に |
石垣へ飛び立った。 3度目の石垣島。 07年、08年以来2年ぶりの訪問だ。 1週間前、6月19日に梅雨明けした沖縄。その本島からさらに420キロ離れた石垣島で待っていたのは、今度こそ期待通りのエメラルドグリーンの海、抜けるような青空、ぐんぐん成長してゆく巨大な白い雲。陽が沈めば浮かび上がる満天の星空。島の空は広かった。 そうだこれを求めてまたここまで来たのだ。 3年前の七夕、到着したてのホテルで灯りを消したオープンデッキから満天の星空を眺め、オリオンを干した。あの日を忘れることができない。 3年前は、石垣港沖に目をみはるほど多くのクリアランス船が浮かんでいた。 通関手続きだけして出港してゆく船のことだ。 台湾と大陸の直接交易ができない政治状況下の抜け道だったが、時代は変わる。台湾と中国の自由貿易構想が進行している昨今、石垣経由の必要性がなくなったか。ここ1、2年の間に台湾からの船便は1/4程度になってしまったと昼、タクシードライバー氏が言っていた。 3年前、リタイアする団塊世代の移住を目論んで進めていた不動産開発もリーマンショックを経て、尻すぼみ状態だろう。 先の事などわからないのである。 先のことはわからないが今夜のことは決めている。島最古のチャコールステーキレストラン「坦たん亭」で石垣牛のフィレを食べるのだ。ついでにハンバーグも食べることにしよう。 ん?そー言えば昼もジャッキーで食ったな。 なんくるないさ~。 |

| 過去2回、いずれも海軍(クルーザー)で急襲していた沼島の木村屋。 4年ぶりの侵攻作戦が発令されたが、今回は海軍の支援を得られない。 地上侵攻作戦をたてることになった。 マスターから作戦参謀を任じられた筆者。 侵攻ルートを確認する。 沼島は淡路島南端の東側に浮かぶ漁師の島。 舞子から明石海峡大橋を渡って淡路島を縦断。南淡の港から船で島に渡るのが正規ルートだ。 別ルートがあるとしたら・・・ (大阪南港から船はないかな) ない。 (和歌山から船はないかな) ない。 正攻法でゆくしかない。 参加メンバーは大阪駅に集合。JRで三ノ宮へ行って高速バスに乗った。三ノ宮からその路線の終点淡路島の福良(ふくら)へ行く。福良までは1時間半程度。福良から土生(はぶ)港へはタクシーを使うしかない。海岸沿いの峠越えで20分。タクシードライバーが昔話をしてくれた。 「最近やっと2車線の舗装路になりましてね。対向車とすれ違えるようになりました。ここはガードレールもなかったんですよ」 断崖を削って作ったであろう道は嵐のときには波をかぶる。台風接近のときに無茶な客を乗せたそうな。波の押し引きを見ながら車を止めたり走らせたりしてこの難所を切り抜けたとのこと。 「朝走るとよく車が(海上へ)ダイブしていたもんですよ。夜なんか外灯もないからカーブを曲がらずにまっすぐ突っ込んで、海の岩の上に車が載 |
っているんですから」 どこまで僻地?淡路南淡町。 土生港についた。港と言っても町らしい町があるわけではない。 渡船は1時間に1便程度。明らかに観光用ではない。島の学童の通学の足かもしれない。 土生港を出て10分程度で沼島に到着。 木村屋から送迎のバンが差し回されていた。と言って、それほどの距離ではないのだが、ありがたく乗車。 木村屋は料理旅館だ。 入り口の水槽で巨大な鱧が泳いでいる。 2階に上がって、さっそく鱧づくし。 鱧の刺身は、あじやいかと一緒に。 鱧の焼き霜は醤油で。 鱧の湯びきは梅肉あえで。 そして、鱧すき。頭とアラでダシをとって、身と子・内臓・浮き袋をしゃぶしゃぶする。 骨切りされた鱧を熱々のダシに浸すと薄いピンクの透明な身がパァーッと白く身をくねらせるように丸く反り返る。すかさず口に入れる。 旨い。 大きな姿からは想像もできないほど身が締まり脂ものっている。今が旬なのだ。 鱧の天ぷらは塩で。 鱧の押し寿司はそのままで。 鱧のお吸い物。 まさしく鱧ずくし。 締めは鱧雑炊。雑炊用に少し残しておいてくれと言われた鱧の子を入れ、とき玉子を流し込み、ふわっと仕上げる。 これが旨い。 |

高松行4→→→back 高松行 高松行2 高松行3 高松行4
| 香川県には何度も行っている。 うどんを食べまくったこともある。屋島に登って平家の無念を偲んだこともある。金比羅さんの奥社まで1368段を登ったことも、丸亀城を制圧したことも、宇多津のゴールドタワーで「純金のトイレ」だって見たこともある。 でも「栗林公園(りつりんこうえん)」には行ってなかった。 「画竜点睛を欠く」とはまさにこのこと。 「純金のトイレよりも先にまだ見るものがあるだろう」と言うことか。 卯月の上旬、知己と待ち合わせのため、高松へ飛んだ。 アポイントまでの空き時間を使って栗林公園を訪れた。 日本で一番狭い県が香川県。ただし県域に占める平野は広い。県を南北に分断する溶岩台地の五色台(考えてみれば、ここも未訪)の東側を東讃(とうさん)西側を西讃(せいさん)と呼び、東讃に位置する高松市は、五色台と東岸に盛り上がった八島に挟まれた平野の中央にある。 その高松市街の真ん中に一塊の隆起がある。 石清尾山塊(いわせおさんかい)と呼ばれるその一峰が、標高170mの紫雲山(しうんざん)。 この紫雲山の麓に山を借景として広がる回遊式大名庭園が「栗林公園」である。 JR高松駅とその向かいにある「ことでん」高松築港駅の間をビジネス街の番町にむかって延びる中央通りが高松のメインストリートだ。 この道を、番町を過ぎてなおしばらく行くとそこに栗林公園がある。 正面口にあたる東門から入園。もうひとつの北 |
門は搦め手にあたる。 雨量の少ない香川県。玉砂利を踏みしめて歩けば微細な砂埃が靴の甲にうっすらと積もる。 上方の視界を妨げる木々の梢のトンネルを抜けると・・・ (おお!) 思わず声を漏らすほどの景色が広がっていた。 大小の木々が濃淡のある翠を幾重にも塗り重ねながら背後の紫雲山に連なっている。 それがこの景色に深い奥行きを与えている。 これほどまでに高度と深度をあわせもつ公園はそうはない。 庭師でもないし、作庭のことなど門外漢の筆者だがとりあえず暫定日本一ということで、ひとつ。 日本3名園の水戸偕楽園、金沢兼六園、岡山後楽園に行ったこともある。京都の寺社仏閣、彦根や福井の城郭と隣接した玄宮園や養浩館なども目にはしてきた。 それでもなお、今、眼前に広がる栗林公園に匹敵する筆者好みの庭園には出会ったことがなかった。 いや、実にいいのである。 のんびりしているのである。 市街地に立地している以上、背景の紫雲山に背をむければ、公園を縁取る緑のむこうにマンションやらなにやら近代建築の頭部が僅かに顔を覗かせてはいる。でも、それすらどこか恥ずかしげで控えめな風情なのだ。 筆者の脳裏に山口の瑠璃光寺が浮かんだ。 あの光景と似ているな。つまり、筆者は山を背景に緑織り成す景色が好きなのだ、ということでひとつ。 |

| 在阪8年を過ぎて、やっとこさ六甲に行った。 ここまで放置していたのに深い訳はない。 ただ、何となくどー行ったらいーのかわからなくて、かつ、どー行くか調べる気になるほど執着が生まれなかったからである。 なぜ行く気になったか、それすらも定かではないほどなし崩し的に行った。 外出しなければ後悔するかもしれないほどの好天続きのGWの最終日。仕事も一区切りし、ぱらぱらとめくっていた雑誌「ミーツ」の特集号「日帰り名人」のバックナンバー六甲の一角に「ジンギスカン」の文字を認めたからかもしれない。 (これから出かけても昼飯かわりになる。六甲でジンギスカンもいいじゃないか) ちゅうことで・・・北大阪急行、大阪市営地下鉄線で「梅田」駅へ13分。阪急神戸線で「六甲」駅へ特急、各駅を乗り継いで28分。神戸市営バスで「六甲ケーブル下」駅へ10分。六甲ケーブルで「六甲ケーブル山上」駅へ10分。六甲山上バスで「六甲ガーデンテラス」へ10分。 乗り継ぎの連続で13時には目的地のジンギスカンパレスについた。2時間ぐらいはかかったか。あんまり近くないぞ六甲山。 「こどもの日」特別サービスで子供は乗車料金タダ。「自分はまだまだ子供ダイ!」と言い張る勇気は出せず、正規の料金を払って乗った。 そして気がついた。六甲って乗り継ぎに次ぐ乗り継ぎで乗り物代をふんだくり、山上のさまざまな施設で客の懐の最後の一滴までをも搾り取るテーマ(集金)パークだったんですね。 関東圏で過ごした幼少期、読売ランドや向ヶ丘遊園(すでに廃園)、多摩動物公園に向かう雰囲 |
気に似ている。いや、最も酷似しているのは箱根だな。あそこも、電車→ケーブル→モノレールと乗り継ぎリレーで山上を目指す。 とにかくジンギスカンを食べよう。 パオをイメージさせるログ風店内は多くのアルバイトで運営されている。テーマパークのそれと同じであまり多くのことを期待してはいけない。無論、OK牧場である。 眺めはいいはず。でも花曇りなのか、黄砂のせいなのか、眺望は鼻が詰まったようにスッキリしない。ちょっとがっかし。 「お待たせしました」 「羊三昧」コースがやってきた。 「タレは?」 「あ、失礼しました」 (OK牧場よん) 平たい取り皿とタレの入ったタレ指しが出てきた。あれ?タレがなみなみと注がれた小鉢がくるんじゃないの? 「いいえ、焼いた肉を皿に置いて、タレをかけて食べてください」 札幌のジンギスカンに洗脳されてしまった筆者はジンギスカンと言えば、あのスタイルかと勝手に決めこんでいたようだ。周りを見れば、牛肉のジンギスカンや海鮮ミックスのジンギスカンをオーダーしている人も多い。ここは関西、肉と言えば牛の土地なのだ。当然、食べ方も変わる。ここでは羊を食べるのは狼だけなのだ。 それでも、追加のラム肉をオーダーして、昼間から赤ワインのハーフを空ければそれなりにGWを消費した気分になった。 OK牧場。六甲牧場・・・・・ゴメンナサイ。 |

| 「榛原」駅。 読めます? 関東以北や岡山以西では難読のはず。 「はいばら」が正解。 どこにあるでしょう? 奈良です。奈良県。奈良県宇陀市榛原区。 右を向いたミジンコのような奈良県(嗚呼、またまた奈良の皆さんゴメンなさい)。その上方、ミジンコの口のあたりに宇陀市はある。 「榛原」駅は宇陀市を代表する近鉄大阪線の駅。 特急も停まる。西隣に「長谷寺」駅があり、東隣には「室生口大野」駅がある。 長谷寺駅は長谷寺の玄関口。「花の寺」と呼ばれる真言宗豊山派(ぶざんは)の総本山。 室生口大野駅は室生寺の玄関口。「女人高野」とも呼ばれる真言宗室生寺派大本山。 長谷寺は各駅停車しか停まらないから榛原で急行からローカルに乗り換えねばならない。室生口大野は急行も停車する。今乗っている電車でそのまま行ける。必然のなりゆきで室生口大野で降りた。駅で降りた客は3人だけ。 駅前にはロータリー。ただし、それしかない雛な佇まい。駅から室生寺まで6.6キロとある。 路線バスは1時間に1本。2時台には1本もない。 観光案内所らしい窓口も建物もない。たぶんこっちに室生寺があるのだろうと地図も案内も持たずに安閑と歩き始めた。悩むような分岐もなく、室生寺と表示された交通標識の指し示すままに県道沿いをテクテクと歩く。宇陀川沿いの崖に弥勒磨崖仏が彫られ、なかなかの景観だ。 「東海自然歩道」という大きな標識が現れた。県道からはそれるが迷わず踏み入った。 |
奈良と言えば森林県。「自然歩道」というのどかさとはうらはらに森閑としたじゃり道は、頭上を覆う木々に陽光を遮られ昼なおほの暗い。足元もなぜかしとどに濡れている。坂道はかなりの斜度になり、今や、渓流沿いにつづら折れとなった登山道である。室生寺まで4.8キロと書かれた標識を見てからずいぶん歩いたつもりなのに、次に見かけた標識には室生寺まであと4.2キロ。 (600mしか進んでいない) 急坂を下ると広々とした公園に出た。完全にひと山越えのコースだった。 さらにしばらく歩いて門前町の佇まいを残す町並みに出た。前には渓流。川を越える太鼓橋。 山門に風神雷神。その前に「女人高野室生寺」の石碑。女性の入山が許されていたのだ。 伝承は役小角(えんのおづぬ)の草創、空海の中興という。実際は朝廷の命により賢璟(けんきょう)が造りかけ、その没(793年)後、弟子の修円に引き継がれたというところらしい。 高野山系の寺である。 山岳密教だ。だから体に優しくはない。 五重塔を越え、賽の河原の先にある石段は胸突きだ。一山越えてきた身にはチト辛い。 シャクヤクの名所らしい。混雑するのは春。帰路に乗ったタクシーの運ちゃん「紅葉は京都に負けますよ」と屈託がない。カエデは好きだがモミジ(紅葉)には執着はないという筆者の言葉には無反応。「長谷寺はこれからですがね。あそこは牡丹があるから」 2時間強の山越えルートも川沿いにうねる県道をタクシーで走れば10分ほど。このコースを歩けば1時間半程度でついたんじゃないか? |

| 「橿原市」。 読めます? 関西圏以外では難読のはず。筆者も在阪するまで存在すら知らなかった。 「かしはらし」が正解。 どこにあるでしょう? 知らないでしょ? 奈良です。奈良県。 奈良県橿原市。 右を向いたミジンコのような奈良県(奈良の皆さんゴメンなさい)。その上方、後頭部の真ん中あたりに橿原市はある。北に京都、東に三重、南に和歌山、西に大阪と4府県に囲まれている奈良県にあって橿原市は大阪寄りの街。 実際、奈良県民は京都よりも大阪に出ることの方が多い(と思う)。私鉄中、日本最長の営業路線網を誇る近鉄という巨大輸送機関が奈良線、大阪線と2本の主要幹線を奈良の北部と中部へ大阪から送り込んでいるからだ。大阪線はそのまま奈良を横断し伊勢湾に臨み、北上して名古屋に、南下して伊勢志摩に至る。 奈良線、大阪線間を南北に結ぶ路線は、北上して京都へ、南下して吉野に向かう。 近鉄大阪線の「大和八木」駅は大阪難波から特急で30分強。そこで橿原線に乗り換え、1駅だけ南下すると「八木西口」駅に至る。 駅から徒歩3分。小さな飛鳥川を渡る赤い橋(蘇武橋)が見える。その対岸に大きな榎が今にも朽ちて倒れそうな体を添え木に支えてもらっている。 その一点を北東角として東西600m、南北310m。 かつては環濠に囲まれ、「海の堺、陸の今井」と |
までその栄耀を謡われた自治都市「今井町(いまいちょう)」の街並みが広がっている。 中世の町家がこれほどの規模で残っているのは珍しい。それも映画セットのような観賞用の無人スポットではなく、あたりまえの日常生活が営まれている普通の町並なのである。 類似の雰囲気を求めれば、金沢東茶屋街の裏通りや、倉敷の美観地区がそれにあたるが、その規模と日常性において今井町はそれらの観光地区を凌駕している。 町並保存のために行政も住人も大変な努力を払っているのだろうが、町をそぞろ歩く旅人にとって、そこはまさに中世から現代に至るまで、何百年もの間変わらずに存在し続けた日常生活の連鎖の一環でしかないように思われる。 屋根甍は鈍くくすんだ銀鼠色。その下、漆喰の白壁が美しい。白壁の下には濃い茶、あるいは焼き板の黒が下板壁として地面に刺さっている。細かく刻まれた格子戸、低層に造作された2階、家と家の間に刻まれた用水路(?)、丸く、くだけた書体の表札。どれもこれもがノスタルジックである。自動販売機すら、町並みにあわせて茶色く塗られている(一台限りだったが)。 寺内町なので町内に寺が多い。その造りは豪奢だ。豊臣秀吉が吉野の花見の途中に本陣を定めたとする御茶屋々敷などもある。 どこよりも目立とうとガンガン張り出す巨大看板、右に左に上に下にと蠢きまわる人形など、隣県、浪速の商業主義とは一線を画すかのように町内の商店はいずれも、営利を追求しているとは思えんほど静かに町中に溶け込み、佇んでいる。 奈良って、ホンマのどかやねえ。。。 |

| 最初はよかった。だが、時として木杭を見失うようになってきた。見失えば前の杭まで戻って、これと思う方向へ慎重に進む。そして赤いペンキを見つけるといった具合に、あまり効率的でない進行になり始めた。 (これは決して一般的な登山道じゃないな) そもそも道らしい踏み分けの後もない。 岩場が尽き、急傾斜とともに枯れ草の積もったすべりやすい斜面になった。 滑る。 滑るとどこまで滑り落ちるか考えたくない斜面もある。 手で樹木を掴み、足を切り株にひっかっけて3点確保で降りざるをえない。 それでも滑る。掴んだ枝が腐っていてポキリと折れる。支えを失った身体がミニ滑落を始める。きっと目が吊りあがっていたろう。 木の切り株に肘をひっかっけ滑落をとめたり、太い幹にすがりついたりして高度を落としていった。 もはや何度滑ったか、ミニ滑落をしたか覚えがないほどに体中、泥だらけ、枯れ草まみれ。 見れば肘やら手のひらに血豆や切り傷、擦り傷がいたるところについている。アドレナリンが全開だったのだろう。痛みは感じない。 やっと急斜面を抜けた。 今度は小さな渓流沿いに木杭が続いている。水が流れていなければ、枯れ沢を歩けるが水量は膝くらいまではある。渓流沿いと言っても道があるわけではない。渓流の淵を右に左に木々にしがみつきながら進むしかないのだ。 いったい、この木杭は誰が何のために打っているのだ。俺はヤマカシじゃないぞ! 山頂部で下した己の決断を心底後悔した。 小さな渓流とは言え、淵から2メートル程度の高低差が生まれる場所もある。そこに渓流を跨いで1本の倒木がかかっていた。 木杭はこれを渡れと告げるかのように対岸の地面に刺さっている。 無理、これは無理・・・おずおずと足をかけてみる。泥濘がつまったソールは足をかけた瞬間にズルッと滑った。 (無理だ) 迂回して何とか対岸に渡るコースを見つけた。 水面からかなり高くなった岸をそろりそろりと歩いていると ズボ! 左足が枯れたシダの群生を踏み抜き、身体がその下に隠れていた渓流にスッポリと落ちかけた。 (ふんぬ!) 奇跡的に岩場にかかっていた右足でヒンズースクワットのような踏ん張りをきかせ、脇に伸びていたツルを掴む。これが枯れ枝だったら、落ちていた。ツルは筆者の体重をささえてくれた。 「ぜってえ!このコースで生きて麓にたどりつい |
てやる!見ていやがれバカ野郎!」 筆者の咆哮が山中にコダマする。 この下山中、どういうルートをとって足場を確保するか、どの幹につかまるか、あるいはそこまで手が伸びるのか、駄目なら飛びついて幹にしがみつくか、といった判断と実行を繰り返した。ここまで視力・知力・体力を試された登山の経験はない。 木杭のナンバーが「1」になった。 入ってきた登山道とは明らかに違う所だが、平坦な道が梢の先に寺の屋根を覗かせる明るい場所に向かっている。 (帰ってきた) ヨロヨロと出口に向かうと・・・ 神よ、まだ我に苦難の道を与えたもうか。 フェンスが筆者を囲んでいる。扉に手をかけると鍵のついたチェーンでしっかりとくくられているではないか。 フェンスを乗り越えるか、と見上げればフェンス上には碍子のついた鉄線が3列に並んでいる。その鉄線は明らかに電線に繋がっている。 ここはいったいどこなんだ。 (俺は害獣扱いをうけている・・・) フェンスに沿って歩く。 大きな鹿が3頭、突然現れた人影に驚いて大きく跳ねて逃げていった。 (驚いたのはこっちだ!) 電流つきのフェンスはずっと、私有地だか国有地だか知らないが、このエリアを囲っている。 200m程先に団地が見えた。その手前のフェンスは色が違っているように見受けられた。一縷の望みにすがりつき歩を進める。 (あった!) 電流つきフェンスのかわりによくみかけるフェンスが団地の前にあった。 とりついて乗り越えようとする。 靴の先端が大きく丸くてフェンスの菱形の空間に挟めない。ズルとすべって上に上れない。 靴を脱いだ。 両方ともフェンスの向こう側に投げる。 ぐにゃり。 泥を踏んだ靴下が嫌な感触を伝える。しかし、これでフェンスに足をかけられる。しがみつき、オーバーハングして乗り越える。 (やった!) 自由の地に降り立った! 目の前の団地のベランダから一部始終を見ていたオバチャン。筆者が靴を履き、その場を立ち去るとき、家のドアを開け不審者の逃亡シーンを見送る善良な市民のような視線をむけていた。 (警察に通報の必要はありませんからね) ブツブツ言いながら、近江高島の駅にむかう筆者であった。 時計は14:00を指していた。 (登山より下山の方がかかっている!) |
黒が登山道。赤が木杭沿いに筆者が下ったコース
| 京都駅から山科を越えたところで東海道線から分岐する湖西線は琵琶湖西岸を福井、金沢、富山の北陸方面に向かう。高速化を目指したこの路線に踏み切りはない。 山科を出た湖西線新快速は次駅「大津京(昔は西大津だった)」から北上を開始する。その後、比叡山坂本・堅田・近江舞子・北小松・近江高島と停車を重ねる。 近江高島までは京都から40分弱。 近江高島とひとつ前の北小松の間に「リトル比良」と呼ばれる山歩きのコースがある。 滝山(たきやま703m)岩阿沙利山(いわじゃりやま689m)岳山(だけやま565m)などの山と峠、稜線を結んだロングコースですべてを踏破すると所要時間は7時間程度。無論、ハイキングとして短区間を歩くオプションもありだ。 運動不足の筆者は短区間のハイキングとして近江高島に近い「岳山」登山を選択した。 10:00 近江高島着。 観光案内所で登山道への道を教えてもらい、テクテクと歩き始める。 10:20 登山道に入る。 登山道入り口に長谷寺がある。 先般、播州、竹田城に登ったときもそうだったが、山域がフェンスに囲われて登山道入り口には扉がついている。開けたら閉めるようにと「獣害対策」の注意書きがあった。 広いのどかな道を登る。だんだん道幅が狭くなり、登山道らしい雰囲気になってきた。 いつ雨が降ったのだろうか。日のあたらぬ斜面には時にぬかるみが広がっている。 足場はあまりよくない。足首に優しい斜面とは誰も言うまい。 石灯籠の立つ見晴らしのいい踊り場から琵琶湖が見下ろせる。 10:50 白坂(しろざか)に出る。 真っ白に風化した花崗岩地帯が登山道右手に広 |
がっていた。道をはずれてこの坂を上る人も多いらしい。やっておけばよかったとは後の反省。 ハイキング程度と言うには、運動不足の我が身にはちょっと傾斜がきつい。ときに垂れ下がっている縄を掴み、岩場をせりあがる。 稜線に出た。 それなりの勾配の先、斜面が途切れて対面の峰がかなたに聳える。 高所恐怖症のFの顔を思い浮かべる。 近時、平衡感覚が衰えている筆者も若干びびっていたことを告白します。 ふと足元を見ると頭を赤いペンキで塗られた20センチ程度の木杭が等間隔で地面に打ち込まれている。片面に番号が書いてある。登山道に沿って並ぶ木杭を見ながら上ってゆくと、No189程度で頂上に出た。 11:40 岳山山頂。 標高は565m、眺望は芳しくない。岩に登って僅かな視界を確保した。 この先、オーム岩というのがあって、そこが一番のビューポイントらしいが筆者は当初の計画を果たしたので下山することにした。 11:45 下山開始。 先ほどから目に留まっていた木杭に沿って帰りはじめる。でも麓からの登山道にはなかったような気がした。 先ほどの傾斜のきつい稜線までは木杭と登山道はシンクロしていた。しかし、木杭は稜線に向かわず、別方向にむかっている。 目をこらせば、10~20mほど先に赤く塗られた木杭が見える。 (この木杭を結んでゆけば楽に下山できるのではあるまいか) 悪魔の囁きが筆者の脳裏に浮かんだ。 この判断がこの日最大の禍根を生むことになろうとは神ならぬ身の悲しさ、この後に待ち受ける過酷な運命を筆者はまだ知る由もなかった。 |

| 動くモノと書いて動物。 動かない動物は静物だ。 上野動物園、多摩動物園、幼少期、お馴染みの動物園の動物は皆、静物だった。やる気はほとんど見られない。動物を見に来たんだか、動物に見られに来たんだかわからないぐらい彼らは動かなかったような気がする。 巷間、一番人気と言われて久しい「旭山動物園」は北海道、旭川の郊外にある。札幌から旭川までは特急で1時間20分。旭川から動物園までは車で30分。バスなら40分程度。 季節はあたかも冬。 ペンギンやホッキョクグマ、アザラシなど人気キャラクターが一番元気な季節。せっかく札幌にいるんだからちょいと寄ってみようかと朝8時、札幌発旭川行「スーパーカムイ」に飛び乗った。 ウィークデイだからすいているだろうと思ってはいたが、団体客がバスを連ねて来る可能性だってある。念には念をいれて開園30分前の10時には券売所の前にへばりついた。一番乗りだ。 動物園の入り口は「正門」「西門」「東門」の3箇所にある。 筆者は西門に回った。 地図を見るとペンギン館やホッキョクグマ館、アザラシ館に一番近かったからだ。 「ペンギンのお散歩」は11時からとある。 いつの間にか開門を待つ観光客が後ろに並んでいる。それなりの人数だ。駐車場が近いというだけで西門に来た人もいるだろうが、皆、狙いはペンギンと見た。 ペンギン館は西門に一番近い。案の定、開門と同時に、皆ペンギン館に向かう様子。 筆者はまっさきにホッキョクグマ館へ。 しめしめ誰もついてこない。 ホッキョクグマはヤル気を見せている。青いバックに噛み付き、ふりまわし、なげうち、雪に体をこすりつけて遊びまわっている。 迫力あるなあ。 遊び道具がプールに落ちると後を追って飛び込んでくる。 ざっぱーん! 水面下も見える構造なので、客は、クマの遊泳風景やら首から上を出しただけの姿やらいろいろ |
な光景が楽しめる。順路に従うと、氷から頭だけ出したアザラシの視線でクマの姿を確認できるスポットがあったり、先ほどのプールや雪上面を上から覗ける造りになっていたり、空間利用が実に巧みなことに驚かされる。 続いてアザラシ館。 チューブを下から上に泳ぎ抜けるときのゴマフアザラシの顔がキュート。 11時10分前にペンギンのお散歩コースへ。かなりの数の客が並んでいるがお散歩コースは長い。ペンギン館の前よりずっと奥に行く。お散歩コースは途中から片側サイドにしか客を並ばさない。そのあたりならば写真に対面の観光客の姿を拾わずにすむのである。 ペンギンは、予想以上に可愛い。 集団行動をする性行から列をなしてヨチヨチ、それでも存外早く歩いてくる。1羽のお調子者は雪面を泳ぐようにすべっている。 こりゃあ、うけるわ。 猛獣館に行き、ヤル気まんまんの虎と、こいつだけはどこでも同じように動かないライオンのオスを見る。ライオンは声だけは惜しまずに唸っていた。ベテラン演歌歌手のようだ。それにしてもどちらもネコ科だし、寒気に弱いのでは? トラもライオンも尻をむけたらシッコに注意!なんて書いてある。 ヒョウは真上の網棚に丸くなっていた。まるで毛玉。つっつきたくなるが、シッコかけられるのやだからヤメた。ヒグマもヤル気はまったくなさそう。雪中にふてたように寝そべり微動だにしない。そもそも冬眠期間じゃないのか? オオカミやシカ、サル類を眺め、動物園の頂上部にある東門から下方を見下ろすと、旭川の盆地風景が一望できる。 最後にペンギン館に行って、上から横から下からペンギンの遊泳風景を愉しませてもらった。 滞在時間は1時間半。800円の入園料は安いもんだ。 カメラのフラッシュは動物にかなりのストレスを強いるとのことで、それだけは厳に謹んで欲しいとの注意をあちこちで聞いた。なるほど。確かにカメラのフラッシュを浴びまくって喜ぶのは芸能人しかいない。 |

| 「道の駅かでな」に行った。 世界最強のアメリカ空軍。その数ある空軍基地の中でも世界最大規模を誇る「嘉手納基地」。その滑走路脇に「道の駅かでな」はある。 屋上から極東最大の空軍基地を見渡すことができる。(いいのか?) マニアの皆さんも多い。アルジャジーラのインタビュアーも来ていた。同行のYがインタビューを受けてたつ。 F15、KC135空中給油機、MC130輸送機などの戦闘航空団が配備された基地は訓練が日常のルーティンだ(きっと)。 輸送機と給油機がタッチ&ゴーや低空進入のゴーアラウンドを繰り返している。 屋上備え付けの望遠鏡でかなたに見えるハンガー群を覗けば、いるはいるは、F15にハリアー(え?ハリアーは海兵隊所属では?)、VIP用の白いガルフストリームも駐機している。 「戦闘機のテイクオフシーンが見たいなあ」 「12時だからランチタイムじゃないか」 などと言っているうちにF15がタキシングを開始した。お仕事の時間だ。 屋上のマニアの皆さんがいろめきたつ。 動き始めたF15は6機。次いで2枚の垂直尾翼が左右に傾斜している戦闘機が2機。 「F18Aかなあ」でもF18Aは海軍機だ。海兵隊基地もあるから嘉手納にも配備されるのか?などと見ていたが、先般、5~6月にF22ラプターが嘉手納に飛来、それ以来駐在しているらしい。とすればラプターだったのかも(最新鋭機だ)。 戦闘機のテイクオフはさすがに迫力がある。 爆音とともに鋭角的に鋭く上昇してゆく。 |
存在の是非、政治論議はおいて、男の子は兵器には弱い。先般知覧で再認識した反戦感情はかわらねども正直かっこいいとの思いは否定しきれない。無論あの戦闘機に追っ掛けまわされることになれば話は別だ。 我が家に暴漢が侵入すれば家族や我が身を守るために木刀が欲しくなる。相手が刃物を持ちだしたら引き出しに拳銃があったらよかったと思うに違いない。拳銃に対してはショットガンだ。実行制圧力にサブマシンガンが欲しくなるのも時間の問題だ。かくして軍備はエスカレートする。用心棒にお金を払い、住まいを提供する方が安くつくが黒沢明監督の「用心棒」を見るまでもなく、用心棒に忠誠心はない。ただし、自分達で武装を始めたら、維持管理だけでなく終わりのない兵器開発まで担うことになる。 アメリカにとって沖縄の価値は、台湾海峡が政策上どのように位置づけられるかとか東南アジアから中東にかけての不安定地域に対する有事の前面展開の拠点をどこに置くかという政策で決定されている(よーな気がする)。 ピナトゥボ山の噴火によってフィリピンのスービック、クラークの2大軍事拠点を失った米国にとって、自国領グアムの前に前面展開する日本の各基地はどんな政治的ゆさぶりをかけようとも最終的に「サヨナラ」できない物件であることは間違いない(と思う)。 家主と店子の、貸している(?)理由と借りている理由に違いがあり、そこのところ、実はわかっているけどタテマエを前面に押し出して本音を隠すゲームのルールにのっとって詰まるはずもない話を詰めるフリをしていることは当事者は皆了解のうえなんだろうしな。 |

支笏湖行3 →→→back 支笏湖行1 支笏湖行2 支笏湖行3
| 一昨年、冬季イベントとして弘前の雪灯篭祭りを調べていたら、偶然、ライトアップされた氷柱の美しい画像が目にとまった。 それが「支笏湖氷濤まつり」だった。 透明度抜群の支笏湖の湖水をスプリンクラーで骨組みに吹き付けて大きな氷柱やオブジェ、高台を作る。昼は陽光を受け青く輝き、夜はライトアップされ極彩色の彩りを放つ。幻想的な光景が広がっていた。 会場は、支笏湖畔の駐車場を利用している。 支笏湖から注ぎ出る千歳川のほとりにある。 北海道に現存する現役最古の「山線鉄橋」がかかっている。橋の先には「親水広場」。 冬季は雪が積もり足を踏み入れる人も少ないようだ。ベンチの背もたれまで雪に埋没している。 積雪がどれほどの深さか判然としない。しかしバージンスノーに足を踏み入れるのが男の子の性だ。いそいそと橋を渡り、広場の方向へ。 ずぼっ、ずぼっ、と一足ごとに足をくわえ込む雪面だがくるぶしより下までは滅多に沈まない。それでもハーフブーツの足高よりもガクンと沈み込むこともある。何回かの降雪を経て積みあがった雪面はバウムクーヘンのように層を成し、下層は湖面を吹き渡ってくる寒風にアイスバーン化するのか、上に積もった雪の重みで絞められたのか最下層の地面まで足が沈むことはなさそうだ。 雪中行軍は体力を消耗する。 膝まで潜るような雪面を歩きまわったのは長岡の信濃川河畔以来だ。あのときは我を忘れて河川敷に深入りしてしまい進むも退くもままならぬ、まさに進退ここに窮まれりという状況に陥ってしまった。今回はそこまで過酷な積雪量ではない。 |
雪面を歩き回り堪能したところで「氷濤まつり」会場へ向かう。 ウエルカムゲートの前に現在の気温が表示されている。 氷点下10度。そら寒いわ。 オーストラリアからの団体さんがいた。 子供はどこの国でもやはり子供だ。雪と氷を見て有頂天になって走り回る。 はらはらしながらそれを見守る親もまた同じ。 膝が痛い、肘が痛い、首が痛い。「痛くないところを先に言え」というくらい身体のあちこちにガタが来ている筆者はうかつに転ぶことすら憚られる。何かしらの後遺症が怖い歳になってしまった。無邪気にアイスバーン状態の雪上を滑走する子供たちが羨ましい。 夜、オープニング記念の花火大会があった。氷濤の頭上で輝く花火。氷点下の花火もなかなかに趣きがあって良い。 赤、青、緑、黄色、紫、さまざまなライトに照らし出される氷濤。空には雲間から零れ落ちたかのように煌々と輝く満月が浮かぶ。 幻想的なひとときが過ぎていった。 若い頃は秋、冬が好きじゃなかった。 馬齢を重ねて、秋には秋の、冬には冬の良さを認めるようになった筆者。 特に雪に包まれた冬景色に愛着が深くなった。 冬期の祭りも好きになった。弘前は雪灯篭、支笏湖は氷濤、そう言えば、札幌雪祭りって行ったことないなあ。そんなことを考えていたら、ホテルの入口に張られたポスターに新目標を発見。 「層雲峡氷瀑まつり」 来年はこれかな。 |

支笏湖行2 →→→back 支笏湖行1 支笏湖行2 支笏湖行3
| 快晴の朝。 昨夜は闇に包まれてわからなかった眺望が眼前に広がっていた。まさにパノラマ画の世界だ。 180度の開放感あふれる窓のむこうに静寂をたたえた支笏湖(しこつこ)が横たわり、その左右それぞれの両端に恵庭岳(えにわだけ)と風不死岳(ふっぷしだけ)が聳えている。 風不死岳の後背にプリンのような形状の溶岩ドームに雪化粧をした樽前山。 湖面にも湖岸にも山腹にも人工の造作物が見当たらないことが、景色に神秘的な印象を与えている。 風不死岳の山頂が昇りつつある朝日をうけて赤く輝き始めた。 朝食までの1時間、散歩に出ることにした。 2007年、2008年と、冬季の弘前、積丹で滑りまくり転倒三昧だった筆者は、今回、装備を改めることにした。ウォーキングシューズでは寒冷地活動に支障をきたすことがまさしく骨身に染みてわかったからだ。旗下の革靴集団に寒冷地作戦専用部隊を配備した。 アシックス・ペダラ、アイスウォーク。 厳しい低温下でも硬くなりにくいスノーコンパウンドラバーを採用し、路面との接地面積を広げ添加した珪砂がグリップ力をさらに高める。(広告ママ)寒冷地での作戦行動に大きなアドバンテージを得る最新兵器だ。通販で買った。 ええ格好しいのチェスターフィールドコートを予備役に編入し、AOKIで買った1万円ちょっとのキルトハーフコートを実戦配備。見た目よりも性能重視の編成だ。靴下もズボンも無論厚手。 昨夜、手袋を宿に忘れて凍傷になりかけた。保 |
温力の高い手袋もしっかりと携行。外気温は氷点下10度だが防寒はほぼ完璧に果たされた。経験こそが対応力を向上させる唯一の教師なのだ。 支笏湖畔は湖面を吹き渡る風がまさに身を切るようにシバレル。防寒にイヤマッフルかフードがあれば完璧だったかもしれないが、とりあえずOK牧場とする。船着き場の土台にイカでも干してあるのか、白い塊が垂れ下がっている。よくよく見れば波が凍りついたつららの塊だ。 湖岸線延長40.3キロ、最大水深363m。最北の不凍湖にして典型的なカルデラ湖である支笏湖は国内第2位の水深とトップレベルの水質、透明度を誇る。 透明度が高いということはプランクトンが少ないということで、とどまるところそれをえさにする魚も少ないということになる。 数少ない支笏湖の生息魚を代表するのはヒメマス。アイヌ語で「平たい魚」という意味のカパッ・チェプがなまり、地元ではチップと呼ばれるこの魚の料理が湖畔の温泉街や飲食店での名物だ。 支笏湖は当初、円形のカルデラ湖だった。やがて湖岸の南部で風不死岳が噴火、次いで北部で恵庭岳が噴火、円形の湖を南北からへこませるようにそれぞれの溶岩流が湖に注ぎ込み、現在の繭形の湖になった。 湖畔には北海道で現存する現役最古の鉄橋、「山線鉄橋」が千歳川にかかっている。 千歳川はこの支笏湖から注ぎ出て、北流する。JR千歳線がこれを跨ぎ、JR函館本線もまたこの川を渡河する。JR函館本線「江別」の付近で石狩川に流入し、川は100キロ強の旅を終える。 |
画像左から「風不死岳」「恵庭岳」「樽前山」


支笏湖行1 →→→back 支笏湖行1 支笏湖行2 支笏湖行3
| エアの到着と路線バスの発車までのタイムラグが10分しかない。しかしボーディングブリッジから到着出口まで下手すると10分はかかるような空港では幸いにして新千歳はない。ただし支笏湖行きの路線バスは1日4便。その最終便がターゲットだ。乗り逃すとタクシーしか手段がない。タクシー代は8000円くらい。バスなら1000円。 羽田での搭乗は定刻に開始され、幸い乗客数も少な目。(しめしめ幸先がいいぞ) 思ったのもつかの間。どっかの阿呆がチェックインだけして無断で搭乗をやめてしまったようだ。グランドアッテンダントが駆け回っているのが機内から見える。あれよあれよと定刻を10分も過ぎてしまった。さらに5分が経過して、乗機はタキシングを開始した。「1H」に座る予定だった阿呆!もしバスに乗れなかったらタクシー代請求してやるからな。 新千歳でボーディングブリッジが繋がり、機を出たのはバス発車の5分前。ダッシュ!なんとか間に合った。息をきらして席に着いたとたん、バスが発車。きわどいところだった。 バスは近辺の駅、住宅地の停留所をこまめにクルクル拾ってゆく。なんか滅茶苦茶停留所間が短い。気がつけば車内は満員だ。 陽が沈み、夜の帳が下りる頃には、いつの間にか乗客の姿がなくなっていた。筆者を含めて3人しか残っていない。 先ほどまでのバスとは別便のように飛ばす。窓の外に人家の灯りが絶えて久しい。真っ暗闇だ。目に映るのは路肩がここまでという降雪時用の下向き矢印標識の赤や緑の点滅と、対向車のヘッドライトのみ。 |
次の停留所名が表示されてから5分以上は経過している。停留所間が恐ろしく長くなっていた。路肩ライン標識の点滅があまりに単調で催眠効果をもたらす。危なくないか?この標識。峠を越えているようだ。列をなす前方の路肩ライン標識がだんだん沈んでいく。やがてその点滅が今度は浮き上がり始めた。峠を越え坂道を下り始めたのだろう。やがてバスは終点支笏湖停留所に到着。 バスを降りて周囲を見渡す。支笏湖温泉街とは言うが広くはない。今日の宿は確か・・・うろ覚えの方向感覚で歩き始めたが、街灯も少ない。先行きが不安になる方向に宿があるはずだがそれらしい標識も灯りもない。周囲に人影もなくひさしぶりの孤独感に襲われた。九州の大在駅前で特急を降りて以来の感覚だ。 これは危険だと宿に電話をするとバス亭まで向かえに来てくれると言う。 クラシックカーがやってきた。迎えの車だ。 今回の宿泊は「オーベルジュ」だ。5室限定。ゆきとどいたサービスを期待している。 オーベルジュ、それは宿泊施設を備えたレストラン。料理を食べたらワインを飲むフランス人。地産の料理を出す郊外のレストランには車で行くしかない。でもワインを飲んだら帰れない。だから宿泊設備を整えたオーベルジュが生まれた。 要は、フレンチを食べて泊まるのだ。 本館と呼ぶ日本旅館の露天風呂や大浴場には送迎つきで利用可能。しかも24時間稼働。到着した今日は確実に空いている気配。ディナーもレストランに筆者ひとり。本館の浴室も、筆者ひとりだけ。すべてのサービスを独り占め。うほほほほついてる。 |
鹿児島行5 →→→back 鹿児島行1 2 3(疾風怒涛編) 4 5 6 7
| 日常の食べ物に人は意外と無頓着だ。 下手すると昨夜食べたものすら思い出せない。 「自分は大丈夫だ」と胸を張る人も胸に手をやって考えて欲しい。何食前まで思い出せるかを。 何を食べているかに無頓着だから「秘密の県民Show」なんかで実は自分たちの常食が全国的にはまったく無名だったりすることに驚くんである。 博多オフィスのスタッフがひょんなことから「トラキチクン」や「ブラックモンブラン」の話になったときの場の盛り上がりたるや、九州北部の人間にしか通じない話ではある。(ちなみにトラキチクン、ブラックモンブランともにアイスの銘柄である) 故郷は故郷を離れてみないとわからない。 大阪オフィスの鹿児島県出身者は、県を出て初めて、鹿児島は豚肉が旨かったことに気がついた。鹿児島と言えば、すなわち豚肉。足の先、鼻先、尻尾の先、6箇所が白いため六白豚と呼ばれる黒豚バラ肉の脂身の旨さを筆者もこの歳になってやっと認知した。「とんかつはもちろん旨いんだが、ここはしゃぶしゃぶで食べたい」なんてことを言い出したのは最近のことだ。以前は、トンカツで十分だと思っていた。近時、訪問回数が増え、寿庵、花蓮、いちにいさん、あぢもり、黒福多、吾人愛(わかな)など行けば行きたい店も増えた。 鹿児島の市街地は意外に広い。(ただし平地が少ない。住宅は山肌に軒をよせあいびっしりと屋根を連ねている) バス王国だが、市電も走っている。市電はどこで降りても160円。九州新幹線の終点「鹿児島中央駅」は新幹線開業以前は「西鹿児島」という名 |
称だった。地元では「西駅」と呼ばれていた。 「鹿児島駅」は西駅より東にある。旧城下に近いのはこちらだ。 市電はこの鹿児島駅前から繁華街の天文館を通り、高見馬場で分岐する。分岐した線は実は環状である。環状の反対側が郡元(こおりもと)。鹿児島大学などはこちら側にある。 郡元の先にも盲腸線が延びている。市電ではなく電車路線と化し終点は谷本と言う。市町村合併前は、地域で一番でかい町だった。 天文館には地元百貨店の雄「山形屋」があり、先般「三越」が撤退したため、中央資本に勝利した地場勢力が凱歌を上げている。 天文館を過ぎ、山形屋にむかわず直進すると「ドルフィンポート」という港湾商業モール兼種子島、奄美大島航路の港がある。ここから眺める桜島の景観はなかなかのものだ。 鹿児島は「焼酎」だってあるし「ラーメン店」も多い。「つけ揚げ」は薩摩揚げの現地名称だ。紫芋もその気になればもっと押し出せるだろう。地鶏は宮崎より旨いと思っている県人がほとんどだし、鰻の生産量は日本一なんて実は誰も知らない。醤油は甘いし(誉めてるのか)、黒糖、黒酢、黒毛和牛など黒だけで役がつく。 あ、「かるかん」や「カスタドン」など甘味も充実。筆者は「笑々」というかりんとう饅頭を押している。 これほどの物件を揃えながら、観光立国としていまひとつなのはあまり売り出しに能動的なプロデュサーがいないからだろうか。その点、名古屋にちょっと似てる。 ちょっといじれば、もっと稼げると思うなあ。 |
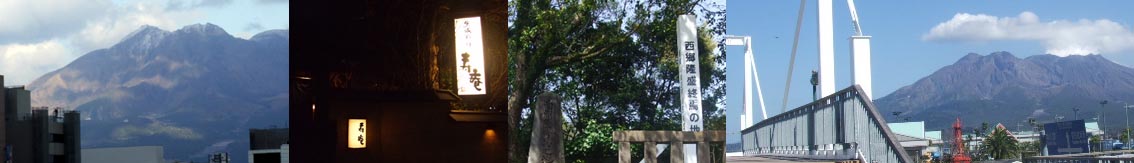
| 沖縄本島東岸、本島中央からやや南、中城湾と金武湾に突き出した触手のような与勝半島。海中道路と橋で平安座、浜比嘉、宮城、伊計の島々と結ばれている。 半島の付け根で中城湾と金武湾を扼し、東岸交通路に睨みをきかせる要衝に勝連城はある。 時、あたかも足利幕府初頭、沖縄では南山、中山、北山の三山時代に幕を引く英雄、尚巴志(しょうはし・尚氏第2代王)が三山統一事業を進めている。 尚巴志の統一事業を助けた武断派の武将が護佐丸。築城の名人とされ、三山統一後は北山監守として今帰仁城(なきじんじょう)に拠り、その後中城城(なかぐすくじょう)城主となる。 その役割は、勝連城主、阿麻和利(あまわり)の監視ならびに牽制。 当時、急激に勢力をのばしつつあった勝連城主阿麻和利。前代の按司(あじ)を攻め滅ぼし下克上によって按司となった。按司とは、地方豪族の長の呼称だ。 阿麻和利は後世の琉球正史で極悪人の扱いをうけるが、正史の編纂は王朝尚氏の命によるもの。逆賊阿麻和利は、江戸幕府における石田三成と同じ役回りだ。歴史は勝者によって作られる。 阿麻和利。しかしながら地元での評判は悪くない。海外との交易を進め、政戦両面において確固とした実力を備え、前代の按司の悪政ゆえに民衆からは救世主のような支持を得た。 一方、忠臣と呼ばれる護佐丸だが、統一事業も完成段階にある今、王朝、尚氏からその存在を疎まれ始めていた。尚氏はすでに初代尚思紹から数えて6代目の尚泰久の時代になっている。建国の功臣はすでに目障りな存在であった。 阿麻和利への抑止力として中城に配置されたはずの護佐丸が、そのための武力増強を阿麻和利によって謀反の印と讒言され、よりによって仮 |
想敵であるはずの阿麻和利に護佐丸討伐の命を王朝から与えることになってしまう。 守城、中城を攻囲する阿麻和利軍が王命を帯びてのことと知り、護佐丸は無抵抗で命を絶つ。 阿麻和利は、尚氏の娘、百度踏揚(ももとふみあがり)を娶り王朝との距離を縮めていったが、彼もまたその妻によって生家への謀反の疑いありと通謀され、政府軍に攻め滅ぼされてしまう。 結局、阿麻和利、護佐丸、王朝尚氏による三つ巴の内乱劇は、尚氏の朝権拡大を果たすだけの結果に終わり、尚氏によるマキャベリズムの実演劇にすぎなかったとされる。 護佐丸はその死後、名誉を回復し、その子孫は顕官にもつく。阿麻和利は今に至るまでその名誉を挽回する機会得られず、多くの謎を秘めた人物として人々に印象されるにとどまる。 阿麻和利の妻だった百度踏揚は、阿麻和利の死後、その討伐軍を率い、読谷の地で逃亡を図っていた阿麻和利を斬殺した鬼大城(おにおおぐすく)の妻となる。彼はもともと百度踏揚の付き人であった。 これらの断片的な出来事だけでも、それらを組み合わせればかなり面白い物語が作れよう。 その後、尚氏は7代尚徳の世で宰相だった金丸によって滅ぼされる。 金丸は第二尚氏を名乗り、中国との朝貢関係を継続させた。王朝が変わってしまうと新たな外交手続きが必要となるからの王位継承だが、1609年第二尚氏王朝7代尚寧のとき、薩摩軍の侵略を受け琉球王朝軍は大敗を喫する。 爾後、日本からの支配をうけることになるが、このときも中国との朝貢関係維持のため、明確な支配関係を結ぶには至らない。 その後の琉球はさらに様々な歴史の糸をつむいでゆくことになる。なかなかどうして興味深いものではないか。 |

| 玄界灘の荒波から博多湾を護るかのように砂州が細く、長く湾をつつみこんでる。 砂州の名は「海ノ中道」。 「香椎(かしい)」のあたりで九州本土と繋がっている。香椎にはJR鹿児島本線の駅がある。そこから海ノ中道へ向かうJR香椎線の終点は「西戸崎(さいとざき)」。海ノ中道の先端近くではあるが、厳密には先端じゃない。砂州の先端には周囲12キロの米粒型の島がある。島の名は「志賀島(しかのしま)」。陸続きなのに島? 「漢倭奴国王」と印字された日本最古(西暦57年)の金印が出土されたことから日本史の教科書の冒頭に登場する。知名度は高いはず。 博多からJRを使い、香椎で乗り換え西戸崎に至るルートはかなりの迂回路となる。所要時間は40分だが西戸崎から志賀島まで歩くのはちょっと躊躇う程度に距離がある。バスを利用することになるが列車2本、バス1本の乗り継ぎはいかにも難儀だ。博多から湾をはさんで間近に望む島へ行くのにそれほどの手間はかけたくない。 博多ポートタワーの袂から市営の渡船が志賀島へ行く。途中、西戸崎と大岳に立ち寄り、終点志賀島まで33分の航路。これが一番便利だ。正午を除き、1時間に1本のダイヤ。 「きんいん3号」で博多湾を渡った。 志賀島の船着場は島の南端、海ノ中道との連絡橋そばにある。土産物屋を除けば周囲に観光施設の姿はない。漁師町の気配が濃厚だ。 島を周回する道路を歩いて「金印公園」を目指す。海岸線を走る道路に歩道はないが道が広いので路肩を歩いても車に対する恐怖はない。 金印公園には、金印のモニュメントがあって、 |
海を見渡せて、でもただそれだけのところ。 時折、ドン、パンという鉄砲のような音が森の中から聞こえてくる。猟期なのかもしれない。人の姿が少ない。誤射だの、流れ弾だのといった単語が思い浮かび、そそくさと公園を後にした。 船着場に戻る途中、志賀島保育園のそばにいい感じの店があった。はためくのぼり旗には「サザエの壷焼き」とある。 開店したての店内に入る。サザエの壷焼きしか扱っていない店だそうだ。人のよさそうなご内儀がすまなそうに言う。 「4個で千円ですけど・・・」 恐らくそれしかメニューにないのだろう(メニューそのものが見当たらない) 「それをください」 海を見渡すカウンター席に陣取り、店内を眺めれば「お茶やお水は自動販売機を利用して下さい」との貼り紙が。店前の自販機でペットボトルのお茶を買う。しみじみといい気分だ。甘辛いつゆがぐつぐつしているサザエ4個をほじくり、舌鼓を打った。 船着場の周辺がきっと島の中心部だ。その集落の入り口に鳥居があった。少し離れた小山の上に古格な神社がある。「志賀海神社(しかうみじんじゃ)」と言う。 小山を覆う樹木はいずれもかなりの樹齢とおぼしき樹相で、神社の造りの重厚さとあいまって社格の高さが伺える。3柱の海神、綿津見神(わだつみのかみ)を祭った海神の総本社だった。 女傑「神功皇后」が朝鮮出兵(三韓征伐)時、志賀島を訪れたとのことで神功皇后まで祀られている。何か得した気分になった。 |

| 高崎で長野新幹線と別れた上越新幹線は長いトンネル群に突入する。 榛名トンネル15キロ、中山トンネル18キロ、大清水トンネル22キロが連続し、トンネルを抜けると駅という線区になる。「上毛高原」と「越後湯沢」だ。トンネル群突入直前に車窓遥かに写っていた山並みがトンネルを抜けた瞬間に眼前に聳える変化がこの線区の乗車経験が少ないためか目に新しい。 越後湯沢駅は駅前がスキー場だ。冬直前の今、まだ雪はない。下車して新幹線から在来線特急に乗り換える。特急「はくたか」は、六日町からJR線を離れ、トンネルの連続する北越急行ほくほく線に乗り入れる。折り重なる山々を抜け、狭隘な日本海岸の「犀潟」に出ればすぐに直江津だ。 なんか既視感がある路線だなと思っていたら、SONY「プレイステーション」の「電車でGO!2」に入っていたのを後日思い出した。 直江津でJRの管区が東日本から西日本にかわる。車掌も交代だ。車掌交代を告げるアナウンスが女性になった。女性乗務員の比率はJR西の方が高い(ような気がする)。 直江津の先、「糸魚川」でクレーンが稼働していた。そして北陸本線沿いに延々とクレーンの林が連なっている。 北陸新幹線高架工事のクレーン群だ。 長野新幹線は北陸新幹線の一部として開業している。東京、金沢間が開通すれば、長野新幹線は北陸新幹線に名前を変える。既存の上越新幹線、越後湯沢、金沢間を結ぶ在来線特急「はくたか」の役割ももうすぐ終わる。 越後湯沢から北越急行ほくほく線を使って直江 |
津経由で北陸へ抜けたコースは長野から飯山、上越経由で糸魚川へ抜けるコースにとってかわられる。 糸魚川を過ぎれば、荒波うちよせる日本海沿岸だ。海岸線に沿って走る細い道路。黒い瓦の古い家並みが道沿いにつながる。その甍のむこうには鈍い翠にくすんだ、白い波頭うちつける日本海。 さきほどまでいた銀座の街並からのこの風景への変化を筆者は愛する。 江戸時代の難所、親不知子不知は、高速道が立体交差し赤坂の首都高速のような景色だ。近代建築と荒々しい自然が交錯するちょっと異次元の景色。 右を見ればいままさに日本海に陽が沈もうとしている。左を見ればすでに山襞に雪をまとった立山黒部連峰。その姿は神々しくさえある。 富山を過ぎれば、次の大きな都市は高岡。 富山と高岡は両市の間にある呉羽山を境に呉東(ごとう)と呉西(ごせい)に二分される。県民気質も完全に分断され、殿様と言えば呉東は佐々、呉西は前田。味付けも関東風と関西風にわかれる。 高岡を過ぎれば、進行方向右側の海が稜線にかわる。能登半島だ。完全に水平線を覆い隠してしまうほど、その稜線は長い。 すでに車窓は夜の帳に包まれている。 やがて列車は終点金沢駅のホームにすべりこんだ。北陸新幹線が開通すればこの間、現在の所要時間4時間が2時間半程度に短縮される。金沢へ関東方面から観光客が大挙押し寄せ、街も変質してゆくことになるのだろうか。 |
沖縄行15 →→→back 96 06(1) 2) 3) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
| 毎度おなじみ弥次喜多メンバーが1名だけ入れ替わって沖縄に向かった。 メンバーはI・Y・F・N からI・Y・F・N へ。 イニシャルだと入れ替わらないのである。 某月某日(1日目) 関空発ANA1731便777-200は、曇天の那覇にランディング。早朝便のため現着も早い。レンタカーを借りてさっそく本部(もとぶ)にむかった。 沖縄自動車道「伊芸SA」で「金武(きん)湾」の景色を眺め、昼過ぎ「山原(やんばる)そば」に着。行列のできる店として有名だ。 行列ができていた。その数20名程度。ウチナーは並ぶの嫌いだから観光客ばかりだろう。30分程度でテーブルにつき、ソーキそばを消費。 次の目的地は「Ke-iki-cafe」。 カフェからの眺望が癒し指数高値の海辺の店。隠れ家に近い。前回同様、ドライカレーとバニラフレーバーのアイスコーヒーを堪能。 店内の愛犬が大きくなっていた。 「前にも同じメンバーで来られましたね」 マスターは覚えていてくれたのか。 「ひとりだけ入れ替わりましたけど」 可哀想にNは戦力外通知。 「古宇利大橋」へ向かう。橋の両脇が超絶のエメラルドグリーンの景勝地だ。曇天にもかかわらずそれでも青い海を眺めて帰路につく。途中、「万座毛」に立ち寄る。ぐるりと回遊するだけで美しい景色を眺望できるコンビニエントスポットだ。 国際通りのホテルに荷物を投げ込み、並びといっていい「波照間」へ。島唄ライブを見つつ、島食材を食らい尽くした。無論酒は泡盛各種。 某月某日(2日目) 体験ダイビング。 那覇港から43人乗りのクルーザーで約1時間。 慶良間に到着。渡嘉敷島と座間味島で3ダイブ。 |
曇天続きだったが、このときだけは青空が広がった。陽光が注いだとたんに海の輝きが変わる。ケラマブルーを体験できてよかったのだ。 那覇に帰り、ぶくぶくアイスコーヒーを喫し、国際通りを散策。市場本通奥のディープな一角にある「呉屋てんぷら店」で魚天ぷらを立ち食い。かりゆしウェアを探してブラブラしたあと松山の「やきにく華」でアグー3種盛りと石垣牛特選カルビなどでワインを消費し、「バー・ステア」でカクテル。 某月某日(3日目) DFSギャラリアでの買い物組と合流し、朝食を「A&W」で。地場のバーガーチェーンだ。 そのまま東海岸へドライブだが、嘉手納で1時間寄り道。その後海中道路を渡って、海の駅で「ブルーシールアイス」。伊計島まで東海岸の海を眺めつつドライブ。帰路「勝連城跡」に寄り、丘上の城からの眺望を愉しむ。那覇に戻り琉球ガラスの体験を。筆者は観客。 夜、「あだん」へ。満席だったので「あだん別館」へ行く。別館は初見だったので行き方を電話で聞いたがウチナーは説明が旨くない。あきらめて自力で探す。カウンター前に並べられた焼き鳥やその他の串を客が選んで焼いてもらう。泡盛と一緒に親の敵のように食いまくった。 某月某日(4日目) 朝10時から開店する南部の「カフェくるくま」へ車を飛ばす。11時前はカフェタイムだった。ここも景色が売りのカフェだ。コーヒー(皆はケーキセット)を飲んで那覇へ戻る。 「ジャッキーステーキハウス」に混雑する12時前に入り、アメリカンなステーキセットを。 13時50分の伊丹行きで無事、帰阪。 沖縄満載ツアー終了。ふ~。 |



| 「天空の城」 ラピュタではない。 但馬の守護大名、山名宗全によって築かれた山城、竹田城の異名である。秋から冬、朝霧の雲海の上に浮かぶ姿で名を馳せた。 標高353mの山上に天守を中央に三方へ縄張りをした石垣遺構は、南北400m、東西100mに及ぶ。完全に近い形で残された山城跡としては日本屈指の規模だ。備中高梁城(松山城)430m、岐阜城329m、岩国城200mを陥落させてきた筆者の次なる攻略目標が竹田城だ。 シルバーウィークの1日、とりあえず新大阪に出た。大阪圏の行楽は西行きが主流。新幹線の博多方面はすべて×印。在来線で姫路を目指すことにした。新快速で1時間。姫路、和田山間65キロを結ぶ播但線に乗り換える。ただし全線を走破する電車は特急はまかぜ以外にはない。電化されている姫路、寺前間と非電化の寺前、和田山間で乗り継ぎが必要だ。 目的地「竹田」は終点「和田山」の一駅前。 駅に降り立てば、山峡の城下町らしい静寂と気品のある佇まいがあまり多いとも思えぬ訪問者に土地への好意を抱かせる。こんな町には礼儀正しく気持ちのいい人々が住んでいるに違いない。無責任な旅人の思い込みはすれ違う老婆の深い辞儀と邪気のない会釈を得て確信に変わる。 住むには躊躇われるが、何日か逗留して雲海に浮かぶ廃城の石垣を朝な夕なに眺めるのもいいじゃないか。そんな思いを抱かせる町だ。 かつては人馬の往還も盛んであったかもしれない真っ直ぐな旧街道に僅かに並ぶ商店。建物こそ近代のそれだが、なぜか街道筋の景色は時代を超 |
えて城下町のそれを今に彷彿とさせる。 駅舎から城山には鉄道を潜る小路を使う。ほぼ目の高さに走る鉄路を屈みながら潜りぬける。頭上を列車が走りぬけるときはさぞかし迫力があることだろう。経験してみたいとは思わない。 城山の麓には寺院が立ち並んでいる。城下町における寺院は、戦時、砦となり兵員の駐屯地ともなる。陽光を反射する黒い甍と古格な鐘楼や本堂、山門は小ぶりながらも尊厳がある。人々の敬意を集めているに違いない。山名氏の後、竹田城の城主となった太田垣光景や最後の城主となった赤松広秀の眠りを守っているようだ。 寺町の手前から城山登山道が伸びている。 山頂353mの城跡まで800m45分と書かれている。 入り口の鉄柵を開けて山に踏み入る。 秋が深まるこの季節、怖いのはスズメバチだ。早期警戒機が威嚇に現れたら即撤退だ。 登山道入り口の階段の段差が最も高い。体を持ち上げるためにかなり踏ん張りが必要だ。このままこれが続くとしたら、しんどいことになると心配したが、途中から段差は小さくなった。 先般、伯耆大山を登ったのだ。300mの山など小指の先でチョイだ、などと思っていたが、重力に逆らって体を押し上げる行為自体のしんどさに変わりはない。瞬く間に全身が汗みずくだ。 30分で頂上についた。 穴太衆積みの石垣が山上を覆っている。 北千畳、南千畳、虎丸、三の丸、二の丸、本丸跡の面積はかなりのものだ。 眺望がすばらしい。 鳶がゆっくりと輪をかき、上昇気流に乗って翼を翻す。風が心地よい。この城はオススメだ。 |

三陸縦貫行4(前谷地-石巻-仙台) →→back 三陸縦貫行1 2 3 4
| 「前谷地」の前の接続駅「気仙沼」では時間短縮の日和見策を採用することもできた。 「気仙沼」を14時33分に発った筆者の1時間17分後、15時50分に「仙台」行きの「快速南三陸4号」が「気仙沼」を発車するのだ。しかもこの快速、最終目的地「仙台」には筆者の乗り継ぎ計画よりも37分早く到着する。 この乗車を見送ったのは、経路が「前谷地」から「小子田(こごた)」経由で東北本線に乗り入れてしまうからだ。三陸海岸は、「牡鹿半島」以北の地域名称だから、少なくとも半島付け根の「石巻」まで行かねば、三陸縦貫作戦も画竜点睛を欠くというものだろう。 ちなみに「牡鹿半島」は「おしかはんとう」と読む。秋田県の「男鹿半島(おがはんとう)」と混乱しやすい。筆者もこの紀行を書いてはじめて違いに気がついた。 「前谷地」で乗車した石巻線で再び海岸線に向かう。さんまで有名な「女川」行きの各駅停車で4駅、「石巻」駅には17時04分に到着した。 いよいよ最後の線区に乗車する。仙石線で「石巻」から「仙台」まで走破して三陸縦貫作戦が完結する。接続列車は17時19分発。 仙石線は、ロングシートの通勤仕様なので旅情はない。おまけに仙台に近づくと地下鉄となる。昔は仙台駅地上ホームから古い中央線のオレンジ色やら山手線の緑色、常磐線のもぐさ色が混入し実にカラフルな編成を見たよーな記憶があるような、ないような。今は仙台の先に「あおば通」駅ができてそこが終点(始点?)となっている。 仙石線には、A快速やらB快速やらの車種が増えていた。でも乗車するのは各駅停車。 |
石巻駅に入線してきた電車を見て情報を修正。1車両だけロングシートではなかった。見慣れぬ仕様の車両が連結されている。「2Wayシート」と表記してある。どうやら、2席連結のシートが進行方向に向きをかえ、クロスシートになったり、ロングシートのように横並びにもなったりする仕掛けのようだ。 トイレ設備も新しい。 ドアは都市部を走る通勤電車にしては珍しく半自動。少なくとも自分でボタンを押さないと開かない。 落日のスピードが早くなってゆく。車窓がどんどん暗くなり、景色が消え、社内照明の照り返しがガラスに反射し始めた。 「陸前大塚」駅前の海は車窓の直下、どんどん満ちてくる潮の流れが川のようにも見える。 松島海岸や本塩釜は、海岸線の景色を期待しても失望するだけだ。 そして18時43分。「仙台」駅到着。 陸奥から陸中、陸前を縦貫する三陸の旅が終わった。総延長409キロ(東京、大垣間に匹敵)新幹線で1時間半の距離を11時間10分かけて走破した。マニアの皆さんは「乗り鉄」とでも表現するのだろうか。筆者にはよくわからない。 翌日、仙台城址に散策の足を伸ばした。 杜の都とはよくいったものだ。青葉通りはまさしく翠蓋の下、のどけき光のシャワーで心まで青く染まってしまいそうだ。初めてこの地を訪れた昔日を思い出し、広瀬川を見下ろす筆者はめらんこりっくなひと時を過ごした。 仙台空港迄17分で接続する仙台空港線が三陸縦貫作戦のおまけ線区となった。 |




| JR 八戸線 |
三陸鉄道 北リアス線 JR山田線 南リアス線 盛行 |
JR 快速 スーパー ドラゴン 一ノ関行 |
JR 気仙沼線 小牛田行 |
JR 石巻線 女川行 |
JR 仙石線 あおば通行 |
|
| 八戸 | 7:12 | |||||
| 久慈 | 9:02 | 9:12 | ||||
| 宮古 | 10:43 | |||||
| 釜石 | 12:02 | |||||
| 盛 | 13:01 | 13:17 | ||||
| 気仙沼 | 14:18 | 14:33 | ||||
| 前谷地 | 16:18 | 16:44 | ||||
| 石巻 | 17:04 | 17:19 | ||||
| 仙台 | 18:42 |
三陸縦貫行3(釜石-盛-気仙沼-前谷地) →→back 三陸縦貫行1 2 3 4
| 「釜石」駅から三陸鉄道南リアス線に乗り入れると再びアナウンスが懇切丁寧になる。 窓から吹き込む海風はあいかわらず冷たい。 名勝地「千歳(せんざい)海岸」で徐行。「吉浜」駅、流浪の借金王石川啄木の歌碑がある。 駅と駅の間はトンネル。 トンネルを抜けると駅。 駅の前は山塊をえぐりこんで湾入してきた太平洋。その繰り返しがリアス海岸を走っていることを実感させる。 13時01分、終着駅「盛(さかり)」に到着。 3時間49分、行をともにした三陸鉄道気動車と別れを告げる。 JR大船渡線一関行き快速スーパードラゴンが停まっている。車内は帰宅の学童でかなりの乗車率。通路側の対座シートになんとか座れた。 この列車で「気仙沼」まで行く。 4駅ほどでにぎやかな男子、女子の各グループが降りていった。窓際席を回復。 車窓は陸前の海に代わっていた。 トンネルの姿が消え、海岸を見下ろすことがなくなった。海面と視線がほぼ水平だ。 列車は、広田湾の沿岸を走っている。養殖のいかだが浮いている。あれは牡蠣?広田湾の牡蠣はブランドものとして有名らしい。 「陸前高田」を過ぎた。14時の日差しは思いの外強く、車窓を覆うシェードがないのでカーテンをひく。車窓を失いちょっと不満。それにしても大船渡線はなぜ「ドラゴンレール」というのか。 再びトンネルが連なり始めた。鉄路は三陸海岸を一旦離れ、大きく北周りに山塊を縫いながら、海にむかっている。 |
この山を下れば「気仙沼」だ。 14時18分。「気仙沼」駅3番ホームに入線。 JR気仙沼線「小牛田(こごた)」行きは14時33分の発車。1番ホームですでに待っている。それにしても三陸縦貫行、接続はかなりいい。 始発電車の乗車前にはホームの隣駅表示を確認する。列車の進行方向を知るためだ。たまに逆向きに発進されてあわてることがある。海際を走る路線で進行方向を誤認し、海が見れないなんて、映画館でわざわざ川合俊一の後ろに座るようなものだ。席を確保したら。窓の開閉をチェック、古い車両は窓があがらないことがあるからだ。 すべてよし。 発車。車窓は完全な住宅地のそれだ。 やがて、何度目かの海岸線の走行。松林の梢の隙間に輝く青い海が美しい。 線路脇の田に落ちる列車の影が長くなった。木々の影も濃い。陽光にオレンジの輝きが混ざり始めた。15時30分。陽が傾きつつある。 「志津川」駅を過ぎると海面に大量の浮きを見て内陸へと向きを変える。山中に入ると背の低い山はすでに他峰に遮られ陽光を失っている。 「柳津」駅と「御岳堂」駅の間で水量豊かな一級河川を渡橋。北上川だ。北上川は長い。遠く盛岡からここまで南下している。鉄橋の下流で分流し北上川と旧北上川となり、牡鹿半島の太平洋岸にある追波湾と内懐の石巻湾に注ぎこむ。 すでに周囲は一面の田。仙台平野だ。細分すれば仙北ということになるか。蕎麦の花が白い絨毯を敷き詰めたように咲き誇っていた。 16時18分終点「前谷地」到着。 八戸を出てから9時間8分が経過していた。 |

三陸縦貫行2(久慈-宮古-釜石) →→back 三陸縦貫行1 2 3 4
| 9時2分、八戸線は終点「久慈」に到着。 跨線橋の上で三陸鉄道の車掌がJRのチケットを回収し、乗車を促す。 「あとで車内で切符を販売します」 三陸鉄道北リアス線は2両編成の気動車。 すでにホームに待機している。乗り換えの乗客も多くはないが、やはり窓側のいいシートには座りたい。乗り換えグループの中ではトップでホームに駆け下りた。すでに何名かの乗客がいる。意外や対座のBOXシートではなくクロスシート。 9時12分「久慈」発。 このあと、「宮古」「釜石」を経て「盛(さかり)」までの道中だ。 三陸鉄道は平成21年4月で開業25周年。おめでとうございます。地元での愛称は「三鉄」。 「久慈」「宮古」間はワンマン運転なので乗降は先頭車両の前ドアのみ。 チケットは懐かしいパチンパチン型。 秋には遡上する鮭で銀色に輝くという安家川にかかる安家川(あっかがわ)橋梁を渡る。 続いて大沢橋梁。 いずれも渡橋時は徐行運転となる。 いい車窓だ。 次々に現れるトンネル。それを抜けると海を見渡す絶景が待っている。三陸鉄道、なかなかにいい。車内アナウンスも懇切だ。近隣の観光ガイドもあますことなく伝えてくれる。「普代」は、北緯40度の地球村。海水浴場と太平洋を見下ろす展望台が有名らしい。 やがて、鉄路は海岸線を離れ、北上山地に視界を遮られるようになる。 「田野畑」で行き違いのため3分の停車。マニア |
の皆さんがカメラをひっさげホームにむかう。筆者はマニアじゃないので暖かく見守るのみ。 「島越(しまのこし)」 団体客登場。いきなり満席になる。何があるのか、あるいはあったのか。 車内が冷え込みはじめた。これは冷房のききすぎなのか、外気温のせいなのか。まだ9月5日なんだけど・・・窓の外側が幾度も曇るということは・・・冷房をきかせすぎだな。窓を開けようにもトンネルが多いので開閉がせわしない。それに風は意外と冷たいのだ。 6532メートル、新幹線を除いた東北の鉄道トンネル中、最長の真崎トンネルを潜る。 「太老」で団体客降車。 10時43分「宮古」に到着。 JR山田線は盛岡に繋がっている。この線区は3往復くらいの乗車経験がある。 列車はJR山田線に乗り入れ、「陸中山田」を経て「釜石」へ向かう。「釜石」まではJRの運行なのだろう。アナウンスがいきなりそっけなくなり、沿線ガイドも途絶える。 山中を走る鉄路だが、たまに太平洋が湾入してくる。 「アボルダージ!(接舷戦)」心の中で叫ぶ。この地にあっては気分はもう土方歳三である。宮古湾海戦のシーンが脳裏に浮かぶ。 「吉里吉里」井上ひさし氏の東北への情念が生み出した邦の駅をすぎれば、釜石まであと20分弱。 12時02分「釜石」到着。 JR釜石線が花巻に向かっている。 列車は8分の停車の後「釜石」から先、三陸鉄道南リアス線に入る。終点「盛」まであと50分。 |

三陸縦貫行1(八戸-久慈) →→back 三陸縦貫行1 2 3 4
| 三陸縦貫作戦を発動するときがきた。 作戦名は「ウミネコ」 「U(ユニフォーム)・M(マイク)・I(インディア)・N(ノーヴェンバー)・E(エコー)・K(キロ)・O(オスカー)」だ。 朝7時12分。 八戸発久慈行きのローカル、気動車は新学期の中高生で溢れかえっていた。たわいもないじゃれあい、あたりはばからぬ笑い声があちこちではじけている。 ひさしぶりだなあ、こういう環境。お願いだから新型インフルに罹患していないでね。 東北新幹線の乗り入れでターミナル化した八戸駅だが、繁華街は6キロ離れた本八戸駅にある。八戸から2駅、ちゃんとそれなりの高さのビルもある。低層の寂しげな集落をイメージしていた筆者。いやはやおみそれいたしました。沿線風景は屋根の連なる立派な都市近郊住宅地だ。 意味不明な長い停車を何度も繰り返しているうちに「鮫」で最後の学生グループが下車していった。それでも車内はそれなりの乗客数。みんな、どこに行くんだろう。 車窓はリアス式の三陸海岸の景色に変貌した。 「種差海岸」駅周辺には、民宿が多い。海水浴場となる砂地があるのかもしれない。海岸線の多くは岩礁を洗う白い波濤で縁取られている。そして、かすかなもやが垂れ込めている。これが「やませ」なのか。 八戸線の走るエリアは台地状の地形となっている。車窓は意外とフラットな平面だ。一面に広がるすすきの穂が風に揺れている。 「階上」と書いて「はしかみ」難読地名はどこに |
でもある。いちご煮の里らしい。いちご煮とは三陸名産のうにとあわびの潮汁の土地名だ。 「Oja」とのローマ字表記を「大蛇」と漢字変換できるのは地元民だけだ。 「種市」でそれまで車内を賑やかしていた私服の学生集団が大挙して降りた。引率者らしい年輩者も数名同行している。遠足か社会見学なのだろう。車内はいきなり静寂に包まれた。 車窓に広がる海がますます大きくなった。 窓を開ける。 むせかえるような磯の香りが吹き込んできた。 開け放した車窓から吹き付ける風はすでに体が冷えるほどに冷涼である。列車が触れる木々の梢から陽光を浴びて輝き落ちるのは朝露か、昨夜、知らないうちに降った雨の雫か。 ローカル線ならば、追憶にひたり回想にふける時間はたっぷりとある。あのときああしておけば、このときこーしておけば・・・人生のいくつもの分岐点が時系列を無視して次々に去来する。そのひとつひとつの選択を決して後悔していないし、現在を肯定すること人並み以上の筆者だが、編みそびれた仮定の人生に思いを馳せ慈しむのもたまにはよい。 気がつけばもうすぐ五十路。街角の警官からは「ご主人」と呼び止められ、初見の店では「旦那さん」と言われる。自覚は二十歳の頃とたいしてかわらないのに外見だけは心を置き去りにしてゆく。四十を過ぎれば男は顔に自信を持てという。男の顔は履歴書とも言う。おぼつかないなあ。 いつのまにか海岸線から遠ざかり森の中に入っていた。やがて視界が開け、住宅地が現れた。 終点「久慈」が近づいてきた。 |
| 「みちのく」への郷愁深まる季節がやってきた。 関東圏に長かったせいか、東北地方は筆者の精神的静養地として古くから存在していた。その時歴は金沢に次ぐ。 渡来人系の遺伝形質を引き継いでいると思われる筆者だが、源日本人の故郷みちのくへの執着もだしがたい瞬間は確かにある。 夏の喧噪が鎮まり、はしゃぎすぎたあとの内省的沈潜が生まれていた。その深度は夏の華やぎの分だけどっぷりと深い。 暮色に憂愁の気配が滲み、黎明の輝きに陰りがさし始める季節、筆者の心は東北に馳せる。晩夏と錦秋のきわどい狭間の東北が待っている。 「はやて25号」は北にむかう。 空を覆う薄い雲の間から地上にさしこむ光条はすでに強さを失い西方に低く柔らかい。 大宮を過ぎれば、仙台、盛岡、八戸にしか停車しない最速の「はやて」は、朝廷にまつろわぬ蝦夷の土地に向け疾駆する。 街に灯りがともり始めた。 それは当初、目立たぬようにためらいがちに、やがてそこここで煌々と輝き始め、暮れなずむ夜の街の装いへ車窓が変貌してゆく。 あの灯りの下には灯りの数だけの人の営みがある。その地に定着した確かな人生があり、漂泊の旅人が求めて得られぬ喜怒哀楽に満ちた家庭生活と幾世代にもわたって引き継がれてゆく人生の輪廻がある。 薄暮の中、車窓に映ずる景色は絵画のように動きがない。 遠く工場の煙突にたなびく煙すら静止画のように中空にとどまり続けているようにも見える。 |
それはモノクロームの世界。 セピアの色褪せた写真の世界。 車の赤いテールランプが浮き立っている。 完全に夜の帳が下りた頃、列車は恐竜の骨格標本のような八戸駅のホームにすべりこんだ。 「おんでやぁんせ八戸」 駅直結のホテルに荷を降ろし、駅前の和食の店「ほむら」の暖簾をくぐる。 心和む酒食のひとときを過ごして宿にもどる。 昨年のこの時期、筆者は山形の芋煮会の会場にいた。鶴岡、酒田をめぐり会津の奥座敷東山温泉でのんびりとしていたのだ。今回の東北行はまったく違うプランを用意した。 仙台、八戸間の新幹線営業距離は280キロ強、東京、豊橋間に僅かに足りない。同区間、陸奥、陸中、陸前の三陸を縦貫するローカルの総延長は409キロ。これは東京大垣間に匹敵する。 今回、このローカル線を利用して三陸縦貫行を実施するのだ。八戸を起点に、八戸線、三陸鉄道北リアス線、山田線、三陸鉄道南リアス線、大船渡線、気仙沼線、石巻線、仙石線と乗り継ぐ。 経由地は、久慈、宮古、釜石、盛、気仙沼、前谷地、石巻、そして終点仙台。新幹線ならば、最短1時間19分で着く経路をローカルで走破する。 実は、東京駅で、東京発、八戸経由、久慈、宮古、釜石・・・経由仙台の1駅前までの片道切符を購入しようとした。片道切符は遠距離逓減制で長くなればなるほど割引率が上がり、お安くなる。無論、筆者はマニアではない。 「あ~それ、できません」駅員の無情な一言。途中2線区を走る三陸鉄道が第3セクターなのだ。いたしかたなし。マニアでないので執着はしない。 |
沖縄行14(チービシ編) →→→back 96 06(1) 2) 3) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
| チービシは、那覇と慶良間諸島の中間に位置する神山、クエフ、ナガンヌ、3つの無人島で構成される環礁の総称である。 那覇市内の泊港からチービシへの定期航路はない。筆者は、ナガンヌ島オフィシャルサイトを運営する会社の専用ツアーを予約した。 泊から高速艇(大型クルーザー、乗客53人乗り)で20分も航走すれば白い砂浜、バスクリンをぶちまいたような真っ青な海のチービシに到着。 7月~9月は1日3便あって、筆者は朝イチ8時30分出発を指定された。出発時間によって、帰りの時間も決まる。8時30分の組はナガンヌ島を14時に出ることになっていた。 上陸してレンタル品の受取に若干の待ち行列ができるが、焦るほどのものでもない。スノーケル4点セット(フィン、スノーケル、マスク、ライフジャケット)とデッキチェア、パラソルのタグを受け取る。ひとり旅なので貴重品を預けるロッカーが必要だったが予約しそびれた。しかし朝イチ組だったので現地でのオーダーで間に合った。 無人島だが、施設はそれなりに整っている。 (宿泊可能なコテージまである) 空いているデッキに荷を置き「使用中」のタグをパラソルにくくりつける。SPF50の日焼け止めを塗りたくり、シュノーケリング開始だ。 ぱしゃぱしゃぱしゃ。 遊泳区画は定められており、そんなに遠出はできない。ライフジャケットを着用していれば外側の赤い浮きまでは行っていいらしい。 波打ち際でも海は透き通っている。 できるだけ遠くへ。魚を眺めゆったりとビーチに戻ってはチェアで寛ぐ。 |
那覇空港を離陸するシップが間近の空を上昇してゆく。軍の偵察機が定期的に巡回飛行を繰り返している。2機編隊の戦闘機が高速で視界を横切る。沖縄だなあ。 夏、ウチナー(地元民)はビーチパーティをする。浜辺のバーベキューだ。(彼等はあまり海に入らない)バーベキューセットを予約していた筆者はダイニングテラスの予約席で、パラソルの下バーベキューコンロにラム肉やソーセージ、焼き鳥、野菜を載せてひとりビーチパーティ。 いいじゃないか。 腹を満たして、4回目のぱしゃぱしゃ。 沖で左腕をちょいと見る。 (まだ、12時45分。時間はたっぷり・・・) ん? 変だ?なぜ海中で時間がわかる? マスク越しに見る左腕に腕時計があった。もちろんダイバーズウォッチじゃない。完全防水でもない。生活防水だ。 じたばた!じたばた! 浜に戻り、時計を確認。何事もなかったかのようにチコタコと時を刻んでいる。よく頑張った。 最後のひと泳ぎを堪能して島を離れた。 ホテルに帰るとヒリヒリ感あり。はてSPF50を塗りたくって、紫外線対策は完全だと思っていたが・・・それは「表」だけだったと気がついた。 シュノーケリングで泳いでいた筆者はからだの裏面を太陽に晒していたのだ。 ライフジャケットのおかげで背中はセーフだったが左右の二の腕と腿からふくらはぎまでの裏側がまっかっかである。ひりひりひりひり。 経験不足を露呈してしまった。 |

画像 下段 中 上空を横切る那覇空港からの離陸便
| 終日、家で過ごす休日は筆者の精神を蝕む元凶だ。1日だけならまだしも、ひさしぶりのフルカウント休日2連荘。2日とも家になどいたら、筆者は腐乱死体と化すだろう。 しかしながら、8月に入っても明けない梅雨のせいで、チャリをこぐのはためらわれる。 思い立って「天安門」に行くことにした。 戦車部隊が民主化を求める学生の無差別弾圧を強行したのは1989年。あれから20年の歳月が流れている。 天安門に降り立つと、日本列島上空の不安定な大気が生み出す雨雲が切れ、雨あがり、爽快な青空が広がっていた。 ひぐらしの鳴き声がお盆の到来を告げる中、「万里の長城」を散策する。 「兵馬俑(へいばよう)」は、秦の始皇帝の墳墓を守るための副葬品だ。世界遺産に登録されている。等身大の兵士や戦車が無機質な蛍光灯の光をあびて亡き皇帝の眠りを守護している。兵士の顔はひとつとして同じものがない。 展示区画は、発掘中のものと、埋葬時の再現をしたものがある。 万里の長城は長い。 兵馬俑を後にして、長城を登ると唐代に建造された巨大な二つの塔を持つ「双塔寺」が現れる。途中、長城を外れると「磨崖仏(まがいぶつ)」があらわれた。断崖に刻まれた仏だ。 炎天下である。 思いのほか登りでのある坂を歩いているうちにシャツは風呂桶に落としたタオルのように繊維の隅々にまで汗を吸い込み、吸水力を完全に失っている。ジャケットにまで汗染みが広がり始めた。 |
「五百羅漢」のむこうに「鶏足寺」が見えた。 その傍らには「スフィンクス」に守られた「ピラミッド」が現れた。 ん? 「石貨神殿」の脇には「マーライオン」が溜め池を見つめている。 なに? 「モアイ像」の裏に「太陽の門」が中空への石段を積み上げ、その脇には「巨石人頭」が転がっている。 ちょと待て。 「自由の女神」と「人魚姫」、分隊規模の「小便小僧」を見る前に筆者は入口で「凱旋門」を潜ってきた。 なんだ、なんだ? 谷を挟んだ対面の山の頂には「ノイシュバンシュタイン城」が聳え立つ。その姿は神々しくも美しい。 おい、そこはどこだ? さて、いったいここはどこでしょう? 答えは、世界の観光資源を一手に集めた播州姫路の「太陽公園」。 姫路駅からバスで30分の距離にある。 広大な敷地を有する公園には、世界各地の観光資源のレプリカが遊び心とかなり真剣な創造性をもって林立している。 施設は、どうやら障害者の授産事業に利用されているらしい。周辺には幾つかの福祉施設が点在している。 なかなかにいいアイデアの事業だ。 |
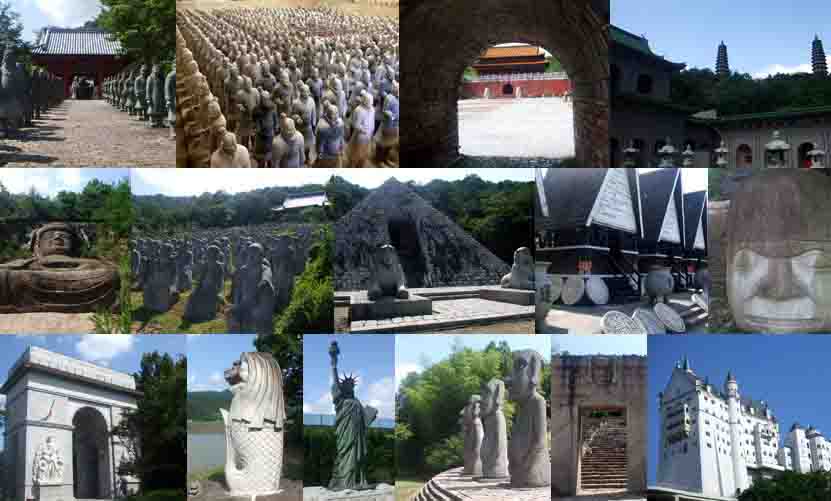

| 宮古諸島を構成する8島のうち池間島と来間島は本島と橋で結ばれている。残り5島のうち伊良部島は現在、架橋工事中で2012年度に完成予定。下地島は伊良部島と6本の橋で結ばれている。伊良部大橋が完成すれば本島と繋がることになる。 残された離島は3島。 宮古島に近い順に大神島、多良間島、水納島(みんなじま)。 大神島は、宮古島の北端4キロに浮かぶコニーデ型の小さな島。神聖な島とされ御嶽(うーたき)がある。キャプテンキッドの財宝伝説もあるが人口は50人にも満たない。最も古くから人が住みついたと言われている。 水納島(みんなじま)は、石垣島と宮古島のほぼ中間、両島から50キロ内外。島民は1世帯、数名しかいない。沖縄本島本部の同名の島(クロワッサンアイランド)と混同しないように。 多良間島は、宮古よりも石垣に近い19.5平方キロの島。非日常の極みを経験できそうだ。 しかし、この3島、今回はパス。 平良港から15分の伊良部島に向かった。 チャリでまわるにはアップダウンが多すぎる。初めての地は観光タクシーにまかせるに如かず。港でつかまえたタクシーが周回道路をぐるりと左まわりで案内してくれることになった。 昭和40年まで使用されていた近在で唯一の井戸「サバ沖井戸(サバウツガー)」は崖下の海岸沿いにある。石段の数は123段。ここで水を汲み上げ集落まで持ち帰っていたとはタフな話だ。 周囲の景色が美しい。 昔、沖縄本島に向かう船を見送った岬が「フナウサギバナタ」。サシバという鳥を模した展望台 |
がある。伊良部大橋建設地そばの牧山(まきやま)展望台はこの造形を近代的に模している。 島の裏側「佐和田の浜」。 遠浅の海岸に幾つもの巨岩が並んでいる。 1771年4月24日(明和8年)午前8時。石垣島近海でマグニチュード7.4の地震が発生し、最大遡上高85mの津波が石垣と宮古を襲った(波高36~39m)。石垣では津波が島を横断したと云われ8500名弱の死者が出た。宮古も死者数は2500名強。下地島の集落は全滅、下地島から流出したおびただしい数の岩が島の海岸線に残されたとされ、それが目の前に転がっているわけだ。津波は「明和の大津波」と呼ばれている。 津波で海岸線奥深くの陸地に流れ着いたとされる巨石が「帯岩」である。 「魚垣(カツ)」と呼ばれる潮の干満を利用した原始漁法の造作物の沖はコバルトブルーに輝き、国内唯一の民間航空機パイロット訓練施設「下地島空港」の滑走路進入灯が凄まじい碧さの海にむかって伸びている。 レシプロ機が訓練をしていた。 何度もタッチアンドゴーを繰り返している。 空港のある下地島から伊良部島に渡るこの海岸線は、まさにオキナワンブルー。「中の島ビーチ」「渡口(とぐち)の浜」などの海水浴場に恵まれ、「通り池」という地底で海と繋がっている2つの池などもある。芸能人御用達のコテージ風ホテルもある。ここで滞在しても面白いかもしれない。夜の繁華街を失うのは痛いが。 2時間半もあれば、伊良部と下地島の基本的な観光は終了する。伊良部大橋が完成すれば観光客、意外とやってくるんじゃないか。 |

↑下地島のパイロット訓練飛行場。タッチ&ゴーの訓練を繰り返すレシプロ機。この飛行場は747ジャンボでも離着陸できる。
↓画像下、左から 「魚垣」「渡口の浜(2枚)」「牧山展望台」とそこからの眺め


| んみゃ~ち(ようこそ)宮古島。 観光スポットがコンパクトにまとまっている宮古諸島は2、3泊の短期滞在にはうってつけだ。 島の中心地「平良(ひらら)」から29キロ弱。 島の東端、東平安名崎がある。東端と言うが感覚的には南端だ。チャリで行こうかと思ったがやめて良かった。標高110メートル程度の宮古島だが、アップダウンはしっかりとある。レンタルのママチャリでは荷が重い。 とは言え、フラットな地形であることは間違いない。島には川もない。島の農産物は、さとうきびとタバコ。農業用水は巨大な地下ダムから供給されている。サンゴの石灰岩が盛り上げってできた島は、雨水を蓄えておくことができない。スポンジを通り抜けるようにためらいもなく染み込んでしまう雨水は放っておけばそのまま海に逃げてしまう。宮古では、海への出口をベトンで塞ぎ、世界初の巨大地下ダムを作りあげた。 中心地を離れれば、島の道路は幅員が似たり寄ったり。交差点には信号もない。どっちが優先かわからない。島のオジイとオバアに停まる気はない。レンタカー組は気をつけよう。 東平安名崎は海にむかって突き出した2キロほどの岬だ。言うまでもなく周囲はコバルトブルーの海原。突端の灯台が白く輝いている。岩場を洗う波はやや猛々しく幾重にも折り重なって海岸線に向かってくる。。 岬を背に海岸沿いに北上すると比嘉(ひが)ドライブパークがある。ここから見下ろす海は岬のそれとはうってかわって穏やかだ。 太陽が雲間に隠れると雲の影が浮かぶ海面だけが鈍くくすむ。陽光が注ぐとみるみる青緑色の輝 |
きを取り戻す。まるで薬剤を海面にスポイトで一滴垂らしたとたん、何かの化学変化がそこに生じたかのようにコバルトブルーの輝きが周囲に大きく広がってゆく。その変化はネコの目のように目まぐるしい。 東平安名崎から島の反対側、正確には北西方向に西平安名崎がある。島西(と言うよりは北端のイメージ)のこの岬にも灯台がある。 東西の岬には3本づつ、風力発電の風車が立てられている。2003年、最大瞬間風速74.1m(空自参考86.4m)の台風14号(アジア名メイミー)に襲われ、この風車は軒並み倒された。踏みとどまった1本も風車が吹き飛んでしまっては単なる柱だ。島中の電信柱もバキバキと折れた。 岬の先には池間島がある。この島も架橋されている。池間大橋の周囲の海はさわやかに碧い。 池間島の先、5~15キロに八重干瀬(やびじ)と呼ばれる国内最大のサンゴ環礁地帯がある。 ダイビングポイントだ。 1年ぶりにダイビング。ひゅー。ごー。 サンゴの大敵、鬼ヒトデは水温が上がり、28度を越えると急激に繁殖する。サンゴは水温が高まると急激に衰弱する。サンゴを守るためには水温を下げるシステムが必要となるが、その役目を台風が担う。台風が海水をかきまわすと海水温が下がる。サンゴは歓び、鬼ヒトデは悲しむ。 台風は水温が28度を超えると発達する。実に微妙な自然界のバランスだ。 人智などあまりあてにならない。 来間大橋完成以前の前浜ビーチは、野球場くらいの幅の白浜が広がっていたそうだ。橋の架橋後バレーボールコートほどの幅に縮んでしまった。 |

| 6月29日、日本列島は全域で雨。 筆者は梅雨真っ盛りの本土を離れ、青空と陽光を求めて宮古島へ向かった。 昨年は6月17日に梅雨明けした沖縄だが、今年はまだだ。本島は近来にない大雨に見舞われ土砂崩れが相次いでいる。 週間天気予報では沖縄から傘マークがはずれない。不安を抱きつつ那覇乗継で宮古空港にランディングした機内にCAのアナウンスが流れた。 「昨日28日に梅雨明けをした沖縄にようこそおいでくださいました」 やったね。 宮古島の空はぬけるような青。気温は31度。 「今年は雨が少なかったねぇ」タクシードライバーが謡うように話しかける。沖縄本島から宮古島まで300キロ、東京-豊橋くらい離れている。那覇の天気予報なんか見ても意味はなかったのだ。 初めての宮古島だ。 まずは土地勘を養うべく地図を眺める。 島の中心は平良。地名では「ひらら」と読み、人名だと「たいら」と読む。 島は全周100キロ弱、159平方キロ、面積的には大阪市の209平方キロよりもちょいと狭い程度。宮古を主島とする宮古諸島は、池間、来間(くりま)、伊良部、下地、大神、多良間、水納の8つの有人島で構成されている。 池間と来間の両島には美しい橋が架けられており、伊良部島へは30分おきに2社の高速船やフェリーが渡海している。高速船ならば15分程度で渡れる。伊良部島の裏側に下地島があり、両島を隔てているのは溝のような狭さの海峡。ここに六つの橋がかけられている。 |
これらの島々の周囲は、とにかくひたすらに碧い。エメラルドグリーンの大盤振る舞いだ。筆者はこのオーシャンビュー群を暫定日本一と認定。 もっと早く来ればよかった。筆者にとって宮古は、那覇と石垣の間で、東京、大阪間における名古屋みたいな位置づけになっていた。どうせ行くなら遠くまでと、宮古を跳び越して石垣に行っちゃっていたのだ。しかし、今回の訪問で認識を改めた。また来ます、必ず。 平良港に隣接するアトールエメラルド宮古島というホテルに空港から向かう途中、しかし、筆者はタクシーを反対方向にむけてもらった。すぐそばに来間島があったのだ。 島の対面には3キロにわたって続くまっ白な前浜ビーチ。宮古一美しいと言われるビーチだ。あるいは東洋一とも言われている。無論、正面の海はエメラルドグリーン。来間大橋がその蒼海を美しい弧を描いて渡っている。渡橋し、来間島の展望台から海峡を見下ろす。 (見事な景色だ) 一瞬で日常から離脱した。 頭の中に居座っていた日常生活の夾雑物がすべてふっ飛んだ。 景色で忘我の境地に達したのは久しぶりだ。 夜、酒食を求めて繁華街へ向かう。 西里通りと下里大通りにはさまれた数ブロックがこの島の最大にして唯一の繁華街だが、その言葉は実態とかなり乖離している。島民5万の宮古だが4万の石垣よりも繁華街に寂寥感が漂っている。稚内や網走に通じる寂寥感だ。 ただし街は寂し気でも個々の店舗は別だ。都合3夜、かなり堪能させてもらった。 |

| 丹波、丹後、但馬の領域認識はかなりアバウトにインプットされている。但馬って言われてもどこからどこまでがそうか、鳥取との境目もよく分からない。(そう言えば、鳥取も「鳥」が先が「取」が先か瞬間的に悩むことがある) 大阪と神崎川を隔てた西岸の尼崎を起点に北上するルートは筆者にとってあまり距離感を感じさせないコースだ。 北上してすぐ宝塚だ。ここを越えると車窓が山間部の渓流モードになり、旅気分が生まれてもいいはずだがなぜか通勤モードから抜けられない。関東圏で言えば、新宿、甲府間の雰囲気に似ている。宝塚は八王子に対比されよう。(宝塚マダムの皆様ゴメンナサイ) 宝塚の先にある三田("みた”ではない。"さんだ”)は但馬牛を肥育してブランド化した三田牛の産地として名高い。牛肉を買いに行く所だ。 その先の「篠山口」までは通勤快速で行って帰ってくるレンジ。そのせいか「篠山口」の北「福知山」もなぜか距離感が希薄だ。明智光秀が丹波経営の要として築いた福知山城があるが、観光立地を目論んでいるとは思えない。天橋立で有名な丹後半島にむかって鉄路が分岐するジャンクションとしてしか機能する気が感じられない。。 「福知山」の先「和田山」は関東圏の人間には?な土地だが播但線で一駅隣に「竹田」がある。天空の城として名高い山名氏の出城「竹田城」跡がある。しかし、それはまた別のお話。 「和田山」の先が「豊岡」。京都府の最高や最低気温を記録する所。但馬の中心地でもある。ここから車で足を延ばすと蕎麦で有名な城下町「出石」がある。 「豊岡」まで来たら、もう目と鼻の先が「城之崎温泉」だ。地名としては全国区だが、利用者は近畿圏に限られよう。冬場になると松葉ガニと温泉がセットで観光客を待ち受けている。 つまり尼崎、宝塚、三田、篠山、福知山、和田山、豊岡と転々としているうちに城之崎温泉で日本海岸に出てしまうわけだ。 実にはるばる感のない路線だが、大阪から特急「北近畿」で2時間40分強。指定席料金にして5,250円、つまり、料金的には福井クラス、時間 |
的には金沢クラスということになり「あれ?コストパフォーマンス的にどーなん?」となる。 この日、城之崎温泉まで来たらもう一足延ばす必要があった。幸い快速電車が接続していた。 よく見たら「全席指定」などという生意気な車両だ。510円を支払い席を確保する。所用時間はローカルとかわらない。何のための快速じゃ? 快速の名は「あまるべマリン」。 ベタだなあ。 約45分の走行で「餘部」に到着する。高さ41.5m、長さ310.7mの餘部鉄橋そばの駅だ。 餘部鉄橋は明治45年に完成した鉄鋼製の橋。今でこそ、明石海峡大橋やら瀬戸大橋などの壮大な橋を見慣れてしまっているが、当時から今に至るまで、このタイプの橋としては日本一だし、いまだに現役と言うのもスゴイと言えばスゴイ。 明治生まれの鉄橋は老朽化し、現在新鉄橋の工事中である。 在りし日の餘部鉄橋を見ておこうと、マニアの皆さんの熱い視線が注がれている(と思う)。 したがって「あまるべマリン」の乗客は「鉄」しかいない(筆者をのぞいて)。マニアの方々が首から一眼をぶらさげ、リュックを背に右の窓から左の窓へとせわしなく移動している。社内の扇風機から製造プレートから、ボックスシートから写撮に余念がない。立ったり、座ったり実に熱心である。頭が下がる思いだ。 豊岡、城之崎温泉から餘部に向かう「あまるべマリン」は偶数番号のD席が海際の進行方向で一番いい。進行方向に後ろ向きになるがやはり海際の席はA席となる。奇数番号は山際になってしまい、B席C席はボックスシートの通路側だ。メモしておこう。(運用によっては別の列車も使われるかもしれんし、責任は持てません) と、言うことで今まで何度か渡橋しているのに夜行列車で寝ぼけてばかりいたため、特に意識もしていなかった餘部鉄橋を見に餘部へ行ってきたとゆー記録でした。 実は列車からは鉄橋の高さや景観を実感できない。降りて鉄橋を見上げないと駄目なんである。だから降りた。無論、筆者はマニアではない。 |

| 「大山山麓の牧場で乗馬しましょうよ~」 馬好きのFの熱心な勧誘に負け、とうとう筆者も鞍上に載ることになった。 馬は高い。乗り手がヘタレだと嘗められる。 蹴られる。噛まれる。落馬する。 スーパーマンを演じた故クリストファーリーブも落馬で脊髄損傷し下半身不随となった。 「落馬して脊髄を損傷して下半身不随になるから馬は嫌だ」と言っていた筆者だが観念である。 老母に米子で馬に乗ると告げると 「あなたは小さい頃から運動神経がないんだから落馬して脊髄損傷して下半身不随になるわよ」とジプシーの占い婆のように不吉なことを言う。 言い返す気には無論ならない。 大山登山の1時間半後、牧場に乗り込んだ。 (無謀である) 同行のYもN嬢も乗馬経験がある。初体験は筆者とNのふたりだけ。 その日は30分の上達コースを1セット。 手綱さばきと馬場での輪乗りをする。 馬高にあわせて、騎乗用の「馬の駅」がある。盛り土して馬の鞍部に比較的近くなっているからあまり苦労せず馬にまたがれる。 幸い、馬はおとなしく、噛まれたり蹴られたり振り落とされたりすることなく30分が過ぎた。 集団行動をする性質の馬は前の馬についてゆこうとするらしい。接近しすぎないように手綱を締めたり、向きをかえるときに振ったりする程度で馬は動いてくれる。(意のままに、というほどには人馬一体感はない) Nは秋山好古かコサック騎兵になったつもりでいる。筆者も「これからは『バロン』と呼んでく |
れ」とビッグマウス化。 翌朝、もう一度30分の上達コースで馬に慣れたあと牧場の外に出る湖畔周遊90分コースを選択。 筆者の馬は馬齢14歳、人間にすると56歳程度。馬場ではそこそこ早足もしていたのだが、外に出たらまったくヤル気を見せず早足にならない。それはそれで筆者的にはOKだが、同行者のペースを乱してしまった。 車道の端を馬列を組んで進むなんて思っていなかったので、当初はやや緊張気味。馬は軽車輌の扱いをうけるらしい。車だって馬力でパワー表現をするのだから当然か。まさしく1馬力である。 とりあえず乗馬初体験は無事に終わった。神の恩寵をうける筆者は、落馬して脊髄を損傷し、下半身不随になることもなかった。 大山に登り、馬に乗り、夜の米子で2夜を過ごし、皆生温泉にも浸かった。イベント数は日頃の筆者の放浪の旅の数倍はあっただろう。 今回、米子を初めて訪れたのだが、市街地が思いのほか大きいのに驚いた。人口15万。県庁所在地の鳥取市19万よりも少ないが、街の大きさ感は米子の方が上かもしれない。繁華街は高島屋のそばに広がっている。町名で言えば角盤町や朝日町の界隈だ。酒蔵の経営する居酒屋「稲田屋」米子店と正調派居酒屋「まんりょう」が今回の収穫だ。どちらもいいよ。 皆生温泉は「かいけおんせん」と読む。「かいきおんせん」ではない。米子から車で10分程度。日本海に面した温泉街は海中から湧き出る源泉を利用している。宿からの眺めもいいし、かなり満喫であった。ツアコンのF、お疲れ様。N、Y両名ともNの新車インサイトの運転、ご苦労様。 |

| 大山は標高1709m、中国地方一の高峰であり、山岳信仰の霊場としても名高い。 その大山に登ろうと誘ってきたのはF。 近くは岐阜城、古くは、備中松山城(高梁)、岩国城、松山城など名だたる城山を征服し続けてきた筆者は、瞬時に諾。 後になって、標高300や400程度の城山と1700の山を同列に考える軽はずみな性格を深く反省することになるのだが、そのときの筆者は神ならぬ身の哀しさ、待ち受ける運命の過酷さを何も知らずにいた。 前日、鳥取砂丘でパラグライダーを堪能してきたF、Y、N、N嬢のメンバーに合流した筆者は、黄色いスタンドカラーのシャツにブルーグリーンのジャケット、白いチノパン、足周りはビジネスでもカジュアルでもOKの革靴。無論ウォーキングタイプだ。 大山山麓の大山寺の参道を歩く5人。周囲は、視程20mほどの霧が垂れ込め、視界を閉ざしている。参道に立ち並ぶ杉の巨木も灰色のシルエットとなってあたりを漂う細かい水滴の中に身を隠している。その影はまるで異界の怪物のようにも見える。霧は音すらも包み込み少しでも離れると声を掛け合うことすらもどかしい。天気予報によれば、停滞を続ける低気圧が日本列島を広く覆い、日本全国を濡らし続けている。 登山者へ入山申請書の提出を求める貼り紙があちこちにあり、それまで軽く考えていた筆者の気持ちに陰りがさした。霧は深く、雨模様、そのせいか登山口もなかなか見つからず、時がすぎる。 (なんとなく、今日は無理そうだな) 誰もがそんな気持ちになってはいたが、とりあえず登山口を探し続け、やがて見つけた夏山登山道にとりあえず足を踏み入れた。すると霧が切れはじめ、太陽の輪郭が白く空に浮かびあがった。 なし崩し的に登山が始まっていた。 |
(うわ、最悪のスタートだ) 筆者は完全に手ぶらで飲料すら買いそこなっている。 登り始めればいつもの城山と同じだ。淡々と黙々と重力に逆らうのみ。淡々とも黙々ともしていないのはNのみ。エネルギーが無駄に溜まっているらしく、発散の場を得て喜々として小隊斥候役を演じている。 一合目まで登るのにも随分時間がかかった気がした。二合目までも同様。三合目で気がついた。 (先は長いぞ。いつもの城山とはスケールが違う) 登山道と言ってもふもとの方はそれなりに整備されている。一応、階段状にもなっているし、周囲を木枠で囲って崩れないようにもしている。ただし、いかんせん一段一段が高い。それも不規則だ。 呆然とするほど長い急勾配の山道がまっすぐ続いている。それを見て出てくるのはため息のみ。 六合目にようやく避難小屋を含めたいくつかのベンチが並ぶスポットが現れた。 もう少しかと思ったが、実はこの先が長く、きつかった。胸突き八丁のガレ場を登るには、もはや手を使わなければ叶わない。 途中、雨にも降られる。 登山経験のあるN嬢は準備よく、筆者用の軍手やポンチョも持ってきてくれていた。水分補給はFから1本、糖質ゼロのスポーツ飲料を分けてもらった。 頂上で、とりあえず記念写真をパチリ。 頂上や、途中すれ違う登山客の皆さんには筆者のいでたちが極めて不自然に映るらしく、失笑やら揶揄やらをたくさん頂戴した。チャリ行同様、駅前にタバコを買いに行くオヤジの格好という筆者のコンセプトは大山でも遺憾なく発揮されたのであった。 |

| 「美濃を制する者は天下を制す」 NHKアナウンサー中西龍氏のやや金属的な響きのナレーションと急流のようなリズムのテーマ曲が筆者の脳裏で流れ続ける。 NHK大河ドラマ『国盗り物語』は当時中学1年の筆者に深い印象を残していた。 全編のエンディングは山崎の合戦に敗れた光秀(近藤正臣)の死とともに稲葉山城(岐阜城)、安土城跡、大阪城の映像が流れ、中西氏のナレーションにより締めくくられる。 『光秀の死とともにひとつの時代は終わる。戦国と呼ばれ乱世と呼ばれた時代、一介の油商人山崎屋庄九郎が美濃一国の主斉藤道三となりえた時代、尾張のうつけと呼ばれた悪童が天下の権を握りえた時代、人が力と知恵の限りをつくし国盗りの夢と野望を色鮮やかに織りなした時代はここに終わりを告げる。そして歴史は中世の破壊から近世の建設へ新しき秩序を作る人々を迎え入れようとしている・・・』 稲葉山城は筆者の漂泊の第一歩を標した城だ。 岐阜城と呼ばずに稲葉山城と呼びたい心理は「国盗り物語」の「斉藤道三編」が好きだったからだ。信長の美濃入城により変名された岐阜よりも稲葉山の方が筆者には心地よい。名古屋に来たついでに岐阜・大垣に寄っていたが、当時、岐阜・大垣をひっくるめて名古屋の範疇に入れてしまっていたらしい。乱暴なもんだ。記録がどこにもないので記憶を弄って指折り数えれば今回4回目の訪問だ。城に来たのは3回目。 いつのまにか市電がなくなっていた。 岐阜市は、人口40万強の都市にしては市街規模がでかい。そのことがまた誰にも知られていない |
のが東海地方特有のブラックホール的な情報非発信性ゆえかもしれない。 駅周辺の人間以外に利用客があるとは思えない東海道新幹線「岐阜羽島」駅から岐阜に向かう。1日平均利用者数3千強は、本塩釜や会津若松とほぼ同レベル。並べてはみたが、どー評価すればいいんだか。 何はともあれ、筆者は岐阜羽島で降りるという稀有な体験をした。JR在来線の駅もない新幹線単体の駅というのが東海道新幹線では珍しい。隣接する名鉄羽島線の新羽島駅から岐阜に向かう。 JRと名鉄の岐阜駅前を通るバスはほぼすべてが岐阜公園に行く。岐阜公園の袂から見上げる稲葉山(金華山)329mの頂上に岐阜城がある。 ロープウェイがあるが、連休中のことゆえ長蛇の列だ。城山に登るロープウェイの行列をGWに見るのは5年ぶりだ。あのときは岩国だった。 岩国の時も同様だが、今回もロープウェイは使わない。徒歩で登る。 稲葉山の攻略ルートは2口ある。百曲口と七曲口だ。百曲登山道は健脚コースとある。 当然百曲口を選ぶ。 岩盤がそのままむき出したような稲葉山の固い地表を踏みしめてゆくコースだ。途中13か所の難所があるなどと書かれている。信長の稲葉山城攻略戦で、土地の猟師、堀尾茂助(後に遠州浜松12万石)に先導された秀吉の間道進軍を想起させる。山頂のコンクリート作りの天守からは、美濃・尾張の平野が一望できる。筆者は初めてこの城に登った30年近い昔を思い出していた。 |

| 山の頂の残雪が思いのほか多い。 4月下旬、北国の花冷えもまた思いのほか厳しい。吐く息が白くゆっくりと中空に漂い、いつまでも消えずにいる。背抜きのジャケットにTシャツとボタンダウンという軽装では厳しすぎる寒気は摂氏10度を切っている。 関東以西ではすでに桜の季節を過ぎ、年中行事である狂騒的なお祭り騒ぎは終わっていた。いつものように、そんな季節があったことなど微塵も伺えない日常生活が始まっている。 漂泊の旅人は、秋田駅頭に降り立った。 故郷の人々の思い出にすら残らず、訪れた土地では名前すらない。それが漂泊の旅人。すべてのくびきから逃れて流れ着いた東北。そこには生まれて初めて見る北国の桜があった。 東京行き最終「こまち32号」は、19時07分に秋田駅を出る。東京までは約4時間。到着は23時08分になる。全席指定の秋田新幹線だが「立ち席特急券」を利用すれば盛岡までは空き席に座れる。 こまちは秋田を出て大曲まで座席反対方向に逆走した後、大曲からスイッチバックで進行方向がいれ替わる。大曲の次駅「角館」は指呼の間だ。秋田を出てからこの間40分強。 旅人は、角館で降りた。 武家屋敷に足がむかう。駅からは10分程度だ。 人影もまばらな街路を歩いていると、道の先に祭りの夜を思わせるような人の流れがあった。どこからともなく人が現れ、ひとつところに向かっている気配。その流れに押し流されるように進んでゆくと目の前に豪奢とは言えないライトアップの中、豪奢としか言いようのない枝垂れ桜が白く浮かびあがっていた。 幽玄な景色のその街区には、いつの間にか人の姿が溢れ、車の列も緩やかに連なっている。すべてがいつの間にかそこに生じていたかのような秘めやかな変化だった。まわりの人影がすべてこの世のものでなかったとしても不思議ではない、そんな春の夜の一幕だった。 頭上から垂れ下がる枝垂れ桜の樹高が思いのほか高く、街路の先まで目の届く限り降り注ぐ桜のシャワーがつながっている。 |
桧木内川の川端に出た。 川端には2キロに渡って400本のソメイヨシノが咲き誇っているはずだが、ライトアップの光源も淡く、その全容を伺い知ることはできない。 土手の内側にはテントが立ち並び、夜店が賑やかだ。にもかかわらず、思い返せば不思議とそこに音があったとの記憶が曖昧になる。何とも奇妙な感覚に包まれ、旅人は帰路についた。 再び秋田に戻ったが、すでに駅東口に灯りは乏しい。繁華な西口、ましてや川反通りに向かう気持ちもなく、侘びしい居酒屋でラストオーダーに追われながらわずかな酒と肴をのどに流し込む。 そんな夜が更けていった。 翌朝、再び角館に向かった。 あいにくの小雨まじりの天気に、花散らしの雨と風にならねばよいがと懸念しつつも、視程の広がる日中ならではの奥行きのある桜並木を堪能した。昨日は闇の帳に閉ざされていた桧木内川の桜もその全景をあまねく見渡すことができた。 角館から大曲に戻り、奥羽本線で山形方面へ向かう。その間1時間強。在来線各駅停車の緩やかな時間感覚に旅人はいつしか眠りに落ちた。 ふと目が覚めると車内に人の姿がなくなっている。列車は「横手」に停まっていた。 対面の出口のあるホームにさきほどまで同乗していた人々が大勢歩いている。皆、ここで列車を降りてしまったのだ。 「横手」に次いで「湯沢」でわずかに残っていた同乗者も降りてしまった。2両連結のワンマン列車の乗客は旅人と隣の車両にひとりだけ。 「横堀」で列車を降りる。車で10分とかからない山裾に1本の枝垂れ桜があった。 「おしらさまの枝垂れ桜」と呼ばれる樹高10m、幅19mの1本桜である。樹齢は推定175年から200年。地元でも特に耳目を集めていたわけではなかったこの桜が写真を通じて人々の口に膾炙されるようになってまだわずかのことだ。 町おこしの神輿になった桜を見ようとそれなりの人が集まっている。白山神社の赤い屋根と背後の深緑の木々と山を背景に薄桃色の枝垂れ桜が咲き誇っていた。→→桜の画像はこちら |

札幌行3 →→→back 札幌行1 2 3 4 5 6 7 8 9
| 巨人機(ジャンボ)の機体ですら姿勢を保つのに苦労する強風だった。発達した低気圧が北海道の上空にあり、大陸から猛烈な寒風を引き込んでいた。フライトのかなりの時間が雲の中。やがて機窓を覆う白い混沌の中に錯覚かと思うほどに淡く、しかし明らかに自然にはありえない直線の区画がにじんだかと思うと、それは瞬く間にくっきりとした道路となり、いつの間にこれほど高度を下げていたのかと目を疑うほどの近さに地上が迫っていた。機はすでに着陸態勢。 しかし次の瞬間、急激な上昇角で機体が浮き始めた。(ありゃりゃ進入復航!)地上の風が相当に強い。函館へのダイバートか羽田へのリターンの可能性も告げられた。 10分後何とか新千歳に降り立ち、所用で時を費やし札幌には20時の入り。荷を解いて店にむかってもラストオーダーまであと僅かという時間ではグランメゾン級の店は無理だ。「すすきの」で店を探そう。 席数の少ない隠れ家のようなそのビストロは「ポアーヴル」という名だった。カウンターは6席程度、奥にテーブルが1脚。一人旅の利点で1席しか空いてないスツールに尻を押し込んだ。 メニューボードを眺める。 「プロボローネチーズのステーキ仕立て」 (うほ、なんか旨そうなのがあるじゃん) 「ラクレット」 (うほうほ) 初めてのラクレットは帯広の「ワインケラー」で食べた。酪農学舎のラクレットをポテトにからめて供された。以来、ラクレットは筆者の好物になった。その後、店は屋台に移り、さらに店舗を |
かまえ「らくれっと」という名になったらしい。 ハーフのスパークリングとグラスの赤でちびちびとやっていたが辛抱たまらん。ボトルに切り替えだ。テッレデルバローロのバローロがすすきので飲むにはリーズナブルプライス。迷わずにオーダー。道南産豚のグリル、オムレツ、ザワークラウトを消費。締めにチョコレートタルト。(嗚呼糖質制限の神様、お許しください)ちゃんとグラッパ2杯を流し込み、血糖値の上昇を抑止させましたから。 翌日、朝から札幌を離れる。夕方に帰ってくるはずの計画は案の定、暴風のおかげで頓挫。リカバリープランの発動でジンギスカンへ。 「さっぽろジンギスカン本店」でラム肉のジンギスカンを消費。 あいかわらず、主人は黙々とラムの脂をカットしている。スタッフの女性陣も黙々と客に対応している。北海道のジンギスカンは焼肉屋のようにテーブルを囲んでというイメージではない。カウンターにズラリと並んで、各人(多くてもカップルで)もくもくと食べて飲むのである。 ジンギスカンで腹を満たし「バー山崎」の扉をあけた。おそらく日本最高齢のバーテンダー山崎氏は88歳。金沢の「バースプーン」のオーナーバーテンダーH氏から教わったとおりにオーダーして時をすごす。 その後何となく足が勝手に「ポアーヴル」に向かってしまった。はまってしまったことは否めない。尻のすわりが筆者にシンクロしたのだ。 ホエー豚のソーセージ、プロボローネチーズのステーキで白のグラスを2杯、パンナコッタで(嗚呼、糖質制限の神様)グラッパ1杯。満喫。 |


| 錦江湾を左右から包み込むように薩摩半島と大隅半島が腕を伸ばしている。 1914年(大正3年)の大噴火で桜島と繋がったのは大隈半島だ。都邑鹿児島の反対側にある。 鹿児島は、薩摩半島にあり、湾奥部から湾全体の三分の一程度の距離に位置している。 薩摩半島を南下すれば、突端に「薩摩富士」の異名を持つ開聞岳が半島にできた瘤のように海岸線に盛り上がり、その質量とバランスをとるかのように開聞岳のそばで池田湖が窪んでいる。 「知覧」は、その薩摩半島突端中央にある南九州市の首邑である。 鹿児島の繁華街「天文館」そばの「やまざき屋バスセンター」からバスで1時間10分あまり。指宿枕崎線の平川駅を跨ぎ、錦江湾を見下ろす手蓑峠を越えて知覧の玄関口「武家屋敷入り口」に向かう。そこには藩政時代の面影を残す山間の静かな城下町がある。 飫肥(おび)杵築(きつき)秋月、そしてここ知覧。江戸時代の名残りはなぜか九州の地方都市に多い。これらの町の老人(おとな)びた面影は廉恥をともなった謙譲の徳目とともに現代人にとって強い憧憬の対象となりうる。 知覧を貫く1本の街道脇を流れる透き通った水流の音が心地よい。そこには期待通りに錦、金、赤銅の鱗で光を弾く鯉の姿があった。 武家屋敷に足を踏み入れる。ここは有料だ。 背景に母ヶ岳を背負った古い家並みと手入れの行き届いた生け垣が青空の下、照り輝いている。 琉球貿易の港が近かったせいか、家の造りにオキナワンなテイストがある。門と玄関の間に岩を立て視界を遮るのは沖縄の「ヒンプン」だ。屏風岩とも言うらしい。路地の突き当たりに「石敢當 |
(いしがんとう)」まである。路地の突き当たりを曲がりきれない魔物を吸い取る沖縄の石仏だ。 1本道の周囲に武家屋敷が並び、道を突き抜ければ観光が終わる。 武家屋敷から2キロ先に太平洋戦争の陸軍神風特攻隊の記録を残す「知覧特攻平和会館」があるのでそこまで歩くことにした。 平和会館には実物の零戦(海底に沈んでいた零戦を引き上げた状態)が展示されている。終戦末期の傑作機「疾風」も実物だ。日本にただ一機現存する「飛燕」もある。 第1次から第9次(?記憶やや不鮮明)の特攻に出撃した1053名の乗員の写真が並んでいる。その写真の一枚一枚が彼らの出撃前の手記とともに見る者に悲痛の念を抱かせる。 修学旅行の生徒や若者が館内に溢れていた。鼻をすする音がそこかしこから聞こえ、そのことに筆者は軽い驚きを覚えた。十死零生の攻撃作戦(それを作戦と呼ぶことすら空しい)に命を預けた若者たちの様々な想いを時代と年代を越えて汲み取ろうとする思いは廃れはしないということか。 国防をないがしろにしてはいけない。 筆者は我が身を犠牲にしてまでの非戦論者ではない。しかし、有意の無為無策からあのような敗戦の仕方を招いてしまった為政者とこのような作戦を実施した軍政・軍令の関係者はやはり指弾されねばなるまい。 今、あの時代以上に良い政治が布かれていると力強い肯定は悲しいかなできない。しかし、少なくとも良い時代であることは間違いない。十死零生の作戦に身を挺した彼等への時間を越えた負債の念が沸いてしまうのは、平和ボケな我が身の何に対する自責の念からだろうか。 |

特攻隊員達の兵舎 平和会館内は写真撮影禁止:写真は窓外からの1枚

| 襟裳岬の停留所に降り立った筆者。 バスが立ち去った瞬間、横殴りの突風に重心を失った。バスが風よけになっていたのだ。すさまじい風が岬に吹き付けていた。 この日、道内各地で瞬間風速25m以上が記録されていた。今、立っている襟裳では33.4mがマークされている。 正対すると呼吸すら困難な風など経験したことがない。完全に風に体を預けるように斜傾して歩く。それでも時折、風にあおられバランスを崩してしまう。氷った路面は絶対に歩けない。岬にむかう階段は雪に覆われていた。断崖を見下ろす階段を降りるのは命にかかわりそうなので断念。 雪のない展望台に上がり、岬を眺める。 北海道を東西に分断する日高山脈が道内を南下しここで地上での行き場を失う。それでも南下をやめない山塊がまさに海に沈みこんでゆく現場がここ。襟裳岬だ。 森新一の名曲が耳元に何度も流れる。iポッドに仕込んであるのだ。歌詞を刻んだ碑もある。 再び猛烈な風に身をさらしてバス停ヘ。往きは知らなかったから何の不安も抱かなかったが帰路は違う。この突風の存在を知ってしまった今、筆者は結構心配していた。 バスはスピードを落とし、風に翻弄されつつも様似にたどり着いた。 続いて日高線だ。 暴風吹きすさび、砕け散る波頭押し寄せる海岸線をひた走る。当方、海はもう食傷気味だ。 不意に列車が停車してアナウンスが流れた。 「線路上に障害物があるので取り除くために停車しました」とのこと。 |
風で飛んできたトタンがレールに落ちていたらしい。保線区員なんかいない。ワンマン運転だから運転手が降りて、自分ですべてを処理するしかないのである。トタンを取り上げ線路脇の枯れ草に巻き付けている。 運転手が席に戻り、気動車は再び黒煙を上げて動き始めた。 しかし、気がつけば列車のスピードがまったく上がらない。歩いた方が速いのではと思われるスピードで峠を越えようとしている。一時的なことと看過していたが、いっかな状況は変わらない。わざとしているかのように進まないのだ。なぜエンジンを絞っているのかとイライラしてきた。 後で知ったが、高波でレールに海水が付着し、車輪が空転し走行できなかったようだ。 「波の花」だって危険だ。同日、留萌線ではこれを踏んだ列車がスリップ。37mもオーバーランしている。 太平洋に日が沈み、あたりを宵闇がつつもうとする刻限、キタキツネが一匹、線路を横切って列車を振り返った。 先般、釧網本線では鹿と目があった。今度はキタキツネ。次はきっと熊だ。 結局30分以上の遅延で苫小牧に着く。 接続を期待していた「北斗」はとっくに発車して姿はない。特急はローカル線の遅延などのために接続待ちはしてくれないのだ。 札幌に着いたのは夜7時半。朝の7時に出たのだから、ほとんど終日12時間ちかく乗り物に乗っていたことになる。 無論、筆者はマニアではない。 |

| 札幌から襟裳岬は遠い。 朝7時の列車に乗って襟裳岬に降り立つのは12時30分。片道5時間半だ。 たぶん車の方が速いだろう。 マニアではないがペーパードライバーの筆者は鉄道を選ぶしかない。 終日吹き荒れた春の嵐のせいだろうか。朝日を浴びた雪原の表面が水飴で薄くコーティングされたように硬く輝いている。昇ったばかりの陽光は角度が浅く、それを受けた白樺木立の影が長い。 いかにも北海道な車窓だ。 札幌始発の函館行き特急「スーパー北斗」は雪原を疾駆する。 40分ほどで「苫小牧」に着いた。 太平洋に近いこの街に残雪は少ない。 「苫小牧」から「様似(さまに)」に向かう折り返しの日高線は車両を切り離し一両編成のワンマンカーとなった。 様似までの道程は3時間16分。かなり長い。 鉄路は太平洋の海岸線に沿って延々と続く。道内でも極めつけに知名度の低い町が連なるこのエリアは、支庁名である「日高」でくくられることが多い。 進行方向右側の車窓を占めるのは一面の海原。発達した台風並の低気圧の影響で泡立つ白い水面が次々に盛り上がり岸壁に襲いかかる。砕け散る波濤が列車の足元を濡らす。「波の花」が宙空に舞っている。 雲間から除く陽光が遠い海原を青く輝かせる。眼前の鉛色の海と空との対比が鮮やかだ。 反対側の車窓には牧場が広がり、牛馬が雪の間から覗く草をはんでいる。日高はサラブレッドの |
ふるさとだ。 海上がもやに包まれ始めた。 霧もまた日高の名物である。 列車がその中に分け入り、車窓が視界を失う。 やがて減速し、霧に包まれた町に停車。 携えた本に目を落としているうちにいつの間にか霧から抜け出している。人の静かな一生を彷彿とさせる列車の歩みである。 苫小牧から1時間40分弱「静内(しずない)」で乗客の多くが降りた。ローカル特有の息の長い停車。 日高支庁のある「浦河(うらかわ)」についた時は苫小牧を出てから3時間弱が経過していた。 さすがは支庁の街。コーストガードの船が接岸している。 しばらく海岸線から距離を置いて走っていた日高線だが再び海岸線に寄り添い始めた。 波は変わらず荒い。出発時に比べて車窓がかなり汚れてきた。そう言えば、夏場、北海道を車で移動するとフロントグラスが虫の衝突跡でいっぱいになったのを思い出した。 やっと終点の「様似」に到着。 新幹線に乗っていたら「東京」から「岡山」に到着している時間だ。 「様似」駅前からJRバスで約50分。道路も鉄路と同じくひたすら海岸線をなぞる。 ふと車外に目をやると、枯れ葉が宙に舞い、後方から走行中のバスを追い越してゆく。一瞬、目の前に滞空しているかに見える黄色い葉だが、バスは走行中なのである。その奇妙な光景が意味するところはバスを降りて判明した。 |

沖縄行13(アッテンド編) →→→back 96 06(1) 2) 3) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
| 「博多にはいつ連れて行ってくれるの?」 何がこれほどまでの博多への執着を老母に植えつけたのか? 「寒いうちは足がつらいでしょ」 「暖かいところなら平気よ」 博多は暖かくないのだ。日本海性気候の話をしてもチンプンカンプンのママ。 沖縄へ連れてゆくことにした。 2月21日から筆者はツアーコンダクター。 服が問題だ。老人は寒さに弱い。沖縄の今の服装が読みきれない。自宅伊丹間の移動もある。厚めの外套は空港のコインロッカーに放り込んでしまえと意を決する。想定外はすべて現地調達だ。 出立の日、大阪は寒かった。最高気温9度。指先がかじかむほどの寒さ。一方、降り立った那覇は20度。空港内は暑い。「ゆいレール」の車内はクーラーが動いていた。 翌日の気温は24度。当然のごとく市内のあちこちでクーラーが効いている。最低気温が17度では厚着の必要はない。ウチナーの何割かは半袖姿だ。テレビで見た大阪の最高気温は11度、最低気温が2度。(そうこなくっちゃ) 筆者はジャケットの腕をまくって過ごした。 旅先での夫婦喧嘩はよくある話だ。親子であっても似たようなもの。喧嘩にならない唯一の心胆は「自分も楽しもう」などというスケベ心をおこさないことだ。アッテンドに徹する。この一点である。男と女、青年(?)と老人、感性は決して一致しないのである。老人の体調を推し量るすべは観察しかない。 などと偉そうに書いたが想定外のことだらけ。 あんなに花に食いつくとは思いもしなかった。 |
那覇空港に並ぶ大蘭の鉢植えを前にすでに棒立ち状態。ふり返れば、ぺたぺた後についてきているはずの姿がない。はるか後方で蘭の花に触れまくっている。 (そーきたか) 旅の初心者を穴場や現地人しか知らないスポットには連れて行けない。友達との土産話で必ず相手から「××へは行った?」と聞かれるからだ。この「××」は誰もが知っているベタな物件。ここで「行っていない」と応えると話が続かない。「どこに行ったの?」と聞かれて「○○」と応えた「○○」が「???」となると土産話で盛り上がりたいオバチャンの欲求不満が爆発する。 穴場探訪の自己顕示欲はポケットに詰め込み、首里城に行って、県産品の名物を食べて、観光タクシーで知念岬(中部までは距離がありすぎ老母の体力では疲れが溜まる)の光景を堪能し、ニライ橋カナイ橋を渡って、カフェくるくまでカレーを食べさせる。完璧な入門コースである。 沖縄ワールドで満開の大輪のハイビスカスを見たときが老母の喜びのピークだったことは想定外だ。やっぱり景色より食事より花なんである。 さらにドライバー氏に「蘭の花を売っているホームセンターに連れていってちょーだい」などと言い出した。2軒まわって蘭の花がお土産になった。巨大な水ゴケも買わされた。何で沖縄で? アロハはビッグサイズのレディースを購入。 「2枚欲しいわ」 もう1枚、購入。 夜、マチグワァで黒糖を2袋買い込んだ。 無論、重い。 当然、筆者が持つ。無論、蘭も水ゴケも・・・ |
| 「赤目四十八滝」は「あかめしじゅうはったき」と読む。・・・女殺油地獄。 すいません、何となく打鍵してしまいました。 語感が近松門左衛門してないか? してない?・・・失礼しました。 奈良と三重のほぼ県境に位置する赤目渓谷に点在する滝の総称が「赤目四十八滝」である。 「四十八」は単に数の多さをあらわす記号として使われている。長崎の九十九島と同じである。滝の数はもっと多い。 近鉄難波駅から上本町経由で近鉄大阪線に乗り入れ、区間快速か急行で1時間10分強。「赤目口」駅から車で10分。赤目四十八滝の滝口に至る。 「法隆寺」「桜井」「長谷寺」よりも東、奈良を抜けて三重県領に入った処にこの渓谷はある。 車止めの先に幾つかの土産物店や飲食店が並んでいる光景は大阪の箕面と同様だ。その先に道を塞ぐ関所のように「日本サンショウウオセンター」がある。入山料300円をここで支払う。 建物内を突き抜けると「赤目四十八滝」の遊歩道が始まる。全長3.3キロ、不動滝、布曳滝、千手滝、荷担滝(にないたき)、琵琶滝の赤目五瀑を筆頭に渓谷の最奥部の岩窟滝まで大小様々の滝が現れ、訪問者の目を楽しませてくれる。 那智の滝や華厳の滝のような落差はないが、水量が豊富でなかなか迫力のある水流である。前夜まで雨が降り続いたせいもあるかもしれない。 歩き始めてすぐに現れる「行者の滝」からしてなかなかに勇壮だ。岩を噛み流れる急流が複雑に刻まれた地形が生み出す効果でチューブライディングのように身をくねらせている。 遊歩道とは言っても、渓谷に沿って刻まれた石 |
段は不規則で足元も心もとない。濡れ落ち葉が敷き詰められた泥濘のような踊り場では足を滑らせないように慎重に歩を進めざるをえない。 次々に現れる滝の脇を登ってゆく感覚は巨大な階段を一段一段這い登ってゆくイメージに近い。 頭頂部から何段にも渡って落ちてゆく滝を一段ずつ制覇してゆくような感じである。 渓谷全体にマイナスイオンが充満している(と思う)。無論、マイナスイオンの何が、何にいいのか筆者はまったくわかっていない。 渓谷は、時に深く静かに澄みわたり水底に魚影を映し出す。早朝の大阪平野は快晴だったが、赤目の空は雲に覆われている。しかし、風に舞うスカートから覗く白い素足に目を奪われる少年を誘ういたずら好きな女の子のように、気紛れな陽光が時折、雲間から水面に銀鱗を撒き散らす。その瞬間、水は深い青緑の光彩を身に帯びる。 最奥部の先800mほどにバス停があるらしいが昼の間に1本しかないような注意書きがあった。しかも「赤目口」駅にはゆかないようだ。 来た道を折り返すしかないのである。 滝口に帰ってきたが、ここでもバスは2時間に1本。タクシー乗り場にタクシーはいない。タクシー会社の電話番号が書いてある。迎車を頼む。やってきたタクシーは朝、駅でつかまえたタクシーだった。駅前に停まっていたタクシーはこの1台だけだったのだ。 「どーだったお客さん?」 ドライバー氏も朝乗せた客を忘れていない。 「けっこう感動しましたよ」 その瞬間、ルームミラーに映った彼の顔は実に深い満足感に満たされていた。 |


| 松代城(海津城)の櫓から飯縄、高妻、戸隠、虫倉の山々と北アルプスの高峰が望める。 その姿は清々しく、いかにもここが信州であることを実感させられる。 緩やかに時が流れている。 城跡を背にゆるゆると山にむかって歩く。 なが電の線路を渡りしばらく歩くと象山神社が現れた。佐久間象山を称えるための神社だ。 幕末に活躍した佐久間象山は、松代の出身だったのだ。 そう言えば、師(吉田松陰)を失った高杉晋作が松蔭の師匠にあたる蟄居中の象山を尋ねたことがあった。高杉は松代に来ていたのだ。 ただし象山と意、通じあわず「象山先生の大法螺ふき!」と怒鳴って立ち去ったシーンが司馬遼太郎氏の「世に棲む日々」にあった。稀有壮大すぎるのか、虚喝の気味あるか、彼に衒学趣味のきらいを覚える筆者には象山は測れない。 しかし神社のなりはなかなかにいい。 象山神社の先にも坂が続いている。先ほどまで太めの側溝だった流れが小川に変わる。 山が眼前に現れる。 象山(ぞうざん)と呼ばれ、佐久間象山の号はここに由縁する。 川沿いに稲荷神社や禅寺が趣のある佇まいを見せている。 さらにその先に大本営象山地下壕がある。 建造中に終戦をむかえたため、使用されることはなかったが、長大な地下坑道は75%ほど完成していた。この象山と周囲2箇所あわせて10キロの長さの地下壕だったらしい。象山地下壕は、全長5.5キロ。そのうち500メートルほどを無料で開放 |
している。 縦横に坑道が延びているため、遭難の危険もある。安全上の観点から見学通路は1本道を行って引き返す作りだ。 ヘルメットをかぶり、地下壕への穴を下る。 周囲に人の姿がなかった。 最奥部までの500メートル、途中幾つもの側道が掘られている。金網で覆われているが光が届かぬ先にも延々と闇が続いている。 なぜか壕内が埃っぽい。 浅間山が噴火をしたばかりなので、なにがなし松代群発地震を予感させ、生き埋めの恐怖が背中をむずがゆくさせる。壕内の温度が高いのかもしれない。かなり温かい。にもかかわらず時折ゾクッと背筋が凍るような時がある。 (しっかりしろ!この地下壕は使用されなかったのだから心霊現象など無縁なはずではないか) 自らを叱咤するも足取りは妙に速い。視線も前だけを見据えるようになったのには、いささかチキンと言わざるをえない。 出口に日の光を見出したとき、安堵したことを告白します。 長野への帰路はなが電を使った。 八代線の終点須坂(すざか)まで行き、同じくなが電の長野線に乗り換える。(ごく少数だが直通電車も走っているらしい) なが電の車輌は、なぜか妙に懐かしい。 よくよく見れば、東急や地下鉄の車輌を使っているようだ。特急に至っては、どう見ても小田急のロマンスカーだ。Fがこの場にいれば、すべての謎を瞬時に解き明かしてくれるのだが。マニアでない筆者にはなすすべもない。 |

| なだらかな傾斜地に集落が形成されている。 集落を貫く清流の幅は狭いが水量が途切れるほどに乏しくはない。冷たく澄んだ水がむしろ豊かに細い川幅を満たしているのだが、そうとも見えないのは白く波立つ水流が速すぎるからだ。 丘陵はさらに奥で山裾に融けこみ、眼前のその山の後背から白く輝くアルプスの名峰が背のびをしているかのように顔をのぞかせ、中空に浮かんでいる。 筆者にとって信州という邦のイメージはまさにそのようなものだ。日本の屋根と呼ばれる山々がその中心にドスンと腰を据えている。 松代は、そのイメージを裏切らない。 真田氏10万石の城下町だが、筆者は不覚にも真田は上田が本拠地と勘違いをしていた。 善光寺の門前町長野から松代へはバスで行く。 松代駅前まで30分という近さだ。 途中、川中島古戦場がある。 長野駅前からは20分。 途中下車してとりあえず謙信と信玄の取っ組み合いの銅像を見る。(すいません。とっくみあってはいません) 武田と上杉、両軍にとって最大の激戦となった第4次川中島の合戦で、単騎、武田軍本陣に疾風のように襲いかかった謙信が信玄に切りつけたのがここだ。 世に言う「三太刀七太刀」の跡である。刀を振るった回数は3回とされていたが、後に太刀を防いだ信玄の軍配に7箇所の刀傷があったことからそう呼ばれた。 川中島古戦場での長居は難しい。 長閑な公園があるだけで、観光資源に乏しいか |
らだ。ただし、バスは30分ごとにやってくるから待ちぼうけはない。 川中島を後にして松代へ向かう。 乗車したバスは松代駅前に停車する。 松代駅はJRではない。長野電鉄(通称なが電)八代線の駅である。 駅の裏側に松代城跡がある。 完全な平城だ。 天守閣はない。堀と土塁、門と魯だけの新造感あふれる城跡だ。復元されたのは最近らしい。 とは言え、松代城は旧称海津城。 先ほど訪れた川中島古戦場で繰り広げられた第4次川中島合戦の際、武田軍の前線基地となった有名な城だ。 海津城に篭ると見せて武田軍は中入れをする。献策は山本勘助と言う。 対峙持久戦となった戦況で、敵に気づかれないように軍を抜き、迂回させて敵軍を奇襲挟撃するという戦術だが、大軍同士の合戦での成功事例を筆者は知らない。秀吉対勝家の賤ヶ岳戦、家康対秀吉の小牧長久手戦で、それぞれ敗者となった側が採った作戦である。もっとも川中島の合戦の勝敗は明確についてはいない。 上杉軍に中入れを察知され、別働隊を抜いたゆえに手薄になった本陣急襲の憂き目にあう武田軍だったが、ワーテルローのナポレオン軍別働隊を率いたグルーシー元帥ほど無能ではなかった、高坂・馬場の両将による迅速な機動により本軍の危地が救われたからだ。 戦国時代、神格化されるほどの戦上手二人が雌雄を決すべく往還した土地に今、筆者はいる。 |
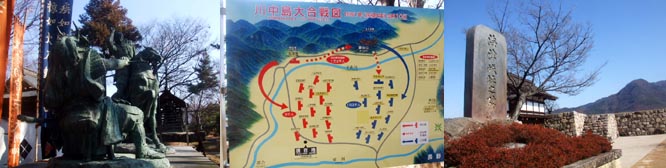
鹿児島行4 →→→back 鹿児島行1 2 3(疾風怒涛編) 4 5 6 7
| 鹿児島空港から市街にむかうリムジンバスが鹿児島城下を眼下に見下ろす最後の峠を超えた。 下りのカーブを幾つか回ると不意に鹿児島市と桜島のパノラマが広がる。 仕事がらみの鹿児島行だが、同行のM氏もA氏も健啖家として知られている。筆者お勧めの天満の串揚げ屋「串八景」でその日の串をこともなげに完食する胃力の持ち主だ。 2人ともアルコールを一切たしなまないので食事中心の構成で夜と昼の2食に命をかけた(かけんでよろしい)。 鹿児島名物と言えば、真っ先に思い浮かぶのは黒豚。鼻先、4本の足、尻尾の先の6箇所が白い黒豚種を六白豚(ろっぱくぶた)と呼ぶ。今日は六白豚を食い尽くすのだ。 以前から鹿児島に来るたびに寄っていた店は、最近ブログでの評判が悪い。ひとり旅ならことの正否を確かめるべく向かったであろうが今回は同伴者がいるのだ。失敗は許されない。 繁華街「天文館」を離れ、騎射場(きしゃば)の「寿庵」に向かった。国道沿いのちょいと洒落た造りの観光レストランという気味もあるが、それなりに落ち着いた店装である。 鹿児島方言は男女で異なるのだろうか。若いお女中の癒し系のふわふわしたイントネーションの注文受けに軽いつっこみを入れながら矢継ぎ早に注文を繰り出す。 「塩しゃぶしゃぶ」「ロースカツ」「ヒレカツ」「とんこつ」「豚バラカルビ焼き」「冷シャブ」「串カツ」 黒豚が連隊を組んでやってくる。 煮て、揚げて、焼いて、締めて、そして、塩で |
、カラシで、ソースで、煮汁で、ゴマで、徹底的に消費しつくすオーダーだ。 「塩しゃぶしゃぶ」が店の看板メニューらしい。 しゃぶしゃぶした豚を、だしに塩を落として食べる。塩の種類は6種類。だしを入れ替えていろいろな味で楽しむ。筆者はガーリック塩が一番よかったが、他に桜島小みかん、バジル、タイム、ローズマリー、唐辛子などがある。 サイドメニューで郷土料理も消費することにした。筆者は糖質制限の修行の身なので手を出さなかったが「さつま揚げ」がバカウケ。サツマイモを使った店独自の料理らしい。実に旨そうだ。 県民はあまり食べないと言われる「きびなごの刺身」も食べないわけにはいかない。 M氏とA氏は「鶏飯(けいはん)」を初体験。しゃぶしゃぶには締めのラーメンがついてくるのだが、麺も飯も消費するのだ。 奄美大島のおもてなし料理である「鶏飯」は鶏ささみにしいたけ、陳皮、錦糸卵などを白いご飯にのっけて鶏ガラダシスープをかけてざくざく食べる茶漬けのような食べ物だ。 堪能しきった3人は店を出た。 翌昼は鰻を食べようということで天文館にある老舗店へ。博多中洲の吉塚うなぎ屋本店のようないかにも大衆老舗然とした雰囲気が漂う。 鰻の脂が強いのか、地焼きではなく江戸風の蒸し焼きである。 もともと甘めの味付けの風土である。地焼きの香ばしさ、あっさりしたタレ好きの筆者にはちとしつこかった。ただし、糖質制限修行の身ゆえ、白焼きと蒲焼、肝串を食べ、ごはんと一緒に食べていないので真価は問えまい、ということで、ひとつ。 |
| 奈良県生駒郡斑鳩町。 区切って読む。 奈良県・生駒郡・斑鳩町。 瞬く間に空気は浄化され、脈拍が落ち着き、血圧が降下するのがわかる。奈良ってなんでこんなに「のんびり」しているんだろう。 JR大和路線「法隆寺」駅は、大阪から快速で35分。生駒山を越え奈良県境に入り、王子駅を過ぎれば斑鳩の里はすぐそこだ。 駅前からややせわしない県道沿いの道を行く。 国道25号線と交差したら左折、しばらくすると南大門に通じる馬場道がある。 周囲には農産物の販売所が多い。奈良は京都と並んで近畿圏の一次産品のヒンターラントだ。 季節は秋。店頭には柿が並べられている。 「柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺」 明治期、正岡子規の句だが、これはもはや立派な観光広告コピーである。名産と名所を組み合わせ、かつ奈良のもつ「脱力感」を17文字で表現しきった子規の写実力は素晴らしい。 世界最古の木造建築を誇る、日本最初の世界文化遺産、法隆寺。 大阪、四天王寺と伽藍配置が似ており、奇妙なデジャヴを感じるのは、両寺が同時代に聖徳太子によって創建されたからか。 中門でポージングする阿吽の金剛力士像の躍動感、リアルな表情は、これまで見てきた力士像の中で暫定日本一の筆者好み。 寺域は意外に広い。 スピルバーグ映画に出てくる宇宙人のような、なよっとしたシルエットの百済観音像、玉虫逗子、平成玉虫の厨子のレプリカなどを眺め、天平文 |
化を満喫。 金堂、五重塔などの西院伽藍の東にある夢殿は聖徳太子の住居跡だったと言われている。太子没後、その威徳を偲び、建てられた。 夢殿の開放サービス期間だった。 観光客の皆さんが一様に中を覗き込んでいる。中央には太子と等身の秘仏救世観音像がある 法隆寺から、思いのほか近代的な構築物の中宮寺を巡り、市中をゆるゆると離れる。 これ、これ、これこそ斑鳩と膝のひとつも打ちたくなる原風景のような田野の中、野焼きの白煙が周囲にたなびく。 法輪寺に至る。 斑鳩3塔のひとつ国宝三重塔が落雷で焼失、再建なったが国宝指定は解除されてしまった。境内はこぶりだ。 法輪寺から法起寺へ。 法隆寺、四天王寺、中宮寺、など太子建立7ケ寺のひとつ。 これまた田畑の中に長閑に佇む寺。 県道9号を下り、国道25号線沿いに駅方向に向かう。25号線は国道とは名ばかりの狭さ。片側1車線の双方向だが、歩道はない。車道の端を歩いていても、行き違いの大型トラックが徐行しなければ人と車が行き交えないほどの狭さ。道路脇には田んぼの側溝が掘られており、段差が2メートル弱はある。生命の危険を感じた。地元の人間は絶対にこんな道歩かんだろうなあ。 文化遺産に注ぎ込む以外、行政にあまり予算なさそう。奈良ちょっと恐し。 |
| 繁華街、天神から西鉄特急で12分。 博多の郊外都市、二日市に至る。 関東圏のイメージで言えば、京王線高幡不動のようなものだ。(少し所要時間が短すぎるが、多摩丘陵の袂のイメージが二日市と似ているのである)関西圏では・・・近鉄奈良線の石切か布施といったところだろうか。 二日市から盲腸線が分岐している。線名は、大宰府線。終点は、名称そのままに大宰府。二日市大宰府間は2駅5分。間の駅はひとつだけ。 ここいらへんも京王線テイストだ。高幡不動から多摩動物公園に行く観光電車のようなものだ。近鉄なら生駒ケーブルか・・・。 西鉄大宰府駅前から参堂が伸びている。太宰府天満宮までは徒歩で5分。 途中、2本の鳥居がある。建物がぎりぎりのところまで鳥居に迫って建てられている。最奥部に本宮の鳥居が見える。 参堂に軒を連ねる土産物の代表は大宰府名物「梅が枝餅」。小豆餡を薄めの餅でくるんだ物件。店頭で購うと焼きたての熱々を食べられる。「中村屋」前に行列が出来ていた。人気店かな。 大宰府天満宮は学問の神様と称えられた菅原道真を祀っている。 宮廷闘争により、都を追われた道真の死後の怨念を恐れ、鎮めるために作られたのが大宰府天満宮だ。同時期、道真を追い出した京においても同様の神社が作られた。これが北野天満宮である。 左遷人事に嘆くのは今も昔も変わりない。現代ならば博多は転勤したい土地ベストスリーに確実にランキングされると思うが、平安の都鄙感では、現代で言えば金星基地勤務を命じられたような |
ものなのだろう。 鳥居をくぐり、左折すると高い屈曲の太鼓橋が途中の渡しを挟んで2連あり、橋を渡ると、桜門、その奥に本殿という構成になっている。本殿の前に飛梅が生えている。道真が大宰府に赴任したとき京都の自宅庭先から一晩で追っかけてきたという「ジャンパー」のような梅である。樹齢が1000年を超えていると言う。 さらに道真には、牛がついている。 丑年生まれの道真は大宰府着任の折も牛に危難を救われ、死後遺骸を運ぶときも牛が動かなくなってしまったことから『道真公がこの地を離れ難いのだ』と言われ、牛が彼の使いだとされた。 梅と牛、あと一役つけば「バビル2世」だ。 牛は黒い臥牛(ふせた状態)だ。皆でこの牛を撫でまくる。だからつるつるになっている。 大宰府は「白村江の戦い」で大敗を喫した倭国が唐軍上陸阻止のために設けた最前線基地だった。海岸線からかなり奥に設けられたことから当時の唐への恐怖感の強さが伺える。 水城と呼ばれる防衛線が博多の海岸から南下する仮想敵への防御線となり、大宰府北面の四天王寺山には朝鮮式山城が築かれ、これが大野城跡と呼ばれている。 時代は下って、安土桃山にはこの大野城跡のそばで岩屋城を守る高橋紹運の750名を5万の大軍で攻め滅ぼした島津の大友宗麟進攻作戦が発動されている。 「岩屋城に行ってきたんですか?」 話を聞いた城跡マニアのNが目を輝かせた。 (しまった) ふった話題を後悔した筆者であった。 |
沖縄行12(着陸復航編) →→→back 96 06(1) 2) 3) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
| 福岡空港発のボーイング777-200が、高度を下げ始めた。小さな機窓に占める碧空と蒼海の割合が入れ替わる。 那覇空港は海岸線にある。周囲の環礁がエメラルドグリーンの縁取りを見せ、バカンスに期待を膨らませる乗客の目を楽しませた。 コックピットでは着陸態勢の手順を機長と副機長が交わしている。 管制塔からの指示が入った。 「ANA487便、最終進入速度まで減速」 機長が指示を出す。 「フルフラップ」 「フラップ作動」 「オートブレーキ、ミディアム」 「Fスピード」 対地速度が落ちてゆく。 「ランディングギア、ダウン」 「ギアダウン」 手順はルーティン通りに進められる。 今や飛行という仕事のほとんどが、機械に奪われつつある。 会社の経営層はコストという言葉が大嫌いで、これを削ることには自身の体脂肪を減らすよりも熱心になる。機械を導入して現場を楽にするという心温まる思いやりは、自分たちの仕事を減らすということと同義だ。 機長は計器を見ながらチラリと考えた。 楽にはなるが面白くはない。プロならば誰もがそう思う。70万時間以上の飛行時間を保有している機長にとって、もはや空はリビングなのだ。 (ただし、機械がどこまで人の変わりを果たそうともランディングだけは、機械に委ねるわけには |
いかない) 給料分の仕事ということだ。 「スポイラー作動」 「スポイラー作動、グリーン」 な~んてコックピットの情景を想像しながら、近づいてくる鮮やかな色彩の海原と、もうすぐ通過するはずの「めんそーれ」の文字を(どこに書いてあったっけ)と考えていた筆者。 しかし、次の瞬間。 ランディングアプローチに入り出力を落としたエンジンが目覚めた。機内に「ヒュィィィィン」という出力を上げたエンジン音が響き渡る。機首が上がり、明らかに空中でのタッチアンドゴーが始まった。 高度が上がり始めた瞬間、それまでエメラルドグルーンに染まっていた機外の風景が、突然灰白色の混沌に一変した。 鉛色の雲とまっ白い雨がポリカーボネート樹脂でできた窓に降りかかる。 初めてではないが、ひさしぶりに着陸復航を体験した。那覇上空の巨大な積乱雲によって空港が突然、スコールに包まれてしまったらしい。 着陸復航。「ゴーアラウンド」とも言う。 着陸態勢に入った機が、着陸を断念して再上昇する運動だ。非常事態ではない。めずらしくはあるが、ルーティンのひとつに入れられる。 大きく迂回するジェット機の窓から、そこだけが完全に白い雨脚に包まれた那覇市街が見えた。その外側は何から何までくっきりと見える晴天。亜熱帯ならではの光景だ。 今回は石垣への乗り継ぎに立ち寄るだけだった那覇だが、やっぱ帰路には立ち寄ろうっと。 |
| 津山。 中国筋の城下町だが、関東圏での馴染みはおそらく薄い。 岡山からJR津山線に揺られて内陸部へ北上すること約1時間。そこに旧国名で言えば、美作(みまさか)の国、津山がある。 街の東西を出雲街道が貫く城下町だ。 出雲街道沿いに東西に流れる吉井川を南面の防御線とし、南北に流れる宮川を城東の備えとした津山城は鶴山城とも呼ばれ、森忠政によって築城された。 忠政は、森蘭丸の弟である。 森家は、池田勝入斎の娘婿として鬼武蔵の異名を取った森長可をはじめ、本能寺で信長とともに討ち死にした蘭丸、坊丸、力丸3兄弟、ほかに長兄1名、5人の兄弟を亡くしている。忠政は、悲運の森家、唯一の生き残り。九州名護屋城の普請奉行を務め、この美作に封じられた。 津山城下には、寺町もあれば、商家町もある。 鍵曲がりによる防衛構築を施された出雲街道沿いにある商家町の風情はやや期待はずれ。寺町はその出雲街道を見下ろす北面の高台に並ぶ。街道にむかって下る一本道が各寺の門前から伸び、その勾配を見下ろす方が城下のイメージを彷彿させる。昔ながらの街並みの維持は徹底を欠けば手前勝手な旅人から中途半端のそしりを免れない。京都のように死に物狂いにならなければ、街の景観など守り通せるものではないのである。津山には杵築や龍野に通じる中途半端さがある。 寅さんシリーズの最終作のロケ地でもあったらしい。そうと書かれた目新しい白い石碑が置かれた作州城東屋敷を覘けば、簡易テーブルを前にい |
かめしい顔をして鎮座している男女と目があってしまった。 (こ、怖い) 「岡山県知事選・投票所」の看板があった。 街のあちこちで「トーヒョーへ行こう!」とのコピーと劇画調のポスターがかかっていたのを思い出した。 街道沿いには、幕末に活躍した蘭学者、箕作阮甫(みつくりげんぼ)の旧家もある。寺町を眺めた後、城に登った。 津山城跡に天守閣はない。 しかし、城山は西日本有数の桜の名所となっている。全山を覆い尽くす桜の季節がこの地のハイライトだ。 天守台跡に築かれた2層の魯に上り、津山市街を見下ろしていると下界から鐘や太鼓の音が鳴り響いてきた。 下城すれば、山車を曳く行列に出くわした。今日は「津山まつり」の開催日でもあったらしい。 津山は、ブランド化こそしていないが、作州牛や黒豚、雉などの肉料理が名物(?)。 出雲街道沿いにある町屋を改造したイタリアン「Cielo(シエロ)」が期待をもてそうな佇まいだったので格子戸を開ける。そこは土間となっていて、さらに奥に店内へ通じる扉があった。(いいじゃないの、この雰囲気)でも、その中扉の前に掲示が・・・「本日は予約で満席でございます」鉄板焼きの「知恵」はホルモンなどさまざまな部位の肉を出してくれる。店の前まで行くとなにやら掲示が・・・「本日、臨時休業させていただきます」 悔いの残る1日であった。 |
| 稲穂の海は、あと僅かな後に一面の黄金色に変わるだろう。 9月の上旬、庄内の地は実りの時を迎える高揚した静けさに満ちていた。 一面の稲田の中を一本の幹線道が貫いている。 その上に、夕陽を浴びた車列が連なり、その赤い影が黄緑色の稲穂の海に長く落ちる。 「ルパン3世カリオストロの城」のワンシーンを彷彿とさせる情景だ。 庄内空港は最上家の山形や上杉家米沢とは山を隔てた反対、日本海側にある。空港からのリムジンバスは鶴岡へ30分、酒田へ40分。明らかに酒井氏12代庄内藩の旧藩領がテリトリーの空港だ。 筆者は鶴岡へ向かっている。 藩政時代、藩府として酒井氏12代の長きにわたり鍛冶された武士の街だ。国替えの話が持ち上がったとき、領民の直訴により取りやめになった珍しい土地だ。 藤沢周平氏の時代小説群の舞台「海坂藩」は庄内藩がモデルであることはつとに有名だ。 街を歩く。 そこここに、藤沢文学の抜書きが表示され、小説中のイメージを現実世界に投影させる試みが為されている。作家井上ひさし氏は、作品に登場する海坂藩の描写から地図を書き起こしている。藤沢文学のファンは多い。 駅前から「般若寺」「龍覚寺」をめぐり、泉町から家中新町の住居表示区を抜ける。旧藩時代、上士屋敷が固まっていたエリアだ。 巨大な松や欅、杉が家内に茂っている。それはこの庄内の歴史と精神性の豊かさを象徴するかのようでもある。樹木を育て、慈しみ、伐採しない |
でいることが、今の世でどれほど困難か。それは不労収入の額を上げんがために経済を遊具のように扱う人生の諸相の一部とは対極にある姿だ。 高級住宅地にありそうな洒落た洋風の家もあれば、板塀のむこうから松が顔を出す木造建築の家の黒い甍がまぶしかったりもする。 青龍寺川から引き込んだ用水のほとりから47号線沿いに致道博物館、鶴岡城跡、藩校致道館へと歩を進める。途中、大山街道木戸口などの案内を眺めつつ、趣のある古屋敷に目が止まれば、なんと「羽前絹練株式会社」の社名が門柱に。 (すごい社屋があったものだ) やがて、内川のほとりに出る。 海坂藩の五間川で知られるその川沿いには、三雪橋、大泉橋など藤沢作品の情景を彷彿させる幾つかの橋がかかり、道は山王町の界隈に到る。 道の両側は商店街だ。無論、その佇まいは静かでおとなしい。山王日枝神社からアーケード街となり、JRの駅に向かうが、その列なりも短い。 庄内藩は、幕末、会庄同盟の誼により会津とともに最後まで官軍に抵抗した。 官軍主力との戦闘がなかったせいもあるが、すべての戦に勝利したと言われている。 徳川四天王のひとり酒井忠次の子孫として、徳川家への忠節を貫き通したとも言える。 清河八郎暗殺後、宙に浮いた「新徴組」を幕府から預けられ、言わば江戸市中における新選組を管理し、さらには江戸薩摩藩邸を焼き討ちしちゃったんだから幕軍につかざるを得ない運命ではあったわけだが、筋を通した藩風が爽やかさを感じさせはしないか。 |
| 「宮島」へは潮時表を確認してから行こう。 床柱にひたひたと潮が打ち寄せていてこそ「厳島神社」の風情もいや増すと言うもの。 鳥居に向かってみるみる引いてゆく潮をなすすべもなく筆者は呆然と眺めていた。 「本日の満潮は9時と15時頃です」 掲出された手書きの告知を見ている今は、正午12時。足しても引いても干満のどまん中だ。 関西圏で幼少期をすごせば、必ずや社会見学か修学旅行で訪れるはずの宮島は、関東圏にとっての日光みたいなものだろう。 宮島に浮かぶ厳島神社は、NHK大河ドラマがまさに大河ドラマ然としていた昭和47年「新平家物語」で登場した。海に浮かぶ厳島神社のシーンが筆者の記憶中枢に住み着いて離れない。 平清盛(仲代達矢)、平時子(中村玉緒)、平時忠 (山崎努)、源義朝(木村功)、源頼朝(高橋幸治)、木曽義仲(林与一)、源義経(志垣太郎)、武蔵坊弁慶(佐藤允)、後白河法皇(滝沢修)藤原信西(小沢栄太郎)・・・思い出すままに書き出してもその重厚な出演陣のあまりの重厚ぶりに押しつぶされてしまいそうだ。実に重厚だ。重すぎる。ブラックホールのように重い。 広島駅から山陽本線で西にむかって30分ほど。宮島口駅で下車すれば駅正面に船着場がある。JRと 松大汽船、2社のフェリーが宮島航路を往復している。乗船券は片道170円。渡し船のようなものだ。乗船時間は10分。 瀬戸内に浮かぶ小島と侮ってはいけない。 思いの外、宮島は「デカイ」。 ちょいと立ち寄って、ぱっと見て、さっと帰ろうと思っていたが、侮りすぎていたことに気が付 |
いた。正直な話、宿を確保してゆとりを持って滞在したくなる風情溢れる土地である。 背後の弥山(みせん)がたっぷりと水気をふくんだ雲の傘をかぶり、水墨画の世界を現出している。ロープウェイがあり、登山もできるようだ。 麓の町の風情もいい。 古格な造りの町並みは、雨に映える。 島の名物は、穴子ともみじ饅頭、そして牡蠣。 もみじ饅頭は同じ会社の店があちこちにある。観光客がどのルートに足を向けようともからめとられる仕掛けになっている。筆者は洋菓子店が作ったもみじ饅頭を購った。もみじの生地がシフォンケーキというのが気を引いた。「きむら」という店舗のりんごとクリームチーズ。木村と名のつく店は他にもあり、注意しないと混同する。 背後の五重塔や、海上の鳥居の配置が巧みな距離感を構成し、開放的に設計された社殿そのものが奥行きのある絵を提供する一方通行の厳島神社を抜けると、御手洗川によって細長く島から裂かれたような松原の先に「清盛茶屋」がある。 知人の海沿いの家で寛ぐような素朴な茶屋で「あなごのかば焼き」と「小鰯の塩焼き」を魚に焼酎の水割りを一杯。 町のあちこちにある「焼き牡蠣」の誘いを拒みきれず、これもついばむ。 鹿が観光客の手提げに鼻をつきだしている。 帰路は、気分を変えるため広島港直行の高速船に乗る。23分で広島港(宇品港)につく。以前、松山に渡る高速船を利用したことがあるので初見の港ではない。フェリーターミナルの正面に市電の駅がある。港から広島駅まで30分弱。JRを使った方が早かったな。 |


| 「博多って知名度の割に、観光資源が少ないですね。名古屋と似ています」と指摘したのは岐阜出身の弁護士K氏。なるほどと納得する筆者。 確かに名古屋の観光資源ってふたつくらいしか思いつかない。名古屋城と熱田神宮だ。 名古屋にとっての熱田神宮は、博多にあっては大宰府だろう。名古屋城のかわりは・・・福岡城か、やっぱり。城域の広さから天守閣が存在すれば江戸城よりも巨大になっていたとの説がある福岡城だが、今のところ城跡に構造物はない。(天守台に見晴らし台ならばある) 負けてるな。 「何ば言うとっとか!」 博多市民の怒りの鉄拳が飛んできそうだ。 博多どんたく、祇園山笠などの祭りは有形の資源ではないということで、ひとつ。 市民の行楽地ということでは、名古屋には伊勢志摩がある。(他県ですが)一方、博多は?ということで呼子である。いやー長い前ふりだった。 夏の某日、大阪から地下鉄、モノレール、エアを乗り継いで福岡空港に降り立った筆者。地下鉄福岡空港駅に停まっていたのは9時21分発の西唐津行き快速だった。 地下鉄内では各駅に停まる快速。5駅目の天神でほとんどの乗客が降りてしまう。筆者も降りるつもりだったが、なぜか乗り続けてしまった。 電車は姪浜(めいのはま)で地上に出る。 そこから先はJR筑肥線に乗り入れだ。快速らしく途中駅の通過を開始する。次の停車駅は筑前前原(ちくぜんまえばる)。ここで下車して車で海岸線に向かえば博多っ子御用達の日帰り海水浴場糸島半島に出る。糸島の糸は、魏志倭人伝に出 |
てくる伊都国のことだと言われている。古くから大陸交流の要衝だった。 筑前前原を過ぎると、進行方向右側に玄界灘の海岸線が広がる。 かなり長い間車窓は海岸線と向きあって走る。 旅の開放感を感じる瞬間だが、通勤仕様のロングシートがいまひとつ心の高揚を阻害する。 車内はガラガラ。1両に4名の乗客。 唐津には10時37分着。乗車時間は1時間11分。 朝のうちに降った雨も止み、雲が切れ、蝉しぐれが蘇っていた。 駅前と駅から徒歩5分程度の大手口バスセンターにバスの乗り口がある。加部島行きのバスは駅前発10時45分。実にシームレスな乗り継ぎだ。 東松浦半島の先端に向かってバスは峠を越えてゆく。乗車時間は30分程度。 イカ漁で有名な呼子に到着。 停留所の前が船着場だ。11時30分出港の観光船「イカ丸」がいた。なんだなんだと飛び乗れば、玄界灘の景勝「七ツ釜」に連れて行かれた。 7つの海食洞が高さ20m、幅40mの玄武岩の断崖に穿たれている。奇観である。潮と波の状態がよければ「イカ丸」は洞窟の中にも入るらしい。今日は叶わなかった。 コンクリート然とした存在感がロシア製のテイストを醸し出す呼子大橋のむこうが加部島。 島に渡る前、橋の袂に、イカシュウーマイで有名な「萬坊」の海中レストランがある。 日本三大朝市が輪島・高山そしてこの呼子である。ただし、房総勝浦を入れる三大朝市もあり、呼子と勝浦の闘いは水面下で熾烈に繰り広げられている・・・かもしれない。 |
| 哀しくなるほどに空が蒼い。 その空が高く遠く広がっている。 会津盆地に秋が訪れようとしていた。 早朝から開館している会津武家屋敷は会津の奥座敷、東山温泉の麓にある。筆者は千七百石取りの家老、西郷頼母の屋敷を再現したこの施設内をゆるゆると観覧している。 前回の訪問から20年の歳月が流れていた。 会津は「武士」と言う精神の酒精分が、あたりに漂う歴史の薫りに共鳴し揮発する土地のひとつだ。その薫りは保科松平家会津藩が辿った幕末の歴史に薫じこまれている。 徳川家に忠勤した会津藩を15代将軍慶喜は官軍の前にスケープゴートとして差し出した。その後の、いかにも武士らしい武士の最期を飾った会津の姿が、この地を訪れるたびに筆者の心にある種の湿り気を帯びさせるのである。 ただし、このかなり濃度の高い会津への肩入れは仇敵の位置づけをされる長州への否定には繋がらない。政策の相違が流血でしか解決されない時代を生きた会津や新選組と薩長を比較してその是非を今の世の尺度で問う作業は空しい。 幕権いまだ衰えを見せぬ頃、会津は新選組を使って京において長州の浪士を切りまくっている。長州には長州の恨みがあろう。2度にわたる長州征伐をきわどくかわし得たからこそ勝者の側に立つことができたが、ひとつ間違えば、会津と長州はその立場を逆転させていたかもしれない。 「和魂洋才」と言うが、和魂が会津、洋才は薩長ということだ。 洋才は今に通じる近代日本の型だから現代の筆者にも容易に同化できるが、和魂は失われて久しい |
民族の遺産だ。失くしたものを哀惜するのは世の常だから、筆者の会津好きもそのようなものだ。 鶴ケ城を出て、市内循環のバスに乗り車窓に焦点の定まらぬ視線を彷徨わせる。「老町」という表示が現れた。「おとなまち」と読よませる成熟したその精神文化がこの地にはある。 阿弥陀寺東でバスを降り、七日町にある斉藤一の墓の前に立った。 新撰組三番隊隊長で副長助勤。近藤、土方、沖田、永倉に並ぶ剣の使い手だった。 会津戦役で仙台に転進する土方等と袂を分かち会津と命運を共にした。「会津あってこその新選組だった」との思いかららしい。戦後、斗南への移封にも従い、容保の媒酌で妻帯し藤田性を名乗る。西南戦争にも出役し大正4年に72歳で病没。 お三階と呼ばれる旧鶴ヶ城内の建屋を移築した阿弥陀寺の一画、殉難した会津藩士一堂の墓の脇に、最期は会津藩士として生きたいと願った斉藤の墓がある。「燃えよ剣」では松前まで土方と行動を共にし、その地で土方から郷里に帰されたことになっている。司馬氏の創作部分であろうか。 墓は小さくひっそりと据えられている。 故人に話しかけるのは、人の性なのか。「斉藤さん」筆者は尋ねざるをえない。 「函館での土方さんの最期も、労咳で夭折した沖田の噂もあんたはすべて聞き及んでいるだろう。残された者にとって死者はいつまでも年をとらない。70余年を生きたあんたは、あの激動の時代を晩年、どう回顧してあの世に旅立った?」 過ごしてきた時間よりも、手持ち時間の目盛が少なくなってきた今、筆者の感傷癖はとめどもなくなっている。 |
| 山形の馬美ケ崎川畔で実施される「日本一の芋煮会」は、毎年9月第一日曜日に実施される。 筆者は山形へ向かった。 平成元年から始まった「日本一の芋煮会」も回を重ね、今年は20周年の年だと言う。 それを記念して従来3万食を準備する芋煮が今年は5万食。参加者20万人を見込むとのことだ。(20万人見込んで5万食とは、これいかに?) 鍋は朝6時から作られていた。県産の里芋4トン、牛肉1.6トン、ネギ4千本、こんにゃく4千枚、醤油900リットルが5万食の原材料だ。 セレモニー開始は9時、芋煮の配食開始は10時頃とのことだが、タクシーを飛ばして8時に会場についた。チケット販売所の前に行列ができていたが、長蛇と言うほどでもない。筆者の後ろにも人が並び始めるが列はさほどに伸びない。あいにくの空模様で雨まで降っているせいかもしれぬ。 そうこうしているうちに8時20分にはチケットの販売が開始された。芋煮の交換チケット(300円)を購入すると整理券も一緒に渡される。 「A上流」と書かれた整理券をうけとった筆者。 このアルファベット順に呼び出されるらしい。 大量にチケットを購入し持参の鍋で持ち帰るつもりの人も多い。 マスコミも多い。 彼等のためにクレーンまで用意されている。鍋を摂り下ろす角度にワゴンを吊るためだ。 大鍋の直径は6メートル。今年は対岸に3メートルの大鍋も用意され、こちらでは庄内の芋煮がふるまわれる。山形の芋煮は醤油味、庄内の芋煮は味噌味。山形は牛肉、庄内は豚肉。芋やこんにゃくは共通だが、庄内は厚揚げが入る。 |
8時45分。ようやく配食所に通じるゲート前への参集を求められた。ゲート前でさっそくインタビューが始まった。「いつから並んでいるか」「どこから来たか」実にフォーマット通りである。 9時。セレモニー開始。 開会宣言に続いて祝辞。 これが長い。呆然とするほどに長い。 芋煮のフタをクレーンで吊り上げるセレモニーは企画のハイライトだ。一瞬、吊り上げられたフタを見失うほどの湯気が吹き上がる。 芸能人ではラッシャー板前氏が起用され、ざるに盛られたわずかな具材を投入して鍋の準備完成という演目を担当する。ようやくありつけると思ったが今度は「味見の儀式」が始まった。 早く食わせてくれー! 10時20分。目がくらみ、足が震え、あと少しで昏倒しそうになったそのとき、とうとう配食が始まった。やっと芋煮にありつけるのだ。 芋煮を受け取り、立ち去ろうとしたらプレスのカメラマンが筆者に「受け取るところを撮りたいのでもう一度戻して受け取って下さい」と注文をつける。なぜプレスはこうまで自己中心的で傲慢なのだ。無論無視である。君の都合にあわせる義務はない。「後ろの人で撮ってください」と丁重に断った。 上空には空自のチョッパーが2機。歓迎飛行をしている。操縦はもちろん山形県出身者だ。 いつの間にか雨も止み、人が増えている。この日、参加者は15万人と発表された。 宿年の願いがかなった1日であった。 願いはかなってしまえば、後は想い出になりかわるのみである。 |

| 16世紀の末、九州の鄙びた漁村が一夜にして大都市になった。土地の漁民にとってはまさにそんな印象であったろう。 忽然として現れた都市は、5ヶ月から8ヶ月をかけて造作され、最盛期の人口は軍民合わせて20万から30万に達したと言う。 土地の名は名護屋と呼ばれた。 佐賀県鎮西町。東松浦半島の突端にこの地はある。半島の付け根は唐津である。中国(唐)との交流のための港(津)という意味のこの地は、後世、石炭の積出港として栄えることになる。 近時の市町村合併で呼子町や周辺地区を統合した唐津市の人口は、約13万。当時の30万という数字の途方もなさが伺える。 都市は、豊臣秀吉が企てた朝鮮出兵の前線基地として縄張りされた。つまり侵略戦の出撃基地としての軍事都市である。 中心となる城塞、名護屋城は当時、大阪城に次ぐと言われ、17万㎡の城域と五層七重の天守閣を誇り、その周囲3キロ四方に約130箇所の大名駐屯地が配置された。 徳川、前田はもとより、上杉、島津、毛利、そして石田、大谷、真田、結城、大友、小西、黒田、伊達、藤堂、加藤・・・諸将の陣屋があちこちに点在していたのである。 秀吉という、日本史上に突出する個性の最大の特徴は、巨大土木建築にある。 利をもって集団を競わせ、成果を迅速にあげるマネジメント能力において、秀吉の右に出る者はいない。その成功体験の積み重ねが希代の建築プロデューサーに秀吉を育て上げたと言っていい。現代なら世界有数のゼネコンオーナーになれたに |
違いない。 今まで筆者の視野に収まらなかった名護屋城だが、訪れてみればその遺構の広さに軽い驚きを禁じえない。ただし、城跡に構築物はない。広大な城域と、それを縁取る石垣が盛時を偲ばせるだけである。 それでも、天守台跡の高台に立つと玄界灘への180度の眺望が広がり、朝鮮侵略の軍を見送る老人性誇大妄想に陥った秀吉の晩年の気負いだけは看取される。 城跡のそばに立派な建築物がある。それは名護屋城博物館であり、無料で開放されている。 展示品は入場無料とは思えないほどしっかりとしたものばかりだ。 朝鮮の役で使用された日本軍の安宅船と朝鮮軍の亀甲船など、大きな模型が陳列されている。亀甲船を3次元で見るのは初めてだ。見るからにこれには勝てないなあという気にさせられる。 これほどの遺構(大阪城に次ぐ城塞)でありながら、観光地としてイマひとつなのは、侵略戦争の出撃基地というマイナスイメージが大きいからなんだろう。 城跡に漂うこのテイストは以前にも経験したことがある。 それは安土城だ。 どちらも当時、その繁栄並ぶもの無しとまで言われた城であり土地だったはず。 そしてどちらもその最盛期は短く儚い。 安土桃山と言う日本史上に類のない派手な時代を創出した信長と秀吉、2人の城がどちらも、その後、人々の記憶から長く薄れてしまったというのも儚くていいではないか。 |



| 猛暑が続いているせいであろうか。折に触れ、涼しかった道東を思い出すことが多くなった。意識しないうちに深く静かに釧路にはまってしまったことを認めざるをえない。 毎朝の天気予報では、かならず釧路の予想最高気温を注視してしまう。 関西圏は暑い。 大阪37℃なんて予報されているのである。でも釧路は20℃だったりする。 決めた。 真夏には必ず釧路を起点に道東に行くことにしよう。 霧にむせぶ幣舞橋(ぬさまいばし)。 釧路川が海に流れ込む河口にかかるこの橋の風情が好きだ。橋上には4人の彫刻家による春夏秋冬を現す4人の女性像が佇んでいる。橋の周囲はアーク灯が輝く近代的な河岸公園。しかしながら稚内の北防波堤ドームに通じる寂寥感が漂う。 どれほどの設備を整えようと人の姿がそこになければ荒涼たるの印象は拭いきれないのである。 しかし、その感傷的低温状態は、旅の漂泊に欠かせない要素でもある。駅そばのホテルに戻る途中、人影のない街路にポツリと提灯の灯を認めたときの安堵感も忘れがたい。 その屋台は「釧路名物こぐまラーメン」とあった。さっぱりとした鰹ダシ、腰の強い中細の縮れメンは、まさに酒食後の締めのためにあるような物件だ、これが筆者の「呑んだ後の一食」魂に火をつけた。「河むら」「銀水」「まるひら」「山島」・・・釧路ラーメンなら、店巡りも辞さないのである。 釧路の夜を契機にこの後、筆者は近時活動を停 |
止していた胃袋の活発な活動再開に悩むことになる。 そうだ。釧路の食事情は筆者の嗜好にジャストフィットしているのだ。 炉辺焼きだって釧路が発祥の地だ。 一夜、つぶ焼きの老舗「かど屋」を目指したのに「くし炉あぶり屋」に入ってしまった。 無性に「カニの甲羅揚げ」が食べたくなったのだ。かなり広壮な店内を埋め尽くす客の喧騒に地元からの支持という気配が漂う。今宵の選択の成功をビールで祝う。 ひとり旅ならば、どんなに客が入っていても、どこかしらの隙間に案内される。 「牡蠣の貝焼き」「帆立の貝焼き」をサッポロのクラシック生とともに愉しむ。 「ザンギ」「かに甲羅揚げ」「もつ煮込み」「ししゃものメス」「だし巻き玉子」と欲望のままに消費しつくした。 多くの町には地図上の目印によく登場する「あーあそこね」物件があるものだ。 金沢だったら「片町スクランブル」広島なら「アンデルセン」岡山では「天満屋」 釧路にはかって百貨店「マルイイマイ」があったがどうやら閉店してしまったらしい。 「オリエンタルプラザ」という歓楽ビルを覚えておこう。いつか役に立つ日がくるかもしれない。いや、別にそのビルに入る必要はないんですよ。目安ですからね、目安。 「和商市場」「八千代本店」は定番となったが、「駒形屋」や「魚政」のさんまんま(寿司)はまだ消費したことがない。 次回は必ず・・・また来る理由ができた。 |
| 台風に発達するはずだった低気圧が消えてしまったらしい。 未消化のエネルギーが海を揺さぶっている。 八重山諸島の島々と主島である石垣島を結ぶ航路の多くは、環礁とそれら島自身によって外洋からの波涛から守られている。しかし、この日、波照間島へ向かう高速船は、西表島と新城島間の水道を抜けたとたん、外洋の荒波に洗われることになった。途中、何度もエンジンカットをする。そのたびに船体は高々と持ち上げられ、次の瞬間傾きながらゆっくりと波間に落ちてゆく。 あまり嬉しくない状況だ。高波に正面から向きあうようにしているが、時に横波に翻弄される。 はらはらしているうちに船は、しかし沈むこともなく有人の島としては日本最南端の島、波照間島の桟橋に横付けされた。定刻を10分程度遅れての接岸である。通常は1時間の船旅だ。 ここは日本で唯一、南十字星を見ることができる島(ただし4月~6月) 竹富島のように港にはレンタバイク・サイクル店の送迎バンが何台も待ち構えている。 内装3段のママチャリを借りた。 島一周道路は、島の外延部を沿わず内陸部でやや大きめのオービット軌道を描いている。 島の周囲は14.8キロ、島は、米粒のような形をしている。反時計回りに周回を開始する。 港は島の北西にある。南岸は荒波打ち寄せるペムチ浜や高那海岸だ。この海岸線に「日本最南端の碑」が据えられている。大きな石碑にこれか?と思えばそれは「平和の碑」。「最南端の碑」は地味な三角形の方向指示盤のようなものだ。たぶんかなりの人が見間違えているとみた。 |
東岸近くには、波照間空港がある。まるで南方戦線の海軍航空隊基地のようだ。ターミナルと言うよりは待合室といった風情の平屋の施設に人影はない。週4日、1日2往復、エアードルフィン社のBN-2が石垣と波照間を結んでいる。 レンタサイクルについている手書き地図に下田原城(ぐすく)を発見した。 日本最南端の島にある城、ということは日本最南端の城ということだ。行かねばならない。 一周道路の途中に「入り口」とだけ書かれた地図。脇道は無数にあるぞ。「入り口」の目安が書いてないからどこが入口だかわからない。八重山でも県民性はアバウト(テーゲー)が基調だ。 標識を発見し、何とか城跡入口にたどりつく。鬱蒼としげる夏草のむこうに石垣が覗いている。 一周道路をほぼ巡り終えると「西の浜」だ。外海の荒波を知らぬ穏やかな海水浴場。美しいエメラルドグリーンの海のむこうに遠く西表島が見える。翠色の穏やかな海を眺め、水着を持ち歩かなかったことを後悔しつつ集落に向かう。「あやふふぁみ」という記憶層への定着を拒否する名称の食堂に飛び込んだ。時間は11時30分。この島ではあらゆる店が12時から3時までお休みになってしまうと言われていたのだ。(ただし「あやふふぁみ」は昼過ぎまで営業しているようだ) 「しょうが焼定食」「てびち定食」「ラフテー定食」「スーチカ定食」メニューは豚肉料理主体。 暑さ負けをしていたので「冷やしそば」を食べてしまった。後から注文した客の「しょうが焼定食」を見て唇を噛み締めた。美味そうだ。 (次回は必ず頼む) 固く心に誓った筆者であった。 |

| 湿原の潅木の隙間に鹿が佇んでいた。 一瞬、その鹿と目があった。(気がした) 大きく見開かれた黒い瞳が「誰?」と問いかけているように見えたのは筆者の感傷癖のなせる技だ。漂泊の旅人が語り相手に動物を据えた。それだけのことである。 湿原を抜ければ、広大な牧草地が広がる車窓はその先でオホーツクの海に景色を変えるはずだ。 鉄路の脇を定規で引いたようにまっすぐに道路が寄り添い走る。その上を列をなして列車を悠々と抜いてゆくバイクの群れ。 ここにあると「道」という概念が妙にリアリティをもって筆者に迫る。道が、町と町を結び、それが生命線となっている。道が断たれれば町が孤立するという危機感がなぜかいまそこにある。 ここに来たってはじめて理解するのである。都市間の接続は道なのだと。そしてその認識は都市間に存在する広大な自然によって強化される。 道路行政は中央と地方ではその意味が異なる。 マニア垂涎のローカル線、釧網本線は、釧路と網走を結んで走る。本線名がついてはいるが、特急も急行もない。1日5往復のうち快速が1本。 快速「しれとこ」は1輌編成のワンマンカーだ。座席はドアそばのロングシート(ショートだが)以外は車輌の中央を境に向かい合わせに並んでいる。ボックスシートではない。乗客の半分は進行方向と逆向きに座ることになる。固定されているため向きを変えられない。 釧路から乗るなら、2箇所あるドアのうち後方ドアから乗車することをお奨めする。前寄りの座席が進行方向に逆向きだからだ。逆向きに座り続けた筆者の貴重な体験から導き出されたノウハウ |
である。大事に使っていただきたい。 釧路湿原は進行方向左側に、そしてオホーツクの海は進行方向右側に現れる。 北へ。 漂泊の筆者は網走に向かう。 そこに、何が待っているのか。 網走は生活者の町だ。ひどくそっけない商店街が駅から離れてあるだけの町。観光目的の浮かれ気分は、そこに漂う海から吹き渡る冷気のような日常性によって氷点下にまで冷やされる。ここは、実用を旨として成り立つ町なのだ。つまり、生活者の町である。 そしてこの町には「志帆川」がある。 9年前に食べた「網走鍋」が忘れられない。 牛乳と味噌、バター仕立てのスープに海鮮はもちろん、じゃがいも、にんじんなど道産の野菜をたらふくぶちこんだ個性派鍋をオーナーのSママの話を肴に消費した。 もう一度、あの鍋を食べに来た。 訪問の真意はそんなところかもしれない。 ビッグママは健在だった。 網走鍋は2人前からというところを拝み倒して出してもらう。かわりに店の瓶詰め商品についてのママの営業に快く応じる。ママの話は奔放だ。 「市長がね、5億で水源を確保したのよ。それまでは渇水もあったけど、おかげで水には不自由しなくなった。最初、市民はブーブー言っていたけど、今では感謝している」 「どこに泊まっているの?」 「C」 「ああ、一番いいホテルだ」 (え?トイレにウォシュレットないんですけど) |

| 釧路湿原は虫だらけである。 湿原の遊歩道を歩くなら、虫よけ装備をお忘れなく。筆者は最高気温12度のおかげで長袖だったのが幸いした。半袖、短パンなどで歩いていたら虫さされ極彩曼荼羅と化していたに違いない。 早朝、湿原西方の釧路市湿原展望台に向かう。 JR釧路駅前からバスで約40分。 湿原に群生する「谷地坊主(やちぼうず)」という植物を模した展望台は「湿原展望台」停留所前にある。徒歩ゼロ分の好立地。 展望台からの眺望はやや狭隘だが、始めて見る分には湿原の広大さを充分に堪能できる。 展望台を起点として湿原内約2.5キロを周回する遊歩道があった。トコトコ歩き始める筆者。帰路の足であるバスの発車時間まで約1時間ある。 入口に看板があった。 「遊歩道でヒグマが目撃されています・・・ひとりでの遊歩道散策は避けてください。物音や声を出しながら歩いてください」 嫌なものを見てしまった。 しかし前進である。ただし早足。口笛を吹いたり、歌をうたったり、これだけはお得意の独り言を叫んだり、たぶん湿原一やかましい筆者。 (出るなよ熊。すれ違うなよ観光客) 遊歩道の途中にある「サテライト展望台」からの眺めは、湿原展望台よりも素晴らしい。そして湿原内は、セミの鳴き声の嵐である。映画ではこの喧騒が不意に途切れ静寂に包まれると、エイリアンとかプレデターが出てくることになっているが、筆者にとっては熊しか感心の対象はない。 熊さんに出会った唄なんぞを歌ってずんずん歩いていたら無事起点に帰り着いた。 |
バスに乗って釧路市内に戻る。 昼の腹ごしらえは「和商市場」と決めている。 「勝手丼」を食べるのだ。 9年前にはこの「勝手丼」という名称を認識していなかった。もしかしたらまだ命名されていなかったのかもしれない。 ごはんだけを購入し、おかず売り場で小ポーションの魚介類を買い、わさびと醤油をかけまわしてもらう。それを簡易テーブルコーナーでわしわし食べる。それが「勝手丼」 要はお好み海鮮丼である。 9年ぶりの宿願を果たし、駅に向かう。14時52分発「ノロッコ4号」が偶然待っていた。 日本一遅い列車という謳い文句の釧路湿原ウォッチング列車である。気動車牽引で5輌の客車が繋がれている。ログハウス風に改造された4輌とノーマル仕様の1輌編成。釧路、塘路間を45分程度で結ぶ。筆者は、途中駅の釧路湿原駅で下車。 ログハウス風の無人駅から徒歩10分の距離に細岡展望台がある。「大観望」との別名は、その見晴らしの良さからきているらしい。 展望台までの坂道の途中、看板が目についた。 「注意!熊出没 展望台より先は注意」 (・・・またか) 展望台から湿原を眺める。 蛇行する釧路川が陽光を反射し銀色に輝いている。視界から人口の造作物が消え去った。湿原のむこう、地平線を遮る丘陵の上にポツリと浮かんだシルエットが午前中に筆者が訪れた「釧路市湿原展望台」らしい。 帰路も偶然、ノロッコ号に乗って市内に戻る。 |

| 褶曲が葉脈のように浮かび上がる緑の山襞に機影が落ちている。 大地の緑の皺の上を乗機の小さな影が時速800キロで移動しながら浮き沈みを繰り返している。 平たく開墾された土地に白い芥子粒のような牛の姿を認められるほどになると機影は幾分大きくなり、瞬く間に急速に眼前に近づいてきた。 接地の衝撃とともに制動がかかり、シートベルトが軽く腹に食い込む。 エアバスA320は、大自然の真っただ中にポツンと築かれた釧路たんちょう空港に降り立った。 6月末日に近い釧路は、最高気温12度。 空気はひんやりとして肌寒い。出立した東京は25度で汗ばむ気候だった。ちなみにその日の大阪の最高気温は29度。沖縄は30度だ。 釧路は霧の町。太陽光が遮られ日照時間が少ないせいか道内の札幌、旭川よりも気温が低い。 この日、札幌、旭川も24度で東京並だった。 地元民の服装は当然長袖。ウィンドブレーカーやフリース姿もちらほら見かけられる。 宿で荷を解き「八千代本店」に向かう。 店は釧路の繁華街「末広町」にある。駅から少し離れているが徒歩の距離だ。 駅を背にしてやや斜めに直進する大通りが「北大通」その先に釧路川にかかる「幣舞橋(ぬさまいばし)」がある。 「北大通」とそれに交錯する「国道44号線」と「釧路川」に挟まれたエリアが「末広町」である。 うろ覚えの記憶を頼りに「八千代本店」へ。 9年前に酒食を愉しんだ記憶が蘇る。 首尾よく店舗を見つけ、カウンターに座る。 とりあえず切ってもらうことにした。 |
おひょう、たんたか、ますのすけ、きんき、そい、ホッキ貝。 おひょうは深海魚、体長2メートル程まで育つ奴もいるらしい。旨いのは1キロほどのものとのこと。鰈の一種である。たんたかも鰈。まつかわ鰈の別名らしい。ますのすけはキングサーモン、そいはめばる・めぬけの親戚。いずれの魚もぴとぴと、しこしこ、ねっとりと旨い。 「鰊の切り込み」が出た。麹にあえた鰊の刺身。 「エビの頭とみそ、それからカニの内子、酒の肴です」 出された皿には緑色(えび)と黒色(かに)のわた系つまみが。根室の地酒「北の勝」夏酒がぐんぐん進む。危険である。 「サーモンの煮付けとあん肝です」 かなり危険である。 すでに釧路の地酒「福司」の上等純米が空きかけている。 かずのこが出てきた。我儘を言って、海苔と白菜の漬物、中トロを2カン、切ってもらう。 海苔の上に白菜を敷き、中トロ、かずのこを巻いてパクッ。きわめて満足。同時に危険。「福司」は吟醸に移っている。 「そろそろ握ってください」 さんま、きんき、かに、はっかく、うに。 はっかくが甘くて旨いことが発覚。 ・・・すいません、もう二度と言いません。 玉子で締める。 店を出れば、9年ぶりの釧路は、もやとも霧ともつかぬ薄絹のようなベールに包まれ、過去と現在が重なり合う不思議な空間に筆者を誘っていた。 |



沖縄行11 →→→back 96 06(1) 2) 3) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
| 夜。 雨は倦むことなく降り続いている。 昼に買った「ゆいレール」1日乗車券は600円。3回乗車すれば元は取れる。今日はまだ2回しか乗車していない。 筆者は「元を取る」体質である。 「牧志」から「美栄橋」まで普段なら歩く距離だがモノレールに乗る。 松尾にある「やきにく華」を訪れ飽食。「タン塩」と「アグー3種」「石垣牛特選カルビ」をオーダー。アグーとは沖縄県産豚のことで3種の内容は、ロース・肩ロース・カルビ。これを塩焼きで食べる。ビールは大ジョッキ2杯。韓国海苔をパリパリと口に入れ、カルビを白菜キムチで包みサンチュで巻いて「はむっ」美味~♪ 想像以上に量が多くきわどく食べきった。次回は作戦を練って食べよう。店を出る。 「流浪のコンサートマスター」Y氏から紹介されたバー「Grass」は近辺の松山にある。繁華街から離れることになるが、ぶらぶらと流す。 頬をなでる風は、ほの暖かい(生ぬるいとも言う)。人通りは絶えている。雨はいつの間にか止んでいた。那覇市松山の路地裏、雲に覆われた空は地上光を反射し、不気味にほの赤い。その空を背景に黒いシルエットが浮かぶ。寺の屋根の龍が黒々としたシルエットで空に吼えていた。 バー「Grass」のバーテンドレスN嬢のカクテルを4杯ほど喉に流す。すっきりとした涼味。 3杯目にレキオというオリジナル。4杯目は琉神。オーナーバーテンダーT氏が沖縄の泡盛を使ったカクテルコンペティションで優勝したレシピだそうな。そしてこの酒は沖縄サミットのときに |
各国首脳に振舞われた。 翌日、N嬢の教えてくれた牧志公設市場奥の呉屋てんぷら店に向かう。ふわふわの衣に魚やイカが包まれている。内地でイメージする天麩羅ではない。スナック食である。魚が旨い。 同じ市場の中央通りには松原製菓店がある。 ここで昔懐かしいバターケーキに出会い、宿でむさぼり食う。あまりの懐かしさに滞在中、都合4個食った。 N嬢に教わったもうひとつの観光スポット、「チービシ」と呼ばれる環礁群は那覇泊港から船で20分程度のところに浮かんでいる。神山島、ナガンヌ島、クエフ島の3島で海水浴気分に浸れるらしい。いずれかひとつ、あるいはすべてが無人島らしい。朝、と言っても寝坊気味の時間に泊港へ向かう。無論何も調べずに行った。 船は出払っていた。この季節、9時台で往路の船は終わりのようだ。つまり1日一便。しかも定期航路は慶良間へ行くものでチービシはちゃんとツアーの予約をしなければいけんようだ。無計画にもほどがあるのであった。ホント今回は肩の力が抜けていていいぞ。島で言う「テーゲー」って奴だ(大概の意。テキトーに、ちゅう感じか) しかたがないので夜、「てだこ亭」で島食材のイタリンを食べ、「タコス屋」でタコライスとホットドックをオリオンの瓶ビールで流し込んだ。 満喫して島を離れる。 ANAの747ジャンボのエコノミー2階席85番ABCは背後に席がないのでリクライニングに気兼ねがいらない。またHJKの87番以降は天上に収納庫がないので面倒くさい。覚えておこう役に立つ。(たつか?) |

画像(左)から 呉屋のてんぷら・てだこ亭のあぐー・タコス屋のタコライス・やきにく華のアグー3種・石垣牛
沖縄行10 →→→back 96 06(1) 2) 3) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
| 雨の沖縄。 沖縄の雨は、スコールのごとく駆け抜けてしまうものと思っていたが、雨は倦むことなく降り続いている。3月は降雨日が多いのかしらん? 満を持しての訪沖ならば、切歯扼腕、神を呪い続けたであろう天気だが、今回は肩の力が抜けきっている。那覇市内を離れるほどの気概もない。 一度、雨が止みかけ雲が切れたのでバスセンターまで行った。名護に行こうとしたが、雲は再び空を閉ざし雨勢が強まったので撤退。 (雨の沖縄の過ごし方でも考えるか) いたって気侭に時間をすごすことにした。 夜着なので、これは定番の活動、国際通りの「波照間」でライブを眺めてオリオンビールと泡盛を数種、島の肴で時を過ごした。 翌日、かねてよりチェックしていた餃子の有名なPへ。ぶらぶらと歩く。沖縄県人は歩かぬと言う。アメリカ人のようにドアツードアで車を使うと言う。筆者のような人間は彼等の目にはターミネーターのように映るのだろうか。それにしても那覇市内は公園が多い。のどかさが増幅する。 Pでは不満足な結果に。にかかわらず見た目が筆者好みのためオーバーオーダーで満腹に。腹ごなしにおもろまちの「DFSギャラリア」へ。 国内唯一の免税ショッピングモールで何を買う気かと問われれば目的はないのである。女性のための施設であった。時計もバックも化粧品も何一つ筆者の消費マインドを刺激しない。 「この××が、こんなに安い!」という安さが40万、50万では話にならん。そそくさと撤退する。無論「あんまりいいのがないね~」という表情を浮かべながら。 |
雨はしとしとと降り続いている。 首里城そばの「龍潭(りゅうたん)」と「玉陵(たまうどぅん)」に向かった。 「龍潭」は中国に範を求めた人造池、「玉陵」は王家の墓である。雨にうたれた景色に風情を求めたのである。蒼い空と白い雲、強烈な日差しの下の景色は確かに沖縄のイメージなのだが、それをはずすのも面白かろう。 「龍潭」の周囲は公園だ。人影はない。静けさだけが友である。石畳もしっとりと濡れそぼち、目論見とおりの環境が筆者を迎えた。 (ん?) 妙に威圧的ながちょう(?)が陸に上がって威張っている。 (なに?こいつ) 鳥ごときがカチンとくる我が物顔ぶりである。 けちらしてやろうかと思ったがあまりに大人気ないのでやめておいた。 「玉陵」も人影はほとんどない。 重厚な石造りの王の墓は、周囲の木々のざわめきをも遮り、王族の静かな眠りを守っている。 ゆいレール首里駅に戻る途中、あきらかに地元のみんなのそば屋然とした「いずみ」という沖縄そば屋が目にとまる。 靴を脱いで板敷きの店内に入る。テーブルは6席ほど。板敷き続きの奥の調理場におばちゃんがひとり。そばを頼む。 後からおばあが入ってきた。常連なのだろう。近所の話をひとしきりすると持ち帰りの何かをおばちゃんが包んで渡した。おばあは、その後そばも食べて帰った。 目の前に繰り広げられる日常に心和む筆者。 |

| 4月29日「みどりの日」は2007年から「昭和の日」となり、みどりの日は5月4日にお引越し。 とは言え4月下旬、山は緑に萌え立っている。 2年前、鞍馬と貴船で新緑の美しさに目を奪われて以来、桜が散り、木々の緑があざやかに染まり始めるこの季節を筆者はこよなく愛するようになった。 モミジと呼ばれる紅葉よりもこの時期の耀くような翠(みどり)のカエデの方が筆者は好き。 「翠蓋(すいがい)を碧空に翳(かざ)すあり」 (徳冨蘆花「自然と人生」) 「翠蓋」とは頭上一面、緑の梢に覆われた状態を指す言葉。 4月29日、翠蓋の下の人生を愉しみに京都方面に向かった。 京都に向かう車中でふと考えた。 世はゴールデンウィークの前半戦だ。京都は観光客でごったがえしているかもしれない。鞍馬や貴船など最悪の選択だ。人ごみを避けるために京都を避ける。今日の基本方針が決まった。 京都から新快速に乗車。湖西線で「比叡山坂本」に向かう。山科、大津京の2駅に停まって比叡山坂本まで18分。 坂本は比叡山の東の玄関口だ。 元亀2年、信長の掃滅戦により街は灰燼に帰した。しかし、それ以前は人口1万を超える琵琶湖畔の一大門前町だった。 行政区分では滋賀県にあたる。延暦寺を擁する比叡山を境に西が京都、東が滋賀である。叡山へは、滋賀方面からの方が入りやすい。 坂本は静かな門前町の佇まいを見せている。 JR駅から比叡山に向かってまっすぐにひかれ |
た道の先、比叡の山裾に全国3千8百余の山王神社、日枝神社の総本山、日吉大社の鳥居が立っている。道は日吉大社の参道である。 国宝、重文が軒を連ねる境内は40万㎡。奥行きのあるいい景色が広がっている。新緑が地面を翠色に染めている。人の姿もまばらだ。 日吉大社にむかう道の両側には里坊が穴太衆(あのうしゅう)積みと呼ばれる石垣構築に囲まれて建ち並ぶ。延暦寺僧侶の隠居所が里坊である。公開されているのは「旧竹林院」と呼ばれる1千坪の敷地を有する国指定名勝。 そんな里坊の連なる参道の手前に、創業3百年あまりと言われる「鶴喜そば」と創業何年かわからない「日吉そば」がある。道の東北角地に立地する「日吉そば」の方がひと目を惹く。造りもそれらしいので「鶴喜そば」と間違えて入店する観光客もいるかもしれない。 参道を日吉大社に向かう途中で南に折れる。 白壁と石垣が重厚な「滋賀院門跡」は延暦寺の本坊、江戸末期まで天台座主の住居であった。道は権現馬場と呼ばれる急坂に出会い、山に向かえばその先に「日吉東照宮」がある。家康、秀吉、日吉大神を祭った社殿は、日光東照宮のプトロタイプモデルと言われている。 江戸幕藩体制の宗教政策は、天海僧正抜きには考えられない。その天海僧正の廟所が「慈眼堂」である。新緑を通した木漏れ日が苔むした地面に光輝を落としていた。 「日吉大社」の北1キロ、琵琶湖を望む景色を楽しめる山辺の道を歩けば「西教寺」に行き着く。伏見桃山城や近江坂本城の一部を移築したと言われる寺域には明智光秀一族の墓がある。 |

| 訪れた街を好きになるときは、大概共通の想いを抱いている。 「この街で夜を過ごしたい」 そんな想いだ。 「この街で夜を過ごしたい」ということは、この街で夜、酒食を愉しみたいということだ。 筆者の場合、鄙すぎていてもこの気持は発動しない。と、言って林立するビルの中に飲食店が吸収されてしまうほどの都会でもいけない。飲食店の立ち並ぶ繁華街は欲しいのである。 適度に都市で、適度に鄙。 ついでに言うと、道路は若干錯綜していただきたい。四角四面に整備されているよりも、行く先に多少の不安を感じる迷走感が欲しい。思わぬところに出てしまったという意外性が街歩きに小さなワンダーランド感を醸し出すのだ。 とにかく福井は夜を過ごしたくなる街である。 ぶらぶらと街を歩く。メインストリートは思いのほか広い。市電と福井城跡を見て思い出した。 記録がないので明確ではないが筆者は25年ほど前に福井に来ている。京福電鉄で三国港まで行った。遊歩道を東尋坊まで歩いた。盛夏の頃だ。途中、蜂に襲われたのだ。市電が走る街の映像が記憶中枢のどこかにひっかかっていたが、城内に県庁があったことで思いだした。 感懐がしばし筆者を包んだ。その記憶はちょっと甘酸っぱい。しかし、そんなことをここに細かく記すわけにはもちろんいかないのである。 福井城跡の北側にある「養浩館」は、回遊式林泉庭園だ。大きな池のほとりに開放的な建物がある。庭園そのものは今ひとつだが、建物がいい。 陽光が正面の池から反射し、その照り返しが室 |
内の天上で踊っている。揺れる光輝を眺めているとうずうずと笑みがこぼれてくるのはどういう心理状態なのだろう。 (こんな家に住みたい) 素直な欲求が生まれた。 (欲しい) と思った。こんな家が、である。住宅物件に関して人生で初めて芽生えた物欲であった。 かつて三国港まで筆者を運んだ京福電鉄は「えちぜん鉄道」に名称を変えていた。 1日乗車券を購入する。車内に液晶パネルのある思いのほか近代的な車両で永平寺に向かう。 福井を基点として永平寺口まで約40分。永平寺口駅は、改札を出るとバス乗り場に直結である。1時間に2本の列車ダイヤにあわせてバスが待っている。神風タクシーのようにぶっ飛ばすバスに乗って10分もすれば永平寺参道入り口だ。 門前には「永平寺おろしそば」と「ごま豆腐」の看板が立ち並ぶ。 山門、仏殿、法堂、僧堂、大庫院、東司、浴室の七堂伽藍を中心に大小70あまりの堂宇を誇る開祖道元の曹洞宗総本山であり、僧門の道場が永平寺だ。観光気分で中に入ると、畳に正座させられ修行僧からの案内を聞かされた。 (正座は苦手なんだよな~) 思いつつも一人っ子の筆者は聞き分けがいい。無理なら崩していいと言われているのに正座で通す。冷や汗が一筋、二筋、つつ~と額を流れるころあいで開放された。 あとは自分のピッチで参拝である。 巨大すりこぎがぶら下がっている。よくわからんが撫でておいた。料理の腕があがるといいな。 |


| 谷を挟んで向かい合うふたつの台地がある。 東西に伸びるふたつの台地は、それぞれの片面を川に守られている。 川は、海に注ぎ込むその直前で急激に川幅を広げ、それに挟まれた台地は両側から押し広げられる川幅にすくまされたようにひょっとこの口のような地形となっている。 ひょっとこの口の先、岬となった高台に城が築かれ、豊後の海を見下ろしている。 海は、国東半島南部、守江湾である。 ふたつの台地は、南台、北台と呼ばれ、双方の台地上に武家屋敷が形成された。台地に挟まれた低い谷筋には町屋が集められている。 南台と北台の往還には、谷町への坂を下り、対面の坂を上らねばならない。 南台の坂を「志保屋の坂」、北台の坂を「酢屋の坂」と言う。この坂越しに映ずる相対する台地間の眺めがこの街の顔である。 「坂のある城下町」 それが街のキャチフレーズである。 街は、譜代大名松平氏3万2千石の藩府「杵築」と呼ばれている。「きつき」と読む。 杵築藩は藩政時代、国東半島のほぼ半分を領有していた。それ以前は、大友氏の支城として木付氏が拠り、島津義弘の武将、新納武蔵守の攻勢を挫いている。 南台の南面は、八坂川が防禦線となり、かつ川が台地をそぎおとしたような崖面となっている。いかにも攻めにくそうな地形である。 北台の北面は、北を守る高山川との距離が相応にある。こちらへの下り口は「「番所の坂」と呼ばれている。 |
北台は東方の、城のある岬に繋がっている分、南台よりも首ひとつ東に伸びている。 地勢は、北台から城にむかって一旦沈み込む。「勘定場の坂」がそれである。 坂の先で岬にむかい再び浮き上がる。 突き出した岬の突端に聳える天守閣は小ぶりである。しかし城下南面の護りとなる八坂川から見れば海を背にしてその姿は美しく見栄えがする。 この静かな城下町は、日豊本線「杵築駅」から4キロほどのところにある。 「杵築駅」は、別府のひとつ手前にある特急の停車駅とも思えぬ鄙だ。かつては私鉄国東線がここから城下の杵築市駅を結び、さらに北上し、国東半島の国東駅まで通じていた。 今は、廃線になってすでに久しい。 軌道の跡地が道路になっている。 バスかタクシーで城下に向かうしか移動手段はない。 「とりあえず杵築歴史資料館で土地勘を養うといいですよ」とのタクシーの運転手氏のアドバイスに従い、資料館に車を寄せてもらう。受付の女性にだいたいの街割を教わった。 国東線の廃線の影響か。街の雰囲気は鄙びたと言うよりは廃れた感じが微妙に漂う。 静かな城下町と言うは容易い。しかし、藩政の名残をとどめつつ、その美観を維持するために払う犠牲は、利便性であり合理性かもしれない。 近世と近代の調和、あるいは秩序ある融合は、ゆきかうだけの旅人の無責任な要求に応えるには重すぎる課題となって地域経済、社会、行政にのしかかる。守ろうとしなければ簡単に文明によって更地にされてしまうのが文化ということか。 |

| レアフード(Registered by 筆者) それは、レアメタル(稀少金属)同様、特定された産地でしか見かけることのできない珍しい「ご当地フード」。 レアフード(Registered by 筆者)。 それは、世間にその存在を知られることのない食品界の秘宝。 レアフード(Registered by 筆者)。 ・・・もう、いいか。 福井にソースカツ丼というレアフードがあるという情報をひっさげ、筆者は福井に向かった。 金沢という光輝に包まれた存在がそばにあるために見落とされがちな福井(まるで太陽と月のような関係だ)しかし福井はなかなかにいいのだ。 越前ガニを筆頭に、越前おろしそば、浜焼き鯖、鯖押し寿司、へしこなどの鯖料理、フグの子糠漬けなど、好き心をくすぐる物件が目白押し。そしてソースカツ丼。 何故今まで見捨ててきたのか、悔やまれることしきりである。 福井から「えちぜん鉄道」に乗れば三國港へ出て東尋坊へ行ける。自殺の名所だ。 「えちぜん鉄道」は、永平寺口にも通じている。 駅を出て向かうは、越前北の庄城跡。 信長の天下統一事業の後継を秀吉と競い、敗亡した旧織田家の筆頭家老、越前49万石の王、柴田勝家の居城跡だ。 城跡と言うにはあまりに小規模なそれは、柴田神社となり、遺構の一部を発掘の状態のままに納めている。勝家の銅像とお市の像が立っている。 粗暴と言うか、精神の格調にきめの荒さが目立つ勝家は、筆者の歴史的嗜好には合わない存在だ |
ったが筆者も老いた。ものの哀れにロマンのゲージが振れるようになってきた。 賤ヶ岳の合戦で佐久間盛政の積極攻勢策にひきずられ敗戦の将となった勝家は、北の庄城にて滅び去る。かつてルイスフロイスにその豪壮を称えられた九層の天守閣を誇る巨城は焼失し、それを伝える人々の口もいつしか閉ざされ、今、かつての繁栄をここに見出すことは難しい。 藩政時代は松平氏が北の庄の北に城を築いた。 織田政権以前、朝倉氏が一乗谷で栄華を誇り北国の王都として繁栄し、そして滅び去っている。 福井という土地には悲運の色彩が滲んでいる。 北の庄城跡の次はいよいよソースカツ丼だ。 発祥の店「ヨーロッパ軒」に向かう。 玉子で閉じず、タマネギもキャベツも載せず、特製ソースに揚げたてのトンカツをザンブと漬けてシャリの上に載せただけのシンプルなカツ丼はパン粉にも工夫があり、通常よりもきめの細かいものが用いられている。 甘辛の醤油タレにつける新潟カツ丼、ドミグラスソースをかける岡山カツ丼と並ぶレアフード界カツ丼部門三強のひとつソースカツ丼。 実にシンプルだ。筆者は気に入った。そして、メニューにはまだまだ楽しめそうな物件が並んでいる。 (パリ丼?) どうやらメンチカツ丼のことらしい。その他のメニューにも心惹かれる。生活圏にあればメニューの端から端まで食べ尽くしていることだろう。 会計をしようとレジに向かえばお土産にカツ丼用の特製ソースとパン粉まで売っていた。 無論、購入。 |

| 島鉄もうすぐ百周年。 島原鉄道は、JR長崎本線と接続する「諫早」駅を起点として「加津佐」まで78.5キロ。島原半島の三分の二を巡る私鉄である。 列車は、長崎に向かうJRと袂を分かつように反対方向の島原半島に向かう。 諫早から島原までは約1時間15分。筆者を乗せたワンマン1両、黄色の気動車が有明海を巡る。 車窓は限りなくのどかである。 有明の渚が軌道のすぐそばに寄り添っている。 途中駅の行き違い時、「鉄」の皆さんが脱兎のごとくホームに飛び出しカメラの砲列を敷く。 久しぶりのローカル線乗車は筆者の体内時計を寛ぎモードに切り替えてくれる。 やがて列車は城郭風の豪奢な駅舎の島鉄「島原駅」に到着。 駅の正面に坂がある。 坂の名は「七万石坂」 坂の頂点に島原城の天守閣が浮かび、その後背には雨煙にかすむ雲仙普賢岳が聳えている。 島原城は、コンクリート造りの昭和の復元物件だが、高々と積まれた石垣が思いの外美しい。高さとアーチのバランスが非常にいい。大手門から天守閣にかけての眺めもなかなかのものだ。 駅から城まで徒歩6分程度。 人影もまばらで静かな城下町との印象を得たが島原に落剥の影は感じない。 1時間に1本の地方鉄道の駅なので、車による観光客が多いのかもしれない。ふと思った筆者の勘は筆者にとって悔やまれる事実によって裏打ちされた。 島原半島の郷土料理「具雑煮」は、正月に趣向 |
をこらした雑煮を食べていたことが起源のものらしい。島原の乱の天草軍の糧食だったとの説もある。島原城の大手門前にある「姫松屋」がいつでもそれを出してくれるとの情報を手に店にむかった。静かな城下町の一角に人だかりがある。 (たぶん、あれがそうだ) マイクロバスが何台も停まっている。パーキングを出入りする車が途切れることはない。 行列はできていないが店内は騒然としている。 滞在時間に限りのある筆者は、気後れして食事を断念した(なにせ1時間しかないのだ)。 飲食情報は、もうひとつ握っている。 「寒ざらし」という白玉である。特製の蜜をかけて食べるそれは茶房「速魚川」で食べられる。しかしながら、そこも時間切れのためアウト。 天守閣からは雲仙普賢岳と眉山が望めるはずだが、折悪しく雨勢を増した天候の下、それらしいシルエットが浮かんでは消えるのみ。 食事も景色もおあずけをくらってしまった。 普賢岳は江戸時代に大噴火を起こしている。 その際、眉山が地震とともに大崩落し、島原城下は押し寄せてきた土砂に埋もれてしまった。土砂はそのまま有明海になだれこみ、波高25mと言う津波を発生させた。対岸の肥後天草地方に打ち寄せた津波は反射波を起こし、再び島原を襲う。歴史に言う「島原大変肥後迷惑」である。死者数は1万5千にのぼった。 ポンペイですら火砕流の発生した当時の人口が1万弱。世界最大の火山被害かもしれない。 城から5分ほどの武家屋敷跡をさっと眺める。 この1本を逃すと博多での約束の時間に間に合わないという列車に飛び乗り帰福。 |


| 石垣港から高速船で25分。周囲16.6キロの小さな島、小浜島。NHK朝の連続ドラマ「ちゅらさん」の舞台となった島だ。 島の最高峰、大岳(うふだき)は標高99メートル。天保山より遥かに高い。 船着場の近辺にレンタカーやレンタサイクルの店がある。 島内がのどかなのはひと目で分かる。自損以外の交通事故を起こすことなど月面で自動車事故を起こすほどに難しそうだ。この島でなら、22年間の筋金入りのペーパードライバーの筆者でもスクーターくらいは転がせるのではないかと思った。 (情けない) しかしながら、やはりレンタサイクルにした。 (今度来たら、密かに運転してみよう) ヘタレな筆者である。 小さな島だがアップダウンはある。 港の反対側にある「ちゅらさん展望台」まで4キロ強の行程の中央部南側に大岳(標高99m)があり、峠(丘)越えをしなければならない。 レンタサイクルに変速機はない。 さとうきびに囲まれた直線の道路は、まっすぐ丘の上にむかっている。炎天下「はひはひ」言いながらペダルを漕ぐ。なぜか脳裏に「坂の上の雲」という単語が浮かんでは消える。 途中、左折して寄り道をした。大岳を征服するのだ。男は山を見たら征服する生き物なのだ。 麓に自転車を置き、鬱蒼と茂る夏草の中、頂上への階段を上る。周囲には物凄く大きな蜘蛛が巨大な巣を張り巡らしている。油断がならない。あんな巣の真中に顔をつっこんだとしたら・・・バタバタバタ!心の中で手を振り足を地団駄する。 |
頂上には天蓋つきの展望台が爽やかな風をたぐりこみながら、待ち受けていた。周囲を見回し、しばしの爽快感に浸る。 「ちゅらさん展望台」まではもはや下るのみ。 島にはヤギもいれば牛もいる。動物クンたちののどかな姿を見ながらも、実は筆者、脱水症状をおこしかけていた。ペットボトルを持ち歩かなかったのが失敗だった。清涼飲料の自動販売機などどこにもない。 「ちゅらさん展望台」の上り口に牧場があった。 水をめぐんでもらおうと畜舎にむかってフラフラと歩きかけたところ、なんと神も照覧あれ!なんでこんなところに!自販機が立っている!電気が通っている!清涼飲料が売られている!売り切れのサインは出ていない! 増えるワカメくんのように水を得て活力を取り戻した筆者。 「ちゅらさん展望台」から番組ゆかりのがじゅまるの木を遠望した(私有地に生えているので近づけないのだ) 集落を目指して再び丘越えに挑む。往路とは路を変えているが、地勢は同じだ。 なぜか沖縄にそぐわぬ一本松に木をとられつつも静かな集落の中に出た。 「喫茶ヤシの木」でトロピカルなかき氷とトロピカルなジュースでほてった体をクールダウン。さとうきび畑に囲まれた「シュガーロード」がヤマハのリゾート施設はいむるぶしの方面にむかってまっすぐに伸びている。 もう、坂を登るのは嫌。下り方面にハンドルを向け続けていたら港に戻ってしまった。 チャリを返して船に乗れば25分で石垣島だ。 |

| 藩政時代を経験した街の多くは、駅を発展の中心に据えてはいない。 鉄道は近代の産物であり、街は近世からの資産だからだ。街は城を中心に繁栄した。 戦火を免れた弘前は、藩政時代の旧市街の街割がそのまま残された。 歴史的に若輩の弘前駅は、街の象徴たる弘前城から南東方向へ押しやられており、駅から城までは一直線の道があるが、繁華街である鍛冶町へは城からも駅からも直線進入ができない。城下町特有の構造で何度かの曲折を経ることになる。 頼朝以来の名門南部氏から独立割拠し、津軽を得た大浦為信(後の津軽為信)は秀吉の小田原征伐に参陣し本領安堵のお墨付きを得た。 彼を藩祖とする津軽がその出自の段階から南部と犬猿の仲になってしまったのは仕方がない。 幕末、官軍についた津軽藩に対し南部藩は幕軍に与し敵対した。結果、津軽藩は明治になって藩府の名をそのまま反映した弘前藩に改称され、さらには青森県となって南部領の一部、三戸、八戸を吸収する。中世の建国、近代の維新、時代を超えて両者の不仲は継承されている。 仙台の伊達、秋田の佐竹、米沢の上杉、山形の最上など東北は油断ならない外様ひしめく土地。 津軽為信、彼もまた油断ならない。しかし、南部から独立した立国時の無理は、本拠地、堀越城での家臣の反乱の憂き目を見、新たに堀越の北西約6キロ、岩木川・土淵川を東西の防御線とする高岡(鷹岡)の地に城を築かねばならなくなる。 何事も無理をすれば反動があるわけだが一般人との違いは、少なくともこのての反動に動揺を見せないというところ。創業者はへこたれない。 |
城郭は5万石の藩領に比して広大であり、当初築かれた5層の天守閣など次代になってやっと完成する。新地、高岡それが今の弘前である。 繁栄の中心は北海道との連絡の要衝となった青森に奪われたが、文化の継承は弘前に濃い。 弘前城を中心に、寺社が多い。 最北の五重塔「最勝院五重塔」は釘を1本も使っていない。子供の頃(太平洋戦争後)に駅から引き揚げてきたと土地の人が言う鐘を吊るした鐘楼との重なりが美しい。 弘前大学があるせいか、病院の数も多い。 学生と医者の街でもある。 雪が多く、直江津の雁木のように店の前に張り出しを作り小アーケード化する。これを「こみせ」と呼び、弘前公園に近い下土手町から中土手町、上土手町と続くかつての中心市街地は「こみせ通り」と呼ばれ活気を呈していたそうな。 夜の帳が下り、鍛冶町の一画にある「津軽路弥三郎」の提灯に灯が灯る。 カウンター席は6席程度。 「貝焼きみそ」は、おおぶりのホタテの貝の上でホタテ貝柱、まいたけ、豆腐を味噌ととき卵で焼いたもの。香ばしい香りが鼻腔をくすぐる。 メニューに「きんきん」とあるのは「きんき」のこと。煮付けを頼む。おおぶりのきんきが砂糖をおさえた甘さ控えめの煮汁とともに出てきた。一緒に煮込まれた豆腐が妙に旨い。その旨を伝えると、メニューにはない冷奴を出してくれた。上に納豆が乗っている。これがまた旨い。 「もつ煮込み」と「ウニのみぞれ和え」も酒飲みの心をくすぐる。みちのくの旅の夜の漂泊感を愉しむ筆者であった。 |
沖縄食行(夏への扉 →→→back 96 06(1) 2) 3) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

| 葉月某日(金) 夕刻、那覇着。同行者3名。YとFとN。 首里城を観光。 あまりの暑さに同行の3名、殺気立っている。散歩をもちかけるも、反乱の気配。やめる。 公設市場とマチグワーを散策。「ひゃっきんさん」でストローハットを購入。土地の言葉かと思ったら「百円均一の店」を縮めたダケ。 訪沖初日なので沖縄料理。 三線ライブを見て、踊って、泡盛を楽しむなら国際通りの中ほどにある「波照間」。この店はすべてが揃うし料理も旨い。大箱なれどオススメ。 帰路、Nと「アメリカ食堂」に寄る。テンガロンハットをかぶったゴーヤーのネオンサインがアメリカンである。タコライスとタコスを食べる。 葉月某日(土) 本部(もとぶ)と北部(やんばる)を巡る。 名護の道の駅で宿願のサーターアンダギーを購入したN。ずっと食べている。あろうことかYもサーターアンダギーに染まる。 「美ら海水族館」に入り、人工の海浜「エメラルドビーチ」で紫外線に焼かれる。 昼、今帰仁村の「Ke Iki cafe」へ。Ke Ikiとはハワイの現地語で小さいという意味。眼前の海を眺めながら、ハワイLION社のバニラフレーバーコーヒーをアイスで飲む。この非日常感は厭世感をすら誘う危険なものだ。ドライカレーが旨い。 この店へのアクセスは難度Dである。カーナビを使ってすらNは同行の我々を遭難させかけたこと一再ならず。 北の突端、辺戸岬(へどみさき)まで行き、沖縄ぜんざいを食べる(氷あずきである) 今帰仁城(なきじんぐすく)まで反転。名護に投宿。 夜、名護市街から車で15分ほどの住宅街にある「クチーナ」へ。 魚と島野菜がメインのイタリア料理店。 やがらのカルパッチョやゴーヤを練りこんだぶっとい平麺パスタ、なぜか骨を感じないグルクンなどをワインと共に消費。 グラッパを頼んだときオーナーの顔が耀いた。 |
旅先のイタリアンでたまにある光景。地元の人は頼まないんだろうなぁ。 帰路、「A&D(通称エイダー。地場のハンバーガーショップ)」に寄る。今夜は誰もつきあってくれず孤独に入店。モッツァバーガーとカーリーフライ、ルートビアを頼む。 葉月某日(日) 仕事で帰阪するNを那覇空港までお見送り。 南部の戦跡、泡盛工場、黒糖工場を巡る。 南部の戦跡は重い。ブラックホールなみの重さに一行3名、無口にならざるを得ない。 昼食は糸満市の「真壁ちなー」へ。 築百年以上の赤瓦の民家を改造した沖縄料理屋で、沖縄そば、ジューシー、ラフティー、スンシー、もずく酢、ニガナの白あえなど沖縄食材ひととおりがセットになった「ちなーご膳」を。 冷房のない古民家で足を伸ばし、夏休みに親戚の家に遊びにきた小学生のような気分になる。 「カフェくるくま」で太平洋を一望しながらトロピカルなジュースで喉を潤す。 沖縄市(旧称コザ)で泊。 「BAMBOO CAFE」で夕食。 さすが基地の街。後ろのテーブルにはジャーヘッド(海兵隊)が陣取っている。 ジャークチキンバーガーをメインに、シュリンプカクテル、生春巻き、アボガドと鮪、オニオンリング、カマンベールチーズ春巻き、BBQ(バーベキュー)、タイカレーを食べる。 カクテルは1杯で腹一杯になることうけあいのアメリカンなサイズ。 さすがに今日は、どこにも寄らずホテルへ。 葉月某日(月) 朝、スパムおにぎり2個(ポーク玉子とタコス)をコンビニで。ちと胸焼けの気味あり。 残波岬を巡り、人生初ダイビング。 那覇に帰り、夜「ジャッキーステーキハウス」にて250gのテンダーロインステーキとスープ、パン。タコスは3人でシェアする。 帰路、国際通りの端にある「龍譚」でソーミンチャンプルー、海ぶどう、ポーポーアイス。カクテルを3杯。 |

| 関ヶ原の役の後、常陸(水戸)54万石から20万石に減封され、移封された佐竹氏は藩府を窪田に定めた。窪田が転じて久保田。主城は久保田城となる。近接した土崎港は、北前舟の寄港地として栄え、行政、経済の両面から街は発展し、秋田市となった。 城下はJR秋田駅の西側に広がっている。 城跡の千秋公園西側に外堀の役割を果たす旭川が流れ、この川むこうが「川反通(かわばたどおり)」と呼ばれる東北でも有数の歓楽街を形成している。 川反通の中ほどに大正7年創業の数奇屋造りの店がある。玄関前の塀に「濱乃屋」の屋号がポツンと耀いている。 「濱乃家」は土地の家庭料理であった「きりたんぽ」や「しょっつる」を郷土料理として初めて供した料亭として知られているそうな。 風情のある料亭に一人で入るのも躊躇われる。何より座敷が苦手な筆者である。料亭の隣にある別館なら単品の注文も聞いてもらえるとのことで気軽に郷土料理を愉しむことにした。 「きりたんぽコース」と「しょっつる貝焼コース」の2コースが目についた。しかし、コースについてくるお造りやら焼き物など、余分なものはいらない。「きりたんぽ鍋」と「しょっつる貝焼」を肴に飲みたいのだ。 その旨お女中に伝える。お女中が問い掛ける。 「お客さん、大食い?」 「そうだ」と胸を張ればIQが疑われる。 「違う」と答えた。 「じゃあ、しょっつる食べてから、きりたんぽに進む?」 |
秋田出身の東京オフィスのNさんと同じイントネーションだ。心の中でくすりと笑う。 東北のラテン気質。秋田は明るい土地柄だ。 「しょっつる貝焼」はハタハタがメインの料理。しょっつるは魚醤のことである。これになすだのしいたけだのせりだの細筍だのを一緒に煮る。 秋田ではとにかくせりを使う。何がなくともせり。細筍は名前のとおり細身の筍である。 「しょっつる貝焼」なのに鍋で供された。 「貝でもできるんだけど、すぐに煮詰まって焦げちゃうから鍋の方がいいですよ」 Nさんと同じイントネーションで言われれば「貝で!」とは言えない。旨いし、いいか。 ハタハタは身がぷりぷりとしている。ただし小骨が多い。「お客さん、食べるの旨い」と言われれ、木に登る筆者。 酒にあうのであっと言う間に鍋が片付いた。日本酒は、新政と飛良泉。次は「きりたんぽ」だ。 「ウチのきりたんぽはご飯3杯分ですよぉ」と言われた鍋も案ずるよりは食うが易し。完食。 「大食い」の烙印を押され、店を出た。 川反通の老舗バー「Lady」に入る。 冬期限定の突き出しは「ビーフシチュー」 (もう、食えんて、ホンマ) カクテルが旨い。テキーラベースのカクテルを3杯。強すぎず、辛すぎず、フルーツの甘味が実にさりげなくスピリッツと調和している。どのグラスも筆者の好きなタイプだった。 (いい土産ができた) 空になったグラスをカウンターに置き、ほろ酔い気分でドアを開ける。 いつの間にか雪が舞いはじめていた。 |

| 1日7回! 個人史を塗り替える記録を達成した。 何の回数か? いろいろな思惑もおありでしょうが、まず読者諸氏の想像の埒外であることは間違いない。 雪上における転倒回数である。 昼夜2回の外出時、凍結した雪上で転げまわった回数、それが7回。無念である。 生命体として生存の危機を感じた。筆者は直立歩行が苦手なのか?自己嫌悪にすら苛まされた。腰が痛むわ、手の平はすりむけるわ、首筋がおかしくなるわ。満身創痍の我が身。 11年ぶりに大阪が5センチの積雪に覆われたその日、筆者は27年ぶりの弘前にいた。 その日弘前では、みちのく5大雪祭りのひとつ「弘前城雪灯篭まつり」が開かれている。 他の四つは、秋田の「横手かまくら」同県男鹿の「なまはげ柴灯まつり」「八戸えんぶり」雫石町の「岩手雪まつり」である。 弘前の雪祭りは1977年から31年間続いている。 27年ぶりだが駅前から弘前城へむかう道筋はおぼろに覚えている。なにせ1本道なのだ。間違いようもない。陽が沈む前に偵察をかねて弘前城へ向かう。 駅前では除雪された雪が壁のように聳えている。誰の家の前と明確に判定できぬ歩道の除雪はおざなりだ。雪が残っている。 徒歩30分弱で弘前城に辿り着く。 現存する12天守のうち最北端のそれは3層3階で小ぶりである。当初5層あった天守閣が焼失し、櫓を移築し天守にしたものである。天守よりも3重の堀によって守られた城域こそが往時の威風 |
を偲ばせる。本丸裏手から見る津軽の象徴「岩木山」は、頭頂部に雲を戴き、全容を窺うことができない。 夜の点燈に備えて雪灯篭やミニかまくらが並んでいる。 城内は、一面の銀世界である。東門から入り、追手門を抜けるまで、足を滑らせ5回転倒した。 夜、雪灯篭の灯火頃、宿を出て再び弘前城へ。 (もう二度と転ぶまじ!) 筆者の覚悟は固い。重心を落とし、一歩、一歩慎重に体重を移動する。 交差点で前方から歩いてきた女性と進路が交錯しそうになった。進路を変えようとしたとたん、足を滑らせ転倒した。 (□●※▽※!!) 冒涜的な言葉が口をつく。神様ごめんなさい。 「大丈夫ですか」 今日、6回目のいたわりをうける。 「ありがとう、大丈夫です」 6回目の返事を返す。 悔しいっ!あまりの悔しさに涙が滲み視界がぼやけてきた。危険である。 城内に入り、雪灯篭やライトアップされた天守や門を眺める。しかし、心ここにあらず。想いはひとつである。 (絶対に二度と転ばないのだ!) 足元を見つめ、手を固く握りしめ、ヨチヨチと歩く筆者。次々と人々に抜かれてゆく。老人にさえ抜かれる。悔しさもひとしお。 追手門を出れば、城域脱出だ。 (やった!もうすぐだ!) 気が緩んだ瞬間、転倒。 |



| 夏に来れば、沖縄の海に劣らぬ青さを見せたかもしれない島武意海岸。その海の青さをシャコタンブルーと呼んでいるらしい。 岩礁が顔を出し、冬のオホーツクの波頭が叩きつけるようにそれらを洗っている今、シャコタンブルーは冷たく青ざめた海の色となっている。 神威岬にむかう。 積丹でも11月の降雪はめずらしいと言う。ただし、この雪はまだ内地の雪だとのこと。道路上に雪団子が転がっている。雪が水分を含んでいるせいで固まりやすいのだ。パウダースノーなら雪団子はできない。雪合戦ができない雪、それが北海道の本当の雪。 岬への峠道が閉鎖されていたらごめんなさいとのことだったが、なんとか道は通じていた。 駐車場に車を止め、岬にむかって丘を登る。 神威岬は、海に向かって身をよじらせつつ沈みこもうとする海獣のようである。 その海獣の背を岬の先端まで一本道が続いている。鳥居のような門をくぐってその道を行けるのは男子のみである。 女人禁制の岬だが、今日は強風のため男子も禁制になってしまった。風に煽られ、断崖から滑落しかねない突風が吹いている。 帰路、羅臼で漁師をやっていたタクシーの運転手氏から、根室方面での漁業の実際を聞く。 漁場は拿捕との戦いだったと言う。 日本漁船は、夜間に侵犯するらしい。なにせ、いい漁場はすべて向こう側にあるのだ。先方も船舶が集団だと拿捕しない。彼等は船団からはずれた船を狙っている。機嫌が悪ければ撃ってくることもあると言うが本当なのか? 船員は皆、出港の際、缶ピースとストッキングを持ってゆけと言われる。拿捕された際の鼻薬に有効だと船員間の言い習わしなのだと。 夜、小樽に宿をとる。 夕景の運河は雪をかぶり幻想的な景色である。廃線となった「手宮線」の線路を残し、散策路としている行政のセンスもいい。 小樽に行ったら「なると」の「ざんぎ」を必ず食べると、別れ際、タクシーの運転手氏が言って |
いた。「ざんぎ」とは北海道の方言で鳥カラのことである。「なると」は寿司屋だ。寿司屋の鳥カラが名物とは、こだわりのない土地のようだ。 M寿司に行った。 温泉旅館のように大きなビル。予約を入れて訪れたが店内に入っても、かまわれることがない。しばらく待ったが、案内にも来ない。こりゃ駄目だとこちらから声をかける。 カウンターに案内される。 ラミネート加工のメニューが渡された。カウンターの握り方と馴染みながらなどと考えてはいけなそうだ。それならそうと、こちらも心構えを切り替える。要は魚の旨い高級居酒屋と心得ればいいのだ。目もくれなかったメニューを引き寄せ、吟味する。いけそうなものがあるではないか。 「中トロのざんぎ」と「もずく酢」を頼む。 寿司屋なのでまぐろを揚げるのか。見れば、鳥のざんぎもメニューにあった。中トロのざんぎが脂がのって揚げ具合も絶妙。おほ、いけるがな。 「もずく酢」も筆者好み。 「いかそうめん」は、いかの上にうにが乗っている。タレには玉子の黄身が浮いている。 「うにをそのタレに入れて、黄身と一緒にかきまぜてから、いかをつけて食べてください」 言われたとおりに試みる。おほ、旨いがな。 当初体中から発散していたであろう(なんじゃこの店)オーラは完全に消え去った。そうした空気はおのずから伝わるものだ。板前だって人間である。握ってもらおうとしたら「おまかせ握り」という名の皿盛り寿司ではなく、1貫ずつ握ってくれることになった。 ぼたんえび・ひらめのえんがわ・きんき(炙って塩で、旨いよ)・うに・けんさきいか・たらのこぶ締め・けいじ(これが狙いだったのだ)・王助(おうすけ…襟裳産のサーモン)・あわび(香りがいい!)・中トロと海水うにの手巻き(旨いがな)・玉子焼き。 ガリの新ショウガはちょっとあたりが強すぎる 岩海苔の味噌汁で締めた。支払いは「すし膳」の三分の一。これはこれでありだな。 |



| 二十四節季の「小雪」の朝、目覚めたときには街は一面雪化粧の世界。 水分の少ない、まさにパウダースノーをサクサクと音を立てながら、踏みしめ踏みしめ駅にむかう。しかし札幌駅前でさっそくヒトコロビ。 肩に下げたバックの上から倒れこむ。ニードロップ気味にバッグに肘をいれてしまった。 (パソコンが!) あたふたとバッグからパソコンを取り出す。 なんとか起動した。 神威岬でも、足をすべらせ転びかけた。 (ふん!) 目一杯腿に力を入れ、転倒は避けられた。しかし、踏ん張りのため筋肉が強張った。 ぴき。 転んだ方がよかったのか。 余市の駅前でフタコロビ目。 腰をしたたかに打った。 このままでは寝たきり中年になりかねん。 旭川の人は厳寒期、マイナス20度、30度の世界で過ごす。札幌あたりのマイナス3度、5度の気温は「暖かい」と言われるレベルらしい。 しかし、厳冬地の冬は体感しなければわからない。長袖のTシャツにハイネックのセーター、ジャケットに厚めのハーフコート、マフラーと手袋で真冬日に臨んだ筆者。氷点下でも、5度程度までなら、これでほぼ大丈夫だが、風が吹くともういけん。フード付のコートが必要だと悟った。靴下も薄手じゃ駄目だ。ズボンも厚手がいい。(ただし筆者は股引は履かない。絶対に) この日、札幌から函館本線で東に向かった。 小樽行きの各駅停車は「あさり」「ぜにばこ」 |
間でロングシートの通勤列車仕様にそぐわない絶景を車窓に映し出す。 海岸線は鉄路の至近に迫り、海の上を走っているかのようだ。 浜にうちつける波は人の営みにあまり好意を寄せているとは思えない。重力に逆らえず、高さの頂点から白く砕ける波頭はその悔しさを籠めるかのように風に煽られた白い飛沫を後方に飛ばす。 鉛色の空と海。その境目は、ただ海の鉛色が少し濃いというだけによって隔てられているにすぎない。 小樽から乗り継ぎで倶知安行きの各駅に乗る。 余市で降車。 日本で初のウィスキー蒸留所を作った竹鶴政孝氏のニッカ工場がある。氏は当初、鳥井信治郎氏に請われ、京都山崎のサントリー蒸留所を設計した。イギリスのように寒冷地に建てたかった工場はサントリーの現実感覚の前に妥協を余儀なくされ、その後、自身の夢を余市に編んだのである。 余市には毛利守館長の宇宙記念館もある。 筆者はタクシーと交渉し、積丹半島に向かう。 海岸線を走る道道229号線はかつてトンネル内の崩落でバスと四駆を巻き込み20名の死者を出したいわくつきの路線だ。96年のことである。事故の教訓からトンネル新設が続いており、今も継続中だ。途中、幾つも旧道のトンネルが閉鎖されていた。 運転手氏のお奨め絶景ポイント島武意海岸に寄る。暗い、小さなトンネルを抜けると、眼前から地面が消え、展望台に踊り出たような錯覚を覚えた。眼下に日本の渚百選に選ばれた岩礁を散りばめた海岸線が広がっている。 |




| 瀬戸内海をチャリで渡る。 広島の尾道から愛媛の今治まで。中国から四国へ、自転車で海を渡ることができるのである。 本四連絡橋と言えば「明石海峡大橋」や「瀬戸大橋」の名が喧しいが、この2本の橋は自転車の通行を禁止している。「しまなみ海道」と呼ばれる尾道から今治へ抜けるルートのみが自転車の通行が許されているのである。総延長80キロ。日本初、海峡横断、大規模自転車道。それが「瀬戸内海横断自転車道」である。 師走の一日、尾道へ行き、レンタサイクルを借りた。 駅前を走る国道2号線ぞいの駐車場の西端にレンタサイクルがある。行楽日和なら知らず、初冬の日曜日に客の姿はない。MTBも3段変則のママチャリも電動自転車もお好みのままだ。MTBを選んだ。荷物は駅前のコインロッカーへ。 チャリは、1500円で借りられる。借りた場所に返せば、保証金の1000円が返還される。 中国尾道と四国今治の間には、向島・因島・生口島・大三島・伯方島・大島の6島が浮かんでいる。尾道から向島にはチャリで渡れる橋がないので船に乗る。2社が競合しており、片道70円と110円で指呼の距離の対岸につける。 向島から先はすべて架橋されている。因島大橋3.4キロ・生口橋3.0キロ・多々羅大橋4.2キロ・大三島橋0.5キロ・伯方大島大橋2.6キロ・来島海峡大橋6.2キロだ。 今日は偵察目的だから、完走の意思は無い。夕方には大阪に帰りたいと思う筆者に覚悟はない。多島の瀬戸内海を眺めながらの走行は爽快だ。島の斜面にはオレンジ色のみかんが成り後背の山々 |
の紅葉と暖色の調和を織り成す。小さな漁港は磯臭さに満ち、観光よりも日常生活の気配をこそ濃厚に感じ取る。 10時半に尾道を出て、12時までに3つ目の生口島(いくちじま)まで渡れるだろうと考えた。その距離約24キロ。そこで引き返し2時前に尾道に帰ってくる。そんな計画だった。 途中、慢心から道を失った。こまめに地図と現地を見比べながら走らなかったためだ。サイクリングコースに復帰するまで若干の迷走。 さらに計算違いは各島に峠越えがあること。小さなアップダウンもけっこうある。最大の誤算は海にかかる橋の高さを考えていなかったこと。因島大橋にのるのに海抜50メートルの高さまで登坂しなければならなかった。息があがった。MTBにしてよかった。ギアが軽くて上りきれるのだ。 タイヤの空気をパンパンに入れず、接地面積の多いMTBは平地でとばすには無理があることも体験しなければわからんかったことである。やはり人生は体験と勉強だ。 そんなこんなで生口橋を渡り終わったところで12時半になってしまった。躊躇わずにUターンである。帰路、足にきた。と言うよりも膝にきた。膝が痛い。さらに追い討ちをかけるように尻が痛みはじめた。筆者のチャリのサドルは中央に穴のあいた長距離用だ。あれは男子の一物を圧迫しない前立腺に優しい構造なのだ。今回やられた。尾道に帰りトイレで小用を足そうとしたら、尿道結石が詰まったような激痛。血が出たかと思った。 (これか!これがサドル禍なのか!) 次回への教訓を得た。今治まで本格的に進攻するためにはマイサドルを持ち歩かねばならんな。 |

| 石垣島のビーチホテルのテラスから海を眺めると、船着場とその付属施設の赤い屋根までが視認できるほど近くに竹富島が浮かんでいる。 竹富島の背後には小浜島、さらにその奥に西表島の山岳部が見える。 石垣島と八重山の島々を結ぶ渡航船の往来は喧しい。竹富島への便は30分ごとに発着している。 バスに乗って隣町に行く感覚に似ている。 ポーチにカメラと文庫本を投げ込みブラリと船に飛び乗った。 石垣港から竹富島までは10分。信じられないほど鮮やかなエメラルドグリーンに染まった海を走り抜け、高速船はアッと言う間に竹富島の桟橋に横付けされる。 筆者は運動不足解消も兼ねてレンタサイクルにまたがるつもりで島に来た。しかし桟橋の近辺にそれらしい店はない。何台かのワゴンが停まっているだけだ。それぞれのワゴンの前には客引きの姿があった。島の中央部にある集落までワゴンで5分、レンタサイクルは集落内で借りることになるらしい。レンタサイクルの出張客引きワゴンだったのだ。予約もしていないが、問題はない。目に付いたワゴンに乗り込み、集落へ向かう。 レンタサイクルは純正のママチャリである。変速機はついていない。島は高低差のないフラットな環境だ。変速機は必要ないだろう。 島内観光は牛車かチャリの二者択一である。 (あ、徒歩もあるか) 遠くから牛車が近づいてきた。牛車の歩みは流石に遅い。まさに牛歩。これは乗るものではなく見るものだと瞬間的に頓悟する。 チャリを借り、あてどもなくペダルをこぎはじ |
める。背丈よりも高い夏草の中を白い道が夏への扉のように、いずことも知れぬ世界へと誘っている。島時間が流れていた。 赤い屋根とサンゴできた石垣の乾いた灰白色の壁、強烈な日差しの下でそれらが時の流れを包み込み、体内で消化してしまうかのように溶かしてゆく。 コッチン・・コッチン・・・メトロノームの針の振れがどんどん緩やかになってゆくようだ。 都市生活に順応していた体内時計がデジタル表示から、アナログ表示へ、さらに振り子時計へと姿を変えてゆく。振り子時計は砂時計となり、とうとう日時計にまでなり、筆者は時間を追うことをやめた。同時に時間に追われることからも解放された。腕時計をはずしポケットに押し込みたくなるような感覚である。 草木に覆われたトンネルのむこうに白い光の入口がある。くぐりぬければいつかどこかで見た沖縄の静かなビーチが広がっている。 「ハブクラゲに注意!」という看板が目にとまった。ハブクラゲ・・・聞くだに危険な名だ。 看板の下にハブクラゲに刺された場合の対処法が書いてある。 「呼吸や心臓が止まったとき・・・」 ・・・かなり危険な奴である。 水飲み場の流しにはヤモリの姿。のどかだ。 夢のような島だが、昼食時ともなると島のあちこちに散った観光客が飲食店を求めて集まってくる。結局のところ、夢を見ているのは自分ひとりではないということに気付かされるわけだが、その事実をつきつけられてそうかと膝を手で打ち頓悟するには筆者はまだ若すぎる。 |

札幌行2 →→→back 札幌行1 2 3 4 5 6 7 8 9

| 5時間で完了する札幌観光を敢行した。 ホテルを出て大通り公園に向かう。 今夜から始まるホワイトイルミネーションとミュンヘンクリスマス市の会場設営が最終調整段階のようだ。夜にまた来ようとスバヤク決断。 札幌観光は「札幌テレビ塔」に登るところから始まらねばならない。 札幌の街区は、テレビ塔を境に東西に分けられる。南北の境は大通公園である。公園を挟んで反行しあう東行きの北大通り、西行きの南大通り、この2本を境に北と南が分かれている。 南北の1ブロックを「条」、東西を「丁」で表示する住所表示は明快である。例えば札幌グランドホテルは北2条西4丁目の交差点の南西面にある。北大通りから北に2本目、テレビ塔から西に4本目の街路の交差点ということだ。札幌駅は北6、西2~3、すすきのは、南4西4の交差点の南側である。 「札幌テレビ塔」の次は「時計台」に向かう。観光名所だから人も多い。筆者は南に向かって歩き始めた。市電二条駅を通過。さらに2ブロック南進すると市電すすきの駅に至る。 札幌の市電はすすきのから南下し西進し北上して東進し、市内を巡回するように二条駅に帰ってくる。つなげてしまえば環状線になるのだが。 竹のささらで除雪する「ささら電車」はこの路線を走る。 ラーメン横丁に立ち寄り「弟子屈」のチャーシュー味噌ラーメンを食べる。縮れた黄色い太麺に味噌味、これこそが札幌ラーメンという刷り込みは筆者の世代ならば納得していただけるはず。 市電に乗り、ロープウェイ入口駅に向かう。 藻岩山からの眺望は札幌の自慢である。特に夜 |
景がいいらしい。しかし、この日ロープウェイは整備期間中のため運行を停止していた。通りすがりのタクシーに山頂までゆけるかと問えば、昨日の雪で通行止めとのこと。 計画修正を余儀なくされ、大倉山に向かった。 スキーのジャンプ競技で有名なあの大倉山である。札幌のほぼ西方、大通り公園の延長線上にある大倉山は、うっすらと雪をまとっていた。 寒い。気温は無論、氷点下である。 リフトが動いていたのでジャンプ台の頂上まで上る。リフトの手すりは、皮膚がくっついて剥がれるかもしれないほど冷やされている。 あまりの寒さにデジカメが動作不良を起こしかけた。しばしポケットに収めてなで続ける。 すばらしい眺望だ。しかし、こんなところから滑り降りるなんて狂気の沙汰である。しかも途中で滑走面は途切れるのである(当たり前か)。 市内に戻り、赤レンガの北海道庁旧本庁舎を見て、昼の観光は終了である。 夜、すでに寿司も食べたしラーメンも食べた。 残りはジンギスカンだろうとすすきのの繁華街から2ブロック西にあるビニールで覆われた簡易建築の店「さっぽろジンギスカン本店」へ向かう。レアで食べられるラム肉との謳い文句に偽りはない。脂身が丁寧に剥がされた新鮮なラムは臭みがまったくない。北海道民は嬉しいことがあるとジンギスカン。哀しいことがあるとジンギスカン。何はなくともジンギスカンなのである。 帰りがけにホワイトイルミネーションを眺め、ミュンヘンクリスマス市で「エゾ鹿バーガー」を食べる。焼きリンゴが載せられ、それなりに食べられた。ま、縁起物ということで、ひとつ。 |

札幌行1 →→→back 札幌行1 2 3 4 5 6 7 8 9
| 札幌は3回目だ。ただし19年ぶり。 別れたカミさんと来たのが20年前。それが始めての札幌だった。 新婚旅行だった。 当時カミさんは競技社交ダンスの選手だった。 1日休めば感覚を取り戻すのに3日はかかる。1週間休めば1ヶ月を失うとまったく乗り気でなかった彼女を会社の慶事有給休暇を使用できるチャンスはそう多くはないのだからと無理やり引っ張り出したのが真相だ。 思えば若かった。自分勝手なものである。彼女の気持ちなど一顧だにしていなかった。 今の筆者ならば 「それはいけない。練習を続けなさい。私はひとりで行くから」 心の底からの真心を込めて言えたことだろう。 そんなこんなでこの紀行への登場が遅れていた札幌。しかし、人は時として過去と向き合わなければいけないこともある。トラウマがあったわけではないがなぜか触れずにいた土地札幌に筆者は向かった。 ところが、旅の出鼻をくじくかのように、エアが機材の遅れで1時間延着。空港で無為の時間を過ごす。 新千歳に着けば今度は空港から札幌にむかうJR快速エアポート号が踏み切り事故で15分の延着。 しかも着いた札幌は、氷点下4度の真冬日。 11月下旬には珍しいという真冬日がすでに3日目らしい。市内は雪がうっすらと積もっている。 流石は鬼門筋の札幌。すべてが悪いほう悪いほうへと転がってゆく。この負の連鎖を食い止めることができるのだろうか。 |
今日はすでに予定を決めている。 寿司を食うのだ。 過去を断ち切りたければガツンとした思い出を作ればいい。先般、宮崎で思い出作りに失敗した筆者は、今日は心に期するものがあった。 「すし膳本店」。 そこが今日のメインイベンターだ。 頼むぞ。厄を祓ってくれい。 予約時間ちょうどに店内に入る。いきなり大量の席待ち行列が筆者の前に立ちはだかった。 こちらは予約を入れているのだ。人をかきわけかきわけ、受付に進み、来店を告げる。 「すいません今日は、チャレンジデーなので」 応対に出た女性が言った。 (何をチャレンジしているのかは聞かなかった) テーブル席主体で騒然とした店内に違和感を覚える。カジュアルである。かなり不安だ。 彼女が電話をかけている。 しばらくの後、迎えが来た。 なるほど店は幾つかの棟に別れているらしい。 案内された店舗はいかにもの雰囲気のすがすがしい寿司屋の佇まいだ。背筋が伸びた。 広いカウンターのみで完成度の高さが伺える。 ゆったりした寛ぎとともに寿司、酒、肴を堪能し、心満たされて店を出ることができた。 握り方がお女中とともに店の外まで見送りに出てくれたのに気付いたのはタクシーに乗ってからだった。いけん。残心を忘れていた。 気持ちのいい店だ。 値段は金沢・博多の2倍。ほぼ銀座並かそれよりちょっと安いというところ。しかしながら、筆者の札幌を復活させた1日となった。 |
| 筆者はこれまで宮崎を空費していた。 いつも立ち寄るだけで泊まったことがない。今回は宿泊予定を立てて訪問した。にもかかわらず今回もまた失敗。酒を抜いたのがいけなかった。 ガツンとした満足をたったひとつ。それだけでその土地への思い入れが生まれる。そうすれば再訪の意欲も高まり、再訪によりさらにガツン物件が増えるという筆者の成功スパイラルの法則を踏み外した。この失敗は後日必ずとりかえす。 フェニックスが高々と並ぶメインストリートぞいに繁華街が広がっている。繁華街だが自転車専用レーンが歩道端にある。無論、自転車は歩道をも疾走するので安閑と歩いてはいられない。 繁華街には小路が多い。この街は金沢片町界隈に似ている。 宮崎と言えば、チキン南蛮だ。 鳥モモ肉をカリッと揚げて、甘辛のタレに浸したあとタルタルソースを添えて食べる。長崎の魚の南蛮漬けにヒントを得て作られたというこの街発祥の名物料理は、やはり、発祥の店で食べねばなるまい。 「おぐら本店」は、ローカル百貨店「山形屋」の細い路地裏にある。メニューには「おぐらで生まれて45年」と書かれたチキン南蛮が950円。 チキン南蛮は若者の食べ物である。ヴォリュームがありすぎる。食後、案の定何も入らなくなってしまった。やむをえない。フルーツに逃げた。宮崎と言えば南国のフルーツである。 歓楽街の一角に「フルーツ大野」がある。「トロピカルパフェ」をオーダー。出てきたパフェはすごかった。 (もー食えん) |
はちきれんばかりの腹をさすり、市内を徘徊。 麺は緩いが人気は高いうどん屋「重之井」を訪れるもすでに閉まっていた。その日の麺がなくなると閉まるようだが、いかんせん早過ぎないか?まだ7時だ。 (どげんかせんといかん) 完全な不完全燃焼状態。 しかし、この日筆者はとことん運から見放されていた。せめて鶏で酒をと探し出した「ぐんけい隠蔵」も閉店まで予約で埋まっていると言う。 トボトボと帰った。 翌日、宮崎空港の「魚山亭」で「チキン南蛮」(まだ食うのか?)と「冷汁」を食べる。チキン南蛮を頼むことはもうないだろう。旨いが筆者は降りた。そのかわり「冷汁」だ。魚をすり潰し、味噌とあわせ、豆腐、きゅうりなどと一緒に麦飯にぶっかけて食べる宮崎の郷土料理である。 洋食の「ADEN」、「地鶏屋修ちゃん」、元祖レタス巻きの「一平寿司」・・・超弩級ではないがクルーザー級の期待は持てそうな店がまだまだ残っている。宮崎は伊勢えびの産地としても有名らしい。「いせえびソフトクリーム」や「青島イセエビもなか」も一度は食べてみたい物件である。次回こそは・・・。 宮崎空港にむかうローカル線にJR九州の特急「みどり」や「かもめ」に使われている車両が運用されていた。指定席と書かれた車両に座ってもいいのだろうか?マニアではないのでわからん。グリーン車両に入ってもいいのだろうか?マニアではないので見当もつかん。車掌に聞いてみた。 「指定席車両も自由に座ってよかですよ。グリーン車は座れんけん」とのことでした。 |

| チュニジアのキャサリン山道にむかう2台のジープがあった。 北アフリカ戦線US第2軍に着任したパットンと副官のブラッドリーの乗るジープだ。 途中パットンは道を右に逸れるよう指示する。 向った先に遺跡があった。 パットンは車を留め、遺跡に足を踏み入れ、そしてつぶやいた。 「ここが戦場だった」 膝を地につけ祈るように目をつぶった。 「市を守るカルタゴ軍は、三方からローマ軍に襲われた。彼らは勇敢に戦ったが惨敗した」 背後のブラッドリーに振り返った。 「2000年前だ。わしもいた」 映画「パットン」のワンシーンである。 堺の街はなぜかこのシークエンスを筆者に思い出させる。 カルタゴと堺。 栄華と衰退、あるいは滅亡。 筆者の中ではふたつの街がひとつに重なり詩の海に漂っている。 安土桃山の昔「東洋のベニス」とまで謳われ、その財力は明らかに一都市の範疇を越え、街は世界に開かれていた。三方を環濠に守られ、ひとたび街中に入れば敵同士と言えども休戦のよしみを結ぶ。傭兵に守られた豪商たちの自治都市。 筆者の脳裏に浮かぶ堺はどこまでも明るい。 カルタゴは滅んだが、堺は今なおここにある。ただしその落剥感は筋金いりである。それでもいいではないか。生きてここにあるだけでも幸いやないか。そんな堺商人のつぶやきが聞こえてもきそうである。 |
「ものの始まりは何でも堺」と言われる。 街の歴史は古い。 仁徳天皇陵に代表される百舌鳥古墳群は堺にある。仁徳天皇陵と言えば、クフ王のピラミッド、始皇帝陵と並ぶ世界3大墳墓のひとつである。 古墳を見下ろす高層建築がないので、この巨大な前方後円墳の全景を捉えることはできない。伊丹空港へランディングアプローチを開始するエアの機窓からしか窺い知ることができないのは、何かしら「もったいない」ことではある。 千宗易、今井宗久、今井宗薫、小西隆佐、津田宗及、能登屋平久、日比屋了慶・・・堺の豪商達が作り上げたギルド、会合衆は時の権力者と虚虚実実の駆け引きを繰り広げる。なにやら大阪よりも大阪っぽい世界ではないか。今でこそ大阪のベッドタウンと化してしまったが、堺は大阪の先輩格の都市である。 千宗易(利休)の屋敷あとはチンチン電車の走る目抜き通り裏にひっそりと囲われていた。 日本史に屹立する希代の茶人の屋敷跡としてはいかにもそっけない。遺跡と呼ぶこともどうかと思われる手のかけられなさである。いやむしろいっそこの方が風情があるのかもしれぬ。利休坊主だって一筋縄ではいかぬのだ。 海浜に向った。 海を見るのだ。貿易都市堺に来たら海を見なければならない。 日本最古の木造灯台が湾岸線の高架下に残されていた。明治に入っての建造物だが、コンビナートと化した堺泉北港を背景にまるでタイムスリップをおこしたかのような時空のゆらぎを感じる空間がそこにあった。 |

画像左から仁徳天皇陵の濠・阪堺電軌鉄道(チンチン電車)・千利休屋敷跡・日本最古の灯台・堺事件の碑と天誅組の上陸碑
石垣島行(3) →back (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

| 石垣港沖に何隻ものクリアランス船が碇を下ろしている。 通関手続きだけを行い、第3国経由で往き来する貿易船をクリアランス船と呼ぶ。台湾船籍の船だ。大陸(上海)に行くのだと言う。 政治上、台湾船が中国へ直接入港することはできない。国際港である石垣島に立ち寄り沖合いで通関手続きをして大陸にむかう。日本からの積荷ということになるらしい。島にも排水量の総トン数に応じた税金が国から降りてくる。 経済は政治の枠を越えて成長を求める。ジュラシックパークの恐竜のようなものだ。 石垣島は翼をたたんだアヒルを上から見下ろしたような形をしている。石垣港や石垣市街はあひるの尻の部分にある。そこから左右に胴体が膨れ上がる。島の全周は、およそ130キロ。この日、西回りに島を巡ることにした。 市街を出るあたりに電信屋がある。電信局の遺跡である。石垣の電信施設の設置は明治30年。 日露戦争の日本海海戦前、北上するロシア艦隊を宮古島の島民が発見した。宮古島には電信局がない。唯一、電信のある石垣島へ5人の漁師がクリ舟(サバニ)で160キロの距離を一昼夜かけて漕ぎ渡った。司馬遼太郎氏の「坂の上の雲」の読者は思い出されるかもしれない。 電信屋の先には御神崎(おがんざき)がある。東シナ海にむかってアヒルの左翼の下から足ツメが2本、はみだしたように突出している。その一本のツメの先端にあたる。 断崖が真っ青な海に落ち込み、白い灯台が空と海の青と絶妙なコントラストを演出している。 ここは島の西端だ。 |
石垣島には3つの灯台がある。御神崎と平久保崎(ひらくぼざき)、冨崎の灯台である。冨崎灯台は市街に近い観音崎にある。その周辺は観光スポットだ。平久保崎はアヒルの頭の先、島の最北端にある。岩礁で彩られた御神崎と違い、なだらかな牧草地が海になだれこむどかな光景が広がっている。 話を急ぎすぎた。御神崎に戻ろう。 胴体の下から突き出した2本のツメの片方は川平(かびら)と呼ばれるエリアである。 北側に深く湾入した部分が川平湾である。黒真珠の産地であると同時に白い砂浜、透明な水、緑なす周囲の陸地が国指定名勝地に選ばれている。これは全国に8箇所しかないらしい。 島の西岸を海岸沿いに79号線が走る。 アヒルの頭部にむかう喉首は細い。まさにキュッと締めたくなるような細さだが、この東岸に玉取崎展望台がある。ここから北を眺めれば、右手に太平洋、左手に東シナ海が一望できる。のど首は幅300メートル。船越(ふなくやー)と呼ばれている。太平洋と東シナ海を船で往還するのに北部の平久保崎へ大きく回るよりも陸地に船を担ぎ上げて運んでしまった方が早い。船が陸を越える。それで「船越」である。 船越を越えて206号線を最北端、平久保崎にむかう。途中、島田伸介の店がある。手術糸よりも細い1本の糸が筆者から伸介につながっているためか、思わず食いついてしまった筆者。 平久保崎のそばにプライベートビーチのように人知れずひっそりと広がる砂浜に運転手氏が案内してくれた。そこは、時の流れがとまってしまったかのような静かな空間が広がっていた。 |

| 壱岐、郷ノ浦町「三益寿司」の料理は鄙に似合わずどこかに華がある。 「お造り」のアラ(クエ)の身の締まっていること。口中でぷしぷし歯を押し返してくる。カツオの腹トロの炙りとカンパチも新鮮で旨い。 下敷きの塩から焔をゆらめかせながら「あわびのバター焼き」が現れた。 一口サイズに切り分けられたあわびとこんがりと炙られた肝。バターとの相性もいい。殻に残ったバターが何とももったいない。飯にかけたら旨そうだとしみじみと見つめていると、あわびの殻の内側にこすりつけるように酢飯が仕込まれていることに気がついた。箸でこそげながら食べる。バターとあわびの旨みを吸って絶妙な味わいだ。 も~たまらん。 「生ビールをください」 冷凍庫で冷やされ、霜をまとったグラスが見た目も涼やかに現れる。咽の奥が鳴るのを止めることはもはやできない。 「さざえのツボ焼き」は甘めのつゆの中に刻まれたさざえがコリッと身を浸している。 そして締めのうに丼。 北海道のうに丼のように丼に溢れんばかりのうにという訳ではない。うには飯の量に比して若干控えめだ。 「うにがつぶれるくらいぐちゃぐちゃにかき混ぜてください」 大将のすすめに従う。 うに丼がうに飯と化す。 いいのか?これで?と若干の疑惑を抱きつつ口に掻きこむ。 旨い。 |
タレにも工夫があるのだろう。ウニの甘味が口の中でふんわりと広がった。こんなに優しいウニ飯、いやうに丼は始めてである。 満喫して店を出る。 静かな商店街にしのつくような雨。商店街の一角でビニール傘を求める。なんと210円也。 芦辺港にむかうためタクシーを頼み、ついでに壱岐のシンボル「猿岩」に寄ってもらう。 そっぽをむいた猿(運転手氏に言わせるとゴリラ)のような形の猿岩は短い、なだらかな草地の先に東シナ海を背景にそそり立つ。なかなかの景観である。 東洋一を誇った40サンチ沿岸要塞砲跡に寄る。大和の主砲46サンチに若干満たないが、1トンの砲弾を射程35キロまで運ぶ堂々たるものだ。いかんせん時代の主役はすでに海から空に変わっており、この要塞砲が日の目を見ることはなかった。 1級審判の資格を持つ運転手氏は、若鷹会に所属し王監督以下球団広報部長、歴代ホークスの面々とも親交を持つ島の顔役のようだ。時間が許す限り島内の案内をしてくれた。 「鬼の窟」は横穴式住居が古墳となった縄文時代の遺跡である。 ここが発祥という日本最古の月読神社を詣で、元寇の際、2百隻の軍船が襲来した湾を眺める。 島の中央には国分寺があり、さらに島内には温泉まである。ホークスの面々はオフには壱岐に息抜きに来るのだと言う。壱岐の懐深し。 「今度来るときは2,3日前に電話をするとよかよ。釣りにもつれてくけん、また来」 と名刺を頂戴した氏はあちこちの知り合いに手を振り、言葉をかけ埠頭から去っていった。 |
| 「壱州」という名を刻んだ看板や標識が多い。 見慣れぬ呼称だ。 筆者はいま壱岐にいる。 壱岐を地元では壱州(いしゅう)と呼ぶ。 今でこそ長崎県の一地方に甘んじてはいるが、上代より一国の尊崇をうけてきたという自負が込められているかのようだ。無論、筆者の思い過ごしかもしれない。 壱岐には国分寺もあった。聖武天皇の国分寺の制は壱岐にまで及んでいたということである。 既存の寺を国分寺にしたというから、国司に義務付けられたこの仏教による鎮護国家思想は、壱岐にあっては恐らくは迷惑な話だったのだろう。しかし同時に壱岐が一国をもって認知されていた証左とも言える。 この島の月読神社は全国の月読社の「元宮」とされている。 「壱岐に歴史あり」である。 博多港からジェットフォイルで約1時間。壱岐は思いもよらぬ近さに浮かんでいる。 福岡や佐賀の唐津が壱岐に近いのだが、壱岐は長崎県である。 今日の行政区分と言えども歴史的経緯の産物であることが多い。後の時代から見れば合理的判断からは程遠い理由によって線引きされたり、名称を変えられたりすることがある。壱岐の人々は平戸藩の支配から続くこの現実を肯定・否定、どちらを主成分として受けとめているのだろうか。 歴史とは愛よりも憎の方が厚く積もるものだ。 (ちょっと壱岐に寄ってみようか) 来福の一日、仕事の切れ目に乗じて気軽な気持ちで天神から博多港にむかった。目標は博多ポー |
トタワーだ。かつて筆者によって日本一の高さを誇る福岡タワーと勘違いされたタワーはその袂に来れば明らかに低い。御免なさい福岡タワー。 海ノ中道や志賀島にむかう高速船、壱岐・対馬へのフェリー、ジェットフォイルが発着する博多港はちょっとしたターミナル並に賑わっている。 10時10分の船に乗るつもりで40分ほど前に船着場に行ったがチケット売り場は意外や人が多い。 チケットを買おうと窓口に並ぶと整理係のような職員に横合いから「電話予約をしているか」と問われた。飛び込みだと応えると氏名、年齢等の記入を求められた。乗船名簿のためらしい。やはりバスとは違う。エアみたい。 ジェットフォイル「ヴィーナス」は海上を時速80キロで疾走する。 船内ではシートベルトの装着が義務づけられている。海上に軽く浮いて航走するせいか、揺動がほとんどない。船内は想像以上に静かである。走行が滑らかすぎて80キロという高速感があまりないのが不満なくらいだ。 壱岐には渡船用の港が三つある。郷ノ浦・芦辺・印通寺の三港だ。 郷ノ浦から芦辺までは車で20分程度との情報を得た上で、往路は郷ノ浦港に着岸。復路を芦辺港発の往復チケットにする。往復で9千円強。それなりの価格ではある。 周囲に商業資本の集積など見当たらない郷ノ浦埠頭を後に筆者は港から10分程度の市街地に向かう。郵便局を目印にいかにも島の小さな商店街然としたたたずまいの一角にお目当ての「三益寿司」を首尾よく見つけだした。 |


| 驟雨に見舞われた。 持ち歩いていた愛用の超軽量折りたたみ傘を開く。雨宿りのためであろう、人の姿が途絶えた。 チャンスである。 人気の無くなった街歩きを楽しむ。雨の城下町なんてのもいいじゃないか。見上げれば雲間には蒼穹。狐の嫁入りだ。 路面をたたく雨しぶきが白煙をあげているような雨勢の強さ。街も木も道も、しとどに濡れてそれがまた妙に艶っぽい。 雨脚が弱まり、苔むした地面に杉木立を通した陽光の輪が水溜りのように浮かび上がり、黒く濡れた路面に青空が映る。筆者好みの画だ。 城跡そば「服部亭」の耀くように磨き上げられた木枠のガラス戸越しの庭を愛でつつ昼食。 おび天の老舗「おび天本舗」でゆで卵まるまるのおび天を求める(筆者はこのバクダンに弱い) おび天とは、飫肥のさつま揚げである。黒糖と味噌を混ぜているためやや甘めの味である。 元は家中の武士が考案した玉子焼きがいつしか人気を集め、ついに刀を置き商家となったのが間瀬田厚焼本家である。門外不出、一子相伝の玉子焼きを今も商っている。愛想が良いとは言えない主人は一子相伝の現当主なのか? 旅の途中で要冷蔵品の持ち歩きは辛い。 「宅配便でお願いできますか」 視界の片隅にクール宅配便承りますの表示を認めながら尋ねた。 「今日は連休じゃけん無理」 (え?) 「連休明けの火曜ならええ」 休日は宅配も休みなのだ。やはり鄙である。 |
「それでは、ここでお支払いしておきますから、火曜日に送っていただけますか」 「そーゆーことはやってなか」 (え?) その日の分だけ対面販売し、その分に限り宅配も受け付けるということらしい。 いっそすがすがしいくらいに融通が利かない。 現代人は便利を享受しすぎている。鄙は不便が多い。至極当然のことで、昔はこの程度のことは普通だったと振り返るだけの過去を幸いなことに筆者は持ち合わせている。 ガラスケースに並ぶ玉子焼きの数は多くない。予約と書かれた包みも多い。観光バスでもやってくれば売り切れてしまうかもしれない。 「それではこの1800円のものを下さい」 「それから保冷材はありますか」 なかば答えを予想しながらもとりあえず聞く。 「なか」 爽やかだなあ。 玉子焼きはズシリと重い。コンビニで買った氷結ジュースを保冷材代わりにする。ホテルの部屋でわくわくしながら包みを開けた。水分が漏れている。水分が抜けた翌日の味がいいらしい。 厚さはおよそ一寸ちょっと。縦が八寸、横五寸の弁当箱のような玉子焼きである。 (すいません、厚さ4センチ、縦横25センチ×15センチ程度です) みっしりと締まった玉子焼きは「す」が入らずまるでプリンのような舌ざわりである。甘味が上品で咽越しもいい。咽にスルリと落ちてゆき、玉子の味わいが後から沸き起こる。嗚呼、しみじみといいなあ。筆者はかなり気に入った。 |

| なだらかな丘陵と、その丘陵を丸く取り囲むように流れる渓流。 街を貫く1本の主街道。 主街道に垂直に交錯し丘陵に向かう緩やかな坂。その先には白い城門が遥かに見える。 家並はごく当たり前のように磨かれており、丘の中腹を流れる用水には幾匹もの鯉が静かに遊んでいる。 低い丘陵の背後にはこの地方を他圏から隔てている山塊の稜線が思いの外、空の高みに浮かび上がっている。 とは言え、空は広い。 驟雨をこぼつ不気味な暗灰色の雲が高層の白い夏雲を隠したかと思えば、不意に抜けるような青空が視界の多くを占めることもある。 映画「ルパン三世カリオストロの城」の舞台、カリオストロ公国のようなテイストがこの街にはある。あちらはヨーロッパ、こちらはジャパンだがどこか相通ずるものがある。 この静かな山あいの街は「飫肥(おび)」と呼ばれている。 宮崎県の日南地方を代表する城下町である。 JR日南線で宮崎から約1時間。 途中「鬼の洗濯板」と呼ばれる奇岩の横たわる海岸線を車窓から楽しんでいるうちに2両編成の列車はいつしか山塊を貫き、その裏側の穏やかな平地に入っていた。 すなわち日南地方である。 海岸線に大きく開かれておりながらこの地方は陸地の周囲を山塊に囲まれている。文明社会との往き来はそれら山塊を越えるか、船で向かうしかないというロストワールドのような地勢がこの地 |
を多くの耳目から遠ざけてきた。 JR飫肥駅から城下まで15分ほどの距離を歩く。 川のせせらぎが見えてきた。 翠色の酒谷川をまたぐ橋のたもとに赤い鳥居がある。単線である日南線の鉄路が大きく山をまわりこむそのふもとに立てられているため、遠目にはあたかも赤い鳥居を鉄路がくぐっているかのようにも見える。 橋の名は稲荷下橋と言うらしい。 橋の袂に案内がある 「ここより先飫肥城下」 実にいい導入である。 人口密集地を川のそばに作るのは至極当然のことだ。飲用水、生活用水、人間の営みは大量の水を必要とする。 都市によってその水の清らかさが違うのは地勢上の問題でしかないが、それが清冽であると街の雰囲気、人心までもが澄み清められているように感じてしまうのは感傷の領域だけでもないように思える。 道が川を渡る前、大きく湾曲したあと真っ直ぐに気持ちのいい直線を成し、その周囲に商家筋をイメージさせる、よく統一された店舗がいくつか立ち並んでいる。 多くの観光地に漂う観光誘致という名のもとの剥き出しの欲が極めて淡くしか感じられないことも飫肥のいいところかもしれない。 「来てもいいし、来なくてもいい」 街に人格があるとしたら、そんな恬淡とした境地にあるようだ。 藩政時代の登城の道がなだらかな丘陵の上に向かいまっすぐに伸びている。 |

沖縄行(8) →→→back 96 06(1) 2) 3) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

| 沖縄のランドマークは海である。 海を臨むカフェを営み、それで生計が成り立つなら明日にでも筆者は移り住みたい。どれくらいで飽きるかはやってみなければわからない。 今帰仁(なきじん)の「Ke-iki‐cafe」で静かな午後の海を見ながら過ごした小半時はまさにそんな夢想を筆者に抱かせた。 南部の「Cafeくるくま」のデッキからの眺めは筆者のリラクゼーション指数を極限にまで引き上げた。 沖縄のカフェは海が商品になる。 エメラルドグリーンの海は陽光の角度により目まぐるしく色彩を変えてゆく。空の一画に浮かぶ雲の下、スコールが海面に降り注いでいる。そこには薄いレースのカーテンのようにスコールラインが引かれ、その薄絹のようなカーテンの前に虹が半弧を描いている。虹とスコールラインが徐々に近づき、やがて頭上から雨が降り注ぐ。 その雨は、しかしすぐに通り過ぎ、陽光が再び周囲を包む。 沖縄のスコールの一過性の速さは本土のにわか雨の比ではない。雨宿りの時間を愉しむぐらいにそれは一瞬のことである。 ウチナーが本土で雨に降られたら気をつけなければならない。沖縄の感覚で雨宿りをしていたらミイラになるまで雨は止まない。 海が沖縄生活の多くの部分を支配している。 ここで高級車を買う人間は、高級車なんか使い捨てカイロぐらいにしか考えていない金持ちか、みるみるうちに錆びていく車の未来を愉しみたい偏愛嗜好家のどちらかだ。 錆びてゆく車は消耗品。だから沖縄の車は大衆 |
車か軽が主流になる。 4人を乗せて車は沖縄自動車道を北に進む。 「美ら海水族館」を覗き、人口の海浜「エメラルドビーチ」で紫外線を浴び、悪路を迷走して行き着いたカフェ「Ke-iki‐cafe」でバニラフレーバーのアイスコーヒーという初物に心奪われ、ドライカレーもけっこういけちゃうのである。 まだまだ海を臨むのだ。島へ渡る古宇利大橋にむかう。途中、狭い水路ひとつを隔てて見えた橋群は、しかし大迂回をしなければ行き着けない。指呼の距離にあるのに。羽地内海を大きく周回し真喜屋から島をふたつ渡るとやっと古宇利大橋である。橋は三つ目の島にかかっている。丘の上から見下ろす道は一直線にエメラルドグリーンの海を貫いて正面の島に向かっている。これほどに広く碧に耀く海を筆者は知らない。沖縄を彩るのはやはりこの碧海なのだ。 島でUターンし、58号線に戻り北部(やんばる)へむかう。行き着いた本島最北端の辺戸岬から眺める海のむこうに与論島が望見できる。与論島は鹿児島県領である。薩摩、ここまで支配の手を伸ばしていたでごわすか。 手つかず(って言うか手つけられず)の景色の中、巨大なヤンバルクイナ像が岬のむこうの崖際に立っている。子供の頃に見た怪獣映画の特撮風景のようだ。内部は展望台だ。3階程の高さに覗き口がある。匍匐前進して覗き穴から顔と手を出すように指そうされたNを、皆が地上から撮影する。 「もっと前へ~!」 「落ちますよ!」 「いいよ、落ちて」 |

沖縄行(7) →→→back 96 06(1) 2) 3) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
| かつて熊野を走破し讃岐を制覇したメンバーがついに沖縄に上陸した。 今回は故あって構成員は4名である。 しかも野郎ばかり。 きっと心が洗われるようなすがすがしい旅になるに違いない。 集合は南海なんば駅。 「鉄」が2人いるのでラピートがいいだろうと考えたのだ。無論、筆者は何でもいい。 台風4号の接近によるエアの欠航を心配していたが杞憂に終わった。台風は日本海側に抜けた。航空会社のホームページで運航状況を確認し集合地点にむかう。 待ち合わせ時間に少しゆとりをもたせたことが幸いした。なんと台風の返し風のせいで「りんくうタウン」から関空への橋が閉鎖されている。JRも同様だ。意表をつく攻撃である。エアが飛べるのに電車が駄目なんて考える奴はそうはいない。筆者は思いつきもしなかった。 りんくうタウンで電車は止まりバスの代行輸送で橋を渡る。バスが渡れるのになぜ電車が駄目なんだ?結局、搭乗時間には煙草3服ほどのゆとりをもって関空に到着。 ボーイング社製777-200(トリプルセブン ダッシュ200)は定常の離陸を敢行した。 上昇中、Fが「どえぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇ!だ、だずげでぐでぇぇぇ) となっていたことなど離れた席にいた筆者は知る由もなかった。 那覇空港に着陸し、ボーディングブリッジへタキシング中、乗機は空自と海自のハンガー前を通過する。P3Cオライオンが数機とF4ファント |
ムが編隊規模で駐機している。 (どえぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇ!だ、だずげでぐでぇぇぇ)となったFはミリタリーには無関心な男である。しかしやっぱ男の子だ。おもちゃには飛びつくのである(自衛隊の皆さんすいません)。「ぐっときた」と後に証言している。 「鉄」が2人いるので「ゆいレール」に乗った。無論、筆者は何でもいい。 チェックインを済まし、首里城に向かう。 炎暑であった。 首里城をめぐり、日本の道百選にも選ばれている石畳の坂道を下ろうとすると「下ったら上ってくるんですよね?」と問われた。「そうだよ」と答えたが、「ええええええええ!」3名から怨嗟の声が上がった。部隊崩壊の危機を感じ「じゃあ下でタクシーをつかまえよう」と慰撫する。反乱軍になりかけた部隊は再び秩序ある行軍を開始した。 夜(と言ってもまだ十分に夕方の明るさだが)「波照間」で沖縄料理をたいらげ、ライブにあわせてエイサー踊りに興じる。気がつけば目の前のNが狂ったように体をツイストさせている。踊狂現象という奴だ。幕末の「ええじゃないか」を始めたのはきっとこいつの先祖だ。よく見ればブート・キャンプも入っている。ほっておこう。 翌朝、いよいよメンバー集合の真価が発揮される時がきた。YとFがレンタカーを運転し沖縄本島を走破するのである。 ペーパードライバーの筆者はいつものごとく後部座席にちょこんと座ったまま。 Nは「サーターアンダギー」をむさぼり食っている。 |
沖縄行(6) →→→back 96 06(1) 2) 3) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
| 沖縄の海でダイビングを体験した。 まさか46になってウェットスーツに身を包みボンベを担ぐとは思わなかった。 気分はもう「海猿」である。 客観的には「海豚」。あ、海豚って「いるか」のことじゃん。ありということで、ひとつ。 今回旅程へのダイビング挿入を主張していたのは高所恐怖症のF。地味だが熱心なプッシュに筆者とYが同意。実現の運びとなった。高所は怖いが海中はOKということらしい。 未知の体験への恐怖と好奇心。どちらも人生には不可欠の要素だ。恐怖が勝ちすぎると「へたれ」と蔑まれる。好奇心が際立つと「無鉄砲」に走り事故にあう。どちらが精神の主成分かにより気質が決まる。歴史を前に進めるのは「好奇心」派だ。集団にはこのタイプの存在が必要である。 気質的に引っ込み思案で慎重派の筆者には「好奇心」派の後押し、あるいは先導はありがたい。 北谷町(ちゃたんちょう)の米エアフォース基地そばにあるダイビングショップ「BBD」にむかった一向。 地上講習のあと実技である。 スーツを着用しブーツを履く。おもりを腰に巻きボンベを背負い、軍手をはめてゴーグルとフィンを携えて練習ポイントへ向かう。つかまっちゃった宇宙人のようにぺったんぺったん。 装備は重い。後の話だが海中から上ったときの足腰のおぼつかなさたるや80代の老爺のごとしである。重力がこんなにつらいとは。宇宙(そら)で生まれた俺には地球は重すぎる。 この日のダイビングは2本。 1本目は完全に入門編。 |
ロープやらチェーンやらをつかんだ海中匍匐前進のようなものである。少しは足をばたつかせるも中性浮力など夢のまた夢である。 浜から約100m沖まで水深7m程の海中散歩。耳抜きやらマスクから水を抜くマスククリアやらに体が馴染むころには楽しめるようになる。 実際、楽しい。 これは楽しいぞ。 検討段階で「子供騙し」と一蹴していたお魚さんへの餌撒き。これがまた楽しい。魚が集まってくるだけで嬉しい。 1本目が終了し、2本目の目的地「青の洞窟」のある真栄田岬(まえだみさき)へ車で向かう。沖縄本島の最もくびれた部分の東シナ海側、残波岬と向かい合う小さな角のような突起部だ。 岬に到着。海までの階段を再びつかまっちゃった宇宙人のようにぺったん、ぺったん。 1本目よりはさまになっているはずである。少しはゆとりもある。 しかしである。 なかなか水深が安定しない。中性浮力など夢のまた夢である。 肺に空気をたっぷり吸い込めば体が浮きはじめる。吐き出せば沈む。その感覚は確かに掴んでいるのだが、タイムラグがあるのでトロい筆者には勘どころが難しい。安定した呼吸をしていれば一定の水深で泳げるのだが何かの拍子にリズムを壊すとぷかぁと浮き始めてしまう。 じたばたじたばた。 浮き沈みの激しい人生である。 洞窟内で海中から青い水面を眺めお魚さんに取り囲まれ、非日常の極致を極めた1日であった。 |



石垣島行(2) →back (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
| 陽が昇ると海と空、島々に色彩が戻ってくる。 何かの溶液につけて化学変化をおこしたかのようにみるみる鮮やかに亜熱帯の青や緑が蘇ってくる。乾燥わかめでもこうはゆかない。 特筆すべきは海の色だ。ツムラのチャーター船がこの海域で沈んだのだろう。もちろん積荷は百万トンのバスクリンだ。そうでなければ、この海の青さは説明がつかない。 海風が島を吹き渡る。 いつものことか風は途切れることを知らない。 台風情報は、接近・通過・返し風の3段階だ。海風が吹き抜けるような島で「上陸」という言葉は使わないらしい。てらいも奢りもない染み入るような現実感覚だ。 石垣島を通過する時台風の勢力は最大となる。台風のエネルギー源は海からの気化熱だ。上陸すると勢力が落ちるのはエネルギー源を失うからである。残念なことに石垣島の地上面積は台風の勢力を殺ぐようなものではない。ピッツァの上のマッシュルームよりも小さい。本土でイメージしている台風は石垣のそれと比べれば、水の出の悪いシャワーのようなものでしかない。(無論被害も出るし実際はそんなものではないが) 本土資本のリゾートホテルは、設計者がそのことを知らないから大型の台風が来ると雨漏りに悩まされる。島で流されるCMは「台風に強いサッシ」の比較広告なのだ。 昨年の台風13号は30年ぶりに風速70m強の超大型だったそうだ。鉄筋コンクリートの電信柱が160本折れたと話すタクシーの運転手には幾分自慢の気味がある。 「瞬間最大風速も過去最大は80m台ということだ |
けど、13号のときは気象台の風速計が壊れちゃったという話ですからね。私は80mはいったと思いますよ」 島にある幾つかのダムは枯れる心配はない。ダムからひかれる水道は最大5万人の人口を想定して設計されている。石垣市民(市町村合併で石垣島も全島が石垣市になった)に充分な量の設計だったが、この島は近年人口が増加している。地方の過疎が進む中、珍しい事例である。 現在4万7千程度の人口だと言う。1年間の転入人口が2000名弱。じきに水道が破綻する。 転入者は本土からセカンドライフを送ろうとやってくるシニア世代と島生活に憧れる若者の移住組にわかれる。若者は生活基盤などおかまいなしに行動する。数名でマンションをシェアするケースも多い。しかし島の経済はそれほど豊かではない。彼等は住民税を納めるほどには経済的に安定していない。島にしてみたら生活資本は利用するが金を払わない幽霊島民ということになる。その数は1万3千とも言う。 シニア世代をあてこんだマンション建設、ホテル建設がブームのようだ。ちょっとしたバブル。本土や本島のディベロッパーが農民を説得してマンションを作らせる。資金を低利で貸し出すとか言うのだろう。マンション経営のノウハウも教えると言うかもしれない(無料であるはずもない)。絵図面通りにゆけばいいがリスクを話す営業などこの世には存在しない。団塊の世代が島に移り住んでこなければ、借り手のつかないマンションはやがて競売物件となり荒廃してゆく。そんなことにならねば良いがと旅人のいささか無責任な床屋談義的な心配はある。 |


石垣島行(1) →back (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
| 夕陽と呼ぶにはまだ水平線との距離が遠い太陽の日差しをうけて、綿飴のように質量感の希薄な雲が浮いている。 エアの機窓から見下ろしているため、その影が海原に落ちている。 影の色が濃い。 まるで双子の兄弟のようにそっくりな雲が上下に並んで浮かんでいるような錯覚を覚える。しかし、双子の数があまりにも多いので、それは海面がミラー効果を発揮しているせいなのだと気付かされるのである。 747はランディングアプローチを開始している。今まで何度かの経験にない進入コースが滑走路に近い環礁群のエメラルドグリーンから筆者の視界を遠ざけてしまった。 18時15分、那覇空港はまだ明るい。乗り継ぎのためロビーで時間を潰す。乗り継ぎ便は19時35分発だ。 19時35分、定刻通りにテイクオフしたボーイング737-500は沈み行く夕陽を窓外に写し、西に向かった。 沖縄本島からの距離およそ420キロ。それは東京、大阪間にやや足りない程度の距離である。 20時15分、意外にも西の空はまだ僅かに青みを残しているが、眼下の視界は失われている。タッチダウンした瞬間、エアブレーキと逆噴射で制動がかかる。かなり性急なその挙動は、滑走路の短かさを想像させた。現在、新しい空港の建設が進められている。 台湾までの距離は僅かに200キロ。大陸や台湾を本島(沖縄)以上に身近に感じる島、石垣島に筆者は降り立った。 |
空港からタクシーで15分程度の海辺のリゾートホテルでチェックインを済ます。メインダイニングは閉まっているが、海に面したテラスは営業時間内だ。潮騒の音が足元から聞こえてくる海辺のチェアに背をあずけビールと何品かのオーダーを済ます。 海風が頬をねぶる。 思いのほか強いその海風にオリオンビールの旗がせわしなくはためいている。丸いアーク灯がテーブルを囲み、オレンジ色の灯りを落としている。 ウェイターがテーブルを回り、星空を写すため照明を落としてもかまわないかと聞きまわっている。否やがあるはずがない。 やがてテラスの灯かりがすべて落ちた。潮騒の音を聞きながら、空を仰げば、満天の星空が広がっている。 ミルキーウェイを最後に見たのはいつのことだろう。北斗七星が浮かんでいる。そのひしゃくの先、5倍の位置に鈍くまたたいているのはポーラスターだ。 白鳥座のデネブ、琴座のベガ、わし座のアルタイル、夏の大三角形がくっきりと見える。ベガは織姫、アルタイルは牽牛である。おりしも明日は七夕。遠い昔、天体小僧であった頃の記憶が蘇った。 オリオンビールのジョッキを傾け、石垣牛のサーロインを齧りながら、筆者はすでに日常から完全に離脱していた。 |



| 九州新幹線「つばめ」に接続する特急「リレーつばめ」に漂うロシアの薫り。 ブリキっぽいのは色のせい?デザインのせい? 博多、鹿児島中央間は288.9キロ。東京、豊橋間に匹敵する。豊橋は東京、大阪間のほぼ中央にある。余談になるが、東京と新大阪の両拠点間を結ぶ最終ののぞみは両駅を21時18分に発車し、豊橋駅周辺ですれ違うのである。 「リレーつばめ」は、全区間の約半分52.4%の151.3キロを最速1時間35分で結ぶ。 JRと競う西鉄。その始発駅は天神である。 博多の衛星都市「二日市」には西鉄も乗り入れている。西鉄二日市は大宰府線の分岐点である。 二日市の先、基山で鹿児島本線は甘木鉄道に接続する。終点「甘木」の先には山中の静かな城下町、秋月がある。 鳥栖で長崎本線が分岐し、佐賀、佐世保、長崎方面に西進する。 久留米で久大本線が分岐し、筑後川に沿って湯布院、大分方面に東進する。 西鉄はJRに併走している。ただし久留米を過ぎると走路を海よりに取り、水郷「柳川」にむかい、終点「大牟田」でJRに三度邂逅する。 熊本に向かう途中、田原坂が進行方向左側に現れる。西南戦争の激戦地、あの田原坂である。 「雨は降る降る人馬は濡れる。越すに越されぬ田原坂」である。 熊本では豊肥本線が接続する。豊肥本線は阿蘇を経て大分に繋がっている。大分は東側のジャンクションなのである。 熊本駅を出ると列車は、鹿児島本線の旧軌道を離れ、高架線に乗り入れるゆるいループ軌道に入 |
る。左旋回してゆく先に、野中の一軒家然とした近代的な駅舎「新八代」が見えてくる。 ホームには九州新幹線「つばめ」が「リレーつばめ」を待っている。 列車の乗り換えはスムーズである。乗客のほとんどが乗り換えると待ちかねたように新幹線が発車する。田畑の真中、新八代で降りる客はまず、いない。 新八代、鹿児島中央間は35~48分。あまりに短いので車内販売もない。 かつての鹿児島本線はこの区間を2時間以上かけて走っていた。時間短縮の代償は車窓から望む八代海の眺望の喪失である。あのオーシャンビューは鹿児島本線の白眉だった。今はトンネルだらけ。トンネルとトンネルの間は山だらけ。新幹線では珍しく急勾配の斜面を登る。 2011年春の博多、鹿児島中央間全線開業に合わせ鹿児島中央と新大阪を乗り換えなしで結ぶ直通列車を運行する合意がすでに成されている。 九州新幹線は車内がウッディーである。座席やテーブルが木を基調に造作されている。洗面所にはのれんがかかっている。 車内放送が流れる。 日本語の次は、なんと韓国語である。 「ニダ、ムダ」言っているから間違いない。 韓国語の次は中国語だ。頭頂部から声を出しているから間違いない。 「キューシューシンカンシェン」で締めくくる。 なぜか英語のアナウンスは流れない。 アジアだ。 欧米は九州には来ないのだ。九州はアジアのものである。 |

| 中央線は東京駅が始発である。 しかし、中央線のドル箱特急「あずさ」は新宿駅から発進する。 1日あたりの乗降客数日本最大を誇る新宿駅だがこの駅を起点とする特急列車はそう多くない。「あずさ」はその数少ない新宿発の特急である。 ただし新宿を発しても八王子までは通勤圏だ。どこにでもあるビルと街が広がっている。武蔵小金井を過ぎれば「いかにも武蔵野」といった風情の雑木林が目につき始め、同時にこれまたいかにも学生の町という気配が、知っている者にしかわからない微妙な気配を漂わせ始める。 鉄路は八王子から登坂を開始。山塊に分け入ってゆく。車窓右手に寄り添うように中央自動車道が走る。山峡の谷をまたぎ、山を穿ち直進する自動車道はやや古色を帯び始めた橋脚が高々とそそり立ち、なかなかの景観である。 大月まで来て、乗客はやっと旅に出た気分になれるだろう。山中の宿駅の佇まいがそこにある。 大月駅からは富士急が河口湖まで走っている。 大月の先が甲州街道最大の難所笹子峠である。このトンネルは完成当時、日本最長のトンネルであった。 笹子トンネルを抜けると、北寄りの青梅街道まで北上する。 青梅街道と接するところが塩山である。ここを越えれば列車は甲府盆地をなだれ落ちるように快走する。ぶどう畑がなだらかな丘陵部を埋め尽くしている。 狭隘な甲府盆地の中心、甲府の次に現れる都市は韮崎である。 塩山、韮崎ともに西村寿行氏の「滅びの笛」の |
舞台となった。 120年に一度という熊笹の一斉開花により大量発生した鼠群(そぐん)が甲府盆地を襲撃するというこの小説は、今ならば映画のネタとしてうってつけだと筆者は思っている。塩山も韮崎も鼠群に蚕食された都市なのである。 このてのデザスターものは、プロローグの良し悪しで出来が決まる。行方不明になった登山客が白骨死体で発見され、家畜が一晩で白骨になり、鼠の天敵である鳥獣たちが姿を消す。何か不吉なことが起こりつつあるというムードを高めてゆく手法に作家の手腕が冴えを見せていた。 「数百万の鼠の群れは瞬く間に笹の実を食い尽くす。飢えた鼠の群れが餌を求めて降りてくる先は甲府盆地しかない。奴らは牛も馬もあらゆるものを食いつくす。人間とて例外ではない」 小説の登場人物、自然科学者右川博士のセリフである。「滅びの笛」は漫画にもなっているがラジオドラマ化もされた。博士の声は刑事コロンボの吹き替えで有名な故小池朝雄氏である。 日本一の標高を誇る「野辺山」駅を擁する小海線との接続駅「小淵沢」を過ぎれば精密機械とメディカルの街、茅野・諏訪である。茅野(ちの)のレンズメーカーがカメラを作った。「CHINON(チノン)」である。茅野だからチノン。ベタである。(チノンは社名を2004年に変更している)諏訪にはEPSONがある。 茅野から再び山を下り、信州最大の湖、諏訪湖畔に出る。下って来たとは言え、諏訪湖の標高は760メートルである。その諏訪湖を半周するように回り込み、塩尻から北上を再開。終点松本はもう指呼の距離である。 |
| 「闘牛ってどんな鳴き声なんでしょうねえ」 畏友Iが問題提起をした。 「モ~ォ~だろう」 「それはホルスタインじゃないですか」 「ホルスタインだろうが黒毛和牛だろうが、牛族はモ~ォ~だろう」 「え~」 いつものように容易に人の話に納得しない。 松山空港で待ち合わせ、Iの愛車で松山自動車道から宇和島街道に向かう車中での話である。 観光誘致にあまり熱心さが感じられない宇和島市営闘牛場は山の上にある。誘致に熱心でないから、誘導のサインがほとんどない。何度か道に迷い、ガソリンスタンドで聞いた道の途中、手書きの古びた看板が小さく傾いてかかっていた。もはやカーナビがなければ生きてゆけない世の中なのか。そう言えば、最近時刻表も買わなくなった。 闘牛場は円形である。フィールドを観客席が取り囲んでいる。なんとドームである。左右の入場口から牛達が入場する。相撲と同じ形式だ。 実況中継も解説者も(解説者と呼んでいい位置づけで座っているのか知らんけど、すいません知らんことだらけで)地場の人(だと思う)。 「出せよ~ぉ~出せよぉ!」--としか聞こえない--独特の呼び出しが流れる。 「出せよ~ぉ~出せよぉ!×××牛出せよぉ!」(と、言っていると思う) すると勢子に曳かれた牛が「ぶっしゅ~ぶしゅ~」と鼻息も荒く現れる。時折、ジュラシックパークの恐竜のような鳴き声になる。 「ブゥフォォォォオオ! BUFUOOOO!」 「ほ~ら、やっぱりモ~ォ~じゃないですよ」 |
Iが勝ち誇る。 事実は受け入れるしかない。 「・・・そうだな」 闘牛のルールはシンプルだ。相手に背をむけて逃げた方が負け。 牛同士は角を付き合わせ、相手を圧倒しようとする。感覚的には頭突きあうという感じだが。 闘っている最中、牛にはそれぞれひとりだけ勢子がつく。周囲に何人かの勢子が待機しており、試合が長引くと交代する。勢子が牛をけしかけ、背中をバンバンと叩き、気合を注入するのだ。 この日の取り組みは全部で10戦。 予定時間は12時から14時までの2時間だったが今日は1時間半ほどで終了した。1試合が15秒程度で終わってしまう取り組みもあるのだ。 試合内容は番付に反映する。小結連中の試合はあっという間に終わってしまうものが多く、やはり格下同士のエキシビジジョンの感は否めない。 闘牛場に先に現れ、中央で相手を待ち受けている奴に、入場口から入場というよりは突進してきてあっと言う間に追い散らす豪の者(牛か)もいる。 小結戦、関脇戦と3試合ずつを消化すると、若横綱戦、大関戦にと進む。さすがにこのクラスになると見ごたえのある試合が多い。 メインイベントの重量級チャンピオン戦は熱戦が繰り広げられた。あまりにエキサイティングなその内容に、勢子同士も集団でもみ合いを始める始末。牛、人、入り乱れての乱闘である。つまらないはずがない。マイクから「てめーら、やめねーか」調の静止が瞬間的に流れたりして、もはや闘牛場内は興奮の坩堝である。十分、堪能した。 |


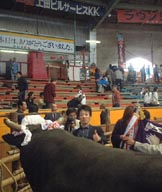
萩行4 「萩行3」からの続き →back 萩行1(1996) 萩行2 萩行3 萩行4
| 投宿先の萩グランドホテルの大浴場でさっぱりとすることにした。以前もここに泊まったが、その頃は大浴場に興味がなかった。温泉旅館に興味を示さない筆者の傾向そのままに内湯のシャワーですましていた。最近、筆者の好みも変化している。 大浴場の営業開始時間から一番風呂を独占し、翌朝の朝イチにもたっぷり浸かった。オヤジになったってことか。 風呂から上がり、フロントで食事処の紹介を求める。4店ほどの候補を得た。日の沈まぬうちに視察をかねて再び町へ出る。4店の佇まいをチェックし、「神の目」により候補を絞り込む。予約の電話を入れて夜を待った。 むかった先は「網代(あじろ)」。 懐石コースを頼んである。 当たりであった。それも予期せぬほどの大当たり。 個室がメインなのだろう。カウンターは4人程しか入れない。大将がひとりでその前に立つ。客は筆者ひとりきり。 これは楽しそうだ。 ふくの湯引きと赤貝のヌタ、ごま豆腐、ふき、菜っ葉のおひたしとふくの骨酒がどん!どん!どん!と突き出しで出てきた。 ふくの白子の炙りをうかべた吸い物には1枚1枚をはがした筍と、山椒の葉を栞のようにまとった大根の薄切りが添えられている。白子の皮が薄いがもちっと、いい塩梅に香ばしい。そして中はトロッと。 この段階ですでに筆者は大将の術中にはまってしまった。期待がぐんぐん膨らんでゆく。 |
お造りはひらめとふくのねぎ巻き、いかのような味わいの切り身は最初、魚かと思った。とてもいかとは思えんけんさきいかであった。 うにのせいろ蒸し飯が、味わい豊かな甘さと香りに満ちている。飯がべしゃついていない。 アマダイの味噌漬けの焼きも香ばしい。瑞々しい。つけあわせのそら豆とれんこんの端々にまで心配りがゆきとどいているようだ。 筍とわらびが強烈に旨い若竹煮は、だしの気配を最小限度におさえている。それが山菜の味を際立たせる。 茶碗蒸しにはふくのアラが使われ、滅法界に旨い。底にはほんのり甘い百合根がしかれていた。この茶碗蒸しは暫定日本一を贈呈だ。 大きめの器の蓋をとった瞬間、突き出しで飲んだ骨酒の香りが鼻腔をくすぐった。ふくのかまの骨蒸しだ。ポン酢で食べるぷりっぷりのかまの身は香りも味も絶品。大将の創作料理だと言う。 てんぷらの後、ふくの雑炊を食べ、店自慢のくずきりで宴が終わった。 聞けば、小泉元総理もこの店を訪れたらしい。萩の正規ルートを通じたら絶対にウチになんか来ない、と大将は言う。地元ではなぜ「網代」に総理が、と噂が走ったらしい。晋ちゃんが教えたのかな。 たった一食が旅の印象を鮮やかに塗り替えた久しぶりの体験だ。萩(ここ)に来ることはもうないかもしれない、としおたれていた筆者の精神に瑞々しい躍動感が戻ってきた。また、来るだけの理由ができた。 「百萬石」の跡は「網代」が継いだ。松蔭の意思を継いだ晋作のような鮮やかな登場であった。 |



画像左から 明倫館小学校 ・ 萩港へ向かう漁船 ・ 山陰線からの日本海
萩行3 →back 萩行1(1996) 萩行2 萩行3 萩行4
| 早世への希求は若者の属性の一典型だ。夭折した天才達への憧憬がヒロイズム菌と融合し、それがもとで罹患する精神のハシカのようなもの。 筆者は若い頃、高杉が世を去った28で自分も、との憧れにも似た思いを持ったことがある。それがどうであろう、すでに46である。 いやあ、生きた生きた。土方歳三も追い越し、河井継之助も大村益次郎も追い抜いた。もうすぐ織田信長を追い越す。たぶん最後は北条早雲と勝負をすることになるかもしれない。 桂クン家(ち)と周布さん家(ち)にも寄る。 周布政之助は桂や高杉のアニキ分のような藩の高級官僚だ。野山獄に投じられた高杉に『貴様は長上(先輩)を長上とも思わず、それを凌ぐことばかりをした。であるがゆえにかような暑中、牢にいる破目になったのだ。牢に三年もいろ。三年もおって学問をしろ。すこし人物をつくって出て来い(世に棲む日日:司馬遼太郎)』と説教して崩壊に突き進む長州藩の前途を悲嘆して腹を切った。かつてNHKの大河ドラマ「花神」で故田村高廣氏が役を演じた。 周布家の長屋門が残っている。 (周布(すふ)さん) 心の中で呼びかける筆者。 案内板に目をむける。 「周布(すう)家長屋門」と書いてある。 「すふ」じゃなくて「すう」。 板きれ1枚に46年間の人生を否定された。 ペダルをこぐ足に力がこもる。 板壁が、いい風情の建物が見えたきた。「明倫館小学校」である。この平成の世で、まさかこの |
ような小学校で少年時代を過ごす子供たちがいるとは。しかもこれは、藩政時代の藩士の子弟を教導した「明倫館」の流れを継いでいるのに違いない。ここの小学生にとって、高杉や久坂や桂は先輩にすぎないのだ。羨ましすぎる話である。 夜の準備をしよう。 11年前、愉しく時を過ごした「百萬石」に行こうと思っているのである。まずは予約だ。 電話のむこうで受話器をとった女性は、なぜか個人名を名乗った。 「すいません、かけまちがえたようです」 「もしかしたら、百萬石におかけになられましたか」 懐かしそうに、静かに様子を伺うような声である。かけ間違いではなかったようだ。 「ええ」 話を聞いた。やはり女将さんだった。 ご主人が亡くなり、店をたたんで数年が経過しているそうだ。 「以前おいでになったことが?」「10年前ですが」「どちらから?」「以前は東京から、今は大阪から」 往時を思い出しつつ、筆者も知っている情景をゆったりと話した元女将は、最後に大変すまなそうに詫びを言い、筆者は。お元気で、と言って電話を切った。 今回の萩行のひとつの支柱を失い、旅の目的が変容してしまった。夜の酒食がなければ泊まる必要もなかった。後悔の念が旅の心に影を落とす。このままではいけない。欠けてしまった気持ちの張りを修復しなければ。 |



画像左から 高杉クン家 ・ 桂クン家 ・ 周布さん家長屋門
萩行2 →back 萩行1(1996) 萩行2 萩行3 萩行4
| 「ちょっと高杉クン家(ち)に寄っていこう」 九州からの帰路、思い立って萩に寄り道することを決めた筆者。JR博多駅のみどりの窓口に立ち寄った。 「厚狭(あつさ)経由、美祢線(みろくせん)で長門市回り、東萩までのチケットをください」 明快なオーダーである。見事だ。 しかし歳若いJR職員は怪訝な顔をしている。 (なんじゃ?わからんちんな奴め) やれやれと経路図をさし示す。 「ああ、厚狭(あさ)経由、美祢線(みねせん)ですね」 (・・・・・・・) 若造に46年間の人生を否定された。 (そうとも読むな) 心のなかでつぶやく筆者。 厚狭も美祢線も意識の視野に入ってきたのは関西に来てからこっち5年程度のことなので深刻なダメージではない。なによりも筆者がマニアでないことの有力な証拠ではある。銘記しておいていただきたい。 久しぶりの晴天に恵まれた週末、「のぞみ」と「ひかり」にバンバン抜かれる「こだま」で厚狭までむかう。JR西日本のこだまは自由席でも左右2列ずつのグリーン車仕様である。窓も広い。文字通りワイドビューだ。 ちょっと不思議なのは博多駅に入線した「こだま」にはすでに乗客があること。 鉄道マニアの間では基礎知識レベルだろうが新幹線は「博多」の西にもう一駅、「博多南」駅を擁しているのである。「のぞみ」も「ひかり」も博多が終点だが、何本かの「こだま」は「博多南 |
」駅が終点であり、始発なのだ。この間、実は新幹線として営業しているわけではない。在来線として規定されている。つまり、在来線を新幹線車両が走っているわけだ。 無論、筆者の周囲のマニアNは「博多南」まで行っている。 厚狭からはワンマンのローカル線にゆられてゆるゆると日本海側にむかう。美祢線から山陰線に乗り換え、碧色に輝く海を車窓におさめながら、やがて列車は東萩駅に到着。 萩は、幕末、維新を牽引した長州藩の藩府である。今日は96年以来、11年ぶりの訪問だ。 街は、いつの間にか「庭園都市」「屋根のない博物館」などのキャッチフレーズを標榜するようになっていた。 萩グランドホテルに投宿。レンタサイクルを借り萩市内を巡る。ひさしぶりのチャリだ。前回の萩行は、すべてを徒歩でこなしたが、今回は機動力を駆使する。決して足が衰えたわけではないので、そこのところは、ひとつ。 萩港から菊ヶ浜にむかう。陰鬱なイメージを持つ日本海だが、それを忘れさせるような海の碧さと美しさだ。景色にふれただけで日常の何もかもが意識から飛んでしまった一瞬である。心のうちから瞬間でもいいから日常が飛ぶとき、筆者はリフレッシュされる。 白い砂浜で時を過ごし、武家屋敷に向かう。 高杉クン家に寄るのだ。 百石取りの上級士官の家とは言え、質素な造りの高杉家で、すでに筆者より遥かに年下になってしまった高杉晋作と話をする。 |



沖縄行5 →→→back 96 06(1) 2) 3) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
| ギィイ。 扉を開けたとたん、背をむけて戻りたくなったが、時すでに遅し。陰気な女性が死んだ魚の目のような視線を投げかけてきた。 (貞子か?) 歓待の意思を持っているとはとても思えない投げやりな態度でふらふらと手を中空に漂わせる。 どこにでも座れという指示らしい。 アメリカ東部から州間高速(インターステート)を乗り継いで立ち寄った南部のロードサイドレストランでスイングドアを開けた途端、それまで談笑していたであろう常連のトラッカーや地元民から明らかによそ者を値踏みするような視線を、上から下までたっぷりと非友好的にはわされた、そんな感じである。 奥から出てきた明るい女性が天使に見えた。 「アメリカンステーキ、200グラムとピザのチリをSサイズで。あとゴーヤジュース」 アメリカ人がこれが肉だときっと言うガシガシのビーフが出た。とうもろこしで育つとこうなるのか。赤身好きな筆者だが、普段の肉とは違う。狩猟民族が食べる肉だ。レアを頼んだのにスーパーウェルダンだ。顎が発達するに違いない。塩加減も何もあったものではない。テーブルの上のステーキソースをかけるしかないのだ。どんな味の食べ物でもきっと食べられるようになる魔法のソースだ。ケチャップとウスターを合わせたような酸味の強いソースである。200gのステーキに多量のポタージュ、多量のサラダ、多量のライスがついて1000円では文句はない。 場所は、辻のステーキ街。夜は歓楽街になる。無料紹介所があった。沖縄にもあるのね。 |
3月初旬、那覇の気温は23度。現地ではすでに半袖姿がチラホラ見られる。 陽が沈めば海は耀きを失う。ランディングアプローチを始めた機から望む沖縄の空も海も灰白色の混沌に沈み始めていた。今回のテーマはステーキの消費なので天気は気にならない。 2食目をステーキハウス88で消化し3食目の肉は、現地の食材を使ったイタリア料理の「てだこ亭」である。店は、牧志の公設市場の先にある。島豆腐とフルーツトマトのカプレーゼ、黄色い島にんじんが印象的な温野菜のサラダがいける。琉球在来種豚アグーの荒挽きミートにフレッシュ生クリームを使ったメディチ家風パスタ、沖縄山羊のシェーブル、たんかん、蜂蜜を塗った骨つきロースアグーもいける。グラスワインもいい。 4食目は、ジャッキーステーキハウスでテンダーロインステーキ150g(1500円)を消化。辻のステーキ街から旭橋の近辺に移転したという店は繁盛している。この店も「Aサイン」の出自だ。 「Aサイン」とは米軍支配下時代、軍関係者に料理を提供できるという米軍発行の公認証である。 今でも店内のメニューボードは英字である。日本語のルビがふられている。「TENDER LOIN STEAK」はガシガシしていない。いけた。 店を出ればサァーっとジョウロで水を撒いたかのように雨が降り始め、スコールのようにぱたっと止む。亜熱帯である。米軍軍属の住んでいたアメリカンなハウスの記事を見た。箱型、フラットな1階建て。21・6・7・7帖のスペースの家が宜野湾で月9万、6.5・6.5・6・6.5・5.5帖スペースの沖縄市の家も9万。どうよ? |
| JR新潟駅周辺の新市街と古町モールをメインストリートとする旧来からの繁華街を萬代橋が結んでいる。橋が渡るのは日本最大の河川、信濃川。夕闇が迫る川面に外灯の火が揺れる。博多中洲の那珂川の風情に似ている。 宿は萬代橋の袂にあるホテルオークラ。逃亡者もたまにはコンフォートな夜を過ごすのだ。信濃川と萬代橋を見下ろす眺めのいい部屋は、広くてラグジュアリー。トイレとバスが別室になっているが、ルームチャージは東京では考えることもできないお値打ちだ。 日も沈み、あたりを宵闇が包み始めた頃、宿を出て古町に向かう。古町モールはショッピング街であり、歓楽街である。北陸の百貨店「DAIWA」の脇にアーケード街が続く。 港町新潟に来た以上、魚を食べないわけにはいかない。 「港すし」でノリのいい握り方の気持ちのいい寿司と肴を食べ、酒を喫する。 「ほうぼう・あら・甘エビ」などの日本海モノを中心に切ってもらい、アテも数品。「さよりの皮」を串に細く巻いた焼き物で酒が進む。薦められるままに「極上吉野川」をお燗で飲む。新潟の酒はすっきり端麗のイメージが強いが燗酒にすると香りと甘味が立ち、肴に実にあう。 太くてしゃきしゃきとした「もずく」の歯ごたえが嬉しい。土地ではオスと呼ぶそうな。細いもずくがメスである。「真鱈の白子焼き」は濃厚。「鯵(あじ)のたたき」はさっぱり。朝採れのサバを〆た「しめ鯖」は脂ものって絶妙である。 「これだけでもいいんじゃないかと思っちゃいますが」と出された「いかの塩辛」で2本目の燗酒 |
を追加せざるを得ない。「ふきのとう味噌ときゅうり」で酒の消費に加速がついた。「代々泉」の3年古酒を冷で。初代が店を開けたのは昭和8年とのこと。ひとり者に優しい旨い店である。 寿司のあとは越後の名物「へぎ蕎麦」を食べなければならない。 へぎとは「板箱のような容器」のこと。そのへぎに布海苔(ふのり)をつなぎに使う淡い緑色のそばがきれいに手繰って盛られる。「須坂屋そば山水庵」は呑み処としても人気があるらしい。サラリーマンのグループが何組も酒とつまみと蕎麦を注文している。 翌朝、新市街の万代シティにむかう。 シンボルとなるレインボータワーは地上100メートル。回転展望室がゆったりと上下している。 新潟市街が一望に納まる。天気も良好。気分がいい。遠くスワンドームが陽光に耀いている。 昼食は「新潟かつ丼」だ。 揚げたてのカツを甘しょっぱい醤油タレにつけ飯にのせるのが「新潟かつ丼」である。卵でとじない。昨夜、発祥の店「とんかつ太郎」に赴いたが臨時休業の憂き目にあった。今日も定休日でやっていないはず。別の店で代替行為をするしかない。「政家」新潟駅前店が筆者の前に現れた。創業40年を謳っている。カウンター形式のファストフードっぽい店装だがイケた。 新潟かつ丼のあとは越後の名物「へぎ蕎麦」を食べなければならない。 「利休庵」駅前店で1.5人前を食べる。 21年ぶりに訪れた街で過去を清算した思いの筆者であった。 |

| 「待てー!」 そう言われて待つ奴はいない。筆者は思いきり地を蹴って走った。 (逃げるのだ!尻に帆かけて高飛びだ!) 追手の執拗な追捕の手を逃れる筆者の前におりよくジェットが現れた。 「乗って!」 CAが搭乗口から手を差し伸べる。その手につかまり、筆者は離陸を始めた機に飛び乗った。ANA513便、A320は轟音とともに地を離れた。 足を組み、シートに背を預け、シャンパンのサービスをうけながらi-Podのイアホンを耳にはめれば、流れる曲はシャネルズの「ランナウェイ」だ。筆者はニヒルに微笑んだ。 一面白銀の日本アルプスを眼下におさめた後、やがて機は銀色に耀く思いのほか大きな川の川面に翼端を触れんばかりの低空でバンクし、思い切りドスンと身を落とすようにランディングした。 川を越える瞬間、鷹並の視力を誇る筆者の目は背後に流れ去る河川名標識を瞬時に捉えていた。そこには「一級河川 阿賀野川」の文字が。 筆者は、その阿賀野川ともうひとつの巨大河川に囲まれた港湾都市、「柳都」に潜伏することにした。 「柳都」正式名は新潟。 幕末開港場となった5都市(他に長崎、神戸、横浜、函館)のひとつである。 江戸時代、当初長岡藩領であった新潟は、中国との密貿易などで幕府からの摘発をうけ、天領となる。 もともとは新田開発の地、そして港で発展した地ゆえ城下町の風情はない。江戸文化を感じさせ |
る成熟した藩政の地ではなかった。行政は新潟奉行が差配した。幕末の開港も結局、幕府の手にはならず新政府によるものとなった。街の歴史はここから積みあがっていったと言って良い。 筆者はかつて81年と86年に新潟を訪れている。往時の旅日記を見ると、その際のイメージは芳しくない。既述のとおり土地に江戸文化の匂いが希薄だったせいかもしれない。今は無いダイエーの周辺にたむろする暴走族の集団に辟易したせいもある。若者の貧乏旅行では、全国チェーンの居酒屋「村さ来」に入るしかなかったので食の記憶も貧しいものだった。感受性は過剰な世代だから記憶形成は極端に走りやすい。その時のマイナスイメージがこの紀行に新潟の登場を遅らせた要因である。 その新潟が平成17年には近隣13市町村と合併、人口約81万の都市となった。 (あれ?) 久しぶりに親族が集まり、小さい頃に会ったきりの甥っ子の成長の早さにびっくりした叔父さんの心境である。 (いつの間に、こんなに大きくなっちゃって) 筆者の中の新潟の街は北国の風雪にひっそりと耐える田舎町のイメージでしかなかった。 思えば、あの頃に初めて訪れた土地の印象はいずれも寂寥感溢れるものばかりだった。夜行の多用で夜型の生活である。宿代を浮かせるべく深夜喫茶で夜を過ごしていたせいもきっとある。あのままでは、名古屋も大阪も街には演歌が流れ、店と言えば吉野家か深夜喫茶しか存在しない冥府のような陰惨な町として筆者の記憶に止められたに違いない。 (続く) |
続編予告編の画像

| 駅からまっすぐに伸びてゆく道の先に山が見える。輪郭がはっきりとしているのは山頂が石垣によって形成されているからだ。 寝そべった牛のようにも見えることから山の名は臥牛山(がぎゅうさん)と言う。函館にも同名の山がある。地名としては普遍的ゆえ、おそらく日本中いたるところに同名の山があるのかもしれない。 天守があれば、壮麗に見えたかもしれない景色の山は、しかし石垣を残すのみである。城下町はその麓に形成されている。寺町、商家、武家町が揃って、初めて城下町と言いうる。この町はそれらすべてを備えている。 海沿いのため積雪量は少ないほうだ。暖冬の影響か、2月の2旬、街中に雪は見あたらない。3年前の同時期に訪れた長岡では信濃河畔で膝まで雪に埋もれたことがある。もっとも、昨年は大雪だったのだ。こうも暖かいと1年前のことすら記憶から溶け去ってしまう。 越後では三八豪雪と言えば、還暦以上の人とならば話が熱を帯びること請け合いである。昭和38年の記録的豪雪のことだ。五六豪雪は昭和56年。融雪装置の整備や除雪能力の向上により昭和38年と平成の現在では比較は難しい。実は昨年は三八豪雪並だったとも言う。 城下町まで駅から歩いて20分ほど。駅前の石田屋旅館の海鮮はらこ丼に舌鼓を打った筆者は、帰路の列車を1本断念して(つまり1時間56分の猶予を得て)街歩きを愉しんだ。 平日の午後、街は静寂の中にある。日本海側の街らしく空には鉛色の雲が垂れ込め、時折雨が路面にまだらな水玉を滲ませる。その雨跡が繋がり、 |
路面を鈍く光らせるほどには雨量は多くない。気温も下がらない。コートの前を合わせる程度で防寒の用は足りてしまう。 城下町だが鄙である。鄙ではあるが朽ちてはいない。少し寂しげな街並は、やさしく年老いているが老いてなお気骨ある佇まいを失わずにいる。気品を兼ね備えたその気色は、盛岡や米沢のように筆者の心を魅了して止まない。またひとつ、筆者好みの街に新しい名が連ねられた。 街の名は村上。越後最北端の都市である。新潟から羽越本線、各駅停車で1時間半程度。 三面川(みおもてがわ)の鮭漁で知られる。街中にある喜っ川(きっかわ(喜の字は七が三つ並ぶのだが漢字が登録されていない))は国の有形資産に指定された150年前の造りの町屋を店舗としている。その町屋の中に鮭を吊るし、鮭の塩引きを作っている。城下町ゆえ鮭の腹は全部を切らず2段に開く。首吊りを忌避し尾から吊るす。吊るされた鮭の群れが古色に彩られた家の中で静かに刻の流れを遡上している。 村上の商店街には趣のある町屋が多く残っている。どれも奥行きが異様に深い。軒先から通り土間に車を乗り入れられるほどだ。実際、車を屋内に停めている町屋がほとんどだ。その先に上がりかまちがあり、仏壇が見える。住居はさらにその奥にある。 村上牛というブランド牛があるらしい。はらこ飯や鮭料理だけでも食指を誘う食堂や料亭が数件ある。村上牛までも消費するとなると宿を確保して腰をすえねばなるまい。再訪の意志を固め、思いの外多連結(4両編成)の羽越線各駅停車の半自動のドアを手であける筆者であった。 |

「喜っ川(左)」と「石田屋旅館(右)」 日本海岸、太平洋岸を問わず、東北ではシャケの子をはらこと呼ぶ。
特性の醤油にきれいにほぐした子をつけて飯の上にかけるはらこ飯は北に上がらねば食べられない。
| 「こわぁいよぉ~」 幼児が階上でむずがっている。なだめて階下へ下ろそうとする親。後ろに行列が出来始めているから焦りもひとしおだ。 (ふ。分かってねえな。現存天守閣、しかも実戦配備の城に子連れで上るとは) 現存天守閣を誇る城は国内に12。うち国宝指定が姫路・彦根・犬山・松本の4城だ。 姫路は装飾性優先の権威の象徴となってしまった。松本は実は登城してないのでわからない。彦根と犬山はまさに煙硝と弾雨によって彩られるべき最前線、実戦配備の城である。だから、侵入者への防御機能として石段は不規則、城内は暗い。階段は急傾斜である。ほとんど梯子と同じ。ステップが細く足の踏み場も心もとない。手すりにしがみつき何とか上れるが、見上げるよりも見下ろすほうが怖い。帰路、垂直落下の恐怖との闘いに負け、段上で幼児は泣き出し、老人は後悔する。 93年以来、14年ぶりの彦根の街。駅から城までまっすぐに伸びる「お城通り」の西側に商店街は発達している。彦根城の大手門は駅に向かわず、西に面しているのだ。 天守閣は小さいが、石垣で穿たれた濠は広く四周を覆い思いのほか巨城である。緑豊かな城山の山頂に小ぶりながら天守閣が天空に映える。城東にある玄宮園の造園技術は高く、散策者の足を止めるほどに奥行きのある景色を作り出している。 安土と同様、往時は東・西・北の三方を琵琶湖に囲まれていたと言う。際立つ2次産業がなかった彦根は高度成長下に日本全土を覆った土木建築ラッシュの魔の手を逃れ、藩政時代の面影をよく留め、おそらく関西では一二を争う趣のある城下 |
町となっている。 駅前には藩祖、井伊直政の像。兜の立物「大天衝(おおてんつき)」が象徴だ。半月を細長く延ばし、クワガタの角のように左右対で天に伸び上がる意匠である。 徳川家中でも屈指の武勇の士、直政は家康と衆道の関係にあったと言う。万千代と呼ばれ、家康に愛でられたが、田舎風儀の徳川家中で譜代でもない彼がそれと揶揄されずにいたのは、政戦両略の才と粗暴とも言える性格(統御は基本的に非違あらばだんびらを振りまわす恐怖政治による)にもよるのだろうが、武田の家臣団70余名を配属され、赤備えをチームカラーに徳川家の武断的代表銘柄となるほど戦場でのかけひきの旨さが余人をもって代え難かったのだろう。三成の領国であった佐和山を与えられた際、その領国経営を踏襲し三成への弔いも許すなど政治センスも良かった。 直政亡き後、全国普請による彦根城構築には佐和山城の石垣、構築物を根こそぎ剥ぎ取り急場の要を凌いだ。佐和山城は5層の天守閣を琵琶湖畔に浮かべ、天下の名城と謳われていたのだ。新幹線で彦根城下の眺めを遮る彦根CCの看板があるのが佐和山だ。佐和山と彦根の間は東西に2キロ強。移築しなければならないほどの距離か?三成の威徳を偲ぶ領民経営が難しく象徴としての佐和山を離れたかったとの説や、佐和山(標高242m)が急峻に過ぎたとの説もある。いずれにせよこの要地の駐屯部隊に徳川軍団の主力、井伊軍を配したことから徳川家の西国経営における彦根の重要性が浮かび上がる。豊臣は大阪に健在である。篠山城が西を扼し、彦根を東からの橋頭堡とし、東西から大阪を囲んでいる。結構、壮大な構想だ。 |





| 引き取り手のいない孤児のような三重県。 東海なのか関西なのかはっきりしないのがいけない。どちらのエリアからも「微妙だで~」「微妙やな~」の声があがっている。 松の内の一日、名古屋での用向きを終え、軽くなった気持ちの赴くままに松阪に足を伸ばした。 三重は南北に長い。松阪まで近鉄特急で1時間6分、この日は急行で乗り換えを含めて1時間34分もかかった。 近鉄は名古屋から紀伊半島の伊勢湾沿いを南下する。沿線には桑名・四日市・津など三重の主要都市群が並ぶ。特急で桑名まで15分、四日市まで27分、津まで48分。その後、伊勢中川で路線は分岐し京・奈良・大阪方面への大阪線が西に行く。南下を続ける路線は松阪・伊勢・鳥羽と結ぶ。終点は賢島。そこに何があるか筆者は知らない。 目的地、松阪(まつさかである。まつざかではない。濁らない)に降り立った筆者。 駅前で牛が暴走していた。(嘘です) 静かな目抜き通り。松阪を代表する「和田金」と「牛銀本店」は駅から10分程度の距離にある。 まず「牛銀本店」に電話をする。 「おひとりは駄目なんです」 不穏な気配が漂い始めた。和田金へ電話。 「8日までは予約を受けていないんです」 |
(え?) 目の前が真っ暗になった。 「直接お出でいただいてお待ちいただくことになりますが」 「すぐに行きます」 5階建ての豪華旅館のような「和田金」は、玄関が広い。何しに来たんだっけ?と思えること必至。すべての部屋が個室らしい。薄いピンクの絨毯の上を仲居さんに先導されしずしずと進む。 個室に入り、こぶ茶を喫し、すき焼を注文。目の前には炭が赤々とおこり始めた。何とも静謐な時間である。時々炭がはじける。はじけた炭は中空でパッと赤く輝き、まるで花火のように赤い小さな火花をその先に幾つも咲かせる。 すべてが仲居さんの手により調理される。肉は思いのほか厚い。旨い。1人前の後、追加でもう1枚、薦められるままに「志お焼」と呼ぶ塩焼きを食べる。野菜も旨い。牛の脂で焼くから香ばしい。野菜の甘味も出る。香の物の赤菜でご飯が進む。普段は赤味噌の味噌汁も松の内は白味噌とあわせるそうだ。中に紅白の餅が入っている。 客の姿が見えなくなるまで続く仲居さんの辞儀に送られ、ほろ酔いの筆者は城下町松阪をぶらつく。城跡もある。蒲生氏郷の居城だった。本居宣長もこの地の出身らしい。何ともいい年の初めの一日であった。 |



| 丹波篠山は京都府と兵庫県どっちでしょう? ・・・正解は兵庫です。 師走もあと数日で終わる一日。丹波篠山を訪れた。JR宝塚線の丹波路快速で始発駅大阪から終点の篠山口まで1時間弱。 街の起源は家康による拠点主義に端を発する。京、大阪どちらにも直行でき、中国地方からの攻略に対しても、山陽、山陰両面への防備が可能な位置にある。関が原の後、大阪城に拠る秀頼を要する豊臣家と西国大名との連携を断つ意味も強かった。 築城の名人と謳われた藤堂高虎の手になり全国普請(幕府の命により大名が自弁で建築を負担する)で急増された篠山城は今、石垣と濠にほぼ往時の姿を留めている。 城下町として発展した篠山だが、特産品が有名だ。丹波ブランドが冠される黒豆や栗、松茸、丸い形状の山の芋など。さらにドイツの街のように猪がイメージの主役だ。 JR篠山口から城下町までバスで15分強、6キロほど離れている。「二階町」の停留所が長くもないメインストリートの中心である。 周囲にはぼたん鍋(猪鍋)の店が並んでいる。目にとまったのは大衆食堂っぽい造りの「大手食道」木枠にすりガラスがはめ込まれた古い引き戸 |
なのに意外にも自動ドアという意表をついた入り口の前には「大手」と染め抜かれた大きなのれんがかかっている。 傾いたショーケースの中に惣菜が並んでいる。それらには手を出さず、メニューから2品を頼んだ。「しし肉うどん」と「牛とろ丼」である。味噌仕立てのしし肉うどん、うどんはゆるいが猪肉はしっかりとしている。牛とろ丼は焼肉をご飯の上に載せ、タレをかけまわし、山の芋のとろろを羽織った物件。旅の昼食を満喫した。 大正ロマンというかつての町役場を改修した、観光あんない所兼みやげもの屋兼カフェはゆったりとしたいい造りだ。黒豆ソフトをなめなめ館内のしっかりとしたテーブルと椅子のセットに腰をおろす。喫茶コーナーのおばちゃんが売店のおばちゃんに挨拶まわりをしている。「よいお年を」世間はもう正月休みに入るのか。 騎兵に対しての歩兵は徒(かち)と呼ばれる。この兵種の居住地がお徒士町(おかちまち)だ。城の東南部に下級仕官の屋敷が並んでいる。今でも数戸が茅葺の古色あふれる家で生活を営んでいる。年末の一日、街は静かだ。車の往来は賑やかだが、歩いている人は少ない。篠山城跡は完全に独り占め状態。静謐な時が流れている。のんびりとやすらぎの時間を過ごした。 |



| 冬が来た。 ブリおこし(雷)が鳴り響き、カニの解禁がすぎたら金沢へ行こう。 日本海の旨味が一堂にうちそろう季節。 今シーズンは、寿司屋を巡った。先般、知人に金沢を案内し、もう少し店の幅を広げておいてもいいかもと思ったのも一因だ。4店の寿司屋を訪れた。おそらくは筆者の知らない旨い店はたくさんあるのだろうが、とりあえず、30・40・50・60(最近70になっちゃった)代の大将が切り盛りする4強店(小松弥助・太平寿し・千取寿司・乙女寿司)を掲載。今回は紙幅を広げてお届けします。 「小松弥助」 大将を落語家に例えれば、三遊亭圓生だ。大名跡の風格。 寿司を握るために生まれてきたような大将がひとりで握る。女将さんがその横で見事なフォローをきかす。いい寿司屋の絵がそこにあった。店内には2名ほどの配膳の女性がいた。 実は初めての訪店である。かなり有名な店だ。ここまで有名になると天邪鬼の気味がある筆者としては何かしらいちゃもんをと邪まな心があったのだが、あっと言う間に飲み込まれてしまった。 寿司に過不足がまったくない。仕事をしているだの、酢が強いの弱いの、甘いのしょぱいの半可通なことを言わせる余地がまったくない。ただただ素直に旨い。「また来たい」という欲求が食べている最中に頭をもたげるのである。今まで何度か予約が入らなかった人気の理由がやっとわかった。金沢の寿司屋は30代、40代、50代、60代とそれぞれに代表する顔がある。小松弥助は60代の代表だ。しかしすでに70代になってしまった大将は体を休め、長く店を続けるためだろう。店の営業時間を12月から、11:30~17:00として水曜と木曜を定休としている。 手巻き風に食べるネギトロが旨い。ウナキュウは絶品だ。突き出しに出てくるブリ大根がまた旨い。その日、ブリにいい奴がはいっていなかったので寿司として食べそびれたのが残念である。 「太平寿司」 落語に例えるならこの店は、立川談志である。 磊落にして豪宕の気味ある大将は、しかし細やかな心遣いを創作性の高い寿司に注いでいる。金沢寿司では40代の代表である。 店は野々市の郊外にある。その日、往きは徒歩。北鉄石川線の馬替(まがえ)が最寄駅との記事を見つけたが、ほとんどの紹介物件では最寄駅の表示はない。覚悟をきめたがやはり徒歩では無理があった。初めての訪店なので安全策をとったせいもあるが、迂回にはなるが幹線道路ぞいに歩いて20分程度。無論帰路はタクシーである。 今回の4店舗中、最も町場の寿司屋に近い風情がある。 大将のほかにタカドンが握りに立つ。タカドンたぶんまだ修行中。頑張れ。 コウバコの創作寿司は手毬である。ほぐし身と外子、内子が酢飯にまぶされかわいい手毬寿司になって出てくる。これにオスのタラバの足を乗せたやや大きい手毬が並んでいる。のど黒の蒸し寿司は絶品。おおぶりな酢飯の上にのど黒を載せ蒸してある。だしが軽くヒタヒタとかかり、小さなしゃもじで食べる。リゾット感覚だ。また食べたくなる逸品。新潟産の鯖の棒寿司は肉厚で臭みもなく実にいい按配の旨さである。ブリの片面を軽くあぶって出された刺身は大根おろしといっしょに。あぶった面が締まって旨い食べ方だ。 イギリスから取り寄せているという塩が寿司の上でちょっと気になる感覚になるが愛嬌ということで、ひとつ。 鯛のこぶ締めは筆者にとってはこの店が一番旨い。 「千取寿司」 大将は50代の代表であるが、筆者がここで食べる時は二代目か右翼席を担当する握り手の手になる寿司である。 店のイメージは「柳家こさん」だ。一門をうちそろえ、正統派の寿司屋をキリッと営んでいる。店の佇まいは今回の記事中の4店舗では一番敷居が高く感じられるかもしれない。金沢大がそばに |
あるので教授の馴染み客も多い。家族で連れ立ってくる常連さんは、親子二代三代のつきあいである風情だ。しかし、常連さんが多い店にある居心地の悪さはまったくない。握り方の接客にわけへだてはない。ただただ、旨い寿司を食べにくる場所なのだ。 ここの「さざえの壷焼き」を筆者はこよなく愛する。味噌仕立てである。また、締めに出てくる「つみれの味噌汁」も旨い。 「乙女寿司」 30代代表の大将の寿司は「古今亭志ん朝」である。 清冽にして端整。居住まいを正して寿司を口に運ぶ心地よさがある。旨い! 敷居が高そうに見えて、非常に居心地の良い店である。大将の人柄がそうさせているのか、優しい店である。金沢にありながら江戸前を感じさせる粋もある。 イカを食べるならこの店だ。塩とゆず、香ばしいゴマの香り。・・・旨い! 白子の刷り流し、能登の塩で食べるアン肝、最近客をうならせているアナゴのネギ巻きは絶品である。HマスターとS氏はアナゴの大きさとそれなのに大味にならない絶品の旨さに唸っていた。Fと訪れた昼にブリの頭を供された。筆者は目のあたり、Fはブリカマ。煮ぐあいも抜群だ。半身にしても1尾で4箇所しかとれない部位を昼に出してくれるのは心遣いだろうと自惚れておく。素直に嬉しい。 30代の若さにしてこれだけの寿司を出す。筆者はやはりこの店が大好きだ。大将が40代、50代になったら、この寿司はどのようになってゆくのだろうか。 今回のメニュー(参考までに 2006年12月中旬) 小松弥助 香箱(半分)・ぶり大根・お造り(あまえび・鯛・まぐろ)・あわび(これが旨い!)・ネギトロ巻き(素晴らしく旨い!海苔もいいぞ)・がっこ。握りであわび・あまえび ・ヅケ(黒七味を軽く振ってあるぞ!)・あぶりトロ・みそ汁(鯛のあら)・あなご(ゆずと塩で)・やりいか・あまえび・あかいか・うなきゅう巻き(熱い、旨い) 日本酒は(あれ忘れちゃった) 太平寿し いか塩辛と赤なまこ(穴水の)・鯛のお造り(ポン酢とわさび煮きり)・松皮焼きのにぎり・新潟のさば造りと押し寿司・手まり寿司(香箱の外子、内子、足、崩し身・雄の足みそのせ)・たらの白子の軍艦巻き・軽くあぶったブリ(大根おろしで)・コハダ・鯛のこぶ〆(ベラボーに旨い)・赤いかのあぶり(塩とすだちで)・獅子えび ・甘えび・あか貝のひもときゅうり・ばい貝・あか貝・トロ・ヅケ・のど黒の蒸し寿司 ・穴子(塩とタレ)・いくら・鯛のあらのみそ汁 日本酒は輪島と菊姫加陽菊酒(大吟醸のひとつ前) 千取寿司 コウバコ・赤貝・万寿貝・きじはた・ひらめ・あまえび・ばいがい・ぶり(大根おろしに一味をふって)・ヤリイカ・しめさば・白子の炙りポン酢添え・さざえのつぼ焼き(麹みそで)・ノド黒の焼き。握りは、あら・ぶり・赤貝・コハダ・甘えび・ずわいガニ・かにみその軍艦巻き・穴子・まんじゅ貝・うに。つみれの味噌汁 日本酒は福光屋の福正宗 乙女寿司 ぶり・きじえび・あら・しめ鯖・香箱・やりいか・ズワイの雄の足(みそあえ)・白子のポン酢あえ(日本酒の宋玄にあう)・コノワタ(宋玄がシャープになる)・穴子のネギ巻き・玉子焼き(これがホワッとしてほんのり甘くて)・ぶりかま(目のまわり) ・白子の摺り流し。握りはこはだ・鯛のこぶ締め・ヅケ・牡蠣・うに・赤いか 日本酒は宋玄と菊姫大吟醸 |
| 戦争が終わって60年。長生きしてよかった、と思えることがひとつだけある。 やっと寿司屋にいけるようになった。 財布の問題もあるがそれ以上に寿司屋は若いモンには敷居が高い。小僧の来るところじゃねえ。とっととけえりな。という無言の気圧が充満している。感染症の研究室では事故で細菌が漏れた場合、室外に流れ出さないように室内の気圧を外よりも低くしている。そうすれば空気は室外から室内に流れ込み、細菌は外に逃げられない。陰圧という状態だ。寿司屋では金を持った訳知り顔の若僧はウィルスと同じ扱いである。しかし、ここは入れるのではなく押し返すから寿司屋の店内は陰圧ではなく陽圧だな。 寿司屋は未熟な若者に金があれば何でも買えるわけではない世界があることを教えてくれる。 寿司屋に行くなら居住地の界隈でことが足りれば問題はない。 寿司屋は本来はそういうところだろう。江戸の文化文政からこっち百四、五十年しか歴史のない江戸前においては特にそうだ。風呂屋帰りのファストフードかスナック食が成り立ちだ。冷蔵技術のない時代は新鮮なネタなんて難しいから仕事をした。しかし食文化は時代とともに変遷する。適応力がなければ廃れるだけだ。今の寿司屋は粋で |
活きが基本。活きがいいからって仕事をしなけりゃヤボって言われる。 残念ながら地元に通える寿司屋がない。 江戸にいたときにゃあ若すぎた。金にあかして銀座の寿司屋に背伸びしたこともあったけど通い詰めるなんてことはできやしない。 上方にいる今は、金沢がある。ネタは新鮮。30万の人口に比して飲食店の数が妙に多い。しかもそれが固まっている(ゴテゴテはしていないところが城下町の良さだ)。寿司屋も多い。でも、恐らくここは旨いというのは一握りのはず。ネタが新鮮すぎるからあまり仕事をしないなんて話も漏れ聞くことがある。仕事をしすぎると新鮮じゃないネタをごまかしてるなどと悪口を言われることがあるそう。しかし、金沢で食べる寿司はどれもちゃんと目に見える所も見えない所も細かい仕事をしています。 あたしゃあね、寿司屋は立ち仕事だから、元気じゃないといけないと思いますよ。金沢で食べる寿司屋で大将が椅子に腰掛けてスポーツ新聞見ながら煙草をふかしているなんて姿は想像もできゃしない。それほど忙しいしピシッとしている。そんな店に入ると「ああいいなあ」と思えるようには馬齢を重ねたってところで、いよいよ金沢寿司行の始まり・・・ってアレ紙幅が尽きちゃった。 |
| JR広島駅、呉線のホームでは4両編成の電車が待っていた。都市圏の通勤電車みたい。 ローカルの鉄則は最長で2両。普段は1両。だから4両編成を見ただけで非ローカルと見て取った筆者。住宅地を走る通勤路線なのだと読みきった筋は、しかし見事に肩透かしをくった。 単線じゃん。 行き違い停車で3分、5分はあたりまえ。何で4両編成なの?ウィークデイの朝夕には、きっと通勤ラッシュがあるのだろう。始発駅広島から呉駅まで45分強。快速で25分強。 海軍工廠のあった街、呉。 大和はこの街で造られた。全長270m、最大排水量7万2千トン、主砲46サンチ砲9門。最大船速27ノット。現在と過去を通じて世界最大の戦艦であった。2008年就航予定のニミッツ級空母第10番艦のジョージ・H・W・ブッシュは10万トンクラスだ。大和の排水量はその7割、とにかくでかかったのだ。同時代の最大級の空母加賀が4万2千トンだから、まさに巨艦である。 その大和が浮かんでいたであろう建造ドックのある港湾部に「呉市海事歴史科学館」がある。別名「大和ミュージアム」。 駅から屋根付の通路が続いている。途中、商業テナントのビルが立ちはだかるが、通路はそのビ |
ルを貫く。ショッピングモールの真中を通路が通るという実に大胆な構造だ。その先にはテラスがある。テラスに立つと目に飛び込んでくるのは潜水艦。なかなか意表をつく仕掛けだ。科学館の前には戦艦陸奥の主砲の1本が展示されている。 大和ミュージアムとの別称のとおり、呉の街造りには大和の影が大きく投影されている。ハードウェアに頼りすぎるのは危険だとは思うが人それぞれだ。大和は単に3千名強の乗組員と供に轟沈した巨大な軍艦というリアリティの域を越えてある種の精神性を身にまとわされ、超人格的存在になってしまった感がある。 ミュージアム内には十分の一スケールの大和の模型が展示されている。模型としては確かにでかい。26.3mもあるのだ。水に浮かんで自走してくれたらそれなりに楽しめるかもしれないが、いかんせん十分の一のサイズは十分の一のサイズでしか見る者に語りかけはしないのである。気恥ずかしさを感じるのは何故だろう。大和で換金術をもてあそぶのはやめたほうがよいような気がしてきた。舞鶴で間近に見た護衛艦しまかぜ4千6百トン強のリアリティの方がインパクトにおいてはるかに勝っている。防衛力(軍備)は精神世界の作用ではなく徹底したリアリズムの世界なのだ。模型と実物の違いが何かを訴えている。何を? |



呉市海事歴史科学館の展示品 画像中:零式艦上戦闘機62型 画像右:回天10型
讃岐行4(阿波・淡路編) →back 1)発動編 2)うどん編 3)高所編 4)阿波・淡路編
| 高松市街から平賀源内の生地、志度に向かう琴電志度線にそって走る国道11号。左に志度線、右にJR。ふたつの鉄道に挟まれNは幸せの絶頂にある。このまま鉄道に挟まれて死にたそう。Fは琴電を見るなり、京急の車両だと言い切った。塗装は当然代わっている。筆者の周りはマニアばかり。マニアに挟まれて死ぬ。幸せか? 波静かな瀬戸内が好きだとYは言う。筆者もこののどかな景色が好きである。 観光客は、恐らく往時の数分の一にまで減っているであろう屋島は、しかし雄大と言っていい光景を誇る。庵治石(あじいし)の産地である五剣山はあおむけになった人の横顔のようなシルエットを浮かべ、砕石場は地肌を露わにしている。五剣山の麓には源平の主戦場が広がる。義経が海から来ると読み、布陣した平家の裏をかき、源氏は右手後背から襲いかかった。左手に広がるエメラルドグリーンの海面が、今はキラキラと輝いている。訪れる者も僅かな朝の屋島は、やはり車でなければ無理だ。企画した皆に感謝である。 屋島城跡。高松港の防波堤にむかって船隊を組むように入港してくるフェリーに向かってNが叫んでいる。「撃て~!撃て~!」(・・・) 讃岐を離れ、徳島方面に南下。鳴門海峡に向かう。鳴門の渦は6時間ごとの潮流の干満時に凪と |
なりその真ん中の3時間目が最も激しくなるそうな。この日は11時頃が最盛だと言う。「源内」のカレーうどんと鳴門の渦潮の最盛時、どちらを取ると迫られればカレーうどんと答えざるを得ない。結果、渦の最盛期ははずしてしまった。 鳴門観潮船は水中の様子を眺められる小型船と400人まで乗船できる大型船の2隻で運航していた。時間の都合もあり、大型船に乗ったが揺れる、揺れる。北海道上空の低気圧の影響で四国には波浪注意報が出ているのだ。足をふんばり右舷と左舷を行き来し、潮を見る。なにか勇壮な気分になるなあ。横ではNがわめいている。 「左舷、撃て~!」「右舷、発射!」 (・・・ちょっと離れていよう) 帰路に立ち寄った淡路島、北淡町の震災記念公園内の実験室で震度7を体験。一度に9人程度がグループで参加できる。実際の震動時間よりも短いが椅子ごと倒れこみそうになった。 地震によって上下に盛り上がり、東西にずれた野島断層を縦・横に見せてくれる展示スペースで地殻変動のパワーを見る。筆者は関東出身だ。いつか来る第2次関東大震災に想いを馳せる。 明石海峡を渡って帰阪。Y、F、毎度運転お疲れ様。N、O嬢、修習きばってや。N嬢もFもYも後に続くから。 |



画像左から カレーうどん暫定日本一の「源内」 ・ 鳴門海峡 ・ 北淡町の震災記念公園
讃岐行3(高所編) →back 1)発動編 2)うどん編 3)高所編 4)阿波・淡路編
| うどん喰いの途中、満濃池に立ち寄る。 溜池と言うにはちょっと巨大すぎる満濃池。もはや湖である。 原型はすでに8世紀に築かれていたが、決壊した堤の工事を空海が指揮したことにより、空海の造作のように思われている(筆者だけ?)。空海本人の意図がどうあれ、信仰と畏敬の吸着剤としてその存在は明らかに他を圧して強い磁力を持っている。人は信じたいものを信じるのである。 満濃池を後にしうどん「山内」で過ごした後、溜まったエネルギーを放出するためにこんぴらさん(金刀比羅宮(ことひらぐう))詣でをする。やっぱ難所である。本宮まで785段。来たことあるのに、オリエンテーションがずれている。「もうここまでだよ」という嘘を5回はついてしまった。O嬢、ご免。 本宮から讃岐平野を見下ろす。讃岐富士がぽつりと据えられ、そのむこうに瀬戸大橋の橋脚がドミノのように立ち並ぶ。いい眺めだ。 次は雲辺寺である。 四国88箇所霊場のひとつ雲辺寺。88寺中、最高峰の標高927mの高みに佇む寺は、白い混沌の中にあった。なぜ毎回霧にまかれるのだ。前回は玉置神社だった。責められるN、可哀想。 四国88箇所霊場巡りは、どの地点からスター |
トしても構わない。何周してもかまわない。ゴールがないのである。通常、聖地への巡礼はゴールが定まっている。四国のお遍路は世界でも稀有な事例であると指摘したのは畏友I。なるほど。筆者も頓悟した。88箇寺を巡るイベントを企画したのは希代のイベンター空海である。彼らしい仕掛けである。人の動かし方がわかっている。 雲辺寺には妙にリアルな等身大の五百羅漢がさまざまなポーズで立っている。霧の中、いつの間にか浮かび上がる羅漢たちのシルエット。彼等に取り囲まれていることに気付いたとき思わず異界にさ迷いこんだような錯覚にとらわれた。羅漢達に意思が宿り哄笑が響き渡りそうな空間である。 この寺に至るには全長2千6百m、山麓駅から山頂駅の高低差約660mを秒速10mで山頂に到着する日本最速で支柱間距離日本最長のロープウェイを使うことができる。四国四県が一望に収められるそうな。高所と言えばFである。前回、十津川の谷瀬の吊橋で正体を明かした高所恐怖症ぶりは今回も遺憾なく発揮された。 ロープウェイからの眺望を愉しみ、ふと振り返ると蛇に追い詰められた蛙のようなFの姿。失笑を禁じえない。しかし、山頂駅につき生気を失い眼窩の落ち窪んだFを見た時深い後悔の念に苛まされた。ごめんね。でも楽しかった正直。 |



画像左から: 満濃池 ・ こんぴらさんから讃岐平野を臨む ・ 雲辺寺
讃岐行2(うどん編) →back 1)発動編 2)うどん編 3)高所編 4)阿波・淡路編
| 筆者の日常の旅では行けないうどん製麺所。かつての記事では負け惜しみから一般店で十分だとうそぶいていたが、正直に告白します。食べてみたかったっす本当は。今回は素直に楽しみっす。 製麺所3店、一般店2店を訪れた。 製麺所は「なかむら」「山越」「やまうち」一般店は「鶴丸」「源内」。 筆者は麺類に関しては「腰」派である。 「なかむら」の麺は外側のモチモチと内側の芯部の二重構造。ユルイわけではないが筆者にはものたりない。ただここのイカ天は旨かった。すべての店でイカ天が誘っている。誘惑に負け4店で食べてしまった。筆者イカ天ランキングは、なかむら・源内・山越・やまうちの順かな。 「なかむら」では「ひや・ひや」を食べた。冷たい麺に冷たいダシである。 「山越」は混んでいた。すごい行列だ。Fが行列をざっと数えた。180人は前にいると言う。でかい駐車場には誘導員までいる。なかむらにも誘導員がいたな。 お薦めの「釜たま」を食べる。釜揚げの熱々(麺)に生玉子をからめ、これに濃い目のだしをかけて食べる。だしは少なめにと書いてあるが、たぶん足りないから少し多目にしても大丈夫だな。腰にはやはり不満が残るが麺の透明度があきらか |
に違う。麺が透き通っている。出汁は旨い。イカ天のほかに玉子天まで食べてしまった。 「やまうち」は既述3店では一番腰が強い。筆者好みである。イカ天はイマイチ。ここでは冷ぶっかけを食べる。 「鶴丸」はフェリー通りにある。何度か来ていたが今回改めて腰の基準はここだと再認識。腰指数は「鶴丸」をもって百とします。強い!とても一般店とは思えん。食べたのは冷ぶっかけである。 「源内」のカレーうどんは、現在のところカレーうどん界暫定日本一である。微妙な甘さとその後からやってくる辛さ、あげの甘さ、ちゃんとしている肉とにんじん。腰が強いからカレーうどん特有の麺の中切れによる跳ね飛ばし事故がない。旨いなあ。今回はYが頼んだ「かしわうどん」のかしわ天(鶏天)も分けてもらった。うまいがな!ここはおでんも旨い。豆腐と牛すじを食べた。 うどん狂のようには数をこなせなかったが、普通の胃袋ならこんなもんでしょ。頑張ればもう少し行けたろうが夜は北古馬場通り「魚好人」で魚を食べるのだ。いくらうどんが旨いと言っても「漁好人」には叶わない。夜のために胃袋を空けておかねばならない。 うどん喰いの進撃エネルギーはそういうことで限界点をむかえたのであった。 |



画像左から なかむら・山越(やまごえ)・やまうち なかむらはネギを自分で抜いて刻む店として世に出たらしい。山越はおそらく
史上最も繁盛したうどん製麺所。画像の行列はまだまだ後まで続き、道を曲がり、ディズニーランドのような蛇行行列コーンに沿
って人々が佇んでいるのである。やまうちはいかにもな造りでしょ。
讃岐行1(発動編) →back 1)発動編 2)うどん編 3)高所編 4)阿波・淡路編
| ひとしく皆の上を刻が過ぎてゆく。 熊野の山塊を疾駆したメンバーにも人生の転機が訪れた。メンバーのうちこの春司法試験を受験した2人が両名とも合格し、11月末から司法修習に入る。社会人となるのだ。 皆が彼等の修習前にもう一度、紙ドライバーの筆者を喜ばしてくれると言う。 今回のテーマは・・・讃岐。 車でなければ行けない処、第2弾。讃岐の製麺所のうどん喰いが戦略目標となった。 メンバーは前回と同じ6名。 YとFによる讃岐攻略ルートの研究会が毎夜、天五(天神橋筋5丁目)で続く。完成されたプランはコンダクターNの厳しいチェックを経て正式な作戦として承認された。 讃岐攻略作戦(コードネーム、ファール・DUON)の骨子は以下の通り。 山陽自動車道を西進、倉敷近郊から南下、瀬戸大橋で瀬戸内海を渡海。渡海の中継ポイントは与島のサービスエリア。その後いよいよ四国上陸。西讃の製麺所のうどんを各個撃破しつつ、満濃池に寄り、さらに近隣の製麺所を制圧。 作戦の第2段階は、琴平神宮に登頂、讃岐平野の眺望を確保。余勢をかって日本一のスピードと長さを誇る雲辺寺ロープウェイを占拠。雲辺寺を |
詣で高松市街に入城。ここで一夜を過ごす。 翌日、八島急襲後、羽立峠に進出し、徳島方面を扼す。作戦の最終局面である。鳴門海峡を海陸両面から攻略。すなわち海峡と鳴門海峡大橋を確保し、淡路島を南端から北上、北淡町の震災記念公園で慰霊後、明石海峡大橋を使用して瀬戸内海を渡海し、勝利の凱旋。と、いう気が遠くなるような遠大な構想である。 11月中旬。作戦は発動された。折悪しく発達した低気圧の影響で山陽自動車道は強い雨に打たれていた。時折フロントグラスが真っ白になるほどの雨足だ。 瀬戸大橋を渡る。 線路と道路が二重構造を成す瀬戸大橋、上部の道路で渡るのは初めてだ。下段の鉄道では上部を道路に塞がれ、側面の橋梁骨格が断続的に視界を遮るのが難点であった。さすがに眺望がいい。 渡橋の途中、瀬戸内に浮かぶ与島に降りる。車を留め、長大な橋を下から眺める。頭上の橋を通過するJR瀬戸大橋線のダイヤが掲示されている。ワクワクしながらそれを待つNとF。「特急うずしお」と「マインライナー」に歓呼の声を送っている。無論、筆者は見ているだけだ。 そして讃岐に上陸。 うどん製麺所を次々に襲撃する筆者達。 |

 画像右: 通過中の「うずしお」 わかります?
画像右: 通過中の「うずしお」 わかります?
金沢行12 →→→back 金沢行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
| オン・オフのスイッチが壊れかけている週末。 切り札を切るときが来た。 逃げるのだ。金沢へ。奇跡的に翌日の宿が確保できた。奇跡的に乙女寿司の予約が取れた。幸運の女神が筆者に微笑んでいる。 土曜日11時13分入沢。 北陸地方は、天候の崩れる太平洋側とは対象的に、この日快晴。哀しくなるほど澄みわたった秋空の青さが広がっている。 寛いでいる暇はない。今日の夜、乙女寿司でなんとか確保した席は17時から19時までの2時間。昼食をのんびりとっていたら、夕食までの間が短かすぎて空腹で店に行けなくなってしまう。 タクシーで小立野通り2丁目交差点前、グリル「ニュー狸」にむかう。 11時40分には入店。いまだに謎の味、こげ茶色のヤキメシと能登牛のヒレカツを食べる。 食後、散策をかねて小立野(こだつの)通りを香林坊に向かって歩く。福光屋(酒蔵)の販売所で先般千取寿司本店で飲んだ日本酒を購う。兼六園脇の広坂休憩所で足を休め、ホテルにチェックイン。長町界隈を流し、消化を促進させる。 夜(というか夕方)半年ぶりの乙女寿司だ。 お造りはアラ・バイ貝・しめ鯖。 次いでブリ。1ヶ月は早いブリ。君に出会える |
とは思ってもいなかった。なんという幸甚。旨いがな!ブリの最盛期前に先陣を張る今の時期、実はかなり旨いのだと言う。このあとの二陣、三陣は駄目で、後はブリおこしと共にやってくる本軍を待つのだそうだ。ラッキーである。 アカイカ。香ばしいゴマの香りを嗅ぐたびに乙女寿司に来ているのだとの実感が湧く。日本酒は能登誉の純米吟醸と珠洲の酒宋玄。 なめら(ハタの一種)の塩焼きにかぶりつく。脂たっぷりのぷりぷり感がたまらない。ガスエビの炙りを頭からガブリ。香ばしい~♪あじのたたきは細かく刻んだ白ネギとコンブだしの味わいが絶妙である。かさごの薄作りは青ネギをまいてポン酢で。これはスゴかった。タコを塩とカボスで食べ、いくらをつまむ。 握りは、あまえび・なめら・づけ・しめ鯖・穴子・かれい・ひらめのこぶ締め・はまぐり。締めの味噌汁がまたしみじみといい。堪能した。 北国新聞社屋のそば、おでん「よし坊」でおでんと日本酒を少々。 翌朝、10時に金沢駅構内のおでん「黒百合」でおでん定食とふぐの糠漬け、硬豆腐を食べる。現在のところ、筆者の金沢おでんナンバー1はここなのである。10時52分のサンダーバードに乗って帰阪。完璧な週末であった。 |



| 塩釜の寿司屋は記憶の味となっている。 17年前のことだ。 嚢中、寒風ふきさすぶ若かりし頃だ。寿司屋なんて怖くて入れたもんじゃなかった頃だ。昼のランチを食べるのがいっぱいいっぱいである。 塩釜と言えば、日本有数の水揚げ量を誇る漁港である。朝水揚げされた魚を昼には食べられる。 特上が2400円だった。カニの味噌汁がついていた。当時の経済力では大散財だったが旨かった。 塩釜であの寿司を食べ、松島に行ってみよう。 17年ぶりの仙石線の旅。仙台、石巻間を結ぶこの路線も昔は地上を走っていた。中央線のオレンジ色車両に乗った記憶が朧に浮かぶ。もしかしたら常磐線の青緑色だったかも、あるいは山手線の緑?記憶は限りなく淡い。しかし、地上を走っていたのは間違いない。仙台駅が始発であった。 今では市街地を出るまでは地下鉄である。始発駅も仙台の先に「あおば通」という新駅が出来ている。車両も近代化していた。なんということだ中央線の方が昔のままではないか。 仙台の地下ホームを出て、本塩釜まで30分弱。 駅のそばにある店に向かう。 あった。 遠い日の記憶のままのカウンターに腰を下ろし特上にぎりを頼む。あれ?カニの入った味噌汁が |
別料金になっている。昔はセットだったよな。原価をおさえる努力ということか。 皿の上の寿司をつまむ。 思い出の味は、少ししょっぱかった。嗚呼、知らぬ間に自分は随分豪奢な食体験をするようになってしまったんだなあ。反省をすることではないが、生来の貧乏性が頭をもたげ、自分を責め苛む時もある。長続きはしないが。 仙石線を乗り継ぎ、「松島海岸」駅に向かう。 駅から5分程度で遊覧船乗り場だ。駅前ですでにチケット販売をしている。複数の会社船が運航しているらしい。販売競争をしているのだ。 途中、浜焼きの店が軒を連ね、香ばしい香りが周囲に漂っている。帆立にいか、さざえが旨そうに網の上で焦げ目を見せている。しまった、寿司にせずここで食べればよかったかも。 遊覧船で松島湾を周遊する。 松島湾は海水の循環が活発ではないのだろう。海はあまり綺麗とは言えない。カモメの群れが客の撒く餌をついばむため船の周囲を飛び交う。それなりに楽しい絵だ。 その日、筆者は松島五大堂の33年に一度の盛儀「御開帳」にめぐり合えた。33年に一度だからね、前回は昭和48年だ。西暦1973年、筆者12歳の時である。ま、言ってみただけです。 |



| 早暁。夜も明けきらぬ刻限、寝具を抜け出し海岸に向かう。南紀勝浦の朝である。 宿泊中の国民休暇村は高台にある。海水浴場と磯場へは予想より長い石段が下っている。 昇りきらない朝日の弱々しい光は周囲の樹木に阻まれ、梢に覆われた遊歩道は、いまだ黎明の中にある。ちょっと不気味と言い換えてもいい。多少、怖いぐらいだ。 (かさかさかさ) 不意に足元で音がした。 暗がりの中、石段の端へ赤いものがすばやく身を隠した。 (何!?) たじろいだね、ちょっと。しかし正体がつかめない。さらに石段を下る。 (かさかさかさかさかさ) もはや目をこらす必要もない。数歩先の石段に赤い生き物が蠢いている。 カニだ。大小のカニが磯からここまで登ってきたのだ。足元に広がるカニの群れ。なにごとにつけ度を越した量というのは恐怖の対象となる。背中が総毛だったのは事実だ。 カニを踏み潰さぬよう石段を降り磯場に出る。波浪の影響か。流木が積み重なり、荒れ果てた景色が広がった。遥か沖合いでは高波が岩礁を洗っ |
ている。 日が昇り始めた。 雲の切れ間から淡い陽光が鉛色の海面に一条の光を落としている。荒涼とした感じで和めるような風情ではない。筆者は先ほどよりは明るさを増した木下闇の石段を登り、宿に戻った。 普段摂取しないような大量の朝食を胃袋におさめ、熊野ツアー御一同は見送りの狸の親子と別れを告げ、勝浦をあとに那智の滝に向かった。 九州方面に上陸した台風の影響で紀伊半島の東岸は吹き付ける波浪と山塊にぶつかる雨雲が充溢し、到着した那智はむせかえるようなマイナスイオンに満たされていた。山中は水蒸気に煙っている。着衣がしっとりと濡れているのは、霧のせいか、雨のせいか、靄のせいか、滝のせいか、もはやわからない。わかったところで意味もない。 那智の滝は全開である。 蛇口を目一杯開放しているような水量だ。出し惜しみはなし。耳を聾する飛瀑の音。 見上げる山上は水蒸気に覆われ、空と地の境目も危うい。折悪しく水滴が大きくなり、雨雲が上空を覆ったことがわかった。 那智は水浸し。 しっとりを通り越してびっしょり。ズブ濡れである。十分に堪能した。日本は水の邦である。 |



| 朝4時。 諏訪湖周回道路を対岸の上諏訪から下諏訪にむかってヘッドライトの車列が近づいてくる。 日の出の時刻5時半までにはまだ間のある今、夜はまだ明けていない。周囲は漆黒の闇である。 筆者は下諏訪の湖畔のホテルに泊まっている。 眼下には諏訪湖が広がり対岸の上諏訪では背後の山腹まで伸びた街の灯りが静かに瞬いている。 車の群れは続々とホテル下の駐車場を埋め尽くしている。人々が吐き出され、大きなプレハブ建てに吸い込まれてゆく。何やら細長いものをかついで湖に向かってゆく人々。十数分後、湖面には10艇ほどの5人乗りレガッタが浮かんでいた。 日が昇り始める頃には湖の一画が簡易な堤防に守られたレガッタ専用のコースとなっていることに気がつく。ミズスマシのようにオールが湖面を掻き、丸い波紋と細長い航跡を残してゆく。 長野ってレガッタ、強いの? 諏訪は冷える。彼岸を過ぎれば春の彼岸まで冷え込み続けると言う。冬季、諏訪湖は一面の氷に覆われる。零下15度くらいの日が20日も続けば両岸から成長してきた凍結が湖の中央でぶつかりあい、盛り上がり現象が起こる。上諏訪から下諏訪にむかって氷の竜骨が出来上がるのだ。これを御神渡り(おみわたり)と言う。 |
諏訪湖は北上すれば松本を抜け越後に至る。甲州街道は南下し、関東の沃野と通じている。諏訪は越後の虎「上杉」と関東の覇者「北条」と甲斐の「武田」の三つ巴の最前線であった。諏訪湖の北西部にある塩尻は越後から遠征してきた上杉の糧食の限界点である。塩が尽き、謙信は春日山に兵を戻す。塩の尽きる処、だから塩尻である。 甲州街道は諏訪湖畔「錦の湯」で中山道と交錯する。その中山道を北東方向に上ると御柱祭の舞台「天下の木落し坂」がある。 さらに北上する。和田峠で旧道に移り、迂回路を登ると「八島ケ原湿原」が標高1630mの位置に広大な野を寛げている。高地を吹き渡る風は思いのほか強い。高い木が生えず、まるで北海道の野のように潅木と下生えの草原が峰を覆っている。木が育たないのは風のせいばかりではない。この湿原の先には霧ケ峰がある。1年のほとんどを霧に覆われる峰。陽光不足も植生の条件の一端を担っているのだろう。 霧が峰にはグライダーの練習場もある。 峰を下る。途中、立石公園で諏訪湖を一望のもとに見渡す。足下に上諏訪の街が広がる。周辺には浮城の異名をとった高島城、今やバルブの開閉によってしか吹き上がらない間歇泉、「タケヤ味噌」の工場兼販売所などが並んでいる。 |



| 遠く南アルプスと北アルプスに囲まれ、東は八ヶ岳、西は木曽駒ケ岳から乗鞍岳に塞がれる標高760メートルの窪地に周囲から十数河川が流れ込み、湖が出来上がった。信州最大の湖、諏訪湖である。 湖は注ぎ込まれる水を蓄え、注ぎ口は唯一、天竜川のみである。 茅野から下り降りる中央本線は諏訪湖の周囲を廻り、上諏訪と下諏訪、ふたつの街に駅を持つ。 筆者は9月の末日、下諏訪を訪れた。初秋の爽やかな風に包まれた静かな街である。 諏訪には日本最古の神社のひとつ、諏訪大社がある。上諏訪、下諏訪に散在する4つの社の総称が諏訪大社である。上社の本宮と前宮、下社の春宮と秋宮で4社を構成している。 下諏訪には下社がある。神は毎年、これらの社を渡り歩く。9月の今、下社には神はいない。 諏訪大社の神事は7年に一度の大祭「御柱祭(おんばしら)」全長16メートルの樅の木を氏子を乗せたまま100メートル弱、斜度35度の木落し坂から引き落とす。氏子は、つかまるものも何もない裸木に乗ったまま落下する。 坂にせり出した御柱を坂の上から引っ張る役と下から引っ張る役がいる。坂上で綱を離すのと下から引っ張るタイミングが一致しないと御柱は坂 |
の途中に突き刺さるように落ちてしまう。すると柱はまっすぐに坂を落ちずスピンをするように転げ落ちる。危険なケースだ。 祭りに使う樅の木は周囲3.5メートル弱、樹齢200年程度の木を3年前から見立てておく。切り出し、枝を打ち、皮を剥ぎ、綱を通す穴をあけ加工し、祭りが近づくと坂を落とし、川を渡り、坂落としの坂まで5キロの距離を運ばれる。コロも使わず、綱をかけた16メートルの樅の木を人力で引き回すのである。 都合8本の御柱を引く役回りは部落ごとに決められ、今も当時の分担区域が変わらず守られている。人手を集めるためこの期間、里帰りする人が多い。お役目を忌避し、旅行になど出かけようものなら村八部は必定だ。 祭りは複数の救急車が待機している。ただし、この祭りで死者は出ない。病院に担ぎ込み即死扱いにはしない。死者が出たことで祭りが廃止されることを妨げるためである。死亡による障害保険もその為おりない。祭りは永続される。 御柱の通り道の家々は祭りの期間、誰が入ってきても酒食をふるまわねばならない。100万ぐらいはふっとぶと言う。ために7年に1度の祭りの年には冠婚葬祭はご法度だ。葬は時を選べないが仮のものとして本葬は翌年にするのだと言う。 |
仙台行2006 →→→back 仙台行 1 2 3 4(2006) 5
| 知らない間に6年という歳月が流れていた。 あまりにも身近で気安い街だった仙台だが、大阪に来てから一度も行っていなかった。都市間の移動時間は東京よりも大阪からの方が短いというのに。東京仙台間に航空便はない。最速の「はやて」で1時間40分である。伊丹仙台間は1時間10分。空港から仙台市街まで40分あるけどね。 昔からこの街を歩いていると、地方都市にいる気がしない。東京や大阪の繁華街を歩いているのと何らかわらない浸透圧がそこにある。 知らない間に牛タンが全国区になっていた。今や、情報は何の苦労もなくネットやマスコミで手に入る。出会う前から知っている状態が基本。人はリアルとヴァーチャルの境を飛び越し共有情報が潤沢である。かつて訪れた店と言えど心せねばならない。混んでいるに違いない。並んでいるに決まっている。 今回は牛タン食べ比べだ。「太助」「利休」「喜助」の3店に行った。(喜助の『喜』は七が三つ、PCでは変換できない。店名はネットのことも考えよう) タンの厚さは、太助>利休>喜助だ。味は、筆者の好みでは、太助>利休>喜助である。筆者は25年前から「太助」至上主義なのでそこのところは、ひとつ。今回「太助」が2店あることに気が |
ついた。「味太助」と「旨味太助」である。筆者が昔から通っていたのは「味太助」である。 「かき徳」の「かき豆腐」は酒にあう。「かきフライ」でビール。クリーミーでジューシーというよりはふっくらと柔らかく丸めた感じ。 蓑寿司に行く。威勢のいい大将は魚好き。魚の話になると止まらない。『鯨が鰯を喰いまくっとる。魚偏に高いと書いて「いわし」となる日がくるんじゃないか』『今年はしんこが高かった。銀座でキロ1万6千円がついたら、もう赤字必至、寿司屋の意地で出している』と話はつきない。 店は広瀬通り江陽グランドホテルの裏にある。 つきだしは三陸の黒もずく、お造りはひらめ、赤貝、本マグロ、煮ダコ、アテにししとうをすずきで巻いた揚げ出し、かつおのたたき(これは★★★である)白焼き。日本酒は店オリジナルの「蓑」。ベースは「蔵王」らしい。旨いので3杯飲んだ。〆あじの磯巻きは海苔の香り高く旨い。さんまの刺身も★★★。 にぎりに入る。本ミルのヅケ、しんこ、あわび(★★★だ)、マグロ霜降り、ひらめえんがわ、まいか、くるまえび、生あわび、かつおの砂ズリ、しじみの味噌汁で玉子焼きとたくあん。満喫である。会計は金沢・福岡・徳島の1.4倍。こんなとこ東京に似なくてもいいのに。 |
| 平泉は岩手県の南端にある。宮城県との県境付近、仙台から東北新幹線で一ノ関まで2駅、一ノ関からほぼ1時間に1本という東北本線で2駅でである。駅前に「わんこそば」や「前沢牛」関連ののぼりや店があるのは、南端とは言え岩手県領にあるせいだ。 平泉と言えば、中尊寺である。奥州藤原氏4代の栄華の象徴。駅から約1.6キロ、途中「義経堂(ぎけいどう)」のある「高館(たかだち)」や平等院鳳凰堂よりもひとまわり大きかったとされる「無量光院」建立の地もある(跡地である。何もない。のどかな草場だ)。 高館は義経最期の場であるとされている。頼朝の圧力に抗しかねた泰衡が義経を急襲、不意をつかれた義経が妻子共々自害した衣河館が建っていたと伝えられている。「夏草や兵どもが夢の跡」芭蕉が詠んだのがこの地である。低い山頂から北上川のゆるやかな流れとその両岸に広がる豊かな青田、背後に聳える束稲山の景色が奥州の豊穣を想起させる。 中尊寺にむかう下り坂で野良姿のおばあちゃんとすれ違う。5,6メートルむこうからニコニコしながら「おはようございます」と明るい挨拶をかけてくれる。いいな、やっぱ東北だ。 中尊寺の寺域に入る。かなり勾配のある参道を |
あえぎつつ登る。広い。杉木立の参道の途上、そこここに堂宇が現れる。全盛期には堂塔40僧坊300が建てられていたと言う。薬師如来坐像・大日如来坐像・千手観音菩薩立像・騎士文殊菩薩四眷属像など仏像マニア垂涎のお宝も豊富だ。 杉木立が切れ、敷地が広がりをみせた寺域の左翼に金色堂が現れる。ガイドブックを見るたびに(金色じゃないじゃん!)と心の中でツッコミをいれていた物件である。今回初めて謎が解けた。写真で見るあの堂は、金色堂を風雪から守る覆堂と呼ばれる建造物であった。金色に耀いていないのは道理である。金色堂はあの中にあった。(な~んだ)って俺だけ?知らなかったの。漆塗りの上に金箔を塗った他に類例を見ない木の瓦屋根5.5メートル四方の堂には清衡・基衡・秀衡のミイラと泰衡の首が眠っている。覆堂は鎌倉時代にも作られている。やはりいつの時代も人間の考えることは同じってことですか。 「五月雨の降り残してや光堂」また芭蕉である。 平泉の周辺は豊穣な穀倉地帯であり、餅の邦である。平泉レストハウスで「弁慶力餅」を頼む。ずんだ餅・あんこ餅・なめこ餅・しょうが餅・雑煮餅がセットになった物件である。いけるね。接客の心配りなども東北の順良さに満ち、心なごむ一食であった。 |



| 「小京都」って言葉を聞くと京都っ子は目一杯これを馬鹿にする。これは彼等だけに与えられた特権であるが筆者も実はあのての表現は止めた方がいいんじゃないかと思う時、思う場所がたまにある。起源が近代以前、都への憧憬からという純粋なものであれば承認。観光誘致のため、何も知らない女子供を欺こうとするのならば却下である。十分魅力ある街並を首都礼拝主義の生贄に捧げる愚にはシビアな視線をむけてしまう筆者。 龍野は兵庫県にある。姫路から姫新線で約20分。鄙びた静かな旧城下町である。 「播磨の小京都」とうたわれているが、それはちょっと言い過ぎ。町並の平仄が整っていないのである。古い建築物に補修の手を加える予算も少ないのではないだろうか。一部の物件を除き古いものはより古くすすけ始め、新しいものは少しだけ古いものにあわせてはいるが、どういう町並を作りたいのか目標が不鮮明な印象をうける。 町造りって難しい。 とは言え、ガイドブックなどに煽動されて過度な期待を抱きさえしなければ、のんびりとした時間を過ごすことができる町である。 JR本竜野駅から旧城下に至る道筋が龍野の顔である。揖保川の川端にはヒガシマル醤油の工場が建つ。空に聳える煙突がなぜか醤油工場のイメ |
ージを際立たせている。 揖保川の軟水、赤穂の塩、播州平野の大豆と小麦が龍野に日本初の薄口醤油の製造と素麺の生産という機会をもたらした。 日本最古の土蔵の白壁や、醤油蔵の黒い焼き板塀、町中を流れる幾つかの小川(用水?)のせせらぎが心にやすらぎを与える。小川の脇、如来寺から城にむかう。背後に一山が樹木をまとい端座している。名を鶏籠山(けいろうざん)と言う。かつて播磨・美作・備前を治めた赤松氏の一族により山頂部に山城が築かれていた。徳川期に信州から入部した脇坂氏が城下町を形成させるが、その際、天守を設けることなくほぼ現在の位置に御殿式の築城がなされた。すなわち鶏籠山の麓にある櫓門、本丸御殿、隅櫓がそれである。ただし、これらはすべて近年の再建物である。 この小さな古い静かな町が生んだ郷土の誇りは童謡「赤とんぼ」の作者三木露風、昭和20年8月14日、終戦阻止を目論む過激派将校の部隊を鎮撫(宮城事件)した東部軍司令、田中靜壹大将(8月15日正午の玉音放送の無事放送を見届け、8月24日自決)などである。いずれもこの地に来なければ、知ることのない人々ではある。筆者にとっては、素麺揖保乃糸やヒガシマル醤油がこの地にあったということの方が身近な驚きではある。 |



| 明石の「魚の棚(うおんたな)商店街」の西端から海にむかってすぐ、淡路島の岩屋にむかう明淡高速船、子午線ラインの乗り場がある。流線型のいかにも高速そうなクルーザータイプの船がここから出港する。 9月初旬の一日、筆者は明石海峡の前に佇んでいた。山はもう飽きた。今度は海だ。 東には雄大な明石海峡大橋がそそり立つ。目の前には手を伸ばせば届きそうな近さで淡路島が浮かんでいる。子午線ラインは、瀬戸内海を挟んだ対岸、淡路島まで僅か13分で渡海する。料金は500円。往復割引運賃が900円だ。 乗船したが、空調の効いた船室などに収まっているわけにはいかない。操舵室の後背、上部デッキのベンチを占拠する。船は軽快に出港した。 爽快である。天は抜けるように蒼く、海はエメラルドに耀く。筆者は、腹の底から声を出していた。「これはいいぞ!」 明石海峡大橋がぐんぐん近づいてくる。 本州と淡路の中間地点は白波が立つほどに波が荒い。船も若干ローリング気味だ。右舷から左舷に身を移すには何かにつかまりながらでないと転げそうである。 やがて見上げるような高さの明石海峡大橋を潜り抜け、あっと言う間に岩屋に到着だ。 |
小さな漁港である。しかし歴史に彩られた港でもある。港の前に地続きとなっている出島は「絵島」。福原に遷都した平家が海峡を渡り、月見の歌会などを催した島である。 東に磯場が見える。近づけばあまり整備されていない様子だ。差し渡された板が対岸に渡った瞬間にずり落ちて戻れなくなった。それほど危険な磯場ではないが、岩の反対側にまわりこむしかない。途中僅かな幅で岩の切れ目があり、これをまたぐため岩に抱きつきながら足場を探るような真似もした。子供の頃なら躊躇なく飛び移り飛び降りる距離も高さも、その感覚を失ってすでに久しい。生命体として自己の運動能力の見積もりができないのだ。老いを感じる瞬間だ。(嫌だ!) 鳥の山展望台は、急勾配の坂の上にある。尾道を想起させる家並と坂の融合した一画を抜ける。たどりついた展望台は、整備の手がとどいていないようだ。夏草が視野を遮り展望はよろしくない。 林屋という魚屋が営む寿司屋があるらしい。記憶にはあったが、場所の見当がつかず、次回への持ち越し案件とした。港のそばの寿司でも天ぷらでも何でも出します然とした店で寿司を食べる。これがかなり旨いから恐ろしい。悪いけど、この間食べた塩釜の寿司屋より旨いと思っちゃった。 |






| 雲煙万里の彼方にある高野山と比べ、比叡山は近い。京都市出町柳駅から叡山電車で終点「八瀬比叡山口」迄14分。駅の周囲は山懐の気配漂い、駅前を流れる高野川が鄙の雰囲気を醸し出す。叡山ケーブルに乗り換える。全長1.3キロ、標高差561mは日本一だ。足元に山の冷涼な空気が吹きつけ涼しいと言うよりは肌寒い。乗車9分。比叡山ロープウェイに乗り継ぎ山頂迄2分。標高は850m弱。気温は9月初旬9時すぎに19度。 山頂からはシャトルバスも出ているが、徒歩にする。杣道の下り坂が続く。 叡山は三つの地区に分割されている。地区名は「塔」と呼ばれる。東塔・西塔・横川の三塔十六谷が叡山の領域だ。東西の塔を歩くことにする。 山頂からの道はやがて東塔と西塔への分岐点に至る。西塔に向かう。最澄(伝教大師)の眠る「御廟」が杉木立に囲まれた階段の下に静かに佇んでいる。さらに奥に進む。ふたつの堂を橋のような回廊で結ぶ「にない堂」の前で修行僧が団体で唱和している。読経のコーラスはなかなかにいいものだ。さらに下ると「釈迦堂」の大きな屋根が見えてくる。「釈迦堂」の先に信長の焼き討ちを免れた唯一の堂「瑠璃堂」がある。400年前、叡山は信長に殲滅戦をしかけられた。叡山のすべての堂塔は灰燼に帰したが、この堂だけは戦災を |
免れ、今に至っている。山道を歩きながら、信長軍の将兵が山内の道を埋め尽くし、堂塔を囲み、そこに居るすべての者を殺戮しようとするイメージが浮かぶ。山道をかきわけ、隠れた堂塔のすべてを捜索し火を放つ兵士の視線が手持ちカメラの映像のようにゆれ動く。荒い呼気の効果音付だ。 瑠璃堂には殺戮から逃れようとした人々が息を殺して潜んでいたのだろうか。 来た道を引き返し、東塔に向かう。 エリア名と同じ「東塔」の朱塗りの姿が比叡山の緑を背景に美しく際立つ。 最澄自作の本尊薬師如来像の前に、1200年不滅の法灯が灯り続ける「根本中堂」が叡山の中心である。不滅とは言うが、根本中堂は信長以前にも叡山の武装解除を計る権力から何度かの攻撃を受け、焼失している。根本中堂の中、内陣は立ち入り禁止だが、参拝者の立ち入る中陣・外陣より低位置にある。薬師如来像を中心に石畳の床の上に法灯や読経の座が据えられている。内部はかなり暗く、荘厳な気配である。かなりいいぞ。 東塔をぬければ、全長2キロ日本最長のケーブルカー坂本ケーブルの延暦寺駅がある。麓で日吉大社の参道を下りJR比叡山坂本駅前に出る。新快速駅停車駅なのでここから新大阪まで一直線である。叡山を西から東に抜けた1日であった。 |






| 高野山の山上、海抜900mに空中都市がある。 弘法大師、空海が開いた密教の都だ。堂塔、塔頭が奥の院を鎮めに多数散在し、一大宗教都市を形成している。その華やぎが地上数百mの高みにあることを忘れさせてしまう。 しかし高野龍神スカイライン、高野山道路、いずれのルートであれ、この都市に向かうか、この都市を去るか、その時に人は思い出すのである。この街の高みを。そして下界からの懸絶を。 山上を開削したのか、すでにあった平地を利用したのか、いずれにせよ壮大な建築事業である。空海という「おやま」の開祖の経歴を考えれば開削したと考えたい。讃岐、満濃池の造作、全国にある弘法大師由来の湯治場、天邪鬼との橋かけ説話など、空海には土木建築の逸話が多く、そのスケールも大きい。 だが、空海はなぜ都からかくも離れた紀州の山岳地にその根拠地を定めたのか。 最澄の比叡山は京の北東、鬼門を固めるために都の隣接地に公費で造営された。 高野は山城の平安京から遠く、旧都、奈良仏教の巣窟、平城京からも十分に遠い。 山岳地に宗教伽藍を据えるという発想は、くしくも叡山と高野双方の特徴である。最澄と空海、両名が留学した唐の寺院、天台山も青龍寺も山岳 |
や高台にあった。彼等以前の南都六宗の寺、南都七大寺は平城京の周囲、比較的低地に建立されていたものと思われる。2人は、教義や体系、精神と一緒に寺院の建立法すらも根こそぎ持ち帰ったということであろうか。それは唐帝国への憧憬そのものの行為であったのか。 国家経費によって育てられた純粋培養物のように生真面目な最澄にはけれんみのない人格を感じるが、空海は大手広告代理店のやりてディレクターのようなけれんみたっぷりのキャラである。 その彼が、高野山を選んだ理由は? 権勢から離れ、しかし、その存在は北斗のごとく耀き続け衆情の中にあり続ける。そのためには距離と仕掛けが必要だと知っていたのだろうか。そしてその読みはあたり、叡山のように権勢に掃滅をしかけられることもなく、徳川家光、前田利長、石田三成、伊達正宗、豊臣秀吉、明智光秀、武田信玄、織田信長、など脈絡もなく多くの武将の墓が置かれ、現代においてさえ一流企業の供養塔が一般の墓石とともに並んでいるという巨大教団の基石を築いたのであった。 あたりである、空海。即身成仏という自らの体を使って大仕掛けを施し、山に登らせるという山岳信仰との習合をも計ったか。ひとりの天才の巨大構想は1200年を越えてなお眩しく輝いている。 |



画像左から UCC(コーヒーカップ) キリン(麒麟) 写真業界(フィルムロールの芯と写真乾板)
仙台行3(ダイバート編) →→→back 仙台行 1 2 3 4(2006) 5
| 「ダイバート」とは、旅客機が目的地に着陸できず、最寄の空港へ避難着陸することを言う。 伊丹発、仙台行きANA731便8時5分発に乗ろうと身支度を整えた筆者が家のテレビを切ったその瞬間、画面は仙台という文字とともに一面の乳白色を映し出していたように思えた。 伊丹空港の九州方面行きサインボードは各便「DELAY(遅延)」のオンパレードだ。九州に台風が接近し、今日にも上陸しようという状況なのだ。しかし、台風の影響がないはずの仙台便にもメッセージが流れているではないか。 「視程不良のため羽田に向かう場合があります」 仙台は今、濃霧に包まれているらしい。 (やっぱり)脳裏にあのテレビ映像が浮かぶ。 それでも機は定刻通りに離陸。眼下には一面の雲海が広がっている。雲の中から円錐状の影が顔を出していた。富士山である。 機長からのアナウンスが流れた。仙台空港の視界は依然不良らしい。安全な着陸に困難をきたすレベルだと言う。目的地に向かうが羽田に引き返すことがあるかもしれないとのこと。 9時15分、仙台空港上空に到達。 視界は依然不良。再び機長からアナウンスがある。着陸ができない。30分ほど旋回、上空待機し、状況の好転を待つとのこと。 |
そして30分後、状況に変化はなく、機は羽田に向かうことになった。ダイバートである。 9時15分には仙台空港に降り立っていたはずの筆者は10時、羽田の地上送迎デッキにいた。タラップで地上に降ろされバスでゲートまで送られたのだ。航空券の半券と引き換えに封筒を渡された。封筒の中には1万2千円のキャッシュ。羽田から仙台までのJR指定席料金とほぼ同額だ。 お盆明けとは言え、夏休み中の今、東北新幹線のチケットが容易に入手できるとは思えない。モノレールで浜松町に急ぐ筆者。東京までならば京急よりもモノレールの方が早い。浜松町から東京まで京浜東北線で1駅だ。浜松町で新幹線の自動券売機にとびつく。案の定、グリーン席も含めて「×」の嵐だ。しかし10時56分の新幹線「はやて」の指定席に「△」がある。喫煙車両だが好みを言っている場合ではない。券を購入した。 隣席でタバコを吸うたびに、口にハンカチを押し当てるデモンストレーションを敢行し、周囲の喫煙を牽制しつつ、仙台についたのは12時37分。霧はすでに晴れていたがこの日到着予定の3便、出発予定の2便が欠航していた。 空を見上げ、3時間前に一度、ここまで来ていたのだと思うと、複雑な気分である。 (やっぱ、なんか腹立たしい) |
| 熊野川の谷川ツアーとなる瀞峡(どろきょう)の観光遊覧船はウォータージェット推進である。水を吸い込み、吐き出す力を推力としている。 「レッドオクトーバーを追え」か? 十津川もそうだが、紀伊半島のこのエリアは完全に外界から鎖されている。瀞峡も同様。質量感あふれる山塊を熊野川が永い年月をかけて削り続け、30キロ強の渓谷美を作り上げた。山峡にわけいった人間が偶然見つけたであろうこの渓谷は人知れず刻の流れとともにあり続けたのだ。 遊覧船乗り場へは、旅館の脇の階段を下りてゆく。思いの外段数がある。渓谷の底部までそれだけの高低差があるということか。 瀞八丁と呼ばれる渓谷を上瀞まで遡上し、旋回し下流の下瀞へと巡る遊覧は20分ほど。あっと言う間に終わってしまう。 下船した一行は、熊野本宮を目指し、熊野川を下流に向かう。 Nの組んだ今回のツアーは世界遺産熊野を縦横に巡る。紀伊半島の山塊踏破距離は半端ではあるまい。今まで十津川街道から玉置山に寄り、縦貫し瀞峡までやって来た。この後、とって返し十津川街道に復帰する。ただし未走破の部分である。その街道を逆行すると熊野である。本宮と熊野古道に足を踏み入れた後、熊野川沿いに十津川街道 |
を下り海岸部の新宮に出、南紀勝浦へ。那智の滝を巡り、往路の十津川街道を遡上、本宮から熊野街道で半島を横断、美人の湯で知られる龍神村から北上し高野山に寄って帰阪しようという修験道のごとき企画なのである。書いているだけで心が洗われる。 熊野本宮は3本足の八咫烏(やたがらす)をイメージキャラクターとして多用している。八咫烏は、神武東征の道案内をしたことから交通安全の守り神にもなっている。 杉木立の先、階段を登ると本宮、本殿がある。古錆びていながら格の高い調べを謳いあげているようなその姿はなかなかにいい。 「この奥に熊野古道がありますよ」 Nが先導し、熊野古道にむかう。1歩でいいから道に足を踏み入れておきたい「熊野古道?歩いたよ」と言うためである。 しかしNが指さす熊野古道は舗装された普通道であった。 (これが熊野古道?) 筆者の前を軽トラックが走りぬけていった。 古道じゃないじゃん。新道じゃん。首をひねりダッシュするN(Nはダッシュが好きである)ダッシュに意味はなかったが、それらしい古道っぽい道を別途見つけ、消費は完了した。 |



| 日本最長の吊り橋「谷瀬の吊り橋」。 「一度に渡るのは20名まで」という注意書きはあるが番人がいるわけではない。 揺れる、揺れる。こんなに揺れるとは思ってもいなかった。高さ54m、かなりの迫力だ。 Fは高所恐怖症である。筆者の15階の部屋のベランダの端に立てないくらいの重傷。それを知る筆者は(Fには無理だ)と思った。筆者自身、橋の揺れと高さに順応するのに多少時間がかかった。しかし、渡り終わって振り返れば「かつて経験のないくらい思いっきり握り締められた(本人談)」と同行のN嬢の証言にある通り、取り押さえられた宇宙人か引き回されるオリバー君のようなFがN嬢の手にすがりつつ、よちよちとこちらに向かっているではないか。(すごいガッツだ)筆者は少し感動した。 女性人の一翼、O嬢は、渡り終わってまだ地面が揺れていると言う。しかし、十津川の郵便配達はこの橋をスクーターで渡ると言う。 吊り橋を満喫後、谷瀬からさらに南下、ダム湖のまわりをうねうねと廻り、廻り飽いてもまだ廻り続け、やっと村役場のある平瀬に出た。久しぶりに目にする交差点がある。 平瀬とは言うが猫の額のような地である。集落と言うのもはばかられるようなそこに歴史民族資 |
料館がある。明治22年の大災害をここで知る。風水害により十津川55郷のほとんどがあるいは水没し、あるいは孤立し、大規模崩壊1100箇所以上、死者249人の大災害となった由。再建を諦めたグループが極北の地、北海道に移殖し、新十津川村を作った。 十津川温泉郷から脇道に入る。目標は標高1076mの玉置山だ。十津川街道がハイウェイだったかと思えるようなすさまじい杣道である。 ガードレールを作れと言いたい断崖ルートを車は走る。すれ違いは無理、という箇所も多い。幸い対向車も少なく(でもあるのだ対向車、どこから来た?)なんとか命をつなぐことができた。ハンドルを握ったFとYの心労が偲ばれる。 玉置神社は神韻あふれる杉木立と視界を遮るモヤに覆われた渺茫たる景色の中に浮かび上がる。霊験あらたかとはこのことであろう。 社域を出、玉置山を縦走し瀞峡(どろきょう)に向かう。この時点で、なおいまだに十津川村を出てはいない。日本一広い村。市町村合併の誘惑など一瞥もせず十津川村であり続けるその気概は買いである。 熊野川町飛地(和歌山県)を越え、瀞峡に入れば三重県である。十津川圏(奈良県)からやっと離脱したわけだ。 |



| 十津川は広い。 どのくらい広いかと言うと、もう筆舌に尽くせないくらい広い。だから、書くことができないのである。(おい!) 紙運転手である筆者が行けない土地。十津川はその最右翼と言っていい。鉄道は無論のこと路線バスもほとんどない。タクシーは無謀だ。 「来るな!」と言われているに等しいのである。 今回、Nを始めYやF、女性陣も2名参加して総勢6名によるドライブ旅行である。 筆者の行けない土地へ連れて行ってくれるという心温まる企画なのだ。 大阪南部を東下し、竹内街道で大和高田市から奈良県に入り南下を開始、五條市で丹生川沿いにさらに南下。用地買収をしたはいいが結局鉄道を引けなかった土地にJRが作ったバス専用路を横に見たり、見上げたりしているうちに十津川街道に入る(あるんだ、そういう所が鉄道&歴史オタクNの面目躍如の場である)。 後醍醐天皇の皇子、還俗して護良親王となった大塔宮が北朝からの追捕を逃れ、隠れていたという大塔村を抜け、(銅像もある。Nはこの銅像を見せたがるが、皆、あまり反応しない。可哀想なNである)新天辻トンネルを抜けたあたりから道は蛇行を繰り返す。杉やヒバが茂る峯、峯、峯、 |
峯、峯、峯の連続。深緑の峯が連なっている、重なっている。森林地帯という表現では実相を伝えきれまい。人煙まれなという言葉も同様である。それだけではまだ足りない。樹木に覆われた山塊の厚さが違うのである。 地図で脇道に目をやれば、崩落危険箇所や断崖ルート、全ルートダートだの道幅狭い対向車に注意だの、道路崩落による通行止め多いだの、断崖ダート南側は大荒れの谷街道だのの注意書きだらけである。 奈良って怖い。 十津川を縦貫する主街道(と言ってもこの1本しか道はないわけで)がこの十津川街道(168号線)である。熊野川ぞいに走るこの道の下、熊野川の幅が広がり河川敷となっている所々にキャンプ場が設けられている。そのひとつが谷瀬である。名の通り、大きく切れ込んだ谷の下に川の瀬が思いのほか広い河原となっている。その広い渓谷を吊り橋が結んでいる。 日本最大の長さを誇る谷瀬の吊り橋である。長さ297m、高さ54m、(高さでは宮崎の照葉大吊橋(綾)の142mがある。この橋は長さは250m)。 渡らねばならない、と筆者は思った。。 渡りたくない、とFは願った。 |



| 盛夏の1日、湯布院に行った。 博多から特急「ゆふいんの森」で約2時間。久留米まで南下した列車は東に向きを変え筑後川に沿って九州をほぼ横断する。大衆化の進んだ別府温泉の奥座敷として開発された湯布院は、別府温泉のすぐ裏手にあるのだ。 駅前のメインストリートのむこうに標高1584mの由布岳が聳える。その姿が覆い被さるように大きく見える。ヨーロッパアルプスの村に来たような錯覚すら覚える。行ったことないけどヨーロッパ。あるいは映画「ダンテズピーク」のイメージか。いずれにせよいい景色である。 メインストリートを由布岳の方角に向かう。日本の景勝地ではよくある話だが、由布岳を視界に収めるポイントの多くで電線が邪魔をする。 豊後牛のステーキ丼を目当てに向かった店は閉まっていた。定休日ではないはずだ。あるいは11時開店と同時に1日50食限定という、しかも店唯一のメニュー「ステーキ丼」が売り切れたのだろうか。平日の、しかも11時45分には訪店しているのだが。45分で売り切れか?店頭に何の案内もないので臨時休業かどうかもわからない。気侭な営業形態なのだろうか。ちょっと失望。しかし予約を入れたわけでもない。文句は言えん。 町の奥には金鱗湖がある。朝霧で有名なこの湖 |
を目指す。20分程度で湖のほとりに出た。 (池じゃねえか) 石神井公園のような佇まいが筆者の前に広がっている。湖とは言いすぎだ。まずいなあ、何かボタンを掛け違ってのど元までそれが進んできてしまった感じだ。町の規模は、大きくない。何があるわけでもないのだ。 (消費のしかたを間違えた) 筆者の紀行パターンでは、消費できない、ここはリゾート地なのだ。宿を拠点にゆったりとすごす。食事も宿で。飲食店が連なっている町ではない。高原の酪農品と豊後牛、野菜、豊後水道の魚、地鶏、これらを宿で食べても十分満喫できるのである。 (退避~!総員、退避~!) 出直しである。高原の朝を満喫し、1日何もしないという贅沢をするための時間と宿を確保してから再攻が必要だ。 今日のところはこのへんで勘弁してやる。 駅の待合室は風通しが悪く、空調もない。椅子は座っていると疲れる設計。早く列車が来ないかなあ。往路は「ゆふいんの森」号だったが、復路は「ゆふデラックス」の最前列、スーパーシートである。・・・最後尾車両のだけど。 無論筆者はマニアではない。 |



| 1日では終わらない街である、長崎。今日は3時間半で終わっちゃったけど。 9年ぶりの訪問である。その前は17年ぶり。26年間で都合3回。ハレー彗星みたい。 金沢のように消費パターンが確立されていないので毎回、場当たり。なのに高満足。まともに消費したらどこまで満足するか、そら恐ろしい。 五島列島を食料庫としているため魚が旨いのは言うまでもない。寿司系がありだ。中華街があるので正統派の中華料理はもちろん、豚角煮包や丼・飯など立ち食い系・カジュアル系中華もあり。 「ツル茶ん」に代表される新規洋食系もあり。長崎伝統の卓袱料理やちゃんぽん、皿うどんなどの地元伝統系もあり。「あり」だらけである。観光資源も「あり」だらけ。オランダ坂や中島川にかかる石造りの橋、浦上天主堂、グラバー亭、出島など、優良物件の宝庫である。 9年ぶりとなると、記憶はまったくあてにならない。にもかかわらず長崎駅を出た筆者は地図も確認せずに街歩きを開始した。案の定、見当違いの方向に進み、道に迷う。(学習能力はないのかおのれは)。街の人に道を尋ね、修正を図る。 石畳の小路が続く「中通り商店街」を歩く。アイスの「ニューヨーク堂」がある。小さな間口の卸問屋のような外見の店だが、びわでアイスをく |
るんだ「びわアイス」や、「ビワもなか」「ざぼんアイス」など秀逸な品々が並んでいる。 観光通りに交錯するアーケード街「浜んまちアーケード」が賑やかだ。長崎で一番古い喫茶店「ツル茶ん」がある。「トルコライス」発祥の店である。ピラフとナポリタンを一皿にあわせ、ドミグラスソースのかかったカツを載せる。それがトルコライスである。9年前、朝早く来すぎて食べそびれた筆者は、今日こそトルコライスを食べるべくやって来たのだ。根室の「エスカロップ」金沢の「ハントンライス」長崎の「トルコライス」。筆者が認定する3大ご当地洋食プレートのうち「トルコライス」だけを食べそびれているのである。(ご当地洋食プレートは、筆者の勝手な呼称である)全国にはまだまだ未知のプレートがあるやもしれぬ。ご存知の方はご連絡を。 歳は取りたくないものだ。トルコライスを食べたら何も入らなくなってしまった。中華街で丼を食べるか「吉宗(よっそう)」で丼茶碗蒸と蒸し寿司の吉宗定食を食べようと思っていたのに計画は頓挫した。しかし、眼鏡橋も見たし、出島も覗いた。昔日の想い出と邂逅する浦上天主堂やオランダ坂は次回の訪問に譲るとしよう。夕方には博多に帰らねばならないのだ。 あっという間の3時間半であった。 |


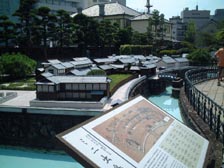
沖縄行2006(その3) →→→back 96 06(1) 2) 3) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
| 鋭い金属音が上空に木霊する。F15が飛翔している。強烈な日差しが雲に機体の影を落とす。影は高速で移動し、雲の切れ間で本体と入れ替わる。・・・沖縄だ。 沖縄本島は南北に細長く伸びている。全長およそ105キロ。玄関口でもあり、人口30万の県下最大の都市、那覇市はほとんど南西端に近い位置にある。那覇から北上し、高速道を沖縄市(旧コザ)、名護市などと過ぎて行くと西北部にこぶのような半島が突き出ている。那覇から約90キロ。本部(もとぶ)半島である。ここから北部を「やんばる」と呼ぶ。 筆者は那覇市を離れ、本部半島に向かおうとしていた。タクシーを借りきったら2万6千もすると言われ、バスにする。ペーパードライバーは悲しいのである。市内のホテルを巡回し、本部半島の「美ら海水族館」のある海洋博公園にむかうバスは1800円の入園料込みで往復4720円。おトクである。夏休み前の平日のせいか客は3名。もはや貸切状態だ。 途中、伊芸SAでコザの海を見下ろす。 轟きとともにF15の4機編隊が低空を横切り、きれいにバンクして東方に消えていく。その後をさらに3機が追尾する。やっぱ、ベースの街だ。見上げる空にはいつもアーミー。 |
深さ10m、幅35m、奥行き27mの巨大水槽を持つ「美ら海(ちゅらうみ)水族館」には複数のじんべい鮫とマンタの群れが悠々と泳いでいる。 じんべい鮫は大きい。いろんな連中が下腹にまとわりつき、おまけに胸びれの上にまでちょこんと何かが2匹取りついている。こいつ、何か考えているのだろうか。たとえ少しは了見があったとしても、どもりだ、きっと。あ、放送禁止用語?じゃ吃音。「お、俺の腹に、く、くっついている奴、ち、ちょっとくすぐったいぞぉ」てな感じ。 人口の海浜「エメラルドビーチ」を歩く。海はどこまでもコバルトブルーに輝き、空は抜けるように青い。「ビーチ」という言葉をためらいもなく使えるのはここ沖縄だけとします。本土では駄目、禁止。「ビーチ」なんて屈託ありすぎ。やっぱ「海水浴場」が相当である。 ビーチだから、ココナッツジュースも本物である。バスケットボール大のやしの実をガスガスと削り、内部の白い皮膜を少しだけ露出させる。そこにストローをさすのだ。甘味の少ないアイソトニック飲料のような味の果汁が思いのほか大量に入っていた。 夏を夏らしく過ごすなら沖縄だな、やっぱ。 |



沖縄行2006(その2) →→→back 96 06(1) 2) 3) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



シーサーさぁ 屋根にもシーサーさぁ 首里城
| すさまじい紫外線を浴びつつ首里城にむかう。 暑い。 蝉がワシワシ鳴いている。 青空をバックに家々の門上からシーサーが笑っている。2匹で一対の魔よけの創造神だ。一体は口を開け、他方は閉じている。風神雷神みたい。「阿・吽」と言っているのか。 沖縄では城はグスクと呼ばれる。部族が相互に攻伐を繰り返し、最終的に尚巴志(しょうはし)が統一国家を作りあげた。1429年のことである。40年後、農民出身の金丸(かなまる)がクーデターにより政権を奪取するが尚(しょう)家という名は継承し王朝としては約450年の命脈を保つ。 首里城は琉球王朝の城である。 累代の王は鬚を蓄え習俗はあきらかに中国である。武を卑しんだのではあるまいか。城とは言うが典礼と王族の住居として機能したようだ。多くの支配者がそうするように首里城も高台の上にある。「西(イリ)のアザナ」と呼ばれる展望台からの眺めは気持ちがいい。 首里からゆいレールで牧志(まきし)に行く。 「牧志駅」は「国際通り」に接している。那覇のメインストリートである。戦後「奇跡の1マイル」と呼ばれ、復興の象徴となった1.6キロの繁華街だ。道路の両脇には高いビルがない。アメリ |
カ映画に出てくる西部の町。その町の中央を貫くただ一本のストリートというイメージだ。 道の両脇に土産物屋と衣料品店が溢れ、Tシャツやかりゆしウェアを売っている。「かりゆし」とは沖縄方言で「めでたい」という意味。沖縄版アロハシャツのことである。開襟で、裾を外に出す。小泉首相も沖縄サミットで着用した。沖縄ではすごく自然。国に帰ればヤクザ。何故だ? 国際通りに「公設市場」への入口がある。「まちぐゎー」と呼ばれるアーケード街だ。 市場には豚の顔のスモークが並んでいる。 それにしても暑い。汗が止まらない。 日没が遅い。7月下旬の午後8時、西の空がまだ蒼い。その分朝は遅い。5時半はまだ薄暗い。 「波照間」という、東京八重洲に支店を出す「龍潭」の系列店は、店内が波照間島の集落をイメージした造りだ。オリオンビールを喉に流し込む。旨めえ。おじい自慢のオリオンビール♪だ。 ラフテーと島豆腐、スーチキー(豚の塩漬け)、どぅる天(田いもコロッケ)、豆腐ようで泡盛古酒を愉しむ。宮の華、海乃邦、北谷長老古酒と締めのポーポーアイス(沖縄のクレープ。さとうきびアイスを包んでいる)。三線のライブを聞くうち立たされて踊らされもした。「お客さんうまい」と言われて木に登る筆者であった。 |



国際通り まちぐゎー 三線LIVEさぁ
沖縄行2006(その1) →→→back 96 06(1) 2) 3) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
| 「月日は百代の過客にして行かふ年も又旅人也」 芭蕉に頼まれて筆者が代書した書き出しだ。 まさに月日の流れは、悠々として、しかし気がつけば思わぬ遠き処にまで運ばれた己が軌跡に呆然とさせられる重さを持っている。 10年ぶりの沖縄。しかも10年前は社用。プライベートでは初めての訪問だ。筆者にとっては国内で残された数少ない非日常的リフレッシュ効果を期待できる土地だ。 北海道を除く本土のほとんどが強い雨域に覆われた一日、伊丹を飛び立ったANA101便は、エメラルドグリーンに耀く環礁に覆われた那覇空港に降り立った。 夏空が広がっている。 完全に盛夏だ。気温は31.8度。 本土とそれほどかわらないが、湿度が低いので蒸し暑さはない。そのかわり亜熱帯の日差しが強烈だ。陽の光をうけているだけで疲労するのは久しぶりの感覚。UVケアを心がけなければ生きてはゆけない。筆者の歳では日焼けはシミに通じるのだ。あ~やだやだ。 2003年に開業した県内唯一の軌道交通機関「ゆいレール」(正式名称「沖縄都市モノレール」)に乗る。那覇空港から首里城のある首里まで14駅を27分で結んでいる。日本最西端の駅 |
「那覇空港」、日本最南端の駅「赤嶺」を擁する交通機関だ。無論、筆者はマニアではない。 終点「首里」で下車。まずは首里城を訪れることにする。ただ、その前に「首里そば」で沖縄そばを食べるのだ。 県下随一のコシを誇る店だ。11時半の開店僅か後に訪れたが、すごい人気だ。すでに店内は人でいっぱい。 ひとり旅の利点はこうしたときだ。隙間に入れるのである。カウンターにあいていた1席をゲット。大・中・小3サイズの中を頼む。ほかにもジューシー(炊き込みごはん)や煮物があるが、初っ端から腹を膨れさせては歩けない。 我慢である。 込み合った店内でフロアー係りは1名だけ。オーダーをとりに来るまでも待つが、その後、モノが来るまでも待つ。沖縄では焦ってはいけない。のんびりすることだ。待つことしばし、その間も続々と客が集まってくる。人気店なのだ。 そばが来た。三枚肉とロース肉、蒲鉾がのっている。スープはすっきり塩味。だしはカツオと豚肉らしい。「針しょうが」がアクセントになっている。麺は、さすが県下一二を争うコシの強さ。ただでさえモクモクする沖縄そばが筋金入りのモクモクぶりだ。顎が疲れる。 |
| その日、筆者はJR水郡線「常陸大宮」駅での下車を余儀なくされた。 水戸駅で発車間際に飛び乗った列車が「常陸大宮」止まりだったからである。 水戸と郡山を結ぶ水郡線は「ローカル線の旅」では必ず俎上に上るメジャーなマイナー路線だ。途中駅「常陸大子(ひたちたいご)」の一駅前、「袋田」駅は、名瀑「袋田の滝」の最寄駅だ。 しかし、「常陸大宮」には何もない。乗り継ぎをするための次の列車は13時49分の郡山行きである。郡山到着は、・・・えっと・・・ (へっ?) 16時26分?・・・郡山到着が? 2時間半もかかるの? 駄目だ、後ろのスケジュールに差し支える。無念の撤退である。思いつきで飛び乗るには危険な路線だ水郡線。 筆者の目の前に自動販売機がある。 見慣れぬ型だが、気にもならなかった。 作業服姿のオッチャンが自販機の前に立った。 「△※□□○※△×」 オッチャン、自販機に何か話しかけ始めた! (危ないやっちゃ) オッチャンの声に耳をそばだてる筆者。話の内容は意外や正常だ。 |
「東京から名古屋、5時につきたいんだけど」 話の中身は正常。おかしいのは機械に話しかけているってことだけ。 「スーパーひたち○号で上野、東京から名古屋までのぞみ○号に乗り継ぎですね」 な、なんと自販機がしゃべりよった! おっちゃんは、それが当然のように機械に返事をしている。 「××円になります」 自販機の応答におっちゃん、金を投入しとる。 ジャラジャラジャラ。自販機が釣り銭まで出しよった。(あたりまえか) オッチャンがいなくなったところで、恐る恐る自販機に近寄る筆者。 それは、ローカル駅の「みどりの窓口」を次々と閉鎖しているJR東日本の秘密兵器「もしもし券売機Kaeruくん」であった。 通信回線による集中制御機構の端末なのだ。 カメラやマイク、スキャニング機能(定期や切符の確認をするため)まで備えている。乗車券、特急券の購入はもちろん、その変更や払い戻しまでできるのだ。 恐るべし、「Kaeruくん」。 |



| やがて、筆者は天理教の総本山を見た。 宗教的権威をここまで巨大かつ壮大に提示されるとさすがに圧倒される。知らないところですごいものが育っているという感じである。街全体に母屋と称する教団の宿泊施設が、これまた均質かつ巨大に林立している。大学までもがとにかく均質かつ巨大な作りだ。バチカンもこうなのか。 本部の敷地を出るとき人々が皆、一様に神殿を振り返り一礼してゆく。ここに観光客はいないのだ。ここにいるすべての人々は信者なのである。 石上神宮に向かう。 境内を鶏が闊歩していた。地面をついばむその姿がなぜか神域を意識させる。なぜだ? この神社を氏神として奉っていた物部氏は武門の棟梁であった。武士(もののふ)は物部(もののべ)からきているとも謂う。歴史のロマンがここにある。 最古の神社を満喫したら、最古の道が待っていた。その名も「山辺の道」。 全長26キロ。奈良から天理までの北部(約10キロ)、天理から桜井までの南部(約16キロ)に区分されている。 少し歩くことにした。無論踏破の意思はない。 石上神宮から峠にむかって上り坂だ。樹木のアーケードをかいくぐるような杣道や見晴らしのい |
い峠道もある。棚田の中道を歩いていると夏を思わせる熱暑が周囲の景色を白くくすませる。過日見たアニメ映画「茄アンダルシアの夏」のスペイン南部の夏のようだ。 4キロほど歩いて脱水状態になる。進行を断念して帰路につこうとするが、鉄道の駅がどこにあるかもわからない。遥か下方にキラキラと陽光を反射させる車列が見える。幹線道路だろう。バス路線もあるはずだ。下界に下る。停留所を見つけたが次のバスが来るまで30分はある。歩いた方が速い。結局天理まで戻り、往復で10キロ程度を歩いた。 駅前で今年初となるかき氷を食べ、近鉄で帰阪する。考えてみれば、大阪から奈良へ京都経由で来たのは完全に迂回だ。大阪・奈良間30分、大阪・京都間30分、京都・奈良間40分という三角形の2辺を使っているようなものだ。 天理から大阪難波まで、2度乗り換えるが接続はいい。天理から平端、平端から大和西大寺、大和西大寺から難波まで。近鉄奈良線は、生駒山を越境する。大阪の市街地を見下ろす丘陵地帯は北の千里と南の生駒のふたつである。生駒山トンネルを抜け石切駅を過ぎたところで沖積平野の大阪市街を一望。 総じていい1日であった。 |



市内はほぼすべて天理教関連施設で埋め尽くされている



画像左から2枚は石上神宮 右は山辺の道
| 梅雨空が割れて久しぶりに終日陽光の降り注いだ6月下旬の一日、筆者は天理で列車を降りた。 天理は、奈良県にある。 奈良よりさらに10キロ弱を南下すれば、天理である。 その日、とりあえず京都までぶらりと東上した筆者が乗り継いだ列車は、奈良線の「大和路快速」であった。のんびりと奈良町を散策してもよかったのだが、何となく桜井線に乗ってしまった。 どこで降りるというあてもないまま、最近M君の行った大神(おおみわ)神社でも覗いてみようかとぼんやり考えた。 大神神社は確か、三輪か桜井で降りればいいのだ。そうだ、三輪で三輪そうめんでも食べるか、とほぼ意を決したその時、奈良を発して3駅目、天理に列車が停車した。 ふと脳裏をかすめたのは「石上神宮」と「彩華ラーメン」。脈絡もない連想だが、「大神神社」と「三輪そうめん」のタッグからインスピレーションが沸いたのか。神社&麺類マッチである。 あるいは会社のスタッフに何かサブリミナルされていたのかもしれない。筆者は魅入られたように列車を降りてしまった。 アーケードの天理商店街を抜け、51号線を右折したあたりに「石上神宮(いそのかみじんぐう |
)」がある。あるいは、日本最古とも言われる、記紀にすらその記載がある神社である。 崇神天皇の代、4世紀頃の創建だ。謂われにはあまり興味がないのだが、筆者のツボをついたのは、この神社が古代の軍事部門を統括した物部氏の総氏神であるということ。 物部氏は、財政・外交の統括者、蘇我氏によって滅ぼされる。細かいところは漫画「日出ずる処の天子(山岸涼子著)」でもご覧いただきたい。ホモの聖徳太子などという驚愕の設定を無視すれば、古代の政治闘争が意外としっかり書かれているのである。ま、少女漫画ですからね、物部対蘇我の戦いなどけっこうサスペンスフルになりそうな題材をさらっと流しているのが男から見ればもったいないが。 「彩華ラーメン」は午後5時からの営業であったため計画の一端は頓挫した。しかし、捨てる神あれば拾う神あり。アーケード街の途中「陽紀屋」という夫婦2人で営業しているお好み焼き屋でめっけもんの旨さの「お好み」に遭遇。ミックスモダン780円は、ラードで焼いたふっくらふんわりの焼き上がり、かつ表面がカリッと実に旨い。 アーケード街で目に付いたのは「天理教」の信者群。襟に修行中やらどこの所属やらを縫いつけた黒い法被を着ている。すごい数である。 |


| 荘園領主である貴族の都、平安京の創建から約400年を経過して生まれた対抗勢力の中心都市それが鎌倉である。 農奴解放運動の根拠地みたいなもんだ。自分で稼いだ(開墾した)ものは自分のものだという新思想の武装農民が首都に叛旗を翻し、立てこもったうえ、対抗勢力にまで成長したわけだ。 大江広元なんて中央では歯牙にもかけられない末端貴族をブレインとし、武力だけではなく政治力でも中央と渡り合った。九条兼実という平家にも院政にも斜めな、その分やや中枢から外れた第3勢力と組むなどなかなかにしたたかな政治闘争ぶりは、血統主義の下では冷や飯を食うしかなかった大江広元がかなり有能な人間であった証左かもしれない。 そういう事情で生まれた都市だけに鎌倉は京都とはいささか風情が違う。 鎌倉五山と言われる禅宗寺院を中心に寺社仏閣も豊富であるが、華美さがない。奢侈に走らず「覚悟」を常に人生の主題に据えた漆黒の艶光りが夕景に映えるような街である。そして早くに(僅か150年)都市としての生命を終えたせいか、どこか鄙びた町内会規模の街というイメージもある。だから観光客でごったがえす様は人様の庭先に無遠慮に踏み込む野盗の群れに襲われた静かな |
山村のようなイメージとも重なる。 鎌倉はそれほどに都市としては小規模だ。 北鎌倉から厨子との境の名越までが都市の主軸であり、駅としては「北鎌倉」と「鎌倉」しかない。この間に複雑な山の稜線が出入りの激しい地形を成し、谷(やつ)と呼ばれる鎌倉特有の地形構造を形成している。唯一相模湾にむかって開かれた海岸部は稲村ヶ崎を南西端としている。鎌倉幕府を滅ぼす戦を担った新田義貞はこの海岸部から東上し、極楽寺坂切通しを突破している。 JR横須賀線で横浜から5駅、関東の駅百選に選ばれた北鎌倉駅がある。ホームが異様に長い。15両編成300メートル長の列車が停車するのだ。ほとんど新幹線並である。しかも改札口は南端にある一箇所のみ。改札から最遠部車両にでも乗ろうものなら大変である。 駅は鎌倉五山、第2位の円覚寺の境内にある。 筆者がぶらりと立ち寄ったのは紫陽花で知られる明月院。特別公開されていた本堂後庭園の花菖蒲が梅雨空の下、あざやかに咲き誇る。紫陽花はまだ満開ではなかった。それにしても人が多い。 明月院の先には鎌倉五山の筆頭、建長寺が広大な宗教都市として49の塔頭を有する威容を誇っている。「けんちん汁」は、この建長寺が発祥である。 |


| 記号化されるほどの象徴を持つと、存在価値の奥行きは記号化の深さだけ浅くなる。 「水戸」って言えば「納豆」。「光圀」ってのもあり。どちらも正解である。ただ、正解しても嬉しくない。それほどにオッズが低い。 この関係性に対抗できる物件は「名古屋」。 「名古屋」=「味噌」。 すわりのよさは磐石とも言える。 「名古屋」=「味噌」、「水戸」=「納豆」。 連立方程式だな。「発酵食品」でくくれる。 「名古屋」×「水戸」=「味噌納豆」。 あるんじゃないか。ないけど。 26年ぶりの水戸である。街の印象がおどろくほど記憶と合致する。変わらないのか、ここは。ま、あくまでも印象ということで。 偕楽園を訪ねる。 庭がゾーニングされている。梅ゾーン、竹ゾーン、杉ゾーン、町の寿司屋の料金体系?。 偕楽園と言えば梅である。「梅七味」「梅ごま」「梅そば」「梅うどん」など何でも梅まみれ。「梅の天ぷら」なんてのもある。食べてみると梅を天ぷらにしたらこんな味になるだろうなという味であった。梅はどこまでも梅である。キャラが濃すぎる。かぶりものをかぶっても安岡力也は、やっぱり安岡力也であるのと同じだ。 |
正しいか?この例え。 今回のおススメ物件は、竹林である。 偕楽園の竹林は、物凄い。竹林に物凄いという表現を使うのもなんであるが、本当に物凄いのである。風にあおられ、葉ずれの音がざわざわと、なんていうのはどこにでもある。ここでは風にしなう竹林から「カツン、カツン」という乾いた音が降ってくるのである。密生した竹同士が風にあおられ、ぶつかりあう音である。始めて聞く音であった。繁った葉の重量に耐えかねて竹が軋む音も「キシ、キシ」と竹林に響き渡る。 さらに、人の背丈ほどにも伸びた竹の子。 これも怖いな、かなり怖い。 小さな筍のように熊の毛皮のような茶色の皮を身にまとったまま、人の背丈以上に伸びているのだ。竹の持つ青いつるつるした表皮はまだ形成されていない。節々に筍のときのままの小さな葉なんだか表皮の一部なんだかを小さくそりかえらせて、茶色の竹の子が薄暗い竹林の中に幾つも伸びている。 異種生命体だと思ったね。「侵略」という単語が浮かんだ、なぜだか。それほどインパクトがある。この竹の子からは決してかぐや姫は出てこない。出てくるのはおそらく遊星からの物体Xである。間違いない。 |



水戸駅前の黄門様御一行 恐怖の筍 偕楽園のつつじと好文亭
| 上野発の常磐線いわき行特急「スーパーひたち19号」は、次駅水戸までノンストップである。上野、水戸間を1時間5分で結ぶ。 常磐線は、海抜ゼロメートル地帯の天井川「墨田川」を越え、次いで「荒川」を越える。 「亀有」を通過。漫画「こちら葛飾区亀有公園前派出所」の「亀有」だ。あの漫画は筆者が中学生の頃に始まったのだ。やがて同アニメの主題歌でも使われた「中川」を越える。 「金町」を通過し「江戸川」を渡河。「松戸」を通過して列車はやっとスピードを乗せ始めた。 発車から16分後「新松戸」を通過。「柏」を抜け「我孫子」通過は11時22分。いずれも身近に聞き覚えがあり、日常圏を離脱した感覚はない。 「利根川」を越え「取手」を通過した。電源切り替えで寸時、停電する。やっと旅モードに入る。 常磐線は、宅地開発の発展が目に見える路線である。都心寄りの住宅は敷地が狭く庭のない切り割り長屋のような造りだが、やがて家の幅が膨らみはじめ、駐車場がつき始める。次いで庭が生まれ、それが広がり始める。都心寄りの小さめの庭は「ガーデニング」といったイメージだが、やがて家同士の間隔が広がると、庭もそれにつれ大きくなる。「園芸」という言葉を使いたくなる。周囲に田畑が多くなる頃には庭は「家庭菜園」とな |
ってゆく。 「牛久」を通過。11時32分。 「土浦」を通過。11時39分。住宅はすでに堀をめぐらせ、屋根瓦もどっしりとしている。門まで構え始めた。住宅と言うよりは屋敷である。 住宅地を抜け、樹木の繁茂する小山の連なる風景に変わる。うっそうと繁った樹林の暗がりの中に飲み込まれてゆく小径。車窓の主役は人の手から自然にとってかわられた。 藤の花の季節である。青い藤の花が木々の間に見え隠れしはじめた。木々の緑は、どこまでも深く野生の藤の青さはどこまでも鮮やかに映える。 花の美しさに心を奪われていたが、やがて、野生の藤の怖さがじわじわと心を蝕みはじめた。普段、藤棚の飼いならされた藤ばっかり見ていたもんだから、野生の藤の姿を忘れていた。木々にからんで咲くものかと感心していたのは最初だけ、木々にかぶさり、たわわな花を咲かせている藤は皆、木々の頭頂部、より日光のあたるところに覆いかぶさっているのである。絡みついた樹木にしがみつき、はいのぼり、まとわりついている。 寄生される恐怖、とりつかれる恐怖だ。 やがて幾反もの水田が連なり始める。完全に水郷地帯の景色となった。 列車はあと10分で水戸に到着する。 |



博多行5→→→back 博多行 博多行2 博多行3 博多行4 博多行5
| 川端商店街を抜け、明治通りを左折し博多川と那珂川を渡る。この両川に挟まれたエリアが中洲だ。明治通りの南側にこの中洲の繁華街が広がっている。筆者の行く「岩政(寿司)」、バー「Vespa」はここにある。那珂川より天神寄りのエリアは西中洲と呼ばれ、「河庄本店(寿司)」や福岡のスタッフが飲み会に選んだ「とわ蔵」がある。 那珂川を越え、緑のテラスに覆われたアクロスの前を通り過ぎると天神である。福岡の中心地、ショッピング街だ。西鉄の起点「天神駅」がランドマークであろうか。 明治通りの北には昭和通りが走っている。大正通りと明治通りが交錯するエリアが赤坂である。南下すると、大名と呼ばれるエリアだ。若者むけの飲食街のイメージが強かったが、大人も愉しい店がけっこうある。福岡のスタッフに紹介された「鳥善大名店」味噌仕立てのもつ鍋「越後屋」炊き餃子の「池田屋」慶州鍋の「いずみ田」「老香港酒家新記」焼き鳥「八兵衛」など周辺地域は多彩な呑み処だ。 明治通りの西進を続行する。 赤坂を越えると裁判所など法曹関連施設の集中する堀端に出る。福岡城跡だ。天守閣はないが城域をよく保ち、巨大な城郭であった往時の雰囲気 |
を知ることは難しくない。 天守台は高く、眺望がよい。この天守台に天守閣が聳えていたか否かが研究者間で争われているらしい。城域の広さから、天守閣を作れば江戸城より高大になる可能性があり、これを黒田家が厭ったというのである。 福岡城跡の西隣が大濠公園である。城の外堀を利用し、中国西湖を模して作った大きな公園である。水量が豊かで眺めが広寛である。春のうららかな日差しの中、子供連れやカップルがのんびりと散策している。 大濠公園を出、さらに西進する。 唐人町駅から川端を歩く人々の列がある。この人波は「ホークスタウン」まで続いている。ヤフードームを中心とする広大なアミューズメントゾーンである。この日、ホークスとロッテのオープン戦2日目が行われていた。 ホークスタウンの裏には海岸が広がる。マリゾンと呼ばれる人工の海浜公園である。 福岡タワーはその先に聳えている。心なしかゴールドタワーに似ている。 (ごめんなさい、こんなに高いタワーなのにポートタワーと取り違えておりました) 心の中で手を合わせて福岡タワーに詫びる筆者であった。 |



画像左:福岡城跡天守台からの眺め(遠くに福岡タワーが見える。右端切れかかっているのがヤフードーム隣のホテルである
画像中:大濠公園 画像右:ヤフードームとホテル(シーホークホテル&リゾート)


画像左:画面右の砂浜がマリゾン、中央が福岡タワー 画像右:福岡タワー
| 飛び乗ったJR鹿児島本線の快速は「羽犬塚」(はいぬづか・・・読めん)行きだった。 「羽犬塚」って言われても・・・ (どこよ?) 目的地は「基山(きやま)」である。甘木鉄道がそこから甘木に向かっている。 ドア上部の路線図をにらむ。どうやら「基山」には行くらしい。「基山」は快速の停車駅で「鳥栖」の一駅手前だ。すると今度は後方4両が「南福岡」で切り離しとのアナウンス。切り離しって宣言されても・・・ (どこよ?) 隣駅だった。幸い筆者の車両は、切り離しを免れた。せっかく確保した座席を捨てるのは悔しいものだ。見知らぬ路線は、前寄り車両に乗ろう。切り離されるのは必ず後部車両だからだ。 「二日市」を過ぎ、列車はうららかな春の日差しを浴び、田園地帯を快走する。瞼が重くなってきた。ここ数日呑み続けだ。体がまいっている。まどろみの中、あと2駅くらいだと思いつつ、意識が薄れていった。 目覚めれば車窓にスタジアムの姿がある。 鳥栖のスタジアムだ。 (乗り過ごした!) 筆者は鳥栖駅の情景には詳しい。駅標も確認せ |
ず、閉まりかけのドアから飛び出した。やはり乗り過ごしていた。 その後40分を空費して「基山」に戻った。日常生活ならば、憤死しているか腹を切っているであろうトラブルだが旅にあれば心は穏やか。 甘木鉄道は2両編成のワンマン電車。「基山」から終点「甘木」まで二十数分の旅程である。 沿線はかぎりなくのどかな田園だ。菜の花の黄色がまぶしい。すみれであろうか、薄紫の花も群生している。そして終点甘木に到着。甘木鉄道甘木駅から徒歩数分の位置に西鉄甘木駅がある。帰路はここから天神に向かうことにした。 西鉄甘木線は単線である。2両編成のローカル車両だ。伏見稲荷の千本鳥居のような架線柱をくぐりぬけてゆく。途中屋根もない完全に吹きさらしのホーム幅のせまい駅が幾つもある。 11駅で天神大牟田線「宮の陣」駅に接続。そのまま2駅進行して久留米で乗り換え。近鉄の旧型特急のような2ドア車両の特急で終点「天神」までの39キロを「二日市」「薬院」の2駅(各駅では24駅)だけに停車し30分程度で駆け抜ける。 天神、大牟田間75キロ1時間を特急で結ぶ大牟田線は久留米の先に水郷「柳川」を持つ。ここはうなぎせいろで名高い。いつか行かねば。 |

 画像左:甘木鉄道 右:西鉄甘木線
画像左:甘木鉄道 右:西鉄甘木線
博多行4→→→back 博多行 博多行2 博多行3 博多行4 博多行5
| 博多、中州の西岸を流れる那珂川をまたぐ明治通り、昭和通りの橋上から港湾部を臨むと、横浜のマリンタワーを「ずんぐり」させたタワーが立っている。 無知とは怖い。 博多っ子の皆様、お許しください。筆者はあのタワーをずっとずっと「博多タワー」だと思っておりました。実は「博多港ポートタワー」って言うんですね。 博多をご案内した数多の関係者の皆様、申し訳ございません。私は虚言を弄しておりました。この場を借りてお詫び申し上げるとともに訂正させていただきます。 『あれは博多タワーではありませんでした。博多港ポートタワーです』以上。 もう、他の人に話してしまいましたか?博多タワーって。そういう場合は、ご自身でなんとか体裁を取り繕っておいてください。 タワー違いをやらかしていた筆者は懺悔の行脚に出ることにした。 中洲の東岸、川端商店街から、正真の「博多タワー」まで歩くことにしたのだ。やはり、街は歩かねばわからん。 博多タワーは、博多の西部にある。ヤフードームスタジアムの隣、人工海岸の西隣だ。タワーと |
しては日本一の高さを誇る(この事実を知ったとき、筆者は既述の勘違いに気づいたのだ。日本一の高さを誇るタワーにしてはあれはあまりに低すぎる。と、言っても100メートルはあるので通天閣クラスということでひとつ)。 市営地下鉄が行脚ルートの下を走っている。博多の地下鉄は明治通り沿いに東西に走行しているのだ。駅名で区間を計ると、「中洲川端」から「天神」「赤坂」「大濠公園(おおほりこうえん)」「唐人町」「西新(にしじん)」までということになる。「西新」までと言うのは実際は少し内陸に入りすぎているという点で今回のコースからやや離れているので無理と言えば無理があるが、そこのところも、ひとつよしなに。 スタート地点に選んだ川端商店街は歴史ある街である。近代に至り、JR博多駅周辺、天神、キャナルシティなどの商業資本の集積におされ、昔日の活気を失ったと言われている。確かに静かなアーケード街ではあるが、趣のある個人商店が並んでいる。博多三大名物「辛子めんたい」「豚骨ラーメン」「川端ぜんざい」のひとつ「川端ぜんざい」が復刻され、商店街中ほどに出店がある。 商店街をぶらぶら流し、博多座のある明治通りに出る。ここを左折し、いよいよ博多散策王道コースのスタートである。 |

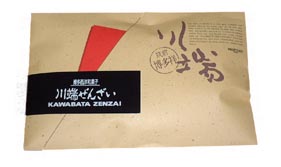
| 山峡の小さな城下町である。 山にむかって緩やかに登る一筋の街道の両脇に商家・民家が立ち並んでいる。追手門へと向かう馬場道が街道の途中から折れてゆく。かつては杉木立に囲まれたその道は杉の馬場と呼ばれた。いまは桜並木に替わっている。 山間にこだまする太鼓の音とともに登城する藩士の姿がそこに浮かび上がるような静かな景色が広がっている。 秋月藩5万石の秋月城跡がこの馬場道の先にある。城跡と言うがそこには長屋門と大手門にあたる黒門、ならびにこれらの周囲にある石垣とわずかな石段しか残っていない。 しかし、その佇まいの落ち着きぶりは、小藩の凛とした姿を彷彿させる。 長屋門から数段の石段を登ったさきはのどかな公園である。そのかたわらには中学校がある。昭和中期までに幼少年期をすごした中高年にとっては、たまらない郷愁を感じさせる光景だ。どこまでが敷地か判然としない校庭は木立に包まれた裏山につながっている。雨ともなれば、降り始めた雨粒にうたれた地面から沸き起こるであろう土ぼこりの匂いさえも鼻腔をくすぐりそうだ。裏山の木立から覗く校庭の白さが周囲の翳りと鮮やかに対蹠する。 |
甘木から国道322号線を遡上すれば、この秋月城下に至る。甘木まではJR鹿児島本線の快速で博多から基山(きやま)まで20分強、甘木鉄道に乗り換えさらに20分強である。甘木から秋月まではバスを使う。 終点甘木まで甘木鉄道に揺られた筆者は、駅前のレンタサイクルを利用した。国道322号線は市内を出れば歩道がなくなる。車道に乗り入れ秋月を目指す。砂利砕石場が途中にあるためか、ダンプの交通量が非常に多い。つまり怖い。国道の脇を小川が流れ続けている。対岸をのどかに走るチャリの姿が見える。もしあの道が秋月まで続いているなら、帰路はあそこを利用しよう。しかし往路の今は基幹道しか載っていないアバウトな地図を頼りにしている以上小さな道路はあぶない。道を見失う可能性が高いのだ。 のどかな田園風景をこぎ続けると、やがて城下町秋月の入り口である目鏡橋(めがねばし)が現れる。道は狭く周囲に民家が連なる緩い上り坂である。甘木駅から1時間とかからない。 帰路は、往路でチェックした小川沿いの道をゆるゆると帰る。往路を引き返すのではつまらないので西鉄甘木駅から久留米経由で天神へ帰る。久留米で特急に乗り換えて1時間15分程度の旅程である。田園を満喫できるお薦めの周遊だ。 |



金沢行11 →→→back 金沢行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
| 「ジャーマンあき」が店を閉めたらしい。それも1年以上前。2005年3月に。金沢の常食「ハントンライス」で知られる洋食屋であった。 ハントンライス、通称ハントン。 トマトケチャップで味付けをしたバターライスに薄焼き玉子をかぶせ、その上にフライを載せタルタルソースとケチャップをかけた食品である。 長崎のトルコライス、根室のエスカロップと並ぶ地の洋食である。 ハントンの存在を知ってはいたが1食分をそれに割くきっかけがなかった。しかし親爺さんの逝去で店をたたんだ近江町市場の「さわいのパン」の件もある。 『いつまでもあると思うな家族経営の店』 「グリルオーツカ」に行くことにした。 ハントンは、いまはなき金沢の洋食屋「ジャーマンベーカリーグリル」に始まり、その味に忠実とされるのが上記「ジャーマンあき」と「グリルオーツカ」である。 片町の奥、ひっそりとした路地裏感の漂う一角に「グリルオーツカ」がある。通りに面した店の側面にあたる2Fに「洋食オーツカ」と、酒造メーカ提供のシンプルな看板が出ている。通りを回りこむと入口がある。カルテが掲げられている。 「うほ、あるある」 |
ハントン風ライス680円、エビハントン風ライス730円、オムライス680円である。ヌードルって書いてあるものなあ、パスタは。ナポリ風スパゲティとミラノ風ミートソース、カレースパゲティ、いずれも680円。 えも言われず、この店が気に入ってしまった筆者。扉をあけると、刻の流れがそのまま刻み込まれたような年輪を感じさせる佇まい。少し薄暗いその入口は、時間の旅人を迎え入れるフロントのようだ。古めかしいけれども清潔感のある食堂は奥にある。拡張に伴って奥の民家まで壁を抜いてしまったかのような短い渡りをくぐって食堂に行き着くような造りだ。洋食屋としての矜持は、テーブルに敷かれた真っ白い布のクロスと銀製の花器に指された一輪の花が雄弁に物語っている。 ハントンが来た。 魚とエビのフライが載っている。載っていると言うよりは薄焼き玉子と融合している。 具のないケチャップライスはオリジナルに忠実らしい。フライの香ばしさとタルタルソースと玉子のしっとりとした味わい、ケチャップの酸味が心地よい。旨いなあ。日常の旨さである。週に1食は食べたくなる。地の常食品である。 量は思いの外多い。満喫して店をあとにした。「ジャーマンあき」にも行きたかったなあ。 |
| 小浜(おばま)は若狭の中心都市だ。 日本海、若狭湾のさらに内側に内外海(うちとみ)半島と大島半島に包み込まれるように小浜湾が形成されている。天然の良港だ。 丹後街道の西隣が舞鶴で、東隣が敦賀である。舞鶴、敦賀という丹後と北陸双方の交通路の先端部間を結ぶ丹後街道の中央に位置する小浜は、つまり交通の便が悪い。立地は宇和島に似ている。 筆者の全国鉄道路線踏破図の中、乗車済みの朱入れがなかなかできなかったのもそれが理由だ。無論、筆者はマニアでないので執着はしない。 鯖街道は、小浜から京都まで一塩の鯖を一晩で運んだ糧食ルートだ。小浜は、京都朝廷の食料供給地として「御食国(みけつくに)」との呼称があてられている。ただし鯖街道という名称は近時のものだ。鯖については櫓山人もなにやら言っているし、その他、カニもカレイもフグも名産なので食いしん坊にはたまらない土地である。 人口に比して寺数が多いのも小浜の特徴。寺数は130あまり。「海のある奈良」と呼ばれる。 筆者は内外海半島の外海をめぐる蘇洞門(そとも)めぐりの観光船に乗り込んだ。1時間ごとの発着だ。次の便まで40分ほどあるので観光船の発着場、フィッシャーマンズ・ワーフ2階の食堂で「へしこ茶漬け」を食べる。へしことは、小浜 |
では鯖のぬか漬けのことである。これを焼きおにぎりで包み、だしをかける。崩してかきまぜて食べるのである。さらに7品盛りの刺身と、さば寿司を2貫別注。少し、喰いすぎ。 食堂の窓は桟橋に面している。遊覧船が桟橋に戻ってくるのが見えた。 階下に下りると館内の香ばしい匂いに身体が反応。何かと思えば「浜焼き鯖」だ。鯖1尾を木串で串うちし炙り上げる。見るからに旨そうだが、もう入らない。最近、胃袋が縮んでいるのだ。 蘇洞門めぐりの遊覧船の乗客は、6人だけ。 気兼ねなく景色を独り占めできた。日本海の風が冷たい。他の5人は船室から出てこないのだ。筆者は終始デッキに佇んで、エメラルドの海と奇岩、洞門、断崖を愉しんだ。本当に美しい。この瞬間、余事の一切が頭から完全に抜け落ちた。ほんの僅かな時間だが、この瞬間をリフレッシュというのだろう。ただ、それだけのために2時間半をかけて来た、そういうことなのだ。 駅に戻る途中「小浜名物『カレー焼き』」の看板が目にとまる。通り過ぎたが駄目だ。正体を確かめたくて引き返す。1個購入。予想通りと言うか、細長い大判焼きの中にカレーが入っているものであった。 名物なの?これ、小浜の? |



蘇洞門の断崖(左端と中央) 中央画像が大門小門と呼ばれるアーチ 左端が「カレー焼き」


| 宇多津は四国の玄関口である。 しかし、JR宇多津の駅頭は都市近郊の住宅街のような佇まいである。隣駅、丸亀が寂しげな地方都市(というよりは町)然としていたが、宇多津と比べれば、立派な街であったと思い返されるほどの何も無さである。 しかし、宇多津には瀬戸内海を見下ろす「ゴールドタワー」がそびえている。ゴールドに輝く外観。映画「タワーリングインフェルノ」の舞台となったビルにどこか似ているタワーである。 料金システムも独特だ。駐車場のようである。基本料金840円で30分プラスサービスの10分間を過ごせる。これを越えると15分で105円が加算されてゆく。入場料としては高値付けである。最上階の展望室に紙コップ型のジュースサーバーがあり、無料で何杯でも飲めるようになっているのは、この高値感を緩和させる装置であろう。展望室にはソファーやテーブルが並べられている。座って飲んでいけということだ。 地上では子供むけのプレイランド、カラオケ、パターゴルフなどの設備が併設されている。入場料は会員、ビジター、タワー見学に分けられ、戸惑うこと必至の入場システムである。タワー見学者は、ビリヤード場のような入場時刻を打刻したカードを渡され、帰りに料金精算をするのだ。 |
150メートル強という高さからの眺めは素晴らしい。瀬戸内、讃岐平野を一望できる。長大な瀬戸大橋の姿も美しい。 瀬戸大橋で渡海してきたJRの線路が高松方面と、松山・高知方面に分岐している。さらに高松と松山・高知方面を結ぶ線路がまっすぐに走る大きなループ型の三角形がタワーから確認できる。 わからないのは、展望室に展示されている「純金のトイレ」である。 このゴールドタワーには「純金のトイレ」が展示されているのである。意図がわからない。 純金のトイレの展示。誰か止める人間はいなかったのか?タワーの行く末を案じる筆者である。 眺めを満喫し、地上に降りる。 昼飯をとろうにもなにせ街が形成されていないのだ。先ほどまで滞在していた丸亀で食べてくればよかったのだが、香川県なのになぜか丸亀にはそそられるうどん屋がなかったのである。丸亀を見限って宇多津へ来たのだ。「一流食堂」って看板に入る勇気を持てなかった自分を反省である。 結局チェーン展開の「将八うどん」でうどんを食べる。けっこういけるから恐ろしい。考えてみれば宇多津には「おか泉」があったではないか。下調べなしのブラリ旅での過ちを今回も犯してしまった筆者であった。 |


| 4層に積み上げられた堅牢な石垣の上に3層3階の小振りな天守が載っている。 「石の城」との別名のとおり、内堀、二の丸、三の丸、本丸と各階層すべての周囲が石垣に覆われている。ところによっては20メートル以上の高さで城壁が続く。「扇の勾配」と呼ばれる美しい傾斜の石垣である。 城の名は「丸亀城」。 四国の国境を守るかのような堅城である。しかし戦国の城ではなかった。慶長2年(1597)と言うから関が原の3年前の築城である。 JR予讃線の車窓からも望見できる。 瀬戸大橋は海を越え、四国入りすると、高松方面への坂出口と松山・高知方面への宇多津口の2方向に分かれる。丸亀は宇多津の隣接駅である。 いつも車窓から眺めるだけの城であったが、まがりなりにも近世の旧天守閣が残っている12城のうちの1城である(他はこちらでどうぞ)。一度は訪れねばならない土地であった。 岡山発の高知方面行き「南風5号」で丸亀に向かう。岡山から2駅で丸亀である。新幹線と組み合わせれば、自由席特急券は260円で済む。 車窓から見えるくらいだから、駅から城までの距離はたいしたことはない。丸亀駅に降り立った筆者はさっそく、丸亀城を攻略した(だから、攻 |
めてどうする)。 駅前の富屋町商店街と通町商店街はいずれも道幅狭く小さなアーケード街である。シャッターを閉ざし閉店した店も散見される。街として、けっして賑やかな観光地でないことは明らかだ。 すぐに城に行き着いた。内堀からデジカメで数枚の写真を撮るうちに電池が切れた。短3電池での補充が可能なので、別に慌てる必要はない。 (コンビニで購おう) と、周囲を見回すがコンビニがない。そう言えば駅からここまでコンビニはなかった気がする。幾筋か歩き回り、コンビニを求めたがなし得なかった。恐るべし丸亀。山陰じゃないのにコンビニがない街(ま、どこかにはあるでしょうけどね)結局、小さな電気屋で乾電池を購入した。 丸亀城は二の丸、三の丸、本丸がそれぞれ平場(曲輪)となっており、そこからの眺望がすばらしい。讃岐の野や瀬戸内の海、9キロ強のかなたで中国と架橋された瀬戸大橋の眺めなど時を忘れさせる何かがある。しかも、観光地ずれしていないから、雰囲気がのどかである。 腰掛けに自然に腰が降りてしまい、時を忘れさせる雰囲気というのは、求めて得られるものではない。松山や明石で感じた「いい城を持っている街」という印象は、丸亀にもあてはまるようだ。 |



| 海軍記念館を求めて歩き回る筆者。舞鶴はサイン下手と断定をした。絶対に行き過ぎていると確信したのは、明らかに行き過ぎていることを示す現在地表示の地図を見たからだ。こんな地図を掲出するなら、該当地に目印を出せ! 来た道を戻り地方総監部の入り口で海軍記念館の所在を尋ねる。 「この敷地内にあります。氏名、住所などを記入してこの見学者カードを目立つところに・・・」 書けよ!そういう大事なことは、地図にも!標識にも! 総監部敷地内を散策。自衛官がランニングをしている。海軍記念館は、総監部大講堂の一部を利用した1階2区画のこじんまりとしたものであった。総監部正面は白く塗装した砲弾の外殻が道路際に並べられ、どこか牧歌的な静寂に包まれた空間である。 総監部の敷地を出て帰路の途上、自衛隊桟橋でも見学を申し出る。迷彩服をまとった守衛が指差す受付にて再び記帳。 「今日は、岸壁までの見学が許可されています」 「写真をとってもいいですか」 「どうぞ」 桟橋には4隻の艦艇が停泊していた。排水量の大きい艦艇を先頭に、排水量順に並んでいる。歩 |
いていると、大きさの違いがよくわかるもんだ。 先頭から護衛艦「しまかぜ(4,650t)」「はまゆき(2,950t)」「あぶくま(2,000t)」ミサイル艇「うみたか(200t)」ミサイル艇は3軸スクリューでめちゃくちゃに速そうである。護衛艦は30ノット、ミサイル艇は44ノットは出るそうな。思わずカメラ小僧になってしまった筆者。対岸に接岸しているのは、イージス艦の「みょうこう(7,250t)」機密の塊、イージス艦はさすがにあまり目のふれるところには置かないのか。換装のためか、機密のためか、SPY1レーダーなどの周囲はブルーシートに包まれている。 ひとつの旅にはひとつの想い出で十分。堪能しきった筆者は、ゲートの守衛の敬礼に送られ帰路につく。思わず答礼しそうになる自分が恥ずかしい。こころなしか背筋が伸びて歩幅も広がっている。 赤レンガ倉庫街らしいエリアは、工事中。あいかわらず、そういう観光資源を示す表示は何ひとつない。確認しようと工事中のゲートをくぐったら、警備のおっちゃんに怒られた。 「あかん!」 途中「長谷川巳之助商店」で甘鯛と鰤の味噌漬を購入。期待をもてそうな物件であった。結果はまた今度ということで、ひとつ。 |



画像左から 「舞鶴地方総監部」・「海軍記念館」・「赤レンガ建造物(市政記念館)ほかにも倉庫街などあり」
| 舞鶴は、何県でしょう? 日本海側であることぐらいは認識できても県名まではわからない人が多いのでは? 「え~と、大陸からの引き揚げ船の港で~(知らないか最近の子は)・・・福井かな?」 はずれ。正解は京都です。 「え~?京都って海に面してないんじゃないの」などという声が関東以東から聞こえる。反省しなさい、そういう人は。ちなみに兵庫にも日本海側に海があるからね。 立春も過ぎた一日、舞鶴に向かうことにした。 かつて海軍鎮守府のあった街だ。現在では地方隊として地方総監部が置かれている。 海上自衛隊の編成は外洋への機動の可能な「自衛艦隊」と沿岸部の防衛・「自衛艦隊」への後方支援を担当する各「地方隊」に分かれている。舞鶴地方隊は秋田県から島根県に至る日本海側が担当海域である。 さて、舞鶴。 大阪からの侵攻ルートはふたつである(ミリタリー菌に冒されているな)。尼崎から丹波篠山を通り北上するか、京都から嵯峨嵐山、亀岡を北上するかである。 尼崎ルートは福知山経由で舞鶴にむかうが、その途上、綾部以降は京都ルートと同一である。福 |
知山、綾部間は3駅しかない。結局、京都からの方が最速で30分程度早い。 舞鶴と一口に言うが「舞鶴」という駅はない。「西舞鶴」と「東舞鶴」ふたつの駅が舞鶴を形成している。両駅間は7キロ、時間にして7分程度は離れている。標高300メートル強の五老ヶ岳が両駅の間を分かっている。街の雰囲気もまったく違う。 西舞鶴は、足利、織田、豊臣、徳川の世を生き抜いた希代の世間師「細川幽斎・忠興」父子の隠居城である田辺城蹟があり、城下町の風情あふれる街としてつとに知られる。 東舞鶴は、既述のとおり軍都である。軍関係の建物があったためか、赤レンガの建造物が多く、赤レンガ建造物残存数では日本一である。 そして東舞鶴は「標識下手」である。駅から徒歩で筆者が目指したのは、海軍記念館。西舞鶴に向かう国道27号線沿いにあるはずのその建物を求め、筆者は歩きつづけた。建ち並ぶ赤レンガの倉庫を見つつ、海上自衛隊の桟橋を通り過ぎ、舞鶴地方総監部のゲートを横目に歩きつづける。しかし、見当をつけた地点にそれらしい姿も案内も何もないのである。 (はて、もう少し先か) さらに歩を重ねたが明らかに行き過ぎている。 |
| 豪雪地白山へ行くか、神秘の富山湾へ向かうか確たる目標もなくのんびりと宿を出る。 金沢は、この冬初の寒波に襲われていた。降雪はまださほどではない。しかし、この寒気が、この後、戦後最高の積雪を記録することになる寒波の第1波であろうとは、この時点では無論知る由もない。 世界に冠たる豪雪地、白山連峰にむかうには少し勇気が必要な寒気である。ルートの確保も実はおぼつかない。JR西金沢へ出、北陸鉄道「新西金沢」から鶴来までむかう。そのあとの行程がつかみきれない。「何とかなるさ」とたかをくくるには、やや危険な気候である。 結局、氷見へ向かうことにした。北陸本線で富山県高岡にむかう。金沢からは特急で30分、在来線でも40分程度だ。 高岡を基点に万葉線(路面電車)が新湊にむかい、城端線(じょうはなせん)は終点「城端」からバスで20分、五箇山に繋がっている。氷見線はブリの街、氷見へ向かう。 富山県人は、郷土愛の深さ、世界一である。 郷土の誇りは、すべて世界一にランキングされる。(無論、自薦である) 氷見線の接続待ちが約1時間。駅周辺をぶらつく。街はかぎりなく昭和である。 |
若者の姿は少ない。駅にいるのは、潮風で吹き締められたような顔の親父の群れ。クリスマスも近い日曜日だが街に浮薄な雰囲気は微塵もない。 クリスマスをこれほど無視できる街も珍しい。すごいぞ高岡、日本男児の街である。 氷見線は1時間に1本。下手をすると2時間に1本のダイヤだ。高岡-氷見間18キロ、30分しかかからない。路線は能登半島の内側を北上する。 これほど湾岸に接して走る線区は、そう多くはない。国定公園「雨晴海岸」を擁する「雨晴駅」で途中下車をした。 「雨晴」と書いて「あっぱれ」と読む。嘘。「あめはらし」です。 駅前には、「世界一の景勝地雨晴海岸へようこそ」の横断幕。やっぱり世界一である。(無論、自称) 寒い。猛烈な寒気団が上空にいる。海は荒れ、鉛色の雲が低く垂れ込め、晴れていれば見られるかもしれない富山湾越しの立山連峰の姿など望むべくもない。わかってはいた。高岡駅には「本日の雨晴海岸の見晴らし」状況が表示されているのである。今日は「×」だった。 観光客の姿はひとりもない。そそくさと帰路につく。次の列車を逃すと1時間、寒風に打たれねばならない。氷見は今度でいいや。 |



| 福岡空港へのランディングアプローチは海からの進入が多い。その際、眼下に広がる玄界灘に突き出す細長い洲が目に留まるときがある。 「漢倭那国王」の金印が発見された志賀島を突端にいただく海の中道である。 博多駅からJRで門司港方面に乗車、快速で10分程度の「香椎(かしい)」で香椎線乗り換え、「西戸崎(さいとざき)」方面のワンマン2両編成のローカル線に揺られること20分で「海の中道」駅に降り立つことができる。博多港から市営の渡海船もあるとは、あとで知った。 「海の中道」には、玄界灘に面した海浜公園がある。マリンワールドや宿泊施設も備わったリゾート施設もある。寒波に襲われたその日、海浜公園を歩いているのは筆者ひとりきりだが。 玄界灘を一望に見渡す潮見台は、たたきつけるように襲ってくる北風と真っ向勝負。 玄海灘のかなた、大陸から吹き渡ってくる寒気は暖かい日本海で水蒸気を生み出し、それが筋状の雲となる。彼等は西高東低の気圧配置で生まれた通り道をまっすぐに日本列島へ向かってくる。衛星写真では筋上だが、地上から眺めると「ぽっぽっぽっ」と小さな雲の固まりがちゃんと列を作ってこっちにむかってくるっぽぉ。 縦列進軍の雲部隊は列と列の間にちゃんと隙間 |
を作っているっぽ。ぽぽぽぽぽ。 香椎線は1時間に2本の運行である。 土地勘のない駅での最大の悩みは列車の行き先表示が「?」なことである。 「××行き」の「××」が知らん地名だ。目的地まで列車が行くのか、途中で終着してしまうのかそもそも、目的地へむかう列車なのか、一切わからない。時刻表を持ち歩いたり、乗り継ぎに時間のゆとりがあれば、駅員や乗客に聞けばいいのだが、えてしてローカル線のダイヤは幹線からのタイムリーな接続設定をしているため、駆け足の乗り継ぎであることが多い。 無警戒でホーム最後尾の階段を駆け下りた筆者は、目前の列車に飛び乗った。しかし、その列車は筆者の乗るべきものではなかった。実は別の車両が同じホームの反対側、最先端に停車していたのである。2両編成の列車に対して、ホームが長すぎる。筆者の視界にその姿が納まらなかったのであった。そうと察し、発車の直前、列車を飛び降りた筆者だが、走り去る列車を見ることすらできなかった。同時刻に3本のローカル列車が発信していたのである。やられた! |


| 佐世保市内のアーケード街が途切れる西端からやや南下、これから山の隆起がはじまろうとするそのふもとに旧海軍のガンクラブ(士官サロン)「水交社」の一部をかたどった「海上自衛隊佐世保資料館(セイルタワー)」がある。 7F建ての資料館には、日本海軍史資料が幕末を起点に現代まで各階に展示されている。 歴代の佐世保鎮守府長官の写真も並んでおり、当時、閑職と言われたこの職に第8代長官として赴任していた東郷平八郎の姿もある。 日露の戦役を想定し、連合艦隊長官にこの東郷を据えた山本権兵衛の判断基準が一言に凝縮された「東郷は運が良かばい」は、筆者の好みの一言である。 セイルタワー1Fの小さな土産物売り場には、佐世保発祥「海軍さんのビーフシチュー」と「入港ぜんざい」がある。横須賀でブレークした「海軍さんのカレー」や呉の「海軍さんの肉じゃがカレー」に対抗する物件である。 さっそく購入。ふとかたわらを見やると、 「日露戦争時の連合艦隊ハガキ!」 買わなきゃ、買わなきゃ。 「缶パン(乾パンではない。缶に入ったパンだ)!」 フレーバーによって海自、陸自、空自の別で意 |
匠をこらしている。買わなきゃ、買わなきゃ。 「キャップ!」 佐官タイプと将官タイプがある。 買わなきゃ、買わなきゃ。 気がつけば手提げ袋いっぱいの購入物件だ。 佐世保と言えば「佐世保バーガー」。 ハンバーガー発祥の地として近年、めっきり街おこしに貢献している。「手作り」と「巨大」がキーワードである。「マヨネーズ」もそれに加わるか。「ヒカリ」という有名店は行列らしい。駅前のLという店の出張所でレギュラーを購入。750円也。出来上がりまで5分待ち。 「ハイ」 と手渡された紙袋は、ぶら下げるようにではなく、横にして差し出される。 ニトロを運ぶように慎重に持ち運び、さっそくチェックインしたホテルの部屋でご対面。 (デカイ・・・な。) 最後まで食べきった。 その日はこれだけ。だって、腹がいっぱいだもの。よかったのか、悪かったのか。 博多のK君から「モスバーガーとどっちが美味しいですか」と素朴に聞かれて、即答できなかった筆者であった。そういえば佐世保にもモスやマックはあったな。 |



画像右端が「佐世保バーガー」、バーガー右下端の角版画像が同率比の500円玉である。
| 駅前がすでに港である。 港には護衛艦が浮かんでいる。JRと松浦鉄道の高架ホームからその姿を望むことができる。 筆者はマニアではないのでそれが第2護衛隊群所属のどの艦艇かはわからない。 横須賀、呉にならぶ軍港、佐世保の景色が筆者の眼前に広がっている。 横須賀以上に平地が少ない。市街地は港を取り巻くわずかな土地に直線状に形成され、周囲を山々に取り囲まれている。その周囲の山々にも住宅が密集し、複雑に入り組んだ湾岸の地形ぞいに道路がつづら折れに敷かれている。 街は北から南に傾くように東西を貫く35号線ぞいに発展している。駅前がその東端となり、途中からふたつのアーケード街が一直線に繋がり、その終点で街が途切れる。距離にして1キロ弱といったところか。 駅前の市バス乗り場から45分程度のところに景勝地「九十九島(くじゅうくしま)」を見下ろす「展海峰(てんかいほう)」にむかう便がある。 「『コロニー』行きのバスに乗ってください」 バス案内所のガイド嬢の言われるままに、バスに乗る。バスは1日5本しかない。 すさまじい屈曲の連続と、市民の足はこれしかないからだろうが、停留所ごとに停車する低速運 |
行である。タクシーならもっと早かろう。 「展海峰入口」という停留所で降りる。 するどく帰りの時刻表を覗いておく。 31分しか持ち時間がない。その次の便は3時間後だ。時間つぶしになる施設があろうとは思えない雰囲気だ。展望台まで急勾配の上り坂をダッシュである。 びゅおおおおおお 「うおお!寒かとですばい!」 九十九島を見下ろす、展望台は丘の上にせり出すように設置されている。 眺望は抜群だが、12月としては20年ぶりという大寒波が日本中に猛威をふるっている。手が凍りつくような寒さと強烈な風に体があおられる。 周囲に観光客の姿はない。 絶景をひとり占めであるが、いかんせんあまりにも寒い。すぐにこの独占権を手離した。 「バスの時間が迫っている!」 再びダッシュ! 慌しいことこのうえないな。 坂道を転がり降り、バス亭に到着。 バスが来た。 案の定、往きに乗ってきたバスである。 運チャンが「こん物好きめ」という視線をチラリと投げかけてきた。 |
金沢行10 →→→back 金沢行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
| 「せっかく来たのだから」とあくせくする必要のない土地がある。 ひさしぶりの金沢で、筆者はのんびりとした時を過ごしている。犀川大橋の袂にある3階建て木造家屋の定食屋「寺喜屋」はレトロな雰囲気の店だ。地元の魚を食べさせてくれる。さばみそで飯がすすんだ。1階が満席になれば、上階にあがることができる。こちらの方が犀川を見下ろせて気分はいい。 食後、街をそぞろ歩く。 「豚バラ(トンバラ)定食」の「宇宙軒」は入口がきれいになっている。干からびたサンプルがなくなっているではないか。電飾ボードに豚バラの写真が載っている。 「えびみそスパゲティ」の「たしの木」柿木畠店がタンタン麺屋に変わっていた。近江町市場「さわいのパン」はご主人が昨夏亡くなって店をたたんでしまった。街はやはり少しずつ変わってゆくのだ。時の流れを押し戻すことはできない。 石川近代文学館で刻を過ごす。 徳田秋声、室生犀星、泉鏡花、井上靖、五木寛之・・・文豪、大作家のオンパレードだ。若かりし頃、そのまばゆいばかりの存在感に圧倒されていた。しかし、筆者も歳を重ねた。作家それぞれの人生に思いが至る程度の経験が、作品への視点 |
を変えている。その変化が我ながら愛しい。 疲労がたまっていたのだろう。睡魔に誘われるままに宿に戻って横になる。ほんのひととき、と思っていたが気がつけば日が沈み、夕闇があたりを包んでいる。 乙女寿司に向かう。 堪能した。 帰路、屋台のタイヤキをほおばる。街はクリスマスのイルミネーションに彩られている。華美ではない。北国の冬支度が進む師走の一夜である。 翌朝、朝から降雪。 大陸から寒波がやってきた。 寒い。 外気にふれているだけで手がかじかむ寒さだ。 高岡に向かい、氷見線に乗る。昼過ぎに帰沢。 雪は続くともなく、止むともなく、断続的に降り続いている。昨日同様、睡魔に身をまかせ、再び深い午睡の時を過ごす。 目覚めると月が浮かんでいた。傘をかぶった朧月だ。 日曜夜の「つる幸」にむかう。 店内は静かだ。 玄関前の庭石にひらひらと雪が降りかかり、積もることなくほぐれるように融けてゆく。 宴が始まろうとしていた。 |



画像左から、定食屋「寺喜屋」、「石川近代文学館」、「香林坊の百貨店「大和」前」
「サンダーバード」の車窓から→→→back 「サンダーバード」の車窓から 「サンダーバード」の車窓から2
| 週末の「サンダーバード11号」富山行き、新大阪9時46分発は満席である。 人気路線の人気列車である。 大阪-京都間は京都線新快速と同じ路線だ。山崎の紅葉と言うよりはまだらな海老茶色の山々を左に見つつ入洛。京都の次は福井に停車。「サンダーバード11号」は停車駅の一番少ない最速編成だ。 山科で東海道線と別れを告げる。列車は右手に琵琶湖を大きく映し出しながら快走する。新幹線や東海道本線が琵琶湖の景色に冷淡なため、この湖西線から眺める琵琶湖が車窓に映るそれの中で最も美しい。筆者は残念ながら、1人がけのC列なので反対側である。毎度のことなのであきらめている。満席が予想されるサンダーバードで2列シートを選び、隣を他人に支配されるのは避けたい。筆者はひとりっこなのだ。 進行方向左側、比叡山の袂を通り過ぎる。 車窓に長らく連れ添った琵琶湖とも別れを告げると、いよいよ路線は山峡に押し入ってゆく。雪が見え始めた。12月中旬の今、湖北ではまだ、積雪というほどの量ではない。山峡の小さな集落はうっすらと雪の白装束に身を包んでいる。静かなその佇まいが車窓ごしに眺める筆者の心を鎮めてくれる。 |
近江塩津で東岸を走る北陸本線と合流。 敦賀の手前、新疋田を通過。北陸トンネルの前に、ループトンネルがある。下り路線は直通トンネルだ。この線区、左右に次々と路線が現れるが、それが下り路線だったり、若狭から来る小浜線だったり、ループ終了後に合する下り路線だったりと、ややこしいことこのうえない。筆者はマニアではないので、無論そんなことに興味はない。 そして列車は、北陸トンネルに入った。長い暗闇が続く。13キロ強の長さは、山陽新幹線の六甲トンネルに次ぐ。 そして列車はトンネルを抜けた。 一面の雪景色と、峰々を包む水蒸気の白いベールが眼に飛び込んでくる。さきほどまでの晴天をすべて別世界の景色へ押しやる圧倒的な変化だ。 やや古びた街並みの福井を経て、海側に大きく広がる平野の中央を、軽快に飛ばすサンダーバード。芦原温泉ではあまり乗客が降りない。次駅加賀温泉でそれなりの降客があった。駅前に菩薩像がそびえているが、何じゃあれは? そして列車は加賀温泉を発し、小松を通過、北陸新幹線の工事が進む金沢駅に入線していった。 |



| 新都心新宿と神奈川県小田原を結んでいるのが「小田急線」である。 営業キロ数にして82.5キロ。新宿-小田原間は特急「スーパーはこね」で1時間10分、急行で1時間40分程度。JRに湘南新宿ラインができた今、JRでも1時間20分で行き来が可能な距離である。 関西では大津-三ノ宮間(83.4キロ)に匹敵する。ただし、この区間はJR新快速で1時間1分。やっぱ、異様に速いな新快速。 長距離を走る路線の宿命で、小田急は乗客が多い。筆者の乗降駅「登戸」では、朝6:31の新宿行急行で座ることは困難だ。その前に乗り継ぎに使う南武線にいたっては座る以前にかなり混んでいる。恐るべし首都圏の過密人口。 「登戸」は筆者にとって故郷の範疇に入ると言っていいだろう。雑然とした猥雑な町だったが、現在小田急とJRの両駅で改装工事が進んでいる。改装中のホームは360度、見晴らしがいい。完成すれば両脇を遮蔽されるであろうから、今のうちに思いの外、川べりであったり、生田緑地の低い稜線が近かったりするこの光景を記憶しておこう。 新宿行急行は登戸駅発車後、すぐに多摩川を渡河する。眼下の多摩川堰は、かつて山田太一脚本の「岸辺のアルバム」の舞台となった。台風による増水で川べりの狛江市の新興住宅が削り取られ |
た、まさにその現場である。 筆者が東京を離れる4年前に進めていた高架工事はまだ続いている。住民の大反対をうけて地下ホームとなった高級住宅地「成城学園前」の次駅かつて筆者の住んでいた「祖師ヶ谷大蔵」はあっと言う間に通過。複々線化が完成したこの区間、急行は急行らしい快足を発揮する。かつては「成城学園前-下北沢」間が癌だった。抜くに抜けない各駅停車が詰まり、急行も各駅停車も所要時間は同じ。超満員のラッシュ時、毎日ひとりは女性が貧血で倒れていたと言っても過言ではない。 「祖師谷大蔵-千歳船橋」間で環八を通過。 高架のせいで眺めがいい。渋谷や新宿の街並みが遠望される。陽が登り、街が一瞬、一面の茜色に染まる。他の一切の色が存在感を失い、やや紫がかった無彩色な街並みが眼下に広がる。 「世田谷代田」の前で環七を通過。完全に都心に入る。「下北沢」に停車後、「代々木上原」に入線。千代田線への乗り換え客は多い。千代田線は表参道を経て御茶ノ水、日比谷方面へ。小田急線はこのあと代々木八幡の大カーブで左に大きく転進、彼方に見える超高層ビル群の袂に向かう。右手に聳え立つNTTドコモのエンパイアステートビルのようなタワーをすり抜ければ新宿である。 それにしても、首都圏私鉄ネタとは、とほほ。 |



| 大雨である。 局地的な集中豪雨により羽越本線のダイヤが乱れている。新潟の手前で列車の運行が止まった。バスによる代替運行が実施されている。 特急数本が運休する混乱のさ中、筆者にとっての幸運が転がり込んできた。酒田方面にむかう特急「いなほ1号」が25分の遅れとなり、乗れなかったはずのこの特急に乗り込むことができたのである。 幸運は続く。「余目」で接続の新庄行き陸羽西線がこの「いなほ1号」の到着待ちで3分の延発である。筆者は「余目」で降車した乗客のトップをきって跨線橋を駆け上がり、駆け下りる。脱兎のごとく待機中のローカルワンマンの車両に飛び込んだ。通常ならば20~30分は接続待ちとなる乗り換えだ(なにせ、陸羽西線は1時間に1本のダイヤである)。すべてがスムーズにつながっている。業界用語で言えば「シームレスな接続」ってやつだ(どこの業界だ?) 大雨の影響で陸羽西線も注意運転中だ。もともと亀のように遅い在来線が、骨折した亀のように遅い。車窓を愉しむにはもってこいである。 陸羽西線は、新庄、余目間を結んでいる。新庄発の下り列車の視点から見れば途中駅「古口」で最上川に接し、以後かなりの距離を川下にむかっ |
て併走する。最上峡の景色が車窓の白眉である。「古口」から最上川下りの屋形船も出ている。 「五月雨をあつめて早し最上川」 本当は筆者の句なのだが芭蕉に100円で売った。元禄2年のことである。 今、筆者は川を遡上している。 新庄行登り列車の進行方向左手に最上川が流れている。列車の進行方向、左側のシートは1席1列だ。しかも車窓にむかって軽く角度を変える事ができるようになっている。対面の右側はボックスシートあり、ロングシートあり、トイレありでなかなかに変化に富んだ車内である。 頬杖をつく筆者の視線は、車窓にむけられている。 周囲の山々の背は高く、谷を流れる最上川の水量は豊かだ。雨の影響か、満々と満ちたその水面は山裾を沈めているかのように木々の梢を浸している。 「峡」という言葉の持つ狭隘なイメージがそぐわない景色をこの川幅の広さは車窓に与えている。 山々は水蒸気に満ち、深緑の山襞から白煙がたなびくように水蒸気が沸き起こっている。 やがて、列車は「古口」を過ぎ、車窓は最上川と別れを告げ、平板な在来線の光景に帰っていった。 |



画像左から、特急「いなほ」、「陸羽西線」、新庄駅に停車中の山形新幹線「つばさ」 無論筆者はマニアではない
| なぜこんなに中高生が多いのか?山形にむかう列車の中は中高生がいっぱい。平日ならば納得もするが今日は日曜日なのだ。駅に停まると中高生が乗ってくる。あ、また乗ってきた。なんなんだ君たち、少しは降りなさい、うるさいんだから。あ、また乗ってきた。山形の中高生は休日の外出は制服でなければならないのだろうか。10月1日から衣替えで冬服着用だそうだ。 この日、東京では10月としては7年ぶりの真夏日、最高気温が30度を越えている。ちなみに山形の最高気温は22度だ。涼しいなあ。 山形を代表する武人は最上義光。山形駅北方、徒歩で5分の距離にある霞城(かじょう)公園には、隣国上杉の宰相、直江兼継率いる2万5千の大軍を前に寡兵7千(実質3千の兵)で徹底防戦を成し遂げた義光の像がある。 堅牢な石垣は往時のままで、水をたたえた堀は重厚と呼んでいい趣きがある。 一再ならず訪れているはずの山形だが、16年の歳月はすべての記憶を忘却の彼方へ流し去ってしまったようだ。懐かしさに浸るとっかかりもないままに新たな思い出作りに励むことにした。 山形と言えば、米沢牛に代表される山形牛だ。そして蕎麦。さらにはフルーツ。ラ・フランス、さくらんぼ、りんごに葡萄、柿、プラム、フルー |
ツ王国は岡山だけではないのである。 まずは山形牛を食べるべく、老舗「佐五郎」に向かう。メニューを眺めて悩む。何を頼むか? 「すきやき・しゃぶしゃぶ・ステーキ」三択である。価値観が確立したまっとうな大人ならば悩まない。断固として肉なら××と言って頼むんだろう。そういう人が羨ましい。筆者の心はいつもメニューを前にちぢに乱れるのである。大阪在住以来ステーキが一番(しかもソースなど不要)という価値観は有しているであるが、なぜか老舗では「すきやき」「しゃぶしゃぶ」を頼んでしまう。今回は「すきやき」だ。庄内麩を使っているのか平たい麩が入っている。同時に頼んだ佐五郎漬は粕漬の山形牛を焼いたもの。これと牛そぼろ豆腐で酒が進む。 蕎麦は「佐藤屋」で芋煮蕎麦を食す。芋煮と蕎麦の両方を食べたと言える便利な名物だ。同じく老舗の「庄司屋」で板を頼む。蕎麦処山形では東京近辺の高級蕎麦屋のような5箸でなくなるような貧弱な盛り付けの蕎麦はない(きっと)。長方形の大きな板にせいろを敷き、通常の2人前程度の蕎麦を盛るのである。 筆者は、七味を蕎麦にかけてもりを食べるのが旨いことに気がついた。今は、わさびもねぎも使わずに七味だけで食べている。これはいける。 |



| 杉木立をたたく雨勢が激しくなった。 雲が低く厚く空を覆い、樹齢300年から600年と言われる杉木立に囲まれた参道は、日中とは思えないほど暗く鬱そうとしている。 雨に煙る頭上の梢には白いもやがからみ、木々の間にたなびいている 石段に跳ね上がる水冠の数が増えた。 石段は静かに下っている。 長い下りだ。 遠く、石段の降りつく先に小さな社が赤い桧皮葺の屋根を濡らしている。 石段を下りつづける。 やがて参道は赤い欄干の太鼓橋に繋がった。 轟きのような底鳴りが橋の下を流れる渓流から聞こえてくる。 雨のために増水し茶色の濁流となって渦巻く音が響いているのだ。 岩の渡しのむこうに滝が白く輝いている。 滝も増水している。 はじかれたように勢いよく白い水を吐き出している。 さらに参道を進む。 周囲の杉よりもどっしりと年輪を重ねた杉の巨木が現れた。しめ縄を巻かれたそれは、樹齢1000年の「爺杉」である。 |
「爺杉」のむこうに塔が見える。 5層の塔だ。 静かな佇まいのその塔は「羽黒山五重塔」と呼ばれている。 平将門が建立したとも伝えられている。とすれば建立は西暦900年代ということになる。再建が1300年代。周囲の杉はその頃に植えられたのだろうか。 京都、奈良などの五重塔と違い、聳え立つことによる権威性は存在しない。周囲の杉木立が塔よりも高いのだ。見ようによってはミニチュアモデルのようにも感じられる。無論、低いわけではない。29.2メートルの高さは法隆寺、瑠璃光寺のそれら30メートル強よりもやや低い程度でしかない(ちなみに日本で一番高いのは、東寺五重塔で、これは50メートルを越える。第2位はそれより僅かに低く興福寺五重塔である)。 柿葺(こけらぶき)の屋根が雨にうたれ鈍く輝いている。かつては周囲に寺院もあったらしいが今はこの五重塔のみが山深い杉木立の中にひとり佇んでいる。 自然の中にポツンと置かれた塔は、人が作ったものとも思えぬ神秘性を備えていた。修験道の聖地であるのも頷ける景色である。雨のせいか霊的な気配が濃厚な絵であった。 |



| 逃げ出したのだ、何もかも置き捨てて。 この世のすべてのものから姿を消したのだ。 (ここまで、大友克洋著「アキラ」調で) 逃亡者は、北を目指す。現実からの逃避を決意した筆者は列車に飛び乗った。プライベートから、オフィシャルから、すべてのものから逃げ出すのだ、バイバイ。(あとが怖い、怖いぞお) 「つばさ107号」は定刻に東京駅を出た。 田端で並走する山手線と分かれ、列車は北に進路を取る。荒川を越え、利根川を越えれば追手のつく心配もなくなる。緊張の糸がほどけてゆく。 ススキの穂が満ちている。車窓に幾筋かの銀線が走る。山峡が霞み始めた。静かに雨が降っている。やがて、列車は駅に着いた。 1989年以来16年ぶりの山形である。 駅前がそれなりに整っているために勘違いしやすいが、中心地は七日町にある。駅から北東方向に徒歩で15分程度の距離だ。 逃亡者は居酒屋を目指す。けっして羽振りのよい派手な振舞いはしないのである。 心覚えの店があるわけではない。ただ街を流し目についた店に入るだけだ。 夜の街を七日町にむかって歩く。街は静かだ。途中、周囲の灯かりも絶え、本当にこの先に繁華街があるのか不安になるが、程なくネオンやショ |
ーウィンドウの輝く明るい街区に出た。本町から七日町に至る山形の中心地だ。 やがて一軒の居酒屋に入る。 生ビールを頼むと、「突き出しを」と言いながら、大量の枝豆ときんぴらが並べられた。枝豆を口に運び、煮込みとホタテバターを注文する。 「メニューにはありませんが芋煮がありますよ」 山形弁で語る店主はちょっとぶっきら坊だ。 山形の芋煮は「芋子煮」と書く。山形牛と里芋、コンニャク、しめじなどを醤油だしで鍋にする。これを食べずして秋の山形に来た意味がない。いや、逃亡のかいがない。 やがて店主が「サービスです」と「もろきゅう」を差し出した。東北の親爺は朴訥だ。無口だが心温かい。そして「もろきゅう」の量は非常に多い。酒も進み、店主と日本酒談義に花がさく。再び「サービスです」と差し出されたのは「蕎麦」である。無論量は多い。かなり腹にきているがこれを食べずには男がすたる。腹におさめた。 「会計をお願いします」支払いを済ませると 「これ、持っていって」 ビニールに包んだ枝豆を差し出す。 「さっきのは冷凍だけど、これは本物。旨いから宿で食べて」 ありがとう。やっぱ、東北はいいわ。 |
高松行3→→→ back 高松行 高松行2 高松行3 高松行4
| 製麺所のうどんは、1時間待ちが常態化しているらしい。もともと足(車)をもたない筆者は、山中にある製麺所を訪れることができない。したがって、最も人気の高いこれらの店が常に視野から外れており、「山越(やまこえ)」など、大きな駐車場も整備され、下手な企業より収益が上っているかもしれないとの話を聞いてもピンとは来ない。しかし、讃岐うどんが元気であるならばそれで良し。メディアに取り上げられた店のいったいどれだけが一時の繁盛とその後の衰退に耐え、生き抜けたことだろう。メディアなんか瞬間芸の世界。ネタになるなら何でも取り上げるが、物見遊山レベルの貪欲かつ無責任な「放送時間が埋まりゃあいい」という程度の意識しかない。税金取られるなら広告費使ったほうがましという大企業ならまだしも、一度メディアに頼るとそこからの撤退は難しい。GRPなどと言う専門用語に縛られ踊らされ、広告という一大消耗戦に突入することになる。 閑話休題。 社用とは言え、讃岐に来た以上、讃岐うどんを食べねばならない。 昼食に提携先の皆さんに案内されたのが八島の先、牟礼町八栗参道にある「うどん本陣山田屋」名前のとおり本陣のような立派な造りの旧家風の |
畳敷きの大広間で「釜揚げぶっかけ(玉子付)」と「冷ぶっかけ」を食べる。八栗は四国88箇所霊場のひとつ八栗寺がある。後背に聳える八栗山はあおむけの人の顔のように見えるので有名。 仕事の後は「魚好人」で魚三昧。 お造りは「すずきの洗い・トロ・いか(これが旨い)・かんぱち(もう絶品である)」まながつおの味噌漬(死にそうに旨い)・あこう鯛のアラ(死ぬかもしれない)」。 前回の訪問時に勧められた「こんぴらうどん」の「しゃぶしゃぶ肉うどん」の感想を伝える。すると締めに「それでは」と、ざるうどんを供された。これが旨いんである。やや細めの麺だがコシが強い。フェリー通りの「鶴丸」の冷ぶっかけのコシ指数を100とするなら、95はゆくな。同行のS氏と別れた後「讃岐家」に行き「なめこおろしうどん」を食す。 翌日、再び提携先の所長の車で羽立(はりゅう)峠の「源内」へ。カレーうどんを食べる。これが旨い。やや甘めのカレーだし汁に腰の強い麺。カレーうどん暫定日本一の座は「五右衛門」から「源内」に移ったのであった。しかも聞くところによると、この「源内」かしわうどんも滅法旨いらしい。どうせえっちゅうんじゃ、これ以上。 |



高松市内、ライオン通り周辺の店。左から「鶴丸」「讃岐屋」「五右衛門」

記事中「こんぴらうどん」の「しゃぶしゃぶ肉うどん」
| 快速「マリンライナー」は岡山、高松間を結んでいる。所要時間は1時間弱。 岡山発の1号車はダブルデッカーのグリーン車仕様だ。1階席は指定席、2階席がグリーン席。グリーン料金は950円。おトクである。先頭車両にはさらに運転席の後ろ、鉄道マニア垂涎のかぶりつき座席が用意されている。しかし、筆者はマニアではないので、2階に上る。 岡山は、瀬戸内沿岸都市とのイメージがあるが実は内陸都市だ。海辺の町児島までは特急、快速で約30分かかる。 児島で宇野行きの盲腸線が分岐する。終点宇野はかつての「宇高連絡線」山陽側発着港である。連絡線で食べた「讃岐うどん」を故郷の味とする香川県人の数は多い。 連絡線を過去の想い出の世界に追いやることになった「瀬戸大橋」は児島を発車後、小山をひとつぬけるとすぐに現れる。 上部を車道、下部を鉄道とした、9.4キロの大渡海橋である。上部を車道が走っているため、渡橋中、天井が延々と続くことになる。ただし、そんなことは先頭車両、しかも運転席の後ろに陣取らないとわからない。 列車が橋を渡り始める。 眼下に広がる瀬戸内の海と、そこに散らばる大 |
小の島々、列をなし、艦隊を組むように走行する艦船が非日常の世界に誘ってくれる。大きく扇状に広がる艦船の航跡が壮大なパノラマにリアルな存在感を与えている。 まさにそれらの船をまたぐように列車は走る。 間断なく眼前を通過する橋脚が思いの外、目障りなときもあるがこれは写真を撮る場合の話で、車窓を愉しんでいる分には気にはならない。 やがて、川崎造船のドックやコンビナートが広がり、坂出の工業地帯に入ったことを知る。四国側に渡ったのだ。四国側の瀬戸大橋接続部は三叉路になっている。正確に言うと、三叉路ではなく大きな三角形をなしているのだが。瀬戸大橋を渡り終えた線が、左に高松・徳島方面へ向かい、右へ松山・高地方面へ向かうため大きなループを描き分岐する。左右に分かれた線のむこうで高松方面から松山・高地方面へ向かう線が左右に分かれた瀬戸大橋からの分規線を直線で結んでいる。 車窓は、途中、四国の山々を映し出す。瀬戸内海に浮かぶ小島でも同様のシルエットが幾つかあったが、讃岐の山はおむすびのような角のない小さなコニーデ型だ。峰を作ることなく、単体で小さな三角形が讃岐の野に幾つもころがっている。 古い地質層のため、侵食をうけて角がとれてしまったらしい。いかにも讃岐な話である。 |



| 「頑張れ琴電!」 とりあえず、主義も主張もなく琴電を応援してみた。他意はない。ただ、応援してみたくなるのである、琴電。部員が9人しかいない夏の甲子園出場校のような感じだ。 讃岐のデパート、ふるさとの百貨店、高松天満屋(瓦町駅)から琴電は出発する。路線は3つ。琴平線、長尾線、志度線。JR高松駅から瓦町までは琴平線の延長路線がつないでいる。志度線が一番ローカルっぽい。ホームが他の2線に比べて改札から一番遠い。ただし動く歩道完備である。自動改札機も整備されている。しかもICカード対応。近代である。 筆者は切符を自動改札機のスロットに差し込もうとした(あれ?)切符の差込口がない。きょろきょろ捜すも見当たらない。無駄と知りつつ、ICカードのかざし口に切符をかざす。無論、無反応である。分かってはいたがやった自分に腹が立つ。(馬鹿にしやがって)つぶやきつつ、機械を撫で回す。何も反応はない(やっぱり馬鹿?)。途方にくれていると、駅員が呼んでいる。 「切符はこちらで改札をします」 切符を見せたら、鋏をいれられた。パッチン。 (うわ、懐かしい!) 琴電、チグハグである。 |
(きっと始発駅以外は、磁気切符なんてとんでもない話なんだろうな) と、考えた筆者のヨミはあたっていた。途中、駅員のいない駅では車掌や運転手がかいがいしく降客の切符を回収していた。(運転手もだぜ) 志度線は毎時3本のダイヤだ。 車両は2両編成。路線はもちろん単線。 スコトン、スコトン、町中、人家の軒先をかすめるように電車は走る。始発から途中駅の乗降による出入りがあっても2両の列車に乗客は6~10名まで。実にのんびりしたものである。時間は土曜の朝10時だ。 終点、志度駅は民家を改造したかのような駅舎で、最初、駅だとはとても思えなかった。このテイストは島根、一畑電鉄の大社駅に近い。 琴電志度駅とJR志度駅は目と鼻の先である。 駅前に名物「ぶどう餅」を売っていた。さっそく購入。3個一串のミニ団子である。口に含むと(しゅわあ!)口中の水分を吸い尽くされた。すっごいモクモク感。(やられた!)夏なのに吸水鬼のような菓子である。志度は、しかし、なかなかにそそられる物件が目に付く。「中華そば専門店」ののれんを掲げるプレハブ店、「つくねフライ定食」をメニューに載せる定食屋。どうも底の知れない怪しさに満ちた町である。 |



| 「近江」は、広闊である。 ただ、その広さは少なからず琵琶湖に担保されていると思っていたのだが、その認識は大間違いであった。なんと近江の平地は琵琶湖の2倍もあるそうな。 最大幅18キロもの湖面を湛える琵琶湖があれば、近江ののびやかな印象の根源をそこに求めてしまうのもむべなるかな、と思うのである。長浜城から琵琶湖を眺めていただければ、得心いただけるものと思う。 その琵琶湖の周囲、寛闊な平面にパッとビーズを散らしたように中世から近世への刻の流れを瞬間凍結させてしまったかのような町が点在している。近江の町は皆、刻の流れの中でそこだけが侵食されずに残された不思議な空間なのだ。 戦国の世、信長を含めた多くの勢力が京を目指した。京を制し、天下を制するためだ。 近江は京に至る戦略的要地である。北国街道や中山道、東海道の山峡から近江に出た瞬間、視界が開け、そこに物成りの良い肥沃な土地が広がる。海かと見まごうばかりの豊かな水量を湛える湖を中央に据えたその眺望は、これを凌駕するに関東平野か蝦夷地にゆくしかないであろう。その近江に橋頭堡を確保し本国との中継地とする。この地を扼することが京を占拠する必要条件であ |
った。だが京を支配すれば近江の役割は終わる。 安土も含めて、長浜、佐和山、小谷、彦根。近江の町は、刻の流れの中、衰微し消滅するか時代に取り残されていった。 近江八幡もそうだ。信長が楽市のために集めた安土の商人達は、安土城の炎上とともに街の象徴を失い、同時に保護者と消費者をも失った。 彼等を再呼集したのは、豊臣秀次。八幡山に城を構え、運河を開き、新たな町を形成した。 2代目となる町の保護者、秀次も秀吉に殺された。再び城がとりこぼたれたが、安土の時とは違い町は残った。 時が流れ、その町、近江八幡は今や近江を代表する一大観光地となった。近江牛を食べ、赤こんにゃくをひらひらさせつつ、井伊家、彦根が持つ城下町としての武張った印象と異なり、明らかに町衆の郷である印象をかみしめる。 JR東海道本線の近江八幡駅は隣の安土駅と違い新快速も停車する。「町」は「街」となった。安土は「町」が「集落」となってしまった。 近江八幡の観光資源は、近江商人の住居が集まる「新町通り」から「八幡堀」周辺である。JR駅から歩いて2キロ強、30分程度であろうか。もちろんバスもある。8つほどの停留所を過ぎれば目的地に到達する。いい風情の町である。 |



| 帰阪しようと川崎の実家を出たときにグラッときた。 地震だ。 路上にいたため、初期微動に気付かなかった。 ちょっと大きめの地震、そんな印象で家を後にした。人は運命の分岐点をその瞬間に意識することはない。この日、筆者を待ち受けていたのは、あの九州行以来の運命のいたずらであった。 「たいしたことはない」そう感じたその日の地震は震度5強。各家庭のガスメーターが自動的にガスをストップするのが震度5である。この日、東京ガスには自動停止したガスメーター復帰動作の確認電話が殺到した。 ガスメーター復帰動作の問い合わせに東京ガス職員が忙殺されている頃、都内を走るタクシーも殺到する乗客の対応に追われていた。地震発生後1時間、都内から空車のタクシーがいなくなっていたのである。筆者はこの時その事実をまだ知らずにいた。 名古屋に用向きがあり、電話を入れようと携帯の画面を見る。「しばらくお待ちください」などという見慣れぬメッセージが浮かんでいるではないか。 (なんじゃこりゃ?) 通話ができない。 「あとでいいや」 深く考えもせず、携帯をしまう。地震後、急増した通話量に回線がパンクしたのだとは後から気づいた。鈍い奴である、我ながら。 最寄の私鉄小田急線では、運行の遅れを告げるアナウンスが流れていたが、電車は走っている。タイミングよく入線した各駅停車に乗り、途中地下鉄乗り入れの急行への乗り換えもスムーズにできた筆者は完全にたかをくくっていた。車内アナウンスが、地下鉄千代田線は運転再開の目処がたたないのでこの急行は本線に入り、新宿までの運行に変わったと告げている。 「ラッキーである」 終点の新宿に到着。すべてが順調だった。 新宿駅構内に入り、東京行きの中央線に乗り換えようとしたときに、はじめて筆者は事態の深刻さに気がついた。 JRは山手、中央、総武、ありとあらゆる路線が運休。しかも、運転再開の目処はたっていない |
と駅員が声を張り上げている。改札は黒山のひとだかりである。新幹線は動き始めたらしい。だが東京駅に向かう手段がない。 地下鉄も全面運休。丸の内線も新宿線も使えない。 「タクシーだな」 気軽に考えた筆者は、大蛇のとぐろにように幾重にも巻かれた新宿駅前タクシー待ちの人波を横目に青梅街道ぞいに向かって歩いた。荷物は重いが、青梅街道と靖国通りの交差点のあたりなら、流しのタクシーを簡単に捕まえられると思ったのだ。しかし、事態はすでにそのような緊張感のない安易さを許容する状態にはなかった。記述したとおり、この時間すでに都心のタクシーで空車のサインを出しているような怠惰な車は一台としてなかったのである。 辻待ちを断念した筆者はヒルトンホテルのタクシー乗り場にむかった。 20人程度の行列ができていた。しばらく並んでいたが、車が来ない。来るわけはない。どこを走っていても客を捕まえられる状態で、わざわざタクシー乗り場に来る車があるはずがない。 そうと気付いた筆者は、ヒルトンよりもセンチュリーハイアットの方が空港から外人客を乗せてくるタクシーの数が多いかもしれない、と場所を変えた。しかし、状況はあまり変わりない。大在駅の記憶が脳裏をよぎる。陽が暮れかかってきた。さすがに焦り始めた筆者の前に空車のタクシーが近づいてきたではないか。ハイアットのタクシー乗り場に折れるウィンカーは出ていない。筆者はまだ路上にいる。と、ハイアットのドアボーイが突進してくる姿が見えた。見上げたプロ根性だ。客のためにタクシーを捕まえようというのであろう。 (ゆずるわけにはいかん!) 咄嗟に手を上げる筆者。 間一髪タクシーに飛び込んだのは筆者である。 「勝った」 何に? タクシーの運転手が言った。どこで客を降ろしても、その場で目を吊り上げた客に車を取り囲まれ、けっこう怖いのだと。 筆者もさっき目を吊り上げていたのだろうか。 |
| 新幹線の車窓は、遠く、近く実に多くの城を写し出す。小田原城、掛川城、名古屋城、彦根城。姫路城・・・近さでは、清洲城と福山城にとどめを指す。旧城域を引き裂くように通過する清洲城より、駅正面に堅牢な石垣と櫓を据える福山城の方が見栄えも押し出しもいい。山陽新幹線、福山駅は岡山駅と広島駅の中ほどにある。中国地方4番目の都市である。駅前の福山城によって実に奥深そうな気配を漂わせている。近隣には「鞆の浦(とものうら)」があるし。 福山城は市街中心地の反対側にある。駅から見える石垣が見事だ。 筆者は様々な誤解を受けている。ひとつ「鉄道マニア」、ふたつ「城を見たら登る男」。誘蛾灯につかまりジダジダバヂバヂする蛾じゃああるまいし、目についた城すべてをやみくもに登ると思ってもらっちゃあ困る。 新幹線を降りて、とりあえず、福山城に登る。天守閣があるのだ。天守閣に登らねばなるまい。 戦後再建された鉄筋コンクリート造りの城で特に味気なく感じるものがある。それは床だ。昔日の小学校によくある表面をコーティングしたコンクリート貼りの床を見た瞬間の脱力感は巨大だ。そして階段。エッジにラバーの溝付モール様のものを接着しているあれ、悲しみをさそう内装であ |
る。イメージが沸かない人は福山城に行ってください。 福山城はあまり、市民に愛されていない気配がする(違っていたら申し訳なし)。石垣を前に盛大に水を噴出す噴水の色が緑色だ。藻が繁殖し、泉はミドロヶ池と化している。 「福」のつく城は相性が悪いのかもしれない。福知山城でも、似たような感じを経験している。 城と反対側の繁華街を歩く。中国地方4番目の都市としての4番目くらいの都市機能を備えた街である。関西在住3年半、名のある関西以西の都市をそれなりに訪れた筆者だが、正直な話、これほど個性を主張しない4番目くらいの都市然とした都市に出会ったのは初めてである。駅前に城のある街。それだけである。周辺の町から都市機能の一端、消費機能を利用すべく、百貨店、あるいは商業テナント施設に若者が集まってくる。それ以上でも以下でもない。 地域の生活者にとっては、旅人の思い入れなど迷惑なだけのシロモノだろうが、少なくとも駅前に城を置いているのだ。もう少し責任をもっていただきたい。誘蛾灯のように立派な石垣に惹かれ、新幹線を降りちゃう奴がいるんだ、世の中には。 |
| 筆者が知る限り、優美さと雄大さにおいて「明石海峡大橋」は「橋」部門、日本一である。データ的には世界一なんだがな。 眼前に広がる瀬戸内海とそこに浮かぶ淡路島。内海というイメージからはほど遠く、瀬戸内海は広い。水平線のかなたは水蒸気にかすみ、対岸の淡路島以外、四国の島影すら映らない。日常の忙しさで失った落ち着きを取り戻すには絶好のロケーションである。 筆者は新大阪から「西明石」まで「こだま」で移動、在来線で「明石」まで1駅を戻り、明石を散策。「たまごやき」や「タコ飯」で腹ごしらえをしてから「舞子」で明石海峡大橋を堪能するルートを確保した。さらに帰路、「神戸」で下車し駅前から元町商店街を東上し、元町を抜け三ノ宮までブラブラ。三ノ宮から新大阪まで戻り、同一ルートを経ない周遊の輪が閉じられる。 「こだま」は、旧型の0系、100系が改良され自由席のすべてが2バイ2のグリーン車仕様となっている(山陽新幹線だけである)。始発駅でしかも、各駅停車である「こだま」はガラガラだ。前の座席を回してボックスシートにしてしまう。足を投げ出す。自由席特急券で2駅分、東京の感覚で言えば、小田原まで。在来線の新快速でも新大阪からは38分、こだまが25分なので所用時 |
間はあまり変わらない。しかし、気分が違う。プチ旅行モードのスイッチが入るのだ。 JR神戸線舞子駅と明石海峡大橋はほぼ直結している。駅を出れば誘導路にそって巨大な橋脚の袂に出られる。周辺は「舞子公園」として整備されている。孫文の博物館(日本で唯一らしい)「孫中山記念館」がレトロな六角塔を橋の袂に据えている。 舞子駅から橋に近づくアプローチがまたいい。巨大な橋脚がそびえ立ち、淡路島まで連なる4キロ弱の長大な橋を実際以上の遠近感で際立たせている。 橋上の遊歩道やレストラン(と言ってもファミレス未満のものだが)のある8階までエレーベーターが47メートルの高さをノンストップで連れていってくれる。 遊歩道を歩く。頭上は道路である。大型車両の通過時はかなり揺れる。そして大型車両の通過はひっきりなしだ。だから、橋は常に揺れている。地震のように揺れ続ける。 遊歩道上には、丸木橋がある。幅40センチほどの丸木橋の周囲は強化ガラスとなっており、明石海峡が見下ろせる。47メートル下の海面がエメラルドグリーンに輝いている。覗き込むのはちょっと怖い。しかし、結構愉しいぞ、これ。 |



| 「太陽がいっぱい」である。 30ノット近いスピードで疾駆するクルーザーのスターンデッキ(後部デッキ)のチェアに背中を預け、筆者はゆっくりと空を仰ぎ見る。気分はもうアラン・ドロン。知らんか、若い人は。 船って出港と帰港時が忙しいのね。 なぎら氏とマスターが作業をしていたのだが、なにひとつ役に立たない自分がいる。マスターなど自分の船でもないのに猿(ましら)のごとくくるくると出港作業を進めている。もはや完全にクルーだ。船舶免許を持っていると後で聞いた。 「何か手伝えることはありますか?」 気の抜けたサイダーのような気遣いを見せるのが精一杯。で、まあいよいよスクリューが回る。両軸のシャフトの回転が上がり始めると、トランサムステップ(船尾の台)の下から海面が大きく盛り上がってきた。(うわっ)声にならない歓声をあげる筆者。関空に渡る橋をくぐり抜けると速度はいよいよ上がる。スクリューが押し出してゆく海水の盛り上がりは高速になると低くなった。ウェーキ(航跡)が長く、遠くつながっている。 クルーザーの跡を追うように関空を飛び立った747が後方から高度を上げてゆく。 艇は紀淡海峡を抜け、淡路島の東岸を走る。一旦キャビンに引っ込み、気分を変えてデッキに戻 |
ろうとした。靴を半分つっかけていたら高速時の船の傾きをなめていた。あやうく船尾から海に転がり落ちるところであった。 皆は2階のコックピットでパッセンジャーシートに座り、なぎら健一氏の操舵を眺めている。今回のメンバーは5名だ。元レーサーのM君などメカニカルなものに引き寄せられるようにコックピットに入り浸りである。マスターの9歳の息子も一緒だ。 そして沼島に到着。ポートに億単位の船が並んでいるときは緊張するとのこと。こすったらどうしよう、という恐怖は神戸ナンバーのベンツに接触するよりも高い。以前に乗っていた艇は一軸(スクリューが1本)だったそうで操舵が難しいとのこと。 とにもかくにも、目的の木村屋にあがり、締めたての鱧をありとあらゆる形で食いつくす。刺身もあれば湯霜、焼き霜も供される。肝や白子、浮き袋なども大皿にのっている。圧巻は淡路島産の玉ねぎと一緒に食べる「鱧しゃぶ」。これは絶品である。旨い。 満喫し、再び乗船、出港。そして帰港。ジャガーで梅田に帰る。考えてみればリッチな1日である。この紀行文も今回は見慣れぬカタカナ多かったし、無理してるな、オレ。 |



| 淡路島南端に沼島(ぬしま)という島がある。漁師町のこの島は鱧(はも)で有名らしい。そして沼島の鱧と言えば料理旅館「木村屋」。 大阪の飲食店関係者が密かに寄る店と聞いた。冬場の定番料理「てっちり(フグ鍋)」のかわりに出す夏場の「鱧しゃぶ」研究に訪れるのだ。 「今度、鱧をやりますから来てください」 と、馴染み客に営業をかける。そんなとき 「ほうか、以前、沼島の木村屋で食ったけど、ありゃ旨いな」 「木村屋さんに行かれたんですか」 「ああ」 「ほな、来んといてください」 てな感じになる。木村屋の鱧しゃぶを知っている人間には出しづらいのである。 ゆきつけのビストロのマスターにこの木村屋への鱧食い行を誘われた。 「どないです」 「是非、行きましょう」 「ほな、行きましょう」 「でも、どうやって行くんですか」 「常連さんのクルーザーで泉佐野のマリーナから行きます」 「クルーザー?」 「そう、クルーザー」 |
「是非、行きましょう」 「ほな、行きましょう」 紀行暦27年。チャリ、鉄、空、車、船(フェリーだけど)数々の旅を経験してきた筆者だが、クルーザーの旅はない。人のふんどし(クルーザー)で相撲(旅)をとるのもいいじゃないか。 で、梅田の新御堂で待ち合わせの時間、目の前にスルスルとジャガーが停まり、助手席からマスターが顔を出した。運転席には、なぎら研一似の店の常連さんがいた。挨拶をすましてさっそく乗車。軽くアクセルを踏むだけでスーパーチャージャー4000CC超のパワーは背中をバケットシートに押し付けてくる。速ええ。関空の手前、泉佐野のマリーナまで30分で到着。 マリーナでは区画分けされた係留スペースにクルーザーが並んでいる。船の駐車場である。すべてのクルーザーの持ち主が松方弘樹にしか見えない。松方弘樹以外にクルーザーに乗る人間がこんなにいるわけだ。あきらかに日常生活圏外の体験だが面白い。今日乗る艇は新品を買ったとのことで5千万ほどだと言う。船のクラスはフィートで表すらしい。船体の長さのことだが例えば50フィート超とか。目の前を通り過ぎたクルーザーを見てなぎら健一が言った。 「ありゃあ億をこえるな」 |
| 田園風景の中、空気の微粒子中に異質な存在が混ざっている。都市生活の中には存在しないものだ。久しぶりの出会い、それは堆肥の香り。 安土山に向かう最もわかりやすい経路が県道2号線である。路上から車列が途切れることがない。幅員はさほど広くない。大型車両の交錯時は少し身を引かねば怖いほどだ。これほど静かな郷に、これほど不釣合いな喧騒も珍しい。 なんとなく違和感を覚えながら、やがて安土城跡の王手道前に出る。 王手道が山上にむかって続いている。石段である。400年前のままの石段が、急勾配で標高200メートル弱の山頂まで屈曲しながら続いている。見事なまでの石段である。筆者の安土城跡に抱いていた「この程度のもの」感を完全に吹き飛ばしてしまった。 想像より長く、広く、高い石段の周囲に石垣がある。道の上り口の左右に秀吉と利家の屋敷跡と伝えられる敷地が配されている。この伝を信じるならば彼らは城郭の門番のような役割と言うことになる。三門に立つ2体の風神雷神像を思い浮かべてしまった。 研究者は、石段の両脇に連結した建造物が繋がり、あたかもアーケード街のようなイメージで山頂まで続いていたのではないかと考えているらし |
い。金毘羅さんの参道を大きくしたイメージだ。あるいは「千と千尋の神隠し」の油屋のようなイメージか。想像するだけでも信長という日本史上類例を見ない創造者の一端を垣間見るようで実に愉しい。 しかし、安土山は今や日本でも有数の鳥獣保護区である。同時に虫の王国でもある。カメムシが喧しい羽音を立て飛び回る。蝿や蜂、虻が蠢いている。トカゲの姿もあちこちにある。天下を取りかけて、この地から支配の羽を伸ばそうとした男の遺跡を今は虫達が支配している。 山頂、天守閣跡からの眺望は樹木に視界を塞がれ北方の琵琶湖畔はわずかにしか望めない。昭和初期には北面の山すそにまで湖面が広がっていたらしい。安土城は琵琶湖に浮かぶ城だったのだ。戦後、湖は埋め立てられ湖ははるか先まで押しやられてしまった。 帰路は総見寺のある百々橋口を取る。途中三重の塔の脇をすりぬけ、仁王門を越える。ここでも急勾配の石段を降りつくすと鬱蒼と茂った山中からにわかに白日の下に飛び出すような色彩の変化が待ち受けている。「千と千尋の神隠し」のエンディングを見るような錯覚を覚える。安土山は山そのものに意識が宿り、意思のある遺跡になってしまったような不思議な空間である。 |



| 次の3人の中から好きな人を選びなさい。「A徳川家康 B織田信長 C豊臣秀吉」って言われたアナタ、どうします? たぶん家康が最下位。信長か秀吉を選んだ人が多いのではないですか。誰を好きかと言うことは人様から自分がどう思われたいかの裏返しの主張ですからね。自分はこんな奴ってことをオープンにするための手段には家康さんはちと暗い。 では、次の3人の中から上司を選びなさい。 「A徳川家康 B織田信長 C豊臣秀吉」 あれ、どうしました?織田さんじゃないんですか?1問目で織田さんを選んだアナタ、なぜ上司に徳川さんを選ぶんです? ね、歴史上の人物としてはいいんです、信長さん。こっちの身に危害は加わりませんから。でも上司は駄目。命にかかわるから。課長席に座っていようと、部長席に陣取ろうと、役員室にいようと、社長の椅子に座っていようと、何を考えているのか分からない昆虫のような反応で無能というだけで命を奪われそう。 そんな感じがするからだろうか、3人のうちで彼だけが自慢の巨城をないがしろにされたままで400年が経った。江戸城は、皇居になっているし、大阪城は2度復興されている。 安土に行かねばなるまい。 |
せっかく大阪にいるのだ。関東圏からの旅でわざわざ安土に寄るにはかなりの勇気が必要だ。好事家と言ってもいい。新快速の終点長浜 に向かう途上、安土駅の風景は何度も見ている。駅前には何もない。沿線にも何もない。覚悟を決めてゆかなければ列車を降りるのを躊躇うこと間違いのない風情なのだ。 東海道本線「安土」駅は新快速も快速も停まらない各駅停車の駅。昼の日中に停まる列車は1時間に2本。筆者の旅立ちの拠点「新大阪」から1時間20分弱。京都を過ぎ、草津を過ぎ、新快速の停車駅、近江八幡で乗り換え、一駅で安土に着く。手っ取り早くなんとかするなら新幹線「こだま」で米原下車、米原から大阪方面に逆行して6駅だ。1駅目には「彦根」がある。これをパスして安土まで向かうのも苦痛が伴う。 しかし、今回は覚悟を決めている。安土へ行くのだ。 駅前に信長の像があるが、縁起に深みのある物件とは思えない。近江商人の血を受け継ぐレンタサイクルのおっちゃんの「どや、どや」攻撃をかわし、徒歩で安土山を目指す。駅から25分程度で県道2号線ぞいに鬱蒼と茂った小山が現れる。安土山だ。初夏の水田の水面が燃え出づるような緑に包まれたその姿を映している。 |



| 駅を降り、街に出たそのときから「ストン」と心のツボにはまる土地がある。それが郷愁なのか旅愁なのかは判然としないが、妙に懐かしさとそこに住む人々に羨望を感じてしまうときがある。 明石がそんな街だった。 JR明石駅をはさんで山側に明石城、海側に港がある。港湾では明石と対岸淡路島の岩屋港を結ぶ「たこフェリー」が発着している。船体の側面に真っ赤なタコのイラストが爽やかだ(爽やかか?タコ) 明石港は、漁港としての機能も大きい。漁港は朝が忙しいというイメージが強いが、明石では昼網にかかった魚もセリに出るのか水産会社のトラックが昼をまわっても忙しく回転している。街中にある「魚の棚商店街(通称うおんたな)」には昼過ぎでも魚がピチピチと跳ねている(誇張ではない。実に元気にピチピチ跳ねているのである。タコはウネウネと這っているのである) フェリータミナルの横に遠く明石海峡大橋の全容を捉えられる広場がある。釣り人がキャスティングに興じている。明石海峡は潮の流れが速く、魚がうまいのだ。波打際に堤防のように張りだしたこの広場の段差に腰をおろし、潮の香りに包まれ、打ち寄せる波と雄大な明石海峡大橋を眺めているだけで静かに時間が流れてゆく。 |
明石駅の駅前と言っていいほどの近さに明石城はある。小笠原忠真が築城し、その後複数の松平氏が累代治めてきた戦国以後の新城だ。計画はあったが天守閣までは造成されなかった。東西の二つの櫓が城としての体面を担っている。城域は広く、緑に包まれ、市民の憩いの場として街と融合している。こういう城は幸せだ。城下町と言っても城主の施政により領民に恨まれそれが城にまで反映する土地もある。 公園となっている城域を散策し、駅の向こう側の商店街を流す。「たまごやき」だらけだ。いったいこれだけの店の経営を安定させるどれほどの人間が「たまごやき」を消化しているのだろう。案外観光収入も多いのかもしれない。 「たまごやき」は「たこ焼き」のことである。大阪の「たこ焼き」と違って小麦粉よりも玉子の成分が多い。ふわふわの玉子の食感からこの名になった。軽くチョンとソースをつけ、三つ葉をまぶしただし汁につけて食べる。完全なスナック感覚である。筆者は創業150年をうたう「松竹」で食した。ふわふわの優しいイメージに油断した。最初の一口で「熱っ!熱っ!」上あごがただれた。 子午線135度の街、明石、なかなかにいい街だ。また来よう。 |

| 日本三景、東北三大祭り、日本三名園。地域や日本のそこかしこにゴロゴロころがっている「三××」。数ある「三××」の中に「日本三大仏」があることをご存知であろうか。筆者は知らなかった。 「三大仏?」 ほぼ、全員がそうだと思うが、筆者は指折り数え始めた。 「奈良だろ、鎌倉、・・・」 ここまでは出るな、普通。しかしこのあと壁にぶちあたる。 「・・・・高崎か?」(それは観音だ) 奈良はすぐに思いつく。次に鎌倉。ここまではいい、一般教養の範疇だ。あと1個が出てこない。わかりますか3大仏。 答えは「高岡」である。 「高岡大仏」というものがこの世に存在しているとは、寡聞にして知らなんだ。 前田利長が開いた城下町、高岡。呉羽山を境に富山県を2分する西の殷賑、呉西と呼ばれるその地域の中核都市である。知らない人のほうが多かろう。しかし筆者は先年、長岡の郷土料理の居酒屋で高岡の名を聞いた。長岡は比較の対象を高岡に置いているのだろうか。人口はどちらも17万から18万、県庁所在地ではなく県下第2位の地 |
位に甘んじている。しかし、県庁所在地よりも歴史的なプライドは相当に高い。 「へ?長岡が?」 筆者の畏友、Iが怪訝な顔をする。Iは高岡近辺の新湊出身だ。郷土愛の権化である。 「高岡の人間は長岡を気にかけてはいませんよ」 ライバル関係というのは、競争劣位の側が、優位な個人や集団を仮想敵とする心理なのかもしれない。したがって仮想敵にされる側は無関心だ。 そのIがかつて、高岡大仏誇りをしていた。 「奈良の大仏も見ましたが、なんだ、たいしたことないな、高岡の方がよっぽど大きいですよ」 見なければなるまい、高岡大仏。 高岡駅前には近代的な高層ホテルがある。鄙と侮るなかれ。夕刻、英字のネオンサインが燦然と輝いている。(おお、「Metropolitan」ではないか、高岡、なかなかにやる!) しかし、よくよく目をこらせば「MantenHotel駅前」であった。 高岡大仏の話だ。急がねば日が沈む。路上で立ち止まり地図を眺めていたら犬に吼えられた。 で、辿り着きました。高岡大仏、こんな物件です。もちろん、奈良の大仏より小さい。しかも台座が高いのである。つまり上げ底仕様。それはないだろう、Iよ。 |


博多行3→→→back 博多行 博多行2 博多行3 博多行4 博多行5
| 11時半に入店した中州のバー「ヴェスパ」はいつも以上に賑わっていた。 すすめられたカウンターの一席に腰を下ろすとバーテンダーに先を越された。 「今日も3杯ですか」 いつも3杯で終わったためしはない。しかし、とりあえずバーでは3杯の組み立てを心がけているのである。 「ええ、お願いします」 「前にお飲みになっていますか」 「いえ、それほどでもないです」 これもいつもの会話である。そこそこにほろ酔い気分の筆者はどのように見えているのだろう。 西中洲で会社のスタッフと愉快に過ごしたあとのことだ。人数が揃っていたので皆を連れてくることができなかった。バーは宴会場ではない。多くても3人までが限度だ。残念だが、夜も更け始めていたので出逢橋を渡ったのは筆者ひとりである。今宵は西中洲だったが博多のスタッフはなかなかに通人で、シラク大統領おしのびの「鳥善」、味噌仕立てのもつ鍋「越後屋」など大名エリアで連れて行ってもらった店も旨かった。しかも信じがたいことに安いのである。筆者の懐具合に気をつかってくれているようだ。しかし、味に妥協はないのである。店選びの苦労が偲ばれる。 |
で、「ヴェスパ」である。 2日前、震度5強の余震に襲われたばかりの店内は、馴染み客の無言の応援で混みあっている。1ヶ月前、福岡西方沖地震に見舞われたとき、店内の長大な棚に並べられた瓶のことごとくがフロアーに落下し、割れた。棚に残されていた酒は6本だけであったそうだ。店長がフロアに散乱したボトルの写真を携帯電話の画面に写し出し、来店する客のひとりひとりに見せていた。ボトル以外にも高価なグラスの多くが破損した。 「今日は休むが、明日は絶対営業してやる」との誓いを守り、翌日、本当に営業し客の度肝を抜いた。熊本・京都・銀座の支店から抜けるだけのボトルを抜いて配達してもらったとのこと。翌日は祭日なのに駆けつけた馴染み客で常より繁盛したそうだ。博多の客は皆、熱い。 見方によっては京都以上の古都なのだが、ま~ったくこだわりがないのが博多である。博多祇園山笠は、観光客よりも、博多っ子自身が愉しんでいる。そのこだわりのなさゆえか、おそらくは日本一排他性が薄い都市である。この土地のかもし出す心地よさはそこにもあろう。 再び、渡って天神に帰る出逢橋の欄干から那珂川の水面を眺める筆者は、この土地がかなり好きなのである。 |
| 背後に幾つかの山を背負いながら右手からなだらかに上ってくる地勢が途中、丘陵部を削り取られたかのような急勾配で盛り上がり、左の登頂部にむかって駆け上がってゆく。その稜線を追う視線のゆきつく先は緑に包まれた小山である。周囲から独立したその姿が蒼天に浮かぶ。 小山にむかって急勾配となる地形の変節点にひとつの塔が置かれている。 塔は五重である。後背の小山の裳裾が、その塔の肩に緑の外套をやさしくはおるように軽く重なっている。 屏風絵のようなこの景色の前には、充分な広さの、景色を絵として眺めることができるほどには客観性を保てる広さの庭園が控えている。できれば県庁方面から徒歩でこの地を訪れたい。そうすれば、最初に塔を見る時、この庭の広がりを前にすることができる。景色の広大さが大きな塔のスケールを希釈させている。しかし、古格なその姿が存在しなければこの絵は価値を失う。そのような存在感が塔にはある。それはオーラのような圧倒的なものでもなければ、あく強く主張する我意でもない。何百年という時の流れによってそれらが揮発してしまい、人工の塔が周囲の自然と一体化してしまった姿である。いい景色だ。 塔の名は瑠璃光寺五重塔。かつて、中国、九州 |
に権勢を誇った大内氏の遺産である。 塔の左手後背、急勾配の坂に墓群がのぞいている。その墓石の白さに、この街に生まれ育ち、そして死ぬ。他郷に出ることなく一生をすごす静かな人生がなぜか彷彿とされる。山口は、そういう生を感じさせる街である。 新山口(かつての小郡)から山口線で20分。山口までは意外と近い。隣駅は「湯田温泉」だ。井上馨の生家の地、周布政之助の墓もある。 山口駅からは、軽い勾配の坂道が伸びる。途中のアーケード街も含めて、街中にファストフードのナショナルチェーン店の姿がない。鄙であることは明らかだが街の印象はいまなお壮健な古老の風情である。 坂道はやがて藩政時代の藩庁の門が残されているかつての政治堂の丘に至る。ここには旧県庁と議事堂がある。この土地は明治・大正のそれら建造物を再建し、資料館としている。丘陵の中ほどに立ち並ぶモダンな建造物が美しい。 途中、信号待ちで心静かに佇む。日常、赤でも渡るせわしなさも、この地にあればそれが気恥ずかしいほどに時の流れがゆるやかである。車が道をゆずってくれる。歩行者優先である。藩政時代を通じ培われたある種の規律感覚が今なお失われずにいるのか。いずれにせよ良い街を見つけた。 |
| 伏見は京都から僅か南にある。京都駅から7キロ程度。駅にして4駅の距離でしかない。にもかかわらず京都市民はここを「京都市伏見区」よりも「京都府伏見市」じゃないかと思っている。距離的にはそれ以上に離れている鞍馬よりも域外扱いの度が強い。羅生門の外にあったからか、何かの隔意が働いたか。伏見よりもさらに南にある宇治が平安貴族の別荘地だったからか。 伏見は大阪への玄関口である。豊臣政権の末期、徳川家康は伏見城詰めを命じられている。家康の大阪城への入城を禁忌とするためだが、聚楽第や武家屋敷を含め、豊臣政権は京都市中ではなく伏見を駐屯の主力にしていた。その印象から伏見城を眺めれば、この城は京都の西の守りとしてではなく、大阪にとっての最東端の防衛線、あるいは京都鎮守府である印象も生まれる。 幕末、坂元竜馬が伏見の船宿「寺田屋」を定宿にしていたのも、新撰組の闊歩する京都市中から一定の距離を保っているというきわどい安心感があったからではあるまいか。 ただし、奉行所はある。竜馬を寺田屋に襲ったのは伏見奉行所の捕り方だ。伏見奉行所は幕末鳥羽伏見の合戦の最前線基地となった。伏見城があった以上、ここは城下町なのだ。伏見別院(伏見幼児園)の門前は、四つ辻の四つ当りと言って東 |
西南北のいずれから進行しても突き当たりになる町割となっている。遠見遮断や袋小路など、城下町の設計なのだ。十字路を設けない。 10石船、30石舟の船着場が運河のほとりに設けられている。その船着場のすぐそばに寺田屋がある。今も旅館として営業され、竜馬のつけたという刀傷が鴨居にのこっている。開放時間は3時40分まで。早っ!船宿らしくそばに30石船の船着場がある。伏見、大阪間の水運は現代の陸運に匹敵した。 周囲を散策すれば、竜馬が幕吏に囲まれ必死の逃走劇を演じたのがこの界隈かと妙にリアルな画が浮かぶ雰囲気がある。鳥料理「鳥せい」の本店や黄桜酒造の蔵などが並び、なかなかの風情だ。 アーケード街の脇から竜馬通りという小道が枝分かれしている。 桃山御陵には明治帝が眠る。坂がきつい。参道は静かである。明治神宮の参道をさらに森閑とさせた感じだ。やがて遠くに陵墓が現れる。 明治帝の崩御とともに殉死した乃木希典を祭った乃木神社が、その墳墓を北面の武士のように鎮守している。乃木はその軍事的非才への非難を明治帝によって救われた経緯がある。乃木神社には彼の生家と日露戦争、旅順攻略時の第3軍司令部として借り上げた農家のレプリカが建っている。 |



右端の画像の民家が、日露戦争、旅順攻略戦の第三軍司令部のレプリカである
| 積雪は車窓を眺める視線よりも高い。積みあがった白い壁を見上げるとその稜線の先に駅舎の屋根が僅かに覗く。 圧迫感を感じるほど間近に雪の壁が視線を遮る。 走り出した列車の視界は自らがまきあげる飛雪によって吹雪の中にいるかのような白煙につつまれている。 雪が静かに降り積もっている。天も地もそれらをつなぐ宙空も白一色である。見上げた空からは無数の雪片が絶えることなく舞い降りてくる。白いその一見易しげに見える綿のような物体にすべてがうずもれていく。このまま積みあがる雪の中に没し去っていくかのようだ。 地上のあらゆる色彩が雪に脱色をされ、力を失っている。確かにそこに存在しているのに妙に存在感が希薄である。色だけではない。音すらも降り積もる雪に吸収されてしまう。車内は静かだ。遮音されたような静寂がそこにある。 列車は「妙高1号」車名までついているが在来線、各駅停車である。長野から直江津まで、信越本線の豪雪地帯を走る。 新大阪発東京、長野、直江津、富山経由、湖西線京都行き片道切符の旅の2日目だ。筆者がこの記事を書いている今は3月中旬である。すでに春 |
の気配が濃厚に漂っているときに何であるが、時計の針を1ヶ月巻き戻して欲しい。わずか1ヶ月前のことなのだ。にもかかわらず、この季節感の違いはどうであろう。日本に生まれてよかった、とつくづく思う。 やがて、列車は高田に入線した。かなりの数の乗客が降りてゆく。この地域の中核都市なのか。車窓はすでに市街地のそれにかわっている。幹線道路は除雪をされているし、先ほど見てきたような圧倒的な積雪量ではなくなっている。 高田の次は春日山。謙信の居城、春日山城の跡地がある。彼はこの地から甲州にまで侵攻していたのか。雪のない季節ではあろうが、先ほど、眼前にあれだけの雪を見せつけられた後だけに、そのエネルギーの強さ・深さには脱帽ものである。ただし、春日山駅は極めて寂しい。 そして列車は次駅、終点の直江津に到着した。駅前に地場のホテルがひとつあるきりの雪国の駅だ。駅前をかすめるメインストリートの両脇に連なる商店の軒先は雁木である。張り出したひさしの下、濡れた歩道が静かな商店街とも呼べぬそれらの店の繋がりの途切れる先まで細く続く。 駅前に戻り、立ち食いそば屋で「もずくそば」を食べる。どのようなそばかと言うと、あ、いかん紙幅が尽きた。 |



| 忙中閑なし。 嘘。週末、1ヶ月ぶりに自分の時間が持てた。電車内でほんのちょっとの隙間に尻を押し込むオバちゃんのように余暇時間を最大限に活用する筆者。 社用で東京に出る。帰路を利用して東京から長野新幹線で長野に出る。長野で旧友に会い、名にしおう豪雪地帯を信越本線で貫き、日本海岸の直江津へ。北陸本線で富山に向かい、キトキトの魚を食べてサンダーバードで帰阪。完璧な計画だ。 久しぶりに片道切符を購入する。新大阪発東京、新幹線長野、直江津経由、湖西線利用の京都行き片道切符だ。運賃14,070円。東京・長野・直江津・富山・新大阪までの区間を個別に買うと21,540円だ。京都から新大阪までは往路と区間が被るので540円を乗り越し料金で支払い、14,610円也。トクトクである。 考えてみれば、長野新幹線は初乗車だ。 高崎までは上越新幹線と同一線区を走る長野新幹線。「はやての車窓から」で既述したが大宮まではトロい。熊谷を通過。山が近づいてきた。うっすらと積雪を身にまとう山々が幾重にも折り重なり、何重ものグラデーションをかけている。 空気の色は基本的には青なのだ。水彩画は、まず薄い黄色を下地に敷いてしまう。その上に緑を |
重ねてゆく。遠くは淡く、近くは濃く。すると空気のフィルターを通したかのように遠景は淡い青に、近づけば緑に近くなるグラデーションを施すことができる。余談ではある。 高崎を通過した。さらに間近に山々が迫る。 凄まじいほど荒削りの山容と周囲よりも頭ひとつ突き抜けた真っ白な孤峰が目を引く。浅間山であろうか。山頂を白い筋雲で隠し、かつ車窓前方に位置し、なかなか全容を捉えさせてはくれない。西日を背に受けた山に目を凝らそうとしたところで列車はトンネルに突入してしまった。トンネルを抜けると不意に周囲が銀世界に変わっている。「雪国」の世界だ。そして、積雪はトンネルを抜けるたびにその厚さを増してゆく。軽井沢についた。屋根に守られていないホームの先端は雪かきもされずに積もるにまかせている。 佐久平に停車。駅前でローラーボードに乗った若者達が新幹線に手をふっている。純朴である。昭和初期の光景だ。雪が、少しずつ薄くなっている。地面がまだらに顔を覗かせ始めた。 上田は川沿いにある。西の峰に身を沈める夕陽の残照をうけ、いかにも清々しげな空気がそこには満ちてる。そして列車は長野に入線。空気がピンと張り詰めた雪国特有の緊張感がそこには漂っていた。 |



| 伊賀上野には「伊賀流忍者博物館」がある。そこでは「くノ一(女忍者)」が案内役となり、ドンデン返しやなにやかやと実演を交えて忍者の説明をしてくれる。さらには「忍者ショー」も開催されているらしい。 人の話はちゃんと聞かなければいけない。筆者は小学3年のときの通信簿に「お調子者で落ち着きがありません。もっと人の話を聞くように」と書かれたことがある。何をどう取り違えてそうなったのかわからないが、「くノ一ショー」と「花魁ショー」(実はよく知らない)を混同した筆者は、慌しく伊賀上野に向かった。「実演!くノ一ショー」を見なければ末代までの禍根を残す。 「実演!くノ一ショー」、名称がいいな!(自分で勝手に作り上げたピンク妄想だが) 魔が差したとしか思えない。一途な想い(しかも明らかに的外れな)が伊賀への執着を生んだ。しかし、伊賀上野へはどうやって行けばよい?伊賀上野の場所がよく分からない。慌しく、インターネットで路線情報にとりつく筆者。 近鉄大阪線で「近鉄難波」駅から「伊賀神戸(いがかんべ)」駅まで特急で1時間強、近鉄伊賀線に乗り換えて「上野市」駅へ30分強。これで伊賀上野市の中心「実演!くノ一ショー」に到達する。 |
近鉄大阪線は、京都、奈良間の南北ラインと交錯しない。奈良のさらに南方、桜井を貫くように南下してから「伊賀神戸」に至る。路線はその後も東進を続け、三重県の津から伊勢湾に出る。桑名を経て名古屋まで至る私鉄としては驚異的な長大路線である。 大和路に沿って走るこの路線の車窓は実に美しい。「里」あるいは「郷」とも言う。まさに日本人がその言葉から連想する風景があるとしたら、今、目の前に広がるこの風景がそれであろう。連なる棚田、幾棟かの広壮な屋敷が集落をなしている。遠くに白煙がたなびき、背後に広がる山並。なんとのどかな光景であろうか。伊賀神戸からは列車は高原を下界へ下るように快走する。近鉄伊賀線は、ストンストンとよく揺れる。 雪が横殴りに降り始めた。 「上野市」駅の手前、「広小路」で下車。元祖伊賀肉「金谷」は大繁盛だ。幸いなことに小部屋がひとつ空いていた。醤油と砂糖だけで肉の旨みで勝負する寿き焼きを堪能。調子にのってヒレとロースのバター焼きも食べた。レモンと醤油を大根卸しにかけて食す。しまった!食いすぎ!嗚呼、つらい。城に登り、芭蕉の生家を覗きこみ、必死に消化をはかる1日であった。 くの一は・・・それはまた別の、お話。 |
| 列車は3種の特急を連結している。長崎行きの「かもめ」ハウステンボス行きの「ハウステンボス」佐世保行きの「みどり」。博多発長崎佐世保方面への特急の編成は混成部隊だ。筆者は「みどり」に乗車した。目的地は佐世保である。博多から佐世保まで約1時間50分の旅程で、その距離約120キロ。東京熱海間、大阪相生間に匹敵する。 博多を出て約10分で列車は二日市に停車。西鉄も通る博多郊外の衛星都市だ。大宰府へ分岐するジャンクションでもある。周囲を山に囲まれた鄙な都市。東京・大阪のような都市部の感覚ではまだ市内という印象だが、九州ではあきらかに郊外都市だ。 鳥栖で熊本へ南下する鹿児島本線と分岐し、列車は3編成ともに長崎本線に入線する。 鳥栖は、サッカーチーム「サガントス」の町である。「サガン鳥栖」が正しい変換だが、「佐賀ん(の)鳥栖」などとベタなシャレではないかと邪推したくなるようなチーム名である。 列車はバルーンの町佐賀を疾駆する。北方にこそ山稜が並ぶが、南面はまさに障害物ゼロ、気球処に相応しい平べったさである。佐賀は内陸都市だが、佐賀県は北の玄海灘と南の有明海とふたつの海に面している。玄海灘の唐津周辺では佐賀県意識が希薄だ。筑肥線の地下鉄乗り入れで博多に |
直結しているためか、どちらかと言えば住民の意識は福岡に属する。埼玉、川崎の人間が都民意識を持つのと同じ心理だ。 肥前山口で長崎本線は佐世保線と分岐する。 「かもめ」が切り離される。佐世保線には「ハウステンボス」と「みどり」が入線。 車窓に赤レンガの煙突が立ち並び始める。窯である。日本最初の陶磁器の街、有田を通過した。有田からは松浦鉄道が伊万里へむかっている。港湾都市伊万里は有田焼の積み出し港となった。赤絵を代表とする有田焼が伊万里焼と呼ばれる所以である。 早岐(はいき)で「ハウステンボス」と「みどり」が分岐。早岐佐世保間の10分強、「みどり」はスイッチバックで後ろ向きに走行する。 峠越えの一本道を通うように終点佐世保に向かう。この感覚は根室にむかう国道44号線の印象と極めて似ている。そして、佐世保に到着。 かつての海軍鎮守府、現在は佐世保地方総監部の街、アメリカ海軍基地の街である。佐世保は、軍港が皆そうであるように海峡の奥に鎮まるようにある。艦船は高後崎水道を通峡し入港する。後背は烏帽子岳、弓張岳に守られ、前面を赤崎岳が覆い、高後崎からも直進では入港できない。まさになるべくして軍港となった天然の要害である。 |



特急「みどり」 JR最西端の駅標
| 富山市最大の繁華街が「総曲輪」である。読めますか?これ。 地域一番街は地の者にしか分からないことが多い。松山市の繁華街が「大街道(おおかいどう)」であると知っている人は、松山にしかいない。「下通り商店街」と言われて頷く人は熊本人だ。「天文館」は鹿児島で「三六街」は旭川である。「八丁堀」と言われて江戸と答えた人は時代劇の愛好家だ。残念、広島です。 さて「総曲輪」・・・「そうがわ」と読むのである。 日本海側の諸県は全体に地味だが、その中にあっても、おそらくは最も人口に膾炙しない地味な県が富山。新潟と石川にはさまれているが、その位置すら曖昧な方も多いはず。しかし、立山黒部アルペンルートを擁し、水深1200メートルクラスにまで急激に落ち込む深湾、富山湾。そこで捕られるホタルイカや、白エビ、氷見の寒ブリ、あるいは海に浮かぶ蜃気楼と、指摘されればああ、そうかと思う優良物件ぞろいの土地なのだ。 市の西部になだらかな丘陵、呉羽山(くれはやま)がある。富山のビューポイントとして知る人ぞ知る公園があるのだが、この山を境に東を呉東(ごとう)西を呉西(ごせい)と言い、県民性がまっぷたつにわかれる。呉東の中心が富山市、呉 |
西の中心は高岡市である。両者はJRで4駅しか離れていない。各駅停車で15分程度のものである。しかし、距離に反比例し両者の間は疎遠である。 富山でお殿様と言えば、佐々成政。一方、高岡では前田利長となる。 どちらかと言えば関東風の富山に対し、高岡は関西に近い。 ただし人生の成功を持ち家におくところは同じである。富山では家を建てねば一人前とは認められないのだ。 駅前には立山黒部アルペンルートへの入り口電鉄富山駅に直結の富山地鉄(ちてつ)ホテルがある。いちいち名称に癖があるのだ、ここは。新鮮で生きのいい魚の状態を「キトキト」と言う。 駅を離れて「総曲輪」まで15分程度は歩かねばならない。途中、市役所があり、その展望台は70メートルの高所から富山中を見渡すことができる。南方に3000メートル級の山々が連なる立山連峰が聳え立ち、その姿は神々しくさえある。 富山城の前を通り過ぎ、総曲輪に向かうと北陸エリア百貨店の雄「DAIWA」がある。しかしその姿は痛々しいほどに古い。富山市全体がなぜか、平成と言うより昭和な感じに満ち溢れているのである。 |



| 太鼓の音がどこからか聞こえてくる。 陽が沈み、宵闇があたりを包み始めている。下弦の月が鎌のように細く白々とした光輝を放っている。市中にもかかわらず長野市の空には星が浮かんでいる。冴え冴えとした星空だ。道はなだらかに登っている。参道である。その先に仁王門がある。仁王門の先には改修中の養生シートに包まれた三門があり、三門を越えればそこに善光寺がある。開基1400年の歴史を誇る日本有数の霊場。それが善光寺だ。 長野は善光寺の門前町である。善光寺は、長野駅前から徒歩20分程度の距離にある。 前職の入社同期に生粋の名古屋人Mがいた。会社が変わり彼は今長野在住だ。名古屋人が長野にいる。これは、東北人が関西にいるほどには珍しい。東京から長野に転勤したのが1年半前。転勤の挨拶をうけとってから1年半もたっていた。 善光寺に行っておこう、2年ぶりに再会した彼の誘いに否やはない。街は歩かねば分からない。しかしそのMが参道の途中で首をひねっている。おかしい、こんなに人がいるわけはないのだ。なぜこんなに賑やかなのだろう? それが先ほどの太鼓の音である。ひとつやふたつの音ではない。かなりの数の太鼓を連打しているようだ。 |
参道がそれらしい様子になる頃には状況が判明した。祭りである。 「灯明まつり」と称するそれが開催されているのだ。参道の途中には膝下くらいまでの高さの「灯かり絵灯篭」が地面に並べられている。内部に切り絵をしこんだ灯篭だ。その灯篭を浮かび上がらせるため周囲の街灯や照明を落としている。浄闇だ。目をこらし注意しなければ人とぶつかる。祭りの夜の愉しさが満ちていた。 長野オリンピックから始めた祭りらしい。善光寺の本堂が真紅のライトに照らされている。視覚的なインパクトはかなり大きい。諸堂も青、緑、黄、白のライトに照らされ、なかなかに面白い祭りである。 闇の中賽銭を投げ入れた。後刻、宿に戻って出納チェックをして気が付いた。5円(ご縁)だと思って投げた小銭は10円(遠縁)だった。 まあいい、M行きつけの地元の板前割烹居酒屋は尻のすわりのいい店だ。酒も肴も旨い。 2件目のバーでは、座席後背に秘密の扉があった。スピークイージーのような雰囲気を醸し出すその扉の内側には会員制のジャズライブ空間があった。お試しで入室し、ちょっと面白い夜を過ごす。長野もなかなかに奥が深い。 |
| 博多から筑肥線直通の地下鉄、快速「唐津ライナー」で1時間。唐津湾に面した港湾都市唐津がそこにある。博多市民の日帰り行楽地の位置づけだ。京都にとっての鞍馬、あるいは宇治・伏見、東京にとっての浦安、高尾みたいなもんである。 ロングシートの通勤列車仕様で旅情はないが、遠く福岡から西進し、唐津湾を舐めるように走る車窓は買いである。 唐津湾に突き出すように街のシンボル唐津城が浮かんでいる。他に比肩する構築物がないせいか、その姿は意外にも凛々しくさえある。 市域は狭い。駅前に巨大商業資本は進出していない。商店街も小ぶりで地域密着系である。観光地ずれしていないというか、観光地としての認識は希薄な町並が静かなたたずまいを見せている。日曜日はほとんどがお休みだ。だからこそ得られる安らぎがたゆたっている。 近隣にイカ漁で名高い呼子町(よぶこ)があるためか、イカ商品が満ち溢れている。「イカしゅうまい」に「イカまんじゅう」(「食卓」の頁、土産品をご覧いただきたい)話のネタに一度は購入してみたい珍品指数高度の物件群である。ちなみに呼子町は秀吉による朝鮮出兵の前進基地、名護屋城跡を持つ。 市内を走るバスは「昭和」である。唐津出身、 |
佐賀県の運輸は「昭和」グループ。福岡は「西鉄」グループである。博多の親不孝通り(旧称である。今では親富孝通りと改称)にあるライブハウスも「照和」。天神を東西に抜ける大通りも「昭和通り」(その隣には「明治通り」がある。ちなみに「平成通り」は、ない)九州はなぜか「昭和」という名称が好きらしい。 玄界灘に面した好立地のため、特産品は必要がない。魚が旨いのだ。接待で魚を食べに来る客も多いのだとタクシーの運転手が幾分かのお国自慢の気配をにじませながら語っていた。 「魚ロッケ(ギョロッケ)」という魚肉練り製品(野菜入り)のフライもあちこちにある。藤川蒲鉾店が存在感を主張していた。特産と言うよりは日常品、常食の類であるが、こちらも唐津に来た以上は一度は口に入れておこう。 JR唐津駅の隣は終点の西唐津。唐津駅は唐津線が分岐し、佐賀県の中心地(あるのか中心地?)佐賀へむかうジャンクションでもある。佐賀へは約1時間。松浦川を遡上しバルーンの街、佐賀に向かっている。 「佐賀人が通るとぺんぺん草も生えよらん」と言う福岡県人がいる。そんなに油断ならないか?佐賀県人。どうにも合点がいかない話ではある。 |



稚内行(旅愁編) →back 1稚内行 2望郷編 3徘徊編 4旅愁編 5追憶編 6追憶編2
| 今、こうして日常生活の多忙さの中にあって目に浮かぶのはオホーツクの海の蒼さである。稚内の開基百年記念塔からの360度の眺望。西に利尻、礼文が銀鱗のような日本海に浮かび、東には高台をうねる一本道がそのまま蒼い海に落ち込むかのような傾斜を見せる。それはトーベヤンソン原作のムーミン谷の挿絵のような錯覚を筆者にもたらした。 誰もいない北防波堤ドーム。 夕日を浴びるノシャップ岬。 空自のレーダーサイト。 アメリカさんのおかげで戦後ソビエトに占領されずに済んだ、ドイツや朝鮮半島みたいに分断国家とならずに済んだ、だからブッシュさんをそんなに責めちゃあいけないよ、と言うタクシーの運ちゃん。 官々接待を禁止しやがったから稚内の飲食店は大打撃だ。中央の連中が自分達の倫理観を押し付けやがると悔しがるオヤジさん。 観光なんか1年のうち3ヶ月しかシーズンはない。農業だって収穫の季節は短い。漁業なんて排他的経済水域のおかげで豊かな漁場はすべてロシアの方にあるんだぜと嘆く土産物屋の大将。 あの夏の日の光景は、すべてが一場の幕間劇のような儚さの中にある。それは、手を伸ばせば掴 |
めそうな距離にありながら、なぜか伸ばした手の先から「つい」と逃げてゆく幻影のような非現実さを伴っている。 確かな記憶はすべてが食べ物だ。 ノシャップ岬に立つバイカーご用達の店は「樺太」と言う。そこで食べた「うにだけうに丼」それは3500円もするが、そのボリュームに圧倒されることだけは請合える。 駅前の鄙な作りの「ひとしの店」で食べた「かにめし」もなかなかに味がある。 5年ぶりに訪れた「寿し竜」の大将はあいかわらずぶっきらぼうに見えて実は暖かい。「先生」と呼ばれる地元の行政書士とその仲間達と話がはずんだ。 「5年ぶりだって?」 「ええ」 「次もそんなに空いてから来たら、もうやってないよ、きっと」 大将の一言に一堂がどっと笑う。 ご馳走様でした。またな。はい。どうにも心が和んでしかたがない。 6月の中旬のその日、稚内のそばの名寄では雪が降っていた。店を出てホテルに戻る筆者の手は確かにかじかんでいる。ラーメン屋の灯かりが、妙に人恋しい夜であった。 |
| 「京阪」のカテゴリーに書いているが、筆者は、関西はヨーロッパ、関東はアメリカという比較文化論を持している。歴史の古い関西では各都市がヨーロッパ各国のように独自の文化風俗を持ち、他エリアのそれを受け入れない傾向にある。大阪を中心として東西南北に30分も列車で移動すれば、あきらかに異文化圏に到達する。京都は大阪とは違うし、神戸(三宮)も同様である。和歌山や奈良、滋賀(大津)もそれぞれに際立った個性の街であり、おそらくは他圏に対しては排他的である。 翻って関東圏では神奈川も千葉も埼玉も皆、東京に倣い、東京であろうとする傾向が強い。どこを切っても東京なのである。県名などやめてしまってもさしつかえはあるまい。首都圏は皆東京。都知事の石原さんは関東管領だ。 この首都圏総都民化現象を人種の坩堝であるアメリカが国家として希求するある種の求心力や、規格化された大量消費を正義とする点において極めて類似しているので関東圏をアメリカと表現させてもらっている。 さて、横浜である。ファッショのような首都圏総都民化現象の中、唯一の個性を主張する土地である。ハマっ子は決して自分たちを神奈川県人だとは思っていない。神戸っ子が兵庫県人、大津っ |
子が滋賀県人とは思っていないのと同様である。関西では珍しくもないが関東では珍しい。 しかも、港町横浜の異国情緒感は掛値なしに青天井である。梅田、三宮間に存在するそれよりも高値がつく。 筆者は遥かな昔、伊勢崎町を散策し、元町のマクドナルドで初めて飲んだマックシェークの巨大さに圧倒された。そのときの強烈な刷り込みが今も抜けていない。横浜=巨大なマックシェーク=港街の外人=異国情緒というどうしようもない価値変換が働いてしまうのだ。筆者にとっての横浜は船員さんの街、マドロステイストである。 しかし横浜には日本一の中華街がある。神戸や長崎の中華街は総じて小ぶりだが、横浜はさすがにでかい。豪勢なチャイニーズレストランが店を並べ、その意味での異国情緒感もでかい。生まれて初めて一尾まるまる鯛のから揚げを食べ、おそらくは食いすぎのため、一晩中胃痛で眠れなかったのも生まれて初めてのことである。筆者にとって生まれて初めての宝庫が横浜だ。関東圏に住まう者にとって近場の別世界、それが横浜。 チャイナドレスを初めて買ったのもこの街だ。その使途をここで詳しく書くわけには、もちろんいかないのである。でも横浜って神戸に比べて、ちょっと暗いぞ。 |
| ホームに入ってきた七尾行き普通電車に乗り込んだのは、まったくの偶然である。日曜日の金沢駅、午前8時11分のことであった。 寒冷地仕様のこの列車はドアの開閉を外側からも内側からも乗客が自らボタンを押して行う。 併走する高架は、北陸新幹線のそれだ。富山、金沢間は、かなり工事が進捗している。北陸新幹線は長野から北陸入りするらしい。糸魚川から日本海側に出るのだ。現在の越後湯沢経由の「はくたか」コースは無くなることになるのだろうな。 柴田勝家の与力大名となった前田利家が領国経営をしていた七尾を散策。駅に戻ると偶然蛸島行きの「のと鉄道」が入線していた。せっかくだから乗車する。このとき初めて知ったことだが「のと鉄道」の穴水、蛸島間が来年3月で廃線になるらしい。 筆者は「のと鉄道」とは縁がある。2年前、老眼のため時刻表の「蛸島」を「輪島」と誤認した筆者は、往路をバスで、帰路を列車で愉しもうと「輪島」行きのバスに乗車した。実際、鉄道は蛸島に通じているのであって、輪島には行っていないから、バスから降りた筆者の帰路の足は存在しない。やむを得ず、乗って来たバスの帰り便にそのまま乗車した悲しい過去がある。 そのとき、バスから見える沿道に、盛り土の軌 |
道が何度も現れた。土塁のように盛り土だけが夏草に覆われてゆるやかなうねりを見せている所もあれば、赤錆びた線路を残し、トンネルには立ち入り禁止の柵やロープを巡らせている所もある。廃線跡だと気づいたその軌道がその前年2001年に廃線となった「のと鉄道」輪島線であった。 「輪島線」の廃線には間に合わなかったが、穴水(あなみず)蛸島間の廃線には間に合ったのだ。これも何かの縁だろう。くどいようだが、もちろん偶然の産物である。 列車は一両のワンマンカー、峡谷を思わせるような左右両脇にそそり立つ樹林の間を抜け、時に富山湾を臨み、ゆったりと走る「のと鉄道」。 片道2時間半もかかるため、筆者の夜のスケジュールに影響が出る。やむを得ず、終点「蛸島」まで行かず、「九十九湾小木(つくもわんおぎ)」駅で降車。20分後に入線する穴水行きの登り列車に乗車する。穴水から和倉温泉で特急サンダーバードに接続し、16時には金沢に戻ることができる。 九十九湾小木の思いのほかしゃれた駅では、地元の女の子が地元の噂話をしている。町と言うか村と言うか、この程度の規模ならば、住民同士の相互干渉はテレビの芸能レポーターのそれを凌駕していることは間違いない。話題はのどかだ。 |
博多行2(中洲礼賛)→→→back 博多行 博多行2 博多行3 博多行4 博多行5
| 店を出たのは深夜12時半。 某S学館発行のコミックで店名から店長名から店内装飾から、まんまやないかというほどストレートに漫画の中で使用されていた某バーで、店長本人から、そこのところの事情をきっちりと教えてもらったのが12月17日。深夜を越えて時計の日付は18日になっている。 筆者はそのとき中洲にいた。旅の吟遊詩人Y氏が一緒である。「岩政」でベラボーに旨い、葱鮪鍋(ねぎまなべ)を食べ、甕出しの焼酎でほろ酔いになる。定番のコースは上述のバーである。この店は、心底愉しい。 2004年度のカレンダー繰りは、来週24日が金曜日でクリスマスイブ、つまり今日17日の金曜日は、ただでさえ賑やかな中州の365日の中でも極めつけに賑やかな金曜日なのであった。 バーを出ると左右にケーキ屋とパン屋がある。パン屋ののぼりに「中洲バーガー」と染め抜かれた一文字がいつも筆者の気をひいている。しかし当該物件を目にしたことは、まだ、ない。そんなことよりも、12時半を回っているのに、このパン屋とケーキ屋は、まだ営業しているのである。人通りは中洲に入った9時頃よりも一層賑やかになっている。 博多川のむこうに看板が逆さになっている「さ |
かさラーメン」がある。ここで辛し高菜ラーメンをすすりホテルに帰る。「一蘭」や「一風堂」は飲んだ後の筆者には重すぎるのである。 深夜1時を回っているが、中洲の賑やかさは静まることを知らぬ。パン屋もケーキ屋も店を閉めるつもりはまったくないようだ。店内は客で埋まっている。 風俗街だから、花屋が空いてるぐらいは納得もするが、ブティックから衣料品店まで営業しているのは、もはや常軌を逸した賑やかしさである。 出逢橋で那珂川を渡り、中央公園を抜けて天神に戻る。 静かである。と、言って地方都市特有の閑散とした静寂に包まれているわけではない。自転車をこぐ女性もいるし、人の姿もそこ、ここにある。屋台はまだ後片付けの段階ではない。客の背中が並んでいる。 博多の中心地天神そしてその繁華街、中洲。ここは日本と言うより、アジアである。しかも熱帯性。いっつもお祭り騒ぎ。筆者はこの街が好きである。金沢、盛岡とは別の意味で居心地が良い。 翌日、福岡駅のミニョンというミニクロワッサンの量り売り店で「チョコ」と「さつまいも」を百グラムづつ買って新幹線内でパクつく。しみじみと癒される筆者であった。 |
金沢行9(昇天編) →→→back 金沢行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
| 後ろの壁に寄りかかるとき、壁との距離はしっかりと見極めた方がいい。まだ5メートルも離れているのにダイブすると、地面に垂直落下することになる。なぜか数日後に尾てい骨の痛みに骨折でもしたのではないかと不安になるからなおさらだ。気をつけねばならない。年寄りはこんなことでも寝たきりになって命にかかわるからな。 金沢の繁華街、香林坊の109前でダイブした筆者はその後、自嘲、もとい自重をすることにした。ビールは1杯か1本まで、そして日本酒を1本、ゆっくり呑む。おかげさまでその後の金沢の滞在は実に充実したものとなった。 筆者は失敗を糧に成長するのである。 金沢中を歩くいつもの習慣は変わらない。今回は、夜は「乙女寿司」「つる幸」「千取寿司本店」と幾つかのおでん屋、昼は「自由軒」「ニュー狸」と決めているのだ。計画は「ニュー狸」以外は完璧に遂行された。おでん屋は、記憶から消えてしまった「赤玉本店」以外では「若葉」に足をはこんだ。 今回は「つる幸」と「千取寿司本店」のメニューだけを記しておこう。本当に旨いんだ。 「つる幸」 しらこ・あんきも・野菜のコールスロー風・さつまいもとれんこんのチップス。(しらこはくり |
ぬいたゆずを器にしている) おこぜの椀(まいたけ・京人参が入っている) お造りは、ぶり・たい・あまえび。(鯛の皮がせんべいになっている) このわたの飯鮨(いいずし)。暖かいこのわた(なめこの腸)が、飯鮨にあう。 ぶりのかまやき。(少し荒くおろした山芋が添えてある) ひぐちこのあみやき。これはなめこの卵巣だ。 コウバコ(松葉ガニの雌)・雄の松葉ガニ。 たこの含め煮。だいこん・ほうれん草(滝口加全の器に盛られている) 門前の蕎麦(暖かいおろしそば)・香の物。 苺・洋梨・無花果。最後に和菓子・抹茶。 「千取寿司本店」は小立野通り、石引東の交差点を左に折れた先にある。 お造りから入る。きじはた・ひらめ・あまえび・ばいがい・ぶり(大根おろしに一味をふって)・あかいか。きすのこぶじめ・しめさば 白子の炙りポン酢添え・さざえのつぼ焼き(麹みそで)を食べたら、にぎりだ。あら・しろこかじき・赤貝・小肌・甘えび・ずわいガニ・かにみその軍艦巻き・ぶり・あじ・穴子・まんじゅ貝・うに。つみれの味噌汁を飲みながらあまりに旨かった赤貝と小肌をもう一貫ずつ食べた。旨えぇ。 |
金沢行奇譚 →→→back 金沢行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
| 久しぶりにやらかしてしまった。あろうことか筆者の聖地、金沢で。記憶をなくしてしまったのである。冷酒の飲みすぎで。 あってよいことではない。なにせ「乙女寿司」でのことなのだ。嗚呼、何かやらかしてはいないだろうな。怖い。非常に怖い。 入沢したその夜、土地に対する甘えがあった。何か、たがが外れてしまったのである。予約を入れておいた「乙女寿司」の出だしはよかった。 先付けの「ヤリイカ」は炒りゴマの香りも香ばしく、しょうが醤油にビシッとあっている。生ビールで口をしめらせて、菊姫の吟醸を冷酒用の徳利で、ちびちび舐める。お造りの「ばい貝・ブリ・しめ鯖」で酒が進む。菊姫が終わり、手取川の大吟醸を頼んだ。「こうばこ」を堪能し酒を注いで熱燗にする。甲羅酒だ。「あん肝」と能登の塩が酒に合う。ということで菊姫の古古酒をオーダー。「のど黒の焼き魚・白子のすり流し・このわた」どれも旨いぞ。「に・・ぎ・・り・・がええっと、う~んと、あれ?あれあれあれ?」お、思い出せない。次々と口に放り込んだ記憶だけはある。でも何を食べたか思い出せない。 これは悲しいぞ、情けないぞ、とほほほほ。しかも、このあたりでお薦めの酒をもう一品飲んでいるのだが・・・ここが記憶の分水嶺か。思い出 |
せない。嗚呼、情けない。 寿司屋は居酒屋ではない。にぎりをつまみはじめたら、酒は控えなさい。2年前、やはり乙女寿司ですごした帰り道、路上でひっくりかえって以来の不祥事だ。恥ずかしいな。情けないな。悔しいな。絶対に旨いものを食べているのに、覚えていない。食べていないも同じことだ。悔しいぞ!ああ、やだ、やだ。風呂に潜ってぶくぶくぶく。 肘がしみる。ひりひりする。あ、擦り剥けている。思い出した!2年前同様、昨夜もひっくりかえったんだ!109の前で!数人の女性グループに笑われていたぞ!とほほほほ。そんなこと思い出さなくてもいいのに。思い出したいことが思い出せず、思い出したくもないことが蘇ってくる。 もういい、ヴォイスレコーダーで出納チェックをしよう。筆者は旅先でもこまめに出納をチェックしているのだ。経理部? 「コンビニで398円」 (え?) カルピス苺とミニメープルロール2個を食っていた。ゴミ箱を覗き込んだら残滓を見つけた。怖ぇぇ。レコーダーを先に進める。 「赤玉本店で2900円」 (・・・・・・・おでんまで食っている!) 信じられねぇぇ。 |
| 松江に着くのは夕刻がいい。太陽は、太平洋側では海から昇り山へ落ちるが、日本海側では山から昇り海へ落ちる。松江の太陽は、宍道湖に落ちる。その夕景が松江第一の「ウリ」である。 10月も終わる一日、夕刻6時少し前に松江に到着。が、なんとしたことか、すでに陽が沈んでいる。秋の陽の沈む早さよ。とほほほほ。 松江駅を離れ松江大橋で大橋川をわたる。宍道湖は左手に広がっているのだが、夜の闇に包まれ湖面はうかがえない。 1年半ぶりの松江である。湖畔のホテルに荷を下ろし、すでに夜の帳につつまれている市中を歩く。地方都市の夜は早いが、その中でも松江の夜の早さは特筆ものだ。まだ6時半にもなっていないのに人の姿が見当たらない、誰も歩いていないのである。日没を逢魔が刻として皆家に閉じこもり戸を閉ざしてしまっているかのようだ。 城の外堀の役割も果たす堀川端を歩き、県庁前から松江城の内堀を東回りに散策する。この内堀も堀川である。城は南面を堀川、大橋川、宍道湖を巧みに利用し三重の防御に巻かれている。 堀端の散策路、露地行灯のような街路灯が低く暗い道を照らしている。暗闇の中、その灯かりだけを頼りに歩を進める。城の北面が、搦め手である。ここから城域に入る。低い街路灯の灯かりが |
逆に周囲の闇を濃くしている。頼りなげなその灯かりに誘われるように位置の見当も危なげながら城山のうっそうとした木々の間を歩いてゆく。 大手門に出た。 明日、ここで菊花大会が催されるらしい。会場準備も終わり、照明を落とした幕の内に菊の花の群れが夜陰咲き誇っている。妖艶というか幽玄というか、リアルな不気味さを秘めた光景だ。 宿への帰路、いずこともなく太鼓と囃子の音が聞こえてきた。騒音も何もない静かな街中に流れるその音がなんと賑やかに愉しげに耳に響くことか。神々の国なのだとしみじみと思った。 そして翌朝。松江の街は宍道湖から流れ出る朝霧に包まれている。 大橋川、堀川の川端も濃い霧に包まれ、街灯と信号機の灯かりだけが輪郭のはっきりしない光芒を放っている。 再び、松江城の堀端を歩く。昨夜の闇に包まれた景色とは別の夢幻の世界がそこにあった。やがて、霧は陽が高まるにつれていずこともなく引いてゆく。 中学生であろうか、部活に向かう自転車の上から「おはようございます!」と元気な挨拶をかけられ目が覚めたような驚きを覚える。思わず「おはよう!」と返す。躾がいい。松江の朝である。 |



| 松山に行って松山城を訪れない愚をおかしていた。今回、そのことに気がついたのである。 いいぞ、松山城。最高だ。城部門、暫定日本一とします。姫路城、残念! これほどに眺望の良い城山は初めてだ。東に石鎚山を伺い、西に瀬戸内海を遠望する。東西ともに市街地を足下に治め、広く開かれた視野を遮るなにものもない。実にすがすがしい光景である。 そして、これほどに写りのいい城郭配置も初めてである。様々な角度で櫓から天守から、石垣から、いいアングルで視野に収まってくるのだ。城の景色は木々が視界を塞いだり、電線が邪魔をしたりすることが多いのだが、松山城ではその心配が一切ない。県あるいは市が意図して工夫をこらしているとしたら、高度な行政手腕と言わねばならない。 天守のある城山頂上には充分な広さの公園がある。ここに植えられた松などの配置や姿も心憎いほどに落ち着きがある。 松山っ子は、まずこのお城をもって郷土の誇りとするに違いない。そしてそれだけの資格は十分にある城である。参りました。 早暁6時過ぎ、あいもかわらず誤った方向へ歩んだ筆者は、いつものとおり無駄な迂回ルートで松山城に登った。なぜ、いつも間違うのだ! |
東口の登山道と二の丸から登城する道、ロープウェイの入口から登る道の3ルートがあるのだが、最も遠回りの東口から登城。おかげさまで競輪場を迂回する大回りをしてしまった。 夜の松山は、今回強力な助っ人がいる。旅の吟遊詩人Y氏である。故あって現在松山在住の彼の手引きで、地元蔵元が運営する立ち飲みスタイルの有料利き酒アンテナショップに押し入った。ここでは、協賛の酒蔵がすべて印刷されたカードを渡される。酒を注文すると朝のラジオ体操のように注文した蔵の欄に判コを押してくれるのである。1杯、100円から300円程度、1杯づつ注文のたびに料金を支払う、キャッシュオンデリバリーシステムだ。軽い肴も用意されており、口すすぎの水もボトルに入っている(仕込み水と筆者はにらんだ)。ここで1杯正3勺程度の地酒を3杯ほど嗜む。あまりに旨いので、本体の瓶を土産に買ってしまった。重いぞ。 地酒で口をしめらせた後、地元密着の割烹で魚三昧、カニ三昧。渡りガニやおこぜの煮付け(一緒に供される豆腐もいいぞ)と締めに頼んだかさごの味噌汁が旨いのにひったまげる。甘めの白味噌仕立てだが柚子の香りと酒粕の香りであろうか、いやはや、なんとも参りました。 |



| 天守の現存する城としては、日本一高所にある山城「備中松山城」。備中高梁(たかはし)市街の北端、臥牛山の山頂にこの城はある。 10月23日10:00(ヒトマルマルマル)同城攻略を開始。同日昼12:00(ヒトフタマルマル、制圧、状況終了。「松山を制する者は備中を制する」と言われるほどの要衝を抑えた今、筆者は備中を手に入れたも同然である。 閑話休題(あだしごとはさておき)・・・ 岡山から特急で30分強の位置に備中高梁(たかはし)はある。旧国名、備中松山の改名は、明治政府の旧幕側への嫌がらせだったのだろう。 ぶらりと訪れた初めての土地で必ず犯す筆者の過ち、それは見当違いな方向への歩行。 やっぱり、やらかした。えらい迂回路をとってしまった。松山城とは向かいの山中にある吉備国際大学のキャンパスをぐるりとまわりこみ、引き返しもままならず、迂回路から松山城に向かう。城の麓まで2.8キロ程度なのに4.5キロは歩いた。7合目までは有料のマイクロバスがあるが、筆者は頑なに徒歩での攻略にこだわる。7合目でバスに乗ってきた後発集団に抜かれた。悔しい。 山頂にむかう遊歩道のそこここに注意書きがある。これがまたしゃらくさいのだ。 「松山城には右手の道を進むべし 城主」 |
「あわてず、ゆっくり歩むべし 城主」 「この先、足元悪しきにつき、気をつけて歩むべし 城主」「ゴミは持ち帰るべし 城主」 うるさいっちゅうの城主!しかし、なかなかの勾配である。息があがってきた。 「このあたりがちょうど中間地点である。しばし休まれよ 城主」 ・・・かたじけない。 山頂には2層2階の天守閣がある。見晴らしは、この山頂の天守からよりも途中の「ふいご峠」からの眺望の方がよろしい。 市内には武家屋敷や高梁川へ流れ込む紺屋川のせせらぎ沿いなど風情のある町並みがあり、訪問者の心を休ませる。街全体の印象としては倉敷のような観光資源への投資の徹底性は感じられないが、そこがまたいいとも言える。郷土資料館など、まるで骨董品のフリーマーケットのようだ。床に無造作に並べ立てた郷土の物産品や遺物が古蔵の日干し状態のようになっている。展示というよりは放置という感じ。 藩政改革の立役者、山田方谷(長岡藩、河合継之介が師事)を筆頭に山中鹿之助、小堀遠州(筆者にとっては庭師)、大石内蔵助などといった面子がこの街の歴史に彩りを添えている。ぶらりと立ち寄るにはいい街である。 |



高松行2→→→ back 高松行 高松行2 高松行3 高松行4
| 世の中に見落としってある。見落とされるのは大抵の場合、身近な存在。人間でもペットでも小物でも身近にあればあるほど見落とし度は高くなる。そしてそれは土地も同じ。関西在住3年弱、2時間足らずで訪れられる気安さから高松は日帰りの街となっていた。言わば使い捨て状態。なんてもったいないことをしていたのだと反省しきりの昨今である。 讃岐うどんブームは今どうなっているのか?ブームである以上、その勢いは終息にむかっていくものだが、讃岐うどんの現状がわからない。どうなの?今。「恐るべき讃岐うどん」のおかげで高松が「うどん」一色になったことは間違いない。あたかも「うどん」を食えば高松を消費したことになるかのような錯覚を人々に植え付けてしまったのではないか。讃岐うどんが旨いのは異論なし。本が面白いのも異論なし。しかし筆者は、高松=讃岐うどんONLYというこの趨勢に異を唱える。って本当にあるのか、趨勢。 高松で宿泊するならワシントンホテルである。それは立地がライオン通りのそばだから。 高松ライオン通り。旨そさ高密度、旨そげ指数120%の実に愉しい歓楽街である。通りの幅は広くない。しかし通りをはさんで向かい合う飲食店の多くが実に旨そうな雰囲気を醸し出している |
のである。 土地勘というか、事前調査もしていなかったので行き当たりばったりである。ライオン通りを北上し、北古馬通りを左折「魚好人(ぎょこうじん)」という店で魚を食べる。旨いがな。お造りにかんぱち、すずきの洗い、まなかつお、けんさきいか。さらにまなかつおを焼いてもらい、うにのわさびしょうゆ、かんぱちのやまかけで一杯、二杯、三杯、四杯・・・ひっく。 すぐそばにカレーうどんで有名な「五右衛門」があった。ためらわずに入る。かなりいい気分である。外に出て、再びライオン通りを歩く。巨大なコッペパンに焼きそばをはさんで売っている出店に気をひかれる。 やがてライオン通りの逆行を終わり、トキワ新町に入る。「ラーメン・餃子の店、ごんな中店」の角をまがると「讃岐屋」がある。ここでは冷やしなめこおろしを食べる。満腹だ。 「五右衛門」も「讃岐屋」も恐るべきさぬきうどんに一般店として掲載されている。このほか「鶴丸」も近辺フェリー通りぞいにある。 高松は魚が旨い。そして酒を飲んでしめにうどんを食べる。この満足度はかなり高い。お見それしました、高松様。 |
| 温泉旅館の大浴場を独り占めすることは、男子一生涯の夢である(浜口雄幸) ウソ。 昼夜を問わず、無人の湯につかり続けること7度。アンチ旅館派の筆者ではあるが、故あってこの男子の本懐を成し遂げることができた。その偉業を記念して今回は箱根湯本温泉旅館行である。渋い!渋いぞ! この「紀行」に何度も載せているように筆者は旅館は苦手である。いつも祈るような気持ちで投宿する。仲居さんの根性がネジ曲がっていないか、まさかテレビにコインキットはついていまい、大浴場に景色はあるのか?部屋で飯を食いたいし、作りおきの再加熱料理や冷めてもおいしい料理など胃袋が許さない。団体客が占領軍のように闊歩していないか。とにかく気がかりなことが多すぎる。予約を入れる前から気疲れするとはどういうことだと言いたい。 宿代の高さはこれらの条件の担保とならない。有名温泉旅館は小都市のような大型宿泊施設だ。見たくもないショーがついたり、ショッピングモールのようなみやげ物屋がついていたりする。 今回は、考えた。故あって両親を引き連れての家族旅行だ。静かなひとときのため宿選びの基本方針を定めた。集合客室タイプはまず、はずす。離ればかりの隠れ家的な宿が良い。客室数が少な |
い分、労働集約性が高まり、料金に跳ね返るがそれは仕方がない。なにせ大浴場を独り占めにし、おもてなし感を極大化させるためなのだから。 次に日程、ウィークデイを選ぶ。日祝ならびにその前日は避ける。もちろん行楽シーズンなんかもってのほかだ。 で、もって選んだのは離れのみ8室、駐車場なんか収容台数が10台までの人数限定の宿。 箱根湯本駅から徒歩10分程度、早川を渡り急勾配を登坂する。 あった。 「歓迎××様」とある。しかも筆者の名前だけ。他に客はいないんか?け、けっこう照れるな。しかし、実際には他に客がいたのだ。翌朝、それなりのカップルが帳場に向かうのを2件目撃した。 なるほどね。 お忍びの宿なわけだ。けっして玄関に「歓迎××様」などと書いてもらっては困るんである。 忍びは隠れ家的な宿を探す。だから全室離れの客室数最小の宿が選ばれる。人目を避けるために各離れには内湯があるのが望ましい。人目にさらされる大浴場なんかには現れない。つまり、大浴場独り占めというわけである。 温泉旅館で浴場を貸切状態で楽しむ秘訣に気付いた筆者であった。 |



箱根湯本のそば処「はつはな」 早川の流れ。夜になるとそのせせらぎの音が静かに響く
| 大宮を越えるまでは新幹線とは思えぬ低速で市街地を走る「こまち」京都線・神戸線新快速の方が速い。関東平野は見晴らす限りフラットである。淀川の沖積平野である河内平野の景色を見慣れた昨今、ひさしぶりの寛闊な景色に心が寛ぎを覚えている。関東平野と河内平野の違いは平野を縁取る山並みの有無だ。関東平野は周囲に山がない。面積の狭い河内平野はかなり間近まで山裾が迫っており、周囲一面遮るもののない視界を求めるのは土台無茶というものだ。 入梅したばかりの空は一面が灰白色で、天と雲の境目すら定かではない。頭上間近にまで雲が降りてきているのか、水煙のような雨粒に邪魔されそのあやめがつかない。関東平野の端に近づいた。短いトンネルが続き、周囲に小高い丘が居並ぶようになる。目に付く丘陵のすべてが深い緑をまとっている。これだ、この景色に再会したかったのだ。丘という丘が噴き出したかのような木々の緑に覆われている。幾つかのトンネルを抜けると、不意に雲が切れた。水溶性の灰白色の絵の具の上を、たっぷり水をふくませた刷毛でひとなですると隠されていた薄い青地が透けてきたかのような空の変化だった。高層に浮かぶ白雲が茜色に輝いている。夕陽の照り栄えがバックの淡い青のせいかひときわ鮮やかに輝く。一面が朱く染まっ |
た空に低層にたなびく暗灰色の千切れ雲。筆者の好きな情景だ。 大阪から東京に降り立った筆者は10分後に発車する東北新幹線「はやて」に飛び乗った。チケットも求めずに乗り継いでやろうと思ったが、それは無理。改札はきっちりと区分けされている。しかも「のぞみ」に自由席車両ができて久しいからか、慣れとは恐ろしいもので東北新幹線も自由席車両があるだろうなどと考えていたわけだ。甘かった。「はやて」はいまだに全席指定だ。「はやて」は秋田新幹線「こまち」と連結している。盛岡まででは「こまち」に乗車する可能性がある。田沢湖線を走る「こまち」は左右2列シートの狭軌車両だ。「のぞみ」から乗り継ぐとやや窮屈なのはやむをえない。 仙台をすぎた。左手に見える孤峰は蔵王。山頂付近に残雪がわずかに張りついている。その姿を軽く後方に置き去り一関を通過。界隈の河川敷は河川の両岸あるいは中洲のすべてに木々が密生している。群生しているかのような緑のかたまりのすきまを水面が豊かな水量を誇りつつ輝いている。左手に見える栗駒山の山頂付近の窪みにはそれとわかるほどの残雪があとわずかばかりで消えゆく運命を予感しているかのような儚そうな雪形を見せている。6月の1旬、北国の初夏だ。 |
九州行(立志編)→→→back 1立志編 2疾走編 3郷愁編 4風雲編 5終焉編
| 早暁4時半に目が覚めた。言うまでもないことだが筆者はジジイではない。夏至をすぎて間もない7月の一旬、空はすでに明るい。何かを求めるのではなくただ無性にひとり、車窓を眺めながら時を過ごしたくなった。旅ごころの起動だ。 この時間、JRのホストは休止している。ネット予約ができないのでチケットは現地で調達するしかない。とすれば、混雑の予想される路線は避けたい。予約も決済もできるのはエアだ。よし九州へ行ってやれ。伊丹から福岡へ飛んで西回りで九州を一周するのだ。無論、日帰りで。オプションとして九州新幹線初乗車、宮崎で1時間フルーツ三昧をする息抜きつきだ。宮崎で休憩をしなければ、1時間早く帰阪できるが夏は宮崎のトロピカルフルーツだろう。 ということでポケット時刻表4月号の九州路線図と当該エリアの時刻表部分をむしりとりホチキスで綴じる。このミニ冊子にデジカメと文庫本、念のため靴下と下着、替え着もバッグに放り込み、ペンとメモ帳をポケットにねじ込んで軽々と旅に出る。 時刻表のちっさい文字をルーペで拡大しつつ立てたスケジュールは以下のとおりだ。 7:45~8:50。大阪-福岡間を空路「ANA421便」で移動。機種は747だ。2階席をとるのだ。 |
9:30~11:13。博多-新八代間を「リレーつばめ39号」で南下。 11:15~12:03。新八代-鹿児島中央間を九州新幹線「つばめ39号」で突破。 12:13~14:19。鹿児島中央-宮崎間を「きりしま12号」で北上。宮崎で1時間のインターバル。 15:37~18:38。宮崎-大分間を「にちりん20号」で急進。 18:44~20:08。大分-小倉間を「ソニック50号」で驀進。 20:21~22:26。小倉-新大阪間を「のぞみ500号」で直帰だ。 やればできるじゃないか。こんなに接続が良いとは思ってもいなかった。 大阪は雨。大気の状態が不安定で大雨雷雨の予報が出ている。伊丹空港のレストランで肉うどんをすすっているといきなり雷光が閃いた。予報の通りだ。予報は九州地方も集中豪雨の警戒を呼びかけている。不吉な旅立ちではあったが、高度を確保したジャンボは離陸時の雲中こそ揺れはしたものの安定した飛行を続けた。福岡上空は若干の雲が浮かんではいるが、晴れである。幸先はいいぞ。しかし筆者は、この日自分を襲うであろう運命のいたずらをいまだ何も知らずにいた。 |
九州行(疾走編)→→→back 1立志編 2疾走編 3郷愁編 4風雲編 5終焉編
| 福岡空港から博多駅までは地下鉄で2駅。福岡空港は市街地へのアクセス利便性が日本一だ。8時50分にランディングした筆者は20分後の9時10分には博多駅みどりの窓口でチケットを購入している。 「鹿児島中央経由で日豊本線、宮崎、大分、小倉経由新大阪までの片道切符を」 久しぶりの一筆書きチケットだ。昔は露骨に嫌がられたこのチケット購入法もIT化の進んだ今、発券はすばやい。総延長1300キロ超。上野から北海道旭川を越え名寄までの距離にほぼ等しい。料金は14,810円。ひとまず、宮崎までの3本の特急券も購入した。鹿児島本線を新八代まで「リレーつばめ39号」その後鹿児島中央まで九州新幹線「つばめ39号」、鹿児島中央から宮崎まで日豊本線「きりしま12号」に乗車だ。 「リレーつばめ39号」は鹿児島本線を南下し新八代のホームで九州新幹線に接続する。在来線が新幹線と同じホームに停車するのはこの路線だけだ。降りたら目の前に新幹線「つばめ39号」が待っている。 筆者は先般不慮の事故により熊本、鹿児島間を急行した。あのとき在来線の特急「つばめ」で熊本、鹿児島間は2時間30分。気ばかり急いても列車は急かぬ。特急とは名ばかりの速度で走る「 |
つばめ」の横を試乗会の九州新幹線「つばめ」があっという間に追い抜いていった。あの悔しさは終生忘れまいぞ。今日はその復讐なのだ。 新幹線によって熊本、鹿児島間は56分に縮まった。新八代、鹿児島間ならば新幹線のみで最短34分だ。信じがたい短縮だ。 博多、熊本間の車窓はさしたる特徴がない。新幹線の登場によって失われた新八代、川内(せんだい)間の車窓こそがエメラルドグリーンの八代海、東シナ海が広がる日本鉄道車窓界の白眉なのだ。この区間は、第3セクター肥薩おれんじ鉄道に引き継がれた。 九州新幹線は九州山地を貫いてゆく。トンネルと切りとおしの連続だ。博多で即日チケットが買えた割に社内は満席である。シートは普通車指定席で2列2列の4座席規格、フル規格新幹線よりも1列少ない。肘掛、テーブル、背もたれが木製である。「和」を意識した設計とのこと。編成は6両で山陽新幹線の8両よりもさらに2両少ない。運行も1時間に2本と節約型の運用だ。頑張れ!九州新幹線。 12時3分、あっと言う間に鹿児島中央到着。短い。あまりにも短すぎる。家を出て5時間半あまり。南国の抜けるような蒼空の下、1日は何事もなくすぎてゆく気配に満ちていた。 |
九州行(郷愁編)→→→back 1立志編 2疾走編 3郷愁編 4風雲編 5終焉編
| 九州新幹線のホームは短い。新八代駅でも短いし、鹿児島中央駅でも短い。6両編成なので短いのはあたりまえだがホーム先端の立ち入り禁止柵がカメラ小僧のからだを遮る。広角レンズならいざしらず、柵を乗り越え立ち入り禁止ゾーンに侵入しなければ新幹線の全景をカメラに収めきれない。悔しい!カメラ小僧の声が聞こえる。筆者はマニアではないので関係ない。 鹿児島中央での乗り継ぎの猶予は10分だ。日豊本線特急「きりしま12号」は3両編成のカラフルボディで待機している。JR九州の車両は個性的だ。斬新なフォルムの新型車両はもちろん、旧来車両でもカラーリングの奇抜さで目をそばだたせる。鉄道マニアの生息地として九州が第一等なのはこのあたりに理由があるのだろう。 「とんこつ弁当」を購入して慌しく乗車したが、ミネラルウォーターを買いそびれた。しまった!車内販売がないのだ。新幹線でも走行時間の短さからか車内販売がなかったのでチャンスを逸し続けたというわけだ。そういえば新幹線の車内アナウンスに韓国語と中国語が入っていたのが耳に新しい。鹿児島までは観光誘致のアジアンワールドだった。しかしながら鹿児島からはスーパードメスティック。久しぶりの日豊本線縦走が始まった。鹿児島から北上するのは初めてだ。 |
鹿児島中央を発車した「きりしま12号」は東隣の鹿児島駅を通過。その瞬間、桜島の雄大な姿が錦江湾のむこうに浮かんだ。列車は錦江湾をまきこむように海岸線を走る。これほどまで惜しみなくオーシャンビューを提供する車窓が他にあろうか。桜島の姿はなかなか車窓から離れない。まるで周回軌道のようだ。美しかですばい。 やがて列車は海岸線に別れを告げる。車窓は、日本の原風景とも言うべきすばらしい緑に包まれてゆく。木、木、木、木、木だ、木だ、木だ、木だ、木だらけだ。人煙もまれな緑の山々の中を列車は走る。人煙もまれなはずなのに畑がある。田圃がある。しかし、そこに人の姿は見当たらない。木また木、山また山だ。 「Feeeeeee!」 列車が警笛を鳴らす。そのかすれたような音色すら懐かしい。 車体を刷くように木々の梢が張り出している。密生した樹木のむこう、こんなところにと思える場所に民家の屋根がわずかに顔を出す。もろこし畑だろうか、淡い穂のかなたに陽光に照る葉を茂らす木々に覆われた山々が浮かぶ。 「ずっとこのまま・・・」との願いも虚しく列車は市街地に入った。今日のその時まであと5時間である。 |



九州行(風雲編)→→→back 1立志編 2疾走編 3郷愁編 4風雲編 5終焉編
| トロピカルフルーツの王国宮崎で1時間の休憩だ。強行軍を続ければ12分後特急「にちりん18号」に接続だが、この特急は1時間後にもある。ここで1時間休憩をしても大分経由小倉行きで新大阪までの「のぞみ」に充分乗り継ぎが可能だ。筆者は改札を出た。人はきたるべき未来を予見することが叶わない。この1時間、この1本の列車を見送ったことがその日の運命の一大分岐点であったことを神ならぬ身の筆者は、このとき知る由もなかったのである。 街に出た筆者はフレッシュマンゴージュース2杯、日向夏ジュース1杯、パイナップル&りんごジュース1杯を飲んだ(馬鹿?)堪能し、駅に戻りホームに上がろうとすると、けしからぬではないか。改札で駅員が引き止めるのである。 「にちりん20号は架線故障の影響で大分行きを中止し延岡どまりになります」なんと!「16:31のにちりん22号にお乗りください」1時間の足止めをくった。とりあえず、フレッシュマンゴージュースをもう1杯飲む。 定刻通り進入してきたにちりん22号に乗り、時刻表をめくる。大分発19:45のソニック54号に6分の接続だ。ソニックは21:13に小倉に着く。小倉発21:26のぞみ502号で23:37に帰阪できる。 嗚呼、しかし筆者は甘かった。大分に近づくに |
つれ、行き違いの停車回数が多くなった。停車時間もやたら長い。妙だと気づいた頃、車内アナウンスが流れた。架線故障の影響でダイヤに大幅の乱れが生じているらしい。特急列車は各駅停車と化し、1駅ごとに延々と停車し続ける。大分まであと5駅だが、1駅あたり10分は停車してきたここしばらくの様子を見ると、最低でも50分はかかると思われた。JR九州ではこのような事故はめずらしくないのだろうか。車中は実に平穏だ。気色ばむ客はひとりもいない。いや、1名だけいる。誰あろうこの筆者だ。車窓の外にタクシーの空車燈が見える。車掌をつかまえてここで下ろしてくれと主張する筆者。 「ちょっとセンターに確認してみます」 「そうしてください」 さすがに車両のドアをあけるわけにはいかないらしい。待つことしばし。 「車掌室からホームに降りていただけますか」 センターから許可をとった車掌の申し出をうけ筆者は車掌室からホームへ降りた。 19時50分。駅前に何もない小さな大在駅頭に筆者はひとり佇んだ。先ほど見えたタクシーの姿はすでになく、駅前にはタクシー乗り場も、バス乗り場も何もない、小さなロータリーがあるだけであった・・・(あれ?) |
九州行(終焉編)→→→back 1立志編 2疾走編 3郷愁編 4風雲編 5終焉編
| (前回までのあらすじ) 九州一周日帰り旅行を思い立った筆者は、分厚い雷雲に覆われた大阪の空を飛び立ち、伊丹から福岡にむかった。博多駅を起点に西回りで4本の特急、2本の新幹線を乗り継ぎ、夜更けには帰阪する完璧な計画は、途中宮崎駅まで順調な滑り出しを見せる。途中下車をした宮崎にて念願のフレッシュトロピカルジュースを5杯飲み干した後、旅を継続する筆者は大分駅を前に思わぬ障害に前進を阻まれた。架線故障によるダイヤの混乱。遅々として進まぬ特急に業を煮やし、大分の手前大在駅に停車した特急列車を見限り、車掌の手引きで後部車掌室から下車した筆者。あてにしたタクシー乗り場もない大在駅頭に19時50分、彼はひとりたたずんでいた・・・ タクシーがない。タクシー乗り場もない。背後を振り返ればさきほど見捨てた特急「にちりん」の窓から明かりが漏れている。 (いまさら、どの面を下げてあの列車に戻ることができよう) 筆者は決然として歩き出した。 商業地でもない地方都市の住宅街、見知らぬ町の静かな夜。それは寂しさと心細さのない交ぜになった久しぶりの漂泊感を筆者に蘇らせた。その夜の筆者は運からとことん見放されていた。ヘッ |
ドライトの行き交う交差点を幹線道路のそれであろうと駆けつければ、どうやら地元民の抜け道程度のものでしかなく通過するのは民間車ばかり。タクシーなどは1台も姿を見せない。バス停は明かりを落とし、終バスはとっくの昔に通過したことを告げている。歩いた。どこへむかっているのか。とにかくタクシーに出会いたい。その一念で道なりに歩き続けた。街灯が小さな明かりの輪を路上にぽつん、ぽつんと落としている。その輪をつないで拾ってゆく先に何があるのか、筆者はわずかな希望を胸に歩き続けた。やがて道はか細いT字路にぶつかり途絶えた。一縷の希望さえも打ち砕くようにかぶさってきた道は、街灯すらない寂しいあぜ道のような田舎道。とぼとぼと悪態をつきながら、結局、筆者は駅にもどった。特急の姿はすでにホーム上にない。呆然としている筆者の前に客を降ろすタクシーが停まった。 21時15分、筆者を乗せたタクシーは大分駅前に車を寄せる。結局1時間以上を費やしてやっと大分にたどり着いたのだ。いずれにせよ今日中に大阪へ帰る方途は失われている。駅前のホテルに飛び込み一夜の宿を確保し、何の予備知識もなく、次々とシャッターを閉めてゆく繁華街で飲食店を求め、夜の街へ消えてゆく筆者であった。 |
稚内行(望郷編) →back 1稚内行 2望郷編 3徘徊編 4旅愁編 5追憶編 6追憶編2
| 関西空港からの直行便ANA735便がランディングアプローチに入る。高度を下げ始めた機は、オホーツクの海岸線と並行に滑空する。稚内空港のすぐ横は広大に広がるオホーツクの海原だ。 5年ぶりの稚内は、6月中旬で気温19度。大阪の予想最高気温が30度だったから、11度の温度差で筆者を迎えてくれた。湿度が低いので快適を通り越して少し涼し過ぎる。夜の冷え込みは手がかじかむほどである。 北の果ては人影もまばら。搭乗客のほとんどは高齢者。皆キャラバンシューズを履き、軽登山のいでたちだ。利尻島に行くんだろうなあ。稚内市内に入りフェリーターミナルまで向かうバスは高齢者のサロンと化した。このあと市内に繰り出したときに気付いたが、観光客も高齢ならば、住人も高齢だ。若者の姿が見えない。神隠し?市内で若者と言えば高校生だ。それ以上の年齢層は極端に少ない。旭川や札幌に若者を奪われてしまうらしい。 「楽しいねえ!」 バスの中、背後から若い女性の歓声があがる。そう言えば最後にバスに乗り込んできた若いカップルが後ろの席に座ったのだ。 「××君、見て!」 2人とも自己開放度120%だ。度を越したは |
しゃぎぶりである。網膜に映ったことごとくを言語化する。 「山!」利尻富士だ。 「海!」オホーツク海だ。 「サニーマート!」コンビニである。 「ソフトクリーム!」見ればわかる。 「セイコーマート」コンビニだって。 嬉しいんだろうなあ。ここまで外聞をはばからない言動はそうそうできるものではない。眉をひそめるよりもほほ笑ましさが先にたってしまった。許す。 稚内は風の街。1年中、風が吹いている。市街地後背の丘を越えて西から日本海の風、東の海からオホーツクの風。細長い半島の身をもむようにして風が吹き渡ってゆく。朝、6月には珍しい猛烈な風に見舞われた。3月頃が一番すごいそうだ。エアも上空待機し、断念して旭川に退避することも珍しいことではないらしい。風のおかげで雪はそれほど積もらない。パウダースノーであることと猛烈な横なぐりの風に積もるいとまがないのだ。道路はアスファルトが見える程度に除雪される。しかし、完全なアイスバーンで2週に一度くらいはタクシーでも休業状態になるらしい。 稚内で最も近代的な施設であろう全日空ホテルに荷を降ろし、5年ぶりの国境の町探訪に出ることにした。 |



開基百年記念塔から稚内港を望む ノシャップ岬 北防波堤ドーム
稚内行(徘徊編) →back 1稚内行 2望郷編 3徘徊編 4旅愁編 5追憶編 6追憶編2
| ホテルに荷を降ろし、北防波堤ドームに足を運ぶ。全長430メートル、高さ14メートルの「巨大な」と形容してもかまわないであろうコンクリートの塊である。古代ローマ調の装飾が北の風浪から港湾を守るための実用性以上の豪奢さをかもし出している。回廊部にはテントがひとつ、バイカーの宿だろう。人の姿はない。時間や人々から置き去りにされたような感覚に包まれるこの空間を筆者は愛する。 昼食の時間をかなり過ぎているので急がねばならない。南稚内「ひな寿司」の存在を旅の吟遊詩人Y氏から聞いていた。電話をいれたが昼の営業は21日からだと言う。1週間ほど早かったか。やむなし。まあいい。また来る理由ができた。 「N寿司」は初めての訪店だ。結果として稚内滞在中3台のタクシーでこの店の名を聞くが昼しか食べていないので真価のほどは不明である。 食後、市街地後背の高台にそびえる開基百年記念塔に登ることにした。日本一短いと思われるロープウェイは丘の中腹まで運んでくれる。短いだけでなく古い。ここまで古いとちょっと怖い。もちろん一人で乗車だ。時刻表はあるのだが関係ないようだ。係員が山上駅と連絡を取りすぐに発車する。山上駅のホーム前でゆっくりと停車。まだ駅には着いていない。宙ぶらりんのままの状態が |
しばらく続く(このまま?)なんという不安感だろう。やっと動いた。プチ恐怖を体感できる。 山上には遊園地があったらしい。少し前に廃園になった。このロープウェイも来年にはなくなるとのこと。寂寥感はこの街の横顔だ。 記念塔まではそこから400メートルほど徒歩で登らねばならない。後背に広がるオホーツクの海の蒼さがまぶしい。フェリーターミナルや全日空ホテルが一望のもとだ。風力発電の巨大な風車がブンブンと羽切り音を響かせる。周囲に人の姿はない。さきほどまで笑いさざめいていたバスの人々はどこに行ってしまったのだろう。 高さ80メートル、標高とあわせて海抜250メートルの記念塔の展望室は360度の眺望が楽しめる。西側日本海のかなたに利尻と礼文の島々が浮かぶ。陽光をうけた水面が銀彩のようだ。 記念塔からノシャップ岬へ向かう途上の稚内公園内に南極観測隊に同行したタロとジロたち南極観測犬の記念碑と供養塔がある。稚内は彼らの訓練地だったのだ。そのそばには、太平洋戦争の無条件降伏受諾の5日後、8月20日に樺太に侵攻してきたソヴィエト軍を前に最後まで電話交換の職務を全うし服毒自殺をした8人の郵便局員の慰霊碑もある。粛然とした面持ちにならざるをえない。ノシャップ岬へ向かおう。 |
盛岡行(ソウルフル編)→→→→back 盛岡行 激闘わんこそば編 ソウルフル編 盛岡行4
| 6年の歳月にも盛岡の佇まいは変わらない。そのことをしごく当然のこととしている筆者がいる。変わらぬことに何の根拠もなく確信が持てるのだ。もっともJRの駅は変わっていたか。 金沢と双璧をなす筆者のソウルタウンが盛岡だ。ここに来れば必ず立ち寄る店が、幾つかある。そのひとつが「南部どぶろく屋」。 店の造りが面白い。低い腰掛が14~5席ほどならんでいる。その腰掛の前に縁側ほどの高さで板敷きの床が広がる。その板敷きの上に並べられた盆の上の料理をつまむのである。板敷きの床は広い。客は全員、一方向つまり床に向かっている。その床の中央に大将が文机を据えて客に対峙しているのだ。まるで牢名主のようだ。でんと尻を据えて客に郷土の話、一族の話をする。 地元の名士なのだろう。400年前までさかのぼれる家系の一員だと言う。平家の落人の一族だそうだ。伊豆の韮山から北に進出してきた。その際、本来の氏であるY姓の漢字を変えた。平家の落人であることを隠すためだ。筆者の前職の東京支店長が同姓だった。聞いてみると店の奥から一族の家系本を取り出してめくり始めた。なんとそこにあのY支店長の名前が載っているではないか(社名まで書いてあった)世の中は狭い。 この店に来れば、とりあえず、煮込みとたこ刺 |
しだ。味噌仕立てではない煮込みが筆者の大のお気に入り。北寄貝刺し、生うにも頼む。盛岡は三陸の魚貝、北上山地の山菜、前沢牛や岩手短角牛など地のものの宝庫だ。柚子をくりぬきくるみをまぜあわせた秘伝の味噌入りの1年間熟成「柚子味噌」がからすみのような外見に似つかわしく酒の肴にぴったりだ。特性のどぶろくをたっぷりと呑み、しめに日本酒をきゅっと一杯。 偶然、隣り合わせた仙台から出張の営業マン氏と話しがはずみ、時が過ぎた。筆者はもう一軒寄らねばならない。バー「ルパン」である。盛岡でバーを探していた営業マン氏にルパンを教えて店を出た。 「ルパン」も変わらずにあった。変わったのはギムレットのレシピ。ローズライムではなくなっていた。フレッシュライムだ。マスターは何の気取りもなくその旨を暴露する。それも良しか。店のカクテルレシピが増えている。筆者にとってはうれしい変化だ。 ドアが開き、先ほどの営業マン氏が来店した。笑いあいながら短い久闊を叙し、かなりの飲み手である彼とのひとときをカクテル談義で楽しんだ。一晩だけの盛岡は、しかし筆者にとって何ものにも変えがたいリフレッシュ効果をもたらしてくれる。だからこそのソウルタウンなのだ。 |
| 思いつきと出たとこ勝負で旅に出る筆者の鬼門筋はゴールデンウィークだ。GWに良い思い出などひとつもない。これっぽっちもない。 頑張れば足は確保できる。どこかしらへの座席はあいているものなのだ。それで気を良くして出かけてしまう。問題はその後だ。現地について確保困難なのが宿。代理店が枠で押さえているに違いない。都市部ですらすべてのホテルが満室であることが多い。 東北に的を絞った探索では仙台方面のエアが空席だらけ。やったね。しかし、ホテルがすべて埋まっていた。断念せざるを得ない。 観光収入を極大化させるため、この時期を狙って各地でイベントを催している。イベント情報にも目を配らなければ、快適な旅は実現しない。GW最大の集客力を誇るのは博多。博多どんたくは200万人が押しかける。 岩国を訪れたのは5月2日の日曜日。タクシーの運ちゃんが驚いた。錦帯橋の周囲の河川敷駐車場が満杯なのだ。滅多にないことだそうだ。滅多のうちの1日は3日後の5月5日。危ねえ、危ねえ。岩国の米軍基地の日米親善デーがこの日に開かれる。人口11万の岩国市に21万人が押しかける。市内大渋滞の1日だそうだ。航空ショーが目玉なそうな。来なけりゃわからんわ、そんな情 |
報。 途中、立ち寄ろうとした広島もフラワーフェスティバルで5月3日からの3日間、130万人の人手が見込まれる。ちなみに広島のライバルは博多らしい。タクシーの運ちゃんは何かというと博多を引き合いにだしていた。曰く『地下鉄で負けている』『球場で負けている』『祭りの集客で負けている』・・・何かで勝てよ、と思った。 岩国駅は思っていたより大きい。ホームの数というよりも線路が多い。基地の関係で貨物列車を引きこむのか?山陽本線のほか、岩徳線、錦川清流線も合流している。 駅から錦帯橋までは距離がある。バス待ちもすごい。やっぱGWなのだ。島耕作バスが走っている。弘兼憲史氏が岩国出身らしい。おはんバスや錦帯橋バスも走っている。錦帯橋のむこう岸、城山の頂上に典型的な山城である岩国城がそびえている。ロープウェイが長蛇の列だ。30分待ちなどという看板の位置からさらに1.5倍は人が並んでいる。無論パスして徒歩で登った。頂上まで45分などと脅しをかける看板もなんのその、20分程度でついてしまった。最近登ってばかりいるからな。 カジカの鳴き声、川のせせらぎ、鳥のさえずりすべてが心地よい。あり、ということでひとつ。 |



ポツンと見えるでしょ山頂に。あれが岩国城(写真左) 川の中央にかかっているのが錦帯橋(写真右)。
| 琴平と言えば「こんぴらさん」ゴールデンウィークを4日後に控えた4月下旬、不意に思い立って琴平を訪れた。 朝7時32分の「のぞみ39号」に乗車。岡山着8時19分。30分の待ち合わせの後「南風3号」で9時53分にはJR琴平駅に降り立った。 不意のこんぴら参りは何ゆえ?お告げ?天啓?そろそろお迎えが? ちょっと煮詰まってしまったので、海を見たくなったのだ。運動も必要だし、安上がりに旨いもんも食べたくなった。それで琴平ね。 瀬戸大橋線で瀬戸内海を見ることができる。こんぴらさんは本宮まで785段、奥社まで583段、計1368段の石段昇降ができる。香川県ゆえ琴平も讃岐うどんが隆盛だ。運動のあとにたらふく喰おうという魂胆だったわけです。 JR琴平駅前は静か。参道のように続く駅前ストリートの先に琴電の琴平駅がある。その脇には日本最大の常夜灯、高燈籠がある。今でも夜間は灯が燈されるとか。江戸慶応元年に建立され、遠く丸亀からもその灯が望めたと言う。この年、長州では高杉晋作のクーデターが成功し、開明派が藩の実権を握っている。 高燈籠を右に見ながら直進、T字路を左折すればいよいよ金刀比羅宮の参道口に出る。みやげ物 |
屋、うどん屋、木彫り彫刻屋が門前、市をなす。 奥社まで1368段の石段を制覇するのだ。筆者のマンションのワンフロア分が15段だから、92階建に登るのと同じ事だ。 登った。思ったほどしんどくはない。石段の高さと幅が適当なのだろう。連続する石段が少ないせいもある。たまに長い石段があっても乳酸が筋肉に溜まりきる前に踊場が設けられている。 観光客は本宮までで満足して引き返すのが大半だ。本宮の右奥に森閑とした参道が続いている。筆者は無論、歩を進め、奥社まで登りきった。丸亀平野が一望のもとに見渡せる。平野の端、瀬戸内海の手前にポンと無造作に置き捨てた三角おむすびのような讃岐富士、その後背には瀬戸大橋の橋脚が遠望できる。奥社まで登りきった者同士には無言の連帯感と優越感が芽生える。本宮までで帰る連中に対して皆どこかで見下す視線が生まれている。「あ、君たちはここで帰るのね。そうなのね、ふん、ふん」 下山し、讃岐うどんを食べる。虎屋と狸屋、獣系の屋号の店で生醤油うどんと冷ぶっかけを堪能する。どちらもセルフの店ではないが、筆者にとっては十分うまい。狸屋がいいな。 翌日、足がぱんぱんになったことは言うまでもない。ロボットみたいに歩いているのである。 |
| 静かな、自らの意志で時間の流れを止めてしまったかのように静かな街である。 播州赤穂、山陽新幹線あるいは山陽本線の相生(あいおい)から赤穂線で3駅、時間にして13分のところにある。 朝夕を除けば1時間に2本しか電車は来ない。2本のうちの1本は相生-播州赤穂間のシャトルのような便で、赤穂から岡山に向かう電車は1時間に1本というわけだ。しかも岡山までは1時間20分かかる。もっとも相生ですら新幹線の停車は1時間に2本しかない。そんなもんなのか播州赤穂、塩の街。 その日、とりあえず岡山までの切符を手に各駅停車ひかりに乗車した筆者は、のぞみ通過待ちの退避駅、相生で途中下車をした。 相生始発の赤穂線に乗ってみたくなったのだ。もちろん目的地は播州赤穂。理由などはない。気がむいたのである。 相生駅も何も無いところだったが、播州赤穂駅も何もない。結論から言ってしまえば、赤穂線自体、何もないところを走っているといっても過言ではない。拾えば少しはネタもあるのだが、それは次の機会に譲るとして、とにかく静かだ。駅前から播州赤穂城へと続くメインストリートは歩道の幅も広く、お城下のイメージを作るためか道路 |
に面した建物すべてが白壁と瓦屋根。街道をイメージさせる松が植樹され、それらしい雰囲気を醸し出している。 もっとも企画そのものがはまったというより、とにかく人がいなくて静かであること、周囲に高層建築がなく、屋根のむこうの空が実に広々としていることが江戸の昔を思わせているというのが真相だ。筆者はこの街の静けさが気にいった。 赤穂城蹟は再整備中のようだ。これが、またいいのである。天守閣など大仰な再建造物がなく、堀割と土塁の多い光景は、妙に砦チックでリアルだ。再整備、造成中の光景も城塞の築城過程を垣間見ているようでこれまた筆者のツボにはまってしまった。幼少時、造成中のジャリ山や盛り土で仲間と日が暮れるまでうち興じた戦争ごっこを思い出す。男の子はこうでなくちゃあいかんな。 城跡内に大石神社があり、参道には四十七士の石造が並ぶ。駅への途中、朽ちかけたような商店街の奥に浅野家の菩提寺である花岳寺がある。ここも静かだ。ここには四十七士の木造がある。 ひとつだけ、鄙に似合わぬイタリアンの店が気を引いた。ピッツアが美味しそうだ。しかもこの店だけは店の外に若干の席待ちがいる。ここはいけるぞきっと。筆者の勘がびんびん働いている。でも寿司を食べてしまいました。ごめんなさい。 |
| 「生とは天の我を労するなり。死とは天のすなわち我を安んずるなり」 高杉晋作の言である。人生は、天が自分に命じた主題を達成するためにある。死とはその主題を達成した自分に天が与えてくれた休息なのだと言う。人生に主題を見つけることができれば、その生はその長短を問わず充実したものになるのだろうか。多くの人は生きるがための生を送り、自らの人生の主題、天が我に課した役割の何たるかを知らずにその生をまっとうする。筆者もまたその他大勢の人生を歩んでいるから高杉28年の人生に限りない憧憬を覚えるのである。 彼が見つけたその生涯における主題は、師、吉田松陰の遺志の継承であった。すなわち『倒幕』この一字につきる。 人生の主題とは実は非常にシンプルなものなのだろう。人生が収斂していく目標として一瞬の光輝がそこにまたたいている。そのようなものかもしれない。 すでに高杉よりも年長になってしまった筆者だが、どうにも彼を身近に感じたいときがある。筆者にとって最も高杉に近づける土地が長府である。長府藩5万石。長州の支藩である。 長府は下関から車で15分程度。関門海峡ぞいを東進する。途中から細い街道筋に入ると攻山寺 |
がある。長府藩毛利家の菩提寺である。 禁門の政変による7卿落ちのあと、5卿がこの攻山寺に落剥の身を寄せていた。長州藩内は保守派が実権を握り、急進派は弾圧され、奇兵隊をはじめとする諸隊も藩からの解散命令を待つのみという危うい時期に、高杉はひとりでクーデターを起こす。誰の目から見ても無謀としか思えないその挙兵につきあった諸隊の隊長は、伊藤俊輔ただひとり、彼の率いる力士隊30名だけが後に長州藩の藩論を180度展開させることになる攻山寺クーデターの実兵力だった。 高杉は挙兵に先立って、5卿に挨拶にゆく。雪に白く化粧された攻山寺を馬上、高杉が往く。5卿を前に彼が叫んだ言葉が「これから長州男児の肝っ玉をごらんにいれます!」 長州という国土を他の誰よりも愛しぬき、『他藩頼むに及ばず』という長州至上主義者の高杉の面目躍如たる光景である。 高杉に会いに行くとしたら、筆者にとってはこの攻山寺しかないのである。 早暁の攻山寺は静寂に支配されている。わずかばかりの石段の先に二重の櫓がかかり、境内には挙兵時の高杉の像がある。高杉が筆者に語りかける言葉は一言だ。 「執着は捨てな」 |

鹿児島行(疾風怒涛編) →→→→→back 鹿児島行1 2 3(疾風怒涛編) 4 5 6 7
| 同一エリアに空港はふたつもいらない。関空と伊丹では明らかに供給過多だ。伊丹一個でいいんだ、空港は。 3月5日金曜日、その日鹿児島で羽田から来る要人を迎えることになった。筆者は大阪から鹿児島入りする。先着し13時半にお迎え後、市内某所のイベント会場へ15時半前に入る予定であった。 大阪発9時15分の便を特割7で購入したのが間違いのもと、2週間も前に予約した内容を完全に失念。ろくにチケットを確認もせず伊丹でチェックインしようとした。すると、あろうことか機械が「ペッ」とチケットを吐き出すではないか。係りの女性がチケットを見て断言した。 「お客様、これは関空からの便です」 案内カウンターに飛びついた。 「次の便は?」「満席です」「その次は?」「満席です」「キャンセル待ちは14番目の登録になります」「うおおおおおお!まずかですばい!」 バッグからポケット時刻表を取り出し(なぜか携行しているのである。エライ!)宮崎から薩摩入りだ。「宮崎行きは?」「満席です」「うおおおお!どぎゃんするとですかあ」「熊本は?」「10時15分発のJASが30席ほど空いています」「それください」「JASのカウンターへお願いします」ここはANAであった。 |
JASへ飛び込む筆者。熊本空港から熊本駅まで車で50分。西鹿児島行の特急「つばめ9号」が12時22分に熊本駅を出る。エアの着は11時20分。なんとかなる。すでに要人との13時半の待ち合わせは無理である。熊本・西鹿児島間は特急で2時間半。西鹿児島着が14時52分だもの。要人に連絡をとり、目的地とのつなぎをつけ現地で合流することにする。要人にはひとりで現地に向かってもらう(要人だろ、おい) やはり、というかエアは遅れる。熊本着11時30分。ターミナルビルを11時40分に出た。バスなどに乗ってはいられない。タクシーを捕まえる。 「運転手さん12時22分のつばめに乗せて!」 飛ばす飛ばす。右に左に急激な車線変更。後部座席の上部手すりにしがみつき振り回される筆者。市内渋滞もあったのに35分で熊本駅着。間に合った!でも、このあとは2時間半なんだわな。 15日土曜日開業の九州新幹線が試乗会をしているらしい。12万人が応募して2万人ほどが当選したそうな。在来線特急「つばめ9号」が出水駅に停車する直前、試乗会の800系つばめがあっと言う間に抜き去っていった。奴は35分で西鹿児島に着く。早い早い早いぞお夢の新幹線。くそお!あと8日遅かったら!歯噛みする筆者であった。 現地3時5分着。何事もなし。本当か? |
| 精神が昂ずる気配を看取するときがある。 昂じきってしまったら、もう四つ相撲だろう。今さら待ったをかけて引く事はできない。危険を感じたら、早めの手当が肝心だ。 客観的な視点を持ちたくなるときでもいい。日常という引力圏内では、持ち得ない絶対的他力の視点を欲するときだ。俺って浄土門徒?まあ、日常から逃げ出すと言い換えてもいい。 どこまで離れれば、沸き立つ精神の血管に満ちた酒精分を沈めることができるのか。 ローカル線ではなく、西にむかう新幹線に乗っていることが、酔いの強さを示している。ここではない遠くへという思いが強いのだ。 オフィスを出たまま飛び乗ったのでスーツ姿のせいもあろうが、なかなかに精神のリズムが静まらない。本を読み、MDを耳に流し始めて1時間。やっと沈殿物は精神の底に着床し、上澄みが透き通りはじめた。求めていた静かなリズムが体を満たしつつある。列車は福山を発ち、新尾道を通過していた。 (かかったな、大夫)時間による鎮静効果か、あるいは距離によってもたらされる安堵感か。夜のしじまを新幹線はひた走る。 目的地は決めていない。博多終点までの切符を持っている。今日はどこで降りてもいいのだ。 |
山陽新幹線はトンネルが多い。瀬戸内という巨大な内海に接しながら走る山陽本線と違い、高速設計の直線指向は車窓というソフトを犠牲にして時間というハードを追求している。ために内陸を、中国山地の内臓を喰い破るように突き抜けてゆく。トンネルを抜けても夜なのでいずれにせよ車窓は退屈だ。 広島着。中国地方最大の都市はやはり洲の街だ。水面に揺れる街の灯りが思いのほか多い。そして広闊だ。 列車は新岩国を通過する。20年近く昔、柳井に寄って岩国を訪れたことがあった。夜の車窓は思いもしない古傷を抉り出すことがある。いてて。 徳山はコンビナートの街だ。昼の車窓が映し出すその圧倒的な画は、映画「エイリアン」の骨格のようだ。大友克彦氏の「メモリーズ」に出てくる大砲の町のシーンにも似ている。加古川あたりでも感じるものがあるけど。 次は新山口だ。在来線で山口に行ける。長州藩の山口政治堂があった土地だ。すでにどこで降りてもいい状態なのだが、新山口はパス。厚狭、新下関を通過。次は、小倉に停車だ。そうか、以前と同じだな。高杉に会っていこう。 手早く身支度を整えてそそくさと小倉で下車をした筆者であった。 |
| 午後8時半だというのに、市営の長岡市民ホールに人影が絶えない。ホールには市内はもとより、県内各地さらには隣接県富山の高岡、氷見の観光案内のカタログまでもが揃っている。インターネット閲覧用のパソコンが置かれ、地域物産の案内がゆったりとした空間に展開されている。この市民ホールは、朝9時から夜9時まで営業している。ここまで市民や観光客に好意的な行政サービスを、筆者は寡聞にして他に知らない。 ちょっと嬉しくなった。長岡という街のひとつの景色なのだろう。 雪国である。 戊辰の役と第二次大戦という2度の戦火によって灰塵に帰した街でもある。河合継之介、小林虎三郎、山本五十六など有為の人材を輩出する街でもある。日本最大の花火の祭典、長岡大花火大会に戊辰の盟友、ともに辛酸をなめた会津の人々を招く土地でもある。筆者はどうにも、この土地を好もしく思う気持ちをおさえきれない。 冒頭に記した行政サービスなど、移転したイトーヨーカドーの空きビルに入居して運営されている。建物は、スーパーのときのままでほとんど手が入れられていない。簡易パーティションによって仕切られてはいるが、内装に金をかけていないのが明瞭だ。公共施設が着実な経営的視点で営ま |
れている。公僕が質朴を旨とした武士の倫理を失っていないような気がする。 小林虎三郎の「米百俵」は小泉総理の登場と共に人口に膾炙した。この小林虎三郎、佐久間象山門下の二虎と言われていたらしい。二虎のひとりは吉田松陰だ。ありゃりゃ、知り合いの知り合いということで途端に好感度アップだ。 河井継之介が主導した戊辰の役の後、救援米を、困窮する旧家臣団へは支給せず、教育投資に援用してしまった話は「教育こそ国家百年の計」と言ったホーチミンを彷彿させる。おそらく戦いたくはなかったであろう継之介も、越後長岡をスイスのような武装中立国にする夢を追って藩経営に手腕を発揮していた。その才覚は同時期の大久保利通を凌いでいたふしがある。大久保が国家経営に識見を発揮するのは明治も数年を経た欧米歴訪の後の話だ。幕末動乱の少し前、すでに河合は備中松山藩家老、山田方谷のもとで国家経営のノウハウを自得している。傲岸不遜な河合が方谷のもとを辞すとき、土下座をしてその恩に謝した話は筆者の好きな情景のひとつだ。 長岡は思いのほか近代的な街だったが、人士の精神性までは、近代の塵埃にまみれてはいないような気配を感じる。贔屓のひきたおしかもしれないが、そのことがなぜか、なによりも嬉しい。 |



| 散策が楽しい街は概して低層だ。視界を遮る城壁のような近代的ビル群はない方が良い。土地固有のそれらしい佇まいの中に老舗の店舗が並んでいてこそ、街歩きは愉しい。店舗がビル群に収納されてしまうと店をみつけられない。京都が建築物に高度制限を設けているのは高い見識だ。 そして街の規模。巨大都市では人は都市に隷属する。人が集い街を成すのではなく、人が都市という巨大な入れ物に放り込まれる内容物と化してしまう。内容物には意思も個性も不要であろう。消費することだけが課せられ、人は都市の中で消費し続け、やがて都市に消化されてゆく。これでは本末転倒だ。街には適性規模がある。徒歩で歩き回って1日~2日。それで大概のところは把握できるか、その目処が立つ程度の規模がいい。 門司港は半日もあればよさそうだ。 ただし、個々の構成要素、商店や飲食店、見所などは消化しきれない。これはひとつひとつ時間をかけて自家薬籠中のものとしなければならないが、それは旅人の活動領域ではない。生活者の領域だ。旅人は所詮、その土地の表面を概括的に撫でていくに過ぎない。過ぎないながら、そのわずかな接触においてすら印象は形成される。 門司港は非常に楽しい街だ。 アーケードの商店街も楽しい。そば打ち研究会 |
とは何だ?店ではないのか。「テキにカツ」との看板のむこうに平和食堂がある。「大衆むけ」と書いてある。地たこ焼「たこ膳」そそられるなあ。路地がまたいい。折れ曲がる寸前に支那そば屋の看板が旅人をさらにその先の見えない空間へと誘っている。バナナの叩き売り発祥の地とは、それをどう評価させたいのか。理解しようとすれば途方に暮れるが、ただただ楽しいのである。理屈ではなく、感性が喜んでいる。 JRの駅舎は、ローマのテルミニ駅を模して建てられた。大正3年のことだ。同じ年、東京では赤レンガの東京駅が産声をあげている。ホームを木造の屋根が覆っている。筆者の小学生時代の校舎と体育館を結ぶ渡り廊下のような造りだ。 駅を出れば、目の前が関門海峡。赤間関とも言い、馬関とも言う。関門橋がわずかに霞みながら短い海峡にまたがっている。景色そのものが絵巻物の中のそれのように奇妙に非現実的だ。 その門司港から対岸の下関唐戸港までは270円、5分程度の船旅だ。船と言ってもバス代わりの渡し舟のようなものだが、これがなかなかどうしてスピード感がある。波荒い馬関を波しぶきをあげ、上下にバウンドしながら疾駆する。 あっと言う間に下関に上陸。関門はひとつのエリアだと気付かされた。 |



| その日の小倉はいつもと違っていたのかもしれない。いつもがわからないので推測だが。 夜の10時半だと言うのに、駅そばのバス停にたむろする人の数が多すぎる。そもそもこんな時間でもバスが走っているのが不思議だ。 その駅前に伊勢丹がある。この時間でも店内は明るい。もちろん閉店しているが、従業員が後片付けをしているのが外からも伺える。煌煌としたその耀きが小倉の夜を明るく彩っている。 この一種高揚した夜半の景色の謎は、翌日解けた。伊勢丹の開店日だったのだ、小倉の。 そごう閉店後、実に3年ぶりの大型百貨店の出店らしく、平日火曜日の開店にもかかわらず予想より2万人多い14万人が訪れたそうだ。初日の売上は2億6千万。 筆者は、その日の夜、小倉を訪れたというわけだ。開店初日の店じまいにでくわしたのだ。 小倉駅の造りは面白い。近未来の風情がある。 在来線と新幹線の改札を出ると、大きな吹き抜けのようなドームをいただくエントランスが広がる。その駅ビル構内から何の遮蔽物もなく、すぐ間近の頭上にモノレールが停車している。サンダーバード基地のようなイメージだ。 モノレールなので発着が実に静かだ。軽いモーター音とともに、まさに発進という感じでモノレ |
ールが小倉駅からヌッと顔を出す。駅間が短い。始発のモノレール小倉駅から2百メートルもいかずに平和通駅がある。3駅目の旦過駅との距離はさらに短い。 夜の繁華街は、このモノレール平和通駅付近を東西に走る幾筋かの通りぞいに広がっている。 モノレールの百メートルほど西側を紫川が流れている。 この川端の整備はかなり徹底されている。 橋の欄干には、スピーカーがしこまれているらしい。ヒーリング系の音響が欄干から鳴り響く。付近には中華レストランやNHK、芸術劇場などがデザイナーズ系の建築物らしい佇まいを川面に映している。 北九州市役所と市議会棟がガラス張りのその全面に南蛮破風の小倉城を映し出す。 美しいと言っていい光景だ。 なぜか、平成ガメラシリーズの天王洲アイルに写る東京タワーの崩壊シーンを思い浮かべてしまう。ごめんなさい。 小倉城は高杉晋作の生涯をしめくくる最後の舞台となった。細川忠興の作ったこの城の落城が彼への追悼の碑であった。高杉びいきの筆者にとっては敵の城となるのだが、仇ながらも、この城は美しい。 |
| 福知山には、京都から山陰本線、大阪から福知山線というふたつの進攻ルートがある。攻めてどうする。 保津峡をまわる山陰本線ルートは途中、亀岡を通る。丹波平定の明智光秀を偲ぶルートとしてはこちらがオススメ。福知山線は大阪を出て尼崎から北上を開始する。宝塚を越え、三田(さんだ)を過ぎれば沿線は中央線の大月近辺のような山峡の気配が満ちてくる。平地に構える農家の作りが皆立派だ。石垣を組み、幾棟かの家屋が廊で結ばれている。豊かなのか?丹波の国。古くからの土豪が割拠し、治めづらそうな気配が満ち満ちている。大変だったろう光秀。 福知山には昼過ぎに到着。 福知山城は由良川のそば、小高い丘の上にある。光秀の主城は近江坂本城だ。丹波攻略を信長に命ぜられ、その侵略拠点となったのが丹波亀山城(今の亀岡)。福知山城は制圧後の占領政策の拠点。光秀がそこに居たわけではない。ちなみに本能寺に進発したのは亀山城からだった。 城を美しく見せるポイントが見つけられない。何かしら建物が邪魔をするか、転落防止用のフェンスや電線がファインダー内に写りこんでしまう。土師川ぞいの公園からのアングルは、石垣を含めた天守の最も映える角度にはならない。この |
一事でだいたい街の意志が知れた。 市内はさほど広くない。幹線をはずれれば、道筋も狭い。その割に車の往来がその狭い道筋で活発だ。少し荒っぽくさえ見えるハンドルさばきで車が走り抜けてゆく。 古刹が幾つかと明智家の軍法書などがおさめられている御霊神社などがあるが、どれも明智光秀の威徳を偲ぶ、という気配は感じられない。街が観光誘致に積極的な様子はなく、丹波と丹後の交通の要衝としてしかレーゾンデートルを持つつもりはなさそうだ。福知山は、山陰本線と福知山線、丹後半島を巡る北近畿タンゴ鉄道のジャンクションとして機能する。それだけのことらしい。 市内を流れる由良川は古来、氾濫を繰り返し、その治水に手を焼いたとのこと。「二十八災(にじゅうはっさい)」と呼ばれる昭和28年の堤防決壊は、台風13号によってもたらされ、ために街が水没してしまったそうだ。地方の災害は、鳥取の大火事、新潟の三八豪雪など地元では歴史に名を残すものでも、都会人は意外と知らない。知ってどうする、ということもあるが、訪問した土地の地理的環境と歴史ぐらいは知っておくべきことだろう。勿論、食べ物の方が優先順位は高い。福知山には食欲中枢を刺激する物件がなさそうだ。和田山経由播但線で姫路に出て帰ろう。 |
| テレビに照葉樹林が映し出され、歩道釣り橋としては世界一の高さという照葉大吊橋が筆者の旅心をくすぐった。 「照葉樹林」という言葉がすでにジャストフィットだ。明るそうな感じがする。針葉樹林よりも500ルクスは明るそうだ。筆者は暗っちいのが嫌いだ。まあ、少しは影があったほうがいいとも思うが、やはり陰より陽。冬より夏だ。 「どこだ?ここは」 宮崎だった。 なんと、筆者は宮崎をまったく消費していなかったことを痛感させられた。 行ったことはあるんだよ。でもそれだけ。 たまにあるんだ。基礎知識なしに街へ繰り出して、印象を深める何ものかにめぐり合わないまま土地を離れてしまうことが。基本的には気持ちが入らないまま現地についちゃったときが多い。筆者の宮崎行がそれだった。失敗したなあ。 筆者の印象では宮崎は「日向ぼっこな街」。呑気が市民権を得ている。あきらかに主流だ、呑気が。殖産興業だとか、街おこしといった、ひたむきさはここでは「人生の浪費」そんなことしてどうなるのよ、といったポリネシアンな空気がたゆたっている。気張らなくていい、という勅許がおりている。誰から? |
つい数十年前まで熱海と並んで新婚旅行のメッカであったというのが、信じられない。NHKの「映像の世紀」ででも流してくれんもんだろうか。『ホームでの万歳三唱、「新婚」と大書された車窓に貼られる辱めの紙片』など、いやもう今思い出しても顔が赤らむような時代があったのだ(筆者は関係ない。幼少時のニュース映像の記憶である。念のため)あの頃、新婚さんは、ここで何をしていたのだろう。あ、野暮な疑問か。撤回、撤回。それにしてものどかだなああ。 フェニックスが揺れている。南国ムードを演出するためのベタな道具として各市町村でかなり重宝されている、このフェニックス。筆者の地元、大阪でも植わっているが、あれは何か寒い。抜いてしまったらどうだろう。 さすがに宮崎にフェニックスはよく似合う。 結局、駅前の大通りを歩き、寿屋だの山形屋だの地元資本の百貨店をものめずらしげに眺めただけが滞在記録だからなあ。 日向地鶏のチキン南蛮、日向夏、甘めの醤油で刺身、冷汁、宮崎駅の駅弁「しいたけ飯」、麦焼酎。綾町の照葉樹林に高千穂峡、考えれば遊び道具には事欠かないではないか。 宮崎もう一回ちゃんと消費することにしよう。 |
| 旅先でのちょっとした楽しみのひとつに天気予報鑑賞がある。いや、別に気圧配置とか注意報、警報に興味があるわけではない。 その土地固有の地域区分名が耳に新しいことが多いんである。これが思いのほか楽しい。現地密着・現場主義といった言葉が浮かぶ。社会化では習わなかった新知識、それも実学系。どのような実益が伴うのかはわからないが、使い道のはっきりしないお役立ち感だけは濃厚である。いつの間にかたまってゆく一方の百貨店やブランド店の手提げ袋にも似ている。 例えば福井県の地域区分は2分割で「嶺北・嶺南」である。「嶺北」は福井を中心とし、「嶺南」は敦賀が代表となっている。 もちろん、47都道府県すべてがこのようにその地域個有の名称を使っているわけではない。「北部」だ「南部」だ「東部」だ「西部」だ、で済ましている方が多数派だ。 前置きが長くなってしまったが、福島の県内区分は太平洋岸から内陸にむかって3区に分けられている。浜通り・中通り・会津だ。郡山は中通りにある。 何がある街というわけでもないが、福島と並び交通の要衝だ。すいません、あんまり気持ちの入っていない紹介で。しかし、駅を出た瞬間に「や |
っちまった」と思える処です。 明らかに近代に入ってからイケイケで大きくなった街という感じ。だから歴史を感じさせない。歴史があればいいのかってこともあるが、都会的なものは見飽きているし、あるいは何か個性があればいいのだが、残念ながらそこのところも希薄のようだ。 要のところをしっかりおさえずに箱物だけ大都市を真似ようとした地に足がつかないおぼつかなさが漂っている。都会ではなくて都会っぽい地方都市感が漂っている。筆者の経験では、このタイプの街は周辺の高校生がバイクや改造車に乗ってジャージ姿でたむろしにくることが多い。実際は知らんけど。 しかし福島は酒どころ。 その日の宿の前に「木綿の家(分店)」という居酒屋があった。店内は福島の地酒オンパレードだ。栄仙(えいせん)と国権(こっけん)を呑みまくる。きわめていい状態になった。郡山万歳! あれから10年を経て、阿佐ヶ谷にある、居酒屋のマスターがこの「木綿の家」にいたことがあると聞き世間の狭さに驚いた。 さて、ここで質問です。青森県の区分名称(3区)愛媛県の区分名称(3区)を答えなさい。答えはCMのあとで。ってここをクリックしてね。 |
| 東京大阪間の移動は新幹線と航空機のどちらが有利か。今回はそこのところの白黒をきっちりとつけることにする。誰に頼まれた訳でもないのだがニーズは高いと踏んだ。あるのか?ニーズ。 さて、レース区間は筆者の職場がある梅田から品川までということで。 14時25分に梅田を出た。 新幹線、新大阪駅までは地下鉄御堂筋線あるいはJRを使う。職場前からタクシーをつかまえるのが最も早い。オフィスを出て15分後に新幹線に飛び乗ったことのある筆者だが、今回は鉄道を使おうとタクシーを使おうと、乗車する新幹線は14時53分発「のぞみ18号」しかありえない。品川着は17時22分だ。この時刻を胸に刻んで筆者は空路で東京へ。 伊丹へ向かうため、阪急宝塚線の急行14時40分に乗車。13分をかけて蛍ケ池着。モノレールに乗り換え1駅で伊丹だ。 15時10分には伊丹空港ゲート内に到着。搭乗手続きを済ます。同時刻、新幹線は京都を発っている。 15時30分発のJAL118便。フライト時間は47分程度。楽勝だ。 15時45分テイクオフ。同時刻、新幹線は名古屋に到着。搭乗手続きとタキシング(地上滑走 |
)に思いのほか時間を取られるのがエアのネックだ。しかし、一端テイクオフしてしまえばこちらのもの。あっと言う間に名古屋上空を通過。伊豆半島をつっきり、大島上空を通過。あとは羽田まで80キロ。一直線だ・・・「?」あれ?東京湾を横に見ながら房総半島を横断しちまった。80キロの目的地表示がまったくカウントダウンしない。やがて機は大きく左バンクしてUターンするように羽田へランディング。羽田は広い。タキシングが長い。ボーディングブリッジが繋がり機を後にしたのは16時45分。 羽田から都心へのアクセスはエアポートバスか京急かモノレールだ。夕刻の都心の渋滞を考えれば車はあり得ない。浜松町まで24分のモノレールよりも品川にとまる京急の方がいい。京急は羽田-品川間14分(快特)だが乗れたことが無い!いつ走っているんだ!快速特急! 京急の急行で品川まで20分弱。 品川着17時15分。へ? 「のぞみ18号」の品川着17時22分。なんとその差わずかに7分。なんだかなあ。 料金はエアがE割で16,650円。特割で13,400円。新幹線はグリーンで18,640円、指定で13,750円。さあ、あなたならどっち? |
金沢行4(食い編1/4) →→→back 金沢行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
| 心を亡くすと書いて「忙」。 いつ果てるとも知れぬ忙しさは、しかし自らの心が創り上げているときが多い。気持ちにゆとりがなくなるのだな。だから「忙」。 心を取り戻すために金沢に向かった。先般、またしても鳥取で蟹を食いそびれた仇を今回も再び金沢で討つのだ。わははははは。 気がかりなのは食生活を改善した筆者の胃袋。飲食を規則正しい少量摂取に切り換えたため、かなり小振りになってしまった。2泊の間、昼夜朝昼夜という5食だけのチャンスを十分に活かしきれるのだろうか。 12月6日土曜日昼、入沢。 駅構内に旧駅舎時代からあるおでん「黒百合」で「おでん定食」を食す。680円。ここのつみれの旨さときたら・・・。固めの豆腐とちくわなど気取らぬ具材が抜群の塩梅のだしに身を委ねている。店内も気取らぬ民芸調で、広々とした造りが居心地の良さを助長させる。 常宿の金沢ニューグランドホテルに荷を預け、近江町市場へ散策。あいかわらず、あちこちの店が行列だらけだ。ここでものを食べるのは運と根気が必要だ。「さわいのパン」で「ばくだん」と「ヨーグルト風味のバターパン」「茹でキャベツ入りドック」を購入。コロッケ販売所の「タココ |
ロッケ」と「かにクリームコロッケ」「甘えびコロッケ」を携えて片町へ散策の足を伸ばす。 洋食屋「宇宙軒」はビルの合間を縫うようにして入る。戦後蒲田の闇市のようだ知らないけど。食品サンプルは干からびて外縁部がめくれあがっている。ひとことで言えば、ボロい。「豚(とん)バラ定食」を注文。600円也。店内には「目標!豚(とん)バラ定食1日500食」とある。18席程度のカウンターがぐるりと取り囲んだ厨房の中央に何でもこなせそうな鉄板で親爺がジュージューとバラ肉を焼いている。トンバラは、つけダレが実に微妙な味わいだ。甘からず辛からず、味噌も入っていると聞くが、とてもとてもそれだけの味ではない。「ダブル」で頼んでおけばよかった。ダブルは肉が倍で1000円也。 ホテルでしばし休憩。小腹がすいたので「ばくだん」と「カニクリームコロッケ」をつまむ。ばくだんは甘味のある揚げパン生地の中に茹で卵が入った一品だ。カニクリームコロッケの中のカニは量がたっぷり。カニ肉をこんなに感じられるコロッケを筆者は他に知らない。 夜、片町の乙女寿司に向かう。今回の金沢行主役の一翼だ。片町の奥、こんなところに、という奥まったところに乙女寿司はひっそりと佇んでいる。この続きは次号へ。 |
金沢行5(食い編2/4) →→→back 金沢行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
| 乙女寿司の夜。 お造りとあてをお任せで頼む。ビールで舌をしめらせて日本酒は菊姫からスタート。 次々とカウンターに繰り出されるお造りはどれも絶品。ぶり・ひらめ・ばい貝・あまえびをつまんでゆく。ぶりは脂がとろけるようだ。マグロと違いしつこさがない。あまえびは極上ものが入ったそうで、これも子と一緒にぱくっ。あまっ!うまっ! 「コウバコ」が供された。内子も外子もかにみそも足の身肉と一緒に小振りな甲羅の中にぎっしりと詰まっている。かに酢で食べる。旨すぎっ!全部きれいに食べたあと、甲羅に「立山」を注いで熱燗にする。嗚呼、癒されるなあ。 「白子のすり流し」は中ぶりの猪口で呑む。白子のポタージュスープのようだ。これまたガツンときた。 「あんきも」を能登の塩につけて食べる。この塩が舌の両端に反応するときの絶妙の味わいが堪らない。酒はすでに菊姫から手取川に変わっている。いよいよ握りだ。1カンづつタイミングを見計らって出される身の引き締まるような清々しい寿司をどう表現すればいいのだろうか。 酒は手取川から吉野川に移った。 しめさば・たいのこぶ〆・ぶり・こはだ・あな |
ご・かに・うに・万寿貝・あかいか・甘えび。夏が最盛期のあかいかがまだ獲れているとのこと。水温が暖かいのだ。暖冬のおかげで、ブリとあかいかの両方が食べられる。あなごは煮つめを使わず、塩とすだちで。あかいかも塩と柚子。ぶりにいたってはあまりの旨さにもう一カン握ってもらってしまった。万寿貝の磯くささもたまらない。 万寿貝のひもやその他を貝焼きで出される。醤油のこおばしさと塩っけが酒を進ませる。 あらの味噌汁で締めくくり、店を出る。 ホテルに帰る途上、おでん「赤玉本店」を探すも不本意ながら、見つからなかった。どうやら南北と東西の道筋を逆に覚えていたらしい。って、まだ食うつもりだったのか? はい。 やむなくホテル最上階のバー「ディヒテル」でカクテルをオーダー。 雪国とスレッジハンマー、バラライカを頼む。レーズンバターとフルーツをつまみにグレンリベットのダブルをミストで締めくくる。4杯目もウォッカ系の心積もりでいたバーテンダー氏の意表をつく攻撃で1日目を無事、終了。 夜半「茹でキャベツ入りドック」と「甘えびコロッケ」を食べた奴がいる。朝、目覚めたときに無くなっていた。誰だ?勝手に食ったのは?! |
金沢行6(食い編3/4) →→→back 金沢行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
| 12月7日日曜日。 「タココロッケ」と「バターパン」で朝食を済まし、10時に外出。昨日来の雨降りやまず。気温も10℃下がって最高気温7度の予報。強風と波浪、雷などの注意報、警報が出ている。傘を広げてもあまり役立たぬ。 香林坊を折れ、兼六園下へ。濡れ落ち葉を踏みしめつつ広坂を登る。辰已用水沿いの小立野(おだつの)通りを直進すれば、金沢大学医学部付属病院前、おでん「若葉」を通り過ぎる。途中、右折すれば「千取寿し」があるはずだ。しかし今日の目標は金沢洋食の双璧「ニュー狸」だ。双璧の一翼は東の廓にある「自由軒」。 小立野3丁目にあるはずの店が見つからない。住所の石引1丁目の1だけが頭に残り、小立野1丁目であったかとそのまま直進する。が、さすがに様子がおかしい。いっかな店が現れない。さすがに通りすがりの人に聞いてみた。やはり通り過ぎていた!逆進。目印はスーパー「マルエイ」だと言う。確かにスーパーはあったが、見落としていたか?ああ、ありました!これは店のイメージが違いすぎる。看板は頭上遥かな高さにそびえ、道路に少し奥まった瀟洒な造りのガラス張りの建物は、当方の勝手なボロイメージ、白い看板にそっけない赤文字の店名などとはまったくかけはな |
れた物件です。 オーダーは「サーモンステーキ」と「ヤキメシ」。サーモンステーキはカリカリの表面と柔らかな身、レモンの香りをのせたバターとステーキソースの絶妙なマッチング。添え物のポテトとタマネギもヴォリューム感をいや増す。こげ茶色の「ヤキメシ」も面白い。ソースやきそばのような色あいに食欲が昂進する。別にソース焼きそばの味がするわけではない。スープはコンソメのようだが、ネギがのっている。洋食なんだなやっぱり。しめて2300円。 帰路も徒歩。さすがに少し足にきている。途中、兼六園の広坂休憩所の談話室にて休む。金沢第九師団長の官舎を利用した休憩所は古い洋風建築の佇まい。ゆったりとしたソファーにひとり腰掛け、15平米ほどの談話室を占拠して雑誌「金沢」のバックナンバーを何冊も広げて時が過ぎる。途中、固辞したのだが館員の女性がストーブをつけてくれた。室内に暖気が満ち、なおいっそうの寛ぎに浸された。席を立ち部屋を出るとき管理室を覗く。先ほどの女性館員の姿はない。交代したのか男性館員がひとり。顛末を話し、礼を言いストーブを止めてもらうよう頼んで休憩所を後にする。いつもなら、そのままいなくなってしまうだろう。金沢効果だな。 |

 天徳院(左)と広坂休憩所(右)
天徳院(左)と広坂休憩所(右)
金沢行7(食い編4/4) →→→back 金沢行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
| 夜、寒月が白々と浮かぶ。吐く息も白い。身が引き締まるような寒気だ。冬が来た。 雨や霰(あられ)が時折激しく道をたたく。 おめあては勿論「つる幸」だ。 まずは「なますの酢の物・あんきも・白子」表面を炙った白子はゆず皮の器に入っている。 「ひしこの羽二重蒸し」はなまこの卵巣の干物「ひしこ」の茶碗蒸だ。表面に細かくきざんだみょうがの食感と味覚が愉しい。 「あまだいのみぞれ煮」みずみずしいアマダイの身がほくほくだ。 「お造り」はカニとフグ、甘えび、フグ皮の湯引き。そうだ!今回は「カニを食べたい」と伝えてあったのだ。 「ぶりトロのにぎり2カン」寒ブリは今や筆者の魚ランキングでマグロを抜いた。 「本鴨の炭火焼とネギ焼き」 途中、茶会から帰ってきた大女将の挨拶をうける。以前、京都の修行時代の話を伺ったことがある。当時、365日のうち休みは正月の3が日だけだったそうだ。ご主人の河田三郎氏が金沢に店を出したのは1965年。筆者は山口瞳氏のエッセイでこの店の存在を知った。すでに若主人の代になっていたが、先代もたまに板場に立つときもあるらしい。偶然、その日に居合わせたとき「今 |
日は大旦那様が板場に立たれているんです」という仲居さんの眼には「どうだ」という自信があふれていた。 「コウバコと越前蟹」コウバコにぎっしりと詰め込まれた内子と外子、そしてカニ足。みそは蟹肉と和えて別に盛り上げている。この2日で鳥取の仇は十分に果たした。 「あわびのステーキ」「かぶら寿し」一切れ「カニ雑炊」カニづくしだあ。これもカニ肉、外子、内子がたっぷりで食いでがある。 「フルーツグラタン」ってこれがまた、どうも、ああた。キウイ・バナナ・いちご・洋ナシ・マンゴーが練乳とソースに浸かって表面をこおばしく炙った?一品。ガツンときた。 勘定を終え、雨と霰が交互に降りしきる外に出る。傘も持たずに見送る仲居さんに挨拶をし、店を離れる。20mほども歩いたろうか、背後で大きな声が聞こえた「ありがとうございましたあ」振り返れば大女将が遠くでお辞儀をしている。ちょうど席をはずしたときに店を出てしまったのだろう。不調法だったな。大女将に挨拶をしてから店を出るべきだった。若干の後悔ともてなしの心に触れた嬉しさとともに深く辞儀を返す。 雨は変わらずに降りしきっている。夜半、雪に変わるのだろうか。 |
| リゾートホテルが苦手なんである。 めっちゃ苦手。 なぜ、ひとりだと泊めてくれないの? なぜ、二人分の料金を提示してくるの? なぜ、二人分の料金を払っているのに食事は1人前なの? なぜ、ホテルなのに畳の部屋なの? 疑問は次々と沸き起こり、尽きることを知らない。 畳の部屋が苦手なんである。 だだっ広い畳の部屋に入ったとき、どこに腰をおろします?筆者はすみっこ。悲しい性である。 ひろ~いスペースのすみっこにいってしまう。ゴキブリ? 裏磐梯の高原ホテルである。猪苗代駅からバス。ここいらへんからして悲しい。リゾートには車で行けよな!オープンカーぢゃなきゃ駄目だ。 時期も悲しい。9月初旬。東北の観光シーズンはひと段落。猪苗代駅の前に猪苗代湖畔駅で降りてみた。ホームは1本。駅舎はなし。 駅前ロータリーのすぐ前が湖畔だ、誰もいないけど。海の家ならぬ湖の家がある、閉まっているけど。秋風が湖面を渡り、誰もいない浜にサザンの歌が寂しく流れる。いたたまれなくなってすぐに引き上げた。 |
裏磐梯は水蒸気爆発で頭頂部が吹き飛んだ磐梯山のまさに爆裂口側だ。周囲には五色沼など散策にはもってこいのリゾートエリア。 筆者の知友M君はリゾートのプロ。ランカウイ島で1週間はボケーっとしていられる。練馬の自宅のリビングより広いバスルームでボケーっとしていられる。筆者にはそれができない。しかもホテルなのにメイドが刑事のように部屋に押し入ってくる。布団はたたまれるわ、掃除のために部屋から追い立てられるわ。これってリゾート? ホテルの従業員も近在から調達するらしく箸が転がってもおかしい年頃の地元の女の子って感じ。食堂(レストランとかダイニングではありませんよ。絶対に食堂)で地酒を頼んだ。何があるのか聞いてみた。 「少々お待ちください」 ぴゅっと奥に引っ込んだかと思うと 「・・・っですってえ・・・」仲間に話しているらしい。嬌声があがる。 「きゃははははははははははは」 ・・・・ぜってえ俺のことだな。 「お待たせしましたあ××でございます」肩が震えている。 そんなに面白いですか?わたしのこと。 3泊4日の滞在は多すぎたな、絶対。 |
徳島・鳥取行 →→→back 鳥取行1 2(砂丘地獄編) 3(徳島鳥取行)
| 行き当たりばったりの無計画な旅は危険だ。久し振りの思いつき旅行は『北陸大返し』以来の不本意の連続。それも旅のだいご味って奴っすか。 高速バスで徳島へ行く。 出発早々、神戸線で事故渋滞。イライラがつのる。車はこれがあるんだ。出発早々暗雲垂れ込める展開。徳島には30分延着。しかし『栄寿司』でモヤモヤを挽回。癒された。オッケイ♪ 翌朝、帰るか足を伸ばすか悩む。こういうことは珍しい。優柔不断な心理状態のまま、とりあえず岡山まで。ホームのベンチでうじうじしていると掲示板に岡山発鳥取行きの『スーパーいなば3号』の表示。これだ!時あたかも11月2日、うまくすれば松葉ガニが食えるかも! 指定席はすでに満席、人気があるのか『スーパーいなば』その人気はつまり「カニ」ってことか。勝手に筋を読む筆者。自由席をラクラク確保。ホテルフロントでのカニ情報はどうも要領を得ない。それでも市中の専門店と鳥取港(加露港)の「海鮮市場かろいち」を教えてもらう。 専門店はすぐそばだ。昼食に間に合うぎりぎりの時間だ。急げ!徒歩5分。店頭に立つ。閉まっている。むっ!看板が出ているぞ。 『かに吉は11月6日から営業します』 解禁日は6日だそうです。今は2日、調べてお |
けよそれくらい! あきらめきれずにタクシーで「海鮮市場かろいち」へ。現着して気がつく。帰りの足となるタクシー乗り場がない。かつて鳥取砂丘でも同様だった。タクシーの運転手がカウンターを止めて待っていてくれるとのこと。助かった。 施設の飲食テナントは行列の嵐。行列のない『カニラーメン』の店に入る。カニがないので今はラーメンのみ。塩ラーメンを下さい。あと、カニチャーハンの小ね。ぼそぼそ。 もはや期待のとっかかりを失っている筆者。したがって安価な割にカニ肉がゴロゴロ入っていたカニチャーハンに、それだけで幸せを感じてしまった。幸福感のデフレ状態。こうなりゃ夜だ。 マスコミうけがするのか、店内にテレビクルーの色紙だらけのお店へ。5~6人でいっぱいになるカウンター席で予約は受けないとのこと。 廉価で旨い寿司がウケの理由らしい。いや、別に廉価でなくともいいから、もうちょっとペース配分に意を払って・・・ああ、お造りを氷の上に乗っけては水っぽくなっちゃうし・・・ちょっと不本意だぞお。 『スーパーはくと』で帰阪。 大阪は雨。筆者の街の筆者の家のある駅出口では傘を売る店すらない。濡れそぼちながら帰宅。 |
| 出雲市を始発とする「スーパーやくも」は松江駅を7時37分に発車する。3月上旬の朝である。車窓が広い。出雲の象徴、伯耆大山が近づいてきた。中腹から雲をまとい山容の把握は難しい。標高1700米、中国地方第一の高峰、霊場としての歴史も古い。 伯耆溝口を過ぎる頃、地面には残雪がはりついていた。松江市内に雪はなかった。列車が中国山地に分け入ると車窓はますます白くなってゆく。雪が残るというより積もっていると言ったほうが実情にあっている。根雨(ねう)駅通過時、ホーム上の雪が除雪されることなく積もるにまかませているのを見た。車窓は完全な雪景色だ。 山襞にそって渓流と伴走するかのように列車は走る。粉雪が舞っている。雪は思いのほか深い。急勾配の屋根から雪が滑り落ちてゆく。その雪の厚さは遠目に見ても30センチはありそうだ。 光り輝く白銀の世界に目が疲れたかうたた寝をした。ふと気がつけば「新見」駅着。驚くべきことに雪が消えかけている。ホーム上にすでに雪はない。それまでの渓谷沿いの峻険な巌を見上げるような沿線風景が山裾の盆地を寛ぎつつ見渡すような優しいアングルに変わっている。線区も明らかに設計思想が違う。地形に合わせて右に左に縫うように走っていた鉄路は、蛇行する渓流と山容 |
を貫くように橋で渡り、トンネルで抜ける。 備中高梁が近い。藩政時代の備中松山だ。お城下の街だ。地名の改称に伴い、松山城は高梁城となった。しかし道路標識は備中松山城となっている。方谷(ほうこく)駅の手前で雪は完全に消えた。方谷、備中松山の藩政改革を成し遂げた家老の名前をとった駅名である。JRで人名の駅は珍しい。幕末の動乱直前、越後の河合継之助が師事した。越後長岡から江戸を経てついには吉備路のこんなところにまで来たかと思える僻村である。 城下からも離れた人里とも思えぬ段々畑の上に墓だか屋敷だか構造物が見えた。山田方谷と由縁のあるものか。なくてもかまわない。いっそ出自もはっきりしないまま筆者がそのように決め付けたとて何の問題もないような、いやむしろそれがふさわしいような土地であり、方谷の人柄である。情報化社会という、もはや他人に対する配慮といった旧世代の資質はスピードという価値基準の前に唾棄すべき旧弊となってしまった今日、人に会いに行くことによってしか情報が伝わらなかった往時に筆者はたまらない温かみを感じる。 とは言いつつも、やっぱり現代人でしかない筆者は、結局鈍行ではなく特急で時代の体温をほのかに残しているかのような備中の集落をまたたく間に車窓の後方に置き捨ててゆくのであった。 |
| あれ、こんなに居心地のいい町だったかな、倉敷は。二十数年ぶりの訪問で筆者はその居心地の良さに戸惑いを隠せない。 なにせ、女子供の町として気恥ずかしい土地AAA格付けだったのだ。言うなれば「るるぶ」な町。御免なさい、とりあえず謝っておこう。 と、いうことで懺悔と禊をすませて、筆者は断言する。癒されたければ倉敷へ行け。 金沢が筆者の心の故郷だとすれば、倉敷は逃避の新天地だ。煮詰まったら倉敷へ。筆者の当面の疲労回復剤として倉敷は認知された。 距離感がまた絶妙だ。大阪から1時間強。岡山まで新幹線で50分、岡山から在来線で3駅。時間的にも金額的にもお手頃、お値打ち。 倉敷は町の広さが実に手頃。広すぎず、狭すぎず。1日もあれば町中は観光できる。と言ってすぐに倦んでしまうほど底は浅くない。軒が連なる狭隘な路地に足を踏み入れると途端に方向感覚が怪しくなる。夜陰、暗い路地の向こうに旅館の行灯だけが浮かんでいる。誘われるように路地に吸い込まれる。どこに繋がっているのだろうか。歩き回るうちにいつの間にか同じ所に舞い戻ってしまう。しかし、徒労感はない。むしろうきうきするように迷路を歩く自分がいる。 町はすべてが小振りでいながら古格である。物 |
持ちの良さが伝わってくる。皆がこの町の風情を大切に取っておこうとしているのがよく分かる。 さらに今回、洋食屋でも満喫。名代とんかつ「かっぱ」とんかつが名物らしいが、ポークステーキとチーズ入りクリームコロッケが当たり。ドミと僅かなケチャップのマッチングが厚手の豚肉に見事に適合。添え物のポテトサラダも絶品だ。 大原美術館のためにできた開業40年の倉敷国際ホテルの入口は、踏み磨かれた黒曜石のような鈍い耀きを放つ。古風なヨーロピアンタイプ。一歩踏み外すと単なるボロさに堕しかねない細部の造りは微妙なバランスで味のある年代物と評することができる。ドアボーイがいなくとも、ボールペンが安物の文具であってもなぜか許せる。空間全体に大きなゆとりがある。それはエントランスはもとより各フロアのそこここに配されたチェアとテーブルによって表現される。ドアノブの位置の高さも外国人観光客の誘致成功を物語っているのである。 町の中央に盛り上がった標高50米にも満たぬ鶴形山が倉敷という町の臍。山中にある阿知神社も倉敷の町そのもののように小振りでいて古格である。早暁、再び散策に訪れた筆者は、境内で静謐な時間を過ごしている。かつて宇和島で得た静けさと同じ時間がここにも流れていた。 |


広島行(その2) →→→back 広島行1 広島行2 広島行3
| 広島城の南に原爆投下の目印にされたT字型の橋、相生橋がある。かなり大きな橋だ。 広島駅前から市電に乗れば猿猴川、京橋川、元安川、本川と次々と川が現れる。本川の西には天満川も流れている。広島は大きな洲なのである。 その洲の中心に原爆ドームがある。広島城から南下すると、予想に反して低層なその姿を川ぞいに見出すことができる。 被爆時、相生橋は爆圧によって上下にバウンドするようにうねり、橋梁のコンクリートはほとんどが剥落した。しかし、橋桁そのものはよくこの惨事に耐え、なんと被爆後35年間も使用された。橋はその後昭和58年に架け替えられた。 原爆ドームから本通に足を踏み入れる。 広島の繁華街は八丁堀を中心とした本通と呼ばれるアーケード街だ。通りの中頃のアンデルセンという洋菓子店の白亜の店舗が目印だ。 広島名物と言えばお好み焼きだが、どうやら広島つけ麺という新勢力も台頭しているらしい。寡聞にして知らなかった。 「麺地鶏」という店に入る。 広島つけ麺の特徴はつけダレにあるようだ。唐辛子を使った辛味が身上。中辛を注文した。最初のうちは何てこともないのだが、後半来るな、辛味が。唐辛子の辛味だから、くちびるが腫れる。 |
麺は丸麺中細直。茹でたキャベツ、ネギ、キュウリ、脂身の少ないチャーシューが乗っている。あり、ということでひとつ。 広島駅ビルの名前は、ASSE。ここの2階に飲食店が並んでいる。それほど大きいわけではないが、駅ビル内であることを忘れさせる活気がある。まるで高架下の屋台の活気だ。麗ちゃん、よっちゃん、ぶんちゃん、お好み焼きの屋号はなぜか「ちゃん」づけ。あ、第2麗ちゃんもある。では、麗ちゃんに入ろう。客席の前はL字型の巨大な鉄板。その鉄板からもうもうと立ち昇る水蒸気。水蒸気の向こうに焼き方がいる。威勢のいいおばちゃん軍団だ。 隣の客が注文を決めかねていると、何やらブツブツ言っている。広島弁の悪態っぽい。無愛想な感じもするが気にならない。キャラなのだろう。 「そば入りは7番から」おばちゃん、ちょっとぶっきらぼう。この軍団の組長らしい。 クレープのように薄い生地だが、しっかりとした弾力がある。キャベツも天かすも肉もえびもいかも、とにかくギュウギュウ押し付ける。ギュウギュウギュウギュウ押し付ける。これでもかと言うくらい押し付けても生地は切れない。 つけ麺とお好みで腹がふくれきった。・・・帰ろう。 |
広島行(その1) →→→back 広島行1 広島行2 広島行3
| 9月下旬、台風15号は紀伊半島をかすめつつ北上、近畿・東海・関東に雨を降らせている。 早朝、社用で泊まった京都を発ち、台風をすり抜けるように広島へ向かった。 京都を発って1時間45分。広島着。大阪からは1時間半といったところだ。東京、名古屋間の1時間40分に比肩する距離だ。 関東者は中国地方の距離感覚に疎い。恥ずかしながら、岡山も広島も神戸のむこう、すぐそばにあると思っていた。 広島駅、新幹線の出口を間違えると反対側にぬける駅コンコースがないので要注意だ。地下道を使わなければならなくなる(広島は地下道が大好きだ。そこかしこで幅広の車道をくぐる地下道網が広がっている) 東海、関東の台風接近が嘘のような青空。雲ひとつない抜けるような秋空が広がっている。台風が夏の名残を連れ去ってしまったのか。風は涼しく、どこか儚い。 街路は広い。駅前大通りなどまるでロスアンゼルスのような斜度と広がりを見せる。市電の繁栄もロスに似ている。行ったことないけどロス。あるいは全国でもっとも市電が活躍している街かもしれないぞ広島市。ひきもきらさず行き交う市電の姿はスターウォーズの国際空港のようだ。いい |
なあ。3両編制なんてのもある。 町名がまた独特だ。ご当地クイズに地名当てがよくあるが、広島なんて駅前からして馬鹿にならない。東京では松濤(しょうとう)大阪では放出(はなてん)あたりが定番だが、どこにあるやら地名の海に沈んでいる。広島の市電なぞ、始発から二つ目、四つ目あたりに「猿猴橋町」「銀山町」「胡町」なんてのが並んでいる。 (えんこうばしちょう)に(かなやまちょう)(えびすまち)と読む。 猿猴の猴も猿の意だ。頼まれもしないのに雑学を押し付けてみました。 松江まで171キロ、三次まで68キロ、道路標識を見ただけで、毛利家の支配が日本海側まで十分に届いていたことが伺える。普通、市内に171キロ先の地名は表示すまい。平家による支配は厳島神社を浮き立たせ、毛利家による支配は、中国9ヶ国、112万石の大封の中心地として中国一の繁華街を形成させた。 「鯉城(りじょう)」は「広島城」の別称である。秀吉に大阪城へ招かれた毛利輝元(元就の孫)は、その城下の反映に肝をつぶし、これにならって居城を吉田郡山城から太田川のほとりに移し、2年を経ずしてこの城を完成させた。この近世城郭は世界で唯一の被爆体験を持つに至る。 |
| キャッチフレーズは大切だ。 岡山はなんとフルーツ王国ときたもんだ。 フルーツ王国ってのもこりゃあ腹に力がこもらない。呼ばれて嬉しいか?フルーツ王国。なぜか知らないが聞いた瞬間『アンパンマン』を思い浮かべた。 しかし筆者はフルーツ王国支持を表明する。いいではないか。フルーツ王国。桃だな、桃。 とりあえず桃が王様。ピーチ姫なんて呼称もあるが、桃太郎もあるしな、男性名詞でゆこう。 清水白桃である。 数ある桃の中でも、岡山の清水白桃は当代一の果実と言っていい。この旨さときたら、もうジュルッ、あ、失礼しました。皮がすぅ~と剥けるのである。一枚、一枚薄絹を脱がせるようにすぅ~とね、剥けちゃう。 これはもはや官能の世界だ。王様だって言い切った舌の根も乾かないうちに官能か、無責任だ。言いっぱなし御免。 清水白桃は、白さをもって上とする。桃色に色づいてちゃいけない。 岡山名産品は、ほかにもマスカットやピオーネなどのぶどう、さらには梨、フルーツ以外でも「ままかり」や吉備団子などの定番メニューを揃えている。桃とマスカット以外は主役をはる器量 |
ではないがそれなりの個性派ぞろいと言える。 岡山は、さらに観光資源にもめぐまれている。駅周辺の市街地に岡山城や後楽園がある。市街地は城下町ということになるが、その面影は微塵もない。駅前から市電をかかえこみながら「桃太郎大通」が東に伸び、その先に岡山城が黒いその姿をのぞかせる。城の袂を流れる旭川をはさんで後楽園が広がる。なかなかに明媚な土地だ。 表町(おもてちょう)商店街というアーケードが東西に伸びている。なぜか飲食店の数が少ないアーケード街だが、ここが消費の中心らしい。 街を歩けば、そここに刀剣の店がある。なるほど備前長船刀鍛治の土地なのだ。 岡山は多彩な顔を隠している。しかも本当に隠してしまっており、あまり認知が進んでいない。 鉄道の要衝で、吉備路、四国路、山陽路、津山路への一大分岐点でもある。新幹線、在来線、吉備線、瀬戸大橋線、津山線が岡山に集線し、少し離れた倉敷や東岡山からはそれぞれ伯備線、赤穂線が散ってゆく。ターミナルの悲しさか、あまりに便利すぎて人が降りないのかもしれない。しかし岡山を拠点にして四方に足を伸ばせばかなり寛いだ旅路を楽しめることなる。 東日本出身の筆者にとって中国地方はどこか縁遠いものだったがこの機会に少し攻めてみるか。 |
| 梅雨は例年より長く、まだ明けていない。 早朝、6時56分「はやて1号」八戸行に乗車した。昨年2002年12月に開業した東京-八戸間を結ぶ東北新幹線だ。 上越新幹線軌条での試験走行で営業車輌としては国内最高の362キロをマークした(ちなみにテスト車輌では300Xが443キロという目玉が飛び出すようなスピード記録を持っている) 車内は混んでいる。指定席が満席、グリーンにすべりこんだ。グリーン車サービスのおしぼりとドリンクが配られる。JR九州と同様のサービスだ。ドル箱のくせにおしぼりのみという東海西日本の殿様商売に厳しい視線を送らざるを得ない。 高速車輌の「はやて」と言えど上野、大宮と小刻みに停車。しかし、大宮発車後はその本領を遺憾なく発揮し、仙台、盛岡にしか停車しない。 列車は大宮以北の広大な関東平野の只中をひた走る。利根川を越える頃、水田の緑が陽光を照り返し、梅雨の合間のさわやかな青空が広がり始めた。高層建築の1本とてない甍の波が視界の続くかなたまで続いている。週末土曜日の朝、あの波の下の多くはまだ軽いまどろみの中にあるのだろう。沿線の道路は皆、曲がる必要のないのびやかな直線で地平の彼方に向かっている。 やがて、明らかにそこから市街が始まるのだと |
いう鮮やかな句点を打つように宇都宮の街が近づいてきた。背後には雲を掻い込み上州の嶺がおぼろに浮かぶ。上州の象徴、男体山。それらしい孤峰はやがて緑の田の彼方に現れる。水田の新緑と山容を覆う深緑が目と心になぜか優しい。 深い木立に守られた家々が目立ちはじめた。どの家も同一の方角に高く厚く木立を配している。上州名物からっ風への備えは想像以上に厚い。 やがて、ガラスとコンクリートに装われた近代建築ビル群が宇都宮のとき以上に鮮やかに視野に飛び込んできた。仙台だ。東北第一の殷賑は緑の海に浮かぶ人口の浮島だ。 仙台を発ち、一関を通過。次の停車駅は盛岡。初夏はまだこの北国の手前で足踏みをしているようだ。車窓に広がる土手の緑がどこか硬い。盛岡でかなりの乗客が降りてゆく。 身軽になった列車は心なし軽やかに八戸に向かう。しかし、仙台、盛岡にしか停車しなかった「はやて」はこのあと「いわて沼宮内(ぬまくない)」「二戸」と各駅停車クラスの駅に次々と停車する。ふたつの停車駅は深山幽谷の中にある。 やがて恐竜の骨格標本のようなアーチ状の終着駅八戸駅構内へ。ドアが開き、どっと繰り出す新幹線乗客の波がおさまれば、駅はまたたく間にもとの静寂を取り戻すのであった。 |
金沢行(その3) →→→back 金沢行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
| 遠くに置き去り、忘れ去っていた大切な何かを思いもかけず取り戻した悦びの中に筆者はいる。 それが筆者をして幾度も金沢へ足を運ばせる衝動となっている。三つ子の魂百までとはよく言ったものである。十七だったんだけど実際は。 お盆のこととて街は静寂のしじまに浮かんでいる。 夏の日差しは強いが、風は思いのほか涼しい。セミの鳴き声、鞍月用水のせせらぎ、人影もまばらに金沢の夏がそこにある。 大阪在住1年半で3度目の金沢だ。来てるなあ、随分。 犀川のほとりに出る。 25年の歳月にも、この川の景色は変わらない。夏草に覆われた堤に腰をおろせば昔日の思い出がポロポロと零れ落ちてゆく。 腰を上げて金沢城にむかう。金沢大学を追い出してまで観光資源化を狙った金沢城、天守閣はないが、先年の大河ドラマに間に合わせるべく急造したとしか思えない五十間長屋に初めて入った。 「急ごしらえ」の標本のような五十間長屋は外郭に松などを植えて、芝生を養生している。 植樹と五十間長屋の設計はまったく連携していなかったのかもしれない。長屋をカメラに収める好適ポイントのことごとくで松が絶妙に邪魔をす |
るのである。 とてもすぐ隣に「兼六園」という名園を持つ土地の仕業とは思えない。金沢城址の広さを行政はあるいはもてあましているのかもしれない。 25年ぶりといえば、忍者寺と呼ばれる妙立寺も訪れた。一国一城の制度下、幕府による領地没収、減封政策が加賀に及んだ場合、幕府との一戦辞さずとの政策から設計された城の外郭城塞である。戦闘を想定した各種意匠の巧みさから忍者寺と呼ばれているが、実際に忍者とは何の関係もない。堂内見学ツアーは昔のままだ。 さて、金沢のとある寿司屋のカウンターに花器が置かれている。丸い、なで肩の上部から下部にむかって漆黒から朱へのグラデーションがかかっている花器だ。天井のランプとカウンター、客の姿が映り込み、筆者は、この花器が映し出す情景をえも言わず気に入っている。浅学のため、陶磁器か漆器かの区別もつかず、金沢を訪れるたびに九谷焼の店でその姿を探し求めていたのだが、このたびやっと輪島塗の「曙」と呼ばれるシリーズであることが解った。 さっそく購入。 現在、筆者の家の黒テーブルの上で毎夜、筆者の手で撫で回されているのである。 |
| 目的を定めぬ旅にも期待はある。 何に期待するかは、旅人の心のままだ。 歴史的遺産としての建造物ばかりが観光資源とは限らない。その街固有の空気でもいい。新鮮な海の幸、山の幸だってありだ。 いずれにせよ、人は何かを期待してその土地を訪れる。 しかし、世の中は広い。何を期待すればいいのかわからない土地も稀にある。親からも期待されない四男坊のようなもの。 不順な天候の中、お盆に訪れたのが和歌山。 満を持しての訪問だ。かつて途中下車までしたのに、すぐ駅に戻ってしまった街。 駅前には「暴れん坊将軍」の銅像がある。白馬にまたがった松平建が和歌山城の方を向いている。嘘です、ごめんなさい。 なんでかなあ。期待のとっかかりがないんだ和歌山。城はある。あとは梅干とみかん。梅干もみかんも消費マインドをくすぐらないこと北海の氷山のごとし。和歌山ラーメンもなあ。 JR和歌山駅から街に出る。南海の和歌山市駅がそれなりの距離を置いて西にある。どっちが繁華なのか、地方都市の通例で私鉄駅のほうが賑わっているのだろうか。JR駅前はそれなりの街並みのように見えるが瞬時にして店が消えた。せま |
っ!和歌山城にむかって「けやき大通り」が伸びている。この大通りのまわりがまた何もない。 和歌山城は55万石の象徴だ。堀端の雰囲気はそこに繁華街があるなら松山城に似ている。でも繁華街はここにはない。樹木に囲まれた石垣は「天空の城ラピュタ」のようだ。これは買い。 アーケード街を発見。お盆のせいもあってか寂しい佇まいだ。店も古い。 街を東西に突き抜けて、南海の和歌山市駅前に出る。JR駅前とどっこいどっこいの面積。JRも私鉄も寂しさは五分。ややJR駅前の方が優勢なくらいだ。これは珍しい。 市駅にJRが乗り入れている。2両編制のローカル線が間に紀和駅ひとつをはさんで市駅とJR和歌山駅間を往復している。 同行のS君がぽつりと言った。 「松戸に似ている」 筆者は、ぽんと膝を叩いたね。それだ、その感じ。大都市の南に位置し、海に突き出た半島の真ん中にある街、小岩や亀井戸、船橋などの下町、密集した住宅地を越え、コンビナートを抜け、ベッドタウンなんだか独立した都市なんだか性格が曖昧な街。さらに南に進めば漁港があり、景勝地がある。そうだ、そうだ、千葉だ、千葉に似ていたんだ、和歌山。 |
| 「高原へいらっしゃい」 ただし、避暑ではなく労働で。 3食宿泊付日給2千円で徴兵された筆者の担当戦場は、高地の峰と谷に広がる畑だった。小型軽トラックの荷台に乗車して移動する。 レタスの種まき、トマトのガジいれ、キャベツの刈り入れ、農薬散布、若芽の間引き、農作業にさぼる暇はない。 高地の上下の畑で栽培される作物の種類は、当然異なる。上の畑は稜線のかなたまで続くキャベツ畑だった。キャベツを入れるダンボール箱が4メートルほどの高さに積みあがっている。はしごをかけ、上から投げ下ろす。大きなホチキスでバッコンバッコン底うちして長大なキャベツ畑に4~5メートル間隔で放り投げる。 包丁を握り締め、キャベツの外葉1~2枚をばさっと広げ、根元でズクっと刈る。ばさっ、ずくっ、ゴロンだ。これを延々と続けてゆく。広げた葉の中から芋虫がごろんと転がったりもする。 下の畑ではレタスの種まきだ。レタスの種は小さく、朝顔のそれと似ている。種を一握りつかみ、きざなカラオケオヤジのように小指を立てる。その小指を関節まで土中に差し、握り締めたこぶしの底をゆるめて種を数粒下に落とす。すっと挿してぱらぱらっと落とす。ちょっと前進。す |
っと挿してぱらぱらっと落とす。ちょっと前進。あっと言う間に腰がガチガチに固まる。しかし若き筆者はこのての作業に異様に強い。本職の農家の皆さんをグングン引き離す。あっという間に50メートルのターンだ。 「いやあ、早いねえ」持ち上げられてその気になって、ますますスピードアップ。馬鹿。 そしてトマトのガジいれ。 鍬を使って、雑草を刈り取る作業だ。トマトは、中腰で入れる程度のアーケードにつるを巻きつけトンネルを形成している。100メートルほどのトマトのトンネルが何列も並んでいる。トンネルに入って5メートルも進まないうちに異様な羽音に囲まれた。アシナガ蜂に制空権を奪われている。最短記録でガジいれを終わらせてやった。 高地のてっぺんに畳敷きの6畳ほどの小屋があった。寝具もあるし、電気も引かれている。どういう意図で作られたのかは知らないが、わがままを言って一晩ひとりで泊まらせてもらった。 夜半、小屋の扉をあける。 周囲に灯ひとつ存在しない。心細くなるほどの暗闇だ。背後の室内灯の明かりだけが、漆黒のキャベツ畑を白く四角く切り取っている。その中央に遠く長く伸びている己の影。筆者の「記憶のアルバム」中ベスト10に入る貴重な1シーンだ。 |
| きわどいところだ、尾道。実にきわどい。 清里とは別の意味で気が抜けない。 「尾道に行ってきたよ」と言うときは、周囲に気を配ろう。必ずそこに(は、はあん)という表情を浮かべる輩がいるからだ。 (は、はあん)に気づいた瞬間、すかさず「違う、違う!」と否定しなければならない、って何をよ。無論『大林宣彦監督作品オタク』ではないことをだ! ノスタルジック(懐旧的)よりもリリカル(叙情的)なんだな、大林映画。だから美少女を使う。(若き小林聡美が美少女か?という議論に踏み込むつもりはないぞ) 尾道三部作や新三部作で原田知世・富田靖子・石田ひかり・高橋かおりなど、もうマニア垂涎のキャスティングでブイブイ言わせている。もともとCM畑出身だと思う。映像に実験をしたがる傾向がある。今からではちょっと想像もつかないが、若き池上季実子 で「ハウス」なんてホラー作品を作ったころからすでに美少女好きだった。 尾道はすでに大林映画の記号としてしか認識されない危険性が高いのだ。 断っておくが、筆者はマニアではない。いかに1983年公開時「時をかける少女」の原田知世が可愛かったといえども、そんなことで尾道を訪 |
れたりはしないのだ。 新幹線で福山迄。山陽本線に乗り換えて20分。大阪から片道1時間半で尾道にゆける。 坂だらけ。ついでに寺だらけ。それが尾道。足腰が弱る前に訪れよう。 細い坂道が葛籠折れのように山頂にむかっている。途中幾つもの分岐があり、闇雲に歩いているといつの間にか民家の敷地に迷い込んでしまう。 隣家が裏庭で繋がっており、その間、樹木の間を縫うように人が踏み固めた小路が続く。そんな田舎の光景を筆者は持っている。母方の実家の千葉の山奥の情景だ。 どこに繋がっているのかわからない境界線のあいまいな感じが、今歩いている尾道の坂と、どこか重なり合う。 駅裏の山頂に尾道城がある。天守閣だけのその構築物はすでに遺構の観がある。さぞかし眺望はすばらしかろうが、入口は閉ざされ、蔦が石垣を覆っている。眼前に広がる尾道水道は狭い。対岸を2隻の小さなフェリーが行き違いのようにして結んでいる。海風だろうか、都会の猛暑が嘘のように涼しい風が吹き渡る。 ああ、この坂は「転校生」で小林聡美が自転車でこぎ登った道だ。 断っておくが、筆者はマニアではない。 |



青森行(望郷編) →→→back 青森行(望郷編) 青森行2(食いしん坊バンザイ編) 青森行3
| 青森はかつて「さいはて」の地だった。 列車を降り、青函連絡船のタラップに繋がるホームを歩く。国鉄の乗車券では継続路線扱いだが、明らかに本土はここまでなのだという刻印が胸に刻まれる仕掛けだ。 4時間で北国の海峡を渡る船旅は、津軽海峡線で2時間に短縮されてしまった。陸続きというイメージが青森から「さいはて」感を奪った。 トンネルだけではない。青森駅後背に浮かび上がる「青森ベイブリッジ」は駅前からの視界に奥行きを与えている。 筆者の記憶の中、青森は低層都市だった。フラットな街並みのイメージは、このベイブリッジの橋脚により額縁ごと架け替えなければならなくなった。街の光景が近代化している。ブリッジは、その実質的な交通便宜性よりもはるかに視覚的観光資源性に重きを置いて建設したとしか思えない。そして、それは正解であったようだ。 いいことなのかもしれない。少なくとも、どこかあかぬけた観がある。 筆者が青森を訪れたのは1981年。今や青森都市観光の顔である「アスパム」もまだ出来てはいない。いわんや青森ベイブリッジをや、だ。 その後、87年に青函連絡船を利用、青函連絡船の廃止、青函トンネルの開業は1988年だ。 |
青函連絡船は記念艦として「八甲田丸」が繋留されている。函館には「摩周丸」がある。何か懐かしい記憶でも蘇るかと乗船したが、客室など多くを展示室に改装しているため、残念ながらセンチメンタルジャーニーにはなりえないようだ。 青森ベイブリッジの下を岸壁ぞいに板敷きの遊歩道が緩い彎曲を描いている。テラスのように張りだした作り、海にむかったベンチ。いい施設だ。名前は「青森ラブリッジ」 何とかならなかったのか。 22年前の記憶は蘇らない。おぼろな記憶の中でたったひとつ、そこだけが明々と照らし出されたように明確な情景がある。青森駅の待合室だ。時間はかなり遅い。筆者は列車を待っていた。地元の親爺が数人待合室になだれ込んでくる。時は9月の中旬、かなり肌寒い気温に筆者は窓を閉めていたのだが、なんとその親爺ども「今日はあっちいなあ」とか言いながら、窓を全開にしやがった。 ぴゅう。 「さ、寒い」小声で一人ごちる若き筆者。「いやあ、ちょうどええ。涼し!」大声で笑いあう親爺の群れ。北国の親爺の体は寒冷地仕様だとそのとき知った。 それだけが青森の記憶。情けないっす、本当。 |
青森行2(食いしん坊バンザイ編) →→→back 青森行(望郷編) 青森行2(食いしん坊バンザイ編) 青森行3
| 駅前から伸びる新町通のアーケードは柳町通まで続いている。その光景がどこか盛岡と重なり合う。雪国特有の雰囲気があるのか。 歩道が広い。自転車レーンが確保されているのだ。柳町通はさらに歩道が広い。ねぶたのメーンストリートかもしれない。 7月上旬の今、「アスパム」の裏に巨大テントが幾つも設営されている。その前には「青森山田学園ねぶた」「自衛隊ねぶた」「日本通運ねぶた」などなど、団体名が掲げられている。徳島阿波踊りの連のように各団体がねぶたを作っているのだろう、「自衛隊ねぶた」のテントの前に行き、隙間から中を除く。 (やってる、やってる) 骨組みに紙で肉付けをしている自衛官の姿があった。非番なのか? 日本の防衛は?などと言う奴もいないのだろう。いいなあ、時間の流れが緩やかだ。 メインストリートの百貨店「松木屋」はどうやら閉店らしい。駅前の市場団地も規模を縮小させているような気がする。二十数年前の記憶は蘇らない。あ、ひとつだけ思い出した。 帆立のバター焼き定食を食べたはずだ。 青森と言えば「帆立」だ。さっそく帆立料理専門を掲げる店で帆立のバター焼き定食を食べる。 |
貝の上で焼いたレアな帆立のステーキ。軽くレモンがしぼってあるのか、香りがする。旨い。 店を出て、そのまま、あたりをつけた次の店に向かう。帆立の貝焼き味噌定食を食べた。 貝の上で帆立と味噌、ネギを焼き、玉子とじにした料理で、この店では上に雲丹がのっていた。 そう言えば、昼は八戸で「焼きうに」を1個食べただけだったのだな。 夜、地料理で舌鼓をうつ。季節ならば陸奥湾のタラのアラを使う「じゃっぱ汁」に「ほや」「お造り」「活うに」うにとあわびの吸い物「いちご煮」で田酒(でんしゅう)の生酒を一献。ぷはあ、旨え。 朝、駅広市場の寿司屋で三色丼を頼んだ。まるまる1個のあわびとウニ、いくら。朝からこれ?という一品。旨いなあ。 「ウニは龍飛のものです。醤油をつけずに食べてみて」と気の良さそうな大将に言われ、パク。旨い。甘味が口中に広がる。 「ムラサキ雲丹ですか」 「エゾバフンだと、全部食べると胸がやけます。脂がのっているので」 「なるほど」 「最近ではここでも7割は海外からのものです」 「へえ」やっぱり旅は記憶より腹だ。 |
| 「おトクでございますよお客様、長浜は」 こんな物件は、そうめったやたらと出るものではございません。まさしく掘り出し物。 まず第一にロケーションがいい。 大阪から新快速で1時間半、京都ならば1時間。特急料金も払わずに乗車券だけでこれだけ日常から逃避できるなんてボロ儲けというものです。 そして何よりもこの眺望。 どうです。琵琶湖を一望のもとに見渡すことができるこのバルコニーからの眺め。東のバルコニーにもどうぞ。あ、足元にご注意くださいね。排水のため床が外に向かって傾いていますから。 ほら、あれが近江の象徴「伊吹山」です。え?削られているところは何だって?そんなことわかりませんよ。何か造成でもしているんじゃないですか。それよりも、湖面を吹き渡るこの風、さわやかじゃありませんか。ええ、そうですね。ちょっと間取りが広すぎますねこの長浜城では。 では、駅のむこうがわに参りましょう。 ほら、どうです。この黒壁の続く宿場町のような商店街。これが「北国街道」です。なかなかの風情でございましょう?この「安藤家」など赴きのある町屋じゃあありませんか。魯山人ゆかりの家だそうですよ。 |
この先には「大通寺」という伏見城の遺構と言われる大寺があるんです。ね、いつおむかえがきても大丈夫、あ、失礼いたしました。 曳山まつりは4月です。ええ日本三大出車まつりのひとつということはご存知ですね。 浅井長政のいた小谷城は北東の方向です。ええ、戦国時代の。そうです。信長に滅ぼされた浅井氏です。いえ、お客様「アサイ」ではございません「アザイ」です。そう濁るんです。長浜は尾張美濃から京都への侵攻ルートの戦略的要地なんです。あ、お客様、あくび。つまりませんか?戦国の話。そうですか戦争がお嫌い。了解です。 それでは、このガラス細工などいかがでしょうか。名産品です。あ、これなどどうですか、古道具屋の棚にかけられたこの槍、15万円。え、また戦争の話になる?失礼いたしました。 ではこちらへどうぞ。今や日本最古の駅舎となってしまった、旧長浜駅舎と鉄道文化館です。ほら、こんなに古い時刻表を見たことがありますか。え、ないけど、興味がない。鉄道マニアではない。ええ、実は私もそうなんです。鉄道なんてこれっぽっちも興味がなくて。そうですよね、あ、でもこれだけは見ておいたほうがいいです。旧長浜駅29号分岐器ポイント部の・・・あら、お客様、もう出ちゃいます? |
徳島行2(寄り道編) →→→back 徳島行1 2(風雲帰阪編) 3(寄り道編)
| 3年ぶりの徳島だ。 市街地後背に眉山がそびえる。標高290メートルながら、街並みとこの秀峰は一幅の絵のように美しい。 にもかかわらずまだ一回も山頂に赴いたことはない。ロープウェーも展望台もあるというのに。結局今回も行かずじまいだった。次こそは訪れよう。 大阪から徳島に立ち寄るルートは三つ。鉄路、道路、海路と多彩だ。 今回は往路を鉄路、復路を海路とする。 往きの鉄路では、岡山、高松経由で徳島に入る。レールスターと瀬戸大橋、讃岐うどんがオプションで着くコースだ。レールスターはJR関西の新幹線。のぞみ700系車輌を改装、指定席はグリーン車と同じ左右2列の4列シート(もちろん料金は通常指定料金)車内で表示される最高速は285キロ(東海の「のぞみ」より早い)さすがに編制は8両と短躯だが、4人用個室やサイレンス車輌(車内放送がない)など工夫が凝らされている。 サイレンス車輌はJR東海に慣れた身には新鮮だ。停車駅に近づいても放送がない。降車準備をする客も黙々と身づくろいをする。 岡山から徳島行特急「うずしお」に乗ってしま |
うと、高松で途中下車がつらい。ここは快速マリンライナーで特急料金を節約して高松で降りる。時間差はほとんどないのが京都線の新快速を思わせる。 高松に立ち寄り、うどんを3軒はしご。山間部の製麺所を兼ねた店まで行く根性も趣味もない。市街地のセルフの店で十分だと思っている。今回は「うどん市場」というセルフの店が一番旨かった。ちょうど昼飯時分、近隣のサラリーマンが最も並んでいる店だったからはずれはあるまい。箸や食べ残し、湯呑み、どんぶりを分別して返却口へ戻すため、返却口が混み合うめずらしい現象が見られる。 単線で急傾斜のバンクが連続する、思いのほか楽しい高徳線でいよいよ徳島へ入城。 今回の徳島行の目的はまず「栄寿司」だ。 3年前の訪問で、そのネタの新鮮さと寿司の旨さ、居心地のよさに思わず「日本一!」と心に叫んでしまった寿司屋さんである。 寿司の後、徳島ラーメンを食べるのも愉しいだろう。前回も「ラーメン東大」でラーメンを食べた。今回もそうしよう。 |
徳島行3(風雲帰阪編) →→→back 徳島行1 2(風雲帰阪編) 3(寄り道編)
| 徳島、栄寿司の佇まいは年季を経た古木のように質朴で重厚、それなのにどこかすがすがしい。客あしらいも3年前のままだった。 「さばの刺身とたたきがあります」いただきます「ミョウバンをつけない取れたてのうにを潮水で・・・」今すぐ下さい「鯛の肝と皮です」地酒をお願いします「小鯛の一夜干しを」焼いて下さい「あじとボーゼ(エボ鯛)、あおりいか・・・」もお、どーにでもしてください。 にぎりも一巻ずつ次々と平らげ、地酒を堪能する。前回同様、実に居心地が宜しい。 「ご馳走様でした」会計も銀座の高級寿司屋の半値に近い。 「ラーメン東大」の店内も3年前と変わらずにいた「弱冠29歳の店主が全国をめぐり塩と味噌を開発云々」のポスターが変化らしい変化だ。3年前「弱冠26歳の店主が開店1年で支店を出せた訳」なんてコピーがあった。弱冠25歳で店を始めたらしい。そろそろ弱冠は卒業では? 徳島ラーメンの特徴である濃い目の醤油味、甘辛の豚肉がのっかり、生卵(無料)を落として食べる。ごはんが合うんだ、これに。 徳島満腹旅行の夜は静かに更けていった。 翌朝、慌しく帰路につく。タクシーでフェリー乗り場へ。海路は徳島フェリー発着場から和歌山 |
港へ。和歌山から南海特急で難波に帰る。鉄路と同じ3時間弱の旅だ。ただし、料金はべらぼうに安い2,620円だからJRの三分の一程度。 タクシーが船着場に到着。あれ?桟橋にフェリーの姿がない。なんか嫌な予感。 乗船口の時刻表を見ると「休航」のプレート。 やられた!「メンテナンスのために休航します」ですって!徳島駅前の旅行代理店のオネーチャン、やってくれました。明日8時10分のフェリーをって言ったのに見事に見落とされていた! クーポンの払い戻しをしてタクシーで駅に向かう。かくなるうえは陸路だ。 JRバスで大阪駅桜橋口にむかうことにした。 陸路のオプションは、鳴門大橋と明石海峡大橋、淡路島の縦断というあたりか。 平年より4日遅い、昨年より1日遅い梅雨入りの今日、天候は雨模様。しかし初めての景色は愉しかった。淡路島がなぜか妙にのどかで懐かしい情景だ。淡路でバカンスもありな気がする。 神戸から大阪へ、湾岸の眺めは東京のそれよりも数段美しいことを始めて知った。何層にも重なる道路、様々な形態の多数の橋、眺望の広がり、これはめっけもんだ。渋滞を嫌って「舞子」でバスを降りJR神戸線に乗り換えるという手もあったのだが、実行しないでよかった。 |
| 窓が大きくて、目線が低い。 特急「スーパーはくと」の車窓は、高架からの見下ろしに慣れた新幹線のヘビーユーザーにはひときわ新鮮だ。並走する線路がすぐ鼻の先にある。地を這うような感覚。 非電化区間を走るため、ディーゼルだ。つまりパンタグラフがない。架線まで背伸びをする必要がないから背が低いのだろうか。 ディーゼルとは言え、この特急は馬力がある。加速時、シートに背中が押し付けられる。130キロ走行が可能なのだ。 「スーパーはくと」は京都始発で大阪、姫路、相生を抜け、第三セクターの智頭急行線に乗り入れ鳥取へむかう比較的新しい路線だ。従来4時間以上かかっていた大阪、鳥取間が2時間半で結ばれた。来阪時、大阪を起点とした2時間半という時間半径の円周上に東京、金沢、鳥取があるということを知ったとき、筆者は新鮮な感動を覚えたものだ。 季節は3月中旬。少し広めの窓枠にひじをかけ、流れ去る窓外の風景を見るともなく目に映す。ふと気がつけば、陽光あふれる山陽道から播州の山並み重なる内陸に路線は向きを変えていた。空を雲が覆い始める。 青空をバックに耀いていた明石海峡大橋の姿が |
懐かしい。ほんの少し前の景色だったのに。 雲間からこぼれる陽光が心細い。 千種川を渡り、水墨画の世界が広がった。いつのまにか外は雨。霞む山並みと白く泡立つ川の瀬。一瞬、雲が切れ、思いのほか力強い陽光が注いだと思うまもなく、またたくまに灰白色の世界に逆戻り。そして再び雨。ふと目線をそらした数分の後、車窓一面が白い粉雪に覆われていた。 沿線の山容はすでに白一色だ。 見る見るうちに吹雪に変わる。遮光性の高い分厚く白いカーテンが幾重にも激しくたなびくような降雪だ。 雪のカーテンのドレープは、しかしこれもまたあっというまに粉雪の一片一片が見てとれるほどにほどけてゆく。 大原に着いた。雪は止み、太陽が顔を出す。雪景色はかわらない。 智頭に着く。今までの山峡の駅よりもあきらかに大きい。それでも宿場町というイメージだが。 川沿いに山並みはやや後退する。川幅が広がり、沿線には梅の花が咲き誇っている。すでに地面に雪はなく、再び太陽が顔を出し陽光が注ぐ。これほど劇的な車窓の変化は経験したことがない。山陽から山陰に抜けるこのコース、ありだな、あり。 |
| 筆者の知友M君は車窓にまったく興味がない。 だから列車に乗るのが昼だろうが夜だろうが窓側だろうが通路側だろうがそんなことは一切関係なし。筆者は昼夜の車窓が決定的に違う以上、旅客列車の夜の運賃はその分安くしてしかるべきだと思っている。M君はそんな筆者を理解しがたい鉄道マニアだと決めつけている。 筆者は鉄道マニアでは断じてない。 三脚をホームの先端にすえつけて列車の写真を撮ったことはないし、時刻表の定期購読者でもない。ましてや、時刻表を片手に列車のすれ違い時間を計算したりもしないし、青春18切符を買って鉄道2万キロ走破の計画を立てたりもしないのである。 筆者は旅好きなのであって鉄道マニアではない。 旅好きと鉄道マニアの区別は簡単だ。 訪問地の滞在時間ですぐに陰性か陽性か判明する。滞在時間が恐ろしく短い場合は鉄道マニア菌に犯されていると言っていい。 駅から一歩も出ないようでは末期症状だ。 鉄道マニアは駅を出ても半径300メートルを越えて歩くことはない(乗り換え時間が2~3時間の場合は例外だ) そして、多くは駅前のそれらしいそば屋か定食 |
屋に入る。最近では人間関係症候群(何だ?それは)にも罹患しているため、コンビニエンスストアがあれば、そこで買物をしてしまう。 鉄道マニアは滞在しないのである。滞在するくらいなら鉄道に乗っていたいのである。だから鉄道から降りている時間が非常に短い。 くどいようだが、筆者は滞在する。宿泊までする。土地々々を歩き回るし、飲食店では食べ尽くす。したがって鉄道マニアではない。当然のことである。 旅から帰れば、時刻表2冊をつぶして作成した全国鉄道路線図の乗線区間を赤くマーキング。そして、滞在した土地に緑のチェックをいれるだけなのである。 さて、車窓に興味のないM君は、しかし船窓には尽きない愛情を注ぐ。 信じられないと言いたい。 船窓だよ、船窓。海でずぜ、旦那。思わず言葉が濁ってしまった。 水平線に凹凸はない、凸凹がないと魅力に乏しいのは景色だけではない。あ、この一行、削除。 とにかく、最後は飽きるにきまっている。 でも、海外生活が長く、どこかヨーロッパ的なM君はクルーズこそ旅の醍醐味だと言う。船はねえ・・・沈むし。 |
| 山陰はオトナの国。 若者はライダーのみ。青春18組もここまでは来ない。静かなものである。 JR西日本もちゃんとキャンペーンをやっている「山陰は四十を越えてから行きましょう」切符の裏側に小さく書いてある。ないか。嘘です。 宍道湖のほとりに位置する松江は、実は出雲の中心地である。出雲大社のある出雲は西出雲の位置付けとなる。でも、そんなことにこだわる旅人はいない。こだわりを捨てきれないのは現地の人。嫡流なのに庶子に人気をさらわれたような悔しさが松江にはあるのかもしれない。何故か山陰は地元贔屓の度が強い。筆者は鳥取と島根の仲の悪さを島根出身の若者から聞いた。 筆者の独断による不仲の3巨頭は三河と尾張、南部と津軽、会津と萩である。地味な不仲では仙台と福島、沖縄と鹿児島なんてのもある。身内争いでは大阪と京都、広域不仲となると関西と東京、北海道と本州、沖縄と日本。まあ、いい。 城下町松江の好感度は一般に高い。筆者にとっては不思議な高値がついている。小泉八雲も松江で日本の美に打たれた。しかし日本海気候の寒気にも撃たれ、そこそこに逃げ出した事実は案外語れていない。松平治郷(7代目藩主)が不昧公(ふまいこう)などと呼ばれ茶の湯を中心とした |
文化・芸術の華を咲かせた話なども実際どれほど中身の詰まったものなのか。いまひとつ筆者には了解しかねる部分である。 そこで街を歩いてみることに、言わなくても歩くのであるが。宍道湖畔から松江城、さらにその北側にある堀川端の塩見繩手と呼ばれる、武家屋敷跡を歩く。 ほどの良い距離感。無駄のない空間構成。良いではないか。薄暮の中、ライトアップされた天守。すでに閉門時間のため中には入れない。階段を下りてくるひとりの若い女性。すれ違いざまに「こんにちわ」と声をかけられた。不思議なことにためらいもなく自然な挨拶を返す自分がいる「こんにちわ」 なんとものんびりしたいい雰囲気なのだ。露地行灯をイメージしたのであろうか、街路灯が地面に低く据えられ、柔らかな電球色で塩見繩手の道筋や松の幹を照らしている。 繁華街に戻っても、土曜日の夜7時に人の姿は少ない。車道の周囲にクラブやスナック、飲食店がまばらに立ち並ぶ程度で、都市部の繁華街のイメージではない。山陰の夜。しかし宍道湖を前にして妙に落ち着いた、開放的な夜であった。ちょっと表現しづらい大人の落ち着きを漂わせる街、それが松江であった。ありだな、あり。 |
| JR中央本線に小淵沢(こぶちざわ)という名の駅がある。 小海線(こうみせん)の始発駅だ。 小海線で小淵沢から3駅目に清里がある。メルヘンの町だ。まっとうなメンタリティの人間は足を踏み入れることが出来ない結界が張られている。今、どうだかは知らない。しかし、当時は確かに結界が張られていた。 その町では「かき氷」などと言う素朴な食べ物はその存在を許されない。アイスだのフルーツだのを身にまとい「高原のチャペルの乙女の祈り」とか、絶対に実体を想像できない謎のネーミングに包まれ、一杯800円ぐらいで売られているのだ。 若き筆者は清里を否定していた。間違っていたかもしれないが、しかたがないのだ。青春とは酷いほどの断定で障壁を設け、傷つきやすい自己を守るものだから。 さて、その清里の隣に小さな駅がある。駅は小さいが標高は高い。JR(当時は国鉄)の駅中日本一の標高を誇る「野辺山」駅だ。 1980年の夏、ひとりの若者が野辺山駅頭に立っていた。 夏の1ヶ月を高原ですごすためだ。避暑地の夏「高原へいらっしゃい」だ。古いか(昔、田宮次 |
郎主演のTVドラマがあったのだ) 若者は迎えを待っていた。 やがて、陽炎の向こうからエンジン音が近づいてくる。迎えがきたらしい。 サングラスをはずす。夏の日差しが物理的な痛みを伴って若者の肌を刺す。UVなどという言葉は当時、まだ存在しない。 車が止まり陽に焼けた青年が白い歯を覗かせながら降りてくる。たくましい男だった。 「やあ、××さんの紹介の××さんだね」 長い1ヶ月の始まりを告げる短い挨拶がかわされ、若者は泥だらけの軽トラックの荷台に乗った。着いた先は巨大な農家。休むまもなく、長靴と軍手、麦わら帽子が支給され、1日2000円でかりだされた兵隊は強烈な日差しが降り注ぐ高原野菜の激戦地へ投入された。 そこは日の出と共に、村中に響き渡る大音量の「星影のワルツ」が流れる村。 千昌男の次には「本日のキャベツ市況」が流れる村。 「L玉1個××円××銭、M玉1個・・・」高原野菜市況の最新ニュースがテレビ東京の株式ニュースのように流れ続ける。 ねずみが毎夜、運動会を催し、アブがトイレで大量に飛び回る村だった。 |
| 宇都宮はいつの間にか「餃子の町」になっていた。若かりし日々に訪れた土地がいかにも歴史的所産のような顔で「××の町」と自称を始めると昔日をなつかしむ身としてはちょっとしょっぱい。 無論、訪れた頃からそのとおりなら何も問題はない。ありきたりなツッコミで申し訳ないが 「昔はそんなこと言ってなかっただろ!」ということがあまりに多いもんで言ってみました。ミエミエの観光誘致政策に当方、鼻白んでしまうのである。思い出をいじられるという嫌さも数滴混ぜ合わさる。 で、もって場所が宇都宮だ。何を意図してのことか?観光地にはならないだろう、いくら何でも。『首都圏まで45分』なんて新幹線通勤を前提にした強引な不動産営業だってうようよしているぞ。ちょっと目を離すと際限もなく広がってゆくJR車輌の首都圏近郊路線図には『宇都宮』がしっかりと掲載されているし。あの路線図は近いうちに仙台と越後湯沢、浜松までは取り込むに違いない。近いぞ!仙台、もうすぐ首都圏だ! 筆者は大学生の頃、自動車免許取得のためこの宇都宮で16日間を過ごした。例の合宿免許って奴。その頃、町全体に餃子の影は微塵もなかった。マスコミがいかんのだ。マスコミが。低 |
予算で制作できる旅番組あるいはご当地立ち上げ企画(はやったなこれ、たけしの番組が先鞭をつけたと記憶している)で必要な目玉、奴らはそれを捏造する。これをヤラセと呼ぶか、誰も取り上げてこなかったネタの発掘取材と呼ぶかの線引きは難しい。まあ、誰が不幸になる話でもないので明らかに黙認されているが。 と、言うことで宇都宮で新幹線を降りた筆者とM。事前情報を入手したMが「餃子館」の訪問を提案。嫌な予感がした。そもそも宇都宮の餃子を代表するのは「ミンミン」だろう。2人前を「ダブルで」と注文するなど個性化の先鞭はこの店から始まったのではなかったか。 しかし場所もわからんし、Mに従った。 その餃子館でMは『とんかつ餃子』を頼んだ。豚ロースのまわりを餃子のあんで包みパン粉で揚げた一品。開発努力が正しい成果を生み出すとは限らない。筆者のテーブルをうらやましげに見るM。筆者は、焼き揚げ蒸しの餃子3点とスープワンタンが配された「メンズセット(このネーミングセンスは栃木だ!)」で難を逃れた。「餃子の町」が生み出した自覚は限りなく自己増殖し、企画者の意図を超えた別種の何かに間違いなく変貌していることを知った夜であった。 |
| 列車は粉雪を舞い上げ、舞い散らしながら山岳地帯を走る。快晴の早朝だ。 朝陽が上り、その照り返しが山々の頂から裾野に向かって降ってゆく。雪を頂いた山容の暗灰色がみるみる蒼く澄んでゆく。粉雪が光り輝きながら車窓を包み、視界を遮る。 やはり、列車の旅は日中だな。 昨夜、時間がとれない身の上から夜行に乗ってしまったが、今こうして復路の車窓を眺めているといかにも往路の車窓を覆っていた漆黒の闇が恨めしい。運賃を少しはまけたらどうだとJR東日本に言いたい。 列車は在来線規格の新幹線「つばさ」だ。東北新幹線と連結されて運行するが、山形にむかって福島で袂を分かつ。今はその帰り道だ。 最上川であろうか、目前の山容との間を渓谷がとりもっている。その間隔が適度な視界のバッファとなり、視界に収まる山々の襞に奥行きが生まれる。 不意に視界が広がり、山並みが遠ざかる。 一面の雪景色の中に地面がまだらに顔をのぞかせ始める。点在していた茶のまだらがやがて混じりあい、瞬く間にその面積を広げてゆく。雪面は追いやられ、やがて日のあたらぬ窪みに逃げ込んでいった。 |
吾妻連山を抜けたようだ。 福島県は太平洋側から浜通り、中通り、会津と区分される。福島市は山々に囲まれた大きなくぼ地に街を形成させたようだ。雪をいただいた遠い北の山並みは登ったばかりの朝陽を浴び、蒼く輝く。南の山々に雪はない。 福島の中心地は永らく会津若松だった。鶴ケ城という藩都の象徴もそこにある。中通りの福島に県庁がおかれたのは、幕末の賊軍となった会津藩へのむごいほどの制裁の意味でしかあるまい。 この季節、周囲を山々に囲まれる土地ではさまざまに春の息吹を捜し求める。 雪形という言葉がある。春の訪れとともに雪が融け、山肌の一部が顔を出す、その状態を指す言葉だ。毎年、雪が解け始める場所はほぼ同じだが、現れる地肌の様相は年により異なる。その形で春の到来、その年の気象を占うのだ。 すでに地面に雪はない。郡山を過ぎ、宇都宮を越えればやがて列車は大宮から関東平野の中枢に向かう。見渡す周囲は一望の大平野だ。山並の姿はない。首都圏1200万の府となる必然のような豊饒を予感させる闊がりだ。 荒川を越え、前方に新宿副都心の高層ビル群が待ち構えている。旅が終わり街に帰ってきたことを知らされる瞬間だ。 |
金沢行(その2) →→→back 金沢行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
| 3月20日でズワイガニは禁漁となる。つまり食べられなくなるということだ。 鳥取でしくじりを犯した今、筆者に残された時間は少ない。タイムリミットまであと10日。彼岸も間近の一日、筆者は慌しく金沢に向かった。鳥取のかたきを金沢で討つのだ。 カニだ、カニだ。わはははは。 特急サンダーバードは湖西をかすめて金沢に向かう。大阪、京都、滋賀、福井、石川、富山の各県が3時間強で結ばれている。大阪、金沢間は2時間半。金沢は身近な土地だ。東京から伊豆に向かう感覚で金沢に行ける。 福井、石川、富山の北陸三県の比較を「越前詐欺に加賀乞食、越中強盗」と教えてくれたのは越中強盗の畏友Iである。越前は福井、加賀は石川、越中は富山だ。 福井は勤勉で仕事熱心、近江を近隣に持つせいか商人的。商機に聡く機敏な様子を詐欺漢呼ばわりされるのも気の毒だが、保守的で競争心が乏しく、先祖伝来の家督を失えば乞食にでもなるしかないと言う石川県の言われようよりは救いがある。富山は真面目で仕事熱心、経済的な成功を強く追い求めるため強盗扱いをされた。 いずれにせよ、けっこうむごい。 暑さ寒さも彼岸すぎまでとは良く言ったもの |
で、彼岸前のその日、北陸の道行きに残雪の気配は微塵もない。はるか立山連峰の頂きだけが冠雪の耀きを残している。 5ヶ月ぶりの金沢だ。タクシーの運ちゃんは相変わらず愛想がない。非常につっけんどんな感じがするのは何故だろう。人によるのだろうが、つっけんどん度はかなり高いと見ている。 前回も堪能した片町の乙女寿司で昼を過ごす。あいかわらず旨い。筆者はここのアカイカが大好きである。 近江町市場をぶらつく。冬休みの週末、市場の飲食店は行列だらけだ。夜の予約をいれていなければ筆者もおやつがわりに腹に何かをおさめてしまうところだった。しかし、今夜は空腹で店を訪れたい。我慢である。夜食用に「さわいのパン」でばくだん(揚げパンの中にゆで卵が入っている)と「近江町コロッケ販売所」のタココロッケを買うだけにして宿に戻る。途中、尾崎神社と尾山神社に寄る。 夕刻、つる幸に向かう。 表通りである百万石通りの裏に鞍月用水が流れ、その脇を歩くと金沢の夜はしみじみといいのである。つる幸でカニを食べ、酒を飲み、ほろ酔いの帰路、やっぱり金沢はいいなあと再びしみじみと思うのであった。 |
鳥取行(その2砂丘地獄編) →→→back 鳥取行1 2(砂丘地獄編) 3(徳島鳥取行)
| いいことを教えよう。 チェスターフィールドコートを着て砂丘にはいかないほうがいい。 なぜなら、砂まみれになるからだ。 こんな大事なことが、なぜ鳥取砂丘のガイドブックには載っていないんだ! 繰り返し言っておく。 砂丘にいいコートを着て行ってはいけない。 毛皮のコートに至っては言語道断だ。 駄目になるからだ。 なぜ駄目になるのか。 いい服は織り目が細かく毛足が長いからだ。 なぜ織り目が細かく毛足が長いと駄目なのか。 顕微鏡で拡大すれば、ジャングルのように屹立する織り目の隅々まで細かい砂丘の砂粒がびっしりと侵入してゆくからだ。 そして、この砂粒を完全除去することは不可能だからだ。はたいても、はたいても、コートが砂を吹くのである。もういいだろうと、はたきの手をとめる。でも念のためにもう一度はたいてみるとやっぱりコートが砂を吹くのである。 (ちきしょう) そしてはたく。コートから零れ落ちてゆく砂。 はたいても、はたいても、はたいても、はたいても、はたいても、はたいても、高価なコートが砂を吹きつづけるのである。気がつけば、涙が頬を濡らしていた。 その日、筆者は國領經郎氏の絵そのままの鳥取砂丘にいた。 砂丘の入口は唐突に現れる。 周囲に比較すべき物件がないので距離感が喪失する。馬の背と呼ばれる砂丘の頂点にむかって歩を進める人々が芥子粒のように小さい。空は鉛を含んだような重々しさに垂れ込めている。ここしばらく雨天が続き、砂は湿気をはらみ、砂丘には |
オアシスが現れていた。 一歩ごとに足元が砂に沈む。馬の背にむかって砂丘を登る。 不意に風が吹き始めた。逆風だ。砂が舞い上がる。下から見上げる砂丘の輪郭がぼやけ、やがてその風は徐々に強さを増してゆく。砂丘の頂点に到達する頃には、砂つぶてが面を打ち、その痛みはいささか耐えがたいものとなっていた。顔を風にむけられず、背をむけて登坂する。風は最高潮に達していた。風にむかってかなり傾斜をしなければあおられる。肩にかけた鞄が風帆船の帆のように宙を泳いでいる。 (これはすげえ) 「びゅおおおおおお!ひゅおおおおお!」 カメラを海に向けるべく正面を振り向く。 「びし!びしびしばしばしばし!」 「痛え痛え痛え痛え痛え痛え痛え痛え痛え痛え」 砂つぶての恐怖。 室戸岬で台風接近の実況中継をやらされている新米アナウンサーのようだ 周囲で頑張っていた何組かのカップルも撤退していった。砂丘頂上には筆者だけだ。裂ぱくの気合とともに風上にカメラをむけた筆者は、前方で風にたちむかう勇者の姿を瞬間、捉えた。 「おお!ひとりタイタニック!」 言い知れぬ感動が胸をうった。 すべてが終わり、砂丘を降りたとき筆者は悲劇を知った。 髪も目も耳も口も鼻も、どこもかしこも「ぢゃりぢゃり」である。そして、コートからは「ささささささささ」黄金色の細かい砂粒がとめどもなく流れ落ちてゆくのであった。 まるで涙のように・・・しくしく。 カニどころではなくなった。砂を噛むような思いで鳥取を後にした。 |
鳥取行(その1) →→→back 鳥取行1 2(砂丘地獄編) 3(徳島鳥取行)
| 3月20日でズワイガニは禁漁となる。つまり食べられなくなるということだ。 まずい、食べておかねば。 啓蟄が過ぎた一日、筆者はうごめきはじめた。 カニだ、カニだ。わはははは。 日本海のズワイガニは山陰では松葉ガニ、北陸では越前ガニと呼ばれている。松葉も越前もオスのカニの呼称だ。ズワイガニのメスはコウバコとかセイコ(ガニ)、セコ(ガニ)、コッペなどと呼ばれている。すべて同一の種だ。 今シーズンは金沢でカニ漁の解禁前に偶然、網にかかったコウバコを食べることができた(偶然かかってしまったものはいいらしい)大阪でもセコガニと言って饗された。 あとは松葉ガニだ。 だから鳥取だ。 鳥取といえば、松葉ガニ。あ、鳥取砂丘もあったな。 よろしい。カニを食べる前に鳥取砂丘に寄っておこう。実はまだ1回も訪れたことがなかったのだ。この機会、逃すべからず。と、言うことで鳥取砂丘に向かった筆者。 嗚呼、神ならぬ身の悲しさ、この意思決定が今シーズン最大の不幸を招くことになろうとはこの段階では知る由もなかった。 |
鳥取砂丘、観光資源として非日本性を前面に押し出しすぎるきらいがある。そんなことをしなくとも十分に美しい景色である。 筆者はかつて毎年、日展に通う一時期があった。第13回(1981年)から18回(1986年)頃までが記憶に鮮明だ。何度か通っていると、自分の好みの絵が見えてくる。会場で買った絵葉書や印刷物を幾年分か通して見ると、明らかに共通のモチーフなりタッチなりの絵が知らず知らずに集まっている。画家の名を見れば、なんと驚いたことに同一人なのだ。 そのような収集物の中で砂漠の絵が一再ならずあった。 それが國領經郎氏の作品であった。なぜか、中近東のドライなイメージとは異なる湿潤性砂漠気候とでも言うべきシーンが何号という大きなカンバスに細密画のように書き込まれていた。 鳥取砂丘はまさに、國領氏の絵、そのままの世界だった。 なつかしさすら感じる光景は、しかし絵画の世界が故郷なのだ。筆者は不思議なデジャブにつつまれていた。國領氏の砂丘には必ず鳥が飛翔していた。今、目の前の砂丘に無論、鳥はいない。おだやかな風がたおやかに頬をなぶっていた。そして悲劇はこの十数分後に訪れるのであった。 |
| 一般に認知されている地名と繁華街の最寄り駅の不一致はこの紀行でもたびたび俎上に載せた。 萩は東萩駅で降りねばならないし、鹿児島は西鹿児島だ。もちろん萩駅も鹿児島駅も存在する。 大阪の繁華街は、大阪ではなく梅田。大阪という名称はJRだけが使用している。その他の私鉄、地下鉄などはすべて梅田だ。まあ、この場合は同一エリアをダブルネームで通しているだけなので実害はない。 博多駅で降りても中心地は天神、というのもファールラインぎりぎりだ。このパターンは松山駅と松山市駅という関係にもあてはまる。もちろん松山市駅の方が繁華街だ。 地方に出かける場合はそれなりに注意するから大事故には繋がらない。しかし、大都市でこれをやられると不意をつかれて防ぎようがない。 筆者は遠い昔、神戸でやられた。 神戸駅で降りちゃったんだな、これが。そしたら神戸の繁華街は三宮だって。知らないちゅうのそんなの。 悔しいから湊川神社に行った。単なる悔し紛れである。 三宮駅前から隣駅の元町まで大規模なアーケードが続いている。震災前に訪れたときに較べれば、元町に近づくほど閉鎖店舗が目につきはする |
が、三宮周辺にそれほどの変わりない。と、言うよりも7年でここまで復興したのだろう。 元町と言えば、横浜にも元町がある。函館にも長崎にもあった。 横浜・神戸・長崎・函館、皆、幕末の開港場だ。地名はそれ以前からのものなのだろうか。それとも故あっての地名なのだろうか。 問題提起だけしてさっさと話題を変えよう。 横浜と対置されがちな神戸だが、街の印象はどちらかと言えば東京に近い。それも六本木や白金、青山、渋谷公園通り界隈の大人びたところを抜き出してアーケードに再配置したような感じだ。しかも東京よりもどこか上品だ。 坂道を登れば、街の風情がまた変わる。この街の表情は一度や二度の訪問では捉えきれない。 横浜に較べれば小ぶりな中華街は、その分そぞろ歩きに適している。買い食いできる点心もこの街ならではの景色のひとつだ。 途中、カジュアルに肉を食べたくなった。 ふと目にとまった店構えに惹かれて入ったのが「六段」というお店。店内には店名のとおりの琴の音が流れ、ファミリービジネスの様子がうかがえたが、こんなにリーズナブルで旨いステーキを食べさせてくれる店があるとは、やはり神戸、侮りがたし。 |
| 再生プラケースの駅弁容器はやめていただく必要があろうかと愚考する次第である。 なんて大上段な物言いだろう。我ながら空恐ろしくなってきたな。 しかし、勇をふるってもう一度言わせていただく。再生プラスチックケースの駅弁、断固反対! 地球環境の保全に努め、再生プラケースを開発された方々、あるいは少しでも安い駅弁を届けるため容器コストを銭毛単位で切り詰め、試作を繰り返してきたかもしれないメーカーの方々など関係諸方面の皆様には誠に申し訳ないが、やはり言わせていただく。断固反対と。 まず第一に旅情がない。コンビニ弁当と区別がつかんもんね、あれ。せっかく旅客列車の旅に出ようというときにコンビニ弁当を食べさせられてはたまらない。 もちろん、駅弁に旅情など不要とおっしゃる駅弁機能説に立たれる方々もおられるであろう。それらの方々にはこの場でご退場いただきたい。即刻。今すぐにである。 第二に、腰がないので手に持って食べづらい。 腰が低いというのは好意をもってうけとめられる貴重な資質だが、腰がないというのは不安あるいは存在への否定につながる重大な欠陥である。 容器に腰がないと、手にもって食べることがで |
きない。したがって、車輌シート備え付けのテーブルとも呼べず、トレイと言い切るにも自信のない、あの台に弁当をのせて食べなければならない。しかし、あの台に弁当を乗せてしまうと、人間様のほうから弁当に身を寄せなければならない。背もたれから背中を離し、ひじを腿の上にのせ、あごを突き出し、前かがみの姿勢でこぼさぬよう、ふるえる箸の先に懸命に食物を乗せ、口から出迎えにいかねばならない。そこには人間の尊厳など微塵も存在しない。 もちろん、自分はそんなことまったく気にしないとおっしゃる姿勢軽視派の方々もおられるであろう。それらの方々にはこの場でご退場いただきたい。即刻。今すぐにである。 合理性と効率優先でやってきた結果が何を生み出したか、我々は今一度総括する必要があろう。 そう言えば、昔はもみだしの熱いお茶なんていう風流な物件もあった。ティーパックのお茶をお湯の部分に投げ込み、周囲から容器をもみこむのである。ひとこぶラクダのような形状の容器の小さなフタをコップ代わりにけっこうみみっちく溶け出したお茶を注いでズズッなんて飲むと言うよりはすすったりしたあたりが日本人の身幅に合ったちょうどいい時期だったのではあるまいか。 |
沖縄行1996 →→→back 96 06(1) 2) 3) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
| ウチナンチューはアバウト。 ウチナーに移り住んだヤマトンチューからそう聞いた。田舎のネズミと都会のネズミの話ではない。沖縄はウチナー、本土はヤマト、沖縄県人がウチナンチュー、他県人はヤマトンチューと呼ぶのが沖縄ロコなのだ。 ウチナンチューのアバウトぶりは、待ち合わせに現れるらしい。まず間違いなく定刻に人は集まらない。 定刻の感覚がないからか、沖縄に鉄道は存在しない。太平洋戦争前はあったらしい。しかし、戦後廃線となった。 だから沖縄の移動手段は車だ。バス路線もあるが、皆、自家用車で移動する。高校生になると車を持つのだと言うが、どこまで本当の話か、眉唾ではある。しかし集客商売に駐車場が必須と言うのはほぼ事実だ。京都における学校経営に駐輪場が切っても切り離せないのと同じ話だ(本当の話である。京都の朝、各大学正門は天安門広場の様相を呈すると京都っ子は真顔で言う) 車が錆びやすい。海風が自家用車の最大の敵だ。縦に細長いその国土は台風の波浪が陸地を跨ぎ越して反対側の海にまで届きそうだ。その細長い陸地を沖縄自動車道と国道58号が南北に貫いている。沿道風景には沖縄特有の墳墓が幾度も現 |
れる。かなり立派な石室のような墓だ。 琉球新報と沖縄タイムスが沖縄のマスコミ2大紙だが、その新聞紙面の1ページ全面を訃報が占める。人の死が祭事につながる精神風土があるのかもしれない。 高速道を那覇から宜野湾(ぎのわん)にむかう。周囲の風景がアメリカナイズされてきた。 ベース(基地)の街なのだ。 アメリカ東部の大富豪の敷地のように米軍キャンプが広がっている。幅員も十分な道路をハマーが走る。やがて車は沖縄郷土料理の店へ。 沖縄の酒は泡盛。3年以上熟成させた泡盛を古酒(クースー)と呼び、豆腐ようという郷土食材が、この古酒によく合う。豆腐を発酵させたチーズのような食品だ。甘口・辛口・XO(エックスオー)など品種が幾つかある。サイコロ大の豆腐ようを楊枝の先で極僅か削り取り、泡盛を飲む。旨い。店で食べたその豆腐ようが美味しかったので土産にしようとメーカーを聞いた。 「どこにでもありますよお」 そうかメーカーは一社なのかと思った。帰路、空港の売店に寄った。非常にたくさんのメーカーの豆腐ようが並んでいた。どれが店で食べたものかわからなかった。ウチナンチューはアバウトだということを忘れていた。 |
| 何故だろう。 こういう街は圧倒的に東北地方に多い。自然と人の営みの調和がもたらす凛とした緊張と質朴の美を備えた街、という意味である。 街全体にある種の精神性が宿っているかのようだ。会津や盛岡にも同様の気配が感じられる。北陸だが金沢にも似た雰囲気がある。これらの土地は皆、豪雪地帯であるのが共通項だ。金沢を除けば、周囲を山に囲まれる土地でもある。 米沢15万石上杉の城下町と言うが、何度かの大火を経験した米沢にそれらしいたたずまいはない。南にむかって吾妻連山が米沢と福島間に立ちふさがる。東は蔵王、北西に朝日連峰、南西を飯豊山地に囲まれた盆地のたたずまいこそが米沢の景観である。雪景色の中、周囲の山々の白い頂きを間近に見るとき、この地の美しさに言葉を失う自分がいる。 米沢と言えば、米沢牛。牛肉販売店の2Fがレストラン部門になっている。登起波牛肉店、扇屋精肉店(ミートピア)などがそうだ。店の造りは凝っていない。拍子抜けするくらいに肩肘のはらない店内に、昨今はやりのプロの料理人とは対極にある風情の調理師によって出される米沢牛はしかし端倪すべからざる旨さだ。 米沢の夜は早い。金曜の夜と言えど遊びまわる |
人々の姿はない。静かだ。登起波牛肉店のそばに粉名屋小太郎という老舗のそば屋があるのでどちらかは開いておろうと19時半頃宿を出る。除雪された雪が歩道に作る丘を越えて向かった店頭に「閉店」の看板と「終了仕候」の木札。 商店街に転進。焼肉屋とミスド、ラーメン屋の看板以外は灯を落としている。早い!奈良みたいな店じまいの早さだ。扇屋ミートピアが開いていた。かじかんだ手をほぐしながらほっとする。 すきやきと肉納豆(?!)を頼む。肉納豆は、生肉に納豆とネギを混ぜた、納豆版ユッケだ。これが旨い。 この店、11月下旬に必ずその年のチャンピオン牛を競り落とすそうで、来るなら11月末がいいのだと、カウンターで隣に座った常連の佐竹氏に教授される。氏は、さらに筆者の食いっぷりが気に入ったのか、自分のオーダーした牛タンステーキを半分ほども分けてくれた。そしてレアに焼いたこの牛タンステーキが極めて美味!実はこのステーキこそがここの目玉であるらしい。やはり地のものは地の人に聞けだな。 米沢に40年とおっしゃる氏の佐竹姓から「秋田からですか」と聞けば「会津の出」だそうだ。そうか、関ケ原以前は佐竹は常陸が所領であったわ。支藩か親族であれば会津もありか。 |
| 旅のスタイルは様々だ。風光明媚な景色を巡る観光の旅、旨いモンしか目のゆかぬ食いしん坊バンザイの旅、仲間とワイワイ愉しむ弥次喜多の旅、日常の喧騒から身を置く漂泊の旅。 筆者はたまに列車に乗るのが目的のような旅をする。日常空間からの離脱が動機ではあるが、正直な話、見たことのない車窓、乗ったことのない路線への憧憬もだし難しといった心境からの行動であることが多い。 96年に紀伊半島を一周した。結果としてそうなってしまったが、本来はもう少し味のある旅にする予定だった。目的地を決めず名古屋に出た。その地に住む旧友と遊び、翌日再びひとりで大阪へ。山陰に向かうつもりがなぜか和歌山を目指すことになる。大阪環状線の南端、天王寺から快速に乗車。 和歌山で特急「黒潮」に乗車して終点新宮(しんぐう)まで。紀伊半島の突端ではないが、その界隈だ。JR西日本と東海の境界線の駅である。無目的な乗車を繰り返したため、宿を決めていない。そもそも何処で泊まるかを決していなかった。紀伊水道を眺めているうちに適当な駅で降りればよかったのだが、機を逸した。駅という駅が皆小さいのだ。筆者は基本的には都市部に泊まる癖がある。民宿とか旅館はできれば使いたくないのだ。空は急速に色を失い暗くなりつつある。夜 |
が迫っている。 今にして思えば、白浜か紀伊勝浦あたりで手を打てばよかったのだろうが、結局新宮まで乗ってしまった。日はとっぷりと暮れ宿も決まらず、新宮駅のまわりはヒジョーに寂しい。久し振りの漂泊感が身をつつむ。うら寂しいビジネスホテルで一夜を過ごす。 翌朝、特急「南紀」で名古屋にむかった。グリーン車だった。実はこのときがグリーン車使用の初体験。以後筆者はどんどん堕落してゆく。堕落は快楽の言い換えだ。あ~ラクちんラクちん。しかしこの時はラッキーである。指定席車輌では高校生の団体がワルプルギスの夜を演出している。危なくまきこまれるところであった。 新幹線以外で行き先表示を車内で流すのを見たのもこの頃からだろう。 This is the limited express Nanki No2 bound for Nagoya with stops at Ogush,Matsuzaka,Yokkaich and Kuwana. 名古屋についた。新幹線に乗り、東京へ向かう。ただ、電車に乗っているだけの3日間だった。持参した文庫本を2冊読み潰した。読書に飽きて表示を見る。 We will soon make a blief stop at Shizuoka,After leaving Shizuoka we will stop at Tokyo. Thank you. |
| 「晩白柚」と書いてなんと読む? 果物である。熊本の名産品。 巨大なはっさく、あるいは夏みかんのようなものだ。世界最大の柑橘類。それが「晩白柚」・・・『ばんぺいゆ』と読む。九州縦貫の出発には、西鹿児島駅でばんぺいゆジュースを飲まねばならない。定期を持っていれば、割引価格で飲める、覚えておこう、ってあまり意味はないな、このトクトク情報。 晩白柚は人頭大にまで大きくなるらしい。車内では出張集団であろうか、上役らしい男性が女性社員が語る加納姉妹のバスト話にちゃちゃをいれている。 「加納姉妹の胸って・・・」 女性社員はけっこう楽しそうだ。 「シリコンを入れてるらしいですよお」 すかさず上司がつっこむ。 「おまえはシリコンじゃなくて晩白柚だもんな」 セクハラである。 しかし薩摩おごじょはその程度では動じないらしい。カラっと明るく笑っている。 晩白柚の用例でした、以上。 西鹿児島から川内(せんだい)、水俣、八代を経て熊本まで、エル特急「つばめ」で2時間半。途中、風光明媚な八代海の眺望を楽しめるが約2 |
00キロの距離を2時間半は特急としてはやや遅い。来春、九州新幹線が開通すれば1時間ぐらいだろう。 熊本と言えば西南戦争でも落ちなかった堅城、熊本城がランドマーク。加藤清正の設計である。清正以前、佐々成正を利用して成正と抱き合わせのように反抗勢力を一掃したのは秀吉。これで清正は統治がやりやすくなった。議論好きの土地柄だが男ぶりも要求される。清正はその意味でうってつけの存在だった。それだけに清正後の人事が難しかったが、足利将軍家、織田家、豊臣家、徳川家を渡り歩いた練達の処世術士、細川家が入部する。宮本武蔵も晩年、一種の名士としてこの地で老境の日々を過ごす。仕官を求めて、武技を磨いた武蔵は、しかし平時の行政職を司る高等官としての評価を得ることが適わなかった。食客というか賓客のような立場で九州を回った武蔵。九州はそのレベルでは武蔵に優しかった。 熊本から博多までは1時間15分。途中、松田聖子の出身地、久留米を通る。地味な街だ。次の停車駅は九州の大分岐点鳥栖、大分起点の割に地味な駅。 途中、日が暮れた。博多市街までの車窓は暗い。人家の灯りは絶えて久しい。九州は巨大な自然王国だと気づくのはこんなときだ。 |
鹿児島行2 →→→back 鹿児島行1 2 3(疾風怒涛編) 4 5 6 7
| 10年ひと昔と言うが、5年は半昔か。小学校にあがった子供は6年生になっている。中学1年生だったら高校3年生だ。それなりの時間の経過ではあるな、やっぱり。 鹿児島は5年ぶりだ。前回は宮崎から日豊本線を使って鹿児島入りを果たしたが、今回は空路だ。鹿児島空港から市内へはリムジンバスが小一時間で結んでいる。空港は山間部にあり、市内へは山を越えてゆく。途中峠から見下ろせば、市街の背後に桜島のシルエットが浮かぶ。そういえば、城山公園などに上らねば、繁華街である天文館の界隈では桜島は見えなかったな。 「鶏飯」で奄美の郷土料理、鶏飯を食べる。店は5年前と変わらずそこにあった。しかし、もう一軒のお目当てであった黒豚料理の「黒福多」がなくなっている。記憶違いかと思ったが、そうではない。どうやら近くに移転したらしい。5年という歳月と呼ぶには短かすぎるような期間ですら、街や人は変化してゆく。生活空間に置き換えればあたりまえのことが、なぜか旅先の土地に対して人はわがままな要求を押し付けるきらいがある。(変わってほしくないなあ)というやつだ。今回は店が廃業したのでないと知り安堵する。 西鹿児島駅にむかう。 鹿児島のメインターミナルはJR駅で言えば西 |
鹿児島駅だ。鹿児島駅ではない。薩長は妙なところで歩調をあわせる。萩のメインターミナルもやはり地名そのままの萩駅ではなく東萩駅だ。 西鹿児島駅では来春いよいよ開通する九州新幹線のパブリシティが喧しい。とりあえず西鹿児島-新八代(しんやつしろ)間を開通させるらしい。東北新幹線「はやて」八戸開通に次いで今度は南日本に新幹線が走る。 新幹線が開通すれば現在1時間に1本西鹿児島-博多間を結ぶL特急「つばめ」は廃止されるのだろうか。特急名がついてはいるが、確かに「つばめ」は遅い。鹿児島本線は単線区間も長い。行き違いのための停車時間のロスもある。それ以上に鹿児島・熊本間の山間部を縫うように走る線区では、スピードが出ない。八代に出るまでの「つばめ」はスピードが乗らないこと鈍行列車のようである。 すでに新幹線高架の特徴のある、あるいは見慣れた光景があちこちでほぼ完成に近い姿を見せている。山塊に押し出されるように海岸線を走る鹿児島本線の八代海を望む光景は新幹線からは見ることができまい。「つばめ」が走っている間にもう一度満喫したいものだ。A席(海側)が取れずにD席(山側)であった今回、新幹線の高架を眺めながら、ぼんやりとそんなことを考えていた。 |
| 新幹線、大阪方面、シートは窓際っと(自動券売機でボタンをぽちっ) あ、A席!Eじゃないもの。ああ、もう駄目、絶望的。車窓のつまらなさは筆舌に尽くしがたし。しょうがない、退屈しのぎに車窓の変化をレポでもしよう。と、いうことで今回は「のぞみ」A席の車窓から。 東京駅発車後9分で多摩川を渡河。NECのビルをまきこむように90度の左転進、直角に近い方向転換は高速目的の直線指向が支配する新幹線ではめずらしい。転進後右にバンク、けっこうめまぐるしい進路変更。 鶴見川の狭い川幅を越えてトンネルを抜ければ発車15分で新横浜。 横浜の郊外は丘陵地帯だ。斜面のそこここに時代を経たかつての新興住宅が立ち並ぶ。 丘陵地帯越えに小さなトンネルを6本程度ぶちぬいて丘がつきると相模平野だ。視界がフラットになり、しばらくすると相模川を渡河。車窓の右端から山すそが広がり始める。丹沢山塊の裾野だ。この山塊を越えるのにトンネルを11本。11本目の弁天山トンネルは長い。イトーヨーカドーが現れ発車後30分で酒匂川渡河。 発車30分強で小田原。 小田原城は天守閣を思いのほか近くに、しかし瞬時にしかとらえられない。すぐに連続するトンネル群に突入。小田原をすぎて10本のトンネルを抜けると熱海。7本目が長い。 熱海は出発から35~6分。熱海を越えると再びトンネル群。数は7本。2本目の新丹那トンネルが長い。 三島を通過。出発から40分。 45分で新富士駅、E席ならば富士山の絶景が見られる。E席からの富士の眺めは小田原の手前、相模平野の頃から望むことができる。 新富士通過の約1分後に富士川渡河。再びトンネルの山。 55分で静岡通過。すぐに安部川渡河。並走する東海道線の駅は「もちむね」大崩海岸の松並木を遠望。静岡県は平たい。車窓一面フラット。 1時間で大井川渡河。再び山容いりみだれてトンネルをうがつこと幾たび。 1時間5分で掛川通過。資生堂・丸大食品・サンコー・ポーラ・大塚製薬の工場やR&Dセンターが沿線に立ち並ぶ。東名の沿道だからか。 小さな川を軽々と越え、ふくろい市の袋井メロ |
ンの野立てが見えた後、車窓の視界が開けたそのとき、A席唯一の楽しみ、恐竜を見るのである。1時間6~7分だな。その後、窓外はまたもフラット。 1時間10分で天竜川渡河。 1時間12分で浜松通過。 1時間15分で浜名湖。東海道線と併走。鉄道と自動車道の橋脚が水面すれすれだ。東海道線「あらいまち」を間近に見て同線と乖離。丘陵地帯に入る。湖西市のスズキ自動車の工場が広大な様子。ふたたび車窓を空が大きく占めだすと遠くに高層建築が1本だけ建っている。ユニチカの工場か。 1時間20分で豊橋通過。豊川とその放水路を渡河。またまた1本だけにょっきりとビル、エッソの工場のタワーであろうか。豊橋・三河安城間で海面が広がる。観覧車も見える。海面が陽光を反射し銀面の美しさ。前方からかぶさりはじめた山並みが墨絵のような濃淡のグラデーションを山襞ごとに何段階ももたらし、きわめて絵画的な美しさだ 矢作川を渡河。 1時間30分で三河安城。 1時間40分で名古屋。 名古屋を過ぎると木曽川、長良川、揖斐川を渡河。木曽川・長良川間に岐阜羽島駅。 やがて関ケ原に入る。関が原石材の工場が小と大、2箇所で現れる。やがて小山を回りこむように新幹線にむかってU字の接近を試みるのが東海道本線。この区間、在来線である東海道本線はまるで新幹線とワルツを踊るように何度かの交差を見せる。 関ケ原トンネルを抜ける。ヘイワドーだ。近江に帰ってきたぞ(ヘイワドーは近江近辺のバンタムスーパーだ。名古屋の近辺ならユニーとそのCVSサークルKだな) 関ケ原を越え、近江に入れば京都はすぐ。E席ならば伊吹山・米原・彦根・大津・山科と変化を体感できるがA席はもうひたすら無味乾燥な車窓。そしていつのまにか京都入城。後方の山並みに城郭のシルエット。あれは何城だ? 京都発車後、東寺の五重塔を見たら桂川を渡河。大きくバンク。90度近い進路変更。渡河したはずの桂川と併走し、うやむやのうちに新大阪着である。 ああ、つまらなかった。 |
| どこにむかおうとしているかでその人の趣味嗜好が推し量られるとしたら脇の甘い対応は声望にかかわるというものだ。うかつな選択はできないし、不用意に行き先を明かすわけにはいかない。 新島や倉敷に行くってことを何の屈託もなく言ってのける人はすでに解脱しているな。 今回の物件はいぶし銀の渋みをきかせる「山形」である。これは渋い。苦いくらいだ。あ、舌の両端がしびれてきた。「7人の侍」の宮口精二「荒野の7人」のジェームス・コバーンが好きという人にはオススメだ。しかも今回は渋味の効いた山形の中でもひときわ渋い山寺。 仙山線という仙台・山形間を結ぶ1日5~6本程度しか全線貫通列車のない路線の快速停車駅ではある。 駅前にエアーズロックのような岩山がそびえたつ。1枚岩のようなその岩山のそこここに穿たれた空間に堂があるいは宙空に突き出し、あるいは岩穴に潜むかのように散在する。 山の名前は宝珠山、寺の名前は立石寺。 天台密教の由緒正しき古刹である。 芭蕉が「閑かさや岩にしみいる蝉の声」と一句を詠んだ、その舞台となった寺である。 長い石段が幾重にも続く。拝観というよりはほとんど登山に近い。岩肌をかいこむように設けられたお堂は下から見上げるよりもその場に立ち下 |
界を見下ろしたほうがその荘厳さがいや増すようだ。ちょっと怖い。 山が寺をあらわす意味を持つとすれば、全山が日本的ではない造形美を奏でているようだ。それは前述したとおり下から見上げるよりも、その胎内のような山中から見下ろしたほうがより強く意識される。 ひとことだけ言っておく。足腰のしっかりしているうちに行くべきだ。 山を降りると膝が笑っている。駅近くの小さな渓流のわきにペンションをかねた休憩所があったように記憶しており、そこで休んだ。 畳敷きの、それなりの広さの店内で何を頼んだかは記憶にないが、とんぼが飛び込んできたことが忘れられない。 赤とんぼのようなかわいい奴ではない。入ってきたときはスズメ蜂かと思ったくらいだ。でかい。そしてすごい羽音だ「どい~ん」っていう感じ。そして滞空。「ぶぶぶぶぶぶぶ」ものすごい勢いで飛翔。壁にぶつかる「ばし!」 「ぶぶぶぶぶ、びいいいいいん、びし!ぶぶぶぶぶぶ、びいいいいん、ばし!」 こいつは壊れないのか?ターミネーター?とんぼごときがこんなに怖いとは知らなかった。2メートルほど前でこっちをじっと見つめて滞空する「ぶぶぶぶぶ」本当に怖い。山寺侮りがたし。 |
| 飽きちゃったのである。新幹線。ま、それほど利用しているってわけだからその存在を否定はできないのだが。 沿線風景を眺められるだけでも東海道新幹線はまだいい。山陽新幹線となるとトンネル区間が5割を占める。2002年12月開業の東北新幹線「はやて」は盛岡・八戸間の7割がトンネルだそうである。いったいその間何をしていればいいのか。 今日は「大阪発新幹線の車窓(E席)から」である。E席は東京方面にむかって左側窓際のシートである。今回は琵琶湖・伊吹山・大井川・富士山をキーワードにしてまとめてみました。 琵琶湖は、しかし新幹線からは遥かな湖面を僅かにしか望むことができない。京都を発車し、山科と音羽山のトンネルを抜けると、すでに車窓後方に大津を過ぎている。湖面は僅かに細く望む程度。瀬田で宇治川の源流となる琵琶湖からの注ぎ口を越えてなおしばらく、実は米原までは路線は琵琶湖畔にそって東よりに北上しているのである。したがってそこここで細く長く琵琶湖を見ることはできる。彦根城を遠望するときも視線の先には細く湖面が控えている。車窓の大半を占める存在感を主張できないため、刺身のつまのような位置に甘んじているは残念至極。米原通過時に琵琶湖はここまでついてきたのか、とその長さを多少は実感していただきたい。別にいただかなくてもいいけど。 米原で琵琶湖に別れを告げ、中仙道関ケ原に向かう。周囲の山並みを圧して伊吹山の山様が聳え立つ。標高1377メートルながら近江の象徴となる山だ。季節は秋から冬にかけての姿がいい。周囲 |
の山並みの紅葉を従えて、山頂付近に雪を頂く伊吹山の姿は目に新鮮だ。 関ケ原クリニックの看板で関ケ原を過ぎているのだと認識したあと、車窓は単調な田園風景に終始する。この区間を愉しむには始発近くの車輌に乗る必要がある。関ケ原の周囲の田畑を白いもやが覆っている。朝露が陽光を浴び蒸気となって大気に還ってゆく。この最も基本的な自然現象ですら都市圏に育った人間の目には新しい。 揖斐川・長良川・木曽川と3大河川を越えれば尾張名古屋である。長良川の上流遥かに金華山がサメの歯のような三角形の姿を見せる。山頂には米粒大の岐阜城。長良川と木曽川の間に『鉄道・道路の地元誘致=国会議員の正しい集票還元』の鑑、大野伴睦の岐阜羽島駅を越える。この駅がなければ新幹線は三重を通っていたのだろうか。 名古屋を過ぎ、浜名湖を見た後、新幹線はず~っと静岡県の横断に時間を費やす。長すぎるにもほどがある。新幹線は静岡県の横断が目的の路線である。駿遠三、3カ国を1県にまとめてしまったのはいかがなものか。まあ、区割りすれば車窓が変わり時間が短くなるというものでもないが。 東京到着の1時間前、大井川を通過する。その前に渡河するのは天竜川。大井川渡河後10分強で富士川渡河、製紙工場群の煙突がいかにも裾野という斜面を背景にさかんに白煙を吐き出している。その背後に富士の雄姿が浮かび上がればラッキーである。東京到着の30分前に小田原を通過する。新大阪と同じような新幹線用の開発都市、新横浜を過ぎ、多摩川を越えればやがて列車は東京駅のホームに滑り込むのであった。 |
金沢行(その1) →→→back 金沢行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
| 金沢を歩く。 初めて訪れた1978年以降街に魅せられ81、82、83と3年連続で訪れて以来19年ぶりのまとまった滞在である。99年のゴールデンウィークに無謀としか言いようのない「北陸大返し」をしたが、あれは数に入らない。 駅前は大規模な改装工事中で往時を彷彿させるものはない。かつてそうであったように徒歩で東の廓を目指す。記憶は遠い日の幻燈のように断片的で輪郭が曖昧だ。駅前から武蔵が辻に至る道筋は明らかに記憶と異なる。駅舎が西方に移動したか、大幅な区画整理があったとしか思えない。いくら時が過ぎようともその場に立てば何がしかの記憶が蘇るはずなのに何も思い出せない。金沢を愛する者がこのようなことではいかんといささかの焦燥感が足を急がせる。急いでどうする? 武蔵が辻で繁華街香林坊方面を右に見つつ浅野川にむかう。 途中尾張町の界隈で、不意に感懐が胸をつつんだ。記憶のかなたの霞みのむこうにある町並みと眼前の光景がカメラの焦点のように一致したのだ。ああ、やっと帰ってきた。20歳のあのときたしかに自分はこの道を歩いていた。 それは逆行したデジャビューのような感覚だ。このまま歩き続けていると20年前の自分と今が重 |
なり合うような曖昧な時空のはざまが身をつつんでいる。周囲の光景は変化せず時間の経過はわが身にしか訪れていないかのような感覚だ。 あのとき、この界隈のいずことも知らぬ店でカツ丼を頼み、関東のそれとあまりに違う味覚に驚き風土というものの多様性を知った。 よしよし、いい調子だ。 東の廓の一画、銭湯のそばにある自由軒でハヤシライスを食べる。旨い。カウンターと小上がりのみのこじんまりとした店内を家族で運営しているのであろうか。ファミリービジネスっぽい雰囲気だ。ハヤシライスのドミグラスがしつこくないのは珍しい。ご飯の量に比して微妙に少ないところがミソだな。 このあたりでモードを現在に切り替える。今回は食べまくるのだ。 山口瞳氏のエッセイ「行きつけの店」に載っていた「つる幸」に行く。すごく旨い。滞在中に3回行ってしまいました。和室とテーブル席の個室が数席のみの立派な造りだ。和田氏の原稿とは趣きを異にする。繁盛したのだろう。しかし味に手抜きはないと思う。旨いもの。乙女寿司、若者の多い片町のかたすみの隠れ家的なロケーションにある。すごく旨い。何が旨かったかと言うと・・・あ、いかん紙幅がつきた。 |
| 「どちらからお出でになりましたか」 他県で出身を聞かれれば基本的には県名で返す。和泉とか吹田とかは言わないものだ。「大阪から」これで終わり。大田区とか世田谷とか言わずに「東京から」これで十分。しかもこれで、幾分かの誇らしさを漂わせたりするのが大都市圏の人間の通弊。在所にすらブランド信仰は存在する。 県名で応えず、地名を使う地域がある。まるでワインの原産地証明のよう。行き着く先は村名か? 神戸や横浜出身者は、兵庫や神奈川とは決して応えない。大津も同様。滋賀とは決して言わない。 大津へ何をしに?と正面きって問われれば、ちょっと困る。山科を越えれば京都がある。梅田の隣の中津、新宿の隣の大久保のような位置が大津だ。つまり、そこで人は列車を降りない。 駅前から西に向かうアーケードを散策した。途中、理髪店に入る。夏なのに店内にクーラーがない。狭くて古い店内。冷風機であろうか、四角い箱が足元にむけられる。生暖かい風。 「大津の理髪師」によって筆者の髪型は4半世紀を逆行した。髪は撫で付けられ、ナスカ地上絵のような完璧な櫛目が髪を七三に分割している。鏡の中に見たことのない男がいた。 店を出てしばらく歩いてから、髪をくしゃくし |
ゃにして手櫛で整えた。 アーケードを横切る目抜き通りで鉄輪の制動音がした。道路をレールが走っている。市電が停車したのだと顔をむけた。 そして、錯乱。 目の前に4両編成の電車が止まっている。 道路に電車が止まっている。 歩行者信号は青だから渡っていいはずなのに、思考の糸がもつれてしまった。え、電車が?青だから、でも電車が通る以上踏み切り待ちで、いや、ここは道路で、あれは電車で・・・もう何を考えているのやら。 京阪電鉄の大津線らしい。確証はない。 線路づたいに琵琶湖畔に出る。ショッピングモールの名は「アーカス(A・QUS)」おそらくここが大津のランドマークだ。そのまま遊覧船に飛び乗った。南湖遊覧船のエンジン音は物凄い。話し声など吹き飛ばすような音量だ。琵琶湖大橋で船を降りる。最寄りの駅は湖西線の堅田(かただ)1キロ程歩くことになる。途中、廃園となった遊園地の巨大な観覧車が寂寥としたたたずまいを見せる。堅田から京都に帰った。 それにしても、この琵琶湖。北陸から、中仙道から、多くのルートがこの湖を通る。おおらかなその湖面を見ると、なぜかしら幾分かの湿度が心に沸く。近江というのは日本人の原初の記憶になにかしらのDNAを植え付けているのだろうか。 |
博多行 →→→back 博多行 博多行2 博多行3 博多行4 博多行5
| 何度か訪れることがあってもなぜかいつも乗り換えや、駅構内程度しか歩き回ることのなかった博多。「知人数人に聞く『全国やさしい街』ランキング」で堂々の第1位である。あっぱれ! やさしい街は住みたい街でもある。しかし、博多は日本海気候、冬は寒そうだ。 博多の市域は広い。さすがは九州一の大都市である。地下鉄の上を走る片側4車線の道路にはフェニックスが植えられている。地下鉄空港線はやや北むきの迂回路を描いて中洲・天神にいたる。博多-天神の最短コースではないせいか、地下鉄の上をなぞるように走るこの道も広いわりに寂しい。名古屋と宮崎をミックスしたようなこのコースは街の印象を形成しない。 JR駅には筑紫口と博多口がある。海に面する博多口に市街が広がり、中洲は博多の中心地天神と博多駅の中間点、両者を東西に分断するように流れる那珂川とその分流博多川にはさまれた中州にある。地形がそのまま地名に転じたのか。この中洲の那珂川端から天神にかけてが博多の街の表情を作り上げる。 那珂川のゆるやかな流れをはさんだ街の風情は、人になぜか落ち着きを与える。ネオンも派手だし、あきらかな繁華街の様相を呈していながら癒し系の顔を見せるとは不思議な街だ。 |
適度に広い川幅、そこに満々と満ちながら穏やかに流れる水流、水面と視線の近さ、そして水面の広さに呼応するかのように空も広い。大都市圏に見られる無秩序に林立する超高層ビルが見当たらないためか、ビルに空が遮られないのである。これは道幅の広さ、川を挟んだ空間のゆとりからくる恩恵かもしれない。いずれにせよ、日本においてこのような街は他にない。 川端を歩けば「鰻釣り」が目を引く。「ただし1回で2匹まで」というのは何を狙っての但し書きか?対岸のビル壁面にタレ幕が下りる「幻の巨大鯱しゃぶ食べたことありますか」ない。あるわけがない。いや、博多は面白い。 夜中の12時にケーキ屋がやっている。タクシー代行が多いのも土地柄か。 かつては会員制のラーメン店であった一蘭というラーメン屋は席間に間仕切りがあり、投票所のような空間でラーメンを食べる。追加オーダーは割り箸の袋を使う。なんと袋に追加オーダーが印刷されているのだ。シャイなラーメンマニア、顔を見られたくない芸能人にはうってつけかもしれない。鮪の大トロを使ったネギマ鍋に舌鼓をうち、VESPAというこれまた居心地のいいバーで時をすごせば博多の夜は優しくすぎてゆくのであった。 |
金沢行(序章) →→→back 金沢行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
| 「国敗れて山河あり」というが、誰しも心にひとつやふたつ山紫水明の風景画をかけているはず。生まれ故郷の景色が多いだろうが、別にその画が故郷である必然はない。 「いずこの地もそれぞれ忘れがたく、比較は難しいと・・・ローマです!なんと申しても・・・ローマです。この地を訪れた素晴らしい想い出を私は一生忘れないでしょう」 可憐なアン王女(オードリー・ヘップバーン)がこみ上げる想いを抑えきれずに、最後に本心を叫ぶ。「ローマの休日」である。想い出が埋まっていれば、その土地は十分にマイホームタウンだ。筆者にとってのローマは・・・金沢です。なんと申しましても・・・金沢です。 高校時代、クラブの仲間と訪れたのが金沢だ。筆者にとっての旅人生のそれが第一歩であった。無論引率者のいない旅としてだ。あれは1978年のことだ。その後、暇を見つけては、あるいは暇がなければ無理やりこさえてでも筆者は旅を続けることになる。都道府県レベルで言えば訪れていない土地はない。いずこの地もそれぞれ忘れがたく比較は難しいが、人は初めての体験を貴重なものとして胸にしまいこむらしい。 周遊券がいまの解りにくいシステムになる前、名古屋で東北ワイド周遊券を購入すると東京で購 |
入するよりも有効期間が約1週間伸び、金沢経由で東北入りができた。だから東北に行くのに一端西進し名古屋へ向かう。そこで周遊券を購入し金沢を訪れるのだ(すでにJRに東北ワイド周遊券は存在しない。ゾーンと呼ばれる周遊区間も次々に削られている。どうやらひとつの時代が終わったようだ) 金沢はトーマスマンの「トニオ・クレーゲル」にすっかりはまっていた若き筆者のヒロイックでセンチメンタル、シニカルにして未成熟なメンタリティにジャストフィットしてしまった(カタカナだらけでごめんなさい)犀川のほとりを歩き(本当は浅野川であった。後でわかった。若造のひとりよがりの陶酔などたいていこんなものだ)黒い瓦屋根の峰が続く街並みに魅せられた。屋根の切れ目には樹木の緑が陽光に耀いている。幹線道路を一歩外れると街の喧騒は不意に音を失う。用水路が狭い道の脇を流れ、色香に満ちた静寂があたりを覆っていた。 ああ、いい街だなあ このときの金沢の印象と感想がずっと筆者の心の中に棲みついている。 だから、その後に訪れたいかなる土地もこの想いだけは架け替えることができないのだ。 ま、早い者勝ちってやつだな。 |
| バスの行き先表示に「××駅前」と書いてあっても、そこに鉄道の駅があると思うのは早計だ。ましてや、発車時刻に終われてそのバスに飛び乗るのは危険だ。不用意でもある。視力が落ち「蛸島」と「輪島」の区別がつかないならばなおさらだ。 朝10時前、北陸鉄道バスの金沢発輪島漆器会館前行きの特急バスに飛び乗った。終点のひとつ前「輪島駅前」で降りて「のと鉄道」に乗り変え七尾経由で金沢に帰ってくる。未乗車区間の鉄道に乗るのが目的だ。持参の時刻表を開き、スケジュールをチェックする。12時前には輪島駅前に到着だ。どんなに1日の本数が少ない電車でも夕方には帰ってこれよう。 時刻表の路線図では輪島は能登半島富山湾側の突端にある。12時10分発の電車で珠洲(すず)で乗り換え和倉温泉からサンダーバードに乗る。金沢帰着が16時前。けっこうかかるな、もっと短くならないのかと仔細に時刻表を眺める。ふと気がついた。 「輪島」の文字が少し変だ。滲んでいる文字の輪郭を必死に追う。「輪島」→「輔?島」→「蛹?島」→「蛸島!」蛸島だ!輪島じゃない!輪島は能登半島日本海側の中程にあった。やっちまった!じゃあ、このバスがむかっている輪島駅は? |
駅があれば、線路がある。線路があればそれはどこかに繋がっている。しかし、路線図の輪島に鉄道の表示はない。 バスは日本海を左に見つつ、能登有料道路を軽快に走る。海岸線と並行して長い直線が続く。北海道のようだ。そう言えばこの風景はオホーツクの重苦しさとどこか似ている。みはるかす直線のかなたまで続く波打ち際。白い波が延々と重なり打ち寄せるその光景は荒涼として寒々しい。 やがて、道路と並走する鉄路の姿があらわれる。よく見れば、レールが真っ赤だ。枕木もない。すべての橋やトンネルの入口、出口に「立ち入り禁止」の柵が立てられている。 廃線であった。 小型のクレーンがそこここで作業をしている。あるいは廃線になってまだ間もないのだろうか。「スタンド・バイ・ミー」を思い出す。と、言って歩いて帰るわけにもいかない。終点の輪島漆器会館まで行くことにした。 バス路線を乗り継ぎ、蛸島あるいは珠洲までむかうプランを考えるも、金沢駅に戻るバスが10分後に出る。焦る筆者を地元のオバチャンたちがああせい、こうせいと親切にアドバイスしてくれるが、提案内容を咀嚼できない。残念である。結局来て見てなすことなく帰ったのであった。 |
| 夏の想い出を作っておかないと後悔するので函館に行った。8月最後の日曜日、夏の想い出なのに半袖ではちと寒い。ジャケットを羽織って程の良い気候に北海道の夏の短さを知る。 函館に行けば、朝市だ。北海道だからソフトクリームだ。市電にも乗っちゃう。坂道も登っちゃう。ウニを食べちゃうし、カニも食べちゃう。イクラはどうだ。パティスリースナッフルズのチーズオムレット、サービスでシュークリームまで貰っちゃったぞ。鮭のハラス焼きだ。トラピストバターラーメンは塩ラーメンだ。うはははは。函館山は・・・時間がありませんでした。 あれ?イカを食べ忘れた。 ムキー! 限度を越えた自己解放ほど端から見て見苦しいものはない。ここまでにしよう。 許していただきたい。1泊しか時間がなかったのだ。昼の11時半に到着し、翌日の12時までしかいられない、まさにシンデレラジャーニーなのだ。 朝市を歩く。昼過ぎ、遅くとも2時頃には閉まってしまうので着日が昼前と言うのは幸甚だ。翌朝もそぞろ歩く。 「お兄さん。お兄さん・・・」 市場で掛けられる声が「お兄さん」のうちはま |
だ若い証拠とひとりほくそ笑む。市場の売り子は人を見て声をかける「旦那さん」とか「社長」と言われるようになったら現役引退だ。 かなり観光地ずれした観のある函館だが、さほどの不快感はない。ただし、朝市の食堂など人気店ではたとえ空いていても4人がけのテーブルには座らせてもらえない。座ろうとしても相席を強要される。それも、他のテーブルが空いていてもだ。そういう店もあるし、それはそれでそういうものだと思っていれば何故か許せる。ちゃっかりと言うよりしっかりという感じか。 テレビや雑誌の取材も多かろう。 食べていると店主が電話で「ポジでいいんでしょ。後で若いもの2人で伺いますから」なんて言っているのは、雑誌の編集部に対してだろう。若干の興ざめは否めない。でも、函館は好き。 新撰組副長土方歳三、終焉の地だ。一本木関門で35年の生涯を閉じた。 函館駅からさほど遠くない総合福祉センターの敷地内に、その一本木関門を移築したのか、土方の墓碑とともに静かな佇まいを見せている。会津で近藤勇の墓を訪れたときもそうであったが、今日も日照雨が降っている。筆者の感傷に感応するのか演出過剰気味の自然もまた函館らしいということか。 |
| 何事にも『初めて』は存在する。 『初めて』を経験せずに、経験を積んだ人間は有史以来ひとりとしていない。そして『初めて』の経験で人は失敗をする。しない人もいるけど、そういう人とはつきあいたくない筆者。筆者はかなりの高率で失敗を犯す。 熊本で犯した失敗は、筆者の心に深く刻まれている。 初めてホテルを予約し、宿泊したのは19の夏だった。場所は熊本。駅前にある小さなビジネスホテルである。かれこれ22年も昔の話だ。 予約の電話をするだけなのに緊張で心臓がバクバクした。とにかく一方的に当方の用件を伝えて早く電話を切ってしまいたい衝動にかられる。相手が何を言っているのかよく解らない(聞こえないのではない。内容を咀嚼できないのだ。頭の中が真っ白だからね)フロントにむかうときも緊張を強いられた。もう、こんなことならホテルなんて泊まりたくないや、野宿の方がよっぽどましだ、などとうそぶく若き筆者。思い出すだけでも恥ずかしい。 ちゃんと予約ができていたと見え(あたりまえだ)、キーを渡され、ホッとする。何か失策を犯しはしないかと、ホテルの約款を熟読し始める(何をしているんだか)しかし、これが間違いの元であった。ふと目にとまった一行に『電話料金は1通話10円で計算させていただきます』とある。 ん?1通話10円?・・・つまり何分話しても10円なのか?さすがはホテルだ、電話はサービスなんだ・・・明らかな錯誤である。当時、筆者は1通 |
話とは受話器を上げてから下ろすまでのことだと思い込んでいた。 よ~し、それならば電話をかけねば損だ。と東京の友人に電話をかけまくる筆者。 友達は選ばねばならない。自分より優秀で、つきあうことによりさらに自分が大きくなれる友を持つべきだ。筆者の友人は皆バカだった。 「お~俺。ど~だ今どこにいるか解るか?」「解るわけねーだろ」「フフン!いいか聞いて驚け今な、熊本だ」「なにい?」などとたわいもないヨタ話を続ける筆者。友人どももさすがに不審を感じるらしい。「電話代は大丈夫なのか」「無知蒙昧の輩め。いいか、よ~く聞け。今なここにホテルの案内がある。それを聞かせてやる、いいか『電話料金は1通話10円で計算させていただきます』ってな。ど~だ?」「おお!それはスゴイ」 ・・・ 筆者の友人は皆バカだった。 翌日、チェックアウトする際、宿泊料3500円程度のビジネスホテルで「ずいぶん電話をかけられましたね」と言われ、請求された電話代は7000円を越えていたと記憶している。 もう22年も昔の話だ。駅前は健軍行きの市電が相変わらず弧を描くように走り抜け、城下町の鉄則のようにJR駅前はあいかわらず街の中心地ではない。駅前にあるのはビジネスホテルくれない。あの夏の日の舞台は、このホテルだったのだろうか。22年の時を過ぎ、訪れた筆者の記憶は限りなく淡い。 |


| エンターテインメントが商業主義と結びつき、同義語となってしまったとき、すなわちなにごとにつけ大量という概念を至上の目標とするアメリカ的消費文化が日本にもたらされ、礼賛されたときから、日本人のエンターテインメントはその本質を見失い、あるいは捨てるべきではなかったなにものかを失ってしまったのではないか。京都を訪れると、そのような述懐が脳裏をよぎるときがある。 日本人は決して創造性に乏しい、娯楽下手な民族ではない、という励ましにも似た再認識は京都において強く感じることができる。 逆に京都を創り上げた日本人と「そこそこでいい、ここまでやっておけば、まあ十分」というような自己憐憫なのか客を舐めているのかよくわからない中途半端なクリエイティブを大量に生み出している現代日本人を民族として同一視することは胸に若干の痛みを伴う。 日本人は今日、京都という都を歴史的所産として持ちえたことを誇りとするよりも、救いとすべきなのかもしれない。京都という都市はそれほどの豊穣を日本人にもたらした。そして、おそらくは今ももたらし続けている。 京都の神社仏閣、古来からの構築物のクリエイティブは「完璧」を追求した日本エンターテインメントの精華と言える。庭内の造作の配置、ある |
いはそれを望む屋内の構成、それらすべてに対して何らかの配慮を施し、自然によらざる人工物にして、もっとも自然的な美のすがたを追求し、表現する。一木一草に至るまで細やかな意図と計算がそこには働いている。その造形に費やされた富と時間を想像することは今日、筆者のレベルでは不可能であるが、その投資が膨大なものであろうことは容易に推察できる。それは、商業主義のはびこる近代以前であればこそ持ちえたディレッタンティズムの産物という側面もあろうし、逆に権威主義を徹底的に具現化することに惜しみのなかった為政者の存在を許す時代背景の側面もあろう。 などと、柄にもなく硬質な文章を書いてしまうのも、あるいはこの「紀行」における京都の登場がこれほどまでに遅れてしまったことも、やはり中途半端なことは書かれまいぞ、という筆者の力みようの中心地に京都という1200年の王都が存在するからなのである。 ああ、硬い。硬いなあ。肩がこっちった。 しかし、まあ京都はやはりいい土地であるな。奈良の拘らなさと、細部まで拘りをもつ京都の対比は両都を股にかけて訪れるといっそう際立ち、それがまたたまらぬ愉悦であることに最近気がついたのであった。 |


| 7月末の夏真っ盛り、しかし敦賀は涼しかった。さすがは北国街道における日本海玄関口。 駅前のメインストリートの看板に「JR直流化を推進。敦賀-京都に新快速を」の文字。高松で見た「頑張れ琴電」の看板と似たテイストだ。 「敦賀に行った」と言えば、多くの人から「原発の?」という問いが返ってくるのに驚いた筆者。「いやいや、敦賀5万石大谷刑部のご城下の」と言い返すが、不得要領な顔をされて終わり。それほど無名か?大谷刑部少輔吉継。 秀吉幕下の奉行衆にあって三成の盛名に隠れはするが、島津征伐、朝鮮の役でのロジスティックスを担った有能な軍官僚ぶりをかわれ、秀吉をして「100万の兵を預けてみたい」と言わしめた男である。賎ヶ岳合戦の折、勝家の養子、長浜城主の柴田勝豊を調略するなどの武勲も調略好きの秀吉に気に入られたものであろう。 本能寺の変後、もともと秀吉の居城であった長浜城をよこせと主張した勝家に対し、養子とはいえ勝家との不仲が噂されていた勝豊にならば譲りますと応えた秀吉。北国街道を扼す長浜をおさえ、きたるべき秀吉との決戦に野心満々の勝家、そのむきだしの芸のない要求に対し、勝家ではなく勝豊にならば譲ると言った曲線的な思考法で応える秀吉の器量の差はその時点で両者の帰趨を暗示してはいたが、いざ、勝家出陣のとき長浜を取り戻すべく勝豊に伸ばした調略の手が吉嗣であることが秀吉の吉嗣への信頼の篤さを物語っている。 昭和60年、TBSの6時間ドラマで司馬遼太郎氏の「関ケ原」をドラマ化したとき、大谷刑部は高橋幸治氏が演じた。これが、なかなかのベス |
トマッチ。もともと氏は信長役が好適と思っていたが(実際、何を考えているんだかわからない不気味さと突如、甲高い声で突拍子もないことを言い出す信長の危なさ加減を演じさせたら高橋幸治氏の右に出る役者はいないだろうと、今も思っている。あ、国盗り物語の高橋英樹さんではありませんからね、念のため) それほどの大谷刑部だがハンセン氏病を患う。 ある日、茶会があった。茶会の席上、招かれた大谷刑部が口をつけた茶には同席の者、皆口をつけることがなかった。鼻水を落としちゃったらしい。その茶を全部飲みほしてしまったのが石田三成。大谷刑部、その夜自邸にて声を殺して泣き続けた。 この時の吉嗣の感動が、功利主義が正義であった戦国時代においてはめずらしい友情という絆で吉嗣と三成と結んだ。当時の時代認識では友情などという価値観は存在しない。だからそのような日本語も実はない。 関ケ原の合戦前、家康への挑戦を勝ち目のない戦と判定し、三成に翻意を促す吉嗣。しかしすでに会津の上杉へ(家老の直江兼次も三成と友情らしきものを分かち合っていたらしい)決起の書状をしたためていた三成には説得の余地なし。そうと決した吉嗣勢は、三成に殉じるがごとく西軍に荷担することになる。 まあ、そうした人物像なわけです。大谷刑部吉嗣。いい話でしょう。だから、敦賀は大谷刑部の城下町というわけ。あ、カニの町でもいいか。駅前のモニュメントはどうやらカニのはさみを模しているようだし。 |


| 「シングル2泊で予約をいれておいた××です」 「はい、××様ですね(ぱらぱら(予約台帳を開く音)・・・(かちゃかちゃ(端末をたたく音)・・・××・・・様ですか?」「はい」「・・・(かちゃかちゃ、ぱらぱら)・・・」 「・・・・恐れ入りますが、××様ではご予約は承っておりませんが・・・」 「えっ?!」 嫌なシーンである。ましてやそれが観光シーズンで部屋にゆとりのない時期ときた日にゃあ「嫌さ」は倍増。ワタクシ、旭川で体験しました。 旭川、道内第2の都市、人口は約36万、通称三六街(さんろく)と呼ばれる一大歓楽街を擁する、駅前にワシントンホテルがふたつある街。 「旭川ワシントンホテル」と「藤田観光ワシントンホテル」ま、あとで知ったことだけど。 結局筆者が予約した「旭川ワシントンホテル」はすぐそばにあることを「藤田観光ワシントンホテル」のフロント係りに教えてもらい、野宿はしないですんだ。 JR旭川駅前は駅正面と駅後背のギャップが大きい。正面は北海道第2の都市にふさわしく、ビルが立ち並ぶ。一方、駅後背は恐ろしく何もない。フラットな土地が広がるのみ。かつて九州の大分岐点「鳥栖駅」の巨大操車場前に深夜、たた |
ずんだときに感じた何ものにも癒されることのない寂寥感と同じ想いが胸を去来する。いや、旭川は鳥栖以上だ。だって何もないんだもん、操車場ですらない。 操車場にはカクテル光線を放つ照明塔が立っていたりするのだが(これがまたこれでウラ寂しいものだ)しかし、ここにはそれすらない。つまり夜の帳が下りてくれば、駅後背は漆黒の闇のカーテンに閉ざされることになるのではなかろうか。 富良野線のホームは集線してきたJR各線ホーム群からひとり離れ、100メートルほど先に閑散とした風情でたたずんでいる。きっと富良野に行く人々であろう、数名の人影が見える。富良野にむかう人を見分けるのは簡単だ。なぜか知らないが皆バンダナを頭に巻き、バックパッキングを背負っているから。いいのか?そんな無個性ないでたちで、って感じ。筆者は「北の国から」ファンではないので富良野によってイメージされる共通の記号が読めない。 さて、旭川と言えば腰の強い、表面油ギトギトの旭川ラーメン。滞在中、とりあえず3軒ほどまわった。「蜂屋・青葉・味特」。「西山軒・梅光軒」は休日だったので未消化。旨いと思ったときはいいのだが、そうでないときは1回こっきりの訪店で判断してはいけないと思いました、マル。 |
| 大暑を過ぎた一日、播州姫路に向かった。 在来線の山陽本線を地元では神戸線と呼ぶ。 新大阪・姫路間は新快速で約1時間。夏休み2週目の土曜日、正午。車内はかなり混雑している。大阪で降りた人の数だけ神戸へ向かう人が乗ってくる。乗車率に変化はない。大阪から神戸への移動には下心が同伴する。 若き恋にはロマンチックが必要不可欠な要素だが、大阪にロマンチックは存在しない。赤・青・白の浪速3原色が燦爛(さんらん)し、巨大看板の群れが蠕動(ぜんどう)する。しかも史上最強の生物、浪速のオバハンが闊歩(かっぽ)している。カップルにとってキスするスキもないのが大阪だ。(京都にはカップルのメッカ鴨川河畔がある。神戸はそれこそ全市がそれだ)だから、皆神戸へ行く。 神戸にキスをしにゆく。 刺激を求めて陽気に遊ぶ大阪、ロマンチックな神戸、知性の見せ場、京都。3都はそれぞれの役割を担っている。しかし、筆者は神戸をも越え姫路へ向かう。新快速の終点は姫路だ。 山陽道は古来、大宰府と都を結び新羅・百済・唐からの使節を迎えいれる最大の官道だった。 大和朝廷によって設置された宿駅の数は56。 大化の改新後の行政区、五畿七道は大和/山城 |
/摂津/河内/和泉、そして山陽/東海/東山/北陸/山陰/南海/西海の諸道で、この道はエリアを表すと同時にそこに通じる幹線名ともなった。幹線としての山陽道は唯一の大路であり、東海/東山の両道が中路、他は小路の格付けとなっていた。文化のベルトウェーは山陽道だった。 電車は神戸の繁華街、三宮を発ち、蛸で名高い明石にとまる。明石を発ってすぐ、電車はフロントグラスに明石海峡大橋を映し出した。 でかい。 巨大な橋梁が遮るものとてない明石海峡上をSF映画の背景映像のように聳え建つ。新幹線では山側を走るため、この巨大な橋は遠景でしか捉えられない。在来線はまさにその下をくぐりぬける。見上げるような橋脚は優美ですらある。 かつて山陽道最大の宿駅であった加古川(賀古)を越えると、街は高度を失い急速に低層化する。家々の間隔が広がり始め、やがて隣家と呼ぶには距離がありすぎるほどに離れてゆく。そして家よりも山や森、田が車窓の主役に代わってゆく。1時間を軽く2分ほど過ぎた頃、姫路城の姿が前方に現れた。残念なことに、先ほどの明石海峡大橋がまぶたに残ってしまい、白鷺城の優美さに異論はなくも、構えの大きさにおいて今ひとつとなってしまったのはいかんともしがたい。 |
| 22年ぶりだった。 初めての一人旅は19の夏、九州を目指した筆者の途中下車駅のひとつが姫路だった。あの日から22回目の夏を迎えた。 とりあえず、姫路城へむかう。途中、かつて大手門のあったあたりであろうか、大手前という町名に行き当たる。分譲マンションの捨て看に曰く。「大手前に住まう」 不動産の手法はいずこもかわりはない。しかし、虚栄心のくすぐりが「大手前に住まう」ことなのか。大手前の建物はけっこう古いぞ。ご城下の一等地ということか。しかし徒歩10分程度の賃貸の家賃は3LdKで6万6千円~7万強だ。 姫路城内は、ほぼ記憶のままだった。ただし、当時、外国人観光客はこれほど多くなかったような気がする。て、言うかいなかったぞ、外国人。今や、歩き回る観光客の半分は外国人だ。それも大阪城と違い、アジア系よりも白人観光客のほうが多い。 国宝だけに、城内に空調はない。エレベーターもない。だから暑いし、足にくる。主に暑さのためにへとへとになる。この日、鳥取37.3度、兵庫37.1度。この夏一番の暑さだった。 22年前、九州からの帰路、その日大阪から東京行きの夜行に乗る予定で立ち寄った姫路で、筆 |
者はパチンコをした。そして珍しいことに勝ったのだ。懐具合はその日の夕食と東京から家までの私鉄運賃を残すのみであったので思わぬ雑収入に頬が緩んだ。 北九州ワイド周遊券の有効期限はその日が最後。大阪からの夜行に乗ってちょうど満期だ。 その旅程計画は大阪に着いて驚愕の事実をむかえる。 なんと、乗車をもくろんでいた夜行列車は、運転日指定であったのだ。そしてその運転日は全然別の日。つまりその日は走らない。マズイ!周遊券の期限は切れるし、金もない。筆者は窮地に陥った。 時刻は遅く、列車はすでにない。金もない。時間もない。焦るな、焦るな、と自らに言い聞かせつつも、しっかりと焦る若き筆者。そのとき窮余の一策を思いつく。 「周遊券で往路、復路の深夜国鉄バス利用が可能!」 しかし、深夜バスの指定席券は別途購入しなければならない。金はどうだ? 「ギリギリ間にあう!」 姫路で手中にした臨時収入が筆者の窮地を救ったのであった。姫路での最大の想い出はやっぱりこれだったな。 |
| 大暑を越して間もない一日、近江の長浜に向かった。在来線の東海道本線を地元では京都線と呼ぶ。京都線新快速は新大阪・京都間が23分。かなり飛ばす。時速は100~130キロ。 京都までは茨木・高槻・山崎など、歴史の表舞台に名を連ねる地名がまさに数珠繋ぎだ。 山崎は京都・大阪間にあって、京都の西の防衛ラインとなる。中国大返しを成し遂げた羽柴秀吉と明智光秀の会戦も、江戸幕府軍が東上する官軍を迎え撃とうとして藤堂の寝返りにあったのも、この山崎の地である。どちらの戦も味方の寝返りで勝敗が決した。 羽柴対明智の山崎の合戦では前線基地と先陣を高槻城主高山右近、2陣を茨木城主中川清秀(瀬兵衛)が担った。摂津の国の両将の膝元を電車は過ぎる。 新大阪・長浜間は新快速で1時間26分。夏休み2週目の日曜、着席ができる程度には空いているが空席はない。京都でかなりの人数が降りた。 京都を過ぎて、京の七口のひとつ、東の口、山科を抜ける。大津で琵琶湖が左車窓に姿をあらわす。いよいよ近江だ。近江平野の寛ぎはそれまでの京阪間の狭隘な感覚を解放する。 琵琶湖の大きさは対岸の湖西線からの車窓の方が実感を伴う。対岸が霞んで見えぬほどの巨大な |
湖は、大陸の大河かあるいは海をすら想起させる。やがて、あっけないほど唐突に安土山があらわれる。織田信長の普請による安土城が聳え立った山だ。もちろん、今は何もない。 そして電車は彦根を過ぎ、米原で一部車輌の連結を切り離した後、終点長浜に到着。秀吉が信長に始めて領国支配を許された土地、旧名は今浜。 秀吉は信長の5大軍団の筆頭としてひとことで言えばこき使われた。領国経営に専念する暇は少なかったはずだが「郷のもの」という呼び方で領民の心をとり、年貢を放免した。その後播州・因幡が拠点となったがこの地への愛情の密度は変わず続いた。感傷的な側面もあろうが、北国街道を抑える戦略的要地として天下盗りの重要なポイントであったことが大きかろう。長浜はその後北陸の雄、柴田勝家との戦において前線基地となる。 長浜城は歴史博物館となっている。コンクリート作りで冷暖房完備、エレベーター付だ。この天守に立ち、琵琶湖を望むと、近江の地を中心とした戦国の要地が実は肩をよせあうような意外な近さで隣接しあっていることを実感する。浅井の居城、小谷城が指呼の間にある。姉川の合戦・賤ケ岳の合戦・関ケ原の合戦、いずれも長浜城から5キロから20キロの距離でしかない。歴史を肌で感じる土地のひとつが長浜だ。 |

| 喜多方は『蔵の町』として記憶していた。それがいつの頃からか『ラーメンの町』に宗旨替えをしてしまった。情緒より経済ということか。蔵よりもラーメンの方が観光誘致としてはわかりやすい。空前のラーメンブームにあやかったということもありそうだ。もっともラーメンブームの前にブレイクしたような気もするが・・・ 喜多方は会津若松の北方、磐越西線で6駅ほど、17キロ弱の距離に位置する。快速で16分、各駅停車でも30分強でついてしまう。 しかし、この17キロがことのほかよろしい。 ディーゼル機動のローカル線が会津盆地の田園をのびやかに走る。 野焼きの季節には夕なずむ薄暮の中、盆地の低空をなめるようにたなびく白煙が外輪山を淡い灰白色にかすませる。車窓からうかがうその光景は、これが日本の原風景であるかのようなのどかさにつつまれている。 町の目抜き通りは駅前ではない。JR喜多方駅頭は、多くの地方都市(というほどの市域でもないが)と同様、実に殺風景でよろしい。 町内観光用の馬車が人待ち顔でそこだけ景色に似合わぬ色彩感覚を放っているのもそれなりの風趣がある。その7年後、この光景は沿道に林立するラーメンの旗差物にとってかわられていた。 |
駅前ロータリーを直進した後右折「支那そば源来軒」の先を左折すれば喜多方の中心地、本仲町界隈に出る。蔵を模した喫茶店や漆器店、素朴な食材店などがごく自然な営みを続けている。 唯一の目抜き通りを横切るわずか2、3メートル幅の道路にも信号がかけられている。信号が赤に変わり、人々が立ち止まる。道の左右を見渡すと視線を遮るものとてない一直線の細い道をむかってくるものの姿はない。しかしこの2、3メートルを横断するための信号が赤である以上、断固として遵法し、信号が青に変わるのを待つ。人々の顔に眉間に皺よせるいらだちは伺えない。赤だから待ち、青になれば渡る、そうした自然な自己規律がいっそ清々しいほどに美しい。ここが会津武士の土地であることを思い出す。 桐工芸がさかんな土地柄である。下駄の原木を積み上げた工房が蔵の間に垣間見える。昔からそこにあり続け、それが永い歳月を経てきたということに何の気負いも感じられない風情がある種の凄みを放つ。古都京都は人々の営為により1200年にわたり磨き清められてきた珠のような澄み方をした街だが、この東北の草深い一集落とも言える町には、手もかけずに放置しておいた木彫りの彫像が不思議と古錆びた深い光沢を放つようになったかのような重厚さがある。 |
| 逃亡者は北へ向かう。南へ向かう逃亡者はいない。まっとうな逃亡者は南へなどという了見は決して起こさない。ストイックなヒロイズムに肩までつかって芯までセンチメンタリズムを染み込ませるには北でなければならない。南は駄目。まぶしすぎるし、暑すぎる。自然も人も。 旅の漂泊もまた必然のように北の大地に打ち寄せられてゆく。 北の大地にはすべてを受け入れてくれそうな母性がある。こんな俺でも受け入れてくれそうな何かがある。だから北海道。しかも、やはりここですね。オホーツクを望む町、網走。 今、網走で思い出すのは網走川。そして短く少し寂しげな300メートルほどのアーケードもない商店街。街路と街路を結ぶ怪しげなブロック、まるでシカゴかピッツバーグのダウンタウンのよう。行ったことないけどピッツバーグ。 きっと降雪で潰れてしまうからアーケードなんてかけないんだろうな。 ノワール調のつかみは、やはり土地柄のせいか?網走と言えば映画『網走番外地』 しかし筆者は見ていないし、興味もない。だからこの地と高倉健はイメージの上で重なりあわない。網走刑務所にも行かなかった(健さんが北海道のイメージってのは確かにあるんだけどね。邦 |
画出演近作のほとんどは北海道が舞台ではないんでないかい?『幸せの黄色いハンカチ』『遥かなる山の呼び声』『居酒屋兆次』『鉄道屋』みなそうだべ)。 北海道には人をして感傷的にならしめる何かがある。その感傷的な憧憬の念は、広大な自然を前に自己の矮小化を認識したすべての人に現れる症状だ。 社会的な生命体である人が、その身にまとうすべての衣をはがされ個に帰る心もとなさ。北の大地は意図せずにそれを強要する。 虚飾や権威といった衣を剥奪された裸身の自身の姿に対する愛惜が、北海道という大地に投影される。虚心坦懐という言葉はこの土地にいる限りは有効だ。あまりに広大で、とっかかりのない自然は当初、人の心を饒舌にさせる。だが、やがてその饒舌に疲れた心は再び沈黙する。 などということを思いつつ、ビッグママとでも呼びたくなるような、北海道という土地が人格を持ち、そこに現出したかのような豪快なママの店「志帆川」で味噌とバターと牛乳で作られた特製「網走鍋」の旨さに、やっぱり自然と言っても、食べてナンボのものだな、などと胃袋で納得するのであった。 |
| 矢も盾も堪らず、汽車に飛び乗りたくなることがある。新宿駅7:00発の特急スーパーあずさ1号で上諏訪にむかうことにした。飯田線の踏破が目的だ。豊橋経由で東海道線、小田急で帰ってくればいい。 新宿駅みどりの窓口でチケットを買う。係員に満席と言われた瞬間、キャンセル席が発生、その一枚を買うことが出来た。ラッキィ。あずさは超人気路線。ウイークデイならともかく休日に飛び込みで当日券など取れないものと思ったほうがよい。 山国を快走するスーパーあずさ。 車窓は『無尽会の予約承ります』の看板を映し出す。韮先のあたりか。「無尽会?」 上諏訪で降りる。心なしか涼しい。街をぶらつく。裏通りでは剥き出しの用水路が流れている。東京ではすべてが地下に沈められ、ふたをされてしまった。用水路なんてもはや、死語だろう。流れる水が清んでいる。鯉まで泳いでいるではないか。 静けさが街全体を覆っている。時間の感覚がせわしない東京とは異質だ。マクドナルドでさえ、朝10時からの営業だ。 中央線各駅停車9:40発で上諏訪を離れ、岡谷へ。飯田線、岡谷発天竜川行き、2両編成、 |
トイレ付に乗車。登山姿の客が目立つ。発車までの30分ほどの間にあずさ号が3本止まる。中央線特急はドル箱路線だな、きっと。あずさが止まるたびに登山姿の客がホームに増えてくる。立ちが数名出る程度だが思ったより客が多い。 汽車は岡谷を発車し辰野からいよいよ飯田線に入線する。駅数は多いが乗客は少なく降客が多い。車掌がホームで降客の検札をしている。駅ごとに前へ走り、後で乗車し、忙しいことこのうえない。検札とドアの開閉すべてを一人でまかなっているようだ。次駅の出口の場所によって、事前に前に行ったり、後から乗り込んだりしているのだ。伊那市でかなりの乗客が降りた。登山客は駒ケ根でどっと降りる。駒ケ岳ゆきのバスはいっぱいだった。前のシートに足を投げ出して座ったのは何年ぶりだろう。でもいささか尻が痛い。 飯田線各駅停車の旅、景色がいい。車窓は山々をバックに寛闊に広がる野と旺盛な夏草の繁茂する沿線風景を大きく切り取って写しだす。駅のそばでは、思いのほか線路に近いところに家があったり、沿道が寄り添ってくる。ローカル線の良さであろう。『農免農道』の標識が見える。「農免農道?」 |
| 飯田線各駅停車の車中、オバチャンの大声に囲まれていた。会社の掃除のオバチャンと同じイントネーションだ。オバチャンは甲府の出身。 「だけんど、だけんど」と「なら、だら」のオンパレードだ。 掃除のオバチャンに囲まれて八方から話しかけられている絵が脳裏をよぎる 飯田で降りる。街をぶらつく。思いのほか大きい。地方都市の街の大きさは聳え立つビルの高さによることもあるが、広さによることの方が、実感を伴う。飯田の商店街と目抜き通りはいくつかの街区にまたがり、結構広い。街のつくりはJR駅が山へ連なるゆるやかな斜面の中ほどに位置し、商店街はどこまでも続くかに見える下り道に沿っている。途中、神社へ通じる大きな参道が商店街を横切り、なかなかの街だ。 今日は街を上げてのお祭りらしい。商店街の飲食店は休みが多い。縁日の屋台がずらりと並んでいる。ミスリンゴの発表もあるらしい。人形の街飯田で人形フェスティバルも催されているとのことだ。人形の街なのか、ここは。 飯田線の駅数は非常に多い。各駅停車で走破しようとしたが、さすがに尻が痛い。日和ることにした。 飯田発豊橋行きの特急伊那路2号が入線。ワイ |
ドビュー車両だ。指定席を買ったが、自由席がガラガラ。セミコンパートメント指定席がある。かこってるだけだけどね 伊那路2号は豊橋行きなら、右側席の方が眺めがいい。指定席は左側。よくある話。自由席に移るのも悔しいなあ。 甲斐武田と三河徳川の国境争いはどのあたりであったのだろうか?飯田を出て、天竜峡界隈を走っている間、空は薄暗くなり夕暮れを感じさせる暗さに覆われたが、三河の野に出ると夏の日は傾きを知らず、明るい田園風景が広がっている。ああ、山国の人はこの野を求めていたのだろうと考えさせられる変化だ。 豊橋からこだまに乗る。尻が痛いのでグリーン車にする。無理がきかなくなってきたなあ。2F建て車輌だ。通過やすれ違いのひかりやのぞみの屋根が車窓の下をかすめる程度。ああ、高いんだと思うと見晴らしもいいような気がしてくる。浜名湖の上のちぎれ雲が手に届くかのような低みに漂う。 小田原で魚と肴にビールを2杯。常連のいる小料理屋。扉を開けると、好奇の目の砲列にさらされた。 小田急はロマンスカーで帰宅。充実の1日であった。翌日は疲労でダウンした。 |
高松行 →→→ back 高松行 高松行2 高松行3 高松行4
| さぬきうどんがブームなのか。 火をつけたのは「恐るべしさぬきうどん」という地元出版社発行のさぬきうどん探訪記? 出版界ほど二匹目のドジョウを安直に狙える業界は少ない。雨後の筍のごとく類似企画の本がジャバジャバ出た。ちょっとうかれすぎ。 とても人様からお金をとる売文とは思えないものもある。目に余る自己解放ぶりだ。 『いただきま~す』『う、う、うま、うま、うま、うまひゃひゃひゃひゃひゃ~!!』 何だ!この『うまひゃひゃひゃひゃひゃ~!!』とは!うどんぐらいで情けない声をだすんじゃない!!(ああ、中島らもさんごめんなさい) さぬきうどんはなんと言っても安い。100円~300円くらいで食べられる。ラーメン探訪に血眼の東京ラーメンマニアは高松でうどん探しもすればいい。安いしうまいが、旅費はかかる。 出張で高松を訪れたのは今をさること14、5年前。案内されたさぬきうどんの店、入り口にずらりと並ぶ大、中、小のうどん玉の群れ。その隣に「天ぷら」「きつね」「コロッケ」だのが並んでいる。順路にそってトレイのうどんにトッピングを次々と放り込んでゆく。順路の終点にレジがあり、そこで合計金額を支払う。つまりカフェテリ |
ア形式。うどん店なのにカフェテリア。つゆはなんと客席前の銭湯の湯だし口のような蛇口からかける。 その後さぬきうどんと言うと、あのカフェテリアの情景が蘇るようになってしまった。舌の記憶はあてにならないが視覚の印象は驚くほど色褪せしない。 ゴールデンウィーク明けの1日。大阪在住という地の利の良さを利用して高松まで2時間程度のセンチメンタルジャーニーを敢行。かつての銭湯のようなうどん店は今もあるのだろうか? ブラリと高松へ瀬戸大橋を快速マリンライナーが走る。美しい橋はその橋を使っていては見ることができない。エッフェル塔を見たくない建設当初のパリッ子がエッフェル塔で昼食を食べたのと同じ理屈だ。なにそれ? 高松市内、中央通りぞいにアーケード街が続く。あちこちのうどん店にかかる「セルフ」の文字、ああ、あのカフェテリア形式はセルフと呼ぶのか。結局、昔日の店とは出会えなかった。 うどんに思い入れの強い人は郊外のそこここに点在する製麺所が運営する店に行くと良さそうだ。うどんは生ものなので午前中に行かないといけないのだと言う。わざわざ行くか、都合良く行くかはともかく覚えておくといいかも。 |
| 四国という土地は若いうちにはその良さがわからない。わからないから足がむかない。旅のプランを練る際、真っ先に切り捨てられる選択肢が四国、いや選択肢にすらのぼらない可能性がある。つまり無視。 「お遍路さん」のイメージが若者には抹香臭い。四国と言えば、そろそろお迎えが来る頃になってから伺うところ、だから今はパスね。僕は北海道、私は九州、沖縄。遠出できなきゃ京都か金沢・飛騨高山と選定作業が進んでゆく(あ、海外が普通か)何とか上位にランクインするのは坂本竜馬を輩出した高知ぐらいでは。 これだけ、あまり足のむかない四国にあってさらに陸の孤島のようなロケーションが宇和島への訪問を遅らせる大きな要因となる。 宇和島と言えば松本清張の「砂の器」と司馬遼太郎の「花神」を思い浮かべてしまう筆者。 「砂の器」では、東北弁が捜査のキーポイントとなっていた。伊達家が江戸期に東北から移封されたため、宇和島が西日本では珍しい東北訛りのある土地だということをこの小説で印象づけられた。「花神」では大村益次郎が宇和島の地に請われて訪れたことを知った。蒸気船建造の任にあたるためだ。中学高校という多感な少年期にうけた印象というのはなかなか揮発しないものだ。しか |
し、少年期・青年期を越え、壮年期となってやっと宇和島を訪れるようになれば、心(ロマン)よりも体(胃袋)だ。宇和島の食文化は筆者の胃袋と味蕾にジャストフィット。 まずは「鯛めし」。「鯛めし」に二つの種類あり。丸々一尾の鯛をのせて炊き込み御飯とするのが「徳島方式」。鯛の切り身を生卵と甘辛のだしにつけてご飯にぶっかけて食べるのが「宇和島方式」宇和島の鯛めしは家でも簡単に真似ができるのがいい。 「あげまき」は蒲鉾を油揚で巻いた鳴門巻きのような食べ物だ。これが旨い。酒にもあうが小腹が空いたときのスナック代わりにもなる。 「じゃこ天」はさつま揚げのことだが宇和海で獲れる小魚を骨ごとつぶしていい塩梅に味付けしており、純粋なさつまあげとは趣きが異なる。 「さつま汁」は鯛のすり身を甘めの味噌タレに入れ、それをご飯にぶっかけて食べる。とにかくぶっかけて食べるのが多いのは、漁師や海賊の多い土地柄であったせいなのか。 魚のそぼろを紅白にして卵そぼろやネギ、蜜柑の皮?などを麺のように細切りしたコンニャクにのせる「福めん」など宇和島の郷土料理は個性に富んだラインナップだ。個性的にしてなお旨い、それが宇和島料理。 |
稚内行 →back 1稚内行 2望郷編 3徘徊編 4旅愁編 5追憶編 6追憶編2
| 北海道の最北端、稚内。 8月の末だが、肌寒い。北国の北辺の街、国境の街でもある。かつては樺太(現サハリン)へ渡る定期連絡船の基地として繁栄した街だ。 宗谷本線、天北線が大正末期にはすでに開通、北の要衝への動脈となっていた。定期連絡船は鉄道連絡線として函館から樺太大泊までを鉄道で繋ぐ一端を担った。 戦後、樺太はサハリンとなり、宗谷海峡は鉄のカーテンに閉ざされる。稚内の繁栄は歴史の1頁となった。天北線もすでになく、北海道を縦横に結んだ旧国鉄の線路網はその多くが廃線となり歴史的な使命を終えた。 筆者は往時の稚内を知らない。しかしこの土地に漂うある種の寂寥感は観取できる。それは源平の昔から言い慣わされた「栄枯盛衰」を、それほど古錆びてはいない歴史という後知恵の視点で俯瞰した結果ではある。しかし、あきらかな物寂しさが確かにここにはある。 北辺の寂しげな街並みに不釣合いな近代的高層建築が稚内港の袂にそびえたつ。それが全日空ホテル。客室から稚内港が見渡せる。潮騒プロムナードと呼ばれる豪奢な防波堤に繋がるドームも見える。樺太はこの海の彼方にある。停泊中のフェリーは利尻行きだ。これが大泊へむかうことは絶 |
えてなかった。近年、民間航路で若干の往来が復活したらしい。 宗谷岬は稚内から若干の距離がある。日本最北端の岬からの眺めは筆者の予想に反して広くておおらかだ。海岸にむかってなだらかな階段が続き、大河の河岸にうちよせるようなたおやかな波がその上をあらう。あいにくの雨。日露戦争時、海軍が建てた望楼も雨に濡れている。 「日本最北端到達証明書」を「日本で一番北の店」の柏屋で購入。さらに最北端の郵便局の投函証明やNTTのスタンプだのを押しまくっていると見事に台無しになった。よくある話ですよね。 稚内と言えば利尻のうにだ。時期的には旬のギリギリのタイミングであったらしい。寿司屋の大将が教えてくれた。抜群の旨さ。身がプリプリして甘みがたっぷり。いやあ極楽極楽。 名物と聞く「たこしゃぶ」も頼もうとしたら「やめときな」の一言。水だこは活きのいいところをお造りで食べるのなら旨いが、たこしゃぶのために冷凍してスライスしたものなど食わないほうが良いのだと。「まあ商店街のつきあいでメニューは置いているけどね。うまいもんじゃないよ」との弁。いい大将だなあ。また必ず寄らせていただきます。日本最北端の地酒「国稀(くにまれ)」もキリッと辛口でなかなかいけました。 |
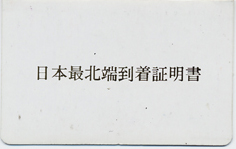
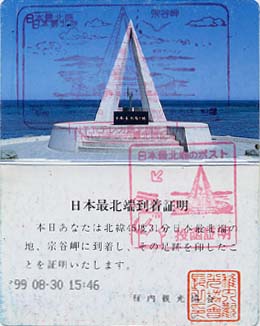
| 夏の思い出を作っておかないと後悔するので犬山に行った。本当は郡山経由磐越西線で会津若松へ行き、只見線・上越線・飯山線・篠ノ井線を乗り継ぎ松本経由中央線で帰ってくるという計画だったが、おりあしく甲信越に大雨。只見線、飯山線が不通という憂き目にあう。しかも前夜の酒が残って体調がイマイチ。皆さん、旅立ちの前日に深酒はやめましょう。おかげで夕方6時に家を出るはめに。東京駅で新幹線に飛び乗った。 8月4日の土曜日、新幹線の車窓は大輪の花火を映し出す。その日2つの河川敷で花火大会が催されていた。初めての光景。車窓のむこう、闇夜の彼方に浮かび上がる華やかな花火の群れに目を奪われる。 名古屋で一泊した翌日、名鉄で犬山城に向かう。最寄り駅は犬山遊園駅。新名古屋駅から急行で約30分。住宅地を貫く通勤電車という感じ。 犬山を初めて訪れたときは車だった。橋の上でバックミラーを覗くと背後から電車が同じ橋の上を追っかけてくる。車道に線路が乗り入れているのだ。あれにはたまげた。 犬山城は旧城主成瀬氏が保有する日本ではおそらく唯一の個人所有の城。戸主と言うより城主というわけ。しかも国宝指定を受けている。木曽川河畔のラインシュタイン城みたい。 |
暑い。汗が止まらぬ暑さに豪雨のような蝉時雨を浴びながら天守に辿りつく。 天守閣は外装三重、中四層の変わった造りだ。つまり見かけは3階建てなのに実は4階建てでしたという仕掛け。地下2階が入口で天井はかなり低い。階段のステップは足をまっすぐに置けないほど狭い。そして場所によっては階段と言うよりもはしごと言ったほうがよいほどの急勾配。階上への間口も狭い。彦根もそうだが現存する古城はどれも戦時むけの実用性で装われている。最上層には低い欄干つきの狭い回廊がめぐらされており水はけのためか外側に低く傾いている。木曽川沿いの面などあまり端に近寄りたくない気分。しかし眺望の良さにたたずむことしばし。 帰路は新幹線のぞみ500系。この車輌はかっこいい。ジェット機のようなシルエットに家族旅行の子供達が歓声をあげる。航空機との集客合戦を勝たねばならないJR関西の開発だけあってこいつは300キロで走る。JR東海は東海道新幹線がドル箱のため高速にこだわりがない。関西との共同開発700系は250と300の間をとって275キロといういかにも日本的おとしどころに満ちた設計。もっとも500系は高速対応の流線型を完成させるため運転席のある先頭車両は、客席数をかなり犠牲にしている。あ、どうでもいいことか。 |
仙台行 →→→back 仙台行 1 2 3 4(2006) 5
| 杜の都、仙台。 東北第一の殷賑はどこか東京っぽい。そう思っているのは自分だけか。 東京から新幹線でかっ飛ばして2時間弱(のぞみを除く)西に向かえば名古屋、北に向かえば仙台。時間軸では等距離にある名古屋と仙台だが、何故か仙台には名古屋を訪れたときに感じる「遥々(はるばる)」感がない。 仙台には「ちょっと新宿へ買物に」出てきましたというちょっとそこまで感が濃厚だ。どこか隣町のような気安さがある。 訪問回数の差ではない。名古屋の方が訪問頻度は高いのだから。 駅前に大名古屋ビルヂングという反則技的ランドマーク(本当か?)を配する名古屋が印象づけという観点において有利なのは当然と言えば当然だが、どうもそれだけが理由ではなさそうだ。 仙台は地場感が希薄。 どうもこれが理由らしい。 「伊達男」の語源を生み、天正の少年使節を送るほどの独自性を持った伊達家の江戸期の藩政はしかし基本的には農本主義に終始した。信長の時代から商業資本の集積が都市機能の中心となった名古屋との違いはそんなところにあるのかなどと思ったりもする。 |
商業資本が都市の顔の一面を作るとすれば、おそらく明治維新の後、その普請の強化を始めた仙台は名古屋のそれとは年季が違うのであろう。地場感の希薄さは、商業資本の蓄積が後発ゆえの擬似東京化にあると見た。 とは言え、筆者の仙台好きはそのようなことでは左右されない。 東北に向かうとすれば、とりあえずは仙台まで。これが筆者の基本パターンだ。 北に盛岡へ向かう東北本線・新幹線、東へ塩釜・松島へ向かう仙石線、西には山寺・山形へ通じる仙山線、常陸に繋がる常磐線など四通発達した交通の要衝として仙台は非常に便利な位置にある。 「遥々感」がないため、気楽に訪問できる。少年期に抱いたなんとなく冒険心をくすぐる隣町への憧憬のようなものがそこにはある。 初めて仙台を訪れたとき、杜の都をイメージしてか盲人用歩道路の凹凸のあるプレートが街中緑色なのに感心した。緑と言うよりは翠と書いたほうがしっくりするか。 都市全体をコーディネートする感覚はおそらく東京では考えられない。センスの良さに驚いた初体験の印象がこの街への好感度を高くしている。 |
仙台行(食いしん坊バンザイ編) →→→back 仙台行 1 2 3 4(2006) 5
| 仙台は食のパイオニアでもある。冷やし中華や牛タン、笹かまぼこは仙台が発祥だ。 牛タンの老舗「太助」(でも戦後生まれ)では蟻塚のように山盛りの牛タンを次々に焼いてゆく。店内のメニューはおそろしくシンプル、牛タンとテールスープ、麦めし、あとはビールと日本酒としか書いていなかったような気が・・・しかしオーダー内容はそれ以上にシンプル。酒を飲むなら「おさけ~」食事のつもりなら「しょくじ~」2通りの掛け声しか行き交わない。 牛タンは肉厚で東京のひらひらしたそれとは似て非なる地味がある。旨いなあ。それにしても牛タン専門店「新宿ねぎし」の仙台店があるのはちょっと不思議。発祥の地へ逆進出ってことか? 牡蠣(かき)を食べるのは「かき徳」、かき豆腐がなんともいえない。 なぜか秋田風のおでん「おでん三吉」の親爺さんは初めて訪れたときから20年、久し振りに店に入れば姿が見えない。そろそろ危ないのかなどと思い、ふと客席の奥に目をやれば若い女の子に囲まれて相好を崩している。とほほ、今も元気でいるのだろうか。 瓶の口にレモンをさして呑むコロナビールの作法を知ったのもなぜか仙台。メキシコ料理の店「ぺぺ・ゴンザレス」でのことだ。 |
大学卒業後、就職した飲料メーカーで問屋の「廣屋」がコロナビールの輸入元だと知ったとき、なぜか仙台の夜が思い出された。ノスタルジックだなあ。 笹かまぼこはイロモノが好きだ。鐘崎の「いぶり笹」。桜チップで焚いたスモーク笹かまの中にチーズやサラミ、わさびチーズがはさまれている。土産として持ち帰ろうとしても車中で食べてしまうのでなかなか無事に家に辿り着かない。 車中といえば、伯養軒の「しゃけはらこ飯弁当」筆者にとっては崎陽軒の「シュウマイ弁当」とならぶ駅弁界の飛車角的存在だ。鮭の切り身を炊き込んだごはんにイクラと鮭の切り身をのせた逸品。 飲料メーカーから転職した今の会社の仕事で仙台を訪れたのは比較的最近だ。同行のMと尻の座りのいい寿司屋を探して町を徘徊した。 やがて見つけたそれはアーケード街にある「喜樂寿司」仙台で魚を愉しむのはここに決まり。尻のすわりの良さはさすがは隣町感あふれる仙台ならではって勝手に決めるな。ネタも新鮮、客あしらいもうまい。しみじみと腰がすわるなあ。 Mはもうかなりの御馴染みさんらしい。滅多に暖簾をくぐれない筆者の位置付けは「Mさんの先輩さん」なのである。 |
徳島行 →→→back 徳島行1 2(風雲帰阪編) 3(寄り道編)
| 徳島と言えば、阿波踊り。踊る阿呆に見る阿呆同じ阿呆なら、でも、できません阿波踊り。 阿波踊りに限らず踊りは無理、だって恥ずかしいんだもの。学生時代に社交ダンスを習っていました(ああ何故?)抹殺したい過去があるとすればまさにこれがそれ。阿波踊りもワルツもタンゴもチャチャもパソも皆同じ。 文科系の人間に踊りは無理。体質があわないんだってば。自意識過剰の無駄遣いだな。誰も見てないって、笑ってません。そう言い聞かせてもやっぱり駄目。だって笑われてるもの。 さて筆者はこの日、高知から徳島にむかった。 高知駅を朝早くに出る「しまんと2号」は発駅では空き席が目立ったが阿波池田に着く頃にはほぼ満席状態。勤労感謝の日をはさんだ連休のせいだろうか。阿波池田で特急「剣山(つるぎさん)3号」に乗り換えいよいよ徳島に向かう。 指定席が先頭車両の先頭座席15番A。これはついている。特急「剣山」の運転席は進行方向左側にボックス席のように造られており、右列先頭席の筆者の眼前は列車のフロントウィンドウになっている。徳島線、単線の車窓を堪能した。まるで小学生だなこのメンタリティは。 阿波・・・「土佐日記」の昔から海賊のメッカとして勇名を馳せた。海賊はやがて大名の軍事力 |
として水軍となった。紀伊水道と鳴門海峡に臨むこの地は筆者にとってはなよやかなイメージが強いが、これは大きな誤解なのかもしれない。 県庁所在地だけあって、街は程よく大きい。飲食店も多い。古刹、瑞厳寺を拝観し反対側の徳島城博物館に向かう。小山の上にある城址を見ようとしたがアシナガ蜂が哨戒飛行と威嚇をしているようだ。怖気付いて登山を中止。 日本料理「弾」のランチメニュー海鮮丼に舌鼓をうつ。極めて美味。そして夜は「栄寿司」へ。 筆者はこの「栄寿司」が大好きになりました(小学生みたいで申し訳ない)鳴門の小鯛の一夜干しは肉厚で醤油不要の旨さ。たちうおのたたきだの火であぶってから出される穴子の握りだの、鯛の皮のサービスだのどれもちょっとした感動を覚える小品の数々。むらさきうにを潮であらってあしらわれる軍艦巻きなど醤油をつけずに食べるのだが、あのようなうには初めての経験である。一見の窮屈さなど微塵も感じさせない客あしらいもよく、阿波の夜はふけてゆくのであった。 そして美味い寿司のあとは徳島ラーメン。ラーメン「東大」に寄ってご当地ラーメンを満喫。 甘辛味の豚バラ肉、かなり色の濃いしょうゆ味スープに直麺、生卵はただでいくらでもトッピング可能。OKですね。 |

| 納沙布岬と野寒布岬を地図で指し示しなさい。 「えっ?!」 ふたつ?ふたつですか?のさっぷみさきってふたつもあったけ? 指が北海道の上をさまよう。ましてや5秒以内で答えなければ死刑だなんて言われたら頭の中は真っ白。何を血迷ったか「ここっ!」って知床あたりを指差したりして即刻死刑。皆さんはどうです? ついでに積丹岬と襟裳岬を指し示しなさい。って日能検の額面広告かっての。 納沙布岬(のさっぷみさき)は根室の先端 野寒布岬(のしゃっぷみさき)は稚内の先端 東と北にわかれている。皆さんわかってました?あ、わかってた。じゃあいいや。 日本最東端の納沙布岬まで約20キロの町が根室。8月下旬のウイークデイ、釧路から国道44号線を一直線に東進、根室を訪れた。海から吹きつける強風に飛ばされまいとひっそりと地に伏せているような町並み。静かで寂しい町並みだ。 駅前の喫茶店でご当地名物「エスカロップ」を食べる。長崎が「トルコライス」なら根室は「エスカロップ」だ。 バターライスの上にひらひらの薄切りトンカツ、ドミグラスソースがかかっている。添えもの |
のポテトサラダがいやに旨い。本体はほっておこう。メニューに書かれた「ホットパイン」の文字が目に飛び込む。得体の知れない懐かしさを覚えオーダー。濃縮パインジュースをお湯で割ったのだろうか。舌がとろけるどころか腐乱しそうな甘さ。うわ~。しかしなぜか何もかもみな懐かしい雰囲気におされてOKサインを出します。 納沙布岬から北方領土を望み、意外な間近さに驚く。旧ソビエトの監視塔やレーダーサイトを見ることができる。北方館で北方領土返還請求のサインをすると根室市長名の入った北方領土視察証明書をもらえるそうだ。何のイデオロギーも持たずに証明書を手に入れた。 夜、炉端焼「俺ん家」へ。店構えも内装もどっしりとした民芸調。尻のすわりがよさそうなことは店内に入ればすぐにわかる。盛岡の「南部どぶろく屋」と共通のテイスト。 8月~10月が旬の花咲ガニが根室の特産。 甲羅のとげが硬く身に独特の脂っぽさがある。高知で食べたエガニもどこかこの花咲ガニに似ていたような気が・・・ 花咲ガニを頼むと花咲ガニがまるまる一匹出てきた。でかすぎ。めんめ焼き、いかそーめん、さんまの飯寿司、鳥手羽唐揚げ、さけ茶漬けを頼んでいるのに・・・結局全部食べた。 |
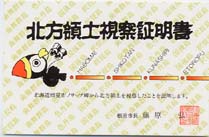
| 霧につつまれる恐怖をご存知でしょうか。わたくし、阿蘇で初めて経験しました。あれは怖い。 スティーブンキングの中篇に「霧」がある。 遠く湖の彼方から霧が白い壁となって近づいてくる。その霧に包まれた人間は超自然の恐怖と直面する。 知人から聞いた話である。海に面した温泉浴場で日本海を眺めていると遠くに白いもやのようなものが現れた。しばらく目をそらしているとその白いもやはいつの間にか間近に迫っている。つい先ほどまではっきりと見えていた近くの小島を包み込み視界から奪い去ってしまった。それが冬の日本海の寒冷前線だと彼が言っていた。 自然が人間に対してあまり好意的とは思えない表情を見せたときに感じる不安がそこにある。 豊肥本線で熊本から阿蘇に向かったその日は、折悪しく低気圧が近づいていた。阿蘇駅のバスセンターでは天候悪化のため草千里までの折り返し運転との情報が流れている。地上では山頂の様子は分からない。バスに乗った。しかしすぐに後悔した。霧に包まれたのだ。 視界がきかない。数メートル先の視界もおぼつかない。なのにバスは走っている。何故だ。 対向車のフォグランプが不意に現れる。先方は徐行しているがバスは徐行していない。どちらか |
と言えば飛ばしている。無謀だ。 脳裏に夕刊の見出しが躍りだす『観光路線バス、霧中の暴走。崖から転落、乗員乗客3名死亡』 墓碑銘をまだ考えていないのにだ。 やっとのことで草千里に到着。バスを降りたが草千里と言うほど眺望の良いはずのここでどっちの方角に何があるやらまったくわからない。 やがて白い混沌のかなたから微かな音が聞こえてきた(何だ?)耳をすます。短いが確かに人の声だ。かけ声のようだ。こちらに近づいているのか。しばらくの沈黙の後、再び聞こえてきた。 「えい!」しばらくの間、そして再び「えい!」 あきらかにこちらに向かってくる。嫌だな。腰が引けるが右も左もわからない霧の中どうしてよいか判断がつかない 「えい!えい!えい!」 不意に乳白色のベールを切り裂くように黒い影が踊り出てきた(うわっ)黒っぽい剣道着を着た老爺が木刀を振りかざしている。 「えい!」 裂ぱくの気合とともに木刀を振り下ろす。 呆然と立ち尽くす筆者には目もくれず霧の向こうに消えて行った。遠ざかる声だけを残して。 今でもあのときのことはどこか現実離れしたお伽草子の世界であったように思えてならない。 |
| ハッピーマンデー法による土曜日を含む10月の3連休。9月下旬にも3連休があった。3連休の飛び石2連発だ。 3連休初日は自転車を使って会社に行く。何をやっているんだろう、まったく。 そんな気分になったからだろうか、ひさしぶりに旅立ちモードのスイッチが入った。午後4時頃、朋友Iからの電話でどこかに行こうということになった。とは言え、秋の行楽シーズン3連休の初日のこと、案の定行きたい土地の宿はすべて満室。18時の待ち合わせはキャンセルして、翌朝8時40分の待ち合わせに切り換えて宿の確保を目指す。 同行のIは日本温泉旅館党の党首。 古風、古格なそのキャラクターは絶滅種「武士」の趣きがある。筆者は温泉にはあまり興味がないし、旅館は好きじゃない。しかし今回はIの嗜好にあわせることにする。 95年に訪れた伊豆熱川の温泉旅館「熱川館」が記憶に残る宿だったのでここに電話をいれた。キャンセルがあったため部屋を用意できるとのこと、ついているぞ。 翌朝、小田急線ロマンスカーで新宿から小田原へ。小田原城をぬけて蕎麦の「田毎」でもりそばを食べる。これは小田原での定番的活動。 |
その後、伊豆急乗り入れのJR特急「踊り子」号で熱川駅下車。そして目的の「熱川館」へ。 「熱川館」平成2年に新装オープンした温泉旅館は太平洋に面した海岸線に建ち、客室全室が海に臨む絶景の宿。大浴場も海に面した全面がガラス張り。地上高4階の高さで切り通しの丘陵上に突き出ている。 客室窓からの景色は前面180度すべてが太平洋。遠くに大島や利島などの伊豆七島の島影が浮かぶ。台風20号が遠くにあるせいか波は荒い。潮騒が耳を打つ。波や炎のような不定形のものはいつまで見ていても飽きを覚えない。ただ打ち寄せる波を見て時を過ごす。 眼下の突堤近辺にはサーファーが波待ちで浮かんでいる。同行のI曰く「何ですか?あのカモメの群れは」 そして温泉三昧。夜陰と早暁、太平洋を眺めてつかる温泉は最高の贅沢。夜明け前の午前5時すぎ、たったひとりで大きな浴場を独り占め。広大な湯船につかり明けゆく太平洋を眺める気分は爽快の一語だ。小田原に立ち寄った一時など遠い昔のことのようだ。何もしていないにもかかわらず、何をしている時よりも充実した時が流れる。短時間でこれだけリフレッュできればコストパフォーマンスは最高の部類だろう。 |


| 会津若松を訪れた。 駅前から鶴ケ城にむかってメインストリートが一直線に伸びている。国道118号線で、車の往来もそこそこに忙しい。 その隣にもう一本、ひっそりとした通りが並行している。この通りの印象が筆者にとっての会津の象徴である。静けさと大人の落ち着き、ひとことで表現すればそうなる。 初めて訪れたお盆の一日、真夏の日差しが視界のすべてを白い紗のフィルターで覆っていた。一直線に伸びる道のむこうに陽炎が非現実的なゆらめきを見せている。 あまりにも静かな昼下がり。 道を歩く人の姿が途絶えていた。 自分ひとりだけが、炎天下の城下町にたたずんでいる。人の気配が感じられず、音すらも失われたような午後。実際は隣に並行するメインストリートから商店街のアナウンスや、車の排気音などが聞こえていたはずだが、記憶の中のあの夏の日は、キリコの絵のように無音の世界であった。 城下町の静けさとはこのようなものであろうかと思った。そこに最も武士らしい武士の府の江戸の昔を見出したようでもあった。 それは一種の憧れを伴った感傷である。 ずっしりと腰の据わった大人の沈黙に憧れてい |
た頃だ。おそらくどれほどの歳を重ねても老成できないであろう子供大人の筆者にとって廉恥を伴った大人の落ち着きは終生の憧れになるとの予感が、二十歳そこそこの頃からあったのであろう。 その予感は残念なことにあたっていた。 いまだに筆者は上っ調子な腰の浮いた幼さの世界にいる。 その日は会津酒造歴史館を訪れ、鶴ケ城の天守に登った。奴郎ケ前茶屋を経て武家屋敷まで足を伸ばし、駅に戻る途中近藤勇の墓を訪れた。 奴郎ケ前茶屋では田楽を食べた。 田楽は「でんがく」である。筆者の知り合いの若者は二十数年間の人生を「でんらく」で通していた。偶然、居酒屋で彼がこの「でんらく」をオーダーしたときの楽しさはちょっと伝えようもない。 さて、近藤勇の墓である。下総流山で捕縛され斬首された近藤の墓が会津にあるのはちょっと奇異だが、土方が会津に来た折に立てたのかもしれない。あるいは騒乱の京都守護で親交のあった会津武士の誰かが、あまりに哀れな最期をはかなんでこの地に墓を設けたのだろうか。 偶然、というべきか墓にむかう山中で日向雨がぱらついた。今日は自然までもが演出過多なようだ。 |
| なぜか奈良が好きだ。 奈良公園を歩いていると妙に落ち着く。 自然体でいられる自分がいる。 同じ古都でも京都だとこうはゆかない。肩に力が入るっていうんですかね。寛ぎ度に若干の差があります。 その差が何であるのか自分でも判然としない。ただ、奈良はいいのである。 京都からJR奈良線で南下する。近鉄の特急を利用したほうが早いし便利なのだが、かつて周遊券を利用していた癖からか、JRを利用してしまう。 奈良線は幹線というよりもローカルなイメージ。これは天王寺から奈良を経て三重県亀山までを結ぶ関西本線にも当てはまる。 東海道に幹線の座を奪われ、近鉄・阪急・南海などの私鉄網に乗客を奪われるつらい路線だが、味がある。都市圏なのにどこかのんびりしているのがいい。ただし、これは通勤通学の時間帯に同線区を利用したことのない旅人の無責任な感想かもしれない。 奈良も地方都市の例外に漏れず、JR奈良駅よりも近鉄奈良駅の周辺の方が繁華だ。 奈良線で天平の都城に入京する筆者はいつもJR奈良駅前からまっすぐに伸びる三条通りを歩 |
く。やがて右手に池を臨み、そのほとりにクラシックな「奈良ホテル」が現れる。まだ宿泊したことはないが立派のひとこと。これは東京都心部の国際ホテルとは別種の趣きがある。 やがて春日大社参道の入り口前で左折すると世界最大の木造建築東大寺大仏殿に向かう。 巨大である。鎮護国家の要、東大寺。筆者が最も好きな建造物だ。 京都に都を奪われた平城京は仏教によるシンボライズで都市としての命脈を保った。平城京の東にある大寺、それが東大寺だ。平城京跡は現在の繁華街の西方2~3キロにある。 奈良公園内を散策する。日々の営みで知らぬ間に強張っていた心の窓が開き、寛ぎに浸されてゆくのが実感される。 鹿のフンに気をつけながら、ベンチに横たわる。 夕暮れが訪れる。東大寺が夕霞のむこうにたたずんでいる。この光景を忘れられずにこの地を何度も訪れてしまうのだ。 しみじみとした感懐に心を満たし、夜の街へと足を伸ばす。食事と酒を楽しもう。 しかし・・・奈良の街は夜の8時にはもう閉店のラッシュになってしまうのであった。 |
| 早暁、夜行列車の車窓を覗く。 すでに夜は明けている。 雲とも朝霧ともつかぬ白い混沌が地を覆い、その遥かに山並みのシルエットが朝陽を背にわずかに浮かび上がる。 朝霧は地から沸きあがる白煙のように時に薄く、濃く視界を横切ってゆく。初めての山陰路。神話の世界に向かうにふさわしい朝だ。 車窓の新鮮さが心を浮き立たせる。 ほんの一瞬のささやかな光景や出来事が精神にみずみずしい弾力を取り戻してくれることがある。まさしく今がそのときだ。一昨日、旅に倦み今回の旅をそろそろ切り上げようかと思っていたのだ。よかった帰らなくて。 山陰本線は「本線」名がついてはいるが単線だ。香住-浜坂間の山中などまさに自然そのままの景観。ひとことで言えば、木だらけ。おかしいなあ、海際を走っているはずなのに・・・ JR路線図では山陰本線は日本海側を走っている。自然、海岸線の眺望を期待するのだが暗に相違してなかなか日本海を臨めない。 さて、焔立つ神々の国、出雲にやってまいりました。JR出雲市駅の隣にいかにも古い造りの駅舎がある。これが電鉄出雲市駅。 電鉄とは私鉄、一畑電鉄のこと。 |
「いちはたでんてつ」とベタな読みそのままのベタな私鉄。電鉄出雲市駅を出た列車は途中「川跡」駅でスイッチバックのような行き交えをして大社前駅へ。これがまたレトロな駅だが廃線となったJR大社駅というのがこれに輪をかけてポストモダンらしい。実はこの時行かなかったのでこれは後で宿の人に聞いた話。後悔先に立たずで実に残念。 大社前駅からしばらく歩くと大鳥居に迎えられる。でかい。日本人はなぜこのようにでかいものが好きなのか。 やがて松の木に左右を囲まれた参道に出る。これまた大きなしめ縄のある拝殿がその先に現れ、さらにその背後には国宝の本殿がある。1744年に造営されたこの本殿はそれ以前には100メートル近い高さの高殿だったとの話もあり、古代への興味をそそられる物件である。 季節はずれであったせいか、出雲大社に人は少ない。神話の世界に造詣が深ければきっと、もっと楽しく時をすごすことができよう。 出雲そばを食べて特急「いそかぜ」に乗車した。出雲市を過ぎてからやっと進行方向右側に海が広がり山中の景色に飽いた目を楽しませてくれた。右側はC席・D席だ、覚えておこう。でも・・・海が現れるのが遅すぎるぜ! |
| 関門海峡を望む下関。対岸は門司。門司の右手に小倉がある。 関門海峡が迎えた三度の合戦に思いを馳せた。 1185年、壇ノ浦合戦(源平最終決戦) 1863年、馬関戦争(四カ国艦隊下関砲撃) 1866年、四境戦争(第二次長州征伐) 壇ノ浦合戦においては平知盛を、馬関戦争と四境戦争においては高杉晋作を思い出す。 一の谷、屋島、と義経の騎兵による奇襲攻撃で次々に拠点を失った平家の最後の根拠地が壇ノ浦であり、武門の家平家の最後の綺羅を飾る武将が平知盛であった。 平知盛卿、清盛の四男で新中納言と呼ばれていた。平家の武門としての最後の名誉は彼が担った。文武両道ではない。平家の血には珍しく、文については置き忘れてきたかのように無粋な人柄で宮中の女官からの人気はない。しかし、連年の源氏との戦闘ではその戦術能力の非凡さが配下からの信頼を集めた。 不幸にして主戦場に立ち会うことなく最終決戦場で初めて平家の総司令官となったが、すでに平家の敗勢を立て直すには遅すぎた。 壇ノ浦の潮流を利用した巧緻な戦術は当初平家優勢のうちに進むが干満の時期を読んだ義経により、午後に至って戦勢は逆転、平家は敗亡した。 |
筆者は悲運の名将に弱い。 もうひとり、高杉晋作は第二次長州征伐で九州方面軍(小倉口)を率いた。同時に海軍をおさえ(とは言え、本人が柴船と自嘲しているような4隻)当時東洋一をうたわれた幕府海軍と大島口でも快勝をおさめている。 第二次長州征伐は幕府側の呼称であり、長州では四境戦争と呼ぶ。幕府が四方面から長州を包囲殲滅しようとしたからである。作戦案としては壮大だったが各実施部隊の連携が悪く、戦意も低かったため、祖国防衛戦争の位置付けにある長州軍にことごとく破られた。 山陽方面の芸州口、山陰方面の石州口、九州方面の小倉口、幕府海軍が主攻する大島口が四境である。高杉は幕府海軍を敗走せしめると、小倉口を攻めた。28年という短い生涯の総決算が小倉城の攻略であった。 今宵の宿は下関グランドホテル。 海峡を見下ろすホテルの一室、潮の流れを遡上する船は遅々として進まない。潮の流れというよりは水源に近い河の急流だ。 関門橋が浮かぶ。海峡にかかる月影が水面に揺れている。月の通い路が自分にむかって伸びている。浮きいかだがキィキィと音を立てきしんでいる。知盛も晋作も同じ月を見ていたのだろうか。 |
| うみねこの鳴き声にむかえられ、どこか一抹の淋しさを漂わす港町釧路に到着。 さっそく釧路駅そばの和商市場へむかう。 海産物がメインの市場だ。市場内の寿司屋に入るがこれはやや不満足な結果に。 市場内を歩くとあちこちで「ごはん」を売っている。大盛や特中盛、中盛、小盛と種類も豊富。でもたんなる「白飯」なぜごはんだけを売っているのか。 丼に盛られたライスと手渡された割り箸を持ち歩き市場内を徘徊する人々の姿がある。 見ると別の店で小さな皿に盛られた刺身やいくら、うにを見繕ってライスにトッピングしてもらっている。醤油とわさびをかけて手元に戻ってくるライスはもはや立派な海鮮丼だ。さっそく真似をした。 市場の中央に数箇所、簡易テーブルと椅子が並んでいる。ここに座って食べるのだ。ベラボーに旨いぞ。釧路滞在中3回も来てしまった。 八千代本店という寿司屋もよかった。タラバガニのサラダがうまい。貝焼き、かき焼き、タラバガニの黄身焼き、にぎりは「めぬけ(めんめ=きんきの大きなもの)」に「おひょう」「ぼたんえび」「するめいか」「ぼたんえび」はシッポをぴゅっと押して食べる。これが最後のおまけ。北海 |
道を堪能。ここも2晩続けて来てしまった。 北海道と言えば広大な自然が売り。釧路に来たなら車で足を伸ばそう。360度の展望がきく開陽台の見晴らし台を見ようということになった。標津からでも網走からでもあまりかわらない距離ですけど。 小高い丘の上に立てられた展望台は目の前を遮るなにものもない眺望。地平線に囲まれ地にすいこまれそうだ。8月末だが肌寒い。さすが北海道だ。 そのまま車で摩周湖へ。俗に裏摩周と呼ばれる地点から、人為的な造作物のなにもない静かな湖面と湖岸を望む。湖面に陽光が散りばめられ神秘的な光景を満喫する。 あれ?よく考えてみれば霧が出ていないぞ。 ラッキーなんだかアンラッキーなんだか。売店のおばちゃんは「ついてるね」と言ってくれた。 帰りに多和平の展望台にも立ち寄った。ここも開陽台と同じ360度の眺望を誇る。こちらの方がのどかな感じがするのは放牧の草原が広がっているからだろうか。雲の陰がゆっくりと草原の上を流れてゆく。白黒のごまつぶのようなものは牛の群れだ。ここで食べたメイクイーンまるまる1個入りのビーフシチューとヨーグルトが思いがけずもなかなかいけた。ラッキー。 |
| 高知である。 鹿児島と並ぶ性、木強「漢」の土地、土佐。 土佐の高知と言えば、はりまや橋と桂浜。 はりまや橋はすでに橋ではなく道。界隈に帯屋町を中心とする繁華街が広がる。JR高知駅からは市電で3つ目か4つ目。 桂浜は高知駅からバスで30分強、少し距離がある。 背後を松に囲まれた広い砂浜のむこうに広大な太平洋が広がる。台風が接近しているせいだろうか波が高い。太平洋の波だ。波濤もこの浜のひとつの顔かもしれない。月夜の静けさだけが桂浜の魅力ではあるまい、と勝手に解釈する。 ああ、ここに来たかったのだと不意に思ってもいなかった感慨が胸を満たした。流木に腰をおろして小半時も過ごしたろうか。 坂本竜馬記念館に行く。どちらかと言えば高杉晋作や大村益次郎に傾斜する筆者だが、やはり竜馬は無視できない。ただし、ご当地自慢と竜馬ブームに便乗したありがちな観光施設であろうとたかをくくっていた。しかし竜馬暗殺の場にあった血痕つきの屏風に意表をつかれた。 坂本竜馬と中岡慎太郎の血痕。 歴史が、単なる資料から人肌の感触を持つ現実に姿を変える一瞬。まさにそんなインパクトをう |
けた。130年の時を越え目の前に慶応3年11月15日近江屋2階の光景が現出しそうな錯覚を覚えた。 そしてはりまや橋に戻る。 街の上空をサーチライトが掃いている。どのような意味があるのか。そう言えば徳島でも同じような光がいったりきたりしていたっけ。 はりまや橋界隈の繁華街はストリートミュージシャンが多い。これは土地柄か。 土佐料理「司」でカツオの刺身、トロ刺、くじらのサエズリ(咽喉のところ)くじらの天ぷら、酒盗を肴に酔鯨を鯨飲した。いい夜だった。 4年後、再び訪れた高知。夜遅くの来着で滞在時間の不足を嘆きながら、ちゃんこ料理「早川」で「えがに」を頼んだ。甲羅が硬く脂身が多い。食感が「花咲がに」に似ている小ぶりのかにだ。酒は司牡丹の船中八策、+8の辛口。「はらんぼの塩焼」「チチコ照焼」をつまみにこの時もかなり飲んだ。いずれもカツオの部位だ。はらんぼはカツオの腹身、チチコは心臓。 土佐赤牛をみそで煮込んだ「すじ煮込」を追加オーダーし、土佐の夜がふけていった。 「くじらのすきやき」や「カツオ茶漬け」「かつおたたき丼」も食べたかったなあ。 4年たっても、サーチライトは健在だった。 |
| 新幹線に乗っていると野立てが気になる。 ぼんやりと車窓を眺めていると視界に飛び込んでくる奴がいる。それが野立てだ。気にしだすと一再ならず現れる。気がつくと次に現れるのを期待していたりする。広告として成功ってことか? 野立てとは「野立て看板」のことです。 丘の上とか田んぼの真中、農道の一画に立てられている看板。 沿線で少し見晴らしがよい地点に通りかかるとなぜか「穴吹工務店」や「毛皮のエンバ」「727」「金長ゴン」などの看板が群生しているでしょう?気づいてました? 一枚だけ独立して立っているときもあるが群生していることが多い。やはり置きやすいところには集中するのだろうか?他社に出し抜かれるとすぐに近辺に立てるのだろうか? 「穴吹工務店」はブルーを基調に白抜き文字で統一されている。「727」は白地に赤く727という数字がペイントされその下にコスメティックとある。何よ?727って?気になるでしょう?コスメティックだから化粧品メーカーなのだろうが今に至るまでこの野立てと東京駅前の大きな看板(あれは本社ビルの看板なのかそれとも広告塔なのか)以外でこのメーカーのプロダクツを見たことがない。でも自分の中では有名ブランド。 |
穴吹工務店も東京駅のそばにビルがあったような。車窓が前ふりで東京駅が本編? 野立ては東海道と東北新幹線ではメンバーが入れ替わる。東北では「白松が最中」や「酒は大七」がレギュラーだ。でも727は健在。上越はどうだっけ? あの野立ては、やはり各企業の広告部あるいは広告代理店に「野立て部」とか「屋外広告部」とかいうのがあり、定期的に新幹線に乗って候補地探しや既存看板のメンテナンスをしているのだろうか? 「のぞみ」に乗ってしまうと「お、ここはいいぞ」と思っても名古屋や大阪まで連れていかれてしまうから「こだま」に乗ってね、進行方向左側の窓に陣取って適地を見つけたら次の駅で降りていろいろ調べたあげく地権者のところに顔を出す。「おたくの土地に看板を立てさせてください」とかやっているのだろうか。 そんな話をしていると偶然エンバと727の担当者が出くわしてしまい、気まずい空気が流れたりするのだろうか? そして帰路は東京行きのこだまで往路と反対側の設置作戦を敢行しているのだろうか? どうも今回は「?」だらけだ。どなたか業界の方がいらしたら実情を教えて下さい。 |

| 19年ぶりに秋田を訪れた。 でも何も覚えていない。昔どこに泊まったのかも忘れてしまっている。秋田駅前は大アーケード街の建設中で昔日の記憶を喚起するなにものの気配も感じられない。 時節は3月下旬、盛岡経由田沢湖線周りの秋田新幹線「こまち」を利用した。途中田沢湖線に入ると沿線風景が一変し、旅順要塞のベトンのような積雪が車窓を覆う。雪支度をしていなかったので不安になる。 しかし入線した秋田駅には雪がなかった。ラッキーなんだか寂しいんだか複雑な心境。 しかし寒い、しかも強風。寒気団が居座っているらしい。千秋公園前の堀に浮かぶかもめのような鳥の群れもみんなまるまっている。強風にむかってみんなでまるまっている。堀端の鳩の群れもまるまっている。 まるまっている、まるまってる。寒そーだ、寒そーだ。すっごい風だ。寒いぞ。 平野政吉美術館に立ちよる。 ピカソ・マチス・ロートレック・ゴッホなどの素描画などがそっけなく並んでいる。これはいい。絵を先入観なく見せることだけに徹した姿勢が感じられる。おかっぱ頭のとっぽいアーチスト藤田嗣治(つぐじ)の世界最大という大壁画「秋 |
田の行事」は圧巻だ。思わず時を忘れて見入ることしばし。 やがて街の徘徊を開始。土曜日の昼なのに街に人影がないのはこの強風と寒さのせいか。 ローカルな百貨店を見つけるのも楽しい「木内百貨店」うんうん、北海道では「フジマル」とか「丸井今井」とかね。宮崎の「山形屋」とか「寿屋」も味わい深かったなあ。 途中旭川ぞいにあるオープンでこじんまりとしたスタジオ「FM76.5」がいい雰囲気を醸し出している。大町4丁目界隈の繁華街、料亭「濱乃屋」おお、なかなかのたたずまいだ。郷土料理「味治」ここもなかなか。しかし、時間が早すぎた。今度来るときは必ず寄ろう。 晴れているのに風とともに粉雪が舞う。砂丘の風紋のように雪が地を刷いてゆく。じっくりできない旅程のためお手軽指向。なんでもありそうな郷土料理屋で昼食をとる。「きりたんぽ」と「稲庭うどん」お手軽な割にいけた。 秋田の列車はドアを閉めっぱなしにして停車している。ドアの外にボタンがついている。乗車するときにこのボタンを押す。ドアを閉めて暖房効果を散逸させない工夫だろう。このような工夫は秋田に限るまい。 ああ、もっと日程をとればよかったなあ。 |
| 尾張名古屋は城でもつなどと言うが、実際は違う。尾張名古屋は食でもつのである。独特の食文化こそが名古屋の真骨頂である。 食の街と言えば大阪であり、その事実にいささかの異論もないが、大阪の食文化は基本的にいかに「安くて旨いものを食わせるか」というテーマを忠実に実現したものであり、その意味で小麦粉を中心とした粉モノ文化としての予定調和を感じてしまう。想像ができる味と言い換えればよいか。 名古屋は違う。 「え?」というセンスオブワンダーがある。 カツに味噌?サンドイッチにあんこと生クリーム?なぜスパゲティソースにとろみをつける?うなぎにねぎとわさび?さらにそこにだし汁を注ぐ?甘辛の小さな鳥手羽先?本当にえびの入ったせんべい?ひらたいうどん? ミスマッチもあれば想像を絶する発想もある。 しかも基本的にアリである、アリ。 名古屋は観光資源が少ない。名古屋城と熱田神宮ぐらいだ(あ、怒らないでくださいね名古屋の方)したがってこの食文化をもっと大々的に売り出せばいいのにと思っている。 もっとも駅構内のファーストフード的な飲食店は避けたい。 |
「ご注文はよかったでしょうか」 (過去形でくるのだ名古屋は。例えば喫茶店で「お飲み物はよろしかったでしょうか」と聞かれる。よろしかったでしょうかとは何だ?よろしかったでしょうかとは!まだ頼んでもいないぞ!などと思った頃もあったが今はもう慣れた) 「じゃあ(味噌)ヒレカツ定食を」 「はい、お待たせしました」 もう来るのか! ちっとも待っていないぞ。前の客の食べ残しじゃないのか? ああ、そう言えば「きしめん」も客を待たせない工夫として茹で時間節約のためにひらたくなったという説があったな。さすが名古屋商人の町、時は金なりか。 じゃあ、きしめんも食べてみよう。今度は同じ駅構内の別のきしめん店へ 「ざるきしめんを」 「お待たせしました」 待っていない!絶対に待っていないぞ! 早すぎる。ビジネスで忙しいときはいいがこれでは趣向に欠けるし、なにより作りおきを食べさせられているようで物足りない。 やっぱりキンサン(錦3丁目)あたりに行くか。 |
 -東海道五十三次池鯉鮒(つりう)の宿-
-東海道五十三次池鯉鮒(つりう)の宿-
『名物 ハチミツ入り大あんまきと食事の藤田屋
名物 珍しくて美味しい天ぷらあんまき』
などと包装紙に広告がちりばめれている藤田屋の
「チーズ入りあんまき」と「天ぷらあんまき」
あんことチーズ?
ここでも名古屋テイストが存分に発揮されている。
しかも不思議なことに、ちゃんとバランスがとれている
なぜだ?
| 光速に近づけば近づくほど移動する物体内部の時間はゆっくりと過ぎてゆくってアインシュタインは言っていた・・・聞いたわけじゃないけど。 新幹線とローカル線の車中でも物理的には極ミクロなレベルで新幹線の車中が時間の経過は遅いはず。 しかし筆者にとっての心象はまったく逆。 映画はカット数によってスピード感が変わる。 カメラの切り換えなし、つまりフィルムを切ることなく流しつづけるシーンが1カットだ。 何万フィートのフィルムを回そうと、フィルムを見ながらこれをちょん切り繋ぎ合わせる編集という作業によって、映画のイメージはまったく異なったものになる。映画は監督のものだと言われるゆえんがここにある。 冗長さを嫌う監督は説明的なシーン(カット)を徹底的に省く。ただし、あまり大胆すぎるとモンタージュを失敗して前衛的なひとりよがり映画になってしまう。観客が切られたフィルムの行間を読みそこなうのだ。 たけし映画など1カットが長い割に説明的なシーンは極力省かれている。結果からモンタージュされる映画と筆者は呼んでいる。あ、話が脇道にそれすぎた。 カット数が多い映画はテンポのいいスピード感 |
に溢れた映画になると言わている。逆にカット数が少ないと冗長的だが独特の味が出るということでこれを好むオールドファンは多い。 名画を見たあと近時のアクション映画など見ようものなら、腰をぬかす程映画のテンポが違う。 新幹線とローカル線の車中での心理状態がこれに近いのである。 新幹線の座席に座っているとカット数の多いアクション映画のように次々と脳裏に浮かぶ画像が切り替わってゆく。しかもその画(え)のほとんどがプライベートなことよりもオフィシャルなこと、ひとことで言って仕事のことですね。 これでは心が休まらない。 旅に出ているのにあまりウキウキしない。 これがローカル線に乗ると小津安次郎の映画のように情緒的な思考がほわ~と浮かんでは消えてゆく。仕事のことなんかこれっぽっちも思い浮かばないから不思議。 沿線の風景にそって自由な思考がとりとめもなくとめどなく沸いてくる。 それは昔日の封印されていた想い出であったり、未来への希望であったり、見も知らない土地への地勢学的な推察であったりする。 ここで予土線や山田線の話になるところなのだが、ああ前ふりが長すぎた。カット割の失敗。 |
| 山田線は盛岡-釜石間157.5キロを結ぶローカル線だ。内陸部にある盛岡から北上高地をまたいで三陸海岸に向かう。山中を走るディーゼルはやがて宮古で三陸海岸に出る。幕末「宮古湾の海戦」が行われたあの宮古だ。 函館に本拠地を据えた榎本武明率いる旧幕府海軍の軍艦「回天」と官軍の鋼鉄艦が接舷戦を演じた戦いである。旧幕軍には新撰組の副長だった土方歳三も参戦している。官軍のボロ船「春日」の砲術士官は東郷平八郎、後に連合艦隊を率い日露戦争で日本を勝利に導くアドミラル東郷だ。もちろんこのときは三等士官にすぎない。 盛岡-宮古間の山田線の数は恐ろしく少ない。 快速・各駅停車をあわせてもおそらく5本程度しかあるまい。1日5本ですぜ。12時間運行しているとしても2時間半で1本の割合。いかにもローカルなダイヤ設定が旅心をくすぐる。 盛岡-宮古間は快速で約2時間、各駅だと2時間半。東北新幹線の東京-仙台間351.8キロの所要時間にほぼ匹敵する「うさぎと亀」みたい。 さて、盛岡を出た山田線は途中、飛び降りたとしても追いつけそうなスピードで気息奄奄と北上高地を登坂する。 区界(くざかい)駅がこの路線の分水嶺だ。 まさしく駅名のとおりここを境にディーゼル列 |
車は軽快に山を駆け下り始める。それまでの悪戦苦闘ぶりが列車への感情移入を促す。 「よかったなあ、おまえ」と思わず声をかけている自分がいる。列車に人格はないぞ。でもそういう列車なんですう山田線。 宮古からは「浄土ケ浜」へ向かう。 初めて宮古を訪れたときは宮古湾海戦の地を望む御台場展望台に上った。土方歳三の人形が顔だけくりぬいてあった。行楽地によくあるあれですよ、あれ。顔をはめこみました、あの時は。懺悔します。なかったことにして下さい。 浄土が浜は静かだった。極楽浄土もかくありなんという美しさに寄せられた名に恥じず一面玉砂利の海岸にうちよせる波はただひたすらに清らかで美しい。季節は8月末。海水浴客の姿もなく、ほとんど独り占め状態で静かな海辺のひとときを堪能できたのは僥倖だ。 時間の経過が都会とまったく違うひととき。 そうだ、これを手に入れたいがために旅にでているのだ。ひとり砂浜に腰をおろし、静かにうちよせる波に手を濡らす。 同行したMの携帯電話が鳴り響く。大久保の中国人か大阪の地上げ屋のように声高に仕事の指示を出すM。これからはこいつを宿に置きすててくることにしよう。 |
萩行 →→→back 萩行1(1996) 萩行2 萩行3 萩行4
| 秋彼岸を過ぎた一日、萩を訪れた。 JR山陰本線には萩駅と東萩駅がある。うっかりして萩駅まで行ってしまうところだった。皆さん東萩駅が萩の最寄り駅なのでご注意を。あ、知ってるか。 萩は静かだった。 静かと言うより、時代に置き去りにされた感じ。藩政時代も長州藩は幕末から萩を不便として山口に政庁を置いていたくらいだから萩のこの落剥感は筋金入りだろう。 無理もない。徳川家は関ケ原合戦の西の盟主毛利家を徹底的にリストラした。あげく山陽道から遠く離れた萩に藩都を置かせ、徳川家への潜在的反乱分子を当分足腰の立たないようにさせることが目的であったのだから。 同じ西軍の薩摩は「チェスト関ケ原」と叫び復仇の念を後世に伝えつづけ、長州では江戸に足をむけて寝ていた。 萩はその辺境にあって、しかし幕末多くの人材を世に送った。その多くが自分達の夢の達成を見ることなく世を去っていったが、筆者は長州人怜悧、あるいは議論倒れと呼ばれたこの集団に幾分かの愛着がある。 その日、萩中を歩き回った。おそらく唯一のアーケード街を抜け、菊屋屋敷に高杉晋作の生家を |
訪れ、そのまま萩城址へそして指月山の詰め所へ登った。菊ケ浜を歩き、再びアーケード街の入り口まで戻り、今度は松蔭大橋を渡り松蔭神社へ。 28年の生涯を駆け抜けた師弟、吉田松蔭と高杉晋作の人生のように何かにつかれたように歩き続けた。 商店に空きが多い。城下町はいりくんだ小路が多いので走っている車も小型車が多い。 その日の夜「よく歩いたもんだ」と感心してくれた郷土料理「百萬石」のおかみさんが萩の話をしてくれた。次々に注文をたいらげてゆく客に好意をもってくれたものか。 高校生の修学旅行が94年頃から減ってしまい、小・中学生が多いので店には訪れない由。萩の人口が郡部もあわせて5万程度なのに飲食店が多すぎるそうだ。 郷土料理の「いとこ煮」も食べた。 萩では何にでも「いとこ煮」を出すそうだ。中のもちの色で慶弔を分ける。お祝いは赤、弔事は青。汁が澄んでいないと駄目なのだそうだ。前日からあずきを仕込んで作るので手間がかかる。いつでもこれを出すのはうちだけだと言う。 昆布だしとしいたけのだしで作ったうにごはんも旨い。酒は東洋美人。 昼の疲れが溶けていった。 |
| 城下町の静けさというものがある。 時はおおよそ夜の8時前後。あるいは季節で言えばお盆の昼過ぎ午後2時あたりか。 商店街が閉まるのはだいたい夜7時。開いている店は数えるほど。地方都市の夜は早い。 車道の脇に自転車用のラインが引いてあるのも共通項だ。 部活帰りの高校生が自転車をこぎまわっている。 彦根の商店街も静かだった。 ただし刻限は昼。 本屋に入る。地方都市に行くと本屋に入るのが行動様式だ。店内に客の姿はなし。店番のおばさんが異邦人を伺うような眼差しをむけてくる。 異様に静かな店内。いたたまれないほどの静寂の中おばさんの視線がちくちくと痛い。大丈夫、万引きではありませんよ、怪しいものでもありません。 そう言えば、本屋の店内に有線放送がかかっていない店も多いなあ。 彦根の商店街はかなり長い。ただし静か。一番町商店街をぬけNTTの前を通ると中央町商店会があった。その先には銀座街商店会だ。さらにその先の登リ町商店会を歩いていたら、もとの一番町商店街に戻った。そぞろ歩きが楽しい。 |
路銀が心細くなったので銀行を探したが、口座を持つ都銀の支店がない、と言うより都銀の支店が1行も見当たらない。地銀と郵便局ばかり。なるほど郵便局は強い。日本全国各都道府県市町村にもれなく郵便局、民営化したら強いだろうなあ。効率の悪い店舗が閉鎖されることを恐れているむきもあるようだが全体で見れば恐るべき営業力だと思うのだが、などと時事ネタをいじってみました。 閑話休題、井伊家の城下町彦根のランドマークは国宝彦根城だろう。近世の大名居城で旧天守閣が残っているのは全部で12、弘前・丸岡・松本・犬山・彦根・姫路・高梁・松江・丸亀・松山・宇和島・高知である。そのうち4つが国宝指定をうけている。すなわち彦根・犬山・松本・姫路の4城(姫路は世界遺産ですけどね)だ。 彦根城、武門の誉れ高い井伊家の居城は急勾配の階段、低い梁などがいかにもの雰囲気を醸し出している。井伊は旧家好きの家康が旧武田の遺臣団を大量に預けたため「井伊の赤備え」などと呼ばれ徳川の武断派の顔となった。 彦根の街並みは瓦解のあとも大きな変革がなく「藩政」などと、もはや遠い記憶のかなたの言葉がなぜか息づいているような気がするのであった。 |
| 梅雨の一日、横須賀に行った。 川崎(京浜川崎)から京浜急行で横須賀中央まで。 快速特急は気が狂ったようにぶっとばす。 男らしい電車だなあ。 音が違うね。 時折、モーターが高速回転域に達したかのような「クォーン」という音が沸き起こる。あの音の正体は何なんだろう。 電車のすれ違いなんてチキンランのような感じ。 横浜を過ぎると、住宅地の騒音問題のせいだろうか、いきなりペースダウンしたのにはちょっとがっかり。 三浦半島に平地は少ない。宅地の多くは山を切り開いて造成している。斜面に連なるように屋根が重なっている。 鉄路を迎え入れるトンネルの数が増えてきた。 横須賀は三浦半島の中心地だ。 海軍の街でもある。 横浜はハイカラだけど、横須賀はバンカラ。どこか荒々しさを感じるのは軍都として栄えたからだろうか。 山の斜面が海までせり出すような地形で、東京湾の入り口にあるため、太平洋戦争中は米軍艦載 |
機の侵入路上の対空基地の役割を担っていた。 遥か洋上から雲霞のように侵入してくるグラマンだのロッキードだのを高射砲陣地が迎え撃つ。 今やかつての海軍鎮守府の建物はその米軍の艦隊基地となったが、日本海軍の伝統は自衛隊横須賀総監部として健在だ。 街には水兵さんや外人の姿が数多く見られる。 飲み屋街とか、洋品店が多い。それらがどこかあかぬけなさを漂わせているのが横須賀らしいと思う。 横須賀に行けば、記念館「三笠」を訪れないわけにはいかない。 日露戦争時の連合艦隊旗艦「三笠」である。地上につながれて記念艦となっている。 世界三大記念艦というのがあるらしく、イギリスのビクトリー、アメリカのコンスティチューションがそれだそうだ。 三笠は三笠公園にある。 三笠公園に向かう途中、静かで洒落たつくりの小路を歩く。さっき、あかぬけないだの、荒々しいだの好きなことを書いたが、この小路の一画にイラストレーター鈴木英人の絵などが壁面に画かれていたりして、けっこうヤルとの意を強くした。 帰りに海軍さんのカレーでも買って帰ろう。 |


| 17年ぶりの長崎である。 17年もたつと何も覚えていないのである。 いや、遠い日の思い出がひとつだけあった。 早暁の大浦天主堂で見たステンドグラス越しの朝陽だ。 若造の貧乏旅行ではまともな宿泊施設など贅沢の極みだ。 当時は、周遊券を利用して夜行列車で車中泊を繰り返し、寺の境内での野宿や久留米から鳥栖まで歩いてたりして夜を重ねていた。九州内を急行が走っていた頃だ。 朝早くに辿りついた長崎、大浦天主堂の礼拝堂で神様には失礼ながら、疲労がたまりベンチ(でいいのかな)で横になった。朝まだきの礼拝堂には訪れる者もなく、ましばしいねつるかも、の一時を過ごした。 やがて、ふと視線をあげた先にその光景があった。天井高く切り取られた窓枠にはめ込まれたステンドグラスに朝陽が差し込み七色の光条が堂内に注がれている。神秘的な光景だった。宗教的と言ってもいい。 偉大な宗教家ならば、このようなときに何らかの啓示をうけるのだろうが、偉人ならぬ身の悲しさ、ああ綺麗だなと感じ入っただけ。 しかし長崎の唯一の思い出となった。 17年もたつと人は変わる。何が変わるかとい |
って懐具合が変わるのである。 したがって、飲食店には気兼ねなく入ることができる。 といって、まず入ったのは「雲龍」という一口餃子の店。L字型(だったと思う)のカウンターのみの小さな店だが繁盛している。 常連客が皆「二人前」と言って注文している。 郷に入れば郷に従え、で「二人前」を連呼。ついでに「ブタニラ」と「ビール」を注文。いいぞ。 昼には長崎チャンポン発祥の店「四海楼」を訪れる。庶民的なこじんまりした店を思い描いていたが、案に相違して大きなビルがまるごと「四海楼」だった。修学旅行の団体でも受け入れられそうな大きな食堂のようなホールでチャンポンを食べる。なんかツアー客みたいな気分になった。 トルコライスという長崎ならではのメニューも狙い目だったが、九州一古いと言われる喫茶「ツル茶ん」には早くに訪れすぎた。午後近くからのメニューのためこれは断念。 「天一」という寿司屋で食べたやりいか・うに・いさき・たこ・あじ・あまだい・はもずくし(白子や肝、卵など)などで長崎の夜を堪能した。外では「あ~お~え~」と宗教的音律の白装束の集団が船を担ぎ上げている。長崎っぽくてよいね。 |
| 松山は四国第一の殷賑だ。奥座敷には道後温泉が控え、街中には松山城がどっしりと構えている。 JR松山駅から俯瞰すると、細長く発展した街を貫くように市電が走り、思いがけない市域の広さに驚かされる。 地方都市によくある例だが、JRのターミナル駅と地元私鉄のターミナル駅が離れている。 そしてこれもまたよくある話だが、JR松山駅前よりも地元私鉄の伊予鉄道松山市駅前の方が繁華だ。 賑やかな街並みだが、目前にそびえる城山とその上の天守閣の存在が、街に落ち着きを与えている。なるほど、城下町とはこうしたものかと思わせる趣きがここにはある。 長州藩の高杉晋作が道後温泉を訪れている。 筆者のこのときの旅の主題が「高杉ゆかりの土地」であった。 萩を起点に下関、小倉を訪れ、広島港から松山港に高速船で渡り、松山を訪れた。 JR松山駅と道後温泉を結ぶ市電は市の中心部を通る。既述のとおり思いのほかの街の広さに新鮮な感動を覚えた。 道後温泉の商店街でみやげ物を買った。松山の名産は「一松タルト」、ゆずがほのかに香る餡を |
ロール状のカステラで巻いた菓子だ。風情のある店構えの老舗に入る。 店番をしているおばあちゃんはきっちりしていた。 宅配便で配送を頼むと、伝票記入を求められた。かなりはしょって住所記入をしたところ、さっそくおこられた。 「あきまへん」 書き直し。 目移りがして、おみやげを追加した。支払いを先の分と一緒にしようとしたら再びおこられた。 「別々にします」 別々に会計した。 レシートなんかないので、領収書を手書きしている。不要だと断るとまたおこられた 「あきまへん。何かしら渡さんといけまへん」 領収書をうけとった。 城下町の老人というのは一本筋が通っている。これと比べると、都会育ちの若造などとても同じ脊椎動物とは思えない。ふにゃふにゃの背骨で重力に逆らえず地べたに這っているようではこのような老人と太刀打ちはできないのである。 地方都市でこのような古格な存在に接すると嬉しくなってしまう。松山で久し振りに出会うことができた。 |

 画像は2002年8月撮影
画像は2002年8月撮影
八重勝の長暖簾前に並ぶ客
| 大阪は好きな街である。日本中探してもこれほど陽気で猥雑な都会はちょっと見当たらない。底抜けの明るさと場末の一抹の寂しさが同居している。乾いているようで湿気っている。この独特の湿度が好きだ。大阪と言うよりも浪花と言ったほうがおさまりがいい。 この地で必ず訪れるのは「新世界」と「天神橋筋商店街」 どちらも結構濃い。 「新世界」は大阪のランドマーク「通天閣」の界隈だ。地下鉄御堂筋線か堺筋線の「動物園前」で降り、地上に出る。 いきなり轟音が真上から襲ってくる。 「なんだ?なんだ?なんだ」ビルの中からジェットコースターが飛び出してきた。あっと言う間に反転してビルの中に引っ込んでしまう。ちょっと意表をつかれる。 フェスティバルゲートと呼ばれる屋内遊園地を背にし、ほんの少し先に「ジャンジャン横丁」への入口がある。ナニワオリジナルへの玄関口。 街の雰囲気は浅草・上野界隈と北千住界隈を足して2で割ってどろソースをかけたような感じ。 横丁内をチャリンコに乗った「オイチャン」が走り抜ける。こんなに大量のハンチング帽をかぶった通行人を見たのは初めてだ。紐つきのミニポ |
ーチを抱えた「オヤジ」も多い。みんなジャンパー姿だ。 人だかりがある。なんだ?覗きこめば、将棋クラブだ。ガラス戸越しにみんなが将棋指しを見ている。「吹けば飛ぶよな将棋の駒に♪」思わず誰もが口ずさむに違いない。 弓道場だ!スマートボールだ!パチンコ台も機種が古いぞ!もう、無茶苦茶に楽しい。 異様に長いのれんがかかっている。そこは串かつの店「八重勝」。牛肉のみならず、ゆで卵、じゃがいも、たこ、なす、何でもかつにしてくれる。カウンター前のトレイになみなみと注がれた二度漬け禁止のソースにつけて食べる。漬け足りなければ、無料のキャベツをつかってソースをかけてやれば良い。この店、異様に安い。そして旨い。 店の奥に置かれたソースの一升瓶に「羽車ソース」とある。しかし今にいたるまでこの銘柄、どこの小売店でも見たことがない。欲しいなあ。 次は「丸徳食堂」でホルモンうどんだ。ついでに「づぼらや」でふぐも食べちまおう。ああ、気がついたらもう食べられません。残念!今日は通天閣裏手の「グリル梵」には行けそうもない。 こうして新世界食い倒れツアーの夜がふけてゆくのであった。 |

 将棋と囲碁会所が満席
将棋と囲碁会所が満席
| 8月下旬、北海道へ行った。道央・道東・道北を総なめする予定だ。行路は帯広-釧路-根室-網走-旭川-稚内。 できれば鉄道を利用したかったのだが、同行のMが強硬に反対。やむなく航空機と車を使った。使ったと言っても優良ペーパードライバーの筆者がハンドルを握ろうはずも無く、1500キロの行程のすべてをMが運転した。 さて、初日は帯広。 帯広空港は周囲を樹木に囲まれた静かな空港だった。旧ソビエトのシベリア空軍基地みたい。見たことないけど、シベリヤ空軍基地。 鉄道の旅と違い、空路の旅はプロセスがゼロ。したがって旅の過程で得られる沈潜する深い内省的思考などとは全く無縁である。深刻ぶるのが好きなわけではないが、ああもったいない。 帯広は道央の中心都市ということだが、メインストリートを一回りすれば、街の様子をほぼ把握できる。とりあえず喫茶を楽しむ。 三方六というバウムクーヘンを「柳月」で食す。小売部でショーウインドウに並べられた商品を小分けして出してくれるのかと思っていたら、あらら、そのまま持ってきちゃった。全長20センチ弱はある巨大バウムクーヘン。食べましたね二人で。よかった一人じゃなくて。 |
帯広に来たら豚丼だろう、ということで豚丼で有名な「ぱんちょう」を訪れた。しかし残念、連日休業中。かわりに「辨慶本店」で食べた。甘辛たれで付け焼きした豚肉をのせた丼。うまいっす。 北海道に来たのだからと、小鉢でうに・いくらも頼む。ああ、うまい。ビールをがぶ飲み。 夜は「サイロ」という店を訪れた。 店の前でオヤジがふたりダベっている。 店に入った。カウンターが厨房を囲んでいるだけのこじんまりとした造り。8人程度でいっぱいになりそうな店内には誰もいなかった。 外でダベっていたオヤジが後から入ってきて「いらっしゃい」と言った。店の主人だった。 かんかい(干氷下魚と書くらしい・・・こまいのこと)やら鹿肉のステーキを食べ、ビールをがぶ飲みする。鹿肉のステーキはおそらくウスターソースをベースにした濃厚なオリジナルソースで食べる。味が淡白なので、これくらい濃い味でないと料理がひきたたないのかもしれない。 自身も鹿撃ちをしていたオヤジの話がリアルで面白い。しとめたエゾシカと一緒に写った若い頃の親父の写真が我々の背後の壁にとめてある。ああ、紙幅がつきてしまった。帯広編は次回へと続くのであった。 |
| 鹿の数が増えているらしい。 今や、田畑を荒らす立派な害獣扱いだ。 店のご主人の鹿撃ちをしていた頃の話が面白い。 山に入ると草の揺れ、梢の陰、何でも鹿に見えてくるそうだ。ライフルは500メートルくらいならば、6倍スコープで十分に狙える距離。 「もっとも大抵、照星なんかあわせないけどね」 パッと構えて勘で撃つ。 大型の鹿は脂があるから、口径の小さい弾ではまわりの肉と脂で締めてしまう。効果がない。それなりの口径でないと駄目だ。 弾頭のひしゃげた実際の弾をコロンと手の平にのせてもらった。ほんの小さな塊だが意外と重い。 「こいつは銅だから軽い方よ。やっぱり鉛が重いよね」 熊に出くわすこともあるらしい。 4~500メートルの距離ならば、アバラを狙って打てばよいが、至近距離ではライフルは不利とのこと。 ライフルの弾は銃口を放れてから、空気抵抗を受けて回転が高まるものらしい。至近距離では回転が上がらないので破壊力に乏しく効果がない。 あばらを狙うのは、弾の回転であばら骨をぐし |
ゃぐしゃにするため。それで心臓を傷つける。あるいは弾をはじけさせるのが狙いなそうな。あばらを外すとそのまま貫通してしまう。 熊に出くわした猟師の話。 猟師も驚いたが熊も驚いた。互いに距離を置いて身を離す状態ではない、まさに鼻先をぶつけ会うような出会い頭の邂逅。 両者くんずほぐれつで崖から落ちた。 猟師は助かり、気がつけば熊が横で死んでいたという、映画のような話。ご主人の口からは次々と思い出話が湧き出てくる。いかにもプロらしい話は、峰の上に鹿を見つけたときの対応だ。 峰の上で鹿の全身が露出している。周りにまぎれるものもない。格好の狙撃対象のように思われるが、このような時は決して撃たない。 はずした時のことを考える。 峰の向こうはこちらからは見えない。そこに何があるか解らないところへは弾は打ち込めない。 「ライフルの弾なんか、何キロも飛んでっちまうからね」 なるほど。 池田町の町民用ロゼワインもこの店にあるときは風情がある。ご主人のハンター姿の写真の上に帯広の空撮。20年前の帯広が広がっている。気持ちのいい夜だった。 |
鹿児島行 →→→back 鹿児島行1 2 3(疾風怒涛編) 4 5 6 7
| 9月上旬、盛岡からの帰り道、東京駅で特急「富士」に乗り継ぎ、鹿児島に向かった。 鹿児島では何度かタクシーに乗った。そのうち2人の運転手から同じように聞かれた。 「お客さん何処から?」 東京、と言いかけてやめた。「ええ、盛岡から」・・・事実だもんね。 「ほお~、盛岡?・・・盛岡って言うと仙台のそばの?」「ええ」鹿児島人にとって東北の北限は仙台あたりらしい。運転手2人が同じような反応をしたからきっと、そうだ。 幕末、加治屋町の狭い一画から日本史の舞台に沸き起こるように登場した青年達も同じような感覚でいたのだろうか。お城下の隣近所で育った遊び友達グループがやがて一国の政治・軍事の中枢をにぎっていったという事実は世界の歴史でも珍しいことではあるまいか。 時代が進んでも、鹿児島のイメージはあくまで無骨・木強である。 天候までもが、そのイメージに呼応するかのように9月の鹿児島の残暑としては記録的という35℃という気温で迎えてくれる。車中一泊をはさんで昨日まで18~9度の盛岡にいた身には少しこたえる。 |
日向・薩摩・大隈、島津家による三州統一事業は1578年耳川の戦いで大友宗麟軍4万対島津義久・義弘父子の島津軍4万3千が激突し、戦死率10%に達した大友軍の敗走により、前年に伊東氏を日向の領国から追い、確保した島津家の日向征服を確実なものとしたことで完結する。 島津家はその後、九州3強の残り1雄、龍造寺隆信と1584年肥前沖田畷(おきたなわて)の戦いにより、島津軍7千が龍造寺軍2万5千を隘路に布陣し向かえ討つことになる。大軍の利を生かしきれない龍造寺軍を島津の奇襲部隊が後方より襲撃。敵主将龍造寺隆信の首級をあげ、これを壊走せしめ、九州全土統一を確実なものとした。 この地だけはいまだに鹿児島と呼ぶよりは薩摩と呼んだほうがおさまりが良い。 名産黒豚を使ったとんかつを食べた。 店の主人はあくまで無口だ。カウンターから話の水をむけても反応は鈍い。しかし、不愉快になる対応ではない。ただ、何を言っても「ん!」という単音節の返事が返ってくるだけ。会計になってやっと声をかけてきた。 「どじゃった?」「脂っぽくないし、ジューシーでおいしかったですよ」と応えれば、満足そうに 「ん!」 やっぱ、薩摩だなあ。 |
盛岡行 →→→back 盛岡行 激闘わんこそば編 ソウルフル編 盛岡行4
| カクテルを頼むとフレッシュにこだわるバーが多い。フレッシュとは生ジュースのことだ。生絞りのフルーツを使ってカクテルを作る。 盛岡にバー「ルパン」がある。 銀座の名店、太宰治や三島由紀夫が通ったあの店と同じ名前だ。 こじんまりとした大人のための隠れ家的な店だった。後でマスターから聞いたのだが、スコッチにこだわりのある店らしい。 その日はカクテルを飲んでいた。何杯目かのオーダーをギムレットにした。 そう、レイモンド・チャンドラーのハードボイルド小説「ロンググッドバイ」で登場人物が「ギムレットには早すぎる」とつぶやいて飲む酒だ。 ジン3/4・ライムジュース1/4をシェークしただけの、シンプルだが、シャープな切れ味のカクテルだ。ウォッカ好きのアメリカ人は、ジンのかわりにウォッカを使ってヴァリエーションを楽しんでいるらしい。ベースをウォッカにするとカクテルの名前も「スレッジ・ハンマー」となる。 その日、カウンターで目の前に出された「ギムレット」はいつも飲むそれとは様子が違っていた。 「ギムレット」は、軽く粉雪を巻き上げたような |
白濁色か、薄緑色の透明なものが多い。 ところがその日、目の前に出されたギムレットは透明だった。マティーニのように透明なギムレット。いつも飲んでいるそれよりもやや甘いがシャープさは変わらない。普段よりも美味しいと思った。 「うちはローズライムなんだよ」 ためつすがめつカクテルグラスをひねりまわす客の様子にバーテンダーが、説明の必要を感じたのだろうか。答えを出した。 (ローズライム?・・・ああ、ローズ社のライムジュースのことか!) レイモンド・チャンドラーは「ギムレット」のレシピをジンとローズ社のライムジュースを半分ずつと言っている、そのことを思い出した。ただし知識はあったが経験がなかった。その日、初めてローズライムに出会ったわけだ。 楽しい夜だった。 盛岡でレイモンド・チャンドラーのギムレットを飲めるとは思わなかった。 この街は、ソールシティのひとつだ。 訪れるたびになにがしかの感懐を与えてくれる。この日はバー「ルパン」でそれに出会った。 それだけのことだが旅の楽しみのひとつである。 |
盛岡行 激闘わんこそば編 →→→back 盛岡行 激闘わんこそば編 ソウルフル編 盛岡行4
| 何度も訪れている盛岡であったが、なぜか名物「わんこそば」を食べたことがなかった。 「わんこそば」については、断片的な知識しか持ち合わせていない。次々に投入されるそばをひたすら食べる。ギブアップをするには椀のふたをスバヤク閉じなければ箸を置くことが許されないシステムらしい、という程度の知識である。しかも真偽の程は定かではない。 そこで、今回「わんこそば」にチャレ~ンジ。 その日の決戦場は「直利庵」となった。 靴を脱ぎ、かなり広めの畳敷きの部屋に通された。向かい合わせで2人ずつ、4人が座る座卓が並んでいる。当方2名なので他の2人組の男性と相席になる。 大勢の仲居さんが大きな盆に小さな椀をのせて厨房と座敷の間を忙しく往復している。 ここにきて懸念のひとつが解消した。 最後のそばをすすり終わったあと、新たなそばを投入させずに、いかにタイミングよくふたをするかという技術開発に頭を悩ましていたのだが、卓を担当する仲居さんが一人だけなので、そばの補給に中座するというチャンスが必ずあることを知ったのである。なんだこれなら恐るるに足らず。 さて、ヒトフタヒトマル。開戦。敵爆撃機の搭 |
載量はざっと15杯程度(違ってたらゴメン)常に頭上にホバリング(空中で静止)し、1卓4人の客の椀が空になるのを虎視眈々と狙っている。しかも威嚇行動付。頭上でまだかまだか?と蕎麦の入った椀をふるふると小刻みに振っているのだ。これはかなりのプレッシャーだ。 当方は椀が空くと軽く中空へ差し出す。そこへ蕎麦とつゆがザッと投げ込まれる。当然蕎麦やつゆがはねて頭上から降ってくる。よそゆきの服はやめた方がよい。杯洗のような鍋があり、溜まりすぎたつゆをそこへ捨てる。そばは少量。8杯でレギュラーのかけそば1杯程度だそうだ。意外だったのはそばが暖かかったこと。 やがて、皆の腹が満たされ始めるとピッチが落ち、再び頭上で「ふりふり」が始まる。4人の客は互いに(ここで戦線離脱は絶対に許さない)という視線を交し合う。ひとりでも抜けると、残された3人で戦線を支えねばならず、それは敵からの圧迫が8%増加することを意味する。 敵機が爆弾を投下しつくして補給のため、基地へ帰投した。目の前に刺身などの副食物があるが、箸をつける気がしない。刺身つきのコースではなくプレーンなコースで十分だった。 ああ、遠くからまた空襲警報が聞こえてきた。 |
北陸大返し 「プロジェクトX」風に。BGMには中島みゆき →→→back
| GW(ゴールデンウイーク)に塩尻→名古屋経由で北陸の殷賑、金沢にむかった。 GWにどこかへ出かけたのは初めてだった。 だから知らなかった。GWがあんなに恐ろしいものだなんて。 気楽に飛び乗るつもりだった特急「あずさ59号」、混んではいるが、「あずさ」はいつでも混んでいる。指定席が取れずに自由席となった。1時間前から行列に並ぶ。前から6番目、席取りに不安はない。 車内放送で「自由席は混雑のため車内販売がゆけない」と言っている。やはりGWだからなのか。茅野(ちの)を過ぎたあたりでやっと車内が空き始めた。しかし車内販売は来なかった。 塩尻で中央本線特急「しなの22号」に乗り継ぐ。「しなの22号」は周囲を山また山にかこまれた木曽路を思いがけない高速で駆け抜けてゆく。視界が山峡で塞がれるためか、スピード感がある。中津川で視界が開けた。まさに踊り出るように特急は山並みを後にした。名古屋まであとわずかだ。 同行のNが口を開いた。 「なんで、新幹線を使わなかったんですか」 「ん?飽きたから」 「え?そんな理由で?」 |
騙すつもりはなかったが、Nはちょっぴり不機嫌になった。 名古屋の宿は簡単に取れた。これがいけなかった。いつもと同じ・・・そう錯覚した。 翌日米原から特急「加越5号」で金沢にむかった。その金沢で恐ろしい目にあった。 観光案内所の窓に「本日の宿泊施設に空きはありません」と掲示されていた。ホテルや旅館に電話をかけまくった。すべて満室だった。 宿がない。初めての体験だった。 金沢にいても埒があかない。特急「はくたか15号」に乗って富山まで行った。富山で寿司を食べようと思った。 状況は同じだった。 富山の市内中、さらに高岡や新湊の宿泊施設まで電話をかけまくった。 すべて満室だった。 日が暮れてきた。このままでは野宿だった。 Nが絶望的な顔で空を眺めていた。 夜がすぐそこまで迫っていた。 やがて決断が下った。1時間後、2人は特急「雷鳥44号」の乗客となっていた。 その日ふたりは名古屋-米原-金沢-富山-大阪643.2キロを走り抜けていた。 |
| 初秋の旬日、山陰を訪れた。 京都、「奥丹」で湯豆腐を食べ、不意に思い立った山陰路行。乗り継ぎも考えずに飛び乗った山陰本線は保津峡を渡った後、亀岡駅で降車を強いられる。終点であった。 山並のむこうに日が沈もうとする刻限、周囲を田に囲まれた亀岡駅はあまりに寂しく旅愁を感じるひとときを過ごした。 福知山のビジネスホテルまで辿りつき、その日は一泊。 ホテルでくつろぎ、時刻表をめくると出雲大社行きの特急「出雲3号」が福知山に早暁停車することを知る。これに乗車しよう。 旅慣れているつもりで抜けていることに気づかされたのは翌朝5時にチェックアウトしようとしたとき。 フロントが24時間稼動しているものだと考えてはいけない。福知山のビジネスホテル、午前5時のフロントは真っ暗闇。ドアにもロックがかかっている。何とか呼び起こしたフロント係りのあからさまな迷惑顔を背にホテルを後にする。 追い討ちをかけるように、駅の券売所では特急券の購入を断られる。 「コンピューターが動いていないんだよねえ。悪いけど列車の車掌に空きを聞いて車掌から切 |
符を買ってくれないかなあ」 はいはい、悪いのは私。み~んな私が悪いんです。 列車に乗り、車掌からA寝台個室ソロの切符を無事購入。そして私はこの特急「出雲3号」で寝台列車にはまってしまった。 カードキーで寝台個室に入ると、タオルや洗顔関連のアメニティグッズが収められたビニール製のポーチが個室におかれていた。 うほ、なんとなく得した気分。 車掌から渡されたもう一枚のカードシャワー室キーでシャワー室が6分間使えるとのこと。6分と言うのがなんとも微妙な設定だ。 折畳式テーブルの隣にVHSテープ用のモニターとデッキがある。ベッド兼座席の脇にはシャワー室使用お知らせ灯とトイレ使用お知らせ灯がついている。 寝台は電動のリクライニング機能つき。車窓にむかって足を伸ばし、風景を満喫できるしかけだ。 私はもう有頂天になっちゃいましたね。 ただ、車窓に足をむけて寝っころがっている人間に向けられる通勤通学時間帯のホームからの視線は物理的に痛い。かなり痛い。 市街地を走っている間はカーテンを閉めておこうっと・・・。 |
| 季夏の旬日、盛岡で遊んだその帰り道、東京駅で特急「富士」に乗り継いだ。 「富士」は東京発西鹿児島行きの夜行特急である。東北へ出かけ、帰りに九州にまで足を伸ばす。自分で自分を誉めてやりたい。何を? 山陰を訪れたとき特急「出雲」に乗った。それ以来寝台車にはまっている。その日もまとめて取得した季節はずれの夏休みに十分な余裕があったことから、帰路の東北新幹線で時刻表上の「富士」に目がとまった。これで決まり。 その日の「富士」の個室A寝台は「出雲」のそれと比べて若干見劣りがした。狭いのである。設備も古い。最悪なのはベッドを座席として使用すると進行方向に背をむけることになる点だ。まじですか? ドアの鍵もカードキーではなく、ダイアル設定式のプッシュボタンキーだ。 「出雲」にはついていたベッド背もたれの電動リクライニングも「富士」にはない。洗面台にふたをする形となるテーブルもこうとなっては貧乏臭い。洋式便所じゃあるまいし・・・などと非難の矛先が向いてしまう。心の狭い私。 寝台車でゆとりを追求すれば北海道にむかう「カシオペア」につきるのだろうが、これはまだ未乗車なので比較ができない。私が乗った北海道行き夜行特急は「北斗星」である。 |
それでも夕刻に発車する「富士」に連結されたロビーカーの車窓はいつものそれとは違って風趣があった。これだけでも元がとれた気がしてしまうから我ながら単純だ。 普段、列車進行方向に向かって列をなす座席の一切がそこにはない。ソファーが4席進行方向左側に並び、単座の椅子が右側に4席かなりの席間を確保して並んでいる。 車窓は広く、天井近くまで切れ込んでいる。ゆったりとした時間がそこには流れている。 東京発23時43分発の大垣行き快速。藤沢、平塚を越えるまでは完全に通勤電車の体をなす対面4人掛けのノーリクライニングの垂直座席のその列車は、前の座席に足をのせてもL時型に寝るしか身の置きようがない。 ロビーカーの座席にくつろぎながら、17年前のあの頃、幾度も乗ったあの快速で自分は何を考え、何を想っていたのだろうか。あの頃とは比べるべくもないゆとりの中で夜のしじまを映す薄暮の車窓が語りかけてくる。 夜の車窓がつむぎだす湿度の高い感情のうねりに身をゆだね、ふと気がつくと豊橋を過ぎ。岡崎へむかう漆黒の車窓に遠く一条の光の帯が駆け抜けてゆく。新幹線だ。文化と文明の交錯点を感じる一瞬・・・今私は限りなく詩人だ。本当か? |
| 立夏の一日、小田原に足を伸ばした。 小田急小田原線の向ヶ丘遊園駅から特急ロマンスカーに乗り込む。 当日券、しかも発車の20分前に禁煙の窓際席が簡単に取れた。今日はすいているようだ。お客さんついてるね、と駅員に声をかけられる。 ロマンスカーは狭軌車輌では世界最高速の記録を持つ。デビュー当時は車内で結婚式も行われたというエピソードもあり、いわばモダンな電車の先駆け的存在である。 向ヶ丘遊園に停車する小田原行きロマンスカーの旧称は「さがみ号」だがダイヤ改正で「サポート号」に変名された。味わいにかける改称だ。 小田原までの所要時間は約50分。沿線は宅地開発が進み住宅地が続く。通勤風景とさしてかわらない。 この路線で車窓を楽しめるのは渋沢駅を通過してからだ。渋沢・新松田間は異様に長い。それまでこきざみに設けられてきた駅がここにきてネタがつきたかのように姿を消す。 沿線風景も急変する。不意に丹沢山塊に分け入るように新緑の山ふところを電車は縫うように走る。東名高速が鉄路をまたぐ。国道246号線が並走する。なかなか趣きのある車窓だ。 そして、電車は山峡から不意に広闊な平地に |
飛び出す。酒匂川に沿って松林が一直線に並ぶその景色への変化はこの路線における車窓中の白眉である。 右手やや後方、今まで走り抜けていた山峡の中腹に一昔前の国際観光ホテルのような建物が妙に目立つ。あれが第一生命の建物だと教えてくれたのは誰であったか。 生粋の戦国大名後北条氏5代100年の覇府小田原の象徴はやはり小田原城だろう。1561年上杉謙信9万5千、1569年武田信玄4万の大軍に囲まれてもびくともしなかった堅城は1590年の豊臣秀吉軍に城下の盟を誓うことになる。 小田原城址公園には小さな遊園地や動物園もある。これらはもちろんお子様むけだ。1000本とも言うソメイヨシノや藤棚が訪れる者の目をなぐさめる。 藤の花は思ったよりも色が淡白でイマイチの感を否めない。下記の画像は色のバランスをいじっているのでヤラセである。 城址公園をひとまわりしたら「小田原に田毎あり」と呼ばれるそばの名店にむかう。ここのもりそばはさすがに旨い。 魚も食べねばなるまいと網元直営の店も訪れたが、こちらの寿司はいまひとつであった。 帰りは各駅停車で1時間半。ゆったりと帰宅。 |


あなたは旅派?旅行派? どっちでもいいんだけどとりあえず聞いてみました。
旅派は目的を定めませんね。
ろくに日程も組まずに思いつきで出かけるタイプ。楽しむのはプロセスそのもの。まあO型のみずがめ座に多いタイプ、違うかもしれないけど。
旅行派はもうガチガチにスケジュールを組んじゃう。
買物をするなり名所旧跡を訪ねるなり、明確な目的をもって行動する。プロセスは無視、すぐに飛行機を使うのがこのタイプ。企画は規格と化し、目的専一主義の権化と化すA型のいて座ですね、よくわかんないけど。
筆者は旅派。思いつきで旅に出て、飽きるか金がなくなったら帰ってくる。
いくら日常からの逃避とか言っても、帰る家があっての話ですからね。明らかなセィフティゾーンを確保したうえで擬似漂泊感を楽しむ。これがミソ。
とはいえ、旅立ちモードのスイッチが入るパターンは明らかにあります。
午前中・快晴・平日・寒くない日・かたずけられた家事・・・この諸条件に当日の体調・心理状態が微妙に影響し、突然旅に出たくなるモードに突入。これがパターンです。
そして旅の手段は圧倒的に列車。しかもスーパードメスティック派・・・国内旅行専門。なにせパスポートを持っていません。
気が向いたら鞄にパンツと靴下、時刻表(大判)、ポータブルMDプレーヤーと電卓をつめこんで出かけちゃう。これが一番! →→→back
キップを買おう
とりあえず家を出て、とりあえず東京駅にむかう。
とりあえず混んでない列車を探し、とりあえず適当な近場までの切符を買う。そして、とりあえず乗り込んでしまう。
あとは車中で乗り継ぎのキップを買えばいいですね。
したがって、北へ行くか南へ行くか、日本海へ抜けるかはその時の時刻表と列車の混雑率次第。
キップは片道切符で楽しむ。毎回ではありませんが。
例えば、東京から仙台へ。一泊した後、盛岡経由で秋田へ。秋田でまた一泊、その後日本海側を南下し上越線で帰ってくる。
そうすると大宮までは同一線区を使いませんからJRの区分で言う片道切符になります。東京発、盛岡、秋田、経由上越線で大宮までの片道切符、大宮から新宿までは乗り越し精算。
するとJRの運賃計算法、長距離逓減の法則に従って切符が非常に安く買えます。
下手な切符の買い方をしてしまうともったいない。例えば上記コースで東京-仙台、仙台-秋田、秋田-大宮とつぎはぎで3枚の切符を購入してしまうと2000年3月のJR運賃では2万60円かかります。
途中下車という制度に慣れている場合、東京-秋田、秋田-大宮の2枚の切符を買うかもしれません。この場合は1万8千590円。
コースは変わりますが、東京-秋田の往復キップを買えば1万7千208円です。
これが、一筆書きの片道切符ならば、なんと1万3千760円です。チーン、ジャラジャラ。
ああ、小市民的楽しさ。
出不精の方には『途中下車』など意味不明な言葉だと思います。
この乗車手段も知られているようであまり知られていないようです。
長距離切符の場合、有効期限が定められています。この期間内ならば目的地との間で逆走しない限り、何度途中駅の改札を抜けても有効という制度が『途中下車』です。
これは知っているとけっこう便利です。例えば上記東京→大宮の片道切符ならば有効期間は8日間です。8日間、路線内ならば乗り降り自由で旅をできるのです。
長距離の片道切符はコンピューターがみどりの窓口に設置される前は、購入に覚悟が必要でした。バーで七色の『プースカフェ』を頼むくらいの勇気がいります。面倒なんですよね、計算。
後回しにされることもあれば、背後から舌打ちが聞こえることもある。
それが、今ではコンピューターで経由地点にポイントをうつだけであっさり料金計算が終了してしまう。これは嬉しい。 →→→back
列車を降りたら
駅前の本屋に入ります。探すのは地元のシティガイド。地元新聞社のものもあれば、ローカルな出版社発行のものもあります。
肝心な点は東京で売っている全国区のガイドブックには手を出さないこと。特に若い女性むけのガイドブックは危ない。ここからの情報を計画の基礎に据えると火だるまになります。
筆者はかつて、ガイドブックのすすめるままに入った高知のイタリア料理店で爆砕した経験があります。
駅構内にある観光案内所で街の地図も入手しましょう。シティガイドで地図が賄われるケースもありますが、何に役立つかわからないので観光案内所にも顔を出しましょう。
宿でそれらをゆっくり吟味します。喫茶店でも、ファミレスでもいいんですけど・・・この時間が楽しいですね。
ある程度街の様子もお目当ての飲食店も把握できたところで街に繰り出します。
そして歩く。とにかく歩く。
歩かなければ街はわからない。街には街ごとに匂いがあり空気があります。これは歩いてみないと解らない。歩くついでに、目星をつけておいた飲食店の前を通り過ぎる。このとき、研ぎ澄まされた旅人の感性で紹介記事の真贋を確かめるわけです。
よし!と思えばその日の夜のスケジュールが確定します。予約をしておいたほうが無難な店構えならば散策の後、宿から予約の電話をいれるか、その場で電話をいれておく。
まあ、暇ならば土地の名所旧跡をそぞろ歩くもよし、博物館などで風土記を把握するもよし、好きにすればよろしい。筆者は博物館に行くことが多いですね。 →→→back
店に入る
ひとり旅の場合、最も肝心なのはリズムですね。
店に入る。
カウンターでもテーブルでも、とにかく居所を据える。
店内を見渡す。
メニューを頼む。
オーダーを吟味する。
酒を頼み、料理を頼む。
杯を傾ける。料理をつまむ。しみじみと首をふる。
再び杯を傾ける。
店内を見渡す。
しみじみと首をふる。
これら一連の流れが淀みなく運ぶお店はきっと居心地がいいはず。
何かかがひっかかる。
例えば、メニューがなかなか来ない。ほったらかしにされる時間が長い。常連さんの視線がチクチクと痛い。
そうした空気を感じたら、とっとと勘定を済ませて店を出るべきです。
「おいしさ」の限界効用逓減の法則はやはり存在します。 →→→back
裏をかえす
居心地のいい店に出会うことは、旅の楽しみのトップに据えられていい喜びです。
日常からの乖離、すなわち漂泊感は尻のすわりのいい店に出会うことによって癒されます。
そしてお店の人と交わす幾ばくかの会話。
媚びることもなく、背伸びすることもない、自然な賛嘆の念は自ずと先方に伝わるでしょう
それがその場の空気をさらに柔らかいものとしてくれるはずです。
そこまでいったら、カウンターごしであれ、テーブル席であれ、ちょっとチャレンジ。
異なる食種の飲食店を教えてもらいましょう。
これは土地勘のないところでは有効です。店の人もプライドにかけてそれなりのお店を紹介してくれることが多い。
ただ、間違っても例えば寿司屋で他の寿司屋を訪ねたりしてはいけません。違うジャンルの店を教えてもらうことです。
そしてその地に連泊するなら気に入った店をもう一度訪れる。
『裏を返す』ってやつですね。
花街では翌日訪れることを裏を返すっていうそうで、『上は朝来て昼帰る、中は夜来て朝帰る、下下の下の下が居続けをする』なんて申すそうで、へい。
これはかなりききます。
なんとなく前回よりもちょっと濃いサービスをうけているような気がします。
『裏を返す』中でも究極がその日のうちにもう一度顔を出すってやつ。
これは強烈に効きました。過去2回ほどしか経験がありませんが・・・
何年もの御馴染みさんのように歓待されました。飲み屋の話ですよ、これは。ああ、何様のつもり?私。 →→→back
宿
宿には懲りません。
ちょっとローテーションを組む程度。
リーズナブルなホテル→リーズナブルなホテル→ちょっとしたホテル→リーズナブルなホテルなんて感じ。
帰京の前日とか、疲労が溜まるとゆったりしたホテルを選ぶ。
旅館には原則泊まりません。駄目なんです。一泊二食の二食が。やはり餅は餅屋で料理は料理のプロが長年やっている料理屋で食べたい。宿は寛げればそれで十分。
それに旅館のプライバシーの無さもやや敬遠。温泉にあまり興味がないのもこの傾向に拍車をかけますね。
・・・といったところで、ああまたぞろどこかへ行きたくなってきたなあ。
どっか行くか。 →→→back
訪問地
→→→back