あらすじ
大学および各種研究機関に「三年の間に一定水準の論文を書いていない研究者は即解雇」という通称「(論文を)出すか(大学から)出されるか法」が施行された。
フィールドワークを伴う様な長期スパンでの研究者には不利な法律だ。研究者たちは湧き出る研究テーマを次々こなしたいとか、雑用に追われ論文執筆に時間がさけないとか、自分では書けない事情を抱えているとか、文章力がいまいちとかの理由で代書屋を頼む。字が書けるだけでいい落語の代書屋とは違い一定水準以上の”論文”の代筆。しかも成功報酬だ。その上執筆のみならずデータ集めや分析までも依頼されることがある。
第一話「超現実な彼女」
第二話「かけだしどおし」
第三話「裸の経済学者」
第四話「ぼくのおじさん」
第五話「さいごの課題」の連作短編集
感想
「山手線が転生して加速器になりました。」の作者による2012年頃の作品。
第四話「ぼくのおじさん」で帰納法というのがやっとわかった。というアタシには本作を読み解くのはなかなか難しい。無理そう。
話が進むにつれ文章がうまくなっているようには感じたな。それが作者の成長なのか主人公ミクラの成長を表わしているのかはわかりません。
主人公のミクラは科学史科を卒業したての代書屋新人。ポスドクの惨状を目にし大学院に進むことはなかったが、アカデミックな雰囲気が好きらしく大学周辺に居残り代書屋を始める。研究者を観察するというミクラのフィールドワークなのかもしれない。その傾向と対策はビジネスに繋がりそう。
初めて依頼された論文は『結婚と業績の相関 男性の研究者や芸術家は結婚後に生産性が落ちる』(単に若い時の方が成果があがるんやないの)というものだった。
コレを始めとして、単に興味をもっただけ・・・の研究が並ぶ。話をおもしろおかしく盛ってあると思うけれど(であって欲しい)、中卒や高卒で働いている人たちが払った税金もコレに使われるのかと思わないでもない。が、研究とは数撃ちゃ当たるのか、もともと何かの「役にたつモノ」ではないのかもしれない。
というアカデミックの甘さと、教授は研究者というより研究室を維持するための経営者となりはて雑務に追われているという「あるべき姿」とはかけ離れた現実も書かれている。
主人公はフワフワと脳内恋愛と脳内失恋している。だいたいお話が浮世離れしている。まあ世の中にはこういう世界もあるんやし、それも必要なことなんだと思う(おそらく)。主人公はピーター・パン症候群みたいに見えるし、いっぽう路傍土(ろぼうど)として一人前になろうともがいてもいる。これ作者自身を反映しているんちゃうかな。
作中に出てくるミクラ作一行自由詩が面白い。「すわればやっぱりゆでたまご 路傍土」 「きょうもさぼてんとふたり 路傍土」
★★★1/2戻る
ビリー・サマーズ
ビリー・サマーズ
2021年 スティーブン・キング著 白石朗訳 上307頁 下314頁
あらすじ
殺し屋ビリー・サマーズ44歳は報酬200万ドル(約3億円)の仕事を引きうける。
これを最後に引退することに決めた。
しかし「最後の仕事」って響きがとっても不吉・・な気がする。映画「現金に手を出すな」も最後の仕事だった。
感想
ビリーは頭の回転も速いけれど、じっくり物を考えるタイプでもあると思う。色々おもいを巡らす男。
最後の仕事はいつになるかわからないので、待っている間周囲にとけこむため「小説を書いている」という仮の身分を与えられる。
そこでビリーは手持ちぶたさもあり小説を書き始める。ここが面白い。
小説と言ってもまずは良く知っている自分の話。17歳半で海兵隊に入りイラクのファルージャでの戦闘シーンは「これを書きたいために作者はこの小説を書いたんじゃ」と思えるほどの出来。
下巻を読み始めて「上巻の方が面白かったかな」と思っていたが、最後は怒涛の様。
映画「つぐない」のようなラストもよかった。
さすがスティーブン・キング。
ビリーは若いビリー・ボブ・ソーントンかなと思って読んでいた。まあビリー・ボブ・ソーントンに元軍人は無理があるか。
どうやら映画化はレオナルド・ディカプリオの可能性が高いらしい。演技うまいからビリーが装っている「お馬鹿なおいら」も上手だと思う。
ところどころトランプ氏について書かれているところがあって、今読んでるとちょっと哀しい。
★★★★1/2戻る
檜垣澤家の炎上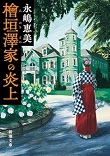
檜垣澤家の炎上
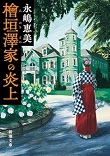
新潮文庫 2024年 永嶋恵美著 774頁
あらすじ
1904年(明治三十七年)日露戦争開戦の年に高木かな子は横濱に生まれる。七歳の時に母を火事で亡くし父の家、檜垣澤家に引き取られる。
母は父檜垣澤要吉の妾だった。
感想
一代記のさわりと言ってもいいかもしれないけど、作者渾身の作は読みでがあった。続編はでない気がする。
日露戦争に勝利し、1914年から始まった欧州戦争(のちの第一次世界大戦)で大戦景気に沸く大正期港湾都市横濱の情景も面白い。
高木かな子が暮らし始めた檜垣澤家は絹物の貿易で財をなした。
当主要吉は病に倒れ要吉の妻”大奥様のスヱ”、長女の”奥様の花”、孫娘の”若奥様の郁乃”が婿を表に出しながら内実は商売を仕切っている女系一族。
女性には選挙権も無く、女学校を出てもどこかの家の嫁、妻、母になるしかなかった時代に、ネットワークを築き情報を得て事業を動かしている女たち。
使用人でもなければ、一族でもない高木かな子は、亡き母の教え「人の顔色、声色、腹の色を見る」を守り、いずれ商売に都合のいい相手に嫁がされる運命に知力の限りをつくしてあらがう。
かな子が「人の顔色、声色、腹の色」を見る訓練に一族や使用人だけでなく書生たちも一役買っている。
書生たちは田舎では神童と呼ばれた頭のよい、勉強のできるひとたちだ。かな子はもまれ鍛えられていく。
最初はかな子は感情のない合理的なひとなのかなと思っていたけれど、段々と人間味がでてくる。
この小説の特色は、薄幸なのは女性ではなく男性なの。
★★★★戻る
殺人は夕礼拝の前に MURDER BEFORE EVENSONG
殺人は夕礼拝の前に MURDER BEFORE EVENSONG
早川ポケットミステリ 2022年 リチャード・コールズ著 西谷かおり訳
あらすじ
英国の田舎の村で教会にトイレを設置するか、いままで通りトイレ無しのままとするかで信徒の意見が真っ二つに分かれる。
司祭のダニエルは「造る派」であり、穏便にトイレ設置を推進するのに頭を悩ませている。
感想
地主一族と館、村の教会と司祭、そして村人の信徒たちという英国のお家芸とも言えるミステリ。
地主一家が相続税軽減のために、年二回屋敷とお宝を一般公開するのが面白い。村の一大イベントになっている。
お芝居好きの英国らしく村人たちは使用人もどきとなり観光客をもてなす。地主の仕事はうっかりパジャマ姿で屋敷内をうろうろしないことだけ。
ドラマ「ブラウン神父」や「シスター探偵ボニファス」の世界であるが、時代は1988年。21世紀が見えてくるころだ(ちなみに日本は昭和が終わり平成に入る頃)
読んでいると1950年代初めと思われる「ブラウン神父」の世界に心地よくどっぷりつかるが、時代はヒタヒタと変わりつつある。
1962年生まれの作者はラジオのパーソナリティやミュージシャンを経て2005年から英国国教会の牧師として活動されているそうです。
ゲイであることもカミングアウトされているとか。
クリスチャンでもプロテスタントでもない英国国教会の村の聖職者は、信徒から司祭でも牧師でも神父でもなく「先生」と呼ばれているのがあたらしかった。
★★★1/2戻る