| ◆◆◆◆ 船橋浄水場 ◆◆◆◆ (道明寺浄水場・野中配水場Ⅰ・野中配水場Ⅱ) |
| (ふなはしじょうすいじょう) 船橋浄水場:船橋町15-1 所管:大阪広域水道企業団藤井寺水道センター(市役所4階) TEL:072-939-1302 FAX:072-939-7036 近畿日本鉄道道明寺(どうみょうじ)線・柏原南口駅より南へ約570m徒歩約9分 同 南大阪線・土師ノ里(はじのさと)駅より北東へ約1.4km徒歩約22分 府道12号堺大和高田線・石川橋西詰から堤防道路を北東へ約870m 敷地面積:6,710.5㎡ 延床面積:2,026.0㎡(管理棟ほか4施設) 開設:1967(昭和42)年6月 |
| 石川の伏流水を利用-地下水を浄水 かつて藤井寺市水道局のサイトにあった「藤井寺市の水道」の説明では、『藤井寺市の水道は、大和川水系石川沿いの伏流水(浅井戸)を 水源とした道明寺浄水場・船橋浄水場の自己水と、淀川を水源とした大阪広域水道企業団からの浄水受水でまかなっています。主な施設は 道明寺浄水場、船橋浄水場、野中配水場Ⅰ、野中配水場Ⅱの4ヵ所です。給水区域はすべて管網で連絡しており、各施設からポンプ圧送で 市内配水しています。』とありました。船橋浄水場を代表とする藤井寺市の水道施設を紹介します。 藤井寺市の水道事業は、70年近くに渡って旧道明寺町・旧藤井寺町、合併後の藤井寺道明寺町・美陵(みささぎ)町、市制移行後の藤井寺市と いう自治体によって運営されてきました。しかし、近年の大阪府内では、水道事業のより効率的な運営を目指して広域事業化が求められて きました。そして府内の市町村による協議を経て、「大阪広域水道企業団」が創設され水道事業の広域協働化が進められてきました。企業 団は大阪市以外の42市町村による一部事務組合として構成され、藤井寺市の水道事業も2021(令和3)年4月1日より企業団に移管・統合され ました。藤井寺市水道局は「大阪広域水道企業団藤井寺水道センター」と名称を変えて、従来通り市役所内で業務を行っています。 |
||
| 船橋浄水場は藤井寺市に3ヵ所つくられた浄水場の一つ で、1967(昭和42)年6月に2ヵ所目の浄水場として完成し ました。ここから1.2kmほど南には最初にできた道明寺 浄水場があります。どちらの浄水場も大和川や石川のすぐ 近くにありますが、川の水を直接取水しているわけではあ りません。川の地下深くにある伏流水をポンプで汲み上げ て利用しています。 船橋浄水場では浅井戸で伏流水である地下水を汲み上げ て浄水しています。浄水能力は 7,030 は 4,000 てできた水道水を貯めておく大きな貯水槽です。ここから ポンプで送出されて行きます。 船橋浄水場は敷地が狭いため、濾過池(ろかち)を造る代わり に、タンク形濾過機7基を設置して使用しています。この 浄水場は藤井寺市の東北の端っこにあり、ここから送水さ れた水はおもに藤井寺市の北側半分ぐらいの地域で利用さ れます。他の地域では、大阪広域水道企業団(旧大阪府営水 道)から受水した水や道明寺浄水場から供給される水が利用 されます。 船橋浄水場は地下水を利用しているので、ここから送ら れる水は比較的、夏は低め冬は高めの水温です。道明寺東 |
 |
|
| ① 船橋浄水場(南東側石川堤防上より) 2010(平成22)年6月 合成パノラマ 敷地は、手前石川堤防と後方近鉄・道明寺線軌道敷に挟まれた盆地のような地形 である。 敷地が狭いため、濾過池の代わりに濾過機(濾過タンク)が並んでいる。濾過 機後方の建物が主棟で、送水ポンプ室がある。 |
||
 |
||
| ② 船橋浄水場(北東側石川堤防上より) 2010(平成22)年6月 合成パノラマ 中央の青いカバーのある施設は、着水井・薬品混和池・沈澱池。この後、濾過機に送 られ、配水池に貯められる。 |
||
| 小学校は船橋浄水場の最も近くにある学校なので、真夏でも給水して間もないプールに入ると大変冷たく感じて震えることがあります。一 晩かけて給水するのですが、翌朝プールに入った子どもたちからは、決まって「冷たっ!」の声が出ていました。 |
||
|
||||||||
| 三つ目の浄水場は野中浄水場で、市内人口の急増に対応して市の南部に造られました。市内では 最も標高の高い部分なので、200mもの深井戸で地下水を汲み上げ利用していましたが、水量の減 少や水質低下などにより、数年後には浄水事業は停止しました。大型の配水池を増設して、府営水 道(現・大阪広域水道企業団)から購入する水道水を貯水してから配水する配水場の役目に変わり、 施設名も「野中配水場Ⅰ」となりました。近くにもう一つの配水場「野中配水場Ⅱ」があります。 こちらの方が前からある配水場ですが、規模の違いから野中配水場Ⅰの方が中心となっています。 これらの配水場から送水される水道水は、おもに藤井寺市の西側地域を中心に利用されます。 藤井寺市域の公営水道のあゆみ 藤井寺市域内で最も古い上水道の歴史は、公営水道ではありませんでした。1927(昭和2)年3月に 藤井寺駅近くで住宅地分譲を開始した当時の大阪鉄道(近畿日本鉄道の前身の1社)は、藤井寺駅の 南西一帯に約11万坪(約36ha)にも及ぶ「藤井寺経営地」という、今で言うニュータウンの開発事業 を行いました。その中には、藤井寺球場や藤井寺教材園も含まれていましたが、大阪鉄道は藤井寺 |
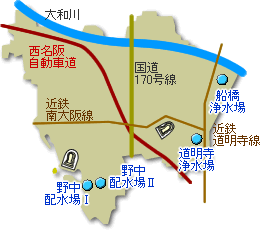 |
|
| ③ 藤井寺市の浄水・配水施設 旧藤井寺市水道局サイト「藤井寺市の水道」より |
||
|
球場敷地内に水源施設を設置して、経営地内の500戸余りに給水する上水道を整備しました。これが藤井寺市域における初の上水道施設で した。ちなみに、藤井寺経営地の住宅地には下水道も整備され、電話線の引き込みもいち早く行われています。 ところが、この藤井寺経営地以外の従来からの村落では依然として井戸の使用が続いており、上水道による給水は戦後10年近くまで待た なければなりませんでした。 戦後、まず上水道事業に取り組んだのは旧道明寺町でした。1951(昭和26)年に道明寺村から町制施行した道明寺町は、上水道の敷設をす べく、翌昭和27年には水源地(現道明寺浄水場)の用地買収を行います。そして、翌昭和28年に工事を進め、年末には一部で給水を開始し ました。旧道明寺町はその東部が石川に接しており、地下水として存在する石川の豊富な伏流水が水源として利用できました。 一方、旧藤井寺町でも上水道の早い実施が強く望まれました。1952(昭和27)年12月の町議会で上水道敷設事業の施行が議決され、翌昭和 28年3月31日に敷設が認可されますが、その「理由書」には、『…、近時隣接の道明寺町、国分町(現柏原市)、駒ヶ谷村(現羽曳野市)等に於いて 水道敷設せらるるに至り、特に数年来世論は上水道の速成を高調するに至りしが、然るに本町は上水道敷設中もっとも重要なる水源町内に なく今日に至りしに、…』 (『藤井寺市史第三巻・通史編3近現代』)という一節が見られます。この時の「目論見書」(同市史)で事業内容を見 ると、水源としては大阪府営水道からの受水計画が書かれていますが、旧藤井寺市水道局サイトの「水道事業のあゆみ」では、道明寺町の 水源地からの送水を受けたことになっています。この辺りの経過については、市史の記述内容だけではよくわかりません。 この後、旧藤井寺町と旧道明寺町は一部事務組合をつくって、水道事業を共同で経営することになります。旧藤井寺町は近畿日本鉄道か ら水道施設の譲渡を受けますが、この施設や道明寺水源地施設を両町の共有財産とする契約が交わされました。旧藤井寺町は道明寺水源地 から送水を受けて給水を実施しました。1959(昭和34)年に両町が合併して一つの自治体となり、1年後には水道事業の運営も一本化されま した。その後は、人口急増に対応して府営水道からの受水や浄水場の増設など、水道事業の急速な拡大が続きました。人口増加が止まって 以降は、初期の配水管の老朽化対策が課題となってきており、配水管整備事業が計画的に実施されてきました。 下の表は、藤井寺市域の水道事業の簡単な歴史をまとめた年表です。二つの旧町が独自に水道事業を開始し、やがて合併によって統合さ れた水道事業となる歴史でもあります。 |
||
| 藤井寺市域の水道事業の歩み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旧藤井寺市水道局サイト「藤井寺市の水道-水道事業のあゆみ」(現在は掲載されていない)の内容を基に一部追加して構成。 |
| 道明寺浄水場 | |||
|
|||
| 上で述べた通り、道明寺浄水場は藤井寺市域で最初に設置された公営の浄水 場です。旧道明寺町が設置した道明寺水源地がもととなっています。旧道明寺 町の給水人口を想定して造られたので、もともとの規模は小さいものでした。 後に給水能力の強化が図られますが、敷地も狭いものだったので、限りがあり ました。石川の伏流水を汲み上げて浄水としていますが、1980年頃に大阪府営 水道(現大阪広域水道企業団)からの受水のために配水池が増設され、自己水と 府営水の両方を給水するようになりました。道明寺浄水場から供給される水は おもに藤井寺市の南西部の地域で利用されています。 右の写真⑤は、GoogleEarthの衛星写真を3D機能で疑似鳥瞰写真にしたもの です。ポンプ室の表示がされた主棟とその駐車場がもともとの敷地でした。狭 い敷地であったことがわかります。 写真④⑤の様子は、大規模な改修工事を終え2020(令和 2)年に完成した新し い道明寺浄水場の姿です。ろ過器が設置された長方形の敷地が、もともとの半 地下式貯水池でした。ろ過器は以前はポンプ室の左側、線路側に並んでいまし た。もとの敷地では濾過池を造るスペースはなく、ろ過器が設置されていまし た。道明寺浄水場も石川に近く、浅井戸で伏流水である地下水を汲み上げて浄 化しています。 2021(令和3)年4月1日より市営水道が大阪広域水道企業団に移管・統合された ことにより、従来の市水道局のWebサイトが廃止されました。そのため、新し い道明寺浄水場の施設延床面積や1日当たりの浄水能力などのデータを取得す ることができなくなりました。 |
 |
||
| ④ 道明寺浄水場(南西より) 2022(令和4)年4月 | |||
 |
|||
| ⑤ 道明寺浄水場(南西より) 〔GoogleEarth 3D画 2020(令和2)年〕より 主棟建物の向こう側には近鉄南大阪線が通っている。 |
|||
| 野中配水場Ⅰ・野中配水場Ⅱ | ||
| (旧野中浄水場) (旧野中配水場) | ||
|
 |
| ⑥ 野中配水場Ⅰと野中配水場Ⅱ(南より) 〔GoogleEarth 3D画像 2015(平成27)年〕より 野中配水場Ⅰは敷地も広く、タンク式濾過機ではなく濾過池が設置された。 文字入れ等一部加工 |
| 上の写真⑥も、3D機能による疑似鳥瞰写真です。野中配水場Ⅰと 同Ⅱは、すぐ近くにあることがわかります。もともと、1965(昭和40) 年に野中配水場(現配水場Ⅱ)が先に造られました。昭和30年代に始まった人口ドーナツ化現象の中で、藤井寺市域(当時美陵町)の給水需要 が増大しており、その後の人口の大幅増加も予想されていました。当面府営水道からの受水を増やす必要があり、その受水施設として野中 配水場が造られました。配水場は府道31号に接していますが、配水場ができた時にはまだ府道は開通していませんでした。昭和40年代初 めに、この府道31号ともう少し東側を南北に通る大阪外環状線(現国道170号)の建設工事が進められますが、この新しい幹線道路のルート に沿ってその地下に府営水道の送水管が敷設されたのです。この府営水道の送水管は、藤井寺市を通過するとともに2方向に分かれます。 府道31号に沿う西向きの送水管は堺・泉北方面へ、大阪外環状線に沿う南向きの送水管は南河内地域から泉南方面へと延びていきます。 経済高度成長下で人口急増が続く中、大阪府全体の水需要増加に対応する上水道拡大事業の一環でした。なお、府営水道の送水管が経由・ 分岐する藤井寺市内には、2ヵ所の府営水道ポンプ場(現大阪広域水道企業団ポンプ場)が設置されました。「藤井寺ポンプ場」と「美陵ポ ンプ場」です。送水する水量や水圧の調整などを行う中継ポンプ場です。 野中配水場Ⅱでは、大阪広域水道企業団から受水した水を配水池に貯水しておいてポンプで地域に送出します。配水池は、2,600 ものが一つあります。 野中配水場Ⅰは、市内3ヵ所目の浄水場「野中浄水場」として1974(昭和49)年に開業しました。それまであった道明寺浄水場と船橋浄水 場はどちらも市の東の端にあり、西側の旧藤井寺町地域は多くを府営水道水に頼るようになっていました。水重要の急増に対応すべく、第 3の浄水場建設が、市の南部であるこの場所で進められました。この地域は南から延びる羽曳野丘陵に続く、市内では最も標高の高い地域 であるため、地下水の水位が低く、汲み上げのために200mもの深井戸が掘られています。この辺りは、昔から灌漑用水として多くのため 池が分布していた所でもあったのです。 200mもの深さの地下水を利用することに、もともと無理があったのかも知れません。野中浄水場は開業後10年ほどで浄水事業を停止し ます。地下水の水量減少が起こり、ついには水源枯渇で浄水機能を果たせなくなったのです。給水量の不足は府営水道水に頼ることになり 野中浄水場には配水池を増設し、配水場として事業を行うことになりました。上の写真で、芝生敷きの配水池が元からのもので、台形のコ ンクリート敷きのものが増設された配水池です。野中配水場Ⅰでも、大阪広域水道企業団から受水した水を配水池に貯水しておいてポンプ で地域に送出します。配水池は、4,000 野中配水場Ⅰ・Ⅱから送水される水は、おもに府道12号・堺大和高田線以南の藤井寺市南西部で利用されています。現在、藤井寺市の水 道の水源比率は、およそ半分強が自己水(地下水)で、残りの約半分弱が大阪広域水道企業団送水管からの受水分です。 |
