|
コロナ禍の間、夏の舞踏ワークショップは中止となりましたが、昨年2022年に再開しました。 |
(以下は2016年以前の内容で、昔ののメモ書きとして残しています) 昨年から、土日を中心にして金曜日や月曜日を含めた「週末ワーク」に参加する方が少しずつ増えています。海外からフラリと参加されるのですが、だいたいBUTOHのワークショップを海外で体験して刺激を受けた方が多いです。それでも、わざわざ札幌まで脚を伸ばしてくれるのは有り難い限りで、こちらも舞踏による身体訓練をきちんと指導して、舞踏ということをわかってもらえるように指導しています。 ほとんどの人が横浜にある大野一雄舞踏研究所でのWSに参加しているようです。今は慶人(ヨシト)さんとお弟子さん達が切り盛りしていますが、国内で何十年も継続しているスタジオなので、海外から来た人が立ち寄る「舞踏のメッカ」のようになっています。 それにしても、ここ数年に札幌の竹内実花BUTOH研究所で舞踏ワークショップを受けた海外の人の共通点としては、「日本発の舞踏」の基本についてほとんど知らなかったり体験したことがない項目が多いことです。 「ゲタ足」を知らない、「上体の前傾」について知らない、「コウベを垂れること」や「ガニ股」を知らない…。他にも驚くようなことがいろいろありますが、アメリカやヨーロッパのbutoh-dancerやbutoh-groupでレッスンを受けただけなので、舞踏の基本中の基本を体験することがなかった、ということがありました。 こうした形や姿勢や動きは、しかし、振り付けとしてあるのではなく、暗く深く痛みを伴う「前衛舞踊」つまり「アバンギャルド」としての「舞踏という踊り」の「精神」と言っても過言ではありません。 振り付けとしての動きということならば、昨今のプロモーションビデオなどで踊るバックダンサー達の動きの方に、なかなかのものがあるくらいです。しかし、舞踏というところに長くいる私から見ると、正面志向性が強すぎて飽きる…頭の中でカウントしているのが見えすぎる…、動きを思い出してなぞっているのが見える…などが気になります。私の個人的な嗜好に過ぎませんが…。 そういうダンサー達は、誰も見ていないところ、鏡のない所、カメラのないところでは踊りにならないか、あるいは踊らないのかもしれませんね。 舞踏に限られませんが、痛みとくぐもった身体を持ち生きてきた私自身を、カミなのか祭壇なのかに捧げること…。「踊り」には日常を超えた、そうした側面があるわけです。そうしたことのために踊る…。フツーのダンスと舞踏との違いの一つともいえるでしょう。 青空の広がる高い世界を見上げながら、公園やストリートで踊るとき、誰かに見せようとする踊りがどのくらい「卑小 いやしくてちいさい」かをふと感じてしまいます。独り言…。 昔、札幌雪祭りの大雪像の雪の舞台で踊っていたとき、どんどんと強まる吹雪の中で観客が一人減り二人減りして、少しずついなくなっていくのです。 吹雪でよく見えなくなる中で踊ったデュオの偶成天の踊りは、もう人様に見てもらうとか、観客に見せるとか、そうしたことではない踊りとしてありました。凍えて動きにくくなった指先を温めながら踊るとき、生きていること・死んでいくことの狭間を感じていたと思います。 舞踏ということによって、心にしみるそうした時間を過ごすことができたこと。あらためて思い出したりします。 森田一踏
以下はこれまでの書き込みです。参考まで掲載しています。
(1/15, 2014)
2014年、午年(うまどし)…。最近、久しぶりにダンスのレッスンを見る機会がありました。20代から40-50代くらいまで年齢の幅が広く、かつてのジャズ・ダンス的な動きから最近のヒップ・ホップやストリート・ダンス的なものまで、様々な踊りが含まれていました。その意味では見ていて楽しかったのですが、舞踏ということとずいぶん違うなあ…と感じ入りました。当然といえば当然ですが。 昨年、大野一雄や舞踏をこよなく愛していた釧路のジスイズもマスターの東さんが倒れて休業となり、舞踏の世界が急にしぼんだ感じがしたのですが、今回、レッスンを眺めていて、技術的にも精神的にも舞踏 BUTOHという踊りには命が残っていると感じられたのでした。 いろいろな感想がありますが、「踊りや身体や姿勢やスタイルを見せようとする意識」が妙に目立っていたことが印象的でした。テレビ映りがよい方が良い―ということでしょうね…。 舞踏では、音楽のカウントを数えたり音に合わせて踊ったりは、あまりしません。それに対して、音やリズムに合わせて踊る踊りでは、カウントやリズムが十分に身体化していないときは、頭の中で数えたりリズムをとったりしているのが見えてしまいます。若くてエネルギーにまかせて動いているダンサーは、上手下手よりもそうした迫力に魅せられることもありますが…。 また、ときには「…私はかっこうよく動いている」「ここで向こうに行ってみよう…」「こんな風に展開してみよう…」などの意識も妙に見え透いてしまいます。それは、そのような気持ちが働いて踊っているため、そうしたことが頭の動きや目線や姿勢の準備状態などに浮かび上がってためですが、まあ、どの領域でも練習、稽古が必要ということで。 それにしても、この20年近く精神科領域でリアルでシリアスな動きやあり方に遭遇してきたので、そうした経験も影響しているようです。最近は舞踏以外の踊りは、テレビで見るクラシックバレエや民族舞踊以外はほとんど見なくなったのだ…と思い出してしまいました。 それでは舞踏ではそういうことはないのか?!と尋ねられそうですが、「はい、そういうことに陥らないのが舞踏という世界です」と答えることになります。ではそれはどうやって実現しているのか?!とさらに追求されれば、「リアルであること」とリアリティの話になりますが、なかなか説明しにくいので、「まあ、そうですね。レッスンに来てみてますか!?」と言ってしまいがちです。 言葉で説明できないことはないのですが、舞踏の体験のない人には分かりにくい言葉で説明することになるので、結局は体験してもらうのが一番だと、この25年ほどの経験から、つぶやくことになります。 昨年は、日系オーストリア人の若い女性でウィーンでダンスを学んでいるダンサーが、舞踏の集中ワークショップに数回参加しました。「今年の夏休みにもまた来ます」ということなので、それなりにレッスンが面白いようです。それは当然で、他のダンスではやらない様々なレッスンがあるので飽きないし深まる…ということのようでした。 ところで、彼女は他のダンサーと同様に、若いのにひどい腰痛持ちで、このままでは近々踊れなくなりそうでした。そこで、骨盤の角度を変えて背骨の長さを長くするレッスンをして、腰痛にならない姿勢を作ることにしました。普段はやらない姿勢ですが、舞踏ではよく出てくる姿勢で、やや猫背で田植え的な姿勢と動きですが、これだと腰痛にならないのですねえ。「コンテンポラリー・ダンスはやめて、もう舞踏にしたら?!」などと誘っていますが、腰痛が悪化したら最後には舞踏的な踊りしか残らないと思われます。 ところで、舞踏について技術的なことで言うと(企業秘密的なところもあるので詳しくは書きませんが(^_^v)、あなたは踊りの中で「あごのレッスン」をしたことがありますか?それでは「上顎のレッスン」はどうですか?ため息とともに「花魁の歩行」をしたことはありますか?「肘の踊り」「膝の踊り」をしたことがありますかねえ? えっ? 聞いたことのないものばかりですって?! 舞踏では動きや体の使い方について、踊りのパーツの稽古もいろいろとあります。どこかの誰かが作った動きや姿勢をなぞるだけではなく、自分の身体の長さや重さや角度や速さの違いを生かして、他の人にはできない動きなどをどんどん探し当てていきます。私はこのあたりが特に面白いと感じることが多いです。 ということで、私もだいぶ年をとりましたが、まだワークショップや稽古をしているうちに、気が向いたらどうぞスタジオを訪ねてください。私の経験したことを伝えていくつもりでいます。皆さんは、それを手がかりにして自分の舞踏や踊りをどう作り出していくか…ことで良いと思っています。 舞踏「偶成天」 森田一踏 (1/15, 2014 )
資料: 以下は旧年度の内容です
2012年は例年のように海外からの参加者を中心にワークショップを実施しました。竹内実花の舞踏レッスンを受けている生徒さんも参加してくれましたが、様々なダンスの背景をもってわざわざ日本・札幌までやってきた海外からの参加者との交流は大変に刺激になったようです。踊りやあり方にずいぶん変化がありました。 2013年は、これまでやったことのない冬のワークショップを実施します。三月は札幌はまだ雪が残っており、まだ春ではありません。そうそう、このことは海外からの参加者に連絡しなくては…。 三月に実施することになったのは、その時期に参加したいドイツの人がいたこともありましたが、今年からまたあらためて舞踏活動を深めていく予定だったのでちょうど良いタイミングでした。それと意外にも三月にやってきたいという希望者が他にもいたこともあり実施に踏み切ったわけです。 ということで今、三月のワークショップの受付などをしているところですが、その最中に大きな転機が起こりました。 釧路のジャズ喫茶「ジスイズ」のマスターの小林東さんが脳梗塞で倒れた…ということが伝わってきたのです(1/26, 2013頃)。函館出身の舞踏家・大野一雄の大ファンで、釧路の小さなジャズ喫茶に何度も来てもらっていました。大野一雄や土方巽夫人の元藤燁子さんを呼んで行った舞踏公演では、私は微力ながらお手伝いしたり、その縁もあって森田一踏+竹内実花とで元藤さんと一緒に踊ることもありました。大野一雄が舞台の前に小さなメモを握りしめて舞台の準備をしていたところ、実花さんが大野さんの手を引いて舞台へと導いたこともありました。今は全て懐かしい思い出です。元藤さんは2003年2死去、大野一雄は2010年に死去、103歳でした。東さんにはいろいろと励ましてもらったり、近々、踊りに行きますと言いましたが、そのまま何年も経ってしまいました…。東さんにはまた元気になってもらいたいですが、ジスイズは店を閉じるようです。残念ですが、これも一つの時代の流れと感じています。 私は人見知りというか、人との関わりが少ないのですが、元藤さんのホームページを作ったりなどして、元藤さんとはつながりがありました。その関係で、butoh/ittoのサイトには、土方巽と元藤燁子の写真が掲載されています。そうした写真は元藤さんに掲載の許可を得たものですが、しかし、そうした舞踏の世界が、私の周りからどんどんと遠のいて行っています。私自身の一部がどんどんと消え去っていくような寂しさに襲われています。 そうした最中、私で伝えられることは次の世代や関心のある国内・国外の人たちに伝えられればと思い、今年は精力的にワークショップや舞踏活動を行うことにしています。 (以下は2012年の説明です)
|

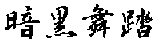
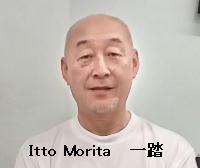 この20数年間、毎年行っている夏の集中舞踏ワークショップへのお誘いです! 今年もアナウンスをする時期になりました。ワークショップは1990年代から継続していますが、SNSなどで共有することなく、ひっそりと実施しているのは、
この20数年間、毎年行っている夏の集中舞踏ワークショップへのお誘いです! 今年もアナウンスをする時期になりました。ワークショップは1990年代から継続していますが、SNSなどで共有することなく、ひっそりと実施しているのは、