|
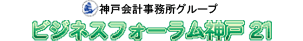
Business Forum Kobe 21 |
|
|
�g�b�v�y�[�W�@�����Z
| �N�������T�v |
�P�D�ی����̈����グ
|
�i1�j |
�����N���ی����̌��s13.58���̗������A���N��10������A���N0.354�����A����29�N10����18.35���ɒB����܂ŁA���グ���Ă����܂��B |
|
�i2�j |
�����N���ی����͌��s13,600�~���A���N��4������A���N300�~���A����26�N10����16,600�~�ɒB����܂ŁA���グ���Ă����܂��B |
�Q�D60�`64�܂ł̍ݐE�V��N���̉���
|
���s�@�F�ꗥ�J�b�g�@���@�@(�N���{���^�|28���~)�~0.5���J�b�g
�����āF�ꗥ�J�b�g���p�~�A(�N���{���^�|28���~)�~0.5���J�b�g

����̗၄
�N��10���~�A���^30���~�̏ꍇ
���s�@�F10���~�|{10���~�~0.2�{(8���~�{30���~�|28���~)�~0.5}=3���~
�����āF10���~�|(10���~�{30���~�|28���~)�~0.5}��4���~ |
�R�D65�`69�܂ł̍ݐE�V��N���̓K�p�g��
|
���s�@�F65�`69�܂ł̍ݐE�҂�ΏۂɁA(�N���{���^�|48���~)�~0.5���J�b�g
�����āF65�Έȏ�̂��ׂĂ̍ݐE�҂�Ώ��ɁA����̔N���J�b�g���s���܂��B

���Ή���
�@�������70�Έȏ�ɂȂ��Ă��A���^�̋��z���N���z�{48���~�ȏ�ł���A�N����1�~���ł��Ȃ��Ȃ�܂��B

�@�������A�ݐE�V��N�����K�p�����̂͌����N���K�p���Ə��ɋΖ��������N���ɉ�������ꍇ�Ɍ����Ă��܂��̂ŁA�����N���ɉ������Ȃ��Ă��悢����ŋΖ�����ꍇ��A�����N���̂Ȃ��l���Ə��Ȃǂœ����ꍇ�ɂ́A�N���J�b�g�͂���܂���B |
�S�D��Ǝ�w�̔N������
|
������x�������ی����ɂ��ẮA�v�w���������S�������̂Ƃ݂Ȃ��āA�v�̘V������N�������z�́A�v�w���Ƃ���65�ɂȂ����i�K�ŁA��Ǝ�w�̍Ȃɕ�������Ďx������܂��B |
�T�D�������̔N������
|
�������ɕv�w�̍��ӂ�����ꍇ�A�N�������O�̊��Ԃ��܂߂��������Ԃɉ������N���z�����z�����x�ɕ����̑Ώۂɏo���܂��B |
�U�D�q�̂��Ȃ�20��̍Ȃ̈⑰�N��
|
�q�̂��Ȃ�20��̍Ȃ��ł���⑰�N�����A���s�͍Ȃ̎��S���܂Ŏł��܂����A�������5�N�������ł��Ȃ��Ȃ�܂��B |
�V�D�玙�x�ƒ��̕ی����Ə�
|
�i1�j |
�玙�x�ƒ��̕ی����Ə����Ԃ��A���s1�N����3�N�ɉ�������܂��B |
|
�i2�j |
���A��A���^�����������ꍇ���A�q��3�ɂȂ�܂ł́A�x�ƑO�̕ی����z��[�t�������̂Ƃ݂Ȃ��Ă��炦�܂��B |
|
�� ���̃y�[�W�̃g�b�v��
���Z�̃g�b�v�y�[�W��
�g�b�v�y�[�W��
�@ |
| ���K�͊�Ƌ��� |
1.�@���x����|
|
���K�͊�Ƌ��ϐ��x�́A���K�͊�����l���Ǝ��̕�����Г��̖����̕������Ƃ�p�~������������ސE�����ꍇ�ȂǂɁA���̌�̐����̈���⎖�Ƃ̍Č��Ȃǂ̂��߂̎��������炩���ߏ������Ă������߂̋��ϐ��x�ŁA����u�o�c�҂̑ސE�����x�v�Ƃ�������̂ł��B |
2.�@���x�����F
|
�E�����^�c���Ă��鐧�x
�E�|���Ƃ��̉^�p�������S�Č_��҂ɊҌ������
�E�^�c�ɕK�v�������o�����A�S�z���ɂ���⏕����Ă���
�E����L��
�E���ϋ��̎���́A�ꊇ�����A���������A���́A���҂̕��p���I���ł���
�E�|���͈͓̔����ݕt���x�����p�ł��� |
3.�@�������i
|
�펞�g�p�����]�ƈ�(���j��20�l�i���ƂƃT�[�r�X�Ƃł�5�l�j�ȉ����l���Ǝ�����Ђ̖����A���K�͈ȉ��̊�Ƒg���E���Ƒg���̖����̕��ł��B
(��)"�펞�g�p����]�ƈ�"�ɂ́A�Ƒ���Վ��]�ƈ��͊܂܂�܂���B�܂��A������ɏ]�ƈ��������Ă����ό_��͌p���ł��܂��B |
4.�@�|��
|
�����̊|����1,000�~����70,000�~�܂ł͈͓̔��i500�~�P�ʁj�Ŏ��R�ɑI�ׂ܂��B������A���E���z���ł��A�O�������ł��܂��B�i�������A���z����ꍇ�A���̗v�����K�v�ł��j
�܂��A�|����[�߂邱�Ƃ�����ȏꍇ�́A�|���~�߂��ł��܂��B |
5.�@���ϋ�(�P�ʁF�~)
| ���� |
�|�����v�z |
���ϋ��` |
���ϋ��a |
�����ϋ� |
| �T�N |
600,000 |
621,400 |
614,600 |
600,000 |
| �P�O�N |
1,200,000 |
1,290,600 |
1,260,800 |
1,200,000 |
| �P�T�N |
1,800,000 |
2,011,000 |
1,940,400 |
1,800,000 |
| �Q�O�N |
2,400,000 |
2.786,400 |
2,658,800 |
2,419,500 |
| �R�O�N |
3,600,000 |
4,348,000 |
4,211,800 |
3,832,740 |
�@���蓖��
|
12�����ȏ�̊|���[�t�����ɉ����āA�|�����v�z��80%�`120%�����z�ƂȂ�܂��B
�������A���蓖���ɂ��ẮA�|���[�t������240���������̏ꍇ�́A�|�����v�z�������܂��B |
6.���ώ��R
|
(1)���ϋ��`
�E�l���Ƃ���߂��Ƃ��i���S���܂ށj�B
�E��Ђ��Ƒg���E���Ƒg���̖��������̖@�l�̉��U�ɂ���߂��Ƃ��B
(2)���ϋ��a
�E���������a�E�����ɂ���������߂��Ƃ��B�i���S���܂ށj
�E65�Έȏ��15�N�ȏ�|�����Ă��鋤�ό_��҂��琿�����������Ƃ��B�i�V��t�j
(3)�����ϋ�
�E�l���Ƃ������o���ɂ���Бg�D�ɂ����āA���̖����ɂȂ�Ȃ������Ƃ��B
�E�l���Ƃ�z��҂�q�ɏ������Ƃ��B
�E���������a�E�����E���S���邢�͉��U�ȊO�̗��R�őސE�����Ƃ��i�Ⴆ�Ζ����̉��I��C�������Ȃǁj�B
(4)���蓖��
�E�C�Ӊ���Ƃ��B
�E�l���Ƃ������o���ɂ���Бg�D�ɂ����āA���̖����ɂȂ����Ƃ��i���K�ȊO�̎��Y���o�������ꍇ�ł��B���̏ꍇ��Ȃ��Ōp�����邱�Ƃ��ł��܂��j�B
�E�|����12�����ȏ�ؔ[�������߁A���Ƃ��ꂽ�Ƃ��B |
7.�@�Ŗ@��̎戵��
|
(1) �|��
�@�|�����S�z���u���K�͊�Ƌ��ϓ��|���T���v�Ƃ��āA�ېőΏۏ������z����T������܂��B
�@�܂��A1�N�ȓ��̑O�[�|�������l�ɍT������܂��B
(2) ���ϋ�
�@�ꊇ���苤�ϋ��ɂ��Ă��ސE���������A�������苤�ϋ��ɂ��Ă����I�N�����̎G���������ƂȂ�܂��B |
8.�@�ߐŌ���(�P�ʁF�~)
|
�@�@�ېŏ��� |
10,000,000 |
|
|
�A�@�|���i�N�x�j |
840,000 |
|
|
�B�@���Ŋz |
361,200 |
|
|
�C�@�N�� |
20�N |
|
|
�D�@�|�����v |
16,800,000 |
|
|
�E�@���ō��v |
7,224,000 |
|
|
�F�@���ϋ��` |
19,504,800 |
|
|
�G�@�ސE���ې� |
1,248,000 |
|
|
�H�@���v |
8,680,700 |
�@�@��@�E + �F - �D - �G |
|
�I�@�����Ԗߗ� |
151.67�� |
�@�@��@�i �E + �F - �G �j �� �D |
(��)�ʎ���ɂ��v�Z�l�ɍ��ق������邱�Ƃ�����܂��B
9.�@�������\����
|
�S�������Z�@���̖{�x�X�A���H��A����A�s�����̏��H��A���H��c���A������ƒc�̒�����A������Ƃ̑g���A�F�\����Ȃ� |
|
�� ���̃y�[�W�̃g�b�v��
���Z�̃g�b�v�y�[�W��
�g�b�v�y�[�W��
�@ |
| ������ƑސE�����ϐ��x |
�����A��v�r�b�O�o���̈�Ƃ��đސE���t��v���N���[�Y�A�b�v����A��ƔN���̐ϗ��s�����������Ƃ��Ă悭���グ���Ă��܂��B����ɂƂ��Ȃ��A�ސE�����x�̌������̋@�^�����܂��Ă��܂��B���N�@�������ꂽ�m�苒�o�^�N���̓��{��401K�̓��������̂ЂƂł��傤�B

�����悻�A����ƈȊO�W�̂Ȃ����̂悤�ɂ��v���܂����A�]�ƈ����ٗp���Ď��Ƃ��s���Ă������A�ސE���̎x���Ƃ����ꎞ�ɑ��z�̕��S���������郊�X�N�́A������ƂƂ����ǂ��A�l���Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��ł��傤�B

�����ŁA������Ƃ�ΏۂƂ����ސE�����x�ŁA�ł����y���Ă���m�苒�o�^�N���ł��钆����ƑސE�����ϐ��x�����グ�A���̊T�v���q�ׂĂ݂܂��B |
�P�D�ړI
|
������Ƃɂ�����ސE�����x�̊g�[ |
�Q�D�����ł�����
�R�D�틤�ώ�
�S�D�|��
|
5,000�~�`30,000�~
�i5,000�~�`10,000�~��1,000�~���݁A10,000�~�`30,000�~��2,000�~���݁j |
�T�D�|���������x
|
1) |
�V�K��������
���ދ����x�ɏ��߂ĉ�������������Ǝ҂ɑ��āA�|�����z�̂P�^�R���_����Q�N�ԍ����������܂��B |
|
2) |
�|�����z����
�|���z�i�ߋ��̍ō��̊|�����z�����鑝�z�j���鎖�Ǝ�ɑ��āA���z���̂P�^�R�z����������P�N�ԍ����������܂��B |
�U�D�x���z
|
�E�@�|���̔[�t�����ɂ�茈�肳���
�E�@��{�ސE���{�t���ސE��
�E�@��{�ސE���͊m��^�A�A���A�^�p�����i������j�ɂ������i�����j����� |
�V�D�x�����@
|
�E�@�ꎞ�����͕��������i�T�N�R�[�X�A�P�O�N�R�[�X�j
�E�@�ސE�Җ{�l�i�⑰�܂ށj�Ɏx�� |
�W�D�s�x���[�u
|
�E�@������P�Q���������̏ꍇ�͕s�x��
�E�@�����ɂ�錸�z�x������(���Ǝ傩��̐\�o/�F��) |
�X�D�ʎZ���x
|
�E�@�����Ə��ł̒��ދ��Ɣ[�t���Ԃ̒ʎZ�\
�E�@�ߋ��Ζ����ԁi����P�O�N�ԕ��j�̒ʎZ�\
�E�@����ސE�����ρi���H��c���E���s��Ȃǁj�ւ̈ڊlj\ |
10�D���Ǝ�̃����b�g
|
�E�@�|���͐Ŗ��㑹�������ƂȂ�
�E�@�V�ސE���t��v�̓K�p���O
�E�@�ސE���ɂ������p���S�����ł���
�E�@�u�����̎x�����̊m�ۓ��Ɋւ���@���v�ɒ�߂�ꂽ�ۑS�[�u�ɂ��đ[�u�������̂ƔF�߂���
�E�@���̏�����Z�����x������ |
11�D�]�ƈ��̃����b�g
|
�E�@�]�E�̍ۂɉ�����Ƃł���Ί��Ԃ�ʎZ�ł���
�E�@��g�T�[�r�X������
�E�@���ڋ��ϋ@�\����̎x�����ƂȂ�ސE�����ۑS����� |
������ƑސE�����ϐ��x�̃z�[���y�[�W
|
�� ���̃y�[�W�̃g�b�v��
���Z�̃g�b�v�y�[�W��
�g�b�v�y�[�W�� |
|
|
| Copyright (c) 2006�@Business Forum Kobe21�@All Rights Reserved. |
|