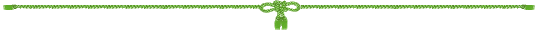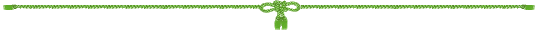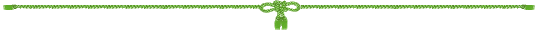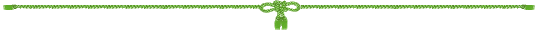十六夜心中2は、ニ話から構成されています。一話完結ですが、キャラが繋がっています。
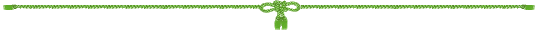

第三話 恋 慕
憧 憬
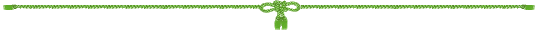
1
九月になったというのに気温は一向に秋らしくならない。
今日も朝からテレビの天気予報が
「本日の最高気温三十六℃」
などと、癇にさわることを伝えてくる。
冗談じゃない!
テレビに向かって無意識に「バカヤロウ」と叫んでしまった。
(夏は半月前に終わるはずでしょうが!?)
「地域によっては夕立もありますので、傘の用意を忘れずに」
恩着せがましく付け加えるアナウンサーにそうボヤくと、私はもったないと思いつつ
エアコンのスイッチに手をもっていった。
電気料を思うと頭が痛くなるが、それでもこの蒸し暑さを思えばまだ我慢ができる。
高い電気料と引き換えにしても今は快適な温度が欲しいのだ。
そんな私のささやかな欲望はスイッチを入れて数分後に叶った。頬にさわやかな風が
触れていき、部屋の中にある肌にへばりつくような空気を追い出していく。
そして、その頃になってやっと隣で寝ていた男がムクリッと体を起こしたのだった。
「おはよう。頭は痛くない?」
「!!」
眠気まなこを擦りながら起き上がった男は自分の目の前にいるのが私と分かると、急
に言葉を失ってしまった。
こうなるんじゃないかと半分予想はしていたものの、こうも見事に驚いてくれるとさ
すがに拍子抜けしてしまった。
見ているこっちとしては、まさに開いた口が塞がらない状態である。
(やっぱり何も覚えてないんだ。結構ベロンベロンだったからね……)
疲れを隠しきれないため息が私の口から漏れていく。
その間も男は納得のいかない顔で部屋を見回したり、着ている服をまさぐったりと、
記憶の糸を紡ぐのに必死になっている。
けれど、どうしてもある一定の場所で思考能力が停止してしまうらしい。
一生懸命頭を傾げ考えていたが、とうとう自分の限界に根負けすると最終手段をとっ
てきた。
捨て猫のようないたいけな瞳をして私を仰ぐと、
「なぁ、なんで俺、ここにいるんだ!?」
と首を斜め四十五度に傾げ、情けない声で尋ねてきたのだ。
(参ったなぁ……)
ブツブツと心の中で呟きながら、心の隅のほうではしっかり悪戯心が芽生えていた。
(いいよね!?)
自分に了解を得ると、私は布団の上につと膝をつき、まじまじと男の顔をみながら、
「無理やり私にあんなことしたのに覚えてないの?」
と、今にも泣き崩れそうな顔と声で訴えてみる。途端、男の顔はサーッと血が引いた
ように青くなっていった。
「俺、長瀬先輩に顔を合わせられないことしたのか?」
早口で聞き返してくる声は当然のようにうわずっている。
(全く。二十歳を過ぎた大の男が女との情事ひとつでうろたえるなんてどういうわけ?
情けないったらありゃしないわ!)
男の反応に私はホトホトうんざりした。けれど、男にとって私の台詞はよほどショッ
クなものだったらしい。項垂れたまま一向に顔を上げようとしない。
(ちょっと悪戯が過ぎたかな?)
目の前の男の姿を見ていると、すこしの罪悪感を感じてしまう。
「冗だ……」
謝ろうとした瞬間、男の台詞が私の台詞の上に重なった。
「なぁ、俺、どうしたらいいんだ?」
あまりにも真剣な男の台詞は私の罪悪感をどこかに吹き飛ばしてしまった。
プッと一度吹き出してしまうと、もう我慢なんかできない。気が付いたときには豪快
に笑いだしていた。
「冗談よ、香取。香取は何もしてないわよ」
必死に笑いをこらえながら、しょぼくれている香取の背中を私はパンパンッと勢いよ
く何回も叩いた。
「本当に?」
上目使いに恐る恐る聞き直す香取に、私はもう一度大きく頷く。
途端に、ぱぁーっと香取の顔に元気がよみがえった。
(げんきんな奴。でも、このすぐに立ち直るところが香取のいいところなんだよね。そ
して私が香取を好きでいる理由の一つでもあるし……)
ホッとしている香取を見ながら私はクスッとほほ笑んだ。
「良かった。長瀬先輩を裏切るようなことをしていなくて……」
ブツブツと独り言を言いながら香取は、胸を撫で下ろし安堵の息を吐く。
きっとこれが香取の正直な気持ちなんだろう。
『俺は先輩の彼女に変なことをしていなかった』
心の中で呟いているはずの律義な香取らしい台詞が聞こえてきそうだ。
でも、そんな香取の姿を私がどんな気持ちで見ているのか、はたして彼は知っている
のだろうか?
急に心の中が複雑になっていくのを私ははっきりと自覚した。
2
「何かしてくれても良かったのに、香取ったら布団に入った途端、バタンキューなんだ
もんネ」
香取に背を向け、布団が敷いてある横のタンスから着替えを取り出しながら私は冗談
めかしに一言言ってみる。でもその中には面と向かって言えない本音が隠れていた。
「優香!!」
反応はすぐにきた。かんぱつ入れずに香取の戒める声が耳に入ってくる。振り返って
みると、こわい顔をした香取がこっちを見据えている。
「冗談に決まってるでしょ? 昨夜、ここに泊まったのだって長瀬には内緒にしておい
てよ。あいつ、見かけによらずやきもちやきなんだからサ」
まだ納得しないでいる香取にクスッと笑いかえすと、私はタンスから必要なものだけ
を取り出して脇に抱え、真っすぐにバスルームに向かって歩きだした。
……と言ってもワンルームの小さな部屋だ。十歩も歩かないうちにバスルームにぶつ
かってしまう。
バスルームのノブを掴みながら、私はいささか遅くなってしまった朝食の件を思い出
し、香取に向かって提案する。
「香取、今日は遅番なんでしょ? 私も今日は遅番なんだ。だから、お風呂に入った後、
近所のモーニングのおいしい喫茶店に一緒に食べにいかない?」
軽い調子で誘った私に香取は、
「いいよ。俺、このまま会社に出るから」
とあっけない返事をよこした。
その台詞に私は目眩を覚えずにはいられなかった。
(この男はこんなぼさぼさ頭のまま、会社に行く気なのか?)
はっきりいって、ここまで香取が鈍感とは思いたくなかった。こんな姿で会社に行っ
たものなら、女共になんて言われることやら分かったもんじゃない。自分がOLをして
いる分、そんなことに関しては容易に想像がついてしまうのだ。
(誰がそんな女共の犠牲に香取をさせるもんですか!)
答えは簡単に出た。こっちの気も知らず、無造作に髪の毛をかきあげながら立ち上がっ
た香取に、
「良くない! 昨日、あんたお風呂も入ってないでしょう。すぐに上がるから入って行
きなさい!」
と、指を突き出しながら怒鳴る。
「いい!? 分かった?」
「う……うん。分かった。優香には頭が上がらないからな。それに昨日はここに泊めて
もらったし……」
私の迫力に負けた香取がしぶしぶ承知する。と言うより、本人自身が気が付いてない
のか、香取は人に強くものを言われると断れないのだ。
そのおかげで今回もその例に漏れず満足な返事を聞くことができた。
「よし。早く上がるからね」
ニコニコしながら香取に言うと私はバスルームの取っ手を引いて中に入って行った。
そして、顔だけ外にもう一度出すと意地悪な言葉を口に乗せた。
「香取。待きれなかったら入ってきていいからね」
「優香!」
眉間にしわを寄せて香取が怒鳴る。それを「冗談よ、冗談」と流しながら、私は顔を
引っ込めた。
けれど、本当のところは違っていた。
湯船にお湯を張り、ほどよい熱湯に肌を打たれながら、私が考えていたのは「本当に
ここに香取が入ってきてくれればいいのに」なんていう不届きなものだった。
3
期待には決してそってくれず、シャワーを浴びている間、香取はバスルームに入って
来る様子を見せなかった。
それをすこし残念に思いながら、とりあえず着替えをすませると、私はタオルで髪の
毛をふきながらバスルームから出てきた。
部屋の中を見てみると、ちょこんと香取が部屋の真ん中に落ち着けない様子で座って
いる。隅のほうには、いままで敷いていた布団がきちんとたたんであった。
髪の毛を拭いていたタオルを首に引っかけ直すと、私は冷蔵庫から牛乳を取り出し、
口をつけながら、
「お湯、はってあるから入っておいで!」
と、香取を促した。
「じゃ、お言葉に甘えて……」
ムクリッと立ち上がると、香取はバスルームに足を向ける。
「バスタオルも置いてあるからね」
すれ違いざまに言うと、
「ありがと」
と、小さな返事がかえってきた。
デカい体を申し訳無いほどに小さくして香取がバスルームに消えていく。
しばらくしてシャワーの音が私の耳に聞こえてきた。
テレビの声が多少聞きづらくなる。右手に持っていた牛乳パックをテーブルに置くと、
私は視線をテレビに釘付けたまま、リモコンを取ろうとローチェストに手を伸ばした。と、
その指先に何かが触れた。
香取の手帳だ。
黒い牛革のカバーがかかったその手帳は、本当に香取が何かの拍子にポイッと置いたよ
うに、ローチェストの上に何げなく置かれてあった。
とりあえずリモコンを取り上げ、ボリュームを上げてはみたものの、すっかり私の気持
ちは手帳の方に向いてしまった。
手帳の中身が気になって仕方がない。
少し躊躇した後、私は後ろめたさを感じながらも手帳を手に取り、パラパラとめくりだ
した。
ウィークリーには、びっちりとスケジュールが詰め込まれている。長瀬と違って結構ま
めに書き込んであるのにびっくりする。そして、最後の住所録のページで手が止まってし
まった。
テレビの音でかき消していたシャワーの音が突然大きく耳に響きだす。
何故か理由の分からない涙が込み上げてくる。
(こんなものを見たくて私は手帳をめくったんじゃない!)
声にならない叫び声が心の中で上がる。
そこには現実が存在してあった。
一番最初に書かれてある名前は私も知っている女の名前だった。
「木村綾子」
それは香取にとってこの世の中で一番大切な存在。どうしたって私がなれない香取の彼
女の名前だった。
4
「どうしたんだい? 暗い顔して。彼氏とケンカでもしたの?」
コーヒーのお代わりを持って来てくれたマスターが私の顔をのぞき込む。
「そんなふうに見えます?」
「ああ。でも、今日一緒だった彼氏は優香ちゃんの彼氏じゃなかったよね!?」
そう言いながら、マスターはちゃっかり椅子をひくと私の前に座った。コーヒーはちゃん
と二人分テーブルに用意している。
「営業中でしょ?」
諌めるような私の台詞にマスターは苦笑すると、
「お客が来たら営業を再開するよ」
と返事した。
「エッ!?」
見回してみると、かきいれどきを過ぎた店は閑散としていて客は私だけになっていた。
少し前まで一緒に朝食を取っていた香取は会社に遅れると慌てながら二人分の代金を置
いて店を出て行ってしまった。
分かっている。
本当のところは長瀬に義理立てしたのだ。遅番なのだから、後一時間ぐらいはゆっくり
して行けるはずなのに逃げるように出て行ってしまった。
「ねぇ、マスター。二股かけるなんて不届きだよね」
三十歳半ばぐらいのマスターは私の台詞に一瞬キョトンとした後、優しく笑いかけ、
「確かに道徳上じゃ、不届きなことかもしれないね。でも、気持ちなんて自分でもどうし
ようもない生き物なんだよ。頭でそう理解していても上手くいかないのが普通さ。二十歳
をすこし過ぎただけの優香ちゃんが簡単に気持ちをコントロールする方が僕は恐いね。二
股おおいに結構。長い人生、そんなことの一つや二つあったっていいじゃないか!」
「マスター」
マスターのなにげない台詞が心の奥底に暖かく染み込んでいくのが分かった。
目の前で自分の勝手さを否定せず、ただニコニコと笑って理解してくれるマスターの顔
がうれしかった。
そんな顔を見ていると、今までの出来事が走馬灯のように脳裏を駆け巡り出した。
5
コンパで知り合った長瀬に「好きだ」と告白したのは私のほうだった。長瀬はその返事
をヘヘッて照れ笑いを浮かべながら「いいよ」と告げてくれた。そして、私達は付き合い
だしたんだ。それからしばらくして、長瀬から「学校の後輩だ」と香取を紹介され三人で
遊びに行くようになった。
楽しかったけれど、いつもなにかと私達に遠慮する香取が嫌で、私が長瀬のように「学
生時代の親友」といって木村綾子を紹介したのだ。
遊びにいくのが三人から四人になって、長瀬ともうまくいって、楽しくて仕方がなかっ
た。負け惜しみじゃなくて、それが一番好きだった。そう、香取が「好きだ」と木村綾子
に告白するまで……。
その時になって私は初めて自分のもう一つの気持ちに気が付いた。
いつの間にか長瀬と同じくらい香取のことを好きになっていることを……。
でも、それは表にだしちゃいけない感情だ。
私は長瀬が好き。そして香取は綾子が好き。それで今は総てうまくいっているのだ。今
更この気持ちを香取に伝えて何がメリットになるんだろう?
この感情は隠していかなければいけない。
けれど、そう思えば思う分、香取を思う気持ちが日に日に大きくなっていく。
長瀬のことだってこんなに好きなのに……。今のこの気持ちは『無い物ねだり』なんだ
ろうか? それとも……。
6
「大丈夫だよ。時が解決してくれるさ」
自分の考えに浸っている私にマスターの声が聞こえてきた。
「優香ちゃんは、それまで自分をしっかり持っていればいいんだよ。何が大事で何を大切
にしなければいけないか、優香ちゃんには分かっているだろう!?」
マスターの台詞に私はコクリッと頷いた。けれど、依然と心の中は複雑なままだった。
長瀬も香取も大切。二人ともずっとそばにいて欲しい。私のものだけでいて欲しい。
不意にプツンッと自分の中で何かが切れる音がした。
(何でこんなこと気が付かなかったのだろう?)
思いついた事があまりにも現実離れしていて私はマスターを目の前にククッと笑いだし
てしまった。
「優香ちゃん?」
心配そうに私をのぞき込むマスターに手のひらを振りながら、私は「違う違う」と呟き、
すくっと立ち上がった。
「ごめんなさい。自分の考えが突飛すぎて思わず吹き出しちゃって。本当にごめんなさい。
でも、マスターの話を聞けてよかったわ。ありがとう。それにごちそうさま。今日もここ
のモーニングはおいしかったわ」
「ありがとうございます」
まだ納得のいってない顔のまま、それでもマスターは客に対する一礼をすると私をドア
の所まで送ってくれた。
「またのご来店をお待ちしております」
社交辞令のマスターの台詞で店を出された私は思いついた考えを言葉にした。
「そうなのよ。長瀬はこのままでも私のもの。だから香取を私のものにすればいいのよ。
私のものだけにね。……簡単じゃない。私のために死んでもらえばいいのよ。一人が嫌と
言うなら私も付き合ってあげるわ。まさに心中ね。これが現実になるのなら……」
この危険な思想がまず現実化する事はないだろう。だから、せめて口に乗せようと思う。
そうしないと、自分が壊れてしまうから。
中天に向かう太陽を眩しげに仰ぎながら私はもう一度、現実にしてはいけないことを思
い浮かべクスリッと笑ったのだった。
〈了〉
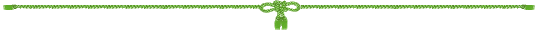
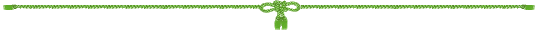
メールで感想なんかを頂ければ、うっれしいな♪