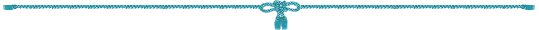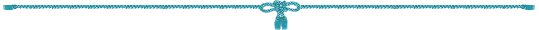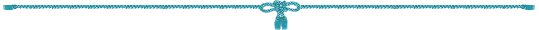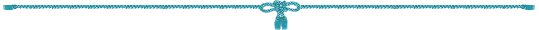十六夜心中1は、ニ話から構成されています。一話完結ですが、キャラが繋がっています。
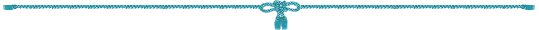

恋 慕 第四話 憧 憬
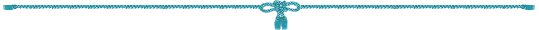
1
カランッカランッ。
ドアの上部に取り付けているベルが勢いよく鳴る。
男は読んでいた新聞から目を離すと、無意識にドアのほうに向かって声を出した。
「いらっしゃいませ……と、なんだ、恭子ちゃんか」
男はドアの前に立っている女の子の姿を確認して残念とばかりにため息をこぼし
た。客だと信じて疑わずに振り返った先に立っていたのは、なんのことはない半年
前からバイトにきている女の子だったのだ。
男は「やれやれ」と呟きながら視線を再び読みかけの新聞に戻すと、何もなかっ
たように近くにあった煙草に手を伸ばした。
それを女の子は肩をすくめ一瞥すると、カウンターの中に入りながら、
「恭子ちゃんですみませんでした。でも、私も時間給でバイトをさせていただいて
ますので約束の時間には来ないとネ」
と厭味を言い放つ。そして、
「今日も閑古鳥ですね」
と、ちゃんと店の状況を付け加えることを忘れないでいた。
「すみませんね」
恭子の辛辣な指摘に今度は男が肩をすくめる番だった。
恭子の台詞通り、店の中は夕暮れというのにガランとしている。
今日ももうすぐ夕立がきそうな天気なのに誰ひとり雨宿りがわりに店に入ってき
そうな気配がない。
「やっぱり、風水が悪いんですかね」
ケラケラと笑い声をたてながら恭子はカウンターのまだその奥の──壁の向こう
側にある厨房に入って行く。
その後ろ姿に男は何か言い返したいのだが、さすがに自分もそう思い始めている
のだから言い返す言葉が見つからない。
ただ、フゥーッと煙草の紫煙を天井に向けて吐くのが精一杯の反撃だった。
そんな惨めな思いを男が抱いているとは知らない恭子は、猫の額ぐらいしかない
小さな厨房に入って行くと、壁にかけてある赤のエプロンを取って身につけながら
壁の向こう側にいるマスターに尋ねる。
「マスター。ここにある洗い物は全部洗っておいていいんですね?」
目の前の流し台には数脚のコーヒーカップとソーサーが洗剤のプールに浸かって
いる。
「ああ、お願いするよ」
のんびりとしたマスターの声が煥発いれずに恭子の元に返ってくる。けれど、そ
れは以外と近くで聞こえたのだった。
振り返って見ると厨房の入り口に男が立っている。
その姿を見て恭子はクスリッと男にほほ笑み返した。
「今日は忘れたのかなって、心配したんですよ」
人並より少し大きなクリクリとした目に期待と少しばかりの不安を同居させ、恭
子がはにかむように声を出した
そんな仕草に男は年甲斐もなくドギマギする。
(逆らえないな)
心の中で男はそっと呟くと、答えるように恭子の顎をつと持ち上げ、自分の唇を
恭子の唇に重ねた。
唇同士が触れるだけの軽いキス。
そこにお互いの感情が入っているのかいないのか、容易に推し量ることはできな
い。
そんな挨拶代わりのキスが始まったのは半月前のことだった。
きっかけが何だったのか男は、もう覚えていない。ただ初めてのキスは、恭子の
ほうからせがんだものだった。
それから毎日、恭子が店に来ると、男は恭子にキスをするようになった。それは
男が求めたものでも、恭子が願ったものでもなかった。ただ、それが当たり前のよ
うにキスは繰り返えされた。
長くもなく短くもないキスが終わると、恭子はうれしそうな笑みを浮かべ、後ろ
を向くと洗い物を始めた。男のほうもそれをしばらく見ていたが、ドアが開く音を
聞きつけ、表のカウンターのほうに戻って行ったのだった。
2
あれはキスを始めて一週間ぐらいしてからだったか……。
(確かあの日もこんなふうに雨が降っていたな)
予報通り降りだした雨を眺めながら男は、恭子に何で自分のような中年男にキス
を許すのか尋ねた日のことを思い出していた。
湿気を含んで膨らんでいるポニーテイルを揺らしながら、せっせとテーブルを拭
く恭子に男は声をかけたのだった。
「こんな中年オヤジとキスするのは嫌なんじゃないのか?」
と。
その問いに恭子は手を止めて、改めて男の顔をマジマジと見つめながら、
「別に減るものじゃないし……」
と、簡単に返事をよこすと、また何もなかったようにせっせとテーブルを拭き始
めたのだった。
そんな恭子をみて、男はまさに今時の女の子らしい返事だと呆れながらも頷いた
のだった。
きっとこんな返事をする女の子がいるからベットに誘ってもお金を出してくれる
のなら、ちゃんと処理をしてくれるのなら、減るものじゃないからと言って男の欲
望に身を任す女の子が増えたのだろう。
そう思いながらも男は恭子だけはそんな女の子じゃないと何処かで信じていた。
否、信じたかった。
「マスター。私とキスするのが嫌なんですか?」
不意に起こった問いに何か不安を感じたのか、拭き終えてカウンターに戻ってき
た恭子は男に問い返したのだった。
「別に……。若い女の子とキス出来るなんてこんな中年には滅多にないことだから
ね」
肩をすくめながら男は当たり障りのない答えを恭子にした。
事実、嘘は言っていない。三十代も半ばを迎えたバツイチ男にキスをしてくれる
若い女なんてそんなにいない。
「街頭で配っているティッシュの場所に電話すれば私より若い子がキスしてくれる
かも知れませんよ!?」
冗談なのか本気なのかよく分からない台詞が恭子から返ってきた。
「恭子ちゃん!!」
からかわれた!
眉間にしわを寄せ怒鳴った男に恭子はクスリッとほほ笑み返すと、
「私が欲しい答えを言ってくれないマスターが悪いんです」
と言った。
それ以上、会話は続かなかった。
だから、恭子がなんて言って欲しかったのか、自分がどう言えばよかったのか、
男はとうとう分からずじまいになってしまった。
3
「ねぇ、マスター」
洗い物を終えた恭子がエプロンで手を拭きながらカウンターへと戻って来た。
「なんだい?」
セーラー服の上に掛けたエプロン姿が今日は妙に眩しく男には感じられた。
目を細めながら見返した男に恭子は
「マスターは再婚のことを考えたことあります?」
と聞いてきたのだ。
恭子の質問にびっくりしたマスターはすこし考えた後、
「一応はね」
と答えた。
「誰と?」
容赦のない恭子の質問が続いた。
「誰とって……」
執拗な質問に男は口ごもってしまった。
実際、男に特定の女性などいなかった。先妻と別れて三年。その間に彼女らしき
女性がいなかったとは言わない。けれど、結婚を考える程の女性は現れなかった。
言葉を失ったままの男に恭子がまた質問をする。
「マスターはなんで私とキスをしてくれるの?」
「エッ!?」
「マスターは私のことをどう思ってるの?」
真剣な目が男の目の前にあった。
「私じゃぁ……。私じゃ、マスターの結婚相手にならない?」
「恭子ちゃん!?」
思いもよらない恭子の台詞に男はどう答えていいのか迷った。
まさか恭子が自分をそんなふうに見ていたなんて想像すらしなかった。毎日のキ
スだって体のいい挨拶だと思っていたし、外国じゃ通常のことだと自分に言い聞か
せていた。
自分だって男だ。女を抱きたいという欲望だって持っている。まして、自分のタ
イプの若い女にキスをされて嫌なことなどない。うまく行けば、押し倒して自分の
思い通りにすることだって出来るかもしれない。けれど、そう思う度、どこかで自
制心が働いていた。
相手はまだ成人式も迎えていない女の子。きっと、ほんの好奇心で自分とも付き
合っているのだろう。そんな女の子を傷つけてはいけない。そう思っていた。
なのに、いま恭子が言葉にしているのは間違いなく自分への愛の告白なのだ。
「恭子ちゃん。よく考えてものは言うもんだよ。僕とは年齢だって一回り以上離れ
ているんだ。憧れと恋愛を履き違えているんじゃないのか?」
「履き違えてなんかいませんっ!! 私は真剣にマスターのことが好きなんです。年
齢が離れているからって恋愛が成立しないなんて、そんな古くさいことをマスター
は言うんですか? それじゃ、年齢の近い夫婦は離婚なんてしませんよ。私の言っ
ていること間違ってます?」
「いいや」
男は首を横に振る。
「それじゃ!」
目を輝かして恭子が身を乗り出してくる。それを男は手を挙げて押し止どめた。
「でも、これとそれとは問題が違う」
きっぱりと言い切る。それは自分に言い聞かす台詞でもあった。でも、恭子には
もう通じるものではなかった。かえってむきになると、挑むように言い返してきた
のだ。
「何が違うんです!? 何も違いませんよ!! 私はマスターのことが好き。決して憧
れとかでものを言ってやしません。マスターだから……、マスターだからキスだっ
て許してるんです。遊びや好奇心からじゃない!」
聞いているだけで真剣だと分かる恭子の声が男には痛かった。ここまで自分のこ
とを言ってくれているのに自分は世間体に縛られて素直な気持ちを表すことが出来
ない。
ずっと無言でいる男の姿をどうとったのか、恭子は突然長いため息を吐くと、
「……もういいです。マスターが私のことを何とも思っていないのは分かりました。
けれど、今のままでいさせて下さい。たとえ遊びと分かってていても私はマスター
の側にいたいから。私はいつまでもマスターのことを好きだから……。それだけは
覚えておいてください」
まるで別れ文句のような台詞が恭子の唇からでてくる。
今、男の目の前に立っているのはいつも明るい笑顔の絶やさない少女ではなかっ
た。恋に破れたと勘違いしている女の姿だった。
でも、世間体を大事にするつもりだったら男は、そのまま恭子を放っておくべき
だった。なのに、男にはその恭子の姿に耐えることができなかった。
自分も愛している女が勘違いをして苦しんでいるのだ。
「俺は、バツイチなんだぞ。年だってお前と一回りも違う! それでもお前は俺と
一緒になるなんて言えるのか!? 友達に『この男が自分の夫となる人間です』と自
慢出来るのか!?」
口にだしたものはもう二度と引っ込めることが出来ない。全部いい終えた時点で
男はそれに気づいた。そして、うれしそうに頬をほころばしている恭子の顔にも気
づいた。
「結婚は自分のため。友達に自慢するためのダンナなんていりません。年齢だって、
一緒に死ねば同じです。同じ場所で同じ時間をともに出来るのならそれだけで十分」
幸せそうに恭子が呟く。
「本当にいいんだな?」
男は念を押す。
もう自分の気持ちを表にだしてしまったのだから仕方がない。恭子に、そして自
分に問いただす。けれど、結果は同じだった。
「世間に反対されたら心中でもしましょうか?」
冗談ぽく恭子が話す。
「……そうだな。恭子とならそれもいいかもな」
男のほうも口の中で小さく答える。
「エッ!?何か言いました?」
小首を傾げて恭子が聞き返してくる。それに首を横に軽く振ると男は恭子の耳に
囁いたのだった。
「今日は早めに上がろう。高校生じゃぁ、外泊も出来ないし、まだご両親にも挨拶
に上がってないしね」
「マスター!!」
顔を赤くして恭子が声を上げる。けれど、顔はうれしそうに笑っている。
(結婚式にもそんな笑みを浮かべてほしいんだけどな)
その笑顔を見ながら男はそっと心の中で呟いたのだった。
〈了〉
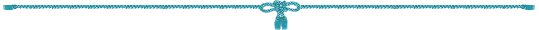
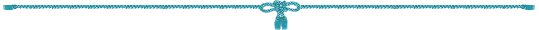
メールで感想なんかを頂ければ、うっれしいな♪