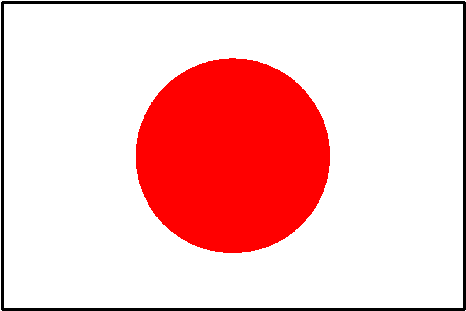 |
中国黒竜江省酪農乳業発展計画 |  |
|---|---|---|
| top › 中国黒竜江省酪農乳業発展計画 › 飼料生産管理 › 活動と成果(サイレージ調製技術) | ||
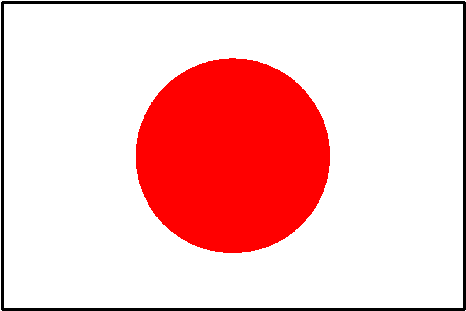 |
中国黒竜江省酪農乳業発展計画 |  |
|---|---|---|
| top › 中国黒竜江省酪農乳業発展計画 › 飼料生産管理 › 活動と成果(サイレージ調製技術) | ||
当地ではサイレージの原料はほとんど全てがトウモロコシである。トウモロコシの栽培については、食用(穀実生産)トウモロコシとほとんど同じであり、栽培に関するノウハウは既にあると判断され、概ね当地の在来技術を踏襲して差し支えないものと思われる。しかし、施肥や土壌改良等一部に問題があり、改善の余地がある。
2元交配ではあるが(日本や米国では4元交配が一般的)、サイレージ用トウモロコシ品種があり、これを用いている。
当地は土壌の性質が悪く、これの改善のためには堆肥の大量施用が有効と考えられるが、実際には堆肥の施用は少ない。今後は堆肥施用を増加させることが望ましい(その旨指導した)。
プロジェクトの予算でコーンプランター、畦立機、カルチベーター、スプレーヤー等の管理用農機具を導入したが、導入時期の問題もあり現時点では十分な利用がなされていない。従前通りの人力に依存した管理(中耕、除草)を行ったが、今後は農機具利用による管理に切り替えていきたい。
際だって問題となるような病虫害は無い。
友誼牧場及び近隣農家におけるサイレージ調製時点でのトウモロコシの水分含量を測定したが、いずれも60%を超える値であり、サイレージ調製には高すぎる水分であった。現状よりも収穫時期を遅らせ、50%台の水分とすることが望ましい。
友誼牧場で栽培しているトウモロコシは既存の(プロジェクト実施前より有している)コーンハーベスターにより収穫している。農家より購入する分は、農家が手刈りしたものをサイロ脇まで運搬し、これをサイロ脇に置いたフォーレージハーベスターにより細断、吹き込みしている。
農家においては、手刈りしたものをサイロ脇まで運搬し、ここでカッターにより細断してサイロ内に吹き込んでいる。小規模経営ではこの方法が適切であろうと思われる。
友誼牧場において従前より使用しているサイロは、割石を積み、石の間にセメントを塗り込んだものである。これは壁面に代償の凹凸があり、また石の間のセメントがひび割れが入っており、ここから調製中のサイレージ内部に空気が入り込みやすい。
またサイロ詰め方法が奥の方から詰め込み、全部を詰め終えてから踏圧する方法をとったため、最初に詰め込んだ分は数日間空気にさらされ、好気性発酵(腐敗)が進み、かなり発熱していた。また全部詰め込んでからの踏圧は圧力が底の方まで十分に伝わらず、踏圧効果は少ない。底面から順次踏み固めながら詰め込み、厚さ1m分程度細断したトウモロコシを詰め込んだら均して踏圧し、再度詰め込むという方法を繰り返すのが望ましい。また当日分の詰め込みが終わったら表面にシートをかけ、空気が内部に流入するのを抑制することが好気性発酵を抑えるのに有効である。
また、側面に凹凸やひび割れがある場合でも、ここにシートをかけてサイレージ原料を詰め込めば、側面からの空気の流入を抑制することができる。
これらのことについて2003年及び2004年の2度にわたり指摘し、指導したが友誼牧場としては従来通りの方法でサイレージ調製を行った。
2004年にJICA予算で幅6m、高さ3m、長さ30mのトレンチサイロを建設した。完成し、使用可能になったのが、トウモロコシサイレージを調製する適期を過ぎていたため、当年の利用はできなかったが、2005年より使用する予定である。
近隣の農家のサイロ及びこれを使用したサイレージ調製の状況を調査した。
当地の農家が有するサイロは間口が2〜3m×3〜4m程度、深さが3〜4m程度のものを2つ連ねた形のものが多く、構造は当地の一般的な家屋建物と同様に煉瓦を積み、その外側にモルタルを塗って仕上げたものである。
友誼牧場において2003年及び2004年に調製されたトウモロコシサイレージの品質については、優、良、可、不可の4段階で評価するとすれば、現時点では「可」という評価になると判断される。
この理由としては先ず、牛による採食については大きな問題はない(詳細は次項で述べる)といえる。しかし、2003年に調製したサイレージではシートより30cm程度下の部分及びサイロ両脇に近い部分において変質(黒変)が見られた。またこの部分は開封時に既に発熱していたことが観察された。
また、サイレージ利用中には断面全体において二次発酵による発熱が見られた。特に2003年に調製したサイレージでは、同じ切断面が長期間空気にさらされる状況にあったため、この面の部分のサイレージは外気温が零下十数度ないし二十数度という寒冷下にあるにもかかわらず、長期間二次発酵により発熱しつづけた。
このような貯蔵中におけるサイレージの変質や二次発酵の原因として次の二つが考えられる。
いずれも容易に改善されうるものであり、これらについて指導した。
このように日本の標準的なサイレージからすれば問題だらけであるが、特に悪い部分を除いたものを牛に給与したが、特段採食が悪いということはなかった。これはここに使用されている牛群が品質の良いサイレージを食したことが無く、「サイレージとはこんなもの」として食べているのではないかと思われる。
| 「飼料生産管理」のメニュー画面 | |||
| プロジェクトのトップへ |