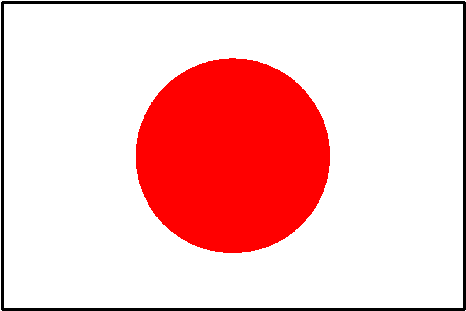 |
中国黒竜江省酪農乳業発展計画 |  |
|---|
| top › 中国黒竜江省酪農乳業発展計画 › 関係資料等 › プロジェクト紹介記事 |
| 以下はプロジェクトのチーフアドバイザーがプロジェクト紹介のために書いた文章である。 |
新潟空港から中国南方航空に乗ると、約2時間で中華人民共和国(以下、「中国」という。)黒龍江省ハルピン空港に到着する。ハルピン市に所在する我がプロジェクトは、おそらく世界中のプロジェクトの中で日本に一番近いプロジェクトではないだろうか。
黒龍江省は、中国の最東北部に位置し、面積は約46万平方キロメートルで日本の約1.2倍に相当する。人口は、3,811万人(2001年)で、省都ハルピン市は、人口が約330万人といわれる大都会である。ハルピン市は、北緯44度から47度にかけて位置し、日本の稚内市に相当する緯度に位置している。大陸性気候のせいもあるが、冬は最高気温が零下15℃程度、最低気温が零下30℃程度と厳しく、夏は最高気温が30℃以上まで上がる寒暖の差が激しいところである。ただし、湿度が低いことから、通常日本のような蒸し暑さはあまり感じないし、木陰に入るだけで涼しくなるとのことであった。しかし、今年は異常に暑いとのことである。
中国経済について語るには役不足であるが、南部沿岸地域を中心に目覚しい発展を遂げており、今後もこの傾向は続きそうである。これらの発展は、国内特に内陸部との経済格差をますます強めることとなっている。労働者は都市に集中し、農村部は過疎化、高齢化が進んでいる。中国政府は、都市と農村間の格差を縮めるため、税金を免除するなどの諸対策を講じている。
ここで黒龍江省における酪農の現状について、少々述べておきたい。黒龍江省の乳牛の飼養頭数は全国では4番目に多く、全国の13~14%を占めている。しかし、生乳生産量は国内全体の18%を占め、全国一の生産量を誇っている(表1)。このように黒龍江省は、中国でも有数の酪農王国である。この数値を見ると、黒龍江省の乳牛の改良が、中国国内ではいかに進んでいるかがご理解いただけると思う。このように、黒龍江省の乳牛の能力は中国国内のそれからするとかなり高いものの、日本の搾乳牛1頭当たり約8千㎏などのレベルと比較するとかなり立ち遅れたものといえる。黒龍江省政府は、これら酪農を農業の基幹作目とすべく、その普及推進を図っている。
| 飼養頭数 | 生乳生産量 | 1頭当り 搾乳量(㎏) |
|||
| (万頭) | % | (トン) | % | ||
| 全国 | 687.3 | 100.0 | 1299.8 | 100.0 | 1,891 |
| 河北省 | 94.4 | 13.7 | 148.9 | 11.5 | 1,577 |
| 内蒙古 | 98.4 | 13.7 | 165.2 | 12.7 | 1,679 |
| 黒龍江省 | 93.3 | 13.6 | 235.8 | 18.1 | 2,527 |
| 新疆 | 143.6 | 20.9 | 94.9 | 7.3 | 661 |
| 資料 | : | 中華人民共和国農業部「中国畜牧行年鑑2003」 |
| 注 | : | 「内蒙古」は内蒙古自治区、「新疆」は新疆ウイグル自治区 |
| 規模 (頭) | 飼養戸数 | 飼養頭数 | 生乳生産量 | 1頭当たり 搾乳量(㎏) |
|||
| (戸) | % | (頭) | % | (千トン) | % | ||
| 1~4 | 119,821 | 74.8 | 350.580 | 32.7 | 676.4 | 29.9 | 2,214 |
| 5~19 | 36,060 | 22.5 | 345,146 | 36.9 | 878.4 | 38.8 | 2,545 |
| 20~49 | 3,760 | 2.3 | 133,679 | 14.3 | 330.6 | 14.6 | 2,473 |
| 50~199 | 385 | 0.2 | 55,953 | 6.0 | 136.2 | 6.0 | 2,435 |
| 200~499 | 132 | 0.1 | 35,572 | 3.8 | 89.2 | 3.9 | 2,507 |
| 500~999 | 49 | 0.0 | 27,065 | 2.9 | 69.7 | 3.1 | 2,574 |
| 1000~ | 17 | 0.0 | 31,556 | 3.4 | 81.9 | 3.6 | 2,595 |
| 合計 | 160,224 | 100.0 | 934,551 | 100.0 | 2,262.4 | 100.0 | 2,421 |
黒龍江省の酪農を飼養頭数規模別でみると、1~4頭飼養規模が飼養戸数の74.8%、5~19頭飼養規模が同22.5%で合計97.3%となる。一方で、20~1,000頭飼養規模もわずかながら存在する。このように、零細農家が大多数である。これを飼養頭数別について見ると、1~4頭飼養規模が飼養頭数で32.7%、5~19頭飼養が同36.9%で合計79.6%となり、飼養頭数規模の大きいところがそれなりの部分を占めていることが分かる。また、生乳生産量でみると、このことはもっと顕著に現れる。すなわち、生乳生産量は、1~4頭飼養規模が29.9%、5~19頭飼養規模が38.8%で合計68.7%となり、小さな飼養規模のシェアが少なくなる。この一連の数字は、酪農家が飼養している乳牛の能力を示している。すなわち、零細規模の乳牛の1頭当たりの泌乳能力が、いかに悪いかがお分かりであろう。(以上、表2)
一方、中国における牛乳乳製品の消費は、これまで乳幼児、病人等への栄養食品として位置づけられてきたといい、一般人の消費習慣はなかったという。最近になって、健康食品として消費されるようになっているが、その伸びは飛躍的である。(表3)
| 年 | 1990 | 1996 | 2000 | 2001 |
| 生産量(万トン) | 475.1 | 735.8 | 879.5 | 1,122.9 |
| 一人当たり生産量(㎏) | 4.3 | 6.0 | 7.0 | 9.0 |
| 一人当たり消費量(㎏) | 4.2 | 5.6 | 6.5 | 8.8 |
牛乳乳製品の消費量を都市部と農村部で比較すると、それぞれ大きな伸びを見せているが、農村部の消費量が著しく差が見られる。(表4)
| 年 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| 都市部 | 5.56 | 5.92 | 7.25 | 9.19 | 11.55 | 13.76 |
| 農村部 | 0.80 | 0.95 | 0.93 | 0.96 | 1.06 | 1.20 |
いずれにしても、今後生活レベルの向上に伴い、畜産物の消費はますます増加傾向での進展が見込まれるので、酪農業に対する期待は計り知れないものがあろう。
中国政府は、国家開発第9次5ヵ年計画(1996年~2000年)において、食糧増産を中心とする農業の発展、増強を重視していた。黒龍江省政府は、「黒龍江省を農業大省から農業強省へ転換し、全国の農業生産基地とする」との目標を掲げた。
黒龍江省は、寒地で冬期間が長いため、年間を通じて収入を得ることができる農業は畜産業しかない。他方、広大な草地面積を有しており、農産物収穫後の茎葉や大豆粕、中国の焼酎に当たる白酒粕等の飼料資源も多いことから、酪農に適しており、牛乳と乳製品の生産は全国第1位となっている。黒龍江省政府としても、酪農乳業の発展を重視しており、畜産業の割合を農業全体の半分まで高めるという願いを込めた「半壁江山」のスローガンの下、酪農乳業の振興に努めているが、牧草の質が悪いこと、1頭当たりの泌乳能力が低いこと、飼料の開発が遅れていること等の問題を抱えていた。
このような状況であったため、中国政府は1996年8月30日、日本政府に対し、酪農と乳製品の製造技術に関する新技術の開発研究を行うプロジェクト方式技術協力を要請した。
要請を受けた国際協力事業団(現国際協力機構)は、1997年10月に事前調査団を派遣し、黒龍江省の酪農乳業の現状からプロジェクト実施の妥当性を認めた。しかし、中国側の要請内容が予想以上に大規模であったことから、通常のプロジェクト方式の仕組み、予算の制約の中では実施不可能であり、相当の絞込みが必要であると指摘した。
日本側は、1998年に短期調査を計画したが、黒龍江省で大規模な洪水が発生したことからこれを延期し、1999年7月に調査員を派遣することとした。しかしながら、同調査の対処方針案を中国側に示したところ、「日本側方針案が中国側の要望している協力内容より大幅に後退したものであり、調査員の受入は困難である」旨の連絡があった。日本側は、日本側の対処方針と中国側の要望との乖離は大きく、中国側の受け入れ態勢が整っていないと判断し、直前になって同調査員の派遣を延期した。
その後、双方の歩み寄りによって2000年8月に第1次短期調査員が派遣され、追加調査を実施するとともに、実施期間、プロジェクトサイト、協力分野について協議し、プロジェクト実施の可能性を確認した。さらに、2001年1月には第2次短期調査員が派遣され、協力基本計画案、プロジェクト・デザイン・マトリックス(PDM)案、暫定実施計画(TIS)案、実施体制案を作成し、合意した。
これらの調査結果を踏まえ、2001年4月に派遣された実施協議調査団が、プロジェクト実施に係る討議議事録(R/D)の署名を取り交わし、同年7月には長期専門家が派遣され、5年間の技術協力が開始された。
以上述べたように、プロジェクト開始まで数年を要するなど、紆余曲折があった。技術協力の内容は次のとおりで、チーフアドバイザーを含め6名の長期専門家が派遣されている。
| (1) | 対象地域の酪農家が良質な飼料を生産できる。 |
| (2) | 対象地域の酪農家が乳牛の適切な飼養管理を行えると共に、生乳の品質が向上する |
| (3) | 乳製品の品質向上・多様化が図られる。 |
| 1-1 | 友誼牧場において、以下の飼料生産技術を確立する。 ① 小規模な草地改良技術 ②未利用資源の飼料課技術 ③サイレージ調整技術 ④飼料分析技術 ⑤アルファルファ採種技術 |
| 1-2 | 友誼牧場で飼料生産技術の実証展示を通じて対象酪農家へ普及すべき技術を確立する。 |
| 2-1 | 友誼牧場において、以下の飼養管理技術を実証展示する。 ① 乳牛の飼養管理技術 ②搾乳衛生管理 ③受精卵移植技術 |
| 2-2 | 友誼牧場で乳牛の飼養管理技術の実証展示を通じて対象酪農家へ普及すべき技術を確立する。 |
| 3-1 | 乳製品製造技術を改善する。 ①原料乳品質管理技術 ②乳製品製造技術 ③乳酸菌収集、保存及び培養技術 |
| 3-2 | 確立された技術をセミナー等を通じて乳業関係者に普及する。 |
本プロジェクトは、メインサイト及び乳業サイトはハルピン市を、酪農サイトはハルピン市から北西に150kmほど離れた安達市の先源郷を、それぞれ拠点として活動している。酪農サイトのある安達市は、「牛の街」を標榜にしたまさに酪農の街で、本プロジェクト実施を契機に酪農振興をさらに進めようとしている。
このプロジェクトは、各長期専門家に対し通訳がつけられるなど恵まれている。これは技術移転の進捗に大きく貢献し、中国側のプロジェクトに対する意気込みを感じさせ、大いに評価している。しかしながら、①本プロジェクトのC/Pが人民政府の公務員及び国家乳業工程技術研究センターの職員が大半で兼職のため、本来業務との関連で技術移転がなかなか進まないこと、②ハルピン市と安達市との距離があるため、両サイトの連携がままならないことが悩みの種となっている。
黒龍江省における酪農は、当地の基幹作物であるトウモロコシ及び収穫後の茎葉を主な飼料源として利用している。トウモロコシ収穫後の幹は、畑のいたるところに山積みとなっており、冬季間の重要な乳牛の飼料や燃料となっているものの、かなりの部分は未利用のまま放置されている。これらの有効利用もこれからの課題となっている。
酪農地帯の土壌は、アルカリ性土壌で生産性は低い。裸地が目立ち、裸地部分は塩分の結晶で白くなっている。そのため畑として利用できない土地は、共同の放牧地として利用されている。しかし、過放牧等により放牧地の生産性が低下すると「中華人民共和国草原法」(2004年12月)に基づき禁牧等の措置がとられるが、回復までに数年かかるといい、酪農家に対する影響は計り知れないものがある。
プロジェクトサイトの友誼牧場では、自然草地の改良、アルファルファ等牧草の導入及びトウモロコシサイレージの生産、調製を中心とした技術移転を行っているが、極寒地であること、降雨量が少なくしかも降雨が夏季に集中していること及び土壌の物理化学性が不良(アルカリ、泥濘)であること等自然条件が厳しく、技術移転が順調に進まないのが難点である。
特に、既設のトレンチサイロは、極寒地であることから凍結予防のため半地下式になっているが、石組みであることから亀裂が入り機密性がなく、地下式であることから排汁や雨水が溜まってサイレージの品質の低下が見られること、量的に3か月分程度しか貯蔵できないこと等問題があった。良質サイレージの調製を実証展示するため、本年度は新たにバンカーサイロを建設することとした。
アルファルファの栽培については、短期専門家による技術指導のほか、アルファルファ育種を行っている黒龍江省畜牧研究所の技術的な応援を仰いでいる。
また、これまで肥料としてあまり利用されてこなかった牛糞についても、適切に処理されているとはいえない。本プロジェクトでは、2003年に堆肥舎を建設し、堆肥の有効利用を実証展示しており、このことが草地改良や飼料作物の生産量アップにも貢献するものとみられる。
友誼牧場における家畜飼養管理は、機材到着の遅れ等から除角、削蹄、体尺等基礎的部分から始められた。友誼牧場は飼養頭数150等程度の大きな牧場であるが、施設面、技術面の両面からのてこ入れが必要であった。
搾乳は、バケットミルカーによる1日3回行われており、これまでバルククーラーで8℃程度で保管していたが、細菌数が70万個/mlと、品質に不安があった。最終的には細菌数は、50万個/ml以下となるよう目指している。
乳牛の資質もBCS (Body Condition Score)は3以下と飼料不足は否めないが、乳量は平均5,300㎏/年程度と高い水準である。しかし、体格はまちまちで乳頭の形態が不揃いで、機械搾乳に適していない。これらの改善は、今後の家畜改良に待たなければならない。 また、初生子牛管理は、初乳の給与時期が適切でなかったので、分娩直後に給与するように改善し、初生子牛の生存率の向上に努めた。また、子牛の離乳時期を短縮し、補助飼料を給与することで、発育を促進させることができた。
搾乳牛の飼養管理は、理想的なトウモロコシサイレージの通年給与を目指しているが、これまでは前述のトレンチサイロで3ヶ月分程度までしか確保できなかったので、新たなバンカーサイロの建設によって改善されることが期待されている。また、2004年にTMR(Total Mixed Ration)飼料攪拌機が供与されたので、飼料給与面での問題は解決の方向にある。
このほか、日中の投資によって乳牛舎、搾乳舎が完成し、本格的な近代的飼養管理が可能となり、バルククーラーによる良質な乳質管理も可能となる。
本年からは、規模の大きい友誼牧場をモデルとしながら、零細なモデル農家を決め集中的に指導し、周辺農家への波及を目論でいる。モデル農家への指導は担当C/Pを決め、その効果を上げるべくお互いに競わせることとしている。
乳製品にとって原料乳の品質管理技術は、その出来具合を左右するので、おろそかにできない。しかし、現実には需給の関係や担当者の認識不足等からそれが厳密に行われているとは言い難いのが現状である。
黒龍江省で一般的な集乳方法は、各乳業会社が酪農家集団の中に搾乳施設を設置し、酪農家はそこに乳牛を移動して酪農家自ら搾乳するのが基本である。搾乳衛生の指導は基本的には乳業会社が行うが、的確に行われているかは疑問である。集乳所によっては、冷却装置が不備なところもあり、その上タンク車には冷却装置がないのが普通だから、季節にもよるが輸送車の故障や事故は牛乳の鮮度に致命的な打撃を与える。冷却装置がない集乳所は、搾りたての牛乳の鮮度を落とさないため、その都度工場へ輸送している。このように、全体的にみると原料乳の品質管理にはまだまだ問題がある。
本プロジェクトでは、国家乳業工程技術研究センターへ乳成分測定機を供与することによって、確実に成分測定が行われるようになっているが、原料乳の温度管理という基礎的な技術への理解がまだ乏しく、確実に行われていないのが現状である。
チーズの製造については、中国はまだ未開発国である。本プロジェクトでは、ナチュラルチーズを3品目、プロセスチーズを5品目製造することを目標としている。
これまでナチュラルチーズの製造目標となっている3品目のうち、先ずゴーダチーズ及びチェダーチーズの製造について技術移転が進められ、基本的な技術はほぼ修得された。残りの1品目の製造については、消費者に受け入れられやすいエダムチーズが候補として上がっており、その準備が進められている。ナチュラルチーズ製造技術は、ある程度の技術練磨が必要であり、C/Pによる技術練磨が続けられている。
これら製造したチーズを素に、ハード系及びソフト系プロセスチーズの製造も試みられている。中国人の嗜好にあったチーズの味を求めて、試行錯誤が繰り返されており、目的に叶ったプロセスチーズが製造されるものと期待している。
発酵乳についても新たに1品目以上を製造することを目標としている。この技術は、発酵乳製造技術が既に中国ではある程度定着している状況の中で行われることになるが、プロバイオティクスヨーグルト等最新技術については、緒に就いたばかりである。発酵乳の製造の技術移転は、これまでは基礎技術について行われてきたが、4年目のこれから本格的に稼動することになっている。
また、乳酸菌収集、保存及び培養技術については、フィールドの乳酸菌及びビフィズス菌の分離、収集を行っているが、技術練磨が必要であり、C/Pによる技術練磨が続けらている。
プロジェクトが始まってから、本プロジェクトサイトの目の前に安達市先源郷人民政府が57戸の建売牧場を建設している。飼養規模は合わせて3,000頭規模となるという。必要な乳牛を揃えられるだろうか、飼料は確保できるのだろうか、入植者のレベルは十分なのだろうか等の我々の心配をよそに、建設は着々と進んでいる。
中国側はプロジェクトの専門家の技術力に期待し、専門家側は技術の普及に期待している。この建売牧場群を含む黒龍江省の酪農家が、プロジェクトによって確立された技術をもって今後とも発展し、ひいては酪農家の所得が向上することを望んでいる。
| このページの冒頭へ | |||
| 「関係資料等」のメニュー画面 | |||
| プロジェクトのトップへ |