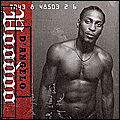2000.2.2

|
 |
The Hurting Business
Chuck Prophet
(Hightone) |
|
ソロ5作目。2年近いブランクを経ての登場だ。
前作よりも静かな、しかしソウルフルな仕上がり。ループとか、ターンテーブルとか、そういった手法も無理なく取り込んで、新鮮さとルーツっぽさとを併せ持つかっこいいシンガー・ソングライター・サウンドを作り上げている。ちょっとやりすぎている曲もないではないけど、両者のバランスが絶妙にハマった曲はなかなかの仕上がりだ。フルーム&ブレイクとか、トム・ウェイツとか、そういう連中からの影響が強いのかな。
でも、この人の場合、やはりアプローチがどこかポップなので、音像の手触りがダークにならなくて。そこがいいとこだね。
|

 |
Cowboy Sally's
Twilight Laments
...For Lost Buckaroos
Sally Timms
(Bloodshot) |
|
一時、といっても10年以上前だけれど、イギリスのオルタナ・カントリー・バンド、ミーコンズに在籍していたこともあるサリー・ティムズの新作ソロ。何枚目くらいだろう。ミニ・アルバムとかも入れると5〜6枚にはなるよね。
今回のハイライトは、もうなんたってオープニング・チューン。ガイ・ローレンス作の「ドリーミング・カウボーイ」だ。ビング・クロスビーというか、ダン・ヒックス/マリアン・プライスというか…でおなじみの「アイム・アン・オールド・カウハンド」調のグッド・タイム・ソング。こういうムードって、イギリス人だからこそ出せるエキゾチシズムなのかも。
その他、ロビー・ファルクス作の「イン・ブリストル・タウン・ワン・ブライト・デイ」や、ジョニー・キャッシュ作の「クライ・クライ・クライ」、ジル・ソビュール作の「ロック・ミー・トゥ・スリープ」なども披露。テファノ・チューン「カンシオン・パラ・ミ・パドレ」やドリーミーな「ザ・サッド・ミルクマン」「スウィートハート・ワルツ」など、自作曲も悪くない。
|

 |
Lost And Gone
Forever
Guster
(Sire) |
|
通算3作目かな。今回はスティーヴ・リリーホワイトをプロデューサーに迎えて、ロサンゼルスとウッドストックでレコーディングされている。国内盤も出たけれど、何やら日本の音楽雑誌では煮え切らない評価しか得られてないみたい。確かに煮え切ってないといえば、うん、そういう音ではあるけれど、聞き込むうちに情がわく(笑)。なかなかよいです。
すべてを素手でこなすというドラム&パーカッションに、ヴォーカル&ギターが2人。この3人を核に、さりげないバッキング(トニー・レヴィンとかも参加)を付した音像も、豊かなメロディ感覚も好感度高し。ビーチ・ボーイズっぽい瞬間もちょっとあったりして。
|

 |
Life'll Kill Ya
Warren Zevon
(Artemis) |
|
ここ3年ほどレコード会社との契約がなかったらしいジヴォンさんながら。これ、久々にいい出来なんじゃないかな。70年代のアサイラム在籍時以来というか。
今回もホルヘ・カルデロンとがっちりタッグを組んでのレコーディング。1曲、なんとスティーヴ・ウィンウッドの「バック・イン・ザ・ハイ・ライフ」の渋いカヴァーが入っているけれど、その他はすべてジヴォン単独あるいはジヴォン&カルデロンの作品だ。
相変わらず皮肉なというか、世をすねたというか、残酷なというか、そういう歌詞の世界が展開されている。“家が燃え落ちたとき俺は家の中にいた”と歌われるオープニング曲をはじめ、そのものずばりのアルバム・タイトル曲、“俺はお前の囚人になる、人質になる”と歌われる曲、「My Shit's Fucked Up」なんて身も蓋もないタイトルの曲などなど。えんえんとハードな曲をたたみかけておいて、しかしラストの曲では、“うんざりさせないでくれ。年老いた気分にしないでくれ。自分が愚かだと思わせないでくれ。いいかい? 勇敢な気分にしてくれ。うまく演奏できるようにしてくれ。今夜、一緒にいさせてくれ……”みたいなことを静かに、祈るように歌うわけですよ。泣きますよ、こりゃ。
|

 |
Evergreen
Boy
Steve Forbert
(Koch) |
|
これまたベテラン・シンガー・ソングライターの移籍第一弾だ。9枚目のスタジオ・アルバムかな。
今回はメンフィス・レコーディング。ジム・ディッキンソンのプロデュースのもと、クレイ・バーンズ、グレッグ・モロウ、デイヴ・スミスといったメンフィス人脈がバックアップしている。マッド・ラッズのウィリアム&バートラム・ブラウンがコーラスしていたり、ホーン・セクションが入っていたり、1曲だけベン・キースがプロデュースしていたり、その曲にスプーナー・オールダムがオルガンで参加していたり。ルーツ・ミュージック・ファンにはたまらないツクリです。
若いころは、なんだか“薄い”なぁと思った歌声も、さすが年輪とともに渋く熟成してきた。楽曲も粒ぞろい。「ストレンジ」と「ブレイキング・スルー」って曲が特にしみました。
|

 |
April
A Live Album
Elliott Murphy
with Olivier Durand
(Last Call) |
|
パリ在住なんだっけ? 間もなく新作スタジオ・アルバムをリリースするらしいエリオット・マーフィーだけど、その前にこいつが出ました。アルバム・タイトル通り、99年4月にドイツで収録されたライヴ・アルバム。アコースティック・ギター2本だけをバックに、相変わらずシャープな歌声を聞かせている。
「ロック・バラード」をはじめ自作曲がもちろんいいのだけれど、「ワイルド・ホーシズ」のカヴァーもよいです。
|

 |
Havana Midnight
Bob Neuwirth
arranged by Jose Maria Vitier
(Diesel Motor) |
|
国内盤も出ましたね。「ベンツがほしい」の作者として、あるいは映画『ドント・ルック・バック』に出てくるボブ・ディランのロード・マネージャーさんとしてもご存じ、ボブ・ニューワースの新作は、なぜかキューバで地元のミュージシャンを従えてのレコーディング。国内盤のライナー読めばなぜこんなシチュエーションで録音したのかわかるかもしれないけど、読んでないので事情は全然わかりません(笑)。
とにかくホセ・マリア・ビティエールのアレンジのもと、例の渋い歌声をじっくり聞かせてくれる仕上がり。アルバム・タイトル・チューンを別アレンジで聞かせた「ハヴァナ・フェアウェル」ってのが絶妙の出来です。
|

 |
Are You Through
Yet? ...Live
The V-Roys
(E Squared) |
|
ニューヨークのライヴハウスで見ましたよ、この人たち。
当日は1番手がトッド・ティボーで、2番手がこいつら、3番手がダムネーションズTXというラインアップで。トッド・ティボーのときは客なんかぼくを含めて5人くらいしかいなかったのに、この人たちが出てくるころには店も満杯。立ち見でぎっちり。テキサス出身だからってナメんじゃねーよ…とでも言いたげな、ツッパリまくったダンディズムが印象に残った。
というわけで、その夜のことを思い出させてくれるライヴ盤の登場。ニール・ヤングの曲やら、La's の曲やら、ラウドン・ウェインライトIII の曲やら、ポール・ウェスターバーグの曲やら、バップ・ケネディの曲やらを交えつつ、チンピラっぽくホンキー・トンク・ロックンロールを聞かせる。グルーヴ自体がチープっちゃチープなので、なぜメジャーなフィールドで売れないのかがよくわかるのだけれど。そこがまたぼくの胸をわしづかみにしてくれるわけやね。
前作のようなスタジオ盤では見えない、この人たちの本質が味わえる。
|

 |
Risin' Outlaw
Hank Williams III
(Curb) |
|
CRTの『補習』で、鈴木カツ先輩にボロクソ言われたハンク・ウィリアムス三世。お孫さんです。ジュニアの息子、ね。
オルタナな手触りもあるとはいえ、けっこうおじいちゃんのホンキー・トンキンな持ち味を意識した音作りがなされており、カツさんはそこんとこが気に入らなかったみたいなんだけど。なるほど、それも一理ある。けど、ベックがロック/ポップ寄りのフィールドからやろうとしていることとか、G・ラヴがブルース/ソウル寄りの方面からやろうとしていることとか、エヴァーラストがヒップホップ寄りの方面からやろうとしていることとか、そういうベクトルを、このハンク三世くんはカントリー方面から逆にたどろうとしているんじゃないかと思えなくもないわけで。
そういう意味では楽しめる1枚だと思う。ぼくはわりと好きだった。ジャケットもかっこいいじゃないですか。
|

 |
'Til You've
Seen
Mine
Tom House
(The Catamount Company)
|
|
80年代、詩人として、あるいは雑誌編集者として活動していた人だとか。97年にアルバムを出して、遅いデビューを飾ったわけだけれど。それからは年1枚のペースでアルバム・リリース。これが3作目になる。
ぼくにとってはデビュー盤に続いて2枚目のトム・ハウスだけど、持ち味は変わらず。トラディショナルなカントリー、フォーク、ブルースに乗せて、さすがは詩人、シニカルで深い歌詞を聞かせる。別に歌がうまいわけじゃないけれど、歌声はまっすぐ聞き手に届いてくる。まるで30年代のレコードを聞いているような、すすけた音像もたまらない。
サウンド面ではさらに充実。デビュー盤のときと同じメンバーも参加しているが、今回はサム・ブッシュ、パット・マクラフリン、トレイシー・ネルソンなども加勢しており、ふっるーい時代の手触りを感じさせる音を確かなテクニックで見事に構築している。セカンド・アルバムも買わなきゃ。
|

 |
Doin' Time
On
Planet Earth
The Brooklyn Cowboys
(Leap) |
|
バンド名の通り、ニューヨークで結成されたバンドだけど、現在はナッシュヴィルが本拠なんだとか。グラム・パーソンズに「ハーツ・オン・ファイア」を提供したことでもおなじみのシンガー・ソングライター、ウォルター・イーガンを含むカントリー・ロック・バンドだ。ソロでも活躍している女性シンガー、ジョイ・リン・ホワイトや、ニュー・ライダース・オヴ・ザ・パープル・セイジのバディ・ケイジなどもメンバー。なかなか魅力的な顔ぶれだ。
音のほうは、真っ向からの古き佳きカントリー・ロックって感じ。半分くらいの曲をアル・パーキンスがプロデュース。ヴァッサー・クレメンツも客演。「ハーツ・オン・ファイア」の再演もあります。まあまあです。
|

 |
The Skiffle Sessions
Live In Belfast
Van Morrison,
Lonnie Donegan,
Chris Barber
(Exile) |
|
アメリカン・ロックの直球ルーツ・ミュージックがブルースとカントリーならば、イギリスのそれはスキッフル……ってことでしょうか。以前、モーズ・アリソンを引っぱり出して彼の音楽への愛情を表明したヴァン・モリソンが、今回は復活ロニー・ドネガンとクリス・バーバーというその筋の大御所を招いてライヴ・レコーディング。スキッフルの魅力を今の時代によみがえらせている。CRTみたいなものですかね(笑)。
ロニー・ドネガンの変わらぬ元気ぶりが印象的だ。2曲ほどドクター・ジョンが参加。
|

 |
Spiritual
People
Speech
(Vagabond/Fabulous/Toshiba
EMI) |
|
for Music Magazine (Revised)
99年の夏ごろになってからセカンド・ソロ『フープラ』(数曲追加ヴァージョン)が本国アメリカでもようやくリリース。年間ベストに選出する評論家もいれば、片やこてんぱんに酷評する人もいたり。かの地ではいまだ前作が論議を呼んでいるようだけれど。『フープラ』なんか98年のアタマにはすっかり堪能しちゃってたわれら日本のファンは、もはや次の段階だもんね。スピーチ、ソロ第三弾の登場だ。
確かにこの人の、いい意味での音楽的興味のとっちらかり具合は、バラエティ豊かなアルバム作りを歓迎する日本の音楽ファン向きなのかもしれない。本作に渦巻く音楽性も相変わらず多彩だ。スティーヴィー・ワンダーっぽかったり、マーヴィン・ゲイっぽかったり、スライ・ストーンっぽかったり…という70年代ニュー・ソウル風味は当然強い。ボブ・マーリーのカヴァーが収録されていることからもわかる通り、メッセージ面も含めたレゲエ感覚も少なくない。南部出身ならではのアイデンティティを再確認させるようなゴスペルの手触りも重要な要素だ。
とともに、曲によってはタジ・マハールやリッチー・ヘイヴンズに通じるフォーキーな感触があったり、ブリティッシュ・ロック臭があったり、ヨーロッパ的/クラシック的な哀愁がまぶされていたり、ソリッドなホーンをフィーチャーしたアーバンR&Bでグルーヴしていたり。アーシーな手触りとアーバンな手触りが交錯する。リズム・アレンジもそこそこ偏差値高し。なるほど、アメリカでこのすべてを一気に受け入れるメディアを見つけるのは大変かも。
もちろん、出が出だけにヒップホップ感覚がスピーチの重要な下地のひとつであることは今なお疑いようがないし、それは本作からも存分に漂ってはくる。わりと真っ向からのオールド・スクール・ラップふうアプローチも聞かれるし。けれども、これまでの二作のソロ盤同様、ここでも歌が主、ラップが従。というか、ラップも歌のひとつの手法として織り込まれているという印象だ。
歌詞のほうにはそれなりに過激なアジテーションも聞かれるが、総じてずいぶんとスピリチュアル。アレステッド・デヴェロップメント時代同様、生真面目すぎるきらいはいまだにあるものの、それはこの人の直しようのない性格ゆえか。そんな持ち味も含め、21世紀に向けて大切に聞いていきたい素晴らしい黒人シンガー・ソングライターだと思う。歌もさらにうまくなった。
|

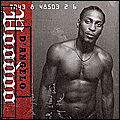 |
Voodoo
D'Angelo
(Virgin) |
|
これはかっこいいなぁ。見事なセカンドだ。4年半ぶりぐらい? お待ちしてました。デビュー盤『ブラウン・シュガー』の衝撃よ、再び!
エレクトリック・レディ・スタジオで、ザ・ルーツやトニー・トニー・トニーのメンバーも含むバンドを率いてほぼ一発録りされたものだとか。フェンダー・ローズ・ピアノの使い方が相変わらずうまい。ちょっとくすんだ音像の組み上げ方に才能を感じるというか。ミディアム〜スロウのファンキー・グルーヴは鉄壁だ。繊細さとドスケベさとがいい具合に交じり合う。エッチ度で言うと、よく引き合いに出されるマーヴィン・ゲイとかカーティス・メイフィールドとかいうよりはバリー・ホワイトに近いか。バリー・ホワイトのファルセット版みたいな(笑)。
レッドマン&メソッドマンの客演もあり。傑作!
|

|