デジタル化にどう向き合う? 〜公民館大会で議論 2025.3.18
 |
| デジタル化について語る茂木氏。 |
 |
| 基調講演を聞く参加者。 |
令和6年度みどり市公民館大会が3月8日(土)、笠懸公民館で開かれました。群馬大学共同教育学部兼任講師(前橋市未来政策課副参事、元前橋市桂萱公民館館長)の茂木勇(もてき・いさむ)氏を講師に迎え、デジタル化と公民館をテーマに講演会と分散会が行われました。
今大会のテーマは「デジタル化で公民館のつ・ま・む(つどう・まなぶ・むすぶ)はどうなる?」。公民館利用者や社会教育関係者ら63人が参加しました。午後1時半から始まった大会では、大矢副実行委員長による大会趣旨説明、須藤みどり市長と保志教育長の来賓あいさつに続き、茂木氏が約1時間の基調講演を行いました。
茂木氏は、新型コロナの影響で中断していた公民館大会が昨年度5年ぶりに開催されたときにも講師を務め、「住民が語らい、つながる場としての公民館」の大切さを話しました。今回は、昨年度の話を振り返りながら、デジタル化に対する国民の意識やコロナ禍で浮き彫りになったデジタル化の課題をはじめ、自治体のデジタル化の事例としてみどり市の公共施設利用システム、前橋市のオンライン講座やデジタルデバイド対策、石川県能美市のインクルーシブシティ事業の取り組みなどを紹介しました。そして、「デジタル化は、移動困難者や障害者の社会参加を後押しするなど、利便性の向上と生活支援に効果はあるが、コミュニケーション(雑談)の総量が減るデメリットが懸念される」と話し、「公民館活動を円滑にする潤滑油として『デジタル化』は存在する。住民目線で使っていくアイデア出しが必要」と、住民参加の取り組みの大切さを訴えました。
基調講演に続き、参加者は3つのグループに分かれて約1時間の意見交換を行い、その後行われた全体会で各グループから出された意見が報告されました。意見交換では、「高齢者にはデジタルに拒絶反応が多い。教えてもらってもすぐ忘れる」「活用するにはサポーターがいればよいが」「若い人の参加にはデジタル化は必要ではないか」「公民館はコミュニケーションをするところ」「スマホやパソコンの利用で脳は退化していないか。10年後が心配」などの意見が出されていました。
さまざまは分野でデジタル化が進んでいます。公民館の周辺でも例外ではなく、デジタル技術を使えば、これまで公民館の利用が難しかった人たちの参加にもつながることなど便利な点もあります。デジタル化と公民館をテーマに取り上げた今回の公民館大会では、今後デジタル化とどう向き合うかということを議論しましたが、「アナログ」ともいえる公民館の「つどう・まなぶ・むすぶ」ことの大切さを改めて確認する機会にもなったようです。
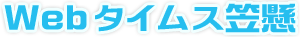
 ホームへ
ホームへ