大西さんを講師に迎えて利用者懇談会 〜笠懸公民館 2024.11.26
 |
| 講演をする大西さん。 |
 |
| グループに分かれての話し合いも行われました。 |
11月23日(土)、笠懸公民館利用者の会(上山利夫会長)は笠懸公民館を会場に、元桐生市公民館運営審議会会長などを務めた大西康之さんを講師に迎え利用者懇談会を開きました。40人が参加しました。
講演会のテーマは「公民館てどんなところ?〜考えよう、つどう・まなぶ・むすぶVol.2〜」というもので、同会がここ3年ほど取り組んできた利用者と公民館の関わりについて参加者による話し合いも行われました。
講師の大西さんは、「桐生市内で行っている町おこしも社会教育の一環」と話し、「江戸時代の町民教育も武家制度と思われがちだが、誰もが平等にまなぶ制度があり、それが欧米の民主主義を受け入れやすかった要因」と話しました。また、「公民館は社会教育法のなかで定められているが、社会教育といわれても答えられる人はいない、答えもない」とした上で、「公民館は来た人に何かを求めているぞ、と思っていただきたい」と話しをむずびました。
講演後は、2つのグループに分かれて話し合いが行われました。その中では、大西さんの「公民館は来た人に何かを求めているぞ、と思っていただきたい」という言葉を受けて、公民館の利用者は求めに対してどのような行動をしているかについて話し合われました。
昭和30年代の公民館を知るある利用者は、「青年団や老人会が集まった。夜の1時2時まで集まった。原点は、みんなで集まって地域をよくしていこうとしてきた。公民館は自分たちのためにあるんだ、皆のためにあるんだ。しかし、今は当時と変わった。かつては鍵の管理も自分たちでやった。公民館は集いの場だ。ボランティアの場だったりした。みんなのための公民館で大切な場所だ」「公民館が出会いの場で、結婚に発展し、式も公民館で挙げた」という貴重な話を聞くことができました。
東京から越してきたという人は、「公民館活動で友だちが見つかった。その後桐生に越したが、桐生と笠懸は違う。桐生は昔からの社会があるからか、転々と建物があり分散している。公民館組織そのものが、ここ(笠懸)の方がしっかりしていると感じている」など、笠懸野公民館活動を俯瞰的にみた意見も出されました。
公民館を利用するなかでの意見では、「若い人が公民館を使わないといけないと感じている。高齢化や人口減少でわずかな人数しか残らない。自己研鑽と社会貢献を目的としている。若い人が増えてくれたらいいなと思う。若い人が参加する公民館、そこに若い人が繋がってきたらいいと思います」といったものや、「サークルのなかでも高齢化と会員不足になっている、他の市の人も会のメンバーにすることで活性化できないか」という意見もありました。
話し合いのようすを見ていた笠懸公民館の割田館長は、「公民館は地域住民のために作ったという経緯がある。かつては市民が使えないほどの利用の多さだった。半数以上は笠懸の人でないといけない、という公民館運営審議会での答申もあって、7割くらいという数字となっているが、絶対7割というものでもないですし検討する時期でもある」と話していました。
他にも様々な意見が出され、高齢化で若い人がいない、また話し合いに参加した20人のうち男性が3人と圧倒的に女性が多い状況です。これらのことからも、若い人を巻き込んだり、男性の参加者を増やすイベントや企画が利用者の会や公民館に求められていそうです。
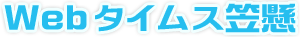
 過去の記事indexへ
過去の記事indexへ