岩宿博物館と連携して体験学習 〜笠懸東小 2024.7.16
 |
| アンギン編みに取り組む児童ら。 |
6月25日(火)午後、みどり市立笠懸東小学校(柳澤かおり校長)の6年生が総合学習の授業として、勾玉づくりと石器づくり、アンギン編みの3種類の体験学習を行いました。指導は岩宿博物館の職員と友の会のボランティアです。
図書室でアンギン編みのコースター作りを体験したのは7人でした。アンギン編みについて、学芸員で元館長の小菅将夫さんから、「アンギンというのは、からむし(青苧)、アカソ(赤苧)、ミヤマイラクサなどの繊維を原料として編まれた布で、法衣や敷物、袖なし、前掛け、袋などさまざまな用途に使われていました。見てください、こちらに縄文時代の衣料を再現した貴重な資料を机の上に展示してあります。これからケタ(織機のようなもの)に麻の横糸を止めて、6本の縦の色糸をコモヅチ(糸巻きのようなもの)に巻き付けて交互に移動して織ります。アンギン編みは時間がかかる作業なのです」と説明がありました。
友の会のスタッフがマンツーマン状態で、織り始める前の準備のコモヅチの糸通しや糸巻の仕方をていねいに指導し、児童らは指先の慣れない作業に四苦八苦しながら取り組みました。「できるかも、覚えた」と手が動きましたが、「慣れてくると要注意、気を付けて。網目が外れたりするから」と声をかけられていました。
縦横10cmほどのアンギン編みはコースターなど使い方はいろいろです。最後に結び目を作り、仕上げます。“結ばない靴紐”“縫わない裁縫(針と糸を使わないハンドメイド)”などを耳にする昨今、6年生は「糸結び」の言葉も作業も初めての体験らしく、ゆっくりとていねいに結び、終了のチャイムが鳴るころには全員で作品作りが終わりました。
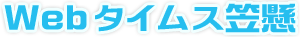
 過去の記事indexへ
過去の記事indexへ