ヤングケアラーとは? 〜更生保護女性会が研修会 2022.10.25
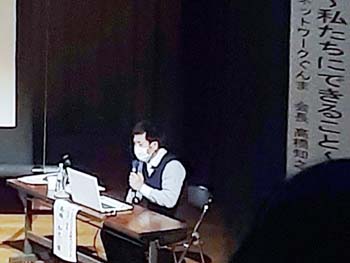 |
| 「ヤングケアラー」のことを知ってほしいと話す高橋さん。 |
10月5日(水)午後1時から、ながめ余興場においてみどり地区更生保護女性会(会長=木暮喜美枝さん)と群馬県更生保護女性連盟の主催で第一ブロック研修会が開催され、桐生・伊勢崎・舘林邑楽・太田・みどりの各地区から100人が参加しました。
研修会は「ヤングケアラーについて、私たちのできること」をテーマに、講師にヤングケアラー支援ネットワークぐんま会長・高橋智之さん(群馬県社会福祉士会事務局長)を迎えて行われました。
ヤングケアラーとは、家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポート等を行っている18歳未満の子どものことです。ケアの必要な人は主に障害や病気のある親や高齢の祖父母ですが、兄弟や他の親族の場合もあります。
ヤングケアラーの問題点は、介護や世話をすることで勉強をする時間や友だちと過ごす時間がとれなくなり、そのことが心身や精神的な成長に負の影響をもたらし、進学や就労、ひいては人生全体に影響が出ることがあるということです。
ヤングケアラーが困っていることは、やることの多さや勉強・進路への不安、睡眠不足、疲労感、むなしさ、誰にも話せない孤独感、気が休まらない、自分の時間が持てない、友だちの家族がうらやましい、などがあります。平成2年度の厚生労働省の調査では、世話をしている家族がいる中学生は約17人中に1人、高校生では24人に1人いるということです。この調査では、平日1日当たり世話に費やす時間として、中学2年生では平均4時間、全日制高校2年生は平均3.8時間と長い時間です。
群馬県では、第1回ヤングケアラー支援庁内外連絡会議が令和4年7月13日に開催されて、今後は県内での調査を実施予定しています。
講師の高橋さんは、「私たちにできることは、ヤングケアラーかなと思う子どもに出会ったときは、声をかけましょう。あいさつだけでもOKです。注意してほしいことは、本人はかわいそうな子と思われたくない、『頑張ってね』と言われてももう充分頑張っている、『いい子だね』の言葉がだれかに頼れない子どもをつくることもある、家族のことは悪く言われたくないと思っている、などに気を付けてほしいです。自分の寝る時間、友だちと過ごす時間、勉強をする時間を削って家族の世話をしている子どもが実際に存在しています。大人そして社会の義務として、そういった状況にある子どもを、少なくとも支援する必要があります。たった一回の声かけが、その子どもの人生を変えるきっかけになるかもしれません。ヤングケアラーが生じる背景を理解し、家族を責めることなく、家族全体が支援を必要としていています。情報を地域で共有し、社会で支える、今はまだ福祉が足りていません」と私たち大人の気づきの大切さを話しました。
最後に高橋さんは、「ヤングケアラーの今を、そして未来を守るために、できることからいっしょに支援をお願いします。参加者の皆さんが取り組む青少年の非行防止等犯罪予防のための地域活動と共通する取り組みです。この講演会のようすをスマホで撮影してたくさん拡散してください」と声をかけ、講演を終了しました。
【ヤングケアラー支援ネットぐんま】とは…教育・福祉・行政・医療・地域等を対象にヤングケアラーの啓蒙や理解の推進を目的として研修や出前講座などをしています。周知啓発、人材育成、居場所づくりを通してネットワーク構築を図っています。
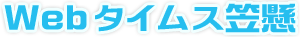
 過去の記事indexへ
過去の記事indexへ