「公共施設」「広域観光」をテーマに未来創生会議 2022.2.15
 |
| リモートで行われた未来創生会議。 |
第2期2回目の桐生・みどり未来創生会議が2月9日(水)、オンラインにより開催されました。協議テーマは「公共施設のあり方」と「広域観光」について。委員らが意見を出し合いましたが、慣れないオンラインでの会議のため音声が途切れるなど発言が十分に伝わらない場面もありました。
今回座長となった須藤昭男市長は、「委員の皆様の貴重な意見をいただき、両地域が魅力的な地域とする貴重な会議」とあいさつしました。公共施設のあり方については「生活圏を同じにする地域で、将来的に両市の資源を効果的に利用するもの」と議題の趣旨を説明しました。
委員には両市が持つ公共施設の一覧が配布され、その内、公民館や集会所などについては、「IT化により高齢者でも使いやすい施設にできないか」といった意見のほか、利用状況などについての質問も出されました。学校については、「両市で隣接しているところもあり、効率化できないか」といった意見も出されましたが、「現在両市が立地適正化と統廃合をそれぞれ進めている」との答弁で、学校を両市で共用するのは難しそうです。
広域観光については、桐生信用金庫で理事長を務める津久井真澄委員は、「コロナ収束後に向けて何ができるか、それぞれの自治体をPRすることが大切」と話し、複数の信用金庫がそれぞれの街で中心となるものを観光ルートとして案内するパンフレットを作っていて、桐生・みどり地域を絹産業のシルクロードとして紹介する予定があることをアピールしました。
このほか、「東武鉄道の活用で、阿左美駅に特急が止まるようにしてはどうか」というものや、「観光にはストーリーが必要」「キャッチーな観光ルートを考える必要がある」など、観光を巡るルート作りや、そのルートにはストーリー性と興味を引くネーミングがポイントとなりそうです。
興味深い意見としては、「桐生・みどりでピンと来るところがない。若い世代では観光という言葉で見ると見間違う。地元の人が楽しんでいないものは廃れる。地元の人が楽しんでいるかというとそうでもない。足利のワイン、桐生の地ビール、みどりの赤城山、歴史、文化、食べ物など、地元の人が楽しめる組み合わせのメディア戦略やSNSの組み合わせが必要」というものがありました。
観光に関しては、第1期では現時点で両市が行っている観光イベントの調整でしたが、今回はテーマとストーリー性を持たせた観光資源の発掘と企画の重要性が挙げられていました。
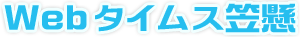
 過去の記事indexへ
過去の記事indexへ