コロナ禍における公民館活動は? 〜難題に挑む公運審 2021.12.21
令和3年度第3回みどり市公民館運営審議会(公運審)が12月9日(木)に多世代交流館で開かれて、主に先に諮問された案件に対する答申作業について審議が行われました。
協議に先立ち、新型コロナの影響で大間々公民館の市民講座が中止になったことや、笠懸公民館職員の作成による館紹介動画が完成し、今後広報の一環としてネットなどで活用していく意向や、笠懸野文化ホールとともに電源設備工事のため1週間ほどの休館を予定していましたが半導体不足により工事の見通しが立たなくなったので当面の休館がなくなったことなどが報告され、その後本題の答申についての協議に入りました。
答申作業は令和2年11月26日付で公民館長から発せられた「新型コロナウィルス禍における公民館活動」と題する諮問に対するもので、仲間と交流することで推し量られてきた公民館の相互教育がコロナ禍で大きく制限を受け、「つどう・まなぶ・むすぶ」という公民館機能が危うくなっているとし、公民館の機能をどう維持し充実していくべきかを問う内容です。
公運審ではこの問題について全員で議論を重ねたうえ、6人の答申素案策定委員会を組織して答申に向け取り組んできましたが、公民館がコロナ禍で長く休館となって審議が不十分であったことや、“ブレインストーミング”という新たな会議手法がうまく機能しなかったことなどもあって、でき上がった素案は不十分なものとなっていました。“ブレインストーミング”は集団発想法といわれるもので、委員各人から出される多角的意見を集めて問題解決に向かう手法ですが、委員からの意見は似たり寄ったりで多角的とは言えず、問題解決にはうまくつながらなかったようで、素案では解決策を見出すことが難しく、結局は要望の羅列となってしまいました。
この日は、素案に加筆修正を加えて答申書を完成させたいとして協議に入りましたが、委員から「コロナ禍で協議が十分といえない中で委員の意見を拾い集め、この素案は良くまとめていると感じる。しかし、ここには『お願いします、頼みます』と列挙していて答申の体をなしているとはいえないと感じる。答申は館からの質問に対して方向性や考え方、解決策などを示して意見を具申するもので、お願いするものではないはず。これは要望書であって答申書とするには躊躇を覚える」とする意見や、「素案では公民館がこれまでどおりに利用できるよう要望し答申とすると述べていて、具体的な意見具申や提案が不十分であり審議不足を物語っている。館長に諮問を取り下げてもらうか答申時期を遅らせる検討が必要なのでは」などの意見が出されました。これに対し館長からは、「諮問は公的に発せられたので取り下げはない。審議未了ならばコロナ禍で審議が不十分となり答申に至れない旨を書面でほしい」との見解が示され、委員からは「本来の答申書になっていないとしてもせっかく協議を重ねてでき上がったものだから、さらに体裁を整えるなどして提出に至りたい」との意見が出されました。話し合いの結果、素案に修正を加え予定通り今年度末までには答申書として提出することになりました。
公運審は本来諮問機関なのですが、現在の委員のほとんどは一度も諮問答申の経験がなく、今回は慣れない作業となり、コロナという見通しの立たないことがらが相手で、難しい答申作業となりました。新型コロナウィルス感染の詳しい知見もなく、県などから発表される感染状況は具体性を欠くもので、感染対策にも限界があるため、公民館の機能維持に有効な方策を見つけるのは至難というほかなかったようです。
コロナ感染はもはや個人の不注意や慢心によるものでなく、不運と考えるべきことではないでしょうか。“個人責任”とことを矮小化せず、天災のように地域一帯で取り組むべきものとして風評被害に及ばないことが肝心と思われます。コロナ感染を秘密にしていては日々人の集まる公民館などでは対応が手遅れになり、適切に対処することは難しいのです。今回の答申も、このような秘密主義を貫けば集団学習、相互学習は実現が不可能となること必至です。今回の答申では、秘密主義の打破や感染情報の共有などにも触れ、公民館や利用団体が一丸となって対処できるような答申になって欲しいものです。
次回の公運審は令和4年1月25日(火)を予定しています。
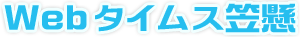
 過去の記事indexへ
過去の記事indexへ