【投稿】学校給食、自校方式の良さを見直して 2021.3.9
 |
| 笠懸西小学校のイメージ図。給食は大間々学校給食センターからの配食が予定されています。 |
平成31(2019)年の夏、子どもが通っていた幼稚園からの案内で、大間々学校給食センターの見学会に行ってきました。数人のママさんたちといっしょに、最初は「240円のランチだ」という思いで。
見学会では市の職員から、「今の学校の給食室は不衛生、狭い、暗い」と説明されました。センターにはフライ専用のスペース、野菜を洗うスペース、アレルゲン用など色々なスペースがあって、無駄と思えるほど広いと感じました。アレルゲン対応スペースはその時は使われていませんでした。ほかにも今は使われていないスペースがあると説明されました。そのため、本当にこの大きな箱物の必要があるのかと疑問に思いました。
試食では焼きそばを食べました。温かい給食を食べるのは当たり前です。ですが、2時間も前に調理し保温された麺は延びきり、ピーマンの色は変色してヘナヘナに。このような食事を子どもたちが食べているのかと思うとかわいそうになりました。
他のママさんたちも、幼稚園の給食を食べたことがある人たちですが、口々に「おいしくない」「一番おいしいのは外部委託の蒸しドーナツだった」といった感想でした。フライを保温しておいたらどうなるのでしょう。
給食とは栄養を摂るだけでなく”食育“だと思います。五感で味わうもので、給食室からのおいしそうな臭いや音、配膳された食事のおいしそうな色、味、舌触り。柔らかいものや堅いものを噛む音、そして食べる楽しさ。
ファーストフードに慣れた子どもたちの味覚をスローフードに慣れさせることも大切だと思います。お金には代えられない良いことがらを無にしてしまっていいのでしょうか。地産地消、笠懸の農家の人たちが作った野菜や果物、きめ細かなアレルギー対策など、自校式のメリットは計り知れないと思います。
センター方式のリスクについては話されているのでしょうか。前橋のセンターでは調理員さんが新型コロナウイルスに感染し、13の学校で給食の提供ができなくなり、お母さんたちはたいへんだったと聞きます。
数年前、笠懸小学校で委託のご飯に異物が混入し、ご飯が提供できなくなったことがありました。この時は調理員さんたちの努力で献立を替えて提供してくれました。緊急時の対応力は自校方式ならではだと思います。
リスクマネジメントを考えてもなぜセンター方式にこだわるのか理解できません。県内では自校方式に戻しているところもあると聞きます。ぜひ自校方式の良さをもう一度見直してください。そしてそのために私たちにできることはないでしょうか、誰か教えてくれませんか。
小学生を持つ母親(39歳・笠懸在住)
【参考】
笠懸小学校の規模適正化をすすめるため分離新設することが決まり、みどり市教育委員会は平成31年4月に「みどり市新設小学校基本計画」をまとめ、その中で「教育部としての考え方」として「笠懸地区の給食施設は、『老朽化した給食室を改修又は建て替えを行うより、給食センター方式に変更した方が食の安全性と経済性が確保できる』との判断のもと、自校方式から給食センター方式へ変更していく考え方とし、将来的には笠懸地区に給食センターを建設し笠懸地区全幼小中学校に配食したい」「新設校は、給食室を建設せずに、当面、大間々学校給食センターから配食したい」としました。そのため、新たに建設される笠懸西小学校(仮称)には給食調理室は建設されません。
また、みどり市笠懸地区における学校給食の提供方式のあり方を検討するために令和2年8月に設置された「みどり市笠懸地区学校給食提供方式検討委員会」は、今年1月に報告書をまとめ、その中では「衛生的な環境での給食調理・給食提供が可能であり、かつ、運用経費を抑え今後数十年以上にわたり、公共サービスとして持続可能な給食提供と施設運用を行うことができるセンター方式を採用することが望ましいと総合的に評価いたしました」としています。
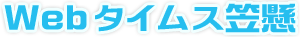
 過去の記事indexへ
過去の記事indexへ