
|
橋印のラミー糸は、靴業界で古くから使われている、定番的な麻糸です。国産では、最も信頼できる麻糸のひとつだと思います。素材も紡績工程も吟味されて作られています。レザークラフトの手縫い糸としても、もちろんたいへん使いやすい糸です。
30/3・20/3・16/3 は、画像左側のコーン巻になっています。ミシンで使うことを想定した製品なのかもしれません。
16/4・16/5・16/6 は、画像右側のチーズ巻になっています。
|
糸の太さ
|
撚りの向き
|
糊加工
|
重さ
|
長さ
|
30/3
|
左
|
あり
|
225g
|
1305m
|
20/3
|
左
|
あり
|
225g |
855m |
16/3
|
右
|
あり
|
225g |
675m |
16/4
|
右
|
なし
|
450g |
990m |
16/5
|
右
|
なし
|
450g |
765m |
16/6
|
右
|
なし
|
450g |
630m
|
重さと長さは、およその数値です。
|
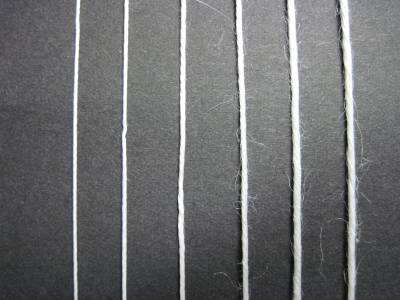
|
上の画像は、黒い台紙の上に糸を並べてみたものです。それぞれの太さや、毛羽立ちの感じの参考にしてください。どの糸も撚りは安定していますし、使っていて気持ちの良い糸です。
|

|
チーズ巻の糸を、最も簡単に使う方法は、ビニル袋に入れて口元をモールなどで止めてしまうことかもしれません。糸が汚れにくくなります。糸は中央の内側から引き出して使います。
|

|
だんだん糸の量が少なくなってくると、巻の形が崩れやすくなってきます。持ったときにつぶれてしまうということもあります。そこで、ちょうどいい大きさのタッパーなどに入れておくと、扱いやすくなるのではないかと思います。
上の画像のタッパーは、ほんのすこし高さが足りなかったので、革のふたを縫い付けてから、タッパーの本来のふたの天を切り取っています。それで少し高さが増して、糸がちょうど良く収まるようになっています。ジャストサイズです。
|
 |
細番手のコーン巻の糸は、細長いタッパーに入れて使うのが良いかもしれません。使うときは、タッパーのふたを外さないといけないのですが、収納場所の都合などもあり、私はこの様にしています。
|

|
糸は染色することもできます。手軽に染められる、手芸店などで販売されている染料で十分だと思います。(念のために書いておきますが、革用の染料は麻
の繊維には向きません。)上の画像の右側の糸は、染色後に玉巻器で巻いた物です。重さは100gです。玉巻器で巻くと、重さの割に大きな玉になります。
細番手の糸は糊加工がされているので、染色する時は、本来は糊抜きと精錬をするべきなのだと思いますが、革の手縫い用途でそこまでの手間をかけるのも気
が進みませんね。糊の成分を糸のメーカーから教えていただくことはできなかったのですが、おそらくPVA系の糊が主成分だと思われます。
PVAの糊は、お湯で煮ることによってかなり落ちます。もちろん、糊残りもあるのですが、色は付きます。その色が革の手縫いにあたって問題なければ良い
わけです。自己判断で決めていただきたいのですが、お湯でよく煮るだけでも十分かもしれません。洗剤も加えて煮たほうが効果が上がるようです。
|

|
上の画像は、糸の染色のときに使うと便利な、綛繰り器(かせくりき)と玉巻器です。
左の綛繰り器は、使うときには傘のように開いて、作業台の端などにセットします。真ん中に取手が付いているので、早く回転する観覧車のようにぐるぐる回して糸を綛にします。
私が使っている玉巻器は、糸の撚り機能も付いているので、玉巻器としてはちょっと形状の違う部分もあります。でも、撚りの機能は使うことがないので、た
だの玉巻器として使っています。もともと、毛糸などを巻くことを想定した道具だと思いますので、撚りの機能も革の手縫い用途では使うことがないと思ってい
ます。
昔は、普通に家庭でよく使われた道具らしいのですが、今ではこれらの道具を常備している家庭は少ないでしょうね。
|

