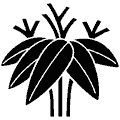ヘイ、家紋!
8/31
3年ほど前、父が寝たきりになってまともな会話ができなくなってから、ぼくは父方のルーツが気になり始めました。生前父は、自分のことも先祖のこともほとんど何も話してくれなかったのです。そして今年の5月には、残された唯一の家族である伯母も亡くなり、父方の家系を探る生き証人がいなくなりました。
ルーツの一つが家紋。日常生活で使うことなどほとんどありませんが、知っていたいと思うようになったのも、年のせいかな。
昔、祭りの時、玄関に飾る垂れ幕(正しい用語はわかりません)に家紋があるのを見た記憶があります。もしその幕が残っていればわかるはずなので、探すことにしました。
この夏、帰省したときに母に尋ねて幕を探しましたが、見つかりませんでした。でも母が、着物に紋が付いているはずや、と言ってタンスから出してきました。うーん、母の認知症も結構進んでいるのだけど、こういうところではまだ充分に機転が利いている。感動的です。
着物の背中にある紋を見つけてデジカメで撮影し、昨日、インターネットで調べました。わが家の家紋は「根笹」というものでした。今度は意味とか、どの土地から出てきたものかを調べようと思います。
家紋関連のあるサイトには今、家紋が静かなブームなのだ、と書かれていました。ほんとうかどうかはよくわかりませんが、そう言えば去年の秋、倉本聰脚本のドラマ「祇園囃子」でも、家紋を用いたエピソードが出てきましたね。日本のデザインはずっとずっと昔から高水準を示していますが、江戸時代には世界的に見ても頂点に達していたと言っていいでしょう。家紋は優れたエンブレムです。そんなデザイン的興味もあって、少し家紋を研究してみたい気持もあるのです。
カネタタキがわが家に
8/30
日曜日の夜、息子が「カマドウマって、小さくて足長いの?」と聞いてきました。「そうだよ」と答えると「カマドウマがうちにいる」と言います。えつ、こんなところに?見に行ったら壁に、確かに足が長くて小さな虫がいました。外から入って来たのでしょう。網で捕まえてから図鑑で調べると、どうやらカネタタキだと言うことがわかりました。
部屋でこの虫の鳴く声が聞こえていたそうです。金属音で小さくキュッ、
キュッ、
キュッ、
あるいはチッ、チッ、チッ、と鳴きます。この声から、鐘たたきという名前になったのでしょう。
撮影しようと思って網に入れていたら、いつの間にかわずかの隙間から逃げてしまい、今は和室のどこかにいます。明け方や夜、鳴き声だけが聞こえてくるのです。なかなか風情があります。でもぼくはすぐに、餌は大丈夫かと思ってしまいます。エアコンの後ろかどこか知らないけれど、そんなところにいると餓死しちゃうよ。
ちなみにカマドウマという虫は、子どもの頃家の縁の下など、ジメジメしたところにたくさんいました。一見コオロギに似ているけれど、なぜか気持ち悪くて(足の長さのせいか?)、ぼくは今でも好きになれません。東京の町中ではあまり見かけませんが。カネタタキの姿のほうがずっときれいです。
夜、耳を澄ますと、窓の外ではコオロギなど秋の虫の声が繁くなってきました。都会の明るい光で夜遅くまで鳴き続けていたセミの声が、少しずつ減ってきています。まわりはもうすっかり秋の準備が進んでいます。
斎藤祐樹君と亀田
8/28
高校野球決勝戦から1週間が過ぎても、日本中が斎藤祐樹君熱に浮かされています。久々のアイドル登場はいいけれど、今の時代は一般市民でもマスコミでも過剰な追っかけが発生しているから、本人はえらい迷惑をしているようです。一方、駒苫の田中投手は、斎藤君に世間の注目が集まったおかげで、少し助かっているかも知れません。
26日(土)夜、NHKで斎藤投手人気の理由を分析していました。100人にアンケートを取ったところ、「人格」をあげていた人が6割を占め、続いて「外見」が17%くらいだったかな(はっきりとした数字は覚えていません)。
「外見」が2番目に来ていますが、アイドルと呼ばれるためにはむしろ「外見」の方が必須条件でしょう。次に「実力」。「人格」はそれらのずっとあとに来るもので、乱暴な言い方をすれば、アイドルに人格はそれほど期待されていないものです。実力と人格を兼ね備えている代表として、ぼくたちはヤンキースの松井を思い浮かべますが、彼は昔も今もアイドルという範疇ではありません。その方がぼくはずっと好きですが。
ここでぼくは大胆な分析を試みます。もしかするとこの斎藤フィーバーの裏には、みんなの記憶にまだ新しい、ボクシングの亀田(急に呼び捨てになる)に対する反動があるのではないか(我ながらものすごい独断と偏見)。大衆はマスコミが無理やりつくり上げ押しつけているアンチ・ヒーロー像の胡散臭さにうんざりしていて、そのモヤモヤが甲子園決勝戦で一気に解消された。そして斎藤投手という古典的美男子(彼の場合「イケメン」より、こういう表現の方がふさわしい)に自分たちの抱く「純粋さ」を託した、と。だからアンケート回答者は彼の「人格」をことさら強調しているように思えるのです。
日米親善野球も控えてますから、人々はもうしばらく、甲子園の夢の続きを見ることができそうです。ところでぼくは、田中投手にも大いに注目していこうと思っています。
高校野球決勝戦とオオムラサキ 8/24
高校野球の決勝戦は歴史に残る名試合になったようです。ようです、と書くのは、試合の一部しか見ていなかったため、リアルタイムの感動を体験することはできなかったからです。どちらの試合の時間も、ぼくと家族はオオムラサキを探していました。
山梨県北杜市の長坂にオオムラサキセンター(オオムラサキ自然公園)があります。ここは2年ほど前から行きたいと思っていた場所。オオムラサキはぜひ一度見てみたい蝶の一つなのです。4日間の帰省から東京へ戻る途中に訪れました。
センターの中には人工で蝶を育てている施設があるのですが、ここで見た数頭のオオムラサキはどれも羽がぼろぼろになっていて、美しくない。実物に出会えたという感動がありませんでした。園内の遊歩道でも、羽のかけらは見つけたものの、生きた蝶の姿は見られませんでした(他の種類ならいたけど)。
ちょっとがっかりして宿泊先のペンションに行ったのですが、部屋に入ってしばらくしてテレビをつけたら、高校野球の試合が映し出されました。えっ、まだやってるの? 延長13回裏、早実の攻撃。早実がんばれ!見応えのある攻防は再試合へ。
さて、ぼくたちの蝶探しも再試合。翌日もう一度センターに戻り、今度は公園内ではなく、すぐ近くの「自然観察歩道」を探索しました。でもやっぱり見つからない。歩き疲れた妻と娘は、帰ろう帰ろうと言い始めましたが、息子とぼくは諦めきれずに進み続けました。
しかし歩き始めてから約1時間、ついに見つけました。木々の高い梢の間を舞うオオムラサキを。やった!大きい、美しい。しばらくそこにとどまって、飛ぶ姿を数分後に再度確認しました。捕まえることも写真に撮ることもできませんでしたが、一つの達成感は味わえました。さあ、これで帰れる。
車に乗り込んでラジオをつけたら、早実の校歌が流れていて、優勝を知りました。
脳の活性化 8/16
花や何やらの塗り絵、奥の細道や百人一首を文字をなぞって鑑賞するといったたぐいの本が中高年の間で流行っているそうです。「脳の活性化」という唱い文句さえつけば売れてしまうと言うのが何とも貧しい。日本人が脳の老化を防ごうと必死なのは、世間から取り残されたくないため、という分析が先日の新聞に出ていましたが、ほんとにそのとおりですね。
ぼくも4年ほど前から脳には興味を持ち続けていますが、ただ昨今の脳ブームは、他のブームの例に漏れず、本質からかけ離れて、流行にのっかって売りたいだけという浅ましさが見えるから、いやになってしまうのです。
塗り絵なんてしなくたっていいのですよ。真っ白な画面に自分で線を引く、自分で色を塗る。それは確かに勇気のいることだけど(ぼくがいつも経験していること)、そっちのほうがよほど脳の活性化に効果的です。
NHKの「プロフェッショナル」の案内役をやっている茂木健一郎さんは、どんなゲストが出てきても、脳に関連づけて話をします。茂木さんが取り組んでいることの一つは、従来の科学では説明できないものを脳科学で説明することのようです。
「世界一受けたい授業」の中で茂木さんはよく、「何かを思いだそうとするときのモヤモヤとした苦しさが脳にいいのです」と言っています。それは現状を超えようとする苦しさでしょう。その考え方からすれば、あらかじめ描かれている線をなぞったり、その枠内に色を塗るという安心感より、自分で線を引いたり色を塗ったりする時のドキドキ感を味わう方が、よほど脳に刺激になるわけですよ。
絵が下手だから塗り絵でいいやとか、人がやっているからやってみよう、という安定志向を選んでしまっているのだとしたら、その時点で、わたしたちの脳はすでに老化を促進してるのではないでしょうか。
クレームをつける 8/14
修理に出していたコンピュータMac mini が土曜日に戻ってきました。「検証いたしましたところ、ご連絡いただいている症状は再現せず、異常は見つかりませんでした。お客様のお手元で再び症状が発生した場合は、次のような原因が考えられます。→周辺機器との接続性」
あれえ、熱のことはどうなったの?と思ったのですが、故障の数時間以外は順調に動いていたので、これで様子を見ることにします。
先週まで、ぼくが企業に相談したりクレームをつけることがいくつか続きました。
8月4日(金)、Mac
mini で圧縮ソフトを使う必要が出てきたので、開いたら「標準版を購入してください」というメッセージが出ました。おや、これは試用版だったかな?まだ正式に購入していなかったのかと思い、インターネットでダウンロードしました。ところが、同じものを5月に買っていたことが、あとでわかりました。そして、サイト内のFAQを見ると、間違って購入しても払い戻しはできないと書かれてある。5250円を捨てろと?
それはおかしい、初期画面のメッセージが誤解を招くような紛らわしいものになっているのが原因じゃないかと思って、すぐに抗議のメッセージを書いて送りました。と。そしたら、月曜日(7日)に「支払い手続きは取り消しました」との返事が。また、表示についても改善しますと、謝罪してありました。そのかわりぼくはダウンロードしたデータと登録番号は廃棄しました。当然ですね。
いい返事を期待していなかったので、これはちょっといい方向に意外な結果でした。言うべきことは言ってみるものです。
クレーム受付係もストレスのたまる仕事だろうとは思うのですが、電話の場合、最初から横柄な態度で応対する人も時たまいます。昔、某日本経済新聞社のクレーム係もそうでした。へんな客もいるかも知れないけど、正統な抗議をする人もいるんだから、もう少し相手を見極めてから態度を決めろよ、と言いたくなることが間々あるものです。
見なくて良かった 8/8
ずっと忙しいおかげで、亀田のボクシング試合を見ずに済みました。各種報道を見ていると、どうしようもない内容だったようで。ぼくはもともとああいうキャラは嫌いなので、始めから見る気はなかったけど。
あんなキャラを組織ぐるみで売り物にしているビジネスにはうんざりします。笑いの世界でも何でも、変なのが多すぎるのでは?
いまだに余震やまずといった感じですが、彼の父親の言動がまた低レベル。この詭弁、誰かに似ているなあ。論理のすり替え、傲慢さ、そうそう、わたしたちの国の首相とそっくりじゃありませんか。
亀田を嫌って批判すれば、それがまた話題になり、彼をとりまく関連事業はますます儲かる、という仕組みになっています。つまり金が儲かる勝ち組にさえなれば手段を選ばないということです。
あれ、これも誰かに似ているなあ。あ、そうそう、ちょっと前までマスコミをにぎわしていたホリエモンや村上なにがしの考え方そのものじゃありませんか。
そして、世界レベルとの差には目をつぶって、マスコミが国民の気分だけをあおっているところは、2か月前のサッカーW杯日本代表とそっくり。あーあ、何ちゅうこっちゃ。日本の異常さをもっと自覚した方がいいんじゃないか。
ボクシング業界やテレビ局が、リング外の殺伐とした演技をしつこく見せることでしか儲けられなくなってしまったのだとしたら、あまりにもあさましいし、国民がそれに乗せられているだけだとしたら、あまりに貧しい。
でもTBSへの抗議やベネズエラの日本大使館に送られたメールの驚くような数は、希望も抱かせるものでした。そこにぼくは日本人の健全なバランス感覚も見出します。
暑さでMacもやられた 8/6
8月に入って、一気に夏らしくなりました。猛暑が続くと気力体力の維持が難しいのですが、暑さに弱いのは人間だけではありません。コンピュータは人間以上にデリケート。そのことを思い知らされた事故が、先日起きました。
Mac mini を4月末に買ったことはここでお話ししましたが、使い始めてからまだ3か月しか経たないのに、1日(火)の午後、突然コンピュータがプッツーンと切れてしまったのです。フリーズではありません。画面が真っ暗になり、本体のランプが消えています。なんで? と思ってまた起動してやっていると、3分くらいでまたプッツーン。その後何度やっても電源が落ち続け、その間隔は次第に短くなっていきました。
このコンピュータが使えなくなったら、仕事にならない。すぐにサポートセンターに電話をして、状況を話して指示を受けながら回復を試みたのですが、どれも失敗し、対応した人たちも原因が分からない。万策尽き果て、修理に出すしかないと言うことになりました。しかも最短で2日後にしか渡せず、戻ってくるのは早くて3日後。事態が深刻ならもっと延びる。その間仕事はどうする? あれこれ考えたあげく、兄の事務所へ相談に行きました。
コンピュータに詳しいU君がぼくの話を聞いて、「それは熱のせいですよ」……そう言えば、機械が異様に熱くなっていたな。コンパクトな機械は小さなスペースにめいっぱい詰めるから、熱がこもって、そう言うトラブルが起こりやすいとのこと。そんなことサポートセンターの人たちは誰も言ってくれなかったぞ! 結局、増設用メモリーチップと外付けハードディスクを貸してもらい、古いG3の能力を高めて、そちらで作業することにしました。
一応の解決を見るまでに9時間。まる一日棒に振ったわけですが、あきれたことに、数時間使わないでいたおかげで、Mac mini はその夜からまた普通に動き始めたのです。もちろんぼくは翌日すぐに小さな扇風機を買って、今は風を当てながら動かしていますけど。
続きはまた今度。さあ、仕事だ。
梅干し作ってます 8/5

梅雨が明けて良く晴れ上がった昨日の朝、
This is the day! ……なーんて言いはしなかったけど、ついに実行に移しました。干しながら数えてみたら84個。奇しくも8月4日で大安(笑)。おいしい梅干しになりそうです。
生存の厳しさ
8/1
虫の観察で学ぶことは多いのですが、自然の厳しいしくみをつくづく教えられます。たとえば個体の優劣差と、種としての生存の関係。
きのうとおととい、たまたま息子がアブラゼミの幼虫を続けて捕ってきて、羽化の様子を見ることができました。おとといの方はごくふつうに羽化して、昨日の朝、元気に飛び立ちました。
ところが、昨日の幼虫の方は歩き方が最初からおぼつかなく、枝にしっかりと捕まることができませんでした。その中途半端な状態で殻が割れて、なかから柔らかい成虫が姿を見せ始めました。こうなるとやっかいなのです。
息子がセロテープで殻を枝に固定しようとしたのですが、中から出てきたセミは、まともにぶら下がることができず、落ちてしまいました。足の力がなくて、自分の殻にぶら下がることもできないのです。そうなると今度は、空中で羽をきれいに伸ばすことができなくなってしまうのです。
あとは悲惨な過程を歩むだけです。くちゃくちゃの羽と歩けない足を持ったまま、色だけはアブラゼミらしい焦げ茶色へと変わっていきました。できるだけのことはしてやりましたが、ぼくたちにできることなど知れています。かわいそうですが、ただ見守るしかありませんでした。
そんな例をぼくたちはたびたび目撃してきました。殻からあと一歩で抜け出せると言うところでこと切れたトンボや、蛹の部屋をしっかりと作れずに、昨日のセミと同じように、くちゃくちゃの羽で土から出てきたカブトムシなどなど。
昆虫たちはそういう欠陥を持つ個体が出てくることを想定した上で、圧倒的な数でもって、種の存続をはかってきたのだということを、身近な羽化の観察からも、深く知らされるわけです。