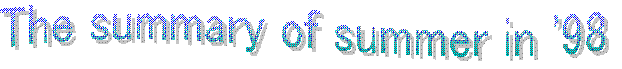
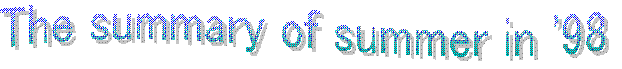

あなたは 人目の訪問者です
'98.9.11.更新
ホームページへようこそ。夏も終わって秋を迎えようとしています。モンシロ蝶のあとに黒あげはなどが多数見受けられる年は通常であれば猛暑になるのがこれまでの私の観察結果ですが、今年はどうもそうではありませんでした。七月の初めに記録的に暑くなる日が何日かあった後には、梅雨前線が停滞してずっと曇りがちだったり雨だったりの日が続きました。インド・中国・韓国では記録的な豪雨と洪水が起こり、日本でも大量の降雨によって那須地方を初めとして集中豪雨の被害が出ました。今年の夏は、私にとってもちょっとした出来事に出会った夏でした。それは下に示す写真のような蝶を発見したからです。
一目でお分かりのように羽の発生が不完全な奇形の蝶です。自宅の門の前で発見したのですが、飛ぶことは不可能で地面を羽でたたくようにして移動できるだけでした。発見した当時は羽も痛んでおらず羽化したあとそれほど時間は経っていないとも思われましたが、羽化の失敗によって羽がこのような形になったのではなく発生そのものに異常があったのだろうと思います。この蝶をもっとカメラを接近させて撮ったものが下の写真です。
これらの写真は’98年6月22日(月)に撮影したものです。すなわち発見した日付けがその日だったというわけですが、この蝶はその後丸五日間は生きていたのです。6月27日の朝に死亡しているのを確認しました。門のところから我が家の庭に移して寿命のある限り見取っておこうと思ったので以上のような事もわかりました。正常の蝶の平均的な寿命がどれくらいなものかを私は知りません。写真からお分かりのようにこのちょうは黒アゲハの一種です。かなりの地域で身近に見ることのできる蝶だと思いますのでご存知の方がおられたら教えていただければ幸いです。
この奇形の蝶を発見する前の6月6日の地元の湘南新聞には、平塚の隣町の大磯町のダイオキシン濃度は神奈川県下で最高値を記録しているという記事が載ったばかりでした。この写真を撮ったのは平塚市内というわけですが、そのようなセンテンスの中で奇形の蝶を発見したので、蝶を哀れと思うばかりでなく違う心配もしてしまいました。不吉な予感、すなわち「ひょっとして奇形の原因が化学物質による影響だったら......」というわけです。そのためこのページにリンクされている平塚市へ電子メールを出したところ、平塚市博物館の浜口さんという方から電話をいただきました。「奇形の原因が化学物質だとしたら奇形の蝶が多数発生してもいいはずなので、これからも良く観察しておいてください」とのことでした。この蝶を発見した後にもたくさん蝶を目にはしましたが、幸いなことに奇形の蝶を眼にすることはありませんでした。
私は小学生時代の夏休みには毎年昆虫採集に一夏明け暮れていましたが、このような奇形の蝶を目にするのは生まれて初めてのことでした。そのためまず最初に頭に浮かんだのが「自然界では一定の割合で奇形の蝶が生まれ出ているのだろうか」ということでした。そこで私が中学生時代に理科で世話になった先生に電話をしてみました。その先生の自宅で以前たくさんの蝶の標本を見せてもらったことがあったからですが、先生の話では、「奇形の蝶は時々見受けられる。ことに氷河期から生息していたといわれる古代蝶には奇形が多い」とのことでした。古代蝶というのは比較的に小型の羽が透明な蝶です。
このような奇形の蝶が発見されて、皆さんは「そんなところにすんでいるなんて不吉だ」と思われるでしょうか?私は身近なところに小動物や水棲動物・昆虫がたくさんいる環境のほうがむしろ安全だとも思っています。たとえ化学物質によって小動物や水棲動物・昆虫などに奇形が現れたとしても、それは人間への危険信号として人間が奇形になる前にわれわれにメッセージを送ってくれるからです。人間が暮らしている生活環境をすべてコンクリートで固めてしまってこれらの小動物や水棲動物・昆虫をすめないまでにしてしまえば、自分の生活環境の周辺で起こっている異変を人間は前もって察知できないことになってしまうからです。なんの前触れも無く突然人体に異常のある子供が生まれ出てしまって大慌てするよりもむしろ安全な環境だと思います。
上の蝶は地面を羽でたたいて移動するため、また地面にずっといるためにアリなどに食われることによって以下の写真のように徐々に羽は小さくなっていきました。惨めな姿に変わり果てたかもしれませんが、蝶は自分に与えられた生を全うして死んで行きました。
アリに食われて死んだ姿は無残ともいえますが、われわれに何かを伝えようとしているのかもしれません。本来なら優雅に空を飛び花に群れることができたであろう蝶の死の姿です。美しいものの裏にある悲劇でしょうか?
本当だったらこんな風に飛べていたかもしれない蝶の、ちょっと不運な話でした。しかし飛ぶことのできる蝶はすべて幸福に生きて行けるかというと、決してそうではないようです。蝶の身の回りにも危険はいくらでもあります。くもの巣に引っかかって死んでしまっている蝶は皆さんも見たことがあるかもしれません。私はこの同じ夏にカマキリにモンシロチョウが捕らえられてしまう瞬間を撮影しました。蝶は動きが速くまた警戒心も強いのでなかなかカメラに収めることが難しいのですが、花に止まって蜜を吸っているときにはそのような警戒心も解けてカメラを近ずけても平然としています。そんな瞬間を写そうとしていたら、あろうことかそのモンシロチョウがカマキリに捕まってしまったのです。非常に偶然の出来事だったのでピントが幾分合っていないのですがご覧ください。
上の左側の写真のどこかにカマキリが隠れているわけですが、草花の茎と非常によく似ていて見当たらなかったのです。普通保護色といえば弱い生物が強い生物から身を守るために自分自身を周囲と似たような色にしてカモフラージュすることをさして言いますが、この場合はカマキリのほうが相手に警戒されないように自分をカモフラージュしていたというわけです。蝶を写そうとレンズを向けていたら急に蝶の動きが止まってしまいました。「どうしたのだろうか」と思ったらそれがカマキリに捕まった瞬間だったのです。まさに一瞬の出来事でした。昆虫たちの世界も生存競争は激しいようです。人間を含めすべての動物も食物連鎖で生きているわけですから、自分のための食料を確保することは必須です。そのことが頭ではわかっていても、そのことを目の当たりにするとやはり驚かされるものです。
何かこのように書いてくると、私には夏休みの宿題をやっているという感じがしてきます。一夏の間に起きた昆虫たちの観察記録を書いているといった、まるで幼い頃の自分に戻ったような気分です。大人になってから昆虫を注意して観察し始めたのはここ何年かの間でしかありませんが、今年の夏はその点では私にとって記憶に残る夏だったといえます。
今回のTopページは以上です。今回からページのつくりが変更されました。これまで紹介してきた本は完売して在庫が無くなってしまったので、その本の紹介は別立てで違うページに載せることにしました。Bookのコーナーに載っています。良かったらご覧ください。
このページの制作はHasegawa Study Assisting (HSA) でした。HSAでは中学生・高校生の英語・数学の個人・個別指導を承っています。対象地域は神奈川県平塚市・大磯町・二之宮町などです。またHSAでは英文の日本語訳・日本語の英文訳なども承っています。入塾希望や翻訳依頼などは下記の電子メールか電話でお知らせください。
Tel:0463(32)4971
All rights reserved
![]()
