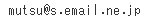HOME -> 城跡データ -> 青森県の城跡一覧 -> 野辺地城
野辺地城 のへじじょう
- 別名
- 野辺地代官所
- 時代
- 南北朝時代~江戸時代
- 分類
- 中世平山城
- 規模
- 標高:14m、比高:約10m
- 現状
- 町指定史跡/資料館、公民館等
- 場所
- 青森県上北郡野辺地町字野辺地
- 最終訪城日
- 2010年12月30日
七戸氏一門の野辺地氏の居城。近世には南部藩の代官所となる。現在は資料館や図書館等の公共施設の敷地となる。
城史
| 年代 | 出来事 |
|---|---|
| 1335年 | 野辺地は伊達五郎宗政の所領となったが、伊達氏が遠く離れたこの地を管理できたかは不明である。 |
| 南北朝時代 | 七戸南部氏がこの地に一族を派遣し、野辺地城を築いたとされる。 |
| 1456年 | 「蛎崎蔵人の乱」を起こした蛎崎軍は田名部より七戸に向けて進軍し、南部領の拠点を次々落として金鶏城(野辺地城)へと攻め込んだ。城は七戸南部氏一門の菅氏が守備していたが、多勢に無勢のためすぐに落城したという。 『東北太平記』 |
| 1592年 | 豊臣秀吉の命により南部領の城は破却されたが、七戸将監の持ち城だった野辺地城は破却を免れた。 『南部大膳大夫分国之内諸城破却書上』 |
| 1598年 | 石井伊賀が2千石で野辺地城の城主を務めていた。 『館持支配帳』 |
| 1665年 | 七戸城の代官の野辺地氏が野辺地城の代官を兼任し、横浜、野辺地、七戸を治めた。 |
| 1691年 | 西野氏が野辺地城の代官となる。 |
| 1735年 | 南部領内二十五代官所が制定され、野辺地城は以後は代官所に改めらた。 |
| 1868年 | 「戊辰戦争」末期の9月22日に新政府軍へと降伏した盛岡藩だったが、同月23日に弘前藩・黒石藩の兵が盛岡藩領へと攻め込み馬門村が放火されて全焼となった。夜襲だったために対応が遅れて野辺地城下まで攻め込まれるが、安宅正路率いる盛岡藩の援軍が到着したことで弘前藩・黒石藩の部隊は大打撃を受け、弘前藩の小島左近が戦死したことで壊走状態となった。この戦いでは津軽側、南部側両方に戦死者が出たが、盛岡藩の降伏後に行われた戦いのため、新政府からは私闘として処理された。 |
| 1870年 | 「戊辰戦争」の結果、旧盛岡藩領北部へ会津藩が転封され、新たに斗南藩が成立した。この時に野辺地代官所は斗南藩に接収され、船で斗南藩へやってくる旧会津藩士の重要な中継地点となった。 |
| 1871年 | 廃藩置県により野辺地代官所は廃城となった。 |
縄張り
城は野辺地川の右岸の台地の端に築かれており、主郭の北と東は空堀で台地から切り離され、西と南は川に面した崖となっている。
関連施設
アクセス
- JR大湊線、青い森鉄道の野辺地駅から徒歩15分。
- JR大湊線、青い森鉄道の野辺地駅から「むつバスターミナル行き」のバスに乗り、「野辺地下町」で下車して徒歩4分。
関連リンク情報
- 野辺地町の公式サイトの「史跡/文化財」の「歴史民俗資料館」ページで資料館の情報を確認できます。
- 本ページでは
 の地図リンクサービスを使用させていただいています。
の地図リンクサービスを使用させていただいています。