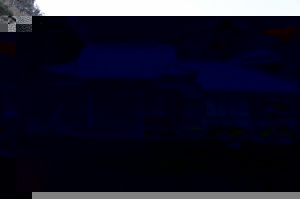|
伊豆横道33観音霊場巡り 第11回 海蔵寺・善福寺・潮音寺 2015/02/12 |
|||||
|
写真のスライドショー https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=UIFMwyh3Rmo |
|||||
|
|
アプローチ(バス) 入間口へは下田駅から10:00発吉祥行きが直通で便利(入間口着10時54分) 妻良・子浦・伊浜方面へは入間口13:31発(吉祥で乗り換え接続) 妻良から子浦・伊浜方面へは14:52発ほか数本ある ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 伊豆横道33観音霊場巡りはあと4観音を残して、南伊豆の天気、特に風の穏やかな日を様子見しておりましたが、本日その機会を得て巡って参りました。ただし、最終の結願寺は時間切れでお預けとなりました。また日をあらためて訪問したいと考えています。 本日の納経は30番海蔵寺、31番善福寺、32番潮音寺。
バスを乗り継いでの巡礼なので、バス待ちの間を如何にして過ごすかがもう一つの焦点です。今回は、30番海蔵寺の入間を訪ねるのに、石廊崎港にて時間調整することにしました。前回の宿題だった城山の周遊コースの踏査にあてました。 他には、入間の漁港と村落の風景、妻良の漁礁、そして子浦の海岸はいずれも風光明媚。特に入間は初めての訪問で印象に残りました。
寺については、入間の海蔵寺の和尚に説教を延々といただきました。巡礼では初めての有難い経験です。妻良の善福寺はご住職が女性でした。子浦の潮音寺は無住で、本堂にて自分でご朱印の押印です。これも初めてのことでした。 第30番 海蔵寺 入間の里には、白坂トンネルの手前のバス停入間入口で下車し、左に海の方へ下って行く。石灰岩だろうか、山を削って造成した道路の山際は、白っぽい部分が露出して何重かの層になっている。
道路は窪地を迂回するように三度曲がりくねりながら高度を下げ、海岸線にたどりつく。その間、山間に広く展開する斜面には段々畑が里まで続いていた。見下ろすと、青々とした畑で野菜の収穫をしている二人の男女の姿があった。下まで降りてくれば、「入間キャンプ村」がある。
ご住職は本堂におられた。窓際の一画に書見台を置いて、その周りは書棚や手回りの品が散らばって足の踏み場もないほど。新しい卒塔婆が何枚もあり、硯の墨もたっぷりなところをみると、梵字をしたためていたらしかった。かなり大柄なかたである。 立ったまま納経の許しを請うたら、座るように言われた。なるほど本堂内では座って納経すべきであった。これまでの29寺はすべて立ったままだった。私が納経を終えると、方丈さまは長々と説教を垂れはじめた。しかし、大半がぼそぼそ声で、耳が悪い当方にはよく聞き取れなかったのが残念。それでも、ときどき、当方の意見を訊かれるので、懸命に耳を澄ました。
入間の浜は綺麗な砂浜が左右に伸び、夏は海水浴場として賑わうものと思われる。漁船が数艘北側の突堤に係留され、また船揚場にもその倍の数があった。なお、南伊豆歩道が整備されているらしく、千畳敷経由で吉田へ約4時間で行けるという。いつか歩いてみたいものだ。 第31番 善福寺 妻良は漁港と民宿の町。漁港はここ数年できれいに整備された。私が初めてここを訪れたのは2011年4月のことだった。二十六夜山という藪山を登った帰りに寄った港だ。鄙びた民宿の町と言う印象は今や港がきれいに整備され、すっかり近代的な漁港に生まれ変わった。
仏壇に、もしや金剛峰寺の大塔か?と目を奪われたが、この寺は真言宗であった。金剛峰寺は真言宗の総本山である。もはや、ふた昔も前になるか、吉野の桜見物と抱き合わせに、私ども夫婦で旅行した高野山だ。
本堂には勝海舟が宿泊した「勝海舟の間」というのがあった。8畳くらいの部屋に座卓が一つ置かれている。額入りの説明には、勝海舟が幕艦「昇平丸」で入港し、安政2年9月8日〜13日の間、宿泊したという。風待ちだったらしい。
納経を終えて港に出たら、犬と散歩しているお年寄りがいた。この方から、実は寺のご婦人が現在の住職であると聞いた。先代の父親が亡くなった後を継いだとのこと。ご主人は下田の小学校の校長先生だった由。 妻良の盆踊りは県指定の無形民俗文化財だそうだ。夏の、その日の宿はもう塞がっているに違いない。盆踊りと聞くと、隣町へでも飛んでゆく女房殿には、やっぱり内緒にしておこう。 第32番札所 潮音寺 潮音寺の場所は分りづらい。バス停子浦で下車した時、年配のオジサンが後から降りてきたので道を訊くと、彼の家がすぐ近くだと聞いて案内して頂いた。
一旦、海際に出てから、密集した人家の裏通りに入った。海から離れて山の方へ向かってゆく。一緒に歩きながら、彼の年を訊くと、昭和5年生まれの85歳だとのこと。ここは彼の生家で、40年勤務した東京築地の魚河岸から20年前に戻ってきたという。市場でセリを担当していたそうだ。 しかし、ここでは単身の生活で、月に2,3度、家がある月島に帰るそうだ。住民票が東京のままなのは、何と言っても、今では60年になる東京暮らしが板について、田舎の不便さが身に沁みるからだという。しかも、ここでの生活は幼馴染も一人二人と失って、頼りに出来る相手が居なくなってきている。生家が今や別荘となっている感じだ。
きょうは下賀茂で買い物をしてきたという。両手にポリ袋を提げている。前方に、上に伸びた細い石段の先に寺の廂が見えてきた。石段の手前から右の路地へ入る彼の後姿をじっと見送った。
堂の真ん中の奥に座すご本尊はさすがに暗くてはっきりしないが、多分、聖観音だろう。左手に蓮華を持っているように見える。とにかく、本日最後の般若心経を納めた。 時間に余裕があるので、海岸に出る。去年夏に孫たちと水浴して遊んだ子浦の海水浴場には人の姿はなかった。一抹の寂しさは一人旅のせいか。32観音を済ませ、最後の伊浜の普照寺を敢えて残して帰ると決めたのは、そんな気持ちが動いたせいかも知れない。 |
|
|||