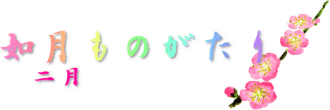
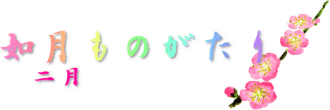
| ここでは、毎月厳選してその月を代表する物語を紹介。 今月の物語は「梅一輪」。 |
| 梅一輪 |
| 東吾がふと前を行く女に目を止めたのは、その女が寒風に身を縮めて歩きながら左右にきょろきょろと目をやる動作が不審だったからで、思わず女の後を尾けた。もう夕暮で、東吾が見ていると果たしてその女は永代橋の袂で、前から来た男に体当りした。「どうもとんだ粗相を・・・・・・」女が笑顔で会釈をし歩きだそうとするので、東吾は前に立ちふさがった。 体当りされた男に向かって、懐中を調べるようにいうと、男は慌てて懐に手をやった。 「ございません、財布がございません・・・・・・」 東吾に押さえられた女は何を思ったのか、 「疑うのでしたら、私の体を改めて下さいまし」 と、いきなり着物を脱ぎだした。廻りを取り囲んでいた野次馬が一瞬ぎょっと息を呑んだのは、素っ裸になった女の背中に鮮やかな滝夜叉姫の彫物が描かれていたからである。 「じゃあ掏摸じゃなかったんですか」 東吾は「かわせみ」の居間で、るいと嘉助、お吉を前についさっきの掏摸騒ぎの顛末を話していた。 掏られた男は材木問屋の主人で財布には三十両からの金が入っていた。 女は番屋につれていかれ、長助のところの若い者が女の着物を改めたが、どこからも財布は出てこなかった。東吾は女の後ろからみていて、実際女が掏摸とるところは見ていないが、あの格好は間違いなく掏っているはずだ。 「女の人の裸にぼうっとなっている間に、仲間に財布を渡してしまったんじゃありません」 るいが東吾の盃に酌をしながら笑った。 そこへ、番屋から釈放された女の後を尾けていった長助が、源三郎と一緒にやってきた。 長助はぼんのくぼに手をやると、「あいすみません、どじをやらかしました」 女の前を若い男がずっと歩いており、その男の後を追うように女は歩いて行った。番屋を出ると、下の橋、中の橋、上の橋とまっすぐ突き抜け万年橋の橋袂まで来たところで、二人はもやってあった小舟に乗り移った。長助があっと思った時にはもう小舟は大川へ向かって漕ぎ出していた。 「申しわけございませんでした」としきりに恐縮している長助に東吾が苦笑した。 「長助のせいじゃねえ、俺のどじだ」 女の前を歩いていた男と聞いて東吾がピンと来たのは、女がぱっと裸になった時半天をかしれくれろといった相手が仲間だと気がついたからで、半天を借りると見せかけて財布を渡したのであろう。 「ところで東吾さん、その女、いくつぐらいでした」 源三郎が、去年の暮から正月にかけて掏摸の被害が目立っているといった。その時期は毎年掏摸の稼ぎ時だが、今度の掏摸のたちが悪いのは、掏られた相手が気づいて声を上げると、いきなり刃物でぶすりとやるという。 「それじゃ掏摸とは言えませんよ。辻斬と同じじゃありませんか」るいが眉をひそめた。 話を聞いていた嘉助が「昔の掏摸には職人だという自信があったものですが・・・・・・」 「待ってください・・・・・・」嘉助が考える目になった。 「若様がごらんになった女の背中の彫物、滝夜叉姫とおっしゃいましたね」 東吾がまたかという顔で頷いた。「いえ、あっしがそんなことを聞くのは、滝夜叉姫ってのは平将門の娘でしたよね」昔、将門の彦六という掏摸の名人がいたと言った。 名人中の名人で、掏った財布から一両だけを抜いてまたその財布を戻しておくという。あとで掏られた相手が財布を調べてみると彦六と書かれた紙切れが一枚入っている。その鮮やかな手口にいっとき人気があったという。その将門の彦六は、六年前に神田明神の境内で殺されていた。嘉助がいうには、その彦六には娘が一人いたという。「それじゃ、あの滝夜叉姫の彫物があった女掏摸が彦六の娘じゃありませんか」お吉が言いだして、東吾が源三郎をみた。 掏摸騒ぎから三日後、東吾は方月館の稽古に出かけた。夕方まで稽古に汗を流し、一風呂浴びてから正吉の素読を聞いていると、表に女の声がしておとせが出て行った。東吾が見ていると、若い女がおとせに礼を言っている。地味な身なりだが、どこか垢抜けている。善助に聞くと、おまさといって飯倉の観月亭で働いているという。ご亭主は観月亭の板前だったが流行り病で歿り、今は亭主の両親と暮らしていた。数日後、東吾は方斎と一緒に飯倉の刀屋に招かれて観月亭へ出かけた。その座敷にやってきた女中がおまさであった。その席で東吾は先日の掏摸騒ぎの一件を面白可笑しく話した。方斎もおまさも熱心に聞いていたのだが。狸穴の稽古を終えて、八丁堀へ帰ってくると早速源三郎がやってきた。 「東吾さん、ちょっとこれを見て下さい」と源三郎が差し出したのは、小さな紙片で、やさしい女文字で「彦六」と書かれている。ここ数日、財布の中から一両掏られこの紙片が入っていたという掏摸の被害が出ているといった。まるで彦六の幽霊だな、と東吾がいい、源三郎が娘の仕業ではないかといった。名人彦六を真似た掏摸が起こる一方、今までの強盗まがいの掏摸も相変わらずで、ひどいときは一日に三人も殺されていた。「源さん、早いとこその荒っぽい連中を突っつかまえないといけないな」 その夜から、東吾は源三郎について町廻りをはじめた。「かわせみ」が気になりながら、この寒空に毎日黙々と町廻りを続けている源三郎の気持を思うと、東吾も「かわせみ」でぬくぬくとしていられる性分ではなかった。四、五日も町廻りを続けていた朝、源三郎が長助と一緒に八丁堀の屋敷へやってきた。ちょっと東吾に首実検してもらいたい女がいるので、「かわせみ」まで来て欲しいという。話を訊くと、長助のところの若い者が永代の門前通りで不審な素振りの女を見かけ後を尾けると、別に掏ったところをみたわけではないが奇妙な素振りをした。 相手の男はたまたま顔を見知っていたので、そのまま女を尾けるとなんと「かわせみ」へ入ったというのだ。嘉助に訊ねてみると七、八日も前からかわせみに泊っている客で、人を探しに江戸へ出て来たらしい。 「その女がいつかの女掏摸だというのか」るいが宿帳を持ってきた。「このお客様ですよ」目黒村百姓 おまさ と書かれている。「おい、この女なら知っているぞ」東吾が声をあげた。「ご存じだったんですか」東吾が観月亭で会った話をすると、長助はすっかりしょげかえってしまった。だがおまさとすれ違った男は入船町の貸席の主人で、財布を調べてみると十五両持って出た筈が十四両になっていて彦六と書いた紙切れが入っていた。どうも東吾にはいつかの女掏摸がおまさなのかはっきりしなかった。「女は化粧で化けるからなぁ・・・・・・」と苦笑し、「そうだ・・・・・・」顔は化粧でごま化せるが、背中の彫物は隠せない。そしておまさが湯に入ったところを東吾がそっと風呂場の窓から覗いてみると、真っ白い背中には彫物なぞどこにもない。気がつくと後ろにるいがいて、東吾は思いきり背中をつねられた。 居間に戻ってくると、お吉が一枚の紙を差し出した。おまさの部屋に落ちていたという。 おとっつぁんをころしたげしゅにんをしりたければ あす、みょうじんさまへ と書かれている。翌日おまさは明神様へ出かけるのに、嘉助に案内されて頼んでおいた舟にやってきた。舟にはすでに東吾が乗り込んでいた。「お前、彦六の娘だったのか」おまさはうつむいたままで否定もしない。 「俺の話を観月亭で訊いて、江戸へ出て来たんだな」おまさが顔をあげて答えた。「あたし、お父つぁんの仇が討ちたかったんです」下手人は仲間の丑松に違いないといった。丑松はおまさと夫婦になりたいと言いだしたが、彦六は突っぱねた。すでにおまさには決まった相手がいたし、丑松は掏摸とはいえすぐに刃物を持ち出すことから、彦六は丑松を嫌っていた。それを怨んで丑松が殺したに違いないといった。彦六が殺され、おまさは板前をしていた恋人の吉二郎とすぐに江戸を離れた。暫く諸所を転々とし、やがて吉二郎の両親のいる目黒村に落ちついた。子供も生まれ十二年の歳月が流れたが、父親を殺された怨みは忘れることが出来なかった。おまさは捨て子だったという。神田明神の境内に捨てられていたところを、お詣りに来た彦六に拾われ、将門様の思し召しに違いないとおまさと名付けて大事に育ててくれた。その父親がこともあろうに自分が原因で殺された。今、自分が怨みを晴らさなくちゃ、お父つぁんが浮かばれませんと泣いている。観月亭で東吾の話を聞いて、また丑松達が江戸で掏摸を働いていると知って、敵と討とうと江戸へ出た来た。「かわせみ」のことは方月館の善助に訊いたといった。大川端のかわせみには始終、若先生が来ているから、ひょっとしたら・・・・・・東吾が笑い出した。それであの手紙をわざとお吉に見つかるようにおいておいたのか。「あたし、殺されたっていいんです。せめて丑松に一突き・・・・・・」袂に彦六の形見の匕首を忍ばせていた。「そんな物騒なもの、振り回すんじゃない。丑松たちのことは俺にまかせろ。その変わり丑松達を捕まえたら奉行所へ言って、証人になってほしいんだ。悪いようにはしない」おまさは素直に頷いた。神田明神につくと、おまさが一足先に境内に入っていった。境内にはすでに畝源三郎も張り込んでいる筈であった。東吾はおまさのあとを尾けながら、四方に目を配っていた。一万坪からある広い境内、どこから丑松達が襲ってくるか知れない。あれだけの大見得を切った以上、なんとしてもおまさの命は守らねばならない。おまさが末杜の方へ歩いていくと、社の裏手から男が出て来た。一人、二人、三人、四人の男と女がおまさを取り囲んだ。「おまさ、よく来たな」声を掛けたのは、いつかの掏摸騒ぎの時、半天を貸した男であった。「お父つぁんを殺した下手人を教えてくれるんじゃなかったの」おまさがいうと、そこにいた女が薄笑いをうかべた。「決まってるじゃないか。この丑松って男はね、女と金のためなら人殺しなんぞ、屁の河童さ」やはり彦六を殺したのは丑松であった。そこまで聞いて東吾は木影からとび出した。源三郎、長助もかけつけ、男女四人の掏摸仲間は一網打尽にお縄になった。「おい、おまさはどこだ」いつの間にかおまさの姿が消えていた。ふとみると東吾の懐に小さな結び文が入っている。 おとっつぁんのはかまいりをしてきます。あす、いまごろ、ここで まさ とある。 翌日、同じ頃神田明神の境内に、東吾はるいと一緒にいた。昨夜のかわせみでは、るいをのぞく全員がおまさは来ないというほうに賭けた。さすがにるいは東吾の気持を思って口には出さなかったが、東吾が頭からおまさの言葉を信じていることが内心面白くなかった。「誰かさんは、きれいな女の人のいうことは、すぐ信じておしまいになるんですものね。今までだって・・・・・・」甘い痴話喧嘩をしているうちに、すっかりたそがれて、「とうとう来ませんでしたね・・・・・・」寒いところでずっと待っていたせいかるいの手はすっかり冷え切っていた。るいの手を握りしめながら仙台堀のほとりまでやってきたとき、いきなり目の前におまさが走り出てきた。「おい、どうしたんだ」東吾が声をかけた時には、おまさは力一杯東吾を突きとばしていた。あっと思う間もなく、東吾はふんばりきれず仙台堀に落ちていた。船宿で借り着をして「かわせみ」へ帰り、熱い風呂で暖まりやっと人心地のついたところへ、源三郎が訪ねてきた。「源さん、俺のはお人よしの上に、馬鹿がつくな」としょげているのをみて、源三郎が思いがけないことを言いだした。「おまさが、手前を名指しで奉行所に名乗ってきました」もう神林様のお調べも終わり、特別の計らいをもって目黒村へ帰ったという。「それじゃなんで・・・・・・」神田明神へやってこなかったというと、源三郎が「いえ、おまさは神田明神へ行ったそうですよ」るいが居間を出て行ったすきに早口で告げた。 「東吾さん、よせばいいのにるいさんとべたべたしてたそうですな。おまさはそれをみて、つむじをまげたんです」「誰がそんなことするか」源三郎が懐から、小さな枝を取りだした。「おまさが神田明神へ行った証に東吾さんに渡してくれと預かったものですから・・・・・・」廊下をるいが戻ってくる足音がする。 「そんなもの、ここへ持ってくる奴があるか、しまえ、しまえ」東吾が慌てて言った。 たった一輪なのに、部屋中に甘い香りがひろがった。 |