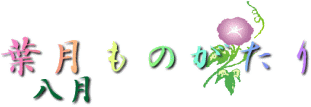
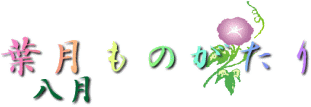
| ここでは、毎月厳選してその月を代表する物語を紹介。 今月の物語は「秋の螢」。 |
| 秋の螢 |
| その日、大川端一帯は夕方から激しい雷雨になった。 稲妻がなりひびき、どしゃぶりの雨が道を川のように流れていく。 大川もどんどんと水嵩を増したが、幸い満潮をずれていたのでこれ以上は上がるまいと思われた。 「かわせみ」でも念のため、大事な荷物を二階に上げ、二組ほどいた客は万一を考えて日本橋の宿屋へ移ってもらった。 夜になって一段落すると、外を吹き荒れる雨と風の音が耳についた。遠雷が聞こえている。 そんな時、神林東吾がびしょ濡れになりながらやってきた。 「るい……おい……るいはいないのか」 「来て下さったんですか」 るいはもう涙ぐんで、水浸しになってやってきた東吾にすがりついた。 他人でなくなって一年余り、夫婦のような暮らしをしていても、そこは晴れて夫婦になれないるいにしてみれば、こんな嵐のような雨の中、屋敷を抜け出して来てくれた東吾がうれしかった。東吾は嘉助と一緒に大川の様子を見に出て行った。 小半刻もすると雨も小降りになってきた。びしょ濡れになった東吾もやがて湯に入り、るいの居間に落ち着いた頃、表の大戸が叩かれた。 「おたのみ申します……おたのみ……」 若い女の声である。お吉が出た行ったが、すぐに居間にやってきて、客だという。若い娘とその父親で、父親の方は怪我をしているという。やがてお吉が二人を二階へ案内した。 るいは無論東吾の傍によりそって、部屋を出ていく気配はない。 その大雨の日から三日後の夜半、馬喰町一丁目の旅籠屋「ひさご屋」に押し込みが入った。続いて馬喰町三丁目の旅籠「笹屋」。翌日は本所の旅籠屋。その後も旅籠ばかり次々と襲われて、抵抗する者、逃げる者は斬り殺され、金目のものはことごとく奪われた。その凶悪な手口に江戸中の宿屋稼業の者はふるえあがった。この頃は、はやばやと大戸をおろし、部屋があいているのに客を泊めないという旅籠まであらわれた。 源三郎は昼夜探索に追われ、やっと源三郎に会えた東吾はさっそくどうなっているのかと訊ねた。 「かわせみが心配ですか」 「かわせみ」には嘉助がいるからという東吾に、源三郎は嘉助一人では心もとない、出来れば東吾が泊まり込んだほうがいいと言う。それほどに賊は手ごわい。最初は八、九人で押し込みをしていたらしいが、最近では二組に分かれて一夜に二軒の旅籠を襲っているという。 また金を奪うことより、誰かを探しているらしく、押し込んだ旅籠で必ず宿帳を奪い、泊まり客の顔を確かめていく。 源三郎に「かわせみ」も充分気をつけて下さいと言われたのをこれ幸いに、東吾はさっそく「かわせみ」へ出かけた。ところがるいは暢気であった。 「うちに入るわけはありませんよ。お金もありませんし」 「かわせみ」には嘉助の孫のお三代が来ていた。母親が二人目を安産し、しばらく「かわせみ」であずかることになっていた。 東吾が居間で一杯やり始めると、るいが案じ顔で訊ねた。 この前の大雨の日の外泊がばれたことで、兄上からおとがめがなかったかという。 「いっそ、ばれた方がけりがついていいと思うんだ」 るいは返事をしなかった。その話になるとるいは決して本心を口にしない。東吾は諦めた。どっちにしても、るいと別れる気は毛頭ないし、添い遂げるためには兄に背くことがあっても仕方がないと思ってもいた。 「かわせみの客は大丈夫か」東吾は話題を変えた。 るいの返事では、今夜の客はみな常連ばかりだという。はじめての客はこの前の大雨の日の娘と父親だけであった。 父親の怪我はかなり酷くて、結局かわせみへ泊まったその夜から熱を発し大変だったらしい。二日ほどで熱は下がったがまだ歩けない。娘のお糸の話では、犬に噛まれたというが、嘉助は刀傷だという。 ほろ酔い加減の東吾は、大川へ続く庭へ下りた。庭のあちらこちらに螢が小さく光っている。 月が変わっても、旅籠を狙う盗賊の跳梁はやまなかった。町方の必死の探索をあざ笑うかのように、被害は重なった。 ただ、連日のように襲われていたのが、この頃は二日おき、三日おきと変わった。そのかわりというように、今度は川筋を往来する荷舟が襲われるようになった。通之進や源三郎の調べで、どうも旅籠を狙う盗賊と荷舟を狙う盗賊とは同じ仲間ではないかという。 源三郎が目をつけたのは水鳥の大三を首領とする一味で、十数人の手下と一緒に悪事をかさねている凶悪犯であった。 さらにこの水鳥の大三一味で最近仲間割れがあり、船頭の長七というのが娘を連れて一味を抜けたらしい。 「娘を連れて……」 東吾の心にひらめくものがあった。東吾は源三郎と一緒に屋敷を飛び出した。まっしぐらに「かわせみ」へ向かう。 萩の間には誰もいなかった。が、娘のお糸が押し入れに押し込められていた。 「お父つぁんを助けて……」 父親の長七はお糸のために仲間であった水鳥の大三一味を殺しに行ったという。そこへお吉がやってきた。「嘉助さんも、お三代ちゃんもいないんです」 東吾は嘉助が長七を尾けたのではないかと思った。お三代はその嘉助をみつけてついていったに違いない。 嘉助は必死に追っていた。背中に孫娘のお三代を背負っている。 大雨の日に長七親子を見た時から怪しいと睨んでいた。長年八丁堀の御用聞きをつとめていた時の勘であった。それとなく気をつけていると、果たして足の傷も癒えたと思われた今日、長七が裏梯子を伝って部屋から抜け出したのを見つけ、あとを尾けてきた。うっかりしたのはその嘉助を見つけて孫娘のお三代があとを追って来ていたのを、永代橋を過ぎてから気がついた。一人で帰すには心もとなかった。とりあえずお三代を背負い、長七のあとを追った。深川を過ぎた辺りから、急に空が暗くなり今にも降り出しそうな気配である。 長七が行ったのは、法乗院という寺の中にある閻魔堂であった。背中のお三代はぐっすりと眠っている。嘉助がはがみしたのは、単身だったからである。法乗院の本堂へ行けば住僧がいるだろうし、お三代を預けることも出来るが、その間になにかあっては取り返しがつかない。あたりを見廻すとすぐ脇の堀割にちょっとした屋根のついた舟がもやってあった。嘉助の頬を雨がかすめた。急いでお三代を舟の中にいれた途端、大粒の雨がおちてきた。嘉助は草むらに身を伏せて、なにか大きなことがおこる気配を感じていた。 どのくらいそうして待っていたのか、やがて一人、二人と男達が集まってきた。全部で9人。そのうちの一人を見て嘉助は息が止まりそうになった。 かつて、るいの亡き父と一緒に当時中川筋を荒らしていた水鳥の大三一味を追い込んだことがあった。結局取り逃がしてしまったが、その時大三他数名の顔をみていた。今目の前にいるのは、その水鳥の大三に見間違いない。これは大捕物であった。しかし嘉助一人では知らせを出すことも出来ない。 一味は長七の潜んでいる閻魔堂に向かった。長七は閻魔堂の屋根の上に隠れ、やってくる大三一味に吹き矢で挑んだ。 やがて大三一味が長七に気がつき取り囲む。嘉助は草むらに潜んでいる時に拾い集めた石礫を投げた。 抜刀した一人が今度は嘉助に向かって斬りかかってくる。雨の中を必死に逃げた。息が弾んでもうだめかと思った時目の前に東吾があらわれた。 「嘉助……大丈夫か」 水鳥の大三一味は、東吾と源三郎の峰打ちに叩き伏せられ捕縛された。 「お父つぁん……」雨の中をお糸がかけよった。 長七は神妙にお縄を受けると、源三郎に向かってお糸は自分の本当の子ではないと言った。 その時、嘉助がわあっと叫び声を上げた。 お三代を乗せた小舟が、もやっていた綱が切れたのか激しい堀割の流れに押し流されていく。堀割は大川に出て、やがて海になる。舟は激しい勢いで海に向かって吸い込まれて行く。のっているのは五歳のお三代だけである。もし横波でも受ければ間違いなく舟は覆る。 「旦那、あっしがお三代ちゃんを……ちょっとの間だけどうかお縄を……」長七が言った。 房総の荒海育ち、この辺りの水路を知り尽くしている手前なら助けられるという。 堀割沿いの小舟に飛び乗ると、あっという間に流れにのって、お三代の乗った小舟が大川に出る手前で廻り込む。 大川はそこから海へ向かって渦を巻いている。長七はお三代の舟にとび移ると、ぐったりしていたお三代をしっかりと抱き上げた。 長七はお調べに対して何もかも話した。お糸は行徳の大地主の娘だという。やはり十三年前、江戸川を流されていたのを長七が命がけで助けた。ちょうど女房子を津波でなくし悪い仲間にも入っていたのだが、お糸が自分の娘にかなさってみえた。 お糸は長七によくなついた。お糸のために盗賊の足を洗いたいと考えていたが、江戸中の水路を知り尽くしている長七を大三は放そうとしなかった。それどころかひた隠しにしていたお糸のことも気づかれて、仲間に入れろと言いだした。 それを訊いて長七はお糸を連れて逃げ出す。しかし仲間の追跡は執拗だった。このままではどうにもならないと思い、とうとう仲間を殺す決心をして閻魔堂に呼び出した。 長七がお調べを受けている間、お糸は「かわせみ」へ預けられていた。 「あたしは長七の娘です。お父つぁんは優しくて、幸せな歳月でした」 どこかで働きながら、お父つぁんが罪を償って出てくる日を待つという。お糸はそのまま「かわせみ」で働くことになった。 るいはお糸に肩入れして、なんとか長七の罪が軽くて済むように通之進に言ってくれという。東吾にしても長七の裁きは気になっていた。 或る日兄に呼ばれた東吾は、水鳥の大三一味の刑が決まったと訊かされた。また長七は入牢中に病死したという。東吾は愕然とした。だが兄の眼が笑っている。 「お糸と言ったな。まもなく父親と一緒に暮らせるせるようになるだろう」盗賊の長七は歿り、船頭の長七は嘉助の孫娘を助けた褒美を与えられる。 「知らせるところがあるのではないか。」東吾は屋敷を飛び出した。 「かわせみ」ではるいが東吾の来るのを待ちかねていた。 庭の隅を、小さな光がすっととんで見えなくなった。 |