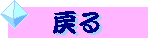岐阜県恵那郡蛭川村田原 |
採集できる石
| 鉱物名 | 量 | コメント |
|---|---|---|
| 水晶 | 少ない | 運しだいですね |
| トパーズ | 少ない | 運しだいですね |
| 緑柱石 | 少ない | 運しだいですね |
| 雲母 | 少ない | 運しだいですね |
| 蛍石 | 少ない | 運しだいですね |
| 長石 | 少ない | 運しだいですね |
岐阜県恵那郡蛭川村田原 |
採集できる石
| 鉱物名 | 量 | コメント |
|---|---|---|
| 水晶 | 少ない | 運しだいですね |
| トパーズ | 少ない | 運しだいですね |
| 緑柱石 | 少ない | 運しだいですね |
| 雲母 | 少ない | 運しだいですね |
| 蛍石 | 少ない | 運しだいですね |
| 長石 | 少ない | 運しだいですね |
昼2時くらいに、ようやく恵那のインターに到着した。石友のK氏もここは初めてで、二人とも地理勘は全くなかった。とりあえず遅い昼食を取るために恵那橋の手前にある喫茶店に入った。今回は一泊二日(テントでのキャンプ)の予定である。まだ二人とも独身なので気楽なモノである。
まず、かねてからの計画通り、一日目は道路を覚えるためにあちこちを走ってみることにした。田原の大きな採石場を中心に、できるだけ多くの道路を通ってみるつもりだった。
博石館をスタートし、5つほどの採石場を見て回ることができた。それぞれの採石場で、少しずつではあるが収穫があった。
最初は小さい採石場だったが、いきなり両錘の水晶を採ることができた。
二番目では晶洞のはがれ落ちたもの(5Cm×4Cm)が、くず石材の上に置いてあり、まるで、持っていってくれと言わんばかりであった。(石材所の人にして見れば、それ以上中に入らないでくれといった意味だったのかもしれない。後で聞いた話だが、鉱物だけでなく、道具まで勝手に持っていく不届き者もいたらしく、鉱物愛好家のつらよごしである。)
四番目では、40Cm×25Cm×15Cmの花崗岩の中頃に小さいながら晶洞のついた者が得られた。これは今でも我が家の床の間に飾られている。(小さい蛍石が付いているだけだが)
五番目では、収穫はなかったが、少し移動しただけで、これだけの鉱物が得られ、さすが、日本を代表する産地であると感心させられた。
まだまだ行きたいところはあったが、今回は道を覚えることに徹することにし、後ろ髪を引かれながらも、次の産地へと向かった。
次の産地は並松地域である。目的は関戸川の川砂の中のトパーズであった。木積沢は明日に入ることにし、様子を横目で眺めながら関戸川に向かった。下呂温泉に通じる国道234号線に出て中津川市の方に右折し、しばらく進んで屋根に飛行機が墜落している喫茶店のあたりで左りに折れ、しばらく走って目的の関戸川の産地に着いた。
初めてここを見た感想は、人の力はすごいものだなあというものであった。同じ目的の者がトパーズを求めて掘ったところが、まるで巨大な爆弾が爆発した後のように深く大きくえぐられているのであった。「塵も積もれば山となる」と言うが、これはちょうど逆のパターン「みんなで掘ればでかい穴」であろうか。ちょうど橋を中心に100mくらいが川幅も広がり、橋げたも落ちそうな勢いであった。
とりあえず、川に入ることにし、できるだけ掘られていなさそうな、上流部にねらいを定め、大型スコップで川の中をさらい、ふるいの中に入れ水で洗い始めた。掘り初めて3分ほどでK氏がトパーズ(5mmくらいの頭付き)をふるいの中から見つけだした。すぐに気をよくする単純な二人であったが、K氏の話を聞くと、ここからは錫石も出ているとのこと。その他母岩の様子も見ておきたいこともあって、ふるいに入っている物全て(5〜10mmくらいの粒)を持って帰ることにした。それから約30分、掘りに掘ってたまった砂はバケツ5杯分以上は十分にあったと思う。重さは40Kgは越えていただろう。それを川底から運び上げ、車に積み込むのは重くて一苦労であったが、帰ってからの楽しみができ、心はうきうきしていた。こんな輩がいるのだから大きな穴があくのも無理はないなどと、みょうに感心をしてこの産地を後にした。(現在はこの産地は採集禁止になって、教育委員会その他がパトロールしているらしい。)
後日、帰ってからの楽しみで、K氏と二人で早速川砂を干し、選別にかかったが、錫石は全くなく、トパーズも苦労した割には合計10個で、K氏と山分けにした。後は小さい水晶も、10個ばかりであった。
次の目的地は福岡鉱山である。恵那の鉱物の三種の神器と言えば何といっても水晶・トパーズ・緑柱石であろう。(チンワルド雲母・サファイア・自然蒼鉛と言う人はもう相当なマニアである。この世界からは足を洗うことができないかもしれない?)ここまでで、すばらしいとは言い難いが、すでに前者は採っている。残るは緑柱石だけなのである。
あらかたの場所は判っているのだが、どうしてもその場所を特定することができず、日が暮れてきたので、今日の日程は終わることとし、テントを張る場所を探しにかかった。(未だに場所がわからない。そのうち見つけてやろうと思うが、いっこうに機会がない。)付知川にはちょうどいいキャンプ場があってそこで一晩を明かすこととなった。
次の日は、朝7時から起き始め、洗面は付知川の川の水でし、テントをたたんで、今日は昨日の逆のルートで戻る計画である。昨日に見残した、木積沢と、田原周辺である。
まずは、木積沢に入ることにした。昨日、下見をしてあったので地理的には、わかりやすくなってはいたが、これと言った鉱物の収穫はなかった。
長靴の中まで水で濡れながら、いくら歩いても何も得られない。少し休憩する事にし、上の水田の土手に上がって、一休みを決め込んだ。
幸運というものはどこから飛び込んでくるかわからないもので、しばらく休憩した後、ようやく周りを見渡す余裕ができたときに気がついた。8月の最後であれば水田には稲の穂が出ているはずである。ところが、ここは水田の形はしていても稲が全くない。実に不思議な風景であった。しかも、土手が、すごく新しい。いま法面を作ったばかりのようだ。これは、今年新しく水田を造成したに違いない。そうであれば、土をかき回しているはずである。気になったので、水田の中に入っていった。
目を凝らしてあたりを窺うと、あちこちに黄色がかった白い石がぽつぽつと見える。拾い上げてみると、果たして、トパーズであった。クラックが多く土の鉄分が浸み込んで、とてもきれいとは言い難いが、3Cmを上回る大きさは標本にはよい大きさであった。結局5つのトパーズを拾い上げることができた。
K氏も横に積んであった石の中から径10Cm高さ15Cmもの煙水晶を拾い上げていた。ただ、長い間の川の流れと畑の中に積まれていたことで、見るも無惨な川ズレで角がみんななくなり、一見しただけではそれとは見えないものになっているのであるが、トパーズの方は劈開があってよくわかるし、水晶も側面・頭部と川ズレで欠けた部分の形を頭の中で補うと本来の姿が見えてくる、大変立派なものであった。
川の中より土手の方が収穫があったので、今度は土手を行くことにした。今回はそれが的中し、1Cmくらいではあるが、ごく透明なトパーズを2個採ることができた。
沢も終わりに近づき最後の橋にさしかかった時、橋の下をのぞくと川の中に白い棒状のものが落ちている。何だろうと川に入って拾い上げてみると、それは頭付きの長石であった。それも、バベノ式が2つと正長石が1つとが並んで落ちていた。橋の真下である。たぶん誰かが捨てたものであろうと思われた。ずいぶん思いきったことをする人もいるものだと思ったが、この時代は長石に魅力を感じる人もまれだったのか、よほどたくさんの所蔵品があって整理のためだったのか、それにしても今以て不思議である。
車に戻ろうと歩き始めると、川の中で中華鍋を回しておられる30歳くらいの人が2人おられた。(別に皿回しをしているのではない。「よなげ」とか「パンニング」と言って石の比重で選鉱するのである。)お話を聞かせていただくと、名古屋から来られた人で、フェルグソン石(といわれたと思うのだがはっきり記憶にない。放射能が云々の説明を聞いた記憶だけが残っている。)と錫石を採っているとのこと。川の中まで入って見せていただいたが、確かに1mmくらいの赤い粒が見えた。錫石の方は全然わからなかった。しかし、私はなぜか興味がわかず後になって自分もなぜ採らなかったのか悔しくてならなかった。10年程後にやっと沢に入る機会ができたが、もう何も採れなかった。水晶一個だけの収穫であった。
次は、田原地区に戻ることにした。帰りの時間まで、後3時間くらいであろうか。できるだけたくさんの産地を回ろうと考えてはいたが、残暑の厳しさもあり、博石館に戻り、展示物を見ながら涼むことにした。現在の建物とは比べものにならないほど小さく、展示物も少なかったが、見事な鉱物展示に我を忘れて見入ってしまった。スペインの5Cmもある黄鉄鉱をはじめ、販売のコーナーもありすっかり満足した。ただ、元気も気力も体力も使い切って、もう産地を回ろうとどちらも口に出さず暗黙の了解とでも言うのであろうか、帰途につくことになった。
しかし、おそるべし田原地区。
帰ろうと思って、駐車場に行って車に乗ろうと思ったそのときなんと自分の靴の3Cm前に、径1Cm長さ5Cmにもなる。晶洞から今落ちたばかりの綺麗な煙水晶が落ちていた。(この時まだ博石館の駐車場は砂利を引いただけの単なる広場であった。)トランクの中に収穫物を満載した私たちの車は、一路奈良を目指し5時間の移動を開始した。体は疲れてはいたが、心は満足し、帰りの車ではK氏とたくさんの話をしながら帰った。
(現在は採石場での採集は禁止されており、個人では入ることはできません。)