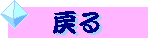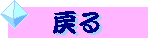採集できる石
| 鉱物名 | 量 | コメント |
|---|
| 磁鉄鉱 | 多い | 拳大のものです |
| 磁硫鉄鉱 | 多い | 見分けはつきません |
| 灰鉄輝石 | 多い | 菊のような模様が綺麗です |
| 石灰岩 | 多い | 結晶しているものもあります |
| 緑水晶 | 少ない | 1Cm以下のかわいいものです |
| ガーネット | 少ない | 2色ありました |
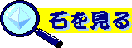
1995年9月9日
妻と娘がお盆で実家の方に帰ることになり、久しく遠ざかっていた石取りの虫が騒ぎ出した。結婚や子供が産まれたりの騒動の中で長らくこの方面から身を引いていたのだが、ちょうど大阪の紀伊国屋書店に行く機会があって、フィールドには出ないのでせめて石の本でも買おうと、2万円分ほどまとめ買いしたばかりであった。妻はびっくりしていたが、フィールドに行けば2万円で済むはずは、まずないのでこちらとしては安い出費だと思っていた。しかし、それがまた石取りの虫に火をつける結果となって、よけいに出費をすることになろうとは思っても見なかった。
朝7時に息子を起こし、ご飯を作って食べさせ、いざ出発となった。今はお盆だが洞川への道は混んではいないだろうと思った。私の母の実家が吉野であり、免許を取った頃からよくこの方面は運転させられていたので裏道まで熟知していて、少々道が混んでも、抜け道で行くことは朝飯前でもあったので安心であった。
予想はしていたが、吉野川を渡る橋だけは、どこも混雑はしていた。しかし、そこさえ抜けると後は快適なツーリングになった。
ここ吉野川には支流を含めて丹生という地名が多い。丹生という神社もある。いろいろな解説によると、赤い顔料として、また、メッキ用の水銀の鉱石として採掘されたところで、辰砂が採れるということがよく書いてあるが、この洞川までにある丹生はたぶん赤鉄鉱が出ていたのではないかと思う。丹生という地名の川の中に入っても見たが、辰砂らしきものはかけらも見えず、片麻岩のようなものが見えるだけであった。
くねった道が大半のこの国道も近頃はショートカットのトンネルができ、道幅も広くなり、走りやすくなってきていて驚いた。先へ進むにつれ、山の村々の雰囲気や谷の様子など、心和む風景が車窓にあふれ、下界を見下ろす景色など心が洗われるような感じのする所であった。吉野川の分岐点から約一時間でやっと洞川温泉への標識が見えてきた。そこを左折した辺りからキャンプに来ている若いお父さんやお母さんと浮き袋を腰につけたままの子ども達が目につくようになり、あと15分ほどで目的の五代松鉱山に到着である。五代松鍾乳洞の看板を目標にすればすぐわかるので都合がよかった。。
鉱山の場所はすぐにわかった。鍾乳洞を過ぎ、銘水「ゴロゴロ水」(奈良ではよく目にするミネラルウオーターである。)の湧き出ている前を通ると、50mほど先に車6台程の駐車できるスペースが目につく。ここが現場である。横に黄色い鉱山施設の跡があるのですぐわかる。その下には坑口があいているが、中からは鉄バクテリアによって赤くなった水がちょろちょろ出ている。どうも中は塞がれていないようだ。
車を止めたすぐ後ろがズリの山なのであるが、踏み分け道もない。しかし、よく見ると、大人の人が一人で登った跡がある。といっても、草が倒れているだけだが、こんな所に目的もなくたった一人で来る人はいないだろう。たぶん石取りの人である。だが、こちらは3歳の子供をつれているのである。とても登れそうにない角度であった。
試しに息子にチャレンジさせてみた。両手両足をズリの山に付け、まず右手を上に出して踏ん張る、今度は左足を上に出して踏ん張る、次に左手を上に出した瞬間にずるずると落ちてしまう。結局30Cm登るのがやっとであった。
しばらくは登り道を探したが、あきらめて先ほどの人が登った跡を上がることにした。しかし、そのままでは上がれるわけがない。そこで、作戦を立てた。名付けて「親子ガメ作戦」である。まず私が四つん這いになり、私の足に息子の足を乗せ、私の手に息子の手を乗せるのである。何か、カンガルーの親子のようで、誰かに見られたら恥ずかしい光景であっただろうと思ったが、せっかくここまで来て指をくわえて帰るのもしゃくである。
5m程上がると平坦な道がついていた。林業の人が歩く道であろうか。とりあえずそこまで登って様子を見ることにした。前の人が石を捜して掘った跡が、何カ所かに見えた。その人が来られたのは2日程前であるらしく、倒れた草が起きあがりかけているものもある。しかし、注意してみると確かに石を掘った跡のようである。先ほどと同じ格好で今度は逆に下に降りはじめた。息子も災難であったろうと思う。
やっと目的の場所について、ズリを少し削り、平らなところを作って息子をそこに座らせ、二人で採集をはじめた。3歳の息子にはまだ石の見分けはつかないらしくいろんな石を積み上げていたが、30分程で上記の鉱物はほぼ得ることができたので終わることにした。また先ほどと同じ格好で、下まで降りたが、息子の方も少しは楽しめたようであった。
しかし、いくら何でも、それだけでは息子も物足りないだろうと思い、五代松鍾乳洞にも入ってみることにした。入洞料を払い、入ろうとするとボランティアの人であろうか、登山服姿の40歳くらいの女性が案内役をしてくださった。息子は「しょうにゅうど」という言葉を初めて覚え、その中のすごさに感激して、一週間くらいはこの話題を続けて話してくれた。この鍾乳洞はもちろん石灰岩であるが、中はあまり熱変成を受けてはいないようであったが、化石は入っていないと説明をされていた。微化石くらいは出そうに思われるのだがどうだろうか。
あまり遅くならないうちに帰ろうと、朝の11時頃にはここを出発した。3歳の子供には昼寝というものも必要なのだ。私もできるものならしたいが、そんなわけにもいかず、昼寝の時間に合わせようとしたのである。吉野川に到着した頃、ようやく昼寝から起き出してきた息子の腹の虫が訴えを起こしている。そういえば12時である。ここには名物の「柿の葉寿司」がある。サバを柿の葉で包んだ押し寿司だと思ってもらえばよい。(最近は鮭や色々なものが登場している。)慣れないと臭いが気になるが、私は小さい頃から母の手作りの柿の葉寿司を食べていたので全く気にならず、大好きである。
ちなみに我が家でも鮭よりもサバの方が人気で、子どもが先に食べてしまい、私はいつも残った鮭を食べさせられてしまうのであった。