地下鉄 銀座線ストーリー
|
||||||
|
●駅デザインの謎 「赤門」といえば東京大学。これは元加賀藩江戸屋敷の跡ということで、ボクが生まれ育った(今も住んでいるが)石川県でも結構知られている話ではある。 東京地下鉄道はそれぞれの駅に個性を持たせようとデザインに工夫した。最初の開通区間である上野-浅草間では特に凝ったようで、浅草駅には浅草寺を模した出入口がつくられた。これが赤門と呼ばれ、現在の吾妻橋口、4番出口がそれである。
● ● ● 田原町駅のホーム柱と天井の境目には、家紋がズラっと並んでいる。これは浅草六区にちなんで、歌舞伎、新派の家紋をデザインしたものである。開業当時、東京地下鉄道が水谷八重子の家紋を作成しようといたが自信がなく、とうとう本人の自宅まで出掛けて確認したという話も残っている。 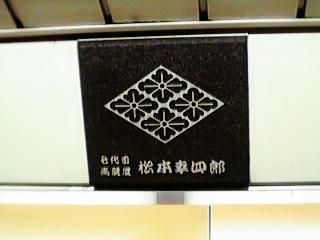
ところが今度は、どれが誰のだか判らなくなってしまったらしい。そこで昭和48年には恥を忍んで(?)田原町駅に身許探しのポスターを貼って協力を求めた結果、大部分が解明出来たのだという。 田原町駅浅草方面行きホームの中程にあった家紋の一つ。松本幸四郎だった。 その他、駅のイメージカラーとしての考え方だが、田原町は薄い青、稲荷町は薄いクリーム、上野はスクラッチタイル貼りと、各駅に個性を持たせていた。 
地下鉄ストアの名残を調べていて、上野−浅草間以外にも凝った装飾があるというのが判った。 神田駅6番出口は、上にあった地下鉄須田町ビルを取り壊したために上半分が新しいが、あとは開業当初の面影をそのまま残している。この壁のタイルを見ても、新しい方(左側)は普通の壁用タイルを貼ってあるのに対し、古い方(右側)はタテ長のタイルとモザイクタイルを色、形、大きさをデザインして貼ってあり、使用材料までも工夫していたことが伺える。 今の建築デザインとはまた違ったものがある。また「…らしさ」などという安直なデザインではなく、担当者の心意気やちょっとした遊び心までもがにじみ出ていると言ってもいいだろう。 新橋までの全通。こんな華やかさとは裏腹に、時代は戦争色がますます濃くなっていきます。太平洋戦争の残した傷痕は地下鉄銀座線にもありました。 次回は戦災についての話です。 【予告】 銀座駅の謎 【参考文献】 鉄道ジャーナル 1974年10月号 特集「日本の心臓 東京の鉄道 第一部」 (株)鉄道ジャーナル社 【協力】 帝都高速度交通営団(現:東京メトロ) 地下鉄博物館 地下鉄互助会(現:メトロ文化財団) このサイトからの文章、写真等内容の無断転載は固くお断り致します。 |
||||||
|
トップへ |


