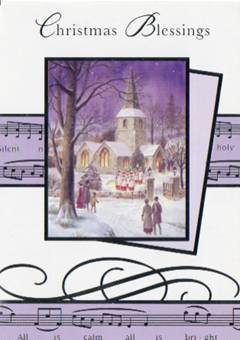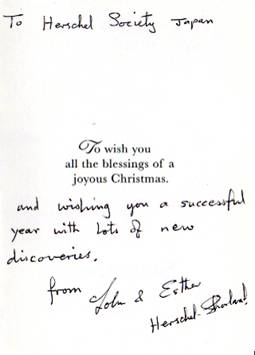�@Letters to Webmaster 2010
���@���@���@�B �@�O���@���̂��тٍ͐e�̍ڂ����uWEB�����v��8���������艺�����܂��Đ��ɂ��肪�Ƃ������܂��B�k�����l ���㌴�厡���́u�R��崓��̑�F���_�ƒn���O�����_�v�ɂ��� �@���{�v�z��n64�w�m�w�@��x�A��g���X�A1976�Ap.463�̓����ɁAWilliam Whiston, Astronomical Lecture, 1728, 2nd ed. �Ƃ����{�̖����������Ă��܂��B�܂��L�◲�����͓��{�v�z��n43�w�x�i����E�R��崓��x�A��g���X�A1973�Ap.199�̓����Ɂu���z�����t�˗ʂɂ��āA�E�B�X�g���́w�V���w�����Ə@���x�ɁA�����Ɠ������l���݂���v�Ə����Ă��܂����A���{��Astronomical Principles of Religion, Natural and Revealed�i���R�@������ь[���@���̓V���w�I�������B�o�ŔN�s���j�ł��낤�Ǝv���܂��B�i�n�Ӑ��Y�Ė�A�wOU�Ȋw�jI�\�F���̒����x�A�n���ЁA1983�Ap.354�j �@�����������u���C�����@�v�i1798�j���ɍڂ����u�����c���v�́A�}�Ƌ��ɑS�������{�v�z��n65�w�m�w�@���x�A��g���X�A1972�Ap.432�ɍڂ��Ă��܂��B ���̈ꕔ�������܂��ƁA �u����i�n�]�������āA�ȑO�������������m�V�������̒��ɁA�O���͑��z�ł���Ƃ��������ڂ��Ă���Ɛ\���܂����B����͂��˂Ď��̉����Ă����l���ƈ�v���A���m�l�����ɓ����l���������Ă��邱�Ƃ��������v���܂����B�܂����̊ԁA������a�k�ɐ��K���ˎ叼�������璉�a�l���炨�肵�������ɍ��̂悤�Ȑ}������A���̐��Z��ςݏd�˂��悤�Ȃ��̂͂��ꂼ�ꒆ�S�ɍP���������ē����Ȃ��l�q��`�������̂Ǝv���܂��B����܂������̐��Ɉ�v���A���悢�掄�̍l���̌��łȂ���(����)���ƈ��S�v���܂����B�v �@�ނ͍X�Ɂu�O���V�ʃj�e�n�A�V�̃n�����z�V�V�@�����̂𐔏\����d�˂�����̃g������ԁA�M�X�L�喳�Ӑ����j�����v�Əq�ׂĂ��܂��B ���u���̌��͂ǂ��ɂ���v�ɂ��� �@p.22�̐}�͒���ɒ��w���_���c�̊ϑ��x�A�P���Ќ����t�A1978�Ap.231�ɂ���܂��BP.23��}�͗�،h�M���A�w�X�Y�L�����}���x�A�P���Ќ����t�A1970�Ap.125�ɂ���܂��B������������̓|�W�Ŕw�i���������猩�₷���ł��B�W�����E�n�[�V�F���̃X�P�b�`�͔��ˋ���p�������߂��}�����Ԃ��ɂȂ��Ă��܂��B�u���̌��v�̃X�P�b�`�́A �@A. Hirshfeld and R. W. Sinnot (eds.), Sky Catalogue 2000.0, vol.2, 1985 p.xlvii�ɁAFish�fs Mouth. Dark nebula. In M42, northeast of the Trapezium, at 5h35m.4, �|5��23���i2000.0�j�FWS2, page34 �@�X�~�X��A Cycle of Celestial Objects �́u�V�̂ЂƏ���v�Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��ł��傤���B ���u���̐ԊO���̉��x����@�v�ɂ��� �@����z��Y�ҁA�w�ߑ�M�w�_�W�x�i�Ȋw�̖���13�j�A�����o�ŎЁA1988�Ƀn�[�V�F���̘_���̖���܂��B �ԊO���̓n�[�V�F���̑O�ɔ��������l�������悤�ł��B �@�㌴���͂��������[���e�[�}�����グ����̂Œ��ڂ��Ă��܂��B���オ�y���݂ł��B�����ɂ͋������̏������A�A���̍����ɂ͂ւ���C���ł��B���炩�������G�����L���܂����B �i�ȏ�A2010�N8��18���t�j �i�ȉ��A�ʕւŒ��Ղ������ւ�ł��j �O�ւɏ����lj������Ă��������܂��B ���n�[�V�F����6�N�O�ɐԊO���������̂́AJames Hutton�i1726�`97�j�ł��B�n�Ӑ��Y�O�f��pp.158�|166�����ĉ������B ���z�C�w���X�̓g���y�W�E���̔����҂ł����A1656�N�A�ނ̕`�����I���I�����_�̃X�P�b�`�i����Ɂ@�O�f��p.229�j�ɂ́u���̌��v�����h�ɕ`����Ă��܂��B ��R.�o�[�i���́A�I���I�����_�̒��S���ɂ��Ă��������Ă��܂��B �@�z�C�w���X�̈�iHuyghenian Region�j�Ƃ��Ēm���钆�S���͔��ɍ��ݓ����Ă���A�\�ʋP�x���������ߍ��{���ł��悭������B���邢�����G�ɋÌ��������܂́u���킵�_�̏o����v���A���H�ifrost-work�F�K���X�ʂɂł��鑚�͗l�j�ŕ`�����͗l�Ɏ��Ă���B���̖��邢�̈�̐^�k�ɂ����Ă����u���̌��v�ƌĂ��Â��ˏo���́A���S��8�����ɂ���ďƂ炳�ꂽM43�Ƃ����藣���ꂽ����_�̎啔���番�����Ă���B�i�ٖ�j �iRobert Burnham, �gBurnham�fs Celestial Handbook.�h Vol.2. p.1324. Dover, 1978�G�ēc����u���S�ȑ厖�T�@�����Łvp.503. �n�l����, 1988�j ��Hutchinson�fs Splendour of the Heavens, 1923, p.553 �ɂ̓n�[�o�[�h�J���b�W�V����Ŋϑ������I���I�����_�̃X�P�b�`������܂��B�����炭�{���h���q�ɂ����̂ł��傤�Bp.890 �ł͎��̂悤�ɏ�����Ă��܂��B �@��{�����o����Γ|�����Ō���ƁA���_�͖��邢�z�C�w���X�̈�i���S���ɗ^����ꂽ���́j����g����ɂ�ĒW���Ȃ��`�Ɍ�����B���Ȃ�̍��{���ł悭�����邱�̗̈�͐��_�̑��̕�����肸���Ƃ������肵�Ă��āA8�Z���`�ȏ�̌��a���ƃ����̂�����̍\���������B�c�Ƃɑ����̂͒������Â������тŁA�����Ƃ��됯�_�̖��邢�������ɑł����܂ꂽ�悤�Ɍ����邪�A�����̐l�͂���͈Í��������������̂ƐM���Ă���B��]�����͂���Ɩ��邢���_�Ƃ̃R���g���X�g�����ۗ������Ă����B����͂����u���̌��v�ƌĂ��B �@���̖��͓̂����̐��N�ɓV���w�ւ̋�����A���t���܂����B�����w�҂�Freeman John Dyson�i1923�|�j���{��������������z���Ă��܂��iDavid W. Swift �ҁA����M���E���������u�F���l�T���̃p�C�I�j�A�����v�A �����o��1992�@p.360�j�B�{���̐}�ł͎R�{�ꐴ�ҁu�}���V���u���v�S8���A�����t�E�P���Ёi1937�`42�j�ɑ����]�ڂ���܂����B �k�����l ����K���e���i1885�|1977�j�͒����Ŏ��̂悤�ɏq�ׂ܂��B �@�S�V�œ���Ɍ����鐯�_�́A�A���h�����_���̗�����启�_�ƁA���̃I���I�����̖���`���_�\�w�҂ɂ���Ă͂�������`���_�ƌĂԁB�������ւA�}���{�[�Ƃ��Ӌ��Ɏ��Ă�܂��\�Ƃ����ł��B�i�u��������v�����Ё@1925�@p.11�j �@�������]���������̐��_�ɋ߂Â��čs���ƒW��������̂₤�Ȗ��邳�����ė��āA����啁i��������j�̂₤�Ȍ��̑���͂�A���̓����Ɏl�d���Ƃ��A�g���y�a�E���i�s���l�ӌ`�j�ƌĂ��`�Ɏl���̐^�������߂����Ă�܂��B���̌`����s��`���_�ƌĂ�A�܂������J���Ă�鋛�ɂ����Ă�邽�߁A���`���_�Ƃ��Ă�܂��B�i�u�V�����߂���@�~�̊��v�����Ё@1947 pp.57�|58�j �@��K���̓I���I�����_�S�̂����`���_�ƌĂ�ł��āA�u���̌��v���z�C�w���X�̈�̌`���痈�Ă��邱�ƂɋC�t���Ă��Ȃ��悤�ł��B �Ȃ����̓I���I�����_�̈��̂́u�������萯�_�ibat nebula�j�v���ӂ��킵���Ǝv���Ă��܂��B ���g�c�����Y���u����Ɍ����鐯�̌����v�x���Ё@1922, p.80��p.81�̊ԂɃI���I�����_�̎ʐ^������܂����A���̗��ɂ� �@�I���I�������̃t�C�Q���X�E��̒������́A���n�����̋����̔`�����ł���B���B�́A��������F���̐[�݂��_�Ԍ���B�}�Ă̑z���͂�����̋�`�����ނ̂��B���T���`�e��₵���s�ςɎ��̐S�͖���B�Ⴆ�A����͈�̋̓�������\�Wࣂ��鐯�_�̓����̐[�݂������邱�Ƃł���B���͋��炭����Ɍ�����ő�̔��ۂ��B����I���̓a�����A���Ɖ~���Ɖ��L�ƃy�[�������g���F���̐[�݂̐[�݂ɍ݂�̂��B�R���^��̋P�����ȂĂ��ꓙ�̑f�ނ͊e�X�ނЂ��Ȃ�����Ȍ������Ă��ł͂Ȃ����B �Ə����Ă���܂��B�ނ͋��̌����u�V��̌��v�ƌ����̂ł��傤�BBarnard�͓V�̐�̎ʐ^������1919�N�A182�̈Í����_�̃J�^���O�\���܂����B �i�ȏ�A2010�N7��27���t�j �i�Ǘ��l���c����I�m�ȏ������肪�Ƃ��������܂��B�O���Ɍf�ڂ����{�V�����Ɓu���̌��v�̘b��Ɋ֘A���āA����Ȃ�ڍׂ��������܂����B�j �@
���@���@���@�B �uWEB�����v��7����L��������܂����B �@�uWEB�����vp.13�̐}��King �̖{��p.208�ɂ���}���A���傤�ǔ��Α����猩���`�ɂȂ��Ă��܂��B�㕔�ɔ��^�ؘ̖g�i�₮��j������A�����Ɋ��Ԃ������ċ����ƕ��t���Ƃ��Ȃ��ł��܂��B�����W.�n�[�V�F����40�C���`�ɂ͂Ȃ��H�v�ł��B����ɂ��Ă��A�o�܋V���ˑ�ialtazimuth stand�j�̖ؑg�݂͂ǂ����Đ��삵���̂ł��傤���B�_�̒�����10���[�g���ȏ゠��܂����A�p���ڂ�������܂���B �@�@�@* " " �@ �u�n�[�V�F���̖]�������v�Ɋւ���㌴���Ƃ̉������ȁA��ւ��[���q�ǂ��܂����B �@�u�t�����X�`�[�h�V���}���v�i�P���ЁA1943�jp.29�ɂ́A���J�C���̓�V���}���ڂ��Ă��܂����A�����ɕ`����Ă���]�������̓w�x���E�X�̎g�����悤�Ȓ���Ȃ��̂ŁA���̏�[�̊��ԂɊ|�����j�Ŏx�����Ă��܂��B�������h�͂��̐V������1763�N�o�ł� Coelum Stelliferum �ɔ��\�����悤�ł��iR.H.Allen, Star Names. Dover, 1963, p.14�j�B �@�V�����͂�������132�Ԑ��̓�P���̕ӂŔ�������܂����i�������B�A�V�����̔����ʒu�A�@�����V���w��s�u�X�e���v��Q���Ap.20�A1991�Q�Ɓj�B�}B�̂��̈ʒu�ɕ�������܂��B�������ēǂ߂܂��A�h�C�c��ŁuURANIA. 1781�N3��13���n�[�V�F���̔��������V�f���v�Ə�����Ă���悤�ł��B�������E���j�A�� Mousai �̈�l�ŁA�V�����i�鏗�_�ł��B����͓V�̒j�_�E���k�X�Ƃ͈Ⴂ�܂��B�{�[�f��1784�N�A�ߋ��̋L�^�ׂāA1690�N12��23���Ƀt�����X�`�[�h���V�������P���ƊԈႦ�āA��������34�Ԑ��Ɩ��t���Ă����i���t�����̂̓������h�ł����j���Ƃ����܂����i�ēc�����u�ߑ�V���w�̖閾���v�A�������V���ЁA1982�Ap.73�Q�Ɓj�B�}H�ɁgHerschel�h�Ƃ���̂�����ł��B �@�~�h���g���u�V���}���v�iJames Middleton, Celestial Atlas, 1843�j�ɂ���u�n�[�V�F���̖]�����v���}F�̂Ɠ����ł��iP. �E�B�b�g�t�B�[���h���A�L���G�s��u�V���}�̗��j�v�A�~���[�W�A���}���A1997�Ap.116�Q�Ɓj�B�Ȃ����̖{��p.112��Samuel Reigh, Urania�fs Mirror, 1823 ����]�ڂ����u������v�̐}������܂��B �@���́u�W���[�W�̋Ձv���R���ɂ��Ĉꕶ�𑐂������Ƃ�����܂��i�u�V�E�vNo.961, p.343, June 2005�j�B���̍ہA���b���u�����̐_�b�v�i�P���ЁA1975�@p.272�j�Ɂu�W���[�W�U���v�Ƃ���̂́u�W���[�W�V���v�̌��ł͂Ȃ����Ə����܂����B����ƐV�����̎R�c�a�r�����uD. J. Warner, The Sky Explored, 1979�v�̒��̃��B�[���V����iEphemerides astronomicae ad meridianum vindobonensem calculis definitae, 1790�F���B�[����ʂ�q�ߐ��Ɋ�Â��Čv�Z�����V�����Z��j��Hell���V�݂��������̕\��� Monumenta aere perenniora inter Astra ponenda: Primum serenissimo Regi Angliae, Georgio III�i���M�ōł����N�ȉp�����W���[�W�V�����i�v�ɋL�O���āA���̊Ԃɒu���j�Ƃ���̂����܂����i�u�V�E�vNo.977�Ap.653�AOct. 2006�j�B���b�������̖{��ǂ�ŁA���̌�̉����łł̓W���[�W�U�����V���ɉ��߂܂����i�u�V�E�vNo,963�Ap.473�AAug. 2005�j�B�R�c���̂��̕��ɑ��鎄�̉́u�V�E�vNo.964�Ap.537�ASept. 2005 �ɂ���܂��B �@�uWEB�����vp.20���̐}������ƁA�u�n�[�V�F���̖]�������v�ɑ����鐯�̓�2, ��3,��4, ��5 Aur, �� Gem �Ȃǂł��邱�Ƃ�������܂��B��1 Aur �͊܂�ł��܂���BCamille Flammarion, Les Étoiles et les CuriositÉs du Ciel�i���X�ƓV��̖����j�AParis, 1882�ɍڂ��Ă��镶�ٖ̐�����ڂɂ����܂��B �@�u��104�}�i���j������ƁA���債����̓��ɔ��Ɋ�Ȍ`�̓V��������̂�F�߂�B����́w�n�[�V�F���̖]������ le Telescope d�fHerschel�x���ŁA�I�[�X�g���A�̓V���w�҃w���_�����A1781�N3��13���V��̂��̗̈�œV�������������ꂽ�̂��L�O���Đݒu�������̂ł���B���ہA���̏����Ȑ��̌Q��́A�������ꂽ����V�������ʉ߂����ӂ�������N�����Ă���B�������A���ׂĂ̓V���w�҂̐S�̒��ɂ���̑�ȃE�B���A���E�n�[�V�F���ւ̎v���o���ǂ�ȂɉX�����A�ǂ�ȂɋM�d�ł��낤�Ƃ��A�V����ɂ��� ����t�����邱�Ƃ͐��}�𗐎G�ɂ������ŁA�����Ė��ɗ����Ȃ��B����̂���ɏ������鐯�X�����債����A�ӂ������A��܂˂����ɕԋp���A���̃f�b�T���������Ă��̊G��P�ɗ��j�I�L�O�i�Ƃ��Ă̂ݍl���邱�Ƃɂ��悤�B�v�ip.162�j �@�u�X�Ɏg���Ă��Ȃ���̐���������B���Ɏx���^���邱�ƂȂ��\�����ꂽ�����Ȑ��X���A�G���_�k�X���̗̈�ɑ��݂���B����͑O�i�u�����f���u���O��│̏ꍇ�j�Ɠ��l�ł���B1789�N�w���_�����p�����W���[�W�V���Ɍh�ӂ�\���āw�W���[�W�̋� le Harpe de Georges�x������邽�߂ɁA�G���_�k�X���Ƃ����������珬�������X�������B���̉��̓E�B���A���E�n�[�V�F����ی삵�A�������A���h���A���Q�����B�����Ă�����A�������h�ƉȊw�̗L�p���Ɗw�҂̎Љ�I���l�ɂ��ĉ�k���A��C��C�e�����鐻�B���ɏ�����C�M���X�|���h���A��]�����̌��݂ɐU�������������悢�g�������ƔF�������B�ނƓ������炢�̗ǎ��������ċc�_����N��͂߂����ɂ��Ȃ��B�������Ȃ���A���̉��̐�������d�Ɏg�p����A�V���ʂɍǂ��ł��邱�Ƃɂ͕ς��͂Ȃ��B�v�ip.513�j �@�k�����l �@��Ԏ����������т�Ă��邤���ɍ��̋G�߂�����Ă��܂����B��炪�x���Ȃ������Ƃ����l�т��܂��B �i2010�N3��24���t�j �i�Ǘ��l���c�i�Ǘ��l���c����I�m�ȏ������肪�Ƃ��������܂��B�O���Ɍf�ڂ����{�V�����Ɓu���̌��v�̘b��Ɋ֘A���āA����Ȃ�ڍׂ��������܂����B�j �����A���J�Ȃ��莆�����肪�Ƃ��������܂��B���������莆�̒��œ��{�l�ƓV�����Ɋւ���L�q�́A�ʍ��̖����Ɂu���v�Ƃ��Čf�ڂ����Ă��������܂����B�j �@
�ё�@�\�z�q �V�o���̓��{�n�[�V�F������WEB������7���������艺���肠�肪�Ƃ��������܂����B������ǂ�2009�N�̑���Ő����Ɋp�c�l�Ɉ��p���ꂽ�������_�@�ɁA����̐V���Ȋ����ւ̔�������Ă���܂��B���͓r������̉���ł������̐��ڂɊ����ʂ̎v���ł��B���N�x����낵�����肢�������܂��B ���āA2��20���`21���ɎD�y�s�̖k����N���u(�ʐ^�͐ᐰ��̉��)�œ����O���琯�D�����W��A�\�L�̂悤�ɂ��Ƃ���14��ڂ̉������܂����B����́g���̊ώ@�A�ϑ��A�V�̎ʐ^�S�ʁA�F���ɂ��ĂȂǁA�V���Ɋւ��邱�ƂȂ牽�ł��h�ƕ��Ђ낭���\�̏�Ƃ��Č𗬂�[�ߍ����l�ވ琬�ƓV�����y���˂炢�ł��B ���͂��Ƃ����̎Q���ł����B���ȏЉ�����˂āA�e�[�}�u�S�V88�����̎����i�v�����W�����Ɖ摜�ɂ�锭�\�̒��ŁA�n�[�V�F�������`�[�t�ɂ��������i�A���p�̃n�[�V�F�������n�[�V�F���q���̏������ƍu������D�y�ł��J�Â������Ɠ��̊����ɂ��Ċ���Љ�����܂����B ��i�͉�����12�����Ɨ��j�I�ȃn�[�V�F���̑召�̖]��������J�����C�������������a���A�ё���V���Ɛт��e�[�}�Ɉ�������i�Ȃ�20���_�ɑ��Ď�������������A����ւ̊S���ƂĂ����������̂͂��ꂵ�����Ƃł����B �������Ԃ��u���Ԃɉ߂����̌�ɋL�O�B�e�A��͐[��3���܂Ŋe�X�����[�����\���������悤�ł��B �Ƃ����̂́A�����ɂ����͓����̑��Q�K���Ɛ���̒��̃h���C�u�ł��̒�����1���߂��ɑގ����܂������A���������ɋ������E�H�b�`���O�̊F����̂��Ɨ����u�₩�ɏW������Ă܂����B���ꂩ����l���܂ȋ@��Ƀn�[�V�F���W�̘b��ł��𗬂��ł��邱�Ƃ�����Ă��܂��B�����ւ�Ӌ`�[���܂��y��������Ԃł����B �@
�@ �i2010�N3��8���@��́j �i�Ǘ��l���c�ё������ŋ߂̊��������������܂����B ���������Ǝ���A�����ăn�[�V�F���̘b��ŁA�k�C���̊�����M���߂����ꂽ�悤�ł��B�n�[�V�F���W�ł̌𗬂��A�܂��܂�����ɂȂ�܂��悤�ɁI�j
�i�Ǘ��l���c�V���[���b�g����͂����N���X�}�X���b�Z�[�W�ɂ��A2009�N�͂����g�₲�Ƒ��Ɍl�I�C�x���g�̑����N�������悤�ł��B���̐��͓I�Ȋ����̈�[�����Ă��Љ�܂��B�j �@�ł��傫�ȏo�����́A7���̃����J���V���[�̏B�c��I���ł����B�c�Ȃ���邽�߉ߍ��ȑI����𑱂�����ɁA�����đI���ʂ����܂����B�c���ł�4�̈ψ���A2�̐R����A2�̃��[�L���O�O���[�v�A2�̊w�Z�����A3�̕]�c��ɑ����A�����Z�����߂����Ă��܂��B �@6���ɂ͎���70�̒a�������j���܂����B����ɂ��Ă��A�����������̊Ԃ�70�ɂȂ����̂�����H 6���̏I���ɂ́A�����É��̉��V��ɏ�����܂����B���̃L���T�����ɓ��s���Ă�������̂ł����A�ޏ����w�o�b�L���K���{�a�܂ł��肢���܂��x�ƃ^�N�V�[�̉^�]��ɗ��ނ̂����Ƃ��͖{���Ƀh�L�b�Ƃ��܂����B����Ȃ��Ƃ��āA����܂Ŗ��ɂ��v��Ȃ��������̂ł�����I �@8���͋c����x�݂Ȃ̂ŁA�F�l�ƃT���N�g�E�y�e���u���O�܂ł̗��ɏo�����܂����B�A���X�e���_���ł̓S�b�z���p�ق�K�ˁA����ɃX�E�F�[�f���A�G�X�g�j�A�̃^�����̒����o�āA�T���N�g�E�y�e���u���O�ցB�ʐ^�Ō�������A���������f���炵���Ƃ���ł����B �@�q���⑷�������݂ȒB�҂ł��B ���̂��莆�������Ă��鍡�A�Ⴊ�͂������~���Ă��܂��B���̂��߁A�B�s�����J���ōs���Ă�������ېłȂ�тɗ\�Z�Ă��������郏�[�L���O�O���[�v�ɏo�Ȃ��邱�Ƃ��ł� �܂���B���������ƁA�Ȃ���w�Ȍ��͎҂̂悤�ɕ������܂����ǁA�F�A�����J���V���[�̐������ǂ��ɂ��������Ǝv���Ă���A�������ʂ̐l�����ł��B���̒��Ԃł��邱�Ƃ����͊������v���܂��B �@���̐�ƃN���X�}�X�J�[�h�������̂��x���Ȃ��������ŁA���̃J�[�h�����茳�ɓ͂��̂��x��Ă��܂������ł����A�ǂ��N���X�}�X�����߂����ɂȂ邱�ƁA������2010�N���f���炵���N�ɂȂ�܂��悤���F�肵�Ă���܂��B �@�i�ȉ��A�y���œY�������j ���N5�Ԗڂ̃n�C���C�g�B5��15���ɁA���̓n�[�V�F���ƃv�����N�F���]�����ł��グ�̂��߁A���[���b�p�̈�p�A�h�C�c�̃_�����V���^�b�g�ɂ��܂����B�ł��グ���̂̓t�����X�̃M�A�i�ōs���܂����B���łɐ��_�̓������ʂ����ŏ��̎ʐ^�������Ă��܂������A����͂ƂĂ��������A�������Y��Ȏ���H�ɂȂ�܂���I �@
�i�ȉ��̓^�b�u����̉��l�W�F�[������̃��b�Z�[�W�̔����ł��B�j �@�N���X�}�X���߂łƂ��������܂��B��N�̃N���X�}�X�́A�o�[�X�ɂ��鎄�̕���̂��Ƃ��̈�ƂƗ[�H�����ɂ��Ċy�����߂����A�N�������Ă�10���܂ł͖��������������̂ł����A���̓��A���̎U�����ɓ]��ō��������܂��Ă��܂��܂����B�v�̃}�C�P��������11�J���O�ɍ���܂������Ƃ�������̏ł��I��������6�T�Ԃ��M�v�X���͂߂āA�ӂ���Ɠ����悤�ɕ�点��܂ŁA�����12�T�Ԃ�������܂����B4���ɂ͌���40�N�̃��r�[�������j�����̂ł����A���̎��̂̂����ŁA�������ւŒ��H������������ōς܂��܂����B �@�}�C�P���̑��͂�����������ǂ��Ȃ�A���Q�h�~�^����A�n�[�V�F������ƃn�[�V�F�������ق̊����A����Ƀo�i�[�_�E���ƃ\�[���Y�x���[�̎��R�ی��̊Ǘ��������肵�āA���ς�炸�Z������炵�Ă��܂��B�q���������F���ꂼ�ꂤ�܂�����Ă��܂��B �@�C�[�X�^�[�ɂ͎o�̃��A���[�Ƌ`�Z�̃��`���[�h�v�w������Ă��܂����B���A���[���q�[�X���[���甭�̂𑗂�����A�������̓��`���[�h���A�b�s���K���ɏZ�ތÂ������̂Ƃ���܂ő���͂��A���̂܂܋߂��ɔ��܂�܂����B�����Ď��̔ӂ̓I�b�N�X�t�H�[�h�ɔ��܂�A�C�M���X�̍������y1000�N�ƃC�M���X�̖]����400�N���L�O����W��������Ă���A�r�ɂ��܂����B �@6���̖��ɂ́A�V�I���E�n�E�X�i�e�[���Y����͂���ŃL���[�E�K�[�f���̌������ɂ���܂��j�Ŗ]����400���N���j���܂����B�}�C�P���͂��̍s���̂��߂ɁA2��̖]�����삵���̂ł����A��������K�����I��萔�J�������A�g�[�}�X�E�n���I�b�g��1609�N�Ɍ����ϑ�����̂Ɏg�����@�ނ𐄒蕜���������̂ł��B9���ɂ̓E�B���{�[���̋߂��ŁA�}�C�P���̌��Q�h�~�^���̒��Ԃ��v���l�^���E����10���l�ڂ̓���҂ɂȂ����̂��j���p�[�e�B�[�ɏo�Ȃ�����A�i�V���i���E�g���X�g�����L����فu�L���O�X�g���E���C�V�[�v�Ŋۈ�����߂����܂����B �@���͂܂��Q�̍����c�ʼn̂��Ă��܂����A�}�C�P���Ƌ��Ƀz���C�g�E�z�[�X�E�I�y���̔M�S�ȃT�|�[�^�[�ł�����܂��B���T���j���ɂ́A�h���V�[�E�n�E�X�E�z�X�s�X�܂Ŋ��҂�����Ԃʼn^�сA�[�H�̒��������Ă��܂����A����W�̊����ɂ��M�S�Ɏ��g��ł��܂��B �@�ǂ����ǂ��N���X�}�X�ƕ����ȐV�N�����}���ɂȂ�܂��悤�ɁB �i�Ǘ��l���c �V���[���b�g����Ƃ����A�^�b�u�v�ȂƂ����A�C�M���X�̏n�N����̊���ɂ͖{���ɋ�������܂��B����͂��Њw�т����_�ł��ˁB �j
�i��f�̃V���[���b�g����Ƃ́u���Ƃ��v�̊W�ɂȂ�A�V���[�����h����i�E�B���A���E�n�[�V�F�����n�̑��ASir William James Herschel �̂���ɑ\���ɂ�����܂��j������A����ĂɈȉ��̂悤�ȃN���X�}�X�J�[�h�Ղ��܂����B�j
�@ |
�@
�@
�@