mori's Page 騒音の対策
2.消音器の考え方
音源(機器)は通常管路で結ばれチャンバ等を介して大気に放射されている。このため様々な音響素子(管路・チャン
バ等)で結ばれた音響回路を構成している。このため消音装置を考える際には音源から大気に放射されるまでの系と
して考える必要がある。(図2)
バ等)で結ばれた音響回路を構成している。このため消音装置を考える際には音源から大気に放射されるまでの系と
して考える必要がある。(図2)
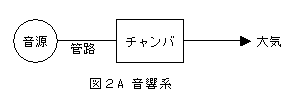
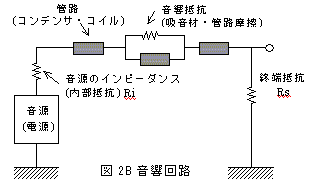
2.1.音源の定義(定速度音源、定音圧音源)
音源内部のインピーダンスは正確には分っていないが、一般に内燃機関のように内部が固い壁で閉じられている系
は、内部インピーダンスが極めて大きいと考えることができる。
は、内部インピーダンスが極めて大きいと考えることができる。
従って、消音器の有無によって音源に負荷されるインピーダンスが変化しても、音源出口の体積速度が変化しないこ
とを意味している。このような音源を定速度音源という。
とを意味している。このような音源を定速度音源という。
また、音源の内部インピーダンスが小さく、負荷されるインピーダンスが変化しても、音源出口の音圧がほとんど変化
しないことを示している。これは広い壁の狭いすき間から音が漏れるような、管路系とは別に大きな孔がある場合など
に相当し、定音圧音源という。
しないことを示している。これは広い壁の狭いすき間から音が漏れるような、管路系とは別に大きな孔がある場合など
に相当し、定音圧音源という。
図3は音源のインピーダンスを電気回路で表したもので、粒子速度を電流、音圧を電圧に置き換えて考えられる。内
部抵抗Riが負荷抵抗より十分大きければ流れる電流値は負荷抵抗Rsによらず一定となる(定速度音源)。またRiが十
分に小さければ負荷にかかる電圧は負荷抵抗の大きさにかかわらず一定の電圧となる(定音圧音源)。
部抵抗Riが負荷抵抗より十分大きければ流れる電流値は負荷抵抗Rsによらず一定となる(定速度音源)。またRiが十
分に小さければ負荷にかかる電圧は負荷抵抗の大きさにかかわらず一定の電圧となる(定音圧音源)。
音源の内部インピーダンスは正確には分かっていないが、図4は各音源の内部インピーダンスを大きい順に並べた
ものである。
ものである。
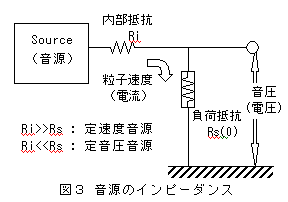
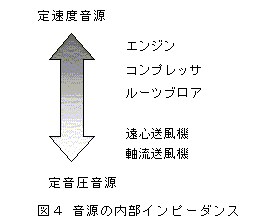
前へ ページの先頭へ 次へ
|

