mori's Page �A�N�e�B�u�T�C�����T�[
�P.�R. �����Ԕr�C����AAC�A�N�e�B�u�T�C�����T�[�ɂ��ጸ
�@��p�Ԃł͔R��������������}���ŁA�����ԗp�r�C�n�̈��͑������A���R�@�ւ̃K�X�����ߒ��ɒ��ډe��
���邽�߁A���̒ጸ�v�������܂��Ă���B�܂��ԗ��̐Ïl���m�ۂ̊ϓ_����A�r�C�������x���̒ጸ���]�܂�Ă�
��B�������Ȃ���r�C�n�ɂ����鈳�͑����̒ጸ�Ɣr�C�������x���̒ጸ�Ƃ͓����I�ɑ������鐫���������A�]����
�������邱�Ƃ�����ł������B
�@��X�͍\�����ȒP�ʼn������ɗD�ꂽ�A�N�e�B�u�f�q�ō\�����ꂽ�����f�q�ł���AAC(Active Acoustic
Conductance)�̎����ԗp�G���W���r�C������ւ̓K�p�����݂��B AAC�̎����ԃG���W���r�C�n�ւ̓K�p�Ɋւ���
�����ׂ��Z�p�ۑ���������邽�߁A���Ԏ�̏�p�Ԃɓ��ڂ��đ��s�������s�����B���̌��ʂ��q�ׂ�B
�EAAC�A�N�e�B�u�T�C�����T�[
�@TCM(Tight-Coupled Monopole)�͐}1a�̂悤�Ƀ}�C�N���z���A������A�����ō\�������B-G(��)�̓}�C�N���z��
�ւ̓��ˉ���������܂ł̓`�B�W���ł���B�Q�C��G��������̎���TCM�̈ʒu�Ɋ��S���˖ʂ��ł���B�ǘH
���̉����P�������f���ŕ\�������ꍇ�A�i�s�g�A��i�g�ɂ��ău���b�N�}�ŕ\���Ɛ}1b�ƂȂ�B����Ɋ�Â��A��
�H���̉����A�̐ϑ��x�ɂ��Ẳ����l�[�q�萔�����߂��
�ƂȂ�A�����ŁAY=2G(��)/Z�AZ�͊ǘH���̓����C���s�[�_���X�ł���B���Ȃ킿�ATCM�͐}1c�̂悤�ȃA�h�~�^���X�œ�
���I�ɕ\����A�Q�C��(G)�������̏ꍇ�͏��R���_�N�^���X�ƂȂ�B�����Active Acoustic Conductance(AAC)�ƌĂԁB
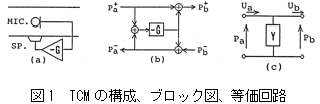 |
���R���_�N�^���X�ł���AAC��}�Q�̂悤�Ɋg�����ɓK�ɔz�u����Ɗg�����̏������ʂ����P�ł���B�}�R�͊g����
��AAC��z�u�����ꍇ�̏��������iTransmission Loss�j�Ŋg����������1/3�̈ʒu�ɔz�u���邱�Ƃɂ��Q�C����������
�Ă��g���^������̏������ʂ̒J�Ԃ������Ƃ��ł���B
�}�R�̓Q�C�����P�̏ꍇ�ł��邪�AAAC�̃Q�C���𑝂����Ƃɂ��A�L�����g���ш�ŕ��R�ȏ���������������B
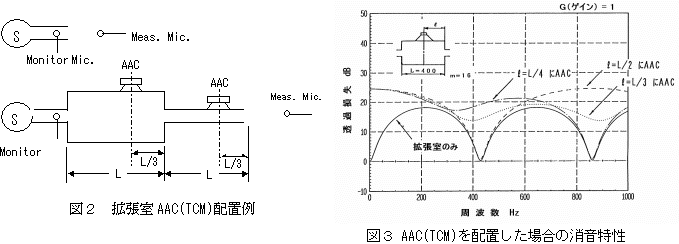
�E�r�C�����n�̉�������
�R.�P. �r�C�����n�̍\��
�}�S�Ɉ�ʓI�ȏ�p�Ԃ̔r�C�����n�������B
�G���W���r�C�͐G�}���o�āA�Z���^�[�}�t���[�A���A�}�t���[�ŏ�������e�[���`���[�u����r�o�����B
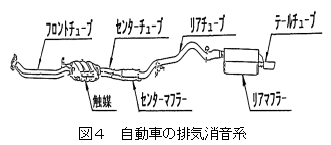 |
�r�C�V�X�e���ł͎�ȏ����f�q�ł��郊�A�}�t���[��AAC�g���^������𓋍ڂ���B�@�]���̃��A�}�t���[�͐}�T�Ɏ�
���悤�ɑ��i�g���A����ō\�����ꕡ�G�ȊǘH��r�C�K�X���������Ă���B�}�U��AAC�ō\������AAC�g���^����
��ŏ]���̃}�t���[�Ɠ����傫���ł��邪���H�͒����ŃX���[�X�ɔr�C�K�X�������\���ƂȂ��Ă���B
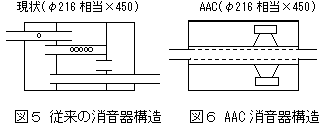 |
�R.�Q. AAC������̏�������
�{�����ł̓X�y�[�X�̖�肪����AAAC������͊g�����{�̂ɂ̂ݐݒu����B
�}�V�̓G���W���V�~�����[�^�Ōv�������r�C�Ǐo���ł̏]���^�}�t���[��AAC������Ƃ̓f�o�r�C���̔�r����������
�̂ł���B AAC�̃Q�C���͔��U���N�����Ȃ��P�ł��邪�A���������͑S�ш�ɂ����ď]���^�Ƃقړ����̏������\��
�L���A���������ɔ��AAC�̓G���W����]���ɉ����Ĕr�C�������x���͂قڔ�Ⴕ�ω�����B�@�����g���тɂ�
���Ă͏]���^��傫��������������������Ă���B�i�����F�V�����_�e��2000CC, 6�C��, 4�T�C�N��, 300���j�@
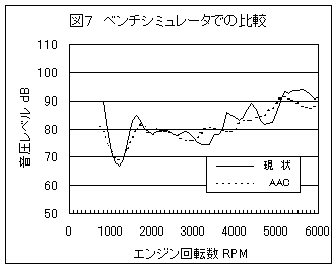 |
�EAAC������𓋍ڂ���ɂ������Ă̋Z�p�ۑ�Ƃ��̑�
�\�P��AAC��������Ԃɓ��ڂ���ɂ������Ẳ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Z�p�I�ȉۑ�Ƒ�Ă������B
�}�W�͏���������̊e�����ʼn��x�A�����A�����������Ă���B
| |
|
| |
|
| �ő�170dB�ȏ�ɂ�����ԎQ�Ɠ��͗p�}�C�N���z���̍\���Ə����p�X�s�[�J | �s�̈��d�f�q�𗘗p�����}�C�N���z������ё�U���E�[�n�̗̍p |
| �ō�200m/s�ɒB����ǘH���̐È��ɂ��X�s�[�J�ւ��e�� | �e�[���`���[�u�̌a�����X�Ɋg�剻���邱�Ƃɂ��g�������̐È��̃R���g���[�� |
| �ō��K�X���x550���ɑς�����}�C�N���z���ƃX�s�[�J | �f�M�ނ̓K�Ȕz�u�Ɨ�p�����̉��P�i�r�C�ǂ�➑̂Ƃ��M�I�����j |
| �}���ȃG���W����]�ω��ɂ����鐧�� | AAC�͊�{�I�ɒǏ]���ɖ��͂Ȃ� |
| �V�X�e���̌o�ϐ� | ��{�I�ɐ���n���ȒP�ł��邽�߈��� |
| ������̌`��E�z�u�̐��� | ����̃��C���}�t���[�̗e�ς�ύX������AAC������ɒu�������� |
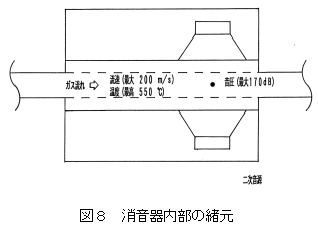
�E���Ԃւ̓K�p
�T.�P. �d�l�A���@�E�`��
AAC������̓X�y�[�X�I�Ȑ����茻��̃��A�}�t���[�Ɠ��l�̐��@�Ƃ���B
�\�Q�Ɏ����Ɏg�p���������Ԃ̃G���W���������A�\�R�ɔr�C�n�̊e�����������B
�}�X�Ɏ����Ԃɓ��ڂ���Ă��錻�s�̃��A�}�t���[�Ǝ����Ɏg�p����AAC������������B
�}�P�O��AAC������𓋍ڂ��������p�̏�p�ԂŁA�}�P�P�ɓ��ڂ����������B
�}�P�Q��AAC������̓����\���ł���B
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|||
| |
|
||
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
||
| |
|
||
| |
|
||
| |
|
||
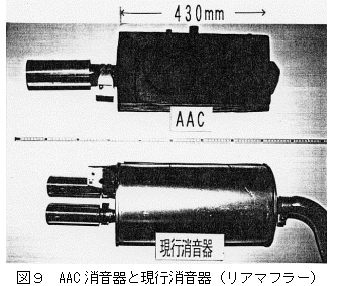 |
||
 |
||
 |
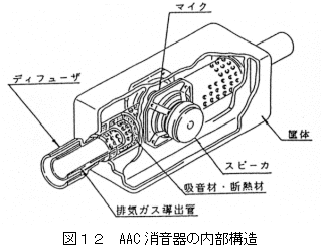 |
�T.�Q. ����
�����͊Ǔ�����170dB�������o���邱�Ƃ������ł��邪�A�\�S�Ɏ����悤�Ȏs�̂̃X�s�[�J�[�i�E�[�n�[�j���Q��
�g�p���邱�Ƃʼn\�ł������B�܂��A�X�s�[�J�[�R�[�������ŏo���Ă��邽�ߑϔM�I�ɂ͌�ɏq�ׂ���@�ɂ��Ώ���
��B
| |
||
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
�[���G���W���̃E�I�[�~���O�A�b�v���s������A�A�C�h�����O��]������6000rpm�܂ŘA��80�b�Ԃ̉���������������
��}�P�S�Ɏ����B
�}�P�R�͑���ʒu�������B
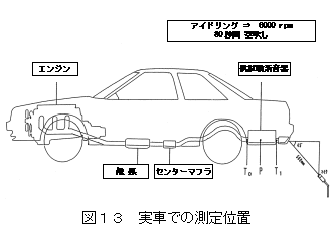
�}�P�T�͔��U�킸AAC�̃Q�C���𑝂����߈ʑ����������P���邽�߂̕⏞��H��t�������Ƃ��̔r�C���̉���
���x���ŁA�L�����g���ш�ɂ�����2�`10dB�̉��P���ʂ�����ꂽ�B
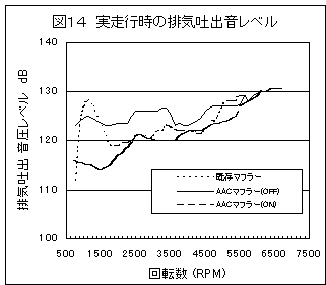 |
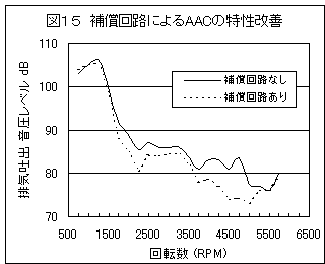 |
�T.�S. �r�C��R�ƐÈ�
�E�r�C��R�̌y��
�}�P�U�Ɍ��A�}�t���[��AAC������̔r�C��R�𑪒肵�����ʂ������B
����}�t���[�̓X�|�[�e�B�ȎԂƐÏl�����K�v�ȍ����Ԃō\�����قȂ邽�ߔr�C��R���傫���Ⴄ�B
�\�T�͂Q��ނ̏�p�Ԃ�AAC�����t�����Ƃ��̌���}�t���[�Ɣr�C��R�̔�r�������B�i�l�͊Ǔ�����60m/s���j
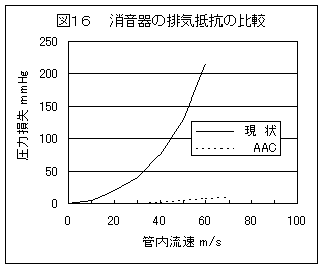
����̎����ł�2000CC�N���X�̍�����p�Ԃ̏ꍇAAC������Ɏ��ւ��邱�Ƃɂ��5�����x�̔n�̓A�b�v���}��
��B
��B
| |
||
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
���Ǔ����� 60m/s��
|
||
(2) �Q�ƃ}�C�N���z���Ɠ����ɑ���È��̉e��
����������ł͐}�P�V�Ɏ����悤�ɏ�����Ɣr�C���ł̖��C��R�ƒf�ʕω��ɂ�闬�̒�R���������A�����ƃZ���T�[���ɐÈ��������B���̐È����傫���Ȃ�ƃZ���T�[��X�s�[�J�[�̖ʂ����������A����ȐM�����̎�ł���
���A�܂��X�s�[�J�[���特������������ɂȂ�Ȃǂ̖�肪��������B
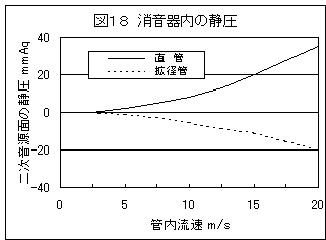
���̖����������邽�߁A�}�P�V�Ɏ����悤�ɏ�����o���̔r�C�ǁi�e�[���p�C�v�j�����X�Ɋg�債�ă��b�p��ɂ��邱
�Ƃɂ�����������̐È����R���g���[�����邱�Ƃ��o����B �}�P�W�͊e�����ɂ����ăe�[���p�C�v�����ǂ̏ꍇ�ƃ�
�b�p��ɂ����ꍇ�̓����ʂł̐È������������̂ł���B�e�[���p�C�v�̊nja�����ɉ����È������̕����Ɍ�
�������Ƃ�������B
�Ƃɂ�����������̐È����R���g���[�����邱�Ƃ��o����B �}�P�W�͊e�����ɂ����ăe�[���p�C�v�����ǂ̏ꍇ�ƃ�
�b�p��ɂ����ꍇ�̓����ʂł̐È������������̂ł���B�e�[���p�C�v�̊nja�����ɉ����È������̕����Ɍ�
�������Ƃ�������B
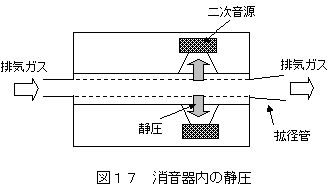 |
�T.�T. �ϔM
�G���W���̔r�C���x�͍ő��550���ɂ��B����B�s�̂���Ă�������i�X�s�[�J�[���j�Ɖ����Z���T�[�͂��̂悤��
�����ɑς�����̂͏��Ȃ��B�܂��������Ƃ��Ă������ŏ�p�Ԃɂ͎g�p�ł��Ȃ��B�@���̂��ߐ}�P�X�Ɏ����悤�ɁA
�@�����A�Z���T�[�Ɣr�C�ǂ͋z���E�f�M�ނŎՕ����M�ɒ��ڂ��炳��Ȃ��\���Ƃ���B
�A�r�C�ǂƏ�����O����уX�s�[�J�[�̎��t�����͒f�M�ނŎՒf���A�M���`���Ȃ��\���Ƃ���B
�B�X�s�[�J�[�ʂ͑ϔM�h���ŕ����B
�ȏ�ɂ��O�͊O�C�ŗ�p����邽�߉��x�͏オ�炸�B���ʓI�ɓ�����Z���T���ł͊ǘH���ɔ�ב傫����
�x���ቺ���Ă���B�@
�}�Q�O�͎Ԃ��~������ԂŃG���W���o�͂��グ�e���̉��x�𑪒肵�����ʂł���B�f�M�ɂ����ʂŊǘH���ɔ��
�X�s�[�J�[���ʼn��x���ቺ���Ă��鎖��������B���s���ɂ͏�����O����p����邽�߁A��p�����͑����ƍl��
��B
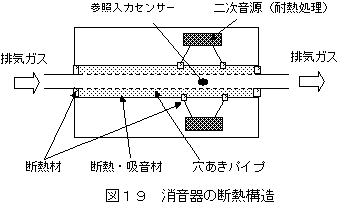 |
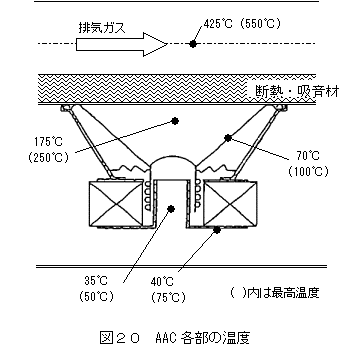
�E������
�{�����͎s�̂̐��i�i�����Z���T�[�A�X�s�[�J�[�j���g�p���A���Ԏ�̏�p�Ԃɓ��ڂ��Ĉ�ʓ��A�������H�A�R�x�H
�ɂ����đ��s�������s���[���ȏ������\���BAAC�����V�X�e���͐���n���̏Ⴕ���ꍇ�ł��A�V�X�e���̖\��
�͂Ȃ��A�������_���p�[�Ƃ��ē���������x�̏������ʂ��ێ��o����B
��p�Ԃ͑ϋv�⏞�ʂȂǑ�ώd�l���������A�܂��R�X�g�ʂɂ��Ă�����������10�{�ȏ�̉��i�ł���A�c�O�Ȃ�
����p�ɂ͋����Ă��Ȃ��B
�����Ԃɂ����ăA�N�e�B�u�T�C�����T�[�͎Ԏ��ɑ��ĕt���I�Ɏg�p����Ă���ɂ������A�{���̔R������O����
���鑛���ጸ�ɑ��Ă͎�������Ă��Ȃ��B����r�C�n�ւ̎��p�ɂ��ẮA�Z�p�I�A�o�ϐ��Ȃǎ�X�ȖʂŊJ��
�������K�v�ł���B
�E�ӎ�
���̌������s���ɂ�����A�����e������ �����E���喼�_�����ł��� �� ���e�m��搶�Ɋw��I�E���_�I�ɑ�ς���
�b�ɂȂ�A�܂��AAAC�̊�b��͂�Z�p�ɂ��Ď�s��w�����̑������������n�߁A������w�@���ł������X���B
�Ǝ��A���������A�ߓ��k�K���ɂ����_�I�Ȗʂŋ��͒������Ӓv���܂��B�܂����Ԃɓ��ڂ��Ă̎����ɂ��܂��ăJ��
�\�j�b�N���i���J���\�j�b�N�E�J���Z�C���j�̒|�X�Njv���A�����������A���n�W���ɕ��X�Ȃ�ʂ����͂܂������Ƃ�
���Ӓv���܂��B
�E�Q�l����
(1)�u�����̖��������m�|�[���ɂ��ǘH�n�����̃A�N�e�B�u�R���g���[���v �A���� �������A���{�����w��u���_��
�W�A1989.3�@
(2)�u���������m�|�[����p�����g���^������̓������P�v�A�X ��x���A���{�����w��u���_���W�A1989.3�@
(3) �u�ǘH�n�����̖������^�A�N�e�B�u�R���g���[���v�A�X�� �B�Ƒ��A���{�����w��u���_���W�A1989.10�@
(4)�gActive Noise Contorol in A Duct Using Active Acoustic Conductances�h, M.Taki & T.Mori Proc. Of Inter-Noise 90,
1990
1990
(5)�u�����Ԕr�C�n�ւ�AAC������̓K�p�v�A�|�X �Njv���A���{��������H�w��u���_���W 1991.9
(6)�u�����ԗp�r�C�n�̊g���^AAC�A�N�e�B�u�����V�X�e���̊J���v�A�X ��x���A���{��������H�w��u���_���W�A
1992.9
1992.9
(7)�gAprication of AAC Silencer to Reduce Automobile Exhaust Noise�h, , Takuji Mori "Niichi Nishiwaki , Proc. Of Inter-Noise
91, 1991.11
91, 1991.11
�O�� �y�[�W�̐擪�� ����
|
|

