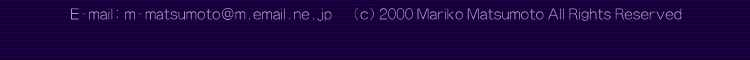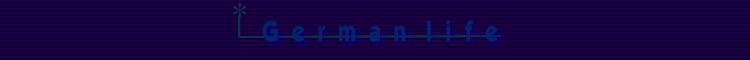

*
音楽の国ドイツとフラメンコ (後編)*
- ドイツ在住中のれぽ〜と 98年11月
-
レナーテのレッスンの初日に、身長が180cmはある大柄な女性が話しかけてきた。
「あなた日本人? 名前は何ていうの?」
「まりこっていうの。日本人よ。でも”マリ”って呼んでね。以前、スペインにフラ メンコ留学に行った時に、スペイン人の先生に名前を聞かれてね。“ソイ マリコ(まりこです。)”って言ったら、そばでそれを聞いていたスペイン人の男の子達が
“おい、聞いたか。あいつマリコン(オカマ)だってよ。笑っちゃうぜ。わっはっはっ。”って笑い者にされたことがあるのよ。(スペイン人は確かに陽気で親切だけ
ど、時として尻のひとつでも叩きたくなるような礼儀知らずな人もいる。) このスタジオにも、スペイン人が習いに来
てるんでしょ? お願いだから、“マリ”って呼んでね。」 …そういえば、フラメンコ留学していた日本人男性で“コウジュン”という名前の人 がいて、その名はカターニャ語(バルセロナ地方の言語)で男性の“オチ○チ○”をさすので、スペイン入国のパスポートコントロールでは笑い者にされ、スペインでは本名を使えないという気の毒な人もいたっけ------------------------------
自分の名前で話は盛り上がり、そしてマンハイムのスタジオを見つけるまでのエピソードを語った。
「レナーテのレッスンは最高にいいんだけど、家から遠すぎるのが残念ね。フランク フルトから2時間以上もかけて電車で来るのは、すごく疲れるの。」
「たしか、パトリシアがフランクフルトから車で来ているはずだから、彼女の車に乗せてもらったら?車だったら電車よりも早いし、安いしね。私が頼んであげるわ。」
と言って、すぐパトリシアの所に行って私を紹介してくれた。とても親切な女性だ。
この日以来、パトリシアがいる時は彼女の車でフランクフルトに帰れることになった。その当時、私はドイツ語がほとんどしゃべれなかったので、よって会話は英語となった。だからといって、お互い流ちょうに英語が操れるわけでもなかったので、コミュニケーションをはかるのに、かなり苦労をした。自己紹介や簡単な日常会話くらいはしゃべれても、それ以上のことを語ることが出来ない。そのせいもあってか、
レッスンの後に「お茶でも飲みにいかない?」と誘っても、きっぱりと断られ、ひどく落ち込んだこともあった。
ドイツに限らずヨーロッパでは、プライベートな時間がとても重要で、約束なしの 「ちょっとお茶でも」は日本のように通用しない。特にドイツでは、学生を除いて、
女友達だけで食事や旅行をするという慣習が日本ほどない。集団で行動をし、仲間意識の強い日本人にとって、こういう環境は疎外感と孤独を味わうことになる。まあ、
慣れてくると逆にこっちの方が楽になってくるから不思議でもあるが。
もちろん、親しくなれば話は別。今では、「寿司を食べに行こう。」「泊まりにお いで。」と誘ってくれる。これから外国に行かれる方、現地の生活を十分に楽しみた
いのなら、どんなに難しくても、現地の言語を使うことをオススメします。
本題がそれてしまった。元に戻ろう。
レナーテのレッスンは、日本のレッスンとは違って同じパートの振付を数カ月かけて何度も繰り返してやるので、少し退屈になってきた。ドイツ人はなかなか振付を覚えないの
で、新しいパートに進めないからだ。 日本人は物まね上手
だから、先生に教えられた振付を覚えるのは早い。とっくに覚えた振付を何度も練習していると、(えー、今日もまたこれを練習するの?)と、フラメンコ熱も次第に冷めてきた。
そんなある時、レナーテのスタジオでティモという“ブレリアス”(お祭りには欠かせない最もジプシー的な踊り)で有名なスペイン人のワークショップ(短期間に1曲の振付を教える講座)があり私も含めて多くのドイツ人が受講した。レナーテのスタジオは、定期的にスペイン人のワークショップがあるので(しかもかなり安い) ドイツならではの特典だろう。
ワークショップ中級クラス3日目の、まだほとんどの人が振付を覚えていない時に、 ティモが突然クワドロ形式で一人づつ踊ろうと言い出した。《クワドロ形式とは、
舞台の後ろにグループ全員が並んで立ってパルマ(手拍子)を叩きながら、一人づつ舞台の中央に出てきて自分の踊りを披露すること》
(えっ、まだ早すぎるよ。大丈夫なのかなぁ、、、) しかし、それはいらぬ心配だった。
物まね上手な私は、ティモに教えられた振付を一つも間違えずに忠実に踊ったのに対して、ドイツ人のほとんどが“ブレリアス”のリズムをはずすことなく(これが重要なのだ)ティモの振付をアレンジしたり、自分の“ブレリアス”を披露したのだ。
それも、実に堂々と、楽しそうに!
本来“ブレリアス”は即興で踊る曲なので、大切なリズムさえおさえておけば、あとは自分の心の欲するまま楽しく踊ったらいい曲である。私はそんなことにも気付か
ずに、ただ与えられた振付を表面的に踊っていたのだ。この時、クラスで一番“ブレ リアス”を踊れると思っていた自分が、実をいうと一番フラメンコを理解していなかった、という事実に気付かされた。
ショックでありながら、しかしフラメンコの違う世界の扉を見つけることが出来た喜びと、それと同時に自分の世界が広がっていくのを実感できたワークショップだった。
音楽の国ドイツに大きな夢を膨らませて来てみれば、最初は期待していたそれとはかなり違っていた。そのような印象があまりにも強烈だったので、ドイツ人の多くはリズム感が悪いと勝手に勘違いしていた。確かに、振付を覚えるのにはかなり時間が
かかるが、本当は、それはフラメンコのリズムを覚える為の重要なレッスンであったのだ。そんなことにずっと気付かなかった自分を情けなく感じる。
「リズム感の悪いドイツ人」というレッテルを貼り、そしてその偏見は、ドイツ人 のもつ個性的ですばらしい面を発見するのに大きな障害になってしまった。
自分が目にしたごく一面だけで、その全てを判断してはいけないと反省している。 フラメンコを通して、ヨーロッパの文化や考え方に刺激され、偏りのない国際人になりたいと願っている。
オレ、フラメンコ!
後日附記(日本帰国後)
日本にもひどいリズム感の人が存在することを発見した。日本人もドイツ人も、そう差はないような気がする。
日本人は、自分のリズム感が悪くて他人に迷惑をかけると感じた時点で、習うのをやめてしまう。しかし、ドイツ人は自分のリズム感が悪くて他人に迷惑をかけると感じても、他人の目を意識しないし、先生にどんなに怒られてもあまり気にしない。
だからへこたれずに習い続けるのである。
これが、 日本人とドイツ人の違いだろう。