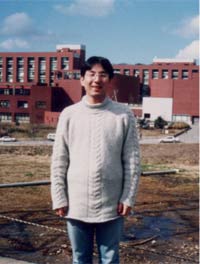−角間移転前後のこと− 1991年入学 Vn 岩井大典 90年代前半のコメントがないから書いてくれと、大先輩Tp中西氏(同じ電情の畑研だったのには驚いた)になにか書くことないかと言われ10年前のことを思い出してみました。 91年4月に入学し卒業したのが97年3月、金大フィルが角間に移転したのが、94年春だったので今思えば城内の大練生活と角間への通い生活をちょうど3年ずつ経験できた珍しい世代だったのかもしれません。比較するに及ばず、城内の生活は音楽に浸ることができる最高の環境にあったと思います。 柱は邪魔だったがフルオケが十分入るだけの広い大練習場、管分奏がちょうどできる程度の中練習場兼金管楽器置き場、カルテットやバイオリンのパート練習用の小練習場、団員のたまり場のオケ部室とこれらがほぼ金大フィルに独占使用権が与えられていたことは角間との違いを語る上で十分ではないかと思います。その他にも、大練習場の裏口には楽器庫と呼ばれる細長い通路、小練の並びにあった落語研究会や琴尺八部の和室もいなければ使えるという練習場所にはピークと言われている160名の団員が在籍した1993年であっても事欠くことはありませんでした。  特に夜の楽器庫は除湿機のせいかほのかに暖かく、さらにコンクリートで囲まれた通路のため非常に響くので、岩井のお気に入りの場所でした。先輩方が残してくれた、数々のコンチェルトの楽譜を取り出してきては弾けないなりに音符を追いかけ、うまくなったかのような錯覚に酔うという楽しみも覚えました。楽器庫で練習していると、楽器をとりにきた同僚が、プルトすっかとか カルテット(麻雀)すっか とか、飲みに行くか とか声をかけてくれいろいろな誘惑もありました。もう一つのお気に入りの場所は、大練の上の食堂の上にあった屋上です。柵があったのですが、バイオリンをもって乗り越えると、そこは誰からも見られない貸し切りの屋外練習場になりました。 ウダツ山がはっきり目の前に広がり、天気のよい日は内灘の海まで見渡せました。思い出の風景だったのですが、写真にとっておけなかったのが残念でなりません。 こんな感じだったので、本業の大学の勉強はといえば、3年までは出席のためだけ顔を出す程度でした。とはいえ、不可をとったのは体育の1個(さすがに行かなすぎた)だけで残り9割『可』で留年もせず進級できたのは要領がよかったのかもしれません。お父さんお母さんごめんなさい。そしてありがとう。 まんまとオケにはまってしまった私は計11回の演奏会にのせてもらいましたが、一番印象に残った演奏会はと聞かれたら、迷わず大学3年の定期にやったラフマニノフ交響曲第2番を答えます。 当時PLだった私は選曲委員?として選曲に関わっていましたが、ラフマニノフ交響曲第2番なんて知りませんでした。正直な話、ピアコンの2番以外ラフマニノフの曲なんて聞いたことなかったし、対抗馬にあがっていたショスタコの5番がどうしてもやりたかったので、あーでもない、こーでもない、と悪あがきましたが、選曲総会ではあっさりラフマニノフに決まってしまいました。  やってみるとおもしろいのなんの、あっさり曲の魅力にとりつかれてしまいました。これでもかと同じ旋律を何度も何度も弾かされるのですが、同じ旋律の繰り返しって意味があるのですよね。4楽章通して真剣に弾くと何とも言えない疲労というか満足感というかに満たされ選曲が決まってから定演までの半年強の間ラフマニノフの世界に浸りきって楽しむことができました。 ← ラフマニノフのステージより 1stVn 1994.1.22平均年齢は22を越えた?  指揮の小松先生も当時の金大フィルとしてはかなりインパクトを与えいただき、いい意味で緊張を本番まで持ち続けることができたのではないかと思います。はじめて来沢され指揮をされたとき、上から下まで真っ黒の装いで、頭もピシッとセットし、威圧感さえ感じさせる張り詰めた空気のなか全曲を止めずに、ほとんど無言で指揮をされた練習の時のことは今でも覚えています。まじめな顔でオープニングのオベロンを振られる前に、「妖精の国のお話」とボソッと言われたのを覚えています。 指揮の小松先生も当時の金大フィルとしてはかなりインパクトを与えいただき、いい意味で緊張を本番まで持ち続けることができたのではないかと思います。はじめて来沢され指揮をされたとき、上から下まで真っ黒の装いで、頭もピシッとセットし、威圧感さえ感じさせる張り詰めた空気のなか全曲を止めずに、ほとんど無言で指揮をされた練習の時のことは今でも覚えています。まじめな顔でオープニングのオベロンを振られる前に、「妖精の国のお話」とボソッと言われたのを覚えています。今思い出しても、その時のバイオリンのレベルはけっこう高かったですね。さらにかなり個性的な人ばかりでした。(当時を知っている人は誰も反論しないでしょう) 我々の世代が金大フィルの時のことを思い出す時、豊精園という焼き鳥屋を思い出さない人はいないだろう。 誰が探してきたのか豊精園という長町にあった焼き鳥屋にみなが入れ替わり毎日のようにオケ面子でカウンターがうまっている。なぜかマスターが手品好きだったりする。(もう閉店してしまったようで残念)たいていは、オケのあいつはどーだとかハイフェッツはどうだとか、どうでもよい話をしているわけだが、厚揚げと生ビールで何時間も時間を費やした時間は無駄ではなかったと思う。 練習が終わってすぐに飲みにいける、飲んだ後も部室に戻りくだらない話を繰り返すことができる。これって大学オケに必要なことだと思うのです。 角間になって一番変わったなと思うのが人との付き合いが希薄になってきているではないかってことです。
と、今思い出しても角間に関して良い思いでは少ないです。そういう意味で、今現役でオーケストラの運営をされている方の苦労は相当なものだろうと察します。 私自身金大フィルの将来を心配していたのですが、卒業した次の年に聞きに行った58回定期の第9は本当に良い演奏だったと思いました。角間という環境に負けてしまうのでは案じていた自分は嬉しかったです。 (特にバイオリンをまとめてくれていた唐木・荒木には感謝です)
最終更新 2002/4/13 |