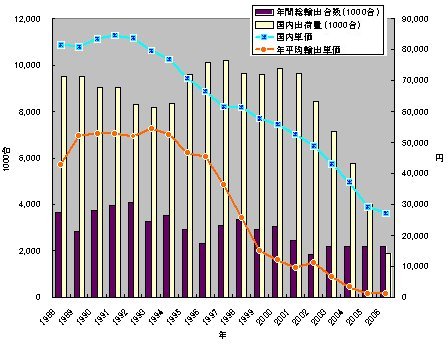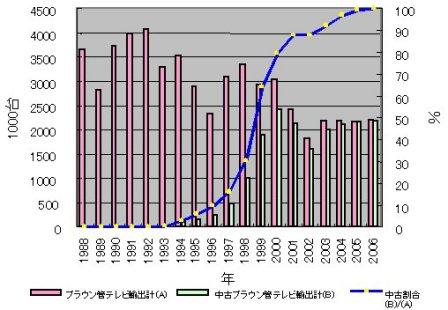ピコ通信/第112号
目次 |
|
杉並病損害賠償訴訟
あまりにも理不尽な判決内容 小椋和子(ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議) 去る9月12日に、杉並病の被害者の一人が東京都を相手に約1億円の損害賠償を求めた裁判の判決が、東京地裁でありました。 9月12日付新聞報道によると「東京地裁は12日、一部の体調不良に対する都の責任を認め、約128万円の賠償を命じた。女性側は「施設からの排気などが原因で化学物質過敏症になった」と主張したが、矢尾渉裁判長は「自覚症状は心因的な疑いが強く、過敏症とは認められない」と判断。都が健康被害の原因と認める「排水中の硫化水素」で生じた頭痛や腹痛などの体調不良について、都の過失を認定した。判決によると、施設は1996年2月から試験運転、4月から操業。約100メートル離れた集合住宅に住んでいた女性は、直後から呼吸困難やけいれんなどに苦しんだ」 この判決のあまりにも理不尽な内容に驚き呆れ、それでもなんとか記しておきたいと思い、感想を述べたいと思います。 ■検出された物質は数百におよぶ 杉並病に関しては、私たちが知る限り重症・軽症あわせて数百人のオーダーの被害者がいます。そのなかでたった一人が提訴したことは、事実を知らない人から見ると理解しにくいことだと思います。そこが地域で起きた公害事件の共通の問題ですが、今となってはそのことを詮索するのは困難です。 東京都との公害調停が不調に終わり、18人の被害者が1997年に公害等調整委員会に対して原因裁定を申請しました。2002年6月26日に下された裁定の結果、被害と杉並中継所から排出された化学物質との因果関係が、化学物質を特定せずに認められました(ピコ通信第107号参照)。 検出された物質は数百にも及び、物質名が判明したものも200種以上を超えます。そのほかに、東京都や区が行った分析方法で検出できない物質もおそらく数多くあったことが推定されます。 ■画期的であった裁定委員会の意見 裁定委員会が最後に述べた意見を参考に記します。 「本件は、特定できない化学物質が健康被害の原因であると主張されたケースである。ところで、この化学物質の数は2千数百万にも達し、その圧倒的多数の物質については、毒性をはじめとする特性は未知の状態にあると言われている。このような状況のもとにおいて、健康被害が特定の化学物質によるとの主張、立証を厳格に求めるとすれば、それは不可能を強いることになるといわざるを得ない。本裁定は、原因物質の特定が出来ないケースにおいても因果関係を肯定することができる場合があるとしたものであるが、今後、化学物質の解明が進展し、これが被害の救済に繋がることを強く期待するものである」。 この公調委の裁定は非常に画期的で、化学物質による被害に光を与えたと感激したものです。しかし、残念ながら、被害を受けた時期が稼働年の8月までと限られました。その原因は、被害調査を行った行政の取り扱いに欺瞞があり、偽りの報告が一人歩きした結果です(これについてのいきさつは、ピコ通信107号参照)。 被害はなくなるどころか、被害を受けた人は転地をしても後遺症に悩まされています。一方、引き続き在住している人や転入してきた人は、中継所が不燃ゴミの圧縮作業を続けているために未だに被害が持続しているのです。 提訴した被害者は、稼働年の7月に現地にとどまることが出来ず、転々とした結果、故郷に帰られて治療に励んでいますが、体調は回復していません。 ■裁判所の判断の問題点 判決内容を読む限り、被告・東京都の言い分がそのまま認められたように思いました。私が注目した主な要点は、以下の3点です。
まず、最初の硫化水素説について反論します。東京都は石原都知事が2003年3月に硫化水素説をかかげて謝罪し、賠償を約束しました。その理由は、排水処理をせずに下水管に排水したために、所内に溜まっていた汚水から発生した硫化水素が下水管から周囲に漏れ、被害を発生させたというものです。 この筋書きは、多くの被害者が判明しているにもかかわらず、保健所への少数の有訴者のみを健康不調者と位置づけ、訴えのピークが7月であり、下水の放流を取り止めた時期と一致させるというからくりをでっちあげるためです。 東京都の謝罪に従って6人が申し出ましたが、却下されました。本当の原因は硫化水素ではないので症状等が該当しないためで、当然です。 この説には矛盾点が数多くあり、そのうちのいくつかを紹介します。 大気中の硫化水素濃度は一度も測定されていません。判決文では「10ppmの濃度であった可能性がある」と書かれていますが、硫化水素は0.005ppmでもその悪臭でわかるので、もしそのような濃度なら住民の多くが訴えていたと思います。しかし、硫化水素臭を感じた住民はほとんどいません。 硫化水素は人間の腸でも発生し、おならに含まれています。普遍的に存在する物質なのです。したがってこの物質が被害の原因であるはずがないのです。多くの化学物質が検出されているにもかかわらず、硫化水素に固執して広い視野で検討していないことは、裁判官が化学物質についてまったくの無知であることを証明しています。 裁定委員の意見として述べられているように、中継所から出た化学物質の種類の200種以上が判明していますが、その他にも数多くの化学物質の存在が推定されます。また、それらの毒性はほとんど不明のままでこのような判断がなされたのは、被告の東京都だけでなく、化学工業界にとって大変な利点です。誰のための判決かということを考えるべきです。 ■「気のせい」論の誤り 2番目に「気のせい」論ですが、化学物質による被害についてこのような考え方を持つ人が裁判官を勤めている事に寒気がします。杉並病の被害者は、一般的な「化学物質過敏症」といわれる症状以外に多くの症状や後遺症を持っています。 「化学物質過敏症」という言葉は約半世紀以前にセロン・ランドルフによって提唱されており、プラスチック容器で反応する女性の例が書物に書かれています。しかし、医学者の不勉強により未だにその存在を否定する人がいます。最近は環境ホルモンについても遺伝子レベルの研究が進み、種や遺伝子によって被害の多少がある事がわかってきました。現実に被害者がいる事を謙虚に受け止めて、研究するのが医学者の役目だと思います 。 エール大学のカレンは、1987年に中毒の発現閾値以下の微量かつ多種類の化学物質により、複数臓器に臨床症状が誘発される病態不明の過敏状態を「多種化学物質過敏状態(MCS)」と概念化しました。1999年の米国立衛生研究所主催のアトランタ会議において、臨床環境医の間でのMCSの合意事項が決議されています。 合意基準は次の通りです。
■拡散・希釈論の誤り 3番目の問題ですが、日本は化学物質の規制は大変遅れています。とくに大気に関してはひどいものです。私達は空気を吸わない限り一時でも生きることはできません。ちなみに、私達が1日に吸う空気の重量は約15キログラムです。飲料水や食べ物と比較してみてください。 中継所からの排出規制濃度は、東京都の環境確保条例ではベンゼンを例にとると、なんと大気環境基準の濃度の3万倍に設定されています。このような高い濃度で設定されているので、よほどのことがない限り条例違反になる筈がありません(本来は総量といって化学物質全量の重量で規制するべきですが、日本はやりません。注:四日市公害などの原因物質の二酸化硫黄では設定しています)。 この条例での規制濃度で排気したとすると、排気された空気を3万倍に希釈しないかぎり、大気環境基準以下になりません。しかも、換気塔からは1分間に2833立方メートルの排気ガスが出ているのです。3万倍にすると、1分間に8500万立方メートルの空気が必要です。希釈するためには、想像を絶するほど大量の綺麗な空気が必要だということですが、それは無理です。 環境省は「有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質」として平成8年(1996年)に234物質を挙げています。その中の55物質が中継所から検出されています。また、234物質のなかでも「特に優先的に取り組む物質」として22物質がありますが、そのうち、14物質が中継所から検出されています。 また、厚生労働省が定めている「室内空気中化学物質濃度の指針値」の対象物質(いわゆるシックハウス対象物質)13種類の中で、シロアリ駆除剤を除くほぼすべての化学物質が検出されています。さらに、欧州委員会環境研究所が定めている「室内のTVOC決定に対して必要な必須測定VOCsリスト」のうち、約50種近くが検出されています。 これらは、人間にとって有害であるからこそ対象とされているはずです。これだけの毒性物質が中継所から検出されていることがわかっているのです。 ■有害物質はすべて外へ流れた 燃焼ガスのように高温ではない、また、焼却ガスにくらべて分子量が大きい排気ガスは、拡散希釈されることなく、おそらく斜面を水のように流れて被害者の住宅を襲ったのだと思われます。 換気塔は建屋の屋根から2.9mと低い位置にありますが、1時間に約17万立方メートル(2833立方メートル/分)の空気を排気したのです。1時間あたり15回換気を行うためには、そのくらい大量の空気を出す必要があったのです。そのために、施設は負圧(外部より圧が低くなる状態)の状態にありました。したがって、プラスチックを圧縮した際に発生した有害物質は、すべて換気塔を経て外気に流れたのです。 なぜそのような大量の換気量を確保する必要があったかというと、設計者の話によれば、労働者を保護するために厨芥を扱う際の換気量に合わせたためだそうです。労働者に被害者がいないのを不思議に思う人がいるかもしれませんが、中継所の労働者は直接この有害物質を浴びることはなかったのです。 ■プラスチックを圧縮すると有害ガス発生 今回の判決ではわずかな賠償金額が提示されましたが、住まいを転々とし、仕事を失ったことに対する代償にはほど遠く、さらには肉体的精神的な苦痛と未来を断たれた苦しみを考えると、この判決は司法の残虐さが際だっていると思われました。原告は当然控訴をされています。 最後になりますが、事件が起きてから丸11年が過ぎようとしています。東京都は、十年一日の如く、誤りの硫化水素原因説を唱えています。それに対して、プラスチックを圧縮すると有害なガスが発生することが東大の影本研究室ならびに柳澤研究室の実験で確かめられました。さらに、多摩市の廃プラ圧縮処理を請け負った栗本鉄工所の担当者は「プラスチックを圧縮すると有害物質が発生することは、すべての業者は認識している」と、説明会で明言しました。 裁判所だけではなく、すべての人がこの事実を知り、廃プラスチック圧縮を回避するべく智恵を働かせて欲しいと思います。 【資料紹介】 「新しく始まった揮発性有機化合物汚染の実態−不適切なプラスチックゴミ処理施設、杉並中継所(杉並病)問題をふまえて−」 化学物質による大気汚染を考える会編 申込先:〒102-0074 東京都千代田区九段南3-4-5フタバ九段ビル3階 森上教育研究所 TEL 03-3293-0176 FAX 03-3264-1275 頒価 2000円 |