|
|
|
|
![]()
プロ店員。
さらに、彼女は作曲活動にも興味を示し、協奏曲のためのカデンツァや、他の楽器のフルートへの編曲なども行っているのだそうです。そして、指揮者としての挑戦まで始まっているようですね。 ご自身のバイオによると、現在はバーゼル交響楽団の首席奏者を務めているということですが、オーケストラのウェブサイトのメンバー紹介には彼女の名前はありませんでした。もう一つ、ベルヴィエ音楽祭管弦楽団のメンバーという情報もありますが、これは、実際に今月末のアジア・ツアーのスケジュールが公開されているので、間違いはないのでしょう。 このアルバムは、彼女にとって3枚目のソロ・アルバムです。これまでには2021年にORPHEUSレーベルから、今回も共演しているハープのチャシャ・ガフナーとフルートとハープのためのレパートリー、そして2022年にはCHALLENGEレーベルからヴェロニカ・クイケン(ジギスヴァルト・クイケンの娘でヴァイオリニスト)のピアノ伴奏でフランスの作曲家たちのアルバムをリリースしています。情報によれば、5月の初旬にはラヴェルの曲のレコーディングが予定されているようですね。 今回は、モーツァルトの作品を集めたアルバムになっています。ニ長調のフルート四重奏曲、ニ長調のフルート協奏曲、そしてフルートとハープのための協奏曲という、まさに「名曲集」といったラインナップです。 まずは、とりあえず現在は4曲楽譜が存在している、フルートとヴァイオリン、ヴィオラ、チェロという編成の「フルート四重奏曲」の中で、始終耳にするニ長調の作品です。時には「第1番」と呼ばれることもありますね。もう、隅から隅まで知っている曲ですから、彼女の演奏ではどのようなアプローチが聴けるのかとても楽しみにして聴き始めましたよ。それはもう、なんとも穏やかで、優しい肌触りの演奏でした。彼女がバロック・フルートも演奏していることも関係しているのかもしれませんが、それはモダン・フルートでありながら、刺激的な低音などは全く聴こえてこない、ふんわりとしたサウンドで貫かれていました。まさに「高貴」というか、「優雅」というか、まるでモーツァルトの時代のサロンでの演奏のような雰囲気が全編に漂っていましたよ。ですから、ここでは、よくあるようなフルートだけが目立ってしまう、というようなことは全くなく、常に他の弦楽器としっかり溶け合っていました。歌い方もとても優しくて、フレーズの最後はきちんと音を小さくして「これでおわりです」感が誰でもわかるようになっています。もちろん、倚音が解決された音などもしっかり弱くなってほとんど聴こえなくなっていることもありますから、時には最後の音を間違えたのかな、と思ってしまいます。 そのような吹き方は、周りの編成が大きくなった協奏曲でも全く変わりませんでした。ニ長調の協奏曲の場合などは、出だしの部分で連続して低音が出てきて、モダン・フルートでは普通はそれをこれ見よがしに倍音たっぷりに響かせるものですが、彼女はあくまでソフトな処理に終始していましたね。 ハープと一緒の協奏曲でも、やはりフルートだけが目立つことは極力避け、あくまでハープを立てるというスタンスは変わりません。そんな柔らかい音色とハープが混ざったサウンドは、とても安らぎに満ちていました。 おそらく、協奏曲でのカデンツァは彼女が作ったものなのでしょう。あまり難しいことはやっていないようですが、個性的で独特なテイストが感じられます。 モーツァルトではなく、もっと新しい時代の作品ではどのような音を聴かせてくれるのか、とても興味があります。 CD Artwork © Claves Records SA |
||||||
ウィーン八重奏団というのは、ウィーン・フィルのコンサートマスターで、ニューイヤー・コンサートでの最多出場(ヴァイオリンを弾きながら指揮)を誇るウィリー・ボスコフスキーが、弟の、やはりウィーン・フィルの首席クラリネット奏者、アルフレート・ボスコフスキーとともに他のウィーン・フィルのメンバーも加えて1947年に創設したアンサンブルです。編成は弦楽五重奏にクラリネット、ファゴット、ホルンが加わった8人、そのような編成で最も有名なシューベルトの作品を演奏するために作られたのだとも言われています。 1959年にはヴァイオリンのボスコフスキーがアントン・フィーツに替わりますが、そのメンバーで最初の日本公演が、NHKの招聘によって行われました。正確な年代は資料が見つからないのでわかりませんが、おそらく1960年代初頭あたりのはずです。それは、テレビやラジオで幾度となく放送されていたので、この曲はすっかり覚えてしまうほど聴くことが出来ました。同時に、そのメンバーも、「ギュンター・ブライテンバッハ(ヴィオラ)」とか、「ヨハン・クルンプ(コントラバス)」といった、少年にとっては耳に新しい、ちょっと変わった名前も刷り込まれることになりました。 現在でも、このアンサンブルは適宜メンバーの入れ替えを行って活躍しています。もちろん、オリジナルメンバーは一人も残ってはいません。 その、オリジナルメンバーによる2種類のLP、一応録音されたのは最初にあるように1954年と1958年なのですが、その演奏を聴き比べてみると、とても4年後に録音されたとは思えないほど、違いが顕著にみられます。まず、テンポが、モノラル盤はかなりゆっくり目ですが、ステレオ盤は全ての楽章が明らかに速くなっています。ただ、トラックタイムだけを比べると、第3楽章のスケルツォと第4楽章の主題と変奏は、モノラルが05:32と08:13、ステレオが05:57と11:20ですので、演奏時間は長くなっているのですが、これは、ステレオ盤ではすべての繰り返しを演奏しているのに対して、モノラル盤では繰り返しを省略しているからです。 テンポだけではなく、表現もかなり違います。ファースト・ヴァイオリンのボスコフスキーは、とても歌心のある豊かな表情を見せてくれているのですが、モノラル盤だと、かなり頻繁にポルタメントをかけているのに比べ、ステレオ盤ではもっとあっさりとした弾き方に変わっています。たった4年で、これだけの芸風の違いが出てしまうのは、普通は考えられません。 ところが、いろいろ調べているうちに、この2つの他に1948年に録音されたシェラック盤(いわゆるSPレコード)があったことが分かりました。DECCAの場合、1945年にはジャケットの右下にあるロゴの「ffrr(full frequency range recording)」という、周波数レンジを大きくとった高音質のテープ録音方式を確立して、それからカッティングしたシェラック盤も作っていたのですね。ですから、もしかしたら、この音源は結成直後の1948年に録音されたものなのではないでしょうか。  ジャケットは1954年のLPのものなのに、中身は1948年のシェラック盤(もちろん、そのマスターテープ)かもしれないと想像してみるのは、ちょっと楽しいかも。大声では言えませんが(シャラップ!) LP Artwork © The Decca Record Company Limited |
||||||
ただ、この4チャンネルのLPは、日本では発売されてはいませんでしたから、このアルバムを4チャンネルで楽しめたのは、US盤を入手することが出来たごく一部のマニアだけだったのでしょう。 そんな大昔のレア・アイテムが、その「50周年」に合わせて、ハイブリッドSACDになってリイシューされました。それは、4チャンネルLPのために作られたマスターが、そのままSACDのマルチチャンネルに収録されているという、再生クオリティとしては確実にLPを超えているはずのものでしょうから、それを聴かないわけにはいきません。SACDとしてはかなりの高額商品でしたが、迷わず購入です。 そのパッケージは、確かに価格に見合うだけのものはありました。まず、ジャケットはしっかり4チャンネル仕様です。  正直なところ、ビリー・ジョエルのヒット曲は知ってますが、そのアルバム1枚を全部聴くのは初めてのことでしたので、これを聴いて彼の音楽性が思っていたより多岐にわたっていたことに気づかされました。よく聴くロック・バラードだけではなく、ブルーグラスからゴスペルまで、とても間口が広いミュージシャンだったのですね。 1曲目の「Travelin' Man」がそんなブルーグラスの曲調でした。まずはリアの右から細かいスネア・ドラムのリズムが聴こえてきますが、その粒立ちがものすごいことになっていました。それに続いてフロントの左からベースが聴こえてきます。そして、ビリー自身のピアノは、フロント前面に幅広く鍵盤が広がる音像です。バンジョーがフロント右から聴こえてきます。あとで普通のCDを聴いてみたら、まずは楽器のバランスが全然違っていました。ドラムス系がSACDではかなり強調されています。ですから、このSACDを聴いてしまうと、普通のSACDでは全然物足りないサウンドに感じられてしまいます。 例えば4曲目の「You're My Home」では、イントロでリアからアコースティック・ギター(3本?)が聴こえてきますが、それはもうそれぞれの楽器がくっきりと浮き上がっていて、CDとは段違いの存在感です。 5曲目の「The Ballad of Billy the Kid」では、ストリングスとティンパニが加わって、壮大なサウンドに仕上がっています。そのティンパニの質感などにも圧倒されます。 そして、なんと言っても圧倒的なのが最後のトラック「Captain Jack」です。ここでは、多くのオルガンがダビングされていて、崇高なほどの「サラウンド」が実現されています。ヴォーカルも、ここではしっかりリバーブがかかっていますが、CDではそれが全く分かりません。 と、まさにSACDで蘇ったとてつもないサウンドを体験できたのですが、今のオーディオ事情では、それを楽しめる人はなかなかいないのではないか、という気がします。もはや、マルチトラックに対応しているSACDプレーヤーやユニバーサルプレーヤーは、ほとんど市場から姿を消してしまっているからです。このレーベルは、なんたってSACDの生みの親ですから、それにこだわるのは仕方がありませんが、同じようにサラウンド再生が可能なBD-Aであれば、もっと多くのリスナーに聴いてもらえるはずなのに。  ↑今回のSACD  ↑オリジナルLP SACD Artwork © Sony Music Entertainment Inc. |
||||||
その「オルフェオ」と並んで、彼の大作として「有名」なものに、この「聖母マリアの夕べの祈り」があります。確か、ミシェル・コルボが1966年にERATOレーベルに録音したものが、最初の全曲盤だったような気がします。そのレコードは各方面で絶賛されていたようでしたが、あいにくこの指揮者にはあまり良い印象を持っていなかったため、それを聴くことはありませんでした。だいぶ後になって、この人が録音したモンテヴェルディのマドリガーレ集が6枚組のCDで出たので、買ってはみたのですが、とうとう全曲を聴くことはありませんでしたし。 そんなわけで、この曲も、他のアーティストによって録音されてはいたのですが、コルボによって植え付けられた「モンテヴェルディはつまらない」という先入観は、なかなかぬぐえないでいました。ヴェルディは好きなんですけどね。 そこに現れたのが、「マタイ」で素晴らしい演奏を聴かせてくれたラファエル・ピションとピグマリオンがこの作品を指揮したアルバムでした。このチームなら、苦手だったモンテヴェルディももしかしたらすんなり聴けるかもしれないと思いました。 そして、それを聴き始めたら大正解、もうその魅力がストレートに伝わってきた思いで、とてもうれしくなってしまいました。確かに、断片的にどこかで聴いたことがあるような音楽なのですが、それまでのよそよそしい印象は全くなく、1時間以上かかる曲のすべてが、心から楽しめるものに変わっていたのです。 まず、沢山のソリストが出てくるのですが、みんなレベルの高い人たちで、この作品で登場する様々な表情を、それぞれの音楽にふさわしいものとして伝えてくれていました。ほんと、かつては何の意味もないと思っていた細かい音符のつながり(メリスマ)が、確かな表現として聴こえてきたのですね。 さらに、なんと言っても素晴らしいのが合唱です。その表現力の豊かさは、現代の細やかな情緒を表現するためのスキルには違いないのですが、それがモンテヴェルディで使われていても、何の違和感もありません。というか、それは、400年以上も前に作られたものが、そのまま現代人にも通用するようなスタイルで豊かな情緒をもって歌われていたのです。 その一例を挙げてみましょうか。最後のパートの「Magnificat」が始まるちょっと前に詩編 147の「Lauda Jerusalem」が合唱によって歌われるのですが、そのシンコペーションの扱いがとことん現代的なのですね。他のどんな演奏を聴いても、こんなに弾けているものはないのではないでしょうか。 もちろん、ここでのプレーヤーはピリオド楽器を使っていますし、発声も基本的にその時代のものを目指したものなのですが、もしかしたら、このような演奏は、学術的な面からは多少はみ出しているものなのかもしれません。でも、それを聴くのは私たち現代人なのですから、こちらの方がより共感をもって聴けることは間違いありません。そんな「爽やかな」モンテヴェルディも、今の世の中では必要なはずです。 その「Magnificat」ですが、これには最初に作られた7声版と、それを少人数でも演奏できるように6声版に直したものの2つのバージョンがあります。その6声版の方は「Magnificat II」と呼ばれています。まあ、言ってみれば「第2稿」ですから、演奏する時にはどちらか一方だけが演奏されているようですね。今回のピションも、「I」だけを演奏しています。 ただ、録音では、そもそも1966年のコルボ版で、その両方を続けて演奏していました。調べた限りではもう一人、ジョン・エリオット・ガーディナーが1989年に2度目の録音を行ったときにも、同じことをやっています。ただ、サブスクで聴いてみると、コルボ盤では「II」、つまり「6声版」の後に「I」、つまり「7声版」が聴こえてきます。これは、3枚組のLPでリリースされたときにも、3枚目のA面が「6声版」、B面が「7声版」だったからです。ですから、これはサブスクの表記が間違っています。 CD Artwork © harmonia mundi musique s.a.s |
||||||
彼が最初に作った合唱曲が、このThe Armed Man(A Mass for Peace)です。作られたのは1999年、そして翌2000年の4月に初演されました。それ以来、この作品は世界中50ヶ国で、3000回以上演奏されているのだそうです。もちろん、日本でも人気がある曲です。 初演と同じ年の7月には、作曲家自身の指揮によってVIRGINレーベル(現在ではWARNERレーベル)への録音が行われました。その時の合唱はナショナル・ユース合唱団、オーケストラはロンドン・フィルです。  今回のアルバムは、オリジナルのフル・オーケストラを、演奏の機会を増やすためにオーケストレーションが室内オーケストラ用に改訂されたバージョンの最初の録音となっています。作曲家によれば、楽器は少なくなっていても、オリジナルが持っているテイストはいささかも損なわれることはない、ということです。 この曲は全体の尺が1時間ちょっとというかなりの長さの「ミサ曲」です。日本語では普通は「平和のためのミサ曲」でしょうが、なぜか「平和への道程」という訳語が横行しています。いずれにしても、この中ではカトリックのミサのためのタイトルが数曲作られています。そして、それらの前後には、様々なテキストによる曲が演奏されています。 最初の曲はタイトルである「The Armed Man」の元の形、ルネサンス時代に多くの作曲家が自らのミサ曲のモティーフとして使った「L'homme armé」というフランスの古謡です。「武器を持った人に気を付けろ」という歌詞でしょうか。それが、暗に「平和」への願いに通じるのでしょう。3拍子のシンプルなメロディが、太鼓のリズムに乗ってピッコロで奏でられ、合唱が続きます。曲は段々盛り上がり、トランペットの伴奏に変わりますが、時折ヘミオレになっているのが、ちょっとオシャレ。 そんな曲に続いて、いきなりアラブの祈祷が始まったのには、驚きました。タイトルは「Call to Prayers (Adhaan)」、「アラーは偉大だ」と祈っています。 その後の「Kyrie」は、初めてのミサのパーツ。メゾ・ソプラノのソロの深みのある声でちょっと陳腐なメロディが歌われ、それが合唱につながります。この合唱が、それほど上手ではないのは、初演時の児童合唱のテイストを持たせた配慮なのでしょうか。 次の詩編からのテキストの「Save Me from Bloody Men」では、男声だけのユニゾンで、まさにグレゴリアン、といった、それっぽい旋律が流れます。 そして、「Sanctus」というミサのパーツです。行進曲風のシンプルなメロディとハーモニーですが、「Osannna」の部分では派手に盛り上がります。 次の「Hymn Before Action」はとてもスペクタクルな、まるで映画音楽のような音楽、シンプルな訴えが伝わってきます。その後が「Charge!」という、金管によるファンファーレの嵐が6/8拍子で始まる勇ましい曲です。それが後半にはカオスに変わり、それが収まると雨の音のSEの中から、悲しげなラッパが聴こえてきます。 そして、「Angry Flames」は、自ら広島で原爆にさらされ、その惨状を伝える多くの詩を作った峠三吉の、「原爆詩集」の中の「炎」という詩の英訳がテキストになっています。メゾ・ソプラノの暗い歌が印象的です。 次の「Torches」では、合唱からは切迫感が伝わってきます。それが、次の「Agnus Dei」になると、まるで「カッチーニのアヴェ・マリア」のようなキャッチーで穏やかな世界が広がります。 「Now the Guns Have Stopped」では、メゾ・ソプラノの切々とした訴え、そして「Agnus De」ではとても美しいチェロのソロに続いて、それを合唱が引き継ぎます。 そして最後は、「Better Is Peace」という、第1曲目の再現ですが、その最後にはア・カペラのコラールでしめやかに幕が下ろされます。平和な方がいいに決まってます。 CD Artwork © Signum Records Ltd. |
||||||
さらに、彼は「ホルスト・シンガーズ」、「オランダ室内合唱団」、「デンマーク国立ヴォーカルアンサンブル」などの混声合唱団の指揮者も務めます。男声合唱団はありません(それは「ホスト・シンガーズ」。そして、2006年から2023年という長期にわたって音楽監督を務めていたのが、ここで共演している「ケンブリッジ・トリニティ・カレッジ合唱団」です。こちらも、やはりこのレーベルから20枚以上のアルバムを出していました。なお、現在はスティーヴン・グラールという方が、レイトンの後任となっています。 レイトンは、オーケストラの指揮者としても活躍していて、2010年から2016年までは、「シティ・オブ・ロンドン・シンフォニア」の首席指揮者も務めていました。 今回のアルバムが録音されたのは2022年の7月、このあと、退任までに何枚のアルバムが作られていたのでしょう。 このトリニティ・カレッジ合唱団は、例えば同じケンブリッジ大学のキングズ・カレッジのような、すべてのパートが男声によって歌われるという「伝統的」なメンバー編成にはなっていません。もちろん、創設された当時(14世紀!)は男声だけでしたが、1980年代のリチャード・マーローが指揮をしていた時代に、現在のような女声が加わった「混声合唱」の形に変わっています。そのメンバーは30名ほどの合唱団と、何人かのオルガニストから成っていますが、それらは全て在学中の学生です。つまり、メンバーは毎年入れ替わっているのでしょうね。それなのに、常に高い水準を保っているのはすごいことですね。きっと、厳しいオーディションなどを行っているのでしょう。 今回取り上げられている作曲家、デイヴィッド・ブリッグスは、同じメンバーでの2009年の録音を以前聴いていました。彼は、レイトンより4歳年上ですが、やはり同じようにキングズ・カレッジでオルガンを学んでいたのですね。同時に在学していたわけではありませんが、先輩、後輩という間柄だったのでしょう。 そのブリッグスがオルガン・ソロの曲で自ら演奏しているトラックが、まずはこのアルバムの最大の聴きどころではないでしょうか。これは、前作でも行っていたことですが、今回はオルガンが以前彼の職場だったイギリスの教会の楽器ではなく、パリのサントゥスタシュ教会のファン・デン・ヘルフォルによって1989年に作られた楽器ですし、何よりも建物自体のアコースティックスが全然違いますから、もう浴びるような残響の中での、目が覚めるような即興演奏を楽しむことが出来ます。録音スタッフは前作と全く同じですから、それは録音のせいではないはずですし。 合唱団も、やはり年代が違っていますから、今回の方がより洗練された声を聴くことが出来ます。それも、豊かな残響によって、とてもリッチな響きを醸し出しています。ですから、今回のレパートリーの中では、オルガン伴奏のつかないア・カペラの曲で、その柔らかいハーモニーに存分に浸りきることが出来ることでしょう。 その中で、タイトルとなっている「Hail, gladdening Light」では、いきなりヘンデルの「見よ、勇者は帰る」が聴こえてきてびっくりしますが、その後はブリッグスならではの美しい和声に戻ってくるので、一安心です。 伴奏でオルガンが入るときには、この合唱団の現在のオルガン・スカラーである2人が、交代で伴奏を務めています。それぞれにとてもインパクトのあるオルガンと合唱の掛け合いが聴けますが、もちろんオルガン・パートも素晴らしい演奏です。 CD Artwork © Hyperion Records Ltd |
||||||
2020年にはDGレーベルとのアーティスト契約を結び、ファースト・アルバムの「I Am Hera」をリリースします(「I Am Here」ではありません)。今回の「BREATHE」は、それに続くセカンド・アルバムとなります。 今回のアルバムでは、前作同様、彼女のレパートリーであるオペラのアリアの他に、現代の作曲家によって作られた曲も演奏されています。アルバムタイトルの「BREATHE」は、「息をする」つまり「ブレス」のことですが、この中のカナダの作曲家セシリア・リヴィングストンが彼女のために作った「Breath Alone」という、まるでミュージカルのナンバーのようなキャッチーな曲のタイトルから取られているのでしょうが、それに先立って、最初に聴こえてくる、オーストラリアの作曲家ルーク・ハワードの「While You Live」という曲でも、伴奏の中に「ため息」が使われているということもにも関係しているのでしょう。そこからは、それと同質の「波の音」なども加わって癒しモードたっぷりの情景が現われます。そこに入ってきた彼女の声は、まさにその前奏と同じテイストを持つ、とてもシンプルな歌い方と、音色でした。 そんな、ほとんど「ヒーリング」に近い、ナチュラルで包み込まれるような静かな声だったものが、音楽が密度を増すのにシンクロして、次第にダイナミックなものに変わっていきます。そして、クライマックスでのパワフルな声にまで達した時には、このソプラノ歌手のたぐいまれな資質に驚かされることになるのです。しかも、その最高潮に達した時の声でさえ、彼女の声は澄み切っていました。そこにあったのは、オペラ歌手にありがちな、ビブラートたっぷりの、まるで絞め殺されるような威圧する声ではなく、とても心地よいフル・ヴォイスだったのです。 そんな彼女が歌うロッシーニやドリーブの、なんと美しいことでしょう。もう、すっかり彼女の歌の虜になってしまいます。初めて聴いたリチニオ・レフィーチェというプッチーニの次の世代の人が作った「チェチーリア」というオペラのナンバーも、とても魅力的、その第一印象が彼女によってもたらされた幸運をかみしめているところです。 この中には、韓国の作曲家、ウー・ヒョウォンという人が作った「Requiem aeternam」という、韓国のテイストがいっぱいの詰まった曲も歌われています。それは、「アジェン」という、韓国の楽器だけの伴奏で演奏されています。  かと思うと、スペインの作曲家ベルナト・ヴィヴァンコスが作った「Vocal Ice」は、ほとんどペルトのエピゴーネンのような音楽ですが、彼女のヴォカリーズには、ペルトのような冷たさはありません。 バックを務めるのは、ヨッヘン・リーダー指揮の、ジェノヴァのカルロ・フェニーチェ劇場のオーケストラ、オペラでは、とてもノリノリで、フルートなどはとても目立っていて、思い切り明るさを振りまいています。 CD Artwork © Deutsche Grammophon GmbH |
||||||
ここで歌っている合唱の人数は、コーラス1が22人、コーラス2が17人、まあ、現在では標準的なサイズですね。オーケストラも、写真を見るとヴァイオリンとヴィオラを合わせた人数が、それぞれ9人ずつのようですから、こちらもまず普通のサイズ、つまり、人数的にはピリオド楽器とあまり変わらないようですね。 聴いた感じも、フルートのソロでは明らかにモダン楽器だということはわかりますが、オーボエやオーボエ・ダ・カッチャ(コール・アングレ)などは、もともとモダンとピリオドの違いはフルートほどではありませんから、違和感は全くありません。 ですから、かなり早いテンポで始まった第1曲の響きも、最近の主流となったオーケストラの響きにかなり近いものでした。たぶん、弦楽器はノンビブラートを徹底させているのでしょう。 前奏に続いて合唱が入ってきます。そこで、ちょっと、今の時点でこの曲の普通の合唱と思えるものとは、かなり違っているな、と感じてしまいます。おそらく、メンバーはそれぞれがしっかり声楽の教育を受けているのでしょう、それぞれに立派な声を持っていることは、よく分かります。ところが、この曲を歌う時には、それがあまりに「立派すぎる」ので、何か違う、と思ってしまうのですね。具体的には、ソプラノのビブラート。音域が高くなると、もうみんなが朗々としたビブラートをかけて歌っていますから、やはりバッハの音楽との隔たりを感じてしまうのですね。 ただ、コラールを歌っているときは、それほど高い音は出てこないので、とっても美しいハーモニーで紡がれるしっとり感を確かに味わうことはできました。 ソリストに関しては、パートによってあまりにも落差がありすぎて、驚きました。ソプラノとアルトのパートでアリアを歌っている方は、本当に素晴らしかったですね。ソプラノの人は声がとてもキュートで、受難曲だからと言って湿っぽくなることのない、勇気を与えてくれるような歌声でしたね。そしてアルト(ここではメゾソプラノの方)は、もうその素晴らしさにはひれ伏したくなるような深みのある声でした。 ところが、この曲では最も出番の多いエヴァンゲリストが、とんでもない人でした。このロールの楽譜には、高い音がたくさん使われていて、それが魅力にもなっているのですが、この人ときたら、それがまともに出せないのですからね。下痢で力が入らなかった、とか。 どうやら、このコンサートではテノールにダメな人が集まってしまったようで、アリアを歌っている人も音痴の上にメリスマも歌えないというひどさでした。 あと、これはマイク設定のミスなのでしょうが、イエスの声がとてもオフだったのは、聴いててつらかったですね。 ネットにこのコンサートのチラシの画像があったのですが、そこには「公演アドバイザー・字幕 磯山雅」という文字がありました。磯山さんはもうだいぶ前にお亡くなりになったはずですから、どのような形でのアドバイスがなされていたのでしょうね。 一つ気になったことがあって、23番のバスのアリア「Gerne will ich mich bequemen(喜んで私も覚悟を定め)」のイントロのヴァイオリン(トゥッティ)が、すべての音を切って演奏されているのですね。  CD Artwork © NAMI RECORDS Co., Ltd. |
||||||
今回のアイテムは、CDでは出ていないようで、ストリーミングだけでのリリースなのでしょう。1963年にアメリカのVANGUARDレーベルによってステレオ録音されたマーラーの「交響曲第8番」です。録音担当はMarc J. AubortとEd Friednerという、いずれもこのレーベル専属のエンジニアです。 指揮者は、モーリス・アブラヴァネルという、とても懐かしい名前の方。1946年に、ユタ州ソルトレークシティにあるユタ交響楽団の指揮者となり、1979年までそのポストにありました。 その間に、VANGUARDなどのレーベルに多くの録音を残すことになります。この「8番」を皮切りに、1963年から1974年にかけて、マーラーの全交響曲のツィクルスも完成させました。同じころに、COLUMBIAにバーンスタインがやはり全曲録音を行っていましたが、その時の「8番」はNYフィルではなくロンドン交響楽団でしたから、すべて同じオーケストラで行った全曲録音は、これが世界初?この頃のVANGUARDは録音が売り物でしたから、この大編成の曲は、まさにそのデモンストレーションのような感じで、気合を入れて録音されていたのでしょうね。 ただ、このストリーミングの音源はマスターテープが使われていたのではなく、たぶんLPからの板起こしなのではないか、という気がします。 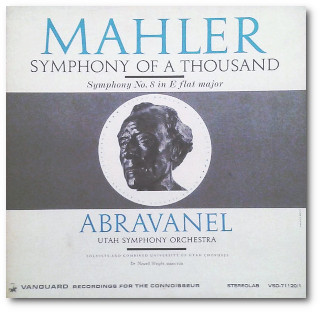 それは、第2部になっても同じことです。トータルは52分なのですが、22分あたりと40分あたりで、明らかに音が変わっていることが分かります。最後の面は12分しかないので、最後のクライマックスでもそれほどの破綻は見られません。 そんな情けない音ですが、VANGUARDのエンジニアたちの仕事には、確かにユニークなものが見られました。まずはオーケストラの配置。なぜか、ここでは、普通のコンサートでは絶対に見られないような、ヴィオラ以上がすべて右チャンネルから聴こえてくる、という配置になっていました。そして、チェロとコントラバスが左のチャンネルです。金管も左、木管はセンターですね。 かなりたくさんのマイクを設置していたようで、普段はまず聴こえない楽器(マンドリンなど)がくっきりと聴こえてきます。このあたりが、彼らのサウンド・ポリシーだったのでしょう。 ソリストたちは右端のソプラノから右端のバスまで1列に幅広く並んでいます。最後に登場する「栄光の聖女」だけは、左から聴こえてきます。 合唱は「I」が右、「II」が左、その間に児童合唱という配置です。この児童合唱がなかなかのものでした。大人の合唱は、クレジットによれば大学生のようですから、男声などはちょっと拙いところもありましたね。でも、全体的にはまとまっていたのではないでしょうか。 アブラヴァネルの指揮ぶりは、とても明るい音楽、というか、第2部の最初のパートなどは、不気味さなど全く感じられない明るさでしたし。それがアメリカの音楽なのか、あるいはそういう時代だったのかは、分かりませんけど。 Album Artwork © Urania Records |
||||||
そして、オーケストラがトロント交響楽団というのにも、注目です。このオーケストラは、現在の音楽監督であるヒメノの6代前の小澤征爾とともに、この曲を録音していましたからね。それは、1967年のこと、RCAレーベルからリリースされたときのジャケットは、こんなインパクトのあるデザインでした。  それから何度かプロのオーケストラによる演奏がありましたが、1987年には、早稲田大学交響楽団というアマチュアのオーケストラが、岩城宏之の指揮でこの難曲を演奏してしまいました。アマチュアが手掛けるにはハードルの高い作品は何曲もありますが、これは群を抜いています。それを軽々とクリアしたのは、日本のアマオケのレベルの高さを示していたのでしょう。最近でも、こんな演奏会が予定されているようですからね。  そんなことはどうでのいいのですが、今回のヒメノの録音を聴いていると、聴き手にとってはこれはもはや「現代音楽」ではなく、ある意味「ヒーリング・ピース」とでも言えるほどのしなやかさを提供してくれる作品なのではないか、という気が、強くしてきます。やはり、何度も演奏されていることによって、演奏家の精度も上がり、作品の持つ本来の姿をきちんと示すことができるようになった、ということなのでしょう。 そんなことを感じたのは、今回と同じトロント交響楽団が小澤の指揮で録音したものを改めて聴き直してみたからです。例えば5曲目の「星の血の歓喜」では、冒頭がこんなことになっています。 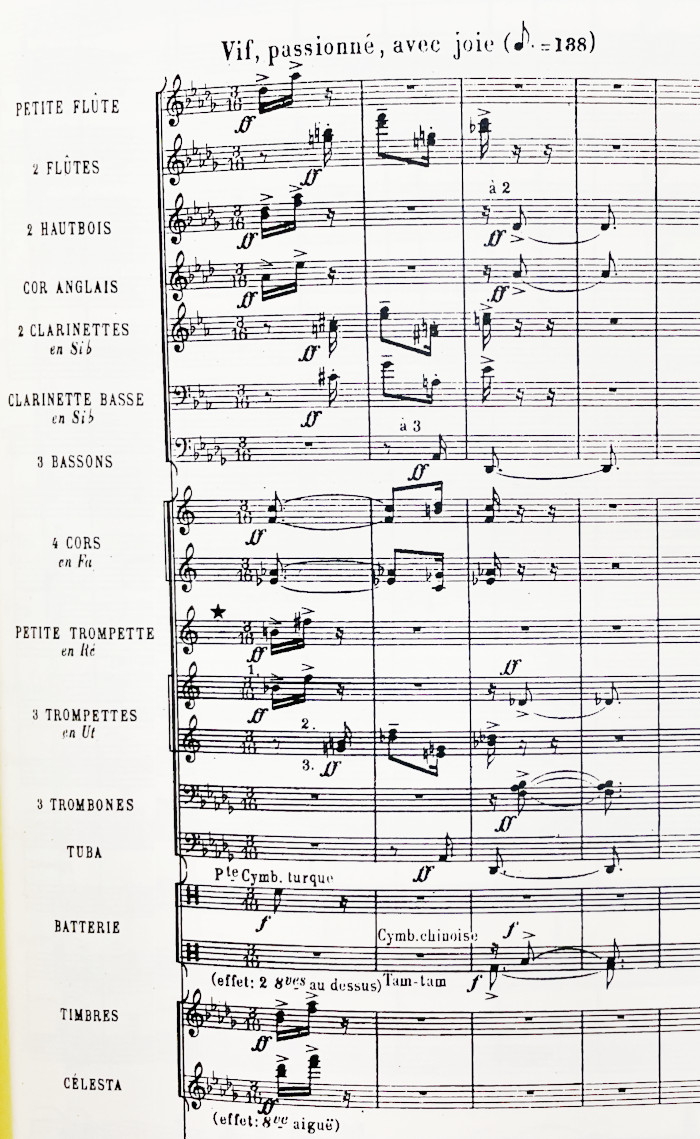 それが、今回の同じオーケストラ(もちろん、メンバーは全員入れ替わっていることでしょう)では、その部分をいとも美しげに、そしてスマートに紡いでいるのですね。そこからは、溢れ出る生気のようなものも感じられます。この部分だけだったら、おそらくこれまで聴いたものの中でのベストではないか、とさえ思いました。 さらに、オンド・マルトノもはっきり聴こえるバランスの録音で、しっかり歌いこんでいるのが、よく伝わってきます。 CD Artwork © harmonia mundi |
||||||
おとといのおやぢに会える、か。
|
|
| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |
| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |