![]()
割れ胡瓜....渋谷塔一
相変わらず、世間では「癒し」ブームが続いているようでして、某メーカーでは、例の大ヒット作「イマー×ュ」の続編を発売決定。またもや若い女の子を中心に大売れ、うはうはを画策しているとか。他社でも、同じようなアルバムを製作してるそうで、新聞紙上でも、ある大型店のこのCDの紹介記事が掲載されていましたっけ。
JOHN TAVENER
Songs and String QuartetPatricia Rozario(Sop)
The Vanbrugh Quartet
HYPERION/CDA 67217
でも、おぢさんには、あのノリはちょっとついていけないな。
「別のところで癒しは求めるからいいや」なんて購入したのが、このタヴァナー作品集なのです。
このアルバムは、タヴァナーお気に入りのソプラノ、パトリシア・ロザリオと、以前、ベートーヴェンの弦楽四重奏曲で素晴らしい名演を披露してくれたヴァンブルーSQの共演による歌曲集と、弦楽四重奏曲を集めた1枚です。
例の如く、どの曲にもタヴァナーの思い入れがたっぷり。最初の曲「The World」はイギリスの詩人、キャスリーン・レインの90歳の誕生日を記念して作曲されたもの。「最初から最後まで激しく演奏すること」と注釈がつけられています。ただし、タヴァナーの持ち味である、神秘的な音はあまり感じられず、どちらかというと、エスニックな味わい。なかなかおもしろいじゃん。と聞き入ってしまいました。
次の「ディオディア」。こちらは彼の3番目の弦楽四重奏曲なのですが、この作風はたぶん好き嫌いが別れるところでしょう。最小限の音のみを使い、ごく単純な音形を組み合わせていく方式なのですが、私のような根気のない者には、かなり苦痛の世界でした。同じメロディが出てくるたびに、「ああ、まただよ」といらいらしてしまうのです。でも、人によっては、これが「癒し」になるのしょうね。ミニマル系の音楽が好きな方には、おすすめできる逸品です。
友人でもあるチャールズ皇太子の50歳の誕生日を記念して、98年に作曲された「Many Years」は、ちょっと洒落た小品です。(でも、ちょっと怖いかも)このような曲でお祝いしてもらえるなんてとても幸せな事ではありませんか。いつも神秘のヴェールの包まれている(振りをしている)タヴァナーのくつろいだ素顔を垣間見る気がします。
「アフマトーヴァの詩による歌曲集」。これが、いかにも彼らしい作品。もともとは、チェロのイッサーリスとロザリオのために作曲されたのですが、ナッシュアンサンブルの委嘱で編曲された版をつかって今回録音されたものです。ロシア語のテクストに基づく難解な詩に付けられた6つの歌。一度聴けば容易に覚えられそうな単純な旋律を、霧の中の虹のような微妙な和声で色づけして行くという、不思議で美しい作品です。
この人の作品は、よくアルヴォ・ペルトと並び評されますが、こうして聴いてみると、まるで違った作風なのがよくわかります。ペルトは、余分な音を取り去った後に残った響きで曲を構成するのに対し、タヴァナーは余分な物がくっつく前の、ある意味、原始的な音を使うのに終始していたのでは。出来上がったものは、一見同じような様相を呈しているけれど、本当は全く違うようですね。
この作曲家、以前は16世紀の教会音楽作曲家と同姓同名(スペルが若干異なる)のため、「タヴナー」と表記されていましたが、最近は「タヴァナー」になったようです。イギリス音楽を束ねる重鎮ということで。
昔、マーラーにはまっていた時に、リュッケルトの歌曲もさんざん聴いたものです。若い時というのは、必要以上に感傷的になるもの。まあ、夜、「真夜中に」なんかに感動して涙ぐんだなんて、今ではとても告白できない恥ずかしい思い出です(言ってるって)。それで、あまり聴きすぎたものだから、すっかり飽きてしまい、このところ全くご無沙汰していたこの曲。
SPECULUM VITAE Monika Wiech(Sop)
Albrecht Schmid(Org)
Martin Müller(Pf)
CAVALLI RECORDS/CCD309
今回聴いてみようと思い立ったのは、なんとこの曲の伴奏をピアノでも、オーケストラでもなく、オルガンで演奏しているからでしょう。
確かに敬虔な佇まいの曲ではありますが、やはりオルガンで伴奏するのはちょっと無理があるんでないかい?そう思いつつ聞いてみました。これがなかなかいいのですね。このヴィーヒ(?)と人、現代音楽を得意とするソプラノですが、歌い方はどちらかと言うと、今流行のヒーリングヴォイス系とでも言いましょうか。透明な声と、教会でのたっぷりとした残響が溶け合って、得も言われぬおだやかな音に仕上がっていたのには驚きでした。
この曲目当てで買ったのですが、このCDのメインはヨーゼフ・ハース(1879-1946)の3つの歌曲集と、アルバムタイトルにもなってる、ベルギーのオルガニスト兼作曲家のぺーテルスの、SPECULUM VITAE(人生を映す鏡)と言う連作歌曲です。
このような、歴史の片隅に置き忘れられたような歌曲がまとめて聴けるのは、とてもうれしい事です。
ハースという作曲家、今ではすっかり忘れられていますが、1937年にカッセルで初演されたオペラ「気まぐれトビアス」は当時の批評家をして、「ドイツ民族オペラの発展の肯定的な一例にして、プフィッツナーの『パレストリーナ』以来の最高傑作」とまで言わしめた作品。凄い人なのです。(ただ、ここで聴く歌曲は民謡調の素朴な物で、あまりその凄さは感じませんでしたが。)
ぺーテルスの歌曲はなかなか面白く、さすが自身がオルガニストだった事もあってか、伴奏部の素晴らしさは絶妙です。荘厳なコラールは、一度聴いたら必ずや耳に残るでしょう。
惜しむらくは、彼女の歌い方。どの曲もあまり変化がなく、淡々と歌っている印象です。逆にいえば、そこがヒーリングアルバムにもぴったりということでしょうか。そういう観点からいえば、早逝した作曲家、ジュアン・アランの「アヴェ・マリア」などは、いつぞやのグレツキの「悲歌のシンフォニー」にも負けぬほど泣かせてくれるフィーリングたっぷりの作品かもしれません。
今年の成人式の例を持ち出すまでもなく、いつの世も若者というのは無鉄砲なものです。その行いが、後世に美しき詩となって残るか、はたまた映像として、ワイドショーを賑わすかと言った違いはありますけれども。
SCHUBERT
Die schöne MüllerinWerner Güra(Ten)
Jan Schultsz(Pf)
HARMONIA MUNDI/901708
この「水車小屋の娘」に登場する水車番見習いクンも、当時の典型的な若者像でしょう。彼の憧れの人・・・・(これは多分、第3者から見ると、どうって事ない普通の娘なのですが。)その人のちょっとしたしぐさに敏感に反応して、泣き、笑い、そして絶望する。その若さゆえの、直情的な心の動きを、シューベルトは単純ながらも美しいメロディに載せて書き上げたのですね。これを聴くと、おぢさんは過ぎ去った青春に一瞬だけ立ち返る思いがするのですよ。
さて、ここで歌っているギューラについて。何とも若々しい声の持ち主で、等身大の若者の歌を聴かせてくれます。とはいっても、シャーデのような感情過多な歌い方ではなく、どちらかと言うと、プレガルディエンのような抑制した歌い方。それでいて、微妙な心象風景をきっちり歌い上げる才能は並大抵のものではありません。
この連作歌曲の中でも有名な第7曲「焦燥」。これを聴いてみましょうか。曲の作りはいたって簡単で、揺れ動く三連符にのせてはずむようなメロディを4回繰り返すもの。至るところに「私の心はあの人のもの」と書き付けよう、そんな内容の情熱的な歌なのですが、これが驚くほど上手い。喜び、ためらい、そして絶望の片鱗。そこまで全て歌いこまれている気がするのです。例えば、ほんの最後のところで、一瞬だけテンポを落とすのですがこれが絶妙。これはとても私の拙い言葉では表現できませんね。ピアノがまた素晴らしい。ちょっと攻撃的なんだけど、それが何ともいい味をだしているのです。
全てこんな感じで、驚くほどこまやかに歌いこまれているのです。この人の名前、どこかで聞いたことあるな。と思ったら、そのはずです。ヘレヴェッヘの「マタイ」でテノール歌ってた人でした。道理で上手いはずです。
さて、この若者は失恋の痛手から、小川に身を投げてしまうのですが、このすばらしい歌を聴いてしまうと、その終わり方はなんだかかわいそう。
「若者よ。失恋くらいなんですか。とりあえず心の痛みを小川と話し合い、その気持ちだけを川の底に投げ捨てましょう。それで、そんな女の事はきっちり忘れて、次の娘でも探しなさい。」
こう言ってあげたくなる事自体、純粋さを失った狡猾なおやぢでの証明かも。
ま、それはさておき、過去の幾多の名演のCDをを凌駕するぎゅーらいに、また素晴らしい一枚が加わったのは間違いありませんね。
「20世紀音楽なんか怖くない」というタイトルのこのCD、実は、昨年の大晦日にハンブルクで開かれたコンサートのライブなのです。大晦日のコンサートというと、例のベルリン・フィルの「ズィルヴェスター・コンツェルト」が有名ですね。アバドが死神のような姿を全世界にさらしたという、あれです。
Who is Afraid of 20th Century Music? Ingo Metzmacher/
Philharmonisches Staatsorchester Hamburg
EMI/CDC 557129 2
で、こちらは、その向こうを張って、ベルリン・フィルの陳腐な企画に対抗しようと、現代音楽が得意なメッツマッヒャーが、彼らしい選曲で開催したコンサート。おととし初めてやってみたら、あまりにも好評だったので、20世紀の最後の年となった昨年、再度行ったというものです。
タイトルどおり、演奏されているのは20世紀に作られたものばかり、1908年のストラヴィンスキーの「花火」から、1991年のマイケル・ドハーティの「Desi」まで、15人の作曲家の作品です。
しかし、いわば、お祭り騒ぎのようなコンサートですから、あまりシリアスな曲目は巧みに除かれています。シェーンベルクやベルクといった、「聴いて自殺したくなるような曲」は、20世紀音楽を語る上では決して避けて通ることは出来ないものですが、「何も大晦日にやらなくても」という健全な自制心が働き、プログラムに上ることはありませんでした。
その結果、演目のメインを占めたのは、ダンスがらみの景気のよい曲と、オネゲルの「パシフィック231」とかモソロフの「鉄工場」といった能天気な描写音楽です。なるほど、20世紀のクラシック音楽には、他のジャンルからの影響は見逃せませんから、ダンスもいいでしょう。しかし、とことんリズム感の悪いこの指揮者にかかってしまっては、ファリャの「火祭の踊り」から民族色を感じるのは極めて困難ですし、バーンスタインの「シンフォニック・ダンス」から、浮き立つようなマンボのステップを連想することは不可能に近いのです。
「20世紀を現代音楽で締めくくろう」というコンセプトで開かれたこのコンサートですが、全部を通して聴いてみると、いったいこの世紀とは音楽にとって何だったのかという暗澹たる気持ちにならざるを得ません。コルンゴルトのマーチや、コープランドの「ロデオ」などといった、一見エンタテインメントを追求したかに見える曲の醜悪なこと。もっと他にも聴くべき曲がたくさんあるのに、勘違いで、このような曲が20世紀の成果だと思い込む未熟なリスナーがいるとすれば、これ以上罪なことはありません。ラヴェルの「パヴァーヌ」や、武満徹の「グリーン」といった真の名曲が、妙に居心地の悪いものに聞こえてしょうがないこのCD、現代音楽をいとおしむおやぢの心の琴線には、残念ながら触れることはありませんでした。隠れたファンの間では好評で、なかなか売り上げも良いということですが、間違って買ってしまった人には、金銭的にも罪なこと。
「前期バロックから後期ロマン派までの合唱音楽」というタイトルの、とても素晴らしいアルバムです。1530年生まれのヤコブ・ハーンから、1889年生まれのルドルフ・マウエルスベルガーまで、5世紀に渡る作曲家による教会音楽が、年代順に収録されています。すべて無伴奏(ア・カペラ)ですが、8声程度の大きな編成の曲が集められており、豊かな音響空間を味わうことが出来ます。
Chormusik vom Frühbarock
bis zur SpätromantikKarl-Friedrich Beringer/
Windsbacher Knabenchor
RONDEAU/ROP2012
最初は、ヤコブ・ハーン(ラテン名ヤコブス・ガルス)の二重合唱のためのモテット。まだルネッサンスの様式を思わせるような、壮麗な曲です。次に、大バッハの大叔父にあたるヨハン・バッハという人の、やはり二重合唱ですが、片方の合唱は遠くから聞こえてくるような、やはりルネッサンスのなごりが見られます。
次のヨハン・ルートヴィヒ・バッハ(大バッハのいとこ)になってくると、ポリフォニーを残しながらも、テキストの内容を大胆に表現しようとする意思が見えてきます。
ここからがロマン派。しかし、メンデルスゾーンのモテットは、確かに語法は紛れもないロマン派のものですが、前の曲から100年以上隔たっているとは思えないほど、似通った肌触りがあるというのは、意外な発見です。
次は、お目当てブルックナー。ついこの間ガーディナー盤で聴いたばかりのモテットですが、あちらは成熟した表現なのに対して、もっと若々しいストレートな魅力が味わえます。
ブラームスのいかにもという生真面目な曲に続いて、最後に演奏されるのが、ドレスデンの聖十字架教会のカントールも務めたマウエルスベルガーの「弔いのモテット」。第2次世界大戦で灰燼に帰したドレスデンの死者を悼むという、旧約聖書の「エレミア哀歌」をテキストにした曲ですが、作曲技法的にはこれまでの曲と何の違和感もないものです。
こうして全体を聴いてみると、いかに時代を経ようと、何か共通のテイストを感じ取ることが出来るような音楽を作ることを可能にした、キリスト教というものの力の強さを感じずにはいられません。
歌っているウィンズバッハ少年合唱団の芯のある輝かしい発声が、このアルバムをさらに魅力あるものにしています。実は、この録音は2回に分けて行われていて、その間には10年近くの隔たりがあるのですが、それを全く感じさせないクオリティの高さが維持されているのです。少年合唱ですから、このぐらい時間がたてばメンバーは完全に入れ替わってしまうのですから、これは驚異的なこと。
ところで、ブルックナーの「アヴェ・マリア」の最後、「Sancta Maria, ora pro nobis」の、最後の単語の「no」の部分の2つ目の音に付けられた和音が、楽譜では減7なのに、ここではアルトを半音下げて属7になっています(譜面とMIDI参照)。こんな風に変わったところがあると、なんか気になるものです。
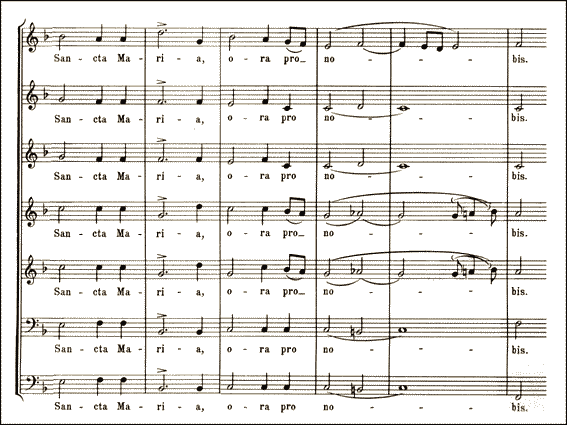
オペラもそうですが、オーケストラだってお金がかかるのは同じことです。なにせ、100人以上のプロの音楽家を、それなりの待遇で迎えなければなりませんし、指揮者や、協奏曲のソリストに対するギャラも大変です。人気のある指揮者などは世界中で奪い合いですから、相場はどんどん上がっていきますし。
BERLIOZ
Symphonie fantastiqueColin Davis/
London Symphony O
LSO LIVE/LSO 0007 CD
もちろん、そのような経費を演奏会のチケットだけでまかなうなどというのは、プロ、アマを問わず無理なこと。足らない分は、公共機関からの補助金や、お金持ちのパトロンからの寄付に頼ることになるわけです。最近では、それに加えて「レコーディング収入」というのが、かなりの割合を占めるようになってきました。ベルリン・フィルなどが新しい指揮者を選ぶ時に基準にするのは、「CDが売れる」かどうかということ。カラヤンほどとは言わなくても、そこそこの実績があげられないときには、留任は難しくなるのでしょう。
ところが、レコード会社の方から見ると、クラシックなどは全社的に見れば不採算部門の最たるものですから、何とか切り棄てようと考えても当然なこと。現に、フィラデルフィア管弦楽団ほどの名門オーケストラでさえ、EMIから録音契約を打ち切られてしまうという時代なのですから。
SONYやBMGといったメジャーレーベルは、本気でクラシックからの撤退を考えていますから、プロのオーケストラが生き残るためには、もはやこういったレコード会社に頼るわけにはいかないのです。
そこで考えたのが、自前でCDを作って売り歩くという、産直野菜みたいな商売です。さいわい、今はインターネットというもので、流通コストを考えなくても販売が出来る時代ですから、有名オケの自社ブランド商品は、ネット上に氾濫しています。
ロンドン交響楽団が「LSO LIVE」というレーベルで、ライブ録音をリリースするようになったのも、そのような流れの一環でしょう。最初はネット販売だけでしたが、これに眼をつけた某チェーン店が店頭販売も始めたことで、にわかに脚光を浴びるようになりました。
ベルリオーズの「幻想」を収録したこのCDは、昨年9月のバービカン・センターでのコンサートのライブ録音。ライブとは言っても、2日分のコンサートをゲネプロも含めて録音して、それを編集するという、最近のオーケストラ録音の手法を使っていますから、ミスなどは殆ど目立ちません。トニー・フォークナーなどというエンジニアを起用して、ちょっと前の放送音源のような曖昧さとは無縁の、分離が良くレンジの広い素晴らしい録音が実現しました。ティンパニあたりが少しモヤモヤしているぐらいは我慢しましょう。コルネット付きの版を使用しているのもうれしいところ。
唯一の欠陥はデイヴィスの指揮。もってまわった深刻な音楽からは、フランスのエスプリなど微塵も感じとることはできません。ライナーにある評論家の賛辞はミスプリでしょう。以前ベルリオーズのオーソリティであると書きましたが、研究してるからといって、演奏が上手いとは限らないという実例です。
今年はヴェルディイヤーです。もう、この部屋でもちらほらヴェルデイアイテムが登場してますね。昨年のバッハイヤーの時のように、ファイルの中に必ず1つは彼の作品が入るということになれば、ヴェルディのファンは喜べるでしょう。ただし、オペラはなかなか録音も大変なので、新作が登場する事はあまり期待できないかもしれませんね。
VERDISSIMO
The Very Best of G.VerdiVarious Artists
TELDEC/8573-86386-2(輸入盤)
ワーナーミュージック・ジャパン/WPCS-10671(国内盤)
で、今回の1枚。こちらのアルバムもコンピレーション物です。TELDECレーベルの持つ音源のなかから、聴き所を集めた1枚。以前、2001年の時にお話しましたが、こういったアルバムは企画が勝負です。その上使える音源が限られているとあって、製作者はかなり知恵を絞るのですね。選曲、使う音、曲の並べ方。これらを周到に検討して、1枚のアルバムが出来上がります。だから成功するかどうかは、製作者のセンスにかかっているといっても過言ではありません。
まあ、私が製作者だったら、こう考えますね。「ヴェルディの数ある名曲のなかからエッセンスを抽出して、初めて聴く人にも親しみを持ってもらう。」だから作曲順に有名な曲を並べてみましょうか。ナブッコの有名な合唱、女心の歌、乾杯の歌、神よ平和を与えたまえ。などなど。でも、きっとこれは素人が考える選曲なのですね。
なにしろ、このアルバムは選曲が渋いのですよ。第1曲目がアイーダの「凱旋行進曲」ですから。えっ、渋くない?でも聴いてびっくりでした。普通だったら勇壮な合唱から始まるこの曲、こともあろうに、ここでは中間のアイーダトランペットの部分から始まります。で、そのままバレエの部分に突入して、じらしにじらして最後に合唱で盛り上るというもの。別に間違っているわけではありませんが、なんか拍子抜けです。次はドミンゴの「清きアイーダ」。まっ、これはいいか。
で、椿姫。「乾杯の歌」は92年録音のニル・シコフの名唱が聴けます。でも、次のカラスの「そはかの人か」は「花から花へ」のカヴァレッタは省略(そこが聴きたいのに!)。リゴレットは、バリトンのアリアは1曲も含まれていませんし。細かく挙げていくときりがありませんが、全体的に選曲が中途半端な気がするのは私だけでしょうか?
結局のところ、どちらかというと歌手を楽しむ1枚ですね。例えば、リゴレットのマントヴァ公の聴き比べはいかがでしょう?「あれかこれか」でのお下品なパヴァロッティと「女心の歌」での若々しいカレーラス。運命の力の「天使のようなレオノーラ」。これは往年の名テノール、ディ・ステファノの若々しい声が聴けます。若々しいといえばマンリーコを歌うドミンゴの68年の声。これには月日の変遷をしみじみと実感しました。
そんなわけで、ちょっとヴェルディに親しむためだったら、他にもっといいCDがありそうです。それよりも、ちょっとヘンな物を探している方にだったらぴったりかもしれませんね。
今回の1枚はシカゴ響のトップ奏者によるR・シュトラウスの管楽器の協奏曲集です。またまたシュトラウスですみません。こうなったら、おやぢの部屋をシュトラウスの部屋とでも改めてもらいましょうか。休んでばっかりだったりして…(ストライキの部屋!)。
R.STRAUSS
Wind ConcertosKlein(Ob), Clevenger(Hr) etc.
Daniel Barenboim/
Chicago SO
TELDEC/3984-23913-2(輸入盤)
ワーナーミュージック・ジャパン/WPCS-10638(国内盤)
R・シュトラウスの協奏曲といえば、やはり管楽器のためのものが素晴らしいですね。もちろんそれは、高名なホルン奏者であった彼の父親の影響も大きいでしょうが、シュトラウスは基本的に「歌」を愛した作曲家なのでしょう。このような協奏曲のソロの使い方は、ほんとにオペラのアリアのよう。オーボエ協奏曲はそのままソプラノ、クラリネットとファゴットのための二重コンチェルティーノはメゾ・ソプラノとバリトンのデュエットに置き換えても充分説得力があるのでは。
そんな曲だから、ソロは相当上手くないと、オケの豊かな響きにかき消されてしまいますね。
今回のアルバムの中で、一番楽しみにしていたのが、オーボエ協奏曲なのは言うまでもありません。アレックス・クレイン。以前、シューベルトのアルペジョーネでの目の覚めるような演奏を聴いて以来、彼の新作を心待ちにしていたのですから。
で、聴いてみましたよ。まず驚くのが、あまりにもゆっくりした始まり方です。時間が止まってしまう一歩手前の危うい歩み。一音一音を極めて濃厚に演奏しているのだけど、それでいて、オケの音は意外にも乾いた音。これが何とも不思議な味わいを醸し出していて、聴き進むうちに、すっかりバレンボイムの術中に絡め取られている自分に気付きました。
ふと我に帰るのが、オケのTuttiの部分。今まで抑えていた感情が爆発するかのように、色合いの増す音楽。
聴く人によっては「わざとらしい」と感じてしまうほどの表現には正直なところ、少し戸惑ってしまったものです。くどいほどのテンポの揺らし方は、今までのバレンボイムではあまりなかったこと。何か心境の変化でもあったのでしょうか?
クラインのオーボエは、今回も温かみのある美しい音です。1楽章ではたっぷりと伸ばした深みのある音が聴けますし、3楽章では、まるで転がるような煌く音が魅力的です。
この曲はオーボエ協奏曲と言う事になってますが、実は、全ての楽器に聴き所が用意されていて、上手いオケですと他の奏者の名人芸も楽しむ事が出来るのです。その面でもこの演奏は二重マル。
私の最も愛するオーボエ協奏曲で字数が尽きてしまいましたが、他の曲も良いのですよ。ホルン協奏曲のソロのクレヴェンジャーも、友人A(ホルン吹き)のイチオシの人。とても上手いですよ。
おまけでバレンボイムのピアノ独奏が収録されてます。これは、まあ箸休めと言う事で。
ニューフィルの今度のプログラムはサン・サーンスの3番ですね。例によって、便乗好きのマスターは、サン・サーンスの若い頃の交響曲のページを作ってましたね。そんな折、タイミングよく交響曲第1番のCDが新しく出ました。これで、この曲が聞けるCDは3種類が入手可能ということになりました。
SAN-SAËNS,BIZET
SymphoniesIvan Anguélov/
Slovak RSO Bratislava
ARTE NOVA/74321 80795 2
今回の指揮者とオーケストラ、憶えてらっしゃらないかもしれませんが、以前同じレーベルからオペラ合唱曲集を出していたコンビです。あの時はいかにも田舎のオケ、洗練からは程遠い演奏だったのですが、ここでは、その資質がよい方向に作用して、見違えるような素晴らしい演奏を展開しています。
サン・サーンスの交響曲第1番は、実は、マスターのページにあったCDを私も聴いてみたのですが、マルティノンにしてもプレートルにしても、とても雑な演奏でがっかりしていたところなのです。珍しい曲だから、とりあえず録音してみましたという意思がありありとうかがえますし、特にマルティノンのオケはアンサンブルもガタガタ、とてもプロの仕事とは思えませんでした。
そこへ登場したのがこのCDです。確かに音色に華麗さはありませんし、技術的にも未熟な部分がないわけではありませんが、演奏のひたむきさという点からは、ピカイチの仕上がりになっています。何よりも、指揮者のアンゲロフの音楽の作り方に好感がもてるのです。ブラティスラバ国立歌劇場の首席指揮者として、オペラに関してはスペシャリストですから、交響曲でも全体の構成がとても見事です。歌わせるところは思い切り歌わせ、聴くものを飽きさせません。特に、第3楽章の、ハープの伴奏に乗って木管と弦によって奏でられる夢見るような美しい歌は、心に染みるものがあります。そこからアタッカで勇壮な第4楽章へ続く時の切り替えも見事。こういうのを、メリハリのきいた演奏と言うそうです。
ただ、この楽章の後半で、弦の各パートがソロで出てくるあたりは、もっと厚みのある艶やかな音色が欲しいところですが、これは我慢することにしましょう。
カップリングは、ビゼーの交響曲「ローマ」。ビゼーの交響曲と言えば第1番が有名ですが、この曲はもう少しあとに作られたもので、なかなか演奏される機会がないものです。実は私も初めて聴きました。題名の通り、ローマに旅行した体験が創作の源となっている、いかにも明るい雰囲気の曲です。これも、メロディーの歌わせ方が命。第1楽章のメインテーマや第3楽章の、まるでとろけるような甘美なメロディーが、胸に迫ります。第4楽章の浮き立つような明るさも申し分なし。こういう珍しい曲が、手抜きではないきちんとした演奏で、しかも安く手に入るというのが、ARTE NOVAのいいところですね。
つくづくオペラというものは、お金のかかる楽しみだと思います。見に行くにしても、万単位の出費は覚悟しなくてはいけませんし、もちろん、演奏するにも、録音するにも莫大な費用がかかるのはみなさんご承知の通り。だから日本で「指環」全曲上演というだけで、NHKのトップニュースになるほどの大事業なのです(ウソですからね。「なるほどそうなのか」などと納得しないで下さい。)。
WAGNER
Die Walküre-Act IWilliam Cochran(Ten)
Helga Dernesch(Sop)
Otto Klemperer/
New Philharmonia O
TESTAMENT/SBT-1205
そんなわけで、オペラの新録音も、あまり期待できない今日この頃、ヴァグネリアンは既存の音を聴いて満足するほかないのでしょうか?
そんな嘆きの声の中、おととしのクナッパーツブッシュの「神々の黄昏」の発売には多くのファンが喜びの涙にむせんだものでした。まだまだEMIは隠し音源を持っているに違いない・・・。そうです。ありました。今回のクレンペラーの「ヴァルキューレ第1幕」もEMIのプロデューサー、レッグの秘蔵音源です。クレンペラーのこの曲の演奏と言えば69年の物が有名ですが、こちらは72年、彼の死の半年前の録音、もちろん初CD化です。
69年盤もかなり厳しい演奏でしたが、こちらはそれを更に突き詰めた究極の逸品。とにかく素晴らしいの一言です。クレンペラーといえば、「緊張」、「厳格」と言った形容詞が使われますが、まさに、それを顕現した演奏とでもいいましょうか。前奏曲の重苦しい雰囲気からして、尋常ならざる物を感じます。まるで、スコアの音をひとつも漏らすまい、と必死になっている奏者の息遣いまで聴こえてくるような、極めて緻密な音世界。これは雷鳴によって引き裂かれるまでの4分間、ある種の息苦しさを伴って続くのです。
このヴァルキューレ第1幕は、「指環」という大掛かりな舞台装置を必要とするオペラのなかでは特異な場面で、たった3人の登場人物による、緊迫した心理劇。もちろんワーグナーらしく、最後は許されぬ愛が成就するのですが。
歌手については多くは望みません。当時は、もっと上手い人もいたはず。デルネシュは、カラヤンの時もそうでしたが、少し弱々しいし、コクランもまだまだ未熟かな。という感じ。しかしながら、歌と歌をつなぐオケの雄弁な事。これで2人の揺れ動く心を見事に表出しているのです。
まるで青白い炎に燃え尽くされるかのように、許されぬ愛に向かって突き進んでいく様は、まるでクレンペラー自身を回想するかのようで、終曲の「ジークムントは私の名」での盛り上がりは本当に美しく、感動的なものでした。「歴史的名演」という言葉はあまり好きではありませんが、こういうものに対して使う分にはいいかな、と納得したおやぢです。
一言書き添えておきますと、最初の部分を聴いて、「コントラバスが左から聞こえる。これは不良品だ」と言った友人がいましたが、これはクレンペラーが最後までこだわった両翼配置に拠るもの。スコアをみればわかるように、第2ヴァイオリンとの掛け合いのため、ちょっと聞くと右、左が反対と勘違いしてしまうようですね。リマスタリングの技術には定評のあるTESTAMENTのことですから、音のクオリティは最高です。
(3月10日追記)
その後、ライナーノーツを読み返してみたところ、この音源は69年に録音されたものであることが分かりました。このCDの録音データに「72年11月録音」と明記されていたものを鵜呑みにしてしまい、「秘蔵音源」などと書いてしまいましたが、これはしたがってまちがいです。関係方面にご迷惑をおかけしたことを謝罪するとともに、ここに訂正させていただきます。
きのうのおやぢに会える、か。
| (since 03/4/25) |