オルタナティブ研究会 講演学習会 報告
改めて「大きな物語」を問う時代へ
デヴィッド・ハーヴェイを手がかりに
オルタナティブ研究会では11月8日、哲学者の田畑稔さんを講師に学習講演会を開催した。研究会ではデヴィッド・ハーヴェイ『資本主義の終焉―資本の17 の矛盾とグローバル経済の未来』をテキストにしているが、これは田畑さんの発案を受けたものである。現在の時代を読み解く上で、ハーヴェイの優れた点や限界について幅広い理論枠組みの中で指摘いただくとともに、研究会活動が目指すべき時代との向き合い方についても、ご意見をうかがうことができた。以下、概要を紹介する。
地理学と『資本論』の接合
この本(『資本主義の終焉』)の著者紹介では、デヴィッド・ハーヴェイの専門は経済地理学と書かれています。実際、彼の中心的な仕事としては、地理学とマルクスの『資本論』を接合した『空間編成の経済理論―資本の限界(上・下)』(松石・水岡訳、大明堂、1989年)、『都市の資本論―都市空間形成の歴史と理論』(水岡監訳、青木書店、1991年)などがあげられるようです。一方で事実の蒐集的な従来の地理学を歴史展開の内的論理を組み込んで再展開、他方でマルクス資本論を地理的空間的側面を組み込んで具体性の次元へと接近するということでしょう。『資本の〈謎〉―世界金融恐慌と21世紀資本主義』(作品社、2012年)の第6章、第7章では、地理的環境の歴史的所与から資本主義的再生産へ、資本の越境性と空間支配、地理的集中と多様性の並存、立地と地価、都市空間と過剰資本の吸収、領土化とグローバル空間、地理的不均等発展と地理的ヘゲモニー、そして地政学的イデオロギーが論じられています。
マルクスでも「生活位置Lebensstellung」「都市農村編成」「ヨーロッパと東洋」「異時並存的歴史空間」など社会歴史的空間論や場所論的テーマがあります。この面に光を当てる上で、ハーヴェイの仕事は大変参考になります。『資本論』は、支配的な経済システムとしての資本の動態を純粋モデルで描いています。『資本論』の1巻、2巻、3巻と、徐々に具体的な資本のありかたに迫っていくのですが、基本的には原理論なので、地理的な問題をはじめさまざまな具体的な問題はいったん脇に置いて、抽象的なものから具体的なものへ一歩一歩たどっていくという「概念把握」をしています。しかし具体的なものといっても資本の歴史・論理的モデル化であり、現実の資本主義社会を扱っているわけではありません。現実の資本主義社会を扱おうと思えば、地理的なファクターも含め方法的に捨象しておいた諸側面を組み込むことが不可欠です。
しかし、いわゆる唯物論的歴史観というような視点に立てば、空間的な諸規定というのはもちろん欠かせません。たとえばモノの交換というのは本源的には山の民と海の民の間に行われるような地理的な差異がベースになって展開される。分業が成立して初めて商品交換が成り立つわけですが、アテナイのアゴラのような都市の中心に市場がたつ。「世界システム論」から言えば、中心・周辺構造という視点がなければ、現実の近代世界は見えないわけですが、中心・周辺構造それ自身が歴史空間的な規定です。背景として歴史世界はつねに前提されていますが、資本の論理的叙述としてはいったん方法的に捨象されます。
 |
デヴィッド・ハーヴェイ(David Harvey) 1935年、イギリス生まれ。ニューヨーク市立大学名誉教授。専攻は経済地理学。『資本論』を中心とするマルクス主義を地理学に応用した批判的地理学の第一人者。邦訳書に、『ネオリベラリズムとは何か』、『ニュー・インペリアリズム』、『都市の資本論―都市空間形成の歴史と理論』、『新自由主義 その歴史的展開と現在』などがある。 |
だから、経済地理学的に展開することによって、具体的な歴史的過程により近いモデルによって資本主義を描くという道を新しく拓いたこと、資本主義の具体的な歴史的プロセスに比較的近い形で地理学と『資本論』を接合したこと、これが彼の中心的な仕事なのだろうと思われます。
「生活過程」と「社会的位置」の問題
僕の場合は、マルクスを「生活過程論」で再展開したいと考え、作業を進めています。その視点からすると、「生活位置」というものを挙げることができます。これはマルクスのキーワードの一つで結構の頻度ででてきます。私たちは、かならず「生活諸関係」の内部で「生活諸条件」に条件づけられながら、また特定の「生活位置」を占めつつ、生活しています。このうち「生活位置」は権力や富の不均等な空間的配置などを前提にした社会空間における場所を表す規定ですね。
マルクスの「生活過程」は、近代社会では基底過程としての物質的生活過程のほかに社会的生活過程、政治的生活過程、精神的生活過程に分節化しつつ、また相互媒介しながら、総過程として進行するものとされています。この場合、生活過程は行為、構造、過程という3つの層を持っていると私は考えています。この点から言えば、廣松渉さん(註1)のマルクス解釈は行為論ベースではなく構造中心で、行為している当事者を反省すると諸関係の中で動いていることが見えてくるというのが基本です。だから「モノや個人に対する関係の存在論的第一次性」というテーゼが提出されます。僕としては、それだけでは「反省の哲学」「本質の哲学」にとどまってしまうのでは、と疑問を感じてきました。生活過程は、まずは個別的共同的な行為(活動、実践)が地盤にあって、次いで行為の構造の反省へと至り、さらに過程(生成過程、構造過程、崩壊過程)へと至る。こういう形で見ていくことになります。たとえば政治的生活過程はマルクスでは「社会の公的総括」の過程なのですが、まず問題になるのは無数の政治的行為です。その上で、その諸行為が持っている構造の反省が進み、われわれは常にすでに、特定の政治的生活諸関係や諸制度に入り込んでいることが自覚されるのです。しかしまた、この構造は生成過程や崩壊過程に連続していて、この過程もまた無数の行為なしに進むわけではもちろんありません。
行為者を反省してみれば「関係の束」「法権の束」として見える。それ自体は間違いとはいえません。しかし、それだけではスタティック(静的)な思想にとどまります。行為を地盤にしなければ「実践の哲学」にも「変革の哲学」にもなりません。構造といっても、実は行為の構造なのです。たとえば、言語を問題にする際にも、常に無数の言語行為をベースに置かないといけません。言語行為の背後に意識されない形で言語諸構造があることはたしかです。これは歴史的に生成したもので、特定の言語が社会制度としてあって、その中にわれわれは「生まれ込む」という事態が反省される。しかし、それだけではありません。われわれはそうした構造の中で言語行為を行いながら、不断にそれを再生産してもいます。つまり、諸構造もまた生成過程や崩壊過程を含んでいるし、行為なしに生成過程も崩壊過程もない。そういう構えをとらないと、マルクスの視点を生かせないのではないかと思います。
しかしハーベイの経済地理学に示唆されていえば、反省レベルで「生活諸関係」「生活諸条件」とは異なる「生活位置」(広くは「生活空間」)の問題の独自性が確認されるのではないか。個々のモノや諸個人があって、それを反省すれば諸関係が見えてくる、モノであれ諸個人であれ常に条件付けられており、諸条件の中で存在し行為している。こういう反省はもちろん重要である。しかし諸個人やモノは常に特定の社会的歴史的空間、場所を占め、またそれを構築、更新してもいるわけですよね。
マルクスの視点から生活過程論にそくして社会的歴史的空間論や「生活位置」論(場所論)をどう展開するか。たとえばマルクスは「ザスーリチへの手紙」で、ロシアの農村共同体を扱いつつ「異時の併存」について考察しています。ロシアの農村共同体では、近代と前近代という異なる歴史的時間が空間的に併存している。そこからオールタナティヴ(別の選択肢)を問題にしようとしている。こういう歴史的社会空間における異時並存や中心―周縁構造は『経済学批判』(1859年)の序言ではまったく扱われていないものです。都市農村構造、鉄道発達など速度による距離の克服、労働者たちの居住空間や労働空間の惨状、もちろん領土紛争と戦争などは具体的レベルの言及ですが、これと区別して、「生活空間」「生活位置」などカテゴリー的レベルでも注目しておくべきだと思われる。「地域」視点や都市の解放空間(対抗ヘゲモニー空間)や陣地、グローバル化やサイバー空間の問題など、空間視点なしに今日の変革論は語りえないこともまた事実なのです。
積極的に捉えるべき「主要矛盾」
僕が皆さんにこの本を薦めたのは、現実にダイナミックに展開している資本の動きに触れるようなものを勉強すべきだと思ったからです。ハーヴェイはこの本で17の矛盾を挙げている。基本矛盾が7つ、運動する資本の矛盾が7つ、資本の崩壊条件をなす矛盾(複利的成長、環境破壊、人間性疎外と反抗)が3つ列挙されている。疎外論が重要な位置を占めていることがわかるし、いかにも英米系の学者らしいというか、あれもこれもと盛りだくさんな割には、論理的な関連付けや展開についてはあまり気にしていない。ただ若い人向けの本としては、この点はあまりこだわるべきではないのかもしれません。
その上で、指摘したいことは二つあります。一つは、17の矛盾を挙げる中で、「主要矛盾」という捉え方を否定している点です。それは、多様な運動を資本のさまざまな矛盾と接合させることで変革の流れにつなげなければいけないということから要請されてくるものでしょう。毛沢東のように、この局面ではこれが「主要矛盾」だと、多様な闘争を一枚岩化することへの危惧だと思われます。しかし、主要矛盾論はどちらかというと実践的革命家としての毛沢東の柔軟性を示す優れた側面でもあります。諸主体が目標に向かう長期の過程における局面局面、客観情勢や主体的諸条件の現状や変化に対応した、中心課題の柔軟な推移を示していると思います。
我々の時代で考えると、たとえばフェミニズムがあり、エコロジーがあり、アイデンティティ型の政治がある。多様な領域に関わって多様な運動があります。それぞれの運動は実践的な問題意識から、フェミニズムは男女間の性別分業による男性支配を主要矛盾として闘い、エコロジーの運動は地球環境劣化にかかわって開発や濫費や次世代への責任放棄などを主要矛盾として闘うでしょうし、国民国家形成過程で暴力的に隷従を強いられたエスニック集団はそこに主要矛盾を見るでしょう。むしろ主要矛盾そのものが多様性を持っていると捉えるべきでしょう。もちろん、たとえば戦争の切迫という事態があれば、多様な運動間でマルクスの言う「アソシエートした知性」が働き、行動調整を積み重ねつつ、反戦や平和構築へと当面の主要矛盾を移動させるでしょう。
実際、フェミニストもエコロジストもアイデンティティー型運動も、ハーヴェイの挙げた17の矛盾の中で生きているわけで、その上で、それぞれの社会運動の集団が持っている中心的な課題を主要矛盾として打ち出しています。こういうパースペクティヴ(立ち位置による見え方、闘い方の差異)の重要な意味を自覚することは、実践家としては不可欠なセンスだと思います。ハーヴェイの意図からしても、むしろ主要矛盾を生かした方がよかったのではないか。「この局面では我が指導者のいう主要矛盾のみが主要矛盾だ」というようなセクト主義とは区別すべきものだと思われます。
疎外論とヒューマニズム
もう一つは、この本の最後に資本主義の存続に関わる3つの矛盾として、「エコロジー」と「複利的成長」、そして「人間性(ヒューマニズム)疎外」を挙げていますが、人間性疎外を挙げていたのは正直言って意外でした。60年代の初期マルクス・ブームへの先祖返りのような気がしました。
一口に疎外論といっても、精神主義的疎外論もあれば、宗教的疎外論もあれば、人間性疎外論もある。そのなかで、ハーヴェイは人間性疎外論をストレートに打ち出しており、日本では廣松さんが、海外ではルイ・アルチュセール(註2)が行ったような疎外論批判の内容をほとんど顧慮していないように見えます。これは彼が経済学者だからでしょうが、しかし、ズブズブの疎外論ではいけません。疎外論批判で提出された論点を多少は意識するべきだと思います。
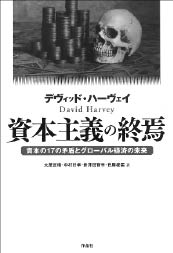 |
| 資本主義の終焉 ―資本の17 の矛盾とグローバル経済の未来 |
だからこそ、廣松さんやアルチュセールの疎外論批判が重要な意味を持ったわけです。もっとも、その際に彼らが疎外論そのものまで否定してしまった点は間違っていたと思いますね。いわゆる「疎外論から物象化論へ」という捉え方は解釈として間違っている。なぜそうなったかといえば、疎外論を「素朴なヒューマニズム」と一体のものとして捉えてしまったからでしょう。初期マルクスの疎外論は確かに人間主義ですが、疎外論そのものはかならずしもいわゆる人間主義と一体のものではありません。廣松さんやアルチュセールの致命的な欠陥は、それを混同して、疎外論そのものを捨ててしまったことだと思います。
社会的に限定された場所で生きている人間たちがさまざまな可能性を考える中で、自分たち自身が構築した現状を疎外されたあり方として否定的に評価することは十分あり得ます。その際には人間性一般が疎外されているわけではなく、特定の場所で生きている人間たちが持っている可能性に対して、現に自分たちが行った、あるいは再生産している現実が疎外として立ち現れてくる。マルクスは『経済学批判要綱』で資本主義は「現実から見れば」物件的権力、他者の権力として直接生産者たちに向かって立ち現れてくるが、「可能性から見れば」共同的に産出した世界の自己獲得と自由な個人の実現の可能性である、と対比的に論じている箇所があります。これが疎外の基本構造です。とりたてて絶対的な「人間の本性」なるものを前提にしているわけではありません。
この場合、マルクスは「各人の自由な展開が万人の自由な展開の条件であるような、一つのアソシエーション」として未来社会を構想しているように、諸個人の尊厳の相互承認、諸個人の目的存在としての相互承認という近代社会で歴史的に自覚されてきた理念(単なる理念でもあるもの)を、生活の実在諸条件の下で実現する運動という意味での「ヒューマニズム」は当然、前提されていると思います。
理論と実践
ところで、皆さんからこの本に対して、“ハーヴェイには実践の方策が欠けている”といった感想があったと聞きました。しかし、ハーヴェイは経済地理学をベースにした理論家であり、彼の作業はあくまで基礎理論であることに注意する必要があります。その点は僕自身も同じです。アソシエーション論で展開しているのは、たとえば現実の協同組合をどう組織すべきかといったようなことではありません。国家集権型の変革が失敗に終わったことを踏まえて、再出発の際に基礎理論として何を置くかということです。その際、僕としてはマルクス再読を通じてアソシエーション論に新しい可能性を見ていこうとしました。だから、基礎理論以上の実践の方策を期待されても困る。その点ではハーヴェイも同じだと思います。彼はあくまで理論家です。ただし、僕もそうですが、活動家と研究者の媒介をしたいという志を持っていることは間違いありません。
この点がよく分かるのが、先に挙げた『資本の〈謎〉―世界金融恐慌と21世紀資本主義』の最終章「何をなすべきか? 誰がなすべきか?」です。理論家の枠組みの中ではありますが、ギリギリの実践の呼びかけだと思います(僕自身も『アソシエーション革命へ―理論・構想・実践』[社会評論社、2003年]という本を編集しましたし、季報『唯物論研究』でも4回にわたって「アソシエーションの理論と実践」と題する特集を組み、理論家や実践家に参加してもらいました)。
ただ「何をなすべきか?」という表題には困惑しましたね。もちろんロシア革命の中心人物レーニンの同名の著作を意識したのでしょう。その中でレーニンは、“社会主義的意識は労働者大衆の外から持ち込むものであり、そのためには職業革命家による党組織をつくり、全国政治新聞をつくらないといけない”と主張ました。この本は長らくソ連型社会主義を目指す運動にとっては必読文献とされていました。そうした歴史を踏まえると、ハーヴェイが新しい実践を呼びかける中でこの表題を使ったことには、“無理しすぎ”という印象が否めません。
ヘゲモニーとアソシエーション
ともあれ、その最終章でハーヴェイが言っているのは、まずは限りなく運動の多様性を認めようということです。ネパール、ボリビアの太平洋地域、ミシガンの産業衰退した諸都市、ムンバイや上海の未だ活況を呈している諸都市、ニューヨークやロンドンなどの金融中心地……。彼は、それぞれの歴史的多様性や地理的多様性を生かしながら、それらを反資本主義運動として括ろうとします。これは彼のいいところだと思います。
そうした多様な運動がポスト資本主義の未来社会に向かって社会革命を起こす、彼はそれを「共―革命的(co-revolutionary)」と名付けますが、しかし、どのように「共―革命的」になりうるのか。この点でハーヴェイは諸運動の「共通の目標」にかかわって「いくつかの全般的な指導的原則」を設定します。自然の尊重、社会的諸関係におけるラディカルな平等主義、何らかの共同利益の感覚に基づいた社会的諸制度、民主主義的な行政手続き、直接生産者によって組織された労働過程……。
このあたりが「何をなすべきか」の「何」だとすれば、次には「誰がなすべきか」の「誰」が問題になります。レーニンの場合は職業的革命家の組織だったわけですが、ハーヴェイの場合はどうかというと、5つの主体を列挙しています。①膨大なNGO(非政府組織)。体制内的なもの新自由主義的なものも含めてです。市民社会の中で自ら社会問題を解決していく主体となっていることはたしかです。②アナーキスト、アウトノミア(註3)の諸運動。③伝統的労働組合と左翼政党。歴史的限界を露呈しているとはいえ、変革主体には加えています。④土地収奪などと闘うサバルタン。⑤性や宗教、人種や民族などのマイノリティ。この5つを挙げています。
これ自体に異論はないでしょうが、問題はそれらをどのように「共―革命的」に接合できるのか、ということです。この点で、ハーヴェイは「ラディカルな平等主義」という概念を提起しています。おそらくエルネスト・ラクラウ、シャンタル・ムフらのラディカルデモクラシーの議論(註4)に学んでいると思われます(『民主主義の革命―ヘゲモニーとポスト・マルクス主義』ちくま学芸文庫、2012年、参照)。
ラクラウとムフによれば、多様な運動の主体、たとえば非正規の労働者とフェミニストは議論つまり言語行為を通して接合され、つながるわけですが、その際に軸となるのが「平等」という概念です。ただし、それは「現在の民主主義国家では平等が保障されている」というような現状肯定的なものではありません。そうではなく、「平等」を現状変革に向けて機能させる中でさまざまな主体を接合していこうというのが、ラクラウとムフの言うラディカルデモクラシーなんです。
さらに言うと、それは「ヘゲモニー」(註5)ですから、それぞれの運動の本質は反資本主義だから「平等」を置けばすぐに接合されるというものではありません。それこそ「平等」を現状変革に向けて機能させるさまざまな調整や取り組み、仕掛けが必要とされます。その点で見ると、ハーヴェイには“ヘゲモニーとしてのラディカルな平等”という政治過程論的視点が弱いように感じます。もっとも、彼の専門は経済地理学なので、無理からぬことかもしれません。逆に、政治学者であるラクラウと哲学者であるムフが政治過程の固有性を強調するあまり、経済面での現状分析や資本主義批判については弱い側面があり、ハーヴェイはその点を補完していると見ることもできるでしょう。とはいえ、実践的に最も困難なのが多様な運動を歴史運動としてどう接合するのかということにあることを考えれば、やはり「何をなすべきか?」というような大きな看板をあえて持ち出すのはいかがなものか、というのが率直なところですね。
変革と国家的手段
もう一つ大事な点ですが、ハーヴェイは多様な運動が接合できたとして、ポスト資本主義に向けて社会を変革するに当たって、「国家権力を握り、それを根本的に変革し、その立憲的・制度的枠組みをつくり直すことこと、このことなしに、反資本主義的社会秩序が建設されうるというのは、とうていありえないことである」と言っています。要するに、アナーキズムはローカルな社会運動としては非常に優れていても、グローバルな課題については無力だと。これははっきりと言っています。
このあたりは、伝統的な「マルクス・レーニン主義」の臭いを感じるところです。要するに、“まずは国家権力を奪取して、上から社会を改造しなければならない。なぜなら社会主義的意識は労働者の中からは出てこないからだ”ということですね。
しかし、これはレーニンの特徴であってマルクスの特徴ではありません。これは、僕がアソシエーション論の中で言いたかったことでもあります。マルクスの基本的な主張は、社会の中のアソシエーション過程の蓄積の上で、副次的手段として国家的手段を用いるべきだというもので、アソシエーション過程の蓄積なしに国家権力が上から社会を改造するなんてことは、マルクスはまったく考えていませんでした。アソシエーション過程の連続性こそが変革の基本であり、資本主義社会の中で対抗的なアソシエーション運動から始まって政治権力を奪取する、それを手段として新しい社会へと自己を変えていくわけです。
そもそも社会主義を目指す運動や社会主義思想、社会主義的な政策というものは、資本主義とともに形成されていくものです。つまり、資本主義は支配的なシステムであっても、一枚岩的に世の中を覆っているわけではありません。だからこそ、資本主義が支配的な社会で対抗的なアソシエーション運動を積み重ね、拡大する中で支配的なシステムの転換を図っていくことになります。
しかし、ロシア革命の場合、歴史的な条件として、とてもそんな状況にはありませんでした。革命権力は握ったものの、教育を受けていない労働者・農民がほとんどで、対抗的なアソシエーション運動で鍛えられる機会など皆無に近かった。そんな現実に直面して、最晩年のレーニンは社会主義を可能にするための条件をまずは形成しないといけないということで自己批判し、1921年に市場経済システムを取り入れ国家資本主義で進む新経済政策(NEP)に転換を図ります。ただし、レーニンはその後すぐに亡くなり、スターリンの下で国家権力による上からの社会改造が強行的に押し進められていきます。
たしかに、国家的手段(国家権力)の行使を最初から原理的に否定してポスト資本主義社会を切り開くことはできないでしょう。しかし、それだからこそ伝統的な「マルクス・レーニン主義」の負の歴史を踏まえる必要があると思います。その点から見れば、ハーヴェイもアナーキズムを批判するならアソシエーション論的な視点を中心に据えて、副次的・補完的な手段として国家権力を位置づける必要があったと思います。国家権力から新しい社会が出てくるわけではありません。新しい社会の芽は、常にすでにこの社会の中にあるわけです。
とはいえ、そうした新しい社会の芽が力をつけて行く中で、国家的手段を通じて社会改造を加速するということは認めるべきだと思います。純粋なアナーキズム、つまり国家的手段の行使を拒絶するというのは、むしろ現実的ではないでしょう。もちろん、簡単な話ではありません。改良と妥協も避けられないでしょう。国家的手段を自己目的化して、現在の社会の力関係をそのままに国家的手段を行使してしまうことの危険性は、民主党政権の失敗に明らかです。しかし、社会の中の対抗陣地を形成しつつ、この社会が孕んでいる新しい社会の芽を開花させるテコとして国家的手段を用いる。こうした課題を回避してはいけないと思います。
おわりに
ハーヴェイは『ポストモダニティーの条件』(青木書店、1999年)という本も書いています。彼の関心の多面性を感じます。ポストモダンの諸思潮はそれ自身多面的で、ひとまとめにして論じることは慎むべきでしょうが、少なくともその思潮の中には、全体知の陳腐化、倫理から美へ、事柄より記号へ、「大きな物語の終焉」、シニシズムと歴史相対主義へ、といった傾向が確認されます。ハーヴェイは、ポストフォーディズム時代の表現様式としてポストモダニズムを解釈し、「ポストモダニズムのフレキシビリティーは虚構、幻想、非物質的なもの、擬制資本、イメージ、はかなさ、偶然性、隙間のフレキシビリティーに支配されているが、存在、場所、カリスマ政治への傾斜、新保守主義の安定した諸制度への肩入れを体現」してもいると見ています。
たしかにソ連・東欧が崩壊し、冷戦が終わった際に、「大きな物語は終わった」と言われました。それに対してハーヴェイは、“しかしそれでいいのか”と問題を投げかけているのです。現在の世界を見れば、もう一度「大きな物語」(もちろん今のところ悲劇の予兆に満ちたものではありますが)を考えないといけないような状況が現実にあるわけですね。明らかに歴史の舞台が大きく展開しています。
もちろん諸個人の「小さな物語」などにこだわらず、諸個人の犠牲を必要悪として「進歩」する理性や国家の「大きな物語」に焦点を合わせるべきだとする倒錯(ヘーゲル『歴史哲学』でも確認される)を復活させよと言いたいわけではありません。僕の理解では、我々は自然世界、生活世界、歴史世界の3層の世界を同時に生きていて、「小さな物語」と「大きな物語」をつなげつつ共に生き続けているのです。
ただし、局面が変わったと思います。ソ連型社会主義体制の大崩壊という歴史体験があったことを考えれば、人類史的展望からシニカルに距離を取ろうとする態度は、ある意味で自然だったと言えるのかもしれません。しかし「大きな物語」をいつまで避け続けているのだ、という声が内からも外からも聞こえない日はなくなりつつあります。ハーヴェイには、こうした課題に応えようとする姿勢が鮮明です。これは学ぶべき点ではないかと思います。
(構成・文責:当研究所)
【註】
(1)廣松渉(1933年~1994年)は日本の哲学者、マルクス研究者。東京大学名誉教授。『ドイツ・イデオロギー』に関する研究を通じて、初期マルクスにおける疎外論と後期マルクスにおける物象化論の断絶説を提唱。「疎外論から物象化論へ」を軸としたマルクス解釈の先駆けとなった。主著は『存在と意味』など。
(2)ルイ・アルチュセール(1918年~1990年)はフランスの哲学者。第二次世界大戦中の対独レジスタンス当時から共産党に所属。『資本論』以前のマルクスをヘーゲルの強い影響下にあると捉え、真のマルクス主義哲学は『資本論』に始まると主張。マルクス主義理論を構造主義的に捉え直したものと評価される。
(3)1970年代にイタリアを中心として、学校・工場・街頭での自治権の確立を目指して行われた社会運動。空家占拠や海賊放送などを伴った。
(4)ラディカルデモクラシーについては、本誌第161号「『民主主義の危機』にどう立ち向かうか―ラディカル民主主義という試み」参照。
(5)イタリアのマルクス主義思想家アントニオ・グラムシ(1891年~1937年)に由来する概念。支配には「強制」と「合意」の2つの側面があり、合意による支配をヘゲモニーと捉える。合意には被支配階級が下から形成する能動的合意、支配階級が主に国家機構を通じて上から抱え込む受動的合意があり、グラムシは両者の合意の確保に伴う力関係のあり方に着目した。
