研究会報告:たべもの歴史研究会
たべもの歴史研究会は、風土と農業・文明・社会の関係を問題にした前半の5回に続き、後半5回は日本に焦点を当て、日本列島に住む人々が「これまで何を食べてきたのか、これから何を食べていくのか」を軸に考えていくことになった。
「照葉樹林文化論」とは?
その最初として、今回は中尾佐助の照葉樹林文化論を下敷きに、照葉樹林地帯における食べものの伝播のあり方について取り上げられた。
中尾佐助(1916年〜1993年)は大学在学中からアジア各地を探検し、植物分布などの学術調査を行った植物学者である。ネパール・ヒマラヤにおける植生や生態系を調査する中で、この地方と日本とに文化的共通点が多いことを発見し、ヒマラヤ山麓から中国西南部を経て西日本に至る一帯を「照葉樹林帯」と捉え、そこでの文化的共通性に着目した「照葉樹林文化論」を提唱した。なお、照葉樹林とは、冬でも葉を落とさず、表皮に光沢の強い深緑色の葉を持つ常緑広葉樹の森林で、夏期に降雨量の多い暖温帯に成立する。
照葉樹林文化論の内容を一口で言えば、日本の生活文化の基盤を形成する諸々の要素が中国雲南省を中心とする東アジア半月弧に集中していることから、この一帯から長江流域・台湾を経て日本の南西部につづく照葉樹林地域に共通する文化の要素が同一の起源地から伝播した、とする仮説である。特徴として、根菜類の水さらし利用、絹、焼畑農業、陸稲の栽培、モチ食、麹酒、納豆など発酵食品の利用、鵜飼い、漆器製作、歌垣、お歯黒、入れ墨、家屋の構造、服飾などが挙げられる。
実際、本野さんによれば、日本ではワラビを食べるが、ワラビを食べる習慣は照葉樹林文化の東アジア半月弧にしかない。また、お茶の葉を刈り取って煎じて飲む方法も、やはり東アジア半月弧だけである。一方、コンニャク、ヤマノイモは南の根栽文化から伝わってきたものを受容し、品種改良した結果である。
さらに、ミカン、ヤマモモ、ビワなども照葉樹林文化の共通点である。ミカンもビワも、もとは西日本の気候に適していたが、現在では北限がやや北上している。こうした特徴的な農産物は、1万年〜1万2000年前から伝わってきたという。
文化と文明の違い
ところで、なぜ照葉樹林「文明」ではなく照葉樹林「文化」なのか。言い換えれば、文明と文化の違いは何か。
本野さんによれば、文明とは制度と装置の組み合わせから成り立つシステムである。
そもそも、農耕の始まりは約1万2000年前にさかのぼる。氷河期が終わり地球が温暖化していく8000年前から6000年前、農耕は世界中に拡散した。その3000年間は、気温は現在よりも2度高い高温の時代だった。
ところが、そこから温度が下がりはじめる。それまで、高温のおかげで豊作に恵まれ、増加する人口も賄えたのが、温度が低下する中で農耕の困難さが増していく。こうした時期に、合理的に生産力を上昇させるための必然性から、広い範囲で社会秩序をコントロールする組織、つまり国家というものが生まれてくる。こうして、生産する者と生産をコントロールしながら余剰を搾取する者が生まれていく。
つまり、本野さんによれば、文明のはじまりは国家のはじまりと軌を一にしており、それは階級支配の形成でもある。そのシステムは歴史を下るにつれて複雑さを増し、農業文明から商業文明、さらに法律や官僚制などの制度と産業革命に伴う生産装置の拡大が合わさって工業文明が形成され、今日の近代文明へと連なっていく。
一方、文化は宗教も含めた「情報の体系」であり、前の時代から受け継いできた情報体系の総体である。したがって、それは法律や制度、生産装置などとは関係のなく、体験して習慣化したものを次世代にバトンタッチしていく営みである。
本野さんによれば、かつて縄文人はおよそ1万種類の食べものによって自らの生存を維持していたという。それらについて、「これは食べたら危ない、これはおいしい、これは晒したら食べられる」という形で次世代に継承してきた。そうした情報体系の継承の中で次第に、狩猟採集から半栽培へ、そこから栽培へ、さらに農耕へという展開が生み出される。
こうして農耕は文明へとつながっていくが、本野さんによれば、問題にすべきは文化ではなく文明である。というのも、文明は国家を含む制度だから、法律やシステムの変更によって改変できる。しかし、文化は歴史的に積み上げられた情報の体系であり、それを次世代に継承する作業なので、改変すべきでもないし、しようもない。
本野さんは、先祖代々から受け継いできた文化に立脚することで、たべものの歴史を考えることができるが、文明と文化の違いに注意を払わなければ、風土や文化は国家のために利用される、と危惧するのである。
いずれにせよ、当初は文明圏に属する地域や人は極めて少なかった。たしかに、現在、世界人口のおよそ9割が文明圏に属するようになったが、それは人類の歴史から見れば、ごく短時間に生じた現象に過ぎず、大部分は文明の外、農耕文化の中にいる地域や人が多数派を占めてきた。
こう前置きした上で、本野さんは、中尾佐助が代表作『栽培植物と農耕の起源』(岩波新書)で取り上げたものこそ、そうした文明以前の文化圏の展開に他ならず、その刊行が高度経済成長真っ只中の1966年だったことも示唆的だ、と指摘した。
栽培植物の四つの中心
以下、本野さんによる中尾説の紹介である。
中尾によれば、栽培植物が発生した中心は世界に四つある。一つはメソポタミア。これは、小麦、大麦、ビート、エンドウなどを中心とする「地中海農耕文化」と名付けられる。ここから、西はヨーロッパや北アフリカ、東はシルクロードを通って中国、さらにその北方から朝鮮半島の最南端まで伝播したと見られる。
もう一つの中心はアフリカ西部ニジェール川上流域で、「サバンナ農耕文化」と名付けられる。代表的な栽培植物はシコクビエ、ササゲ豆、瓢箪、ゴマ。いずれも日本で当然のように栽培されている植物が、実は1万2000年前の西アフリカ発祥なのである。
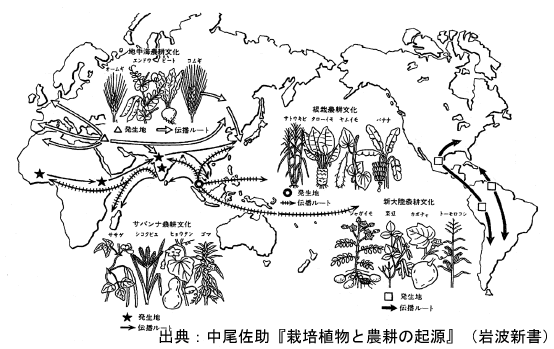 |
ちなみに、シコクビエは1960年代まで、四国の山地で栽培され、名前の由来となった。ヒエとともにやってきたイモチ病の菌はイネに移行し、いまも水田でイモチ病を発症させ続けている。
三つ目の中心はインドネシアで、「根栽農耕文化」と名付けられる。代表的な栽培植物はサトウキビ、タロイモ、ヤムイモ、バナナ。気候的な限界があったバナナやサトウキビはともかく、タロイモやヤムイモは日本列島に入り、品種改良を経て定着した。タロイモはいわゆるサトイモ、ヤムイモはとろろにするヤマノイモとなっている。
とくにタロイモは、日本で稲作が拡大していく3000年前から1万年前ぐらいまでは主食の位置にあったと考えられる。本野さんによれば、いまでも京都をはじめ、正月に小芋を入れて雑煮をつくる地方が結構あるのは、その名残だという。
そして四つ目の中心として中南米。「新大陸農耕文化」と名付けられる。代表的な栽培植物はジャガイモ、トウモロコシ、カボチャ、菜豆。
栽培植物の伝播順序
こうした四つの中心の栽培植物は、どのような順序で照葉樹林文化圏に入ってきたか。中尾によれば、採集時代から青銅器時代、およそ1万2000年前から1万年前という範囲の話である。すなわち、①ワラビ→②ヤマノイモ→③サトイモ→④コンニャク→⑤雑穀→⑥イネ→⑦コムギ、オームギ→⑧ソバ→⑨大豆、となる。このうち①〜④までが南方の熱帯「根栽農耕文化」から、⑤がアフリカの「サバンナ農耕文化」から、⑦は「地中海農耕文化」からもたらされたという。
照葉樹林文化で最古の栽培植物であるワラビは、根茎からとれるデンプンを晒して食用にしたものと考えられるが、その意味で根栽農耕文化を受容する基盤があったと考えられる。こうしてヤムイモがヤマノイモになり、タロイモがサトイモになって定着していく。これが1万2000年前から1万年前の間。
次に1万1000年前くらいに、ヒエ、アワの雑穀がサバンナ農耕文化から入ってくる。その後にイネが、さらに地中海農耕文化圏から、コムギ、オームギが入ってくる。最後のソバや大豆は、1万年前くらいと考えられる。
ところが、このうちイネ、ソバ、ダイズの由来は明示されていない。言い換えれば、中尾としては、いずれも照葉樹林文化圏に自生したものの栽培化として捉えられているのである。
もっとも、本野さんによれば、イネの栽培でベースとなったのは、ヒエの栽培技術だという。イネはもともと陸稲で、水田栽培ではなかった。ヒエの栽培技術に長けた人々がイネを発見し、ヒエと同じようにイネを栽培したところ、同じように栽培できたことから広がったと考えられる。その過程で、照葉樹林文化圏あるいはモンスーン地帯におけるイネ栽培の特色として、水田の優位性が発見されたのだろう。さらに、イネの栽培技術を基盤としてコムギやソバの栽培が展開された。
「五穀豊穣」と「たべもの史観」
以上の中尾説を踏まえ、本野さんは最後に一つのキーワードを提起した。「五穀豊穣」、すなわちイネ、ヒエ、アワ、ムギ、ダイズという五つの穀物の豊作こそが幸福だという考え方である。それはまた、1万1000年前にさかのぼる照葉樹林文化圏の文化的エートスでもあるという。
唐突な印象を持つが、本野さんによれば、現在のように政治的にも社会的にも変革の展望が見出しづらい状況の中では、ありきたりなスローガンでは力にならない。むしろ、「五穀豊穣」の歴史的地平から将来社会を展望するくらいのスケールがなければ現状は突破できない、とのことである。すなわち、「五穀豊穣」の地平から、たべものに依拠して歴史を見直すことこそ、「たべもの史観」の本意なのだろう。
その心意気やよし。だが、懸念もある。かつて古代中国では、天子や諸侯は国家の守り神として
土地の神(社)と五穀の神(稷)を祭ったという。そこから転じて、後に「社稷」は国家そのものを意味することになった。言い換えれば、「五穀豊穣」と「国家繁栄」とは極めて密接で、同時に危険な関係でもある。照葉樹林文化の受容した「五穀」の「豊穣」が国家の形成を準備し、文化から文明への転換を促したとすれば、果たして「五穀豊穣」の地平から説き起こされる「たべもの史観」は、近代文明を超えるための変革の立脚点となり得るのだろうか。
(研究所事務局)
地域・アソシエーション研究所 114号の印刷データ PDF
©2002-2012 地域・アソシエーション研究所 All rights reserved.
