|
☆清和天皇(せいわてんのう 850〜880 31歳) 佐竹氏をさかのぼると清和天皇にたどりつく。清和天皇は第56代の天皇で、藤原氏の後ろだてのもとに9歳で即位し、858〜876年の18年間在位した。平安時代初期は天皇が自ら政治の実権を握っていたが、清和天皇の頃になると藤原氏が摂政・関白になって政治の実権を天皇家から奪っていった。文徳天皇が即位した際に、年長の惟喬親王をさしおいて惟仁親王(清和天皇)が生後8ヶ月で皇太子になったのも、藤原氏の圧力である。清和天皇が即位した後の政治は摂政・太政大臣の藤原良房が行い、天皇は単なる傀儡であった。以後、藤原氏の栄華は、藤原道長・頼通まで続く。 ☆貞純親王(さだずみしんのう 874〜916 43歳) 天皇の子は男なら親王、女なら内親王と呼ばれる。貞純親王は876年に臣籍降下して源氏の姓を賜った。天皇の子女を臣籍降下させるのは、嵯峨天皇の時から盛んに行われた。天皇が子をたくさん設けて「血縁の壁」で天皇家を守るとともに、生母の身分が低く皇位につく見込みのない親王を臣籍降下させて、財政上の負担を軽くすることが目的であった。親王のままでは皇族の一人として国費で待遇する必要がある。しかし、嵯峨天皇は50人もの子を作って天皇家を守ろうとしたが、結局、藤原氏に「血縁の壁」を崩されてしまった。 |
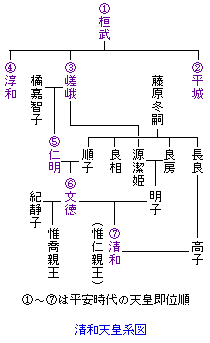 |
|
☆経基(つねもと ?〜961) 賜姓皇族(臣籍降下して姓を賜った皇族)の中で有名なのは清和源氏と桓武平氏である。貞純親王の子の源経基は清和源氏の祖と呼ばれている。経基は940年に平貞盛・藤原秀郷らとともに、関東で起こった平将門の反乱を平定し、941年には瀬戸内海を中心とした藤原純友の反乱も平定した。この2つの反乱は承平・天慶の乱と呼ばれ、武士の力が大きくなるきっかけとなった。 ☆満仲(みつなか 925〜997 73歳) 源満仲は、摂津に土着して勢力をのばすとともに、藤原摂関家にとり入って清和源氏発展の基礎をつくった。藤原氏は自分の娘を天皇の妻にし、その子を天皇にすることで天皇の外戚として力をふるった。貴族社会では、母方の縁が重要視されていたのである。 ☆頼信(よりのぶ 980〜1048 69歳) 源頼信は、1028年に房総地方で起こった平忠常の乱を圧倒的な武力の差で平定し、源氏の東国進出のきっかけをつくった。「戦わずして」平忠常が降伏したと伝えられていることからも、頼信の武力の強さが相当のものであったことが推察される。 ☆頼義(よりよし 999〜1082 84歳) 陸奥の安倍氏が朝廷に反抗したとき、源頼義は陸奥守、兼、鎮守府将軍として子の八幡太郎義家とともに奥羽に進み、清原氏と協力してこれを滅ぼした。(前九年の役1051〜62)また、義家が陸奥守の時、奥羽で勢力を得た清原氏の内紛を藤原清衡と協力して平定した。(後三年の役1083〜87)これらの戦役を通して源氏はその名声を高め、武門の棟梁としての地位を固めたが、奥州を手中に収める野望を果たすことはできなかった。その代わりに、奥州藤原氏が清衡・基衡・秀衡と三代100年に亘って、金による豊富な財力をバックに平泉で栄華をきわめることとなった。源氏の全盛は頼朝の登場を待つことになる。 |
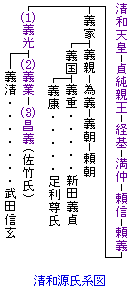
源頼義 |
|
(1)義光(よしみつ 1055〜1127 73歳) 佐竹氏初代の新羅三郎義光は頼義の三男として生まれた。母は長男義家、次男義綱と同じで、検非違使の平直片の娘である。平直片は関東平氏の代表的な存在で、源氏の関東進出に大きな影響を与えた。義光には後三年の役の際に、兄義家苦戦の報を受けて、自分の官職をなげうって義家の救援にかけつけたという美談がある。また、義光の墓は滋賀県大津市の三井寺にある。 (2)義業(よしなり 1077〜1133 57歳) この頃、藤原道長の子頼通に天皇となるべく外孫が誕生せず、藤原摂関家を外戚としない後三条天皇(位1068〜72)が即位した。次の白河天皇(位1072〜1086)が皇位を幼少の堀川天皇(位1086〜1107)に譲って上皇として院政を開始する頃には、藤原氏の力は完全に衰えてしまった。 (3)昌義(まさよし ?〜?) 昌義は源氏の私領地であった佐竹郷に住みつき、初めて佐竹氏を名乗った。昌義を佐竹氏初代とする説も有力である。朝廷より命を受けて常陸国の奥七郡(那珂・東西佐都・東西久慈・東西多賀)を制圧し、その功績により太田城に封じられて6万石の土地を賜った。 |
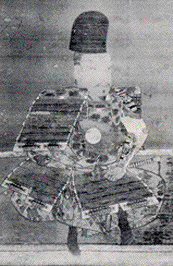
新羅三郎義光 |
|
(4)隆義(たかよし 1118〜1183 66歳) 院政は白河・鳥羽・後白河と約100年間続いた。鳥羽上皇の頃より平氏が台頭し、朝廷内部の争いを発端とした保元・平治の乱(1156〜59)で源氏(為義・義朝)をおさえて、平氏(清盛)が政治の実権を握った。しかし、平清盛が武士では初めて太政大臣になったものの、平氏の政権は長くは続かず、1180年に後白河法王の皇子の以仁王が平氏打倒の兵を挙げると、源頼朝・義仲をはじめとする各地の武士が相次いで蜂起した。このとき佐竹は平氏についた。源頼朝が挙兵した際に平清盛は隆義を常陸介に任じて頼朝に対抗させたのである。 (5)秀義(ひでよし 1151〜1225 75歳) 隆義の兄の忠義は頼朝に欺き殺され、隆義の子の秀義も頼朝に攻められた。秀義は金砂山城でこれを防いだが、隆義の弟の義李が頼朝に内応したことで城が落ち、秀義は敗走した。その後、秀義は頼朝に許されて臣下となり、1189年に頼朝側で奥州藤原氏の制圧に参加した。佐竹の家紋の「月印五本骨軍扇」は、源氏伝来の無地の白旗で参加した秀義に、源氏の嫡流の頼朝が与えたものである。1185年に平清盛の子の宗盛が檀ノ浦で義経に殺されて平氏が滅亡し、その義経が頼朝と対立し、義経をかくまった奥州藤原氏が1189年に滅亡したことで頼朝の奥羽制覇が完了した。後白河法王が死んだ1192年には、頼朝は征夷大将軍に任命され、名実ともに鎌倉幕府が確立した。 |

源頼朝
月印五本骨軍扇 |
|
せっかく始まった源氏の政権も、頼朝の死後は頼朝の妻の政子の実家である北条氏に実権が移った。北条氏は1221年の承久の乱で朝廷側の反乱を退けた後は、執権として皇位の継承にも介入するほどの権限を持った。鎌倉時代の佐竹氏は、常陸介として常陸国の長官の任にあたっていた。 |
鎌倉時代の佐竹氏 |
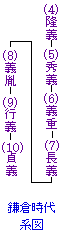 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
鎌倉時代の末期には、後醍醐天皇が隠岐に流されたのをきっかけに楠木正成らが兵を挙げ、1333年には足利尊氏・新田義貞によって北条氏は滅ぼされた。佐竹氏は足利尊氏を助け、室町幕府側の有力武将となった。当時、常陸国の守護職は鎌倉幕府創設に功のあった小田・宍戸氏が独占していたが、ここで佐竹氏は激戦をくりひろげ、ついには常陸国一国の支配権を確立し、1335年に常陸国の守護職に任命されることとなった。これにより、佐竹氏は一国を領有・支配する守護大名となっていくことになる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室町時代の佐竹氏 第14代の義人は上杉憲定(鎌倉執事・安房守)の第二子で、第13代義盛の娘を妻にして佐竹氏の養子となった。また、義人が夫人の菩提を弔うために建てたお寺が天徳寺であり、以後、佐竹宗家の菩提寺となる。また、佐竹氏の分家である東家・西家・南家・北家の四家が発生した。ちなみに私は南家である。 |
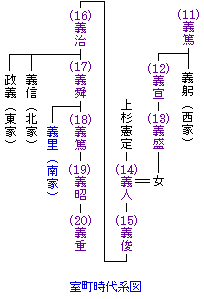 |
|
(21)義宣(よしのぶ 1570〜1633 64歳) 義宣の母は伊達政宗の父の妹であり、義宣と正宗はいとこ同志になる。義宣は17歳で家督を相続し、豊臣秀吉の小田原攻めに参陣するなどして豊臣方の大大名としての地位を獲得した。1591年には水戸城に本拠を移し、国内を完全に平定して全国第7位の54万石までとなった。また、石田三成・上杉景勝と関係も深く、完全に豊臣方であった。 豊臣秀吉が死ぬと、徳川家康は各大名を配下に入れ始めた。会津の上杉景勝がこれに従わないため、1600年に家康は会津攻めを発令した。義宣にも命令が下ったが、景勝と親交の深かった義宣ははっきりした態度を示さなかった。その後、石田三成が京都で挙兵し関ケ原の戦いで家康が大勝して徳川の時代が始ったが、豊臣陣営にいた義宣が処分を受けるのは当然で、1602年に一通の書状で石高も未定の北方の地に転封されることになる。結局、秋田での石高は半分以下の20万石であった。 転封先では大きな家臣団を維持できないとの判断から、家臣団の整理が行われた。その結果、多くの家臣が残され、一家離別・一族離別のようなケースも多かったとのことである。また、義宣が最初に入城したのは秋田一円を治めていた秋田実季の湊城であったが、すぐに久保田の地に築城を開始し、1604年には久保田城が完成した。 |
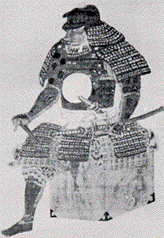
佐竹義宣 |
江戸時代の佐竹氏 第21代の義宣から第27代の義明までは、右図の通り系図が複雑である。また、第23代の義處の弟の義長は、佐竹壱岐守家の祖である。この壱岐守家と東西南北の四家を合わせて「佐竹五家」と呼んでいる。 |
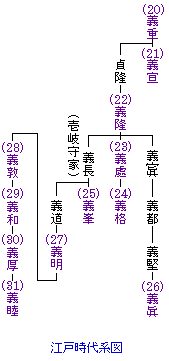 |
|
(32)義堯(よしたか 1825〜1884 60歳) 義堯は奥州中村城主の相馬益胤の三男として生まれた。最初は壱岐守家の義純の娘を妻にして壱岐守家を継いだが、その後、宗家の第31代義睦が早世したため宗家を継ぐことになった。
明治以後の佐竹氏 |

佐竹義堯 |