
|
|
|
|
| ここ「たわごと/その他」は現在、以下の項目を含んでいます。これら項目間に順序はありません(すなわち順不同)。 | ||
| 著作権への疑問 | ||
| 複製権の主張 | ||
| 月並みな表現 | ||
著作権への疑問
よく個人のつたないホームページにも堂々と、Copyright と All rights reserved、あるいは許可無く転載禁止というような注意書きがされているのを見ます。
ペットの犬が妙に下心ありそうにこちらを見ている写真と、ホームページ作成ソフトに付属の画像ファイルで大半が構成されているホームページ。旅行会社のパンフレットかガイドブックを引用したかのような、客観的だが「美しい」「楽しかった」としか感想の見当たらない旅のページ。市販本に掲載されているノウハウを再構成しただけとしか思えないホームページ作成講座のページ・・・なのに、どこからか拝借してきたのか、著作権表示が実に格好がいい。そんなページに当たると、著作権意識が高いのは結構なことだが、著作権を主張するほどの自信がお有りなの、と言いたくなることさえあります。
で、ひるがえって考えてみると、私がこのサイトで書いているようなものに著作権はあるのでしょうか。そもそも著作権の有る無しは、どこで判断されるのでしょう。
著作権は、著作物を創作すればそのとき自然に生まれるそうです(*1)。そして著作物は思想や感情を創作的に表現したものとのことです(*2)。上記のような不満を覚えるサイトや私のホームページが、この著作権を有する著作物に該当するのでしょうか。
*1. 私は法律にはうといので、この意味がもひとつ、はっきりしません。もちろん創作前には、それに関する権利は発生しないのでしょうけど。
*2. 「注意点としては、
・『思想や感情』を表現したものなければならないので、単なる事実(日本の人口数や、富士山の高さなど)は著作物ではありません。新聞に掲載されている死亡記事のうち、個人の経歴や葬儀の日時などが書かれているものは著作物とはいえませんが、個人の業績に対する評価や評論が書かれていれば、その部分は著作物といえます。」
久保田 裕、佐藤 英雄、『知っておきたい情報モラルQ&A』、2002年3月、岩波アクティブ新書、pp170-171
不満を覚えているわけではないですが、多くの方がポータルサイトにされている検索サイトにも、著作権についての疑問を持ちます。多くの分類項目を順序立てて並べている以外は、企業広告を貼り付けているだけといってもよいページが、それほど創作性を持つものとは思えません。サイト名のロゴには知的財産権が明白でしょうが、これとて商標権であって、登録を要するものです。作れば発生する著作権は、どの部分を指して言うのでしょう。
分類項目の編成に思想が表現されているといえるのかもしれません。また検索用のトップページだけではなく、他の独自コンテンツを含めた全体に対して著作権を主張なさっているのかもしれません。
複製権の主張
著作権は author-right ではなく copy-right であるということに思い至りました。「著作」というにふさわしい著述内容を持っているか否かではなく、勝手にコピーしてもよいかどうかにポイントがあるのですね。前節「著作権への疑問」は、創作性にこだわり過ぎました。
複製権に焦点を当て著作権を理解しようとするとき、私はコンピュータ・プログラムに関する権利が頭に浮かびます。
職業プログラマならご理解いただけるでしょうが、プログラミング作業の大半はそれほどクリエイティブではありません。すでにあるライブラリとかコンポーネントといった部品を適切に組み合わせれば、ほぼ形はできあがりです。後は1にも2にも、不具合探し、異常対策です。一般の方が思われるほど発想力が問われるものではなく、ひたすら膨大な数の参考類例から使えるものを見つけ出し、誤りの無いよう組み合わせていくという忍耐作業です。
*3. かつては業務ソフト制作でも、独自のルーチンで大手メーカー(Microsoft 社とか)に戦いを挑むようなクリエイティブな連中も多かったと思うのですが・・・ウイルス作成ですら、お手軽ツールが出ている時代です。
| 「忍耐作業」が必要であるからこそプログラムにも著作権が認められる、というのは言い過ぎでしょうか。たとえ凡作であったとしても、その労力に対して権利を与えようとするのが著作権の本義だと思えます。 秀作はもちろんのこと、凡作でも、勝手に複製されることで本来得るべき利益を失ったり、作者をおとしめるようなことが無いよう努める、そこに著作権の目的があるのかも知れません。 そこに著作権と特許権との違いがあります。右図のように知的財産権は著作権と工業所有権とに大きく2分することができますが、工業所有権はいずれも「類似」を排除するのに対し、著作権は盗作でない限りにおいて類似も排除しないそうです。 |
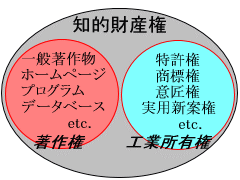 |
特許は何らかの機械の発明・工夫をイメージすることが多いため、コンピュータ・プログラムをはじめソフトウェアなど無形のものには該当しないように思ってられる方がいるようですが、ソフトウェアに関しても特許権は認められます(*4)。ただし特許権を得るには進歩性が認められる「発明」でなければならず、その該当分野やコンピュータ専門家なら誰でも思いつくようなレベルのプログラムは認められません。凡作ではダメなのです。
| 著作権 | 特許権 | |
| 権利発生 | 作成すれば自然発生 | 出願、審査、承認が要 進歩性を有すること |
| 公開要否 | 公開しなくてもよい | 公開が必須 |
| 侵害要件 | 類似であっても、別個に作成なら、いずれも侵害にはならない | 類似物が同じ発明にあたるなら、特許登録側を非登録側が侵害 |
*4. 2002年4月改正の特許法で、コンピュータ・プログラムは「物の発明」として取扱うことになりました。
なお、すでに特許権を持つプログラムに対し、リバースエンジニアリングを行なっただけでは(類似プログラムを制作しない限りは)特許権の侵害とはなりません。また、そのリーバースエンジニアリングからヒントを得ても、新たな改良を加え、元とは異なる発明とみなされるものを発案したならば、特許権を得る権利が生まれます。
一方、著作権は作品の優劣は問いません。適法な引用のレベルを超えて他に勝手に使われることを拒絶できる権利なのです。その権利の主張として、たとえ凡作を自覚していても、自作のホームページやプログラムには堂々と Copyright を書くことができるのです。あなたの個人ホームページに著作権が表記されていないなら、書き加えられてはいかがですか。
月並みな表現
雑誌などから適当に言葉を拾い、再構成してみると、次のようないかにもありそうな作文ができました。
今や、ネットワーク技術はビジネスはもちろん家庭生活においても欠くことのできないものとなっています。インターネットなどのネットワークを介したデータ交換や資源の共有など、当然のように使われ、またさらに次々と新しい技術が登場しています。迅速な経営革新のためには、幅広くネットワーク関連技術を取り込んでいくことが必要なのです。
もっともらしいけれど、なんと月並みな言いようでしょう。同類の文章はちまたに山ほど見つかります。特に経済誌や官公庁関係の報告書などに多いように思います。
しかし、何かレポートするとき、つい導入部や結語にこのような文を埋めることは、ままあることです。上の文章の場合、後に具体的なネットワーク技術の紹介とか、技術系企業の宣伝文が続くことは容易に想像できるでしょう。現代を切り崩すなぎなたを大上段に振りかざしておけば、文章に箔がつくし、流れもそれなりに流れるわけです。一概にこのような文章をけなしてはいけません。作者にとっては、こんな作文ができるのも技の内、です。
問題は、すべてが見せ掛けのなぎなた、子供の持つプラスチックの刀だったときです。読む方が、せいぜい竹刀だと見破ることができれば被害は無いのでしょうが、上の文のように適当に技術の香りのする語(「ネットワーク技術」だとか「データ交換」とか)を散りばめていれば、なかなか看破はむずかしいものです。多くの場合、ただ単に文章がバブルしているだけでしょうが、時にはあなたをだまそうとしているのかもしれません。
警戒は怠り無く、でも歌舞伎の大見得を楽しむ余裕も望まれます。
ちなみに私はプラスチックの刀をなぎなたに見せかけるのが得意です。この「草庵」は、そうして作りました。
ニタッ!
とりわけ、コンピュータの応用に関して書かれたものを、本物なのか体裁を整えただけのものか判定するのは本当にむずかしいことです。判定するどころか、英略語やカタカナ用語の群れの中で、どこへ連れて行かれるのかすらわからなくなります。多くの群れは死の行進をしているのに。
(英略語については自分なりのメモを作っていました。「英略語集」へ。)
| darokugawa@master.email.ne.jp | このページ最終更新日 : October 30, 2003 |
