
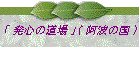


★ ホーム(目次無しの先頭ページ)へ戻るときは、
この下のボタンをクリック !!

| 寺 院 名 |
第三番札所 |
| 亀光山(きこうさん) 釈迦院(しゃかいん) |
| 金泉寺(こんせんじ) |
| 御 本 尊 |
釈迦如来 |
| 真 言 |
のうまく さんまんだ ほだなん ばく |
| 御 詠 歌 |
極楽の宝の池を思え
ただ黄金の泉澄みたたえる |
| 宗 派 |
高野山真言宗 |
| 開基寺院者 |
行 基 |
| 住 所 |
徳島県板野群板野町大寺亀山下66 |
| 電話番号 |
088−672−1087番 |
| 駐 車 場 駐車料金 |
駐車場あります 約10台 |
| 無料 拝観自由 |
| 交通手段 |
JR高徳線「板野(いたの)駅」下車。 徒歩で約10分 |
| 宿 坊 |
ありますが、現在は休止中 |
- 「大師が掘り当てた黄金の井戸」があり、
- その水を飲むと「長寿をもたらす」ことで有名です。
- 行基が奈良時代の天平年間(729年〜749年)に聖武天皇の
- 勅願により金光明寺を開祖したと伝えられております。
- 亀光山 釈迦院 金泉寺仁王楼門建立之誌 から引用
-
- 当山は徳島県板野郡板野町大寺と謂う地名に所在し。
- 亀光山釈迦院金泉寺と称す。本尊は釈迦、阿弥陀、薬師の
- 三如来を奉祀し、高野山真言宗に属し、四国霊場第三番なり。
- 柳々当山の建立は、人皇第四十五代聖武天皇の勅願にて、
- 天平年間に鎮護国家のため、行基菩薩をして此の地に寺塔を
- 建立せしめ、金光明寺と号せり。その寺域は頗る広く、今に
- 地名を大寺と云う。その後、大同年間、弘法大師四国霊場
- 御開創にて御巡錫の砌、住民常に水不足にて苦しむを知り、
- 井戸を掘らせられるに、不思議や霊水湛々として湧出す。
- 住民これを見て黄金の泉と称えり。
- 大師金光明寺を再建し、寺号を金泉寺と改ため四国第三番
- の霊場と定められたり。
- その後、人皇第九十代亀山天皇文応元年、即位し給うも
- 在位二年にして譲位し、上皇となり給うて院政を行い給い、
- 文永、弘安の役には自ら伊勢神宮に籠り身を以って国難に
- 当たらせ給い、また朝廷訴訟の法を制定なし給いて徳政の
- 興行と呼ばれ給いしも、皇統継承順位の乱れに失意なし給い
- 二年後には譲位し法王とならせ給うて、大師の遺跡また霊場を
- 巡拝し給うに、当山之の御叡信殊に浅からずして玉履を
- 留まらせ給い、寺内に御座所を設らい、寺背の丘陵をして亀山
- と名付け、寺の山号を「亀光山」と賜号なし、荒廃の諸堂は
- 新たに改修し給い、また特に御勅命にて洛陽の蓮華院を擬して
- 三十三間堂を建立し、千手観音を勧請なし給い、寺を経所房
- となし、いつでも遠近の学侶相集り講論研鑚の肆となし給い、
- 更に当山の寺紋を菊水と定め給う等、七堂伽藍の偉容は念々
- 整い隆栄たりき、其の頃、長慶法王辛酉革命にて当山に
- 御駐輩あり、久しく御不豫なれど、応永五年三月十九日、
- 御宝壽五十三才にて崩御遊ばされしとぞ傅う。
- 斯の如く由緒交々にして威勢なるも、時は戦国の世にて
- 天正十年八月、長曽我部元親氏の兵火にて当一山の伽藍
- 並びに開創以来八百四十一年に亘る寺績も悉ごとく灰燼に
- 帰せり。誠に惜しむ可きなり。其の後の復興は至難にして
- 容易ならざるも時の住房、寛昌、宥由、義渕、の先師に依り、
- 三十六年間、の歳月を経て元和六年、護摩堂を再建し績く
- 法印、宥昌、宥義、宥盛の先師にて現存の寺域を確定し
- 天保三年現存の本堂を再建せり。
- その後、方丈、大師堂等々の復旧を見るも既に老朽化の
- 現象多く顕現せり、依って以って宗祖、弘法大師御入定
- 一千百五十年御遠忌に係る報恩謝徳の御爲めに裏面の如く、
- 山内諸堂の整備を営なみ、且つ当山守護の金剛力士を
- 新たに勅請せんが爲めの山門を新築し落慶して、大師の
- 報恩に奉答し且つ永えに由緒を後世に伝え、当山護持の
- 資にあらん事を希い、是が銘をして残すもの也
-
- 亀光山金泉寺中興第二十五寺住職 弦元和信
- 合掌
-
- 1月18日頃に「観音堂」の中を通って、
- 「ミニ四国八十八ヶ所のお砂踏み」が
- 毎年一回だけあります。
- 詳しくは、お寺にお尋ねください。

- 第三番札所「金泉寺」の概略位置図を下に示します。
- あなたが観てみたい 建物、景色、駐車場やその他のものが
- あれば、下の地図内の文字をクリックすると、別ウィンドウで
- 表示されます。
-
- クリックした後、表示された別ウィンドウ窓を閉じるには、
- そのウィンドウの右上にある [X]閉じるボタン を
- クリックしてください。
-
- 中の詳細を見るには、下にある詳細のリンク部分をクリック
- してご覧ください。
-
- 全ての文字に画像が表示されるわけではありません。
- 位置関係、大きさは正確ではありません。目安にしてください。
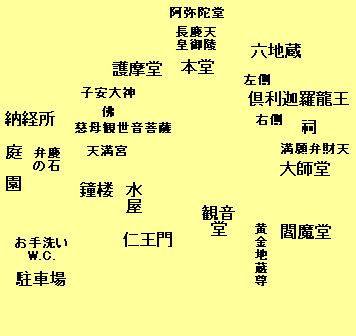 「金泉寺の概略位置図」
「金泉寺の概略位置図」

- 観音堂 に行く
- 建立年は室町時代の応永年間(1394〜1428)で
- 天正年間に長曽我部元親により焼かれました。
- 観音堂の内 を参拝をする
- ミニ四国八十八ヶ所 のお砂踏みに行く
- 黄金地蔵尊 に行く
- 黄金の井戸 のところへ行く
- 黄金の井戸に顔を映して見る 占う
- 自分の影がはっきり写れば3年は死なない
- 影がぼやけていると短命に。
- ★注意★
- この写真は大きいものを利用しておりますので
- 部屋を暗くすると、モニターに自分の顔が
- 映れば大丈夫?
- 液晶画面は映りにくいかもしれません。
- 黄金地蔵尊 を参拝をする
- 北向き地蔵とも云われ、手でさわって
- 願をかけると良いそうです
- 特に首から上の病気に良いそうです
- 倶利迦羅龍王と十二支の御守本尊 前のところへ行く
- 倶利迦羅龍王 を参拝する
- 倶利迦羅龍王は不動明王の化身といわれる
- 龍王です。
- 左側の四支の御守本尊 のところへ行き、参拝する
- 阿弥陀如来
- (いぬ・いのしし年生まれのお守本尊)
- 無限の慈悲と永遠の存在と徳を与えられます。
- すべての人々に大悲をもって永遠の救いを
- なされます。
- 不動明王
- (とり年生まれのお守本尊)
- 慧刀、羅索ほ保持し一目にして威怒身て猛炎の
- 中岩盤上に立っているお姿より御仏の守護で
- あると申せましょう。不動の明王は私達の煩悩を
- 除き一切の災いを打ち砕いてくれます。
- 大日如来
- (ひつじ・さる年生まれのお守本尊)
- 宇宙すなわち昼夜の別なる日の神の力よりも、
- もっとはるかに上まわる智恵と慧の光明をもって
- すべいの現象の根源とされる仏様です。
- 全世界の平和と繁栄をつかさどる仏様といっても
- 過言ではないでしょう。
- 勢至菩薩
- (うま年生まれのお守本尊)
- 阿弥陀様の脇に観世音菩薩とお並びになり智慧
- 第一の菩薩と称されます。
- 合掌されたお姿からは、一切の苦難を離れ安楽
- ならしめるでしょう。
- 右側の四支の御守本尊 のところへ行き、参拝する
- 普賢菩薩
- (たつ・み年生まれのお守本尊)
- 釈迦三尊に文殊菩薩と共に左右にお並びに
- なりますこの尊像は、一名遍吉菩薩ともいわれ
- ます。理智と慈悲の徳によって永遠の華福な
- 人生を得ることでしょう。
- 文殊菩薩
- (うさぎ年生まれのお守本尊)
- 「文殊の智慧」といわれますように智慧と戒律を
- つかさどる菩薩です。我々の日常生活に普遍の
- 智慧と悟りをみちびくことでしょう。
- 虚空蔵菩薩
- (うし・とら年生まれのお守本尊)
- 虚空が無辺の功徳を包み入れるように限りない
- 智慧と慈悲とをそなえた大菩薩で、人々に福徳
- 円満をさずけます。
- 千手観世音菩薩
- (ねずみ年生まれのお守本尊)
- 千手の手とその手に目をもつ観世音菩薩で、
- 千とは方便が無量であると意味します。
- 延命・滅罪・除病を祈り、さしのばされた手は、
- 永遠の幸福をさずけることでしょう。
- 本堂 に行く
- 本堂の中 へ入り、参拝をする
- 本堂の内 へ行き、参拝をする
- 本尊は三尺の釈迦如来です。
- 脇仏の薬師如来、阿弥陀如来の
- 三尊ともに行基が造ったものです。
- 護摩堂 に行く
- 弁慶の石がある庭園 へ行く
- 弁慶の石 を見て、参拝をする
- 源氏と平家が戦った、寿永四年(1885)に
- 香川県の屋島へ向かっていた源義経一行が
- この寺で一服をしていた時に、弁慶に力試し
- として持ち上げさせたという大きな石です。

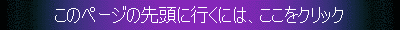
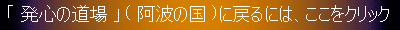
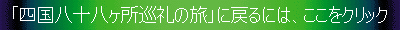
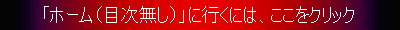

![]()
![]()
![]()
![]()
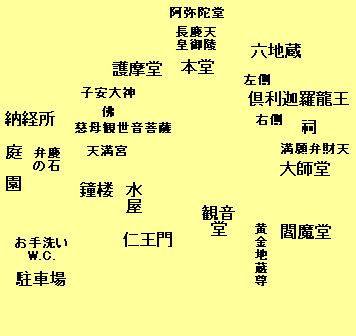 「金泉寺の概略位置図」
「金泉寺の概略位置図」![]()
![]()