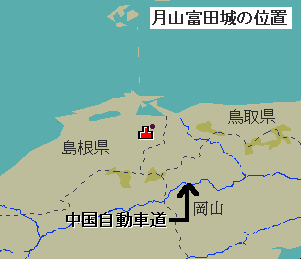
月山富田城がいつ頃に作られたかはよくわかってませんが、12世紀後半、源頼朝が出雲国の守護として佐々木義清を任命し、義清がこの地に館が建てたというのが始まりとされています。室町時代に尼子(あまご)持久が守護代としてこの地に住み着き、その孫の経久ときに富田城は最盛期を迎えます。尼子経久が勢力下においた場所は、出雲、石見、伯耆、因幡、播磨、備前、備後、備中、美作、安岐、隠岐、と11カ国に及びました。 経久の孫の晴久が天文九年(1540年、桶狭間の戦いの20年前)に毛利元就の吉田郡山城を攻撃するが失敗。当時、毛利元就を庇護してきた大内義隆がこれにつけこんで、同十二年に尼子晴久のこもる月山富田城に二度にわたり、攻撃を仕掛けましたが、落城しませんでした。大内氏はこの敗北が原因で家臣の陶氏に謀反を起こされ実権を失い事実上滅亡。そして、陶氏も1555年、厳島の戦いで毛利元就に敗れて滅亡。やがて、毛利元就は出雲に謀略、調略を施したのち、月山富田城を攻撃。このときの尼子氏の当主は義久。1年半の籠城の末、偽の和平策にだまされ、1566年に月山富田城は開城され、毛利氏の手に渡ってしまいました。 1600年関ヶ原の戦いで毛利氏は西軍(豊臣方)に味方したのですが、西軍が東軍(徳川方)に敗れると、毛利氏は月山富田城を追われ、代わりに徳川家康に味方していた堀尾吉晴が月山富田城に入りました。しかし、堀尾氏は月山富田城が山奥で港と離れているためすでに太平の世には不向きと考え、城を松江城に移しました。その後しばらくして、元和の一国一城令(1615年)によって廃城になったようです。 関連事項 |