対
人
社
会
動
機
検
出
法
|
対人社会社会動機検出法 (寺岡隆著) から
[ ページ 4 ]
4.条件比較
実施状況
本項では、実験条件が異なる場合の動機成分分布の差異について
考察することにする。被験者群は、前記の実例2における北星学園
大学の被験者群である。
この実験では、最初に「標準型基本方式」としての一般反応傾向を
検出する検査課題を実施したあとに継続して次に述べる3種の実験
条件を実施したものである(寺岡、1991)。
実施条件
ここで用いられた条件は次の3種である。
l)信頼関係条件(mutual trust condition)[T条件]
相手は自分がよく知っている個人で、自分が十分信頼できる相手
であると限定されている条件。この実験では、統制する意味で、た
とえば自分の恋人など、“信頼できる異性"というかたちで限定し
て想定すると要請したが、現実にいない場合はそのような人物がい
ると想定して、その相手に対して反応することを要請した。
2)敵対関係条件(mutual hostile condition)[H頁条件]
相手は自分がある程度は知っている個人で、自分にとってはいわ
ば不倶戴天の敵である相手であるというかたちで限定されている条
件。この場合相手も自分のことをやはりそのように敵として考えて
いることに限定した。もしも、そのような人物が現実にいない場合
は、そのような人物がいると想定して、その相手に対して反応する
ことを要請した。
3)無関係条件(mutual unrelated condition)[U条件]
相手は公私共にまったく無関係な個人で、利害的にも感情的にも
中立的相手で、将来も無関係であると考えられるかたちで限定され
ている条件。この場合、将来、接触する機会があるとは考えられな
いが、現在たまたまこのような事態におかれた事態を想定させて反
応を要請した。
被験者験者は、T条件34名(男子16、女子18)、H条件
32名(男子11、女子21)U条件32名(男子16、女子16)であった。
条件比較の具体的手法
この3種の条件は「標準IF-THEN法」を用いる場合に、被験
者がある程度以上の人数があり、かつ、時間的余裕がある場合には
しばしば用いられる1種の基本的条件になっている。同一人物に
3種全部を実施することは、現実としては時間的に余裕がないことが
多いので、このような場合は、通常、被験者をほぼ3等分していず
れかの条件に割り当てるようにする。また・この割り当て方は、あ
らかじめ一般反応傾向を記入する課題用紙と条件別の課題用紙を教
示用紙と共に一緒に綴じた課題材料を配布すると効率がよい。この
際、一般反応傾向に対する検査を常に先にした方がよいであろう。
なお、このように同一被験者が2度続けて実施するときは、各人ご
とに課題型をそれぞれ変えた用紙を用いる方がいい。また、集団実
験の場合、各条件に割り当てられる人数のバランスをよくするため
には、あらかじめ、T条件・H条件・U条件・T条件H条件・U条
件のように循環的に配布できるようにした綴りのセットを構成して
おいて教室でそのまま配布すれば、各条件に割り当てられる被験者
がだいたい同数に近いデータが得られる。このように2度続けて実
施する場合は、一般に、被験者は反応に慣れてくるので、2枚目の
反応用紙に対する所要時間はかなり短縮する。
分析結果
FIG.4-7は上記3条件に対する結果である。この条件別の
場合には、全被験者が3分割されているので、条件別に上位・下位
と分けて考察するには被験者が少な過ぎよう。したがって、ここで
は上位・下位を合併した群で結果を眺めていくことにする。なお、
以下の記述では、たとえば、「優越動機成分」や「共栄動機成分」
を単に「優越」とか「共栄」などと略して記述ずることにする。
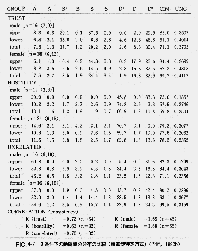 まず、「信頼条件」(T条件)では、男女とも「平等」(D0と
「共栄」(S+)が高く、男子では「献身」(B+)がこれに続き
、さらに「卑下」(D-)・「単利」(A+)となり、女子では前
記2成分に「卑下」(D-)が続きさらに「献身」(B+)・「単
利」(A+)となる。順序には多少差異があるか、この5成分が信
頼関係の主要成分で、最初の3成分だけで70-8O%、5成分で
は90%を超すかたちになる。「敵対条件」(H条件)では・男女
とも「優越」(D+〕が圧倒的で「単利」(A+)・「平等」(D0)
がいくらか出現し、これだけで約9O%になり、他は無視できるく
らいに小さい。「無関係条件」(U条件)では、男女とも「単利」
(A+)が最大で「優越」(D+)と「平等」(D0がほぼ同程度
で続き、男子はこれで約90%、女子は「単利」〔A+)が最大で
はあるがこれらの結果からみて、条件によって男女差は多少あるが
それほど大きいとはいえず、「信頼」・「敵対」・「無関係」の結
果は、すべて、結果を得てからの感想ながらきわめて常識的に納得
できる結果を示したといえよう。
ということは「IF-THEN法」
は、結構、常識的な結果を数値的に表現してくれる技法ということ
になろう。
まず、「信頼条件」(T条件)では、男女とも「平等」(D0と
「共栄」(S+)が高く、男子では「献身」(B+)がこれに続き
、さらに「卑下」(D-)・「単利」(A+)となり、女子では前
記2成分に「卑下」(D-)が続きさらに「献身」(B+)・「単
利」(A+)となる。順序には多少差異があるか、この5成分が信
頼関係の主要成分で、最初の3成分だけで70-8O%、5成分で
は90%を超すかたちになる。「敵対条件」(H条件)では・男女
とも「優越」(D+〕が圧倒的で「単利」(A+)・「平等」(D0)
がいくらか出現し、これだけで約9O%になり、他は無視できるく
らいに小さい。「無関係条件」(U条件)では、男女とも「単利」
(A+)が最大で「優越」(D+)と「平等」(D0がほぼ同程度
で続き、男子はこれで約90%、女子は「単利」〔A+)が最大で
はあるがこれらの結果からみて、条件によって男女差は多少あるが
それほど大きいとはいえず、「信頼」・「敵対」・「無関係」の結
果は、すべて、結果を得てからの感想ながらきわめて常識的に納得
できる結果を示したといえよう。
ということは「IF-THEN法」
は、結構、常識的な結果を数値的に表現してくれる技法ということ
になろう。
考察
FIG.4-7における「上位群」(upper)・「下位群」
(lower)というのはこの実験の場合には、前記の一般傾向に
おける「安定群」・「不安定群」の規準で分類したもので、新たに
この条件別の「一致係数」で分類してはいない。この2つの実験に
おける反応安定度に関する関連性は表の下部の相関係数どおりであ
る。これは「一般反応傾向」における「一致係数」と条件別におけ
る「一致係数」との間におけるPearsonの相関係数であるが
、相関係数としてはそれなりの高い数値を示しているけれどもけっ
して完全相関に近いといえる数値ではない。特に「敵対条件」にお
ける相関係数が低くなっているが、これは「不確定度」におけるU
が多少低くなっていることに関係しているかもしれない。
すなわち、「信頼関係」というのは多次元的な成分、たとえば、
「共栄」「平等」・「献身」・「単利」・「卑下」などに分かれると考えら
れる要素が対応しているが、これに対して、この「敵対関係」とい
うのは、この動機成分に関していえば比較的少ない成分、たとえば
、「優越」・「単利」、および、場合によっては「平等」・「加害」
(実験結果では出現していない)を加えるくらいで表現できること
が多いのでどちらかといえば構造的に単純で比較的反応しやすく、
少数の動機成分に集中するために「不確定度」が小さくなり、それ
だけに、「一般反応傾向」の場合には不安定群に分類された被験者
でも「敵対条件」のときは安定した反応を示す者が多くなって、結
果的に相関が低くなったのではないかと推察される。
ところで、この3条件の結果と先に示した「一般反応傾向」と比較
するとおもしろい結果を示す。ここで示されている表では、被験者
は完全な対応がなく全員の結果と3分割された被験者群の結果との
比較になるが、「一般反応傾向」の動機成分分布に一番近い動機成
分分布は、もちろん、「分布差指標」を用いて確認することができ
るけれども、直感的にも「無関係条件」の動機成分分布であること
は容易に気が付くであろう。ここで、女子はほとんど同じ傾向であ
るのに対して、男子は「一般反応傾向」では結構出現させている
「共栄」(S+)や「平等」(D0)が「無関係条件」ではそれぞ
れ減少して、その分が「単利」(A+)と「優越」(D+)に上乗
せしたかたちで増加していることである。これは一般傾向としての
話であり、実証結果といっても十分な資料とはいえないが、いくつ
かの点で興味がある結果を示唆しているように思われる。すなわち
、1つは、男子の場合、“今後とも無関係な人間"に対しては、多
少熊度が変わる傾向が強いということであり、しかも、その方向は
自己を有利にもっていくという常識的に理解できる方向になるとい
うことである。
もう1つは、女子の「一般的反応傾向」というのは
“今後とも無関係な人間"に対する態度とほとんど同じ傾向を示す
ということである。そして、さらに興味のあることは、これら3条
件の動機成分分布を各成分ごとに平均した新たな分布を作ってみる
と、この分布は「一般的反応傾向」における社会動機成分分布に一
番近い分布になるということである。いうまでもなく、対人関係は
この3種だけではないし、特別の対人関係の代表といわれるものを
集めたわけでもないが、少なくとも、それぞれは基本的関係のいく
つかではあるということになる。
このようなことから示唆されることは、「一般的反応傾向」という
ものは、多くの対人関係に対処できるような平均的な反応傾向なの
ではないであろうかということで、少なくとも、そのような仮説を
立ててもよいような結果であったということである*7。
[もどる] [次を表示]
(寺岡隆 『対人社会動機検出法』から。 北大路書房, 2000)
|