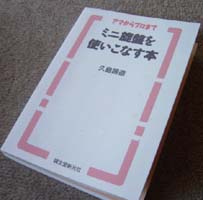MORI Hiroshi's Floating Factory
Model Railroad Workshop
<機関車製作部>
スロープ開発とライブスチーム
 /☆Go Back☆/
/☆Go Back☆/
上の写真は、積み荷のない運材車を引くデキ3。良い季節です。休日は、少し時間があると庭に出て、土でも運ぼうかな、雑草でも刈ろうかな、と考えてしまいます。いつも機関車がそこにあれば、もっと楽ですが、実際には、室内から重い車両を運び出してセットする作業がわりと大変。もちろん、後かたづけもあります。ライブスチーム(蒸気機関車の模型)だと、走るまでに1時間。終わってからの掃除に1時間はかかりますから、それに比べたら、電気機関車は簡単。5分もかかりません。それが億劫だといっているようではいけませんね。
そうなのです。欠伸軽便鉄道には、実は蒸気機関車が既に在籍しています。1つは3.5インチのクラウスという小さい蒸気機関車で、この弁天ヶ丘線よりもまえに作ったもの。弁天ヶ丘線は線路の幅が5インチ(13cmくらい)ですので走らせることはできません。もう1両は、玄関に鎮座したままの5インチのイギリス型のタンク車LADY MADCAP(「20世紀の本気」参照)なのですが、これは重すぎて(約90kg)線路に載せることができません。そういう理由で今まで一度も本線に蒸気機関車が走ったことはありませんでした。
さて今回は、重い機関車の搬出・搬入のための工夫と、突然現れた蒸気機関車についてレポートします。
<草刈りと吹付け塗装の秋>

1週間で草は数センチ伸びます。だから、毎週末にはちゃんと草を刈ることができるのです。楽しいですね。両手でじょきじょき切るタイプのハサミが大小2つあったのですが、ホームセンタで安売りをしていた電動のバリカンタイプのものを買ってみました。マキタの製品です。シーズンオフだから安かったのでしょう。動かしてみると、とても好調。レールの間の草も刈れます。片手でできるので非常に楽。でも、石が飛んだりすると危ないから、メガネをかけていた方が良いでしょう。もう少し音が小さかったらもっと良かったかも。これを2機前方に取り付けた「草刈り専用車」を構想しましたが、危ないのでやめておきます。
<デキ3の搬出スロープを開発>

デキ3が重いため、いつも玄関から下ろすときにスバル氏を呼ばなければなりませんでした。なんとか自分一人で運び出せないかと、ずっと、吊り上げるクレーンのことばかり考えていました。クレーンならば、どんな段差にでも適用できるし、使い道が広いからです。アングル材で作ろうと、幾つか設計図も書いたのですが……。
しかし、場所が限定できるならば、その場限りのものが簡単に作れるのでは、と急に方向転換。結局、スロープを製作しました。上の写真のように2組に分かれています。材料は、宅配便で届いた荷物を梱包していた木材。まったくの廃材利用です。現物合わせで、切っては木ネジで止め、1時間ほどで完成してしまいました。最初は何も考えずに作り始めたのですが、作っている途中でいろいろ面白い発想があって、出来上がったものは、ちょっとしたアイデアが盛り込まれていますので、多少詳しくご紹介しましょう。


いつもは機関車はホビィ・ルームに置いてあります。絨毯に車輪の跡が付かないように、普段は電話帳や漫画雑誌の上に載せてあります。機関車の片側を持ち上げるのは比較的簡単なので(理論上約10kg程度)、片側ずつ台車の上に載せて移します。それから、機関車にブレーキ機構がないので、写真のようにストッパの木片を下に挟んで車輪を浮かせます。これで傾いても動きません。
右の写真が玄関の段差。ここが約20cmほどあります。これまで、2人がかりで台車ごと持ち上げて下ろしていました。写真のように、高い方のスロープが、ここの段差に合わせてあります。



玄関を出るときは、高低2つのスロープを直列に並べて、ドアの敷居もついでに跨ぎます。20cmを2mほどで下る計算。かなり急ですから、慎重にゆっくりと下ろします。
2枚目が次なる難関。玄関の外にある10cmほどの段差です。ここでは、低い方のスロープだけを使います。こちらは、この段差に高さが合わせてあります。そもそも、長短2つのスロープを最初は造るつもりでしたが、短い方のスロープを、長い方の下半分に使えるようにして、木材を節約した点がアイデアというわけです。
3枚目が、スロープを下ったあと。トータルすると、床の高さから約30cm下りたことになります。このレンガ敷きのレベルが、弁天ヶ丘線のレールの一番低いところとほぼ同じ高さになります。レールを使って下ろす手も考えましたが、ハンドリングが悪そうなので、この台車を用いる方法を採用しました。
10分の1の超急勾配ですから、自力で上り下りするには、ラック式にしないと駄目でしょう。


今度は、載っている台車から線路の上へ機関車を降ろさなくてはいけません。そこで、また思いつきました。低い方のスロープをリレーラのように使おうというもの。ちょうど本線がカーブしているので、その線路の上にスロープをはめて、台車から機関車を転がします。車輪の間隔(つまり5インチ)に板の間隔を合わせるために、微調整用の細い角材を使いました。スロープは、下の線路がちょうどはまるように切り欠きが入れてあります。
最後が線路にのったところ。スロープの内側の先端が斜めになっています。今回は、何も考えずに作り始めたので、やっつけ仕事になっていますが、もう一度作ったら、ちゃんとしたものになるでしょう。しかし、このいい加減さが弁天ヶ丘線らしいといえばらしいかも……。
片づけるときは、手順がこの逆になります。どちらかというと、スロープを上げる方が安定していて簡単です。もう一人のときでも機関車が出し入れできます。車庫ができれば、こんな苦労も必要なくなるのですが……。でも、大型模型をやっている人は、みんなこんな工夫をしているのでしょうね。


では、運転開始。黄色の無蓋車を挟んで、その後ろに運転台車を連結しています。無蓋車には、羊が乗っています(右写真)。運転台車は前回のレポートで紹介した新設のポケット部にバッテリィを搭載しています。コントローラがその上のテーブルに載っています。
乗用トレーラも耐久性・安全性がほぼ確認できたので、今回は、家族のみんなに運転してもらいました。スバル氏が一番飛ばしていました。デキ3はホイルベースが短いためか、それとも車輪のテーパの加減なのか、カーブできいきいというスリップ音がしません。レールの継ぎ目で僅かにガタンゴトンと良い音を立てるだけで、とても静かに走ります。現在、ホイッスル音を出すために、電子パーツの製品を調査中です。
<突然ライブスチーム!>


予定外のことですが、突然、弁天ヶ丘線に新しい(古いのですが)機関車が入線しました。青い塗装のイギリス型っぽい蒸気機関車です。間違ってもお面を付けたりしてはいけません。
ライブスチームとは、蒸気機関車をほぼ本物のままスケールダウンして作ったミニチュアです。材料もほとんど本物と同じです。石炭を焚き、水を温めて蒸気を作って、その膨張力でピストンを動かして走ります。だから「生きている」という意味で「ライブ」スチームと呼ぶわけです。電気機関車はモータで、ディーゼル機関車はエンジンで走らせるのが「ライブ」ですが、でも、電機やディーゼルは、何もかも本物の縮尺とはいきません。昔のメカニズムである蒸気機関車だけが、そのままのスケールダウンが可能なのです。
とはいっても、すべてがスケールモデルではなく、この機関車のようなフリー(模型のために設計されたオリジナル)も沢山あります。これは中古品をオークションで落札しました。この種のものは、製品はほとんどなく、大多数はマニアの手作りです。数十年まえに作られたものだと聞きました。

動輪は2軸でB型です。後ろにテンダを従えています。蒸気機関車は大きく分けて、このテンダのあるものと、ないものがあって、小型はだいたいテンダがないタンク型に属します(機関車トーマスは小型のタンク型で、ゴードンなどが大型のテンダ型です)。この機関車は小さいくせにテンダ型なのが変わっています。このテンダを、普通の人は「石炭を積む車両」だと認識しているようですが、実は大半は水を入れるタンクです。石炭は上部にちょっと載っているだけ。蒸気機関車はとにかく水を沢山食うのです。
前部の機関車部(エンジン部と言います)にも、円筒のボイラの横に四角い部分がありますね。タンク車では、ここに水を入れています。どうも、もともとはタンク車だったものを、あとでテンダにしたような感じもします。どうでしょうか。テンダの一番後ろに斜めに立っている棒が見えますが、これは給水ポンプのレバー。ボイラに水を手動で送るためのものです。


キャビンの中の様子。小さな圧力計や、ガラス管の水面計が見えます。中央の下にある円形の部分が、石炭を投入する釜の蓋です。
この機関車はかなり軽量で、エンジン部は25kg程度しかありません。その点ではハンドリングは良いでしょうけれど、牽引力はあまり期待できません。コンプレッサで圧力をかけて検査してから、一度試運転をしてみたいと思います。クラウスのときに買った石炭がまだ残っているはず。ライブスチームは冬が良いのです。蒸気が見えるし、なにより暖かいし。うまく走ったら、これが5号機になります。
最後の写真は、ホビィ・ルームの窓際に飾ってある3.5インチのクラウス。テンダがないタンク型です。緑のキャビンの両サイドにタンクがあって、やはり給水ポンプのレバーが突き出しています。もう4年ほど動かしていません。文字通り「窓際族」になってしまいました。3.5インチの線路は直線しか持っていないのです。小さいエンドレスを作れば良いのですが……。
<Gゲージの整備>


前回レポートでオレンジの無蓋車(ゴンドラ)を紹介しましたが、同じHARTFORD社プロダクツのボックスカーも塗装をして仕上げました。ここのキットは20.3分の1のようです。作ったのは2年ほどまえで、ずっと無塗装のまま飾っていたものです。ブルーのつや消しです。シックな貨車が2台揃ったので、機関車もウェザリングしたポータあたりが欲しいところ。どれか1台犠牲にして(という表現は不適切ですが)汚そうか、と考えています。
もう1枚は22分の1のトーマ。レイアウトのどこかに置いて、「トーマをさがせ!」ごっこができます。
<その他の備品>


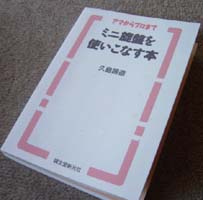
まずはディーゼルエンジンのピストン。直径が125mmほどで、これも5インチなのかな。オークションで1000円で購入。そうですね、重しになりますね。
2枚目に写っているのは、機会があると集めてしまう自動車やバイクのライトのカバー。落ちていることもあります。一番上の大きいのはバスのテールライトでしょうか。500円で購入したもの。真ん中の2つは、オークションで200円で手に入れた電車の部品(らしい)。これはガラスです。こういうのを何かに使いたくなりますが……。
3枚目は、ようやく手に入れた久島諦造著『ミニ旋盤を使いこなす本』です。完全な技術書ですが、お値段は4100円。この分野では評判の名著です。もう1カ月ほど、毎日5Pほどずつ読んでいます。自宅に旋盤が早く欲しいです。
<グース野郎>


トラックなんかが沢山付けている色とりどりのライト。ホームセンタで500円だったので黄色を1つ買ってきました。どこかに付けたくて、やっぱりグースでしょう。邪魔にならない場所ということで、この位置になりました。保線を行う整備車にぴったし。
2枚目の写真が、バッテリィが入っている部分の蓋を取ったところ。このようになっています。黄色のライトは小さなトグルスイッチを付けて、点灯できるようにしました。夜は迫力があります。
<足の踏み場しかないホビィ・ルーム>

また1台増えてしまって、置き場所が大変。Gゲージのレイアウトはこれからどうしようか、と考えています。シーナリィを作るなら、こうした床置きでは駄目で、ちゃんと専用の台枠を作る必要があります。しかし、そんなものを作ろうものなら、もう部屋から出せなくなってしまいます。この家と心中する覚悟がいりますし、移動や、線路の変更も面倒になります。しかし、このレイアウトが床からある程度持ち上がれば、その下に膨大は収納スペースが確保できるなあ、とか考えたり……(笑)。とりあえず、Gゲージはデジタル化したいので、そっちの方がさきでしょう。デッキや庭に新線を建設する予定もありますし。まあ、予定ばかりいっぱいあるのです。一生工事中でしょう。
/☆Go Back☆/