 |
2013年6月29日(土)高等部大会議室に25名が集まり、相良先生のお話を通して、今一度キリスト教について考える時を持ちました。讃美歌256番『主に任せよ』の歌詞に込められた意味を考えながら、皆で讃美し、お祈りを持って始めました。 |
☆「目からうろこ」とは
聖書が出典となる言葉で、教会(青山学院)の歩みの中で、一つの大切なお話です。使徒言行録で、目からうろこのようなものが取れて、復活の主との出会いの中、新たな光の中で再び見えるようになったパウロに起きた出来事から来ていますが、現在では、分からなかったことが突然分かること、として使われています。そのように、聖書の一節が一般的に知れ渡り、その言葉が一人歩きしている場合が多くあります。例えば、エヴァンゲリオン(本来は福音・よき知らせの意味)やタレント、などの単語もそうです。
教会でよく聞くお話の中には、わたしたちにとって「目からうろこ」の経験となる物語が多く語られています。そのいくつかをご紹介しましょう。
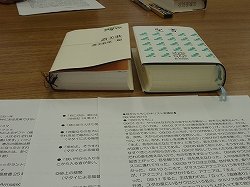 |
☆天国と地獄
どんなところか見せてあげようという話。地獄とは、机の上のご馳走を目前に、飢えて渇いた人々が長い柄のスプーンを持ちながらも、椅子から動けずに、食べようとしても自分の口に入れることが出来ないでいます。彼らの目は血走り、口々に罵り合っているのです。
一方、天国は、見た目は全く地獄と同じ。ご馳走を前に長い柄のスプーンを持っていますが、スプーンの届くところにいる人の口に運ぶことが出来ます。皆、幸せそうに、分け与えあって、誰もが満足しています。
どちらも同じようなところであるのに、そこにいる人々の心や行ないが、そこを天国にしたり地獄にしたりするのです。
誰かを喜ばせることが出来て、神のみ心にかなったなら、その人は幸せでしょう。仕え、支え合うことの本質がここにあります。
我々は、少しでも工夫して考えて、(もっと)得たいと思うのが正直なところですが、その考えを逆転させるのが、聖書の言葉です。
『人の子は、仕えられるために来たのではなく、仕えるために来たのである』
何が本当に心を温めたりするのか、その土台に何があるのか、確かめることが大事です。 |
☆インド・ヒマラヤのお話
雪の中、二人の人が必死で歩いています。目的地に着くかどうか、いつになったら着くかも分からない時に、倒れている人を見つけます。一人は、自分たち二人が死んでしまうから助けられないと道を急ぎ、もう一人は助けない訳にはいかないと倒れていた人を背負って歩き始めます。背負って歩き続けていると、また倒れている人を見つけます。それは、先に一人きりで行った友人が息絶えた姿でした。
後で、倒れた人を助けたと思っていたが実は自分が助けられていた、と気づきます。背負ったことで体温を分かち合い温められたのかも知れないと気づいたのです。
幸せは、「仕合せ」とも書き、支え合う事を表しています。日本独特の表現ですが、どの文化であっても、人に尽くす行ないが、神に喜ばれるように思います。
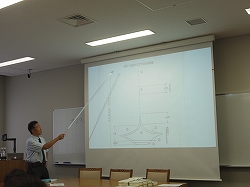
☆ブドウ園の労働者の話
労働時間が違うのに同じ賃金であるのは、我々の理解からするとおかしいですが、約束通りですから不当ではありません。明日の食糧さえも心配する者には、命を繋ぐ為のお金です。ここではブドウ園の主人が一番損をしていますが、それでも異議を差し挟ませない、神様が決めたことを、あなたはどう受け止めるかが、問われています。
神様のみ心は、誰に対しても、私はあなたによくしたい、それが届けようとしたメッセージです。そういう神様であるけれど、あなたは信じますか、と聞かれています。
聖書を難しく読む必要はありません。素直にメッセージを聞こうとしているか、良い思いを持って互いを大事にしなさいと、言われています。
|

☆青山学院は幸いな場所である
み言葉は、普通の感覚とは逆のものが語られ、そこで価値観を入れ替えるような経験を、青山学院の生活の中で誰もがしているのではないでしょうか。卒業していった学生が、自分自身の中で当たり前のことのように思っていた価値観と、違うものにぶつかり、傷つくことがあると言っていました。そして、高等部の生活の中に、聖書があり、礼拝がおかれていた意味に気付くのです。
青盾会の方の声を聴くことがありました。高等部在学中、戦時中でも、渋谷キャンパスの学院内には自由がありました。検閲を受けていた時代であったのに、高等部の先生は「この戦争は間違っている」と、聖書のみ言葉に照らし合わせ発言していたそうです。
青山学院に招かれたということは、「目からうろこ」のような経験を、み言葉を通して導かれていることであり、それを家族や友人たちと分かち合えることは賜物です。
もともと欧州は文化としてキリスト教が先にあり、近代文化が整ってきたので、読む・書く・話すという新しい英語の土台は聖書にありました。日常の話し言葉がみ言葉を土台として普通に使われていた言葉と、日本語は違い、現在でも、教会内で話す言葉で、外では通用しない言葉があります。その意味では、今、青山学院が大きな課題を持っていると言えます。本来の意味とは違った聖書の言葉が使われるようになると、どのように語るか、アイデンティティを保つのが難しくなります。
|
神様は、誰ひとり欠けることなく手を差し伸べられます。青山学院は、そのことを大事に、学生を社会に送り続けてきました。
今春3月に初等部生と高等部生8名とで、2週間フィリピンに行きました。現地の人が出迎えてくれた歌「Wellcome to the family」を紹介したいと思います。出会った子は、都市型貧困にある自分の生活を教えてくれました。最低限の生活を守り生きていくとはどういうことなのか、幸せの質とは何なのか、学ぶ機会を与えられました。支援の意味やその限界、共に生きるとはどういうことか、生徒には「目からうろこ」のような体験だったと思います。この体験が歩みのスタートとなり、今後につなげられたら良いと考えます。
|

現地の少年に、夢は何かと聞いたところ、夢など考えたこともなくどんな仕事をしてでも家族を養えればいい、との答えが返ってきて驚かされました。誰かが誰かを切り落としている現実や、(現状を)どの基準で考えるのか、その基準がみ言葉であれば道を誤ることはないですが、別の基準であれば危うくなります。それは、青山学院にも当てはまることかも知れません。 |