大学時代のサークル活動に熱くなるのは、青春期の一種の熱病のようなものか。
後に思い出して、苦笑いをする場面もあるかもしれない。
しかし、その一時期を持った者と、持たなかった者では、後の人生に対する青春の重みが異なってくるのではないだろうか。 |
 |
部室前で厳かな開会式を行った後はチャーターバスに乗り込み、
伏石でバスを降りたところから、それは始まる。 |
 |
 |
|
|
|
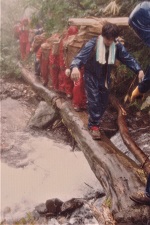 |
雨中行軍。
ほぼ辛いだけの経験だが、自然相手の活動では、避けられない苦難。
全パーティー行動をとっている時は、最後の一団がそろうまではザックを下ろさない。 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
名物の鍋さらい。
一応は、食べ物を粗末にせず、
かつ山でごみを出さないという
名目のもとに行われていた。
女子は免除される不文律も
なくはなかったが、
この代は積極的に参加。 |
 |
 |
お約束のお披露目。
どこまで徹底して綺麗にしたかを
誇る。 |
 |
|
| キャンプファイヤーは、一体感を高揚する効果がある。 新錬では三日目の夜の定番行事。 |
 |
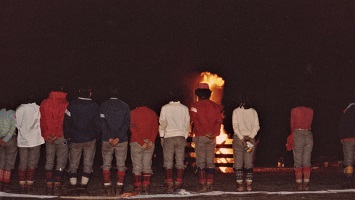 |
|
「起床~っ」の号令がかかると、外に駆け出て整列点呼。軍隊?
並ぶのが遅いと叱られるが、一年生を置き去りにして二年生が駆けると怒鳴られる。テント設営と撤収も、力を入れる訓練の一つ。 |
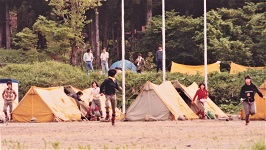 |
 |
 |
|
| 新錬最終日の最後の中休。勝山の変電所で非常に和やかに休憩をとる。 |
 |
 |
 |
 |
|
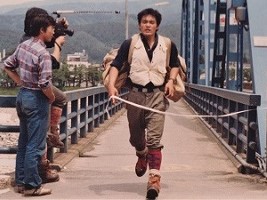 |
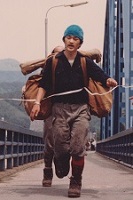 |
そして、新錬名物の最後の一発。
一年生一人一人が、先輩のあとについていくのではなく、自分の全力で勝山橋まで駆ける。 |
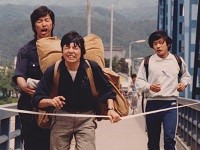 |
 |
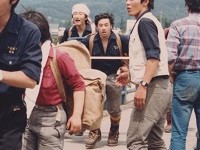 |
|
|
|
 |
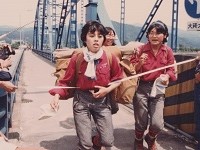 |
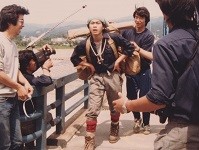 |
「演出された感動」と揶揄した者もいるが、それは違う。
自然を相手に活動する以上、最後に頼るべきは、
先輩ではなく自分自身でなければならない。
そのことを象徴化するのが、「最後の一発」。 |
|
 |
順位に意味はない。
力を使い果たしている者もいれば温存していた者もあるだろうし、そこまでの過程で荷の重さも千差万別。
肝心なのは、一年生が自分に納得のいく最後の一発を駆け抜けること。 |
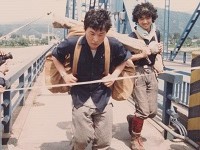 |
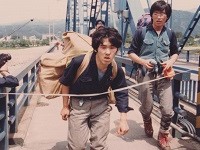 |
 |
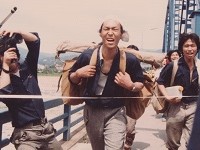 |
|
| 勝山橋近くの河川敷で閉会式。 その後、リーダーは川に流される。 |
 |
 |
 |
|
社会に出た後も、新錬の意味を考えることがある。
FUWVも1979年の事故を契機に、新錬の意義も位置づけも意味合いも変化してきた。
元々「しごき」ではなかったが新錬自体の厳しさは低下しただろうし、時代性とも相まって、部の求心力も低下したかもしれない。
新錬がクラブを創り、クラブが新錬を創る。 クラブが時代を造り、時代がクラブを造る。
これからも形は変わっていくだろうし、それはそれで良いのだろうと思う。 |
 |
|
|
 1982年のTOPに戻る 1982年のTOPに戻る |